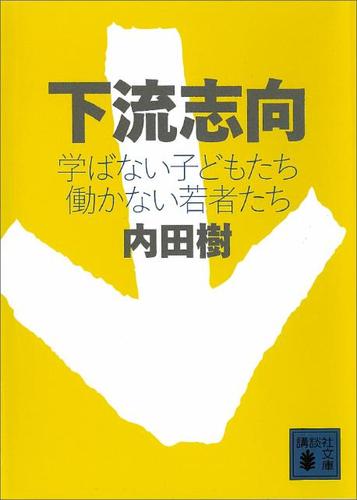
総合評価
(258件)| 84 | ||
| 96 | ||
| 32 | ||
| 8 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ今の子供たちが、勉強や労働から逃走しているのかがよくわかった。また最近アクティブラーニングが叫ばれているのも、学習の中身ではなく、学習する方法を学ばせることが重要で、その理由もそういった学びから逃げている子供たちが背景にあるのだなと感じた。
1投稿日: 2013.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ・労働より消費を先に覚えてしまったため、学びへの仕方が変わってしまっている。労働から得れる人からの賛辞よりも、消費者として対等に渡り歩ける味を占めてしまったら、教育への姿勢も好感となってしまう。 ・これによって得れるものは何ですか?まだ学んでいないものに、初めから得るものは分からないし、そこで判断してしまうのはもったいないし、判断なんてできない。 ・教育は時間的価値で、自分自身がそれによって変わるもの。
0投稿日: 2013.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了日: 2013.12.09 22:08PM 大学時代の先輩からの借り物。 難しかった。なんかもう小難しかった。
0投稿日: 2013.12.18前半は
ほぼ現場にいる身としては,前半はとても興味深くおもしろかった.
1投稿日: 2013.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学べる」ということの豊かさを もう一度 確認する時がきてるんだろうなぁ。 ・・・・・納得できるとこと できないところがあるだけに考えさせられる。
1投稿日: 2013.11.25社会としての危機感
身近な現象としては、珍しいことではないものの、それがこの先何を生むのか、ということを見せつけられた気がします。
1投稿日: 2013.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログつまるところ、あまりに合理的過ぎるのだ。無駄に時間を使うな、効率性を追求せよ、常に対等であれ…いや、全てその通り。でも、今この現実で起こっている様々な社会の歪は、合理性をあまりに極端に社会に持ち込んでしまった結果なんだと思う。特に、本来は合理的とは対極にあるはずの「教育」という分野に極端な合理性が持ち込まれたなら、その歪が大きくなるのも当然の話だ。 教育には時間がかかる。そしてその投資効果が確実に見えるとは限らないし、ましてそれを明確に数値化することなとできない。そのことが、我々消費社会に生きる人間には耐えられないのだ。消費社会では時間というものは関係ない。然るべきものに、それと等価のものが、時間とは無関係に交換される、徹底的に無駄を省いたシステム。最初からこのシステムに組み込まれた子どもたちが、教育に於いて合理的に「等価交換」を求めるのも、ある意味納得のいくことなのかもしれない。 教育の崩壊や若者のニート化、こうした"敢えて"下層にとどまろうとする子どもや若者を単に経済的に助けたり、合理的な解決方法を求めてもさして意味がない。なぜならこれはイデオロギー的な問題であるからだ。一筋縄ではいかないからまた経済的に解決を図ろうとする。実に悪循環である。
0投稿日: 2013.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初の方は筆者の言っていることは正しいのかと思ったが…小学生が不快を貨幣と考えて授業を受けない、というのはまったく共感できない。殆どの小学生は教育を受けるのが権利か義務か?ということだって考えないでしょ。それで教育は権利だから勉強しないのはこちらの自由と考える小学生なんて本当にいるの?そんな小難しいこと考えないでしょ。ただ勉強が嫌いなだけ。それをビジネスモデルに当てはめてめちゃくちゃな分析をしている。てんで的外れな主張。この授業は10分しか聞く価値がないから残りの40分は授業を聞かないという小学生なんて絶対にいない。努力してサボっているとか本気で信じているのだろうか?さらに家族内でも誰が一番不快に耐えているのかを競っている、なんてバカバカしいにもほどがある。リスクヘッジとか贈与と交換とか納得できない話ばかり。理論ばかり先行して現状、生身の人間をまったく考えていない、考えられないという感じ。なんで何もかも経済に当てはめられると思うんだろうか。
3投稿日: 2013.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人に薦められて読みました。多少表現が難しい所もありましたが、学びを放棄した人や働かない人への切り口が面白かったです。
0投稿日: 2013.10.15「意味」のある人間になるために
学ぶ意味、働く意味なんて考えなくていい。学べる時には学べ。働ける限り働け。その結果として、お前はこの社会において、他者にとって「意味」のある人間となれる。超要約すればそういうことか。その「意味」は、「意義」「価値」「すばらしさ」その他のプラス表現に変換可能。100パー同感です、内田先生。
0投稿日: 2013.10.05学ぶ子の育て方?!
何故、子供たちは学ぼうとせず、若者たちが働こうとしないのかを、自説・他説を交えながら明らかにしていく良書。講演をベースにし書き下ろされているので、平易な言葉で書かれているので非常に読みやすい。本書の中では、貧富の格差による家庭の教育力格差、それにより生じる正負の拡大再生産により、一層の格差社会化が進むことを指摘している。 教育会の末端にいるものとしては大変興味深い内容で、改めて公的教育の役割や家庭教育のあり方について考えさせられた。個人的には、階層格差をブレイクスルーしていける人材を育てることが公的教育の役割だと考えている。そのためには、お為ごかしの教育改革ではなく、義務教育から高等教育、そして就労まで見据えた教育のグランドデザインの再設計が必要なのだろう。教育関係者のみならず、子育て中の方にもおすすめの一冊。
3投稿日: 2013.09.28まともな授業ができないのは何故?
今、学校でまともな授業が行われにくいという話や、大企業に入社出来て、親がやれやれと安堵していると3年以内には辞めてしまう…理由は「自分に合わない」ことのようです。そんな社会現象をどのように、分析しているのかに興味がありました。 読みはじめましたが、教育について授業時間を増やせば学力低下が防げるなんて言う簡単な問題でないことが分かって来ました。 何をするにも「本人のやる気」がなければできない。豊か過ぎてその芽を摘んでいるからだ…わたしはそんな風に考えていたのですが、いやはや根は深い。 そんなことを感じながら、ざっと読み進み、2回目に読めば、もう少し内容理解が出来るようになるだろうと考え始めています。つまり小説を読むように1回読んで終わりには出来ない本です。
4投稿日: 2013.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ下流思考という言葉でしめされているが、 教育、しつけというものに関わる昨今の問題にしっかり向かった良著。 自分自身も余裕のない時に「下流思考」に陥っている。 戒めの意味も含め、何度も読み返したい一冊。 学びからの逃走、労働からの逃走。 その背景にあるのは無意識的な等価交換の考え方。 等価交換の際には時系列がなく、 その場で自分の払う対価と得るものが同等であることを求める。 教育の現場は非常に難しい。 教育自体、受益するのは後になってからだが、教室は不快と教育サービスの等価交換の場となってしまいがち。教室では貨幣が使えないため、生徒側は不快を貨幣のかわりにする。 教育に関わる自分にとっては非常に考えさせられた。
1投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強しない子ども、働かない若者についての考察がおもしろいと思います。こんな意見があるんだなぁと…。 前半は大方納得がいき、なるほど~と思って読み進めましたが、後半の質疑応答の辺りは個人的に私の中に落ちてきにくく、共感度が下がりました。 もうすぐ2才になる子とまもなく産まれる子の母親ですが、一般的な育児書の内容では稚拙すぎる部分が多く、このような鋭い分析の多い本は今後の子育ての参考になります!何を子どもたちに教えるべきか、少し見えてきました。参考にさせていただきます。
2投稿日: 2013.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
買い手マインドで勉強に対峙していると考えると結構納得できてしまうことに驚いた。彼らの合理的な行動による意思表示は、私がいくら考えたところで想像もできないような意味を持っていた。 街場の教育論と並行して読んでいたので同じ話も出てきて、復習しつつ読み進めることができた。今時の学ばない働かない若者について一般的に言われていることとは違う角度から問題を指摘していて、むしろ彼らは合理的なのだというのが新しかった。内田さんの言うことが100%の正解ではないだろうけれど、こういう意見を無視することはできない。子どもと関わる人、子どもを理解したい人、つまり世の中のすべての人に、こういうメッセージが届いて考える機会を与えてほしい。
2投稿日: 2013.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹先生の本、初めて読みました。日本の子供たちが勉強しなくなったことを「勉強しないよう努力している」などちょっと驚く説明をしていて、しかもその新しい見方が合理的に納得できました。この本は講演会の書き起こしで粗っぽいので、もう少ししっかり書いた本を読んでみたいものです。
0投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学びや働くことから逃走する子供たち、若者たちについて、何故なのか、その理由を時代的、社会的背景から分析。 小さいうちから消費者となり、費用対効果にあうサービスを求めることから入る子供たちの特性に衝撃。 家庭における手伝い等から誉められるという労働、生産性ではなく、お金を払って物を買うまたはサービスを受けるという、子供と大人の区別のない消費の世界で社会とのセッテンを早くに体験することが持つ影響力。 短期スパンでしか物事を捉えられないため、即効性のないものへの努力を無駄、苦痛と考える。 親、大人の責任を考えさせられる。
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ネタバレ多しです。 |逃走の違い エーリッヒ・フロムの”自由からの逃走”・・・独裁政権や機械化に屈服する倒錯。 今の若者の”学びからの逃走”・・・先人の民主化と人権拡大の営々たる努力の歴史的成果としてようやく獲得された"教育を受ける権利"をまるで無価値なもののように放棄している現代の子どもたち。 教育される義務から逃れることにより、喜びと達成感を覚えているように思える。 |分からないことがあっても、気にならない。 分からないことを、読み飛ばすことは、人間に必要な能力でもある。 しかし、最近の若者は、あまりに読み飛ばしすぎる。若者は、意味の分からない言葉と出会うことに、ストレスを感じない。この物事を知らないことを不快に思わないロジックは一つしか思いつかない。 それは、"自分の知らないことは、存在しない、ということ" にしている。 今までの人は、意味の分からない言葉にぶつかると気になって仕方なく、 自ら学び知ろうとした。 しかし、昨今の若者は、世の中に意味の分からない言葉がありふれて、 まるで、チーズの穴が無数にあるように、その穴自体が気にならない状況に陥っている。 |オレ様化する子どもたち 過去の子どもたちは、例えばカンニングしている所を見つけられると、 悪いことをしていたと認める。 しかし、昨今の子どもたちは、現場を押さえられているにもかかわらず、その事実さえもとりあえず認めない。 これは、最近の不祥事を起こした会社でも同様の事が言える。 これは、子どもたちが"等価交換"を行おうとしている結果と考察する。 |子どもたちの等価交換・・・ 彼、および彼女は自分の行為の、自分が認定しているマイナス性と、教師が下すことになっている処分をまっとうな"等価交換"にしたいと考える。・・・ そこで自己の考える公正さを確保するため、事実そのものを、"なくす"もしくは"小さくする"ことを選んだ。 |義務教育の認識の間違い 義務教育とは・・・両親が子供に教育を与える"義務"であり、 子供が教育を受けることは、"権利"である。 子供は将来、可能性を広げる為に、この権利を有効に活用すべきなのに、 勘違いした賢いつもりの子供は、”この勉強は何の役に立つのか”と教師を試すような質問をする。 こんな馬鹿げた質問には、答える必要もない。 生存権・・・すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、について、"何故、このような生活を営む必要があるの?"と質問するぐらいバカな質問。 |どうして人を殺してはいけないのか? という質問。 こんなバカな質問をする人間には、自分が逆の立場に立つことを考えることが出来ないという想像力の欠如が考えられる。 この質問の正しい答え方は、この質問者の首を締めて、相手の苦しみを理解させるしかないかもしれない。 これは、学ぶことの理由を聞いた子供にも言える。自分が学びの機会を奪われるなんて、全く想像出来ないのである。 この学ぶことの理由について、大人が絶句したり、お粗末な回答を引き出させることに、子供は妙な達成感を得てしまう。これをきっかけに、子どもたちは等価交換することを身体に覚えさせてしまう。 |何もしないことを求められる子どもたち 社会で認められる存在となる第1歩として、昔は、家でのお手伝いがあった。 大人の果たすべきシゴトを、子供がお手伝いすることで、大人から感謝され 少しずつ存在を認められ、少しずつ外の世界へと足を踏み出す。 しかし、今は、家でのお手伝いの機会がなく、逆に大人しくしていることを 求められる事が多くなった。 |初めての社会活動が"労働"ではなく、"消費"である子どもたち 今の子供達は、3~4歳にして、既にお金を持って、買い物をした経験があることもあるだろう。 3歳程度の子供が大人と対等に相手にされるのは、普通ではありえないが、 お金を持つ人間として立ち現れる場合は、その人の年齢、見識、社会的能力などの属人的要素は誰もカウントしない。 ですから、社会的能力がゼロに近い子供達が、贅沢なお小遣いを手にして消費主体として市場に登場した時、彼らが最初に感じたのは、法外な全能感だったはず。消費主体として立ち現れる限り、買う主体の属人的性質については誰からも問われない。 ”ぼくは買い手である”と名乗りさえすれば、1人前のプレーヤーとして参入することが許されるのは、痺れるような経験になる。 すると、何よりもまず対面的状況において、自らを消費主体として位置づける方法を探すようになる。 当然学校でも、同じように”教育サービスの買い手”というポジションを無意識のうちに探す。まるでオークションに参加した金持ちのように・・・。 教師に対して、"で、キミは何を売る気なのかね?気に入ったら、買わないでもないよ!"と。等価交換的な取引の大きな特徴は、"買い手はあたかも自分が買う商品価値を熟知しているようにふるまう"こと。 消費主体にとって、自分にその用途や有用性が理解出来ない商品、というものは存在しない。つまり、学ぶことの意味を(小学生に理解出来るはずもないが)理解出来ず、不要と切り捨てている。 |教育の逆説 教育とは、ある程度成長するまでは、全ての意味を理解出来ないもの。 昔の子どもたちは、学校での勉強、家での労働(どちらも英語でwork)は 同一のもので、一生懸命workすれば、家族や地域から有用な社会的存在として承認された。つまり、”workすることに何の役に立つのか”という問はありえなかった。 それに対して、消費主体で出発した子供達は、目の前に差し出されたモノを商品として扱う。そして、常に値切ろうとします。最小の貨幣で最大の商品を手に入れようとする。 |不快という貨幣 50分間の授業を聞くというのは、子供達にとって、苦役です。 教室は、不快と教育サービスの等価交換の場となる。 例えば、50分授業を聴くという不快の対価として、"教育サービスの価値"が"10分間の集中"と等価であると判断されると、残り40分の不快は、支払うべきではない、ものであるから、私語をしたり、漫画を読んだりして、不快ではない行為に当てられる。 せっかく10円に値切って買うことにした商品を20円出すというのは許されない。同様に10分の価値しか無いと判断した授業を50分間も聴くなんて、許されず、残り40分間は、別の不快では無い行為に一生懸命努力している。 子供達は消費者マインドで対峙している。 |生徒達の意志表示 子どもたちは、一生懸命興味が無いという意志表示をする。 普通に起立・礼をしたほうが、楽なのに、一生懸命ダラダラと起立・礼をする。 これは、いかにも購入意欲が無いという表示で、今から値切る!という意志である。 彼らはただ、自分の不快に対して等価である教育サービスだけを求めている。問題は等価交換が適正に行われることであって、彼らにとってはそれが何よりも重要である。 |不快貨幣の起源 家庭内において、他人のもたらす不快に耐えることを家庭内貨幣として認識する。 昔は、父親が給料を持ち帰ることで、扶養者への感謝を確認することが出来たが、今は給与振込で済ませる時代。 父親の威厳は薄れつつあります。それを取り返す為に、父親が取った行為は、いかに自分が不快なシゴトを耐えているかという事実を疲労感という態度で示すようになった。母親も同様に、家族の家事を耐えること、他人の存在に耐えること、で資産の半分を手に入れる。子供達には生産する能力が無い為、彼らは勉強したり、塾へ行きます。夜遅く帰宅し、彼らもまた、疲労と不快を示します。 家族の中で”誰が最も家産の形成に貢献しているか”=誰が最も不機嫌であるか、に基いて測定される。 |クレーマーの増加 このゲームは、先に文句を言ったモノの勝ちである。 誰よりも先に、被害者のポジションを先取りする能力に長けていく。 瞬間的に、私は被害者-加害者であるあなたは私を不快にする人間、というスキームを作り上げる。 |学びと時間 学びとは、本来等価交換の空間モデルで表象することが出来ない。 それは時間的な現像です。時間的ではない学びなど存在しない。 等価交換とは、2つの物が同時に存在する必要がある。 |母語の習得 例えば、日本人は日本語を気がついた時には習得していた、と思います。 つまり、起源的な学びというものは、自分が何を学んでいるかは知らず、それが何の価値を見出すものか分からないうちから始まるもの。 むしろ、自分が何を学んでいるのかもしらず、その価値や有用性を言えないという、当の事実こそが学びを動機付けている。 |自分探しイデオロギー 自分探し、と呼ばれる行為は、自分の知らない世界へ旅をする行為と言われている。異文化に触れることで、いったい何を見つけるのだろうか。 本来、自分を知りたければ、自分をよく知る人物へロングインタビューすれば良い。つまり、自分探しの目的とは、何かに出会うことではなく、外部の評価をリセットすることにある。 自分探し、という言葉を発する人間の特徴として、内部評価>外部評価が上げられる。自己評価に対して、外部評価が低い。 人々が何かを行おうとする時、その行為の動機がどれだけ個人の心の内側から発するものか。教育心理学の用語を使えば、”内発的に動機付けられているか”どうかによって、私達の社会はその行為を価値付けることに慣れ親しんできた。打算や利害よりも、自発性が尊ばれる。 金儲けや権力、名声といった、自己に外在的な目標を目指して行動するより、自分の興味や関心に従った行為のほうが望ましいとされる。 つまり、”オレ的に見て”有用性が確証されなければ、あっさり棄却される。 |未来を売り払う子どもたち ”何のために勉強するのか?”という言葉は、 回答次第では、納得すれば、自分は勉強するし、納得出来なければ、私は勉強しない、と宣言しているようなモノ。 傲慢さと無知の具合に感動すら感じる。これは、つまり自分の持つ愛用30cmのモノサシで世の中の全ての事象を測りきれると勘違いしている、とても恥ずかしい発言です。 10~20代の学生の手持ちの価値の度量衡を持ってして、計量出来ないものは世の中に無限に存在する。 有用であると判断すれば、学び、有用でないと判断すれば学ばない。 発言の歯切れは良いが、その有用性の判定の正しさはの責任は誰がするのか? それは未来の自分です。”何のために役に立つのか”という功利的問いを下支えしているのは、自己決定、自己責任論です。 |パイプラインの亀裂(リスク社会の若者) 一度パイプに入ると、何度かの分岐を経て、自動的に様々な職業や階層へ振り分けられる。これは努力と成果の相関が確実な過去数十年で成り立っていた。 しかし、昨今、努力と成果の相関が不確実になることで、二極化が進む。 努力が”報われたモノ””報われなかったモノ” 重要なのは、パイプがなくなった訳ではないということ。 大学に行ってもホワイトカラーに職業出来るとは限らない。それは、 大学に行かなくても良い、という意味ではない。大学に行かなければ、 ホワイトカラーになるのはもっと困難になる。 努力におけるごく僅かな入力差が、成果において、巨大な出力差として結果することがある。 |階層ごとにリスクに濃淡がある。 学歴によるパイプラインシステムは、現状傷んではいるが、なくなってはいない。現在も上手に活用している人も存在します。 上層家庭の子どもたちは、下層家庭の子供より成績が良いと認識されている。理由の1つに教育コストの違いがあげられるが、他に重要な要因がある。それは、努力についての信憑性の差です。 努力の成果を享受して生活している家庭に育った子供と、 現在社会的に低い身分にいるが、その原因は自分の努力不足に無いと言い張り、勉強しても意味が無いと公言するような親に育てられた子供を比較すると、決定的な差が生まれることは避けられない。 つまり、努力しても仕方がない、という結論を出しているのは、最もリスクを被っている階層であるということ。 リスク社会とは、そこがリスク社会であると認める人だけがリスクを背負い、 あたかもリスク社会では無いかのように振る舞う人だけが、リスクヘッジをすることが社会である。 |リスクヘッジを忘れた日本人 正しいソリューションを選択しなければならない、というのはビジネスにおいて当然かもしれないが、実際には不可能なこと。 (例:100万円を正しく使う為、協議を繰り返し、協議の為の弁当代が100万円を超えてしまうというジョーク) 正しいソリューションを選択する、ことが当然とされるのは、間違っても命までは取られないという、楽観ベースがあるから、言い続けられること。 日本人は過去60年間戦争から遠ざかっている。(これは幸せなこと) 生死の瀬戸際になれば、正しいソリューションよりも、間違えない為のソリューションを考えるべき。 |日本人の法意識(川島先生) 調停的仲裁は、どちらが正しいかを明らかにすること。(現代の法はこちら) 紛争解決方法は、争いを丸く収めることを目的とする。 当事者も仲介者も誰もがこの解決から利益を得ないという解決方法。 つまり、誰にとっても同じ程度に正しくないソリューションが正しい落とし所であることが多々存在する。 |青い鳥症候群 若い世代が入社直後に辞めていく理由として、頻出なのは やりがいや達成感を得られなかったことを上げている。 つまり、自己利益を最大限に高めたいという、最もな理由である。 しかし、世の中には、雪かきのように、誰からも感謝されず、誰がやったかも知られないけれど、周囲の人から必要とされることもある。 このように、周囲の人の不利益を最小限に抑えるという、大切なシゴトもあることを理解する。 |思春期に引きこもる子供の親の特徴 子供の発信する”何か嫌な感じがする”というメッセージを聞き取る能力が低い。子供の発信する不快なメッセージとは、言い換えれば、製品の発するノイズのようなもの。 ノイズを何かを意味するシグナルとして聞き分けるには、耳を澄まして、子供の声を真剣に聴くしか方法はない。 |失語症の人が言葉を発することが出来ない理由 失語症の人は、相手の気持ちを全て理解してしまっているが故に、何も言葉を発したいという気持ちにならない、かもしれない。 それはニートをにも言えることで、ニートは働く意味、勉強する意味を全て理解した気分になっていることで、あえてニートになることを選んでいるのかもしれない。
1投稿日: 2013.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学ばない子どもたち、働かない若者たち」が社会問題になって久しいですね。 内田先生の鋭い切り口で、フムフムと納得させられます。 例えば、学ばない子どもたち。 物質的な豊かさと利便性が向上した社会において、子どもが成長するときに、「労働主体」として育つのか、「消費主体」して育つのかという点を指摘されています。 「労働主体」の子どもとは、共同体や社会との接点を、家の手伝いなどの労働から身に付けた子どものこと。 当たり前に掃除をし、洗濯や近所の小さい子の面倒を見たりしながら親や周囲の人に認められていく経験を積んできた子どもは、、「なぜ働かなくちゃいけないの?」なんて疑問にも思わないものです。労働に見合う報酬もない中で、時間をかけながら、「しっかりしてきたな」と認められていって育つ子どもです。 一方、「消費主体」の子どもとは、豊かさと便利さの中で、上記の労働をすることも求められず、物を消費するという行動から社会との接点を学んでしまった子どものこと。 お小遣いを持ってお店に行けば、大人と同じようにお客さんとして遇してもらえる。そこでは、持っている価値(金額)で、消費活動が出来る。大人であるのか子どもであるのかは全く関係がない。 いわゆる、瞬間的な等価交換で社会と関わることを覚えてしまうというわけです。 等価交換は、経済の側面からいえばただの価値の移動であり、合理的ではあるけれども、何も生み出さない。交換するその瞬間で行動が完了するので、時間をかけて成長するスタイルにもならない。 そんな「消費主体」の子どもが、学ばない子どになるのであり、その子どもの深層では、「先生の授業は、僕の時間と集中力を注ぐに見合う内容なのですか?」と聞いているというのです。 ですから、「時間・集中力」>「授業内容」となる授業は受けない方が良いと「合理的」に判断するのだそうです。そうやって、学ばない子どもが増えているとの指摘です。 長くなっちゃいました。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学び」も「労働」も、今の自分にはどちらも重要で自分の内に取り込んでいきたいと思う対象だ。 特に「学び」は学生という強制的な場から卒業したらやたらとモチベーションが高まっていることを実感しており、だからこそ「ああこれが大人なのか」と思ったり。 どちらの概念も、モチベーションのポイントとなるのは参考となる人を見つけられるかどうかだと思う。子どもに対して「学び」を求めるのならば、まずは大人である自分が「学び」の姿勢を見せていき、また「学び」や「労働」から得られる喜びをしっかりと伝えていけるようにしなければならない。
0投稿日: 2013.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもたちが、学ばないらしい。 学校で先生に、「それを勉強する意味はなんですか。なんの役に立つんですか」と聞くらしい。納得できる答えが返ってこなければ全力で授業を聞くまいとするらしい。そしてそういう子どもたちが大人になって、働く意味や見返りに納得できずに、労働から遠ざかっていくらしい。 「最近の子どもは」などと言える立場ではないけれど、この国の将来を思ってうすら寒くなってしまった。筆者の考える子どもたちが学びや労働から遠ざかる理由に、すごく納得してしまったからだ。 子どもたちは、学校で学び始める以前に自らを消費者として確立してしまっているから。自分が納得できるものしか買わない。少しでも安く、自分に有利な取引をしようとすることに、慣れすぎてしまっているから。 そして今の社会では、努力したところで幸せや安定を得られるとは限らないということを、子どもたちは肌で感じ取っているから。 学びとは、自分を変えていく能力。学ぶことの意味は学んでいる最中には分からないもの。教師や他者が答えられるものではないのだ。その価値は、未来の自分が判断するしかない。 非常に示唆に富んだ内容でした。子どもたちに、楽しく生きている大人の姿をたくさん見せてあげたいと思った。いるんなことを知りたい、やってみたいと思える希望を持ってほしい。世界はそんなに捨てたものでもないはずなのだ。
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学ばない子どもたち/働かない若者たち」のサブタイトル通り、学びから逃げ、労働から逃げ、自ら下流に向かう子どもたち、若者たちの傾向を分析した本。 2005年くらいから、講義を受ける学生たちが、ふてくされているように見えた。大学1年生も同様だった。高校1年生から、すでにその傾向が表れている。 なぜ、こんな風になったのか。長年の疑問が一気に解消されたような気がした。 この本の主張は以下の3冊を基礎にしているところが大きい。 苅谷剛彦『階層化日本と教育危機~不平等再生産から意欲格差社会へ~』 諏訪哲二『オレ様化する子どもたち』 山田昌弘『希望格差社会』
0投稿日: 2013.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったです。「先生の話を聞かない生徒」は積極的に話を聴こうとしていない、という着想から始まる考察、でしょうか。刺激的でした。
1投稿日: 2013.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすいとは思う。 印象としては「最近の若いものは」という内容が殆どかと。 はっきりとは論証されていない仮説の上に、同レベルの仮説をのせ、その上にさらに同レベルの仮説をのせた上で、それに基づくストーリーを延々と述べている感じ。 ものすごい砂上の楼閣感。 〇〇という話と△△という私の仮説は同じことだ、という言い回しで述べられた内容は同意できないものが多い。無理に例えなくてもよいのに、と思う。
1投稿日: 2013.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたま人に借りて3日で読みました。 <要点> ①等価交換システムとしての教育 教育をサービスととらえ、それに答えられない先生、学校は要らないと考える人が増えたが、教育とはそもそも先の見えないもの。(絶対的な師弟関係の間の信頼を例に挙げていた)また、子供が発するノイズは人生全体の中の一部に過ぎないことがあるのに、すぐにペイを求める大人が多い。これはビジネスの論理と同じだが、教育はそうじゃない。 ②リスクヘッジ 常に正しい選択を選ぼうとし、リスクヘッジを考えない。(リスクがあったとしても今の日本で死にはしないから。)椅子取りゲームで落ちる人が居ることは分かっているのに、椅子取りゲームで椅子を取れることしかイメージ出来ない。これは国際外交の論理と同じ。 <分からなかったこと> 周りの学力が下がることで自分の位置をキープ出来ると考えるから、足の引っ張り合いをし、それが結果全体のレベルを下げている、という意見についてはよく分からなかった。→人が勉強をしないのが得なのは分かるが、だからといって「自分が」勉強しないのが得と思わせる原因は何かが分からない。その理屈だったら、一人でこっそり勉強するのでは?
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の_内田樹先生は、神戸女学院大学文学部教授。このBooklogでも、先生はえらい、ためらいの倫理学などを紹介してきました。 私が_内田先生の著書を読むようになったのは、まだサイクリングを始める前に遡る。高くなってしまった血圧を下げるために江戸サイをウォーキングしていた頃。その日は、たまたまラジオを持って出かけていました。大竹まことさんのラジオ番組で、先生の「先生はえらい」を紹介していたのだ。この偶然の重なりによって、私は先生の著書に出会ったのです。 この本も凄い本です。日本の子供たちの学力低下は、ゆとり教育のせいにされているようだが、先生は、この問題の違う切り口を見せてくれています。 学びの場で、学ぶことに対して、教師に「先生、これは何の役にたつんですか?」と聞く子供たち・・・何の役に立つか知らなければ、自分にとって有益な情報でなければ、学ぶことを拒否する子供たち・・・ 内田先生は「起源的な意味での学びというのは、自分が何を学んでいるかを知らず、それが何の価値や意味や有用性をもつものであるかも言えないところから始まるものなのです。学びのプロセスに投じられた子どもは、すでに習い始めている。すでに学びの中に巻き込まれていしまっているのでなければならないのです。学び始めたときと、学んでいる途中と、学び終わったときでは学びの主体そのものが別の人間である、というのが学びのプロセスにに身を投じた主体の運命なのです」と書いています。 この考え方は、養老孟司先生が仰っていることにも相通じることであると思います。つまり、学んだことが何の役にたつかなんてことは、学ぶ主体が変わる(成長して視点が広がる)のだから想定できないわけだし、現時点の視点でこれから学ぶことを評価するなんてことは非常にナンセンスだということだと思います。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ労働と消費についての講演録。 2005年の講演だが、書かれていることは全く色褪せていないどころか最近になってようやくみんなが何か変だな?と感じ始めたようなことばかり。 相変わらず消費者は偉い風潮は強まる一方だし、教育がビジネス用語で語られる。 労働は、等価交換ではない。 物心ついたときから、いろんなものを受け取って生きている、だから、それを返していかなければならない。そのために自分が差し出せるものを差し出す、ということが労働である、と。 自分もなかなかに消費者マインドが浸透しているようだ。 まずは時間性を取り戻していきたい。
0投稿日: 2013.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代人の性格をうまく表した本だと思う。 現代の若者は確かに、消費主義的で時間軸が 昔と異なっているのかもしれない。ただ、そこまで現代人に浸透しているのか、 気付かないほどにまで、この文化がもう浸透しきっているのか、どうなんだろう。 とにかく、現代人のモチベーションや原動力がわかり、とても為になった。 資本主義の限界と言われるようになり、 これからの日本は消費主義的性格が抜けていくような気がするけど、将来の日本が楽しみだ。
0投稿日: 2013.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない子どもたちはあらかじめ、自分にとって価値があるのかを判断して学ぶが、学ぶことは知らないことを吸収することであり、知らないものに価値判断を加えることは難しい。よって自分の価値判断に依存して学ばない、働かない若者を下流志向と著者は表現しているが、私はこう思う。学んだあとでさえその学問や労働行為に価値判断を加えることは難しい。なぜなら何を学んだかは人によって様々だからである。ただ学ぶ行為を未知への探究心、積極性と捉えるならば、人生を歩む上では他者とのコミュニケーションが欠かせない以上ある程度は求められる行為であるとは思う。他にも消費者の捉え方や労働が本質的贈与であるということなど、前提を記した上で論を展開しているためいい意味でも疑問点を掘り下げて読める本だと思います。
0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない子どもたち、働かない若者たちを、独自の視点から分析した一冊。 現代の子どもたちは、あまりに幼いころから「消費主体」として自立してしまっているため、教育という「商品」を、我慢して勉強するという「苦役=貨幣」で等価交換しようとすると筆者は指摘する。 最近は、学校でも職場でも、成し遂げるのに労力のいる課題を与えられると、「それは何の役に立つんですか?」と聞く人が多い気がする。 そこには、あらかじめ意味や成果が見えないと労力をかけたくないという、金額に見合う商品やサービスを購入したいと思うのと同じ消費者的視点があるということだ。しかし、学びと経済活動を同じ構造のものと捉えてはいけない。 塾で教えてた頃も、「勉強って何の役に立つの?」と問われてよく困った記憶がある。でも、今ならこう言うだろう。 「何の役に立つかお前自身がわかっていないから勉強するんだ」と。 まぁ、そんなことで納得する子どももいないだろうが、少なくとも、「勉強なんて社会に出たら何の役にも立たない」なんて大人が言ったら絶対ダメだ。 極端すぎる表現や、決めつけに過ぎると感じる箇所もあったが、総じて納得できる内容だった。
0投稿日: 2013.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がファーストゆとり世代なので、指摘されてる内容を実感として納得。言われてみると確かに「解らないものを解らないまま放っておく」ことに抵抗ないし、逆に、理解するためのコスト(金・時間・労力)を払うことへの心理的ハードルは結構高い。そして思考スパンが短く、時間の概念に弱い。“未来の自分”が思い描けない。…などなど、当事者ですら自覚無かった問題をここまで鮮やかに切り出したのは見事としか言いようがない。
0投稿日: 2013.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ等価交換する子供達。 今の子供はなぜ学ぼうとしなくて、なぜ若者は働こうとしないのか、働くっていったい何なのか。答えと対処法が打ち出されているように思えて衝撃的でした。 等価交換する子供たちのテーマでは深く納得できました。「どうして教育を受ける権利を使わないといけないの?」という問いが出てくるという問題。そして、本当に大人が否定出来ていないという事実が悪いのも確かだと思う。 当事者である子供や若者、そして労働者である大人まで全員に是非読んで欲しいと思う。
0投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない子ども、働かない若者を一般的な論理とはまったく違った視点で解説する。 大学の先生らしく、まわりくどく難解な表現ではあったが、なぜ学ばないのかなぜ働かないのかということについては概ね理解でき、納得できた。 教育自体が経済合理性を追求した消費主体になってしまっていることが原因だということだが、それに対しての明確な対処方法は論じられていない。 自分なりの答えを出して行くことが必要だと思う。
0投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直、これを読んでいない教育関係者、人材関係者はにわかと言いたいくらい今の若者を説明している本。2ページ毎にドッグイヤーをしてしまいました(意味がないw)。 データがないとかそういう人もいるんだろうけど、ぼくは理論的にはすっと入ってきた。 そして、この本を読んでぼくの方向性は間違いないと思ったし、この考え方を世の中に少しでも広めていこうと思う。
0投稿日: 2013.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない、働かないというのは「消極的」な現象と捉えられがちだが、 今の若者は「積極的に」学ばない、働かない。 その理由をスリリングに論じた本です。 教育の分野ってのは、新自由主義的市場原理の弊害が一番分かり易い分野ですよね。 現代の子供が消費主体として人格を確立していることが…ってあたりは納得。 ニートに関しては、半分納得。 内田せんせいの好きな、贈与経済やら反対給付ってのは、僕はあんまり好きじゃないんで。 だいたいいつも内田先生が言ってることと内容的には一緒なので、 ★3つで。
0投稿日: 2013.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現代の子どもたちの話・・と思って読み始めてみたのだけど、どうやら「学び」から「逃走」する世代って、ぎりぎり私たちあたりまで含まれているらしい(?)ということに途中で気づいた。とすると、もしかして私も「逃走」してきた一人なのか・・と自分を顧みながら読んでみた部分もある。 ちなみに「学びからの逃走」という言葉は、東大の佐藤学先生が言い始められた言葉だそうで、この先生のほか何人かの方の著作を参考に、「すべての日本人が率直に議論の足場を作ることが本書の第一の目的」(まえがき)とのこと。講演されたものを本としてまとめられたのだそうだ。 家族も後で読むかもしれないと思って、書き込む代わりに、オレンジ系の広めの付箋に感想を書き込んで貼り付けながら読んだら、黄色の装丁に鮮やかなビラビラがいっぱいつくことになってしまった。途中「地域差」を感じる発言や、少々違和感を覚えた部分もあったのだ(特に第一章)。その一方で「リスクヘッジ」についての部分は、私自身がこの言葉についてあまり知らなかっただけに、非常に示唆に富む部分だと感じた。 それと若干、ステレオタイプかな・・と思える部分と、ちょっと矛盾してるんじゃないかと思う部分、定義があいまいじゃないかな・・と思える部分もあった。ただ、まあいろいろこうやって議論(思索)を重ねるというところで、この本の「目的」は果たせているのかもしれない。
1投稿日: 2013.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強から逃走する子ども、労働から逃走する若者についての非常に鋭い分析。 幼児期に経済主体として自己を確立してしまった私自身の下降もスッキリ説明できる。 まっ…いいか。
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の『無知』に頭の真がしびれるような感覚。頭のイイ人に合った時の衝撃と同じものを、この本から受けました。 内田さんのツイートや、ブログは時々拝見してましたが著書を読んだ事が無く、たまたま平積だった本書を手に取りました。 今の子供たち。学級崩壊やニートも問題について、内田さんなりの仮説を説いています。 仮説ではありますが、裏付けられたデータがある。恥ずかしながら、驚くことが多かった。 私達世代の常識としては、日本の子供は学力が高く先進国の中でも上位1~2位に位置と言う事。それが今では・・・ 数年前、GNPが中国に抜かれたと言うニュースを聞いて驚きましたが、そんなレベルの話じゃない。 しかもそれが問題視されていない・・・知らないと言うのは怖い事です。
4投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ考察がおもしろかったです。 全体が下がれば、自分はそれほど努力しなくても集団の中では上位でいられる。 自分のまわりが一緒に下がれば、自分の位置を下に感じることもない。 教育の機会も経済で考えるとマイナスに思える。 不思議です。
1投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの学習への動機づけについての考察は、斬新で非常に興味深いものであった。最近の子供は昔に比べ、家事労働をしながら、労働主体としての意識を醸成するよりも先に、買い物という社会的な体験を通して、消費主体として自己を形成してしまう。そのため、教育に対しても、自らの消費(学習という苦役)と同等の対価を求めてしまうが、そもそも教育というものは、その受益者が、どのような利益を得ているか、もしくは得られるのか、ある程度教育が進行しなければ(場合によっては教育課程が終了するまで)、言うことが出来ないものであり、その逆説の存在こそが、現代の「学ばない子供」を生んでいる、というものであった。 「なぜ勉強するのか」、「勉強が何の役に立つのか」という問いかけは、それ自体が、自分の持っているものさしで世の中の事象を全てを押しはかろうとする傲慢さの表れでもある。これらの質問に対する、大人の健全な回答は、経済合理的な利益誘導ではなく、絶句なのである。 全体を通しての作品評価は、尻すぼみ感がどうしても拭えず、★3つ。上述した通り、前半部分については、著者の(被害者的立場での)現代の教育政策や思想に対する批判や考察はなるほど納得できるものが多い。しかしながら、それを受けての後半部分では、自らの政策的な提言は皆無に等しく、(インタビューの内容を好意的に汲み取ったとてしても、)道徳の教科書に出てくるような精神論や「携帯電話を無くす」といったような実現可能性が低く、時代錯誤な提言に終始している。そのオチは、いかにも人文系の大学教授らしい。
0投稿日: 2012.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
諏訪哲治という方の「消費主体としての自己」の概念を中心にして、学ばない子どもたちを理解していく第一章にはかなり面白く読みました。何で勉強しなきゃいけないの、これは何の役に立つのという疑問に対する一つの納得いくスタンスを知ることができます。 その後もリスクヘッジ、自己決定・自己責任論など、全く新しい考え方ではないものの、分かりやすく論じてくれます。最後の第四章「質疑応答」も魅力的な話ばかり。個人的には「余計なコミュニケーションが人を育てるのです」(p254)に共感、納得。
0投稿日: 2012.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界は広くて、知らないことはまだまだあって、分かったふりをして生きていくのはやだな。 「なぜ学ぶのか、学び終わったときに初めて分かる」という話が印象的だった。
0投稿日: 2012.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
教育・働くということを経済の論理である等価交換という枠組みに当てはめて述べている評論。 早くから消費行動を経験する現代の子供たちは、教育に対するリターンを消費行動(例えば商品を買う行為)と同じくすぐに期待する。しかし教育とはそもそもそういうものではなく、学んでいくうちに後から価値が付いてくるもであると著者は主張している。 私もこの勉強をしてなんの役にたつのかと考えることがしばしばあったが、読みながらそもそもその考え方自体がおかしいという良い気づきがあった。
0投稿日: 2012.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文章理解の問題を解いていて、一番面白い文章と内容だと思った人。それで読んでみた。 たいへん有意義だった。第一章の『学びからの逃走』は平成の馬鹿者たる、実際に逃げ続けてきた俺をして納得せしめるものであった。特にこの章は広く知られるべきだろう。子供が学力から努力して離れていること、おとなしく授業を受ける苦役を貨幣として認識していること、自己決定・自己責任の穴、どれも的を得ている。これらに加え、俺のように実際にこの子供の世界を生きてはいないのに、自分探しの真の目的をここまで言い当てている。素晴らしい洞察力だと思う。 第二章のリスクヘッジの話も面白く、納得させられた。しかし第二章以降の、『ニートの面倒をより深く見てあげる』などの施策は、実現不可能なことに思える。今の社会では、お互い様など思える人間は極めて少数派だ。文中にもあったと思うが、誰しもが他人に迷惑をかけられることを恐れて、迷惑をかける人間を軽蔑する。内田樹さんのような人格者でなければ、自分で否定している施策であり、思索のように思える。しかし、目指すならばそれが成り立つ社会を目指していくべきだとも思った。この本は売れない。
0投稿日: 2012.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学ばなくなった子供たち、働かなくなった若者たち。なぜ、そのような社会になってしまったのか?それには、誰のせいでもなく、社会構造の仕組みが関係していた。子供が勉強するのに「なぜ?」と理由を求める意味。社会と子供の初めての接点が"消費者"であるという考え方には、考えさせられると同時に、なるほどなと思う部分があった。
0投稿日: 2012.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体として、検証不可能だが面白い視点を与えてくれる。 ●面白かった点 消費主体だからべんきょうしなくなったという考え。いくらでも反論が思いつくがなかなか面白い。 今でこそあたりまえのリスクヘッジなどの概念が2002年にはなかったのかと思うと面白い。みんな1点張りで賭けて、商社とか金融業とかない現代を想像させてくれるトテモトテモ面白い視点でした。 ●気になった点 残念なことに2章はほとんど賛同できない。冒頭でリスク化を安定性の欠如と説明して、リスク=不確定さ(ボラティリティ)と説明しているのに、途中で単なる危険性の意味で使うことがあるんで、そもそも論旨が意味不明。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ下流志向ということで、 現代の若者や子供たちというのは、努力して下流へ下流へと自らを追いやっているという視点から、 その現象に対しての内田氏なりの解説を行っている。 講演が行われた当時高校生であった自分または友人にとってもあてはまるようなところが多々散見されていたので、内田さんの解説や推察というのが、腑に落ちやすかった。 現代の様々な問題点を考えるうえで内田氏が繰り替えし指摘している、経済合理性、無時間的思想絶対主義的風潮の蔓延によるものということは正しいと思われる。 今後の日本の行く末や自身の志向性などをもう一度考える点においても良書だといえるだろう。 あと、大変読みやすいのもよかった。
0投稿日: 2012.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は2005年の講演会がもとになっているにもかかわらず、今なお、状況は改善されていない。むしろ、もっと悪い方向に進みつつあるかもしれないと感じた。こどもたちの学びからの逃走も依然としてあり、また、就職も厳しい状況が続いている。学校や教師に求められる対応や能力も増すなかで、教育のありかたについて改めて考えさせられた。 私自身、下流志向の真っ只中にいる。その下流志向が分析されていくのがなんだかスッキリするようで、おもしろくも感じた。一方で、時には自分にも当てはまるようでドキッとしたり、これからの自分のありかたについて考える場面もあった。
0投稿日: 2012.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には「勉強したくない」「働きたくない」という人はどうぞご自由にと思うわけですがな.ただし「なぜ学ぶのか」は考察しがいがある.
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ教育は一朝一夕に行くものじゃない。 今の国は一体どんな子どもを育てたいのだろう? 子どもが大人よりも先に悪くなるなんてないと信じたい。
0投稿日: 2012.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田氏の著作を読んだのは初めてやけど、かなりおもしろかった! 現代の「学問からの逃走」「労働からの逃走(ニート)」という問題が生じる原因を、労働主体と消費主体という観点から分析していたのは、言われてみれば確かにと思わされることが多くて、納得させられた。 経済合理性が教育の中に持ち込まれることで、教育に対する考え方も大きく変わってきて、それが新たな社会的問題の原因になっている。というのは、実情に即している見方やと思う 「なぜ勉強するのか」 その理由を考えようとすること自体、おかしいということ。 学ぶことに何かを求めるのではなく、学んでみて何か気付きを得れるかどうかが大事。 それが筆者の考えであり、それも間違っていないとは思う。 けど、それでも時代は動く。 時代が動けば、人の考え方やあり方も変わってくる。 上のような質問に対する答えを用意しなければならないこの時代を嘆くだけでは何も解決できない。 今自分たちにできることは、上の質問に対して、子どもが納得できる答えを用意すること。 それが、教育者や大人の仕事やとオレは思う。
0投稿日: 2012.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「消費主体」としての人間はすぐに価値が出ないと何もしない無時間的な人間である。 キブアンドテイクが一瞬で出るものにしか興味がわかなくなるというのはこういうことか。そりゃ勉強しなくなるよなと妙に納得できる。
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見すると、えらい学者さんが 「今時の若いものは・・・」と嘆いてるだけのように見えるのだけど、 きちんと、なぜ、そんな事態が起きているのか、 を歴史的なバックグラウンドとともに明示してるので説得力がある。 こどもが労働ではなく消費行動により社会主体を確立したことで、学習は自分になんのメリットがあるのか? という交換性を求める。 不快が貨幣として流通し家庭は不機嫌により維持され(ここが実感としてすごい当てはまった)クレーマーが増加する。 物事の価値や意味にとらわれ実学が人気を集める一方芸術など教養が廃れる。(国際競争力は低下するのではないか) 必要以上に自己責任を唱え弱者を切り捨てるのではなく、弱者には手をさしのべこれから陥ろうとしてる人にはやめた方がいいよと言う。 そういうことができなきゃ日本は這い上がれないでしょうな。 とても難しい本質に迫る本でした。 とにかく私は学びたいと思った。
0投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ消費主体として、即時的等価交換を求める心性(典型的なのが、「これやって何の役に立つんですか?」という質問)が、学生・生徒、若年社会人に蔓延しているという警鐘。
0投稿日: 2012.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びからの逃走、労働からの逃走、 経済合理性に基づいた行動がいきすぎていることがその原因 この本書いてあることはそのとおりなんだけど、でも何か違和感が残る もう少し考えたい
0投稿日: 2012.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
市場主体と労働主体の2つが述べられている。最近は市場主体となり、教育や労働に対して、等価交換を求めるようになってきた。労働主体という考え方がとても新鮮な概念でした。自分も市場主体に偏りがちな気がした。市場主体の等価交換は無時間であるが、逆に労働主体は時間の概念がある。時間性への回復という点で、登山が労働主体に通じるものがあるなと思いました。うまく咀嚼できていないですが、新しい概念を教えられました。
0投稿日: 2012.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変おもしろかった。久しぶりに読書の喜びを感じた。 無時間的交換という考え方を頭に入れると、いろんなことが、見えてくるように思えた。 なんで勉強するんだという問いには、言葉につまるというのが正しい反応。と本の中で言われていた。
0投稿日: 2012.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現代の子供たちは就学前に労働主体としてではなく、消費主体としての自己を確立している。それにより学びを単なる等価交換と見なしている。学生たちの対価は「不快」である。「この授業は十分程度の集中の価値しかない」と思えばそれ以上は対価を「払わない」のだ。 消費社会のうねりの中で、生き残るためにはそうするのが利口だと思ってやっているのだから、不真面目というよりもむしろ真面目と言っていい。 学生は学びというものをコンビニの商品と同じと考えている。対価を支払って商品を受け取るのは、ほぼ同時に行われる。これを「無時間モデル」と呼んでいる。 しかし「学びは市場原理によっては基礎づけることができない。」 学びというものは時間的・身体的なものだ。学ぶことによって刻々と自分自身が変化していく。始めたころの自分とは似ても似つかなくなっている。そこにこそ学ぶことの意味がある。 「努力が報われる」は本当? リスク社会が進むにつれて上層階級と下層階級ではその努力信仰にどんどん開きが出てくる。 格差とはせんじ詰めれば「努力する能力」の差の開きのことじゃないだろうか。 「リスク社会とは、そこがリスク社会であると認める人々だけがリスクを引き受け、あたかもそれがリスク社会ではないかのようにふるまう人々は巧みにリスクをヘッジすることができる社会なのです。」 でもって勝手に格差が広がっていくなら現状維持=リスクヘッジも立派な生存戦略であろうと。 作者がいうには「個人でリスクをヘッジする」ことは原理的に不可能なんだそう。 自分がダメなら誰かに頼れる、そして相手がダメなら面倒を見るといった、いわば「迷惑をかける・かけられる」という相互扶助的な関係性において初めてリスクヘッジが可能になる。 相互扶助的な関係は「自己決定・自己責任論」とは対の関係にある。言いかえれば、相互扶助とは自分の利益わがままはひとまず置いておいて、他者のためを考えて行動するということじゃないかな。 逆に「自己決定・自己責任」を取るならば構造的に孤立せざるをえない。そしてリスク社会において孤立することは進んで弱者になることを意味する。「リスク社会には自己決定・自己責任を貫けるような強者は存在しない」のだ。 「日本では、社会的弱者が進んで差別的な社会構造の強化に加担するという仕方で階層化が進んでいる」という指摘はなるほど、と思った。端から見たらニートなんて自ら進んで下降しているようにしか思えないけども、そうならざるをえないという社会構造があるのですね。 ……とか言って、僕にしろここに書かれている「若者」と大差ないので、「雪かき仕事」の価値を理解しないとか、物事を時間的(つまり迂回的)に考えられないとか、客観的に見ると明らかな挫折であっても、そこから抜け出たことを「成功」とカウントしてしまうためにまた同じことを繰り返すだとか、とても耳が痛いですね。 それだけに時間と身体性の回復のためにはどのような教育をすべきか、というのは今後とても気になるところ。 師匠と弟子の関係性についても新鮮だったので、こちらも気になる。
0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹さんが、珍しく教育一本について考えた一冊。 ちょっと難しくてわかりづらいところもあったけど、全体としてはおもしろい。 不快貨幣という概念、時間性の回復策は一日のルーティンをきちんと守ることという話がめちゃくちゃ印象的でした。 あと、内田さんがやろうとしている「道場共同体」がすごくおもしろそうで、気になる。
0投稿日: 2012.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ自己決定・自己責任論を真っ向から批判。現代人は骨の髄までグローバル資本主義が染みついてるんだなぁと実感。えぇ私自身、下流志向に侵されている部分がたくさん…。 震災以降方向転換を求められている今、何か指標になるものが見えた気がした。日本人が読むべき1冊だと思います。
0投稿日: 2012.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだ内田樹さんの本がこれ。無意識に積まれ散乱してた社会への疑問や思いが、一気に整理整頓され、いつでも言葉にして取り出せるうに目の前に出されたという感じの衝撃を味わった。非常に影響を受けた本。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ朝日新聞に著者の記事が出ていたので、興味を覚え読みました。 著者が考える「何のために学ぶの?」というところが、この本の中で強く印象を受けた部分です。 小学校1年生の教室で、先生がひらがなを教えようとすると、「先生、これは何の役に立つんですか?」と聞く子どもがいるそうです。著者は、子供が消費主体としての自己を確立をしており、労働主体や生活主体の自己が確立できていないので、このような問いかけが生まれると書いています。学びとはそれが何に役に立つかわからず、どんな価値を持つか自分の度量衝では計測できないからこそ、学ぶ理由だと書かれています。 ひらがなが読める大人はそんな質問はしないと思いますが、小学1年生が理解できる範囲で、この質問の答えを説明するのは難しいかもしれません。 この話を読んで、大人も実は変わらないのではないかと思いました。私は社会人の大学院に行っていましたが、人から、「何のために行くのか?」とよく聞かれました。自分では、(昇進とか)すぐ結果の出る利益のために行っているつもりはなかったんですが、何のために通っているかうまく説明できませんでした。 この本を読んで、自分が学校に通った理由がよくわかった気がします。
0投稿日: 2012.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ学級崩壊やニートの問題について説得的な論証がなされており、興味深く読めた。 社会学というより、論理に論理を重ねた哲学的な論証が読んでるこっちにも頭の体操になる。 エビデンスがないのはこの手の論証には仕方のないことか。
0投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強しない子供にせよ、働かない大人にせよ、そうしようと努力してるんですね。確かに、当たり前に教育を受けて、勤労する義務がある中で、それに抗っていくのには相当な体力も要るはず。なるほど。 社会への参入のスタート地点として、消費者としての立場から入る、っていうのも言われてみればその通りで。人生のそんなに早い段階で、金銭に対する感性が身についてしまうとなると、三つ子の魂~ってことで、その後の人生に大きな影響が及ぶことは想像に難くないし。 自分が育児する立場になったとき、もう一度紐解きたい本ですね。
0投稿日: 2012.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の将来に価値があるものしか勉強しない 非常に単純で明快なロジック しかしこのロジックが教育に持ち込まれた時、学ばない子供を量産する なぜこのロジックが学ばない子供を生むのか 学ばない子供たちと若者はどんなふうに今生きているのか 学びとはそもそも何か 現代の教育とこれからの生き方について、鮮やかに述べる教育論
0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ学歴社会というのは、知識や学力で計られているのではなく、 わからないことに対して敬意と忍耐を持って静かに向き合ってきたことこそが、評価されているんだ、と思いました。
0投稿日: 2012.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログアプローチの方法が興味深かった。最初に「消費」したことの影響が絶大であるとのこと。現状からどう解消するのかが問題となると思われる。
0投稿日: 2012.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は結論は至極まっとうで、保守的とも言えるところに行き着くのだが、現状分析の手法は他に見られないほど独特。マルクス経済の理論には今日的消費社会は全く想定されていなかったが、消費社会の病理の分析に応用したらこうなるという試みとして読める。 生産主体と新しい消費主体といの違いは前者がハイデガー的な「時熟」の機会に触れうるのに対し、後者は無時間的な世界経験をし続けるということだ。つまり、生み出し築き上げていくという「暮らし」と、商品の消費として構成されていく「生活」との違いと言い換えてもよい。その消費生活は結局「何ものをも持っているが実は何ものも持っていない」という過保護のアホの若者ばかりを生んだということだ。加えて、著者の言う「自己決定フェティシズム」という状況が背景にある。自己決定の押しつけ(みんながSMAPの例の歌を声高らかに『歌え』というファシズム)の論理が反転すれば、そこから零れる子供たち(つまり「イケテナイ」者たち)は、落伍者となるより道はないという訳である。携帯やツイッターなども同じ、はしゃいで調子に乗ってる奴が勝ちという社会を生み出すことになるが、著者は「経済合理性の原則が社会のすみずみにまで入り込んだ」せいだと言う。ネオ・フランクフルト学派とでも言いたいような理論展開で興味深い。 経済合理性の教育では、時間性の欠落した「実学」ばかりがもてはやされ、「シラバス」や「単位」といったアメリカの工場で用いられるjob・discipliningの発想が蔓延する。「知性」とは「自分自身を時間の流れに置いて、、自分自身の変化を勘定に入れること」であるが、正反対の「無知」への固着が現在の教育破綻を生み出した。 また、ブルデゥーの「社会資本」の概念を持ち出すが、著者は神戸という狭い場所で「上と下」の差がきつい場所に住んでいることも現状がリアルに感じられるのだろう。 ところどころに飛躍や無理があるが(第1章「学びからの逃走」の「不快という貨幣」は納得させられない)が、結論に落ち着く三点は次の通り、1、師を持つ・私淑する。2、「おせっかい」の復権。3、ルーティンな生活の持続となる。1は、歴史教育 2は、共同体、3は農業といいうことにになる。 ともかく多くの示唆を与えられた。疑問は一つだけ。日本国憲法という主体性の放棄の権化を著者が擁護するのは如何に?という点である。
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://kumamoto-pharmacist.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-b9fa.html
0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近の若者は.. と、頭ごなしに批判するでなく、 冷静に考察した一冊。 これで内田さんのファンになる。 こうして俯瞰しつつ、論理的に組み立てられる人間に、 自分もなろう↑
0投稿日: 2012.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の若者は学ぶことや働くことから逃避して、自ら下流を目指すという、恐ろしい現代志向を解明した(かもしれない)怪著。「自己決定・自己責任論」の欠陥、下流志向というイデオロギー形成を促す消費主体の自己形成とは? 「“学ばない”ための真剣な努力」という恐怖。
0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ(「BOOK」データベースより) なぜ日本の子どもたちは勉強を、若者は仕事をしなくなったのか。だれもが目を背けたいこの事実を、真っ向から受け止めて、鮮やかに解き明かす怪書。「自己決定論」はどこが間違いなのか?「格差」の正体とは何か?目からウロコの教育論、ついに文庫化。「勉強って何に役立つの?」とはもう言わせない。
0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の子供たちはなぜ学ばなくなったのか。自分自身にとてもあてはまるところがあって感心してしまったが、一方でちょっとショックだった
0投稿日: 2012.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいくうちに気付いた言葉があった。それは「情けは人の為ならず」。 今の社会というのは、今この努力をしたら、すぐにその成果を等価交換として得られなければならない、という考えが基本となっている。このビジネスライクな「ゼロ時間市場原理」を全ての生活活動の基本としている所から、様々な歪が生じている、というのがこの書の考えだ。 しかし、「学習」や「貢献」といったものをこの公式に当てはめることはできない。今この「学習・修行」をしたら、即、何かを得られるといったものではない。その「学習・修行」に向き合うその過程において、そこにつながる様々なものから得られるのであり、その過程が終了した時にその学習なり修行なりの価値がわかる、といったことが理解されない。 かつての時代はこういったことが常識的であり、私たちは何らかの形でそこへ帰る必要がある。 この書の元となった講演は2005年のものであるが、2012年の現代において、リーマンショック・震災を経て後、この行き過ぎたグローバル化からの反動を予見したような表現が見られることに気付くものである。
0投稿日: 2012.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ下流というとはやりにのってる臭くて好かんかったが面白かった。最初の方の仮説は首をひねる箇所も多かったが、後半の方は確かにそうやなーと頷きながら読めた。
0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ相方に借りた。 釈然としない部分もあるけども、面白かった。 相方の考え方は結構これに影響受けてるのかな。 自分は普通科高校だったから、という理由だと思いたくないのだけど、疑問に思う/不思議に思うアンテナが低いなぁと思う。悩ましい。 もっとちゃんと生きないと ※本の感想はあんま関係ない
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の書き出しは、 「学ぶことや労働することから逃走する人々が生まれつつあるけれども、その外部要因を明らかにする&そーいう人々が増えると日本の先は暗いから対処法を考えよう」 と始まります。 しかし、そもそも論の前提条件である「逃走する人々」の存在や定義に、客観的かつ定量的なデータがないままにグイグイ話が進むんで、 そういうアプローチに慣れてない私は、激しくコケてしまいました。 どういうセグメントの人の内、何割がそういう傾向にあって…その値は有為かそーじゃないかと前提条件決めてやらないと、 以降の主張って著者の妄想じゃん! と思いました。 それとも、綿密に定義や数値化するまでもなく、そういった傾向の人々はすでに顕在化しているのが明らかだから割愛ってことなのかな。
0投稿日: 2011.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ”現代社会の刹那性”を教育と労働の面から語ってくれてる感じ。 ここまで深く掘り下げてないけど(掘り下げれるわけもないけどw)なんとなく考えてたようなことが述べられていたのでよかったです。 ところどころ反論したいとこあるけど概ね納得できました。 さすが樹先生です。 第4章のQ&Aが結構おもしろかった。 ”親密圏の構築”ってのがいいよね。 深すぎず浅すぎず、そんな感じ。
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一章 学びからの逃走 「等価交換」でものを考えるこども。自分が支払う【苦役】に対してどれだけの【対価】が支払われるのかを考えている。これは、労働主体ではなく消費主体として自己を確立していることに起因する。 「シックス・ポケッツ」がもたらす消費主体としての自己の確立。 不快感を表した方が、交渉をより有利に進められるという価値観の広がり。 しかし、そもそも… ★【学び】は等価交換の空間モデルによって表象することができない。それは時間的な現象である。そして、時間的でないような【学び】は存在しない。 第二章 リスク社会の弱者たち 「勉強努力に対する確実性」がなくなる事態が生じている。 努力におけるごくわずかな入力差が成果において巨大な出力差として結果することがある。 リスク社会では階層ごとにリスクの濃淡がある。さらなる二極化の促進。 ★このリスク社会における生存競争において有利な位置を占めているのは、僕たちの社会が努力が必ずしも報われないリスク社会であるという基礎的事実に逆らって、依然として努力している人々なのです。 出身階層の影響を受けた「努力の不平等」。 リスクヘッジの重要性。「落としどころ」を考える。 ★代替プランを用意することを優先的に考える。 相互扶助組織の中にビルドインされることでリスクヘッジできる。 「自立」というのは集団的な経験を通じて事後的に獲得される外部評価です。 つまりは、自分の頭で考えながらもつながりを大切にし、人との関係を築いていくことが大切なのでは。 第三章 労働からの逃走 「こことは違う場所」を求めて、「今、ここでベストを尽くすこと」を拒否しているうちに、どうにも身動きならなくなってしまった。という事例。 「むずかしい仕事」や「重要な仕事」を与えられるということは、それだけ期待されているということ。しかし、現代の若者は、直接的な評価を期待するためこういうことを不満に思う傾向がある。 「時間の流れの中にいる自分」を想像できないというのは「無時間モデル」でしか世界を見ることができないということ。=消費主体としての自己形成が根底。労働でも学びと一緒の現象が起こっている。 労働という入力から、ネットワークの再編という出力までのあいだには一定の時間が必要。 今の若者は、時間を勘定に入れ忘れている。 労働それ自体は等価交換ではありえない。→学びと一緒。 時間や変化を考慮することがキーワードとなる。 第四章 質疑応答 時間意識を持つこと、が知性の基礎である。 グローバリゼーション=社会活動全体の高速化、それによる無時間モデルの洗練 ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズは、黒澤明の姿三四郎へのオマージュ。 「無時間モデル」のちょうど正反対の「最大時間モデル」、一瞬が永遠の感覚。 無時間モデル:匿名性、非身体性 最大時間モデル:唯一無二性、身体性 あとがきより 下流志向ではない、現在起こりつつある新しい徴候。 収益や株価や財務格付けといった数値や記号ではなく、温かく、持ち重りのするたしかな身体実感の上に(経済活動を含む)社会関係を再構築しようとする志向です。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【推薦】 「何のために学ぶのか?」「安い給料でこき使われている」昨今、このような文句が生徒や若者から聞こえるのはなぜか?本書が主張するのは、近年の「実学志向」のように、学びを換金率のいい投資(というか、すぐさま利益を出すことを欲する投機的動き)と考えることは教育は教育を崩壊させるということだ。なぜなら「学び」や「労働」は時間軸に自らを組み込み、自分の成長に伴って得られる「知」に対する期待が存在するからこそ成り立ち、不合理なものが混じるからだ。市場原理はその不合理を廃し、人の成長を「勘定」に入れない無時間制に立脚する。時間を廃した教育は、子どものながらの幼児性に固執したままの人間を生み出すことになる。 日本には自己決定出来る「強者」など存在しない。「強者」は自己決定ではなく相互扶助の中で「強者」になり、「弱者」は自己決定から得られる高揚感によって自らの脆弱性を高めていく。これによってリスクは不平等に分配され、弱者は進んで弱者になることを強いられる。ではどうすれば良いのか?本書に答えはのっていない。しかし、その解き方は知ることが出来るかもしれない。問題の答えは、私たちが自らの「知」に期待して解決していくものであり、それこそ本書が主張するところだ。 【書評】 読み易さや筆者独自の視点が面白い。ただ、ニートなどに関しその見方に画一性があるように感じる。しかし既存の教育論とは一線を画した新規性があり、教育や労働について基本に戻って考えるには良い。☆4 【コメント】 常識を疑い、社会に流布する主張の逆説を指摘する点が興味深い。学びや労働が自らの変化を時間軸に組み込み、成長することで得られる「知」に期待することだということに啓発された。一方で、市場原理の等価交換が社会の隅々まで広がり、結果として今あるような学級崩壊や学びからの逃走があるのか、それは市場原理だけの責任なのかと疑問にも思う。筆者が言う市場原理とは、新自由主義型の資本主義を指すことは間違いないが、新自由主義と教育の他にもネット、ITや予備校(の競争)などの無時間モデルを教育との関係で検討しても面白いと思う。子どもが幼児的になるのは、誰の責任だろうか?
0投稿日: 2011.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の自分を見ているようだった。 学習することに疑問を感じている人や、どういう風に学習する必要があるのかに困っている人は必読。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
何故若者たちは働かなくなったのか、何故生徒たちは学ばなくなったのかを説く名著。 彼らはただ怠けて働かず・学ばずという末路に至ったのではなく、「全力で」働かないように・学ばないように「努力する」ことが正しいと思い込んでいる、というのがこのお話の筋だから驚き。 これは何度でも読みたいな。教育関係の方にはおすすめです。 引用 子どもにとって「それ要らない。だって何の役に立つか分からないもの」というのは極めてロジカルな対応です。教師は子どもの機嫌を窺いながらなんとか「勉強してもらおう」とする。それはバザールで出来の悪い商品を「いくらでもお安くしますから」と懇願するように子どもの目には見えているのでしょう。
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない子ども、働かない若者について論じた本。 無知により、自分では気付かずに自分の将来を簡単に潰してしまう というのは本当に悲劇だと思う。 世話焼き行動、師弟関係、他人と自宅で共生する能力などが推奨されているが、確かにそういうものを重視している人が増えているような気がする。
0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今の格差社会に対するデモを見て改めて読み返した。人間のすべての営みを投資とリターンで解釈しようとする資本主義社会の限界が訪れたように感じる。
0投稿日: 2011.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ若者は「学ぶこと」「働くこと」から逃走するようになったのか? 学校・親にその責任を問うのは筋がちがう、それは社会全体が「消費者体質」となってしまったことによる――。 自らを「選択する権利を有する消費者」と無意識に位置づけ、「意味のない(と、思える)もの」「わりに合わないこと」を徹底的に排除しようとする風潮の恐ろしさ。「これを学んで何になるのか」を常に問いたがる学生たち。 あくまで「等価交換」を求める人びとが作る社会に未来はあるか。 帯にある通り、読後「親と教師を震撼させ」る本。
0投稿日: 2011.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学級崩壊からニート、非正規雇用まで、教育と労働についての話です。読んでいて暗くなるような話ばかりだったけど、これが今の日本の現実なんだろうなあ。自分も気質は持っているような気がするので、危ない時はこれを読みなおそうと思います。
0投稿日: 2011.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さい頃からそうであったが、大学で商学部に入ってから特にその傾向が強まったのか、経済的にものを考える習慣が出来てしまったというか、「それは役に立つのか立たないのか」という視点でしかものを見られなくなっていたように思う。 それはそれで合理的な世の中で生き残っていくためには必要な思考で、自分一人そういう視点を捨てて生きようとしても難しいのだから、個人の力とは無力だと思うけれど、そういう考え方に完全に支配された世の中はやはり危険だと思うし、この本を読んで多くの人の意識が少しずつでも変わってくれたらと思う。
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ同書の文庫版。 わざわざ紹介するのは、「文庫版のためのあとがき」が秀逸なので。 たった二文で『下流志向』の内容を要約している。 教育と労働の現場での子どもたち若者たちのふるまいに見られる理解しがたい趨向性を「下流志向」というふうにまとめてみました。 彼らはそのような意思を持つようにイデオロギー的に誘導されているのです。 あらら、やっぱり読んでみないと、内容は納得できないか・・ お財布にも持ち歩くのにも優しい文庫版 ぜひ一読をおすすめします!
1投稿日: 2011.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を選んだ理由: 下流○○系に興味があるので。 働かない若者にも興味あり。 この本に感動した理由: 自分が受けてきた教育とか、周りの空気感を思い返してみれば、「わかる」と共感できる点が多かった。 自分にどのように影響したか: 高校のころはとかく勉強することに意味があると思っていたけど、大学に入ってから、何のための勉強なんだろうと思ってしまうことが多かった。 努力が結果になるかどうかはわからないけれど、結果を出すひとは必ず努力しているということを改めて考え直した。
0投稿日: 2011.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ損得勘定で学習をしたり、費用対効果を考えながら勉強していた節もあったので耳が痛かったです。 改めて「学び」とは何なのかを考えさせられました。
0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ事象発生時の構造を崩すことによって、事象が崩壊することを指摘。 資本主義、ビジネスで全てを考える癖がついてたことに気づかせてくれた、それだけでも読んだ意味があった。
0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ氏の話はこれまで著書はブログ等で何度か読んだことがあったが、これは平易な文章でわかりやすく書かれており、私のようなものにもすとんと落ちる話であった。氏がかねてから展開する消費社会の子どもたちへの浸透が、学びからの逃走、そして労働からの逃走を引き起こすとして、昨今の子どもの学習意欲の低下とニートに代表される若者の労働意欲低下の原因を看破している。特に「時間」という概念を使った説明には驚嘆した。つまり、消費経済の浸透により、経済主体に幼くしてなってしまった若者が、教育や労働においては、成果という名の「商品」が瞬時に等価交換されないことへの不満が、彼らをして、労働や学びから逃走させているとの指摘である。現場で教えるものとして、日々感じているリアリティからかけ離れておらず、また同時に、現場を的確に抽象度を上げて俯瞰する説明であり、納得がいくものであった。 経済用語で語りつくせないはずの教育界や社会全体のことまで、経済用語で説明しようとする昨今の風潮、という氏の指摘に、私もなんでも経済学的に物事を見ているところがあったため、ハッとさせられた。言葉は事象をとらえるパースペクティブになるため、その言葉が経済学に由来するものであれば、やはり視点もそうならざるを得ないなと自分を振り返ることになった。それにしても言葉を丁寧につむぐ人の書物は、それを読むだけで大きな癒しになる。氏の言葉は美しい。これからは寺子屋的な新しい親密圏をつくっていくとおっしゃる。氏の今後に注目したい。
0投稿日: 2011.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読む前に、最近おぼろげに 「ああ、人ってだんだん変わるよねぇ。急にじゃなくて、だんだん変わるなぁ。」って考えたことがあり、 その「だんだん変化する」ってことに気づいたという事実と 本書の節々に出てくる「時間」と「消費」という言葉がリンクして、 今まさに読んで良かったと思えた。 今、3歳の娘がいるが、もしかしたら彼女は消費主体が初社会活動となってしまったかもしれない。娘が「どうして学ばなくちゃいけないの?」と学校で質問してしまうことにならないように、親としてワタシがやるべき事がある。 そもそも私自身も「1・2の3!」という現代のスタイルに随分と慣れてしまって、待てなくなっている。数年前に比べたらパソコンの起動も早い、お腹空いたらコンビニで何か買える、とにかくいろんなことが無時間で出来てしまう。何もかも無時間で考える癖がついているかもしれない。 子どもの成長も、学びの意味も、働くことの有意義さも、意味や成果が出るまで時間がかかる。頭でわかっているようで、実際には気づいてなかったかもしれない。 本書でリスク・ヘッジの説明部分、坊や哲の話しが分かりやすかった。リスク・ヘッジは一人ではできない。
0投稿日: 2011.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本で内田さんが語られているお話は、私にとって聖書のように大切な本である養老孟司さんの「バカの壁」と重なるところがとても多いように思えた。 どちらもとても深く深く頷けて、膝を打つ思いがする内容ばかりだった。 子を持つ親として、そして曲がりなりにも「先生」と呼ばれる仕事をしている身として、心しておかなければならない言葉が満載で、これからも折に触れて読み返したいと思った。
0投稿日: 2011.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供がいないので、「学び」の方はよくわからない部分もあるが、「就職」やその後の「仕事」について、最近の若者の対応の変化を見ていると、この本のいうとおりな部分も多い。師弟関係の欠如で、アナキンスカイウォーカーを例に出していた部分が面白かった。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田先生の著書は毎回多くの見識を得られて、読んでいて非常にためになる。本著も同様、比較的読みやすい割には非常に示唆にとんだ、考えさせられる内容だった。 キーワードは「時間」と「消費」。 「教育」や「労働」の問題について、その原因を幼い頃から身についてしまった資本主義的価値観に原因を見いだし、時間という切り口を中心にその本質を紐解いていくという内容。 氏によると、「無時間的」な消費活動に幼少期から身をさらすことで、本来「支払い」と「価値」との交換がその場でし得ない教育や労働といった分野まで無時間モデルで考えてしまうところに問題の本質があるという。つまり、例えば「勉強をしても何の役に立つのか分からない」という状況があったとすると、「これは割に合わない。(なぜなら自分が支払っている対価(学習の苦痛)に対して、それ相応の価値がこの場で提供されていないから)」と考え、教育から逃走してしまう。 若者がこの「無時間での価値の等価交換」という価値観を無意識に抱いてしまっていることに起因して、学ばない子供たち、あるいは労働から逃げる大人(=ニート)が発生してしまっているというのが大まかな趣旨。要はレートの良い取引しか受託しないという考え方です。 非常にクリアな論理であり、このフレームワークに当てはめて考えると、現代で問題とされていることは大概説明がつくような気もする。 そして同時に、現代社会においては社会全体の風潮として、「時間的なものを排除しようとする力」にどんどん流されていっていると感じる。 スマートフォンやタブレットの普及、Googleによる情報整備などがまさにそれに当たり、こういったIT技術はまさに「現代人の時間との戦い」によってもたらされた成果物である。今まで労力を考えると「割り合わなかった」情報収集が、時間の壁を越えてくる。更に「フリー(無料)」という要素が加わったエンターテイメントも、今や多くの人々の日常生活に欠かせない。 人類は時間という今まで越えれなかった壁をまさに崩しにかかっているだけではなく、サービスの無料化によってレートの良い取引増やし、ますます「無時間かつ等価交換に基づいた思考」を拡散しているのではないかと考えると、少し恐ろしくもある。等価交換におけるこちらがペイする基準が下がっていくと、ますます割に合わない教育や労働からの逃走は加速されるのではないか…と。 ただ一方で、本当にこの単一のフレームワークだけで問題を論じることが出来るのか、という単純な疑問も抱いた。学びからの逃走にしろ労働からの逃走にしろ、顕著になってきているのは最近のこととはいえ、昔は全くなかった問題ではないはずである。昔は「消費活動的な価値観が根付いていなかった。」と仮定すると、このロジックで行くと昔の人は皆優等生ということになってしまう気も。 全体を通して現代を嘆き過去を美化する傾向にあったが、おそらく著書の周囲はエリート層が大半を占めていたと考えられるので、深く突き詰めるためには他の角度からの検証も必要なのではと感じた次第。 最後に、アナキンとオビ=ワンのくだりは秀逸だった。
0投稿日: 2011.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の言うとおり、いくつかポイントがずれてるが流れとしてはまあ納得できる。ちょっとスタイルがいらつく感じ。
0投稿日: 2011.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔と時代が違うんだから 昔のシステムに押し込もうとすること自体 がおかしいんだと思う。 昔のほうがいいことがある 今のほうがいいことがある それを 上手にシステムに組み込んでいかないと 国がおかしくなるよ 悪いことばかりかいたって 時代が違うんだからしょうがないよね それは 子供のせいでもなく 親のせいでもなく ただ 進化したから 起こっている問題なんだ それを 未来をきっちり見据えて 対処するのが お偉いさんの仕事じゃないのかな 偉い人ほど ぼくは能無しのおばかさんだと思っているから じゃー 選挙行けってね ぶっちゃけ世の中がどうなろうなんて 関係ないんですよ 僕がいい状態で 僕が良い波動を出していれば 僕の周りの人も良い波動を出して それが 連鎖していくものだと思っているから 大切なのは自分 何よりも自分 そう思います。
0投稿日: 2011.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の方はわりと面白かったけど、後半部分はちょっと・・・でした。 なぜ最近の子供たちが学ばないのか、という問いは面白かった。 後半部分はニートに関してでしたが、イマイチピンときませんでした。
0投稿日: 2011.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ格差社会の分析的記述が他の著作を引用しつつ記されている。 非常に参考になる。 ただ問題についての具体的提案などは記されていないので 参考にする際は他の文献に求めたほうが良いだろう。 学びからの逃走は、労働からの逃走に通じる。 今の学生は、ビジネスライクな消費者に転じており 与えられることを優先することで何事にも損得勘定が発生することに 警鐘を鳴らしている。まずは以前の家庭のような 手伝いの労働、自主的な奉仕精神が必要だと述べられていることに 新しい発見があった。 ニートは、学ぶことを放棄し、社会において幼稚な消費者としてしか自己を確立していない 社会に貢献するためにも、目指すべき目標を決め、それに向けて努力していくことで自分を見出していきたいと思った。 また読みたい
0投稿日: 2011.05.29
