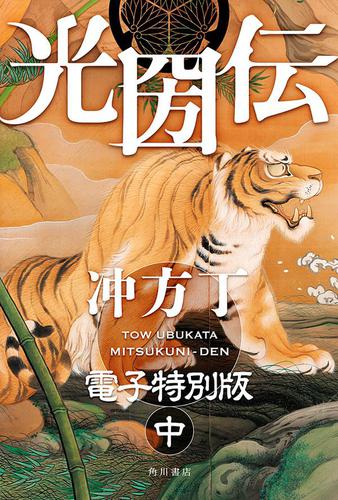
総合評価
(386件)| 173 | ||
| 131 | ||
| 40 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ第3回山田風太郎賞 第1回静岡書店大賞第2位 水戸光圀です。 あの温和なお爺ちゃん姿のイメージしかなかったけど、若い頃はガタイがよく、血気盛んな歌舞伎者として描かれている。 光圀の伝記のようなこの物語のテーマは「義」なのだと思うけど、大義のために覚悟をもつという感覚がわからないので、すごい時代だなと思っても泣けるほどの感情移入はできなかった。 大平の世だから戦国時代に比べて盛り上がりには欠けるし、とにかく「そんな時〜が病んだ」と周囲の人が病死していくエピソードが多い。 時代背景に即して出来事を順に追っていくので、歴史上の有名人がたくさん登場するのは嬉しい。 けどやはり出番は短め。 史実だから仕方ないけど、友や家族と過ごす時間が短くどの人もある程度で死別してしまうので、物足りなく感じた。 学問と詩歌と義に生きた光圀の生涯を知れたのはおもしろかった。 しかし、光圀の義は子どもたちにとってはいい迷惑なのでは、、、?
40投稿日: 2025.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀と言えば水戸黄門。諸国漫遊に悪者成敗を子供の頃にTVで見ていたのが、大人になって史実は異なると知ってビックリしたところからこのお話。 フィクションではあるものの、歴史に出てくる人達や史実も重なり、面白かったです。 光圀の生き様、出会いや別れ…とても濃くて熱のある内容でした。
0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりの分量。読み進めると、次第に周りの人間の死去ばかりになり、その都度、主人公が凹んでしまうのが、何となくウザかったが、総合的な判断としては、はるかに水準を超える力作だった。 何より、登場人物すべてと言って良いほど、皆キャラクターがしっかりしている。これは凄かった。特に奥さんの人物像が秀逸。 長いけど、良い作品だった。
0投稿日: 2025.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて借りる、第141弾。 751ページの大作。 重い。ブロックのようだ。 持ち歩くには適さない。 片手で持つには辛い。 しかし、重くて片手で持つのが辛くとも読まずにはいられない。 面白いのだ。 人の生死、大義、親子の在り方等を光圀の生涯を通して描かれる。 光圀、熱い。 本書は厚く、熱い。 良い。
0投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の生き様にはただただ圧巻です。 水戸黄門というと、夕方テレビに出てくるあの優しいご老人といったイメージでしたが、幼少の時から暴れん坊で、徳川家きっての歌舞伎者。文学に目覚めると「詩歌で天下を取る」といった志を掲げ、己の信念を曲げずに義を貫き通す。今までの人物像と全く違うものでした。そして光圀の豪快っぷりは読んでいて実に痛快。例えるならまさに猛々しい虎の様。 また、他の登場人物も魅力的で、兵法者の宮本武蔵、兄の頼重、妻の泰姫、盟友の読耕斎、等々。光圀の人生に大きく関わった人達との出逢いと別れがとても切なく儚いものでした。 特に泰姫の言葉が胸を打つ。「今日からは、あなた様お独りではありません」、「わたくしが、お傍におります」、「ご安心、ご安心」。。読み進めていくうちにどうしても溢れる涙を抑えることが出来ませんでした。 読み応え満点。この本に出会えて良かった。自分の中の大切な小説の一つになりました。
1投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ爽快感もあり、しみじみ感じ入ることもあり。とにかく面白い水戸光圀の一生。ボリュームたっぷりだけど、面白くてあっという間。
3投稿日: 2024.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大日本史の編纂、水戸徳川家を築いた、いろいろあったがあまり知らなかった人物像が、ここにあった。 兄を差し置いて水戸の当主に就任した光圀。 そのことで、兄への義を守ろうとする。 幼少期のやんちゃさ、負けず嫌い、行動派、そこら辺は水戸黄門作成時の原形としてあるのかも?とか勝手に思った。 84冊目読了。
8投稿日: 2024.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想 光圀の己の存在意義から、友や妻、師など数々の死別を経て、史書編纂を成し遂げた思いが身に染みる。 遂に、左近とは何もなかったのだろうか?心で支え合っていたからこそなのか。 最後の死者の列に加わったという表現が印象的。 良い作品だった。700ページを超える大作だが、スルッと読めた。 あらすじ 水戸光圀の一生。物語は光圀が67歳で家老を殺害するところから始まる。謎は明かされないまま、幼少期へ。第三子の自分が兄を差し置いて、嫡男となった疑問について、天然痘にかかったことをキッカケに考える。 無事に快癒した光圀は大きくなり、江戸で傾奇者としてふらふらしている時に、仲間に囃し立てられ、無宿人を斬り殺してしまう。その時に、宮本武蔵と沢庵と出会い、モノの見方に変化が生じる。 光圀もこれを機に、勉学を始める。ある居酒屋で坊主を論破して調子に乗っていたが、林羅山の息子の読耕斎に論破され、彼に勝つためにさらに猛勉強する。 詩で天下を取る、という目標を掲げて精進する。 京の冷泉為景とも親交を深める。叔父の義直が危篤になり、自分の出生の秘密と嫡男になった理由を聞かされる。光圀は嫡男ではない自分が義に従う行動をするためには、自分の子を成さず、兄から養子を取り、血を戻すことで義を貫こうとするが、京の近衛家より嫁取りの話が持ち上がる。 光圀は義の話を婚姻の日に妻となった泰姫に話し、姫の持ち前の素直さで全てが受け入れられる。光圀は妻を同志を手に入れたかのような心持ちになり、安らかに時を過ごす。 江戸大火と林家の史書の焼失を経て、光圀は史書編纂の決意をする。その後、泰姫や読耕斎との死別により、編纂事業への思いを強くする。 やがて両親を亡くし、藩主になるに当たって、兄の子供を養子にして義を成すことを成し遂げる。その後、明国の朱舜水を師として招き入れ、様々な改革事業に着手する。 光国から光圀へ改名。 最後は、自分の秘蔵っ子の紋太夫の野望を阻止するため葬り去る。
8投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ二代目水戸藩主、水戸光圀の生涯を描いた超大作。 辞書のような分厚い書籍だが、時間を掛けてでも読む価値のある一作だと思う。 舞台は、戦国の世が終わり太平の世となった江戸初期。 「学問」を極め、自分の義を求めて、それを見出し貫き通す彼の一生が綴られている。 彼が義を見出すことを支える登場人物たちも個性豊かで、同じ志を持つ人との出会いや別れがストーリーに彩りを添えている。
0投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の子どもたちは知らないかもしれませんが、水戸黄門です。諸国漫遊はしません。スケさんやカクさん、ましてや弥七も飛猿もお銀も登場しません。ただ、光圀の武士としての矜持、文治政治の志は熱く伝わります。誰に刃を突き立てたのか?最後はグッときました。
0投稿日: 2023.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり前に天地明察を読んで、読みたかったのになかなか読めず、今回ようやく読めました。これぞ大作と言う感じで、時代小説の枠の中に収まらない迫力も感じました。各キャラクターが立っていると言うは、こういう事を言うのですね。
0投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ某番組のお陰で、日本全国を旅しまくった老人のイメージが強い、二代水戸藩主の生涯を綴る。 700ページを超えるボリュームのため、読むのに時間がかかってしまったが、丁寧に『義』という一つの信念を貫き通した男の人生を描ききっている物語は疲れを感じさせない。 ストイックで、何とも烈しく、悲しい話であるが、読んで損はないと思う
0投稿日: 2022.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ出身が近いので興味があり、読んでみた。 750pの大著のため、バランス良く持つのも一苦労…時間がかかった長かった。 破天荒、一方何より義を重んじる丈夫として、日本人に馴染みがある水戸黄門のイメージを一心してくれたのは良かった。ただの昔偉かったお爺ちゃんじゃなかったんだね。まぁそれも、生前の名君ぶりを元に、江戸後期作られたイメージみたいだけど。 水戸の二大英雄(もう1人は烈公。慶喜は賛否あるからね…)の1人の一生を追体験出来ることは、地元にとって価値ある本だと思う。 まぁでもやっぱ長いよね…一生だからしょうがないんだけど、人の生き死にの連続で物語が終わる。そりゃそうだけどちょっと取捨選択してくれても良かったのでは…宮本武蔵とか創作も入れるから余計に…
0投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ関わっているものすべてを成長しの方として生きていく姿にとても感銘を受けました。生と死、挑戦と失敗など 徳川家光圀が実際はどういう人物かはわからないが、こんな人であってほしいと思います。 天地明察がとても好きでしてがこちらも素晴らしい内容でどんどん話が進んでとても読みやすかったです。
0投稿日: 2022.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「剣樹抄」を読んで面白かったので、その流れでこれを読んだら、いやあ長くて読むのが大変だった。でも、良かった。まあ、もう少し読み易くしいぇもらえたら良かったんだけどねえ。ある意味、史実ベースの話なので「剣樹抄」より面白いとも云える。水戸の黄門さん、こんな方だったんだ。全国漫遊してないのは知ってたが、天下の副将軍と呼ばれるだけの人物ではあったんだ。しかし、あの方があっけなく亡くなってしまったのは参った・・・
0投稿日: 2021.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログハラハラと何度も何度もこぼれおちる涙。 この体のどこかにしまいこんでた魂が掴まれ、ゆさぶられる。熱い波が起こり、体中を駆け巡る。 人が生きるということ。生き切るとはまさにこういうことだ、と思える。水戸光圀という生き様。 義に生き、そして、生を全うする。 己が見出し、己を支えるものを信じ、様々な妨げを乗り越え、ときに見失っては新たに見出して、そんなこと繰り返して、己の生を賭けるもの。 その義を見出すに、目を開くために、心を寄り添わせるために、誤らないために、知を習得することが求められるんだ。 論拠あっての信義ということ。義は盲信するものではなく、いくたび危機を迎えようと理智を尽くしてまっとうすべきもの。信義は危機に瀕したときにこそその真価がわかるもの。 死はいつだってそばにある。そんな世の中で自分の生をかけられるもの。そう信じられるもの。それを探し出し、その支えを芯に生き切るということ。 大義をまっとうしろ。 時代は違えど、世界は違えど、自分という人間の小ささを自覚しながらも、でも、そんなコトバを自分の中にも響かせながら、生きたいと思った。生き切りたいと思った。 天地明察 光圀伝 普段はおくびにも出さない。自分の中のクソアツイ部分が引っ張り出される。いつでも自分に火をつけるために、一生傍らに置いておきたい冲方丁作品が、また増えた。
0投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説苦手だけど、光圀伝と天地明察、葉室麟のといにゅうこうは面白かったし、主人公がめちゃめちゃかっこよくて好きになった
1投稿日: 2021.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わるまでかなり時間がかかった。 光圀公が果たして、この作品のキャラそのものなのかはわからないけど、まぁまぁ勉強になった。
0投稿日: 2020.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」がウケけましたが、こっちのほうが、ぼくは好きです。なかなか、サスペンスの作り方がいい!文章も読みやすいですね。当たり前か?!
2投稿日: 2019.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は厚さと重さに圧倒されそうになりましたが本当に読んでよかったです!大日本史を編纂した漢と言うべき水戸光圀がここにいました。登場人物たちの力強さ、潔さ、そして苦悩が手に取るように伝わってきて夢中になって読みました。光圀公ばかりでなく、彼の周りの人々の生き様は本当に格好良く、何度も泣きそうになりました。途中に挟み込まれる「明窓浄机」にはミステリのように引っ張られ、リーダビリティの高さにも驚きました。「天地明察」とのちょっとしたリンクも楽しかったです。
0投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かった〜!読みづらかった〜!でも面白かった! みなさまご存知のあの「水戸黄門」が、なぜあんな感じになったのか。 庶民の味方であり、いつも素性を隠して旅をするご隠居さん。 そこに行き着くまでの波乱万丈の人生が長々と描かれております。 そこにあるのは、 「知性が一番大事なものであり、亡くなる人を悼み、生まれる人を慈しむ」 という人間の基本の生き方を守ろうとする心。 その光圀の姿勢に、心を打たれました。 そして、私は「泰姫」と「左近」の2人の賢い女性がとにかく好きでした! 「天地明察」のときもそうでしたが、冲方丁さんは、 賢く美しい女性を描かせるとピカイチです!
0投稿日: 2019.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川光圀の生涯を題材とした伝記小説。 750ページに及ぶ大作ですが、そのことをあまり感じさせない充実ぶりで、先へ先へと頁を繰らせる力があります。 さすがに『水戸黄門』のイメージとは異なるだろうと予想はしていましたが、ここまでマッチョで聡明な光圀像が描かれるとは意外でした。 改めてWikipediaの徳川光圀の項などを読んでみると、この小説が史実を基本的に忠実に辿りながら書かれていることが解ります。 もちろん、小説の中で描かれる、宮本武蔵、沢庵、山鹿素行、林読耕斎らとの交わりについては多分にフィクションであるとは思いますが。 ただ、このフィクション部分がとても魅力的なんですよね。 個性的な脇役との交わりの中で、光圀のパーソナリティや想いの輪郭が明確になっていくというか。 特に印象的なのは、光圀が生涯で唯一正室として迎えた泰姫と、その傍に仕える左近という二人の女性像。 婚姻生活は泰姫が21歳の若さで病死することで僅か4年で終焉を迎えます。 その儚さと切なさ、そしてその哀切さを永く補い支えていく左近の人物造形が堪らなく魅力的です。 73歳まで生きた光圀は、その長い生涯の中で、数えきれないほどの多くの肉親や朋友たちの死に遭い、送り出していきます。 そして光圀自身、三男でありながら水戸徳川家の世継ぎとして選ばれたことの大義に悩み続け、義を果たすことを生涯のテーマとして生きていきます。 こうしたあたりが、光圀の人物像、そしてこの大河小説を一本筋が通ったものにしています。 由比小雪の乱、明暦の大火、赤穂浪士討ち入りなど、当時の世相を代表する歴史上の出来事も登場するし、徳川幕藩体制が次第に変容していく最初の一世紀の時代感が、光圀の生涯の背景として見え隠れするあたりも魅力です。 これ、いつか大河ドラマ化してほしいな。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい。分厚い本なのに、終わらないでほしくなる小説。どこまでがフィクションなのかわからない。光圀の見方が変わります。
1投稿日: 2018.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読破に一ヶ月かかった大作! 長かったけど面白かったなぁ~。 これほど骨太で個性の強い光圀は衝撃です。 実際の光圀の伝記も読みたくなったくらい。 周囲の人物も個性的過ぎ! 特に左近が良かった。
0投稿日: 2017.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『天地明察』が非常に面白かったので、手に取ってみました。 『光圀伝』も面白い! 人それぞれ、読み方が違うと思いますが、自分自身は、会社での立場もあり、マネジメントの本としても、楽しむことができました。 江戸幕府や大名家の指示命令系統の中での的確にふるまい方は、日本の多くの企業で参考になるように思います。 組織を正しく運営するにあたっては、必ずしもトップが優れている必要はないですが、トップに近いところには、優れた人物が複数いることが大切ですね。
1投稿日: 2017.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ大概こういう歴史物は夢中になるのが常だけど、いまひとつのめり込めず私には魅力的な人物に映らず。残念。
0投稿日: 2017.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ約750ページの大作。4,5日かかったが、一文も読み飛ばす気にならず、物語に深く入り込みながら、集中して読み終えた。前半は、兄がありながら大名家の世子に据えられた己の存在を問い、その答えを容易に与えようとしない父親に対する執着と、己の成すべき義を求めあぐねて身狂いする姿が、しつこいと思うほど繰り返される。聡明で優しい兄、強烈な出会いの後は得難い友人となった独耕斎、高い教養と深く包み込むよな愛情を備えた泰姫、それぞれとの交わりがきめ細かく鮮やかに描かれ、やがて光圀の義はあるべき形に決着をみる。後半は、藩主として政務を執り、幕府と水戸家との関係を裁量しつつ、史書の編纂という大事業を成して行くが、最後に予想していなかった義を全うする始末が残されていた。 天地明察にも大感動して最後に本を置いたものだが、本書も非常に満足。天地明察のテーマであった幕府の政治体制が武治から文治へと変わっていく変化に同調しながら、前半と後半で光圀の人生の変化も描かれている。 その時代、時代で人の生き方も変わる。武士として生まれながらもはや乱世は望めず、代わって文事の追求にエネルギーを注ぐことが出来た。朝廷を頂点とする京都の文化に挑み、猛烈な研鑽の末に才を認められ、天下にその名が知れ渡り、後進との交流にも恵まれる。 光圀の送った人生を、非常に成功した、と安易に言ってよいかは少し迷う。泰姫との契りのくだりは、読みながら涙が落ちたし、長生きした分、別れも多く、寂しい面もあったのだろうか。しかし、儒者として遂に義を違えることなく、史書編纂などの大きな仕事を成し遂げ、大名から庶民にまで広く敬慕された生涯はやはり、よい人生と言ってよいと思う。面白かった。
0投稿日: 2017.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みごたえがあった。厚さに中々手がでなかったけれど、天地明察も好きだったので読んだら違った面白さがあって、すいすい読めた。黄門さまのおじいちゃんイメージからかけ離れた、若々しいアグレッシブさに引き込まれた。人にお薦めしたい一冊。
0投稿日: 2017.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ冬休み用に図書館から借りた本。 いや〜〜〜〜。。。圧巻。 しかもうっかり外に持ち出してコーヒー屋さんで読んでたら、涙が出て鼻水出て困る事象発生。 義のために命をかける。人生をかける。。。そんな人生があるのだなぁ。 これからTVで水戸黄門やってたら見てしまうかも。 全然興味のない人だったのに、すっかり光圀さんのトリコです。 お墓まいりに行ってみたい。 お兄さんがまた素敵で。 天皇の料理番のお兄さんに雰囲気似ていると思ってからは、キャストは鈴木亮平一択!
0投稿日: 2017.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」で本屋大賞、吉川英治文学新人賞をとりその年の直木賞候補にまでなった冲方丁氏が書き下ろした歴史小説『光圀伝』を読了。不勉強で水戸光國というと水戸黄門くらいしか浮かばず、黄門様外伝といったところなのかなあなどと勝手に想像しながら、読み始めた。 ところがところがそんな軽いお話では全くなかった。笑えるところなど1ページもなかったのでは。ほぼ全編にわたり主人公光國は考えに考え続け悩みつづける人間として描かれている。構成としては藤井紋太夫誅殺事件についての光國のモノローグをまず基本に配し、なぜその事件を光國が起こすにいたったという謎を光國の一生をつぶさに追い続ける事で 少しずつ解き明かして行く構成になっている。 悩める人間になったというか考えに考える人間になった発端というのは自分が兄がいるにも関わらず世子(世継ぎ)として選ばれたことだ。兄がいるのになぜだという疑問に誰も答える者はおらず、ただただ後の藩の主となるために過激とも言える過酷な試練を与えられる日々が続く。そんな日々の中優しい兄にも助けられそれらの試練に耐え将来上に立つ武士として育てられていく姿が話の前半で描かれている。すくすくと言いたいところだが残念がらそうではなく青年期には江戸で悪行を尽くし、人を殺めてしまうような事件まで起こしてしまい、道を踏み外さんかという位破天荒な青年であったらしい。ところがとても若いが世継ぎとしては人生の崖っぷちにいたような時になんと宮本武蔵と邂逅する。武蔵と出会いお勤めをする事で後半の大半を占める義(大義)というものを考えるきっかけを与えられるという良く出来た話で青年期は終わる。 このように話の前半は、後半になり光國が我が命以上に大切なものとし生きて行く上の大事な規範とした義(大義)というものを描きだすためのプロローグとして構成されてて、反して後半は前半で基礎をしっかり作り上げられた光国が義(大義)を求めて知の大海を泳ぎまくり大成しつつも決して満足する事のない学究の鬼として一生を終える様が描かれている。よくここまでやるなあという位、剛胆なだけでなく圧倒的な知識・知恵をもってして様々な知識人・文化人と繋がり、そこで得た知識・知恵をもって江戸幕府のなかで重要な地位を占め、かつ朝廷ともつながりしいては民の人気を得るまでに至る様はいにしえの話とはいえ凄まじい。 戦国の世が終わり新たな世の中で新しい価値を求め歴史をしっかりと捉える事(「史記」をまとめる事)をベースに、新たな価値を見つけ新しい生き方を模索する様は、戦後のただ仕事に邁進した時代が終わり、新たな価値と新たな生き方を模索する今のマネージメントを担う人に自分のあるべき道を考える際は一つの鏡となるのではなかろうか。ちょっと軽く読み込んでみるのは悪くないと思う。 難しいことを考えなくても江戸時代をあまり学んでいない普通の方の黄門様のイメージが完全に覆されるのだけは約束します。 水戸黄門様の実は波瀾万丈な一生の話を読むBGMに選んだのはSonny Rollins のBlue Note1558番"Sonny Rollins"vol1.2. 古いけど古くないなあ。 https://www.youtube.com/watch?v=3Ti-VZmPxmk
0投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『天地明察』の作家の次作。 家臣を殺めたご老公、すわ乱心か。青年時代の放蕩、父兄との相克、義への目覚めを経て、名君へ。 冒頭のシーンの謎が暴かれる終盤、まさに泣いて馬謖を斬る 孔明の如し。学問を極め、儒教に傾きすぎるとは、ひとの慈悲を殺すことなのだろうか。すばらしい大作だった。 この人、ラノベみたいな文章力だけど、泣かせるのが上手い上いし、教養が半端ない。
0投稿日: 2016.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった。 割りと読みやすかったものの、本が重くて手が疲れた。 いわゆる黄門さまの生涯を知ることができた。 「義」って、難しいものですね。
0投稿日: 2016.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の目指す道を,探しながらでも真剣に進んでいくと,その道しるべとなる人たちとの出会いにつながっていく様が,読んでいる方も勇気づけられ,心が洗われました。直面した問題から逃げず,一生懸命向き合って考え,信頼できる人たちに助けられながらも乗り越えようと奮闘するまっすぐで力強い生き方が痛快で,またその端々で苦悩する心の動きは,より人間としての深みを見せてくれます。「天地明察」でみた名前を見つけると,何か親しみを感じうれしくなり,また,視点が違うので,付け加わった情報と合わさり,また読み直してみたくなりました。
0投稿日: 2016.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「激情を持って人の世を生きる以外すべを知らない」光圀の一生を清々しく描いた大作です。 光圀と右近の間に、ここで記されている以上のことがあったと願いたいです。
0投稿日: 2016.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ大体この人の本は重くて読むのが疲れるなぁ、と思ってたら、ラノベも書いてるってのを聞いてびびったわけです。関係ないな、しかし重いって言っても大河ドラマの原作みたいな全20巻てなわけじゃないし、このページ数でしっかり一代を書ききって、かつなんだかんだ言いながらも読ませるんだからすごいのかな。 しかし昔の人というか昔の知識人というか、なのかは、義だとか不義だとか大義だとか、なんだかそんな事ばっか言って自分の首絞めまくりでこれじゃ生きるのも大変だよなぁ。このおっさんみたいにイケメンで文武両道ならまぁ生きていけるだろうけど、ヘナチョコで情けない将軍綱吉にはちょっと共感した。いやー、いつの時代でもヘナチョコは大変だわー。
0投稿日: 2016.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の魅力がわかり、それなりに面白いが、あまりに長い!飽きて中断の繰り返しで、読み終わるまでに半年以上かかった
0投稿日: 2016.02.24冲方丁による水戸光圀を描く長編中巻!
光國の嫁取り話が進行して、本人は納得していないまま婚儀が開かれる。嫁いできたのは公家・近衛家の娘、泰姫。光國は泰姫の率直な飾らない性格に安らぎを覚え、泰姫も光國のよき理解者として夫婦で共に歩いていく。 光國は藩主となるが、兄を差し置いて藩主となったことに不義を感じており、いかにして義を正すかを考え続け、一つの結論を得る。その義を全うすることにたいし、読耕斎、泰姫から賛同をもらい、その義を果たそうとする。 本書の中で光國にこれでもかと試練が訪れる。江戸は大きな火災によっておよそ半分もの街が灰塵と化す。心許せる友人、愛する人の死。しかし、支えてくれる人もいる。辛いことも多いが、だからこその喜びもある。そうしたことを本書は語ってくれているようだ。 最終巻ではいよいよ藩主となった光國の姿が描かれる。幾多の試練を乗り越えて義を果たすことができるのか。
0投稿日: 2016.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の一生を読みきった満足感でいっぱいです。近しいものの死を何人も見送る光圀の姿と自身の義を貫こうとする気概に涙が止まらなかった。
0投稿日: 2015.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ようやく読み終わった。 水戸黄門の話しか知らない私にとって、『光國伝』は徳川光國がどんな人だったかサクッと知ることができてしかもエンターテイメント性にとんでいて本当に面白い小説だった。 水戸に行ってみたいなぁと思った。
0投稿日: 2015.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の青年〜隠居まで。 藩主となって治世を行う大黒柱。 史書を編纂し、大事業を成し遂げる文化人。 機知に富み、身分に関係なく素晴らしい人を師とできる柔軟性。一方で、藩主として、咎人を自ら処刑する、いわば手を汚す仕事もやってのける。 悠然と構え、先を見通し、民の声を聞き、民のための政治を行う。後世に問題を残さないように努力し、将来を担う若者の育成にも注力する。 管理者として惚れ惚れするような器だな、と。 一気に読了。良い本でした。
0投稿日: 2015.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ娯楽小説としても歴史小説としても一級品だった。全てが興味深く、長さを全く感じさせなかった。徳川光圀はかくもすごい人物だったか。
0投稿日: 2015.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログしなお勧めで読みました。伏線にひっぱられて夏でもなんとか図書館に怒られないくらいの時間で読めました。義、正義、人として一生を生きるという意味なんかを考えさせられます。歴史を学ぶとか、偉人とされる人のことを知るのは勉強になると中学の社会の先生が言ってたなぁ。正義って言葉は難しいな。遠ざけておきたい言葉。
0投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川光圀の生涯を描いた大作。黄門様のイメージしかなかったが、若い頃は、かなり破天荒なのが意外だった。当時の結婚や跡取り問題は一筋縄ではいかない。それでも、光圀は自分の義のために生きていく姿に見とれた。
0投稿日: 2015.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは義か。 大義のために。裏返せば、それは呪いにも近い。縛りつけ苦しんで、生きる意味を求めた。大義とは、、見つけるものか定めるものか。 一貫した信念の強さに圧倒され、葛藤に苦しくなって、あっぷあっぷしながらの読了。 不義の上に成った義は義にあらず。その徹底ぶりに最後はもう号泣して読んでた。 後に、紋太夫の義が成った史実を思うと時代の流れ、人の人生とはわからないものだとしみじみ考えてしまう。 映像化するなら、この肉厚な感じを保持して欲しい。
0投稿日: 2015.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の良さは、過去の偉人と出会えるところにある。例えその偉人が、作者の感情を投影させたものだとしても、その縁取りは伺うことができる。
0投稿日: 2015.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
黄門様って生涯通して人の縁に凄く恵まれた感じ。 読耕斎が好き。 紋太夫は切ないなあ。 天地明察の算哲がでてきてちょっと嬉しかったり。 しかしちょっと怯む厚さ・・3日かけて読了(笑)
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
冲方丁の2冊目。 厚い。そして字が小さい。 読み応え十分、でした。 天地明察で、ちょいちょい出てきた彼。 水戸の黄門様って、こういうことで呼ばれてたのね、というのは納得。 ある本で江戸時代は世界的にも珍しい、一つの支配階級が300年も支配していた例なんだと書いてありました。 だから、支配階級の人は美しく生きるということが何より大切で、恥をかくくらいなら切腹するという文化まで至ったとか。そういうのの走りが、江戸時代の最初、こういう時期に作られたんだな、と思わせられた。 感動ものというより、お勉強本、かな。
0投稿日: 2015.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀の人生740ページ。詩文、大義、治世、弔い、弔い、弔い。泰姫が面白かったのに出番が少なかったなぁ(´・ω・) 安井算哲も友情出演。 有名な黄門様時代は全体の3%くらい。印籠もでなければ、介さん覚さんと出歩く描写もないけど、あれってファンタジー? 歴史の勉強半分みたいなところがある。「御三家」「後楽園」の語源把握。
0投稿日: 2015.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝記としてとても楽しめました 最後の方は史実を詰め込んだ感があったし、光圀の周りのメンバーが変わってしまいメンバーのエピソードも少なく徐々に失速して淡々と読み終わりました 最初の方は小説と言う感じでしたが、最後の方は歴史の教科書みたいでした 光圀の、心優しく、熱い人となりと意志の強さに共感しました 読耕斎の遠慮のない人柄と泰姫の素直で聡明な人柄が好きでした 光圀は良い出会い恵まれ、自分の大義をまっとうし、心安らかに永眠したと思います 羨ましい生き方でした
0投稿日: 2015.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログBGMはMichel Jackson 壮大でした。 天地明察の算哲さんも光圀の人生に登場しました。それによって、より人と人との交わりが時空を超えて広がっていくように感じました。 学を追究し、詩で天下を取ることを追求する姿が大きくて遠かったです。 水戸黄門というと、テレビドラマのニコニコとしたお爺さんのイメージでしたが、激情家で怪力の者という想像と全く違う姿が面白かったです。
2投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ★3.5、娯楽作として充分に満足。 戦国時代とは違う人間の様々な闘争を競い合いと捉えて、数多の人物を魅了的に描く。 特に保科正之を主人公にした良い小説を読んでみたい気にさせてくれたなぁ。 ご存知な方にはご教示いただきたいくらい。 さて、「見たことない水戸黄門」との帯、期待して読み始めたが、冒頭から何処かで読んだことある筋だなぁ、もしかして忘却してるだけで再読?と思っていたが、吉川英治でしたな。
0投稿日: 2014.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごく読みごたえがあります。 たとえば光圀には兄がいたのに、彼が水戸徳川家の後を継いだこと。 歴史の事実としては知っていたけれど、大事なのは事実を知ることだけではなく、なぜそのようなことになったのか。 事実に関わる人々が、何をどう考えどう生きたのかそこが大事なのだということを、光圀の生き様を通して描いた小説。 つまり、光圀が編纂を始めた「大日本史」のような、人物本位の歴史小説なのである。 …まあ、歴史小説は、大抵人物本位ではあるけども…。 儒教に傾倒した光圀にとって、兄をさしおいて自分が後を継ぐというのは、義に反することなのである。 「なぜ自分なのか?」 それがわからないから、自分に自信を持つことができない。 常に兄に対してコンプレックスを感じなくてはならなかった少年期。 コンプレックスを抱えたまま文武の才を伸ばしていった青年期。 ひととの出会いに恵まれる。 宮本武蔵。沢庵和尚。山鹿素行。林羅山とその息子林読耕斎。保科正之。藤原惺窩の息子冷泉為景。後水尾上皇。滅亡した明から逃れてきた朱舜水。 なんと才能あふれた人たちが多発した時代であったことか。 詩で天下をとると決めたながらも、次々にやるべきことが目の前にあり、まわり道の日々を送るのであるが、それが光圀を成長させていく。 志半ばで世を去っていく人たちから託された思い。 義に生きる光圀は、それらを受け止めながら自分の道を模索していく。 自分の志と義の一致を求めて。 ことに、終生のライバルであり友であった読耕斎との交流と、正妻の泰姫とのたった4年の夫婦生活が、どれほど光圀の心を開放し、才能を伸ばしたことか。 泰姫と左近の関係は、のちの『花とゆめ』の定子と清少納言に似ている。できた女官と才能あふれ心豊かな姫君。なるほど、ここから発展させたのか。 光圀が誰かを殺害するシーンから始まり、誰を何のために殺したのかを謎としながら進められるので、小説的興味も尽きないで読み進められるのだが、実はここも史実なんですよね。 解釈が通説と逆なのに納得させられる筆力。 いや、これが真実でいいんじゃないでしょうか。 徳川3~5代の時を、光圀と一緒にわくわく過ごした。 楽しかった。
2投稿日: 2014.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2014.10.光國は初代水戸藩主水戸頼房の子として生まれる.父からは死人が流れる川を泳いで渡るなど死にかけるほどのお試しを何度もされる.光國は兄ではなく自分が世子になったため兄の子を自分の次の水戸藩主とすることに大義を見いだす.一方,詩歌の天下を取ることを目標に儒学など様々なことを学び,天皇から称賛を得るまでになる.また,史書編纂事業にも力を入れる.兄の息子の綱篠を藩主にしたあと,光圀と名前を変え,若い頃から史書編纂事業を任せていた優秀な紋田夫を綱篠の大老とする.その紋田夫が水戸家から将軍を輩出し,その後に天皇家に大政奉還させることに大義を見いだしてしまい,色々と画策する.仕方なく,光圀は紋田夫を殺めてしまうのだった.面白かった.でも,長い,厚い.上下巻でも良かったのでは?
0投稿日: 2014.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的。光圀のこと、史書のかとをなにもしらなかった。ドラマ水戸黄門は、この光圀をして生まれるべくして生まれたドラマかも知れないけれど、それ以上に知ろうとしない流れを作ったかもしれない。大政奉還に繋がる筋立ても見事。 いつかNHKに渾身のドラマ化を期待したい。 沖方丁、素晴らしい!
0投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
う、悲しい一代記です。こんなにも身近な人を弔い続けるなんて。如在とは言えども、悲しいなぁ。じぶんも40を越えたこの頃、この手の話を読むと、じぶんの身近にもいずれ同じことが、と考えると堪らなく切なくなる。折しも20年来の友人たちとぷち同窓会みたいな感じで会ってバカ騒ぎした後だと、シミジミ。それもまた人生、歴史なのか。 しかし、パワフルな黄門様。TVの介さん角さんでお馴染み水戸の御老公とは真逆の人物像。良く描けますよね。天地明察の登場人物が度々出てきて、話が交差する。 泰姫と読耕斎の死期には号泣。冲方さん容赦ないよね・・・なんて思ったり。 左近もなかなかなかな。光圀公の最後を看取るあたりには、もうね。ハンカチ。 兄、頼重が常に見守ってくれる、そして義を互いに通す。 義。人として、男として、全うしているのか。常に問い続け、あるべき方向に進まないといけない。頭でわかっていてもなかなかできるものではない。 冒頭に始まる、家臣藤井紋太夫刺殺。初めは誰なのかわからないけど、途中からああ、殺されちゃうという流れですが。優秀すぎるのも・・・ですかね。先が見えすぎて大政奉還などと。名かなゾクゾクする展開でした。 次は保科正之伝か。 しかし、またしても電子書籍は残量がわからないということで(ま、ちゃんと見ればわかるのですが)、帰りの電車でさあクライマックス、続きを読むぞと思ったら、2ページで終わっちゃった時のこの何とも言えない、空振り感というか拍子抜けというか・・・
0投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察で予感はあったけど、ずいぶんな大作に仕上がったものです。この人のことを書きたくて仕方ないという感情が伝わってくるようでした。
0投稿日: 2014.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」に出てきた光圀が良かったので読んでみた作品 ドラマの水戸黄門とは全然イメージが違い 光圀自身の強さが魅力的ではあるけど 思ったよりは感動しなかった と言うか、感動した所が前半にかたまったかな、と お兄さん、読耕斎、泰姫が素敵でした 光圀の義と紋太夫の義はどちらが正しかったんでしょうか?
0投稿日: 2014.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近見かける筋肉ムキムキ系、水戸光圀はこの本が出所だったらしい。 合戦シーンの全くない長編時代ものだったけれど、何とか読めた。
0投稿日: 2014.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
歴史を全く知らない私でも楽しめました。 ただ、光圀のことをあまり好きになれません。 天地明察の方が面白かったです。 天地明察の主人公、算哲が光圀伝にも登場したのは嬉しかったです。
0投稿日: 2014.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに大作を読みました。 (期限を過ぎてしまいました。図書館すみません) 俺とっての大義は何だ? (作品中に何度も「(大)義」という言葉が出てきます) 「四十にして惑わず」 あと1年半ぐらいで 40歳になる身としてはしっかりと考えなければ いけない時期かもしれない。
1投稿日: 2014.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログすっかり史伝の方に行ってしまったのか、冲方氏は。面白ければなんでもいいですけど。という訳で図書館で借りましたがなんとも厚い本でした。読み終わるまで随分時間がかかりました。 水戸黄門でおなじみの水戸光圀公ですがこの頃はテレビでも放映されていないようだし段々知らない世代も増えてくるのかな。別にテレビシリーズのような勧善懲悪をしていたとは思っていませんでしたがなかなか色々才能のある方だったんだなあということはよくわかりました。 庶民に人気があったと言うことは反面、いかに諸大名や権力者たちの権利が大きく理不尽な世の中であったか、ということの裏返しなんだと思います。だからこそ徳川御三家で将軍に対抗できる立場に居る人間が庶民の味方(でも無いとおもうんだけど)なのだと言う事がいかにありがたかったか、ということなのだと思うのです。少し前までテレビでも人気番組だった訳ですから。 そういう風に考えると今は反対に絶対的権力者の不在による正義や悪の多面性が出て来たのかなあなんて思います。なかなか面白いですね。
1投稿日: 2014.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀のイメージはテレビの黄門様止まりであったので、冒頭部分からショック。なぜ?とという興味に駆られて、本の分厚さと字の細かさにひるんでいたのも忘れて一気読み。光圀という人物にも、それを取り巻く人々にも大変に興味をひかれた。そして彼らの向学心にも刺激をうけた。もっといろいろなことを知りたい。
1投稿日: 2014.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すごい・・・ 長いのでだいぶ時間がかかりましたが、先を読むのが待ち遠しかったです。 ページをめくらせるのは、光圀は誰を殺したのか、という疑問。とにかくその1点です。 素晴らしかったです。 あとは天地明察読んどいてよかったなと思いました。
1投稿日: 2014.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸出身でありながら、水戸黄門様のことを知らずにいた。 これまで何気なく行っていた西山荘がとても身近に思われる。そして、あの地にこんなにも熱い光圀の想いがあったのだと思うと感慨深い。 光圀がこんなにも博学であり、義の人であったことも知らなかったが、後世にまで水戸黄門様として人気が続くことも頷ける、魅力的な人だったことが、単純に嬉しい。 西山荘にまた行ってみたくなる。
0投稿日: 2014.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ濃密。 光圀の義に生きる姿、文事への情熱、弔う者としての苦痛が達観に至るまでの過程、全てが実に生き生きと描かれていた。 歴史描写もリアルで、その後水戸藩が辿ることになる運命の皮肉さもあわせて、改めて日本史の面白さを感じさせてくれた一冊。 史実をもとに、よくこんなに生き生きとした文章を書けるなあ…冲方丁さんの豊かな語彙と想像力に脱帽。
0投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログただただ圧倒されたwww 本の分厚さと光圀公に。 もう上手く説明出来んから、ただただ読んで欲しい。 それしか言えないwww 読み終わったばっかりやのに、すでに、もう一回読みたくなってる。 それくらい、魅力的な一冊。 あと『天地明察』も、もう一回読みたくなった。
0投稿日: 2014.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察を読んだ後、これを読みたくて図書館に行ったものの、その分厚さに「夏休み・・3人の怪獣を相手に2週間で読み切れるか」散々迷って借りてみた。 読み応えがありすぎた・・!! いや~まず光圀の深さ。旦那が大好きな「水戸黄門」のイメージ+お隣の県にある栗林公園が黄門様のお兄さんの邸園だった・・ぐらいの貧弱な知識しかなかったけれど。 大きかった。豊かだった。深かった。 そして徳川4代5代将軍の世の中がこれまた響いた。私の中の知識では3代までで、そこから明治維新への流れまでとんでしまうんだけれど、少しひろがってきましたよ。 家光の頃はまだ秀吉の世を懐かしむ声もあり、盤石ではなかったであろう幕府も、この頃になるとどんな将軍であろうと崩れるようなことはない、ってすごいことだよな~。 しかし、ここでまた保科正之公がおでましです。3代から5代までつかえ、決して日向に出ることをせず、陰で将軍を支え続ける。 自分の中に取り込むまでにしばらく時間がかかりそうなそんな気がしています。
0投稿日: 2014.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのボリュームで、一気読み。 水戸黄門様で知られる光圀の生涯。 スーパーマンだったのね、この人。 光圀のこだわる大義とか、今の世の中からしたらどーでもいいことだけど、この時代ではとても大切なことで、それ故彼を悩まし、彼の道筋を決めた。心も強く、頭も良く、好奇心も旺盛で、よく学んだ人。強いカリスマ性を持っていて、私もそれに惹かれた1人になるのでしょう。 現代にいても魅力的だったろうなぁ。 佐々の行動が、旅した黄門様に繋がったのかしら? とにかく、面白かったです。 天地明察の人もでてきたね。
0投稿日: 2014.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずとしれたあの光圀の一代記。光圀を知るという事は徳川の世の成り立ちを知る事でもある。子供の頃に黄門様で刷り込まれた穏やかな印象とは異なり、迸る激情を如何にして己の中にうまく昇華させるか、ひたすら自己を厳しく律する姿勢に魅せられた。
0投稿日: 2014.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
パワフルで豪傑。 テレビで見てた黄門様とは全く違う。 大学の設立、税制の改正、海外貿易とこの人が将軍様だったら日本の歴史かなり変わってただろうな
0投稿日: 2014.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.07.18 御三家と言うと、将軍職を巡って仲が悪いというイメージだったけど、もとを正せばみんな兄弟や従兄弟だったんだと改めて気がついた。 知行地も離れてるし会ったことないんじゃないかと思ってたけど、参勤交代でみんなお城で会ってたんだね。 光圀自身は、背が高くて男前、頭がよくて剣も強い。 おまけに庶民にも大人気。 本当に彼が将軍になっていたら日本はどうなってたかな? もしくは戦国大名だったら天下がとれてたかも
0投稿日: 2014.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
徳川御三家の二代目水戸光國(のちに光圀)の生涯。兄・竹丸(頼重)を差し置いて世子となったことで強烈なライバル心や自問の日々、世子として試練を次々と与える父・頼房への葛藤を乗り越え、幼少期、青年期、壮年期、老年期と「義」を貫かんとする生涯。 儒教の話になるとさっぱりわからなくなるけれど、人間としての迷いとか信頼していた愛情を持っていた人に先に逝かれてしまう寂寥の念などは涙なくしては読めなかった。
0投稿日: 2014.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
光圀伝 水戸藩二代目藩主である徳川光圀のお話、ってまぁタイトル見たまんまだけど。面白かったです。「天地明察」読んで保科正之と徳川光圀に惹かれまして、光圀に関しては同じ作者の作品が出ていたのでこちらを読みました。冲方先生お願いだから保科正之も書いて! まぁそんな光圀、若い頃から三男坊である自分がなんで世子に選ばれたのか?その思いに悩み続けます。そして市井でグレて、何の罪もない人を殺したりします。ロックです。 でもまぁ読耕斎やら山鹿やら史実か知らないけど宮本武蔵やらいろんな人に出会って学ぶコトに目覚めていきます。ガタイがデカくてロックなのに文学もしっかり学んで詩で天下取る!とか言い始めるんだからまぁカッコイイです。 そんな光圀のお父さんである初代水戸藩藩主、頼房もロックです。幼い光圀を夜に呼び出し「昼間斬った首持ってこいや」とか言い出します。こんなこと言い出す方も言い出すほうだけど聞いた挙句に首を引きずりながら踊りだす子供も子供です。首は翌日煮ます。目玉をつついて喜ぶ幼少の光國。ロックです。まぁこれは「お試し」と言われる行為で、光國が水戸藩を継ぐのに相応しい人物か?を調べていたんですね。他に方法あるんじゃねぇのか? そんなお父さんは氾濫して死体やら壊れた家屋やらが流れまくる川を見つけて大喜び。「泳いで渡れ」とお試し発動です。光國病み上がりです。流石に周りも静止しますが光國、飛び込みます。行くぜ!と思った矢先にお父さんも飛び込みます。来い!と。お父さん、なにげにツンデレ野郎です。この後光國の婚儀の際には朝廷から嫁さん引っ張ってきます。怖いことするけど子供が可愛くて仕方ないんですね。ロック失格です。 あとは「天地明察」を読んだ後にこの本を読むと、保科正之のかっこよさに濡れること間違いなしです。由井正雪の乱の件で光國を黙らせるシーンはたまらないです。あとは安井算哲が出てきたりするとキタ━(゚∀゚)━!っと思ったりします。 年をとった後の光國の方がやっぱりカッコいいですね。それは父母妻子の死があり、盟友達のの死があり、その上でたどり着いた達観なのでしょう。 でもまぁこれだけの人でも治世って面では頑張ったけどそれほど実績は残せていないんだよねぇ。大日本史も詩のやりとりを冷泉為景やら実質後西上皇としたり奥さんが皇室だったりとまぁそんなんで超朝廷贔屓の影響が出たりと、まぁ思想的には偏りはあるけど、それも彼の義なのでしょう。義の人なのです。だからお兄さんである頼重の子供綱條を自分の跡継ぎにしたりするんですね。 あと左近が可愛すぎです。ガッデム!クールビューティ! 大変面白かったです。
1投稿日: 2014.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読む順番間違えた、まずは天地明察を読むべきだったようである。 が、これだけ読んでも結構面白かった。 主人公光國の生き様がカッチョ良い。そして周りを囲むクセある連中がまたカッチョ良い。 2人のヒロインもこれまた、男が勝手に描く理想の女性像の典型で萌える感じが良い。 頑固なおっさんが、世の中にできるだけ迎合せずに生きている姿を描いているという部分を捉えたら、この小説はハードボイルドとも読める。身体を鍛え筋骨隆々なのに詩文で天下を取ろうと考えたり、史書を編纂するあたりは文武両道のハードボイルド「スペンサーシリーズ」を彷彿させる。そういや、スペンサーも相当にストイックだが惚れた女にはずいぶん弱いところを見せているよな。 俺は、身体も頭も鍛えて、ストイックに生きる人を描いた小説が好きなので、そういう意味ではこの作品も長さを気にせずとても楽しく読めた。 ただ、どうにもワンパターンな展開がちょっと残念。 すげえ出会いがある→光國の人生が開ける→しばらく幸せ→突如その人と別れて悲しむ→でも新しいすげえ出会いがある(以下繰り返し) これだけで、700P読まされるとさすがにちょっと飽きてくるなぁ。光國と主要登場人物野のパワーに引き込まれて読んだけど、再読はないかも。 とりあえず、次は天地明察を読むことにしよう。
0投稿日: 2014.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸藩初代藩主、頼房の三男として生まれた光國(のち、不惑を意味する字に変えて、光圀)。字は子龍(しりょう)。 水戸黄門のイメージとは大きく異なる破天荒さ、猛烈な力強さを新鮮に思いながら読む光圀の生涯。 「なぜ、俺なんだ」の悩み。「義」を見出だし、それをなんとしても成し遂げる生き方。文事、特に詩を極めんとする気概。魅力たっぷりな人物像だった。長い物語だが退屈することが全くなかった。 光圀以外の登場人物もたいへん魅力的。特に、兄の頼重、林読耕歳、泰姫、左近、そして紋太悠。
0投稿日: 2014.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸初期の文化、史記の話などに慣れず、読み進むのに苦労した部分もありましたが、読み終えてじんとするほど良かったです。 歴史上でも史上最悪と思っていた五代将軍綱吉。うん、確かにあの法令は最悪でしたが、決して愚鈍なばかりではなかったろうに、将軍であること、将軍を支える人々というのは大変なのだと改めて考えさせられました。今の世にも通じますしね。 途中『天地明察』での一場面も出てきて、光圀側から見るとこんな感じなのかと思いました。 光圀が生きる時代が早すぎた。そう思います。
1投稿日: 2014.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い!光圀はすごい。才能だけじゃなく、強い気持ちと溢れる人間味が素敵で多くの才能溢れる人達を巻き込んで物事を成すパワーに感服です。素敵な脇役がいっぱいです。こういう人達の思いが連なって今があると思うと、明日も頑張ろって気持ちが新たになる。
0投稿日: 2014.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ分厚い。重い。 読み始めるまでが1番の試練だったけど、読み始めたらあっという間に読み終わった。 見かけによらず文は堅すぎず読みやすい。 光圀と独耕才?の友情に憧れる。 光圀の疾風のような人生を共に過ごしたような爽快感があった。 やっぱり自分は歴史小説が好きだなぁと再認識させられた。
0投稿日: 2014.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白く、まさに大作であり、傑作です。 個人的には、天地明察の方がのめり込んだ感。 テレビの「水戸黄門」ではなく、水戸光圀公が一人の人間として、その生き様、思い、人生が描かれています。 静かな筆致から熱い情念を感じる文章。 とても読みやすく、また、心に染みました。 面白かったです。 先の未来。 大政奉還の折に居合わせたら、光圀はどう思うのだろう。 幼いころの彼へそうしたように、彼へ驚いた顔を向け満足そうな顔をしそうな気もします。
0投稿日: 2014.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白かった!文章は読みやすくキャラクターが魅力的なので、ページをめくる手が止まりません。天地明察より堅めでこちらの方が好み。 身近な人の死が光圀を次々襲い、涙ぐむところが多かった。多くの人が生きて、死んで、それが連綿と続いていく。テレビの黄門様のイメージしかなかったけど、こんなに濃い人生を送った人物だったんだなー。 小さい頃から晩年まで、すごい人物に出逢うとすぐライバル心がムクムク湧く光圀がかわいくてかっこいい。兄も友も妻もすごくいい。 最後の展開は辛いが、「彼」もホッとしたのではないかな。そう思いたい。 光圀は、自分が歴史の大きな流れの中の一点だということをよくわかっている。 私は先の世を生きる人に何か残せるのかな。家族を作らないと、何か大きなことを成し遂げないと、だめなのかな。爪跡を残したいわけではないけど、誰かに良い影響を少しでも与えられたらいいな。そんな事を思いました。 ただ、まー重い。ぶ厚い。
0投稿日: 2014.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察が余りに面白くて、同じ作家の作品を探した。単行本の分厚さにしばし迷ったが、やはり読みたい気持ちが勝り手に取った。 天地明察とは少し趣を異にするが、これもまた別の意味でおもしろい。淡々と光圀の人生を追い、関わった人々が光圀の周囲で生きて死んでいく。 天地明察と同時代であり、同一人物も登場する。基本的にどちらに登場する人物も全く同じキャラクターとしてて描かれている。 光圀の生きる芯になった義、オープニングからエンディングまで、実はある人物に向けて様々な人を通して語られ光圀のものとなっていったそれを、向けられるべき対象の人物は、多くの登場人物と同様に淡々と語られ、決して目立ってはいない。 後半、対象が明確になってからも、他の人々に紛れている。 終始視点は光圀から動くことはなく、他の人物の感情や意思は語られることがない。読み手も、いつの間にか光圀と共に年を取り、光圀と思いを重ねる。 だから、光圀の為すことにも感情にもさもありなんと思う。 描かれ方が淡々としているので、共感というよりも少し離れたところから静かに見ている感じだ。 本を閉じて、ほーっと深い息を吐いた。 因みに光圀伝の登場人物で一番好きなのは、左近。
0投稿日: 2014.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なんで、おれなんだ」光圀の人生は、このことを生涯問い続けていたのだろうと本書を読んで感じました。「生まれるはずではなかった?」みずからの出生の秘密を知り、慣習に照らすと本来なら兄が継ぐべきはずが、自分が継ぐことになった。また、歳を重ねるたびに訪れる近しい人々との死別と…、まるでこの世の不条理を一身に引き受けたような人物という印象を受けました。家族、朋友を失ってもなお「義とは何か」を求め続けた光圀の姿に感銘を受けました。 前作の『天地明察』の主人公である安井算哲、宮本武蔵と沢庵和尚(この部分は著者の創作かと)も登場し、従来の『水戸黄門』とは異なる人物像がうかがえる、歴史エンターテイメント小説です。
0投稿日: 2014.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ知ってる水戸黄門とイメージのギャップが激しくて初めはすごく戸惑った。 読んで行くうちに、一生に打ち込めるものに時間も気力も費やすことに憧れたし、ノブレスオブリージュをここまで強く感じた本は初めてだった。 天地明察と交わる部分は光圀側の視線からで新鮮でもう一度天地明察を読んで照らし合わせて見たいと思った。 今の時代とは慣習もなにもかも違うから、光圀が紋太夫を殺したことがいいのかどうかは判断し兼ねるが、家臣の責任を自分が取る、しかし決して嫌って殺したのではないというのがとしてつもない精神力だと思う。泰姫の死と紋太夫に「大義てあった」と囁く場面は思わず涙が出た。
0投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログここ2ヶ月くらいのスキマ時間の楽しみが終わってしまった。。。 天地明察と同じく、ひとりの熱い生きざまをドラマチックに描写していて、どんどん引き込まれる感覚。 光國が関わる多くの人の生と死が、無常と悲哀を感じさせる場面も多いが、光國の感情豊かな振る舞いと相まって清く受け止められた気がしました。 心に何か熱いものがグッとくる、そんな小説を求める方にはオススメです。 あと、とりあえずサラッとでも論語は読んでおいてよかった。光國の大義を少しでも理解するには、とても役に立ちますよ。
0投稿日: 2014.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ詩とか論語とか難しかったけど、読みおわって「そういうことだったのか」と納得もして泣きながら読み終わった...w そういえば子供の頃伝記を読み漁っていたけど嫌いじゃないんだなって思い出した。 でも次は冲方丁のSF読むぞ〜って気力満々w
0投稿日: 2014.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログアップしていたはずのレビューが今日見たら消えてた……。というわけで再レビュー 図書館より 水戸黄門の通り名で有名な水戸徳川将軍、光圀の生涯を描いた歴史小説。 光圀の生涯はとにかく濃い! ハードカバーで700ページ以上の大作なので、読み始める前は「ちょっと書き込みすぎだろう」などと思っていたのですが、いざ読んでみると、光圀の人生はとにかく濃くて、この生涯を描くのに700ページという厚さは必要だったのだな、と思いました。 将軍家の三男として生まれた光圀ですが、彼は長男を差し置いて父から世継ぎに選ばれます。そんな光圀の生涯の問いの一つは「なぜ自分なのか」という事でした。そしてその問いは徐々に光圀の中で「何を義として生きていくのか」ということに変わっていったのだと思います。 何のために生きていくのか、と思いながら生きていくことは正直しんどいことだと思います。だからというわけではありませんが、僕はあまりそういうことは考えず、日々を生きています。でも一方で光圀のような自分のやるべきことに対し、常に悩み、そしてそれに向かって生きていく姿はうらやましくも感じました。そうした悩みとその苦悩を振り切って彼が生きていく姿はとにかく力強かったです。 また光圀は若くして妻や友人と死に別れ、晩年も息子同前に可愛がってきた家臣との決定的対立を迎えるなど、別れの多い人生でもありました。 またそうした別れが何かが始まろうとしている時だったり、上手くいこうとしている時だったりするのがまた印象的でした。そうした悲しみにも負けず自らの義に向かって真っすぐに突き進んでいく姿は、人生に義を定めた人間の強さを表しているように、そして家臣との対立はそれだけでは如何ともしがたい義と義とのぶつかり合いの果てを見せられたように思いました。 第3回山田風太郎賞 2013年本屋大賞11位
2投稿日: 2014.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログなんというスケールの大きな人間人生劇場。大義、儒教、学問、武士道への追求。この精神性を持続することが、日本人の日本人たる唯一無二の生き残りの道ではないかとさえおもう。
0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ途方もない小説。吸い込まれるようにすすんでいく。どこまでが真実でどこからが創作か浅学のため分からないが、光圀について楽しく知る事が出来た。光圀が妙に身近になった。また、水戸に行きたくなった。 サイコパスというアニメを見てたら、なんと冲方丁が、脚本協力!面白いわけだ。また、甲殻機動隊も、脚本書いてる。
0投稿日: 2014.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えのある本でした。 冲方丁の作品で、前作の天地明察の話も少し入っていたのが面白かった。 光圀のことを美化もせず正確に伝えているんじゃないかなぁと思いました。
2投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビの水戸黄門様とは全く異なる徳川光圀。 光圀のあふれんばかりの詩や武士としての情熱と野心と、それを上手く発揮できない立場や性格から、野生の虎が檻に閉じ込められている姿が浮かびました。とても才能と人間味にあふれた人物であったのだなーと。 泰姫がかわいすぎた。二人で幸せに生きてほしかった。 読耕齊も。それにしても歴史に名を残した人には長命の人物が多いように感じる。 水戸黄門を見たくなりました(`・U・)
2投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀は常に場面、場面に全力でぶつかり生きてきたのだろう。 大義に従い、綿々と世代をつなげていくこと、それこそが我に与えられた役目であると。 「余もまた、この世に生きた」と石に向かって静かにささやくシーンがそれを象徴する。 読後、高村光太郎の『道程』が頭の中に浮ぶ。 「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る。」
1投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ黄門様諸国漫遊しない記。 血気盛んな傾奇者として暴れ回り、様々な人物立ちとの出会いから、学問、詩歌の魅力に取り憑かれて行く。 前半は淡々と進む。中盤~後半は様々な出会い別れがありドラマチック。 人生の短さをまざまざと感じさせられる。 ほとんど知識がなくTVでしか知らないので新鮮でした。 徳川と御三家の関係など歴史にうとい自分にもわかりやすく、かつ自然に解説されてるのが良かった。 ★4かなという感じなんですが、最初がちょっと退屈に感じてしまった印象。 もう一度呼んだら印象変わるかも。 同作者の天地明察のほうが好みでした。
1投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史上でも稀なほどの逸話が残されている徳川光圀の生涯が「儒教の義」という補助線を引いて見事な小説に仕上げられている。 青年期は膂力たくましい傾奇者として描かれておりイメージとのギャップでまず引き込まれたように思う。特に宮本武蔵との邂逅は興奮を感じた。
1投稿日: 2014.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸藩主、徳川光圀の一代記。 かの有名な水戸の黄門様その人であるが、TVの好々爺風情とは違い、何とも力強い、かつ激情的で繊細な一面を見ることが出来た。著者の作品を読むのは、「天地明察」に次ぐ2冊目であるが、断然、こっちの方がイイ。とにかく光圀の生き様が格好イイのだ。周りを固める脇役陣も皆、魅力的で、もの凄いボリュームながら読むのが楽しく、光圀と同様、誰かが亡くなる度に涙が零れた。 読み応えがあって、読後、満足感に浸れる一冊だった。
1投稿日: 2014.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ700ページ超の大作なので、読み終わるのにえらく時間がかかりましたが、それだけの価値はあったと思います。テレビで有名な黄門様時代は少しで、大部分が血気盛んな若い時代の話になりますが、まさに義と文事に生きた英傑の一代記という感じです。
0投稿日: 2014.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいい本に出会えてよかった。 長い話ではあったけれど、怖いもの知らずな子供が血気盛んな青年になり、己を知りしだいに文人として、藩主として成長していく過程はその長さを感じさせない濃密なものであった。プロローグとエンディングが同じで、光圀が目指した義が違った形で表れなことに衝撃をうけた。 己を知ること、精神的自己研鑽に努めることが上に立つ人の備えるものなんだなぁと勉強になった。兄、読耕斉、泰姫、左近、佐々、紋太夫など魅力的な人物がたくさん。江戸時代が過去の一片ではなくて、たしかに存在した時間の一部だったんだ、と描写の細かさで感じられた。
1投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ冲方丁の歴史物2作目。 なんとも雄渾な、力強い作品です。 水戸黄門のモデルとなった水戸藩主、徳川光圀の伝記小説。 「天地明察」とほぼ同時代で、暦の件もあの人物も出てきます。 水戸藩は徳川御三家の中では家禄が低いが、江戸に近く参勤交代を免除され、江戸藩邸に藩主は常住だった。 そのため、副将軍と呼び習わされたとか。正式な役職ではないのですね。 初代藩主は将軍家光と年齢が近く、信頼されていた。 光圀は初代藩主の三男なのですが、この父親というのが苛烈な男。 大勢の側室を抱えながらなぜか正室をおかず、子供をなかなか嫡子と認めない。 父は光圀に会ってもつぎつぎに試練に晒し、跡継ぎにふさわしいか試すかのよう。 優秀な兄がいるのに、ややこしい成り行きで嫡男となった光圀は割り切れないものを抱え、その事情も小説の興味を引っ張ります。 後に、兄の子を自分の跡継ぎに据えることに。 義を貫いた人だったのですね。 父親譲りか?光圀自身もはげしい気性。 もはや戦乱のない時代に、武士がどう生きるかを模索するのでした。 なんと詩で天下を取ろうと高言、京都の冷泉家とも交流を持ち、ついには認められる。 儒家に学び、伯父が大事にしていた日本史をまとめる事業を引き継ぐ。 立派すぎるほど才能と意志とエネルギーに溢れた男。 それでも、何よりの人生の花は、皇族から迎えた正室の泰姫。 感じのいい女性で、心和むひと時を過ごすのですが、残念ながら早世してしまいます。 以後、正室を娶ることはなかったそうです。 泰姫の侍女との信頼関係も、印象的。 光圀は生存中から名君伝説はあったそうですが、「大日本史」の編纂のために家臣を諸国へ視察にやったことなどが、江戸時代後期からの黄門様の話の元になったよう。 読み応えがありました!
13投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほどなるほど。今までのイメージとはだいぶ違ったなぁ。「義」を追求する若い光圀にはかなり引き込まれたけど、晩年が何ともさらりとしていて残念。特に、光圀とは違った考えを持った紋太夫の書き込みがもう少し欲しかった。
0投稿日: 2014.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世間一般で持たれている水戸黄門像とは全然違った、もののふとしての姿で描かれていた水戸光圀。その光圀が主人公。 冲方丁が書いているため、伝記というより、歴史上のファクトから類推して生き生きと光圀や同時代に生きた人々をエンターテイメントに描かれている。 出生にまつわる悩みから、生涯を義という信念のために生きた光圀の姿が、スケールが大きく格好いい。
0投稿日: 2014.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ長生きするとは、大切な人たちの死に向き合うこと。あの時代の人たちは短命。いや、現代が長命過ぎるのか。
0投稿日: 2014.01.22
