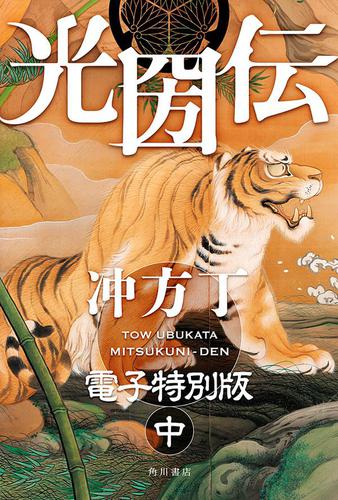
総合評価
(385件)| 173 | ||
| 131 | ||
| 39 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代物・歴史物は苦手で「天地明察」も苦手だったのに、今回ははまった。歴史上の人物を知らなくても問題なし。儒学や詩に興味なくても大丈夫。徳川御三家もろくに知らなかったから「水戸黄門」「先の副将軍」というドラマでのフレーズの意味がやっとわかった。親子・兄弟・夫婦・師弟・主従・友人関係と様々なドラマがそれぞれぐっときて、本の厚みどおりの重量感のある小説。
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門様の話。穏やかで、裕福な人で世間ずれしていないおぼっちゃんがそのまま大人になったような人物(テレビの影響かな・・)と認識していたのですが、そうではなかった。逆にうれしい裏切りでした。 己の義を通す頭が良くて正直で寂しがり屋で人間臭くて魅力的な人物でした。 本にするにはそうとう難しかっただろうな。でも、流石です。
0投稿日: 2013.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『天地明察』の豪快な光圀に興味を持って読んだけど、良い意味で期待を裏切られた。複雑な人物造形と全編を覆う死。不覚にも、ラストであっと唸らされた。 途中から脳内での光圀のイメージが中村獅童で固定してしまったが、他の方はどうだろう?
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読んだ本の中では1番、わくわくして読めました。 分厚いけど、数頁読んだらはまってしまって、あっという間だった。
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ諸国漫遊しない黄門様。 東野英治郎演じる好々爺とは全く違う徳川光圀がここにいました。 ひと言で言うと、『光圀って面倒くさい男だなぁ』という印象? とにかくあれこれと考えすぎている感じで、光圀の言う“義”には同意しきれない部分もあり、主人公には今ひとつ感情移入できなかったのですが、周りを固めるキャラ達の個性が強烈で、一つ一つのエピソードがみんな面白かったです。 父・頼房をはじめとする御三家の面々もいいし、武蔵や保科正之もいいんだけど、何と言っても泰姫。 泰姫が亡くなるところではウルウルしてしまい、人目のないところで読んでいてよかったです。 あー、でも、個人的には左近が好きです。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一つの事件がおきてAさんとBさんが動いて帰結する。その繰り返しで面白かった。 光圀が出逢う人間全員が、読む私の時に心に痕跡を大なり小なり残していってその人が死んでもその人がいた場所をみてしまう様な気持ちになった。 もんだゆうの「ずっとおそばにいとうございました。」では涙腺が緩んだ。そんなに私、彼に対して入れ込んではいないのだが。こういう離された者の叫びに私弱いんだ。
0投稿日: 2013.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ手に取ったときの厚みと前文の読みにくさに参りそうになったが、100ページを超えるとどんどん先が読みたくなった。 日本の歴史はあまり知らない。光圀がどんな人だったのかも知らなかった。義を重んずる姿勢は日本人が今も求めているモデルの一人であると感じた。豪胆なのに、詩作は繊細。権力者としては意外になことに妻を愛し続ける姿勢も素敵すぎる。「水戸黄門」として愛されるには理由があるのだ。
0投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」のスピンオフ作品といったところか。「天地明察」よりも分厚いけど。 てゆうか、完全に「一夢庵風流記」(花の慶次原作)だわね。男どもの友情・情熱(一部女がらみ)が重きを締めているのは慶次も天地明察も同じ。 文章も読みやすいしおもしろかったけど、冲方丁である必要があるのかな〜と思った。
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い話しであった。こんなに長くする必要があったのだろうか。テーマが絞れない。安井算哲が出てくる必要性は無かったのではないか。
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログわぁぁ~~~~っ! 終わってしまった、、、。 『天地明察』を読んで面白かったので 図書館に予約を入れて幾月か 順番が回ってきたのが日曜日。 751ページという結構分厚い本でしたが 素晴らしく魅力的な水戸光国(後半光圀を名乗る) 黄門様として、あの温厚なテレビの容貌くらしか 印象にない水戸光国ですが、 冲方丁の素晴らしい文章で あたかも、その場でシーンの一つ一つをのぞき見たような 臨場感!!! いい男っぷりにはしびれました。 終わってしまって残念と思うほど、 ずっと読み続けたかったわぁ。
0投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ知っていそうで意外と知らない水戸光圀。前提知識が無いので、どこまでが史実でどこからがフィクションか良くく分からなかったが、作品に描かれる江戸初期の文化や政治の雰囲気は興味を持って読む事が出来た。ただ、光圀が命をかける儒教的「義」にはあまり共感できず、作品から普遍的なメッセージのようなものを感じることはなかった。
0投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ労作にして大作。水戸光圀ってこういう人だったんだ、と初めて思うところ多数。そういう意味ではいい作品なのだが、冒頭の紋太夫を殺すシーン、時折挟まる光圀の回想の部分が興ざめで、作品全体を陳腐化してしまっているように感じた。 読んでいて思い出した作品は辻邦生の「背教者ユリアヌス」。キリスト教全盛の時代に古代ローマの宗教を復興させようとした姿など、なんとなく重なるところが多いような。ただ、作品の完成度はやはり… もっと歴史小説っぽくない歴史小説を書いてほしいと期待します。
0投稿日: 2013.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
水戸藩2代藩主徳川光圀=水戸黄門さまのお話です。 水戸黄門って言うと=光圀さんって感じだけど、黄門ってのは中納言のことだから、ほかにも「水戸黄門」はいるのだ! ……ってことより、そもそも水戸藩主は権中納言どまりだったんじゃないかな。 幕末の暴れん坊9代藩主の斉昭さんが死後に権大納言を贈られてるけれども…。 権ってのは「仮の」とか「次の」ってな意味で、サブっぽいことだよ。 で、このお話は光圀さんが同腹のお兄さんがいるのになぜ次男(頼房さんの子としては三男)の自分が藩主になったのか…と悩みながら成長していくお話だよ。 その過程で次の藩主にお兄さんの子を選んだり、歴史書の編纂を行なったり、朝廷とのつながりを得たりしていく生涯が、ちょびっと難しい言葉で描かれていました。 変にドラマチックな描き方はされていません。 でも、何ごとにも興味を示す水戸っぽの探究心がよくわかりました。 やっぱり らじも水戸カピーだな(笑) 水戸カピーとして、良い意味での刺激をいただけた1冊でした。
0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの小説のおかけで、どれだけ日常の憂さを忘れたことか。前半はひたすら痛快に、中盤は悲しみと別離に胸を詰まらせながら、そして終盤の充実と目を見張る展開。光圀、すごい。とても魅力的。歴史ものは今まであんまり読まなかったけど、名前だけ覚えているような人の人物像が立ち現れてくるのが、思った以上にわくわくした。朱舜水とか、しびれたなあ。
0投稿日: 2013.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この小説のテーマ(キーワード)は、「大義」である。 様々な人が考える「大義」。それは、同じ言葉でも、人によって、これほどまでに異なるのか。 隠居した直後の光圀が、側近であった藤井紋太夫を殺すシーンから始まる。 TVドラマでも、しばしば登場していた藤井紋太夫。彼にも、「大義」はあった。 それは、光圀に仕えるうちに、自分なりに考えるようになった「大義」であった。 この「大義」という言葉に注目し、この本を読んでほしい。 読みだすと止まらなくなるので、気を付けてください。 ラストシーンは、衝撃的。 冲方丁は、さすがです。 「天地明察」に続いて、感心しました。
0投稿日: 2013.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ重量感のある本だったので、飽きずに読めるか心配だったが、最後まで楽しめた。徳川光圀というと『水戸黄門』の知識しかなかったが、本書を通して一生を知り、とても親しみが湧いたし、勉強になった。作者の光圀への愛情が伝わってきて、読後の満足感が大きかった。
0投稿日: 2013.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀、水戸黄門として現代の我々に親しまれている好々爺な人物像とはかけ離れた、彼の剛毅なひととなり、濃厚な人生が、強烈な熱意を持って描かれていて、光圀と著者の熱意に引きずられるようにして読み耽った。古き悪しき習慣に縛られず、今でいう行政改革のような英断をする一方で、親しき者たちとの別れに苦しめられる光圀に魅力を感じた。歴史編纂を成す光圀の言葉どおり、歴史を記すことは連綿と続く、人の一生の繋がりを知ることだと改めて意識した。この作品はエンタメ的に魅力あるストーリー仕立てに上手くまとめられていて、「天地明察」同様、歴史を知る一端となる点でもいい作品だと思う。
0投稿日: 2013.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川光圀と言う人を堪能した。 幼き日から、藩主となり、そして退くまでの光圀の喜び悲しみ、そして野望、葛藤が生き生きと描かれていた。 また光圀の傍に纏わる人達も、光圀の人生に重要な役割を果たしていた。 そんな様子を丁寧にじっくりと味わった。 詩歌、史書などと、光圀の学問に対する探求心も深く伝わってきた。 史書に拘った人が、後の水戸藩の運命を知ったらさぞかし面白かったろうと思った。 “連綿と続く、我々一人一人の、人生である” 最後の一節が全てであると思う。
2投稿日: 2013.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは凄い。つけられるなら6つ星以上つけたい。個人的には、天地明察は、あんまりだったのだけど、光圀伝は本当に傑作だと思う。改めて、天地明察も読み直してみたい。
1投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ750ページを越える大作だったが、前に読んだ「天地明察」に比べると展開が地味で今ひとつ。一月以上かかってようやく読了。
0投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の豪快さと話の持って行き方の上手さに最後まで引っ張られて楽しめた。「天地明察」と多少リンクあり。
0投稿日: 2013.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」に比してこちらは「人道明察」とも言うべき作品。主人公の光國(光圀)だけでなく、他の登場人物もキャラが立っている。理想の君主に取り憑かれ「暗黒面」に入ってしまう藤井紋太夫が痛々しい。 映像化するなら映画より大河ドラマのように1年かけてじっくり作り込んだものが見たい。
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「義公」徳川光圀の一生をかけた義の追求の物語。 物語の中心は、彼が水戸家の跡継ぎ(世子)になった理由、そして冒頭の老中刺殺に至った彼のいきさつ、そのふたつの謎を解くものである。ある意味壮大なミステリーだ。彼の思う「義」は今の日本人には通用しない道理かもしれない。それでも彼の生い立ちがそうさせたと言うことを思い知らされる。彼の苦悩がぎりぎりと弓を引くように読者を追い立てるのである。 兄でなく、自分が世子だと言うことに常に疑問を覚え、犠牲になった兄や、世子とした父への想いなどに駆られて生きてゆく光圀。学問、詩作を通じて浄化し、盟友やよき配下、配偶者にも恵まれ、徐々に自分の生きる道を見出し、ねじれた世継問題を元に戻そうと試みる。しかしそこに、信頼し慕った者のさまざまな死があり、彼を奈落の底へ突き落とす。 それでも尚、彼を駆り立てるのは義への道であった。師や朋友、妻の言葉を胸に、学問や政治、将軍に対しても自らの力で切り込んでいく。その迫力や不動の信念。それ故に、自らの希望であった紋太夫を切らねばならなかった苦渋の選択が悲しい。最後に左近の膝で息を引き取るラストに、安堵の吐息を漏らしたのは私だけではなかろう。 私のように、天地明察を読んで、光圀伝を手にした方は多いと思うが、恐らく半分は脱落するのではないかと思われた。確かに算哲や保科正之も出てくるし、その他にも助さんやら風車の八七とかのモデルかなと思う方が出てきたりと、いろいろお楽しみは盛りだくさんなのだが。清々しい前作に比べ、この作品、特にはじめの方は重く難解である。子供に屍の川を泳がせる、斬首した頭を持って来させて杯にするとか、おどろおどろしい部分もあって、読むのにエネルギーがいる。実際私も時間がかかった。でも読んで何度も泣き、充実した読後感を味わった。ある程度まで進むと、まるで勝手に櫂が動く舟に乗せられているように、ぐいぐいと動かされていった。 * * * * * * * * かなりの余談ではあるが、私は茨城在住である。高校の時、文化祭の視察で水戸一高にお邪魔したとき、はじめて「水戸」の洗礼を受けた。多くの県立高が制服の中、水戸一高は私服で、また学生の考え方や教師の学生への対応が柔軟なのである。自分の高校のありきたりの文化祭が恥ずかしいほど、気概に満ちていた。その後仕事で水戸に1年在住したが、水戸の文化や学問に対する考え方は他の茨城の都市に比べて数段上の気がした。当時は県庁所在地だから、と思っていたが、光圀伝を読んで考え方を改めた。たぶん、これは光圀の遺産なのだ。光圀の死後かなり経ってからではあるが、斉昭が総合大学の礎である弘道館を開き、偕楽園を作り、蕩々と続く、彼の志なのだ、と。もちろん光圀伝がどこまでフィクションか史実か、というところはあるけれど。今年偕楽園で見た梅はまた別の感慨があった。また水戸を訪れて、彼の痕跡を探したいと思う。できれば徳川ミュージアム、西山荘にも行きたいけれど、この書き方だとどうやら予約が必要なのでしょうか。 http://www.tokugawa.gr.jp そして光圀や朱舜水の墓は非公開なのですね。 http://www.kadokawa.co.jp/mitsukuniden/blog/
0投稿日: 2013.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大河ドラマを丸々一年分いっきに見てるみたいな 重厚感、満足感。 最初は難しさに「やばい、、、この厚さ無理かも・・・」って思ったけど、 そんなの一瞬。すぐにわくわくして心躍った。 読み終わりたくない!光圀をもっともっと知りたい!って欲求が沸いてった。 どんな感想を書いていいかわからないくらい胸いっぱい。。。 哀しさってこんなに色々あるんだなぁ。 物語を読んだというより、1人の一生を知ったみたいな感覚。 これって一言じゃ表せないような人のいろんな感情がつまってて、気づかされることがいっぱいあった。 どこまでが史実に基づいていてどこからがフィクションなのか詳しくはわからないけど、 光圀という人物が過去にいたという事実を、こうやって私が知ることが出来ていること。 それは故人にとっても私にとっても素晴らしいことだなって思った。 過去を知るのも喜び、未来へ託すのも喜び。 時代時代にスタンダードから外れることを『おもしろい』って思える人たちがいて、 壊して変化を起こして、でも生涯を掛けても足りなくて。。。 期待して次の世代に託してくれてきたからこそ今の日本があるんだろうな~ そんな繋がりが今の世の中にもあるのかな? 図書館で借りて読んだけど、文庫化待てないので買います! もう一回じっくり読みたい!
0投稿日: 2013.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ったより重く長くて読むのに時間がかかったが、歴史背景も含めて楽しく学べた。どのあたりが小説オリジナル要素なのかイマイチわからないくらい自然に読めた。 光國/光圀の周囲の皮肉・軽口を叩ける人物が多くてどいつもこいつも魅力的だった。特に左の字! ひとつ気になったことは終わりにあとがきと参考文献がなかったが何か例示するものはなかったのだろうか。せっかくだからこの時代について更に何か調べ読みしたくなった。(もちろん未読の天地明察は読みたいリスト入りしました!)
0投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川御三家の二代目水戸光國(のちに光圀)の生涯を描いた作品です。武断政治から文治政治へのターニングポイントを歴史的背景として、光圀がどのように人間的な成長を遂げていったかに着目しています。青春小説であり、成長小説であり、儒教思想に触れることができる教養小説の側面もありますね。
0投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログB++ 天地明察がよかったから 光圀公の人生について、これでもか!と驚嘆するほど、掘り下げて書いたお話。 圧巻の一冊。 一つ一つの言葉の言い回しにセンスを感じる。そして、それが600p強も続く。面白さがずっと続く一冊だった。
0投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ事情から一気読みしたけれど、ちょっとしんどかった。 『天地明察』程の引き込まれ感はなかったということかな。 とても似通っている。 同じ世界、重なる時代を描いているのだから、悪くはない。 しかし、話の構造や展開までそっくりな気がした。 『天地明察』スピンオフ小説といった趣か。 これは作者が意図したものなのか、それともこれでしか書けないのか。 今後の作品によるな。 光圀という人物像を想像するには、良かった。 ご老公にだって、幼少時代があり、青春があり、野望があった。 多くの生と死を送るのは、長く生きるものの宿命だ。 紋太夫の抱いた義は、衝撃的だった。 水戸藩が後の世に果たした役割を思い、 光圀が産み落とした大きな歴史の種を思わずにはいられない。 先達がいて、自分が成長し、そして後身が生きていく。 歴史とはそうしたものの重なりで、人の生は連綿と続いていくということか。
1投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ三男でありながら後継ぎになった苦悩 そして、大義のために生きた光圀の一生を魅力的に書かれていて 大変面白く読みました。 太平の世になってからの武士のあり方 家を継ぐという考え方。義への探求心 まだ医療が発達していない時代の病気の怖さ さまざま人たちとの別れ などなど。 いろいろ興味深い読みごたえもあった。 それにも増して テレビでの黄門様とはひとあじ違った 光圀の魅力が存分に味わえ、泰姫、兄上、左近、読耕斎、 武蔵、保科正之等々、とても魅力的な人物がたくさんでてきて おもしろかった。 最後、お互いの義のためにたもとを分かつことになった心を許した家臣を 打つのはお辛いことだったでしょう。
1投稿日: 2013.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと読みにくかった…。 泰姫が好きでした。 左近が好きでした。 女の人の生き様がいい。 天地明察書いて、光圀さんを書きたくなったのかな。 今度は保科さんとか書くのかな。
0投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故この世に歴史が必要なのか。 生涯を賭した「大日本史」の編纂という大事業。大切な者の命を奪ってまでも突き進まねばならなかった、孤高の虎・水戸光圀の生き様に迫る。 『天地明察』に次いで放つ時代小説第二弾! 。・゜*・。・゜*・。・゜*・。・゜*・ H25.4.13 読了 前半は宮本武蔵や沢庵和尚、後半は天地明察の登場人物、保科正之が出てくる。この本のおかげで私の中にいたバラバラな人物たちが、大きな厚みとなってひとつになった。 もやが晴れたような、視界がクリアになったような気分で、とても気持ちがいい。 物語としては少し長くて(でも、ひとりの人の生涯を描くには必要な長さなのだと思うのだけれども)、読み終えるのに苦労した。連休になってから読めば良かったかも。 それでも続きが気になって、手に取ってしまうよな物語でした。 エピソードとしては、泰姫とのやりとりや、子たちに田植えや織物をやらせるところが良かった。 最後の紋太夫のところには本当に惹きつけられた!そういう考えに行き着いたからなのかぁ…。 光圀もすごく良かったし、読んで良かったと思える本でした。
0投稿日: 2013.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の大義と紋太夫の大義 「天地明察」以来のウブカタさん。「光圀伝」という名前から、助さん角さんが出てきて「ひかえおろ〜!」というのを想像していたワタシは内容が難しいのにビックリでした。 前作はそのつもりで読み出しましたが、本作は心構えが違います。京都から光國のお嫁さん「泰姫」が嫁いできたころからだんだんと面白くなりました。光圀の大義と紋太夫の大義、後々に迎える明治での大政奉還を思うと複雑な気分になりました。 助さん角さんのモデルや天地明察の安井さんも登場し、読み終えてみれば面白い作品でした。
0投稿日: 2013.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察に次ぐ冲方丁の時代小説二冊目、とうとう読み終わりました。今まで抱いていた水戸黄門様とあまりに違い、驚きでしたが感動しました。この本のおかげで江戸時代に興味を持てました!
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀伝読みおえた。751ページの大作で、かつ読書スランプということもあり、読み終えるのにほぼ1週間費やした。予想していたとおりの頑固爺の生涯だね。こういう爺さんは、どんな時代にも、どんな世界にも、必ず実在する。正直言って、彼の大義にも、頑固ぶりにも、たいして感銘を受けなかった。ただ、そいう時代を生きた人なんだね、そういう人物に江戸庶民が喝采した時代だったんだね、と。それだけ。 さて、今から予想しておこう。ここ数年のうちに、冲方 丁は、保科正之を主人公にした作品を書くことでしょう。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸の黄門様こと、光圀の生涯を描いた話。 「なぜ自分が世子なのか」 三男に産まれながらも世子となった光圀が 様々な苦悩を乗り越えて水戸の藩主となるまで 不義を義に立ち返らせるまで がおもしろかった。 後半は、近しい人がばたばたと亡くなり 然したる変化もなく長く感じられた。 「天地明察」を読んだときは 光圀カッコイイなーと思ったが 「光圀伝」を読むと 光圀の兄頼重や保科正之がすごく気になった。
0投稿日: 2013.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察でもチラッと登場して、お茶の間で人気の“あの”黄門様とは一味違った、偉丈夫たる存在感を醸し出してた水戸光圀その人を主人公においての長編歴史小説。ボリュームも1.5倍だし、天地明察を経て、自分の中でのかの時代に対する素地も出来上がってるから、世界観にも入り込みやすかったし、理解もしやすかったってのもあって、満足度は上記作以上のものがあった。上記作同様、人物間の交わりを中心に物語が進められ、とりわけ別離に焦点が当てられていて、穿った見方をすればあざといかもしれないが、人物の書き込みが丁寧であり、それぞれのエピソードを印象深いものにしている。いやいや、読み応え十分、感動の大作でした。
1投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門・光圀の生涯について。 「何故自分が世子なのか」 真意を一切話さない父、優れた兄を持ち、悩み続ける光國の記述がかなりの部分を占める。 そして途中から、驚くほど近しい人達が亡くなっていく。 水戸徳川第二代藩主として産まれた時から全てを手にしているかのように見える光圀だけれど、その人生は獲得と喪失の繰り返しだった。 戦乱の世から泰平の世に。 世の仕組みを変えていく時代の話。 次は保科正之の話描いてくれないかな。
1投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
熱いっ、そして厚いっ!! いやーもう光圀の熱量が半端ないのである。 幼少期から青年へ壮年、老年とその一生が描かれていくのだが、 その生があまりに濃密で、とてもじゃないが一気読みなどできるもんじゃない。あと、ほんっと厚い! 最初手にとったとき、これ、読めるのか、と思ったが、 殆ど退屈することなく読み切れた。ただ、私は寝る前に寝っ転がりつつ読むのが好きなんだが、これはムリ。腕が・・・・。もし眠たくなったりしたら 即、凶器じゃん。 自らの立場に疑問と抱き続け、苦しむ光圀。 正直、そのへんの苦しみ具合、とゆーのはそこまで気にすることなん?? と私には思えるのだが、彼にとっては重要なのだろう。 とゆーより、大好きな兄を自分が追い出した、とゆー事実がイヤなだけ、 とも。 最初に現れた武蔵の衝撃はすごかった。そのあと続々と、なんじゃこいつら的ななんかもうレベルが違う人たち続々でしたが、うん、あの真っ赤な 武蔵はほんっとびっくりでした。 その後、お前には藍があうといってくれた兄ちゃんがめっちゃ好き。 読耕斎にしろ泰姫にしろ、まさに朋友とゆうべき掛け合いが とても幸せだった分、それが失われゆくのがつらく。 それからも続々と見送る側に立つ光圀のあまりの死の存在の多さにびっくり。でも意外と医術も今ほどでない時代においてはあたりまえのことだったのかも、 もう二度と会えない、という哀しみを何度も何度もくぐりぬけ、 そのなかからでも人へ生まれ来る、とゆー喜びをみつけていくその姿が とても眩しく、本当に、左近さんは愛おしかったろうなあ、と。 そして冒頭で殺してるのは誰なんだーっとずっと思ってはいたものの 紋太夫だと分かったときはちょっと呻いちゃったぜ。 義、だとか、理想だとか、とても美しいもののようだけれど、 一旦暴走しはじめてしまうと、その下にどれほどのものを踏み砕いても是としてしまう怖ろしさがあるよなあ。 やっぱバランス感覚ってのは大切です。 でも、どうしてかそれほどのものを見出せることには憧れを抱いちゃうんだよねえ。 なんなのか、このないものねだりは。 にしてもほんっとすごい、人の一生をここまで書ききるとは。 フィクションではあるものの、それなりの知識がないと ここまでかけないよなー。歴史的事実ってのはちゃんと踏まえてるのだろうし。 すごい、もうただそうとしかいえないわあ。 学ぶ、とゆーことに対し、ここまで貪欲になれること自体、 なんなのだろう、と。そうそう先日中田さんが、学べば学ぶほど おもしろくなる、と言ってらしたが、そーゆーことなんでしょうなあ。 その楽しくなるとこまでいくのが、どーすればいいのか分かんないんだけど。
0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通り、水戸光圀公の幼少のころから最晩年までを描いた一代記。個人的に歴史小説の肝っていうのは、キャラ萌えだと思う。萌えという言葉が軽すぎてアレなら、歴史上の人物をいかに魅力的に描き出しているかということ。冲方丁さんなら間違いないと思ってはいたけれど案の定、主人公光圀はもちろんのこと、脇役の一人ひとりまでが非常に魅力的だった。萌え萌えしっぱなしだった。 わたしは恥ずかしながら歴史に疎くて、江戸時代といえば同著者の「天地明察」と、あとは漫画「大奥」で得た知識くらいしか持ち合わせていないのだけれど、何のストレスもなかった。歴史に詳しくなくても充分に楽しめると思う。(そして今回「天地明察」と微妙にリンクしており、渋川春海が登場した。読みながらついニヤニヤせざるを得ない……) 一気読みしてから気付いたのだけれど、1500枚と帯に書かれていた……夕方からぶっとおしで読みふけって(食事と風呂休憩は摂ったが)、読了して顔をあげたら深夜二時半だった……面白いに決まっている分厚い本は、ちゃんと覚悟を決めて休日の朝から読み始めましょう、という教訓。
0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ何をどのように厚め、さらに何をどのようにふくらませれば、このような大作の小説になるのか。漢文体の正規の史書ならば、われわれは読むのにあまりに骨が折れて、たぶん誰も手に取ることはない。だからといってTVの「水戸黄門」の再放送を見ているだけでは、歴史も江戸時代のイメージも得られない。 ミステリーはではないのだから、「紋太夫」事件は、読書が、この小説をいかに読んだかの、いわば「試金石」なのだろう。
1投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめと終わりの括り方(家臣をてにかける)も、それほどの重みを感じられないし、義に生きるという全体のテーマも所詮「弟なのに家を継いだ」ということへのこだわりだけで、これほどの長さを書くほどの内容かと思ってしまう。
0投稿日: 2013.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず、予想以上には面白かったです。私的にはそんなに読みにくくもなく、水戸に住んで水戸藩の話を読むのはなかなか面白かったです。 また追記します。 ********************************************** 【追記】 光圀の生涯にぐぐっと迫る感じ、光圀や水戸藩や江戸幕府や江戸時代や描かれている全てのものに対する偏愛っぷりとかは結構好みでした。 キャラ立ちはいいけど、天地明察よりはずっとずっとラノベ感が減ってると思います。長いけど案外すんなり読めたし、天地明察よりも余韻に浸ることの出来るラストのまとめ方が良かった。 私の中では頭の中で小説の世界の描かれていなかった部分を妄想できるのはすごくいい小説なので、これはその意味ではすごく良いと思います。 江戸時代には詳しくないから時代考証がどうとかそういう細かいところまではわかんないけど、小説としての世界観はものすごく一貫性がある。 こっからは気になる点。 まず各章が光圀が自分の生涯を振り返るようにして書いた手記(?)のようなものから始まり、その手記に該当する部分のお話が展開していくのだけど、それがなんかうまくない。 こういう手法は歴史・伝記的なものには珍しくないのだけど、たぶんうぶかたさんも慣れてないんじゃないかな?あってないと思った。 手記のあとに毎回前の章の振り返りみたいな部分がついていてもたつくし、リズムが悪くなる。毎回ブレーキかけられてるみたいな感じで、最後まで嫌だった。 あと、偏愛っぷりはわかるのだけど、小説としては情報が多すぎる。これもこれもこれもこれもいれたいー!って感じがばしばし伝わってくるけど、これも読むときの邪魔。光圀の生涯を描いた歴史的小説(娯楽的なもの)が書きたいのか、光圀の伝記(研究的なもの)を書きたいのかの区別がついてないんじゃないかと思った。読むほうとしてはあくまで娯楽的な(フィクションも混じっていると覚悟の)小説を期待しているので、時々混ざってくる文献的な書き方が邪魔。それを小説に入れたいのなら文体を考えて、って言いたくなる。 そして紙の本愛好家としては気になるのがフォント。 手記的なところのフォントは読みづらくても「まぁ、短いしそういう感じにしたいのね」ってところだけど、本文のフォントが嫌いだった。 まぁ、これは好みの問題かなー。 と、ずらずら書いてみてまとめるとすれば、私はうぶかたさんは歴史もの以外に興味はないかなーというところと、脚本でも書いてみたらおもしろいんじゃないかなぁーというところ(←つまるところうぶかたさんの文章がそんなに好みではないw)。 でも、光圀伝はよかったですよ。多少大目に見ながらよんでやろう(←偉そうw)という気持ちで細かい所に目をつぶれば読後感はいいと思います。
0投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門のイメージが強すぎる感がある光圀だが、実際は非常に優れた文才を持った文武に秀でた人物だったということが分かる内容。 幕末の水戸学につながる思想の原点が光圀にあったことが非常によくわかる作品。
0投稿日: 2013.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ流石にお見事。 水戸黄門知ってるようで、知らなかったことを痛感させられました。 司馬遼太郎と同じように凄い作者なのですね。 次回作はどの時代を描くのでしょうか、期待しています。
0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに充実した読書をした。水戸黄門の知らない部分を改めて 知る事が出来た。実質3日で読了したが、(骨応えのある)小説(評伝かな)であった。力作です。
0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
父への不信から傾奇者としておくった青春時代から、大切な人を早くに亡くし末代まで受け継がれることを信念に死ぬまで従事した史書編纂、 その中での分かれや出会いを経て成長していく光圀の成長期。 帯の光圀の絵からして強烈ですが内容はそれ以上に全日本人が大体思い浮かべる水戸黄門とは違い、衝撃的でした。 文武両道で天下の副将軍と呼ばれ庶民に愛された光圀はどんな人生を送ってそうなったのか。正直これが目に入らぬか~とやってた人がなんでそんなに偉そうなのかよく分かっていませんでしたが、光圀伝読んで納得しました。これは誰でもひれ伏すわ。 文字通り暴れまわった青年時代も戦国武将の一代記を読んでいるような爽快感がありましたが、盟友と愛する妻を亡くし鬱屈とした日々をすごしながらも史書編纂へ情熱を向けた壮年期が面白かったです。 光圀を一番おもんばかっていた忠臣を何故光圀自ら殺さなければいけなかったのか、そこに至るまでの二人の心情がよく分かるぶんやりきれなくなります。 去る人間を弔い、新たな誕生を目の当たりにした光圀がいうからこそ「如才」の意味が輝くのだと思いました。
0投稿日: 2013.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門こと徳川光圀が、ある男を殺害する所から物語は始まる。なぜ男を殺さねばならなかったのか。光圀の一生を追うことで、その真相に迫っていく。 冲方丁という作家は、期待と不安の使い分けがさながら飴と鞭のよう。幸せな状況にありながら、ある人物の死や幸福の終わりを予感させること。また、「明窓浄机」の章を挟み、謎への期待と不安を膨らませること。など、随所にその仕掛けが散りばめられ、続きを読まずにはいられなくなります。人物も魅力的な人たちばかり。光圀は勿論、兄然り、読耕斉然り、、、。泰姫はじめ女性陣もいい味を出しています。 一気に読んでしまいたいところでしたが、漢詩や諸々の知識が足りないばかりに、辞書を引きつつの格闘、結局読み終わるのに一昼夜かかりました。後半は勢いが付きすぎて辞書を引く余裕もなく読み切ってしまいましたけども。 義に取りつかれ、義を追い、義に生きようとした人、徳川光圀。光圀の一生を追う中で、沢山の人が生まれ、沢山の人が死んでいきます。脈々と続く、史書編纂の意思は、まるで生命の脈絡のように・・・。この物語は、小説でありながらも光圀の一生を生き生きと描き出したという点で、紛れもない「史書」の一つであるように思います。
0投稿日: 2013.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門でお馴染みの水戸光圀伝記。 水戸徳川家の三男として生まれ、世子に選ばれた光圀。 その苦悶と波瀾に満ちた人生を詳細に描いている。 改めて感じるのは、人は死んでいくという当たり前の事。 愛する妻、切磋琢磨する友、尊敬する恩人。 命あるある者は死する。 僕の両親も、友人も、先輩も・・・。 いずれは死んでいく。 『如才』 もういない者たち、存在しないものごとを あたかもそこにあるかのようにごとく扱い 綴ることをいう。
1投稿日: 2013.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
冒頭はえぐい描写ありで、なかなか読み進めなかった。 光圀が泰姫と結婚したあたりから、さくさくと 読めるようになった。 紋太夫は今でいう右翼だな。
0投稿日: 2013.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ黄門様の「大義」素晴らしい限り!!内容的には★5つでいい!けど、とりあえず長くて歴史が苦手の私は読み終わるのに2週間もかかりました(*_*)ということで、★4つです!でも、やっぱり歴史ものいいと思ったのも事実なので、他の歴史ものにも挑戦していきたい。 個人的には泰姫の人間性が好き!
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学生のころは「大日本史」の編纂者(当時は作者)として、 でも、僕としては勧善懲悪の象徴の印象の方が 断然強いご老公。 その生い立ちはしらないことだらけ。 後で調べて キーマン藤井某さんって本当にいたのね、 事件は史実なのね、って感じ。 なかでも殉死の禁止に至る経緯にはいちいち納得。 実在の人物かはわからないけど、 泰姫との死別以降の左近との関係性は切ないなぁ。 (男目線であることは仕方ないけど) ただ、とにかく分厚くって、 特に後半は頁が進むと人が死ぬ。正直疲れた。
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ…飛び飛びでしか読めなかったからか…途中棄権。 だから★をつける事はできない。でも半分までは読んだ。 「学」を競う場面が続いて疲れた。スリリングと感じる人もいるんだろうなぁ。 最後まで読めば、「あの場面があってこそ」とか思うのかも知れないけど。
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ★2013年2月17日読了『光圀伝』冲方 丁著 評価A 一作ごとに出来不出来の差が大きく、なかなか評価の定まらない冲方の大作。 水戸のご老公黄門様を幼少の生い立ちより描いて、その人となりを余すところなく描ききった作品。どこまでが、本当の話なのかは判断できないけれど、いかにも真実らしく物語られるため、話として面白く、息をつかせぬ緊張感のある740ページである。 自らの信じる義を貫き、そのために最愛の部下をも自ら殺さなければならなかった悲劇、文武に優れた巨人、それゆえに時の将軍犬公方綱吉からも疎んじられた背景などなど、さまざまな登場人物が交錯しては、消えていく。 天地明察の安井算哲が、登場してくるのもまた面白い。 なぜ、黄門様があれ程いまだに人気なのか、その理由が分かった気もした。 お勧めの一冊です。1995円買っても損はないと思う。
1投稿日: 2013.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ、あの男を自らの手で殺めることになったのか。老齢の光圀は、水戸・西山荘の書斎で、誰にも語ることのなかったその経緯を書き綴ることを決意する…。まったく新しい“水戸黄門”像を描く。 テレビで観た諸国漫遊の爺とは確かに違う、大男で血気盛んな水戸光圀像が描かれている。宮本武蔵や安井算哲(作者の前作「天地明察」の主人公)など、おなじみの人物も登場する。物語に惹きつける力は十分だし、「天地明察」と並ぶ力作には違いない。ただ中盤からやたらと周囲の人が死ぬ場面が多く、読んでいて切ない。大作を貫くテーマは「義とは?」だろうが、私には儒教思想はちょっと理解しづらかった。 (B)
0投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝記と呼ぶべきものか判断しかねるけど、大日本史という史記を編纂した、ご存知水戸黄門様その人の物語。 文武両道にして義の人。人との出会いに恵まれ、得難いものを数多く得る一方で、多くの大切な人をその手で見送らなくてはいけない悲しい宿命を背負った生涯。 兄を差し置いて世継ぎとされたことを疑問に思い、自分の存在を肯定するためにがむしゃらに理由を探していた少年期。 身命を賭すべき大義を見出し、成就のために邁進した青年期。 治世者としてのもどかしさを抱きながら、次代を見据えた事業に取り組む壮年期。 作中を通じて、快活な光圀の人となりを思わせるような清々しい文章で、読んでいて気持ちいいし、熱い思いの炸裂する大義成就の瞬間を始め、身震いするようなエピソードが散りばめられていて飽きない。 『天地明察』の主役だった安井算哲が顔を出す場面もあって、そういえばそっちの光圀公も出ててきてたなーとか思ってニヤリとする場面も。
0投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ冲方丁先生の、文人時代劇第二弾。 物凄い熱量をもって、文業と義のため生きる主人公の姿が熱い。前作に続き、その信念の中に、作者自身を重ねてしまいます。 また、本作の分厚さと比較すると、キャラクターも印象的で覚えやすく、非常に読みやすかった。史実の説明で進めず、あくまで"物語"として展開させていく作者の手腕が伺えました。
0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去と“今”がカラーとモノクロで交互に繰り返される感じ。マンガのコマ割りの様にその場の情景がイメージされる。面白かった。
0投稿日: 2013.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀、テレビで有名な黄門様、でも、彼の生き様は若い時に読んだ黄門の本が全く思い出されないが今回はかなり光圀が生き生きと描かれている。 すでに武士が戦で功をきそう時代ではないことを悟り、文で世のため、天を極めようとする姿は気持ちいい。 また一方で三男である自分が世継ぎになることにずっと心の中にわだかまりを持ち最後に義を貫くところは流石に凄いことだ。 その後の史書の編纂に注力を注ぐところなども天晴れ。 800ページ近くあるが一気に読ませるところは流石です。天地明察の安井算哲、保科正之などが出てくるのは当たり前なのだがさらりとかいてありました。 量が有るが起伏のある物語のため、読んでいて飽きない、座布団一枚! 天地明察よりいいかも。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ大国を光有す 光圀のいわれ 晋書 苦しまずに死なせてやるなら、欠(缶欠)盆(けつぼん)がいい 鎖骨上を肺、心へ刺す 朱しゅん水 明の学者 延宝9年 越後騒動 主席家老小栗美作と敵対する重臣が諍い 高田藩改易
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
水戸光圀の生涯を描いた作品です。文武い優れた天才とも言えるようですが、人生を過ごしていく際に、考えることや苦悩することは、誰にもあることが多く、そこから読者に何らかの示唆を与えようとしているようにも思いました。どの程度史実に合っているのかわかりませんが、勉強になった気がします。途中誰々が亡くなったというのが続き、少し辟易するような部分もあります。若いときに、暴れまわっていた人が、のちに優れた部分が出始めるというのは多いのでしょうか?そういう人が大物になるんでしょうか?途中兄を差し置いて家督を継ぐことになったことへの苦悩が強く描かれていて、個人的にはそこまでか~?と思いましたが、義の人ということですかね?北斗の拳のレイ?何かを成し遂げるには強い意志と粘り強い行動が必要なんだなと思いました。また大人になって、年をとって、成長していく姿は、偉人でも、一般人に近い部分があるんだなと思いました。
0投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀と聞くとドラマの水戸黄門のイメージしか無かったけど、ドラマとは全く違う豪快でどっしりした人物が描かれていました。 その外見と性格とは裏腹に詩で天下をとろうとしたり、義のためにいきた人生。とても読み応えがありました。 始めの300ページくらいまで全然進まなくてどうしようかと思ってしまいましたが、秦姫の登場で光圀が変わったように私も秦姫にやられてしまったのか、そこから一気に読むことができました。それだけに地の章は読んでいて辛いものがありました。 この本では宮本武蔵や光家がほんの脇役であり、多くの歴史上の人物が登場して勉強にもなりました。 最初と最後が繋がった時、紋太夫の義が判明した時のぞくぞく感といったら半端ない。そうくるのかー‼ すごい大作ですね。 天地明察の算哲もちょっとでてきたしそちらも読んだのですが、またいつか読み返したいなと思いました。や光家がほんの脇役であり、多くの歴史上の人物が登場して勉強にもなりました。
0投稿日: 2013.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビの水戸黄門とは全く違う『剛』のイメージの光圀伝。『義』を第一に考える生き方に感銘を受けました。今年No.1の面白さでした!
0投稿日: 2013.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門とは、全く違う光圀。 なんという文武両道をゆく人なのだろう。戦国の世の終わりから太平の世に移り変わる時代を、生きた一人の人間の物語ともいえる。家光の時代までは、本当に武士の世と言っていいくらい血なまぐさい時代だったのですね。 最初から最後までダレるということのない一冊。実写化するなら、映画ではもったいないと思う。大河ドラマな一生。さすがは水戸の副将軍です。 秀忠の正室、江と、初代水戸藩主の確執も、ちらっと描かれ、大河ドラマの江で、もっと江戸時代になってからの江を描けば面白かったのに、って思う。 最初のほうの、光國の義にかける思いは頭でっかちだなぁ、と思わなくもないですが、それも若さということだよね。感想文がいくらでも書けちゃいそうなくらい面白い…
0投稿日: 2013.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだ本の中でベスト10に入るほど面白かった! テレビで知られる水戸黄門のイメージとはガラリと違う、熱く血潮たぎる男、水戸光圀のお話。そしてその男に魅了される人々、魅了されすぎた人。 悪人と言われている紋太夫が誰よりも光圀に惹かれていて、惹かれすぎて色々狂っていく所、泰姫の懐の深さ、朱舜水の祖国を思う心、一つ一つの描写がとても切なく随所で泣かされました。
2投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川御三家である水戸藩の第二代藩主、水戸光圀の生涯。 三男で、長男頼重がありながら、父頼房から世子と定められ、年長者を重んじる儒子学で説く義に反することに苦悩する。 司馬遷の「史記」の伯夷伝」に感銘を受け、兄の子である綱條を養子に迎え、長男の血筋が家督継承すべきという大義を果たす。 小姓として仕え、三代綱條の代には大老まで務めた家臣藤井紋太夫を自ら殺めた理由は、紋太夫の大義が大政奉還にあったとして、一般的な光圀を失脚させるためという説を否定している。
0投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テレビのお茶の間に登場する黄門様像とは違いますが、人生をかけて、「義」を全うする光圀の姿が印象的でした。 剣豪宮本武蔵との出会いは死と生と言う事を考えるきっかけになる。林羅山の息子の読耕斎との最悪な形での出会いが生涯の学問の友となるなど露知れず。光圀の生涯でただ、1人の正室となる泰姫との出会い。そして、生涯人生の拠り所となる兄の頼重との幼少期の葛藤。そして、何より大きい存在である父頼房との関係など1人1人の光圀を取り巻く人たちが生き生きと描かれていました。 当然、人との出会いがある以上は、別れもある。特に、読耕斎と泰姫との別れは光圀が泣きじゃくる姿を見て、こちらまで胸を締め付けられました。 泰姫の「わたしが側におりまする」や読耕斎の「たかが世子」と言った言葉がどれだけ、光圀の心を支えていたか二人がいなくなって良く分かりました。 人生は出会いと別れであり、義があるからこそ人と本気で向き合っていける。久しぶりに、量的にも質的にも読み応えのある本に出合えました。
0投稿日: 2013.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的なボリュームで、とても一気には読めませんが、 次へ次へと、一気に読んでしまいたいと思わせる程の、 とても興味深く、とても面白い内容でした。 水戸黄門は、あまりにもTVドラマの印象が強すぎて、 史実にある実績や人物像をご存知の方は少ないのでは、 と思いますが、なるほど、こういう方だったんですね。 もちろん、冲方さんの解釈と脚色によるものですから、 そのまま、まるまる鵜呑みにすることはできませんが、 登場人物各々が、とても魅力的に描かれていました。 ただし、1点。光圀の大志と大義は伝わってきたけど、 作品からのメッセージが、よくわからなかったかな~。 でも、とても読みやすい、面白い歴史小説でした。 作品としても面白かったし、人物としても興味深いし、 何か、じっくりと読書をしてみたいと思われる方には、 オススメしますね。読んで、損はありません。はいっ。
1投稿日: 2013.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログTBSのドラマによる水戸黄門像に辟易していたのもあり、この小説での光國がとても痛快でした。若い頃の逸話を断片的には知っていたのですが、小説として光國の破天荒ぶりとそうなるまでのいきさつや、彼を支えた人々が「歴史上の人物」以上の存在感をともなって描かれていました。 茨城生まれ&在住の自分には、なじみの深い地名がちらほらでてきたのも嬉しかったです。
0投稿日: 2013.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ一代記を読むと魂抜かれたようになる……。非常に面白かった。 カリスマ性と義侠心を備えた眉目秀麗の殿様の話とか、単純な骨子だけで既に面白いのだが。 『水戸黄門』でお馴染み、二代目水戸藩主徳川光國の生き様を描いた作品である。ちなみに光圀は隠居語の名前。 初代藩主頼房の三男として生まれながら、優秀な長男を差し置いて世子に選ばれた光國は、人生の中で何度も「なぜ自分なのか」と問うことになる。自らを不義と考え、懊悩の年月を過ごすが、かねてから儒教の考えを尊び、よく学んだ光國は、その教えの中に自分の大義を見つけ、それを実現せんと決心する。 『水戸黄門』で培われた好々爺のイメージは『天地明察』で豪快な男に取って代わり、また『光圀伝』によって、詩文を究めんと欲した文事の豪傑というよくよく面白いイメージになった。もう白髪をたたえた尉面のようなイメージには戻れない(笑)。 最初のシーンが衝撃的なので、光國が殺戮を繰り返すシーンが度々出るのかと恐々読みはじめたが、思ったより詳細な殺戮の描写はなく、それより精神的な描写が中心でよかった(と、安心できたのは終盤になってだったが。笑)。 この最初のシーンで出てくる名前もまた衝撃的で、いつ現れるのか、現れたらなぜこの人間が、と謎はずっと残る。 心優しい兄頼重、よき同朋読耕斎に、正室泰姫とその侍女左近など、登場人物たちはとても魅力的だ。ちなみにかの有名な宮本武蔵に、同作者の著書の主人公で一躍有名になった安井算哲も登場する。 だが、歴史上の人物である以上、その生死は不条理である。 光圀の交遊関係の広さでは自ずと親しい人々を沢山見送らなければならず、その場面は毎回苦しい気持ちになった。そのせいか為景との邂逅のシーンは輝くように幸せに感じられ印象に残った。 光國と為景の互いの尊敬する気持ちの和やかさに癒され、近すぎる為景を窘めてあげる読耕斎のつっこみに笑った。 登場人物たちの輝きが強ければ強いほど、その灯が消える場面に於ける光國の寂しさを強く感じる。『光圀伝』最大の輝きを放った光圀の灯が消えた時も、たくさんの人がそれを強く心に刻み、悼み、寂しさを覚えたのだろう。 ところで伯叔の兄弟が、伯父・叔父の語源なんだろうと気付いた。光國が、兄と西山に住み暮らすことに憧れた場面は、なんだかむしょうに切ない気持ちになった。 感じたこと全てを書くのは無理なのでここで終わる。
3投稿日: 2013.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の光圀に対する印象がガラッと変わりました。 テレビ「水戸黄門」は光圀の人生の後半部たった一部に過ぎず、今まで私自身ノータッチだった「水戸黄門様」の正体がわかったような気がします。 どちらかと言えば悪しき人だったというか。 でも光圀の生き方は凄いと思います。私は士気が無いというか・・・。 江戸時代は今のように、きちんとした教科書や参考書がなかったと思うのに学問を極め、武術も極め、己の自己コントロールもして・・・ もっと自分の無知さに恥じらいを持って教養を身に着けてることが大切かな、と思います。いや、もっと色々なことに影響されることが大切なのかな。 とにかく、私は光圀の生き方に心を動かされました。
0投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年初の歴史小説。750ページもある分厚い本やけど、一気読みしてしまう位面白い本やった。何回泣いたかわからんくらいええ本です!
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ沖方さんの書いた水戸黄門の話。 長編だが、よくこれだけのページ数で収まったなぁと思うくらい、まとまっており、飽きることなく読める。光圀の人間性が魅力的で、時間はかかるが一語一語しっかり理解して読み、読み終わるのが本当に残念に思うぐらいのもの。話は全く違うもののドラマの水戸黄門を見ていた事もあり、その違いも楽しむ事が出来た。ずっと持っておきたい一冊。
1投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログまずこの本の厚さに尻込みして半分読むのに1カ月かかり、半分過ぎたところで面白くなったので3時間で読み終わりました。 とにかく頭を使って考えることが多く、あっさり読むものではありません。歴史上の登場人物も多くいるので、歴史を勉強してから読んだ方がより面白いと思います。半分からは歴史っていう感じではなかったので私でも楽しめました。
0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読み終えました。 光圀、なんて恰好いい人間なんだろう‼ 歴史的な細かな部分が勉強不足で読むのに時間がかかりましたが、登場人物がみんなとても魅了的でした。
1投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ最期が少し駆け足だったけど、幼少からとても読みごたえがありました。どのキャラクターも魅力がありましたが、泰姫が素晴らしい。
0投稿日: 2013.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごくおもしろかった。 主人公に、はまってしまったから。 感情豊かな性格は、読んでいて楽しい。 青少年期の光圀の激しさかわいさに萌え~となったり、大事な人たちとの死別に大泣きしたりと、かなり感情移入しやすい。読後は、光圀に出会えて良かった、という気持ち。 ただ、光圀が四十、五十をすぎると感情移入しにくくなるのは私が若いからなのか、作者が若くて老年の感情を描写しにくいからなのか…光圀の三十代までは「わかるわかる、その気持ち!」だったのがそのあとは「ヘェ~、そんなもんなんかなぁ」に変わりました。
0投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い頃は市井で遊びほうけていたこと、兄の子を跡取りとしたこと、自分の子は讃岐の藩主となったこと、大日本史をてがけたことなど何となく知っていた水戸光圀。それが幼少期から最期の時まで時系列に続く小説なのでとても分かりやすかった。 水戸藩特有の思想、勉学などについて分からないことが多かったが、その基礎がどの様に成り立ったのかが理解でき、今後の水戸学について学ぶ時に役立ちそう。 全体的に凄く面白かったが、光圀が神の様に立派すぎるて人間的な面白みに欠けること、本が分厚すぎて電車で読めなかったり腕が疲れることでー星ひとつ。
0投稿日: 2013.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ屏風裏での主従対面シーンは胸熱。 素朴な疑問がひとつ。独特なフォントの光圀伝。扉のフォントだけプレーンなのは、そういうお約束なの?(初めての気づいた!)
1投稿日: 2013.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今この時代だからこそ、全ての人々に読んでいただきたい。孤高の虎『水戸光圀』その生涯を収めた一冊。まさにこれが時代の本。生涯一生読み続けるだろう。これこそが日本の文であり漢の象徴だろう。
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「生きとし生けるもの全てみな、歴史になるのである」「正しい苦楽をもって、生をまっとうすること。そのすべこそ、大義なのである。」義を持ってまっすぐ前を見据え生きる。堅固な姿勢を崩さず、それでも素直な心と聞く耳を持つ。人間、光圀の魅力が存分に描かれた一冊。
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みごたえのある一冊でした。少しずつしか読めずかなり時間がかかったのですが、それはそれで楽しい読書の時間でした。 おなじみの水戸黄門のイメージとはかけ離れた光圀ですが、この雰囲気は好きですね。
1投稿日: 2013.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀がとことん魅力的! 苦悩しつつも義を見出し、義に生きる…まさに“美事”な人生である。 子どもの頃から大好きだった水戸黄門を、鮮やかにそして力強く書いてくれた作者に感謝。
0投稿日: 2013.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビドラマからイメージする光圀像を良い意味で裏切られる。 幼い頃から苦悩や葛藤に苛まれ、それを打ち消すが如く学問、詩歌に打ち込む事で築き上げられていく新しい光圀像。 決して聖人ではなく、私達と同じように悩み苦しみ、生きる喜びを感じるひとりの人間としての光圀に共感を覚えると同時に、どんな事があっても己の信じる道を突き進む姿に魅了され、ページをめくる手が止まらない。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ〈内容〉何故この世に歴史が必要なのか。生涯を賭した「大日本史」の編纂という大事業。大切な者の命を奪ってまでも突き進まねばならなかった、孤高の虎・水戸光圀の生き様に迫る。『天地明察』に次いで放つ時代小説第二弾!
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログお長、子龍と呼ばれる幼少期から光國そして黄門様と呼ばれて亡くなるまでの、まさに光圀伝。その義に生きた生涯が生き生きと描かれている。「大日本史」として編まれることになる史書の意義や背景もよく分かった。 如在など、儒教の教えも新鮮だった。 まさに時代を生きていた人物を描いた著者の史筆にも感心した。 13-2
0投稿日: 2013.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀の生涯を描いた作品。実兄ではなく何故俺が世子なのかという疑問と、文人として天下をとること。この二つが大きなテーマ。光圀の大義は果たして…? 光圀に関しては詳しく無いので時代考証はわからないが、文量の割に読みやすくて良かった。(wikipediaによると、だいたい正しい)
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこ、これが「天下の副将軍水戸光圀公」の一代記か。 ひたすらに「義」の何たるかを求め、それを貫いた、乱世から泰平への繋ぎとなった時代の稀代の大名の一代記だ。 一代記であるが故もあって、見送る人々が多いのが悲しい。 終章にも記されれいるが、幕末にあって会津と水戸が辿った道がすべて得心のいくような物語であった。
2投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ義とは、大義とは。 光圀というと時代劇の黄門さまを見て育ったので、この光圀像ははじめは面喰う。 世継ぎは自分でよいのかと悩みながら史書編纂・詩歌に情熱を注ぐ。 心の支えとした人々をなくしてなお願った大義。 人によって義は不義になり罪となる。 それを乗り越え己の信じた義に生きた人のお話でした。 春海がちょこっと出てきて、また読み返そうと思ったお話でもありました。
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの年末年始をかけて読んだ「光圀伝」。 前作「天地明察」が面白く感動する、人に薦めやすい作品なのに対して、今作は読み応えのある、なかなか凄い作品。 「面白い」とか「好き」といった感想は合わない。まさに、光圀という一人の人間の圧巻の人生を読み切った感じがする。 舞台は泰平の世であり、時代ものといっても戦は出てこない。 けれど、何人も殺めたり、人が次々亡くなったり、死が常に付き纏い、可愛らしい話ではない。 かといって、ずっと重苦しい雰囲気でもなく、魅力的な登場人物や主人公に笑ってしまうところも多い。(個人的には、読耕斉とお兄様がツボ) 冲方さんには、アニメ「蒼穹のファフナー」でハマって、「天地明察」を一昨年の年末年始にいっき読みして感動。(「マルドゥック・スクランブル」は残念ながらなんだか合わなくて読めず…) 志を持って生きる、ということを真摯に描く人という印象がある。 次回作にも大いに期待しています。
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門の生涯を描いた歴史小説。 おもしろすぎる。 義を貫くために生きた人生。 光圀の学問や詩に対する姿勢、政治に対する姿勢、父兄妻友に対する想い。 すごく響くものがありました。 全て光圀の視線で描かれているので、堅苦しい難しさもなくスイスイ読めました。 名著。
0投稿日: 2013.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門として知られる光圀公の生涯。江戸幕府創生期において、徳川御三家がどのような存在であったかがよく分かる。また、大名家に生まれても、いや大名だからこそ、小さい頃から甘やかされることなく、父親から徹底的に厳しく鍛えられているのを見ると、人の上に立つ者としての覚悟と責任感を見る思いがする。 諸国漫遊の黄門様も、ただ御三家という大名のご隠居ということで人気があるわけではなく、光圀の人となりに民衆が敬愛と称賛を寄せていたのだと分かった。 「天地明察」でおなじみの安井算哲や保科正之が違う角度から描かれているのもうれしかった。
0投稿日: 2013.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文芸書の本文は細明朝体が一般的だが、この本はかなり太い明朝。電子書籍のディスプレイを意識しているのかな?
0投稿日: 2012.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川光圀といえば、大半の人がそうであるようにドラマの中の好々爺としての水戸黄門しか知らず、本書の主人公として痛快かつ激情の人、かつこうまでも劇的な人生を歩んだ人物であるとは思いもよらなかった。 帯に「新たな水戸黄門像を示す」といったことが書かれていたが、まさにそのとおりだったと思う。 兄を差し置いて水戸藩の後継として指名されたことを後ろめたく思うがその感情の矛先を方方にぶつけた少年期。親友と伴侶を得て、兄への後ろめたさへひとつの解答を出した青年期。多くの別れと新たな誕生に次代へ繋げることに情熱を注ぎ出す壮年期。徳川光圀という一人の一生をとてもドラマチックに描いています。 天地明察の時もそうだったけれど、この筆者は本当に上げて落とすのが上手い。そして、ただ落とすのではなく、登場人物を落ちた事実から新たな未来や方向性へ進ませるのがとても上手い。 天地明察と時代設定がかなり重複するので、天地明察を前後に読んでおくとより楽しめる。長編ではあるけれど全体的に読みやすいので、歴史小説に抵抗がある人でもすんなり楽しめる一冊ではないでしょうか。
0投稿日: 2012.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ徳川光圀の、義を追い求めた生涯を綴った本。 個人的にはすごい好きな物語で、光國の少年期から話は進む。 天地明察に比べたらテンポは早くないし地味だと感じる人もいるかも知れんけど、読み手に深い感動を与える点ではどちらも同じに思える。 冲方丁の次回作にも期待だわ〜
0投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ一度ページをめくり始めたら止まらない。素晴らしい本に出会えた。 ともかく面白く、且つ為になる。 歴史を編むと言うことの一大事業をなす為の苦労、その「大義」、全てがきれいに折り重なり、独りの人間をなしていることが、精巧に書かれている。 おとぎ話の「水戸黄門」ではなく、一個人としての「徳川水戸光圀」を通して、人の世の常をしっかりと示してくれている。 生と死を繰り返し間近で見ていくうちに、強さを得ていく姿は読み応えがある。 後半の老齢となった彼が、綱吉に対する態度は見事。
0投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログふとすれば江戸年間の、長い歴史に存在した、といった程度の認識を持ちがちな、しかし知名度は抜群である男。その知名度の有り様を激しく揺さぶり覆した。 およそ時代背景に似つかわしくない激しさが鮮やかに読後感として刻まれる。
0投稿日: 2012.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作「天地明察」がとても面白かったので期待してました♪ 登場人物がみーんな真っ直ぐでよい人で、元気と勇気を与えてくれる作品だったからです。 それを期待して読むと今回は主人公の苦悩が多く、殺生も多く、爽快な読後感とは言えない仕上がりですが、それでもとても面白くて感動しました。 登場人物一人一人の個性がはっきりしていてイメージしやすいし、エンテメ性にも優れていて山場多いし、天地明察ファンのために渋川春海や保科正之まで登場させてくれるから盛り上がる盛り上がる! (ただ、私の中のこの小説全体のイメージは「花の慶次」(笑)。わかる人いるかな?ちょっとね、全体的に大げさで漫画チックなの) とはいえ、最後まで義を通す主人公のブレない姿が物語の柱となってしっかりいるから、ラストまで安心して読めました。 次作は清少納言にするつもりだと著者が話してました。期待大♪
0投稿日: 2012.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
徳川光圀の、義に生きた男の生き様を描いた作品。 非常に面白かった、いやとにかく傑作・名作。 途中までは好きなジャンルと言うのもあって「天地明察」の方が上と見ていたが、最後まで読んでその思いが吹き飛ばされてしまった。 一藩主の一生を追い続けながら、その結末はあまりに壮大。 史実と違う解釈ではあろうが、個人的にはぜひとも作者のこの描き方に一票を投じたい。 もちろん自分が心動かされた結末の部分だけでなく、「水戸黄門」でしか知らなかった一面とは別の、やんちゃで、剛毅で、懐の深い人物像は好き嫌いはあろうが引き込まれて行く。 また周りを固める出てくる他の者たち、好きな者にせよ嫌いな者にせよ、「天地明察」同様素晴らしいキャラクターの者たちばかりで、新たな人物が出て来る度にワクワクさせられる。 「天地明察」「光圀伝」両作品に共通するテーマは、時代を越えて受け継がれていくものの重さなのだろうと思う。 この作家の作品は前作と今作の歴史物2作しか読んでいないが、ぜひとも次も歴史物を描いて頂きたい所だ。 久しぶりに歴史の面白さに気づかされた作品だった。 「天地明察」は映画化されたが、ぜひとも『光圀伝』は大河でやってもらえないものかと思わずにはいられない。 最後に自分も一言申し上げたい、「大義なり、紋太夫」
1投稿日: 2012.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かったけど読み終えた!面白かったのは、青年期までかな。やっぱり若い頃の知識欲ってなんかすごいよね。よくもわるくも。
0投稿日: 2012.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビの水戸黄門とは異なる、徳川光圀の人生を描いた作品。いろいろな人との出会いと別れのなかで悩み成長していく光圀の姿。こんな人生、ちょっと強烈すぎる。
0投稿日: 2012.12.19
