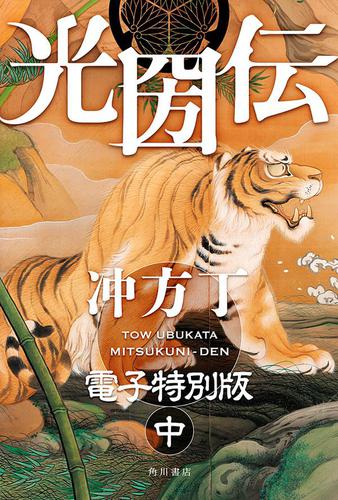
総合評価
(385件)| 173 | ||
| 131 | ||
| 39 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「天地明察」を読み終わった瞬間からこの本を手に取るのを待ち望んでいた。 図書館から予約本の準備が出来たとメールがあった瞬間のテンションは本当尋常じゃなかった。 天地明察にも出てきた徳川光圀の生涯を描いた作品。 開始一ページ目の登場人物紹介の欄でもうにやけてしまう。 予想はしてたが、最初に「あの名前」が出てくるとは思いもしなかった。 基本構成は「天地明察」と全く同じ、イベントをこれでもか、というぐらい詰め込みどんどんどんどん消化していく。 「天地明察」では最後のほうが尻すぼみになったという意見もあるが (それは渋川春海の改暦までのメインの話を主軸にしたため、作者も敢えてそうしてるのだが) 今回は最後まで怒涛。 連載時に大人気だったという光圀の兄、頼重だがこれが、まぁ本当いいお兄ちゃんでもう…。 家を出る話は泣いた。 そしてまさかの宮本武蔵、沢庵和尚。若干時代が被ってるんだな、沢庵幾つだよ、とも思ったが 山田風太郎好きの私からすればこれも思いがけぬ登場人物であった。 そして冲方丁、相変わらずこの時代の恋愛、結婚観を現代風に変換するのが上手い。 「天地明察」でもこの辺は引きこまれたが、今回も泰姫良かったなぁー。 やはり夢を追う、志高き人間というのはこうも輝くのか、と感動した。 徹夜も辞さない程面白い作品。
0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い長い、義を追い求めた光國の物語が、 そっと静かに幕を閉じたなというのが、今の読み終わった心境。 猛る虎のようでありながら、終始、静謐さが漂っているなと思うのは、 光國が武より文に重きをおこうとした結果だろうか。 最後の一文に、光圀の祈りを垣間見た気がする。
1投稿日: 2012.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀伝読了。歴史を紡ぐ物語、という話になると思いきや、徹頭徹尾水戸光圀という、一人の人生を描いた物語だった。異形ではあるが、その人生を通してみることで、異形の人は「義」の一字を貫こうとして生きてきたことが伝わる。 「天地明察」は歴をなす、という一つの目的を持った人間として晴海が描かれた。一方の「光圀伝」は,水戸光圀がどのような目的を持ったか、というレベルではなく、まさに彼の生を描いた作品。だからこその750ページだし、読み終えても分かりやすい答えはない。ただただ、冲方がみた光圀が描かれるだけ。 史実に基づく分、奔放さで言えばやはり、過去の冲方作品には及ばない。がしかし、光圀とその父親、強烈な個性を持ち苛烈さを持つ男を描くからこそ、歴史小説でありながら冲方丁という作家の個性が生きたのだろうなぁ。 そして、親友たる読耕斉や山鹿、最後まで「兄貴」であった頼重などが、本当に気持ちの良い人間たちで。それが鼻につくところもあったのに、読めば読むほど彼らの存在が大きくて。後半の藩主としての光圀の姿を見ていると、余計にそう思ってしまう。 作品として素晴らしいのが、少年であった光圀が、藩主になるまでの間、読んでいて自然に歳を重ねているのだ。傾奇者として江戸を渡り歩く時期の話が好きなのだが、自然と落ち着きを持つようになっている。それ以降の月日の流れが早いのは仕方ないが、未熟ながらもまっすぐ歳を重ねていく光圀の姿がいい。 とにもかくにも、冲方丁の歴史小説デビュー作は「天地明察」ではなく「光圀伝」だ!と、声を大にして言いたい。これが冲方丁ならではの時代小説なのだと思う。 …実は、光圀伝を読んでいて思い出したのが桜庭一樹の「荒野」。これも、主人公の歳のとり方がすごく自然に感じられた作品だったし、何か終着点がある話でもなかった。どちらも、丁寧に主人公の人生を追った作品。
2投稿日: 2012.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「光圀伝」を読んで思うのは冲方さんは博識なのだなぁということと、怒涛の如きエネルギーを持つ方だなぁということです。文章からは溢れんばかりの炎が湧き上がり読み手を軽々飲み込んでしまう。その手腕には感嘆するばかりです。 水戸が第二の故郷とはいえ無知な私に驚きの光圀像を見せつけてくれました。新鮮で面白かったです。 ただ気になったのはクライマックスを冒頭に持ってくるといった天地~と同じ手法。同じ手は喰わないと鼻白んだ。 また事前に何か起こるぞと予告する一文、例えば「だが、そうではなかった」等を多用するのが気になった。これでは何かを予測して構えてしまうし面白みが無い。 また物語の後半、壮年~中年~後年期がやけに駆け足で流れていくのが残念だった。もう少し何巻か分けて丁寧に書いて欲しかったかなぁ。紋太夫の大義についても唐突な気がしたし、それに対する光圀の対応もそれしか無かったのだという根拠がもっと欲しかった。
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい光圀像を描いた もう少し要領良くコンパクトにまとめた方が良かった。 大作だしレベルは高いのだが、前作よりは落ちる
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
徳川光圀の生涯を描いた作品。テレビの水戸黄門とは違い、本当の光圀の生涯に触れて面白かった。天地明察の安井算哲が出てきたりしてそのあたりも面白かった。ただ、個人的には天地明察のほうが面白かった。
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
☆4.5 光圀伝ってなんだろう。ファンタジー?とか思って借りてみたけど、まさか水戸光圀公のことだったとは。あの有名な水戸の黄門様じゃん。この紋所が目に入らぬかーっ!っていうセリフはなかったけど。 生い立ちから最期まで。途中、『天地明察』の安井算哲が出てきて、そういえば天地明察にも光圀は出てきたなぁって。そのほか、見たことある人たちがちらほら・・・・。 創作っていう目線で見たほうがいい話なのかな。史実に基づいたフィクションってとこなのかな。すっごくおもしろかった!
0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログドラマの水戸黄門の穏やかなイメージとは全く異なった光圀。それまで戦国を生きてきた武士達がその遺伝子を泰平の世で持て余し、光圀もまた 普通の青年同様 その激情を周囲に辺り散らしていた。 そんな青年が人と出会い義を全うしていく人生。 ドラマでのすけさんやかくさん、はちべい、 光圀が身分を隠して市中に出没する、というようなエピソードの発端を知って、その演出も成る程と思う。 また、同著者の前回読んだ天地明察の渋川晴海側からでなく光圀側からの心情を読み知りるそんなささやかな面白さもあった。 泰平の世にでてくるべくしてでてきた偉人なのかもしれない。 人は生き、また次の世代も生きていく。´ー`)
1投稿日: 2012.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かった。 文章自体は面白いのだが、幼少期から死期まで順に書き連ねているので、どうしても間延びしてしまう。
0投稿日: 2012.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ高知大学OPAC⇒http://opac.iic.kochi-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?isbn_issn=9784041102749
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀が水戸家大老の紋太夫を自らの手で殺めたのは,まさに正義と正義がぶつかればそこには殺戮が生まれるという皮肉だと感じました。 徳川宗家を補佐すべき水戸徳川家の二代目の光圀は,優秀な側近を育てるべく幼少の頃から紋太夫を見出し育てましたが,紋太夫の大義は既に大政奉還へと向かっていたということでした。 しかし,歴史は更に皮肉なことに,水戸家の血を引く最後の将軍が紋太夫の大義を受け継ぐ歴史的役割を果たすことになるということです。 本書は,実は武闘派であった光圀の生涯を追うもので,「天地明察」の主人公渋川春海も少し登場したりして面白かったですが少し長いです。
0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えがありました。医学の発達していない時代の人の命の儚さと、死との向き合い方。 この「大日本史」が幕末に日本を動かす書物になり、幕府滅亡へと導くとは、運命の皮肉を感じます。 とにかく面白かった。けれど難しかった。
1投稿日: 2012.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりにくく偉大な業績を知らしめるには御伽噺にでもするしかない。水戸黄門とはそのようにしてできたものか。 個々の人物描写の魅力的なこと。決して映像化を媚びていないのに絵が浮かび上がる。 歴史小説の最初にこれを読んじゃったりしたら、もう他が読めなくなるな。
1投稿日: 2012.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ「あの男」を自らの手で殺めることになったのか―。老齢の光圀は、水戸・西山荘の書斎で、誰にも語ることのなかったその経緯を書き綴ることを決意する。父・頼房に想像を絶する「試練」を与えられた幼少期。血気盛んな“傾奇者”として暴れ回る中で、宮本武蔵と邂逅する青年期。やがて学問、詩歌の魅力に取り憑かれ、水戸藩主となった若き“虎”は「大日本史」編纂という空前絶後の大事業に乗り出す―。生き切る、とはこういうことだ。誰も見たこともない「水戸黄門」伝、開幕。
0投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビなどで黄門様として知られる光圀とはかなり異なるイメージでしたが、なぜ自分が世子なのか苦しみ続けた若き時や詩歌への情熱、史書編纂へかける想い、また短くとも幸せだった妻との暮らし、良き友や師との出会いや別れなど光圀の喜びや悲しみをしみじみと感じました。
0投稿日: 2012.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
光圀の子供時代からの一生を丁寧に書ききった大作。泰姫が亡くなる辺りまでは、エンターテイメントとしても史実としても非常に面白かった。父親を求める気持ちとか兄への憧憬とかとても良く表されて、心が痛んだ。だが後半、特に紋大夫を殺めずにすむ方法は無かったのかと、その点が不満です。
0投稿日: 2012.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
やっと読み終わりました。読んでも読んでもページが減らないこの厚さ…。でも、冲方さんの描く人物はどうしてこうも深いんだろう。どの登場人物も魅力的で、どんどん引き込まれる。 戦国時代が終わりを告げ、江戸時代の平和な時代が定着してくまでの過渡期の物語。江戸時代をこういう視点で描く歴史物語をあまり読んだことがなかったので、新鮮でした。もともと幕末が好きなくせに、あまり時代背景を分かっていなかったので、「なぜに徳川御三家である尾張や水戸が倒幕派??」と疑問だったのですが、氷解。幕末に、水戸の流れを汲む最後の将軍慶喜が大政を奉還するに至るその萌芽が、江戸時代が始まった直後にすでにあったとは…!長ーい長ーい物語を読み終えて、この歴史がその後どう紡がれていったのかに思い当たったとき、あぁ~ここまで頑張って光圀の人生を追ってきた甲斐があったー…と思いました。なんとなく。
0投稿日: 2012.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ通勤中に読もうとしたが、想像していた以上に本の重量が重く、通勤中に読むことを断念。 かといって自宅で読む時間も取れず放置していたが、しばらくして電子書籍版があることを知り購入。 本を2冊買ったことになったが、内容に満足できたのできにしないことにした。 冲方丁の2冊連続の時代小説。前作の主人公が登場する場面があるが、連作ではないようだ。 自分の場合、時代小説だとストーリーよりも信憑性が気になり出して楽しさが半減んしてしまうことが多いのだが、この作品については、そんなことを気にする間もなく一気に読み終わってしまった。 時間があったら、もう一度読み直してみたい。 中身が濃く厚さもあるが、そう思わせてくれる作品だった。
1投稿日: 2012.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史に興味の無い人間が、それもこんなに分厚い本を読めるのか!思いつつも止まらなくなってしまいました。本が重くて片手で持って読めないくらい重い。義に生きる光圀の生き様もすばらしいし、彼を取巻く様々な人物も一人一人がドラマの主人公になれそうな人達ばかりです。天地明察より読みやすくて良かったです。
0投稿日: 2012.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ、あの男を我が手で殺さねばならなかったのか。 それは『義』のためである。 三男ながら水戸家の嫡男となり、その事に悩み続けた若者は自らの不義を義に変えんと欲した。 義にいき、義を貫き通した男の物語。
0投稿日: 2012.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀の言う 長男が家を継ぐという 大義がふーんという感じで いまひとつのりきれず・・・ 詩で天下をとるというのも 若き光圀のイメージとちょっと合わず なんだかなあ 宮本武蔵はじめ 歴史に残る偉人賢人たちと 初めて光圀が会う場面は どれもすばらしい とくに奥さんとはじめて合う場面 奥さんの人物像がすごい
0投稿日: 2012.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ気骨稜々に終生義を問い、史を編む。 有名すぎて実は知らなかった水戸光圀公。 読み終わって、また読みたいと心を惹きつけてやまない魅力がある。
0投稿日: 2012.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門こと徳川光圀の一生を描いた物語。 TVで放送される黄門様像が創られたものだとは知っていたが、こうも違ったのかと驚かされる。 豪快で強く、詩歌を愛し、義を貴ぶ。 そんな新たな光圀像を見つけることができた。 長くを生きた光圀は多くの出会い、別れと共に学び、成長していく。 光圀のキャラクターはもちろん魅力的なのだが、光圀を支える妻、友人もまた魅力的な人物達で、物語を彩ってくれる。 光圀の取り組んだ「大日本史」編纂の大事業。その重さ、歴史を知ることは今を生きることに繋がっている。 多くを学んだ老齢の光圀が語る「明総浄机」と、進行している成長の過程が交錯していく展開が面白い。 再読すればまた新しい発見があるのだろう。 冒頭の紋太夫の謎も、最後には成程と思わせ、途中「天地明察」と同じように難しく感じる部分もあったが、読んで良かったと心から思える一冊だった。
2投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初これは無理かも・・・と思ったけど、がんばって読みすすめていくうちに どんどんおもしろくなってきて、後半はがっつり乗って読みきれました。 算哲がでてきて、また「天地明察」読みたくなりますな。 時代劇水戸黄門のイメージが、実はこんな人だったのかという驚きと尊敬に変わりました。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初にいきなり結末を持ってくる構成は天地明察と同じ。でも天地明察は、クライマックスは読み始める人が予想できるので、それでも良かったと思うが、光圀伝は、いきなり手打ちのシーンから始められても、なんのことだかわからない。嫌悪感を感じるだけである。人を殺める嫌悪感は確かに前半のテーマではあった。それはそれで普遍的なテーマだとは思うが、老境になって、あえて殺生した理由はやはり唐突である感は読み終わっても否めなかった。 天の章、地の章はあまり楽しめなかった。たぶん主人公である光圀が、容姿端麗、頭脳明晰で、なおかつ武芸にすぐれ、家柄もずば抜けていて、お金持ち、しかも不良、そんな昔の少女漫画にしかでてこないような恵まれた人物の苦悩など、凡人に共感できるはずもない。史実を忠実に記載するあまり、逆に焦点が定まらない。何をこの本で言いたいのか?テーマはなんだ?何を書きたかったのか?最後までよくわからなかった。 良かったのは、人ノ章以降。強固な官僚体制は、思考することから逃げるようになる、というのが現在の政府の姿と被ることである。その中でどう生きるか、どうあるべきかが描かれていること。でも現実世界では、そんな人はスキャンダルで潰されてしまう。悲しいことに。 まさか紋太夫の意図が大政奉還だっとは!そのオチにだけは関心しました。 左近は、泰姫に忠誠を尽くして、自分を隠して光圀に嫁がなかったのかなぁ。ずっと第一側室だったのが真相だとおもうけど。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ渾身という言葉が装丁されて出てきたような気魄あふれる作品だった。熱さ負けしてすらすらさらさらとは読めない。 今生の生を未来に捧ぐ、人の生命をその手で奪うことも多かった光圀が至った言葉は史書に名前が遺ることない数多の人生もまた背負ったもので、史を遺すことの意義ここにあり、であった。 義というのはやっかいだ。全うするには時期にも人にも恵まれなければならない。そうでなかった者の生にも意義がある、と言われても全うできなければやはり無念であろう。 光圀は支配者として民に尽くす、民と混じり笑い合い、そして使う。そんな描写を読みながら浮かんだのは、全く、日本という国は君主制がよく合う国民性であることだ。
0投稿日: 2012.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ750ページに及ぶ、水戸光圀を描いた大作。さすがに読了に時間かかりました…。 ですが長さをまったく感じさせず、どこまでも前のめりで読める文章はお見事の一言。 父、兄、友、妻、師匠、その他多くの周りの人との熱い交流に胸震え、読みながら何度も表情筋を動かされます。 『天地明察』に続き、忘れられない言葉もたくさん。 個人的には詩の天下を目指すなかでの後水尾天皇との関わりが印象深い。 「義であるか」を問い続け、人生を生ききった水戸光圀。 とにかく描かれている内容のスケールが桁違い。名作でありました。
0投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログかっかっかっと笑うシーンも印籠も無い。 菓子箱の下に小判を入れて、『おぬしも悪よのぉ』 と言うセリフも無い。もちろん由美かおるの入浴 シーンもある訳が無いが確かに読み応え十分有り。 紋太夫の生きる時代がもう少しだけ後になってい たのなら紋太夫は時代に名を残せる偉業を成し遂 げたのかもしれない。生きる時代とタイミングが 合ってさえいれば…あのタイミングでは光圀も苦 渋であるが生かしておけなかったんだろうな。 読了感は大きな達成感だ。光圀の生き様が大きす ぎて、もっともっと頁が欲しかったとも思う。 映像化に期待感がある。これなら大河ドラマの視 聴率が上がるのは間違いないと思うし…そうなっ って欲しい。 『天地明察』の外伝的な要素も少しあり楽しめた どちらも主人公が何故自分が?と言う苦悩のまま 時間が経過していく。大義の為に人はどれだけ本 気になれるのであろうか?と考えさせられた。 水戸へ歴史探訪に行きたくなった。 冲方さんに、今後も歴史大作を期待します。
1投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ750ページにも及ぶ大作で密度も濃い。久々の本格歴史小説を堪能出来た。絶頂期の司馬遼太郎の作品に近いものを感じた。登場人物が全て魅力的で特に泰姫には惚れた。映画化するなら宮崎あおいかな、お付きの左近は、美人だから香椎由宇あたりがいいかも。しかし、冒頭が死で始まり、底流に流れるのは死の連鎖であり死の物語でもあった。次作は、この物語にも重要な位置付けで登場した宮本武蔵を書いてもらいたいな。
1投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが知っている、あの「水戸黄門」伝冲方版は、誰も知らなかった黄門様が描かれます。「天地明察」とも少しリンクしていて楽しめました。ただ750ページと言うボリュームは半端じゃありません。使用している紙のせいもあるんでしょうけどとにかく重たくて、電車の中で片手で読むのは苦労しました。
0投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ光圀さんってTVのお気楽なご隠居さんのイメージで読みはじめたら…幼少期から何故自分なのかを問い続け、結構辛い思いを抱えた「義」の人で、理解者との別れも多く、泣けました。 読者サービスでチラッと算哲も登場し(つながってたか〜)、もう一度「天地明察」を読みたいと思わせるところあり。
1投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白かった。水戸黄門といえば、テレビのイメージしかなかったが、 全く別人だということがわかった。 若い頃の光圀は見栄えもよく、頭もよく、行動力も力もあるという 魅力溢れるキャラクターで描かれていて、ぐいぐい惹きこまれた。 義の通し方が半端ではなく、兄に対して義を通した時には 思わず涙が溢れた。 後半は破天荒なキャラクターが少し落ち着き、 政治的な話、死にまつわる話も多くなるが、それでも読ませる力は衰えず、最後まで一気に読めた。 これを読む前に「海賊と呼ばれた男」 を読んでいたので、義を通すなど、二人の男に 共通点を感じた。
1投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ【今年No.1】 総700ページ超のハードカバー仕様を2日に分けて約6時間かけて読み終えた。 「壮絶に面白い」 これが感想だ。 読んでいる間は、本書に描かれている光圀公の熱量に圧倒されっぱなしであった。 己の出生を呪い、義を求め続けた青年期。 家族、友人の死に打ちのめされながら進んだ成年期。 文学や史書の発展に身を尽くした壮年期。 ここにはTVのような勧善懲悪劇は殆ど描かれていない。 義とは何かを求め、詩で天下を取るという欲望をギラつかせ、史書に人の生きた証を込めた水戸光國公の生涯がある。 蛇足かもしれないが、義に生も悪もないということが改めて分かる。 義はただ純粋に、義である。 「これは義であるか?」 常に己に問いたい言葉だ。 おそらく、来年の本屋大賞の有力候補になるだろう。
1投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ天地明察より、ユーモラスな要素が増え、そして、静かに積み重なる面白さ。歴史物苦手な人でもするする読ませちゃうところは、さすが沖方さんです♪
0投稿日: 2012.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」でちょっとだけ登場していた徳川光圀の一代記。水戸黄門のイメージを一新してくれる良い物語を読む事ができました。単に有名人を登場させて事件を解決というのではなく、水戸光圀の生き様を書ききった傑作だと思います。それにしても、自分を理解してくれる人に先立たれるというのは、半身を引きちぎられるような気分になるんでしょうね、読んでない人は読むべしです。
0投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログすばらしい大作でした。 スケさんとカクさんが言う。 「ここにおられる方をどなたとこころえる。先の副将軍、水戸の光圀公であらせられるぞ」 「えぇい、頭が高い、ひかえぃ、ひかえおろう」 ここで音楽がじゃじゃ~んとなって、 すこし厳しい表情のご老公様の顔がアップ! 誰でも一度は見たことがあるに違いない、ドラマ「水戸黄門」の最大の見せ場です。 長年親しまれてきたあのシリーズも視聴率が落ちてしまってすでに終了していますが、 私はけっこう好きでした。 おそらく、私の年代ではめずらしいことだったのではないかと思います。 大人になってから、 あのドラマあらゆる設定が 史実とはかけ離れていることを知り、 そして本書を読んで、光圀がこれほどまでに苛烈な存在だっとは、と 感動を覚えました。 スケさんもカクさんも全然違う。 八兵衛、「うっかり」さんじゃないじゃん!! 作品ならではの脚色はあるかと思いますが、 まっすぐな光圀の言動にはとても爽快感を感じます。 今の政治家のふがいなさをみるにつけ、 こんな風にひっぱってくれる人が永田町にいれば、 もっと日本も変わることができるのではないかと思うのです。 その一方で、光圀のひたむきさについていくのは、 周囲の人たちもたいへんだったろうし、 光圀の治世下の領民にとっても けして良いことばかりではなかったとも思います。 実際はどうだったのでしょう。 俄然興味が湧いてきました。
0投稿日: 2012.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一気読みに近い状態でガツガツ読み進めてたのにもかかわらず 読了するのに3日かかった。 長い話だったけど、不思議と疲れは感じなかったな。 『天地明察』共々、史実をこれだけ面白く読ませる筆力に脱帽。 とはいっても『天地明察』と圧倒的に違うところは 主人公として語られる人物の知名度だと思う。 水戸光圀の人物像を上書きするというひと手間が加わったことで より深く心に刻まれるものだということを身を以って味わった気がする。 ある意味ギャップ萌えともいえるかも。萌えたかどうかは別にして(爆)。 諸国漫遊記の出どころも史実に隠されていたというのが軽く驚きだった。 助さんのモデルはなんとなく判ったけど、格さんは誰だろう? 紋太夫か? (あとで調べてみたら格さんのモデルは安積覚だった/泣) 途中で挟み込まれた安井算哲のエピソードは所謂読者サービスだろうな。 次回作が既に気になる。 同じ時代を生きた、またちょっとだけ関わりのある人の話を読んでみたい。 その近辺の歴史を調べたうえで、 『天地明察』とセットで時間をかけて再読したい本。 文庫になったら上下巻か。全3巻かもな。
1投稿日: 2012.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) なぜ「あの男」を自らの手で殺めることになったのかー。老齢の光圀は、水戸・西山荘の書斎で、誰にも語ることのなかったその経緯を書き綴ることを決意する。父・頼房に想像を絶する「試練」を与えられた幼少期。血気盛んな“傾奇者”として暴れ回る中で、宮本武蔵と邂逅する青年期。やがて学問、詩歌の魅力に取り憑かれ、水戸藩主となった若き“虎”は「大日本史」編纂という空前絶後の大事業に乗り出すー。生き切る、とはこういうことだ。誰も見たこともない「水戸黄門」伝、開幕。
0投稿日: 2012.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校時代は日本史選んだものの年表も人名も覚えられないし面白さも今ひとつわからないし当然点も取れなかった類の人間ですが、面白い歴史小説っていうのは本当にここまで面白いんだなぁ…と実感できる一冊でした。 『マルドゥック・スクランブル』も『天地明察』も大好きですし、先に大森望さんのレビューをラジオで聞いていたので、まず面白いに決まっているとは思ってましたが、想像以上の面白さ。胸が締め付けられるような場面も何度もありました。時代劇のおぼろげな黄門様のイメージしかなかったのが逆に幸いし、もう本当に展開が新鮮でわくわくして、分厚いのにページを繰る手が止まらず、後半はもう一気読みするしかありませんでした。 冲方さんはつくづく「人の魅力」を描くのが巧みですよね。 また、時代的に当然とはいえ、『天地明察』とちゃんとリンクしている場面もニヤッとしました。 あと、執筆時期が重なっているのでしょうか、明暦の大火からの展開に3.11を思い出します(ご本人も被災されたとのこと)。 それにしても、最近立て続けに本で泣かされているなぁ…あー読めてよかった。
0投稿日: 2012.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクロググッとくる!けど、本当はもっと長編がふさわしかったのではないなかぁ、と。光國と師匠の関わりなんて、もっとじっくり描いてもいいよね。
0投稿日: 2012.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
平和な時代に(徳川家康の孫として)生まれ、三男にして家督を継いだことから苦悩する若かりし時を経て、「大義に則り、仁政を施す」という儒教に裏付けられた君子としてのあり方を実践した光圀の人生から、生涯を通じて貫くべき人間として大事な一本の芯を持つことの重要性(また、それを実践するための心技体の鍛錬の必要性)を感じました。
0投稿日: 2012.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログあの・天地明察の冲方さん~父・頼房は字・子龍の7歳の我に小石川邸の馬場に転がる生首を持ってくるように命じた。人は長と呼び,千代松が幼名だが実際には3男,同腹で6歳年長の兄・竹丸が病弱であり,次兄の亀丸が病没したため,世子となったが,父から脇差しを与えられたものの,肝試しをされているのだ。9歳で将軍家光に拝謁を許されて光國の名を貰い,12歳の正月に疱瘡に罹って死線を彷徨い,優しい言葉を掛けられて兄がいるのに何故世子なのか悩むようになった。寛永の大飢饉で死体が浮かぶ浅草川を泳いで渡らされ,死にたくない一念で成し遂げたが,父も泳いでおり,世子としての試しだとは思う。刀を貰い,鉄砲も与えられたが,兄は下館7万石の大名に取り立てられたものの,自分が追い出したような気がしてならない。14歳からは父と三人の傅役の許しを得て僅かな供だけで外出が可能となり,ありとあらゆる手段を用いて護衛を振り切ることに傾注し,芝居小屋や飲み屋や遊女屋へ出入りするようになり,17歳で仲間となった傾奇者の間では谷左馬之助と名乗って喧嘩もする。水戸関わりの者だと知っているようで,武士なら人を斬ることを恐れないはずと嗾けられ,浅草の荒れたお堂の下に住み着いた無宿者を斬り殺すことになってしまったが,必死の相手を一刀で倒すこともできず,通りかかった蓬髪の老武士が缺盆に脇差しを突き立ててとどめを刺す姿に圧倒される。逃げ出したものの,遺体が消えた不思議に老武士の正体を見分けようと出掛けた品川・東海寺にいることを突きとめて,出掛けていくと,住寺は沢庵・会津浪人の山鹿素行が居て,供養のために寺の雑事を命じられる。彼らは拾った帳面から水戸の御曹司と知って命じている。光國は詩で天下を取ろうと詩作に懸命なのだった。戦国時代を知りたければ瓶にネズミを数番いいれておけば解ると言う。讃岐高松十二万石に移封された兄と瓶の中を覗くとまさに地獄絵図がそこにあり,明を救うための援兵に賛同するのは如何なものかと考え直させられる。町奴と連むのは止めたが,千住で破戒坊主相手に学論をふっかけて撃退することに喜びを見いだしていた。しかし,倒すべき僧侶達を追い払って泥酔状態で光國を倒したのは隻眼の林家の次男・読耕斎で論に破れた挙げ句に反吐まで浴びせられた。詩を論ずるには史書に通じてなくてはならず,猛烈に学んだ挙げ句に読耕斎に再会したのは,尾張の伯父・義直に林家の講義を受けにいった折りだった。読耕斎は水戸家の所蔵する書に惹かれて小石川邸にも出入りし,光國に対しても恐れることなく,たかが世子と放言し,僧の姿を捨て採蕨の故事のごとく西山で隠棲したいのだと希望を述べる。義のない世にほとほと嫌気がさして居るからだが,光國の自分が水戸家を継ぐのは不義かと尋ねると不義だと断言される。兄を水戸家当主に据えるために何ができるかではなく,自分の血統に水戸家を継がせない方策を練る。紀伊の竹橋邸に招かれ従妹のおよつ姫に迫られるが何とかこれをかわし,朝食時に尾張の伯父の家に行き,史書編纂に取りかかっていることを知る。読耕斎の紹介で細野為景と書を交わすようになり,文武の者と褒められ得意となるが,冷泉家を継ぎ勅使として水戸家を訪ねて来た為景と面会し,意気投合して一回りも歳が離れている友を得られたことに狂喜する思いを抱く。伯父・義直が死んで史書の必要を説かれるが,興味のない光貞に代わり目録作りは光國がやらざるをえなくなった。父の奔走で近衛家との縁談が進む中,奧女中・弥智との間に子ができるが,伊藤玄蕃に水に流すことを相談するが,伊藤は子を産ませ,兄に預けると言う。輿入れしてきた近衛家の泰姫に義を貫くため,自分は子を作らず兄の子を養子と迎える積もりだと告白すると,聡明で闊達でもある新妻は子を交換すれば良いと新たな提案を行い,光國は我が意を得た思いだった。後の世に明暦の大火と呼ばれる大火事では家の者を統率し小石川から駒込へ誰も欠けることなく避難させ,駒込に史書編纂の場を設けることを父に許される。光國は赤痢に罹っても一命を取り留めたが,泰姫は二度罹患して命を落とした。旗本の子から抜擢した藤井紋太夫は13歳ながら明人を師として招くべきだと提言し,光國をうならせる。母は家光の子を産む者として懐刀である父・頼房に預けられたが,輿入れなく,兄と自分とを産み,父はこの不義を理由に生涯正妻を持たなかったのだと知る。冷泉為景が,読耕斎が若くして死に,父が59歳で他界し,追い腹を禁じ,儒式での葬礼を強行し,弟妹の前で兄・頼重の子を養子と迎え入れたいと宣告する。一人でなく二人。兄は渋々これに応じ,高松藩の世子に光國の子・鶴松を据えると言う。水戸藩主となった光國は弟達に領地を割譲し,母を見送り,将軍から認められた世子は水戸が綱方,高松が頼常と決まった。念願の水戸入りを許された光國は,水道事業が遅々と進まず,貧しさ故に悪党が蔓延る様を見て,博徒の大物と元忍の元締めを手下に加え,悪道の師とすることに成功する。江戸に戻って,学問の師を朱舜水を迎え,殖産実学を実践する。舜水は治道の四箇条を『政教分離』『税の公平』『大学制度』『海』であったが,淫祠破脚で政教分離はできたものの,税の公平までは至りそうにない。流感で世子・綱方が死に,采女が世子綱條となり,次代の水戸を支える者としては紋太夫が一番であった。紀伊の伯父・頼宣が死に,本紀二十六冊が完成した。火事小屋を小石川に移し,彰考館と変えた。早々に隠居した兄は子らの縁談を調えるよう要請される。別春会で仕入れた噂で僧を捨てた佐々宗淳・介三郎を得,全国で史書を集めるよう指示し,安積覚兵衛を紋太夫に代えて史館の要とすると,藤井紋太夫は不満らしい。詩作では言葉の神・後水尾上皇から依頼され,激賞される。保科正之が死に,改暦に失敗した安井三哲の後援も務め,儒者の蓄髪を強行する。大老の酒井家から松を頼常の妻と迎え,自家の嫁としては公家・今出川家の季姫が決まった。世間知らずの姫君を教育するため,小石川屋敷内に泥田を造り,実がならなかった悲しみを覚えさせた。隠居を考え始め,読耕斎の棲もうとした西山が思い出され,則天文字の圀の字が浮かびあがってきた。家綱が亡くなり,堀田正俊が綱吉擁立に奔走し始めると,舜水は日本の王となれと勧め,紋太夫も熱望しているが天災・火災に苦しむ貧民救済に奔走し,綱吉の治世に納得はできないが徳川の安寧の世を戦乱に陥れることに義は考えられない。後水尾上皇の硯に銘を入れ,朝廷から備武兼文・絶大名士と賞賛されても天下をとった気にはなれない。師の舜水が死んだ。朝廷から天皇直筆の手紙を受け取り,世情は光圀を天下一の善人と認めているが,それは綱吉にとって不快極まるもので,水戸家への嫌がらせは続く。生類憐憫令など笑止千万で相手にする気も起きない。水戸へ就藩すると一揆を煽動する間者が出没する。後ろで手を引いているのは将軍自らで,その稚拙な手口に呆れるばかりだ。大老・堀田が殿中で若年寄に殺害され,稲葉もその場で滅多刺しにされた。次には隠居を求めてくるだろう事を察した光圀は隠退の噂を流すように知己の大名に依頼すると,願いも出さないのに許しを与えようとする将軍に一矢を報いようと,一人の老中だけに大納言の官位を要求し,渋々受けて後,黄門と呼ばれることになる。水戸に隠居すると,またぞろ一揆煽動の間者が入り込むが前よりも巧みだ。さらに他国に一揆を起こそうとする水戸の密偵が逃げ帰ってきた。史書の断片を集めた覚え書きは秘されたが,何者かがこれを盗み見ているらしい。自由に出入りできるのは水戸大老のみ。親戚・知人を集めて催した能の会で,藤井紋太夫を楽屋に呼び出し詰問すると,水戸が将軍となった後,大政を朝廷に奉還するのが自分の義だと述べた紋太夫を宮本武蔵から習った缺盆を突いて命を絶った~天地明察の渋川春海の話は欠かせない。犬の毛皮で造った衣服20着は嘘。若い頃の放蕩生活や隠居した後の百姓屋巡りが膨らんで,水戸黄門になったのね,勉強になったわ。この本は「明総浄机」が織り込まれているのだが,だれを殺したかが最後まで解らない仕組み。なるほど,よく練られているし,よく調べ尽くしたと感心。言葉巧みで,まだ30代とは思えない。邸の根太を踏み抜いたり,茶碗を握りつぶしたり,表紙の絵の虎がこれをよく表している。穏やかな黄門像を打ち破る作りで,そりゃ元から黄門様も爺じゃなかった筈だよ。義に生きようとする猛虎が光圀の姿で,それよりも大きな義に出会って苦悶する最高の文人も,義を貫いた水戸家後々の当主によって成就する歴史の不思議を予見できなかったのだろう。それにしても,泰を失った後の女出入りが描かれていないのが不自然であるのだが,侍女の左近だけを書いて,後は察しをつけろというのか,意地が悪いなあ
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代を終え泰平の世の中に進むなか義のために苦心し、義のために生き抜いた徳川光圀の人生を描いた伝記小説。兄をさしおいて世子として父より指名を受けてからの苦悩の様を周囲の人々の触れ合いと供に絶妙に描く。そして治道、文事を極めた名君として名高い光圀の心のゆらぎを見事に史書から読みきって仕上げる。さすが筆者渾身の大作だな。あと光圀が影響を受けた脇役が兎に角豪華。宮本武蔵、沢庵、保科正之、林羅山。悪役の徳川綱吉もいい味を出してます。司馬遷の史記も学べる、感動と気持ちが高揚しっぱなし圧巻のファイブすた~。それにしてもこの作家凄いな。次は誰を描くのか楽しみ♪
0投稿日: 2012.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「正しい苦楽をもって、生をまっとうすること。そのすべてこそ、大義」ということが大きなテーマだと思うけど、親と子の葛藤や縁のあった人を何人も見送るということ…色々感じる事があって、読み応え大でした。個人的には 重畳 莞爾 善哉 と、外国語のように漢字の意味がわからず、辞書片手に読むという行為が新鮮でした。勉強になります。
0投稿日: 2012.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) なぜ「あの男」を自らの手で殺めることになったのか―。老齢の光圀は、水戸・西山荘の書斎で、誰にも語ることのなかったその経緯を書き綴ることを決意する。父・頼房に想像を絶する「試練」を与えられた幼少期。血気盛んな“傾奇者”として暴れ回る中で、宮本武蔵と邂逅する青年期。やがて学問、詩歌の魅力に取り憑かれ、水戸藩主となった若き“虎”は「大日本史」編纂という空前絶後の大事業に乗り出す―。生き切る、とはこういうことだ。誰も見たこともない「水戸黄門」伝、開幕。
0投稿日: 2012.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ冲方丁らしい小説ではあるけれど、「天地明察」のような読後の満足感に欠ける印象。これは主人公の成長がある意味諦観につながっているように感じたことも影響している気がする。 いずれにせよ、水戸市民は必読である。 ※水戸の記述は実は多くないのだけれど...
0投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『天地明察』が大好きだった。著者もその作品で知った。そういう経緯で本書も購入。 これまであまり興味を持たなかった光圀に興味を持ち、読後に何冊も光圀関係の書籍を購入した。そういう新しい世界を開いてくれた意味で本書は面白かった。 但し読中の感想はまず「残念な」。主人公光圀の行動指針としての「義」の導入がどうにも唐突に感じられる。さらにこの「義」に則って動く登場人物があまりに生身の人間からかけ離れて感じる。つまりは作者の「こう動かしたい」という意思が強すぎて、どうにも「作り物」の感じがしてしまう。人物が作者の「計算」のみにしたがって動いているように感じる。 『天地明察』については「史実と異なる」なんて批判があっても「だからどうしたんだ」と笑い飛ばしたくなるほど、小説としての世界観が素晴らしかったと思う。 残念ながら本書については、さまざまな「光圀論」の「寄せ集め」のように感じられる。登場人物たちに感情移入することができなかった。
0投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ地元の人が主人公なので思わず手に取る。後に冲方先生の作品と気づき、購入。 読んでないが先に貸した人物によると「面白い!」とのこと。読むのが楽しみな一冊。
0投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大作である。黄門さんこと、水戸光圀を扱った小説としては、一番史実に近いのかもしれない。戦争もなく、事件もそれほどなく、平和な時代を淡々と生きていく。地味な人生かもしれないが、いろいろな人たちとの出会いと別れが描かれている。 物語の初めと終わりに自分の後を託すはずだった紋太夫を手討にせざるを得なかった光圀の苦悩が描かれる。奇しくも、紋太夫の大義は朝廷に政権を返納することであり、水戸家出身の最後の将軍がその大義を果たすことになるとは。歴史の綾である。そこが一番のクライマックスである。 700頁以上のハードカバーが、2000円弱であり、お得感一杯の本である。
0投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀のイメージって時代劇の水戸黄門のイメージだったのでそれとは全く違うお話に驚くような不思議な気持ちでした。本当のところどんな人だったのかな?と興味を抱かせる力強い小説だなと思いました。
0投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んで良かったと素直に感じられる一冊。 天地明察に続き、沖方さんの書く文章の魅力に最初から引き込まれる。 梅の詩で始る物語、一人の人生を左右する出会いと別れ。 ネタバレは嫌いなので一言、天地明察では読みながら涙を流しました。 この光圀伝では最後の一文を読み、どっと文章が蘇り涙が溢れました。 素晴らしい一冊をありがとうございます。
0投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなんともすごい大作です。 水戸光圀の生涯が書かれたこの作品、まさに大河小説と呼ぶにふさわしいと思います。なんという読み応え、読む醍醐味が十分に堪能できて満足の一冊です。1週間かけて読了しました。 幼少期から引き込まれます。兄への複雑な思いが切ないし、父への畏れもリアルでした。 青年期も良かったなぁ。 光圀の破天荒ぶり、もやもやする心のうちはとても興味深かったし、江戸の街で若く滾るパワーや人との出会いが格別に面白かったです。 がむしゃらな学問への探究もよし、光圀の人物像にはとても惹き付けられました。 知識人たちとの語らう知の世界には心が震えました。 自分が学問をするわけではないのに(^ ^;)、宇宙を臨むような広がり感じられました。感動! 壮年期がまたじっくり楽しませてくれました。 光圀が歴史に残る人物となっていく生き様が、濃く深く描かれていて力強く圧巻でした。 周囲を取り巻く大きな渦のような政治の世界と人物たちを通し、光圀が成長していくなかで、不思議となにか自分にも教えられることがあるように感じました。人から何かを学んでいく光圀の明晰さ、柔軟さ、心の強さがいい。一方、伴侶を得ての光圀の真っ直ぐさも楽しく読みました。 そして未曾有の火災、多くの死別を経験した光圀の、晩年の思いは胸に迫るものがありました。若い頃には思い至らなかったことにふと気づいたり、ある時は自分の父は昔どんな思いでいたのかと考えたり、懐かしさを感じたり、若き立場には帰れない自分を思う。 涙が出そうになった場面が何度もあった。 光圀が人の世は…。と感じたように自分も人の生きることの移ろいを感じずにはいられませんでした。 大河のような光圀の人生がずっしり迫り、なんとも重厚な小説でした。 見事に書ききった冲方丁さん、本当にすごいことだと思います。 PS. 電車では本が重くて腕がつらかったです。上下分かれていても良かったのでは?
2投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった~!(長かったケド・・・)今更ながらに、知ること多し。わからないことも多数だけど・・・今までより更に(ちょっとは)興味深くなった感じ。『天地明察』の映画を観たせいで、水戸光圀 - 中井貴一、保科正之 - 松本幸四郎のキャストで読んでしいました。だから、読めたのかも(笑)
0投稿日: 2012.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応え満載。 歴史にずっと興味がなく過ごしてきたけれど 最近とっても歴史小説を面白く感じる。 こんな風に過去の出来事と触れ合えていたら、 学生だったあの頃もっと楽しく学べたのに・・・ 凄く勿体なかったと痛切に思う。 テレビの「水戸黄門」しか知らなかった私には 衝撃的で鮮烈な印象を残した。 まだ読んでいない天地明察も是非読みたいと思う。
2投稿日: 2012.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログボリュームがあったが、最後まで楽しめた。 水戸の黄門様としての場面は最後に少しだけ。 義に対する熱い気持ちの持ち主とわかった。 『天地明察』ともリンク。 作者は一生を賭けて何事かをなす人物の造形が上手い。
3投稿日: 2012.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門はフィクションと分かっていたが、水戸光圀とは何をした人なのか、よく知らなかった。 義を大切にし、そのように生きた。 別れも多く経験する。 熱く、切ない物語。
0投稿日: 2012.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」に次ぐ第2弾。すばらしい本に出会った。「明察」が傑作だっただけに2作目は厳しいと思っていたが、初めて山本周五郎「樅の木は残った」や司馬遼太郎「竜馬がゆく」高橋克彦「炎立つ」を読んだ時のような衝撃。しかも、単なる伝記ではなく、詩文の世界の頂点を目指す光圀、大義を追い求める光國が、生き方のすべてを「義」の一点に集約させるために手塩にかけて育てた家老を自ら殺さなければならないドラマを中央に置いたかつてない小説。750Pの長編ということもあり「明察」ほどには受けないだろうが、文句なしの★★★★★。こちらの方が遥かに衝撃が深い。幾度も涙をこらえねばならない場面もあり、ゆっくりと時間をかけて何度も戻りながら読んだ一冊。 「大日本史」編纂という大事業。何故この世に歴史が必要なのか。「人が生きてこの世にいたという事実は、永劫不滅である。」と。 長たるもののあるべき姿も示す。「藩主として最初になさなければならなかったことは「宣言」である。・・藩主とは「託す者」である。託すことの重さこそ、宣言の重さであろう。史書は宣言の軽薄を教えるものではない。宣言ののちに到来する人の世の重みをいかにして背負うかを教えるものである。」 尚、光圀の字は、もとの「國」は惑いに通じることから、晩年、八方の字「圀」に置き換えた不惑の名ということ。
1投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これは凄い。「天地明察」より深いなと感じました。「天地明察」は歴史物にしては軽いなあと思っていたんですが、「光圀伝」は読みごたえも充分で、まさか水戸黄門(いやもうこれが有名すぎて)で来るとはなー、やられたー、という感じです。 黄門様こんな方だったのね……。近頃は、歴史上の人物が登場する作品を読んだ後はウィキペディアも読むことにしているのですが、史実もしっかり押さえられているようで、この一生の書かれ方は見事だな、と。 ラーメン作る件は創作だろうと思って読んでいたのに、史実のようで……おおすごい。 それと、個人的に、儒学など中国思想が好きなので、その点も読んでいて非常に面白かった。 藤井紋次郎がなぜ手打ちにされたのか、の理由は創作のようだけれど、紋次郎の利発すぎることを散々書いてからの、あの大政奉還を狙っているという流れだったので、ゾクっとしました。うん、あの告白のシーンすごいかった。ついつい、「もしも、五代将軍の頃に大政奉還がなっていたら」なんてことを考えてしまいましたもの。 いやー、良かった。面白かった。 あ、ちょろっと安井算哲と絡んだのも面白かった。いらないエピソードといえば、そうとも言えるけれど、「天地明察」を既読で好きならば、ニヤっとするので、いいな、と。 次、山県さん中心でどうでしょう。そしてまたちょろっと前作と重なっていくという感じで。(って誰に語りかけているのか)
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ文句なしの5つ星。休日を丸一日捧げてしまった。 作者は光圀を通じて何を言いたかったのか。作家ならぬ身ではうまく表現できないが、ただ、人の営みが縷々と積み重なっていく時間の重さを感じた。 天地明察は傑作だと思ったが、本作はそれをさらに上回る出来だと思う。作者のただならぬ労力に脱帽。
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者2作目の歴史小説。美事! 前作との関係もあり、(否定するわけではなく)いい意味でラノベ的手法かも。
0投稿日: 2012.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「生涯に、この本と出会って良かった」と思える本の一冊!700頁余の大部で、読み終えるのに一苦労かと思ったが、光圀の世界に浸り、次々に読み進み、最後の頁をめくるのも惜しくなる、もっと光圀と付き合っていたい、そんな気持ちにさせる良書である。光圀といえば、助さん格さんを従えた水戸黄門、あるいは大日本史の編纂者ぐらいの知識しかなかったが(葉室麟の「いのちなりけり」の冒頭に光圀の紋太夫上意打ちの場面があり、光圀の別の面のある予備知識はあったが)、この作品によって初めて光圀の全体像を知った。類まれな資質に恵まれた光圀は、さらに良き理解者、優れた仲間に囲まれる。頼房、頼重、泰姫、読耕斉、保科正之、等々。なかでも、左近のなんて魅力的な女性なことか、思わずほれぼれしてしまう。そしてひたすら大義に邁進する。しかし、多士済々に恵まれながらも、やがて彼らと幽明境を異にせざるを得ず、ひたすら死者を見送るばかりの後半生。光圀の哀しみ、そして苦悩、光圀の心持はいかばかりか。読みながら、無人の泰姫の部屋の場面では、光圀とともに思わず涙した。 比類なき才能の渋川春海、豪放磊落大義のひと水戸光圀。何ともスケールの大きな英雄を、我々に呈示してくれた冲方丁氏は次にはどのような人物を登場させてくれるのか。
6投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「義」を貫くため、不器用なほど真っ直ぐに生き抜いた光圀の一代記。 751頁の大作ながら、飽きることなく読ませる筆力は「天地明察」から一段と上がったような気もする。 テレビドラマのイメージが強いため、晩年は好々爺の諸国漫遊の世直し旅をしていたと思われがちだが、晩年までの精力的な働きっぷりを読む限り、そんなことをする暇はないだろう。 「天地明察」の映像化にあたっては、作品の深い内容を2時間余りにまとめるには無理を感じ得なかった(それに恋愛映画みたいになっちゃってたし…)。本作がもし映像化されるにあたっては大河ドラマとか、じっくり時間をかけて見せる映像にして欲しいものだ。 あるインタビューで「次作は清少納言を書いてみたい」と言っていたが、著者がどう平安時代の女流作家の生涯を描くのか楽しみである。
0投稿日: 2012.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログいやあ、これは大作であった。かの大作、天地明察を凌ぐボリュームでありながら、一気読み必至であり、読み進めるにつれ、話が終わることが惜しくなるのは久しぶりである。人の一生を描く伝である以上、その誕生から死去までの全てを、偉人とはいえ、今は亡き過去の人間像を深堀した話を紡ぎだすための取材と知見は、一体、如何程であったであろうかと思うと、素直に脱帽である。何故、自分なのかというレーゾンデートルに悩む幼少期と青年期から、それを義として見出し、それを助ける伴侶と友人を得た以降の壮年期が圧巻である。話は時間軸とは別に己の回想を交えながら進行するが、その回想に大きくかかわる、お手打ちに至るまでの伏線は武蔵の時代から延々と張り続けたせいか、その結末は少々、拍子抜けに終わったが、それも又、良いだろう。それにしても煌びやかに登場する歴史上の人々を生き生きと描き、まさしく人が生きたことを後世に残すという意味においては、光圀の想いに通じるものがあるだろう。いやあ、まいった。これでは、万能兵器たる鼠の物語や、天かけ地を駆る妖精達の続きを、一体いつ書いていただけるのか、でも歴史ものも読みたい、どれでもよいから早く次回作をお願いしたい。
1投稿日: 2012.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言、壮大だった。天地明察にも劣らぬ内容で、死を隣にあるものとして生きる時代の者たちの人生が如何に熱く、信念をもって生きていたか伝わった。義を真っ当しようとした光圀はもちろん素晴らしいが、心が最も震えたのは泰姫が光圀の義を理解し、子の取り替え案を告げた瞬間だ。また泰姫臨終の際の生きたいという言葉には涙なくしては見れなかった。そして読耕斎、左近、頼房、頼重、ことごとくあっぱれな生き様の人物たち。賞賛は尽きないが、この本は人生において出会って良かったと思える一冊となった。
2投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったです。 とにかく、少年~青年の光圀が可愛くて仕方ないっ 非常に軽い言葉を使わせてもらえば、「萌え!」の一言w 沖方氏は、人物をとても魅力的に描かれますね。 それによって、あるいは史実より遠ざかる部分もあるかもしれないけれど、こんなに面白く物語を読めて、登場人物を愛せるのは至福。
0投稿日: 2012.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
水戸黄門こと徳川光圀の生涯を描く歴史小説。 多くのエピソードを持つ徳川光圀を少年時代からその死までを描く大河小説でありながら、エンターテイメント性もある作品に仕上がっています。 「水戸黄門」の講談的魅力とはまた異なる、その人間性の本質にも迫るものがありました。 構成的にも冒頭の家臣の殺害に至るミステリー的な要素(ちょっと強引な動機かも)もあり、大作ながら、最後まで読ませます。 特に読耕斎や泰姫との心からの交流と別れ、左近の存在による死者の如在感、紋太夫との大義における信頼と破綻が感動させます。 もちろん、スケさん、カクさんも史実に則って活躍しますし、綱吉との確執も上手に処理されています。 また、「天地明察」とのリンクもあり、「天地明察」からの読者サービスもあります。 次回作も大変期待できそうです。(次は保科正之かな)
0投稿日: 2012.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログテレビの黄門様のイメージが強い水戸光圀の幼少期から晩年までを描ききった大作。 700ページを超える分厚さだが、本を支える腕の疲れを忘れるほど面白く没頭した。 光圀は小市民の自分にはほとんど共感できない高みを目指す人物ではあるが、子供時代の屈託、詩に対する思い、自らの義を通そうとする姿勢などが胸に迫ってくる。ただ、儒教や詩について知識があったらもっと面白かったかも。 後半は藩主としての治政、将軍家との関わりなど政治的なエピソードが多くなり、光圀のエキセントリックさは影を潜めるが、日本史的に有名な事件にも言及されていたりするので興味深かった。 『天地明察』でおなじみのキャラも少し登場するのが嬉しい。
0投稿日: 2012.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ものすごくよかったです。 人物がとても魅力的で、それゆえに何度も泣かされてしまいました。 義とは何か 自分の生い立ちからそれを考えざるを得なかった光圀が いかに自分の義をなして さらには、ほかの者の義にどう向き合ったのか。 大変ボリュームのある本なのですが 読み応え充分どころか、通り越して大満足。 さらには、友人にどうぞどうぞと、薦めています
1投稿日: 2012.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
良くも悪くも「若さ」こそが冲方丁の最大の魅力だと『天地明察』と続けて読んで思う。若干35歳という若き作家がこのような長編歴史小説をさらりと書いてしまうことも驚くべきことだが、若い作家だからこそ書ける歴史小説だとも思う。それは光圀の青春期の姿から伺える。 「なぜ俺なんだ」 次男の身でありながら世継ぎとなって苦しむ光圀。物語はその光圀がある解決策を持って大義を成すまでに焦点を当てている。陳腐な言い方ではあるが、それは「アイデンティティ」という文脈で捉えれば非常に分かりやすい。青春期おける光圀は「なぜ俺が世継ぎなんだ」という疑問を持って、一旦自我を失う。自暴自棄になり、遊郭通いに没頭し、放蕩を重ねる。しかし、青年期に入り、理解ある友人に恵まれた光圀は、学問の世界に己を見出すことで、己の成すべき大義を見つけ、「アイデンティティ」を取り戻す。時代背景は江戸時代の初期ではあるが、それは現代に生きる若者にも通じるものがある。いつの時代でも若者は「自分はこれから何をすればいいのか?」という将来に対する漠然とした不安を抱え、それにもがき苦しみながら、やがてあるきっかけで自分の進むべき道を見出していくのだ。普遍的なテーマを持っているからこそ、この小説は力強い。 冲方丁がこうした「若者のアイデンティティ」をテーマとしたのは『光圀伝』が初めてではない。『天地明察』でも安井算哲という算術家を通して、同じような題材を扱っている。あるいは、冲方丁の「アイデンティティ」の追求は己の生い立ちに深く関係しているのかもしれない。海外生活が長く、「日本語に飢えていた」という幼少時代。多感な時期に様々な文化に接触することによって、自身のアイデンティティにも深く考察する時間があっただろう。安井算哲や光圀の煩悶する姿は冲方丁自身に重なる。 大義を成すことでクライマックスを迎えた今作『光圀伝』。それ故に、それ以降のエピソードが少々惰性と感じることがないわけではない。「なぜあの男を殺めることになったのか?」という序盤から引っ張った伏線は、あっさりと片付けられてしまったのは物足りない。それでも、幼年期から青春期、青年期にかけての光圀の姿はそれを補って余りある魅力に満ちている。いずれ大河ドラマになっても不思議ではない、この壮大な歴史小説を書ききった若き大作家に今後も期待したい。
2投稿日: 2012.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ己の卒業アルバムを読んだときに味わう、何とも言えない懐かしさと寂寥感。これを彷彿とさせる書。 750頁に及ぶ大著でありながら一気に通読。 しかし、泰姫のキャラが余りにも強烈過ぎて…
0投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにのめり込んだ小説! 自分の中で水戸黄門こと光圀のイメージは 1.大日本史を編纂 2.朱舜水を師匠に学びラーメンを食った人 3.若い頃の趣味は辻斬り だったが、これを読んで「詩で天下を取る」と熱い思いを持ち、勉学に励み、暴力ではなく筆力や舌力で人を動かした義に熱い人という好きな歴史人物の一人になった。 また、光圀だけでなく読耕斎や泰姫、介さんなど魅力的な人物が多いのも良かったし、その人達との離別のシーンには涙… 次は天地明察を読む!!
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ長編であるが、個性ある登場人物が生き生きと描かれ、面白く、一気に読んだ。 ただ、最後に明かされる紋太夫の「我が大義」は予想外というか飛躍し過ぎて、拍子抜けした。 その点で若干マイナスだが、良い本だった。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「天地明察」の光圀が魅力的だったのでかなり期待して読んだ。 光圀はもちろん水戸家家臣、林家などなど味のある人物がぞろぞろ出てきておもしろかった~ 冲方さん、次は何を書くのか楽しみです。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸黄門のイメージしかないひとに是非読んでほしいなと思う一冊。 「誰もがいずれ去らねばならない。だからこそ世にあることの義を思って生きるべき」 冲方さんがなぜ光圀を選んだのかが納得できる、とても魅力のある御方でした。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
手に取ってびびった。700ページもあるんだもの(笑)。 タイトルどおり水戸光圀の人生だが、「水戸黄門」の好々爺といったイメージより、若いころ辻斬りを行っていた殺人者のイメージか「天地明察」ででてきた「やたら血の熱い人」というイメージのほうが近い。 「天地の狭間にあるもの悉くが師である」と文中にもあるが、父 頼房、兄 頼重、妻 泰姫、叔父 義直、宮本武蔵、沢庵、山鹿素行 林羅山、林読耕斎、後水尾院、冷泉為景、左近、保科正之、朱舜水 などと出会い、学び、見送る。といったのが大まかな流れ。(その中で、自らの存在の確立、詩作、領地経営、史書編纂などを背景に物語はすすむ)。 ただ見送るでいえば例外は冒頭で誅する家老で、「歴史は連綿と続くわれわれひとりひとりの人生である」という記述からその歴史を断ち切る(ひっくり返す)からだった…かな? 4つの治道の記述と硬直化した幕府組織の描写がよい。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テレビ番組のイメージが強く、若かりしころの姿や暮らしぶりは想像だにしなかった「黄門様」。徳川御三家の世子として、どう育っていったのか、周囲の人間関係含め、闊達に描き出してます。そのボリュームたるや圧巻ですが、「眉目秀麗な源氏の中将様」と、光源氏を彷彿とさせるイメージ作りや取り巻くキャラクターの設定など、これからどんどんスピンアウトできそうな内容。光の当たるところも、そうでないところも描いているところにも魅力があります。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ明るく奔放な、しかし終始陰を背負った物語。 「我が今生の大いなる務めは、弔いの喪主か」という光圀のつぶやきの通り、彼が近しい人を見送り、それを無にしないために大義をみつけ、歴史編纂の大事業へと向かっていく話である。 「天地明察」ほど登場人物がマンガ的だとは、今回あまり感じられなかったが、それでもキャラクターは話に都合よく作りすぎなんじゃないだろうか…泰姫とか。そういうキャラ立てのおかげで快調に読めたというのも、確かなんだが。 でもやっぱり面白かったことには間違いないので、この調子で次は保科正之あたりを主人公に書いてほしい。「マルドゥック・アノニマス」が出た後で。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読耕斉や泰姫その他個性豊かな仲間(ライバル)たちとお互いに影響を受けながら成長していく姿が良い。 中国の師・舜水と一緒に調理をするシーンがとっても好き! 「天地明察」の渋川春海とのやり取りを、今回は光圀側から描いていて、面白かった。保科正之が大好きだったので、今回もまた出てきてくれてすごく嬉しかった。
0投稿日: 2012.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も泣きました。ただ、多くの人に読んで欲しい。 光圀公の生き様を知って欲しい。ただ、それだけです。
0投稿日: 2012.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ今度の時代小説は黄門様。750ページものブ厚さを一気に読ませる筆力に唸らされました。 「天地明察」のようなエンタテイメント性は薄いが、青年時代の「詩で天下を取る」という発想にも唸らされました。 儒学にまつわる蘊蓄も適度に心地良く、ライバルとの友情や妻への愛情など青春な要素もまた好し。そのキャラも際立っていて好し。
0投稿日: 2012.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ『天地明察』に続く冲方丁の時代小説第2弾。今度の主人公は黄門様こと水戸光圀。光圀の圧倒的な熱量を持つ生き様に圧倒され700ページ超を一気読み。また、彼の人生を彩る他のキャラクターもそれぞれが皆魅力的。個人的お気に入りキャラは読耕斎かな。『天地明察』の1シーンが光圀視点で描かれるファンサービスも嬉しい。
0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログスルーしてもらってかまいません(笑) うちは昔から大河ドラマを見る家庭なのですが…今、沖方さんの光圀伝が出ているので、(まだ誰も読んでない(笑))それが大河化されたら面白いし、いいよねと、母と妹と私で話ていました。 んで、主人公は誰がやるかって話で勝手に盛り上がり…。 沢村一樹、堺雅人、小栗旬、山田孝之、佐藤浩市… 色々案が出たけど、椎名桔平とかどうかな?? 若いとき→小栗旬、中年→佐藤 浩市 とかさ…って一作品でそんな豪華にできるわけないよね(笑) 光圀伝もマンガ化されて私の好きな作者なので、それもうれしいけど、肝心の沖方さんの原作はやはし格式高い感じで、ちょっと難しそう…。どうやら、光圀は人を何回か殺したことがあるようで、そのへんも奥が深そうです。 ちょうど民放の水戸黄門はやってないし、大河化されたら、水戸も観光客とかで、にぎわうんじゃないかなあ。と、地元民は考えてます(笑) …はい、マニアックでした。
1投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ・・・・・・ やっぱ書けないやレビュー、大作すぎて 断片的にしか知らなかった光圀公の生涯が 本の重さとともにずしりと伝わってきました。 泰姫がステキでした。
1投稿日: 2012.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ義に生き義に死んだ1人の男。 あまりにも有名なこの男の真の姿を、私たちはあまりにも知らなさ過ぎたのではないか。 水戸光圀、ヒゲと印籠はその一部分でしかない、その当たり前の事実の前に立ちすくむようで。 己の力では抗いがたい「宿命」に逆らうことなく流されることなく。それでいて諦めることを知らぬ男の、まさに「益荒男」の生き様に、今の日本に足りない大切なものを見た気がした。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ水戸光圀って、あの時代劇の水戸黄門様のイメージしかなかったけど、この話の光圀は全く好々爺ではない。何度虎のように「ぬぅ」「ぐぅ」とうめく事か(笑)虎のようにって、どんなや?こんなに必死に生きたら大変やろなー。きっと身近に居たら暑苦しい事この上ない。だけど強烈に魅力的。
0投稿日: 2012.08.16
