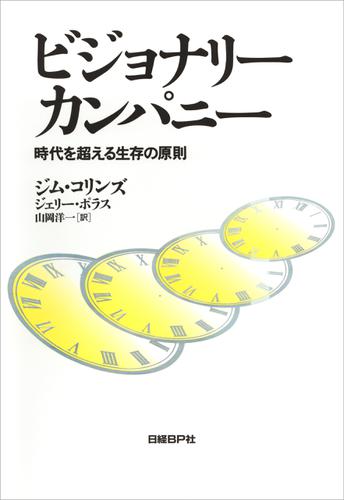
総合評価
(378件)| 149 | ||
| 127 | ||
| 54 | ||
| 12 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社という組織は往々にして利益追従傾倒や時代という変革に適応できずに衰退するか、適応した会社は反映するのかを一つの視点と解釈をを実践という形で提供する内容である。 本著は指すカリスマ経営者では時代を超えて活躍出来る企業にはならないと主張する。淘汰という言葉がある。不要なものを排するという意味だ。会社組織も同じで社会から不要になれば淘汰され、吸収または倒産するという形で消えていく。それはスタートアップだろうが、ベンチャーだろうが、中小企業、大企業や世界企業でも同様に言える。今、正に世界の最先端にいるメガカンパニーだろうが、100年持つかは誰にもわからない。もしかしたら、10年後には無いかもしれないからだ。 さて、本著ではその時代毎の流行に惑わされることなく、自社が主張する核心部分を核としながらも、時代という大きな変化に適応し、自社を更新しせよと強く主張する。この言葉はどの業界業種にも言える。別に時代に無理して合わせなくても良い。ただ、何故、それを今やる必要があるのかという問いを磨き続けて行動しながら修正していくことが必須だろう。 単なる利益や株主価値の最大化を目的にせず、時代が変わっても揺るがない「核となる理念」を持ち続け、その理念を軸に経営判断や組織作りが重要である。 本著は企業や組織作りについて様々な視点と思索を提供するものだ。だが、これは家庭内や副業レベルでも応用は充分に利く。巨大企業も家族という単位でも組織作りは重要なことだ。 自社が掲げる、個人が掲げる大きな目標と同時に、提示して社員や社会の心を惹きつけることが革新と成長を生む。そして、普遍的な基本理念を土台に、変化への柔軟性も持ちつつ、組織自体が永続性を獲得できる仕組み作り――これが「ビジョナリー・カンパニー」(時代を超える企業)の条件であり、何十年にもわたる成功の根本理由だろう。 時代を超えて活躍したい人に向けて読み継がれる良書であるといえよう。
0投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーは偉大なビジョンとゴールから生まれる。 ORの抑圧に負けるのではなく、ANDの才能を発揮すること。 変わらない強さと変わる強さを両獲りしていかなければならない。 時を告げるのではなく、時計をつくる。 (時を告げる予言者から時計をつくる設計者へと発想を転換しているか?) 理念に不可欠な要素はなく、どこまで理念を体現しているかがたった1つの不可欠な要素。
8投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書は様々読んできたが、この本ほど「自分は(自分の属する組織は)どうだろう?」と自問する本は無かった。 「業界内で確固たる地位を築き、長年に渡って世代交代をしながら生き残ってきた企業」を、本書ではビジョナリーカンパニーと呼ぶ。 そのビジョナリーカンパニーたちは、他社と何が違うのか?それを膨大の調査と事例で説明している本。 私は起業家精神のある方だと自負している。そしてそのせいか、若干会社内でも浮いている。 しかし、それがいいと思っている。 会社の理念には賛同しているし、それに沿った新事業を提案し、今はそれに向けて挑戦の日々を送っているのだが、そんな風にして過ごす社会人としての生活は燃える。 常にそうありたいと思う。 会社は私の一存では変えられない。 しかし、自分の考え方は変えられるし、考え方が変われば行動が変わって、自分の周りから少しずつ変わっていく。 『基本理念を維持し、進歩を促す』 本書で徹頭徹尾主張していることだ。 想いは曲げず、しかし柔軟に、挑戦し続けること。 それが、自分も楽しく、そして社会のためになる仕事だと思う。
6投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセンスだけを捉えるなら簡単だけど、読み込んで理解しようとするととても大変。骨太な本。 1章で概ね主張は完結している気がする。 そのあとは、主張を盤石にするための膨大な具体例を用いた議論。 単に色々な企業のことが知れるのは面白い。 でも読み切るには気合いと覚悟が必要。 本棚には置いておいて、気になったときに読み返したい
0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動指針とそれらからくるものが一致しているか。ここからズレた際に修正できるか。短期の利益があり自身からズレてる場合元に戻せるか。 MVVを元に判断、思考伝えるということはする。 Valueを再度読み直す。
0投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
古典的名著とされており、本書に似たようなことを述べているビジネス書は沢山ある。しかし、ここまでデータを調べて綿密に評価されているものは他にない。 ビジョナリーカンパニーとは、持続的に成果を上げられる組織のことであるが、そのためには明確なビジョンと浸透させるための仕組みが肝要だということだ。 とりわけ、自社に置き換えてみると短期的効率OR長期的成長…と、どうしても考えがちだったのだが、それはビジョナリーではないと論破された。AND思考で両立させる方法を考えていかねばならない。 自職場に対してビジョンを明確にすることはまず第一歩ではあるが、外部環境が変わったときにも本当に必要なものは?という視点での絞り込みはまだこれから。浸透させていく仕組みはこれから検討していかなければならないので、集中してやっていこう。
0投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自己啓発本って感じ 大きな驚きはなく、まあそうだよねくらい 結論をただ述べると言うより、その過程をものすごく細かく書いている、好みではない
0投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の大企業がどのような決断を重ねて現在にいたるのか、成長し続ける企業にあるものはなんなのか。さまざまな事例をもとに、 成功の秘訣をのぞいてみませんか。 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長の藤田晋氏は本書について「今の私があるのは、『ビジョナリー・カンパニー』 のおかげ」だとし、「『時を超えて成長し続ける企業』の特徴が解説されてい」ると語ります。 (盛久)
0投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ偉大な会社を作るためにはを徹底的にリサーチした本。 名著といわれるだけあって、素晴らしい本だった。 【ビジョナリーカンパニーのポイント】 - 会社の「基本理念」を持つ それが社内メンバー(特に幹部)に浸透しており、 かつ継続的に生かされている。 - toBe(あるべき姿)をもち、チャレンジングな取り組みを行う ex. ボーイング - 進化による成長 ex. 3M - カルト的なところもある - 最初のアイデアは素晴らしくなかったり、ない時もある - 試行錯誤の上、チャンスを見つけて、進化していることがある - 素晴らしい代表というより仕組み(時計)がある 素晴らしい基本理念をもち、それを継続していく。 そんな素晴らしい人、企業になりたい。
1投稿日: 2025.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ揺らがない理念を掲げている。理念が利益を越えるものと位置付けられている BHAGと呼ばれる大胆な目標を確固たる決意で達成しようとしている
0投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョンがあることも大事だけど、それをどれだけ内部の人間が信仰(半カルト的)して、一貫性持って進歩しようとしてるかが大事なんだと学んだ。転職先は大きなビジョンなどはないけれど、個々のレベルで理念を作っていけるかもしれない。
0投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ビジョナリーカンパニーにとって大切なこと 基本理念は維持し、それ以外のことへは進歩を維持し続ける ・ジョンジョン創業者 失敗は当社にとって最も大切な製品である (大量のものを試して、うまくいったものを残す) ・黒帯の寓話 黒帯は出発点。常に高い目標を目指し修行し続けること (決して満足しない)
0投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
帯:ビジョナリー・カンパニーとは会社という名の究極の作品である 要約: ビジョナリー・カンパニーとは基本理念を維持し、常に進歩を促し、細部まで一貫できる会社 基本理念=基本的価値(信念)+目的 基本理念とはつくりあげるものではなく、見つけ出すもの! とにかく基本理念を犠牲にしてはならない。他は変えてもいいが。 成功とは常に高い目標を目指す旅の出発点である 時を告げるのではなく、心を持った時計をつくる =理念と大志を持った最高の組織をつくる ビジョナリーカンパニーの創業者はカリスマ性はないが、絶対に絶対に絶対にあきらめない粘り強さがあり、組織志向である 特に重要なのは行動ではなく、根本から発想を転換して、どういう組織を作りたいか考え方を見直すべきである 単なる金儲けを超えた基本的価値観と目的意識である ⭐️利益とは人間にとっての酸素や水や血液のようなものであり、人生の目的ではないが、それがなければ生きられない 1基本理念を公言すること自体で、その信念に従って一貫した行動をとる傾向が強まる 厄介なのは数字を上げるが、価値観にあっていない人 2ビジョナリーカンパニーを築くには徹底的に教化する まず文書にする キーワードは本物であること 基本理念を維持し、進歩を促す 1社運を賭けた大胆な目標 BHAG ⭐️BHAGと呼べるのはその目標を達成する決意が極めて固い場合だけである ソニーは研究に適切なターゲットを設定している 組織>>マーケティング、製品、アイデア 2カルトのような文化 ⭐️基本理念を熱心に維持するしっかりとした仕組みを作ること カルト文化は基本理念を維持するものであり、これとバランスをとるものとして、進歩を促す強烈な文化がなければならない 起業家のようなやる気と創意工夫がないものは理念を受けつけないものと変わらないほど失敗する 3大量のものを試して、うまくいったものを試す 進化による進歩を積極的に促す 計画のない進歩←AmazonのAWSがそれ 目標と進化の両方ともが必要 誤りが必ずあることを認める 機軸(業界)から離れないではなく、基本理念から離れない 最も難しい仕事は冒険と挑戦の精神によって成し遂げられる 4生え抜きの経営陣 ⭐️創業者だったらどうするかを考える会社は理念を信じれていない 重要なのは優秀な経営陣の継続性が保たれていること 自分のためではなく、会社の理念のために生きているか 5決して満足しない ライバル会社がいなかったら社内競争したり、他の会社の製品がいいと思ったらそっちを使ってくれと言う精神 長期的な視野を口実に、短期的な利益の追求を緩めたりしない 人生も理念とビジョンを見て、毎日ベストを更新する ビジョナリーカンパニーになるには昔ながらの厳しい自制、猛烈な仕事、将来のための絶えざる努力がいやというほど必要である 近道はない ⭐️ビジョナリーカンパニーの真髄は基本理念と進歩への意欲を組織の隅々まで、企業の動き全てに浸透させていること 一貫性 ビジョン=長期にわたって維持される基本理念+将来の理想に向けた進歩 一貫性を達成するには 全体像を描く 一回ではなく繰り返す 小さいことにこだわる 神は細部に宿る 下手な鉄砲ではなく、集中砲火 相乗効果 流行に逆らっても、自分自身の流れに従う 正しい問いの立て方は「これはよい方法なのか」ではなく、この方法は当社に合っているのか、当社の基本理念と理想に合っているのか 矛盾をなくす ⭐️基本理念 進歩への意欲 一貫性 常に新しい進歩を求める精神を広める仕組みを考え出すべき 1時計をつくる設計者になれ 2ANDの才能を重視しよう 3基本理念を維持し、進歩を促す 4一貫性を追求しよう しっかりとした組織をつくる 顧客に密着するのは正しいが、それによって基本理念を犠牲にしてはならない 民主主義の本質は1人の指導者に依存しないようにし、過程を何よりも重視すること 大量のものを試し、うまくいったものを残す企業が変化に強い 手軽なノウハウ本に成功の秘訣を求めるというのはビジョナリーカンパニーが絶対にやらないこと
0投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024/07/04読破 一言 温故知新 感想 組織としてどうあるべきか?を理念を軸とした組織形成、繁栄している組織の歴史、過程、良いところ、失敗したところいろいろとデータを元に解説してくれています。 下記は印象に残った点 p22 自社ビルを見つける落とし穴を防ぐ →共通点ではなく、際立っている点を探す カリスマ性のない経営者 →ソニー、P&G、3M、メルクのような企業を築いた人々の仲間 p116 基本理念を貢献することの根拠 ①社会心理学の研究によると、人々はある考え方を貢献するようになると、それまではそうした考え方を持っていなくても、その考え方として買って行動する傾向が際立って強くなる。つまり、基本理念を貢献すること自体で、その理念に従って、一貫性行動をする傾向が強まることになるビジョナリーカンパニーは基本理念を貢献する傾向がはるかに強い。 ②ビジョナリーカンパニーは理念を宣言しているだけではなく、その理念を組織全体に浸透させ、個々の指導者を超えたものにするための方法もとっている。
1投稿日: 2024.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な事例と共に示される原則は、自分の実体験からも納得できる内容であり、興味深かった。自分の属する組織の運営にも是非活用したい。
1投稿日: 2024.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログサンプルの企業はかなり古いが、書かれていることは今に通じるところがたくさんある。古いからといって捨ててしまうのはもったいない。
1投稿日: 2024.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆すばらしい意図を持ち、気持ちを奮い立たせるようなビジョンを持っているが、その意図を活かす具体的な仕組みをつくるという不可欠な手段をとっていない組織が少なくない。 ex.ディズニー大学生 ◆カルトのような文化 ・先見性(ビジョナリー)とは、やさしさではなく、自由放を許すことでもなかった。事実はまったく逆であった。ビジョナリー・カンパニーは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向がある。 《カルトと共通する点》 * 理念への熱狂 * 教化への努力 * 同質性の追求 * エリート主義 ・個人崇拝のカルトをつくるべきだということではない。それは、絶対にやってはならないことである。学ぶべき点は、基本理念を熱心に維持するしっかりした仕組みを持った”組織をつくる”ことである。 ・カルトのような文化は、基本理念を維持するものであり、これとパランスを取るものとして、進歩を促す強烈な文化がなければならない。
0投稿日: 2024.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーとは、ビジョンを持っている企業、未来志向の企業、先見的な企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与えてきた企業と定義されている そんな企業に必要なのは、いつ、いかなる状況においても不変の理念を持つこと、そして、それに対して一貫性を持つこと、それを基軸にしてやれることは何でもやること、そこにカリスマ指導者だったり才能だったりはいらないと すごく励まされる内容だ 自分にはカリスマ要素も才能もないけれど、そんな自分にも理念やそれに対する責任を持てば、自分のビジョナリー・カンパニーを創設することができるんだと思えた 反面、この理念をどう設定するかが現状の課題でもある どんな状況においても、いついかなる時も変えることのない理念 それは個人レベルでは使命ともいえよう 自分はここが圧倒的に薄いと感じる 自分の使命は何だろうなぁ
3投稿日: 2023.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 勝利に英雄は必要ない。凡人が足並みを揃えて一心不乱に進んでいける仕組みだけ。企業理念から毎日のルーティンを築き上げる。それが秘訣。
1投稿日: 2023.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
真に優れた会社とは何か、を論理的に突き詰めた伝説的ビジネス書。長く売れている本というのはやはり安定して面白い。 結局ビジョナリーカンパニーってのは「長く大当たりをしている会社」なんだよな。そういう意味で「卓越した指導者」というのは必要ないし、むしろ邪魔になってしまう。大事なのは一つの方向に進め続ける『会社の仕組み』なんだ。 それを端的に表したのが「時を告げるのではなく、時計をつくる」というフレーズで、個人的にだいぶ気に入っている。 社会人として生きていると、思っていた以上に内部の争いが多くて辟易する。実際人が人を管理するのは一定数を超えるとだいぶ厳しくなってしまうため、もしビジョナリーカンパニーのような『統一性(思想の立脚点)』があればすごい楽だろう。そして変な方向に行かずにも済む。 今でこそ会社のビジョンやパーパスなんかが注目されるようになったけど、ガワだけ真似るだけじゃ意味がないってことをキチンと学べた。 ……自分の会社では全く出来ていないことを悲しく思えたのはナイショだぜ?
1投稿日: 2023.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ時を告げるのではなく、時計をつくる 利益を超えて 基本理念を維持し、進歩を促す 社運を賭けた大胆な目標 カルトのような文化 大量のものを試して、うまくいったものを残す 生え抜きの経営陣 決して満足しない 目次の書写しだが、ほぼ本書の内容を表している。 ビジョナリーカンパニー は特別なものではなく、普通の人間が作り上げたものであると。 ここからは感想を。名著なのだろうが馴染みのない企業ばかりでかなり読みにくかった。洋書特有の周りくどい感じが遺憾なく発揮された感じ。もう少しスマートにまとまっていれば良かった。
0投稿日: 2022.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログお客様(=社長)が「自分の会社経営はこの本を参考にしてる。というより、この本から経営の考えもらってる」と言ってたから、商談前に一読。 「世代が変わっても、長く続く会社の特徴」を、そうじゃない会社と比較しながら書いてるやつ。具体的な、事実がベースだから結構へぇ~てなる。 うちの会社もビジョナリーカンパニー目指してんのかな、歴が足りてないだけで、特徴はすごい当てはまってると思う。 -- 雇われの身としては、ビジョナリーカンパニーの社員は勘弁...ほんまに理念にビシィィって価値観合えば最高なんやろうけど、そうじゃない(=8割共感、理解はできるよという)場合はしんどすぎる。 カルトって書いてたのはまさしく。 一般底辺社会人の私には早すぎた! 自分のサービスちゃんと作って、仮に人にお仕事お願いする立場になったら再読!!!
0投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から「読まなくては」と思っていた本です。 ようやく読みました。 自分が想像していた内容とは違っていましたが、会社のあり方を考える上で、参考になりました。 とはいえ、ビジョナリー・カンパニーへの道は、なかなか厳しくて険しく、そして遠そうだということもわかりました。 個人的に気になったのは、この本の内容が、本当に成功の法則といえるのかどうか、という点です。 巻末に、この点に関する補足がありましたが、説明になっているような、いないような…。 この辺り(再現性の立証の難しさ)が、経営学の難しさなのかも、と改めて思いました。 とはいえ、会社の経営を考える上で、よい本であることは間違いないと思います。
0投稿日: 2022.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ概念として4つ ①時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 ②ANDの才能を重視しよう。 ③基本理念を維持し、進歩を促す。 ④一貫性を追求しよう。 かなり古いものではあるが、確かに同じようなことをしていた日本企業もある。理念をつくるなど。 ただ、現在では時を告げる予言者がトップの企業も多く、カリスマ性に溢れる経営者もいる。 少し時代のズレがあるため、シリーズを読んでみたくなった。 そのような経営者たちに、どのような考えを持っているのだろうか。 説明 企業の使命として株主への利益還元がさけばれて久しい。しかし、ジョンソン・エンド・ジョンソンのように企業が奉仕する優先順位として1に顧客、2に社員、3に地域社会、最後にようやく株主という基本理念を掲げる企業がアメリカの経営者から尊敬を集めているのも事実だ。 本書は、アメリカの主要企業のCEOから採ったアンケートによって選び出された18社の歴史に対する6年間の調査から生み出されたレポート。企業を組織する人間が企業内に活力を生み出すのは、カネでは計れない動機づけにあるというシンプルな「真理」が、ライバル企業と比較された各社の資料、エピソードから浮き彫りにされる。著者の1人であるコリンズはコンサルティングも手がける大学教授であるためか、随所に抽象化された概念と企業が取るべき方策が図を合わせて示される。しかし、経営指南よりも、世界を代表する大企業の決断の歴史が斜め読みできる魅力の方が大きいだろう。(青木 明)
0投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ400ページ近い大著であるが、ビジネス書でもあり、誰でも知っている大企業を例に挙げているので、また訳も良いのだろうが、サクッと読める。ビジョナリーカンパニーの定義として業界で卓越した企業、私たちが暮らす社会に消えることのない足跡を残しているなど、があげられているが、長い間、繁栄している企業と考えられる。いわゆる100年企業というものだろうか。それらの共通した項目をあらわしたものである。「ビジョナリーカンパニーになるためには、基本理念がなくてはならない。また進歩への意欲を常に維持しなかればならない。そして、基本理念を維持し、進歩を促すように、全ての要素に一貫性がとれた組織でなければならない」と、基本理念の重要性を強調している。その意味で自分達のお式を見直すと、100年企業への道が見えてくる。息が長くベストセラーたるべき書物だと思った。
0投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白い。永続に続く企業はどんな企業か。。。。 いきなり聞かれてもわからないような事の答え?が書いてある気がします。 個人的には カルトの様な文化 が一番衝撃的だった。。。やっぱり世の中甘くないなと。。。。笑
0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ長いので流し読み… ビジョナリー・カンパニーとして存続するには、目先の利益にとらわれず、長期的なビジョンを持ち、時には大胆な目標を掲げ、常に現状に満足しない姿勢が必要なようだ。 個人の人間のキャリアにもこの考え方は落とし込めるように思った。とはいえ、でっかいビジョンを考えつくことが中々難しいのよね…
1投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は経営者ではないけれど、基本理念と目的を持ち、細部まで徹底して一貫させるというのは、生き方や家庭にも生かせる法則だと思う。カルト的な信者をもつというところで、全く意図せず人を信者にしてしまう父のことを思い出す。
0投稿日: 2022.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、対象企業への知識が足りなすぎたと感じた。アメリカの名だたる企業が出てくるが名前を知っている程度で何を行なってきたのか、どういう歴史があるかまでは知らない。そこを認識した上で読むと理解が深まると感じた。調査方法がとてもシンプルでかなり大変なことだ。ビジョナリーカンパニー(先見的な歴史ある企業)と同時期に過ごした比較企業の差を歴史を遡り比較し、ビジョナリーカンパニーになりうる共通項をみつけていく。基本理念、企業理念が会社に浸透していることが何より大事である。企業は人の集合体であるが、全員他人だ。それぞれ様々な環境の中で生まれ育っている人間が集まり大きな目標を達成する。会社の色や本質が何であるか。浸透しないと意味がない。
0投稿日: 2021.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業がビジョナリーであるために時代を超えて普遍的な在り方が書かれた本。 25年以上も前に書かれていても古さを感じないのは、この考え方が環境が変わっても未来に続いていく考え方なのだと思う。
0投稿日: 2021.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョナリー・カンパニーの傾向の1つとして「カルトではないがカルト『のようだ』」と書かれた文章を見た際は、思わず笑ってしまった(カルトは悪い意味ではなく、事実として忠誠心などを表す表現)。 本書でも述べられているように、だからといって個人崇拝のカルト会社を作れという訳でなく、基本理念を熱心に維持するしっかりした仕組みを持った組織を作ることが企業には求められていると書かれている。 P&Gで働く友人にこの本に書かれたP&Gの具体例をいくつか話すと非常に話が弾んだ。どうやら現在も基本理念を維持する仕組み作りは徹底しているようだった。
0投稿日: 2021.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、時代を超えてしなやかに生き続ける会社の共通点について考察している。経営理念が、ただのスローガンではなく、経営の判断基準、組織のDNAのレベルにまでなっている会社が、なぜ強いのかについて知ると、「企業の経営者がどこを見て、その企業を経営しているのか」について興味が湧く。
0投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日朝日新聞の書評欄に、この本のことが書かれていた。日本での発売が1995年にまで遡り、現在は57刷りまでに及んでいることより、ビジネスマンに根強い人気があることなのでしょう。 未来志向、先見的、業界で卓越した、同業他社でも広く尊敬を集めインパクトを世界に与え続けてきた企業18社をビジョナリーカンパニーと呼び、同じような機会がありながら、同じように成長出来なかった比較対象企業と、何が違うのか、具体的事例を加えて、成長してきた理由を述べる。 ただ安全には妥協を許さないと言われているボーイング社だが、737MAXの相次ぐ事故と自社の非を認めない当社のニュースは、まだ記憶に新しい。また人に優しいと言われているウォルマートは、アメリカでもあまり良い噂が聞こえていないようだ。そもそもアマゾンのようなネット販売会社の急拡大によって、現在の店舗販売の生き残り策は、どうなんだろうか と思ってしまう。 もっとも私が読んだ本は図書館からの借り物で、2003年25刷版だったので、今は少し対象企業が変わっているのかもしれないが。 しかし、企業にとって一流と言われるにはどうすれば良いか、社員 特に経営に関わっている人はどう考え、どう行動すべきかは、大変参考になるし、比較対象企業との違いを具体的に挙げているのは、分かりやすい。 サラリーマンとして、やる気を起こさせる本だったな。
0投稿日: 2021.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョナリー・カンパニー ■偉大な企業の特徴 「基本理念を維持し、進歩を促す」 ・世の中の変化の一歩先を行き、聖域なく自らも変化していく強い情熱 ・絶え間ない変化にもかかわらず、企業が守り抜いてきた基本理念を持つ ・基本理念が組織を束ねる求心力になる。 ・基本理念があるからこそ、経営者や事業などそれ以外の要素を変えても、企業としての継続性を確保できる。 ■仕組み ①不断の改善 ②沢山試してうまくいった突然変異を残す ③社運を賭けた大胆な目標 取組が全てうまくいくわけではない。 それでも進歩への情熱を絶やさず、逆境から必ず這い上がってくる「ずば抜けた回復力」こそが、「偉大な企業」 ■5つの教訓 3M ①試してみよう。なるべく早く。 ②誤りは必ずある事を認める。 ③小さな1歩を踏み出す ④社員に必要なだけの自由を与えよう ⑤重要なのは仕組みである ■GOODはGREATの敵 ・良い企業という立場に安住している。 ・野心あふれるCEOが必要 □リーダーの最大の特徴の矛盾する二面性 ・個人としての謙虚さ ・職業人としての意志の強さ(不屈の精神) ・ヨーロッパは国王の資質に大きく左右されたが、アメリカは優れた大統領を継続して生み出すプロセス・仕組みを作ることに注力した。 ■事業戦略の規律 ①自社が世界一になれる ②経済的原動力になる ③情熱を持って取り組める →3つのうち1つでも要件を満たさない事業は捨てる規律が必要 「偉大な企業は機会が不足して植えるのではなく、多すぎる事業機会に消化不良になって苦しむ」
0投稿日: 2021.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
企業の軸というか、何を大切にしていますか?ということが大切と説く本。 正直、自分が勤めている会社について、これに答えられない。 これは、トップが変わっても、会社に残るものなので、組織の仕組みの問題なのだと思う。 答えられないなら、まずは経営理念を文書化することから始める方が良いとのこと。で、この経営理念は、進歩について、含まれている方が良い。理念が決まれば、戦略、戦術、組織体系、構造、奨励制度、オフィスレイアウト、職務設計などに反映していくことが必要。 ビジョナリーカンパニーのポイントは、不安感を作り出し、動きを生み出すこと。厳しい自制、猛烈な仕事、耐えざる努力があれば、到達できるらしい。
1投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ詳細に読むとかなり時間がかかりそうだったため流し読みの感想。 企業として組織が進むべき方向を示す理念の重要性を説いている。私は本書で説明されている理念=使命(ミッション)にあたると考える。 MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)のミッションにあたるものは途中で変えたり諦めたりしない。その企業の存続する意義である為。一方でビジョン・バリューはその時々に応じて、ミッションに沿った形で変えていくことが望ましい。 また、ミッションは会社によって異なるが成功している企業に共通するのはそのミッションをどれだけ深く信じていたかという点だ。基本理念を維持するためにはカルト宗教的に信じることもおかしなことではない。 仕事の姿勢についても言及されており、どんなに順調に事業が進んでいても決して満足せず、明日にはどうすれば今日より上手くやれるかと考えることを説いている。武道の黒帯は満足しない人がなる。自分自身に対しての要求が高い人が成功する要素の一つである。 理念の重要性と仕事への向き合い方をといた自己啓発の面がある本であった。
0投稿日: 2021.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「七つの習慣」の企業版みたいな感じ。 多くの調査を元にビジョナリーカンパニーと対象企業を比較し、その違いを説明している。 ソニー以外海外の会社で、ほとんどが名前を知ってる様な大きな会社なので、正直そんなに差があるとは思って無かった。というより、一般的に見たら差は感じないと思う。 従業員の多い会社の経営者なら読む価値はかなりあると思う。
0投稿日: 2021.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かった。 読み終わるのに5年。 しかし、最後の1/3は2週間ほどで読み切った。 うちの会社もこれぐらいの気概を持って人事にあたってくれれば・・・
0投稿日: 2021.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業が世代を超えて発展していくために必要な要件について書かれています。経営者であれば一度は読んだほうが良いと思うし、読んだことがない経営者は危ういとも言えるかもしれない。 紹介されている企業のほとんどが米国企業なので、イメージしづらい読みづらさはあります。
1投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・基本理念を明確にして共有すること ・やれないことはないと思える大胆な目標を立てること ・安定を目的とするのではなく変化し続けること 明日から自分が所属する小さな組織でも、できることを考え始めようと思った。
1投稿日: 2021.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーの神髄は、基本理念と進歩への意欲を組織の隅々にまで浸透させて行くことにある。 本書を読んで、どんな状況に陥ったとしても不変で、物事を判断するときの絶対的な指針となる基本理念を貫き通すこと、また、常に満足することなく進化・変化し続けることを選択することが、時代を超えて生存し続ける際立った企業の原理原則であると学んだ。
1投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログテーマは150年以上続いている企業だが、主語を自分に変えて読むと新しい考え方が見つかった!! 1.偉大な企業は偉大なアイデアから生まれるのではなく、心の底からの基本理念から生まれる (創業当時、事業が決まっていない企業が沢山あった) →心の底からやりたい事を続けていれば、いずれは大成するはず!!! 2.基本理念=基本的価値観+目的 これは理論や外部環境・顧客の要求によって、変えるものではない (時には利益よりも優先させる) 3.基本理念を維持しつつ、どこまでも進歩を促す そのために大胆な目標を掲げる 4.基本理念から生まれるアイデアを大量に試し、剪定していく 5.基本理念を達成するための組織・仕組みを作れば、自分の死後何世代も残していくことができる 6.ビジョナリーカンパニーは成功まで20年かかるケースもある 7.同世代の人たちではなく、自分自身に勝つ 8.ビジョナリーカンパニーは芸術の傑作に似ている (自分自身の身体・思考を尊ぶ)
0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者と会話するにあたり、経営視点を持つきっかけの一つとして読みました。 ■概要 社長の世代が交代しても、圧倒的な業績を残し続けている ビジョナリーカンパニーを類似業種企業と比較し、 ビジョナリーカンパニーに共通する特徴についてまとめられている。 【共通する特徴】 1. ビジョンの共有 時を告げるより、時計を作るという言葉が本書内にあるが、 時を告げられる天才社長に依存しては、一代でしか発展できない。 時計を作る(天才がいなくとも、判断基準を全社員がわかる仕組み)こと 2. 基本信念の浸透 明文化された基本信念が、ビジョナリーカンパニーにはある それが、社員を奮い立たせ、ワクワクするものである。 企業の存在意義と言える。 社員はカルト的にそれを盲信するため、そうなれない人には働きにくい 会社である。 3. 大胆な目標設定 従来通りの延長線上ではなく、全く新しい価値観や 通常では考えられないほどに高い目標を掲げる。 明確な達成基準があることは、社員のモチベーションの向上につながる。 4. 試行錯誤 ビジョナリーカンパニーも全ての挑戦がヒットしたわけではない。 100の挑戦をし、1がヒットするように挑戦を推奨する文化がある。 3Mでは、社員の15%の就業時間を自主開発に当てることを許可しており、 そこから新たなヒット商品が次々と生まれている。 5. 常に成長を目指す。 ビジョナリーカンパニーの目指す目標は地平線のように広がっており、 決して満足することはない。 自己成長し、日々新たな挑戦をしていく。
0投稿日: 2021.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ永続的な企業の特徴を、分析結果から考察した経営書。執筆当時から現在に至るまで継続して繁栄している優良企業はもちろん、現在圧倒的な存在感を誇る企業においても、本著で述べている原則・概念は当てはまっている印象を受けた。ゴーイングコンサーン、未来志向、ビジョンについて考える際に参考となる一冊。
0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニー (卓越した企業) の共通項を実例をもとに論じた本。「基本理念を作る」「大胆な目標」「カルトのような文化」「大量のものを試す」など,パッと見は当たり前だし,一見ドライな感じの米国企業の印象とは異なる気もするけど,普遍的なことは当たり前の中にあるのかもしれない。 日本企業は,多少ひいき目かもしれないが,高度経済成長期は上記のような感じだったのではないか? 一方,最近になって事業を絞り込んだり,企業理念みたいなものが希薄化していて,本書の指摘から遠ざかって行っているような気がしてならない。
0投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ビジョナリー・カンパニーを作るための必須条件] 1,自分なき後も組織が繁栄する仕組みを作る 2,利益を超えた目的を見つける 3,基本理念を見つけ、組織全体に浸透させる 4,社運をかけた大胆な目標を設定する 5,カルト的とも呼べる文化を作る 6,多くのものを試し成功したものを残す 7,生え抜きの経営陣で運営 8,決して満足しないよう、不安を明文化する仕組みを作る [企業・個人にとって重要な一貫性を保つ為の指針] ①戦略・理念・具体的な行動の全体像を描く ②日々の小さなことにこだわる ③一つ一つのアクションの相乗効果を考える ④流行ではなく自分の基本理念に従う ⑤組織内・一つ一つの行動の矛盾をなくす ⑥基本理念は守りつつ、新しい方法をどんどん試す
0投稿日: 2020.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログp.14 競争に勝つことよりも、自らに勝つことを優先する。明日にはどうすれば今日よりも上手くやれるか。 p.37 時を告げるのではなく、時計を作る。 自分のスキルを自分だけのものとせずに、後世の者が使えるようにすることの方が価値がある。 p.55 経営者がカリスマである必要はない。3M、ソニー、ボーイング、HP、メルクのような企業を築いた者たちもみな温和で目立つような立場ではなかったから。 p.72 ORの抑圧をはねのけ、ANDの才能を活かす ▶︎どっちかしかできないじゃなくて、両立させる方法を考える。 p.116 何を理念にするかじゃなくて、実際に大切にしているものはなにか?それはなんでもいいからそれを貫き通すことが大切 p.138 今がどんなに順調であっても、決して満足しない限り常に進歩し続け、変化し続ける。 p.156 目標は明確で説得力があるほうがいい。 良い例(GE ):参入したすべての市場で1番か2番になる 悪い例(ウェスチングハウス):トータルクオリティ、市場のリーダー、グローバル GEの方が、説得力があり進歩を促す。、 p168まで読了
0投稿日: 2020.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者が本来読むような本なのだけど、そんなことは関係なくビジネスマンなら読んだほうがいいかもしれない。別に会社のトップがこの本に書かれていることを意識しているかはわからないけど、もし自分で会社を作ったり、なにかを始めるならこの本の考え方は必要になってくると思った。 以下、印象的なシーン 1. 長く続く組織を作り出すことに注力する。時を告げるのではなく、時計をつくる →qpmiサイクルの本にも書いてたなぁ。時を刻むことは人の心にも刻まれることかも 2.明日にはどうすれば今日よりうまくやれるか →これはどんな人でも実践できるのでは。限られた時間の中で沢山の試行を回したい。もちろんちゃんとやったことは記録しないといけないけど。 3.企業として早い時期に成功することと、ビジョナリーカンパニーとして成功することとは、逆相関している →すぐできたものほどすぐ役に立たなくなるに通じるものがあるなぁ 4.理念をしっかりさせ、カルトのような同質性を求めることにより、企業は従業員に実験、変化、適応を促し、行動を促すことができる。 →根幹は持たせつつもある程度は自由にやらせること。会社として芯は示してあげる必要があるのだろう。 5.試してみよう。なるべく早く。じっとしていてはだめ →まずはなんかやれ的なことだけどコレが案外難しい。闇雲にやればいいってもんでもないし時間は有限だし。でもこの姿勢は大事だと思う。 6.HPが何をやっているかと同じくらい重要な点は、何をやっていないか。 →5と矛盾するような考え方だけど、おそらく大事なポイントは芯(目的、一貫性)があるかないかではないだろうか。それが芯を捉えたことであればたくさん試行すべきだと思う。 7.オズの魔法使いの魔法使いは本当は魔法使いではなくただの手品師だった。ビジョナリーカンパニーを作り上げた人たちも必ずしも偉大な人だったわけではなく、ごく普通の人だった。単純さは安易さを意味するわけではない。 →どんなときでも、どんなことでも自分を芯を大事にして進めってことなのかな。誰だって何かしら苦労したり嫌なことがあるから一喜一憂せずに現実と向き合っていこう、、、
5投稿日: 2020.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョナリーカンパニーとは、オリンピックで言えば金メダル級の企業のこと。多くの人から尊敬を集め、2位(銀メダル)とはダントツの差をつけている企業のこと。 そうした企業は最初からそんな企業ではなかったことに驚きを禁じ得ない。 基本理念を維持し 大胆な目標(BHAG) カルトなような文化 とにかく大量にチャレンジ 生え抜きの経営陣 決して満足しない 始まりの終わり そういうことか!
0投稿日: 2020.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
■感想 最高の本。以上。恐れ入りました。という内容。 僕なりのキーメッセージは「理屈を言わずに、やれ」ということだと思います。 ■要諦 本書の最重要項目 本書が訴えるのは、基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整えることの大切さ。これが時計を作る考え方の真髄。↓がキーコンセプト。 基本理念 基本理念=基本的価値観+目的 基本的価値観:組織にとって不可欠で不変の主義。いくつかの一般的な指導原理からなり、文化や経営手法と混同してはならず、利益の追求や目先の事情のために曲げてはならない。 目的:単なるカネ儲けを超えた社会の根本的な存在理由。地平線の上に永遠に輝き続ける道標となる星であり、ここの目標や事業戦略と混同してはならない。 基本理念は熱心に支持されるので、ビジョナリーカンパニーには、カルトのような文化がある。カルトは言い換えると、支える仕組みのこと。ただし、個人崇拝のカルトであってはならない。 市場環境が変化した場合でも変えることはない。 2種類の進歩 BHAG-Big Hairy Audacious Goals・・・具体的な目標 BHAGは、「明確で説得力のある目標」で、ビジョナリーカンパニーは、進歩を促す強力な仕組みとして、時として大胆な目標を掲げる。 BHAGは人々の意欲を引き出す。人々の心に訴え、心を動かす。具体的で、ワクワクさせられ、焦点が絞られている。誰でもすぐに理解でき、くどくど説明する必要はない。 BHAGが有効なのは、それが達成されていない間だけである。企業がBHAGを達成して、別のBHAGを設定しなかった時、「目的達成症候群」にかかる。フォードが、自動車を大衆の手にという目標を達成した後、新たなBHAG設定しないうちに、フォードを追い抜くというBHAGを持ったGMに追い抜かれた。 BHAGは社長個人の目標ではいけない。(チェースマンハッタンの例) 進化による進歩を積極的に促している・・・抽象的な目標 適者生存:繁殖し、変異し、強いものが生き残って弱いものが死に絶える(ダーウィン/進化論) 進化の過程は、「枝分かれと剪定」に似ている。木が十分に枝分かれし(つまり、変異を起こし、)枯れた枝をうまく剪定すれば(つまり、淘汰の中で選択すれば)、変化を繰り返す環境の中でうまく成長していくのに適した健康な枝が十分に持つ木に進化してくだろう。 環境に見事に適合したビジョナリーカンパニーは、主に賢明な洞察力と戦略的な計画の結果であると考えるよりも、主に以下の基本的な過程の結果だと考える方が、はるかに事実に合っていると思われる。つまり、多数の実験を行い、機会をうまく捉え、うまくいったもの(そして、基本理念に適合するもの)を残し、うまくいかなかったものを手直しするか捨てるという過程である。 →基本理念がとても大事。 経営者がすべきこと 試してみよう、なるべく早く 誤りは必ずあることを認める 小さな一歩を踏み出す 社員に必要なだけの自由を与えよう 重要なのは仕組みである。着実に刻む時計を作るべきだ ・・・3Mの15%ルール(勤務時間の15%を自分の時間に)、25%ルール(25%を過去5年間の新商品で上げるように)など。 基本理念を維持し進歩を促す エクセレントカンパニー(トム・ピーターズ)との違い 本書は、機軸(既知の事業)ではなく、基本理念から外れるな、と言っている点 教訓1:時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ。 「時を告げること」:素晴らしいアイデアを持っていたり、素晴らしいビジョンを持ったカリスマ的指導者。 「時計を作ること」:一人の指導者の時代を遥かに超えて、いくつもの商品ライフサイクルを通じて繁栄し続ける会社を築く。ビジョナリーカンパニーの創業者は時を告げるタイプではなく、時計を作るタイプである。時を刻む時計を作るとは、会社を築くことであり。建築家のようなやる方で、組織を築くことに力を注いでいる。 教訓2:ANDの才能を重視しよう ORの抑圧を跳ね除け、ANDの才能を生かす。 ビジョナリーカンパニーは一見矛盾する考え方であっても、両方を手に入れる方法を身につける。これは、中間点のバランスをとるのではなくて、 両方100%獲得しようとする発想である。 例えば、 利益を超えた目的現実的な利益の追求 揺るぎない基本理念と力強い変化前進 基本理念を核とする保守主義リスクの大きい試みへの大胆な挑戦 明確なビジョンと方向性臨機応変の模索と実験 社運をかけた大胆な目標進化による進歩 基本理念に忠実な経営者の選択変化を起こす経営者の選択 理念の管理自主性の発揮 カルトに近い極めて同質的な文化変化し、前進し、適応する能力 長期的な視野にたった投資短期的な成果の要求 哲学的で、先見的で、未来志向日常業務での基本の徹底 基本に忠実な組織環境に適応する組織 「一流の知性と言えるかどうかは、二つの相反する考え方を同時に受け入れながら、それぞれの機能を発揮させる能力があるかどうかで判断される」(F・スコット・フィッツジェラルド)、これこそ、ビジョナリーカンパニーが持っている能力。 ビジョナリーカンパニーでは、基本理念を厳しく管理すると同時に、業務上、幅広い自主性を認めて、個々人の創意工夫を奨励している。ビジョナリーカンパニーは、カルトのような文化を持ちながら、比較対象企業に比べてはるかに権限分散が進み、業務上の自主性を幅広く認めている。 教訓3:基本理念を維持し、進歩を促す BHAGだけでビジョナリーカンパニーができるわけではなく、BHAGを追求するにあたっては、基本理念を注意深く維持するべきである。 例:ボーイング/信じがたいほどリスクが高いB747を開発するというBHAGの背景で、製品の安全性を最優先にするという基本理念を維持した。ディズニー/『白雪姫』『ディズニーランド』でいくら財政難に陥っても、細部にこだわるという基本理念は捨てなかった。 教訓4:一貫性を追求しよう ビジョナリーカンパニーは経営理念を文書にしただけではダメ。 ビジョナリーカンパニーの真髄は、基本理念と進歩への意欲を組織の隅々まで浸透させていることにある。目標、戦略、方針、過程、企業文化、経営陣の行動、オフィス・レイアウト、給与体系、会計システム、職務計画など、企業の動きの全てに浸透させていることにある。ビジョナリーカンパニーは一貫した職場環境を作り上げ、相互に矛盾がなく、相互に補強し合う大量のシグナルを送って、会社の理念と理想を誤解することはまずできないようにしている。 ビジョン=基本理念+進歩のこと。ビジョンは、長期にわたって維持される基本理念と将来の理想に向けた進歩の組み合わせ。 生え抜きの経営陣 経営者の継続性をもたらす好循環 経営幹部育成(後継計画)→社内の有力な後継候補→社内の人材による優秀な経営陣の継続性→「基本理念の維持・進歩の刺激」→経営幹部育成・・・ 上記のような循環を経ないと、経営者の断絶が起こり、経営の空白、救世主探しが必要になる。結果として、「基本理念の維持・進歩の刺激」が失敗してしまう。 ビジョナリーカンパニーの延べ1,700年の歴史の中で、社外の人材が最高経営責任者になった例は4回しかなかった。 決して満足しない ビジョナリーカンパニーにとって最も大切な問いは、「明日どうすれば、今日よりもうまくやれるか?」である。このように問いかける仕組みを作って、毎日習慣にして考え、行動している。 そのために、昔ながらの厳しい自制、猛烈な仕事、正体のための努力が必要で、近道はないということ。 不安をもたらす仕組みを作り、自己満足に陥らないようにし、内部から変化と改善をもたらしつつ、基本理念を維持していくことができるか。 将来の投資をしつつ、今の収益を上げる 不景気にはどのように対処し、投資をし続けるか 安心感が目的ではなく、ビジョナリーカンパニーは働きやすい職場ではない、ということを社員は理解しているか。楽な生活を最終目標にすることを拒否し、いつも明日には今日より前進するという終わりのない修練の過程を重視しているか。 ビジョナリーカンパニーになるためには、①基本理念がなくてはならない。また、②進歩への意欲を常に維持しなければならない。そして、基本理念を維持し、進歩を促すように、③全ての様相に一貫性が取れた組織でなければならない。 ビジョナリーカンパニー何から始めれば良いか? 基本理念を作ること。そして、基本理念は「探し出す」作業である。 基本的な価値観を箇条書きにすること。 項目が5・6つを超えていれば、煮詰まっていない可能性あり。 会社の目的、存在理由を文書にすべき。 今後100年間変わらないものである必要がある。
0投稿日: 2020.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーな(未来のある)企業はどういうものかを実際に業態の似た会社を比較し、ビジョナリーな会社とそうじゃない会社を歴史を追ってわかりやすく説明している。一例を挙げると3Mとノートン、アメリカンエクスプレスとウェルズファーゴ、ボーイングとダグラス、フォードとGM、GEとウエスチングハウス他。組織の上に立つことを目指す方、ビジネスマンマンに限らず非営利組織にお勤めの方も一度は目を通しておきたいビジネス書。ビジョナリーカンパニーに優秀な独裁的経営者は不要であり、基本的理念と組織づくりが最も重要と実感した。
1投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体例が多くボリュームのある本だったが、読んで良かったと思える本だった。 「すばらしい会社=最初からすばらしいアイデアをもっている」という印象があったが、この本を読んで必ずしもそうである必要はないんだなと思った。 細かい計画ではなく、大量のものをまずは試して、上手くいったら残すという姿勢を心がけていきたい。 ■メモ ・時を告げる預言者ではなく、時計を作る設計者になる →カリスマ性や優れたアイデアではなく、組織づくり(仕組み化)の方が大切 ・理念に不可欠な要素はない →お客様や従業員を柱にするなど企業によって異なり、大事なのは「理念の内容<理念を突き通しているか」 ・基本理念は変わらず、文化・戦略・計画・方針は変わる(混同しない) →時間の経過とともに戦略は変えていくが理念だけは変えてはいけない
0投稿日: 2020.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーとはなんだろうか。ビジョンを持っている企業、未来志向の企業、先見的な企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業である。 ・業界で卓越した企業である。 ・見識のある経営者や企業幹部の間で、広く尊敬されている。 ・わたしたちが暮らす社会に、消えることのない足跡を残している。 ・最高経営責任者( CEO)が世代交代している。 ・当初の主力商品(またはサービス)のライフ ・サイクルを超えて繁栄している。 ・一九五〇年以前に設立されている(*)。 ビジョナリー・カンパニーには、ずば抜けた回復力がある。 つまり、逆境から立ち直る力がある。 決定的な点は、理念の内容ではなく、理念をいかに深く「信じて」いるか、そして、会社の一挙一動に、いかに一貫して理念が実践され、息づき、現れているか ビジョナリー・カンパニーは、基本理念を信仰に近いほどの情熱を持って維持しており、基本理念は変えることがあるとしても、まれである。 ビジョナリー・カンパニーの基本的価値観は揺るぎなく、時代の流れや流行に左右されることはない。基本的価値観が百年をはるかに超えて変わっていないケースすらある。 ビジョナリー・カンパニーは、その基本理念と高い要求にぴったりと「合う」者にとってだけ、すばらしい職場である。ビジョナリー・カンパニーで働くと、うまく適応して活躍するか(それ以上にないほど、幸せになるだろう) あとから見れば、じつに先見の明がある計画によるものに違いないと思えても、「大量のものを試し、うまくいったものを残す」方針の結果であることが多い。 ビジョナリー・カンパニーの延べ千七百年の歴史のなかで、社外から CEOを迎えた例はわずか四回、それも二社だけだった。 ビジョナリー・カンパニーは、自らに勝つことを第一に考えている。 「ORの抑圧」とは、手に入れられるのは Aか Bのどちらかで、両方を手に入れることはできないという、いってみれば理性的な考え方である。 ビジョナリー・カンパニーは、安定か前進か、集団としての文化か個人の自主性か、生え抜きの経営陣か根本的な変化か、保守的なやり方か社運を賭けた大胆な目標か、利益の追求か価値観と目的の尊重か、といった二者択一を拒否する。そして、「 ANDの才能」を大切にする。これは逆説的な考え方で、 Aと Bの両方を同時に追求できるとする考え方である。 会社の成功とは、あるアイデアの成功だと考える起業家や経営幹部が多いが、こう考えていると、そのアイデアが失敗した場合、会社まであきらめる可能性が高くなる。そのアイデアが運よく成功した場合、そのアイデアにほれこんでしまい、会社が別の方向に進むべき時期がきても、そのアイデアに固執しすぎる可能性が高くなる。しかし、究極の作品は会社であり、あるアイデアを実現することでも、市場の機会をとらえることでもないと見ているのなら、善し悪しは別にして、ひとつのアイデアにこだわることなく、長く続くすばらしい組織をつくりあげることを目指して、ねばり抜くことができる。 時を告げるために使う時間を減らし、時計をつくるために使う時間を増やすべきである。 ウェルチは生え抜きであり、 G Eの製品である。そのウェルチが G Eを変えた。 ビジョナリー・カンパニーの草創期の重要な経営者は、指導者としてのスタイルに関係なく、比較対象企業の経営者より組織志向が強かった。事実、調査が進むにつれて、「指導者」という言葉がしだいにしっくりしなくなり、「建築家」や「時計をつくる人」という言葉を使うようになった(二つ目の重要な違いは、つくる時計の種類だが、これについてはのちに触れる)。以下に示す対照的な組み合わせを見れば、建築家のような方法、つまり、時計をつくる方法という言葉の意味がさらにはっきりするだろう。 「ORの抑圧」とは、逆説的な考えは簡単に受け入れず、一見矛盾する力や考え方は同時に追求できないとする理性的な見方である。 「 ORの抑圧」に屈していると、ものごとは Aか Bのどちらかでなければならず、 Aと Bの両方というわけにはいかないと考える。 「ORの抑圧」に屈することなく、「 ANDの才能」によって、自由にものごとを考える。「 ANDの才能」とは、さまざまな側面の両極にあるものを同時に追求する能力である。 Aか Bのどちらかを選ぶのではなく、 Aと Bの両方を手に入れる方法を見つけ出すのだ。 「バランス」とは、中間点をとり、五十対五十にし、半々にすることだ。 ビジョナリー・カンパニーは、たとえば、短期と長期のバランスをとろうとはしない。 短期的に大きな成果をあげ、かつ、長期的にも大きな成果をあげようとする。 ビジョナリー・カンパニーは、理想主義と収益性のバランスをとろうとしているわけではない。 高い理想を掲げ、かつ、高い収益性を追求する。 ビジョナリー・カンパニーは、揺るぎない基本理念を守る方針と、力強い変化と前進を促す方針のバランスをとろうとしているわけではない。 その両方を徹底させる。 カネ儲けというのは、会社が存在していることの結果としては重要であるが、われわれはもっと深く考えて、われわれが存在している真の理由を見つけ出さなければならない」。 ビジョナリー・カンパニーは、これと同様に問いかけて、目的をつかんでいる。 目的は、まったく独自のものである必要はない。ふたつの企業が、似通った目的を持っていても不思議ではない。これは基本的価値観として、二つの会社が誠実さを揺るぎない信念として掲げていても不思議ではないのと同じだ。目的の最大の役割は、指針となり、活力を与えることであって、ほかの企業との違いを明らかにすることである必要はない。 マリオットは、 A& Wルートビアー・スタンドから、食品チェーンへ、機内食サービスへ、ホテルへと発展し、二十一世紀も未知の世界に向かっていくだろうが、「自宅から離れている人たちが、友人に囲まれ、心から歓迎されていると感じられるようにする」基本的な任務を捨て去ることは、絶対にない。 ソニーは、炊飯器や粗雑な電気座布団から、テープレコーダー、トランジスター・ラジオ、トリニトロン・カラーテレビ、家庭用ビデオ、ウォークマン、ロボット・システムへと発展し、二十一世紀も未知の世界に向かっていくだろうが、「〔日本の〕文化向上のために」技術革新を応用する真の喜びを感じる基本的な目的の追求が終わることは、絶対にない。 ビジョナリー・カンパニーには、胸がおどるような新しい事業分野へと発展しながら、基本的な目的を指針として守る能力があり、その能力を発揮しているのだ。 サム・ウォルトンはこう指摘している。「一度成功したからといって、それを続けていてはいけない。周囲の状況は常に変化しているからだ。成功するためには、その変化の一歩先をいく必要がある」。 時間の経過とともに、文化の規範は変わる。戦略は変わる。製品ラインは変わる。目標は変わる。能力は変わる。業務方針は変わる。組織構造は変わる。報酬体系は変わる。あらゆるものが変わらなければならない。その中でただひとつ、変えてはならないものがある。それが基本理念である。少なくともビジョナリー・カンパニーになりたいのであれば、基本理念だけは変えてはならない。 概念とは、「基本理念を維持しながら、進歩を促す」であり、これこそが、ビジョナリー・カンパニーの真髄である。 進歩を求める内部の力があるからだ。ビジョナリー・カンパニーは、進歩し、向上し、新たな可能性を切り開こうとするとき、外部の理由を必要としない。 ビジョナリー・カンパニーは基本理念を持ち、進歩への意欲を持っている。しかし、ただそれだけではなく、基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みも整えている。 ボーイングはその典型とも言えるが、ビジョナリー・カンパニーは進歩を促す強力な仕組みとして、ときとして大胆な目標を掲げる。このような目標を、わたしたちは社運を賭けた大胆な目標( Big Hairy Audacious Goals)の頭文字をとって、 BHAGと呼ぶことにした。これは、進歩を促す唯一の方法ではないし、ビジョナリー・カンパニーのすべてがよく使っているわけでもない 第一に、これは軽視すべきでない点だが、女性向けに販売していたがほとんど知られていなかったマルボロが、位置付けを一般向けの商品に変え、カウボーイをあしらったデザインで大成功を収めるようになる。そして第二に、フィリップ・モリスには目標になる相手がいた。 しかし、皮肉なもので、自動車を大衆の手に届けるという大胆な目標を達成したとき、フォードは新たな BHAGを設定せず、自己満足に陥って、 GMがフォードを追い抜くというやはり大胆な目標を掲げてそれを達成するのを、なすすべなく見守るようになった。この点から、 BHAGが組織にとって有益なのは、それが達成されていない間だけであることを強調しておくべきだろう。 BHAGと呼べるのは、その目標を達成する決意がきわめて固い場合だけである。 基本理念の章でも見てきたように、企業がきわめて未来志向の動きをとるのは、収益性を最大限に高めること以外の点に事業の究極的な目標があると見ているときなのである。 最大の違いは、……任務を定め、適切なターゲットを設定していることにある。技術者に完全な自由を与えている企業が多いが、当社ではそうしていない。目的を決め、具体的ではっきりしたターゲットを決め、それを達成するために必要なチームをつくる。井深会長は、ターゲットを決めて研究をはじめたら、絶対にあきらめるなと教えている。この教えが、ソニーの研究開発陣全体に浸透している。 ・ BHAGはきわめて明確で説得力があり、説明する必要もないほどでなければならない。 BHAGは目標であり(たとえば、登るべき山や、宇宙旅行の目的地としての月のようなもので)、「声明」ではないことを忘れてはならない。それで組織内に活力がみなぎらないのであれば、それは B H A Gではない。 ・ BHAGは気楽に達成できるようなものであってはならない。 IBM 360や、ボーイング 747のように、組織内の人々が、なんとか達成できるだろうが、それには英雄的な努力とある程度の幸運が必要だと思えるものでなければならない。 ・ BHAGはきわめて大胆で、それ自体が興奮を呼び起こすものでなければならず、シティ・バンクやウォルマートの例にみられるように、達成する前に組織の指導者が去ったとしても、進歩を促し続けるものでなければならない。 ・ BHAGには、それを達成したのち、「目標達成症候群」にかかって組織の動きが止まり、停滞する危険がつきまとっている。フォードが一九二〇年代に陥ったこの問題を避けるには、次の BHAGを準備しておくべきだ。また、 BHAG以外にも、進歩を促す方法を持っておくべきである。 ・最後に、もっとも重要な点として、 BHAGは会社の基本理念に沿ったものでなければならない。 経営者としてとりわけ重要と考える責任のひとつは、有能な経営陣が継続するようにすることである。われわれは常に、いつでも後を継げる有能な候補者を用意し、とくに優秀な候補者のために移行研修制度を設け、〔後継計画について〕きわめてオープンにすることで、成功を収めてきた。……経営陣の継続性はきわめて重要だとわれわれは考えている。 ジョーンズは第一の段階として、「 CEO引き継ぎの道筋」という文書をつくった。一九七四年、つまり、ウェルチが CEOになる七年前のことである。同社の経営人材委員会の全面的な支援を受けて、ジョーンズは二年間をかけて、当初、生え抜きばかり九十六人にのぼった候補者を十二人に絞り込み、次に、ウェルチらの六人まで絞り込んだ。この六人をテストし、見きわめるために、全員を「事業部門責任者」にし、経営委員会の直属にした。それから三年間、ジョーンズは徐々に的を絞っていき、候補者に厳しい課題を与え、面接し、エッセー・コンテストを行い、評価していった。この過程のひとつに、「飛行機事故問題」があり、ジョーンズが候補者のひとりひとりに同じ質問をした。「きみとわたしが社用機に乗っていて、墜落したとしよう。ふたりとも死亡したら、だれをゼネラル・エレクトリックの会長にすればいいのか」(ジョーンズはこの方法を、前任者のフレッド・ボーチから学んでいる)。このように息切れしそうな耐久レースで厳しい道のりを走り抜き、後継者の座を獲得したのがウェルチであった。最後まで残った候補者も、 GTE、ラバーメード、アポロ・コンピューター、 RCAなどの社長や CEOになっている。ついでながら、アメリカ企業の経営者のなかには、どの企業の出身者よりも G E出身者が多い。 ビジョナリー・カンパニーは比較対象企業よりはるかに、社内の人材を育成し、昇進させ、経営者としての資質を持った人材を注意深く選択している。後継者の育成を、基本理念を維持する努力の柱にしている。 デプリーは会社の性格を守り、それを次の世代に伝えていくうえで、決定的な役割を果たした。デプリーは、プロクター&ギャンブルが株式会社になった一八九〇年からでは、わずか三代目の CEOであり、前任者の二人を知っていて、二人から学んできた。そして、自分のあとに CEOになった四人を知っていて、四人を教える役割を担った。わたしもその一人であり、株式会社になってからほぼ百年で、わずか七人目の CEOになった。 モトローラはこの「執行室」制度を経営トップだけでなく、中間管理職のレベルにまで広げ、通常、二人か三人のチームで管理にあたる体制をとって、会社全体で経営幹部を育成し、経営の継続性を保証する仕組みの中心にしている。 ディズニーの事例から、重要な教訓を学べる。経営者を外部から招かなければならなくなった場合には、基本理念にぴったり合った候補者を探すべきなのだ。そういう人物なら、経営のスタイルは違っていても、基本的な価値観を心から信じているだろう。 ビジョナリー・カンパニーでは、もっとも大切なことは、「どこまでうまくいっているのか」でも、「どうすればもっとうまくやれるのか」でも、「競争に対応するために、どこまでやらなければならないのか」でもない。もっとも大切な問いは、「明日にはどうすれば、今日よりうまくやれるのか」である。ビジョナリー・カンパニーでは、このように問いかける仕組みをつくっており、毎日の習慣にして考え、行動している。これら企業がすばらしい行動をとり、実績をあげているのは、最終目標を達成しているからというより、常に改善を進め、将来のために投資する終わりのない過程の結果、自然に成果が生まれてくるからなのである。 ビジョナリー・カンパニーが飛び抜けた地位を獲得しているのは、将来を見通す力が優れているからでも、成功のための特別な「秘密」があるからでもなく、主に、自分自身に対する要求がきわめて高いという単純な事実のためなのである。 世の中でいちばん大切なものは、自己を律することである。自己を律することがなければ、人格は形成されない。人格が形成されなければ、進歩はない。……逆境は成長への機会になる。そして、なんのために働くのかで、成果は変わってくる。問題があり、それを克服できれば、人格が養われ、成功をもたらす質を獲得できる。 ここまで読んで、ビジョナリー・カンパニーというのは、安心のできる職場ではないという印象を持ったのではないだろうか。まさにその通り、安心できる職場ではないのだ。 安心感は、ビジョナリー・カンパニーにとっての目標ではない。それどころか、ビジョナリー・カンパニーは不安感をつくり出し(言い換えれば、自己満足に陥らないようにし)、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す強力な仕組みを設けている。 比較対象企業ではどうだろうか。今回の調査では、ビジョナリー・カンパニーと同じ程度に不安感を生み出す仕組みをつくっていることを示す証拠は見つからなかった。設立以来、一貫して、厳しく自己を律している企業はなかった。逆に、比較対象企業のうちいくつかは、意識的に楽な道を選び、ときとして、長期的な将来を犠牲にして、短期的な利益を追求している。 ビジョナリー・カンパニーで「長期」というのは、五年や十年を意味しているわけではない。何十年かを意味しており、五十年を意味していることが多い。しかし同時に、長期的な視野を口実に、短期的な利益の追求の手を緩めたりはしない。 ビジョナリー・カンパニーは比較対象企業に比べて、売上高に対する設備投資の比率が一貫して高いことがわかった(十五組(*)のうち十三組でこう言える)。 また、配当性向が低く、毎年の利益のうち、会社に留保する部分の比率が高い(十五組(*)のうち十二組でそうであり、一組は差がなかった)。 J・ウィラード・マリオット・ジュニアは、かなり質素な暮らしぶりであり、本人の言葉を借りれば「モルモン教の勤労観」に導かれて、週に七十時間働き、自社の施設を年に二百カ所訪問し、ほかの経営幹部にも同じように各地を飛び回るよう求めていた。 もっと重要な点は、常に進歩を求める経営者の意向が活かされるように、会社組織のなかに具体的な仕組みをつくっていったことだ。この時期のマリオットにみられる進歩を促す仕組みのうち、ハワード・ジョンソンにはなかったものをあげていこう。 ビジョナリー・カンパニーの真髄は、基本理念と進歩への意欲を、組織のすみずみにまで浸透させていることにある。目標、戦略、方針、過程、企業文化、経営陣の行動、オフィス・レイアウト、給与体系、会計システム、職務計画など、企業の動きのすべてに浸透させていることにある。 「一貫性」というのは、基本理念と目標とする進歩のために、会社の動きのすべての部分が協力し合っていることを意味する(基本理念と進歩をビジョンと言い換えてもいい。 ビジョンとは、長期にわたって維持される基本理念と、将来の理想に向けた進歩の二つの組み合わせだとわたしたちは考えている)。一貫性がとくに保たれている以下の三社の例を考えてみよう。 全体像を描く フォード、メルク、 HPが細かな手段を積み重ねてきたことを読んで、圧倒される思いがしたのではないだろうか。まさにそうで、この点こそが重要な指針になる。 ビジョナリー・カンパニーは基本理念を維持し、進歩を促すために、ひとつの制度、ひとつの戦略、ひとつの戦術、ひとつの仕組み、ひとつの文化規範、ひとつの象徴的な動き、 CEOの一回の発言に頼ったりはしない。 重要なのは、これらすべてを繰り返すことである。 重要なのは、驚くほど広範囲に、驚くほどの一貫性を、長期にわたって保っていくことである。ビジョナリー・カンパニーになるには、圧倒的とも言えそうな数のシグナルと行動によって、常に基本理念を強化し、進歩を促していくことが必要である。 二 小さなことにこだわる 従業員は日々の仕事で、「大きな全体像」に取り組んでいるわけではない。会社とその事業のなかの、ごくごく小さな細部に取り組んでいるのだ。 大きな全体像が役に立たないと言うのではない。そうではなく、従業員に強い印象を与え、力強いシグナルを送るのは、ごく小さなことであり、この点を確認しておくべきなのだ。 ビジョナリー・カンパニーはいくつもの仕組みや過程をばらばらにつくっているわけではない。それぞれが互いを強化し合い、全体として強力な連続パンチになるように、仕組みや過程を集中している。いくつもの要素が相乗効果を持ち、連携し合うようにしている。 四 流行に逆らっても、自分自身の流れに従う メルクと HPが経営の常識に逆らって、自らの立場を守り抜いたことを考えてみるべきだ。 一貫性というのは何よりもまず、自分自身の方向感覚に従うことを意味し、外部の世界の標準や慣行、慣習、力、トレンド、気まぐれ、流行、はやり言葉に押し流されないことを意味する。 正しい問いの立て方は、「これはよい方法なのか」ではなく、「この方法は当社に合っているのか、当社の基本理念と理想に合っているのか」である。 五 矛盾をなくす たったいま、自分の会社を見わたしてみると、基本理念との一貫性がとれていなかったり、進歩を妨げているものが少なくとも十以上は見つかるはずだ。 こうした「不適切な」ものが、どこからともなく入り込んでいるのである。 報奨制度は基本的価値観と矛盾する行動に報いるものになっていないだろうか。組織構造は進歩を妨げるものになっていないだろうか。目標と戦略は基本的な目的と矛盾したものになっていないだろうか。会社の方針は変化と改善を禁ずるものになっていないだろうか。オフィスやビルのレイアウトは、進歩を妨げるものになっていないだろうか。 ビジョナリー・カンパニーになるためには、 基本理念がなくてはならない。 また、進歩への意欲を常に維持しなければならない。 そして、もうひとつ、基本理念を維持し、進歩を促すように、すべての要素に一貫性がとれた組織でなければならない。 以上の三点は、どのビジョナリー・カンパニーにも言える一般的な原則である。 一 時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 二 「 ANDの才能」を重視しよう。 三 基本理念を維持し、進歩を促す。 四 一貫性を追求しよう。 最後に、たぶんもっとも重要な点として、 社会のなかで重要な役割を担う伝統ある機関としての会社に、 常に心からの敬意を払って自分の仕事に取り組むことになるだろう。 会社は、政府組織や伝統ある大学と変わらぬほど、 大切にし、関心を向けるべきものなのだ。 この世界で、とくに優れた仕事のうちかなりの部分は、組織に力によって、 共通の理念のために多数の人たちが協力する集団の力によって、 成し遂げられているのだから。
0投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ○ビジョナリーカンパニーとは * 業界で卓越した企業である * 見識のある経営者や企業幹部の間で広く尊敬されている * 私たちが暮らした街に消えることのない足跡を残している * CEOが世代交代している * 当社の主力商品のライフサイクルを超えて繁栄している * 1950年以前に設立されている ○ビジョナリーカンパニーはこれまで困難を乗り越えてきた。 ・ビジョナリーカンパニーの優れているところは回復力が抜群であること 12の崩れた神話 1.すばらしい会社を始めるには素晴らしいアイデアが必要である ビジョナリーカンパニーはスタートでは遅れをとるが長距離レースには勝つことが多い。 ・時を告げるのではなく、時計を作る 仕組み、組織、思想をつくることが重要 ・最高の製品があるから最高の組織になるのではなく、最高の組織があるから最高の製品が生まれる。組織に作りに時間を費やすべし。 2.ビジョナリーカンパニーにはビジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である 偉大な指導者になることよりも長く続く組織を作り出すことに力を注いだ。 3.特に成功している企業は利益の追求を最大の目的としている、 利益の追求だけでなく基本理念も同じように大切にされている。その結果、ビジョナリーカンパニーの方が利益を上げている。 4.ビジョナリーカンパニーの共通した正しい基本的価値観がある。 理念に正解は無い。理念をいかに深く信じているかそして会社の一挙一動にいかに一貫して理念ざ実践され息づき、現れているかが重要。 基本的理念は5-6個以下が良い。 これはあくまで基本的であるからだ。 5.変わらない点は変わり続けることだけである。 基本理念が変わる事は多くはないが事業内容が変わる事は多くある。 6.優良企業は危険を犯さない 胸躍るような大冒険だからこそ人を引きつけられる気になる前進への勢いが生まれる。 7.ビジョナリーカンパニーは誰にとっても素晴らしい職場である。 基本理念と高い要求にぴったりと会う者にとってだけ素晴らしい職場である。ある意味カルト的。 8.大きく成功している企業は緻密で複雑な戦略を立てて最善の動きを取る。 うまくいった間の中にも偶然によって生まれたものが多くある。大量のものを試しうまくいったものを残すと言う方針。ダーウィンの進化論にもあるように強いものが残るのではなく変化し続けるものが残る。 9.根本的な変化を促すためには社会からCEOを迎えるべきだ。 根本的な変化と斬新なアイデアは社内から生まれないと言う一般常識は何度も繰り返し崩されている。 10.最も成功している企業は競争に勝つことを第一に考えている。 ビジョナリーカンパニーは自らに勝つことを第一に考えている。昨日より成長しているか。 11. 2つの相反する事は同時に獲得することができない。 ORではなくAND。 12.ビジョナリーカンパニーになるのは主に経営者が先見的な発言をしているからだ。 基本的理念を生かすために何千もの手段を使う終わりのない過程をとっており、これはほんの第一歩に過ぎない。
0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の会社に入る前に読んだ。なるほどと思うことや知らないことが多くあり、起業される方やサラリーマンの方にもおすすめ。
0投稿日: 2020.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーを分析し、時代を超えて際立つ企業の本質を明らかにしている。 カリスマ的指導者がそういった企業を作り上げ、継続していくものだという固定観念があったが、本書を通じてその考え方は誤っていると深く感じた。 カリスマ的指導者が存命中はよいが、その後に迷走した企業は数知れない。(ディズニーはその例外であるが) 重要であることは ①時計をつくること 企業そのものを究極の作品にする、ひとりひとりが創造力を発揮できる環境をつくる。 ②ANDの才能を活かす 逆説的な考えを抑圧するのではなく、両方(変化と安定など)を追求する。 ③基本理念を維持し、進歩を促す 企業の存在意義(利益志向ではない)を掲げ、常に向上しようとする内部の力をもつ。 ④一貫性の追求 この方法がよいのか?ではなく、当社に合っているのか?という点で分析し、基本理念との矛盾を生じない。 企業分析の本であるが故に、起業家や経営層が読むべきものであるように思っていたが、個人の考え方として学ぶべきことが多かった。 主語「企業」を「自分」と置き換えて読むことで、自分にも応用できるのではないかと感じた。 上の4つを含めて、個人の考え方・生き方を捉える上で非常に参考になった。
4投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【1.読む目的】 •the VISIONを読んで以降気になっていた大ベストセラーを読みたい •時代を超える企業の共通点とは何か?GAFAの台頭、情報、データ革新を経てなお生きる共通解があるのか? 【2.気付きや気になった点、面白かった点等】 【3.感想】
0投稿日: 2020.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログいい会社を作るには、斬新なアイデア、素晴らしいリーダーなどが必要だと思っていたけど、ビジョナリーカンパニーを見るとそうではなかった。SONYやHPなど今となっては、化け物みたいな企業ですら、どんな事業をやるのか悩み、当初はお金を稼げそうな事を全て試していたことに驚いた。 本書では、基本理念について繰り返し書かれており、この理念から一貫した、商品、カルトのような文化が作られていた。 「テクニックやカラクリで目先の利益を上げる」という考えとは真逆で、誰にでも当たり前にできることを決め、それをただひたすら猛烈な熱意で仕事をしていくという、1番シンプルであり、1番やることが難しいことをやり続けた企業。 社内の仕組みに、会社が更に発展していくような仕組みや、満足させない仕組みを作り込んでおり、この原理原則は、今後どのような時代になっても変わらず残り続ける定石。
0投稿日: 2020.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ主にアメリカの、永続する企業の共通点を論じた本である。 永続する企業とは、カリスマ経営者のみに頼らず、組織として再現性をもって繁栄し続ける、といった解釈をした。 重要なポイントは、以下の4点。 1.時を告げず、時計をつくる(仕組みをつくる) 2.ORの抑圧ではなくANDの才能を重視する 3.基本理念を維持し、進歩を促す 4.組織が一貫性を持っている これ以外にも、組織に厳しさがあり生ぬるさが排除されていたり、カルト的な思想に染まっていたり、高い目標 「BHAG」 Big 大きくて Hairy ぞっとするほど困難で Audacious 大胆な Goals 目標 を掲げていることなどがあげられる。 即座にこのような組織を作るのは難しいが、組織を作る際の目標としては目指すべき本であると思う。 マネジメント経験を積んで読み返すと、その場に応じて学びがありそうな本。また読みたい。
0投稿日: 2020.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログウォルト・ディズニーの最高傑作はディズニー社。 大学、動物園作った。 時を告げるよりも、時計を作る。 基本理念 進歩 BHAG ANDの才能
0投稿日: 2020.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
BUILT to LAST (永続する偉大な企業) 第二章 時計をつくる ・ビジョナリーカンパニーはスタートでは遅れるが、長距離レースでは勝つことが多い ・時を告げる(偉大な指導者)よりも時計をつくる (アメリカの建国者は、彼らがこの世を去った後も、優れた大 統領をずっと生み出すためにどんなプロセスをつくることが できるか考えた) ・ORの抑圧をはねのけ、ANDの才能を活かす (長期的な投資と短期的な成果など) 第三章 利益を超えて ・ビジョナリーカンパニーは利益自体が目的ではない。理念と利益を同時に追求する。 (理念の内容よりも、理念が本物であり、企業がどこまで理念 を貫き通しているかの方が重要) (正しいかどうかは関係ない。フィリップモリスは喫煙の権 利、選択の自由を堂々と掲げている) (基本理念を公言することでその考え方に従って行動する傾向 が強くなる) ・基本理念を徹底して強化し、カルトに近いほど強力な文化を生み出す。 (目標、戦略、戦術、組織設計などで、基本理念との一貫性を 持たせている) ・基本理念=基本的価値観+目的 基本的価値観: 組織にとって不可欠で不変の主義 (外部環境が変わっても、たとえ利益に結びつかなく なろうとも百年に渡って守り続けていくものはどれか) (組織の内部にある要素であり、外部環境に左右されるも のではない) 目的 : 単なるカネ儲けを超えた会社の根本的な存在理由 (目的は不変であり、終わりはない。想像力がこの世から なくならない限り。ディズニーランドが完成することは ない) 第四章 基本理念を維持し進歩を促す ・基本理念を大事に維持し、守るが、基本理念を表す具体的な行動はいつでも変更し、発展させなければならない。 (ノードストロームは顧客へのサービスを何より大切にする が、営業地域や在庫量の方針は変わることもある) ・基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整えることが、時計をつくる考え方の真髄である ・基本理念は維持することを忘れず、以下5つの教訓が重要 第五章 社運を賭けた大胆な目標(BHAG)(進歩を促す) ・リスクが高い目標やプロジェクトに大胆に挑戦する (明確で説得力があり、集団の力を結集するものになる。ゴー ルがはっきりする。例:GE:参入した全ての市場でNo.1かNo.2 になる。ウェスチングハウス:市場のリーダー) (BHAGが組織にとって有益なのはそれが達成されていない間 だけ) 第六章 カルトのような文化(基本理念を維持する) ・すばらしい職場だと言えるのは、基本理念を信奉している者だけ。 (ディズニー) 第七章 大量のものを試して、うまくいったものを残す(進歩を促す) ・計画も方向性もないままに、さまざまな行動を起こし、なんでも実験することによって予想もしない新しい進歩が生まれ、種の進化に似た発展をたどる活力を与える (計画のない進歩であり、生物の種が進化して自然環境に適合 していくのに似ている) (BHAGは曖昧なところがなく明確な目標を掲げるが、進化に よる進歩は目標は曖昧。BHAGは思い切った飛躍をするが、 進化による進歩は、はじめはそれまでの事業の延長線上にあ る小さな一歩(言うならば突然変異)) (3Mのポストイットなど。思いつきの実験を奨励する文化) 第八章 生え抜きの経営陣(基本理念を維持する) ・社内の人材を登用し、基本理念に忠実な者だけが経営幹部の座を手に入れる (外部から招かねばならない場合は基本理念にぴったりの候補 者を探す) (変革をもたらし、新しい考え方を取り入れるために経営者を 社外から招く必要は全くない) 第九章 決して満足しない(進歩を促す) ・徹底した改善に絶え間なく取り組み、未来に向かって、永遠に前進し続ける (長期的に利益を増やせるという期待から短期的な利益を減ら す行動が成功を収めることはめったにない)長期:50年 ・不安をもたらす仕組みを作って、自己満足に陥らないようにし、内部から変化と改善を生み出すとともに、基本理念を維持していく ・安心感が目的ではない。ビジョナリーカンパニーが働きやすい職場ではないことを従業員は理解し、楽な生活を最終目標にするのを拒否し、明日には今日より前進するという、終わりのない修練を重視する 第十章 はじまりのおわり ・一貫性を追求する
1投稿日: 2020.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界で最も重要なビジネス書 (世界標準の知識 ザ・ビジネス)(ISBN・EAN: 9784478200865)で紹介されていたので読んでみた。 ”ビジョナリー”や”ビジョナリーカンパニー”、”どの企業がビジョナリーカンパニーであるか?”といった定義をきちんと序盤で説明してくれていて、入りやすい。 想像と違ったのは、”どうすればビジョナリーカンパニーになれるか?”ではなく、”ビジョナリーカンパニーと言われている企業は何をしてきたか?”に重きを置かれていたこと。 ”研究結果の報告”をただ読む、という感じだった。 個人の好みの問題かもしれないけれど、この手の本にしては読み手に対して総じて謙虚な姿勢?で、時おり出てくる米国っぽい例え話を除けば、全体として読みやすかった。日本語訳が優秀なのかな。 個別のエピソードについては説得力もあるし納得なんだけれど、果たしてこの本で述べられている”ビジョナリー”が「すなわちイコール”良”」なのかどうかについては、「結果論じゃん」と思えないこともなく、個人的には慎重に吟味したい。 自分の会社をビジョナリーカンパニーにしたい、という経営者もしくはそれに準じる人と、「ビジョナリーカンパニー」という言葉を発したいミーハーな人におすすめ。
1投稿日: 2019.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログドラッカーやカーネギーに比肩される名著ということで購入。 「よい会社の条件は何なのか、本気で考えてみた」という内容。実在の企業を、しかも同業他社と比較することによって、本当に歴史に名を遺すような企業が共通して持っている特質が何かを浮き彫りにする。例えば我々が持っている、「歴史的企業」の一般的イメージであるカリスマ的な指導者がいる・画期的なアイデアに基づき起業している・誰にとっても働きやすい等々の要素は、どれも「ビジョナリーカンパニーにとって特に必要ではない」と断じている。その解明に基づき、自らがビジョナリーカンパニーを作るにはどうすればいいかに迫る。 やはり「経営のバイブル」と言われるだけあって、読者対象は経営者に寄っていると感じる。とはいえ、本文にも「経営者に限らず、どの階層・部門でも」とあるとおり、自身が主体として仕事に向き合う際に参考になる考え方は多い。何より、熱がある。仕事に対する自身のモチベーションに火をつけるのには適している。 企業ごとの事例が繰り返し繰り返し語られるので、その部分が冗長という読みづらさはある。恐らく読書慣れしていない人が「名著だから」ということで読むと、その点で挫折してしまうと思う。ただ、逆に言えば企業ごとの事例のところを斜め読みしてしまえば、かなりコンパクトに読める。 どう感じるかはともかく、ビジネスパーソンなら一読しておいて損はない。
0投稿日: 2019.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
興味深い分析の本ではあった。 ビジョナリーカンパニーの選び方として、経営者にアンケートをして選ぶというのは、合理的でありかつ短絡的な気もしたが、ともかくも選ばれた会社と、同規模で選ばれなかった比較対象企業とを比較して、ビジョナリーカンパニーの本質迫るというアプローチ面白いと思った。 その結果抽出された要素のうち心に残ったのは、基本理念を明確にしていること、基本理念は変えず基本理念以外は全て変えるだけの意気込みと覚悟を持っていること、変わり続けるしくみを作っていること、独特の強烈な文化をもっていること、経営者が生え抜きであること、orではなくandを実現する姿勢 などであった。 特に短期的利益よりも理念の実現を目指す姿勢一貫していることが重要であり、また、理念必ずしも最初から掲げられていなくても良いが、理念を明確化しようとするときに、理念は作るのではなく見つけ出すもにであるということが目からウロコであった。
0投稿日: 2019.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ・「ビジョナリー・カンパニー」とは、ビジョンを持ち、同業他社から尊敬される、卓越した企業のこと。 ・ビジョナリー・カンパニーの創業者は、概して商品アイデアで大ヒットを飛ばしたりすることに重きを置かない。最も大切なのは、ビジョナリー・カンパニーになる“組織”を築くこと。 ・ビジョナリー・カンパニーの経営者の多くは、カリスマとは程遠い、控えめで、思慮深い人物である。 ・「基本理念を維持しながら、進歩を促す」こそが、ビジョナリー・カンパニーの真髄。 ・基本理念を維持しつつ進歩するため、ビジョナリー・カンパニーは、次の5つのことを行っている。 ①社運を賭けた大胆な目標を持つ ②カルトのような文化を持つ ③大量のものを試して、うまくいったものを残す ④生え抜きの経営陣を持つ ⑤決して満足しない
1投稿日: 2019.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業で働くどんな立場の方にもおススメできる名著です。 時を超えて存続し、成長し続ける企業について、比較企業との対比でわかりやすく説明されています。 ビジョンを持ち、先見的で未来志向的で、同業他社から尊敬を多く集め、時を超えて成長し続ける会社=ビジョナリーカンパニー。 ビジョナリーカンパニーには、端的に言うと基本理念=基本価値観+目的が存在する。 創業時のアイディアが素晴らしいやカリスマ経営者、利益追求などは必要ない。 私は7人の部下がいる部署の管理者ですが、細かい進捗管理や他部署との折衝に時間を割くことが大切に思ってました。しかし、この本を読み、我々の部署が存在する目的、基本価値観を与える方が、よっぽど大切であることに気づかされました。 50年後も必要とされるチームを目指し、自社のコーポレートステートメントを読み直し、理解し、自部署の基本理念を考え、メンバーと共有して行きたいと思います。 以下、参考になった記述を備忘録で。 売り上げや利益は会社にとって酸素や水と同じく、存続に必要不可欠ではあるが、決してそれ自身が目的ではない。 目的を考える際に、もしも誰にも迷惑をかけずに、会社を解散できるとして、何故それをやらないか。やることにより、どういう不利益を得るか。 維持すべき基本理念と、進歩を促す仕組み、木の幹のように変割らない部分と、枝葉のように常に変わっていく部分の両方が必要。
0投稿日: 2019.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ投資術として読んでみた。「ウサギの中からカメを探す」術が少し分かったかも。 4年前にモトローラとノキア、クァルコムいずれが携帯業界のウサギに変身するか迷ったのを思い出した。結局どちらも買わずにいたのは正解。最後に勝利を納めたのがAAPLとは・・・。 ブームが過ぎてから読んだけど、研究対象が老舗企業ばかりなのであまり古臭さを感じなかった。
0投稿日: 2019.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1995年出版のビジネス書の古典。 50年以上存続する企業の特徴とはなにか?を調べる為に、6年の歳月をかけて行われた調査記録です 読んでいて面白いのは 「成功した会社に共通する成功の法則」 的なハウツーでは一切なく、炙りだされてくるのは、ダーウィンが発見した生物の進化の法則と企業の存続は極めて酷似している、という内容です。 これを見れば永続的企業が作れるわけでもないし、長期存続する企業の素晴らしさというよりも、一種のカルト的不気味さが伝わる内容ですが、純粋に読み物としてとてもおもしろい。 現代の経営のトレンドは、「意思決定スピードの向上」なので、カリスマ経営者がニュースで取り上げられますが、本書でビジョナリー・カンパニーとしてあげられた企業には「カリスマ経営者」はいませんし、創業時までさかのぼっても、カリスマ的なタイプは少ないのです。 本書ではこれを 「自分が時を告げるのではなく、時を告げる時計を設計する職人」 と名付けています。 すごく分かりやすい例えだなと思ったのあ、アメリカ合衆国の建国。 独立を果たした後、誰が統治者(王)になるかを議論するのではなく、この先、建国した人間がいなくなっても、永続的に能力のある人間が厳選されて統治者になる仕組みを作ったこと。 (現代では選挙で能力あるものが選ばれるかはちょっと疑問ですが、市場原理によって統治者が選ばれる仕組みは、現代でも合衆国の源泉です。) ドラッカーの書籍と共有しているのは、一見とてもシンプルで分かりやすいのだけど、それを実行するのはとても難しい。 なぜなら、それはノウハウではなく理念だから。 そして、理念から具体的実行を、ジャブのように高速に繰り返し、そこからフィードバックを得られるかどうか、これは確かに企業の大きな分かれ目だと思います。 観念的で捉えるのが難しい「企業文化」「企業理念」を綿密な調査で、データとして提示したのは素晴らしい。 変な例えですが、このゾクゾク感は、子供の時に読んだ「指輪物語」に通じます。 難しい内容ではありませんし、マネージャーや経営者だけではなく、全ての人が楽しめます。
0投稿日: 2019.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ分厚い本ですが、わかりやすくてスラスラと読めます。 1.この本を一言で表すと? ・いい組織の作り方 2.よかった点を3〜5つ ・究極の作品は会社(p48) →会社を「雇用し、税金を納め、よい製品・サービスで社会に貢献する」という社会一部のものという考えにつながると感じた。また、技術・アイデアだけでは長続きしないものだとも感じた。 ・糸状虫症治療薬「メクチザン」の無料提供(p77) →アメリカにこんな美談があったとは知らなかった。相当な強い意志と覚悟がないとできないと思う。その点に恐れ入りました。 ・BHAGは組織のどのレベルでも使える(p184) →全体的に経営者向けの話が多いが、経営者じゃなくても使えることが書かれている。特に自分自身に大胆な目標がないことを痛感した。 ・基本理念こそが基軸(p280) →それほど基本理念が大事ということ。自分自身の基本理念が必要と強く感じた。 ・黒帯の寓話(p338) →決して満足しない、満足してしまったらおしまい、いつまでも修行というのか日本的に感じた。 2.参考にならなかった所(つっこみ所) ・21世紀になっても調査結果が時代遅れになることはないと断言しているが、本当にそうなのか? 特に、カルトの部分はすんなりと受け入れられなかった。 3.実践してみようとおもうこと ・個人のBHAGを考えてみる。 ・家族の基本理念を考える。
1投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ビジョナリーカンパニーは種の進化によく似ている ・企業そのものが究極の作品である ・すばらしい製品やサービスを次々に生み出すのはこうした会社が組織として卓越しているからにほかならない ・すばらしい経営者を輩出しているのも同じ理由 ・単なる金儲けを超越した基本的価値観=基本理念 ・利益とは人間の体にとっての血液のようなものだ。人生の目的ではないがそれがなければ生きられない。 ・経営手法も目標も、基本的な信念(基本理念)に反すると思われる場合にはいつでも変更しなければならない ・ビジョナリーカンパニーが掲げる基本的価値観はたいてい3〜6つ ・BHAG(BigHairyAudaciousGoals)大胆で明確な目標が組織にとって有益なのはそれが達成されていない間だけだ ・IBM=Think! ・3M:ミネソタ・マイニング&マニュファクチャリング ・何かに偶然ぶつかることがあるが、ぶつかるのは動いているからである ・ヒューレット・パッカード →横並びの製品やコピー製品は市場にどれだけの潜在力があっても日の目を見ないようになっている ・神は細部に宿る…建築家ミース・ファン・デル・ローエ ・正しい問いの立て方は「これはよい方法なのか」ではなく「この方法は当社の基本理念にあっているのか」である ・ビジョナリーカンパニーで変えてはならない聖域は基本理念だけであり、それ以外のものは何でも変えることができるし無くすことさえできる ・会社は政府組織や伝統ある大学と変わらぬほど大切にし、関心を向けるべきものだ。 ・従業員は業務上の自主性を要求しながら、同時に、自分たちの関係している組織が、何かの目的を追って前進するよう求めている ・手軽なノウハウ本に成功の秘訣を求めるのは「あなたにも名画が描けます」というキットをミケランジェロが買うようなもの ・ビジョナリーカンパニーの性格を持った企業の倒産確率:75% ・比較対象企業の性格を持った企業の倒産確率:50%
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本理念を形骸化させることなくシステムから一貫して構築する。そういう会社に合う自分を見つけないといけない、のかな。また目先の利益を犠牲にせず長期的な利益を追求する。ANDの構想。難しい。書いてあることは本質的で実体的なので非常に興味深い。
0投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ数十年まえには、同じような規模の同業社の現在の差を分析し(たとえば、ソニーとアイワ)、その差の原因を探る。結果は、「創業当時に作り上げられた、企業文化、理念」の差である。私は、この非凡な結論に大賛成であるが、この結果を受けいられない人も多々いらっしゃると思う。そういう人は、一読あれ。
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ビジョナリーカンパニーは、その基本理念と高い要素にぴっ足りと合う者にとってだけ素晴らしい職場である ・早い時期に成功することと、ビジョナリーカンパニーとして成功することは逆相関している ・アイデアは諦めたり、変えたり、発展させることはあるが、会社は絶対に諦めない ・一流の知性と言えるかどうかは、二つの相反する考え方を同時に受け入れながら、それぞれの機能を発揮させる能力があるかどうかで判断される ビジョナリーカンパニーはいくつかの目標を同時に追求する傾向があり、利益を得ることはその中のひとつに過ぎず、最大の目標であるとは限らない ・利益とは人間の体にとっての酸素や食料や血液のようなものだ。人生の目的ではないが、それがなければ生きられない ・人々が集まれば個人ではできないことができるようになる、つまり社会に貢献できる ・ビジョナリーカンパニーの基本理念は、理論や外部環境によって正当化せうる必要などないものである。時代の流れや流行に左右されることもない。市場環境が変化した場合ですら変わることはない。 ・BHAGは人々の意欲を引き出す ・ビジョナリーカンパニーは、自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向にある ・アメリカンエキスプレスはいくつもの小さなステップを積み重ねることによって、設立当初の小荷物事業から、またっく違った事業を展開する企業になった ・環境が変わるとその環境にとくに適した変異が淘汰で生き残ることになる ・重要なのは、優秀な経営陣の継続性が保たれていること ・安心感はビジョナリーカンパニーにとっての目標ではない。それどころか不安を作り出し、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す強力な仕組み作りを設けている ・常に進歩を求める経営者の意向が活かされるように、会社組織の中に具体的な仕組みをつくっていくこと ・まずなによりも先に基本理念をしっかりさせること、基本理念は見つけ出すしかない、基本理念が固まれば、基本理念以外の点はどんなことでも、自由に変えられるべきだ 【コメント】 会社が価値を出し続けられるかどうかを決めるのは、商品力でも、個々の人でも、アイデアでも、指導者でもない、その会社自体(=組織)と、その組織がもつ基本理念である。それは会社にも言えることだか、個々のチームにも同じことが言える。 ビジョナリーカンパニーとは、環境や指導者などに左右されない基本理念を持ちながら、その時の外部環境内部環境合わせて基本理念以外のことを変化させていける組織である。
0投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年を超え、読み継がれるだけある。「基本理念」こそ最も必要であることが説いてある。でも、基本理念を持つことは容易ではない。
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョナリー・カンパニー、つまりビジョンを持つ企業、未来志向の企業であり、同業他社からも尊敬を集める企業である。以下、18社の事例が紹介されている。 3M、AMEX、ボーイング、シティコープ、GE、フォード、ヒューレット・パッカード、IBM、ジョンソン&ジョンソン、マリオット、めるく、モトローラ、ノードストローム、P&G、フィリップ・モリス、ソニー、ウォルマート、ディズニー 先見の明がある起業家が、すばらしいアイディアを武器に会社を成長させる。多く信じられている神話であるが、実際には、ビジョナリー・カンパニーの中にはそうした企業は殆ど無い。P&Gは、石鹸とろうそくの会社、モトローラはラジオの部品を修理する零細企業として出発している。こうした企業の創業者は、サステイナブルな持続できる組織を築く事で、卓越しているわけで、製品の優秀性だけで競争優位を得ている訳ではない。 大胆な目標: BHAG Big Hairy Audacious Goals フォードは大衆のために乗用車を作る、かつ価格が安く、道路からは馬車が消え、自動車に乗ることが当然になるというBHAGを掲げて、当時30社あった中の1社に過ぎなかった存在だったにも関わらず、トップに躍り出たのである。 J ウィラード・マリオット 「一番大切な事は、自己を律する事である。自己を律する事がなければ、人格は形成されない、人格が形成されなければ、進歩はない。」 ビジョナリー・カンパニーは、自分に対する要求が極めて高い。自己満足に陥れば、衰退しか無いのである。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーはカルトである。いやカルトみたいな。強い組織の方が仕事はやりやすいのではないかと思う。でも私は行かないけど。
0投稿日: 2018.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社、特に経営を行う場合目先の金儲けだけを考えがちだけど理念など目的を設定することが重要だと感じた。
0投稿日: 2018.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し古い本なので現実とそぐわないところがあるかもしれません。 今までのビジョナリーカンパニーというのは宗教のような側面がたぶんにある、ということがわかった。 理念は大事だが、往々にして排他的になりがち。 最近はやりのダイバーシティを考え方、行動、働き方にも当てはめて、個々人のぶれの範囲内で会社理念に沿った仕事ができるような企業が増えれば、そのような働き方を社会的、経済的に許容できるような社会になればと思う。 ベーシックインカムには何となく期待している。 払ってもいい金額:1300円(上梓から年月が経っているため)
2投稿日: 2018.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業がビジョナリーになるために必要なものは、カリスマ経営者ではなく、基本理念とそれを実現するための仕組みにある、ということがテーマです。 名著だと思います。
0投稿日: 2018.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。やはり圧倒的に名著…。こんなにメモを取った書籍は久々だ。社会に出てから読むとまた一段と凄みが分かる。 今や一般化された感もあるが、本著の主張は非常にシンプル。「①基本理念を守る、②進歩を促す、③一貫性を重視する」。あとはこれを仕組み化すると。 今や古典とすら言われる域に達しつつあるが、微塵も陳腐化することはない。これらの重要性は色褪せるどころか日増しに高まっている。ドラッカー、ポーターらと共に永遠に読み継がれていくであろう良書。
0投稿日: 2017.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ事業家達のバイブル的1冊。創業当初読んだけど改めて読み返してみた。 1.時を告げる預言者になるな。時計を作る設計者になれ。 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。 ビジョンや基本理念に基いて、全ての制度や戦略を作っていきましょうといういうことを詳しい事例と共に書かれている。 翻訳本だけどめずらしく読みやすい。 起業家だけではなく、全ての人が読んで感銘を受ける一冊だと思います。
0投稿日: 2017.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
重要だと思った内容は以下の通り。 ・真髄は、基本理念と進歩への意欲を、組織のすみずみにまで浸透させているところ。このためには、ただ単に上記内容を設定するだけではなく、浸透に向けて粘り強く活動していかなければならない。 ・楽な生活を最終目標にしているわけではない、GoodはGreatの敵である ・不安をもたらす仕組みをつくる(P&Gは社内のブランド間で競争をさせている、ホテルの覆面調査) ・一貫性の追求、And(中長期利益と短期利益等)の追及 ・一種のカルトのような企業文化があり、Fitする人材にとっては良い場所だが、合わない人にとっては悲惨な場所 本書で提示されているビジョナリーカンパニーで勤務する・創り上げるのは楽ではない。従業員として勤務することに覚悟が必要であるが、経営者としてビジョナリーカンパニーを創り上げるのは並大抵の覚悟では耐えられない。しかし、見方によっては、企業の理念を理解し、常に物事を進歩させていくことは、働く上で当然の事であるとも考えられる。この観点と現実にビジョナリーカンパニーが限られた数しか存在しないことを踏まえると、働くことに対して誠実に向き合っていない人間が多く、また、その状況を改善することを出来ていない企業が多いのだと推測できる(本書の文脈上)。
0投稿日: 2017.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
各所で読むべき読むべきと言われている1冊。 かなり重い(物理的に)ので躊躇っていたが、思い切って読了。 1995年当時は経営理念・ビジョン・ミッション、、この辺りが今ほど活発に議論されていなかったように感じる。 今となっては"あぁ、そうだよね"と思える記述も多かったが、20年前だと画期的な目線での分析だったのだと思う。 ----------------------------------------- ◆ビジョナリーカンパニーは”すばらしいアイデア”を持って設立されていたのではない ex)ソニー 設立当初は具体的な商品アイデアは無かった →事業資金を稼ぐ為に、まずどんな商売をするか数週間に渡って協議した ex)ウォルマート 自分の会社を持ちたい、という意欲と少しの小売業の知識だけで設立 →会社が徐々に発展して行く途中で”ディスカウントショップ”というアイデアを発見 ◆利益を最大に高めること、は大きな原動力でも最大の目標でも無い ビジョナリーカンパニーのほとんどが経済上の目的を超えた基本理念を持っている ・基本理念を掲げる時には「心から信じている事」を表現するのが不可欠 ・基本理念は企業の内部にある要素であり、外部の環境に左右される物ではない事を理解する必要が有る ・そして、理念をどこまで貫き通しているかの方が、理念の内容よりも重要である ◆基本理念の維持 重要なのは優れた理念をつくる事ではなく、維持する仕組みをつくる事 ex)ディズニー 「ディズニー・トラディション」というセミナーの受講を義務化 ex)ヒューレット・パッカード HPウェイを掲げるだけでなく、社内人材だけを登用する方針を打ち出す また、理念を従業員の評価と昇進の際の基準にした すばらしい意図を持ち、気持ちを奮い立たせるビジョンを持っているが、その意図を活かす具体的な仕組みを作るという不可欠な手段を取っていない組織が多い ビジョナリーカンパニーの建築家は「戦略」「戦術」「組織体系」「構造」「報酬制度」「職務計画」など、企業の動き全てに一貫性を持たせている ◆カルトのような文化 あるIBM従業員の夫 「IBMは動機付けが上手い。洗脳されているという人も居るが、こういう洗脳ならいい。会社への忠誠心を高め、働く意欲を高めているのだから」 個人崇拝のカルトを作るのではなく、 「基本理念を熱心に維持するしっかりした仕組みをもった組織」を作ること ex) ・入社時のオリエンテーションで技術技能だけでなく理念・価値観・社史・伝統を教える ・社内登用を進め、若い時期に従業員の考え方を自社の価値観に合わせて教育する ・「英雄的な行動」や模範になる人物の神話を絶えず吹き込む ・独特の言葉や用語で価値判断の基準をはっきりさせ、特別なエリート集団に属している感覚を持たせる ・理念に基づいて努力した従業員への表彰制度 従業員に権限を与えて、分散型の組織をつくりたいと考えている企業は ・何よりも先ず理念をしっかりさせる ・従業員を教化し、病原菌を追い払う ・残った従業員にエリート組織の一員として大きな責任を追っている自覚を持たせる →適切な役者を舞台に立たせ、正しい考え方を教え込み、状況に応じたアドリブを使う自由を与える ◆大量のものを試して、うまくいったものを残す ビジョナリーカンパニーの今日を築いた重要な動きの中に、 「計画以外のなんらかのプロセス」によってもたらされた物が多い ex)3M 教会の合唱隊で歌っている時に聖歌の歌詞を見つけやすいよう紙切れを挟んでいた 肝心の時に紙切れが飛んでしまうので、少しばかりの接着剤を塗る事を考えた 3Mには"進化を刺激する仕組み"がある(下記は一部抜粋) ・15%ルール:勤務時間の15%を自分で選んだテーマの研究や創意工夫にあてられる ・25%ルール:部門の売上げの25%を過去5年間の新商品で上げるよう求める ポストイットはその15%ルールの活用によって生まれた 進化の過程はそれをよく理解し、積極的に利用すれば進歩を促す強力な方法になる ビジョナリーカンパニーはその進化の過程の利用にはるかに積極的である
0投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ学者が書いたビジネス書は好きです。 以下では若干ケチつけ気味のことを書いていますが、 それだけ真剣に向き合って考えさせられた本だからこその感想です。 ●ビジョナリーカンパニーとは● ビジョナリーカンパニーの定義は、 短期的に爆発的な利益を上げて、業界一位になったことがある とかではなくて、 ある業界において(あるいは業界を変えながらも) 不動の地位を保ち続けている企業 というようなイメージ。 そういうビジョナリー・カンパニー(金メダル級の企業)と、 完全な二流三流企業ではなく、短期的には利益を上げられるけど、業績が長続きしない会社(銀メダル級の企業)は何が違うのか? 答えは、 前者は短期的な利益よりも優先される、会社がが追求するべき永続的な価値をリーダーがきちんと定義していて、それが組織の末端まで浸透しているから。 後者は短期的な利益を最優先するような戦略をリーダーが立てていて、組織もそういうふうに動いているから。 ・・・って、なんだかトートロジカル(※)じゃないですか? という感じは最後まで拭い去れませんでしたが、 目指すべきところをちゃんと目指す ってことは大切なことなんだなと思いました。 ※トートロジーは、「AはAである」という論理のこと。 論理的には常に真だけど、情報量はゼロです。 ●BHAG● 自己啓発系の本でよく引用されている「BHAG」(びーはぐ) の概念について。 BHAGとは、 Big 大きくて Hairy ぞっとするほど困難で Audacious 大胆な Goals 目標 のこと。 リーダーは、組織のメンバーがワクワクするような 「BHAG」 を発信し続け、 その 「BHAG」 が達成されたら、また次の 「BHAG」 を提示して、 常に組織が 「BHAG」 に向かって ワクワクして 一致団結している状態を作るべきだ! ビジョナリーカンパニーの共通点は、それができていることだ! …というのが本書の主張で、ここから先は私見です。 「大きくて、ぞっとするほど困難で、大胆な目標」 を掲げることで 「ワクワク」 できるようなメンタリティーの人ばっかり集まった会社なら、 そりゃ 「金メダル級」 になって 何の不思議もないのでは?と。 金メダル級じゃない企業の社員のほとんどは、 目標が高すぎると ワクワクするどころか それこそ ぞっとして 萎えてしまう人が多いと思う。 そういう人たちをモチベートして、金メダル級じゃないところから金メダル級に持っていくのは、 「BHAG」じゃなくて「SLIG」(←造語です)じゃないか? なんてことを考えました。 Stretching 少し背伸びしたくらいのレベルで Likely 現実味があって Interesting 興味をかきたてるような Goals 目標 でも、こんな生ぬるいことを言っているようじゃ、いつまでたっても金メダル級にはなれないのか・・・ うーん・・・ 金メダル級じゃない会社に勤める私が、私の会社を金メダル級に返り咲かせるには、どうしたら良いのか・・・ ・・・探求は続く・・・
2投稿日: 2017.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはやっぱり名著としか、言えないな。まずは読んでほしい。 内容の素晴らしさは実際に読んでもらうとして、方法論とプレゼンテーションの素晴らしさについてだけコメントしたい。この本は、納得性のあるケースセレクション、インタビューや定量分析を組み合わせた調査設計の厳密性と言った点で、極めて高い学術的な基準をクリアーしていると同時に、本の全体の構成の分かりやすさ、そしてあまり学術的な書き方ではなく、生の経営者の言葉などを引用した生き生きとした文章になっている。きわめて、アメリカ的な実証科学と説得技術が高度に融合した本だと思う。
1投稿日: 2017.04.30「基本理念」が大事
紙で途中まで読んだ記憶がありますが、電子書籍で再読し、読了。 かなり昔の本ですが、比較対象企業をピックアップするなどの切り口が面白い。ただし、この企業数が多いため、冗長感はありますね。
0投稿日: 2017.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログいくつかのフィルターを設けて米国の企業を抽出し、基本理念などやその会社の特徴を研究した結果からどのような企業が、永続的に発展してきているかを述べた好著。
0投稿日: 2017.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの経営者がオススメしていた本で、読んでみる。2017年最初に読む本がこれで良かったな。 「長期に渡り優良企業と同じようには成長できなかった優良企業を比較し時代を超えて、一貫してみられる経営理念を探す」という内容。お金ではなく、会社の存在意義を定義し、ずっと変わらない「基本理念」を持つこと、そしてそれを社員に浸透させること。 ウチの会社の社長は読んでいるなと思った。変わらない基本理念を3年前位から社員に浸透させる働きをしている。 次期社長予定の友人にあげたいなと思う。 【学】 「ORの抑制」をはねのけ、「ANDの才能」を活かす ソニーはようやく認知されてきた社名を、世界では分かりづらいからとソニーに変えた。 ビジョナリー(未来志向の)
0投稿日: 2017.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログいいこと書いてるけど、退屈で寝落ち連発。 2章買ったがこれまた読み進まない。 でもいいこと書いてた。
0投稿日: 2016.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ永続する、真に卓越した企業の条件とは?それについて、調査した結果について、まとめられた本。少し古い内容だが、導き出された条件は、現代でも十分通用するものと思う。 基本理念を維持し、進歩を促す。それをあるDNAとして、何世代にも渡り、継続させるための制度を作る。当たり前のことを、どれだけブレずに実行できるか。それが重要に感じた。 それは個人にも当てはまると思う。しっかり自分の基軸をもって、それに基づいて、コツコツと習慣化して実行できるか。
0投稿日: 2016.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ後世にわたって語り継がれる企業であるビジョナリー・カンパニーと比較対象企業とを著者が膨大な資料をもとに綿密な調査をもとに調べた一冊。 「時計をつくる」、「ANDの才能」、「基本理念を維持し、進歩を促す」「一貫性」という4つを膨大な資料に基づく調査から著者が定義していく過程は非常に発見が多く、興味深いものでした。 核となる部分と変化することのバランスが大事なことや理念などの共有と内部での人材の育成など企業の運営や発展に非常に重要なことが多く書かれていました。 ビジョナリー・カンパニーに共通していることとして卓越した企業文化、基本理念からぶれないこと、教育や内部統制に出し惜しみしないこと、ANDの才能とORの抑圧、進化を受け入れること、成功に安住しないことなどがあると本書を読んで感じました。 約20年ほど前に出版された一冊ですが、どの時代でも共通する企業の本質を解説した一冊でもあり、多様化する価値や需要のなかでいかに企業として存続するための持続可能性について本書では触れられていると感じました。 同業で比較しているので理解しやすく、またやはり年を経て読み継がれている名著であるだけに、複数回読むことに本質に近づいていくとも感じました。
1投稿日: 2016.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アメリカの大手企業の歩み、ビジョン、考え、経営者についてなどの解析がされている。 多くの経営者が推薦する本であるが、企業や経営に関して、知識が少ないためか、理解が難しかった。 50ページほど読んで、諦めました。
0投稿日: 2016.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くのデータと、客観的になるように最大限つとめた分析。説得力がありました。これらの企業の今後を調べたくなりました。 個人としてもこれらの原則をすぐ始めたくなるような、力と情熱をもった本。
1投稿日: 2016.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業の歴史に立脚したストーリーを、類似企業のそれと比較することによりビジョナリー(先見性)たる根底概念を導き出す。特筆すべきは、『エクセレントカンパニー』でいう基軸と基本理念を分けて捉えている点。ポジショニング、ケイパビリティ、コンフィギュレーションを経た試行錯誤型経営の現代にあっては、立ち返るのに最適な名著といえるだろう。本書では、ダーウィンの進化論を引き合いに出して生物学と経営をオーバーラップさせている局面があるが、より顕著なアナロジーは、人の集団として共通する国にも働く気がする。基本理念が認識されておらず、時計を作る努力もせずに、偉大なる時の預言者の不在を他人事で嘆いている国民ばかりでは、国の行く末も論ずるに値しないのかもしれない。
0投稿日: 2016.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログサイバーエージェントの藤田社長が盛んに雑誌等で載せている名著 やっと読むことが出来ました いろいろと既成概念が覆されます
0投稿日: 2016.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ■20160403 読了 ■あらすじ ・ビジョナリーカンパニー 18社 ・比較対象企業も銀メダリストか銅メダリスト ・ビジョナリーカンパニー は組織 ・12の崩れた神話 ・時を告げるのではなく、時計をつくる ・ORではなくANDの才能を活かす ・本の内容は390ページ 付録含めると469ページ ■コメント ・1995年初版だが、20年経った今でも古さを感じさせない普遍的な内容
0投稿日: 2016.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた名著。 読もう読もうと思って1年くらい経ってしまったので、年末年始に一気読みしてみた。 本当に普遍的なことが書かれていて、今読んでも特段古臭さを感じないのがすごい。 そして、前の会社が目指していたことがほんの少し分かった気がした。 今の会社はどうなのかな、と思いを巡らせました。 へー、なるほど。 で終わるのではなく、ちゃんと自分ごととして捉えたいと思います。
1投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
<2018/12/24> 再読。この内容を、GAFAにあてはめたらどうなるのだろう。基本的価値観、高い目標、チャレンジ、カルト的な文化など、まさに当てはまりそうな気がする。 <2015/11/27> 1995年の作品で、事例はさすがに古いが、指摘している内容は普遍的なものだと感じる。ビジネス書の古典?の一つですね。
0投稿日: 2015.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーを築くには基本理念を文章にすることが重要である。 基本理念=基本的価値観+目的 基本的価値観:組織にとって不可欠で不変の主義。 利益の追求や目先の事情のために曲げてはならない 通常3つか6つ 目的:単なる金儲けを超えた会社の根本的な存在理由。 個々の戦略や事業戦略と近藤はしてなならない。 なぜこの会社は存在するのか? ================== 「ORの抑圧」をはねのけ、「ANDの才能」を活かす (P72) ================== AかBのどちらかでなければならず、AとBの両方というわけにはいかないという考え方。 例)変化か安定かのとちらか? ビジョナリーカンパニーはこの「ORの抑圧」に屈することなく、「ANDの才能」によって自由にものごとを考える。 例)「利益を超えた目的と現実的な利益の追求」 ・始まりの終わり 「一貫性の力」 (フォード、メルク、ヒューレット・パッカード) 1970年代に学習曲線理論・市場シェアについて一世を風靡したが、ヒュレッド・パッカードは全否定。学習曲線理論を明確に否定した。 1「全体像を描く」 2「小さなことにこだわる_ 3「下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせる」 4「流行に逆らっても、自分自身の流れに従う」 5「矛盾をなくす」 6「一般的な原則を維持しながら、新しい方法を編み出す」 ↓ 本を読んで、、以下の4つの概念だけは覚えておいてほしい (P370) 1)時を告げる預言者になるな。時計を作る設計者になれ! 2)「ANDの才能」を重視しよう。 3)基本理念を維持し、進歩を促す。 4)一貫性を追求しよう
0投稿日: 2015.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ名著といわれるだけのことはある。 基本理念という軸をつくり、戦略、組織、給与、レイアウトまで一貫した仕組みを作る。 それも、徹底した仕組みを作る。 簡単なようで難しい。 組織で最も大切なのは、人材マネジメントだと感じた。
0投稿日: 2015.10.06
