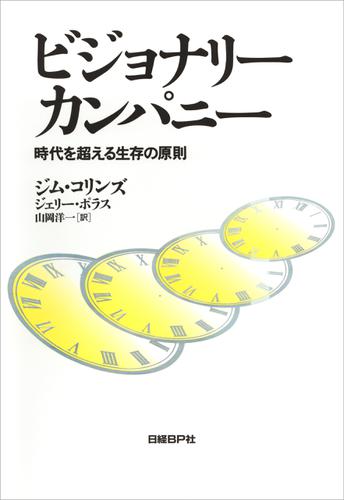
総合評価
(378件)| 149 | ||
| 127 | ||
| 54 | ||
| 12 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「いつか読もう」と思って読んでいなかった一冊。ビジョナリー・カンパニーとして選ばれた企業群と比較対象企業群、この2つにははっきりした考え方の違いがあることがよくわかる、読みやすい一冊だったなと思います。自分の日々の仕事や奥トレにも活かせる考え方はいくつもあって、「まず大量に試して、いいものを残す」ていう考え方は自分のこれまでのスタンスとも重なる部分もあるのかなと。もっと強化していい部分だと思いました。ただ、そういう企業で働けたことが従業員それぞれの人生を幸せにしたかはわからないかな、、とも思いました。こういう企業に合う人もいるだろうけど、いろいろ犠牲にしないと合わない人の方が多そうかなとか。
0投稿日: 2015.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ビジョナリー・カンパニーの真髄は、基本理念と進歩への意欲を、組織のすみずみにまで浸透させていることにある。 目標、戦略、方針、過程、企業文化、経営陣の行動、オフィス・レイアウト、給与体系、会計システム、職務計画など、企業の動きのすべてに浸透させていることにある。 ビジョナリー・カンパニーは一貫した職場環境をつくりあげ、相互に矛盾がなく、相互に補強し合う大量のシグナルを送って、会社の理念と理想を誤解することはまずできないようにしている。』 時代を超えて成長を続ける企業の特徴的な構成要素は以下の4つで、それを徹底し続ける強力な組織的な意志が重要なんだろうな。 1.時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。 自分の会社と比較して読むと面白い。
0投稿日: 2015.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた経営学の名著。 「皆が名著という本は読みたくない病」を発症していたので敬遠していたが、人材採用活動を契機に手に取った。 本書では、ビジョナリー企業(長期間にわたって先見的な企業)を実名で取り上げ、しかも比較対象企業として「いい会社だけどビジョナリー企業とは言えない」企業まで実名で取り上げ、両者を徹底的に調査することで「ビジョナリー」と「そうでない」企業の差を明らかにしている。 たくさんの示唆があるが、その中のひとつに「企業の持つ基本理念」の重要性が説かれている。以下に、一番「なるほど」と思った箇所を引用する。 「重要な問題は、企業が『正しい』基本理念や『好ましい』基本理念を持っているかどうかではなく、企業が、好ましいにせよ、好ましくないにせよ、基本理念を持っており、社員の指針となり、活力を与えているかどうかである」(P114)。 基本理念そのものの重要性は分かっていたつもりだが、その内容が「正しい」「好ましい」はさして重要ではなく、理念を持っていて、社員の指針となるよう徹底されていて、それが活力になっているかどうかだけが重要である、という指摘である。 これには心底驚いた。だが、うまく言えないけど、なるほど確かに経営とはそうしたものなのだろうと直感的に深く腹に落ちた。とりあえず、「理念」をいまの自分なりの言葉で書いた。
0投稿日: 2015.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015/04/26 終始英語が多くて、読むのに厄介であった。特に、海外の会社が多く、馴染みぶかい会社が少なく、そもそも何の会社なのか、というのが分からなかったので、あまり理解の土台ができていなかった。後半からは、速読の素材として利用した。ほとんど内容は、題名以外の事は理解できていないような気もする。また、しばらく時間がたったら、読み返してみるのもいいかもしれない。今の時点で必要な知識や考え方ではないような気もした。 どういうスタンスでこの本を読んでいけばいいのか、いまいちわからない。会社経営の視点でこの本を読むべきなのか、それとも、個人が働く上で意識することと言う意味で、読むべきなのかはっきり立場付できない部分が今はある。 時を告げるのではなく、時計を作るという、組織づくりの考え方が重要であると。 今日の会社において、どの会社でも掲げている、企業理念と言うものは、この本による影響なのだろうか。利益第一ではなく、理念第一にあり、後から力がついてくるものであるという。3年とはその時々の目的ではなく、100年後も普遍であるようなものである必要がある。
0投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界中から注目されたせいか、批判も多い著作。端的に言うと「とても儲かる考え方は・・・ある!!」かと。プロテスタントはカソリックより生涯年収が高いとか。であるならば考え方とビジネス成績がリンクしてるのは間違いなさそう。
0投稿日: 2015.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業は人間的側面があり生き物と似ている、と最近は考えるようになった。読み進めるとダーウィンの進化論を紹介したりと生物学的な記載があり、持論と通じるところがあった。経営者になったらこの生き物をどう取り扱うのかという問題意識のもと読み進めた。 時間を告げるのでなく、時計をつくる。言い得て妙だが、誰しもが言える言葉でいうと、仕組みをつくり定着させ文化が築かれるといったところだろうか。人事担当として自分の仕事は文化をつくることではないか、と思っていた矢先、担当業務は経営者がするべきことの一端を担っていると認識させられた。 飛行機問題。会長と社長である自分が乗っている飛行機が墜落したら、誰を後任の会長とするか。事実かは定かではないがGEの後継者選抜で課される問いらしい。後継者の選択、選抜の仕組みの整備が、経営者の最も重要な仕事の一つということがよくわかる。
0投稿日: 2015.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ビジョナリーとは何か?」を教えてくれる本。この本のおかげで、「では、自社の真のビジョンは何か?」を真剣に考えさせられた。
0投稿日: 2015.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
◎時を告げるのでなく、時計を作る。 ◎『ORの抑制』をはねのけ、『ANDの才能』を活かす ◎基本理念を維持し、進歩を促す。基本理念から離れない ・社運をかけた大胆な目標。BHAG:具体的かつ明確な目標を設定し、達成に向けて行動する。進歩を促す強力な仕組み。 ・カルトのような組織文化 ・大量のものを試して、うまくいったものを残す。3M ・生え抜きの経営陣。 ◎決して満足しない ◎一貫性の力
0投稿日: 2015.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ時計の時刻を読む人(カリスマ)となるな。時計を作る人となれ(ビジョンとシステム)。というメッセージ。教育にも、十分に活かせる内容。良書
0投稿日: 2015.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログとても参考になりました。 長い時間を超えて、一流の「ビジョナリーカンパニー」となるには何が必要なのかを、「ビジョナリーカンパニー」でない企業との比較の中から分析していく。 結論としては、いわれてみれば当たり前、な気もするのですが、その結論を莫大な事例や資料から帰納的に導いているので説得力は高い。 一番大切なことは、理念を掲げて、それをしっかりと実行することにあるのですね。 日系企業も「ビジョナリーカンパニー」に含まれています。国の風土が違えば、異なるといったものではなく、かなり普遍的な真理を追求しているものだと思います。
0投稿日: 2015.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログどのような不安をもたらす仕組みをつくって自己満足に陥らないようにし、内部から変化と改善を生み出すとともに基本理念を維持していくことができるのか。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1/12 業界トップ、時の試練に耐え、尊敬される企業を類似する企業と創業から比較し、教訓を抽出した。 下記がポイント •時を告げるのでなく時計をつくる •ANDの才能 •基本理念を維持し、進歩を促す •一貫性 この手段として、下記提唱 •BHAG •目的のもとでの進化 •不断の努力 •生え抜きの経営者 •理念への熱狂と同質性の追求 ◼︎事実 3Mの15%ルール P&Gの社内競合 自己を律することがなければ、人格は形成されない 成功には独りよがりと自己満足に陥ることへの本能的とも言える嫌悪感が必要 ものごとをシンプルに考えるには極端な仮定が必要 ◼︎背景 リチャードドーキンス ブラインドウォッチメーカー
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログマネジメントを学ぶ上では外すことのできない一冊だと思います。スタートアップをする人にとってもどのような違いがその後の歩みに表れてくるのかを理解することができる一冊です。
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ長年に渡り読まれている本であり、とても為になることが書いてある。データに基づいた分析でありそれなりに説得力もある。 『覚えておくこと』 ・時を告げるのではなく、時計を作る 自分が時を告げるだけじゃなくて、自分がいなくなっても時を告げるものをつくろうぜ。 ・基本理念を維持し、進歩を促す 常に変化していける様な仕組みを作ろう。だけど、基本理念だけは百年たっても変えない、変わらないものにすること。 ・「ANDの才能」 AとBどちらかでなく、両方いいとこ取りできる方法を考えろ。 ・一貫性の追求 神は細部に宿る。全てにおいて一貫性を保つこと。
0投稿日: 2014.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会に影響を与え続ける会社を創るという事につきる一冊である。そして、進歩への継続を持ち続けるという気持ちが大切であるという印象を受けた。
0投稿日: 2014.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ医薬品や最先端化学テクノロジー分野における世界有数の企業であるメルクと、国際的大手たばこ会社であるフィリップ・モリス。事業内容として見た場合には対照的に見える2社ですが、著者によれば両社とも「ビジョナリーカンパニー」であるとのことです。 2社とも決してぶれることのない確固たる基本理念を持ちながら事業を進化させているというのがその理由。 このように「時代を超えて偉大さを維持し続ける企業の共通点」を導き出したのがビジョナリーカンパニーの第1巻「BTL(Built To Last」です。 ビジョナリーカンパニーの選定基準は以下の通り。 業界で卓越した(金メダル級の)企業であること/見識ある経営者や企業幹部たちの間で広く尊敬されていること/社会に消えることのない足跡を残していること/CEOが世代交代していること/当初の主力製品やサービスのライフサイクルを超えて繁栄していること このような選定基準によって選定されたビジョナリーカンパニーと、比較対象となる企業(ビジョナリーカンパニーに次ぐ優良企業であり、銀メダルや銅メダル級の企業)とでは何が違うのかを明らかにしていくことにより、ビジョナリーカンパニーの共通点(条件)が浮かび上がるわけです。 膨大なデータを何年にもわたって調査研究した結果、これまで定説とされていた「すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である」「ビジョナリーカンパニーには、ビジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である」などの“12の神話”が見事に覆されました(特にここに書いた“神話”は、偉大な企業に必要不可欠な条件だと自分も思っていたので、特に印象深かった)。 さらに、調査により導かれたビジョナリーカンパニーの多くに見られる共通点について、第2章以降でより詳細な調査結果が述べられていきます。 詳述は避けますが、一番大切なことは事業の内容云々よりもその根本にある基本理念であり、その理念を貫き通すこと。 企業が社会になくてはならない存在となり、そして満足することなく努力を重ね、社運をかけた大胆な目標(BHAG)を掲げながら成長し続けているということです。 まとめとして、 ・時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ ・「ANDの才能」を重視しよう ・基本理念を維持し、進歩を促す ・一貫性を重視しよう 以上の4つが、読者に最低覚えておいてほしいというBTLの最も重要な概念であるとのこと。 ビジョナリーレベルの企業にまでなる必要はない、自分は起業までは考えていないという人もぜひ読んでみるべき本だと思います。「人の生き方」にも通じる多くの示唆が含まれていますので。
0投稿日: 2014.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーな自分を目指そう。 前半、翻訳モノ独特のくどい言い回しに疲れたけど、実例を議論するようになってだんだん読めるようになって来ました。 中盤なう。 10/22読了。 基本理念の維持と進歩を両方実現すること。 決して満足せず、常に不安感にかられること。 前者は自分もよく言われる。 極論ばかりを論じたり考えたりして悲観的になるな、バランスを取れるようになれ、と。 満足して安心するために生きてるのではなく、常に上を目指し、成長するために生きてること。 忘れないようにしよう。 さて、次はシリーズ2作目を某先輩の勧めで原文で読みます! さて、何ページで挫折するか…! 頑張ろう。 それにしても20年も前の書籍なのね…不朽。
0投稿日: 2014.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ評価の高い本ではあるのだが、正直期待外れ。ここで提示されているビジョナリーカンパニーの条件は、日本企業であればそれほど珍しいものではない。では日本企業はビジョナリーカンパニーだらけなのかといえば、そうとは言えないだろう。 金メダリストと銀メダリストの比較から考察したとは言え、ここでの”金”の条件は本当に普遍的なものといえるのか?つまり”金”の条件を満たしているのに金メダルを取れない会社はないのか?がこの調査方法では判断できない。要するに必要十分条件であるかどうかが示されていない。もしそうでないのなら法則や原則としての価値はほとんどない。 ビジョナリーカンパニーの条件(必要条件) ①基本理念を会社の末端まで狂信的なほど徹底させる仕組みを持つ ②社内生え抜きの経営者を据え、リーダーの継承プログラムがある ③多くのトライアルを試み、うまく行ったものだけを残す ④社運をかけた大胆な目標(BHAG)を掲げる
0投稿日: 2014.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ存続する優れた企業はどうやって作られたのかという視点で調査しまとめた本。中長期的な組織をつくるにはどうすればいいのかについてのヒントが満載。企業理念は拠り所となる点でとても重要になる。
0投稿日: 2014.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
業界で卓越していて長く続いているビジョナリーカンパニーが、優良企業であるがそこそこの比較対象企業と比べて何が違うのかに関するリサーチである。以下の結論は企業が人で成り立っていることを考えれば確かに当然のことと感じた。 ・時を告げる(カリスマ的指導者による経営)のではなく、時計(優秀な経営者を輩出し続けられる卓越した組織)を作る ・ORではなくANDの才能を重視する(両極端に見える選択肢を同時に追求する能力) ・基本理念を維持し進歩を促す ・一貫性を追求する 基本理念を徹底しつつ、進歩していくことは非常に難しいことである。だからこそビジョナリーカンパニーなのであろう。「カルト的」とも表現されていたが、相当クセの強い、濃い組織である点は少し気持ちが悪い感じがするが、組織が長続きするということは実際にそういうことなのかもしれない。 最近読み返したポーターの戦略論(事業戦略)では収益性(ROI)が最重要、戦略=トレードオフとクリアに断言していて、対極的な印象を受けた。ここでは戦略というよりももっと広い範囲で組織という観点からの継続性を考えていることからくる視点の違いであろう。ドラッカーのイノベーション・起業家精神に関する著作も最近読んだが、こちらとは非常に似通っていた。ビジョナリーカンパニーは予想外の出来事を無視せず、事業軸などにこだわらず、大量のものを試して積極的に進歩の機会に結び付けていく(基本理念に沿っている限り)
0投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーに関する一冊。 同業他社の間で広く尊敬を集め、 大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業。 ビジョナリーカンパニーには、 カリスマは必要ない。 基本理念を維持して、進歩を促す素地ができていればいい。 すなわち、 (1)時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ。(自分が引退しても、衰退しないような組織・仕組みを作る。) (2)「ANDの才能」を重視しよう。 (揺るぎない基本理念と前進・変化など相対するものだと思われがちでも、両方を重視するやり方を追求すべき。) (3)基本理念を維持し、進歩を促す。 (4)一貫性を追求しよう。 自分たちの組織もビジョナリーカンパニーになれるよう、精一杯尽力する。
0投稿日: 2014.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社や(社員が業務上で)今差し迫っている事柄に対しての判断基準として、自信をもって企業理念を基準に据えられるか? 判断基準に据えられるほど全員が企業理念を信頼できるような仕組みが構築されているか? 、というのがポイントて見た。 以前、大企業は仕組みが優秀だからそこそこの人間しかいなくても持つが、中小企業は仕組みがしょぼい分優れた人材が必要、なんて文に膝を打ったが、なんか通じるものがある気がする。
0投稿日: 2014.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ(1)アイデアでも、カリスマ的指導者でもなく、理念。(2)理念の内容より、いかにそれを深く信じているか。(3)理念以外は何が変わってもよい。(4)すべての要素に、理念に通ずる一貫性がある。(5)進歩を促す仕組み。
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログソニー、P&G、メルク、HPなどの優良企業たる所以をなんとなく理解できた。OR思考ではなく、AND思考であり、時代を超えた大胆な目標BHAGが必要であることを学んだ。また、これらの優良企業は、カリスマ的経営者ではなく、基本理念をしっかり伝え続けられる経営者であった。
0投稿日: 2014.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界で有数の企業でもさらに区分して明確な「ビジョン」をもった企業を「ビジョナリーカンパニー」と定義して、他の会社との差を比較していく内容であるが、私には、少々極端な例が多くはないか?と思わされた。 確かにしっかりとしたビジョンをもち、企業の目標管理が完璧であれば成長は間違いないが、従業員へどこまで要求していくかは難しい。 従業員も当然会社が成長していくことが望ましいが、全てを企業に捧げて生活することが正とは思えない部分もある。 でも、目標管理が適当であっていいわけではなく、その点は勉強になる本であった。 両極端すぎるのが気になる点ではあった。
0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログPドラッカーの後継者といわれる著者の代表作。 未来志向・先見性のある企業を同業他社と比較しながら 特徴をまとめ、原理原則をつむぎだしている内容。 「時を告げる」のではなく、「時計を作る」など 企業風土・DNAというものを、永年にわたって醸成できた企業が成功する可能性が高い。 一人のカリスマが企業を繁栄させるのではないという考え方が特徴的と感じた。
0投稿日: 2014.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ猛烈なスピードで時が流れ、価値観が多様化し、不安や閉塞感に覆われた時代だからこそ、この本に書かれた「ビジョナリーカンパニー」の法則はとても輝いてみえる。 私は経営者ではないが、まずは自分のチームからはじめてみよう。 *** ・時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 ・「ANDの才能」を重視しよう。 ・基本理念を維持し、進歩を促す。 ・一貫性を追求しよう。 ***
0投稿日: 2014.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー=先見性、未来志向。 長く輝きを持ち続ける企業、 それはどんな企業で、何が違うのか。 一流と言われる企業は数ある中で、 著者の見出したビジョナリカンパニーたち。 18のビジョナリー企業と、比較対象の企業、 その違いを分析し、ビジョナリカンパニーに備わる 幾つかの共通点。それらを企業の歴史に準えます。 読み堪えはありますが、読んでおいて損はない1冊。 特に理念の大切さを改めて実感しました。 企業価値とは?ビジョナリーカンパニーとは? 第1章 最高のなかの最高 第2章 時を告げるのではなく、時計をつくる 第3章 利益を超えて 第4章 基本理念を維持し、進捗を促す 第5章 社運を賭けた大胆な目標 第6章 カルトのような文化 第7章 大量のものを試して、うまくいったものを残す 第8章 生え抜きの経営陣 第9章 決して満足しない 第10章 はじまりの終わり
0投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしいの一言に尽きる。緻密な調査の上に、ビジョナリーカンパニーがなぜビジョナリーなのかわかりやすく書かれている。理念は大切にしなければならない。
0投稿日: 2014.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。1994年の本だが、現在でも十分説得力のある内容にあらためて驚きます。今の日系企業はビジョンがあるのか、疑問です。
0投稿日: 2014.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ時を告げるのではなく、時計をつくること 「ORの抑圧」をはねのけ、「ANDの才能」を活かす 「理念」の重要性 誠実さ 一つ一つは当たり前で、シンプルなことだが、これを永続的に継続していくことが相当難しいことなのだろう。 欲深いばかりに。
0投稿日: 2014.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーとそうではない同業他社を比較することで、ビジョナリーカンパニーを作り上げるのに必要な要素を抽出し、起業家や経営者へのアドバイスを行う。ビジョナリーカンパニーと、そうでない企業の対比において、前者の方がより存在価値が高いという、筆者の考え方が貫かれている。ビジョナリーカンパニーと比較対象の企業を対比させるために、議論がややステレオタイプ的だと感じるところもあったが、各章には時間をかけて行った取材活動から得られた深い洞察が含まれている。
0投稿日: 2014.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ当たり前だけど、突き詰めて出来てないこと、たくさんある。大事にしなくちゃいけないのは何なのか、よく考えないと。個人でも企業でもやるべきことは同じだよね。続刊も読みたい。
0投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功した企業を分析した結果として、時代を超えて存在し続ける企業は、良き組織を作ることがポイントであり、基本理念を持つことが重要であることを説いている。社員のすばらしいエネルギーをどれだけ引き出せる組織をつくれるか、そして永続さ続けられるか。基本理念を維持し、進歩を促す仕組みをつくり育て。選択におけるANDの才能、時代に左右されない一貫性の追求が要素として必要であることを見つけたことが記されている。
0投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログある業界で偉大な業績を残し続けている会社と、そうでない会社を比較して、偉大な業績を残し続けることができる要因を蒸留してみたら、、という趣旨の本。 単なる方法論としてではなく、教養として受け取り、昇華する必要があると感じた。読むのも大変だし、持ち運びにくいしけれど、迷ったり悩んだりした時に読み返したい本。
0投稿日: 2014.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーとそれ以外の企業の比較で、なぜ前者がここまで長く存続できてこれたか、企業の強みや目的が描かれていた。これからの時代にも通じる部分が多くあるし、また、益々変化する時代においてもこのビジョナリーカンパニーは継続していくのか注目だ。
0投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ偉大な企業と優良企業の違いは何かー ただビジョンが大事だよ、っていう本ではない。要は、一貫性。 こういう会社で働きたいし、働く会社はこういう会社にしたい。
0投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な話を読むのが大変で、読むのにかなり苦労しました。 研究、分析の質も凄いが、量も凄い。 良書は良書だが、もう少し簡潔に書いてほしい所。
0投稿日: 2013.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ普遍的な信念の確立とその徹底。で、それ以外は(もしくはその信念を元に)変化・進化させ続けるシステム構築を推奨してた。ちょっとびっくりしたのは、そういう組織はカルトっぽく、部外者には居心地が悪いらしいこと。あと、全般に例示が多くて冗長やった。 「カルト的」というのは、むしろ恋心から来る献身に近いと思う。「基本理念」は法人に与えられるキャラクターと捉えれば理解しやすいし、突き詰めると企業を二次元美少女(少年)化すべきだし、M&Aとかは18禁で大興奮。
0投稿日: 2013.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり読み終わるまで時間がかかってしまいましたが アメリカでも日本的な経営をしているところが強いことが印象的です
0投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下の四点をしっかり肝に銘じておきたい。 ・時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ ・「AND の才能」を重視しよう ・基本理念を維持し、進歩を促す ・一貫性を追求しよう
1投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログいまさらながらの95年出版だけれども一読はしとくべき。 すっごい企業群とそうでもない企業群を比較してみたらどうなるかという話。 「ビジョナリーな企業」として本書にでてくるのは3Mやアメリカン・エキスプレス、ボーイング、シティコープ、フォード、GM、HP、IBM、J&J、マリオット、メルク、モトローラ、ノードストローム、P&G、フィリップ・モリス、ソニー、ウォルマート、ウォルト・ディズニーの18社。 今からみるとビジョナリーかと疑問に思う企業もあるが、抽出された企業の特徴は普遍的だと思う。 基本理念以外はタブーなしに変化・改善させ、妄信的な社員を作り出し継続的な経営者の育成を行っていく。果敢に挑戦していく。カリスマ経営者はあまり良いことがないらしい。 疑問に思ったのは3Mで今現在では革新的ではなくなった紙やすりを作り、売っている人のモチベーションはどう維持しているのだろうと。挑戦する人、生み出す人とは別に既存ラインを維持する人はどう評価されているのかな。
0投稿日: 2013.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログすばらしいアイデアを持っていたり、すばらしいビジョンを持ったカリスマ的指導者であるのは、「時を告げること」であり、ひとりの指導者の時代をはるかに超えて、いくつもの商品のライフサイクルを通じて繁栄し続ける会社を築くのは、「時計をつくること」である。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時を作るのでなく時計を作る。確かにカリスマのアイデアは会社を豊かにする。しかし、そのカリスマが死んだら企業は衰退をたどるであろう。これを時としている。時計というのは企業の風土やシステムのことを言う。時計を作るのがビジョナリ―カンパニーにとって必要である。 利益を超えて 企業は勿論利益を得なければならない組織である。しかしビジョナリーカンパニーは利益以上のものを得ている。それは従業員、顧客、冒険心、製品などものは異なるがポリシーとしているものがある。どれかを手に入れるためにどれかを捨てるのではなくてどちらも手に入れている。ORではなくANDの精神がある。 時計を作ること=基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを作ること ・社運を賭けた大胆な目標・カルトのような文化・大量のものを試して、うまくいったものを残す・生え抜きの経営陣・決して満足しない。 カルトのような文化はその企業で働くにはいいが他の企業では通用しない。PandGは郷に入っては郷に従えという風土はなく、PandGという郷に全社員を入れさせる。そして個人崇拝のカルトは作ってはいけない。 一貫性を追求すること。一貫性を追求しなければ従業員、顧客共に離れていくことになる。 ビジョナリ―カンパニーになるために一番初めにするべきことは基本理念を制定することである。内側から見付け出すものである。
0投稿日: 2013.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスタンフォード大学教授の経歴を持つ方がビジョナリーカンパニーという分類を作った。 日本人でわかる主な企業で、ソニーがある。 比較企業を作り、比較するのだが、CEOがカリスマだからとか、大企業だからとかでは比較はされていない。確かに、後になってカリスマ社長も出てくるが、それは、企業の作られ方がいいからであって、けして、社長が良いからではない。 決めたことを一貫してやり通すということがどれだけ大事か気づかされる本。
0投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニー(先見的な企業)とその他優良企業との対比から、各業界での1位と2位を分かつエッセンスを抽出しようと試みた経営書。 6年という時間を注ぎ込み、先入観を極力排除し、様々な種類の膨大な量のデータを調べ上げることによって答えを導き出すというアプローチは、人為的なビッグデータ解析そのもののような感じがする。 得られた知見にはそれほどインパクトを感じないが、説得力があり、ビジョナリーカンパニーに発展させるには近道がないことを思い知らされる。厳しく自己を律し続ける、その仕組みを作るということである。 経営書ではあるが、専門用語が多用されるわけでもなく、表現が柔らかく具体例が多いため、読みやすい。
0投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログだいぶ昔のメモが出てきたので、こちらにお引越し。 ■第一章 最高のなかの最高 p.5 調査対象企業 ビジョナリー・カンパニー /比較対象企業 3M/ノートン アメリカン・エキスプレス/ウェルズ・ファーゴ ボーイング/マクダネル・ダグラス シティコープ/チェース・マンハッタン フォード/GM GE/ウエスチングハウス ヒューレット・パッカード/テキサス・インスツルメンツ IBM/バローズ ジョンソン&ジョンソン/ブリストル・マイヤーズ マリオット/ハワード・ジョンソン メルク/ファイザー モトローラ/ゼニス ノードストローム/メリビル プロクター&ギャンブル/コルゲート フィリップ・モリス/R・J・レイノルズ ソニー/ケンウッド ウォルマート/エームズ ウォルト・ディズニー/コロンビア p.7 「ビジョナリー・カンパニーのすべてが、過去のどこかの時点で、逆風にぶつかったり、過ちを犯したことがあり、…しかし、…ビジョナリー・カンパニーには、ずば抜けた回復力がある」 p.7 「ビジョナリー・カンパニーは、長期的に優れた投資収益を生み出しているだけではなく、わたしたちの社会になくてはならない存在になっている」 ●十二の崩れた神話 p.11~p.16 「神話一 すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である」 「神話二 ビジョナリー・カンパニーには、ビジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である」 「神話三 とくに成功している企業は、利益の追求を最大の目的としている」 「神話四 ビジョナリー・カンパニーには、共通した「正しい」基本的価値観がある」 「神話五 変わらない点は、変わり続けることだけである」 「神話六 優良企業は、危険を冒さない。」 「神話七 ビジョナリー・カンパニーは、だれにとってもすばらしい職場である」 「神話八 大きく成功している企業は、綿密で複雑な戦略を立てて、最善の動きをとる」 「神話九 根本的な変化を促すには、社外からCEOを迎えるべきだ」 「神話十 もっとも成功している企業は、競争に勝つことを第一に考えている」 「神話十一 二つの相反することは、同時に獲得することはできない」 「神話十二 ビジョナリー・カンパニーになるのは主に、経営者が先験的な発言をしているからだ」 ●調査プロジェクト p.18~p.19 「調査プロジェクトには、…二つの大きな目標があった。 一 ビジョナリー・カンパニーに共通する(そして、ほかの会社から際立っている)特徴やダイナミクスを見つけ、これらの結果をもとに、実践の場で役立つ概念の枠組みをつくる。 二 これらの結果や概念を効果的に伝え、それによって、経営手法に影響を与えたり、ビジョナリー・カンパニーを設立し、築き、維持する力になりたいと考えている人々の役に立つようにする」 ●データはあくまでデータ ■第二章 時を告げるのではなく、時計を作る p.37 「すばらしいアイデアを持っていたり、すばらしいビジョンを持ったカリスマ的指導者であるのは、「時を告げること」であり、ひとりの指導者の時代をはるかに超えて、いくつもの商品のライフサイクルを通じて繁栄し続ける会社を築くのは、「時計をつくること」である。」 「その最高傑作は、会社そのものであり、その性格である。」 p.38 「ビジョナリー・カンパニーをつくり、築くには、すばらしいアイデアも、カリスマ的指導者もまったく必要ないことがわかった」 ●「すばらしいアイデア」の神話 ●「すばらしいアイデア」を待つのは、悪いアイデアかもしれない p.45 「「すばらしいアイデア」を出発点としているものの比率は、比較対立企業より、ビジョナリー・カンパニーの方がはるかに低かった。」 ●企業そのものが究極の作品である p.46 「会社を製品の手段として見るのではなく、製品を会社の手段として見るように発想を転換することになった」 p.47 「アイデアはあきらめたり、変えたり、発展させることはあるが…会社は絶対にあきらめない」 p.51 「ビジョナリー・カンパニーが、すばらしい製品やサービスを次々に生み出しているのは、こうした会社が組織として卓越しているからにほかならず、すばらしい製品やサービスを生み出しているからすばらしい組織になったのではないと思われる。」 ●偉大なカリスマ的指導者の神話 p.56 「ビジョナリー・カンパニーで優秀な経営者が輩出し、継続性が保たれているのは、こうした企業が卓越した組織であるからであって、代々の経営者が優秀だから、卓越した企業になったのではないのだろう。」 ●建築家のような方法―時計をつくる p.57 「ビジョナリー・カンパニーの草創期の重要な経営者は、指導者としてのスタイルに関係なく、比較対象企業の経営者より組織志向が強かった。」 ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ p.69 「会社を築き、経営する仕事に携わっているのであれば、製品についてすばらしいビジョンを考えたり、カリスマ的指導者になろうと考える時間を減らし、組織についてのビジョンを考え、ビジョナリー・カンパニーとしての性格を築こうと考える時間を増やすべきである。」 p.71 「ビジョナリー・カンパニーを築くために必要な点の大部分は学ぶことができるものである」 「基本的な点を学べば、自分たちの会社をビジョナリー・カンパニーにする困難な作業に、だれでも、いますぐ、とりかかることができる。」 ■挿話 「ORの圧力」をはねのけ、「ANDの才能」を活かす p.74 「短期的に大きな成果をあげ、かつ、長期的にも大きな成果をあげようとする。ビジョナリー・カンパニーは、理想主義と収益性のバランスをとろうとしているわけではない。高い理想を掲げ、かつ、高い収益性を追求する。」 ■第三章 利益を超えて ●現実的な理想主義 -「ORの抑圧」からの解放 p.78 「…日本のビジネス関係者に、第二次世界大戦後、日本にストレプトマイシンを持ち込んだのはメルクで、その結果、蔓延していた結核がなくなったと言われた。これは事実だ。当社はこれで利益をあげていない。しかし、今日、メルクが日本でアメリカ系製薬会社の最大手であるのは、偶然ではない。長い目で見ると〔こうした行為の〕結果は、必ずしもはっきりとは現れないが、なんらかの形で必ず報いられると思っている。」 p.84 「「わが社のポリし0は、消費者がどんな製品を望んでいるかを調査して、それに合わせて製品を作るのではなく、新しい製品をつくることによって彼らをリードすることにある。…だから我々は、市場調査などあまり労力を費やさず、新しい製品とその用途についてのあらゆる可能性を検討し、消費者とのコミュニケーションを通してそのことを教え、市場を開拓していくことを考えている」(盛田昭夫他著『Made in Japan』)」 ●基本理念―利益の神話を吹き飛ばす p.90 「ほぼすべてのビジョナリー・カンパニーで、基本理念が文書になっているうえ、企業の動きを決めるものとして、大きな力を持っている。」 p.91 「ビジョナリー・カンパニーは、業種に関係なく、理念と利益を同時に追求する「ANDの才能」を比較対象企業よりも大切にしている。」 p.92 「短いあいさつに続いて、パッカードは、こう話し始めた。 最初に、なぜ会社が存在しているかについて話したい。…カネ設けというのは、会社が存在していることの結果としては重要であるが、われわれはもっと深く考えて、われわれが存在している真の理由を見つけ出さなければならない。この点を追求していくと、人々が集まり、われわれが会社と呼ぶ組織として存在しているのは、人々が集まれば、個人ではできないことができるようになるからだ、つまり、社会に貢献できるようになるからだという結論に必ず行き着く。」 p.103 「ビジョナリー・カンパニーは、価値観を守るか、それとも、現実主義に徹するかの選択を迫られているとは考えない。現実的な解決を見つけ、基本的価値観を貫くのが課題だと考える。」 ●「正しい」理念はあるのか p.111 「ビジョナリー・カンパニーの多くが、社会貢献、誠実さ、従業員の操縦、顧客へのサービス、卓越した想像力、主導的な地位、地域社会への責任などを理念として掲げているが、ビジョナリー・カンパニー全社に共通している項目はひとつもない。」 p.115 「一言でいえば、ビジョナリー・カンパニーの理念に不可欠な要素はない。わたしたちの調査結果によれば、理念が本物であり、企業がどこまで理念を貫き通しているかの方が、理念の内容よりも重要である。」 p.116 「人々はある考え方を公言するようになると、それまではそうした考えを持っていなくても、その考え方に従って行動する傾向が際立って強くなる。つまり、基本理念を公言すること自体で、その理念に従って一貫した行動をとる傾向が強まることになる。」 ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ p.119 「基本理念=基本的価値観+目的 基本的価値観=組織にとって不可欠で不変の主義。いくつかの一般的な指導原理からなり、文化や経営手法と行動してはならず、利益の追求や目先の事情のために曲げてはならない。 目的=単なるカネ儲けを超えた会社の根本的な存在理由。地平線の上に円年に輝き続ける道しるべとなる星であり、ここの目標や事業戦略と混同してはならない。 」 p.120 「ほとんどの場合、基本的価値観は鋭く短い言葉に凝縮され、大切な指針になっている。…ウォルマートのいちばん重要な価値観の本質をこう表現している。「顧客を他の何よりも優先させる…顧客に奉仕しなかったり、顧客に奉仕する仲間を支えないのなら、その人間は必要ない。」ジョン・ヤングはHPウエイの単純さをこう表現している。「HPウエイの基本は個人を尊重し、配慮することだ。つまり、『人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい』。すべてはこれに尽きる。」」 p.121 「ビジョナリー・カンパニーが掲げる基本的価値観はごくわずかで、たいていは三つから六つである。基本的価値観が六つ以上あるビジョナリー・カンパニーはひとつもなく、ほとんどが五つ以下だった。」 p.122 「基本理念は企業の内部にある要素であり、外部の環境に左右されるものではない」 p.124 「自分たちのなかにあるもの、それぞれが肝に銘じ、骨の髄までしみ込んでいる者を表現しただけだ。…問題は、何を信じていたのかではなく、どこまで深く信じていたか、そして、組織がどこまでそれを貫き通したかである。」 p.124 「目的は、まったく独自のものである必要はない。」 p.127 「目的を見つけ出すには、「この会社を閉鎖し、清算し、資産を売却することもできるのに、そうしないのはなぜなのか」と自問し、現在にも、百年後にも通用する答えを探すのが効果的だ。」 p.128 「この章の内容は、組織のどのレベルの管理職にもあてはまる。」 p.128 「企業が全体として理念を持っていない場合でも、個々のレベルで理念を文書化できる。」 p.129 「ビジョナリー・カンパニーのすべてが、設立当初から基本理念をしっかりした文書にしていたわけではない。」 p.129 「しかし、早ければ早いほどよい。…いますぐ基本理念を書きあげるべきだ。」 ■第四章 基本理念を維持し、進歩を促す p.133 「トーマス・J・ワトソン・ジュニアも小冊子『事業とその信念』で強く警告している。 … 「企業として前進しながら〔その基礎となる〕信念以外の組織のすべてを変える覚悟で臨まなければならない。…組織にとっての聖域は、その基礎となる経営理念だけだと考えるべきである。」」 ●進歩への意欲 p.134 「基本理念と、基本理念ではない慣行を混同すると、問題が起こる。…ビジョナリー・カンパニーは基本理念を大事に維持し、守るが、基本理念を表す具体的な行動は、いつでも変更し、発展させなければならない。」 p.135 「基本理念を維持しながら、進歩を促す」 p.138 「新しいアイデアを「不可能だ」という理由でつぶしてはならない。われわれの仕事は、研究と実験を永遠に続け、研究の成果をできるかぎり早く製品に活かし、航空と航空機の新技術が当社と無関係に開発されていくことが決してないようにすることである。」 ●基本理念を維持し、進歩を促す p.141 「基本理念を明確にし、揺るぎないものにすることで、基本理念以外のすべてを変化させ、発展させるのが容易になる。進歩への意欲があるから、基本理念を維持できる。」 p.141 「ビジョナリー・カンパニーの場合は、それを組織にしっかりと根付かせ、組織の仕組みの中に組み入れている。…基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みも整えている。」 p.142 「ウォルト・ディズニー…ディズニー大学 ヒューレット・パッカード…従業員の評価と昇進の際の基準 モトローラ…シックスシグマ品質基準 3M…15%を自分が選んだプロジェクトにあてることを認め、社内にベンチャー・キャピタル・ファンドを設定 具体的であり、現実的であり、焦点がはっきりしており、強固である。 」 ●CEO、経営幹部、起業家のためのキー・コンセプト p.144 「基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整えることの大切さだ。」 ■第五章 社運を賭けた大胆な目標 ●BHAG‐進歩を促す強力な仕組み p.154 「ビジョナリー・カンパニーは進歩を促す強力な仕組みとして、ときとして大胆な目標を掲げる。」 p.155~p.156 「明確で説得力のある目標 …BHAGは人々の意欲を引き出す。人々の心に訴え、心を動かす。具体的で、わくわくさせられ、焦点が絞られている。だれでもすぐに理解でき、くどくど説明する必要はない。」 p.157 「前進をもたらしているか。勢いをつくり出しているか。従業員はやる気に安っているか。刺激的で、興奮させられる大胆な冒険だと見られているか。従業員は想像力を駆使し、エネルギーを注ぎ込むつもりになっているか」 p.161 「BHAGが組織にとって有益なのは、それが達成されていない間だけである」 p.165 「BHAGと呼べるのは、その目標を達成する決意がきわめて固い場合だけである。」 ●重要なのは指導者ではなく、目標‐時を告げるのではなく、時計を作る ●CEO、経営幹部、起業家への指針 p.185 「BHAGはきわめて明確で説得力があり、説明する必要もないほどでなければならない。 … BHAGは気楽に達成できるようなものであってはならない。 … BHAGはきわめて大胆で、それ自体が興奮を呼び起こすものでなければならず… … 次のBHAGを準備しておくべきだ。 … BHAGは会社の基本理念に沿ったものでなければならない。 」 p.189 「不利な条件を克服し、大きな目標に挑戦すれば、とくに、その目標が基本理念に基づくものであれば、社員は特別で、並はずれたエリート集団の一員だという感覚を持てるようになる。」 ■第六章 カルトのような文化 ●「病原菌か何かのように追い払われる」 p.203 「ビジョナリーカンパニーは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向がある。」 p.204 「カルトと共通した点が以下の4つあることがわかった。 ・理念への熱狂 ・教化への努力 ・同質性の追求 ・エリート主義」 ●IBMが偉大な企業になった過程 ●ウォルト・ディズニーの魔法 ●プロクター&ギャンブル―会社に浸りきる ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ p.228 「宗教団体や社会運動団体では、カリスマ的な指導者が中心になって、いわゆる個人崇拝が強まることが少なくないが、ビジョナリー・カンパニーでは、イデオロギーに関してカルト的になっている。」 p.229 「・社内に「大学」や研修センターを設ける。 ・社内から人材を登用する ・「英雄的な行動」や模範になる人物の神話を、絶えず吹き込む ・賞、コンテスト、表彰によって、理念に基づいてとくに努力した従業員に報いる・祝賀行事によって成功を祝い、帰属意識とエリート意識を高める。 ・会社の価値観、伝統、特別な集団に属しているという見方を発言や文書で絶えず強調する。 」 ●イデオロギーの管理と業務上の自主性 p.234 「基本理念を中心に、カルトのような同質性を求めることによって、企業は従業員に実験、変化、適応を促すことができ、そして何よりも、行動を促すことができるのである。」 ■第七章 大量のものを試して、うまくいったものを残す ●進化する種としての企業 p.244 「ビジョナリー・カンパニーは比較対象企業に比べて、BHAG(社運を賭けた大胆な目標)に続く第二の種類の進歩として、進化による進歩をはるかに積極的に促している」 ●3M‐ミネソタの突然変異製造機がいかにしてノートンをつきはなしたか p.253 「ヒューレット・パッカードのビル・ヒューレットにインタビューしたとき、わたしたちは特に尊敬し、手本にしている企業があるかと質問した。一瞬のためらいもなく答えが返ってきた。「3Mだ。これは断言できる。3Mが次にどう動くのか、だれにもわからない。本当にすごいのは、3M自身、次にどう動くのかが、たぶんわかっていないことだ。しかし、次の動きを正確に予想することができなくても、同社が今後も成功を続けて行くことは、確実だと言える。」」 ●3Mでの「枝分かれと剪定」 p.260 「市場規模だけを基準にして洗濯するわけではないことだ。「少量生産し、少量売る」、「小さな一歩を大切にしよう」という評下に示されているように、大型商品が小さな一歩から生まれることが少なくない点を3Mはよく理解している。しかし、小さな一歩のうちどれが大型商品につながるのかは、事前には分からない。そこで3Mは小さなことをいくつも試し、うまくいったものを残し、うまくいかなかったものを捨てている。」 p.268 「3Mが機会をすばやくおらえて、耐水サンドペーパーとスコッチ・テープに進出したのに対して、ノートンは既存の商品群から外れる新しい機会の追求を奨励しないことを会社の方針として明文化していた。 … 何を研究するのも自由だったが、円盤状で真ん中に穴があいているものであるかぎり、という条件がついていた。」 ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ p.273~p.276 「試してみよう。なるべく早く」 「誤りは必ずあることを認める」 「小さな一歩を踏み出す」 「社員に必要なだけの自由を与えよう」 「重要なのは仕組みである」 ●「機軸から離れない」ではなく、「基本理念から離れない」 ■第八章 生え抜きの経営陣 ●社内の人材を登用し、基本理念を維持する ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ p.309 「社外から経営者を招いていては、先見性が際立つ企業になることも、その座を守ることも、極めて難しいと言える。…カギになるのは、健全な変化と前進をもたらしながら、基本理念を維持するきわめて有能な生え抜きの人材を育成し、昇進させることなのだ。」 ■第九章 決して満足しない p.315 「ビジョナリー・カンパニーが飛び抜けた地位を獲得しているのは、将来を見通す力が優れているからでも、成功のための特別な「秘密」があるからでもなく、主に自分自身に対する要求が極めて高いという単純な事実のためなのである。」 ●現状を不十分と感じるようにする仕組み p.317 「ビジョナリー・カンパニーは、不安感をつくり出し(言いかえれば、自己満足に陥らないようにし)、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、カイゼンするよう促す強力な仕組みを設けている。」 p.318 「P&Gのブランド同士が直接に競争するようにする…。P&Gの最高のもの同士を戦わせればいいではないか。市場に十分な競争がないのであれば、内部競争する仕組みをつくり、どのブランドも栄光に安住するわけにはいかないようにすればいいではないか。」 p.319 「メルクは1950年代に、差別化が難しくなり、利益率が下がった製品のシェアを意識的に落としていき、業績をあげ、成長していくには、革新的な新薬を開発せざるをえなくする戦略を採用した。」 p.319 「ゼネラル・エレクトリック(GE)は、社内で不安感を生みだす仕組みとして、「ワークアウト」と呼ばれる制度を設けている。従業員がグループごとに集会を開き、改善の提案を話し合って、具体的な提案をまとめる。」 p.320 「ボーイングは…何人かの管理職に、競合相手の立場に立って、ボーイングを壊滅させる戦略を立案する任務を与える。競争相手が利用できるボーイングの弱点はどこにあるのか。」 ●将来のために投資する‐そして短期的にも、好業績をあげる ●マリオット対ハワード・ジョンソン―アメリカの偉大なチェーンの没落 ●CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ ●黒帯の寓話 ■第十章 はじまりの終わり p.343 「経営理念などを文書にしただけで、必ずビジョナリー・カンパニーになれるわけではない…ビジョナリー・カンパニーの真髄は、基本理念と進歩への意欲を、組織のすみずみにまで浸透させていることにある。」 ●一貫性の力‐フォード、メルク、ヒューレット・パッカード p.352 「わたしはメルクに入社する前に、アメリカのある大手企業に勤めていた。この二つの企業を比べると、一方が美辞麗句を並べているにすぎないのに対し、もう一方がしっかりした現実をつくっている点が基本的な違いになっている。前の会社でも、価値観、ビジョンなどを喧伝していたが、言葉と現実の間に大きな落差が合った。メルクではそういう落差はない。」 p.354 「HPには労働組合が組織されていない。 …労働組合を組織しようという動きは何度も会ったが…寒い日に組合を組織しようとピケをはっていると、経営陣が休憩時間に温かいオフィス内でコーヒーとドーナツをふるまうような企業に、組合が入り込めるはずがないではないか。」 p.356 「技術者自身がぶつかる問題を解決することを、技術の進歩と市場の開拓をもたらす主要な手段としてきた。」 p.360 「「ビルとデーブがわたしのために働いてくれているのであって、逆ではないような印象を持つ」」 ●CEO、経営幹部、起業家のための一貫性の教訓 p.362 「ビジョナリー・カンパニーは基本理念を維持し、進歩を促すために、ひとつの制度、ひとつの戦略、ひとつの戦術、ひとつの仕組み、ひとつの文化規範、ひとつの象徴的な動き、CEOの一回の発言に頼ったりはしない。重要なのは、これらすべてを繰り返すことである。」 p.363 「従業員に強い印象を与え、力強いシグナルを送るのは、ごく小さなこと」 p.365 「下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせる」 p.367 「正しい問いの立て方は、「これはよい方法なのか」ではなく、「この方法は当社に合っているのか、当社の基本理念と理想に合っているのか」である。」 p.368 「ビジョナリー・カンパニーになるためには、基本理念がなくてはならない。また、進歩への意欲を常に維持しなければならない。そして、もう一つ、基本理念を維持し、進歩を促すように、すべての要素に一貫性がとれた組織でなければならない。」 ●これは終わりではない p.370 「一 時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 二 「ANDの才能」を重視しよう。 三 基本理念を維持し、進歩を促す。 四 一貫性を追求しよう」 ■おわりに -頻繁に受ける質問 p.373 「何からはじめればいいのか …会社の基本的な価値観を箇条書きにする… 「状況が変わって、この基本的な価値観のために業績が落ち込むことが合っても、それを守り抜こうとするだろうか。」心からイエスという答えを出せないのであれば、それは基本的なものではなく、削除すべきだ。」 p.378~p.379 「CEOではない立場で、何ができるのか …組織全体にははっきりした理念がないのであれば、なおさら、自分の責任範囲ではっきりした理念を定める理由があり、その自由があるのだ。企業が全体として、、しっかりした基本理念を持っていないからといって、自分の部署がそれを持ってはならないわけではない。 …BHAGは部門のレベルで特に役立つことがわかっている。 …周囲を教育する方法がある。」
0投稿日: 2013.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ターゲットワード』 ・社会に絶大なインパクトを与えている会社はビジョンを持って行動している ・「品質を重要視する」と「低価格を重要視する」という方針が合った場合、ビジョナリーカンパニーは「OR(かつ)」を選択する ・ビジョン達成のために「高い目標」を設定する ・ビジョンをずらさず結果より量の手法で進める ・利益を超えてビジョン達成のために行動する -尊敬される企業は経営難に落ちいった時にビジョンから始める ・決して満足しない ・始まりの終わり ・時を告げるのではなく、時計を作る 『質問』 ・本当にビジョンだけで会社を存続させることができるのか ・自分たちの信念を相手に押し付けることは悪になりえないのか ・相手のニーズを重要視せずビジョンから作ったものが本当に社会にインパクトを与えるものなのか ・ORの考え方は時としてリスクにならないのか ・宗教的に会社を経営していくことは正しいのか
0投稿日: 2013.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これまでの基本理念についての認識は、外部に対しての会社の方針表明と、内部での行動の拠り所、位でした。この本を読むことで、 「企業の永続的な発展や、利益を出しながら(利益は人間の呼吸のようなもの。手段にすぎない)社会に貢献していくための指針」といった考えに触れ、将来、経営に携わる仕事に就くための一つの価値観として加えられました。まだまだ現状業務で活かす、というポジションではないので、また何年後かに読んでみたいです。 「基本理念を維持し、進歩を促す仕組み作りも合わせて必要」 「明日には今日より前進するという終わりのない修練」
0投稿日: 2013.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕組化の話とかすごく共感できた。ただ、参考例として挙げられている企業は大企業ばかりなので(もちろん、スタートアップの企業でも参考に出来る部分は多いと思うが)中小企業とかベンチャー企業にはちょっとリアルじゃないかも??
2投稿日: 2013.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者必読の本と言われる ビジョナリーカンパニー。 2巻で指摘されている通り、 スケールが大き過ぎて、 まだまだ自分には実用的ではない。 しかし、 生活の中に生かすことのできる部分は沢山ある。 平社員でも部長でも、 どのレベルでもこの本の内容を生かすことはできると思うので、 是非試してみたい。
1投稿日: 2013.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ビジョナリー・カンパニー】 ・業界で卓越した企業 ・社会に消えることのない足跡を残している。 ・CEOが世代交代している。 ・当初の主力商品がライフサイクルを超えて繁栄している。 ・1950年以前に設立している。 共通する特徴を見つけ、実践の場で役に立つ枠組みをつくる。 ■基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整えることの大切さだ。これが時計をつくる考え方の真髄である。⇒p145の枠組の図 12の崩れた神話 01:会社をはじめるのに素晴らしいアイデアは不要。 02:カリスマ指導者は不要。 03:利益が最大の目的ではない。 04:ビジョナリー・カンパニーには共通した基本的価値観はない。 05:変わり続ける。(基本的理念は維持) 06:リスクをとる。 07:だれにとっても素晴らしい職場とは限らない。(カルト的) 08:戦略的とは限らない。(試行錯誤、臨機応変、「種の起源」的) 09:社内CEO 10:競争に勝つことを第一に考えない。(自らに勝つこと) 11:相反することを同時に獲得する。 12:経営者の先験的発言がすべてをではない。(第一歩) 「時を告げること」ではなく、「(ある種の)時計をつくること」 企業そのものが究極的作品:どんなに素晴らしい製品も時代遅れになるが、ビジョナリー・カンパニーは時代遅れになるとは限らない。 ビジョナリー・カンパニー一覧(p5) 陰陽思想からとった紋様(p73) ビジョナリー・カンパニーの基本的理念一覧(p112) ビジョナリー・カンパニーは理念を宣言しているだけではなく、組織全体に浸透させている。 基本理念=基本的価値観+目的。信念と存在価値。 基本理念を維持し、進歩を促すための具体的な方法 ①社運をかけた大胆な目標(BHAG) ②カルトのような文化 ③大量のものを試して、うまくいったものを残す。 ④生え抜きの経営陣 ⑤決して満足しない BHAGの例:ケネディの月旅行計画 進化を促す教訓(3M) 「試してみよう。なるべく早く」 「誤りはかならずあることを認める」 「小さな一歩を踏み出す」 「社員に必要なだけの自由を与えよう」 「重要なのは仕組みである。着実に時を刻む時計をつくるべきだ」 ↑チクタク、ピシン、チクタク、パシン 一貫性の教訓 ①全体像を描く ②小さなことにこだわる ③下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせる ④流行に逆らっても、自分自身の流れるに従う。 ⑤矛盾をなくす ⑥一般的な原則を維持しながら新しい方法を編み出す 四つの概念 ①時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 ②「ANDの才能」を重視しよう。 ③基本理念を維持し、進歩を促す。 ④一貫性を追求しよう。
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・理念の内容ではなく、理念をいかに深く「信じて」いるか、一貫しているか。 ★競争に勝つことよりも「明日にはどうすれば、今日よりもうまくやれるか」と厳しく問いかけている。 ・「他と比べて際立っている点は何か?」 ・カリスマ的指導者は「時を告げる」 繁栄しつづける会社を築くのは「時計をつくること」 ・早い時期の成功とビジョナリーカンパニーは逆相関 ・絶対に諦めない。 ・わが社のポリシーは、消費者の望んでいるものを作るのではなく、新しい製品をつくることによって、彼らをリードすることである。 ・フォード:過度な利益よりも、販売台数を多くし、車にのって楽しめる人が増え、十分な賃金で雇用できることが私の2つの目標である。 ・基本理念だけは変えてはいけない。 ・基本理念を維持し進歩を促す具体的な仕組みを整えることが大切。 ・BHAG:Big Hairy Audacious Goals : 目標を達成する決意が極めて固い場合のみ。 ・ノードストロームの規則:その1 どのような状況にあっても、自分で考え、最善の判断を下すこと。 ・SPH(1時間あたりの売上)を意識させる。 ・ビジョナリーカンパニーは自分たちの存在意義や達成すべきことをはっきりさせているので、厳しい基準に泡内社員は働ける余地がなくなる。 ・無駄にした時間は永遠に失われる ・ダーウィンの進化論は、変異と自然淘汰。環境に即した変異が淘汰で生き残る。 ・最高の仕事、もっとも難しい仕事は、冒険と挑戦の精神によって成し遂げられる。 ・世の中でいちばん大切なのは、自己を律することである。自己を律することがなければ、人格は形成されない。進歩はない。逆境は成長への機会になる。何のために働くのか? (まとめ) 1)時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 2)「ANDの才能」を重視しよう 3)基本理念を維持し促す 4)一貫性を追求しよう
0投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まず読む前にどんな本なのか調べてみた 何が重要であると言っている(繰り返してる)のか、 っていうか結局なにが言いたいのか 「基本理念の重要性」を何度も繰り返しているようだ なので、まず基本理念について具体的に述べてそうな章を探す 第三章利益を超えての「基本理念」(p75)と 第四章基本理念を維持し、進歩を促す(p131) っていうか結局なにが言いたいか、については ネットで調べたらすぐ出てきたし、終わりにを読めばわかるので 後でまとめることにする とりあえず今は著者にとっての基本理念を知ることにして、 時間があるときにしっかり他の部分も読むことにする -- p89 基本理念ー利益の神話を吹き飛ばす アメリカの独立宣言、ゲスティバーグの演説のような指導原理のように 基本理念とは企業にとって 基礎の基礎に当たり、めったに変わることはないものである 「われわれが何者で、なんのために存在し、 何をやっているかを示すものである」とも書かれている p131 基本理念を維持し、進歩を促す 基本理念を文化、戦略、戦術、計画、方針などの 基本理念でない慣行と合同しないことが重要である 時間の経過とともに文化の規範が変わるからである (「ユダヤ人大富豪の教え」に書いてあった時代を読む力が重要である) 戦略、能力、目標、業務方針、組織構造 それらが変わっても絶対に変えてはならないのが基本理念である IBMはこれを変えてしまったがために衰退した(と書いてある) 「基本理念を維持しながら、進歩を促す」 これこそがビジョナリーカンパニーの真髄である 進歩への意欲には 「日々進歩するために変わり続けることが大切だ、 変わることは全前進することである、恐れることではない」 というようなことが書かれていた (仕事はたのしいかね?の マックスの毎日の目標と同じであることに気がついただろうか) そしてやはりここにもマスターマインドの話が浮上 ここで思ったことを整理 起業する起業しないに関わらず、 自分の人生においての基本理念(目標といってもいい)を持ち、 それに共感または同じ基本理念を持つ仲間を増やし、 その仲間(マスターマインド、ベストパートナー)と日々進化(変化)し続けることが 有意義な人生だったと振り返るための条件なのではないか、と (ちょっとかっこよく言ってみたかっただけです)
0投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい内容でした。もっと早く読めばよかった。 経営に関係する人はもちろん、全てのビジネスマンにとっても有用な本です。
1投稿日: 2013.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネス書のバイブル的な一冊。 最近、ビジョナリー・カンパニー 4が出版されましたが、私は恥ずかしながら、初めてこのシリーズを読みました。 著者が主張するビジョナリー・カンパニーの特徴(概念)とは、以下の通りです。 ・時を告げる予言者ではなく、時計を作る設計者になること ・ORの抑圧をはねのけANDの才能を活かす ・基本理念(=基本的価値観+目的)を維持しながら、進歩を促す(社運をかけた大胆な目標が必要) ・すべての要素に一貫性が取れた組織 期待度が高かったこともあり、正直「あれっ」ていう感もありますが、自分の理解の悪さも否めないため、2~4にもチャレンジしたいと思います。
0投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い本だとは思うんですけど、 正直、手放しに褒めるには不完全だと思います。 成功からのみの一般化に意味はない訳で、 そういう意味ではビジョナリーカンパニー2も一緒に読むべきでしょう。 根拠ある分析を心がけているのはひしひしと伝わるのですが、 文章はむしろどこか熱いところがあり、 そのテンションと志の高さもなんだかビジョナリーでいいですね。 所々で内容が抽象化されしっかりまとめてあるので、 具体的な話を読むのがかったるく感じられ、 全部読まなくてもいいかなと思っちゃうのはあるかもしれません。
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容薄過ぎで、目新しさも共感もなかった。内容量的には、本当は新書サイズがちょうどいいんじゃないか?古い本だからしょうがないかな。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想は以下。 http://masterka.seesaa.net/article/311154193.html
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ先に「ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則」の方を読んでしまってからコチラを読んだ。なので中身の要約は知っているし感動薄かった。失敗した。
0投稿日: 2013.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ時を告げるのではなく、時計を作る。 経営理念はどこの会社でも作っているが、実際に浸透させようと一貫性のある企業は少ない。 傑出するには、絶え間無く動くこと。
0投稿日: 2012.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ社長の推薦図書 以下要約。ただし、要約よりもビジョナリー・カンパニーと比較対象企業の個々の内容のほうが面白い。買ってもう一度読むかなぁ・・・。 ------------- 第1章 最高のなかの最高 ・ビジョンを持っている企業、未来志向、先見的な(ビジョナリー)企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業。ビジョナリー・カンパニーは組織であり、商品のライフサイクルを超え、優れた指導者が活躍できる期間を超えて、ずっと繁栄し続ける。 第2章 時を告げるのではなく、時計をつくる ・時計なしに時を告げる(カリスマ的指導)のではなく、自分がこの世を去った後も、基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みを整える(永遠に時を告げる時計を作る)ことがビジョナリー・カンパニーの真髄である。 ・企業として早い時期に成功することと、ビジョナリー・カンパニーとして成功することは、逆相関。素晴らしいアイデアを見つけてから会社を始めることにこだわらない。 ・世間の注目を集めるカリスマ的スタイルは不必要。 第3章 利益を超えて ・収益力は、会社が存続するために必要な条件であり、もっと重要な目的を達成するための手段だが、多くのビジョナリー・カンパニーにとって、それ自体が目的ではない。 ・業種に関係なく、理念と利益を同時に追求する「ANDの才能」を大切にしている。 第4章 基本理念を維持し、進歩を促す ・組織にとっての聖域は、その基礎となる経営理念だけである。 ・常に理念に徹すると「同時に」力強く進歩しようとする。 第5章 社運を賭けた大胆な目標 ・BHAG(社運をかけた大胆な目標: Big Hairy Audacious Goals)は、人々の意欲を引き出す。人々の心に訴え、心を動かす。具体的でワクワクさせられ、焦点が縛られている。誰でもすぐに理解でき、説明する必要はない。 ・BHAGは、極めて大胆で、理性的に考えれば、とてもまともとは言えないが、一方で、それでもやってできないことはないと主張する意欲的な意見が出てくる灰色の領域に入る。 ・BHAGには、それを達成した後、目標達成症候群にかかって組織の動きが止まり、停滞する危険がつきまとっている。次のBHAGを準備しておく。またBHAG以外にも、進歩を促す方法をもっておく。 ・BHAGは会社の基本理念に沿ったものでなければならない。 第6章 カルトのような文化 ・ビジョナリー・カンパニーは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向がある。企業の考え方を心から信じて、献身的になれるのであれば、本当に気持ちよく働けるし成果も上がる。そうでないのなら、いずれ辞めていくことになるか、病原菌か何かのように追い払われる。 ・カルトと共通した以下の4つの点が顕著に見られる①理念への熱狂②教化への努力③同質性の追求④エリート主義。 第7章 大量のものを試して、うまくいったものを残す ・失敗は当社にとって最も大切な製品 ・多数の実験を行い、機会をうまくとらえ、うまくいったものを残し、うまくいかなかったものを手直しするか捨てる ・採用するアイデアは本質的に新しいものでなければならない。 ・進化による進歩を促す5つの教訓(3M) ① 試してみよう。なるべく早く ② 誤りは必ずあることを認める。 ③ 小さな一歩を踏み出す:何か革新的なことをやりたいのであれば、実験する許可を求めるのが最善の方法。 ④ 社員に必要なだけの自由を与えよう ⑤ 重要なのは仕組みである。着実に時を刻む時計を作る(3Mで優秀な技術者として認められたいのなら、自分の技術を社内全体に広める) 第8章 生え抜きの経営陣 ・ビジョナリー・カンパニーは比較対象企業よりはるかに、社内の人材を育成し、昇進させ、経営者としての資質を持った人材を注意深く育成している。 ・要するに、ビジョナリー・カンパニーと比較対象企業の差をもたらしている最大の要因は、経営者の質ではなく、優秀な経営陣の継続性が保たれ、基本理念が維持されていることである。 第9章 決して満足しない ・安心感は、ビジョナリー・カンパニーにとっての目標ではない。ビジョナリー・カンパニーは不安感をつくり出し(自己満足に陥らないようにし)、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す強力な仕組みがある。 第10章 はじまりの終わり ・一貫性を達成するための指針 ①全体像を描く ②小さなことにこだわる ③下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせる ④流行に逆らっても、自分自身の流れに従う ⑤矛盾を無くす ⑥一般的な原則を維持しながら、新しい方法を編み出す ・今後のビジネスに活かすための4つの概念 ①時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ ②「ANDの「才能」を重視しよう ③基本理念を維持し、進歩を促す ④一貫性を追求しよう
0投稿日: 2012.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書としてのバイブル的な存在であるため、目を通して見たが、時間の浪費に終わった。 言いたいことは「BE VISIONARY」これだけだった。
0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
企業が長期的に発展していく上で、時代に左右されない基本理念を持つ事が大切。最高法規に当たる憲法に当たるものでしょうか。 その上で、必要なのは時を告げる経営者ではなく、時計をつくる経営者である。これは、長期的な視点に立った時に、1人の人間が会社を経営しつづけることは出来ない。人を育てることが大切と言う事。 ビジョナリーカンパニーは決して、働きやすい職場ではなく、その企業の理念に従える人にとっては、最高の企業であると言う事。理念に従った過ちは許されるが、従わない部分は、たとえそれが利益に結びつくことであっても、許されない。 などなど。 理念を持って仕事をすることは、企業に限ったことでなく、個人にこそ当てはめるべきものでしょうか。 当時、日本からはソニーがビジョナリーカンパニーとして認められていたのですね。
0投稿日: 2012.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本理念の維持。それ以外は全て変えてしまっても構わない。 物事は何でも基本となる部分がしっかりしていないとだめですね。 企業だけでなく、人生にもそのことがいえるかもしれません。
0投稿日: 2012.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11394493395.html
0投稿日: 2012.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ」というフレーズが身にしみた。自分自身が時を告げられねば、これを実践することは困難であり道は相当に険しい、と痛感したのだが、時計を作るという視点を持つこと自体が非常に重要であると思う。 流石に、名著と言われるだけのことはありました。
0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的には、1より2の方が評価が高いが、個人的には1の方が好き。 2がややテクニカルでその分より実践的な印象であるのに対して、1はより大局的で理念的な印象。
0投稿日: 2012.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社とは何か、自らは何のために働くのか、どう働くのかを考えさせられる本。 【引用】の文がすばらしい 「失敗することがあっても、大きなことに取り組んで栄誉ある勝利を獲得するほうが、たいした苦労もない代わりにたいした喜びもない臆病者の群れに加わるより、はるかにいい。臆病者は、勝利も知らなければ、敗北も知らない灰色の生活を送っているのだから。」 " ... his place shall never be with those cold and timid souls who knew neither victory nor defeat ... " Theodore Roosevelt
1投稿日: 2012.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ生存の原則として基本理念の維持、進化、そして一貫性を学ぶ事例が多く挙げられている。時計を進めるのではなく、時計を創るという発想は組織を生存させる為に非常に必要な考え方だと学ぶことができた。
0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ【生き残る会社の特徴を暴く!!】 長い時間生き残る会社、ビジョナリーカンパニー。どういった特徴を持った会社が、その名誉を与えられるのかを書いた本。ケーススタディを基にした研究を長々と書き記している為、若干面倒。だが、今でも通用するであろう、ビジョナリーカンパニーの特徴を学べたことは、とても面白かった。 「基本理念を維持し、進歩を促す」では、 業界をリードするユニクロやマクドナルドが実際に行なっていることに近いもの感じ、本書が提示するビジョナリーカンパニーの条件が、如何に現在にも生きているかが感じられる。 経営者はもちろん、それを目指すものは一読すべきである。
1投稿日: 2012.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ節目に何度も読んでいる本の一冊。 読むごとに、目に留まり、再認識すべきことが違ってきます。 今回は、「文化」とBHAG(大胆な目標)について熟考してみました。 ケネディ大統領の1960年代「月旅行計画」は、国民をわくわくさせる 目標であり、1950年時代まで停滞していたアメリカが 猛烈な前進をしていく礎になったのは間違いありません。 「宇宙開発計画」ではなく、「月旅行計画」としたことも、 人々に、意欲を与え、心を動かしたのだと思います。 より具体的だからこそ、わくわくさせられたのでしょう。 僕自身の活動体のBHAGについて考えていたけれど、 今、日本にBHAGがあれば、もしかすると…と思ってしまいます。 国民全体がわくわくする大胆な国の目標…そんなことを考えました。
0投稿日: 2012.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
以前、この日記でも紹介した「ビジョナリーカンパニー2」の 前に書かれた本です。時代を超えて際立った存在であり続ける 企業は、優秀といわれる(た)比較企業と何が異なるのかを 分析した本です。 ビジョナリーカンパニーがもつ、基本的な概念は以下。 ・時を告げるのではなく、時計をつくる 偉大や指導者やアイディアに頼るのではなく、経営の 世代交代や製品サイクルを通じて環境の変化に適応できる 組織の仕組みをつくる。 ・ANDの才能 いくつもの側面で、両極にあるものをどちらも追求する。 目的と利益、持続と変化、自由と責任、長期と短期、 など。 ・基本理念 基本的価値観や目的を徹底させ、長期にわたり意思決定 の原則とし、組織全体が力を奮い立たせる原則にする。 ・基本理念を維持し、進歩を促す 基本理念をゆるぎない土台にしつつ、それ以外のすべての 面では、変化、改善、革新、若返りを促す。 ・社運を賭けた大胆な目標をもつ 進歩を促すために、社運を賭けた大胆な目標を掲げ、 それに邁進する。 ・カルトのような文化 理念への熱狂、教化への努力、同質性の追求、エリート 主義の特性をもつ ・大量のものを試して、うまくいったものを残す 失敗を恐れず試行錯誤する、誤りが生じることを認め、 一歩を踏み出せるよう、社員に必要なだけの自由を与え る。 これらの考え方は、「ビジョナリーカンパニー2」で紹介され た飛躍企業の特性を長期にわたり継続していくために必要な 要素と位置づけられるようです。
0投稿日: 2012.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時代を超えてビジョナリーカンパニーとして、成長し続けるにはどのようなことが必要なのか、ビジョナリーカンパニーをピックアップし、その特徴・比較対象企業との違いを分析した本。全てを受け入れられるわけではないが、かなり参考・勉強になる良著。 <キーワード>理念の浸透・BHAGの設定・進化する文化 <その他> ・ビジョナリーカンパニー基準 業界で卓越している。経営者・企業幹部の間で尊敬されている・社会に消えることのない足跡を残している・CEOが世代交代している・主力製品がライフサイクルを超えて繁栄している ・崩れた神話 すばらしいアイデアが必要→× カリスマ指導者が必要→× 利益の追求が最大の目的× 正しい基本的価値観がある× 優良企業は危険を冒さない× 誰にとっても素晴らしい職場× 綿密で複雑な戦略がある× 社外CEO× 競争に勝つことが第一×自らに勝つこと OR× ・変化を奨励する環境があること。自ら発展し、変化する組織 ・ORではなくANDを実現する。短期的な利益と長期的な成長両方を実現させる ・収益力は会社が存続するために必要な条件であり、もっと重要な目的を達成させるための手段だが、それ自体は目的ではない。利益とは人間の体にとって酸素や食料や水や血液のようなもの。人生の目的ではないが、それがなければ生きられない。 ・理念に不可欠な要素はない。理念が本物であり、企業がどこまで貫き通しているかの方が内容より重要。 考えを公言すると、それに従って行動するようになる。理念は目標戦略戦術組織設計などで一貫性を保つことが大事。 ・基本理念=基本的価値観(不変のもの=信念)+目的(会社の根本的な存在理由) ・基本的価値観は3つから6つ。多すぎた場合、本当にそれが外部の環境が変わって、利益に結びつかなくても百年間守り続けていくべきものか考えてみる。基本理念を掲げるときには心から信じているものを表現する。基本理念は企業の内部にある要素。 時代の流れや流行に左右されることもない。 ・基本理念は変わらないが、具体的な行動は変わる。例 個人の自主性を尊重するが、15%ルールは変わる。(3M) ・基本理念を維持しながら進歩を促すこと ・基本理念は発展、変化の基礎となる。これを明確にすることで、それ以外を全て変化させられる。基本理念は保守 ・進歩への意欲があるから基本理念を維持できる。革新 ・進歩を促すための具体的な方法①社運をかけた大胆な目標 ②カルトのような文化③大量のものを試してうまくいったものを残す④生え抜きの経営陣⑤決して満足しない 「指標」・時計をつくる設計者か ORの抑圧をはねのけANDの才能を活かしているか 基本理念をもち単なる金もうけをこえた基本的価値観と目的があるか 進歩への意欲があるか 組織は一貫性をもっているか ・BHAGは社内から見たときより社外から見たときの方がはるかに大胆に見える。登山でほんににとってみると自分の力量を考えて十分登れるいわばを上っている感覚 ・BHAGはきわめて明確で説得力があり説明する必要もないほどでないといけない。目標であり声明ではない(登るべき山や月)組織内に活力がみなぎらなければ意味がない ・気楽に達成できるものであってはならない。なんとかできるが、英雄的な努力とある程度の幸運が必要だと思えるもの 例 B747開発 五十億ドル投資しての開発 業界トップになる 業界標準ではなく自分たちのイメージでランドをつくる ・ビジョナリカンパニーのカルトに似た特徴・理念への熱狂・教化への努力・同質性の追求・エリート主義 ・病原菌を追い払い、残った従業員にエリート組織の一員としての感覚を持たせる。 ・進歩には二種類ある。BHAGによる進歩と進化による進歩である、進化は目標はあいまいであり、それまでの事業の延長線上にある小さな一歩である。 ・3M進歩を刺激する仕組み 勤務時間の15%まで自分で選んだテーマや創意工夫にあてることを奨励15%ルール 25%ルール 売上25%を過去5年間の新商品と新サービスであげるよう 問題解決派遣チーム 小人数の精鋭部隊を顧客の現場に送り、顧客に固有な珍しい問題の解決にあたる 教訓 ①試してみよう。なるべく早く②誤りは必ずあることを認める③小さな一歩を踏み出す④社員に必要なだけの自由を与えること⑤重要なのは仕組みである、着実に時を刻む時計をつくるべき ・自分がいなくなったとき、次はだれがそこにくるか。引き継ぎが円滑にいくような方法をとっているか ・明日にどうすれば今日よりうまくできるのかを考えることが最も大事。 ・安心感はビジョナリーカンパニーにとっての目標ではない。ビジョナリーカンパニーは不安感を創りだし、それにより外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す強力な仕組みを設けている。 ・他者より先にいろんなことを取り入れてみること 一貫性の教訓 ・全体像を描くこと・小さなことにこだわること・下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせること。連携し、集中できる仕組みを作る 大事な教訓①時を告げる預言者になるな。時計を創る設計者になれ。②ANDの才能を重視しよう③基本理念を維持し、進歩を促す④一貫性を追求しよう
0投稿日: 2012.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーとは何か? サンプリングの条件設定として、単に成功しているとか、長続きしているといっただけではなく、その業界で長期にわたって超一流といわれる地位を確立している会社としている。 著者は18社を選んで、同業種のナンバー2の会社と比較し、その違いを分析して、超一流企業の条件を洗い出している。最終的に、言っているのは次の4点。 1.時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ。 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。 噛み砕いていえば、1.はカリスマ指導者に頼るな、ということ。特別な才能を持った経営者が在任中に業績を伸ばしても、その人がいなくなったら組織がガタガタになるのではビジョナリーカンパニーとはなり得ない。特別な才能で時を言い当てるのではなく、だれもが使える時計(組織・仕組み)を作ることに専念すべきということ。 2.は、ビジョナリーカンパニーでは、「利益を超えた目的」と「現実的な利益」といった、一見相反する目標を同時に追及しているということ。要は、目的か利益かといった「OR」ではなく、目的も利益もという「AND」を追求している。ビジョナリーカンパニーでは、二兎を追って二兎を得ているということ。 3.は、あくまでも基本理念にこだわることの重要性。時代や社会の環境が変化して、組織がそれに合わせて進化していっても、まるで遺伝子のように、その基本理念自体は変わらないということ。 4.は、ことばの通りだが、いくら美しい基本理念を持っていても、実際の経営の場面で、それの精神が一貫して実現されていなければビジョナリーカンパニーとはなり得ないということ。 この他にも、BHAG(Big Hairy Audacious Goals)を設定すること、すなわち、安定志向ではなく、社運を賭けた大胆な目標を掲げること。カルトのような文化をもち、基本理念に則った企業文化を形成すること。環境の変化に対応するために、ある程度の失敗は認め、数多くの試みから適者生存するものを作り出すこと。経営トップには生え抜きを据えること。以上のようなことが、例に挙げた18社に共通する傾向だったという。 この中で一番困難なことが、一貫して理念を尊重しながら、環境の変化に合わせて事業を適応させていくことだと思う。そういった能力をもった組織を作るのに、多くのビジョナリーカンパニーが、トップの育成制度を設けているという指摘があった。それは、当然ながら経営を引き継ぐはるか以前から計画化されており、その中で、基本理念が継承され、次の世代、またその次の世代に受け継がれるように仕組化しているという点が、自社の弱点と照らし合わせて非常に興味深かった。
2投稿日: 2012.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に必要な部分までそぎ落とした具体的な理念を掲げること それを浸透させ維持、進歩させる具体的な活動、仕組みの構築 ビジョナリーカンパニーにとっては、絶対的な理念だけが変えてはならないもので、そのほかの仕組み、施策はすべて変えてよい 経営者の最たる仕事は、 素晴らしい製品、サービスを生み出すのではなく、 それらを生み出す組織、文化、仕組みを作り出すこと そこには、カリスマ性のある経営者も必要ない 自分の仕事の仕方が択一性の「ORの抑圧」に大きく影響を受けていることを認識し、「ANDの可能性」を最大限とれるように努めねばならないと認識。 ちょうど、コーチングの書籍を平行して読んでいたこともあり、仕事をしているときとは、まったく違う視点で自分の環境を見つめることができた
0投稿日: 2012.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者だけでなく組織のリーダーであれば必ず知っておいた方がよいことが多い。また必要な時期に読み直そう。また、ビジョナリーカンパニーはなぜ成功したのかの理由を、超成功企業と成功企業を比較しながら説明しているため説得力がある。 ■基本理念を文書にしている p.119 ・基本理念=基本的価値観+目標 ・基本的価値観とは、組織にとって不可欠で不変の主義。いくつかの一般的な指導原理からなり、文化や経営手法と混同してはならず、利益の追求や目先の事情のために曲げてはならない。 ・目標とは、単なるカネもうけを超えた会社の根本的な存在理由地平線の上に永遠に輝き続ける道しるべとなる星であり、個々の目標や事業戦略と混同してはならない ■基本理念を維持し、進歩を促す p.146 ■社運をかけた大胆な目標 p.155 BANGは人々の意欲を引き出す。人々の心に訴え、心を動かす。具体的で、わくわくさせられ、焦点が絞られている。だれでもすぐに理解でき、くどくど説明する必要はない。 ■カルトのような文化 p.203 先見性とは、やさしさではなく、自由奔放を許すことでもなかった。事実はまったく逆であった。ビジョナリーカンパニーは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向がある。 ■大量のものを試して、上手くいったものを残す p.249 システムができあがった主因は、経営の天才が戦略計画を立てたことにあるわけはない。変異と選択という進化の過程にこそある。繁殖し、変異し、強いものが生き残り、弱いものが死に絶えた結果なのである。
1投稿日: 2012.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えのある本だった。つまり、読むのに時間がかかった。それでも、手に取り、ページをめくる価値は十分にある。経営に対する考え方が変わった。 実在するいくつもの企業を分析し、そこから時代を超えて生き残る企業の条件を導き出している。P&G、ウォルマート、3Mなどが登場する。「カリスマ的な指導者は必要ない」「無謀としか思えない戦略が有効な時がある」「基本理念を堅持すれば、あとは柔軟に変化させてよい」など、ぶっ飛んだことが書いてあるので最初は驚くが、読み進めていくうちに納得出来る。重要そうな所が多過ぎて、大量に線を引いてしまった。
1投稿日: 2012.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ50年間以上「ものすごくうまくいっている企業」か「すごくうまくいっている企業」とどう違うのかを研究してまとめた有名なビジネス書。
0投稿日: 2012.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分で会社を経営したい方、事業を始めたい方は読んで損はないです。 なぜ潰れる会社といつまでも残る会社があるのか 面白い視点から分析されており、参考となります。
0投稿日: 2012.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーとは、先見性のある企業のこと。 長くに渡ってリードし続ける企業にはどういう特徴があるのかについて研究された結果を述べている。 結論から言うと、大事なことは ・理念が明確であり、わかりやすい ・理念が企業の細部にまで渡って浸透している ・理念に即して行動するが同時に利益も追い続ける (理想を常に口にし続け、同時に現実的な思考も行う) ・進歩を促す仕組みを持っている ・理念に背く行動は企業のどんな細部でも行わない。 (一貫性を常に意識する) 進歩を促す仕組みとは。 ・社運をかけた大きな目標を常に持っている ・カルトのような文化(社風)を持っている ・大量のものを試して、上手くいったものを活かす ・生え抜きの経営陣を幹部に採用する ・決して満足しない 以下は感想。 ビジョナリーカンパニーになるために、個々人が働く上で重要なことは、 『目の前の仕事が好きであり、その企業内での働き方が自分のスタイルに合っていること』 であると思った。 この理由を説明する。 まず、「目の前の仕事が好きであり」について。 これはつまり、仕事が好きであることは、企業の理念と自分の意見が合っているということだ。 これにより、努力すべき対象が自分自身の中で正当化されることになる。 今まさにやっていることが自分のやりたいことであり、自分を成長させてくれるんだ!という気概を持てることである。」 これは、社運をかけた大きな目標に取り組んでいる時に上記のように全社員が感じていれば、ビジョナリーカンパニーに1つ近づく。 次に「その企業内での働き方が自分のスタイルに合っている」について。 これは、基本理念を皆が信じていることが前提にある。 その上で、正当な評価がなされ、個々が尊重されていることが重要である。 なぜなら、決して満足せずに挑戦し続けるためには、正当な評価が必要であり、大量のものを試すには、年代に関わらず全ての社員の意見が尊重される必要があるためだ。 生え抜きの経営陣が必要だということは、その企業の理念を体現できるのは生え抜きの社員であるためである。 すなわち、外部の人間をCEOにしても良いが、理念を体現するのは実際難しいという理由がある。 企業といっても、それは個々の人間の集まりである。 よって、どのような人間を会社に入れるかは非常に重要である。 理念に共感した優秀な人がベストである。 仮に現在務めている企業の理念や社風が合わないとしても、まずは無理やりにでも合わせてみることが必要であると思った。 そうすることが社内の評価に繋がるのではないかと思う。
0投稿日: 2012.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログマネジメントの本ではあるが、個人としてどのように考え、行動すると良いかを学ぶことができた。 印象に残ったのは、”とにかく仕組み・仕掛けを作る”ということと、進化を止めてはならないということ。 学習、努力、業務上の工夫や取組みを一過性のもとせず、自分だけのものとせず、組織として継続させられるような仕掛けを作ること、そのようにして進化し続けないとまずいことになるという不安を駆り立てること。できるようで本当に難しいことと感じる。 日々の仕事や生活に役立てていきたい。
1投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構長く時間をかけて読みました。 いわゆる経営の教科書として有名なこの本、安易に「いい会社」を目指すには、になっていないのがポイント。 「ビジョナリー」な会社がほかとどう違うのか、それはどういうビジョンだったのか。 基本的にはこのメッセージがひたすら書いてあります。 個人的に気になったのが、 「時を作る」こと。 一人のカリスマがすべてをできるようにするのではなく、それをどうやって「仕組化」するか。 これって会社経営だけでなく、それぞれの人の立場の中で必要なことなんですよね。
1投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中でいう、いわゆる「素晴らしい企業」を作るためにはどのようなことをすればよいかということを学んだ。 他と違うことをしながら、理念を崩さないように、自分も生きていきたい。
0投稿日: 2012.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次 第1章 最高のなかの最高 十二の崩れた神話 調査プロジェクト データはあくまでデータ 第2章 時を告げるのではなく、時計をつくる 「すばらしいアイデア」の神話 「すばらしいアイデア」を待つのは、悪いアイデアかもしれない 企業そのものが究極の作品である 偉大なカリスマ的指導者の神話 建築家のような方法 - 時計をつくる CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ 挿話 「ORの抑圧」をはねのけ、「ANDの才能」を活かす 第3章 利益を超えて 現実的な理想主義 - 「ORの抑圧」からの解放 基本理念 - 利益の神話を吹き飛ばす 「正しい」理念はあるのか CEO、経営幹部、起業家への指針 第4章 基本理念を維持し、進歩を促す 進歩への意欲 基本理念を維持し、進歩を促す CEO、経営幹部、起業家のためのキー・コンセプト 第5章 社運を賭けた大胆な目標 BHAG - 進歩を促す強力な仕組み 重要なのは指導者ではなく、目標 - 時を告げるのではなく、時計をつくる CEO、経営幹部、起業家への指針 第6章 カルトのような文化 「病原菌か何かのように追い払われる」 IBMが偉大な企業になった過程 ウォルト・ディズニーの魔法 プロクター&ギャンブル - 本社に浸りきる CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ イデオロギーの管理と業務上の自主性 第7章 大量のものを試して、うまくいったものを残す 進化する種としての企業 3M - ミネソタの突然変異製造機がいかにしてノートンをつきはなしたか 3Mでの「枝分かれと剪定」 CEO、経営幹部、起業家にとっての教訓 「機軸から離れない」ではなく、「基本理念から離れない」 第8章 生え抜きの経営陣 社内の人材を登用し、基本理念を維持する CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ 第9章 決して満足しない 現状を不十分と感じるようにする仕組み 将来のために投資する - そして短期的にも、好業績をあげる マリオット対ハワード・ジョンソン - アメリカの偉大なチェーンの没落 CEO、経営幹部、起業家へのメッセージ 黒帯の寓話 第10章 はじまりの終わり 一貫性の力 - フォード、メルク、ヒューレット・パッカード CEO、経営幹部、起業家のための一貫性の教訓 これは終わりではない
0投稿日: 2012.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョンを持った会社、ビジョナリーカンパニー(急成長を成し遂げる会社)とは、独自の歴史を持ち、独自の社風を持つ。 その会社は特には、カリスマは必要なく盤石としたルールが存在する。 この本では、日本の企業としてソニーを上げているが、現在ではこれがサムソンに変わっていることだろう。 今の日本では、ユニクロだとか、ソフトバンクだろう。
1投稿日: 2012.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経営者の教科書と呼ばれる本です。 今までの良い会社と呼ばれる定義を覆すような 内容に目からうろこでした。 「経営者にカリスマは、いらない」 「orではなく、AND」 ビジョナリー(未来志向型)な企業をつくるには? 起業したい人は、ぜひ読んで欲しい本です。 価値観変わります。
0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ偉大なる企業のエッセンスとして挙げられている様々な内容は、経営だけではなく人生という個人的な観点でも応用すべきものだと感じた。 ・利益ありきではなく、利益以上の目的を追求すること ➡金儲けより自分が情熱を傾けられる何かを大切にすること その結果に価値があれば、金は後から付いてくるはず ・基本理念を維持しながら、進化すること ➡自分の中で大切にしている根源的な軸はブラさず、 社会の変化に対応しながら仕事の成果に変化を加えて行く ・社運をかけた大胆な目標を掲げること ➡手の届きそうな目標を掲げても成長できる幅はしれたもの 大きな目標に真摯な姿勢で取り組めば、 自ずと成長にドライブがかかるはず ・大量のものを試してうまく行ったものを残すこと ➡個人で試すには限界があるが、ハナからダメだろうと思わないこと まずはやってみるということが大切 その他にも組織論として大切な内容が多様な分析結果をベースとして散りばめられている良書 本の中で著者も書いていたが、この本に書かれているエッセンスは新しい業界の新興企業についてもすべからく応用できる、普遍の法則なんだろうと感じた
0投稿日: 2012.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在で、始めてこの本を読むとデジャヴを感じるかもしれない。 これは昨今の経営書が意図しているかどうかは不明であるが、似たような内容の本が溢れている。 だが陳腐なそれらと本書が決定的に違う点がある。 よく経営学は後付だと揶揄されることがある。本書も現在の企業の歴史を研究した上での結果である。だが、この研究が有象無象の本とは違う点である。表面の一点を見つめるのではなく(例;ソニーを叩く書籍)流れを汲むことが経営学である。これを実際に行われ、その結果として本書が生まれ、そして評価された。 しかし、ビジョナリーカンパニーの弊害も考慮しなければならない。過去の成功を研究する経営学が現在の主流であるが、この流れを変える違った観点から経営を探ることも必要である。今の経営学にはパラダイムシフトが求められる。 ※違った観点とは、「確固とした経営理念を創造し、イノベーションを行う」このような思考停止とは違うことは理解していただきたい。
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーとは、時の試練を乗り越えてきた真に卓越した企業のこと。 これらの企業の秘密を膨大な比較データから分析して抽出された結果が記述されている。 ビジョナリーカンパニーには偉大なカリスマ的指導者が必要ではなく、すばらしいアイデアも必要ではないという。 一言で言うと、基本理念を維持し進歩を促す仕組みを作ること。 本では「時計を作る」と表しています。 すごいテクニックや魔法があるわけではなく、やるべきことをひたすらやっていくという印象です。 経営者だけでなく中間管理職や社員も読む価値があり、実践可能な内容だと思います。 そして企業だけでなくあらゆる組織で適用できると思います。 今の職場で実践してみようと思いました。 仕事や組織に不満がある人(おそらくみんなだと思いますが)は読むべき本だと断言できます。
0投稿日: 2012.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功しているだけでなく、長く続いているだけでもない業界における超一流企業がなぜ超一流企業たる存在なのか比較対象企業(こちらも十分有名)と比較しながら紐解く作品。ビジョナリーカンパニーの特徴は根本的な基本原理を据え、1.会社が傾きかねない大胆な目標がある2.現状に決して満足せず将来を見据える3.生え抜きの経営陣を育成(時計を作る)するにある。これらの特徴がゆえに一種のカルト的な要素も含んでいる。 また、ビジョナリーカンパニーが実践していることをそのまま実施すればよいわけではない。他のビジョナリーカンパニーで実施されている施策が自社では成功に導かない可能性がある。成功可否は基になっている基本理念次第である。ゆえに何が正しくて何が正しくないかという評価はくだせない。 本書を読みながら自身の会社の最近の施策が本書を参考にしているものが多いことに気づいた。社長が参考にしているのだろうか。 ビジョナリーカンパニーと弊社との差は1.トップが変わっていない2.基礎研究投資が低い3.経営陣が生え抜きでないの3点にある。いずれにせよまだ若い会社なので今後に期待である。
0投稿日: 2012.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織に所属する人間は必ず読むべし。実にイイ本です。ドラッカーの経営者の条件とセットで人に勧めてます。今日から。。。
0投稿日: 2012.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故、この本をこれまで読まなかったのだろう。 せめて学生時代に読んでおけば、あんな失敗はしなかったはず。 とはいえ今だからこそ感じられるものが沢山あるのかもしれない。 ビジョナリーである事がどういうことなのか、やっとしっくり来た気がする。 すべての組織、そして全ての人にとって心に止めるべき原則達。 このタイミングで読めてよかった。
0投稿日: 2012.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの超大企業と、超大企業になり損ねた企業の比較調査。やや後付け的な考察ではあるが、その膨大な調査量は圧巻。 もし経営改善のヒントにしたいなら、good to greatがお勧め。
0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入から結構時間が経ってしまった。すっと頭に入った本。 企業名がアメリカの企業に偏り、少し読み進めたところで、リスト(ビジョナリーカンパニーと比較対象企業一覧)にして時々眺めながら理解した。付録2、は事前に読んでおくべき。 すぐに何かに役立つ感じはしないものの、なるほどと思わせるところは多く、続編(2)も読む予定。 ただ、3や「ビジョナリーピープル」なる著書まで続くとなると、ちょっと迷う。
0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ事例を積み上げそこから示唆を抽出するという手法を忠実に実行し、かなりまとまった内容になっている。良書です。
0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログシリーズで1番インパクトがありました。この本を読んでから、いろんな会社の姿勢に関心が持てました。自社とは一体何か、問いただすきっかけになりました。
0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ20年近く前に出版されているが、文中にあるとおり美女なりーカンパニーであるための原理は普遍のように思われる。いわゆるビジネスのハウツー本にある内容や、ビジネススクールにある経営戦略と相反するような部分も少なくない。出版された時よりも現代のほうが注目すべき部分が多いのではないだろうか。 主に基本理念の重要性について述べられているが、ボリュームが大きい。1/3程度でも充分に伝わるのではないだろうか。ただし、膨大なデータを下にきちんと比較しているからこそのボリューム感と納得感なのかもしれない。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ全米で大ヒットしたビジネス書。内定者研修第2弾の課題図書。 ボーイング、ヒューレット・パッカード、ウォルト・ディズニー、ジョンソン&ジョンソン、ソニー、IBM... これら50年以上繁栄している企業は、その他の企業と比べてどのポイントが優れているのか。-という問いに、著者は膨大な資料・統計をつかって原理原則を発見した。ビジョナリ―カンパニーの豊富な実例を手引きに、読者に示唆を与えてくれている一冊。 400ページもあった割にはすんなりと読むことができた印象が強い。ビジネス書は世に氾濫しているけれど、主張とそれを裏付ける実例とがこれだけ豊富なのは正直驚いた。ソニーなど現在は苦戦している会社もあるが、他の企業以上に基本理念を大事にし、懸命に働く企業であるならば、これからも繁栄し続けていくだろう。勉強になった。タダでもらえてラッキー。星4つ。
0投稿日: 2012.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ先見性のある企業を分析した本。良い会社をつくりあげる参考にもなるし、良い企業を見つける上でも非常に参考になる本。また、自分の働き方をも考えさせられる本だと思う。就職活動にも役立つ。
0投稿日: 2012.01.29
