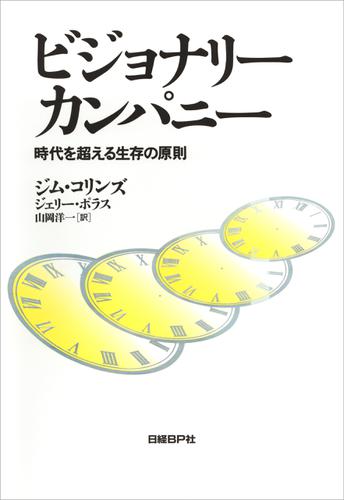
総合評価
(378件)| 149 | ||
| 127 | ||
| 54 | ||
| 12 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネス書の超定番とも言える一冊。著者が定義するビジョナリーカンパニー(≒先見性を持ち、業界で卓越している企業であり、かつ他社から尊敬される企業。)の、他社と決定的に違うポイントが書かれている。そのポイントとは、以下4つである。 ①ビジョナリーカンパニーの創立者や経営者は、時を告げる預言者ではなく、永遠に時を告げる時計をつくる設計者である。(会社の創立者は、自分が死んだあとも会社が継続していく仕組みを作ることが重要ということ。) ②「ANDの才能」を持つ。(例えば、「低コストor高品質」のどちらを取るか迷った場合、両方を実現する方法を創造できる。) ③基本理念を維持し、進歩を促す。 ④一貫性がある。 これらのポイントを、ディズニー、J&J、HPなど誰でも知っている企業を実例にして明快に解説している。経営に興味がある方は一度は読む価値がある一冊。
0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと積読本だったのですがこの年末年始にやっと読み終えました。 一番グッときた部分は第三章「利益を超えて」の中の "基本理念は組織の土台になっている基本的な指針であり、「われわれが何者で、なんのために存在し、何をやっているのかを示すものである」"というフレーズ。 これはやっぱり皆んなが、お客様にっていうのは勿論、自分の子供や、里帰りした時におばあちゃんとかにも言えなければいけないものですよね、本来。 この基本理念を維持することと進歩を促すこと、利益を超えた目的と現実的な利益の追求、これらを両方一緒にやらなければいけない。 そういうことが書かれてるのですが、確かに今のこの時代こそそうなんだろうと思いました。
0投稿日: 2012.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログエクセレント・カンパニーの続編かと思いたくなるくらい、序盤は似通っているような印象を受けた。 中盤から終盤にかけて、やや飽きてしまうようなところもあったが、優良企業に対する思い込みを解消することが出来、読めてよかったと思う。 又、巻末付録の、実際に取ったとされるアンケートも参考になった。
0投稿日: 2012.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「設計者>預言者」 本著は誰から見ても素晴らしい企業(エクセレント・カンパニー)を選び研究するものでは断じて無い。 本著はビジョナリー・カンパニーという社会にとって大きなインパクトを与えた先進的な18の企業に焦点を当て研究したものである。その18の企業に共通する特徴に注目しどうすればそのような企業を創り上げることができるのかを特に追求している。 ここで著者が本著の最後で述べている、周囲の人たちに伝える4つの教訓を引用する。 ①時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ。 ②「ANDの才能」を重視しよう ③基本理念を維持し、進歩を促す。 ④一貫性を追求しよう。 この4つに少しでも興味が湧いた方は是非読むことをおすすめします。
0投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログもはや古典に属するビジネス書。ビジョナリカンパニーに共通なノウハウでなく一般原則を導き出している。 1 時を告げるのでなく時計をつくる 2 ORでなく、アンドを求める 3 基本理念を維持し進歩を促す 4 一貫性を保つ 会社という大きな組織でなく、自分の責任範囲でも適用できると言っている事が好感がもてる。
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログビショナリーな会社ってどんな会社だろうと思って読んでみた。 難しかったので読むのね時間がかかってしまいましたが、読んで満足です。 これを読むと、経営理念を大事にしようと思ってくる。 時を告げるのではなく、時計を作る。 経営者でなくともリーダーというポジションにいる人なら心がけないといけない事だと思う。
0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ時を告げるのではなく、時計を作る。カリスマ性や素晴らしいアイディアにより繁栄をもたらすのでは無く、自身がいなくなったのちにおいても、繁栄が続く仕組みを作る。ORの抑圧に負けることなくANDの才能を活かす。 利益を超えた理念をもつ。自分たちのは何のために存在し、何を成し遂げる為に活動をするのか。存在意義、価値観。 正しい理念などは無く、どれだけ心からそれを信じており、実行しているかが大切。理念にオリジナリティや独自性は必要ない。必要なのは本気度合い。 理念と短期の収益の両方を追う。ANDの才能。基本理念を維持し、進歩を促す。 興奮を掻き立てるような大胆な目標を掲げる。常に挑戦し、成功を確信しながら進める。一人のカリスマ指導者ではなく、組織の体質。BHAGを好む時計を作れているか。 自組織が掲げる基本理念、価値観に厳格であり、社員へ同化を求める。そぐわない社員は切り捨てる。自社へのエリート意識が強い。厳しくイデオロギーを管理すると同時に、同時に業務上の裁量権をものすごく譲渡。 利益を超えた基本理念を維持しながら、同時に興奮するような大胆な目標を掲げ、カルトのような文化を持って挑戦し続ける風土の組織。 進化を促すために、大量のものを試しうまく行ったものを残す。変異を認め、挑戦を促す。ただし、それらは全てカルト的な信仰をされている基本理念をに即していることが必要。そういった挑戦は組織全体から全面的な協力が得られ、賞賛をされるべきである。 基本理念を正しく伝達する仕組みが必要。生え抜きをしっかり育て、常に後継者を意識した経営が必要。 自分自身への要求が極めて高く、常に満足をしない。常に不安感を与え、自己研鑽を推し進める仕組みがあるか。 基本理念は広範囲に細部まで行き届いており、徹底されている。その実現に、全くのほころびがない。 大きな仕事や周囲を巻き込んで行く仕事をするためには、視点の高さは大事。その仕事を魅力的に語ることができるか、という視点が大事。夢を持ち、大義を語り、意思を込めた仕事をすることの面白み。 「自分はこのために働いている」という信念。 持ちたい。 そういった意思を込めた仕事は世の中を変えるダイナミズムを生むだろう。そんな心揺さぶるアツい仕事がしたい。 まず自分の仕事へ魂を込めよう。
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ【リード】 時の試練を乗り越えてきた真に卓越した企業の特徴 【内容】 ○ ビジョナリーカンパニーの選び方 - 有力企業のCEOへのアンケート結果から、50年以上存続している企業 ○ ビジョナリーカンパニーの特徴の抽出方法 - 同時期に設立した同業種の企業との比較 ○ 時を告げるのではなく、時計をつくる - CEOの代が変わっても、継続していける組織にする ○ 基本理念(カルトのような文化) - 基本理念を徹底させ、それを絶対のものとする - 逆に基本理念以外は積極的に変更して進歩を促す = 社運を賭けた大胆な目標(BHAG) = 大量のものを試して、うまくいったものを残す ○ 生え抜きの経営陣 - 基本理念の維持のため、経営陣は生え抜きが適している ○ 決して満足しない 【コメント】 研修で一緒になったT君のオススメ。 基本理念を社内で共有することの大切さを客観的に知ることができる。 この本を読んで、朝会が楽しみになった。 朝会みたいな無駄なものは無くせとのたまっている輩にはぜひこの本を読んでもらいたい。 基本的にターゲットにしている読者は管理職以上のようだが、自分のような平社員が読んでもためになる。 自分を、自分と言う社員が構成する組織と考えることで、この本の考え方を適用できるところがあるからだ。 また、この本を読んでいて気になったのは、アップルコンピュータのことだ。 はたして故スティーブ・ジョブズは、時計をつくることができたのだろうか。 今後の動向に注目したい。
1投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
経営のテクニックではなく、 ビジネスを成功させるための要素をケーススタディから整理している。 経営者だけでなく、 組織のリーダー、またはこれからリーダーになる人は、 まずこういった思想をおさえることが必要。 そのうえで、自らの解釈をつみあげ、 自分のビジネス哲学を形成することが必要だと思う。 ***以下、内容についての自分なりの解釈。**** 前段の崩れた神話は興味深い。 整理すると。。。 ・すばらしいアイディアが、すばらしい会社を作るわけではない ・偉大なカリスマが、偉大な企業を作るわけではない ・偉大な企業は、利益の追求を最大目標としていない ・固定化された『正解』は必要ない(何が正しいかは常に変わる) ・変わっていくべきものと、変わってはいけないものがある(基本理念は変えてはいけない) ・リスクをとらなければ成長はない ・よい企業は、理念を共有したものにのみ心地よい職場となる(理念を共有できなければよい職場にはならない) ・成功には必ずしも最初から綿密な戦略が必要ではない(あれこれ試して、必要なものを残すほうが大事) ・生え抜きの経営トップと、それを支える社内外の知見が必要 ・競争に勝つことではなく、よりよい価値を提供することにフォーカス ・相反する事柄も、それらを超越した上位概念を見出し、全てを包含していくべき ・経営トップに必要なことは先進的発言ではなく、揺るがぬ基本理念にたった発言である また、その上で定義される4つの要点は、経営に携わるものとしてその思想をおさえておきたい。 ・ビジネスの時計を作る 何が起きる、どうなる、という予測も重要ではあるが、 そもそもビジネスをドライブする存在にならなければいけない。 組織をつくり、目標に向かって動かしていくことが必要。 ・「AND」で考える テーゼとアンチテーゼが出た場合に、 上位概念で纏め上げていくことが必要となる。 知識創造の基本的な考え方を持たなければいけない ・基本理念を維持する 社会において、何を実現するのか、何のために行動するのかを 明確にすることが必要となる。 単純な利益至上主義や売上至上主義は表層的な考えに過ぎない。 なぜなら、利益や売上げは、基本理念を実現するための 手段に過ぎないからだ。 また、利益は社会の評価を、 売上げは社会との接点を表す指標でもあるが、 それもまた一側面でしかない。 ビジネスの命運をかけた大胆な目標=BHAGを 基本理念から導き出し、 常に基本理念に向けて行動し続けることが求めらる。 ・一貫性を追求する BHAGを設定し、その達成に向けてカルト的に進んでいくことが必要。 このとき、とにかくためし、そして潔く捨てるものは捨て、 必要なものを残していくことが必要となる。 加えて、基本理念そしてBHAGの達成に向けて、 決して満足することなく、挑戦を続けなければいけない。
0投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故、会社はビジョナリーカンパニーたり得たのか? 1 普遍且つ明快な理念を持つ 2 カルトのように理念の実践に邁進する 3 カリスマに頼らない永続する組織と人作り 永続する会社のみならす、私は人の人生においても、 1 自分の価値観を持つ 2 自分らしくそれに向って邁進する 3 子孫後世に教えや伝統を相続する 応用出来る考え方だと感じた。 昔と今と時代は変われど、不変の法則が。 膨大な調査に基づく仮説思考アプローチ、読み応えある一冊。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ極端な底辺企業と優良企業を比較して考察するのではなく、業界の一番と二番を比較することによって、長い間優良企業として君臨する企業はどのような特徴があるのか、を考察した本。やっぱり大事なのは仕組みを作れる人間になることですね。
0投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーとは 「ビジョンを持っている企業 未来志向の企業 先見的な企業であり 業界で卓越した企業 同業他社の間で広く尊敬を集め、 大きなインパクトを世界に与えつづけてきた企業である。」 こう言われる企業の中に、日本のソニーが入っていて、 戦後のまもない時代、1946年に井深大はボロボロの日本のために 会社を興した際にまずやったことが、企業理念を定め、企業が どういった道を歩むべきかの道筋をたて、儲けではなくまず日本再建を 唱っているいる。 そこがこの本でも評価されているところに、日本人として、社会人として 非常にかっこいいと思うし、自分もそうありたいと強く思わせてくれる 一冊だと思います。
0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1,時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ。 2,「ANDの才能」を重視しよう。 3,基本理念を維持し、進歩を促す。 4,一貫性を追求しよう。
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニー、つまりこの本において優れた企業と位置づける企業に共通している要素は、「カルト的なまでに経営理念が浸透していること」らしい。しかし、理念の浸透は多様性も担保するのだ、と。 理念の実現を目指して専心努力している限りは、性別も年齢も関係ない。こんな会社が、日本にどれだけあるだろう。
0投稿日: 2011.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログTOPPOINTビジネス名著20選より。 真に卓越した企業とそうでない企業との違いとは? 本書は、超一流企業18社とそのライバル企業とを徹底比較し、 長年にわたり際立った存在であり続けるための「源泉」を解明する。
0投稿日: 2011.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニーは変わらない軸を持っていて挑戦的だったりカルト的だったりすることが多い、みたいな話。「時を告げるのではなく、時計を作る」会社だと表現されていた。内容とはあまり関係ないが、黒帯は始まりの証という黒帯の寓話が面白かった。
0投稿日: 2011.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ有名な本なので、すっかり読んだ気になっていた。 あらためて考えてみたら読んだことないと、「ビジネス書の古典を読もう」キャンペーンを実施中なので、読んでみる。 いいこと書いてあるなあ。なんでこれをもっと早く読まなかったのかと思う。 まあ、こういうことはめぐりあいなので、早く読んでいたら「ふーん」で終わりかもしれない。 ただ、BHAGはちょっと疑問は残るな。著者自身が繰り返しエクスキューズしているが、「勝者を取り上げてあとから賞賛している」ということになっていると思う。勝った博打はいいけど・・・ BHAGの存在の大切さそのものは分かる。「だから良くない」ではなくて、もうちょっと掘り下げるべきかと思う。
0投稿日: 2011.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログもし新しい経営陣が、スティーブジョブズが残した(時を告げる)とされる、この先のアップル社の計画を実行するだけならば・・・
0投稿日: 2011.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い本で既にビジョナリーでない会社もあるけど、会社の理念がどれだけ持続する仕組みが練り込まれているかが大切ということ。
0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログサブタイトルは、「時代を超える生存の原則」。 ビジョナリーとは、先見性・未来志向といった意味である。 筆者らがいくつかの条件を設定して選び出した「ビジョナリー・カンパニー」に、共通する項目を探ることで、生き残る企業となるための原則とは何か?を検証する内容の本。 よくある「儲かる会社にするには」といったハウツー本とは異なり、思った以上に面白かった。何より良かったのは、各企業の歴史をきちんと検証した上で、節目、節目におけるトップの経営判断、行動について詳細に記してある点。 一流企業に共通しているだろう、と思ってしまいがちな項目、たとえば「カリスマ経営者の存在」や「ヒット商品」等々、は、実はさほど重要でなく、「ビジョナリーカンパニー」にはもっと違うところに、確かな共通点があるのだ、ということが見えてくる。その共通点とは・・・ それをここでバラすのはやめておくけれど(笑)、それはとてもシンプルなことである。 企業にだけあてはまること、というわけでもなく、一人一人にとっても大切なこと。 今からでも、自身で始められること・・・! ただし、シンプルさは安易さとイコールではない。 安直に真似をしたからといって、このようになれるわけではもちろんない。 それでも、改めて客観的に「大事なこと」を確認することができて、非常に勇気づけられる1冊だった。次作の「飛躍の法則」も、読むのが楽しみ!!
0投稿日: 2011.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ研修が終わったので、再び読書ウィーク。長年の積読本。有名だけど、読んでいなかったので、これから3部作一気読み。 力強い正論には、うなづかされるところがたくさん。決して内容は難しくないんだけど、どこかつかみどころがないような・・・。
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ流石のベストセラーです。着眼点が面白いです。常日頃から、革命期などの有事に活きる人材と平時に活きる人材は違うと感じてます。この考えはこの本でいうと、対応可能な組織(時計)を建築すべきということなのか、個人(時を告げる人=革命家、カリスマ)ではなく、組織で対応すべきということなのか、ちょいと疑問が残りました。これも、『ORの抑圧』ですかね。 『基本理念を維持し、進歩を促す』。初心忘れるべからずですね。
0投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
IBM、ディズニー、メルク、HP、GE、ボーイングなどビジョナリーカンパニーといわれる企業の共通点。 ・基本理念をしっかり持っている。浸透させている。 ・ORではなくAND 排他的ではない考え方 ・変化を促す組織、現状に満足しない ・社員のロイヤリティが高い。エリート意識 ・カリスマガいるわけではない ・BHAG(高い目標)がある。理念にそっている。理念とはわかりやすく、モチベーションがあがる内容。(ケネディの宇宙計画) ・経営者を育てる環境。生え抜き社員を幹部にする
0投稿日: 2011.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ利益は人間に例えると血液のようなもので、血液を増やすために生きている訳ではない、ということでした。しかし、長い。厚い。重い。
0投稿日: 2011.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年読んだ、エクセレント・カンパニーに類似する内容だった。 そのため目新しい発見はあまりなかったが、 カンパニーを自分に置き換えても通用する内容だと思うので、 自分に置き換えて考えを深めていければいいと思う。
0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ1995年に日本語版が発刊された、ビジネス書の中では古典に類するかもしれない名著です。 今まで手に取る機会がなかったのですが、今回やっと読むことができました。 ここでは何世代にもわたって成功を収めた企業を「ビジョナリー・カンパニー」と定義し、同業のうち、成功はしているが、十分に成功していない企業との比較で、ビジョナリー・カンパニーにはどういった特性が備わっているかを調査しています。私たちが陥りやすいミスとして、ビジョナリー・カンパニーの共通点のみを洗い出し、それ以外の企業でもその特性を持っているかどうかを見落とすというのがありますが、注意深くその誤りを排しています。 よく言われる、カリスマ創業者や企業時の大胆な事業モデルなどは、ビジョナリー・カンパニーには必要なかった。むしろ、大胆な事業モデルで一世を風靡した企業は、次の代で評判や業績を大きく落としてしまう傾向となっているようです。 必要なのは、将来にわたって変化することがなく、かつ短期的な利益追求を超える企業理念と、末端の従業員にまで浸透させる企業文化、そして現状に甘んじることなく、成長と変化を繰り返す事業モデルといった部分です。 働く側にとっては、ビジョナリー・カンパニーで働くことは決して楽ではありません。企業文化を心の底から信じることができなければ、やがては居づらくなるでしょうし、成長と変化を常に求められるため、今の成功にあぐらをかいている余裕などないからです。端から見ると、「ブラック企業」のようにも映るかもしれません。 自分としては、ビジョナリー・カンパニーとブラック企業は違うものです。ビジョナリー・カンパニーは企業そのものへの忠誠を誓って働きますが、ブラック企業では経営者への忠誠を誓うことになるでしょう。仕事は楽ではないかもしれませんが、一方は長年培ってきた企業理念の達成、もう一方は目先の利益の達成のためであり、働きがいは天と地ほども違うかと思います。 幸か不幸か、自分はビジョナリー・カンパニーで働いたことはありませんが、企業理念を大切にしていきたいと思うようになりました。 別のときに読んだ『プレジデント』誌の記事(2011.1.17号、P.38)にあったのですが、企業というのはチームプレイ。個人の従業員がいくら個性や能力が突出していても、経営方針や企業理念と相容れなければ、意味がないという指摘もあり、この書籍と同じことを言っているのだと感じました。
0投稿日: 2011.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログコレを読んで企業を志した人は多いと思う。 会社とは、働くとは、会社の目的として目指すものは 様々な答えがココにあると想います
0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・時を告げる人ではなく時計をつくる ・ANDの才能を重視する ・基本理念を維持し、進歩を促す ・大きな目標の追求と環境への柔軟な対応 ・一貫性を追求しよう ・正しいかではなく、理念にかなっているか 今や誰もが知っている先進的大企業(ビジョナリーカンパニー)と他社との比較を通して、ビジョナリーカンパニーがどのように成功していったのか、どのような生い立ちだったのかを紹介。 大きな会社もはじめは小さかったという当たり前のことを思い出させてくれて、自分もいつか仲間入りするぞ!とやる気がわくいい本です。 たくさんの調査や研究をもとに書かれているものの、読みやすく分かりやすい!
0投稿日: 2011.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ洗練された、とはこういう本の事。様々なシチュエーションに当てはまるだけでなく、ビジネスの「本質」が明確に記載されている。
0投稿日: 2011.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の対比が綿密にされておりビジョン浸透の差が明確にされている本。BHAGを築くことが如何に重要かを知ることができる。 ビジョナリーカンパニー視点では私には大き過ぎたため、ビジョナリーパーソン視点で読んだ。結果、人も会社も同じなのではないかと感じた。高い志を持ち、それを遂行させていく気概を持つこと。
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ◇ビジョナリーカンパニーになるためには、基本理念がなくてはならない。また、進歩への意欲を常に維持しなければならない。そして、基本理念を維持し、進歩を促すように、全ての要素に一貫性が取れた組織でなければならない。 ◇基本理念=基本的価値観+目的 ・基本的価値観=組織にとって不可欠の普遍の主義。(文化や経営手法と行動してはならず、利益の追求や目先の事情の為にまげてはならない。) ・目的=単なる金儲けを超えた、会社の根本的な存在理由。(地平線の上に永遠に輝き続ける道しるべとなる星であり、個々の目標や事業戦略と混同してはならない。) ◇当社は正しいことであれば現実的でも可能でもないと思えることに挑戦して、それが現実的であり可能であると証明したい。正しいと信じることをやる。それが成功すれば、それを続ける。それで打撃を受ければ、家屋敷を担保に入れて、一発勝負をかける。(P&Gデプリー社長) ◇当社は確かに、新製品のいくつかに偶然ぶつかっている。しかし、動いていなければ、ぶつかりもしないことを忘れてはならない。 リチャード・P・カールトン(3Mの元CEO) ◇アメリカン・エクスプレスはいくつもの小さなステップを積み重ねることによって、設立当初の小荷物事業から、全く違った事業を展開する企業に変身していった。そして、小さなステップのほとんどは、偶然の機会をとらえたものであり、壮大な事業計画で定められたものではなかった。 <大量のものを試して、うまくいったものを残す> 1.試してみよう、なるべく早く・・・結果がどうなるか正確に予想できなくてもかまうことはない。何かをやる。一つが失敗したら、次を試してみる。手直し、試し、行動し、調整し、動き、前進する。何があってもじっとしていてはダメだ。活発に動けば、特に予想もしなかった機会にぶつかったり、顧客の具体的な問題にぶつかったときに動けば、変異を作り出せる。 2.誤りは必ずあること認める 3.小さな1歩を踏み出す・・・小さな一歩が大きな戦略転換の基礎になりうることを忘れてはならない。 4.社員に必要なだけの自由を与えよう・・・権限分権が進み、業務上の自主性を社員に認めている。 5.重要なのは仕組み。着実に「時を刻む時計」をつくるべきだ。 <一貫性> ◇ビジョナリーカンパニーの真髄は、基本理念と進歩への意欲を、組織隅々にまで浸透させていることにある。(企業の動きの全てに浸透させる一貫性が重要である。) 1.全体像を描く・・・重要なのは、驚くほど広範囲に驚くほどの一貫性を、長期にわたって保っていくことである。 2.小さなことにこだわる・・・ささいな点に言行不一致があると、それを見逃さない。 3.下手な鉄砲ではなく、集中砲火を浴びせる 4.流行に逆らっても、自分自身の流れに従う・・・自社の基本理念と理想こそが現実をとらえる際の指針にすべきだ。 5.矛盾をなくす・・・変えてはならない聖域は基本理念だけである。それ以外のことは変えることもできるし、なくすこともできる。 6.一般的な原則を維持しながら、新しい方法を編み出す <まとめ> 1.時を告げる予言になるな。時計を作る設計者になれ。 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。
0投稿日: 2011.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から読みたくてようやく読みました。 ボリュームがやばい。 会社の良し悪しではなくもっと深い物を感じることが出来る物だと思います。 その中で特に取り入れたいことが2つ。 一つ目は『Andの才能』。今までの決断の部分でorがかなり多かったと思うので、今後直して、もっともっと推進力のある人間に。 二つ目は個人的な進歩を促す仕組み『BHAG』を個人的な物をもっともっと明確にしないと。 一朝一夕で決まる物ではないと思いますけど、とりあえず決め、アクションしなければ。 まずはもう一度読み返し、そしてビジョナリーカンパニー2も読もうと思いました。
0投稿日: 2011.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ黒帯の寓話(P338) めったに与えられない黒帯をとうとう受け取れることになった武道家が、師範の前にひざまずいた。何年にもわたる苦しい修行によって、ようやく、頂点に立つことができるのだ。 「黒帯を受け取る前に、もうひとつ、最後の試練がある」と、師範が言った。 「準備はできています」と武道家は答えた。もう一回、試合をすることになるのだろうと考えていた。「大切な質問に答えてもらわなければならん。黒帯の本当の意味は何なのか」 「旅の終わりです。これまでの厳しい修行に対する当然の褒章です」 師範は押し黙っていた。この答えに満足していないようすだった。しばらくたって、師範は口を開いた。「まだ黒帯を与えるわけにはいかないようだ。一年後に来なさい」 一年たって、武道家は再び師範の前にひざまずいた。 「黒帯の本当の意味は何なのか」「武道で卓越した技を持ち、頂上に達したことを示すものです」 師範は押し黙って、それに続く言葉を待っていた。この答えにも満足していないようすだった。しばらくたって、師範は口を開いた。「まだ黒帯を与えるわけにはいかないようだ。一年後に来なさい」 一年たって、武道家はまた師範の前にひざまずいた。師範は同じ質問を繰り返した。「黒帯の本当の意味は何なのか」 「黒帯は出発点です。つねに高い目標を目指して、終わることなく続く修行と稽古の旅の出発点です」 「そうだ。ようやく黒帯に値するようになったようだ。修行はこれからはじまる」
1投稿日: 2011.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ研修の課題図書として指定されたもの。内容はなかなか面白く、義務的な読書といういやな感じを持たずに済んだ。 この本の中で、「ビジョナリー・カンパニー」というのは、要するに素晴らしい業績を長期に渡ってあげ続けている企業というくらいの意味で、言葉そのものの定義に重要性はない。 筆者(共著だけれども)は、そのビジョナリー・カンパニーとして18社を例にあげ、同一の業界で、同程度の歴史を持ち、かつてはビジョナリー・カンパニーと肩を並べるか、あるいは、それよりも業績が良かった会社を「比較対象企業」としてあげ、「ビジョナリー・カンパニーと比較対象企業の差は、どうやって生じたのか」ということを説明することにより、ビジョナリー・カンパニーが一般的に持っている特性をクリアにする、という方法論をとっている。 筆者はアメリカ人なので、ビジョナリー・カンパニーにあげられたのは主と、してアメリカ企業、例えば、3M、アメックス、ボーイング、GEという企業だ。 結論を簡単に要約すると、ビジョナリー・カンパニーでは、その企業の理念を維持し、更には進歩をとげることが目標として掲げられている。それは、しかし、比較対象企業でも、たいていの場合には同じことが言えるが、ただ、ビジョナリー・カンパニーの場合には、その目標を達成する「仕組」が会社の中にうまくつくられていて、かつ、それが「徹底されている」ということだ。 「仕組」の「考え方」の実例として共通的に見られるものとして、(1)社運を賭けた大胆な目標を持つ(2)基本理念を維持するためにカルト的な文化をもつ(3)試行錯誤を早く繰り返すことが奨励されている(4)経営陣が生え抜き(5)満足しない、安心しない文化をもつ、といったようなことが掲げられている。 こう書くと、簡単なことのように思えるが、それらを仕組としてうまく設計し、ビルトインすること、それらを徹底すること、は簡単な話ではない。結局は、科学的な(あるいは有効な)努力を組織として徹底・継続する、ということだ。原則は簡単(少なくとも理解しやすい)のだけれども、実際に実行するのは大変だよ、ということだ。
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書の世界で「不朽の名著」とされる本書。10年以上たっても本屋では平積みだし、電車の中で大事そうに読んでいるビジネスマンも多い。そんなところに興味をもって読み始めた。 ビジョナリーカンパニーとは「濃い会社」なんだろうな、と思う。自社のアイデンティティに強いこだわりを持っていて、それを何十年も語り継いでいく。こだわりは強いが時々の変化に対しては間違えない。米国企業が多く実感に乏しいのだが、日本代表のソニーにしてみても(最近は普通の官僚的な会社になったとのボヤキを聞くようになったが)、入社するには(できるとしたら)ちょっと勇気のいる会社だ。 米国企業というとドライな人事慣行、資本の論理優先でM&Aを多用、というイメージがあるが、ビジョナリーと尊敬すべき企業には釜の飯型で内部育成重視のベタな企業が並ぶ。なればこそ、今自分のいる会社に愛社心をもち、芯の強い会社になるよう努力することが王道なんだと気づく。 読み進めながらビジョナリーカンパニー自体の魅力だけでなく、膨大なフィールドワークで採取された「ビジョナリーな」経営者たちの言葉に惹きこまれていく。二巻以降は図書館にするけど、読み進めていきたい。
1投稿日: 2011.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョナリー・カンパリーとは、ビジョンを持っている企業、未来志向、先見的な企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業。 ビジョナリー・カンパニーは組織であり、商品のライフサイクルを超え、優れた指導者が活躍できる期間を超えて、ずっと繁栄し続ける。 ・基本理念と高い要求にぴったりと合う者にとってだけ、素晴らしい職場。うまく適応して活躍するか、病原菌が何かのように追い払われるのどちらか。存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、厳しい基準に合わせようとしなかったり、合せられない者には、居場所はない。 ・企業として早い時期に成功することと、ビジョナリー・カンパニーとして成功することは、逆相関。起業し、ビジョナリー・カンパニーを築きたいが、「素晴らしいアイデア」がないため、一歩を踏み出せないのは、素晴らしいアイデアの神話という重荷を肩から下ろすこと。素晴らしいアイデアを見つけてから会社を始めることにこだわらない。 ・世間の注目を集めるカリスマ的スタイルは不必要。製品について素晴らしいビジョンを考えたり、カリスマ的指導者になろうと考える時間を減らし、組織についてのビジョンを考え、ビジョナリー・カンパニーとしての性格を築こうと考える時間を増やす。 ・安心感は、ビジョナリー・カンパニーにとっての目標ではない。ビジョナリー・カンパニーは不安感をつくり出し(自己満足に陥らないようにし)、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す強力な仕組みがある。 ・ビジョナリー・カンパニーになるには、昔ながらの厳しい自制、猛烈な仕事、将来のための絶えざる努力がイヤというほど必要。 ・権限を委譲し、結果に責任を持たせる。従業員にその仕事をする能力が明らかにない場合は、その従業員にできる仕事を見つけるか、その場で解雇する。 ・時計なしに時を告げる人がいた。時を告げるだけでなく、自分がこの世を去った後も、永遠に時を告げる時計を作ったら、もっと驚くべきこと。カリスマ的指導者は、時を告げる。いくつもの商品ライフサイクルを通じて繁栄し続ける会社を築くのは、「時計をつくる」こと。 ・会社を究極の作品と見る。製品ラインや市場戦略について考える時間を減らし、組織の設計について考える時間を増やす。時を告げるために使う時間を減らし、時計を作る為に使う時間を増やす。 ・ビジョナリー・カンパニーは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことをはっきりさせているので、自社の厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地は少なくなる傾向がある。企業の考え方を心から信じて、献身的になれるのであれば、本当に気持ちよく働けるし成果も上がる。しかし、そうでないのなら、いずれ辞めていくことになる。病原菌か何かのように追い払われる。白か黒がはっきりしており、カルトのよう。 ・従業員に権限を与えて、分散型の組織をつくりたいと考えている企業は、理念をしっかりさせ、従業員を教化し、病原菌を追い払い、残った従業員にエリート組織の一員として大きな責任を負っているという感覚を持たせる。適切な役者を舞台に立たせ、正しい考え方を教え込み、その上で、状況に応じたアドリブを使う自由を与える。基本理念を中心に、カルトのような同質性を求めることによって、企業は従業員に実験、変化、適用を促すことができ、そして何よりも、行動を促すことができる。 ・ノードストロームでは、基本的な価値と基準を守ってさえいれば、仕事を進めるために何をやってもいい。 ・失敗は当社にとって最も大切な製品 ・多数の実験を行い、機会をうまくとらえ、うまくいったものを残し、うまくいかなかったものを手直しするか捨てる ・採用するアイデアは本質的に新しいものでなければならない。社会のニーズに合致し、まともな問題を解決するもの。いくら革新的でも、製品にならないもの、いつか誰かが用途を探し出すはずのものには、3Mは興味を持たない。ポストイットの開発には偶然の積み重ねという部分があったとしても、その開発を可能にした3M の環境は、偶然の産物ではない。 ・進化による進歩を促す5つの教訓 1. 試してみよう。なるべく早く 2. 誤りは必ずあることを認める。 3. 小さな一歩を踏み出す:何か革新的なことをやりたいのであれば、実験する許可を求めるのが最善の方法。 4. 社員に必要なだけの自由を与えよう 5. 重要なのは仕組みである。着実に時を刻む時計を作る(優秀な技術者として認められたいのなら、自分の技術を社内全体に広める) ・P&G は最高の人材、製品、マーケティング組織を持っているので、P&G の最高のもの同士を戦わせる。市場に十分な競争がないのであれば、内部で競争する仕組みを作る。 ・ボーイングは、管理職に、競争相手の立場に立って、ボーイングを壊滅させる戦略を立案する。競争相手が利用できるボーイングの弱点はどこにあり、どのような強みを利用し、どの市場なら簡単に進出できるか?こうして作られた戦略に基づき、とるべき戦略を考えていく。 1. 全体像を描く:ビジョナリー・カンパニーは基本理念を維持し、進歩を促すために、制度、戦略、戦術、仕組み、文化規範、象徴的な動き、CEO の発言全てを何度も繰り返す。 2. 小さな事にこだわる:従業員は会社と事業の、小さな細部に取り組んでいる。ウォルマートが一番下のレベルの従業員にも部門の財務報告書を渡しているのは、「会社のパートナーであり、当社は皆さんが自分の部門を自分自身の小さな事業だと考えて経営するよう願っている」というシグナルを送っている。従業員は職場環境にあるシグナルなら、全てを認知し、自分がどのように行動すべきかを考える材料にする。従業員は小さな事を見逃さない。ささいな点に言行不一致があると、それを見逃さない。 3. 下手な鉄砲ではなく、集中放火を浴びせる:ビジョナリー・カンパニーはいくつもの仕組みや過程を互いに強化しあい、全体として強力な連続パンチなるように仕組みや過程をもつ。 4. 流行に逆らっても、自分自身の流れに従う:「これは良い方法なのか」ではなく、「この方法は当社に合っているのか、当社の基本理念と理想に合っているのか」。 5. 矛盾をなくす 6. 一般的な原則を維持しながら、新しい方法を編み出す:ビジョナリー・カンパニーになるためには、基本理念が必要。また、進歩への意欲、基本理念を常に維持し、進歩を促すように、全ての要素に一貫性がある。 ・一貫性を達成する作業は終わりのない過程。矛盾が出てきたら、早くなくす。矛盾はガン細胞と考える。組織の全体に広がらないうちに、早く切除する。 <引用> ・起業家のようなやる気と創意工夫がない者は、理念を受けつけない者と変わらないほど、失敗する確率が高い。 ・顧客の要求に従っていけば、基本理念から離れてしまう場合、顧客の要求を無視する。顧客に密着するのは正しいが、それによって基本理念を犠牲にしてはならない。
1投稿日: 2011.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
原文:Successful Habits of Visionary Companies Used for Claiming PDU of PMP(Applied PDUs 26Dec2016 - 26Dec2019) レビューは以下のリンクにて。 http://mutsukisetsura.blog137.fc2.com/blog-entry-67.html
0投稿日: 2011.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログスミスの本棚で紹介されていたので読んでみました。今まで読んできた経済書で述べられている内容とは大きく異なる視点の内容で興味深く読みました。膨大な対象企業の調査にも関心しましたが、一番驚いたのは、当初抱いていたカリスマによる経営が長期成長の源泉と思っていたのですが、違ったことです。基本理念や高い目標については、素直に理解できました。
0投稿日: 2011.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は良かった。 データに裏付けられた、ビジョナリーカンパニーの条件。 何らか、自ら組織的に行動しようと思うなら、 持っておくべき知識だと思う。
0投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ最良経営指南書のひとつ。自分にはまだ早いかな…と思わせるが、組織の如何なる階層でも適用可能な、示唆に富んだ内容です。一度でなく、読み返すほどに発見のある良書。
0投稿日: 2011.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ダイヤモンド社 10年後にあなたの本棚に残るビジネス書100 神田正典+勝間和代」(2008年) 掲載図書】 【仕事に効く!人生が変わる! すごい本。Index(インデックス) (日経BPムック)(2011年) 掲載 本】 【日経ビジネス Associe 今こそ読むべき本 2011年 5/17号 掲載本】
0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーに勤めるのは、きわめて同質的なグループや組織に加わるようなもの。企業の考え方を心から信じて、献身的になれるのであれば、本当に気持ちよく働けるし、成果も上がる。しかし、そうでなければ、たぶん失敗し、みじめになり、居所がなくなり、病原菌かなにかのように追い払われる。
0投稿日: 2011.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ・時を告げるのではなく、時計を作る ・「ANDの才能」を重視する ・基本理念を維持し、進歩を促す ・社運を賭けた大胆な目標(BHAG)を掲げる ・カルトののような文化を作る ・大量のものを試して、うまくいったものを残す ・生え抜きの経営者を育てる仕組みを作る ・決して満足しない ・全ての要素に一貫性を持たせる 時代を超え、商品のライフサイクルを超えても、社会に確固たる地位を築き、広範に影響を与え続ける企業、ビジョナリーカンパニーを創るにはどのような仕組みを創れば良いかが解説されています。 会社を作りたい!と思っていなくとも、一社員として参考にすべきと思う要素も多々ありますし、人間関係の構築などにおいても参考になるんじゃないかと思います。 なので皆さん是非どうぞ。
0投稿日: 2011.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ先験的な企業とは何か?企業にとって大切なことは何か?これまで抱いていた"良い"企業のイメージが変わり、はっきりと正確な事実を受け取ることができた。基本理念を維持し、進歩を促し、長期的に継続可能な企業活動にとってのエッセンスが詰め込まれたレポートであった。利益を第一の目標とせず、企業理念を叶えるための活動を通して副産物的に得る事ができる利益。これからの自分の行動がどうあるべきか?企業の理念に沿った仕事が出来ているかを振り返るきっかけとなった。これからいいろんな場面で悩む事があると思う。その時は理念に立ち返り、自分を見つめ直してみたいと思う。この作品は1995年の出版であった。『ビジョナリーカンパニー2』には何かが書かれているか?今の時代をより生き生きと生きて、仕事を楽しんでいきたいと思った。
0投稿日: 2011.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ評判通り面白い本でした。 とても地味ですが底力のある理屈とデータ分析、 納得させられましたよw。 「カルト的」とか「時計」とか「理念」とか それぞれわかりやすくてユニークなキーワードも この手のジャンルは良書じゃないと眠くなりますよね…
0投稿日: 2011.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
永続的に価値を提供し続ける企業を事例を元に分析している本。 ・ワンマン経営者は必要でなく、有能な経営者を生み出す仕組みを持っていること ・基本理念を持っていること ・一貫性を持っていること ・常に新しいものに挑戦し、生み出す仕組みを持っていること などが条件に当てはまると説いている。 何度か見直して読む価値がある本。 皆が働いている企業はどうでしょうか。
0投稿日: 2011.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いい会社ってなんだ?に対して「ビジョナリー」かどうかという目線で研究を行なっている著者。 確かに、売上規模では図れない価値ってあるよな、と納得の内容です。 また、訳者が上手なのか、英訳本であるにも関わらずとてもわかりやすく読みやすい文章でした。このあたりは、先日読んだ「数学で世界を操る〜」とは大違い。1週間弱でさらっと読めました。 本書がくり返し述べる大事な概念は以下の4つ。 1.時を告げる予言者になるな。時計を作る設計者になれ 2.「ANDの才能」を重視しよう 3.基本理念を維持し、進歩を促す 4.一貫性を追求しよう ビジョナリー・カンパニーはカルト的な性格がある、ということと、万人にとって働きやすい環境ではない、とう考察が面白いです。 この本を読むと、会社を作って育てていくっていうのは面白くてやりがいがあることなんだろうな〜と思います。(自分がそれをやりたいかは別として)
0投稿日: 2011.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者視点だけでなく、一社会人としても 有用な内容多数。名言というか目から鱗の 内容多数であり、さすがというところ。 時間できたら他シリーズも読んでミマス!
0投稿日: 2011.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本を読む目的】企業選びの際に役立てたる。 【レビュー】 ビジョナリー・カンパニー(卓越した企業、SONYとかジョンソン&ジョンソン)は他の企業とどう違うのか、そこからビジョナリー・カンパニーの作り方のヒントを教えてくれる本。 この本を読んだ目的が「企業選びの視点を得ること」だった自分にとっては、今一つこの本の良さを活かしきれなかったように思う。 ただ、理念が行き渡っている会社かどうか、というのを会社選びの軸の一つとして持とうと思った。
0投稿日: 2011.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わすと知れた名書。 経営者としてのマインドをぶれないものに支えてくれる本。 企業経営・組織運営で悩んだ時のためにずっと本棚に置いておきたい。 「ANDの才能」で自由に物事を考える、 利益は会社経営の正しい目的ではなくすべての正しい目的を可能にするもの、 どこにでもある会社で働いていると思ったらどこにでもいる会社になってしまう、、、 どれも当たり前の事といえばそうかもしれないが、見失いがちなことである。そんな経営の本質がまさにここにあると言えるのではないか。
0投稿日: 2011.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功し続けているビジョナリーカンパニーの特徴を研究し、明らかにした本。 2を先に読んだが、こちらの方がより広範囲な企業に当てはまるように思え、大変興味深い。 経営学の教科書で重視されている部分と共通する所が多くあり、その理由をより理解できる本である。
0投稿日: 2011.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
個人も組織も哲学が必要である。 ビジョナリーカンパニーたちはそれぞれの組織哲学似基づき毎日毎日新たな挑戦を繰り返している。 経営者は哲学者であるとおもう、そして組織はその哲学を実践する存在。 ビジネスで人生を充実させたいと思うすべての人が必読すべき一冊。
0投稿日: 2011.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョンの重要性と、それを仕組み化する重要性を改めて理解した。 TOPは時計を刻む人になるのではなく、時計を作る人であるべきで ビジョンに基づいて仕組み化し、環境を整える。 非常に奥が深い内容だったため、改めてアウトプットしたいと思う。
0投稿日: 2011.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーシリーズは、私も読了しました。なんか、これと、カーネギーははずせない感じがして。(マイク)
0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1.時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。 どれも、心に残る言葉です。 15年以上前の本だけど、今後益々大切な考え方であり、 自分の今後にもとても参考になりました。 35歳以上で、管理職の方、またはそれを目指す方には 必読かと思います。
0投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ビジョナリー・カンパニー』3部作の第一作目。名著。 本書の最後のほうで、本書の重要なポイントを4つ挙げている。 1.時を告げる予言者にはなるな。時計をつくる設計者になれ。 2.「ANDの才能」を重視しよう。 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性を追求しよう。
0投稿日: 2011.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ強力な企業を超える、偉大な企業の秘密とは。 極端な結論にちょっと引く部分もありながら、「たしかに」とうなづく部分も。 思い込みやカンにとどまらず、独自調査で結論を導きだす。 ビジネス書はこうでなくっちゃ。
0投稿日: 2011.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代が変わっても、常にリーディング・カンパニーとして君臨しているビジョナリー・カンパニーがどのような性質を持っているのかについて説明している一冊。「時を告げる」企業ではなく、「時計を作る」企業がビジョナリー・カンパニーである。 ビジョナリー・カンパニーには大きく分けて、2つの特長がある。ぶれない「基本理念」と「進歩を促す仕組み」があることである。 基本理念とは、会社の核となる部分であり、不動のものでなければならない。ボーイングであれば「航空業界のパイオニアになる」であるし、ヒューレット・パッカードであれば「技術の進歩に貢献する」である。会社はこの核となる基本理念を中心として、人を集める。また、必要に応じて、基本理念以外の部分を全て変えても良いという覚悟を持たなければいけない。 「進歩を促す仕組み」とは、経営理念を…。具体的には、基本理念に基づいた社運をかけた大胆な目標(Big Hairy Audacious Goals)を持つことや、基本理念が身にしみている生え抜きの経営陣を持つこと、基本理念を中心としたカルトのような文化を持つことである。 結論としては、ビジョナリーカンパニーとなるためには、核となる「基本理念」を定めて、そこに全員が力をつぎ込めるような環境を、つまり「進歩を促す仕組み」を作ってあげる必要がある。
0投稿日: 2011.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営にはビジョンが必要。 経営哲学を持って、社員、社会の共感を得て会社を正しい方向に導き、成長させて行くことが経営者の責任である。 成功した経営者は、実は泥臭い努力を数多く積み重ねてきた。ありとあらゆる可能性を数多く試み、その中から可能性のあるものを選択してきたから、今がある。 会社は、社会への貢献でその存在価値が問われる。 とかく批判されがちな、利益優先の考え方、しかし会社は利益を上げなければ社会に存在して行けない。 社会に存在できなければ社会貢献ができない。 社員はそのことを理解し、目先の利益をも貪欲に追い求めなければならない。 会社は、少なくともその業界のトップ2以内でなければならない。3番以下は淘汰の運命にある。 成功した会社とは、大きな利益を得た会社ではなく、長く社会に存在している会社である。
1投稿日: 2010.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年も残り少ないですが、今年最も衝撃を受けた本はこれですね!発売時、いやあと10年早く読んでおけばよかったと思いました。駆け足に読んでしまったので、年内にもう一度よみたいです。
0投稿日: 2010.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーと呼ばれる会社が具体的なアイディアをまったく持たずに設立されているものがある点が驚きだった。ソニーが当初は炊飯器や電気座布団を作っていたことも知らなかった。ただ設立時の理念が明確に定義され、社員の気持ちが1つになった時に、BHAGが達成されるのだと感じた。本書の内容はチームマネジメントにも役に立ちそう。 1.時計を作る設計者になれ。 2.ANDの才能 3.基本理念を維持し、進歩を促す。 4.一貫性の追求
0投稿日: 2010.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界を代表する企業はそのほとんどがアメリカの企業であり、しかも19世紀や20世紀初頭から長年続いているという企業が数社存在します。 その中から18社を選び出しビジョナリー・カンパニーと名づけ調査をしたレポートが本書です。 このビジョナリーカンパニーに共通するものは見習うべき点が多々あります。 先日野村克也監督が東北楽天イーグルスを退任した際、「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すは上」という中国のことわざを引用していました。 成功する人、企業には共通する考え方があるようです。
0投稿日: 2010.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリーカンパニー/ビジョナリーカンパニー2まで読み終わって、レビューを書いてます。 偉大な企業と、そうでない企業の違いはなにか?ということで、その対象となる偉大な企業と似通った事業をしているがそこまで至らない比較対象企業とを比べて、偉大な企業に共通するものを洗い出している内容です。 Ⅰが偉大な企業とはどんな特徴があるのかというものを分析したものに対し、Ⅱは普通の企業が偉大になるためにどういったことを取り組んでいったかを分析したものになってます。 話の流れとして、とある発想から論証するものではなく、データを基に考察と結論につなげているためかなり説得力を感じます。個人的にはⅡの方がためになりました。 僕はこの作品を企業といった組織論として見るよりは、一個人として活用できないかという見方をしてました。実は自己啓発としての手段としても有効なんじゃないかなという感想です。 自分の核となるものを持って、大きな目標を設定し、自分はできると思ってひたすら邁進する。一言でいうとこんな感じですかね。 様々な企業が紹介されてますが、その基本理念は本当に会社によって様々でした。様々な考え方の企業がその思想に邁進して飛躍を遂げています。これを個人に置き換えた場合・・・ 周りの評価に左右されることなく自分らしさを追求したらいいのかなと勝手に解釈して、何となくすっきりした気持ちになりました。
0投稿日: 2010.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログどちらもあきらめないこと(ANDの才能) すごいアイディアがあるから成功するんじゃない。 最高の作品は製品じゃない、会社だ。
0投稿日: 2010.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ刺激的だった。 素晴らしい企業、組織、経営者、価値観を知った。 気味の悪いことに、読書中、それを実践する様子を思い描いては、ゾクゾクすることを繰り返してしまった。 特に、印象的だったのが、この3点。 ビル・ヒューレットとデービッド・パッカードの逸話集 ノードストロームのサービス ゼネラル・エレクトリックの掲げた目標 アメリカンエキスプレスの基幹事業の生い立ちも意外で、面白かった。 全てを記憶して取り入れるには、心に残ることが多すぎる。 なので1点だけ、重要で、習慣化すべきポイントを絞ろうと。 ・欲張る ORの抑圧をはねのけ、ANDの才能を活かす 取捨選択じゃなくて、基本方針に沿うものは勝ち取ろう。 状況による、という考えはしない勇気と覚悟を持つ。
0投稿日: 2010.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰も大人にならない世界の作り方 - 読んだものまとめブログ http://t.co/0szFTkN via @sadadad54
1投稿日: 2010.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョンと信念の必要性。二冊目の飛躍編も読んでみたい。これはあくまでビジョナリーカンパニーの概要といえます。
0投稿日: 2010.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ働く人ならば読んだ方が良い本かと。32才の今なら、働く中で考えたことと重なる部分多く『体系書』と思えるが、20才くらいならどうなんだろうか。少なくとも私なら『知識』で終わってただろうなと。
0投稿日: 2010.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一章 最高のなかの最高 第二章 時を告げるのではなく、時計をつくる 第三章 利益を超えて 第四章 基本理念を維持し、進歩を促す 第五章 社運を賭けた大胆な目標 第六章 カルトのような文化 第七章 大量のものを試して、うまくいったものを残す 第八章 生え抜きの経営陣 第九章 決して満足しない 第十章 はじまりの終わり
0投稿日: 2010.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人として働いて行くうえで、考えかたの基盤になった。 仕事をするうえで、常に念頭に入れておきたい理念がつまっている。
0投稿日: 2010.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ時を告げるのではなく、時計を設計し ANDの考え方を維持し、 基本理念を持ち、進歩を促進し、 一貫性を持つ。 どんな企業にも言えることだと思う。 一番印象に残ったのは 「基本理念は設定するのではなく、内側から見つけるものだ。」 というフレーズ。
0投稿日: 2010.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログかの経営本名作ビジョナリーカンパニーを読み終わった。 “時を告げる預言者になるな。時計をつくる設計者になれ。” 数多グッドカンパニーとビジョナリーカンパニーを分ける差異はどこにあるのか。本書が突き止めた唯一の真理はつまるところここにある。 どんなときも時間を正確に把握している天才がいたとする。その人に時間を聞けば正確な答えが返ってくる。 けれど経営という視点から見れば、時を告げる一人の”天才”よりも、みんなが使える時計という”仕組み”の方が圧倒的に価値がある。 何十年も業界のトップをひた走り続けている企業は、要するにこの仕組みが素晴らしく充実しているがゆえに、ナンバーワンなのである。 だけど僕は思った。 時計のような目に見える物を作るのと、組織など目に見えない仕組みを作るのとでは勝手が違う。 僕は小さいころこんなことを考えていた。 小学生が遠足などで一列に並んでいるとき、先生が生徒に「帽子をかぶりなさい」という指示を伝えたいとする。 先生は、 「『帽子をかぶりなさい。』後ろに伝えて。」 と先頭の生徒に言うだろう。 すると先頭の生徒は、 「帽子をかぶりなさい。」 と2番目の生徒に伝える。 すると2番目の生徒は、 帽子をかぶるのだ。 僕の言いたいことが分かるだろうか。先生が「『帽子をかぶりなさい。』後ろに伝えて。」と言った場合、生徒が額面通りにその言葉を受け取ったとするなら、「帽子をかぶれ」という命令は生徒2人までしか伝わらないのだ。 そこで先生が、 「「「帽子をかぶりなさい。」と後ろに伝えて。」と後ろに伝えて。」 と言ったとする。 すると先頭の生徒は、 「「帽子をかぶりなさい。」と後ろに伝えて。」 と2番目の生徒に伝える。 すると2番目の生徒は、 「帽子をかぶりなさい。」 と3番目の生徒に伝える。 すると3番目の生徒は、 帽子をかぶる。 ここで終わり。 つまり生徒が額面通りに言葉を受け取った場合、先生は「帽子をかぶりなさい」というメイン情報の後ろに「後ろに伝えて」という情報伝播のためのメタ情報を生徒の人数分つけ加えなくてはならないわけだ。 もちろん先生が全生徒に聞こえるようにでかい声で命令すれば済む話だ。だけど僕が言いたいのは、膨大な量のメタ情報を不随するにしても、でかい声で命令するにしても、それを実行すること自体が実際の組織マネジメントの現場では難しいのだろうということだ。 このあいだリクルート社員が大量に辞職したニュースで、リクルートもかつてのようなベンチャー精神が失われつつあるという記事を見たことがある。 リクルートでさえもあの規模になるとあそこまでの決断をしなければ新鮮な組織風土を保てないのだろう。 少し気を緩めれば腐敗の影が忍び寄るのが人間の性なんだ。 それでは、社員全員が同じ方向を向くにはどうすればいいのだろうか。 経営者がメタ情報を大量に付随して命令するだとか、とんでもなくでかい声で命令するしかないのだろうと僕は思っている。 より末端の社員にまで浸透するようなメッセージをリーダーが発することができるか。 つまり、経営者にカリスマ性は必要だということ。 (本書は経営者にカリスマ性は必ずしも必要ない、むしろ足枷になる場合が多いと主張する。) 本書では、理念の明文化などがキーワードにあげられているけど、僕は、あくまでも僕は、規則のように書かれている言葉よりも、人間の発する言葉の方が心を動かされる。 大企業にはもちろん優秀な人材が集まるので、自発的に企業理念など意識して行動ができる人が多数いる。だけど、肝心の優秀な人材を競合に奪われてしまっては、明文化された理念などあっても絶対にうまくいかないと思う。 事実ピックアップされている企業は、新規参入の難しい業界が多い。そういった業界では優秀な社員を囲い込みやすい。 逆に新規参入の容易なインターネット業界においては必ず経営者のカリスマ性が重要になってくると思う。
1投稿日: 2010.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーとは何か。 本書冒頭では、 「ビジョンを持っている企業、未来志向の企業、先見的な企業であり、業界で卓越した企業、同業他社の間で広く尊敬を集め、大きなインパクトを世界に与え続けてきた企業」 と記されています。 それではビジョナリー・カンパニーになるためにはどうすればいいのか。 本書はビジョナリー・カンパニーと優良企業であるがそうでない企業を比較し、 なぜビジョナリー・カンパニーとなったのかをまとめています。 それらを比較して発見された驚くような発見、意外な発見を、 「十二の崩れた神話」として以下のようにまとめられています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 十二の崩れた神話 1.すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。 2.ビジョナリー・カンパニーには、ビジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である。 3.とくに成功している企業は、利益の追求を最大の目的としている。 4.ビジョナリー・カンパニーには、共通した「正しい」基本的価値観がある。 5.変わらない点は、変わり続けることだけである。 6.優良企業は、危険を冒さない。 7.ビジョナリー・カンパニーは、だれにとってもすばらしい職場である。 8.大きく成功している企業は、綿密で複雑な戦略を立てて、最善の動きをとる。 9.根本的な成功を促すには、社外からCEOを迎えるべきだ。 10.もっとも成功している企業は、競争に勝つことを第一に考えている。 11.二つの相反することは、同時に獲得することはできない。 12.ビジョナリー・カンパニーになるのは主に、経営者が先見的な発言をしているからだ。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 経営者に一番必要なことは、素晴らしいアイディアを出すことでもなく、素晴らしい製品をつくることでもなく、素晴らしい会社をつくることだ。 良い社員・良い製品は会社が生み出す。 読んでいて、本書で一番重要なのはこれだと思いました。 驚かされることばかりでとても勉強になります。 内容を忘れないうちに2巻、3巻も読む予定です。
0投稿日: 2010.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業したいとか、経営に携わるなら必読でしょうか。 アイディアを持って会社を始めるのは悪いことかもしれない ビジョナリーカンパニーに社外CEO少ない 「自社ビルを持っている」必要条件と十分条件ですね。 時を告げる人から時計を作る人へ アイディアは諦めるが、会社は絶対に諦めない GE コフィン ORの抑圧(って何?) ソニーの理念は内外で簡単に手に入る 90ページまで
0投稿日: 2010.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ豊富なデータに裏付けられた丁寧な調査といい、それを元にして特に重要で普遍的な法則を導き出す論理展開の見事さといい、この先も長い年月に耐えて残り続けるであろう名著だと思う。 この本が面白いのは、膨大な資料の中から、「これこそがビジョナリー・カンパニーだ」と言える企業を慎重に選び出しただけではなく、それと同じ業種で、とてもよく似た環境や条件を備えながら、「しかしビジョナリー・カンパニーとは言えない」比較対象企業を、それぞれ対応させる形で選び出している点だ。 比較対象の材料に選ばれるほどだから、それらの企業にしても、ダメな会社というわけではなく、世間的には一流の企業と認知されている会社ばかりだ。しかし、何百年という時代を生き残るであろう「超一流」の会社と比べると、何かが足りない。 この「比較対象企業」があることによって、ビジョナリー・カンパニーが、単に優秀であるというだけではなく、いかに特異な存在であるかということがよくわかるようになっている。 綿密な調査に基づく、ビジョナリー・カンパニーの説明を読むほどに、その実態には、一般的にビジネススクールで教えられているような「ビジネスの常識」とはかけ離れた点が多いことに驚かされる。 その要素を丁寧に掬いとって、誰にでも理解出来る形でシンプルな言葉にまとめていることこそが、この本のすごい点だと思う。 重要な点は、ビジョナリー・カンパニーが「組織」であることだ。個人としての指導者は、いかにカリスマ性があっても、いかに優れたビジョンを持っていても、いつかはこの世を去る。(p.3) ビジョナリー・カンパニーは、その基本理念と高い要求にぴったりと「合う」者にとってだけ、すばらしい職場である。ビジョナリー・カンパニーで働くと、うまく適応して活躍するか、病原菌か何かのように追い払われるかのどちらかになる。その中間はない。カルトのようだとすら言える。(p.14) ビジョナリー・カンパニーは「OR」の抑圧で自分の首をしめるようなことはしない。「ORの抑圧」とは、手に入れられるのはAかBのどちらかで、両方を手に入れることはできないという、いってみれば理性的な考え方である。しかし、ビジョナリー・カンパニーは、安定か前進か、集団としての文化か個人の自主性か、生え抜きの経営陣か根本的な変化か、保守的なやり方か社運を賭けた大胆な目標か、利益の追求か価値観と目的の尊重か、といった二者択一を拒否する。そして、「ANDの才能」を大切にする。これは、逆説的な考え方で、AとBの両方を同時に追求できるとする考え方である。(p.16) わたしたちは疑問を持った。「ビジョンのある指導力」が、卓越した組織の発展に欠かせないのだとすると、3Mのカリスマ的指導者はだれだったのかと。わたしたちは知らなかった。非常識なのだろうか。3Mは、何十年もの間、広く尊敬を集め、畏敬にも近い念を持たれてきたが、現在のCEOや、その前任者、さらにはその前任者の名前を知っている人は、ほとんどいないのではないだろうか。 3Mは、ビジョナリー・カンパニーとされることが多いが、ビジョンを持ち、世間の注目を集めるカリスマ的指導者の典型のような経営者がいるようにはみえないし、過去にいたようにもみえない。(p.18) ビジネス・スクールでは、経営戦略や起業に関する講義で、何よりもまず、すばらしいアイデアと、綿密な製品・市場戦略を出発点とし、次に「機会の窓」が閉まる前に飛び込むことが大切だと教えている。しかし、ビジョナリー・カンパニーを築いた人たちは、そのように行動したわけでも、考えていたわけでもなかったことが多い。創業者たちの行動をひとつひとつ見ていくと、ビジネス・スクールが教える理論に反するものばかりだ。(p.46) F・スコット・フィッツジェラルドによれば、「一流の知性と言えるかどうかは、二つの相反する考え方を同時に受け入れながら、それぞれの機能を発揮させる能力があるかどうかで判断される」。これこそまさしく、ビジョナリー・カンパニーが持っているの能力である。(p.74) ノードストロームを見ていくと、アメリカの海兵隊を思い起こさせる。ノードストロームでは管理と規律が厳しく、基本理念に順応できない者、順応する意志がない者は、すぐにはじき飛ばされる。しかし、一見矛盾しているようだが、起業家のようなやる気と創意工夫がない者は、理念を受け付けない者と変わらないほど、失敗する確率が高い。(p.233) ウォルマートには、先を読む有能な戦略家がいたように見えるが、これはちょうど、種が綿密な計画のもとに創造されたように見えるのと同じなのだ。同社のある取締役がわたしたちのインタビューで語っている。「当社のモットーは、『なんでもやってみて、手直しして、試してみる』だ。どんなことでも試してみて、うまくいったら、それを続ける。うまくいかなければ、手直しするか、別のものを試してみる」(p.249) 大型商品が小さな一歩から生まれることが少なくない点を3Mはよく理解している。しかし、小さな一歩のうちどれが大型商品につながるのかは、事前にはわからない。そこで3Mは小さなことをいくつも試し、うまくいったものを残し、うまくいかなかったものを捨てている。(p.260)
0投稿日: 2010.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読み終わったぁ? これはまさに「変に完璧主義」を発揮してただ目を通し終えることだけが目標になってしまった本の1つだなあ(苦笑) いや、面白いんだけど。 永く反映し続ける超一流企業の共通点は何かが書かれている。 基本理念があり、それが絶対にブレなくて、組織の隅々まで浸透するシステムがあり、ある意味カルト的なとこがある。 リーダーは1人の天才ではなく、計画的に育てられた秀才たちのチーム。 これ、何も企業だけに限らず、スポーツや趣味の集団でも当てはまるんだよね。そう考えてみてみるとなかなか面白い。
0投稿日: 2010.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニーはなぜ生き残るか、というより、生き残った企業をビジョナリー・カンパニーと呼んでいるだけなんじゃないかという気はしないでもないが(定義にそった企業でつぶれたところも多いはずだ)、それでも示唆は多い。
0投稿日: 2010.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ名だたる企業、ビジョナリーカンパニーとしていわゆる企業との比較をあらゆる側面から分析してる。企業理念の重要性を説いている。トップが変更によって会社が変わるのではなく、その企業そのものにDNAがあり、なかば 抂信的ですらある。
0投稿日: 2010.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのようなつくりのしっかりした本は、じっくり読んでしまう。ページ数も多いので時間がかかってしまった。読後感としては大満足。もっと早くから読んでおくべき書だと痛感。
0投稿日: 2010.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業経営についての新しい視点であり大変面白い。また、ビジョナリーカンパニーの経営手法は自分自身の生き方の「経営」にも通じるところがあり、読むと視野が拓けてくる。
0投稿日: 2010.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログもはや古典ともいうべき経営学の本。業界で卓越しており、長期にわたって繁栄し、私たちが暮らす社会に足跡を残しているビジョナリー・カンパニーがどのような性質を持っているのかをリサーチした本。 この本の素晴しいところは他の経営学のフレームワークと整合性が取れていること、一般的なイメージを覆す革新的な部分を兼ね備えていることだと思う。 他のフレームワークでは生産性×凝集性の理論、イノベーションのジレンマとの整合性をみることができる。 <BHAG>で全員が夢中になれる高い目標を掲げ、<カルトのような文化>を創り出す過程で、集団の凝集性を高める。これは凝集性×目標意識で集団の行動を図った場合、凝集性と目標意識双方が高い場合、最も生産性が高いという理論と整合性がある。(ちなみに最も生産性が低いのは凝集性が高く、目標意識が低い場合。) <大量のものを試し、うまくいったものを残す>ことはイノベーションのジレンマに対応するために必要だったのだろう。「イノベーションのジレンマ」では顧客起点からの分析的、計画的なマーケティングのみに頼ると、顧客自身がニーズを知らない「破壊的技術」を使用する新興企業に市場を侵食され、繁栄していた大企業が潰れてしまう。つまり長期的に繁栄するためには破壊的技術への対応が必要であり、それは計画的な戦略のみでなく創発的な戦略が必要だということだ。それゆえ長期的に繁栄しているビジョナリー・カンパニーでは様々なアイディアを試行錯誤できる仕組みが整っていたのだろう。 また、<生え抜きの経営陣>、<カルトのような文化(ビジョナリーカンパニーは全ての人にとって理想の職場ではない)>など一般的なイメージからはかけ離れた性質を持っている。 長期的に繁栄している企業が優秀な経営者を招いていたり、誰にとっても働きやすい職場を創りだしているかのようなイメージを僕は持っていたが、決してそういうわけではないらしい。 この本には他にも<ANDの才能>や<利益を超えた目的><時を告げるのではなく時計を創る>など興味深い話がたくさんある。 比較的読みやすいし、お勧めの一冊。
0投稿日: 2010.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ泣く子も黙る名著ビジョナリーカンパニーやっと読みました。自社にも通じる箇所を見つけることもあれば、違うなというところもあって、楽しみながら読めた。まとめのキーワードとして、「時計をつくる」「ANDの才能」「基本理念を維持し、進歩を促す」「一貫性」。僕もこのへん意識してやていこう。次は2を読む!
0投稿日: 2010.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ優良企業に共通する特質を解説した著作には様々なものがありますが、最も有名なのがこの本「ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の原則」ではないでしょうか。 膨大なデータを丹念に整理して隠れた法則性を読み取る著者の解析力には元理系の私も脱帽です。同様の本として「エクセレントカンパニー」も有名ですが、データに基づく説得力と文章の分かりやすさにおいて、「ビジョナリーカンパニー」の方が勝っています。 初めてこの本を読み終えたときの感想は「ビジネスって奥が深い…」でした。経営学の教科書には有効なフレームワークやセオリーがたくさん紹介されていますが、それらをも超えるビジョナリーカンパニーの力に圧倒されました。 ビジョナリーカンパニーで働くということは、その価値感をDNAレベルでインプットし、組織文化を継承する義務を背負うため、決して万人にとって働きやすい会社ではありませんが、企業人として目指すべき企業のあり方の一つであると思います。 普通の企業が偉大な企業へと変わるための指針が知りたい方は 続編の「ビジョナリーカンパニー2 飛躍の法則」をお勧めします。 ただし、変化の激しい昨今の経済環境の中ではビジョナリーカンパニーであっても安泰ではありません。実際に一部のビジョナリーカンパニーはその栄光を失いつつあります。「ビジョナリーカンパニー3 衰退の5段階」には偉大な企業が衰退するまでのプロセスが解説されてますので、危機回避の参考にしたい方は、こちらもお勧めです。 このシリーズはビジネスパーソンのバイブルにも位置づけられますので、続編も含めて一読の価値ありです。
0投稿日: 2010.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業研究の教科書です。規模や利益だけでなく、企業文化にスポットを当てているところが特筆です。 大ベストセラー、ビジョナリーシリーズの第1弾です。自分がこの本を読んだのは、新入社員として入社した5年前であり、新人研修の時に先輩から何冊かオススメの本として、紹介されていました。今思えば、新入社員が読むような本ではない、スケールのばかでかい本と感じますが、当時は、言われるがままに書店に直行し、購入したことを覚えています。 著書を読んで真っ先に、うちの会社は「ビジョナリーカンパニー」では無いと感じました。「カルトのような文化」があるわけではなく、「時計をつくる」指導者もいません。得られた教訓は、偉大な企業はなるべくして偉大になったということです。果たして著書を紹介してくれた先輩の真意はなんだったのだろうか、今改めて考えるとよく分かりません。 著書の凄さはそのデータ量です。対象企業の過去100年間のデータを独自に集めており、非常に説得力のある内容となっています。 「ビジョナリーカンパニー」は社会人必読本であるのは間違いないです。ただし、この1冊で充分という訳ではなく、「ビジョナリーカンパニー」に働いていない、圧倒的多数の社会人は続編の「ビジョナリーカンパニー②」と2冊セットで読むのがベストだと思います。 日経BP社より目次 第1章 最高のなかの最高 第2章 時を告げるのではなく、時計をつくる 第3章 利益を超えて 第4章 基本理念を維持し、進歩を促す 第5章 社運を賭けた大胆な目標 第6章 カルトのような文化 第7章 大量のものを試し、うまくいったものを残す 第8章 生え抜きの経営陣 第9章 決して満足しない 第10章 はじまりの終わり
0投稿日: 2010.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
チェック項目15箇所。本書のなかにある教訓は、「自分には関係のないもの、とても活かせないもの」ではないと、自身と意欲を持ってほしい、だれでも、教訓を学べる、だれでも、その教訓を活かせる、だれでもビジョナリー・カンパニーを築けるのである。今回の調査の対象となったビジョナリー・カンパニーのすべてが、過去のどこかの時点で、逆風にぶつかったり、過ちを犯したことがあり、この本を執筆している時点で、問題を抱えている会社もある、しかし、ここがポイントだが、ビジョナリー・カンパニーには、ずば抜けた回復力がある、つまり、逆風から立ち直る力がある。ビジョナリー・カンパニーにとって、ビジョンを持ったカリスマ的指導者はまったく必要ない、偉大な指導者になることよりも、長く続く組織をつくり出すことに力を注いだのである、時を告げるのではなく、時計をつくろうとしたのだ、そして、この志向は比較対象企業のCEOより強い。読者には、この本を批判的、客観的に読んでほしいと願っている、考えに考えを重ねた結果、調査結果を否定する読者を、わたしたちは歓迎する、データはあくまでデータである、判断を下し、審判を下すのは、ひとりひとりの読者である。ビジョナリー・カンパニーになる組織を築くことに力を注ぐ、こうした努力の最大の成果は、すばらしいアイデアを目に見える形にすることや、カリスマ性を発揮することや、エゴを満たすことや、自分の富を築くことではない、その最高傑作は、会社そのものであり、その性格である。わたしたちの調査の結果を見ると、むしろ、すばらしいアイデアを見つけてから会社をはじめることにこだわらないほうがよいかもしれない、なぜなのか、すばらしいアイデアにこだわっていると、企業が究極の作品だとは考えられなくなってしまうからだ。会社を究極の作品と見るのは、きわめて大きな発想の転換である、会社を築き、経営しているのであれば、この発想の転換によって、時間の使い方が大きく変わる、製品ラインや市場戦略について考える時間を減らし、組織の設計について考える時間を増やすべきなのだ。ビジョナリー・カンパニーが、すばらしい製品やサービスを次々に生み出しているのは、こうした会社が組織として卓越しているからにほかならず、すばらしい製品やサービスを生み出しているからこそすばらしい組織になったのではないと思われる。ほとんどのビジョナリー・カンパニーにとって、「株主の富を最大限に高めること」や「利益を最大限に高めること」は、大きな原動力でも最大の目標でもなかった、ビジョナリー・カンパニーはいくつかの目標を同時に追求する傾向があり、利益を得ることはそのなかのひとつにすぎず、最大の目標であるとはかぎらない。「会社は要するにカネ儲けのためにあると、誤解している人が多いと思う。カネ儲けというのは、会社が存在していることの結果としては重要であるが、われわれはもっと深く考えて、われわれが存在している真の理由を見つけ出さなければならない」。ビジョナリー・カンパニーが大胆な目標を掲げ、思い切った冒険をし、ときには業界の常識を無視したり、無謀とも言える戦略を打ち出すのは、自身の表れである、ビジョナリー・カンパニーはこんなんを克服できないとか、偉業を成し遂げられないとか、真に卓越した存在にはなれないなどとは、思ってもいない、その一方で、冷静に自己批判をし、外部の世界から変化や改善を迫られる前に、自ら変化し、改善する。ビジョナリー・カンパニーは、基本理念や進歩への意欲について、漠然とした意欲や熱意を持っているというだけではない、確かに、ビジョナリー・カンパニーは基本理念を持ち、進歩への情熱を持っている、しかし、ただそれだけではなく、基本理念を維持し、進歩を促す具体的な仕組みも整えている。角度を少し変えるなら、ビジョナリー・カンパニーの述べ千七百年の歴史のなかで、社外の人材が最高経営者になった例は四回しかなかった。決定的な点は、次の世代で会社がどうなるか、その次の世代でどうなるか、そのまた次の世代でどうなるかである、偉大な指導者もいずれ寿命がくる、しかし、ビジョナリー・カンパニーは何世紀にもわたって前進を続け、個々の指導者が活躍できる年数をはるかに超えて、その目的を追求し、基本的価値観を貫いていく。もっとも大切な問いは、「明日にはどうすれば、今日よりうまくやれるのか」である、ビジョナリー・カンパニーでは、このように問いかける仕組みをつくっており、毎日の習慣にして考え、行動している。
0投稿日: 2010.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本理念と進化の兼ね合いがよく書かれている本だった。大手だと動きが鈍くてなかなか新しいものに挑戦できないイメージだったが、3Mのように常に新しいことに挑戦し、基本がぶれないまま進んでいける企業に感動した。 結局ウォルトディズニーが作った最大の功績はディズニーカンパニーを作ったことである。
0投稿日: 2010.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログさて、ここまで解りやすいビジネス本は無い。 そしてシンプルなものにこそ、至高の力が眠っていると私は思う。 企業の優位性は掲げるビジョンによって決まる。 そりゃそうだと思う。 人間はカネだけで働くわけじゃない。 よりよい社会を実現するためにも生きることができる。 そんなビジョンを策定した会社が生き残る以上の企業に成長するというのは解りやすい。 起業家になりたいなら読むべき。
0投稿日: 2010.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログちょうどクラブチームの合宿があったので、復習を兼ねて再読。 企業に限らず、多様な組織形態に汎用化できると思う。 「基本理念(目標)」の定め方がキモ。 良い本です。
0投稿日: 2010.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは時を告げる人になろう。 この本は精神論だとかを抜きにして、今ある結果がなぜもたらされたのかを莫大な文献から理由を探した答えが記載されている。 これを読んでみるとうちの会社は程遠いのでは?じゃあ何をしたらいい?とかを考えるキッカケになった。
0投稿日: 2010.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ不朽の名作。 大学生で読んだときに感銘を受けた。 社会人となり、もう一度手に取り読んだ。 時代を超えて輝き続ける、ビジョナリーカンパニーになるためにはどのようにしていけばよいのか。 類まれなる文化、ケイパビリティの強さ。 常に一定ではなく、常に上を目指すということを組織の観点だけでなく、個人としても考えさせられる作品。
0投稿日: 2010.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更レビューを書くまでもない、経営に関わる歴史的名著。 ビジョナリー・カンパニー(未来志向の企業)をある方法で18社選び出し、そのビジョナリー・カンパニーと設立時の環境や事業内容等が近い優良企業とを比較する。つまり金メダル選手の様な企業と、銀メダル選手のような企業を比較し、これによりビジョナリー・カンパニーに共通する特質は何かを調査している。 比較されている企業は ソニー VS ケンウッド フォード VS GM HP VS テキサスインスツルメンツ …等々 本書で最も強く主張されていることは、ビジョナリー・カンパニーになるためには「経営理念」の内容は関係なく、いかにその経営理念に沿ってあらゆる決定を下しているか、またその経営理念をいかに従業員一人一人にまで浸透させているかということである。 本書の良い点は複数の企業の事実に基づいて理論が展開されているため、いち起業家の成功本と違って、非常に説得力がある。 そして見逃せないのが、実際の従業員の言葉など、心に響くエピソードもたくさん詰まっている。 起業家、経営者だけでなく、全てのビジネスマン必読の良書中の良書。前評判に違わぬ素晴らしい内容である。
0投稿日: 2010.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の超一流企業をサンプルとしていますが、管理職としてマネジメントに関わっている方であれば、参考になることが沢山書かれています。 なにげに自分の会社の悪いところが見えてきて、将来が不安になるかもしれません。
0投稿日: 2010.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に書かれている ・組織の理念の共有 ・株主や企業の利益追求ではなく、社会貢献を重視する事 ・時代を先取りするための組織変革 ・人材育成 などの重要性は就職活動をしていると色々なところで聞く(この本は結構10年くらい前に書かれたものだが、本書の影響力なのかは良く分からない)し、実際私の会社選びの軸の一つにしてきた。 学生のうちに読んで損は無い。
0投稿日: 2010.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更書くまでもない、ビジネス本の名著。 50年以上続く、「ビジョナリー(先見性のある、未来的な)・カンパニー」の具体例を調査し、 同業他社との比較対象社との違いを丁寧に検証している。 その結果は意外なものだった。 ・企業の理念を持ち、組織として守り続けている。 ・ただしその理念は様々で、決して共通するものとは限らない。 ・その理念を徹底するのに努力を怠らない。 ・その理念は利益の追求を越えたものであるが、同時に利益の追求も怠らない。 ・カリスマ的な指導者がいる場合もあるが、多くはカリスマを必要としていない。 ・生え抜きから優れた指導者を育て上げるシステムが出来ている。 ・常に前進し続ける意志を持ち、過去は振り返らない。 ・目標、時を告げるのではなく、時計をつくる ・ANDの才能の重視 しかもこれらのことを「全て成し遂げる」ことがビジョナリー・カンパニーに 必要な要件である。 本書は米国企業が主だが、唯一ソニーが上げられている 真理を突いた本はやはり時代を超え色褪せない。
0投稿日: 2010.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更書くまでもない、ビジネス本の名著。 50年以上続く、「ビジョナリー・カンパニー」の具体例を調査し、 その比較対象社との違いを丁寧に検証している。 その結果は意外なものだった。 ・企業の理念を持ち、守り続けている。 ・ただしその理念は様々で、決して共通するものとは限らない。 ・その理念を徹底するのに努力を怠らない。 ・その理念は利益の追求を越えたものであるが、同時に利益の追求も怠らない。 ・カリスマ的な指導者がいる場合もあるが、多くはカリスマを必要としていない。 ・生え抜きから優れた指導者を育て上げるシステムが出来ている。 ・常に前進し続ける意志を持ち、過去は振り返らない。 など。 しかもこれらのことを「全て成し遂げる」ことがビジョナリー・カンパニーに 必要な要件である。 真理を突いた本はやはり色褪せない。
0投稿日: 2010.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログまず、ビジョンって何?液晶?みたいな感じだったので、 ものすごいインパクトがあったことを覚えてる。 時を告げるのではなく、時計をつくる ってフレーズが印象的。 そう言えば、アルバイトのリーダーをしてて、 「自分がいなくても自律的に動ける 有機性のあるチームを作ろう」 と考えるきっかけもなった。 バイトリーダー必読の書ww ビジネス
0投稿日: 2010.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログビジョナリー・カンパニー(真に卓越した企業)が長年その地位を維持している理由を,6年に及ぶ徹底調査によって明らかにする。
0投稿日: 2010.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本も大学の最初の時に読んだ本です。 「なぜやるのか?」を追求して、 組織のビジョンを明確にすること。 その大切さを認識した本です。
0投稿日: 2010.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的に優秀な企業といわれている会社に務めてる周りの友人は、会社にプライドを持ち、モチベーションも非常に高い。いい意味での仕事人間である。 個人の意識の高さはもちろんあるだろうが、会社の文化がそれを伸ばしているんだと気づいた。 自分の会社はどうだろう? この本にあるように経営者でなくても自分の部署から変えていけるだろうか。
0投稿日: 2010.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ『時代を超え際立った存在であり続ける企業の永続の源泉とは?』 すごくいい! 実に膨大な企業調査により解明された事実のインパクト。 時代を超え社会より尊敬を受け続ける企業と 業種・業態・成り立ちが似ている企業との歴史の比較。 その結果、浮かび上がってくる永続の源泉。 それは「基本理念」。 基本理念とは、戦略とは違い、たとえ一時的な不利益を招いても 企業が守り続けていくべきものである。 本書に記されている企業の一部。 ディズニー、3M、アメリカン・エキスプレス、GE、ウォルマート・・・ 特に印象に残るもの ・良い基本理念、というものは無く、その企業が決めたものを守り続けるだけ。 (相反する基本理念を掲げた企業が永続している) ・永続企業にカリスマ指導者はいない。 普通の人達がビジョナリー・カンパニーを作り上げている。 ・”二兎追うものは一途も得ず”では無く、二兎を追求する。 ・社運を賭けた大胆な目標設定が劇的な進歩を促す ・カルトのような文化を徹底する。 (ディスニーの魔法。従業員が受け入れられなければ追い払われる仕組み。) ・大量のものを試して、うまくいったものを残す。 (15%ルール。仕事中15%の時間をやりたい事に費やす権利。) ・生え抜きの経営陣。 (他からCEOを招聘して上手く行くケースは極小。) とにかく一度読んでみて下さい。
0投稿日: 2010.01.19
