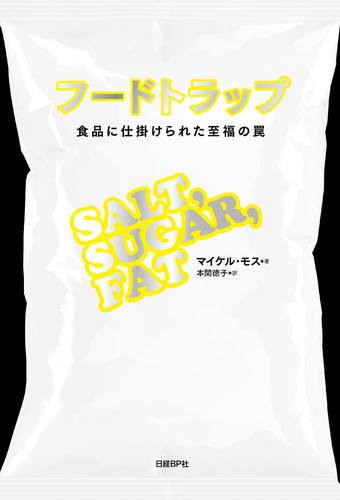
総合評価
(41件)| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ恐ろしい、、、の一言。健康 に配慮した原材料にすると商品としては健康的になるものの、全く売れなくなる。株主たちから元に戻せと言われる。人々が熱狂して買う商品と言うのは、「至福ポイント」を満たした商品。ドーパミンがたくさん発生するような快楽を覚えるおいしさまで砂糖や脂肪や塩の組み合わせた商品。 本書を読むと、今まで以上に添加物の入った食事ができなくなる…
0投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.食品はどの産業よりも隠されている産業であり、最も人の興味をつりやすい話題です。外国人著者ということもあり、具体的な内容が書かれていることを期待して読みました。 2.現在の人間の食は「糖分・塩分・脂肪」で構成されるといっても過言ではありません。これらが必要以上に取られている現状に対して企業と政府側にはどのような思惑が潜んでいるのか、記者である著者は様々なリサーチを通して、業界の思惑について述べています。米国では、この3つの成分は国を支える産業となっており、政治権力にも大きな力を及ぼしています。本書では、上記の3成分がそれぞれ現実世界にどんな影響を与えているのか、業界としてどんな半試合がお行われているのかを述べています。 3.結局のところ、これら3つの成分の摂りすぎによって、現代の食は崩壊しているといっていいと思いました。それは、消費者側である私たちにも責任があると思いました。 スマホの普及によって、情報を得やすくなっているにもかかわらず、受け身であることをやめない消費者は洗脳しやすくなっていると思います。ここ10年で、消費者の情報収集力と精査能力が二極化してきたと思いました。ニュースに踊らされ、特に危険でもないものを危険と声高に叫び、訴えてしまう。それによって、食品工場がどのような打撃をこうむることになるとは知らずに、、、 ちゃんとした消費者を育てていきたいと強く願ったきっかけを得た1冊でした。
2投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ食品産業を徹底的にジャーナリズムした本. ノンフィクション・分厚く緻密で具体的. 時間の都合と結論が見えていたので流し読み. 食品産業の要は糖分・脂肪分・塩分.これら企業が生み出す商品はこれら+αの合成品であり,商品開発とはその配分量や形態を変えるパラメータ調整に過ぎないんだなと感じた. 企業の存在目的は人々の健康じゃなく利益追求だからしょうがないし,これに対し消費者ができることは自分で意思を持って消費するものを選ぶしかないなあと改めて感じる. また食品そのものではなく人にどう幻想を植え付けて商品にポジティブで魅力的な印象を持たせるかという所謂マーケティングも,3大成分のコントロールと同等に重要なんだなということも感じる.いかにお咎めを受けず優良誤認させるかにしか見えないけどね. 自分がスーパーにいったときや食品のCMを見た時,このパッケージやCMにはどんな意図があるんだろうと見ると面白いだろうね. ==================== "加工食品には、色、匂い、包装、味を始めとして、力を決定する要素(=変数)が多数ある。「最適化」を行う食品エンジニアは、これらの変数をごく僅かずつ変化させ何十ものパターンを作り出す。得るためではない。実験を行って、最も完璧なバージョンを見つけ出すためだ。" →加工食品産業は最適化屋、パラメータ調整屋さん "加工食品から塩分・糖分・脂肪分を少々取り除くと。食べ物ではなくなってしまうのである" "彼らが利用してきた塩・砂糖・脂肪は、栄養素よりも兵器に近い。競争相手をまかすためではなく、消費者にもっと買わせるためにも利用される兵器である。" ”「飲みたい!」と言う気持ちを起こさせる新しい清涼飲料を開発するには、「至福ポイント」を見つけ出せばよい。糖分や脂肪分の配合量がある値にぴたりと一致していると消費者が大喜びするというポイントがあり、業界内部の人々はこれを至福ポイントと読んでいる。至福ポイントの発見には、回帰分析や複雑なグラフといった高等数学が駆使される。” ”食品メーカーは競争力を高めるために塩や脂肪の形態や構造を変化させている〜砕かれて微細な粉末になった塩は、より素早く、より強力に味蕾を刺激し... たとえば脂肪を「問題児」として減らしたいなら、黙って砂糖の量を増やす。そうして消費者を繋ぎ止めておく。” →食品業界の企業努力とはこういうものでしょうな。 メイラード反応 "マフィンでもローストビーフでも、食品の加工の際にきれいな焼き色が生じるのはメイラード反応のおかげであり、この反応はフルクトースなどの通がなければ起こらないことが多い。" →糖分は生理学的・麻薬的効果だけでなく見た目という観点からも不可欠 ライン拡張 →派生商品を作る。元祖の商品の置き換えではなく話題性、ブランド向上(元祖商品売り上げへの還元)も狙い →季節限定商品やコラボ商品はこれだな スペースを勝ち取るための競争は熾烈で、各売り場を牛耳るマネージャーの行動原理はただ1つ。「最もよく売れる商品に最も大きいスペースを割り当てる」。消費者科学の専門家らが買い物客の眼球運動を追跡する実験を行っていることを考えれば、スーパーの店内がいかに貴重な空間かわかるだろう。 →スーパーは大衆需要の写鏡 "私は科学者としてのベストを尽くしてきた。生き残るのに必死で、道徳に隷属するような贅沢は許されなかった。" →最後の一言、いいね "我々は、体と脳の栄養が欠乏して実際に補給を要する、と言う状態には滅多に陥らない。我々を食べることに駆り立てるのは他の動因であることを彼は発見した。動因には、感情的なニーズが回れば、加工食品の重要要素を反映したものもある。後者はまずなんといっても味そして香り、見た目、食感などだ。" "食欲をコントロールするのは血糖値と脳の視床下部で、この2つはいずれも糖分に大きく影響される" "本来「シリアル」は、穀物で作った食品を指す単語" "食品業界にとって広告宣伝は塩分糖分脂肪分と並んで魅力を作り出すための強力なツールであり、他者との差別化に使える唯一の手段である場合もあった"
0投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ食品メーカー自身が、塩分、糖分、死亡分という、製品に最大の魅力をもたらしてくれる兵器に依存し続けている 減塩、低糖の商品を開発しても、それが売れず、他社に売り場を奪われる危険がある。 糖分には至福ポイントと呼ばれる、一番おしいく感じる糖度と構成物の組み合わせがある。 これは一般的に、子供のほうが高い糖度をおいしいと感じる。 この至福ポイントは、子どものころの経験によって作られる。 何故人は甘いものを食べるのか?→「空腹は渇望を生む大した力にはならず、幸福への充足のために糖を取る」 また、空腹そのものではなく、「空腹になりたくない」という気持ちが、腹が減っていなくても、これらのものを食わせるのだ。 アメリカで始まった砂糖と添加物の革命は、世の中の女性が仕事に進出し、家事の時間を劇的に減らす「コンビニエンス・フード」として世界を席巻する役割を果たす。 また、ケロッグを始めとするシリアルメーカーが、こぞって広告戦略に力を入れ、「砂糖」へのマイナスイメージを払拭しながら、他社と差別化を図っていく。 強い味は、強い満足を生むが、そのぶん飽きやすい。大切なことは、味に角がなく、強い風味と慣れ親しんだ風味の間のバランスを維持することである。 消費者の健康志向が高まるにつれ、メーカーは果物や濃縮還元など、フレッシュなイメージを持つキャンペーン戦略に舵を取り始める。 【脂肪】 脂肪分には、下に膜をつくり、他の味をコーティングしてまろやかにする作用や、糖と比べ、協力な味はせず、目立たないように味を引き立てる力を持つ。 →脂肪分がたっぷり入っていても、気づきにくい 脂肪分の真の力は口当たり、触感の向上にある。 しかし、糖分や塩分と違って、常にマイナスイメージにさらされている。 脂肪分には、糖と違って至福ポイントが無く、脂肪たっぷりであればあるほどよい。 また、脂肪に少し糖を加えると魅力が高まるというシナジーがある。 チーズがアメリカを席巻する。 その後、脂肪分を見せるのでは無く、隠すことでより人々が気づきにくくなることを見出し、これが加工食品業界全体のテーマとなっていく。 ランチャブルズを始めとする冷蔵加工食品に子供たちが惹かれたわけは、「持たせるだけ」という親の朝の忙しさ回避、調理不要というお手軽さもあるが、何より「自分で作る」という特別感が、子どもの心をくすぐったことだ。 米国民の1/3が肥満となった。 脂肪分はチーズと牛肉に多く、これらおよびこれらを加工した食品への規制は、政府は足取りが遅く、企業が自発的に規制に踏み切った例もある。世間全体が、加工食品を食べることは「消費者の自由選択」などではなく、食品会社の「プロモーション」の影響が大きく、責任は会社にもあるべきだという見方が広がる。 【塩分】 現代人は明らかにナトリウムを摂りすぎであり、そのほとんどは加工食品から摂取している。 何故我々が、ただの鉱物であるナトリウムを好むのか?→もともと存在しない欲求を、子どもの時から植え付けられているから。塩分は生まれつき生物上好きではないが、塩分が多い食べ物を与えられ続ける結果、好きになっていく。 加工食品は、食べ物の保存、調理、味付けに食塩が必須であり、もはや食塩から逃れられないほど浸透している。食塩がなくなると風味、味、食感がガクンと落ちるため、一定ライン以上は減らせない。
0投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体の2割も読み進めないうちに、果糖ブドウ糖の恐ろしさが身に染みた。この本に出てくるお菓子飲み物を口にしたことがない人はいないと思われるほど、あまりになじみの深い製品がずらりと出てくる。名称は異なっても、似たような商品は今もスーパーに並んでいる。果糖ブドウ糖の次には脂肪分、塩分と話はどんどん膨らんでゆく。そのどれもが製品を売る上で欠くことのできない重要なエレメントであるのだ。私たちがお菓子を食べるのをやめられないのは、意思が弱いからなのではなく、計算しつくされたメーカーの思惑に体が反応しているのである。現に、これら食品メーカーの当事者たちは加工品を口にしない、とある。これらの加工品から自分の身を守るのは、容易なことではない。唯一抵抗できるとすれば、スーパーの陳列棚のマーケティング方法を知り、近づかないこと、これに尽きるのではないか。加工品のリスクをテレビでは絶対に放送しない。なぜなら番組のスポンサーには、これら多くの加工品製造メーカーが含まれているからである。この本は、特に子供を持つ親に読んでもらいたい。味覚、味蕾は、子供の頃にある程度作られてしまうらしいからである。加工品は工業製品である、糖分、脂肪分、塩分なくしては、とても食べられた代物でないということを忘れてはならない。
0投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ食品は売れるものを作ろうと思うとどうしても依存性のあるもの開発しないといけないというジレンマがある。 その中で、食品会社に勤めている人は商品に対してどのように誇りを持っているのだろうか?と否定するつもりはないのだが、気になったりはします。 加工食品の方が安いので、フィリピンでもみんな加工食品ばかり食べるようになって太っている人が増えているのでは?と思います。 その反動して、フィリピン政府は砂糖税などを増やしているような印象。
3投稿日: 2019.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ膨大な取材と食料品の研究内容、肥満に関するデータから語られている、ドキュメンタリー作品。ある一面を見れば、タイトル通り至福の罠であり、その罠と半分認識しつつやめられない消費者とのリアルな関係を垣間見える一冊。
1投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ健康に関わる食品の世界も消費者ではなく株主の利益第一主義に走っているのだと知り恐ろしくなった。正しい情報と見極め選択する力が必要だと思った。
1投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ砂糖、脂肪酸、塩化ナトリウムは、人の味覚を依存症にしてしまう強い力があり、かつ(現代の摂取状況では)体に悪い、という話 加工食品を食べないという対策しか無いかも 厚すぎる。長過ぎる。なんで500ページも必要なの。
1投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちが日頃食べている食品、特に加工食品の恐ろしさを科学的に説いた本だった。 糖、脂肪、塩分の3つのカテゴリーを1つ1つ丁寧に書き上げ、これまでの科学者の発見に基づく加工食品が生み出されてきた。 人々の健康よりも利益を追い求め、私たちはそれに気付かず、ただただ至福なひと時を求め、身体を壊して行くことになっていた。 至福ポイントを見つけ出し、それらを操作する技術の進歩は素晴らしいものだった。 私たち購買者は、これからの時代は1人ひとりがよく自分の身体をよく考えて食品を選ぶことが必要だと思った。 そうしなければ、加工食品の依存性、中毒性に引き込まれてしまうからだ。 私たちが食品を選ぶのではなく、食品が私たちを操作していることに気づくべきだ。
1投稿日: 2019.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ健康とは何か? この問いを現代社会を取り巻く複雑な産業構造の視点で、 見解が述べられています。 自分達は、多くの食品企業、メディア、医療機関に、 ただ踊らされているだけかもしれません。 とにかく、著者の圧倒的な取材量を舌を巻きます。 これほどのジャーナリストは、まず日本にはいないでしょう。 文献・論文の読みこなしも、素晴らしいと思います。 食品企業は、消費者が、「はまるポイント」を常に探しています。 これは、食品企業に限ったことではなく、 どの企業も、この視点で、マーケティング活動を行っています。 人の生理機能ではなく、認知機能にまで、 影響を及ぼす情報が、日夜メディアから流され続けられています。 いったい自分達は、こういった社会構造の中で、 どうやって健康を実現していったいいのか? 非常に考えさせられる内容です。 特に、コカ・コーラの記述には、なるほどなと、させられました。 なぜ、コカ・コーラがロングセラーなのか、その一つの重大な秘密がわかります。
2投稿日: 2018.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカっちゅー国はコワイよの~ なんせ、国民よりも利益の方が需要っていうんだから~ 「SALT」「SUGAR」「FAT」 この3つを制するものは全てを制す! アメリカの食品業界においてこの3つこそが食品の売り上げを決める要素と言っても過言ではないのだとか。 砂糖の甘みが増せば増すほど脳は快感を感じ 油は人間の体がリミッターなく求めてしまうもので 塩は全ての生き物が細胞レベルで要求するもの 砂糖をもっと入れろ! 将来大きな消費者になる子供たちの脳に甘さをすり込め 油をたっぷり使った食品を手軽さをうりにして主婦に売れ 塩化ナトリウムが問題なら塩化カリウムでごまかせ! みたいな国民の健康を無視して利益を追求(いかに売れるか)するメーカーがあまりにも多すぎる。 「いや~うちは色々守ってますよ。でも消費者さんが食べすぎるんですよね~」 なんて言い訳する恐ろしさったらない! お手軽なインスタント食品や冷凍食品を売り込みたいがために、アメリカで家庭料理を作らなくさせたのはとある食品団体らしい。 こわ~!食文化が崩壊してるよ! って思うんだけど、 日本でもすでに崩壊しかけてるのかな~? 人の味覚というのは作られるもの 子供の頃に甘いジュースやスナック、加工品、お菓子で育った子供たちは自然の甘みや旨みは感じなくなるそう 自由の国・アメリカが抱える肥満問題や貧困問題 それらは食文化の崩壊とは全く無関係ってわけじゃないそこには文化を犠牲にしても儲けたいという人々の恐ろしい罠が隠されている。
1投稿日: 2018.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
砂糖・脂肪・塩分について、アメリカの食品会社がどのように消費者が好む製品を作るか、その結果どうなったかが詳細な資料とインタビューを元に書かれている。読んでいて糖分(特に清涼飲料水)の恐ろしさを感じたが、読んでいる内にコーラが飲みたくなりました。
1投稿日: 2018.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
●マイケル モス, 本間 徳子「フードトラップ 食品に仕掛けられた至福の罠」 ●畑中 三応子「カリスマフード: 肉・乳・米と日本人」 ●アナスタシア・マークス・デ・サルセド, 田沢恭子「戦争がつくった現代の食卓-軍と加工食品の知られざる関係」 ●ジョン J. レイティ, エリック ヘイガーマン, 野中 香方子 「脳を鍛えるには運動しかない!」
0投稿日: 2018.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はアメリカのことを書いているけど、ではひるがえって我が国の状況を考えると、どうでしょう。食品を売るためにどんな味付けが仕組まれているか。必要以上に欲求を高めるための仕掛けづくりはどうなっているか。実質以上のみかけをつくりだすために偏った情報提示をされていないか。最後のことでいうと、「食物繊維の量を示す基準がレタスになってることが多いけど、レタスはあまり食物繊維は多くない。ゴボウのほうがずいぶん多い。でも、レタスのほうが〇個分っていうときに大きな数字が出やすいのでよく使われるのだ」という噂を聞いたことがあります。検証したわけではありませんが、今でもなんとなく頭に残っています。(2014年7月26日読了)
1投稿日: 2018.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「脂肪です」 「糖分です」 「塩分です」 「出たな、余分3兄弟っ」 なんていう飲料のコマーシャルを思い出した。食事や間食での 摂取量に気をつけないと体に悪影響を及ぼす余分3兄弟。 この余分3兄弟をふんだんに使用しているのがアメリカの加工 食品だ。本書はアメリカの加工食品会社が商品に仕掛けた 巧妙な罠で、消費者を過食へと導く行程が描かれている。 文明かが進めば進むほど、人々は食事に時間をかけなくなって 行く。料理をする時間さえ惜しむほどだ。するとどうなるか。手軽に 食べられるインスタント食品やスナック菓子が喜ばれる。 そこには大量の脂質・糖質・塩分が含まれている。それが人々の 食欲を満足させる。満足させるだけならいいが、「もっと食べたい」 との欲求を起こさせる。 アメリカの加工食品がよく分からないので特定の商品についての 話は理解出来ない部分もあったが、加工食品の実態と食品会社 がいかに消費者の健康なんて考えてないかが描かれていて少々 ぞっとする。 ポテトチップスを例に取ると理解しやすいかもな。日本では食べ切り サイズの小袋も販売されているけれど、あれだと「食べ足りない」と 感じる時があるんだよね。 だからって、大きな袋を開けて途中で食べるのを止めるのも難しい。 実際、本書を読みながらポテトチップスを食べていたのだが、危うく 1袋を空けてしまうところだったもの。気付いて片づけたけどね。 そんな食品加工会社の上級役員たちが自社の商品は食べないよう にしているなんてなぁ。健康に良くない商品を売っているという自覚 はあるんだろうね。 一応、食品会社も商品の見直しはしている。余分3兄弟を減らした 商品を売り出した。ところが、売り上げが伸び悩み、株価が下がり、 ウォール街から「もっと売れる商品を作れ」と尻を叩かれる。 そして振出しに戻る。悪循環だよな。 それにしても、アメリカ人の食卓はシリアル、冷凍食品、スナック 菓子だけで成り立っているのか?いや、忙しいと食事を作るのが 面倒ってのは分かるんだ。分かるんだけど、手料理って大事じゃ ないのか。 日本のスーパーに並んでいる「麺つゆ」。私はあれでそうめんや うどん・そばが食べられない。だって、どんなに薄めても甘いの だもの。大量に出汁を取って冷凍しとけば、それほど面倒じゃ ないんだけどな。 日本もいつかアメリカみたいな食生活になって、余分3兄弟が はびこるんだろうか。
1投稿日: 2017.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカのジャーナリストの力強い調査と追求力は 眼を見張るものがある。渾身の筆圧が感じられる。 アメリカだからできるのだろうか。 徹底したインタビュー。 必要な文献の調査。そして、内部文書まであたる。 日本では、このようなジャーナリストが 育たないような気がしてならない。 なぜなのだろう。 砂糖、脂肪、塩は 『美味しい』を形づくる。 どんどん食べさせ、どんどんのませるには どうしたらいいのか? それを 食品企業は 徹底した 研究をして 戦略とマーケティングを行ない そして 広告宣伝 によって ターゲットを陥落させる。 企業の論理は 収益獲得に徹底してこそ はじめて 生き延びるが そのことによって ニンゲンを 滅ぼす可能性がある。 まさに 食においての ジレンマの中にあることを 浮き彫りにする。 この本の題名は、フードトラップよりも フードジレンマと言った方が良さそうだ。 砂糖、脂肪、塩をめぐって、フードカンパニーの 追及とジレンマを深く掘り下げる。 砂糖には『至福ポイント』がある。 そのポイントを正確に把握することが、 食品会社にとってのコストダウンとなる。 子供は 生まれた時から 糖を美味しいと思う。 3歳から5歳の時に 塩味を覚えるようになる。 塩味は、後天的な味とも言えるが、際限なく食べてしまう。 食べ始めたら、とまらないのだ。 子供は 甘いもの が好きな理由が 明らかになり それを どうやって 飼いならすか が食品会社のテーマだった。 至福ポイントは 点ではなく 点の集まりである。 『欲しがれ;Crave it』 欲求を高める商品。 味 香り 見た目 食感。 お腹がすくから買うのではない。 お腹がすく予定があるから、それを想定して買う。 食品の選択は 偶然が多い。必然的買い物は少ない。 近くにある 便利さが 欲しいものを買う。 アメリカでは 朝ごはんが シリアル。 昼ご飯が 簡単なランチ。それを、どう攻めるか? 砂糖と塩と脂肪まみれにする。 結局は、フードカンパニーは、 健康にいいものをつくろうとするが、 消費者が 受け入れられないことへの 失望と困惑が あるのだ。 結局 炭酸飲料会社は 肥満を生みつづけることになるのだ。 どうにもとまれない現実に ふかい罠が あるのだ。
4投稿日: 2017.02.06この世に残すべき本
本書はアメリカの加工食品業界の状況について大変詳しく書かれています。 目標の性能を出すために最適に設計された機械を開発するのと同じように、加工食品は、いかにたくさん食べてもらえるかに焦点を絞り各種の変数を最適化しながら設計されていることが分かりました。そこには、製品を食べた人が健康でいられるかについては考慮されていないことが書かれています。 本書をこれから読まれる方は、アメリカと日本とでは状況がいくらか異なる可能性があること、本書が出版されやや時間が経過しているため本書に書かれている状況と比べ現在ではいくらか状況が改善している可能性を考慮されてはと思います。 本書はボリュームがあり、気晴らしに読むには少々努力のいる本ですが、私たちが知っておくべき情報を集約した書物として価値があるものだと思います。 とかく健康に悪い製品を製造販売する企業に批判が行きがちですが、私たちが何を食べるかを最終的に決めるのは私たちであることを考えさせられました。
6投稿日: 2016.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログソフトカバーで530P強。ものすごく小さい字のところもあり、読み応え充分……。 「糖分」「脂肪分」「塩分」の三章に分かれていて、ドキュメンタリータッチで真相に近づいていく。加工食品、外食産業花盛りのアメリカの話だけれど、沖縄に住んでいる今、とても他人事とは思えず。 なんにせよ、売る側は買う人の健康なんて考えていないし、自分達が売っている物を食べてもいない(人が大多数)。すごく見下している、というのが率直な感想。 内容的に勉強になったのは、人の身体は「液体のカロリー」を扱うのが苦手、ということ。砂糖も溶けていれば身体に入ってしまう。(個体では、コップ一杯の加糖の炭酸飲料分の小さじ6杯の砂糖は食べられない) 濃縮果汁還元の100%ジュースも、砂糖、コーンシロップ(果糖ブドウ等液糖)と同じ種類の糖分と思っていい。(栄養素は加工過程で抜けている) 私は、「これがないと生きていけない」は好きじゃない。だから、読んでよかったと思う。
1投稿日: 2015.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ塩分、糖分、脂肪分 日本の食品メーカーも、これと似たり寄ったりのことをしているんだろうなあ。 日本も、働くお母さんが増え、子供との食事に加工食品が増えたら、肥満や糖尿病の子供が増えるだろうなあ。
1投稿日: 2015.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読めば読むほど加工食品が怖くなった。食品メーカーで働きたいと思った時期もあったけど、なかなか難しい業界。 それにしても、長くてなかなか読み進められず…
1投稿日: 2015.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ加工食品にしかけられている、数々の罠。 糖分、脂肪、塩分はもちろん、広告から店頭における配置まですべてはメーカーの利益追求のため。 メーカーの重役の多くが、自ら手がけた商品を避ける食生活を心がけているという事実から、いかに加工食品が身体によくないものかがわかるというものだ。
1投稿日: 2015.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞の書評から興味を持って。食品の大企業により仕掛けられた、糖分脂肪分塩分の至福の罠。一日の摂取量を大幅に超えたところにある、人々の満足点。引き換えに不健康を得て(与えて)では健康的な物を開発…しても売れず。企業としては利益を得なければいけないゆえ、リバウンドのごとく盛られるこの至福の3アイテム。 甘いお菓子に手が伸びなくなるほど、ぞっとした内容です。 料理は苦手ですが、新鮮で安いアイテムの手に入る環境に感謝して、自分でも作れるようにしなくちゃと背を押されました。
1投稿日: 2015.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義アメリカ。勝ち残るための戦略で、食品の工業化が、どんどん不健康に。大企業でそれらの仕事をしていた人が、心の呵責からか、それとは反対の仕事に転職する例もあり、少しは救いが。 近代化で便利になったようで、どんどん忙しくなって。時間に快楽に呑まれてる。グローバル化する世界。金、金、金…の力関係。 何が大切か、自分で知ろうとしないと、いけない。 食育は大切だが、金と時間、それに楽したい欲が。足るを知る事か。
1投稿日: 2015.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログつまるところ、勝ち組(金を持つ者)によって、負け組(金を持たざる者)の生命まで左右される時代に入っていることを示唆しているのではないだろうか。すべては「金(利益)」「株価」に収斂されるのだから。 本書は読むのにかなり時間がかかった。
1投稿日: 2015.03.09普段食べる食品にこんな仕掛けがあるとは驚いた。
本書は、食品の袋裏面に小さく記載されている食品添加物の表示項目に健康被害を及ぼす危険のある化学薬品が含まれていることを教えてくれました。 これを読んでからは、必ず食品添加物を確認してから買い物をするようになり、余計な食品は買わなくなりました。 化学薬品の名称が専門的なので、難しく感じましたが、読んでいくうちに慣れました。 食品業界が消費者に如何にリピートして買わせるかという研究がここまで進んでいることに驚きます。
1投稿日: 2015.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
肥満の人へ朗報!デブはあなたのせいじゃない…らしい。砂糖・塩・脂肪、これらの新兵器で人々を殺戮する…。 スーパー・サイズ・ミーとかアメ公の食糧問題を取り上げたジャーナリズム作品はあるが、これもそんなん。 これからの世の中、金のないやつはアメ公のような食事しかできなくなる。国産の高栄養価の本当の食材に遭えるのは富裕層のみになってしまうだろう。 金のないやつは、生活保護のみの収入で、工業製品の食品で不健康な生活を強いられ、食品メーカーと医療メーカーに金が流れていく全自動送金システムが完成するのだ。 こわい。 _____ p444 ラボ アメリカの巨大食品企業はラボを構えている。『チャーリーのチョコレート工場』はリアルなのである。 そこで何が研究されているかというと、「砂糖を減らすためにより甘いものを探す」「脂肪分をより一層感じられる添加物を探す」 頭おかしい。 p455 肥満税 アメリカでは「肥満税」なるものが現実味を帯びているらしい。やばい。 筆者は、肥満税が消費者に課せられる不合理を言っているが、そもそもやばい。 _____ なんか、もう、ヤバいとしか言いようがない。 アメリカの生活保護者(アメリカだけでないだろうが)はもはや消費するだけの機械でしかない。 未来は真っ暗。
1投稿日: 2015.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://blog.goo.ne.jp/nakamana825/e/ee7f808138cb5cb63d4fa5b444a9c696
1投稿日: 2015.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ糖分・脂肪・塩分の正しくトラップにさらされている実態を克明に暴いたドキュメント。 アメリカの、そしてそれを追う日本の思いやられる歴史と現状、余程の選択眼と知識武装なくしてはとても自己防衛できそうにはない。恐ろしや!!
1投稿日: 2015.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ食べるものを 売らんが為に、こんな風に作って、売る、組織も会社もサイテー。そういう物を購入しないように 気をつけなくては・・・
1投稿日: 2015.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログサブタイトルは「食品に仕掛けられた至福の罠」、糖分、脂肪、塩がどれだけ人を至福にするだろうか。加工食品の多くは、たいていこの3つが大量に含まれている。 どれだけの甘さだったら人は幸せになるか、という至福ポイント、なる言葉まで生み出して、当分の含有を正当化するメーカー。脂肪をたくみに隠そうとするメーカー。塩分は、糖分や脂肪と違って健康志向とされるメーカーでも結構使う。この三点から逃れるのは困難だ。 それぞれが人体にどんな役割を果たすのかは、まあ今さら言うまでもないが、組み合わさるとちょっとやっかいになったりする。脂肪は糖といっしょになることで、脳が過食を検知しづらくなって、加工食品はますます売れる。 とにかく、いかに人々を過食させるか、ということに尽力する人々のストーリーである。読むと気持ち悪くなってくるよ。アメリカ人の朝食がいかに甘くなっていったか。食後に読んだら本当に吐きそうになった。 食品業界は消費者のことを気にかけるのではなく、ライバルに勝つことが至上なのである。そのために、この三種の神器が活用されている。食料品店は地雷原だ。 けれど、地雷をさけて、何をどのぐらいの量食べるのかを決めるのは自分自身である。地雷の見分け方とか、地雷を踏むとどうなるか、という話より、いかにしてメーカーは地雷を正当化しばらまいているか、というお話でした。
0投稿日: 2014.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ加工食品は化学で成分を調合された工業製品なのだということが良くわかる本。 脳に快感をもたらす糖分、脂肪、塩分を計算され尽くした商品を 安価で手軽という理由で選択せざる得ない貧困層。 その商品を開発した大企業の社員は高所得で、健康な食品を選んで食べているというのが悲しい。
1投稿日: 2014.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ加工食品に仕掛けられた罠は塩、脂肪、砂糖の大量使用。消費者の至福ポイントを探り各成分を組み合わせるメーカーの試みには健康という要素は入っていないようです。
1投稿日: 2014.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログそれでも、おいしいモノを求めるか? 世界に展開する食品系企業は、食べものを扱う企業ではない。 彼らの主たる商品は、欲望。 食品業界は、人々の心地よさ、購買意欲を徹底的に研究した工業製品のエサを作る。 我々の健康ではなく、彼らの利益を最大限にするよう、厳密に調整された精密産業である。 糖分、脂肪分、塩分は、人間の本能、ソウルに働きかける麻薬だ。常習性はあるが、その危険性は摂取する我々自身に向けられるため、危険ドラッグのように規制されることはない。だが、明らかに、世界的に展開する食品企業の商品は、静かに、そして慢性的に、われわれ人間の身体、生活を破壊する。 それでもあなたは、まだ、あのピーナッツバターを食べ続けるのか? あの、砂糖にまみれたシリアルを食べ続けるのか? 舌触りの良い脂肪の豊富な合成食品、本能に働きかける当分、そして過度の塩分を摂り続けるのか?
2投稿日: 2014.11.10自分や家族の食習慣をオーバーホールするためのヒント
読む前は、「食べてはいけない」のような単なる企業告発物を予想していたが、アメリカ食品メーカーの企業史や新製品開発秘話など、かなり読ませて面白い。 業界ではこれまで、糖分や塩分や脂肪分の配合量がある値にぴたりと一致していると消費者が大喜びするという「至福ポイント」を見つけ出すのにやっきになってきた。 ゆえにメーカーにとっては、塩・砂糖・脂肪は、栄養素というより兵器に近いのだが、あまりにもこれら三つの成分が便利でなくてはならい存在になったため、その罠にも容赦なく引きずり込まれることになったと著者は指摘する。 加工食品の原材料とその配合は、熟練の科学者や技術者たちが緻密な計算のもとで設計し、過食をそそのかすように計算し尽くされている。 われわれの脳は、糖分、脂肪分、塩分に目がない。 なら、これらが入った製品を作ればいい。 利幅を稼ぐために低コストの原料も使おう。 次に、『スーパーサイズ化』して販売量をさらに増やす。 そして『へビーユーザー』に照準を合わせて、広告とプロモーションを展開する。 加工食品業界には鉄則や基本ルールがいくつかあり、「迷ったときは糖を足せ」や奇抜な商品を戒める「80%の親しみ」などもその一つ。 また、体に良いとされるーつの成分を前面に出し、消費者が他の事実を見過ごしてくれるよう期待するなんていう姑息な方法も用いられる。 幹部が「われわれは、需要を作り出すのではありません。発掘するのです。試掘して、見つかるまで掘るのです」と語るほど、マーケティングは徹底している。 それによって、チップス類のように、いままでおやつとして間食で食べていたものを、朝昼晩の食事の常連アイテムに変えたり、贅沢品から成分になったチーズのように、いままで単品で食べられていたものを、原料化して消費を増やすことに成功している。 「糖分」 ・ドーナツはより大きく膨らみ、パンは日持ちが良くなる。 ・“かさ”を増し、色合いを良くする。 ・泣いてる子も泣き止むほどの「鎮痛薬」。 ・脳の興奮作用を持つ恐るべき存在。 ・素早く強力な作用を持つ覚醒剤のメタンフェクミンに似ている。 「脂肪」 ・目立たず、さりげなく作用するアヘンに似ている。 ・食品の口溶けや口当たりを良くし、食感を高める。 ・至福ポイントがない。 ・脂肪分は糖分と一緒になると、脳は脂肪分の存在をほとんど検知できなくなり、過食を防ぐブレーキがオフになる。 ・甘さは、好まれる限度があるが、脂肪分は多ければ多いほど好まれる。 ・多くても少なくても気づきにくく見えにくい。 「塩分」 ・「加工食品の偉大なフィクサー」 ・最初のひと口で味蕾に生じる刺激感を増大させる。 ・糖分の甘味を強めてくれる。 ・クラッカーやワッフルをさくさくに仕上げてくれる。 ・パンの膨らむスピードをゆっくりして、工場で大量生産できる。 ・腐敗を防いで賞味期限を伸ばしてくれる。 ・多くの加工食品につきまとう苦味や渋味といった不快な味を覆い隠してくれる。 ・肉の再加熱臭を手軽に解消できる。 「われわれは安い食品という鎖につながれている。安価なエネルギーに縛られているのと同じだ。ほんとうの問題は、われわれが値段に反応しやすいこと、そして、残念だが持つ者と持たざる者との格差が広がっていることにある。新鮮で健康的な食品を食べるほうがお金がかかる。肥満問題には大きな経済問題が関わっているのだ。そのしわ寄せは、社会的資源に最も乏しい人々、そしておそらく知識や理解が最も少ない人々にのしかかってくる」 本書は、自分や家族の食習慣をオーバーホールするための大きなヒントを与えてくれるが、問題は2つある。 1つは、「便利さの対価」をどう考えるか。 われわれは調理という「単調な繰り返し作業」を回避するために、便利さにお金を払ってもいいと考えている。 塩分への渇望は後天的であり、塩分摂取を減らそうとするなら早くから始めることが重要だとわかっていても、忙しい働き盛りの若い夫婦は、子供のために今日も塩分たっぷりの加工食品を買ってくるだろう。 もう1つは、当たり前のことだが「安全な食品を食べたければ金がかかる」ということ。 例えば、スープの滅塩に適した方法は、カーギルの提案する塩化カリウムではなく、新鮮なハーブやスパイスを使うことだが、コストは安価なナトリウムやそれより割高なカリウムよりもさらに上がる。 また食肉は、脂肪分が少ないほど価格が高くなる。影響を受けるのは、無知な人々だけでなく、貧しい地域の人々やその子どもたちなのだ。
9投稿日: 2014.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ肥満の原因と言って浮かんでくるのが糖分や脂肪だ。意外に思ったのが塩分だ。塩は辛いのでくせになるかと思ったら、ポテトチップスやフライドポテトに使われていて食べると「やめられない、止まらない」状態になり、軽く1箱あるいは1パックぺろりと平らげてしまう曲者だ。 このような麻薬や危険ドラッグよりも怖い「合法食品」を売っている食品メーカーの経営者たちはムシャムシャ食べているかと言えば、むしろウナギのようにスルスルとスルーしていると書かれている。体に悪いと言う自覚があり避けているのだな。 「カロリーオフ」などと甘いことを言って売っている飲み物が浮かんでくる。そんな時に思い出すのが、ルミネ バーゲン「チェック ザ バーゲン2012夏」のCMだ。http://www.youtube.com/watch?v=ix9EkjnAfyc 「ウソウソウソおっしゃい」。 「ありのままで♪」と言ってムシャムシャ、ゴクゴクと人間の古い脳の部分に支配され続けると、雪だるまのように「債務」が膨れ上がり最後には体が悲鳴を上げて様々な病気を引き起こす。食品業界の甘いささやきにマインドコントロールされることなく、自分の体を守っていくことの重要性を改めて感じる今日この頃だ。 それにしても肥満を扱った本だけに分厚いなあ。偶然か。
1投稿日: 2014.09.09「何が欲しいかという人々の言葉に基づいて製品や広告を企画する物は、まったくの馬鹿者だ。」
クラフト、ネスレ、ケロッグ、ゼネラル・ミルズ、ナビスコという食品大手企業や穀物メジャーのカーギル、ADM、コカコーラ対ペプシ、マクドナルドを始めとするファーストフードにコンビニのジャンクフード。彼らによって安くて高カロリーで手軽な食品は消費者に届けられる。健康的な食事が讃えられ、肥満や高血圧といった生活習慣病が問題になるというのにどうやって食品会社は売り上げを伸ばしていっているのか。 この本の原題はそのものずばりSALT,SUGAR,FAT。やめられない、止まらないこの魔力的な力に花を添えるのが色々な規制をかいくぐった広告や包装や商品イメージだ。合成着色料、保存料、異性化糖、精白糖に精白小麦、トランス脂肪酸と言った名前は身体に悪い食べ物として人によっては異常に気をつける。上海の食品会社であった様な消費期限の問題や中国だと成長ホルモンなどもよく話題に上る。それらと同等以上に健康に対して被害があるのに思ったほどには敵視されていないのが「塩、糖分、脂肪」なのだ。 糖分を摂ると脳の報酬系、いわゆる快感回路を直撃する。最初は糖分により多幸感が得られるのだが依存症化すると糖分を摂取しないことに我慢ができなくなる。ニコチン中毒や薬物依存も同じ報酬系に働きかけているのだ。人間は糖分が多い味を好きだと感じるようにできているが、あるレベルを超えると魅力が減退する=飽きるようになる。この最適な「至福ポイント」を研究し尽くした食品業界の伝説的なコンサルタント、ハワード・モスコウィッツは炭酸飲料は飲まないし、健康に気をつけパンを食べる量も控えめにしている。 1800年代から1940年までの間朝食用シリアルにほとんど糖分は入っていなかった。コーンフレークを発明したケロッグ博士は砂糖に禁欲的だったのが1949年にポスト社(ゼネラルフーヅ)が砂糖でコーティングしたシリアルを発売すると瞬く間に他者にも拡がり、仕事を持つ母親にとってはシリアルは手間がかからない便利な朝食だった。1975年にアイラ・シャノンという消費者が立ち上がり78種のシリアルの成分を調べたところ1/3は糖分量が10〜25%で1/3は50%近く、最高で71%が糖分だった。このキャンペーンに打撃を受けた食品会社は品名からシュガーを外し、ある程度糖分を抑えはしたが「集中力が増す」「フルーツの香り」と言ったイメージ戦略に切り替え、ヘビーユーザーに狙いを定めて商品を届けている。有名なコカ対ペプシ戦争で一敗地にまみれたコカコーラはダメージを負ったのか?実は両者とも売り上げを伸ばしている。 脂肪も糖分同様に報酬系に働きかける。しかも糖分と違って脂肪にはこれ以上必要ないというポイントが存在しない。酪農業界が低脂肪乳のキャンペーンに使った手も見事で、元々3%程度の脂肪分を2%や低脂肪と表示していかにも身体にいいイメージを植え付けた。米国人は現在チーズ及びチーズもどき製品を1人あたり年間15KG食べているがこれは1970年代の3倍にあたり、炭酸飲料でさえこの間の増加は2倍どまりだ。 脂肪分を減らそうとした消費者が牛乳の消費量を減らしたのに対し、連邦政府は買い取りによる価格維持政策を続け脂肪分を取り除いた牛乳を販売し続けるとともに、大量に余る脂肪分をチーズとして供給した。レーガン政権が牛乳への補助を打ち切ろうとした85年農務省はマーケティングが不得手な牛肉産業と酪農業者に変わり、牛乳100ポンドにつき15セント牛が売買されるたびに1ドルを天引きで徴収しマーケティング費用に充てるプログラムを用意した。牛肉のマーケティング費用は年間8千万ドルを超え、一方で農務省が健康的な食生活をプロモーションするための費用は年間650万ドルだった。しかもこの費用は脂肪だけでなく、塩分や糖分のカットも訴える勝ち目のない戦いだ。 塩分はドレッシング、ソース、スープといったありとあらゆる商品に大量に投入されており、低脂肪・低糖食品さえ例外でない。2012年の研究によると赤ちゃんは生まれた時から喜ぶが塩分はそうではなく、塩分を与え続けた子供は大きくなるとより塩分を好むようになる。塩味の好みは後天的に獲得する物なのだ。ハーブやスパイスを使えば塩分を控えめにしてもおいしい商品はできるが一番の違いはコストだ。 糖分や脂肪にも言えることだが低コストで高カロリーで消費者に好まれる味を拒否するのは食品メーカーにとっては売り上げ減を意味するためこれまで何かが悪者になるとその成分を減らし、こっそり別の成分を増やしてきたのだ。スナック菓子に含まれる塩分量は増え続けここでもヘビーユーザーに狙いを付けている。不規則な食事習慣をスナックで補う人が増え手軽で高カロリーで塩分たっぷりのスナックが食事の代わりになっていく。
2投稿日: 2014.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ糖分、脂肪分、塩分は、栄養素というより侵略兵器。アメリカの加工食品メーカーが、食品化学、人間の生理・心理・社会・脳測定実験や研究を経て、より多く売れ、株主利益を上げる商品を、いかに開発してきたか。 経営トップたちは、自社商品は体に悪いとして食べないわけですから。世界のための社会実験をやっているようなものかも。
1投稿日: 2014.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何が欲しいかという人々の言葉に基づいて製品や広告を企画する物は、まったくの馬鹿者だ。」クラフト、ネスレ、ケロッグ、ゼネラル・ミルズ、ナビスコという食品大手企業や穀物メジャーのカーギル、ADM、コカコーラ対ペプシ、マクドナルドを始めとするファーストフードにコンビニのジャンクフード。彼らによって安くて高カロリーで手軽な食品は消費者に届けられる。健康的な食事が讃えられ、肥満や高血圧といった生活習慣病が問題になるというのにどうやって食品会社は売り上げを伸ばしていっているのか。 この本の原題はそのものずばりSALT,SUGAR,FAT。やめられない、止まらないこの魔力的な力に花を添えるのが色々な規制をかいくぐった広告や包装や商品イメージだ。合成着色料、保存料、異性化糖、精白糖に精白小麦、トランス脂肪酸と言った名前は身体に悪い食べ物として人によっては異常に気をつける。さらには上海の食品会社であった様な消費期限の問題や中国だと成長ホルモンなどもよく話題に上る。それらと同等以上に健康に対して被害があるのに思ったほどには敵視されていないのが「塩、糖分、脂肪」なのだ。 糖分を摂ると脳の報酬系、いわゆる快感回路を直撃する。最初は糖分により多幸感が得られるのだが依存症化すると糖分を摂取しないことに我慢ができなくなる。ニコチン中毒や薬物依存も同じ報酬系に働きかけているのだ。人間は糖分が多い味を好きだと感じるようにできているが、あるレベルを超えると魅力が減退する=飽きるようになる。この最適な「至福ポイント」を研究し尽くした食品業界の伝説的なコンサルタント、ハワード・モスコウィッツは炭酸飲料は飲まないし、健康に気をつけパンを食べる量も控えめにしている。 1800年代から1940年までの間朝食用シリアルにほとんど糖分は入っていなかった。コーンフレークを発明したケロッグ博士は砂糖に禁欲的だったのが1949年にポスト社(ゼネラルフーヅ)が砂糖でコーティングしたシリアルを発売すると瞬く間に他者にも拡がり、仕事を持つ母親にとってはシリアルは手間がかからない便利な朝食だった。1975年にアイラ・シャノンという消費者が立ち上がり78種のシリアルの成分を調べたところ1/3は糖分量が10〜25%で1/3は50%近く、最高で71%が糖分だった。このキャンペーンに打撃を受けた食品会社は品名からシュガーを外し、ある程度糖分を抑えはしたが「集中力が増す」「フルーツの香り」と言ったイメージ戦略に切り替え、ヘビーユーザーに狙いを定めて商品を届けている。有名なコカ対ペプシ戦争で一敗地にまみれたコカコーラはダメージを負ったのか?実は両者とも売り上げを伸ばしている。 脂肪も糖分同様に報酬系に働きかける。しかも糖分と違って脂肪にはこれ以上必要ないというポイントが存在しない。酪農業界が低脂肪乳のキャンペーンに使った手も見事で、元々3%程度の脂肪分を2%や低脂肪と表示していかにも身体にいいイメージを植え付けた。米国人は現在チーズの類いを1人あたり年間15KG食べているがこれは1970年代の3倍にあたり、炭酸飲料でさえこの間の増加は2倍どまりだ。 15KGのチーズのカロリーは成人一人の1ヶ月分の必要カロリーをまかない、飽和脂肪酸は推奨される年間上限の50%、3.1KGにもなる。チーズは単独の食品としてだけでなく、ピザ、サンドイッチやありとあらゆる加工食品に使われている。クラフトが開発した冷蔵せず何ヶ月も日持ちする工業的に処理(といっても暖めてかき混ぜることなのだが)したチーズは模造チーズやら何やらの食欲を失う名前を退け、「プロセスチーズ」としての地位を確立した。 脂肪分を減らそうとした消費者が牛乳の消費量を減らしたのに対し、連邦政府は買い取りによる価格維持政策を続け脂肪分を取り除いた牛乳を販売し続けるとともに、大量に余る脂肪分をチーズとして供給した。レーガン政権が牛乳への補助を打ち切ろうとした85年農務省はマーケティングが不得手な牛肉産業と酪農業者に変わり、牛乳100ポンドにつき15セント牛が売買されるたびに1ドルを天引きで徴収しマーケティング費用に充てるプログラムを用意した。牛肉のマーケティング費用は年間8千万ドルを超え、一方で農務省が健康的な食生活をプロモーションするための費用は年間650万ドルだった。しかもこの費用は脂肪だけでなく、塩分や糖分のカットも訴える勝ち目のない戦いだ。 牛肉の消費を推進するもう一つの武器が悪名高い「ピンクスライム」。元々ペットフードなどの製造に回されていた最大70%と脂肪分の多い肉を遠心分離機にかけ脂肪分を分離させる。そして食肉工場で他のクズ肉と混ぜ合わされ、殺菌のためアンモニア処理をすると出来上がるのがピンクスライムだ。脱脂牛肉の原料として使われるのは解体中に糞便が付着しやすく大腸菌汚染の怖れが他の部位よりも高い。ピンクスライムはさじ加減を間違えると強烈なアンモニア臭か大腸菌のいずれかが残るが1ポンドあたり3セント節約できるのだ。 塩分はドレッシング、ソース、スープといったありとあらゆる商品に大量に投入されており、低脂肪・低糖食品さえ例外でない。2012年の研究によると赤ちゃんは生まれた時から喜ぶが塩分はそうではなく、塩分を与え続けた子供は大きくなるとより塩分を好むようになる。塩味の好みは後天的に獲得する物なのだ。ハーブやスパイスを使えば塩分を控えめにしてもおいしい商品はできるが一番の違いはコストだ。 糖分や脂肪にも言えることだが低コストで高カロリーで消費者に好まれる味でしかも原料として安い。これを拒否するのは食品メーカーにとっては売り上げ減と利益減を意味するためそう言う決定はなかなかできない。だからこれまで何かが悪者になるとその成分を減らし、こっそり別の成分を増やしてきたのだ。スナック菓子に含まれる塩分量は増え続けここでもヘビーユーザーに狙いを付けている。不規則な食事習慣をスナックで補う人が増え手軽で高カロリーで塩分たっぷりのスナックやファーストフードが食事の代わりになって行く。 中国が安いエネルギーを必要としとうとう我慢できなりつつある大気汚染にも関わらず石炭を燃やし続けるようにアメリカの貧しい家庭では食事の手間を省くため安いカロリー源としてファストフードやスナックが食べられ続ける。ネスレのように同じだけの至福感を糖や脂肪や塩分を減らして得られる様な製品の開発を続ける企業もあるが、これまでのところはそう言う取り組みはあまり成功してこなかった。どうやらちゃんとした食事を食べられるということが贅沢なことになってしまっているらしい。
2投稿日: 2014.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ糖分・脂肪分・塩分に関する内容。 訳本なので、当然海外の事例が多く 直接的に理解できる内容ではないけど面白く 読みました。糖分・脂肪分・塩分の麻薬にも似た 常習性があることがよくわかる内容です。 私も倒れてから食生活を見直さなければなった際に コンビニやスーパで食料品を買う際にパッケージの 成分を見るようになって、習慣として癖 になっています。そこで救われている部分はあると 思いますが。まだまだ適正体重ではないので 節制が必要なのですが。 塩分は特に気をつけるようになりました。。 後、ダイエット法というか糖質制限ってどうなったの でしょう。。それって脂肪はいいんじゃなかったっけかなあ? でも、一応日本での一般的な生活をしていれば (まあ無茶しなければ)そんなに心配ではないと思うのですが。。。(さらに)でも、体重は減らないなあ・・・
2投稿日: 2014.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログコカコーラ、ネスレ、クラフト、ゼネラルフーズ等の巨大食品会社が、清涼飲料水、冷凍食品他の販売競争を繰り広げる中で、糖分、脂肪分、塩分の内容量がいかに増していき、米国人の健康を害しているかを明示的に示した本。 過去何度も加工食品に含まれる糖分、脂肪分、塩分の健康への悪影響が指摘される中で、食生活の健康への影響は総合的なものだ、との主張で切り抜けて来たが、その都度これらの成分比率や健康障害は増してきている。 当の巨大企業で働くエグゼクティブたちは、自分たちが販売する食品の危険性を良く知っており、(昔ながらの)手料理中心の健康的な食事と適度な運動により健康を維持している、というエピソードが象徴的。 日本ではここまで清涼飲料水を始めとする加工食品への依存や肥満が国家的問題にはなっていないように思うが、検証するジャーナリストは誰か出て来るのだろうか。
2投稿日: 2014.08.18
