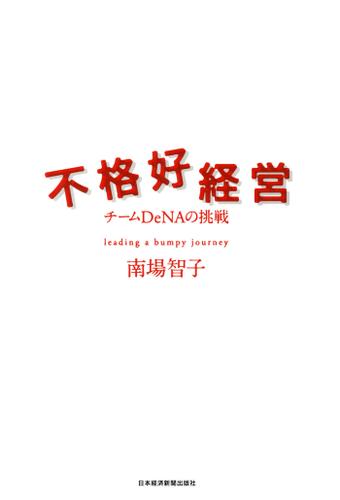
総合評価
(480件)| 172 | ||
| 179 | ||
| 67 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNA誕生~成長秘話としても面白い内容ですが、それ以上に、帯で謳われるように、 「経営とは、こんなにも不格好なものか。だけどそのぶん、おもしろい。最高に。」と、 社長業とは何なのかを問うた著書だと感じました。 特に意思決定の進め方(決定的な重要情報が欠落していなければ継続討議にはせず、 決断をする/決定的な重要情報が欠落しないよう、事前にすり合わせる)は、 あたり前かも知れませんが、担当として、自分ができているか再確認…。 ■社長業、組織/人に関して印象的なメッセージ ・守安(現社長)を増やしたい。そういう人材がどんどん生まれ、 あるいは引き寄せられ、そして埋もれずにステージに乗っかって輝く組織にしたい。 そうすれば、会社が成長するだけでなく、本質的な強さを手に入れることになる。 ・春田(現会長)が入社してしばらくのころ、DeNAを南場カンパニーにしたいのか、 それとも公器として育てていきたいのか決めてくれと言ってきた。 熟考のうえ、社会の公器として発展させるために責任を果たすと決意。 ・社長の一番大事な仕事は意思決定。私のところに来る事案はトップマターのみで、 それ以外はほかの役員や現場に委ねられているが、それでも多くの事案がある。 この意思決定について「継続討議」にしないことが極めて重要。 「決定的な重要情報」が欠落していない場合は、迷ってもその場で決める。 ・「決定的な重要情報」が欠落しないよう、頭出しとして報告を受けた際、 意思決定にはどのような情報がポイントとなるのか、大まかにすり合わせて おくことが重要。この方法でDeNAでは遅滞ない意思決定を実現。 ・意思決定のプロセスを論理的に行うのは悪いことではない。 でも、そのプロセスを皆とシェアして、決定の迷いを見せることが、 チームの突破力を極端に弱めることがある。 ・むしろ、迷いを見せない方が成功確率は格段に上がる。 迷いのないチームは迷いのあるチームよりも突破力がはるかに強い。 ・事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、 それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」とういことが重要。 ・ギリギリな仕事を任せれば当然、失敗するリスクもある。 でも、、不思議と人は顕在化している能力の数倍を有していて、 本人も驚くような大仕事をやってのけるものである。 万が一できなければチームが寄ってたかって助ける。 まれにそれでもカバーしきれず、穴があくこともある。 そのリスクはとろう、でも人が育たないリスクはとらない。 ・自分の「成長」への意識はしかし、ほどほどなほうがよいと考える。 自分の成長だへちまだと言う余裕がなくなるくらい必死になって 仕事と相撲をとっている社員ほど、結果が出せる人材へと 驚くようなスピードで成長する。 ・優秀な人はアクションに対するアドバイスをすると、必ず素直に徹底的にやる。 一方、結論に関するアドバイスをしても、心底納得するのに時間がかかる。 「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」。 労を惜しまずにコトに当たり、他人の助言にはオープンに耳を傾ける、 しかし、人におもねらずに、自分の仕事に対するオーナーシップと思考の 独立性を自然に持ち合わせている、ということではないかと思う。 ・会社の雰囲気が良いのは、「任せる」ことを徹底しているからではないかと思う。 ①全員が主役と感じ、1人1人が仕事や成果にオーナーシップを感じるような チームの組成、仕事の単位となっているか。 ②チームの目標はわかりやすく、そして高揚するに足る十分に高い目標となっているか。 ③チームに思い切った権限移譲をしているか。信じて任せているか。 ・守安は、事業部門だけでなく、コーポレート部門やサポート部門のスタッフに 対してもまるっと「目的単位」で仕事を任せる。 この任せる勇気が活気の源ではないだろうか。
0投稿日: 2013.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログベイスタファンだからと言う理由で手に取った一冊。まぁ売れてるし。 女性の書くビジネス書の面白さ(男性のつまらなさ)は日経新聞私の履歴書を読んでても痛感することだが、 私情満載、感情豊、ユーモア抜群、仕事の話少々 これくらいの方が読んでいてその生き様も仕事の仕方も人との触れ合い方も手に取るように伝わってくる。 どこそこのお偉さんに会い、どこそこのプレゼンが云々かんぬんはあまり好きになれず、こうゆう本が本当に好き。一日で読み切りました。 南場さんの熱い思い(少し軽蔑していた)に心動かされ、この会社に親会社になってもらい、横浜ベイスターズファンとして嬉しい限り。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
響いた所をメモ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ・調整ではなく決めるのが仕事 ・商売人は、買ってもらえなかった時にどれだけいい笑顔を見せられるか ・複雑なプロジェクト管理から作業的な地味な仕事まで、想定外に発生した仕事も全部拾う ・数字と論理に強く、部門を統率出来るブレなさ、強さ ・目を三角にして怒るな ・継続討議は逃げ。 ・意思決定前の頭出しの時に、意思決定にはどのような情報がポイントとなるかを擦り合わせる ・社長を使おう、使い倒そうという現場 ・私をこき使わなければ私がこき使う ・意思決定のプロセスを皆とシェアして決定前の迷いを見せることが、チームの突破力を弱めることもある。実行チームに決定プランを出すときは、これしかない、これでいくという信念を全面に出す。迷いは見せない。 ・重要情報はアタッシュケースではなくアタマに突っ込む ・人の評価を語りながら酒を飲まない ・失敗を他人事のように話さない
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんとDeNAの経営にはずっと興味があったので、こういう形で書籍となってまとめて読むことができたのはありがたい。 久しぶりにこういう経営的な書籍を読んだからというのもあるけど、すごく面白くて一気に読んだ。 何気なくだけど、すごく読みやすく書かれていて、上手な文章だなあと思った。 -- unleaning(学習消去) 検討に巻き込むメンバーは一定人数必要だが、決定したプランを実行チーム全員に話すときは、これしかない、いける、という信念を前面に出したほうがよい。本当は迷いだらけだし、そしてとても怖い。でもそれを見せないほうが成功確率は格段に上がる。 (コンサル特有の)自分を賢く見せようとする姿勢、一銭にもならない。 なんでも3点にまとめようと頑張らない。物事が3つにまとまる必然性はない。 人の成長は階段型 あと10年もすれば、組織に属して仕事をするスタイルは主流ではなくなる。目的単位でプロジェクトチームが組成され解散するようになる。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はかなりおもしろい。 ベイスターズを持つDeNAの創業者である南場智子氏の、創業当時からご主人が病に倒れ取締役となる現在までの様々な経験が、とても正直に書かれている。 よくある成功体験本の類の本ではなく、タイトルの『不恰好経営』からも感じられるように、会社を立ち上げてから経験したありとあらゆる失敗が書かれている。 どちらかというと『エッセイ』っぽい。彼女の周りの社員とのからみからは、気さくで、素直で、少々頑固な彼女の人柄と、彼らへ尊敬と感謝の気持ちが伝わってくる。 たくさんの経験から発せらた彼女の言葉には納得感がある。 ・狙っても達成できないような難しいことが狙わずにできるわけがない。 ・迷っても継続討議にしないことが重要。情報不足と決定を一週間伸ばしても、新たな情報で一週間後にまた迷う。 ・任せる。人は人では育たない。人は仕事で育つ。 ・正しい選択肢を選ぶのは難しいが、選んだ選択肢を正しくすることが重要 多分ベストセラーになると思う。 もうなってるのか?
0投稿日: 2013.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ立ち上げの顛末は面白かったが、途中から記事広告な感じがした。筆者には本書を通じて読者に自社を好きになってもらう以外に伝えたいことはあったのだろうか。
0投稿日: 2013.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA創業者、南場智子氏の話題の著。 口語調で書かれており、かつとてもテンポのよい文章なので一気に読むことができた。 1度講演を聞いたことがあるが、その人柄が文字にも表れていて、こんな人と一緒に働いてみたいなと改めて思わされた。 それにしても成長する企業には何らかの共通項があるような気がしてならない。それは仕事に対する熱意のような気がするが、この類の本は結果に対して言及するから美化されて写って見えるだけなのか。このあたり、解明できたらおもしろい。 仕事に関して熱意がなくなったり、迷うことがあった場合にもう1度読みたいと思う。 ある選択は失敗や成功となるのではなく、その選択が成功となるように努力することが大事であると。納得。
0投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA創業者の南場さんの本。 とにかく、DeNAに対する「愛」を感じる一冊だった。 守安さんの面白いエピソードなど、DeNAの裏側?も読んでて、人間味あふれる感じでよかった。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の自分に非常にためになるエピソードがたくさん詰まっていました。転んでは立ち上がり、また転んではまた立ち上がるというDeNAさんの姿勢が組織として強くなっていく要因だと感じます。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前から気になっていた南場さんの本をついに購入。起業に伴うリアルな苦労話が満載でとても面白く、2時間ほどで一気に読破してしまった。 それにしても、大前さんをはじめとするマッキンゼー人は、起業においても天下無敵と勝手に思いこんでいたが、決して万人がそうではないということもよく分かった。つまり論理的思考力とは、経営(事業運営及び推進)スキルとしては必要条件ではあるが、十分条件ではないということを今更ながら改めて理解。この本は、私のようにベンチャー企業に勤めている人間としては、同感できる部分が多いだけでなく、このように改めて学ぶべき点も多かった。 また、汗と涙と苦労にまみれて泥臭く会社を成長させていく南場さんやその他皆さんの姿がとても人間らしく(笑)、これもまた、この本をグイグイとのめり込んで読み入ってしまう一つの魅力であると感じた。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタントから事業リーダーへの転身、そのなかでもがき苦しんだ様々を著してます。不格好とタイトルにあるけどめちゃめちゃ格好いい。 印象的なとこ引用 ・「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。 ・労をおしまずにコトにあたる、他人の助言にはオープンに耳を傾ける、しかし人におもねらずに、自分の仕事に対するオーナーシップと思考の独立性を自然に持ち合わせている。 ・「誰が言ったかではなく何を言ったか」という表現を用いて、「人」ではなく「コト」に意識を集中するように声を掛け合っている。 文章がスルスルと入ってくる、この人ホント書くのが上手だなあ。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者の自伝。生い立ちから、起業の経緯とその後の発展、個人的な出来事などが、軽妙なタッチで面白おかしく書かれている。創業期の七転八倒や人材集めの部分は特に面白い。コンサルタントとしての考え方と企業経営の違いもわかりやすく述べられているが、一流のコンサルタント会社からの出発で、その人脈の豊かさには驚かざるを得ない。エネルギッシュな著者の今後の活躍が楽しみ。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNAという会社には興味が持てませんが、この本を読まなければならないと思いました。 私はこの南場智子さんのことがどうも好きになれません。向こうも別に私などに好かれなくても何も困らないと思いますが(笑) でももしかしたら自分はこの方のことを実は全く知らずに、イメージだけで嫌いなのかもしれないと思って、この本を読むことにしたわけです。 これまでも雑誌の記事や日経ウーマン・オブ・ザ・イヤーを受賞されたことなどで、少しは知っていましたし、ビジネスパーソンとしては優秀ですごい人なんだろうなとは思ってました。 本の感想だけ申し上げれば、この本は、優秀な方であっても起業というものがいかに難しく大変なものなのかを教えてくれますし、南場さんの仲間への愛を十分に感じましたし、プロフェッショナルとしてどう生きるべきかということも学べたと思います。とてもいい本だと思います。 ですが、やはりこの方の生き方とDeNAという会社のことは肯定的には考えられませんでした。 モバゲーだけが悪いわけではないですが、こういう類のSNSと携帯やスマホで遊ぶゲームが、どれだけ社会に負のインパクトを与えているかについて、全く考えておられないのではないかと思います。 コンプライアンスという言葉の名の下に、法令さえ守っておけばいいんでしょ、という意識が感じられるどころか、若い世代のSNS利用において発生した問題や、コンプガチャに代表される収益の上げ方に対する反省は、ほとんど書かれていません。残念ながら。 別にだましているわけじゃなくて、利用者が自由意思で使ってるんだから、何が問題があるの?という感じなのでしょうか。。。 企業って、法令だけ守っていればいいんでしょうか? この方は確かに優秀な方でしょうし、DeNAという会社は優秀な方が非常な努力をして発展させたものなのでしょうが、まったく尊敬できません。 というか、これだけ優秀な人たちが、社会問題を解決するどころか、多少社会に負の影響を与えていることを平然と行っておられることが、残念でなりません。 若い方には本書は勧めません。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋さんでふと立ち読みしたら、非常に面白く、やめられなかったので購入。元マッキンゼーの著者がさまざまな苦労を経験する様子や、優秀なメンバーとビジネスを大きくしていく姿が生き生きと描かれており、さながら青春ドラマ(?)のようにさわやかである。DeNAって単なるゲーム屋さんと思っていたが、体育会系のサークルっぽい面白そうな会社という印象に変わった。やっぱり最後は「人」なんだと再認識。
0投稿日: 2013.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ事業会社でやっていくことが純粋に羨ましくなった。 コンサルとか知識を売りにする業界横断型のビジネスしている会社から独立目指す人に早く読んでおくべきだなと思わせる本。 語り調が読みやすい。
0投稿日: 2013.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直、5章までの話はどうでもいい。どこにでもある失敗談と回想記です。 6章以降がいい。 家族の不幸に対する考え方の変化やさくらを一緒にみるといった話は、ぐっと来る。自分もこうありたいです。 7章の人材と組織に対する南場さんの思いがストレートに伝わってとてもいい。 ここの部分だけでも読む価値はあったかな。
0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆『不恰好経営』読了 ★4つ(5点満点) 以前から面白い文章書くな~と思っていたDeNA元社長南場さんの本。 http://www.amazon.co.jp/dp/4532318955 (奥さんから「中国語?」と言われたけど、確かにそんな感じの題名(^^)) タイトル通り、ここまで書いちゃいますかというほど、失敗談、その時の心情などを赤裸々に書いています。 マッキンゼー出身にもかかわらず戦略的なところに触れている部分はほぼ皆無です。 失敗談を書いている経営者の本はありますが、ここまでぶっちゃけているのは少ないのでは? しかも、独特のおちゃらけた文体で面白いです。 印象に残ったのは、下記辺り。 『事業リーダーにっって「正しい選択を選ぶ」ことは重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる』 マッキンゼーで「正しい選択を選ぶこと」を徹底的にやってきた著者だけに重みがある言葉。 なお、この本を読んで勘違いしてしまいそうなのがこの言葉の解釈。ロジカルに戦略を考えた話がほとんどでてこないので「結局実行(のみ)が重要だよね」となってしまいがち。 しかし、マッキンゼーのパートナーまでつとめ、あとがきでも「なにごとも理詰めで考える、」という著者が戦略やロジックを考えていないわけがないし、「正しい選択を選ぶこと」を否定しているわけではない。 計画、戦略や実行、ロジックと気合。これらのバランスが重要なのだろう。
0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログまずはDeNAがとても好きになった。 やっている事業とかではなく、面白そうな人がいるなと感じた。 この本のタイトル通り、不格好な体験がかなり書かれていた。 「システムが全く完成していなかった」、「ダイエットラリー」、「マッキンゼー時代の話」など読んでとても親近感が湧いて何度も笑いながら読めて欲しかった。 この話を読んでいると、 事業を起こして経営するという事は、とても綺麗でカッコいいことではなく、不格好な事ばかり何だと感じた。 なんだか、全然話がまとまらないので、 また読んでからレビューを書こうと思う。 多分すぐ読みたくなるはず。
0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの立ち上げから今に至るまでが赤裸々に、登場する人たちのキャラが立っていて読物として本当におもしろい。 今の日本でこんなに泥々と、でも活き活きと仕事している人たちがいるいるということは新鮮だった。
0投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直なところ、そんなに面白いとは思わなかったけど、企業というのは、「1人の天才だけでは成り立たない」ということを思い知らされた。ネットオークションやモバイルゲームといった DeNAのサービスには全く興味がないけど、会社立ち上げから10年で売上が1,000億円ってすごすぎる。
0投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業のドタバタが満載で一つのドラマです。後になって振り返ればなぜあんな失敗したのか、と思うのでしょうが、当事者達はその時、それしか考えられないのでしょうね。次につなげることが大切であると感じます。 心に残ったフレーズを2つ。 ・ユーザーの視点で会社を見ていただける個人株主を増やしたいとの考えから、毎回週末に総会を開催している。 →土日に株主総会を行う企業は上場企業の約1% 誰に来て欲しいか、を軸に考える 数少ない企業の1つであることが伺えます。 ・今日決めたことは明日実装されるスピード感がモバイルサービスには不可欠だと認識していた。 →モバイルサービスでお客様の支持を得るには、 このスピード感で他社と戦わねばならない。 お客様の前で、会社の規模は関係無いですからね。 以上、雑感ですが。
0投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最高によかった!不格好なんて謙遜しているけど、とても格好いいと思う。 南場さんとは、10年前に一度か二度、一緒に食事をさせていただいたことがあるが、本当に気さくな方で、こんなに優秀な方とはそのときは全く知らなかった。一緒に同席していたこちら側の役員が「おまえたちは今、すごい人に会ってるんだぞ。あと何年かしたら、二度と会えないような、天上人になってるからな」と言っていたのが、今でも忘れられない。本当にその通りになった。 DeNA設立までの苦労や、その苦労を一緒に乗り越えてきた仲間たちとの深い絆とその感動、会社や社員に対する熱い想い、七転八倒の飽くなき挑戦心、家族(旦那さん)の突然の癌宣告との闘い。 南場さんの素晴らしいところは、決して偉ぶらず、飾らず、諦めず、勉強家でチャーミングなところ。チャーミングというのは、ご本人も本書のなかで述べていたが、これがある人とない人では、「つかむものが大きく違ってくる」。仕事上は、チャーミングなんてどうだっていい、むしろウザイと思ってこれまで避けてきた私には、重い言葉だった。 優秀な人とはどういう人か。それぞれに優秀な人はいるわけで、一言で共通して表現するのは難しいと言いながらも、あえて言うなら「素直だけど頑固な人」「頑固だけど素直な人」というのも、頷けた。周りに優秀だな、すごいな、と思う人はいるけど、自分はそうじゃない。じゃあ自分に足りていないのは何だろう、と思ったら、「素直」なことだった。頑固なだけで、謙虚さがない。 謙虚な人は、勉強もするし、多様性を受け入れるし、偉ぶらないし、飾らない、恥を恐れない。頑固な人は、諦めない、曲げない、とことん突き詰める。 これを持ち合わせた人は、自然に前向きになるし、バイタリティも必要になるから、当然まわりからも行動力があって、信頼に値すると評されるのではないだろうか。 全体的に、笑いあり、涙あり、怒りあり、悲しみありの、本当に南場さんらしい、人間性が滲みでた経営者論(というより自叙伝に近い?)だった。 ビッターズ立ち上げ当初にオークションに出品した自前ネタが、「大前研一に電話で15分間罵倒される権利」っていうアイデアも面白かったし、それが7万円で実際に売れたのも笑えた。 mixiがDeNAの悪評を立てているという噂の真相を確かめるべく、直接笠原さんに電話しちゃうところも南場さんらしかったし、気持ちよく仕事するために正面からぶつかるところは素敵だと思った。 そして、ネット業界での真の競合は、会社ではなく、「ユーザーの嗜好のうつろいのスピード」というところも、鋭い指摘だった。よくそういわれるけど、本当にそうなの?コアな部分ってそんなに変わらないんじゃないの?っていうのが私の定説だが、そもそもその「コア」な部分に、「もっと」いいもの・便利なもの・面白いものが出てくれば人間はそれを求める、ということが入っているわけで、ネットのなかで日々次々と出てくるサービスや機能は、まさにその「もっと」を与えるイノベーションなのだ。だから、オンラインマーケティングやネットビジネスにかかわる人たちは、このことを肝に銘じておかなければいけない。 マッキンゼー時代のコンサルタントから事業者になって、立場や考え方が180度かわり、マッキンゼー時代の経験が活きる場もあれば、ほとんどは役にたたなかったと言い切っているところもいい。そもそも手伝う側と実行する側では、立場(責任)も違えば、資質も違う。だから、経営者になる前にコンサルタントになる考えは邪道だと、巷の定説を覆すのも、それだけの経験があってこそ重みがある。 南場さんは本当にフラットで自立した人だと思う。それは実際にお会いしたときにも感じたし、この本を読んで、ものすごくそれが伝わってきた。「南場さんについていきます、と言われた、全力で断る」。これがすべてを語っている。そもそも他力本願な人、受け身の人は、一緒に仕事していてもつまらないんだと思う。 DeNA卒業者の光森くんのALLメールの引用もよかった。DeNAを就職先に選んだとき、DeNAを辞めて文筆業を選んだとき、みんなに「お前、そんな選択して大丈夫か?」と言われたが、「”選択”に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけだと信じています」。これは彼自身が生み出した言葉というより、DeNAが彼を通じて生み出した言葉なんじゃないかとすら思う。そういう意味でもDeNAはDNAだ。 いいところばかりじゃない。悪いところもある。会社もそう。私生活もそう。この本ではいいところばかりでない悪いところも正直に書いているし、謝ってもいる。 プライベートでは、夫婦ともに仕事が大好きで決して家庭的ではなかったが、突然の旦那さんの癌宣告に、社長を退任。いままで顧みなかった家庭について、彼女はこう述べている。 「今を起点にベストを尽くす。10年以上経営者をやり、(何があっても動じない)そういう訓練だけはしてきたはずだ。過去を悔いても仕方がない。これからだ。告知されてからずっと暗い不安の淵に行ってしまった夫の目を思い出す。今行くから。助けに行くから。これまでの人生は全部このときのためにあったんじゃないだろうか。そんなふうに思った。」 この本を書くにあたって、私生活での不慮の出来事がきっかけの1つにはなったのかもしれないが、何より、普段言えない感謝の気持ちを関係者に伝えたかったというところも、本を読んでいるととてもよく伝わってくる。この本を読んだ関係者の方たちは、絶対どこかで泣いていると思う。私でさえ、そんな南場さんの飾らない熱い想いが伝わってくるんだから、関係者はよっぽどだと思う。会社設立時に出資してくれたリクルートの信圀さんの話が最初にちょろっと出ていたが、あとがきで一番お礼を言いたかったのは信圀さんだったことがわかる。リクルートからの人材の転出が起因して、二人の仲がこじれたが、55歳までは合わないでおこうと約束したが、44歳で他界される。天国の信圀さんは、南場さんをもう許してくれていると思うし、旦那さんを助けてくれている一人なのかもしれない。 とにかく、久々にとてもよい本を読ませていただきました。元気がでた。ありがとうございました。
0投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下、本文より引用。 自分の「成長」への意識はしかし、ほどほどなほうがよいと考える。・・・入社してからも「成長」オタクのように成長、成長という人は少し変だ。成長はあくまで結果である。・・・ そして、皮肉にも自分の成長だへちまだなどと言う余裕がなくなるぐらい必死になって仕事を相撲をとっている社員ほど、成果が出せる人材へと、驚くようなスピードで成長するのである。 妊娠出産前の自分はこのスタンスに近かった。今はどうだろうか?自分の成長に軸足を起き過ぎているかもしれない。
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAはベンチャー企業から一流企業になったとはわかっていても改めて時系列に追っていくと短いスパンでよくここまでと思わせる。
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社というのは、人が作っていくものなのだなぁ、としみじみ思う。多分、使ったことのあるサービスはひとつもないけど、システムの裏側には人がいるんだよなぁ。 あちこちで涙ぐんだけど、何に起因するのかよくわからない。
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
同僚に借りたもの。 軽く読めるかなあと思ってましたが、存外面白く、買いたくなりました。 そんな話をしたら、快く1000円で譲ってくれました〜^_^ 付箋がたくさんついた。いち経営者の目線は監査的にも参考に。 旦那さんが癌になり、社長を辞めるわけだけども、その辺りは少しうるっときました。 ・p154 公取委立ち入りでの社内メール ・p160 買収後の関与 ・p179 守安調査レポートって、気になる。世のため、公開してほしいっすね。 ・p200 採用活動について ・p214 人が育つ組織 ・p221 誰が言ったでなく、「何」を言ったか ・p242 会社の雰囲気がよい理由。小手先のイベントではなく、「任せる」ことを徹底しているからではないか。
0投稿日: 2013.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ発売日に買って読み始めていたが半ばで自分の仕事が忙しくなり タスクに追われるのを良いことに読了せずじまいのところ、やっと読み終えた。 いきなり話は逸れるけれども、南場さんの文章に僕が初めて触れたのは、 就活生時代、タイトルは忘れたがコンサルタントとはどういう仕事か、について オムニバスでコンサル出身の著名人が語っていくという内容の本の中であった。 コンサルタントの経験が経営者になった時に活きるわけではなく、 むしろハンデにもなり得るというのをキッパリと明言していたのが あまりにも鮮烈だったので今でも覚えている。 コンサルタントという仕事を否定しているわけではなく、 あくまでスペシャリストとしてのコンサルタントという考えが コンサルまわりの仕事に強く興味を持っていた自分には驚かされた反面 妙に納得させられたものがあり、だからこそたとえ将来経営者となり コンサルの経験がその時ハンデとなろうとも スペシャリストとしてのコンサルタントという仕事に尚更惹かれ、 コンサルまわりの企業の説明会をひたすら回っていた。 結局更に別の欲が出て「手も動かして自分で事業の舵をきるコンサル」という 今の仕事に巡り会ってしまったわけだけれども、 自分がコンサルタントへの憧れや敬意の念を 確かなものにするきっかけとなったのは南場さんの価値観に触れられたからだと思う。 当時のDeNAにも、会社説明会だけ参加した。 直接南場さんがセミナー形式で話をしてくださっていた中、 その場でもコンサルと経営者の違い、というのが話題に挙がっていて やはりこの価値観はぶれてないのだな、と感じたのを記憶している。 不格好経営について話を(やっとここで)戻すと、 藤田さんの「起業家」を読んだ時にも感じたのが、 人はとかく結果論の成功談よりも失敗してきた話、苦労話の方が 引きつけられ真に学ぶものがあるということ。 「ここまでかというほどひどい」と南場さん自身も語るような歴史を歩んできた中でも、 その失敗の連続をひとつひとつ確かな血や肉に変えていったのが この会社の強さだったというのをひしひしと感じさせる。 「賢者は歴史から学ぶ、愚者は経験から学ぶ」とも言われるが、 それは逆に言えば誰もやったことのないことに 挑戦してしまったなら賢者になれずとも泥臭く進んでいく他無いのだろうと思う。 不格好とは銘打っているけれども、まさにこの不格好こそが 道を切り拓いていく中でのロールモデルなのかもしれない。 自分もまだまだもっと不格好に、コトを成していこう。
0投稿日: 2013.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんがとにかくかっこよかった。一貫した姿勢、そして、このひともきっとチャーミングなんだろうな、と思った。数ページおきに泣きそうになる気持ちもわかる。 こんな生き方、ちょっとしてみたいけど、ぜったいできないけど、でももしかしたらできるかもな、どうかな。 それにしても、こないだエニグモの本読んだときも思ったけど、ベンチャーの立ち上がりというのは、ほんと泥臭くて一生懸命でなりふり構わずなんだなぁ。とてもアタマがきれる方々が必死で考えて奔走してできるもんなんだなぁ、と思うと、いやはや、会社ってすごいわ。
0投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白く笑いながら読んだ。ビジネス書というかエッセイというか、ジャンルなんてない本だ。 チームは同じタイプの人がたくさんいるより、違う個性の人がたくさんいたほうが強いんだとこの本を読むとわかる。流行りの言葉で言えばダイバーシティーになるんだろうけど、そんなに堅苦しくガチガチにやっていくのではなく、南場さんの考えから自然と多様性を許容する会社になっていったように見える。 新人でものびのびと仕事をやって、成果がでていることにびっくり。個人の努力と個人の能力を伸ばす会社とがいい協調関係を作っているのだと思う。
0投稿日: 2013.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、DeNAを短期間で業界を牽引する存在に育て上げ、プロ野球チームのオーナーになるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長を続けてきました。 しかし、その内情は「誰か遠い他人の仕業と思いたいほど恥ずかしい失敗の経験の連続」で、その失敗の連続を、ひとつひとつ血や肉として強さに結びつけていったとのこと。 詳細なレビューはこちらです↓ http://maemuki-blog.com/?p=838
0投稿日: 2013.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ・経営者は調整ではなく、決めることが仕事 ・時代の波をとらえ、タイミングに合ったものを一番使いやすい形で出す ・本当に重要な情報は当事者になってはじめて手に入る ・リーダーは『正しい選択をする』ことと同等に、『選んだ選択肢を正しくする』ことも重要 ・自分のアホさをさらけだして、他人に協力してもらうことが経営者には必要 ・コンサルが良いとは思わない。無駄に3つにまとめたりしない ・多様な軸で、それぞれトップレベルの人材が必要 ・採用に必要な2つ『全力で口説く』、『誠実に口説く』 ・優秀な人は『素直だけど頑固』 ・人についていくことはできない、人ではなくコトに意識をすべきである
1投稿日: 2013.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの人生の面白話が詰まっている。怪盗ロワイヤルが出てくる所までが本当にベンチャーチックというか、山あり谷ありで吹き出してしまうくらいの逸話も。
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの人柄がにじみ出ている本。たいていベンチャーの創業者が書いた自伝はつまらないと相場は決まっているが、この本はさにあらず。まあ、自分の家の出自とかハーバードのMBAに行ってたことがぼかされてたりとか脚色も感じはしますが、ベンチャーがどうやって大きくなっていくのか、ダイナミックに動いているのかというのが臨場感を伴ってわかります。むかーしDeNAへの転職の薦めを転職会社から受けたことがありましたが、行っとけばよかったか、と思ったというのが一番わかりやすい感想でしょうか。
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ【NAVERまとめ DeNA南場さんの講演「ことに向かう力」がいい話だったので全文読め】http://matome.naver.jp/odai/2137283171836034701 を読んで面白そうだったので。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ人や組織ではなく、“コト”に向かうことに集中する企業風土、創業メンバーの共通項がDeNAという企業の文化の特徴だと、著者、創業者の南場さん本著で語る。 最近読んだビズリーチ南壮一郎さんの著作にしても、本著にしてもベンチャーの創業から成功に至る道というのは悲惨なほど失敗や危機を迎えながら尋常じゃないほどの執念・情熱をもったチームが想像を絶する努力で乗り越えるというところはほぼ共通しているように思う。 彼らを見ていると、“正確には書籍を通じて疑似体験すると”自分がどこまでやれているかを問わざるを得ないと、よく思う。 気分が程よく高揚する一冊。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創設者であり社長、南場智子さんの本。 同社の始まりと歴史は、著者の人生そのものだと感じました。 社会や世界にとにかく大きなインパクトを与えたい! そのための貪欲な組織でありたい! そんな印象を強く受ける本でした。 しかし、そのための方法や仕事に対しては、常に体当たりで 失敗に失敗を重ねて、どうにか成功や生存を掴んできた、 というのがDeNAの歴史ではないかと思いました。 いわゆるベンチャーIT企業なのに、自社プログラマーが弱かった、 というのが個人的には非常に面白く、危うく感じました。 しかし、そこからの底力が凄まじく、人材に対する意識が深まり 人材募集や育成に注力した、というのも面白かった。 学生時代からコンサルタント時代の著者の話も面白く、 経営者としても個人としても結婚相手を支える女性としても 長すぎず短すぎない文章にまとめられたその人生は、 とても読みやすかった。 DeNAやモバゲーの社会における意義や認識に関しては あまり触れられていない。ITベンチャーといえば、 どこか胡散臭く危うい印象がするが、やはりこの本においては ただひたすらに社会にインパクトを与えたい!! という強い気持ちが、そんなマイナスな印象をふっ飛ばしてくれる。 起業とは、会社とは、組織とは、人材とは、経営とは、仕事とは … というようなことに対して、非常に良い刺激を与えてくれる本でした。 堅苦しい書き方や、小難しい言い回しもないので、読みやすく、 なおかつ内容の充実した良書だと思います。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白くて3時間で読了。「誰が言ったかではなく何を言ったか」「マイカンパニーか Social Responsibilityか」金言多し。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者である南場さんの書き下ろしです。書店ではビジネス書枠で平置きされてますが、文面は非常に軽く、さらさらと読めます。 内容も自己啓発書のような、お固い感じでは決してなく、南場さんが重要なシーンでどう考え行動したのかを、面白おかしく、真面目に書かれています。 個人的には、同じ業界ですので非常に参考になりましたし、入社一年目〜五年目の若手社員がcommや怪盗ロワイヤルを立ち上げたと聞くと、自分もまだまだ頑張れると勇気づけられる。 (まぁcommには新入社員らしく、運用面での根本的な考慮漏れもあったのだが) また、コンサルタントと経営者の違いを明確に説明している点も参考になった。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功するための正論を述べる普通の経営本と違って、失敗談を軸にDeNAの成長を綴ってある面白い本でした。 話に逃げがなく、ユーモアもたっぷりで、読み終わった後こんなに爽やかな気分になれたのは久しぶりです。 著者はとにかく人が大好きで、その大好きな人達といい時間を過ごす為に人生をかけて経営をされていると感じました。 おかげさまで自分もまた明日から迷わず頑張れそうです。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「選択に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけである。」 前に見たネットコラムの語り口がなんというか軽くてウィットがあって面白かったから、本が出たとしってすぐに買ってみました。 経営者の本で声を上げて笑ったのはこの本が初めてかもしれない。そしてこれほどに社員のことを書いた、しかも「社員」ではなく一個人として書いた経営者本も初めてかもしれない。 どんな価値を作るかとかじゃなく、誰と作るかの方が遥かに大事なんだと痛感しました。 ビジネス本じゃなく、エッセイとして読める本です。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ***** 南場さんだから、このメンバーで立ち上げたから成功で来たんでしょ、と言われたら恐らくもの凄くイヤだと思う。今まではある程度そうだと思っていた。 そんな何となくのラベリングは全て取っ払ってしまうくらい、本当にぼろぼろになりながらチームを信じて走り続けた結果、なのだと思う。 ***** コンサルタントとしてロジカルに考えることを突き詰めた著者が、最終的に辿り着いたことが「人を活かすこと」であり「人のモチベーションを最大化すること」というのが、改めて重たい。 *****
0投稿日: 2013.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場さんの書籍。コンサルタントという経営者にアドバイスをする立場から自らが経営者に転身することで経験してきた様々な苦労や失敗について記されている。DeNAの歴史と、それを支えてきた人々が鮮明に描かれており、彼らに対する著者の感謝の気持ちがひしひしと伝わってくる。DeNAの強さは①人材②思い切って任せる度量にあると感じた。優秀な人材を得、彼らを育てていく土壌が出来上がっている。当分DeNAは安泰だと感じると共に同じような環境で働きたいという憧れも抱いた。
0投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAファウンダーの南場さんの本。既にレビュー評価高いですが、文句なしの星5つです! 十年近く前に一度営業させて頂いたことがあり、そのときにお世話になったSさんも中に出てきた。当時の印象としても、ワクワクする会社だなという印象あり、皆さんが楽しんで仕事されてるのは伝わってきた。当時Sさんに、今ここで決めてくれないと我々みたいな会社は時代についていけなくなっちゃうんだよね、と言われたことを鮮明に思い出す。 その後、Sさんがいろいろ雑誌に載ってる際にも陰ながら応援してきた。モバオク、モバゲーと爆発的に拡大していき、あぁ、あの幡ヶ谷に行った記憶は、と思って、さらにベイスターズの件。 と、個人的に応援してきた会社だっただけに、なんか勝手な親近感を持って読んだ。すごかった。 本当にチーム力が伝わってきた。閉塞感の世の中で爽快感を得た。 引用したい箇所はたくさんありすぎるけど敢えて二点。 事業リーダーにとって「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。 (前後するが)実際に実行する前に集めた情報など、たかが知れている。 失敗してへこんでいるときに、鉄球のような次の「挑戦の機会」を平気で投げつけてくる、という表現のほうが正しそうです。 以上二点。 大変元気をもらえました!
0投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログいやー面白かった。みんなキャラ立ってて、ちょっと働きマン的なかっこよさ。回りゃあいいのさみたいなとこ。元気出るよ。私も信國さんてきなわだかまりはあるけど。
0投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ選択に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする実行力があるかどうかだ。事業会社ってやっぱりいいな。何より選択と行動ができるから。
1投稿日: 2013.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった。岩瀬さんのHBS留学記を読んだ時以来のわくわく感があった。 高いレベルへの挑戦は難しいしすごく大変だろうけどきっとすっごくおもしろいと思った。
0投稿日: 2013.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者とタイトルから違つた内容を想像していたが内容は本当に面白かった。 病院で読んであて大笑いしてしまい困った位。周りのメンバーにも勧めてみようと思います。
0投稿日: 2013.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不恰好経営というタイトルで、コンサルが経営しても、失敗のフルコースを味わったと書いてある。確かにそうだが、ほんの主題はそこではないと思う。むしろこのタイトルは、本を売るためのマーケティングに感じた。なんだかんだで、いきなりすごい経営をしていると思う。 じゃぁ、主題は何かというと、おそらくリーダーとして愛されるか。愛されるくらいの情熱や人への感謝があるか。たしかにソシャゲは、利益を出しているので資本主義的には社会に還元しているが、実際のユーザーが有意義な行動をしているかは考えられていない。しかし、リーダーとして本当に自分の会社と事業と人が好きなのが伝わる。あと根性がすごい。文章の愛嬌もある。 まずはじめに、コンサルの同僚を二人も引っ張ってこれた。人柄なんだと思う。 次にはじめのオラクルの人もそうだし、最後の新卒での面接の話もそうだけど、やっぱり面接とか初対面で優秀かどうかなんてわからないんだと思った。 あとなんばさんの経験ではじめは不出来だったことで、意外と人っていつ伸びるかわからないのだということ。すぐに決め付けない。 初めてのプロジェクトでコードが全くできていなかったこと。全然規模は違うが、社会人になって共感出来る。ほんと手に入れた情報が意外と正解でないことが結構ある。自分で確認が大切。 お金に困って、苦労した末に、企業理念が出来上がった。ケチケチ理念やエンジニアが企画に口をだすなど。ビジョンなりー会社を思い出した。うちの会社はどうだ? 激痩せラリーは頭おかしい。本当に負けず嫌いの集団なんだろう。 モバゲーを作った川崎さんはすごい。この人のお陰でモバゲーがあるので、ターニングポイントであり、最も運が良かったところ。しかし、人材が必然的に集まると考えれば、高確率で運が舞い込んできたのかもしれない。 上場のさいの、一斉に少しだけ株を売って、約束を守ったこと。お金でもめないのは、すごいと思う。真剣にやれば本当にいろいろなドラマが生まれるのだと思う。睡眠時間2時間とかだけど。。。 経営者と従業員では比べ物にならないけど、それでも少しは理解できる、決めることのプレッシャー。 学生時代には全く経験したことのないもの。そういう想定で提案も出来ないといけない。まだ任せる勇気の方はわかってないな。 あと失敗を恐れないこと。PDCA回せば良いだけ。周りに助けてもらえば良い。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ引き込まれるように一気に読んだ。★3つの良書。失敗、成功、悲しみ、喜びを含め、抽象論ではなく、南場さんの言葉で語られている。簡潔で明瞭であり、ユニークであり、ウィットにとんだ文章。抜群にうまい。参考にしたいなあ。自分を良く見せる人から、自分の弱さもさらけ出し、周りを巻き込み、自分も周りも成長させる経営者に。「とんでもない苦境ほど、素晴しい立ち直り方を魅せる格好のステージだと思って張り切る」というのが一番刺さった。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業と成長が、人間味あふれる言葉で記されている。ベンチャー企業において、なにより大事なのはメンバーですよね、ということを痛感。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入して1日で読み終えた。マッキンゼーのパートナーまでなったコンサルタント(南場氏)がベンチャーを立ち上げて大成功をおさめた経験を平たく語ってくれている。 やはり企業は人材とその人材によるカルチャーが全て。DeNAという新興企業が何故これだけの成長を続けているのかを垣間見ることができた。 チームを率いる上で参考となるエッセンス多数あり。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNA立ち上げから現在に至までの苦労や喜びなど本気の現場がここに書かれている。 こんなことが出来る経営者って超かっこいいと思う。超優秀な人達が目的意識を強くもち、地球に軌跡を残そうと奮闘している姿は社長のリーダーシップの賜物なんだろうなぁ。そんな時間を共有できていた人も濃い経験をしているのだろう。また、所々にユーモアを交えているので、声を出して何度も笑ってしまった。 -引用- それにしても実際書いてみると、我が社の歴史はひどい。世間さまにここまでアホをさらけ出していいのだろうかと思うほど、ひどい。もし歴史を巻き戻して、立ち上げ期をやり直せるなら、あのときと同じようにやることはひとつもないだろう。ところが無駄になったと思うこともひとつもないのだ。チームDeNAは、なにもそこまでフルコースで全部やらかさなくても、と思うような失敗の連続を、ひとつひとつ血や肉としてDeNAの強さに結びつけていった。とてもまっすぐで、一生懸命で、馬力と学習能力に富む素人集団だったのだ。私は仲間に恵まれた。 意思決定については、緊急でない事案も含め、「継続討議」にしないということが極めて重要だ。… 仮に1週間後に情報が集まっても、結局また迷うのである。そして、待ち構えていた現場がまた動けなくなり、ほかのさまざまな作業に影響を及ぼしてしまう。こうしたことが、動きの速いこの業界では致命的になることも多い。だから、「決定的な重要情報」が欠落していない場合は、迷ってもその場で決まる。「決定的な重要情報」が欠落しがちな起案者は優秀ではない。 入社したからも「成長」オタクのように成長、成長と言う人は少し変だ。成長はあくまで結果である。給料を取りながらプロとして職場についた以上、自分の成長に意識を集中するのではなく、仕事と向き合ってほしい。それが社会人の責任だ。そして、皮肉にも自分の成長だへちまだなどと言う余裕がなくなるくらい必死になって仕事と相撲をとっている社員ほど、結果が出せる人材へと、驚くようなスピードで成長するのである。
0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
優秀な人材を口説き落としてきた南場さんが持つVisionはとてつもない吸引力なのだろう。起業を考える上でいい刺激になると同時に、厳しさも実感。 ・不完全な情報に基づく迅速な意思決定が、充実した情報に基づくゆっくりとした意思決定に数段勝る ・「正しい選択肢を選ぶ」ことと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」 ・リーダーに必要なものは胆力ではないだろうか
0投稿日: 2013.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功するまでにはやはりいろんなドラマがあるんですね 挑戦し続ける姿勢というものがとてもよく伝わりました。
0投稿日: 2013.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAがどんな会社なのかちょっと知りたくて、きれいに読んですぐに売り飛ばそうと思っていたが、著者の飾らない考えやユーモアある文章に引き込まれ、読んでいる途中から自分にとって”保存版”の本となった。感想は、他レビューで書かれている通り、元大手コンサル、ハーバードMBA保持者の経営者がこんなにも泥臭く起業してるんだな、ということ。何気なく書かれたエピソードが自分の経験とシンクロすることもあり、共感する点が多かった。 真実に勝るドラマはない。 著者はDeNA社員に読んでもらいたくてこの本を書いたとのことだが、DeNA社員でもない私でもその起業物語に涙してしまう。そして、なんども一人でクスッと笑ってしまった。。。 下手な作り話の小説よりもずっと感動するし、頭でっかちの評論家が偉そうに語っている他の本よりもずっと大切にしたい、そんな本。 こんな素敵な経営者がいたんですね。
1投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログモバゲーで一躍有名になったDeNAが立ち上がってから、今にいたるまでの道のりを元社長(現取締役)の南場さんが語った企業本。 NHKのトップランナーで南場さんを知ったのですが、その体当たりのリーダーシップにはすごく惹かれるものがあり、本書も購入しました。 話中で様々な事業が立ち上がり、それを抜群に優秀な人材たちが軌道に乗せていくという非常に夢のあるストーリーが描かれています。 ただし「飛び抜けて優秀な人材が事業を成功させました」という事実には再現性がありません。読者のほとんどが飛び抜けて優秀ではないためです。 読者がこの本から何かを学べるとしたら、それは南場さんの人格なのではないかと思います。 南場さんの人格がヒトもモノもカネもない零細企業に優秀な人材を引きつけ、資本を集め、すべてのレバレッジになっています。 それだけ。それだけなのですが、その振る舞いの1/100でも模倣することができれば、この本を読む時間を投資する価値は十分にあると思います。
1投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ10分もあれば一読できるのでオススメ。 そいう意味だと文庫サイズの方が読みやすいし、持ちやすい。 ハードカバーにする必要がないと思う。
0投稿日: 2013.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNAと聞くとソーシャルゲーム?球団買ったところ?位のイメージしかなかった。 学生の就職人気ランキングの上位なのですね。 読み終わって、自分が最近悩んでいるもの、モヤモヤしているものが、あーそうだよな!と腹に落ちた感じがしています。 社長業でなくとも、プロジェクトリーダーやマネージャーの方は共感できるのではないでしょうか。 自分でこんなチームを作って回してみたいなぁ・・と前向きな気持ちになれる一冊でした。 以下は特に自分の中で残った内容です。 ◆組織作り 同じ目標に向かって全力を尽くし、達成した時の喜びと高揚感 お互いに切磋琢磨し、時に激しく競争してもチームのゴールを達成したときの喜びが善人に共有され、その力強い高揚感でシンプルにドライブされていく組織。 報酬の競争力も気にするが、ワクワクするような高い目標に挑み自分でさえ気づいていなかったような能力が発揮でき、どこよりも輝けるステージとなっているか。 あと10年もすれば組織に属して仕事をするスタイルは主流ではなくなるだろう。 目的単位でプロジェクトチームが組成され、また解散するような仕事の仕方に変わっていく はずだ。そして多くの場合国境を越えた人材でフォーメーションが組まれていくだろう。 世界中のリソースを柔軟に活用できるチームこそ大きな成果を生み出していくことは間違いない。 独自の思考と力強い突破力で必ず結果が出せる人材は、言語や文化の境目にかかわらずユニバーサルに求められるだろう。 ◆リーダとして リーダーにとって「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。 決める時も、実行するときも、リーダーにもっとも求められるのは胆力ではないだろうか。 リーダの胆力はチームの強さにそのまま反映される。 意思決定のプロセスを論理的に行うことは悪いことではない。 でもそのプロセスを皆とシェアして決定の迷いを見せることがチームの突破力を極端に弱めることがある。 検討に巻き込むメンバーは一定人数必要だが、決定したプランを実行チーム善人に話すときは、これしかない、いける、という信念を前面に出したほうが良い。 本当は迷いだらけだし、そしてとても怖い。でもそれを見せないほうが成功確率は格段にあがる。 不完全な情報に基づく迅速な意思決定が、充実した情報に基づくゆっくりとした意思決定に数段勝る。 実行する前に集めた情報などたかが知れている。 本当に重要な情報は当事者となって初めて手に入る。だからやり始める前にねちねちと情報の精度をあげるのはあるレベルを超えると圧倒的に無意味となる。 それでタイミングを逃してしまったら本末転倒。 ◆人を育てるということ。 人材育成が究極の目的ではないが、組織の成長は人材の成長によってもたらされる。 人材が成長する会社には優秀な人が集まってくる。 なぜ育つか、というと単純な話で恐縮だが、任せる、という一言に尽きる。 人は人によって育てられるのではなく、仕事で育つ。 だから、その人物が精いっぱい頑張ってできるかできないか、ギリギリの仕事を思い切って任せる。 一方で自分への成長への意識はほどほどな方が良い。 成長はあくまでも結果である。 自分の成長だへちまだという余裕がなくなるくらい必死に仕事と相撲を取っている社員ほど結果が出せる人材へと驚くようなスピードで成長する。
0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり共感できなかった。恵まれすぎているよね。すぐに融資受けられたり、困ってると助けられたり。人徳というものなのか、一般人はもっと苦労している。 苦労して苦労して成り上がった下積みの話だと読むと、ちょっと違和感あります。
0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に出会った、一気読みさせられる一冊だった!!自動車業界で10年がかりで起こる変化がたった数年で様相が一変してしまうネットの世界で、いかにして成長をドライブし、世界ナンバー1を目指すほど躍進したかがよく分かったし、本当にドラマのよう。 企業には様々なステークホルダーが存在するし、ユーザー目線、投資家目線などから企業を知ることはあっても、それは一側面で、創業者自らが自分が起こした事業に対する思いや根底にある自らの価値(何がしたいのか?何のために?)という見えない側面を知ることは非常に価値があるし、たくさん勇気と示唆をもらえた。 結論。リーダーは自ら発信すべし! 南場さんの本を読んで実感した。
0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は私の高校の1年後輩である。その彼女が日本のIT企業の雄である会社を設立し、大活躍していることを知り、その彼女の本が出ると聞いて、迷わず購入した。彼女のブログの文章も好きだったので、期待していたが、期待通りの面白い本だった。 人材育成を大切にしていること、社員を信頼してプロジェクトをどーんと任せることなど、教育の観点からも参考になることがあった。活かせるものがあると思う。
0投稿日: 2013.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013/06/21 この本はすごい! なにがやろう。。読み返してみないとわからない。。 でもイミフなのは、なんのために企業したのかってこと。 ゲーム作って売上が伸びればいいのか?情弱な一般人からお金巻き上げて楽しいか?
0投稿日: 2013.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA創業者の南場さんの初の著書ということで、早速購入・読了。起業時のドタバタからその後の混乱を交えた急成長のくだりは、ベンチャー企業の痛快さが伝わってくる。人を大切にし、能力高い人材を集め、負荷の高い仕事を任せながら、個人と組織の成長を引き出すダイナミズムはスゴい。とは言え、そういう中でも、人ではなくコトに力点を置くというマネジメントが効いていると思う。 女性経営者らしい細やかさというのもあるだろうが、個人に配慮し、組織を巻き込むプロセスは見習いたい。人生突っ走ることが必要だよな、と思った次第。「常に前のめり」「現在を起点にベストを尽くす」は実践します。この人いいわ、会ってみたいね。
0投稿日: 2013.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの実話は小説より面白い。 モバゲーで有名なDeNAの創業者、南場智子が明かすDeNA誕生とその急成長の秘密。 ネット業界では、多くの会社が現れては消えていく。 その中でなぜDeNAは、数多くの困難に遭遇しつつもここまで生き残ることができたのか? 読み進める中で見えてきたその秘密、それは集まった優秀で個性的な人材の力の結集だったことが分かる。 大企業での将来を約束された地位を捨てて、多くの才能を持った若者達が続々が転職してくる。 その事実に大変驚いたが、それは南場の人間的魅力と彼女がぶち上げた、その大きな夢に惹きつけられたからであろう。 若くして大きな仕事を任された彼らは、想像を絶するプレッシャーをはねのけて次々と成果を出す。 大企業にいたならば、そんな自由と充実感、やりがいと喜びは味わえなかったにちがいない。 自分はモバゲーをそれほど評価しないが、それでもこの本には、成功することとは何か、生きがいとは何か、について多くの示唆を含んでいる。
0投稿日: 2013.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業とは、ベンチャーとはこうも不確実性の連続なのか。 スマートでは生き抜けない。どうしても不格好になる。が、ゆえにめちゃくちゃエキサイティングで面白い。 いろんな人のエピソードも生々しく綴られてて楽しく読ませてもらいました。
0投稿日: 2013.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ不恰好というタイトルの通り、うまくいかなかった出来事や苦悩がこれでもかというくらいに書かれています。華やかなイメージのあるDeNAだけど、ここまで成功する裏には相応の苦労があるのだと再認識しました。 経営者には色々なタイプがいるけど、南場さんはたくさんの人を惹きつける魅力のある協調型の経営者のように思いました。劇中でも実際に優秀な人達を何人も自分で口説き落としています。 自分の失敗を堂々と公開できちゃうところや、自分よりも一回りも二回りも下の年齢の人材に対しても、優れているところがあれば素直に教えを乞うところや、同じ目線で物事を考えられるのも南場さんの魅力だと思います。 素直であることの大切さをはじめ、たくさんの見習うべき点を得られました。 同時にDeNAという会社へのイメージもかわりました。
0投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんに興味がありこの本を読みました。 マッキンゼーの最上級職のパートナーまでやられた超頭のキレッキレッ人のはずなのに、ユーモアたっぷりで赤裸々にこれまでの失敗などの経験、会社の経緯を書かれている内容でした。 ベンチャー立ち上げ初期に、外部発注したシステムが実は作れていなかったトラブルのときの旦那さんからのアドバイスをもらった時のくだり、思わず涙してしましました。 1)諦めるな。その予算規模なら天才が3人いたら1か月でできる。 2)関係者、特にこれから出資しようとしている人たちに、ありのままの事実を速やかに伝えること。決して過少に伝えるな。 3)「システム詐欺」という言葉を辞めろ。社長が最大の責任者、加害者だ。なのにあたかも被害者のような言い方をしていたら誰もついてこないぞ。 これだけ言うと、またひっくり返って寝てしまった。 なんとも素敵な旦那さんなのだろうか。 肝の据わったとはこういうことを言うのか。と感じた。 そして思わずハッとした言葉を発見。それは、 "選択"に正しいも誤りもなく、 ”選択”を『正しいものにする行動』があるかどうか というDeNAの社員の方の言葉。 これ、最近 お世話になっている方から頂いた言葉で それと全く同じことがこの本に書かれていたので。 やはり覚悟を決めてものごとにあたっている人たちは 同じような境地に至るのだなと、思わされた言葉でした。
0投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。そういえば高校の頃の友達がイギリス留学後、DENAで働いてたな。DENAで働いてたって事で「あいつ、優秀だったんだな」って評価される。スゴイ話だ。投資家の立場から言うと、過去何回も売買したけど一度も負けなし。決して右肩上がりな株価ではないけど、買値より多少下がってもココは大丈夫だろうと安心して持てる。 天才的な人材が集まってくる過程を楽しみながら読める。面白くて一気に読めます。お勧めの一冊。
0投稿日: 2013.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログふつうに面白い。 超一流の集まりであるすごいベンチャーなので、そのまま参考になるかは疑問だが、汎用的な学びも多くある。 言うとやるとでは大違い。 目標をぶち上げて、達成の仕方を必死で考える。※これは、チームの結束と優秀であることがmust。。 bad news first & real 悪いニュースを過小に言わないは、特に共感した、 また、本書で興味深かったのは、DeNAという会社が、リクルートを思い起こさせるほどに採用に力を入れていること。 大きくは二点、代表自らが本気で採用に向き合う。また、社員には自分より優秀な人材を連れてこさせる。この二点を実践しているのは、僕はかつてのリクルートとそのDNAをもつ会社しか知らない。 結論、すべてが本当かどうかわからないが、DeNAは日本が誇るべき偉大なベンチャーなのだろうと思った。
0投稿日: 2013.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ何か誤解してたかも。そんな印象を持った本。 ビッダーズの頃は、オークション事業ってヤフオクある限りしんどいよなー、って思ってたし、モバオクの頃は、専門特化する事でこんなに伸びるんだ、って思ってた。 モバゲーが出てきて、ガラケーの利用を本当にピークまで引っ張り上げて、そのままスマホへの転換。 ここまでの流れで「事業」ばかりに主眼を置いて、「人」なんて気にしない感じの方だと思ってました。Twitterとか見てても何か適当な感じの人だったし(笑 そんな感じの見方をしてたから、この本を読んであまりにも「社員」に対しての思いが綴られてたので、びっくりしつつもなんか感動。旦那さんへの思いもね。 面白かった。 ※グリーに関してはたった一行くらいしか書いてなかった。そこだけは結構気になった(笑
0投稿日: 2013.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年一番の一冊です。 南場さんご本人が執筆することで、創業期から臨場感溢れる内容になっており、苦労や挫折、喜びのエピソードに涙ぐむこと数回。 要所、要所で垣間見れる南場さんの厳しさ、会社への想いなどの考えが身を引き締めさせられます。 印象に残った箇所は多数ありますが、その中でも下記の3つは特に印象に残りました。 「普通に物事が回る会社、普通にサービスや商品を提供し続けられる会社というのが、いかに普通でない努力をしていることか。」 「意思決定のプロセスを皆とシェアして、決定の迷いを見せることがチームの突破力を極端に弱めることがある。」 「事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。」 3年前に南場さんのブログを読み、ユーモアなところに魅力を感じましたが、本書に勝手に作っていた人物像を良い意味で変えられました。 良い本はないか聞かれれば、必ずこの1冊は含まれます。
0投稿日: 2013.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんと実際にお話した際に感じる「引き込まれるオーラ」を本からも感じ、一気読み。 さらけ出す強さ、分け隔てなく接する姿勢など、学ぶところ多すぎます。 人生やはり自分がワクワクすることやってなんぼ、という明白な事実に改めて気づかされました。
0投稿日: 2013.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ買ったその日に3時間で読了。 著者が経験した驚くほどの失敗の数々とそこからの復活がものすごい臨場感で描かれている。またそこに登場する社員が個性的でいきいきと描かれていて、DeNAは魅力的な会社だと感じる。 起きている出来事と人物描写がドラマチック過ぎて何度も涙が出たそれだけの振れ幅と喜怒哀楽を共有できる事業をやっていることが心底羨ましいと思う。 一番心に残った箇所を引用。 「同じ目標に向って全力を尽くし、達成したときのこの喜びと高揚感をDeNAの経営の中枢に据えよう。互いに切磋琢磨し、ときに激しく競争しても、チームのゴールを達成したときの喜びが全員に共有され、その力強い高揚感でシンプルにドライブされていく組織をつくろう。そう決めた瞬間だった。」(46ページ)
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ新潟高 津田塾 マッキンゼー DeNA 苦しい時に意識すること とんでもない苦境ほど、素晴らしい立ち直りを魅せる格好のステージだと思って張り切る 必ず後から振り返って、あれがあってよかったね、といえる大きなプラスアルファの拾い物をしようと考える 命をとられるんじゃないから 掘った穴が大きいほど面白いステージになる。そう思ってやるしか無いのだ。見事に立ち直る様を見せようじゃないか 父よりの手紙 私生活の貧乏は体験としてプラス思考で真摯に処されたし 生き甲斐は処した困難の大きさに比例する bidders モバオク モバゲー 怪盗ロワイヤル 社長の一番大事な仕事は意思決定 緊急でない事案を含めて継続討議にしないということが極めて重要 私が何に苦労したか 物ごとを提案する立場から決める立場への転換に苦労した 不完全な情報に基づく迅速な判断が、充実した情報に基づくゆっくりとした意思決定に数段勝ることを身をもって学んだ 事業リーダにとって「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。決めるときも、実行するときも、リーダーに最も求められるのは胆力ではないだろうか できるかぎり賢くみせようとする姿勢。知らず知らず身に着けている人が多い。これは事業では一銭の得にもならない。会社を経営しているといくつもの修羅場をくぐる。自分のアホをさらけだしてでも助けてもらわなければ切り抜けられないことがあまりにも多いのだ。 DeNAでは、「誰が言ったではなく何をいったか」という表現を用いて、「人」ではなく、「コト」に意識を集中するように声を掛け合っている 選択に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけだと信じている 無料電話アプリ comm
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA史。全く不恰好ではなく、むしろカッコいいです。事業内容よりコンサルタント目線の「決定」に力を注いでいて社長業しているなと思いました。誰が言ったかより、「何」を言ったかを大切にしている。「unlearning(学習消去)」が大変。十年すれば仕事のスタイルは代わり、目的単位でプロジェクトを組み、また解散するようになる。
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ勢いを感じるための本です。 読んだら勢いが付きます。 意味不明ですね。 南場さんが書く文章はユーモアがあって可愛いです。 面白い。
0投稿日: 2013.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタントとしてご活躍されていた方が実業をやったら大変だったということを基にして書かれた本。 すごく勉強になりました。 「経営者(事業家)」と「コンサルタント」の違い 自分がこれと最後決断する際に、どれだけ勇気がいるのかということと意見をまとめることの違い。 やはり自分も経営者として、ただの一教室長ですが、決めること、腹をくくることが大切だと改めて実感しました。 ピンチになった時にこそ +思考というか命までビジネスでとられることは無いという考え方を徹底して、「ピンチを楽しむ」「働くことを楽しむ」マインドが大切だと思う チームを信じる、人を育てることは「任せること」 自分にしか出来ないことをやる などなど都度都度思うこと、感じることは違うのだろうが、このようなベンチャーマインドを持っている人が書かれた本を読むことは非常に勉強になる。 この本は売らないで、定期的に、特に自分が元気が無い時に読み返してみようと思った。
0投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になってたのでミーハー魂発揮して読んでみた(笑) 経営者の自伝を読んでいつも思うのは、内側がどれだけ泥臭いかってこと。 外からだとどうしても華やかな側面ばかり見えてしまいがちだけど、本質は泥臭い部分なんだと思う。 勉強になったのはコンサルタントと事業者の視点の違いが南場さんの実感値をもって書かれている部分。戦略策定と実際の意思決定の間にはとてつもなく大きな乖離がある。言葉としては理解できるけど自分が実感を持って理解するのは今は無理だな。 ユーモアがあってすごく楽しんで読めた。 たまには肩の力抜いてこういう本読むのもいいな。
0投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本読んで、一気に南場さんファンになった。というよりDeNAという企業のファンになった。 冒頭で、成功事例よりも失敗体験を書き記すと書いてあった通り、一見、順風満帆に見えるDeNAのありとあらゆる失敗がこれでもかっていうほど盛り沢山。コンサルと起業家の違いについての分析も、南場さん節満載で非常に面白かった。 おすすめ。
0投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。南場さん自体結構好き。モバゲーはやらんけど。 いわゆる下層向けビジネスって、客としてではなく分析する側としてみると面白いよね。 一つのノンフィクション(あるいはまあフィクション)として楽しめた。とはいえ、なぜ勝ち得たのかなどについてはまあ当事者だからということもあるけど触れられてないよね。まあそりゃそうだしいいんだけど。
0投稿日: 2013.06.12
