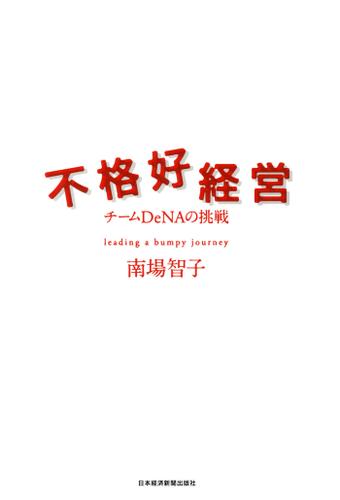
総合評価
(480件)| 172 | ||
| 179 | ||
| 67 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい小説のようでもあり、赤裸々でユニークなエッセイでもあり、ためになるビジネス書でもあると感じた。読んでいて元気になった。失敗を恐れない、許し、挑戦や成長の機会と捉える組織風土の大切さを感じた。私も熱病冒されるようになりたい。
0投稿日: 2013.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ創業時の悩みや意思決定のプロセスが率直に書かれており、非常に面白い。筆者がマッキンゼーのパートナーという事もあり、コンサルティングと事業経営の違いについて客観的に記述されている。
0投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ明るく楽しい!現役の社長職を退いて、プレッシャーから解放されたからなのかもしれない。嬉々としている。仲間に贈るエールのような感じの作品。そうそうたる職をなげうって、腕に覚えのある人材がどんどんと集まるのだから、人材の確保と開発に力を入れているとはいえ、リーダーとしての資質がもの凄いのであろうと思った。これは仕事の能力はもちろん、人間力が大きいのだろう。文章の端々に、可愛らしい人間性と、胆力溢れる親分気質なところが垣間見れたような気がしました。
0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログIT企業、DeNAの創業者である筆者が赤裸々なまでに自らの歩みを綴った著書です。華麗な業界と思える世界のその舞台裏と、自らのやらかした失敗をこれでもかといわんばかりに綴っており、とても面白かったです。 今やモバオクやソーシャルゲームで急速な成長を遂げ、ついには野球のチームまでもその参加に収めるIT企業DeNA。本書はその創業者である南場智子女史が初めて綴った著書で、自らの生い立ちや学生時代。有名なコンサルティングファームであるマッキンゼーのコンサルタントとして大前研一氏の「教え子」として活躍した後に、DeNAを創業するというのが全体の流れです。 南場女史の文章の面白さには定評があって、本書にも収録されている、『日経WOMAN』のリレーエッセイ『妹たちへ』において、自身も参加した社内のダイエットラリーの顛末を書いたもので、それがとてもテンポの良い筆致であったことを覚えております。僕は 「もし南場女子が本を出したら絶対に読んでみたい!」 と思ったものでした。 ここに記されているものは、今をときめくIT企業のその赤裸々なまでの物語で、よくここまでさらけ出したものだなぁと思うくらい、自らのしでかしたことや、すったもんだの顛末をぎっしりと凝縮しております。 南場女史は新潟県の出身で、父親の束縛から逃れたい、田舎から出たいという一心で津田塾大学に合格し、アメリカ留学を経てそこからマッキンゼーというまさに眼もくらむような華麗なキャリアを積むわけですが、周りには自分よりもデキる人間がキラ星のごとく存在しており、挫折感を味わった南場女史は激務から逃げるようにハーバード大学のビジネススクールに留学していくのです。そこでの学生生活を謳歌した後に日本に帰国し、コンサルティングの仕事に邁進するわけですが、 「そんなに熱っぽく語るなら、自分でやったら」 と何気なく言われ、そこから彼女の人生が一変していくのです。 そこから出資者を募り、創業メンバーを集めるわけですが、そのメンバーの一人に 『ベンチャー企業で働くということはこういうことです』 という趣旨のこと伝えるために渡した本が板倉雄一郎氏の『社長失格~ぼくの会社がつぶれた理由』であったことがとても印象に残っております。 創業して最初の目玉がオークションサイトである『ビッターズオークション』でしたが、発表目前になって大規模なシステム障害に見舞われたりするも、何とかオープンにこぎつけるのです。そこまではNHKの『プロフェッショナル 仕事の流儀』にも描かれている通りですが、『その後』がまだまだあるのです。 業界最大手の「ヤフー・オークション」の後塵を拝し続けるビッターズ以外に収益の主軸となる事業であるソーシャルゲームへとシフトチェンジしていく過程で、南場女史や会社を支えるエンジニアたちが、猛烈な勢いでプログラムを作成していったり、思いもよらない人間が活躍していって、それが一気に中核事業にまで成長していく様子は、市場の持つ圧倒的なダイナミズムを感じさせる箇所でありました。しかし、課金制のアイテムが『射幸心をあおる』との理由で『お上』から指導が来るようになり、それに対しても積極的な取り組みがなされていたという事実を本書を読んで初めて知ることができました。 そんな順風満帆だった南場女史のビジネス人生が大きな転換点を迎えるのは、最愛の夫が病に倒れたことでありました。 『夫の看病のために代表取締役を辞任する』 前代未聞の発表を僕は『WBS』で聞いてとても驚いたことを本書を読んで改めて思い出すことができました。自らの後継者選びと夫の看病。2つの重要案件をほぼ同時にこなすことが出来たのは、彼女の元で育ち、後進を任せられるようにまでなった創業メンバーたちと、周りの人間の支えあってのことだなということを読みながら感じさせました。 南場女史は現在取締役として会社の経営に携わり、彼女の旦那様も徐々に回復に向かわれているのだそうで、それは何よりです。新興の業界であり、現在も何かと風当たりが強いITの世界ですが、これからも南場女史のご健勝と、DeNAの更なる発展を心よりお祈りいたします。
0投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[読んだ理由]================== もともとNHKかの番組で取り上げられていて興味のある経営者で、詳しく知りたいと思っていたが、本が出版された後のレビューの評判も高かったので読む気になった。 [読んだ後の感想]============== DeNAという会社が、数少ない一部の天才で成り立っているのではなく、様々な分野で特徴を持った数多くの個性派の集団であるということがよくわかった。そして数多くの天才を引き寄せる魅力のある会社であることも分かった。 それだけ多くの社員を社長が逐一把握しているのも凄い。社員を大切にするというのが口だけでないことが実感できて、言葉に説得力があった。 また単に会社の半生を振り返る話だけでなく、後半に人材観や組織観もあって、そこも凄く「なるほど」と感じさせるものがあった。自分の日々の働き方や、今後のキャリアにも参考になったと思う。 [備忘録]====================== ■第一章:立ち上げ 調整ではなく決めるのが(社長としての)仕事であること、最後は自分の腹に聞くこと ■第二章:生い立ち マッキンゼーでは「お前のバリューは何だ、バリューを出せ」と念仏のように言われる。 ■第三章:金策 トイレにはペーパータオルが置いてあったが、これにも乙部が「手は一枚で拭けます」と書いて貼り付けた。こんなことでいくら節約できるのか、一見みみっちい話に感じるが、こっやって管理部門が一円単位で苦労して節約していることを知ると、システム担当は開発にかかる数千万円の重みを痛感し、効率的なシステムの設計に血道を上げ、調達担当は必死の覚悟で値切る。 自分の足2本だけでしっかり立って家族や従業員を支えている商売人の迫力はとても新鮮だった。椅子に座るやいなや挨拶や社交辞令をすっ飛ばして商売の話に入る。情報感度が凄まじい。仕事抜きで飲もうという集いも、実際は仕事抜きの瞬間など一瞬たりともない人たちだ。「難波さんね、買ってもらえなかった時にどれだけいい笑顔が見せあっれるかだ勝負なんだよ」といった、たくさんの心にしみるアドバイスも頂いた ■第四章:モバイルシフト 川崎は一人で、しかもたった2,3ヶ月で感動するほど使いやすいモバイルオークションサービスを作ってしまった。つまり、3人月?これまでと桁が違う。これを機にDeNA車内のシステム開発のアプローチは、再度大きく見直された。これまでの、要件定義、設計、コーディング、テストというステップを踏んだ開発から、作り手(プログラマー)を企画段階から巻き込み、作り手自身がユーザーにとっての面白さや使いやすさを考えながらプログラミングしていく方式を取り入れていく。 野生を愛し、ハンティングや生命のメカニズムに心躍らせる川田のメッセージは、一言で言えば「エスタブリッシュメントになるな」だ。そうだ、挑戦をやめたら、DeNAじゃない。 ■第五章:ソーシャルゲーム ゲームは作ったことがないどころか、殆どやったことすらない大塚は、その日からフェイスブックのゲームを遊び倒した。人気ゲームだけでなく、ヒットしていないゲームも総ざらいし、成功するゲームのエッセンスを彼なりに抽出した。そのエッセンスを「全部盛り」にし、彼なりにアレンジしてまとめあげたのが、怪盗ロワイヤルだった。 有るとき赤川は、パタリと指示をやめてしまう。このままでは全社の業績に大きな影響が出てしまう。なんとか自分一人でチームの未達分を補おうと、外での営業にもう一度軸足を戻したのだ。日中は全部外出、夜も多くは営業に当て、チームの誰よりも足を使って成果を上げた。会社に戻ってからは提案書や営業アプローチを資料に残し、他のメンバーからも自由に見えるように可視化した。そして赤川はチームに言った。自分は良いリーダーになれず苦しんでいる、助けてくれ、と。 この経験で赤川は彼なりのマネジメントスタイルをみつけだしたのではないかと思う。誰よりも働く、教えるより見せる、上から目線ではなく自分をさらけ出して一緒に戦うスタイルだ。 ■第六章:退任 (守安は)部門を統率できるブレなさ、強さがある。人格は、責任感が強くフェア、権威におもねることがない。そして約束を守る。長年一緒に仕事をして私は守安から多くのことを学んだが、その中でも一番尊いことは、自分の利益や感情と物事の善し悪しの判断を決して混同しない清々しさだ。守安が新米の時からトップになるまで見てきたが、一度足りともそこに曇りを感じたことはない。 新しい技術は、新しい遊び方、新しい事業を生む。すると新しい課題が発生し、事業者は軌道修正を求められる。この課題はワンショットではなく、イノベーションが有る限り続いていく。コンゴも新しい問題は必ず起きる。いや、今すでに起こっていると覚悟するべきだ。事業者は、問題を起こさないようにビクビクするよりも、新しい問題にアンテナを張り巡らし、積極的にユーザや社会、行政と対話しつつ柔軟に対処し続ける姿勢と能力を持つことが重要だ。 ■第七章:人と組織 継続討議はとても甘くて楽ちんな逃げ場である。決定には勇気が入り、迷うことも多い。もっと情報を集めt決めよう、とやってしまいたくなる。けれども仮に一週間後に情報が集まっても、結局また迷うのである。そして、待ち構えていた現場がまた動けなくなり、他の様々な作業に影響を及ぼしてしまう。こうしたことが、動きの早いこの業界では致命的になることも多い。だから「決定的な重要情報」が欠落していない場合は、迷ってもその場で決める。 人材の質を最高レベルに保つためには、 ①最高の人材を採用し、 ②その人材が育ち、実力をつけ、 ③実力のある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、 ④だからやめない、 という要素を満たすことが必要だ 意思決定のプロセスを論理的に行うのは悪いことではない。でもそのプロセスを皆とシェアして、決定の迷いを見せることがチームの突破力を極端に弱めることがある。 事業リーダーにとっt「正しい選択肢を選ぶ」事は当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくsる」ということが重要となる。決めるときも、実効すr時も、リーダーに最も求められるのは胆力ではないだろうか。他のもろもろは誰かに補っtもらうことが可能だが、リーダーの胆力はチームの強さにそのまま反映される。 コンサルティング業界出身者へのアドバイス ・なんでも3点にまとめようと岩盤らない。物事が3つにまとまる必然性はない ・重要情報はアタッシュケースではなくアタマに突っ込む ・自明な事を図にしない ・人の評価を語りながら酒を飲まない ・ミーティングに遅刻しない 全力でくどく、というのは、事業への熱い思いや会社への誇り、それから、その人の力がどれだけ必要かを熱心にストレートに伝えるということにほかならない。 会社は親でも学校でもないので、人材育成が究極の目的ではないが、人材の成長を重視していない会社はない。組織の成長は人材の成長によってもたらされる体。また、人材が成長する会社には、優秀な人が集まってくる。 自分の「成長」への意識はしかし、ほどほどな方が良いと考える。学生が自分の成長を重要ポイントとして就職先を選ぶことはうなずけるが、入社してからも「成長」オタクのように成長、成長という人は少し変だ。成長はあくまで結果である。給料を取りながらプロとして職場についた以上、自分の成長に意識を集中するのではなく、仕事と向き合ってほしい、それが社会人の責任だ。 (学生から、優秀な人の共通点を聞かれて)自分が接したすごい人たちを思い浮かべると、なんとなく「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」ということは共通しちるように感じる。 ビジネススクールに行って人脈を作りたいなどと思っている人がいたら、今日明日のあなたの仕事ぶり、仕事に向かう姿勢こそが人脈を引き寄せるのだと伝えたい。 DeNAえは「誰が言ったかではなく何を言ったか」という表現を用いて、「人」ではなく「コト」に意識を集中するように声を掛け合っている。誰かが言ったことが常に正しいと思ったり、誰かに常に同意するようになったら、その人の存在意義がなくなるし、「誰派」的な政治の要素ともなり、組織を極端に弱くする。 (出戻りについて)私は概ね歓迎する。外を見て、視野を広げた上でまた選んでもらえるならその選択は本物だし、DeNAの良さや課題を客観的に捉えて改革の旗振りをしてほしい。 ■第八章:これから 「任せる」こと 1.全員が主役と感じ、一人ひとりが仕事や成果にオーナーシップを感じるようなチームの組成、仕事の単位となっているか 2.チームの目標は分かりやすく、そして高揚するに足る十分に高い目標となっているか 3.チームに思い切った権限移譲をしているか、信じて任せているか この3つを満たしつつ、全チームの目標達成が全社の目標達成につながる組織設計をしなければならない。 事業の最先端を引っ張っている部門ばかりではなく、コーポレート部門やサポート部門のスタッフもまるっと「目的単位」で任される。このような守安の任せる勇気が活気の源ではないだろうか
1投稿日: 2013.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマッキンゼーのパートナーだった著者が、コンサルティング業では物足りなくなり企業に挑んだDeNA創業記。手前味噌的な部分もあると思うので、ある程度割り引いて咀嚼する必要があると思うが、全体として美談である。経営とはクラフトのようなもので、インテリジェンスだけでは何も為せず、泥臭くてもいから、リテラシーが必要だということが描かれている。
1投稿日: 2013.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業から現在までの軌跡を自身の半生を織り交ぜながら経営者の情熱とコンサルタントの冷静さを巧みに使いこなして描き、ヴェンチャーの紆余曲折を生き生きとした登場人物がドラマチックに盛り上げ一気の読ませます。 東証一部上場企業でありながらゲーム会社として一段下に見られることを払拭するための戦略だろうと思いやや批判的に読み始めましたが、自社の仲間や関わった人々への強い信頼と感謝のこもった好著でした。
0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者、南場智子さんのDeNAがどうやって生まれ、どうやって育ったのか、の振り返り。1999年Mckenseyのパートナーから失敗のフルコース(本人曰く)から不格好な経営でも、面白い、最高にと言うまでのストーリー。「そんなに熱ぽっくかたるなら自分でやったらどうだ」からビッダーズまでのすったもんだは面白い。以下、メモ(1)数字は出し続けなれば意味が無いんです。うちの営業はそこが違います(2)赤字の経営はきつい。利益は世の中にどれだけの価値を生み出したかの通信簿だ(3)DeNA Quality。Deilght, Surface of Sphere, Be the best I can be, Tranparency&Honesty, Speak Up(4)コンサルタントは言う人、手伝う人である。事業リーダーはやる人。…優秀なコンサルタントは間違った提案をしても死なない立場にいるからこそ価値のあるアドバイスが出来る(5)事業リーダーにとって正しい選択肢を選ぶことは当然重要だがそれと同等以上に選んだ選択肢を正しくすることが重要となる。(6)会社を経営していると幾つもの修羅場をくぐる。自分のアホさを曝け出してでも助けてもらわなければ切り抜けられないことがあまりにも多い(7)採用にあたって心掛けていること。全力で口説く、誠実に口説く。(8)優秀な人の特徴。素直だけど頑固。頑固だけど素直。…労を惜しまずにコトにあたる、他人の助言には耳を傾ける。しかし人におもねらずに自分の仕事に対するオーナーシップと思考の独立性を自然に持ち合わせている(9)経営課題の前に階層無し。管理職かメンバーの違いは上下関係の違いではなく役割の違いだ(9)制度は作っただけではメッセージを発しない。多様な働き方を応援するムード作りも必要だ
0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ・文章が軽快でおもしろい。よみやすい。 ・起業はやっぱりかなり大変、でもおもしろそう ・ピンチに陥ったときの、えい!という前向きっぷりがいい ・社長、リーダーに必要な覚悟、がさらっと書かれている。チームや取引先に弱音は吐いちゃいけない(吐く人を限定すること)。胆力。 厳しいことだけど、たくさんの失敗談が書かれていて、最初から強かったわけじゃないんだな、と思う。スゴイ人だ、とは思うけど、かけ離れた人とは思わない。親近感。 それでも近くにこういうリーダーはいない。やっぱり実行するのは難しいことなんだろう。すごい。 ●「この事件は起こらないほうがよかったでしょう。しかし起こってしまった。こうなったからにはどう立ち直るかが問題です。これからの立ち直り方に、ソニーやリクルートから真に独立した経営陣として認められるか否かがかかっています。投資家はそのような目で見ているということを、片時も忘れずに対処してください。」 そうだ、掘った穴が大きいほど面白いステージになる。そう思ってやるしか無い。見事に立ち直る様を見せようじゃないか。 ●事業リーダーにとって「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要であるが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。 決めるときも、実行するときも、リーダーに求められるのは胆力ではないだろうか。 ●「できるかぎり賢く見せようとする姿勢」は、事業では一銭の得にもならない。会社を経営していると、自分のアホさをさらけだしてでも助けてもらわなければ切り抜けられないことがあまりにも多いのだ。 ●「“選択”に正しいも誤りもなく、その選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけだと信じています」
0投稿日: 2013.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さん自身がDeNA創業の舞台裏を描いた1冊。数えきれないほどの過ちやトラブルを格好悪く泥臭く乗り越えて、DeNAが企業として成長していくさまを克明に記していきます。 続きはこちら→ GUEST 106/南場 智子:スミスの本棚:ワールドビジネスサテライト:テレビ東京 http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/blog/smith/2013/10/post154983.html
0投稿日: 2013.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功のモデルは壊される前に壊さねばならない。しかし企業は往々にして成功の復讐にあう。我々はアバターという勝ちパターンにこだわり、新しいトレンドを見失っていた。 南場智子
0投稿日: 2013.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ有名企業の成り立ちや成長を割とリアルに感じることが出来る。文章自体は読みやすくすぐに読了。 でもやはりこの企業の最終ビジョンが「楽しくやって利益をあげる」しか見えず、心に響くとまではいかない。 さらに個人的にはゲーム自体大嫌いなので、余計にそう思うのかもしれない。人の欲望を上手く手玉にとって利益をあげる、だけでは本当の意味での成長は続かないのではと感じる。
0投稿日: 2013.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さん、ちっとも不格好じゃないと思います。 経営者が書いた本は、それなりの数を読みましたが、それらと比べて南場さんがとくに不格好とは思いませんし。 むしろ、かっこつけようとし過ぎな気がします。 あえていうならば、それが不格好だとは思いますが。 どこの会社も同じだと思いますが、人材は大切ですね。 もちろん、人材の教育も。 それから会社の向かうベクトルも大切ですね。 そのあたり、ちょっとおろそかにしている気がするので、見直さなきゃな、と反省しました。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉の端々から、南場さんの勢いが感じられる本。 リアルな描写から、創業時のご苦労や、現在の会社の活気などがビシビシ伝わってくる。 「事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる」という一文に、目から鱗が落ちた。そういう覚悟で取り組まないと、成功するものも成功しないのだろう。南場さんは、「胆力」が求められると表現しておられた。事業部長クラスでない人も、一人ひとりがそういう意識を持っているということが、DeNAの強さの秘訣かと思う。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの起業体験記。 前書き通り、失敗の連続が綴られており、起業の大変さが伝わった。 第七章 人と組織 の経営のポイントは、意思決定の仕方など有益であると思う。
0投稿日: 2013.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログいやー、南場さんはとにかく文章が面白い。頭の回転がめちゃくちゃはやい女性の感じがびゅんびゅん伝わってくる。で、それなりに文量はあるのに、なんだか南場さんが乗り移ったのごとく、すごくスピードでとても楽しく、ハラハラドキドキ、時に感動しながらDeNAの創業から南場さんの社長退任(とその後少し)までを一気に体験できます。 こんどヤフーさんの書籍も出るみたいだけど、やっぱり総力密着取材よりも、少し落ち着いたところで、その時のことをちょっとだけ美化したり、反省したりしながら本人たちが文章にしていく方が、誠実で最終的には面白くなるんじゃないだろうか、とか自社批判してみたり(笑) とにもかくにも、IT業界にいる方はやっぱり読んでみた方がよいかと思います(2013.10.21ごろ読了)
0投稿日: 2013.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログあ、この人だ。この人モノホンのジャンヌ・ダルクだと思った。 著者は、元マッキンゼーで大前先生の御弟子さん、なのにソネットのコンサル案件でソネット社長に「そんなに熱っぽく語るなら、自分でやったらどうだ」と突かれて初まった押しも押されぬ、DeNAの取締役・ファウンダー。 私事で恐縮ですが、ここのところホント、書運(良書に出会う率)が高まってて怖い。本書に関していえば、仕事柄、業種が近いこともあって、他業種では有り得ないようなトラブル事案も頷きながら、そして涙ながらに読んだ。 日本のITC業界は人です。だからこそ故障者も多いし、著者のように開発者を愛し、共に会社行事で死にかけ、外国人に翻弄され、叱咤激励のなかで愛され、何より愛していると上手に伝えられる能力が必要なのだと(電車で)泣きながら知りました。著者の執筆は初とのことですが、そういうのは、あんまし関係なくて、凄い一冊だと感じました。南場智子に恋してる。
0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に優秀な人材で運営されていることが分かる。が、その優秀な人が展開しているサービスは世に必要とされているものなのか? こんな優秀な人材でこの程度のサービスしか提供していない会社は、存在しなくても良いのではないかと思う。
0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営コンサルタントに興味はあるけど、実業に勝るものはないということなのか。それとも隣の芝が青く見えるのか。適正は関係すると思うが、少なくともどの分野でもプロフェッショナルになることは非常に大切で、ある分野で実績を上げた人は他の分野でも上手くいくような気がした。
0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログなんて幸せな経営者なんだろう。 この本は、DeNAに関わるすべてのステイクホルダーへの長い長いラブレターだと思う。
0投稿日: 2013.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの著書、読み応えがありました。特に共感した点は、 ・利益は世の中にどれだけの価値を生み出したかの通信簿 ・人は、人によって育てられるのではなく、仕事で育つ ・何でも3点にまとめようと頑張らない、 物事が3点にまとまる必然性はない、自明なことを図にしない ・プレッシャーの中での経営者の意思決定は別次元、 「するべきです」と「します」がこんなに違うとは ・不完全な情報に基づく迅速な意思決定は、 充実した情報に基づくゆっくりとした意思決定に数段優る 数々の苦難を乗り越えるための根本的な動機は、社会に貢献する、 人の「役に立つ」という点に集約されるのだと、読み進めながら実感。 「企業は社会の機関であり、その目的は社会にあり、顧客の創造に ある」と言ったドラッカーのメッセージとつながります。 皆さんはどのような感想をお持ちでしょうか。
0投稿日: 2013.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログマッキンゼーの卒業生で、マッキンゼーにいた時がバリューの最大値にならなかったのは、最近では南場さん達ぐらいなのではないだろうか。働いてて楽しそうなのがひしひしと紙面から伝わってくる。
0投稿日: 2013.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんが夫の看病のために社長を引くというニュースを聞いたときは少し驚いた。 サイバーエージェントとの藤田さんもそうだが、南場さんも色々失敗したし運もよかったと言う。南場さんのいうように結果論かもしれない。でもね、やはりそうではないのだろうなと思う。 印象的なのは、マッキンゼー出身の南場さんが事業を始めるのにコンサルティング会社での経験は役に立つよりも害になると何度か強調しているところ。とにかく失敗したときのリスクなく推奨することと、失敗のリスクを取って決定することは大きな違いがあると。元気な中小企業の社長さんなんかを見ているとまあそうかなとか思うけれど。 こういうストーリーを読むと、さあ自分もというよりも、何も真剣に向き合ってなかったかなあ、と思ってしまうのは歳を取った証拠か。何かを始めるのに遅すぎるということはないぞ、というが。
1投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタントと経営は一流のコーチになった後、プロを目指すようなもので、本質が全く違う。 会社のこと、同僚のこと、部下のことを惜しみなく褒めれる点、自分の得意、不得意をさらけ出して文に落としてる点がとても素敵。 女の経営者の方が褒める点において上手なのかもしれない。 何度も目が潤んだ。南場さんの文には力がある。 口も悪いし、負けず嫌いな点がとても良いよね。
0投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログいやー、面白かった。DeNAという会社を誤解していました。ソーシャルゲームで金を巻き上げる会社ぐらいにしか思ってなかったです。 本書で書かれているのは、そんな会社の立ち上げから現在までの奮闘記。 熱病に浮かされたまま、仲間を見つけていって、いつのまにか社会的な貢献が出来ているような、そんな話でした。 熱病にかかって、一心になって、コトにあたる。何かを成し遂げるというのはそういうことなのかもしれません。
0投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
プロ野球も持つほどになっているDeNAの 立ち上げから現在に至るまでが、創業者が述べている。 いろんな困難の顛末を軽い感じで書いてあるが、根底には作者のチャレンジ精神ある。 正しい選択肢を選ぶことと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ことが重要など、リーダーとしての心構えについて勉強になった。
0投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに感動するとは思わなかった。「人と組織」あたりから目をうるませながら読んでいた。そこで既に感動しているので、その流れで読まされる「謝辞」はホントまずかった。 自分のチームのメンバーも、ホントはこんなふうに任せて育てられるようにすればいいのだと思う。みんながイキイキと仕事できるのが一番いいに決まっている。うれしい限りだ。でも、36協定に神経をとがらせながらマネジメントにこだわる大企業では、仕事に夢中になれる環境はもはや失われているような気もする。 ちょうど時期を同じくして読んでいる『モチベーション3.0』につながる話でもある。 うちは息子も家内も大の巨人ファンだが、今日から私はDeNAファンになった。
0投稿日: 2013.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこんちくしょう、悔しいよう。こんちくしょう、愛に溢れているよう。こんちくしょう、自慢ばっかりしやがって。 とても、面白かったです。最高でした。
0投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半はとても面白い。後半はちょっと褒めすぎ?で停滞するかな。でも凹んだ今のタイミングとしては良い本だった
0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書かと思ったらエッセイっぽい書き方で読みやすかったです。DeNA創設時のドタバタがとてもよくわかります。
0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA元代表取締役、南場智子氏の自伝。 ご本人の軽快な語り口をそのままに、これまでの経営を振り返る。内輪の実在する人を出して、彼らとどんな風に、あるいは彼らがどんなに頑張ってきたかを称えた、一種のラブレター。 こんな手紙を出せるなんて素敵だ。 意外に印象に残ったのは、社内ダイエット選手権。気持ちで勝てる試合に負けるわけにはいかない、と絶食で挑む。 リーダーたるもの、そうなのか。 たしかに、できる努力はしなくては。 なぜか、泣けた。 こんなにも一生懸命仕事をする人たちの姿に、自分も頑張ろうと思わずにはいられない。
0投稿日: 2013.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA創業者の南場さんの著書。創業時のストーリーをご本人が語っているが、人材採用論、コンサルタントの経験が起業をする際に直接役に立つことではないことなど、終盤ではよく聞かれる質問などをまとめていて、バラエティに富んだ内容。 また文体が柔らかく、直接話してもらってるような書き方なのでわかりやすくすんなり頭に入る。 組織は球の表面積、選んだ選択肢を正しくするなど、印象的なところはいくつもあるが、やはり目標達成の喜びと高揚感の話が最もインパクトがある。 お金じゃない。結局、ここが満たされていれば人はとてつもない力を発揮できる。あとは組織が大きくなった時にいかにこれが失われないようにしていけるか。そこがベンチャー企業が大企業になったときに失ってしまいがちなところ。
0投稿日: 2013.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社や社員のことをまるで家族のことのように話していて、本当にDeNAが大好きなのが伝わってくる。 とことん前向きで明るい人柄が魅力的。 組織は人なり。
0投稿日: 2013.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書や経営者の本は数多く読んだが、人に進めることは無い。薄っぺらいか、理論倒れだからだ。 これは、必ず読むべきだと思う。 アカデミックなことは何一つない。企業経営の臨場感という意味では、社長失格以来の興奮を覚える臨場感、そして感動 うまい文章ではないが、かざりの無い真摯な文章だからだと思う。一線を離れて取り組んだと思う。 ぜひ
0投稿日: 2013.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者南場智子氏。いまや知らない人がいないIT企業。モバゲーを含む人気サービスを次々に生み出しているが、ここまで大きく成長するまでには数々の苦難があり、それにチームでぶつかり続けたプロセスが軽快に綴られている。南場氏はマッキンゼーの出身、決してIT・開発分野のプロフェッショナルではないが、優秀かつ熱い仲間が集まることで夢が形に変わる。成功するWebサービスのシナリオ、人材、経営者としての判断、グローバルへの意識など南場メソッドがふんだんに盛り込まれていて楽しい。
0投稿日: 2013.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ日経産業新聞の連載より惹かれて購入。 リクルートと同じく、徹底的に人材に拘った点が企業の強みか。 筆者は、マッキンゼーやMBAのキャリヤはほとんど役にたっておらず起業するには必要ないとのことだったが、そうは思えない。 起業するに必要かは別として、資金調達や人材、大企業社長との人脈など、このキャリアを積んだからこそ今日の成功があるのだとおもう。 自分が立ち上げた会社ということもあり、若干誇張、バイアスがかかっている部分もあるとおもう。
0投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA創業者の南場智子さんによる、半自叙伝。全般を通じて、中でも特に、第7章「人と組織」で共感できるところが多く、さらに「あとがき」で語られる以下に、感動した。 「社員の数だけ個性があって夢がある。それぞれの個性と夢が集まって、またきっと離れていく。46億年の地球の歴史の中でDeNAの歴史はまだたったの数年だ。これからこの会社がどんなに長生きしようとも、地球や宇宙の時間の中ではほんの瞬間の存在になる。けれどもなにか宇宙に引っ掻きキズみたいな証を残したい。私たちの大きな夢とてんでバラバラの個性で、DeNAが生まれる前とその後では、きっと違う時代になる。」
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、ビジネス本には食傷気味で手を出さないのだが、周囲で「面白かったの声」をいくつも耳にしたので、乗っかってみたw 確かに、筆者の筆が立っていて、「不格好」といいながら真摯に前向きにチャレンジするDeNAの成長物語を追体験できて面白い。
0投稿日: 2013.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに面白い本を読んだ。 コンサルタントとして事業に関わることと、自分で事業を興すこととの差異が赤裸々に書かれており、リサーチャーとして勝手なことをいいながらメーカーに関わる自分自身を反省したりしながら、楽しくためになる本だった。
0投稿日: 2013.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ奥深くて痛快なサクセスストーリー。スピーディな展開と面白すぎる文章にわくわくが止まらない!一気読み。激やせラリーには大爆笑~!著書内にあった板倉雄一郎の「社長失格ーぼくの会社がつぶれた理由」を読んでみたい。さっすが南場智子、悪くない。イイと思います!!
0投稿日: 2013.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ思いが伝わるってこういう文章なんだろうな。 本からの熱量がとても心地よい。 あとがきの最後、二文で最後泣いた。 粋な女性だなーかっけぇー。 みんなのことが大好きです。これからもよろしく。
0投稿日: 2013.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイとして読むと面白いかな。 ところどころ、ベンチャーのスピード感や立ち上げの面白さ、大変さ(出資してもらうときの注意とか)がわかるのがよい。 社長の仕事の話ももちろんだが、ある若手リーダーの成長の話にも興味を持った。 一方でエピソードが多すぎるように思う。そのために内容が薄く感じられた。もう少し悩んだこととか仕事のやりがいや面白いところとかを深堀すると読みごたえが出てくると思う。
0投稿日: 2013.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事を任す。 誰が、ではなく、何を。 実際に会って、話をしたから、もあるだろう。生き方、気持ちが伝わる本。 気取るのでなく、本音だから、かわいい。
0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログパワフルビジネスマンのお話。面白いです。わたしが人生の指針や、女性としてのロールモデルになる、とかは一ミリもないけど。こういう人が沢山世の中で女性として活躍してるのは喜ばしい。応援。 あ、あと、コンサルタントと事業会社での働き方や考え方の違いは少なからず同意があるかも。目から鱗が落ちるってやつなこともあり。
0投稿日: 2013.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場さん起業録。成功体験より失敗体験をたくさん盛り込むようにしたという前書きが印象に残った。 そのまま読み進めていくと、まるで物語のようなでもどこか身近に感じられる飾らない文章が惹きつけて離さない。夢中で読んでしまった。 誰が言ったかじゃなく何を言ったか。 成功体験によって純粋にドライブされていく組織作り。 専門性を持ったパートナーと上手に働いて大きな仕事を達成すること。必ずしも自分が主役にならなくてもいいこと。 意思決定とコンサルタントとしての提案には必要な勇気が違うこと。 結局自分が選んだ決断をどう正しくするか、が成功の半分であること。結局リーダーに必要なのはケツを自分で拭く胆力であること。 これらの内容は自分のキャリアパスにも似ていてとても参考になった。
0投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ指原さんに薦められて読んでみたが、とにかく楽しめた。 やはり仕事はこういう思いで失敗も含めて、楽しまなきゃ と痛感。
0投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタントから事業家に転身して立ち上げたDeNAとの軌跡が書かれており、様々なエピソードから南場さんの人柄が伝わってくる。
0投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ早すぎず、遅すぎず、時代のニーズを的確に捉えて、一番使いやすい形でサービスを提供する。 これを実現してナンバーワンになったものだけが拡大の良循環を手にする。 1、とんでもない苦境ほど素晴らしい立ち直り方を魅せる格好のステージ 2、振り返ったときにあれが良かったねと言える大きなプラスアルファの拾い物をしようと考える お釣りが欲しい 3、命をとられるわけではないんだからおおらかにやろうよ 誰が言ったかではなく、何を言ったかに意識を集中。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ優秀な人が集まっている会社というのはとてもよくわかったので、いつかゲーム課金ビジネスから社会的な付加価値の高いビジネスへ移れればいいよなと思いました。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのタイトルは絶妙。 黎明期のエピソードの一つ一つが面白く、エンターテインメントとして読める本。話題になっただけのことはある。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年88冊目。 1ページ目の言葉の感度だけで、「これはしっかり読み切ろう」と思えた。 そしてその直感は外れていなかった。 「流行本だからミーハーかな〜」と思っていたけど、学び多き良本。 こんな人にオススメ↓ ■「最初のキャリアは今後のためにやっぱりコンサル!」と思ってる人 →マッキンゼー出身の著者が「コンサルよりも事業会社の方がいい」と言ってるのが面白い。 ■トップの意思決定の仕方を学びたい人 →完全な情報を揃えたゆっくりな意思決定よりも、不完全な中でも迅速な意思決定が勝る ■部活のような熱いチームワークを目指す人 →仕事の任せ方や、組織の方針が参考になる
0投稿日: 2013.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ずいぶん前に読了していたのですが、改めてレビューを作成しました。 マッキンゼーを辞して会社を立ち上げ、苦労しながら一歩一歩進んでいく姿は コンサルティングを生業とする僕らにも感銘を与えるものであるし、 自分で事業を進めるということは泥臭いものだということが、筆者の実体験を通じてシミジミと感じられます。 一方で、僕が最も感銘を受けたのは「人と組織」について。 社員を信頼し、その成長を最大限にサポートするという姿勢は、リーダーとして目指すべき姿の一つであり、これも試行錯誤の末にたどり着いたのではないかと思う。成長の場として会社を定義することで、魅力的な人材を集めやすくなる。人の問題は、企業ITを語る上でも一番の課題と言っても過言ではなく、組織設計・戦略においては参考になる点も多いのではないかと思いました。 人材獲得は、ハートをぶつけるしかないですね・・・。 また、南場さん自身には、ロールモデルはないが師匠はたくさんいる、と言います。 色々な分野で尊敬でき教えを乞える人物がいるのは、とても羨ましい。僕も30数年生きてきて、「この人みたいになりたい」というロールモデルを見つけようとした時期もあったのですが、所詮、自分は自分でしかないという結論にたどり着きました。特に、コンサルタントという仕事は、チームプレーが重要でありながらも、最後は個人の人間力に負うところが大きい。ガリ勉では行き詰まるし、遊び呆けていてはクライアントへ価値を提供できない。その上、学ぶこともやたらと多い。そんな中で、色々なジャンルで師匠を持つことは自分を磨くためにも大事だし、温かい人間関係を構築することにも繋がるのではないかと思う。 DeNAの快進撃や南場さんご自身のキャリアに興味がある方は、ぜひ一読されることをお勧めします。
0投稿日: 2013.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書には入らないですかね。私小説です。 なんせもともとの実績やお金や人材の規模が参考になりません。 ただ私小説として読めば面白い。 南場さんの人柄や、チームの作り方や勢いはとても興味深いです。 「勢い」がキーワードでしょうか。 不格好を気にしていないから不格好なのだろうと、そんなことを気にしない勢いが会社や事業を創っていくのだなと。 やっぱり、トップには勢いが必要と感じます。 素早い決断力とでも言い換えられるでしょうか。 それができないトップについていこうとはなかなか思えないなと。 なぜなら、そういうトップは「失敗」に気付いたときの判断力や決断力も人一倍あるのです。 失敗した時の判断が信頼に繋がると改めて感じました。 この本を読んでいて、身近な女性のトップの顔を思い出したりもして。 照らし合わせながら読むのも面白かったです。
0投稿日: 2013.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ日経ウーマンで紹介されていた本。不格好とは言いながら、やはり素晴らしい能力と人材をマネジメントしている。人材って大事だと思うし、それはひきつけられるだけのその人の能力も必要だと感じた。
0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんからわが子へのラブレター&南場スタイルのヒント。 カイシャってなんだか無機質な場のように思っていたけど、中にいるのは人間で、想いがあって、めっちゃがんばったりしてる、有機的な、ひとの集まりなんだなぁ。と、思った。 南場さんの「コト」に向かうってキーワードすごく正しいと思う。 経営者の仕事って、「決める」ことなんだよね。決めるってほんと勇気がいる。かつ丼か天丼かでも悩むのに。社員および家族および株主の人生を左右するかもってことを決めるって、どんな気持ちなんだろ。しかも早く決めなきゃいけないし。想像をこえる。 とりあえず、ハーバードMBAどやエピソードがさらっとしすぎてて流石、と思った。頭いいなー。 すごいぜかっこいいぜ南場さん!
0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんという経営者には以前から興味があったけど、それもこれも旦那さまの病気という岐路に立ったときの判断に共感できたから。そのあたりの心の動きがちゃんと書かれていて、また興味深さのレベルが一段上がりました。
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログチームDeNAを率いてきた南場智子さんが、起業からと将来を赤裸々に綴った一冊。 DeNAが起業から不格好な経営をしながらも成功できた要因は、優秀な人材を執念で集めた結果だと思う。それだけ、南場智子さんは魅力があるのだろう。 起業家の半生として、とても面白く読めた。個性的な文体が、引き込まれる要素のひとつになっている。
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コンサルタントとして気に留めておくべき部分。 >自分が経営者だったらもっとうまくできるんじゃないだろうか。…もしそんな風に感じているコンサルタントがほかにもいたら優しく言ってあげたい。あなたアホです。ものすごい高い確率で失敗しますよ、と。 >事業リーダーになりたいからまずコンサルタントになって勉強する、というのがトンチンカンだということにすぎない。ゴルフでタイガーウッズのようなトーナメントプロになりたいから、まずはレッスンプロになろう、というのと同じくらいトンチンカンだ。 >若くしてコンサルティング会社に身を置くことで事業にマイナスな癖を拾ってしまうこともある。→賢く見せようとする姿勢…上から目線…キーパーソンにおもねる発言
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み物として非常に面白かった。 ちょうど新ビジネス企画中で、"組織力をどう高めていけるか" について議論している時期であったが、 本書はどちらか言えば「個の力」にフォーカスされているように思えた。結局天才がいれば、組織として成り立つ...というような。 経営のイチ事例として、DeNAのポリシーはよく理解できる。
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に、南場さんの温度が伝わる良書だった。ベンチャーならではの軽さがあるかな...と思ったが、それは勝手な思い込みであり、旧態然とした組織に身をおく自分の垢なのかなと感じさせてくれた。 人事部門ではたらく者としては、自然に「人と組織」の章で感情移入するところが多かった。 「従業員一人ひとりが会社や組織の代表者...だから組織はピラミッドではなく、球体の表面」。なるほどな。 また、別に共感したところでいえば、「誰がするかではなく、何をするか」。 別インタビューでは「コトにあたる」という表現がなされていたが、当たり前のようでなかなかできないこと。 自分の会社にもいわゆる『政治』はあり、どうしてもそうした政治に振り回されがち。 そうした現状に対し、皆の前で時折熱病のように「変えたい」という同僚もいるが、そう言う同僚こそ一番政治っぽいところを見てしまうことも多い。 自分はどうか。 コトにあたることに集中するためにも、まずはある人との間にある、変なわだかまりだけでも修復しないとな...。
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ私DeNAを誤解してました。南場社長の強烈なリーダーシップ!で鍛えられた会社なんですね。下手なビジネス書より説得力あります。社長業をやってる人でないとこの面白さは分からないかもしれません。
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログよく言われているように、不恰好どころか一流の人材や支援を事もなげに糾合してDeNAを一流企業に育てていった南場さんの凄さが際立っている内容です 最強メンバーによるスタートアップの書籍って実はあまり見かけないので、その点この本は貴重です
0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタントが事業リーダーになるときに苦労した点 +提案から意思決定。実際にリスクを伴う。同じ立場で提案しているというのは無知でありおごり +決定プロセス:論理的な意思決定のプロセスをチームとシェアすると、決定の迷いを見せることでチームの突破力を極端に弱めてしまう。検討に巻き込むメンバーは一定人数必要だが、決定したプランを実行チーム全員に話すときは、「これしかない、いける」という信念を前面に押し出したほうが良い。事業を実行に移した日から、企画段階で予測できない様々な難題を解決する必要があるため、迷いのないチームのほうが迷いのあるチームよりも突破力がはるかに高い +不完全な情報に基づく迅速な意思決定のほうが、充実した情報に基づくゆっくりとした意思決定に数段勝る(実行する前に集めた情報など、たかが知れている。本当に重要な情報は、当事者になって初めて手に入る) +正しい選択肢を選ぶのも重要だが、選んだ選択肢を正しくするのも重要。リーダーに最も求められるのは胆力 +資金繰りに苦労。コンサルの経費の浪費癖 +できる限り賢く見せようとしないで、あほさをさらけ出しても助けてもらわなければいけない場面もある +残念な上から目線をやめる +具体的なアドバイス -何でも三つにまとめようとしない。物事が三つにまとまる必然性はない -重要情報はアタッシュケースではなく、あたまに入れる -自明なことを図にしない -人の評価を語りながら酒を飲まない -ミーティングに遅刻しない その他 +何の寄り辺もなく起業するものは、有名な大企業のサポートをとても心強く感じてしまいがち。だが、大企業を大株主に迎える場合、状況は変わりうるということを頭に入れる必要。大企業にも株主がいて、その意向が反映される +コンサル時代はクライアント企業の弱点ばかりに目がいく。普通に物事が回る会社、普通にサービスや商品を提供し続けられる会社がいかに普通でない努力をしていることか +PCユーザーとモバイルユーザーは行動が異なる。モバイルユーザーは時間の隙間を埋めようとする。利用パターンが異なるので、モバイルをインターネットサービスの一端末として位置付けるのではなく、特化したサービスを展開することが重要 +社長という立場は一瞬にしてものを作り出すことはできないが、一瞬にして破壊することはできる +売上高1000億円、狙ってもなかなか達成できないような難しいことが、狙わずにできるはずがない。勝手にホワイトボードに目標売上を書く→Visionが最初に来る大切さ +経営の最優先課題は、利益よりも優先される(e.g.,健全コミュニティ促進委員会の立ち上げ) +Role model leadership style:若い人がシニアのチームのリーダーになったときに、成果が出ず、チームの気持ちは離れて崩壊寸前。リーダーは指示をやめ、外の営業に出てチームの誰よりも足を使って成果を上げた。その上で、会社に戻ってからは提案書や営業アプローチを資料に残し、可視化。さらに「自分はよりリーダーになれず、苦しんでいるから助けてほしい」とチームに言うことで、周囲を巻き込んだ +成長への意識はほどほどが良い。入社してからも成長というのは変。プロフェッショナルとして、インパクトを出して結果として成長するのなら理解できる +優秀な人の共通点:素直だけど頑固、頑固だけど素直、容易に成果に満足しない、アクションに関するアドバイスは聞くが、結論に関するアドバイスには容易に納得しない +あと10年で、組織に属して仕事をするスタイルは主流でなくなるし、目的単位でプロジェクトチームが組成され、解散する仕事の仕方になる。多くの場合、国境を越えた人材でフォーメーションが組まれていく
0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんは非常に優秀で、カッコいい経営者。 でも初めは相当な苦労をされ、 一世一代の賭けのようなスリリングな 意思決定をしたこともあったようです。 そんな南場さんが、夫のガンのため社長を 辞める決断をしたのは、本当に素晴らしい事 だと思います。ご主人にも奇跡が起こって良かった!
0投稿日: 2013.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ割と話題の人気本。DeNAの実態はどんなもんかわからないし、内部の人から言わせると意識を鼓舞するために書かれたとかかもしれないけど、普通に読んで普通に面白かった。 それでもやっぱり、南場さんはアホとかではなく、スーパーウーマンなんだろうね。 自分にはああはなれない。
0投稿日: 2013.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創設者である南場さんがマッキンゼーをやめ、DeNAを立ち上げてから現在に至るまでの出来事、心境を語った本。 レベルの高い人材がそろっていたことはもちろんのこと、仲間同士が同じ方向を見ながらお互いを尊重する組織であったことが成功の大きな要因なのだろう。 ベンチャーならでは、若いうちから大きなプロジェクトを任され、苦労をしている社員はどんどん実力をつけていくのだろう。ベンチャー企業でなくとも自分の仕事の中に自分が成長できる要素を見つけ出しながら仕事を進めていくべきだと感じる。 DeNAに限らずベンチャー企業に入社するような「学生時代から専門知識やビジネス基礎体力を身につけている人」と張り合うためには日々の勉強を個人的に進めていかなければならない。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半3分の2は、南場さんの今までの生き様とDeNAの沿革について書かれており、残りで会社経営で得た教訓が書かれている。 人から借りたものなので早く帰すべく、飛ばし読みになってしまった。 2004年に売上16億が2012年に売上2000億になったのはすごい!
0投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代、南場さんが学校に講演に来てくださり、その講義のスタッフをしていたので 南場さんとは挨拶させて頂いたことがあります。 元気な人というイメージで、ドラムを猛練習中、という話もされていました。 ドラムの話は巻末に少しありましたね。 講演時はまだモバゲーができる前でしたので、本の前半部分の話、 プログラムが出来てない時の話はそのままされていたな、と聞いた当時を思い出しました。 そこから10年近い時を経て、この本を読むにあたり気になったのは ・会社を退いた事情の委細 ・コンプガチャなどの問題に対しての考え でした。 旦那様、2度の癌がよくなって、本当に社長を退くという判断をされて良かった、 良かったといういい方も不適切かもしれませんが、 DeNAという会社のためには、早期に創業者が一線を退くというのは良いことだと思います。 問題に対しては、コンプガチャの前の出会い系の問題から、徹底的に対策をしていると。 そのあたりの話題もありました。 社名を出すのは控えますが、いくつかの会社と違うのは会社を「公器」と捉えるか、否か なのでしょう。 実際私はDeNAのサービスを利用したことがないのですが、利用者の幸せになるような サービスのために、これからも南場さんにはご活躍頂きたいと思います。
0投稿日: 2013.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんのキレがよく、ウィットに富み、温かみのある文章が好きで以前はブログを時々拝見していたのだが、DeNAの急成長とともに聞かれるようになった悪い噂にいささかがっかりして、いつの日か足が(クリックが)遠のいていた。 そんな中でのこの本。とはいえ自ら買い求めたわけではなく、先に読了した父が「読む?」と言ってきたので手に取った次第。 父なりに何か娘と重なるものがあったのだろうか。 読んでみて、経歴・才覚・胆力ともに南場さんの足元にも及ばないことを痛感させられまくりで「重なる」なんて非常におこがましいのだが、それでもページをめくるごとに首を縦にぶんぶん振りたくなるような、共感するフレーズがいっぱいに詰まっていた。 また南場さんの語り口が健在(どころかパワーアップしている?)いること、数々の噂に対してはDeNAとして真摯に対応しているらしいことを知って嬉しく思った。読んでよかった。 (こういう、読者を共感させて「南場さんと友達になりたいかも」と思わせてしまうところも、南場さんの筆力の成せる業なのだとは思うが、それはさておき。) 特に第7章「人と組織」。私自身事業会社から転職しコンサルティングファームに数年籍を置いたことがあるので、事業リーダーとコンサルタントに求められるスキルは全く異なることを日々感じる。そして、(勘違いコンサルが世の中に蔓延する中)軌道修正をきっちりやってのけた南場さんを尊敬する。 それから「ロールモデルを作らない」「ついていきます、と言われたら全力で断る」も同感。自分は尊敬する人に「ついていきます」は絶対言わないと決めている。尊敬する人にこそ、自分の個性でぶつかりバリューを出していきたい。 熱が入りすぎて長くなってしまったが、そんなこんなで一読の価値あり。 余談ながら、南場さんが女性だということも大きな意味を持つと思っている。20世紀までやたらと「女性らしさ」を前面に押し出す「女性」起業家が量産されて辟易していたが、やっと性別を超えたカギカッコ無しの女性起業家が日本でも生まれるようになったのだなあ、と思うと興味深い。そう考えるとこの本を女性起業家の黎明の書と位置付けることもできる。
0投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営とはこんなに不格好なものなのか! コンサルと事業家との違いなど、事業家としてもほんとに大事なことが書かれていた☆ とても等身大で描かれていてDeNAという会社を好きになりました☆
0投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
女性経営者の本ということで注目を集めたようだが、実際に読んでみると、「女性」ということをほぼ感じさせない内容。 起業を通して、コンサルタント時代との意思決定の重みの違い、その場その場で判断をしてすすむしかない対応力・精神力、人に仕事をまかせる力といったところが話のポイントか。
0投稿日: 2013.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
会社を作る「コト」。それは本当に楽しいこと、 誇りに感じられることであると改めて教えてもらった気がする。 DeNAってどことなくとっつきにくい雰囲気がある (エリート中のエリートしか採らないなど)と就活中は感じていた。 でも、今回の書籍を読んでみて、イメージがガラリと変わった。 こんな楽しくて希望に溢れている会社だとは思わなかった。 なにより、南場さんという人柄がすごく人間くさくて、好感を持った。 「人」ではなく「コト」に向かう楽しさ、大切さを教えてもらいました。 「素直と頑固さ」を胸に、自分自身も頑張りたいなと思う。
0投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAに対する誤解が多かったけど、読んでその認識が変わった。創業時の苦労を思うと、DeNAをこれから応援したくなる。でも自分が生きている世界と価値観とは全然違うなと思った。違う世界の人って印象だった。だから共感できるところがほとんどなかった。目標売上高をさらに何億円も上に設定し、早急に事業を拡大させようとする発想が僕にはない。気質とか性分が、こういう経営に合っていないだろうなと思った。
1投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ・意思決定については、緊急でない事案も含め、「継続討議」にしないということが極めて重要。だから「決定的な重要情報」が欠落していない場合は迷ってもその場で決める。 ・どんな人手不足のときでも、人材の質には絶対に妥協しないことをポリシーとしてきた。すごい!と思える人、尊敬できる人と一緒にいると自身の気持ちも高揚し、怠惰な自分も最高に頑張れる。 ・人を口説くのはノウハウやテクニックではない。「索」の要素を排除し、魂であたらなければならない。私が採用にあたって心がけていることは、全力で口説く、誠実に口説く、の2点に尽きる。 ・なぜ育つか、というと、任せる、という一言につきる。人は、人によって育てられるのではなく、仕事で育つ。しかも成功体験でジャンプする。それも簡単な成功ではなく、失敗を重ね、のたうちまわって七転八倒したあげくの成功なら大きなジャンプとなる。 ・ギリギリな仕事を任せれば当然、失敗するリスクもある。でも、不思議と人は潜在化している能力の数倍の能力を有していて、本人も驚くような大仕事をやってのけるものである。万が一できなければチームが寄ってたかって助ける。 ・自分が接したすごい人たちの共通点は、「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」。 ・1、全員が主役と感じ、ひとりひとりが仕事や成果にオーナーシップを感じるようなチームの組成、仕事の単位となっているか。2、チームの目標はわかりやすく、そして高揚するに足る十分に高い目標となっているか。3、チームに思い切った権限委譲をしているか。信じて任せているか。 感想 人材採用を重要視する。ほしい人材は魂で口説く。スタッフに任せる。
0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間味溢れる話で非常に面白かった。天才が寝ずに本気を出して作り上げたのがDeNAという企業なんだ…。南場さんの講演を聴いて感じたこととこの本を読んで感じたことは変わらない。「やり遂げる人間になれ」ということだ。そのための任せる文化なのだろう。やり遂げる、成功体験を重ねる。強く意識して臨もう。
0投稿日: 2013.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ株主として、DeNAという会社のことをもっと知りたいなと思っていた矢先に絶妙なタイミングで発刊されたこの本、面白さもさることながら、南場取締役の思いに少しでも触れることができる良書だと思います。これからもDeNAを長い目で応援しようと思います。
0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログいや〜、おもしろかった。映画化しないかな? ありがちな経営者の成功自慢本ではなく、起業から現在までの波瀾万丈が綴られているところがとってもいい。マッキンゼーのコンサルタント出身ということで、経営理論に基づいたスマートな経営かと思いきや、以外とそうでもなくって、なかなかのドラマを展開してきたようだ。ただ、根っこのところではどうやらマッキンゼーの価値観は大切にしているようで、人材育成にはかなり重きを置いている様子が感じられ、かなり好印象を持った。よいカルチャーを持った良い会社を作られたのだろう。 自伝に分類されると思うが、お世話になった方々や、従業員の皆さんへのメッセージとして書かれたようで、南場さんの人間味や魅力が詰まっている。お薦めの一冊。
0投稿日: 2013.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者、南場智子さんのDeNA立ち上げから退任までのビジネス書。 本書の中で特に印象に残ったのは「意思決定」に対する考え方。すべての情報を調べ上げて行う遅い意思決定よりも不確定な情報でも迅速な意思決定をする方がよい。この考えは普段の自分の仕事にも通じると思う。
0投稿日: 2013.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者が起業から今日までの奮闘振りを活写するもの。人気の本書ですが,いやいや,不格好じゃないと思いました。短文で,何を伝えたいかが明確で,かつリズミカルな文章から,様々な苦労がしのばれます。語れないこともあるだろう,オブラートに包んだものもあるだろうと思いながら,しかし,読了後に,なにか,こう,うまく表現できないが,胸にずっしりくる感じがある。いい本です。
0投稿日: 2013.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAについては、携帯ゲーム会社ぐらいのイメージしかありませんでした。 本を読んでいて、会社の成長も人間としての成長も共通点が多いような気がした。 失敗や悪あがきをして、人に支えてもらった経験の方が、人間としてしっくりくるとの言葉が印象に残りました。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり、素晴らしい経営者。 これ程の苦難があったとは意外でした。DeNAの躍進の要因は、人材、組織、社風。『任せる 』が、キーワード。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ就活で、DeNAの会社説明会に行ったのだけれども、そこでの南場さんがすごい面白いおばちゃんという印象を受けたのを覚えている(DeNAはよく知らないで参加したけど、この会社は面白そうと思ったのを覚えている。残念ながら、二次面接で落ちた。)。 その印象はこの本を読んでも変わらなかった(ブログもこんな感じなのでそりゃそうかもしれないけど)。 雑誌のインタビュー読んでても、できるキャリアウーマンみたいな印象にしからないんだけどね。 この本を読んで思ったのは、DeNAは社内英語公用語化なんてしないのだろうなと(現社長が英語苦手らしい)。
0投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ程よい毒舌感。 【引用】DeNAの競争力の源泉は、とよく訊かれるが、答えは間違いなく「人材の質」だ。 人材の質を最高レベルに保つためには、 ①最高の人材を採用し、 ②その人材が育ち、実力をつけ、 ③実力のある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、 ④だから辞めない、 という要素を満たすことが必要だ。
0投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ知人でもあるDeNA南場さんの人柄がよく現れた、読者を元気づけ勇気づける素敵な内容でした。 同じ時代を同じような業界で過ごしている私も、自分なりに懸命に走って来たつもりだけど、彼女の思い切りのよさやエネルギーのかけ方の凄さに、知ってはいたけど改めて感服した。
0投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダシップ、チーム、そして人の成長する機会を重視すること。魅力的な会社です。スピード感が100倍違う。そんな感覚のチームがこの業界に出現したらどんなことになるのか・・・。
0投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAを創業した女性のワクワクするようなビジネスストーリー。同時期に発売されたシェリルサンドバーグとの決定的な違いは、子供がいないことか。 高い能力を持った一人にビジネスマンの起業ストーリーとして面白かった。 仕事上での様々なトラブルや、仲間とのやり取りはビジネス書としては参考になることも多い。仕事をする上で、自分が女性であることを余り意識せずに来たように書かれている。ただ、夫の病気が原因で突然社長職を辞したという経緯は、ニュースとして大きく報道されたこともあり興味深かった。
0投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場智子の不格好経営を読みました。 チームDeNAの挑戦、という副題がついています。 マッキンゼーのコンサルタントをしていた南場智子が一念発起してDeNAを起こし、その会社がモバイル事業を拡大していく様子を描いたノンフィクションでした。 南場智子と一緒に事業を始めたメンバーとの苦闘が描かれています。 才能があって努力することをいとわない優秀な人たちがプロジェクトを進めていく。 いろいろな壁にぶち当たるけれど、何とかその壁を乗り越えてプロジェクトが成功していく。 という物語を読んで、うらやましいなあ、でも私が住んでいる世界とは別次元なんだろうな、と思ってしまいました。 ところで、私は携帯電話は音声通話とメールしか使っていないしパケット定額も契約していないので、DeNAという名前もベイスターズを買ったときにそんな会社があるんだなあと思った程度なのですが、この本を読んで少し興味がわきました。 私は親の遺言でオンラインゲームはやらないのですが、ちょっと覗いてみようかな、と思ったのでした。
0投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルとして提案する立場と事業者として判断する立場の違いが書かれている箇所に興味がわいた。 社長というのは常に挑戦し意識を高くもっていかないとなかなか成長しないのだと感じた。
0投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ友人が来年からDeNAで働くので読んでいたのを借りて読んだ。 読み物としてはドラマがあってとても面白かったけど、もし僕が同じ立場になったとしたら(そんな想像をすること自体がおこがましいが)、たぶんストレスで胃潰瘍にでもなって死ぬだろう。
0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの立ち上げを書いていて面白いのですが、内容が少しブログとかぶっているんですよ。ある程度はしょうがないにしてもダイエット競争の話はブログとかぶってまで載せなくてもとは思いました。会社の雰囲気をあらわそてるエピソードではあるんですけどね。
0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAを立ち上げた著者による創業からの来歴と経営に関する思いを記した一冊。創業者、経営者としての苦労、悩み、そして喜びがライブ感あふれる文章で綴られ、箴言に溢れた第7章が特に示唆に富む。格好の良い経営なんて絵空事、不格好だが懸命に突き進んだ先に格好の良い生き様が残る。
0投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社を起業して、それを組織として育てていくということは、本当に大変なことなんだと思う。資金面からも、それ以外のことでも、サラリーマンをしている自分からは想像が付かないことも沢山。本を読んでいると性別を意識せず、普通に対応している様にも感じられてるが、本当のところはどうなのだろう。
0投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ法人という表現は言い得て妙で、会社は人と同じように成長していくのだと思った。 自分も熱病にかかるほどの何かを見つけたい。そのときはコンサルタントを辞めます。
0投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマッキンゼーで活躍中、クライアントの何気ない一言から起業を決意。しかし利益を出せず、4年間赤字に苦しむ。オークションサイトでヤフオクと戦い、モバゲーで成功するも様々な規制に悩まされ…。DeNA創業者の赤裸々すぎる手記。 南場さんのブログはよく読んでいて、あっけらかんとした語り口が好きだったので購入。ものすごく読みやすく、感情移入もしやすいのだけれど、途中まではあまりピンとこなかった。苦労話を聞くだけかぁ、と思ったりしていて。けれど南場さんの文章には温度があって、他人事ながらも手に汗握ったり、一緒に喜んだりできる。あまりにテンポ良く次々起こるハプニングに、事実は小説より奇なりだなぁと実感した。 コンサルタントとして顧客に様々な指摘をしてきたが、それを実行に移すのは全く次元がちがうことなのだそう。とても印象に残った。どちらが偉いというのではなく、全く違う行動なのだと、知っていなければいけない。 また、周りの人に泣きつき、助けてもらいながらやってきたという南場さんも、引退を考えていることや本当に重要な案件は誰にも話さなかったそう。社長というのは本当に孤独なのだなぁ。我が社の社長のことを思い出し、もっと自分にできることはないかと振り返るきっかけになった。
0投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ清々しい社内外の経営半自伝。「コンサルと企業リーダーはこの部分で大きく異なる」「苦しい時はこんな考え方をした」等、今の自分にとって素直に力づけられる本でした。
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいくうちに、タイトルの意味が分かりました。表面上は輝いているDeNAも、裏ではたくさんの苦労があったのですね。 マッキンゼー、ハーバードでMBA取得、輝かしい経歴をもつ南場さんですが、いろんな人が支え合ってDeNAが起き、発展していったのだと分かりました。働く前の学生が読むんでもわかりにくい部分が多いのですが、1度社会で働いている人であれば、わかりやすいのではないでしょうか。 失敗から学ぶ、メンタリティーを勉強できると思います。
0投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの自伝。ベンチャーにかかわる全ての人にお薦めする良著。南場さんの人柄が良く伝わるし、はっと気付かされるメッセージが沢山。
0投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと茶目っ気があって、 人間的な魅力が、文章にあふれてる。一人ひとりの才能を見抜き、個性を尊重する南場さん。やがてその人材は、力を発揮する。南場さんが多くの人を惹きつける理由がよくわかる。
0投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログほっこり。著者の正直な人のよさが感じられて。組織が人の集まりであることを見せてくれていると思う。また、自分は決定力がなくふわっとさせてしまうタイプなので、「意思決定が仕事」という社長業にははっとする一言もたくさんあった。意思決定したら周りに迷いを見せないほうが成功率が高い、選択自体には正解はなくそれに対し行動したか、「誰」ではなく「何」とか、いろいろ頭においておきたい。
0投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったけど、やっぱりちょっと内容薄い気も。。 ただ、DeNA Qualityの1つにある「球体の表面積」っていう表現はインパクトあった。ベンチャーのような間に落ちる仕事が多い状況ではなおさら。 日々心がけよう。
0投稿日: 2013.07.30
