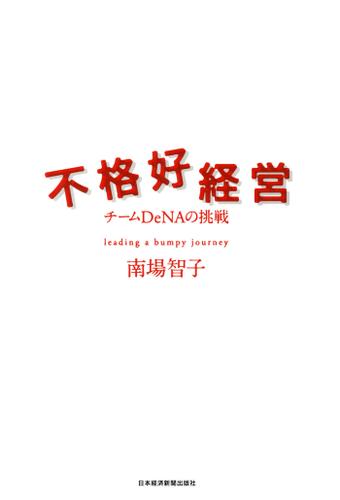
総合評価
(480件)| 172 | ||
| 179 | ||
| 67 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこんにちは、土井英司です。 ノンフィクションからノウハウ、実用書まで、ビジネス書にも いろんなカテゴリーがあるわけですが、名著として長く棚に置 かれるのは、有名経営者のビジネスノンフィクションと相場が 決まっています。 アイアコッカ、リチャード・ブランソン、ビル・ゲイツ、ステ ィーブ・ジョブズ、松下幸之助、本田宗一郎、盛田昭夫、小倉 昌男、稲盛和夫…。 これまでたくさんのビジネスノンフィクションを読んできまし たが、本日ご紹介するDeNA創業者、南場智子さんのノンフィク ションは、今年いちおしの一冊といっていいと思います。 誰もが挑戦したいのに、保守的な気持ちが勝って、なかなか挑 戦できない。結果、起業する人間というのは少数なわけですが、 それをマッキンゼーのパートナー(役員)にまで上り詰めた著 者が挑む。これが面白くないわけがありません。 本書には、エリートコンサルタントが泥臭い実業の世界に飛び 込み、試行錯誤するなかでつかんだ栄光と、それ以上に価値あ る仲間たちの姿が、鮮明に描かれています。 なかでも、本田宗一郎を支えた藤沢武夫のように、著者を陰か ら支えた名脇役、春田氏のエピソードは、読んでいて泣けました。 ここまで清々しく、かつ深い感動を呼び起こす一冊には、なか なか出合えるものではありません。 不完全な人間が未知の世界に挑む。だから起業は困難の連続に なるわけですが、本書には、そのドラマが余すことなく書かれ ています。 経営するなかで、理不尽さ困難を感じたこともあったでしょう が、そこをぐっと呑み込み、あくまで朗らかに語る著者の姿勢 が、文体とも相まってとても気持ちいい。 著者は、オビでこんなことを書いています。 <経営とは、こんなにも不格好なものなのか。だけどそのぶん、 おもしろい。最高に。> 「創業した頃の不格好さを取り戻し、また明日から頑張ろう」 そんな気持ちにさせてくれる一冊です。 ぜひチェックしてみてください。
1投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場さんの半生自叙伝 取り留めはないが、気付きの種になる記述が結構ある。 コンサルやMBAの経験は、事業家になるには役に立たない、ということ
0投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的: 会社経営において大切なことを学ぶ。 目的達成度: 4.8 ★最大の学び・気付き→アクション 1.南場さんが考える理想の組織は下記の通り。 「同じ目標に向かって全力を尽くし、達成した時の喜びと高揚感を経営の中枢に据える。互いに切磋琢磨し、時に激しく競争しても、チームのゴールを達成したときの喜びが全員に共有され、その力強い高揚感でシンプルにドライブされていく組織」 → 自分が経営を行う際は上記のことを実現できる仕組みづくりをする。 2.「競争力の源泉は人材の質」であり、「最高の人材を採用し、その人材が育ち、実力をつけ、実力のある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、だから辞めない」と言う会社であるべき。 → どう言う人事の仕組みを作れば上記のような会社にすることができるかを考える。 3.「誰が言ったかではなく何を言ったか。」が重要であり、「管理職はただの役割であり、エラい訳ではない。」し、「会社での立場が人間の上下関係ではない。」 → 大企業ではよくありがちな誰が言ったかを重視する文化には染まり過ぎないように意識をする。また、自分が管理職になった際は「管理職は人をまとめると言う役割」と言うだけで、決して周りよりエラいと言うような認識は持たないように肝に命じておく。 ★感想 文章もユーモアに富み大変おもしろく、かつ学びが多くあり、モチベーションにも繋がる良書であった。 経営者がいかに大変であるか、しかしその大変さが故に、いかにやりがいのある仕事であるかを感じることができた。
0投稿日: 2019.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャーの創業者がどういう風に考えて起業し、そこからどのような苦難を乗り越えてメガベンチャーに至るのか、とても面白く読めた。 創業者の元に綺羅星の如く優秀(だけれどもどこか人間味のある)な人材が集うというところが、現代の水滸伝風に読めた。 学べたのはやはり思い切りの良さと、人が少ない中での動き方であり、大企業にあったとしても自分が会社の社長のような心持ちで意思決定をするという覚悟を持つことで、より会社の成果にコミットできるのではないかとおもった。 星を一つ減らしているのは、個人的な学びがあったかというと、そこまでの学びはなかったから。読み物としてはとても面白かった。
0投稿日: 2019.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創設者南場智子さんのビジネス書。一気読みとはいかず、時間をかけて読んでしまったのでもう一度読み直さないとなぁと。
0投稿日: 2019.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初はコンサルでやっていた南場さんが実際に経営をやってみると、そんなうまくはいかない。 実際に見るのとやるのとでは違うなと感じました。 また、良いことばかりでなく、本当に苦労した体験が手に取るように感じ取れます。 こういう良いことも悪いことも全てひっくるめてこういう生き方が格好いいなと思います。 飛信隊に例えると、一人で中華統一を目指していたところからどんどんみんなの夢になっていく。 私、渕上真希としてもこれからガンガン仲間集めていきます。
0投稿日: 2019.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAという会社の歴史が明快に躍動的に書かれていて 起業の経験談としても読み物としても面白く読み易い 南場智子さんの生い立ちや人生観の変化も興味深い
0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの創業者の南場智子さんの自伝。ユーモアあふれる文章が快調なテンポで語られ、最後まで一気に読み通してしまった。コンサルティングファームで経営者の相談にのっていた著者が、自分でやってみたら?と言われて一念発起、経営に携わる中で、壁にぶつかり、転んだり助けられたりしながら、著者もまわりのメンバーも成長していき、そして会社も成長していく様子が描かれる。 読み進める中で、次から次へと個性あふれる部下が出てきて色々な場面で活躍し、読み終わる頃にはDeNAの経営陣の一人一人の人となりに詳しくなってしまっていた。高い目標に向かってチャレンジする部下の背後に、能力を見抜いて抜擢し、見守っている南場社長の存在を強く感じた。上司と部下、というより、若い女性教師とやんちゃな学生たち、という趣だ。そして一人一人に注がれる愛情のこもった眼差し。本のどのページを開いても愛が溢れ出してくる。後書きに、長年アシスタントとして一緒にやってきた女性に完成した原稿を読んでもらったところ、電車内で号泣してしまったという話が書かれていたけれど、そりゃ泣くでしょうね。こんな愛のいっぱい詰まったラブレターをもらったら…。
2投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年19冊目 Internetへの接続がPCから携帯、そしてスマホへ 環境が変化する中新しいサービスを立ち上げ 成功してきたDeNA その苦労は半端なく、決して不格好な経営ではない。 著者はマッキンゼーのコンサル出身で、経営アドバイスなどしてきた 立場であるが、コンサルの立場と経営の目線の違いなども面白い。 感想はブログにも書きました。 http://hironakaji.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/by-75de.html 面白い一冊でした。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ* ガラケーの終焉でソシャゲのピークを迎え終わり、社長退任し落ち着いた後に書いた本。いわゆる経営哲学とかはほとんどなく、どちらかというとスポ根マンガ読んでるみたいですぐ読めた。 * 創業期メンバーの内輪なノリを本にするのは、自分が退いた後に今後経営を担っていくメンバーの「人間味」を出してよかったのではないか。現社長が歯かけて記者会見でれなくなったとか、良いエピソード。 * ソフトバンクとか楽天とかサイバーとかもそうだけど、日本の企業って「プロダクトをつくりたい」というよりは「マネジメントをやりたい」っていう動機での起業が多いんだなと思った。オークションだろうがゲームだろうが儲かるならやる。年XX%成長が正義!みたいな。ある意味みんながハイになっていて、どんな事業をやろうが会社のために命かける、カルト的な空気を作り出している。これって日本特有のワーカホリックな文化だから成り立つのかな。プロダクトベースではなく、マネジメントベースの起業だからこその雰囲気なのかな。正しい間違ってるとかじゃなくて、単純に面白いなと思った。 * プロダクトベースだとピボットした時に人離れがちだったりするけど、マネジメントベースの場合はいくらピボットしても残る人は多いのかもしれない。それくらい圧倒的なリーダーとそこに集まる人の空気感さえできてしまえば協力なのかもしれない。
0投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ・意志決定については,緊急でない事案も含め「継続討議」にしない. ・不完全な情報に基づく迅速な意思決定が,充実した情報に基づくゆっくりした意思決定より数段勝る. ・自分が接している情報は断片的であるという自覚を失わない.直接見聞きしたことに大きく影響を受ける. ・事業リーダーにとって「正しい選択を選ぶ」ことは当然重要だが,それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ことが重要 ・採用にあたり心がけていることは全力で口説く,誠実に口説くの2点 ・人を育てるには.任せるに尽きる. ・優秀な人の共通点「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ起業記。元マッキンゼーのパートナー、ハーバードMBAの南場氏のコンサル時代から起業、成長、引退を経て復帰までの自伝。様々な失敗を経て今に至ることを赤裸々に、面白おかしく書き綴っている。高額を稼ぐ一流コンサルタントの能力と経営能力は異なると断じている所が腹に落ちる。がコンサル的能力を企業内に有していた方が有利な事はまた事実でDeNAにはロジカルシンキングが強そうなメンバーが揃ってそうである。この本が面白いと思ったところは、自分自身DeNAが提供するサービスに全く興味もないし意義を感じないが、この企業で働く事が魅力的に映ったこと。この二つは分けられるということか。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年はまだ4か月残っているけれど、おそらく今年NO.1だろう。面白さを共有したかったので、このコメントを書く前に、後輩に貸してしまった。 重要事項の決定時等、その局面局面で社長として考えていた生の声がつづられていて、臨場感が半端ない。30過ぎた自分には、緊張感が伝わってきたし、その時々の感情が染み入った。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ5/7読了 13冊目 南場智子の熱量と人柄が真っ直ぐ伝わってくる。心の底から周囲に感謝していないとこんな文章は書けない。 それに、心の底から周囲の人に感謝できる時は、自分が本当に全力で出し尽くした時だと、経験上思う。
0投稿日: 2018.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社経営は多くの経験と、ご縁を大事にしながら進んでいる分かる。 特に会社立ち上げ時期、葛藤や、家庭の事も考えながら、常に前進にしているところは、本当に大尊敬する。 女性としての芯の強さも書かれている。 起業をする方、女性の起業家の方へ、お勧めの本です。
0投稿日: 2018.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんの人柄が存分に伝わる。面白い。どのエピソードも面白くて、伝え方もユーモアに溢れていて、軽く読むつもりがかなり読み込んでしまった。 「正しい選択肢を選ぶ」ことと同等以上に重要なのが、「選んだ選択肢を正しくする」ということ。 こんなに失敗してきたんだ、ってびっくりするくらい七転八倒。 すごく背中押された。 南場さん、ほんとかっこいい。
0投稿日: 2018.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり胆力、行動力、ユーモアやな。面白い本でした。特に前半部分。終盤は若干読み流してしまったかな。
0投稿日: 2018.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ買ってもらえなかったときにどれだけいい笑顔が見せられるかが勝負 コンサルタント時代は、クライアント企業の弱点やできていないところばかりが目についてしまい、大事なことに気づけなかった。普通に物事が回る会社、普通にサービスや商品を提供し続けられる会社というのが、いかに普通でない努力をしていることか。 真の競合は「ユーザーの嗜好のうつろいのスピード」だと私は認識している。それより半歩先に適切に動かなければならないのだ。~中略~成功のモデルは壊される前に壊さなければならない。しかし企業は往々にして成功の復讐にあう。 何かをやらかした人たちに対する対応は、その会社の品性が如実に表れると感じる。~中略~お詫びをしなければならない事態になって、ますますファンになり、その会社のために頑張りたくなるようなパートナーに恵まれてきた。 コンサルタントは言う人、手伝う人、であり、事業リーダーはやる人だから、立場も求められる資質も極端に異なることは理解に難くないにもかかわらず、誤解がはびこっている 実際に事業をやる立場と同じ気持ちで提案しています、と言うコンサルタントがいたら、それは無知であり、おごりだ。優秀なコンサルタントは、間違った提案をしても死なない立場にいるからこそ価値のあるアドバイスができることを認識している。 検討に巻き込むメンバーは一定人数必要だが、決定したプランを実行チーム全員に話すときには、これしかない、いける、という信念を前面に出したほうがよい。 本当に重要な情報は、当事者になって初めて手に入る。~中略~事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。決めるときも、実行するときも、リーダーに最も求められるのは胆力ではないだろうか。 人を口説くのはノウハウやテクニックではない。「策」の要素を排除し、魂であたらなければならない。きれいごとを言うようで気恥ずかしいが、私が採用にあたって心がけていることは、全力で口説く、誠実に口説く、の2点に尽きる。 成長はあくまで結果である。給料をとりながらプロとして職場についた以上、自分の成長に意識を集中するのではなく、仕事と向き合ってほしい。それが社会人の責任だ。そして皮肉にも、自分の成長だへちまだなどと言う余裕がなくなるくらい必死になって仕事と相撲をとっている社員ほど、結果が出せる人材へと、驚くようなスピードで成長する すごい人たちを思い浮かべると、なんとなく「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」ということは共通している~中略~労を惜しまずコトにあたる、他人の助言には、オープンに耳を傾ける、しかし人におもねらずに、自分の仕事に対するオーナーシップと思考の独立性を自然に持ち合わせている 逃げずに壁に立ち向かう仕事ぶりを見せ合うなかで築いた人脈以外は、仕事では役に立たないと痛感している。誰もが自分のことで忙しいときに、自分の仕事の最短ルートから少し外れてでもほかの誰かのために何かをしようとするならば、それは、ひたむきな仕事ぶりに魅せられた相手に対してだけ ”選択”に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけ
0投稿日: 2018.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
南場さんの人となりが伝わってくる本。 大昔、DeNAの採用説明会に行ったことがあるが、その時と同様、すごくまっすぐで、事業に真摯に取り組まれてきたのだな、と思った。 女性活躍が騒がれる現在だが、政府の女性管理職○%という目標値のために、女性に下駄をはかせるのではなく、本当に実力を持ってやっていらっしゃる第一線の方というイメージが強く、今回この本を読んでみた。 やはり、中途半端な気持ちで事業をしていないし、どちらかというと旦那様が病にかかるまでは、すべての神経を会社に注いでいる。これくらいの気持ちがないと、起業は難しいだろうし、大企業に居ても自分の権利ばかり主張する人が増えてきていると感じるので、自分はそうならないようにしていきたいと思った。 最後、南場さんの言葉ではないが、本の中で一番心に残ったフレーズを。 「選択に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけ」
0投稿日: 2018.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高に面白い。一気読み。 ユーモラスでチャーミング。皆さんのキャラも立っている。 素晴らしいチーム。今後も応援しています。
0投稿日: 2018.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ・責任下で発生した事を他人のせいにしない ・時代の波を捉えタイミングにあったものを1番使いやすい形で出す ・成功のモデルは壊される前に壊す ・勝ちパターンにこだわりトレンドを見失うな ・リーダーは行動で引っ張れ ・誰よりも働く、教えるより見せる、上から目線ではなく自分をさらけ出して一緒に戦う ・成長はあくまでも結果。まずは仕事に集中して向き合えば勝手に成長する ・選択に正しいも誤りもない。選択を正しかったものにするための行動を取れるか
0投稿日: 2018.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA南波さんが書いた本。大学時代に読んで、おもしろかったなーって記憶があるけど内容あんまり思い出せないからそのうち読み直してもいいかな。
0投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「正しい選択をする」以上に「選択を正しくする」ことも重要という文脈が印象的でした。 これからの時代は考え検証し、実行に移すより、実行しながら考えるくらいのスピード感が大事だと思っていたところにストライクな言葉でした。
1投稿日: 2018.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場さんの自伝。 設立当初から現在に至るまでのDeNAの成長がわかり、風通しが良く成長意欲あふれる社員の方々の魅力が伝わってきました。
0投稿日: 2018.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ201711読了。ビジネス本。 購入するまで南場さんが女性だと知らず・・・! 女性だからこそ共感するところ、あこがれるところ、ありました。 ベンチャー企業の成長、起業家・社長としての心構え。血となり肉となることが多かったです。 身近な話題として、「女性として働くこと」が一番胸を打たれた。そうなのです。優遇されたいわけじゃない。ただ『平等』に扱ってほしい。つまりは女性が子どもを産む性であるということは考慮してこそ平等だと思う。産休とったら昇進に影響して、年金も満額はもらえなくて。それじゃあやっぱり不平等でしょう。それなら男も子ども産んでみろっていう。 だけど、割合を高めたいから昇進させるとか、そんなことはおかしいしされたくない。昇進はやっぱり実力です。ただそれは産休や育休に左右されるものではなく、仕事の能力であるべきだと思う。ので、明確に記してくれたことは嬉しかったし、勇気をもらいました。
0投稿日: 2018.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書全体を通して楽しく読ませてもらったが、特に7,8章が良かった。 その部分には際立って南場さんの信念が詰め込まれていたからだと思う。 私は本書を読むまで上下関係はハッキリして、けじめをつけるべきだと考えていた。しかし、南場さんはそういうのは苦手で、DeNAは社風、組織構造でもフラットになっている。だから、組織を球体と捉え、独立した人間として尊敬し合えるチームにしているそうである。 だからこそなのだろうか。南場さんが苦言を浴びるところが多く、私が知っている企業でこんなこと言ったらクビがとぶとヒヤヒヤしたシーンも平気であった。それを受け入れ、次へ繋げている。社長が媚だけしか受け入れず、イエスマン集団になったら会社は危うくなると思っている。それを防ぐために他企業もフラットにするからこそ、下からの意見も受け入れやすいし、言いやすいのかももしれない。 最も、イエスマンに囲まれることは居心地が良いと思うため、現状がそうなっているところを変えることは難しいが…。 自明のことなのかもしれないが、自分なりに経営者の方々本を数冊読ませてもらった結果、最も大切なものは人なのだと実感した。だからこそ、採用にはこだわり、資金をまわす。 周りの人の意見に耳を傾ける素直さとそれに抗う頑固さを持つ人が活躍する。 意思決定をする立場では、人に任せることができる人物こそふさわしい。 本書のメッセージを良い教訓にしたい。
0投稿日: 2018.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は現DeNA社の創業者南場智子さんが自身の操業経験を振り返って書かれた自叙伝です。 タイトルの通りうまくいった話よりも失敗談の方に重きを置かれて書かれている点が他の本とは少し異なるところかと思います。 個性豊かなメンバーとのエピソードが面白く、あっという間に読んでしまいました。特に乙部さんの話が印象に残っていて実際に会ってお話してみたいです。 何事にも大なり小なり壁はあるもの。私も失敗を恐れず行動していきたいと思います。
0投稿日: 2018.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場さんの考え方とこれまでの話し。 意思決定が仕事。意思決定のプロセスには最低限で、決定したプランをチーム全員に話す方がまとまりが出る。
0投稿日: 2017.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白い。以前の職場の上司に読んでおいた方が良いと言われていたの思い出して読み始めたが、本書を読んでその意味を理解できた。 ①事業家と戦略コンサルの違い:意思決定の差。実際に事業投資のプロジェクトにおいて、自分がGoかNoGoかの意思決定を行う立場に立つと、見えてくる景色は全く異なる。自身の経験からもわかるが、戦略だけで勝てるわけはなく、戦場でのその場その場の意思決定によって成否は変わってくる。少ない情報での意思決定、人の扱いなど、実践を通じて学ぶことは多い。DeNA・リクルートのような失敗をプラスに受け止める組織文化を持っている会社はどれだけあるのか。 ②組織の作り方:南場さんほどの人でも、経営哲学や何かしらの信念で組織戦略を考えていたのではなく、やりながら組織を作っていったのかと驚きを感じた。ただ、個人的にはDeNAの組織文化は、リクルートと戦コンの中間に位置付けようとしているように感じる。 ③人間力:本書を通じて感じたのは、南場さんの人間力。幹部陣・リーダー層の信頼関係は厚いのだろうと感じる。採用は非常に重要だと書かれているが、優秀な人材の求心力も社長の人間力に依拠しているのではないかと思う。めちゃめちゃ頭が良いけど、それと同時に人間好きなのだろう。こういう人物の側で働けるのは幸運な環境だと思う。 ④経営目標:DeNAの急成長の一つの要因にこれがあったのだろう。コンサルだと、不合理な経営目標には違和感を感じるが、この高い目標を掲げなければこれまでのような急成長はなかったように思う。ユニクロの柳井さんも同様のことを考えていた。目標の設定次第で、事業戦略の考え方が全く変わってくる。 多くの経営者の本はポジンショントークや結果論で書かれているものが多く、私もあまり好き好んで読まないが、本書はその時々の状況がリアルに描かれていて、他の本とは一線を画すように思う。
0投稿日: 2017.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログことに集中する 顧客第一 自分の感情と物の良し悪しを完全に分けて評価する respect appreciation 素直に、徹底的にやる
0投稿日: 2017.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログコンサルタント出身の南場さんなだけにスマートなイメージを持っていたDeNA。そのイメージが180度変わり戦う事業集団であるという認識を得た本。 今所属の会社もおおいに参考にしている部分もあると思われ、大変参考になりました。 事業を起こす立場はやっぱり楽しそう、
0投稿日: 2017.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
■要約 リーダーの仕事は、調整ではなく決めること 情報が揃っていることなんて少ない。その上で、決断する必要がある ただし、情報が欠落していることをきちんと意識したまま決断すること 決定したプランを実行チームに話すときは、これしかないという信念を前面に出す 正しい選択肢を選ぶ事は当然重要だが、それ以上に「選んだ選択肢を正しくする」ことが重要 なぜ育つか? = 任せるから育つ
0投稿日: 2017.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの南場智子さんの本。 実は私、あまりDeNAのことを良く思っていなかった。 これまでに私の知っていたキーワードと言えば 「コンプガチャ」と「キュレーションサイト」 それも、ちゃんと会見を見たわけではなく、 ニュースが流れているのを見ていただけだった。 謝罪で頭を下げている姿しか思い出せなかった。 日本は、失敗に寛容な国ではないと思っている。 謝っている人は、悪いことをした人だと感じてしまう。 なので、その著作を読もうと思うとは思わなかった。 ところが、尊敬する人が「南場さんが好き」という。 この本がバイブルだという。読みたくなった。 読んでみた感想。南場さんは素敵な方なのだな。 一度現役を退いたが、現在復帰されたのにも納得した。 良い人材がいない、いないという話ばかり聞く。 どうも、今の日本は人材を使い捨てか何かのように 扱うと感じていた。誰でもいいとか思っているような。 それでは、人材は育たない。 育てる余裕がない、というのが実情なのかもしれない。 でも、それだと、もう、先がどうなるのか見えてる。 現状維持は、衰退である。 規模の大小は違えど、私が尊敬するその人は 南場さんのマインドに影響を受けた仕事をしている。 従業員と一緒に、泣き笑いしながら成長できると思う。 さて、では私はどうなのだろうかと考える。 私はまだ、自分のやりたいことで頭がいっぱいだ。 やりたいことを、やればやるほど、その先にもっと やってみたいことが現れ、もっと遠くが見たくなる。 自分が良い人材になれるかどうかはまだ疑問符がつくが 「素直だけど頑固」なのは、それなりに自覚がある。 それなりの素質はあるかもしれないと思うことにする。 経営者になることは、今のところ考えていないけれど、 自分を育てておかないと、いざという時に飛べない。 泣き笑いしながら、成長していきたいと思う。
0投稿日: 2017.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
"DeNA南場さんの著作。 恥ずかしい事にDeNA社がどんな会社で何をしている会社なのかを いまいち判らない状態で本書を読んだが、面白かった。 物事を笑い話に転換できる人はすごい。 失敗を受け止め乗り越え、いわゆる今だからこそ言える話で語っている。 失敗だらけで格好悪いとの事だが、それが格好良く見える。 そんな南場さんの人柄があるからこそ、ピンチの時には周囲が助けてくれるのだろうなと。 また、一流コンサルから経営は畑が違いすぎて上手くいかないという話。 これは少し刺さった。世の戦略助言がいかに現場感がないのかという事なのだろうな。考えたい。 自分もまず目の前の出来事に集中しよう、 そして形を残していつかこんな話があったよと語れるようになりたいと感じました。月並みですが。"
0投稿日: 2017.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ時々こういう畑違いも畑違い門外漢も門外漢の経営者の本を読んだりする。何を読むのか。この本は南場さんの個人史、南場さんが創り出したDeNAの創成期から(その当時の)現在までを描いているので、その偉人伝⁈、近代史、裏話の面白さを読む。そしてやはり文章から伺い知るだけではあるけれど南場さんのパワフルな人間的魅力に浸る為に読めた。
0投稿日: 2017.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログそれほど不格好な描写は無いが、実業に対する姿勢として学ぶべき点が多い一冊。新規事業や経営に携わる人には共感できる部分が多いと思われる。
0投稿日: 2017.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログーーーーー山下2017/5/7ーーーーー 【概要】 DeNA創業の物語 【評価】 60点 【共有したい内容】 ・意思決定については、緊急でない事案も含め、「継続会議」にしないことが極めて重要だ。コンサルタントから経営者になり、一番苦労した点でもあった。継続討議はとてもあまくて らくちんな逃げ場である。もっと情報を集めて決めよう、とやってしまいたくなる。けれども仮に1週間後に情報が集まっても、結局また迷うのである。だから、「決定的な重要情報」が欠落していない場合は迷ってもその場で決める。「決定的な重要情報」が欠落しがちな起案者は優秀ではない。それを回避することにも気を使った。事案は決定の場で初めて経営トップに説明されるわけではなく、その前に「頭出し」として、報告を受けることが多い。そのときに、意思決定にはどのような情報がポイントとなるか、大まかにすりあわせることだ。 ・創業期から一貫して多大な時間んとエネルギーを費やしてきたのが、採用活動である。人材の質を最高レベルに保ためには、1 最高の人材を採用し、 2 その人材が育ち実力をつけ 3 実力のある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、 4 やめない という要素を満たす櫃ようがある。 ・全力でく口説く、というのは、事業への熱い思いや会社への誇り、それから、その人の力がどれだけ必要かを熱心にすとれーとに伝えるということにほかならない。そして、相手にとって人生の重大な選択となるこおとを忘れずに、正直に会社の問題や悩み、イケてないところなども話さなければならない。 【読んだ方がいい人】 コンサルから経営者になりたいと考えている人 【自由記述】 最後に少し経営哲学が載っていたが、それ以外は自伝という感じ。 コンサルから経営者になるとこんなに大変だよという話が載っているので、コンサルと起業で将来迷っている人にはおすすめ。
1投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔、クワガタの繁殖に熱中した時期があり、南場さんのビッダーズには大変お世話になっていました。ヤフオクより豊富なアイテムに。 急に社長退任されてからの去就への興味と、急成長中のDeNAの歴史を知りたく、手に取りました。 かなり率直に綴られているのと、著者の愛社精神を強く感じます。 雑誌PHPなどで、著者の記事は拝見していましたが、女性だからという意味ではないチャーミングな一面を持ち合わせた、素直で誠実な方なんだなと思いました。 著書は、コンサルタント退任からDeNA操業時のエピソード、自身の事が綴られているエッセイ的な内容になってます。 南場さんの組織論はかなり独特で、球体をイメージとしたネットワーク組織であり、全社員がフラットという位置づけです。今までの上下関係が特徴な階層組織ではなく、目的に応じてフォーメーションを形成・解散を繰り返しアメーバ的な組織。 再入社も受け入れ、社員をオトナ扱いし、常にイノベーションを生み出す仕掛けが満載ですね。 社長を退任したとはいえ、全社員に南場さんの経営理念がしっかり根付いているのだなと、感じ入りました。 羨ましくなる会社です。
0投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNAの歴史を見ることができる本。 マッキンゼーから期待エリート軍団が予想もしない事態を色々と解決していく、生々しいエピソードもあり。 印象に残ったのは仕事の極意、難波さんの考えを為になった。 ・不完全な情報決定が完全な情報がまとまった状態より、数段優れていることがある。本当に重要な情報は当事者となって入ってくる。スピード重視 選んだ選択肢を正しくする ・苦しい時を乗り越えた時人間はグッと成長する、リスクがある仕事を選ぶ ・いい人材の条件は「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」 労を惜しまずにことに当たる ・目の前の仕事をやりきってこそビジネスマン ・チーム全員が主役 ・チームの目標はわかりやすく、高揚する目標 ・思い切った権限移譲、信じる ・決定したプランを実行チームに話すときは、これしかない、いけるという信念を前面に出した方が良い 今後の仕事人生にもプラスになる良書
0投稿日: 2017.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃな人だ。経営者にはこういう人が多いのかもしれない。 この人を支えるコンプライアンスや法務の担当のチームがいなかったことが、今のDeNAの苦境を招いているのかもしれない。
0投稿日: 2017.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場智子さんの赤裸々な半生記? 人の名前はバンバン登場するし、エピソードは半端ないし、読み物として面白かった。 その上で、経営の大変さも伝えてる一冊。
0投稿日: 2017.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA草創期の頃の話しが鮮明にかかれている。 マッキンゼーのパートナーだった南場さんでもこんなミスをするのか!という部分やこの意思決定はさすがだなーと感銘する場面もありと経営者には勉強になる一冊だと思います。
0投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
南場さんは昔プロフェッショナルを見てなんとなく好きだったため、今回の報道を見て改めて著作を読んでみようと思った。 「まとめ」 南場さんの生い立ちから、マッキンゼー時代、DeNAの成長を実際の社員さんの名前も含めて書いてある。 南場さんの経営者としてのあり方は ・トップが一番熱く。 ・人は育成するのではなく仕事が成長させる。 ・重要な意思決定を早く、明確に伝える。 の3点に象徴されるのではないか。 「感想」 プロフェッショナルで見た南場さん(放送2006年とかだったかな?この本は2013年)と”変わらない部分”と”大きく変わった部分”が対照的だった。変わらない部分はアツさと成長意欲。トップが一番賢くある必要はなくいろんな対応から純粋に学びを得つつ、組織全体のアツさは南場さんのキャラに起因するものだと感じた。 一方、変わったのは仕事観というか人生観。結婚しても仕事一本な部分は好きじゃなかったが(失礼)、夫の病気とともに足元を見て自分の人勢を見直す姿勢は印象を変えた。 「学び」 マネージャーの仕事(広義の教育者の仕事)は、”明確なビジョンと適切なガバナンスの上で、自由な挑戦の機会を与えること”であると再認識するきっかけになった。もちろん、これを考えたのは今回の報道。任せることは大切だが大枠としての社会的責任は守らないといけない(だめなことはダメだと確認しないといけない)。今回の報道を糧に、DeNAがただ自由なだけではなく社会にどんな価値を与えるのかという点を明確にし、邁進する強い企業に生まれ変わることを願っている。
0投稿日: 2016.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ今では大きくなったDeNAの成功・挫折が詰まった本。 南場社長のフランクな人柄、フラットで正直かつ何事にも本気で一直線な性格が良く表れている。 こんな暑苦しくて賢くてバカ正直で素直で平等な経営者といつか一緒に働いてみたいと強く思わせる本だった。 やはり会社は、「何をやるか」より「誰とやるか」で決めたいと強く思った。
0投稿日: 2016.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダーにとって「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが 重要になる。 「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」 労を惜しまずにコトにあたる、他人の助言にはオープンに耳を傾ける、しかし人におもねらずに自分の仕事に対するオーナーシップと思考の独立性を自然に持ち合わせる、ということではないかと思う。
0投稿日: 2016.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ南波さんと最初にあったのは、大学に入ってすぐの時で、なんのイベントか忘れてしまったのですが、その時に南場さんが、僕を含めた60人ぐらいの学生に向けて 「今の日本が好きなレベルを5段階で表したら私は1です」 と、堂々と話していて、会場を驚かせていたのを思い出しました。君たちはこれから先、こんな沈み行く船に乗らないで、世界から必要とされる人材になりなさいと。 この時点で僕は当時、かなり心を掴まれたのですが、その後の放った「これからは変態と呼ばれる人が重要な人材になる」と言った言葉が頭の片隅に残っていて、変態というのは、この本で出てくる多くの南場さんを支えた方なんだなと読みながら納得しました。 スーツを来た人間よりも、最後はヨレヨレなジャージを来た人間が救う。 なんて事は世の中にそうそうはないと思いますけど、南場さんの周りには変態を呼びつかせる磁場でも働いているんでしょうか?(笑) いずれにせよ、経営者としても、ひとりの女性としても、大変素晴らしい人間だなと思いました。
0投稿日: 2016.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ記述されている様々な状況を見ると、ピンチの連続でよく事業が存続できたな、と思える。 本人が優秀な人で人材に恵まれたからベンチャーでも生き残れたのかな? 特殊すぎて一般的に応用できるノウハウはないが、特殊例として知っておくのには損はないと思う。
0投稿日: 2016.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ・意思決定については、緊急でない事案も含め、「継続討議」にしないということが極めて重要だ。コンサルタントから経営者になり、一番苦労した点でもあった。継続討議はとてもらくちんな逃げ場である。決定には勇気がいり、迷うことも多い。もっと情報を集めて決めよう、とやってしまいたくなる。けれども仮に1週間後に情報が集まっても、結局また迷うのである。そして、待ち構えていた現場がまた動けなくなり、ほかのさまざまな作業に影響を及ぼしてしまう。こうしたことが、動きの速いこの業界では致命傷になることも多い。だから、「決定的な重要情報」が欠落していない場合は、迷ってもその場で決める。 ・事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。決めるときも、実行するときも、リーダーに最も求められるのは胆力ではないだろうか。 ・人は人によって育てられるのではなく、仕事で育つ。しかも成功体験でジャンプする。それも簡単な成功ではなく、失敗を重ね、のたうちまわって七転八倒したあげくの成功なら大きなジャンプとなる。
0投稿日: 2016.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白くて引き込まれます。途中、読んでいて目頭が熱くなり、泣きそうになってしまう場面も。 元マッキンゼーの共同経営者というエリートの南場さんが、あるきっかけから、自分で事業をやってみたいという想いを持ち、DeNAをゼロから立ち上げて、大きくしていく過程を赤裸々に綴った本。 それぞれの過程で、活躍する登場人物にフォーカスして語っており、その描き方から、南場さんの人に対する大きくて温かい想いを感じて、親近感がわいてしまう。 経営者としての考え方、人の巻き込み方、会社の目標設定の仕方、など非常に参考になる部分が多く、将来経営者や事業を引っ張るリーダーになりたい人・人事系の人にオススメの一冊です。
0投稿日: 2016.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ肝っ玉母さんの印象が強い南場さんの著書。 色々施策を打ち、順調に拡大しているように見えるが、 やはり裏ではたくさんの苦労をされているんだと思った。 色んな起業家がいるとは思うけど、 やっぱり失敗したとしても起業する気力があるだけ、 本当にすごいなと思う。 自分でやってみるということが、 大変だけど非常に楽しいことなんだなと正直感じた。 【勉強になったこと】 ・何でもいいから一つの職業で通用する人材になることが 今後の自信にも繋がる。 向いてないと思ってもすぐに辞めるのではなく、 まずはその業界で極めてみることが大切。 ・優秀な人材かつ色んな個性を持った仲間を増やしたい、 これが起業当初の採用の基準。 ・隙間を拾ってくれるメンバーは非常に強力。 自分のことで手一杯でも拾える人材が重要。 ・色んな仕事を協力しながらやっていくのが基本だが、 重要事項の決定だけは社長が死守すべき仕事 ・今決定しないとまずいということが肌感覚で感じ取れ、 かつ即座に対応することが出来るのが優秀な起業家 ・優秀な人材を採ることも重要だが、 離れていかないようにすることも重要。 優秀な人ほど次のステップを常に考えていて、 そのスピードと組織にズレが生じたときに辞めてしまう。 ・正しい選択肢を選ぶことは当然だが、 選んだ選択肢を正しくするという姿勢も大事 ・会社には色んな特徴を持った人材がいないとうまくいかない。 偏りすぎはダメ。 ・優秀な人の共通点は、 「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」
2投稿日: 2016.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの奮闘記 起業して訪れる様々な困難に立ち向かう姿が、イメージできた。 起業家奮闘記のようなもので入り込めず終わることも多いが、今回は熱中して読んだ。 今後、手元に置いて定期的に読みたい
0投稿日: 2016.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ・創業期を知らない社員たちに歴史を知ってほしい ・イメージギャップのある社外に我が社を知ってほしい ・今まで支えてくれた人に謝意を伝えたい ・自分たちの失敗と立ち直りを悩める人に役立ててほしい こんな感じの意図で作られた本なので、所々内輪ネタにしかならない部分もあったり、だいぶダイジェスト&美化バイアスかかった感じはする。タイトルほど不格好な感じはせず、というかこれくらいできるはず、の初期認識が高すぎたんじゃないかという気も。(あとブログもあったけどこちらは死んでるらしい。) それでもピカピカの人材とがむしゃらに挑戦して、No.1になりたい、世のユーザーを驚かせたい、とはっきり言える野心は並みじゃないというか、父君の「生き甲斐は処した困難の大きさに比例する」を体現してる所かなあと思う。 とびきり優秀orアグレッシブじゃないと縁がなさそうな会社だけど、社長のお祭りみたいな精鋭!パワーは爪の垢でも煎じてみたくなる力強さだった。
0投稿日: 2016.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNA創業者の南場さんが明かす創業ヒストリー。マッキンゼーで数々の経験を積んではいたものの、実行するとなるとその困難は壮大なものだった。 読んでる自分が熱病にかかるようなそんな一冊。いつまでも青春を感じられるような熱いエピソードや生き生きとした言葉たちが詰められてます。
0投稿日: 2016.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場智子さんの会社、知る事が出来ました。 興味有る会社でした。 又、読む事が出来きました。 (2025年3/8)
0投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログエリート集団で起業したDeNAでもいかに最初は苦難の連続だったかが綴られている。 ビッターズ→モバオク→モバゲーの流れは非常に美しく、コネクティングドッツをうまく体現できていると感じた コンサル出身である代表の南場さんが、「するべき」と提案することと実際に「します」ということに違いにこれでもかというほど苦しめられた コンサルは情報を時間をかけて調べるが、実際の経営では不完全な情報でも迅速な意思決定をしていくことのほうがよっぽど重要である
0投稿日: 2016.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ今流行の「スタートアップ」という言葉のイメージからはだいぶ離れた、チームDeNAの様子が垣間見れて面白い。横浜DeNAベイスターズもこのような人たちが経営していると思うと、ますます興味が惹かれる。
0投稿日: 2016.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・7年前、DeNAに就職することが決まったことを告げた時も、彼らは同じように言っていました。 「お前、大丈夫か?」「将来をちゃんと考えているか?」と。 〝選択〟に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけだと信じています。 ・DeNAが逸材を引っ張り込むのを見て、どうやって口説くのかと訊かれることが多い。が、人を口説くのはノウハウやテクニックではない。「策」の要素を排除し、魂であたらなければならない。きれいごとを言うようで気恥ずかしいが、私が採用にあたって心がけていることは、全力で口説く、誠実に口説く、の2点に尽きる。 ・事実、マッキンゼーのエース(自称)3人が1年で黒字化させますと宣言して会社をつくり、実際は4年も赤字を垂れ流したわけだ。コンサルタントの言うことは信用しないほうがいい。というのが本題ではなく、会社には、戦略立案が得意な人、サイトデザインができる人、システムがつくれる人、お客さんがとれる人、お金を守る人、チンピラを追い払える人、安価で斬新なマーケティングが組める人など、いろいろな役者が必要なのである。 ・事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。決めるときも、実行するときも、リーダーに最も求められるのは胆力ではないだろうか。 ・嬉しくて泣けたのは起業してから社長退任までの12年間でたった1回、このときだけだ。赤字の経営はきつい。利益は世の中にどれだけの価値を生み出したかの通信簿であり、赤字は資源を食い潰している状態だ。 ああこれでやっと世の中のすねかじりから卒業できた、存在が許される経営者になれた。そんなふうに感じた。
0投稿日: 2016.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の経営者の著作と異なり、南場智子氏によってユーモア溢れるタッチで描かれた、日記のような、社史のような、エッセイのような作品です。 しかし、本作のコアな部分は、他の経営者(例 稲盛和夫氏や小倉昌男氏)と同様の凄みを感じさせます。 マッキンゼーでの実績や、ハーバード留学経験を持つ著者だからこそ、それらと経営者としての実務との違いを浮き彫りにさせています。 只、そのような固い話だけでなく、減量競争や失敗談、家族とのことも包み隠さず綴っているところに同氏の性格か表れていると言えるでしょう。 同氏のインタビュー記事でも載っていましたが、「ヒト」よりも「コト」に臨む意識を大切にする考え方は、私たちの仕事への取り組み方に対して振り返りを求めます。 上司に評価されようと考えるのではなく、与えられた仕事に集中することの大切さを説いており、頷くところが多いです。 会社を利用してスキルアップを示唆するビジネス本もある中、仕事に熱中する、会社を発展させるべく努力することの素晴らしさを感じさせる一冊です。
0投稿日: 2016.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログチームDeNAは、なにもそこまでフルコースで全部やらかさなくても、と思うような失敗の連続を、ひとつひとつ血や肉としてDeNAの強さに結びつけていった。とてもまっすぐで、一生懸命で、馬力と学習能力に富む素人集団だった。創業者が初めて明かす、奮闘の舞台裏。 p23 調整ではなく決めるのが仕事。最後は自分の腹に聞くことを教わった気がする。コンサルタントではなく、事業家なんだ。 p25 睡眠時間は30分で往復の2回のみ。 p32 パニックは人間の能力を極端に下げることを身をもって知る。社長へのプレゼで寝坊 p62 賢い振りがうまい私は、就職活動で落とされたことがない。 p91 なんの寄る辺もなく起業する者は、有名な大企業のサポートをとても心強く感じてしまいがちだが、他社から大きな割合の資本を導入することは慎重に考えよ。ソネット、リクルート。 p93 利益は世の中にどれだけの価値を生み出したかの通信簿。赤字は資源を食いつぶしてる状態。 p197 目を三角にして怒るな 孫さんの鞄持ちをしたい。同じ24時間、何に時間をかけているのか知りたい。 社長の一番大事な時間は意思決定。 p199 自分が接している情報が断片的であるという自覚を失わないこと。 p202 物事を提案する立場から決める立場への転換に苦労した。勇気がいる。 p204 迷いのないチームは迷いのあるチームよりも突破力がはるかに高い。 p205 事業リーダーにとって、「正しい選択肢を選ぶ」と同等以上に、「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要 →自分は、自分の人生という事業のリーダーや!! p206 財務→キャッシュフロー管理の重要性や利益(財務の健全性)を尊ぶ コンサルタント→利益より戦略の完成度を尊ぶ p208 ・何でも3点にまとめようと頑張らない。物事が3つにまとまる必然性はない ・重要情報はアタッシュケースではなくアタマに突っ込む ・自明なことは図にしない ・人の評価を語りながら酒を飲まない ・ミーティングに遅刻しない p216 ・素直だけど頑固 ・頑固だけど素直 p220 ・仕事ぶり、仕事に向かう姿勢こそが人脈を引き寄せる。 南場さんについていきます、と言われたら、全力で断る。 ・誰が言ったかではなく、何を言ったかに意識を集中。 p223 ロールモデルはいない。師匠はいっぱいいる。全ての経営者が尊敬できる面を持っている。 p229 選択に正しいも誤りもなく、選択を正しかったものにする行動があるかどうかだけだ!! p233 女性というだけで、話を聞いてもらえるところまでの、土俵に上がりやすかった。 p240 自然に生意気な態度が気に入った。 p248 なぜ、なぜ、と議論するのは他者に任せ、ピカピカの成功事例を自らの手で作ることに邁進する。 p251 何事も理詰めで考え、無駄を省いて生きてきた私が、ちょっとした寄り道や揺らぎが愛おしく思えてきた。
0投稿日: 2016.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ正しい選択をするだけではダメで、選択を正しくするのも経営者の役目なんだというのは刺さった。 とても小さかったDeNAが、今ではあの任天堂と組んで、あのスクエニと肩を並べて市場を泳ぎ続けている姿を思うと、南場さんや、共に戦い抜いたチームの人たちの力強さを感じる。すごいなあ、かっこいい。
0投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログベイスターズファンは「DeNA」でなくて「横浜」のファンだと思っている人が多い。横浜スタジアムでは、応援歌で「DeNAベイスターズ」って歌うところで「横浜ベイスターズ」っていまだに歌ってるし。「前の某TV局よりまし」「なんか胡散臭い」「企画は一生懸命だけども」みたいな微妙な感情をもっている。ならば、キャンプインの今日、創業者の南場智子さんの著書を読んでみた。思ったよりも、苦労人。なんか人間臭い。結構、ウチのチームカラーにあってるかも・・・九転十起の明治の女性実業家広岡朝子を思い出した。
1投稿日: 2016.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に本人の日記のような文体。気取ったビジネス書という内容ではなく、とても面白かった。仕事に対する熱意と、ハッとするような言葉もいくつかあった。
0投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスが継続していくことがどんなに大変か?そして人材がどれほど重要で、結束が大事か。 社風と言ってしまえばそれまでだが、会社という組織が継続して運営していくには、どれだけの人がどれだけ苦労しているのか。 ネット業界の経営とは何ぞやということを包み隠さずこの本では裏の部分を公開している。
0投稿日: 2016.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAという会社の挑戦を創業者の南場さん目線で見ていく。 南場さんという人、驚くほど素直で自分で成し遂げたいという責任感が強い。 そんな人だからこそ、メンバーに恵まれDeNAが紆余曲折ありながらも軌道にのっていったんだと思う。 南場さんがどんな考え方をしているのか、どんな歩みをしてきたのかが垣間見られる一冊。 モバゲーのブーム、DeNAベイスターズの盛り上がり、新規事業への取り組み、時代を先取らなければどれもなし得ないこと。 真の競合は「ユーザーの嗜好のうつろいのスピード」で、それより半歩先に適切に動かなければならないのだ、というところはこれからの世の中、万事共通なんだろう。
0投稿日: 2016.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA立ち上げの奮闘ばなし。 ベンチャー企業のスタートアップってこういうものかと、感じながら読んだ。起業の予定がある人はもちろん、ない人でも楽しめる。
0投稿日: 2016.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログDenaを創業した南場さんも普通の人間なんだなあ。 と思えるところがたくさんあってすごく親近感が湧いたし、女性としてすごく尊敬できると思った! なぜか、私も頑張れそうだって自分を鼓舞してくれる本だと思う。
0投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ二回お会いして話したが、二回ともパワフルな生命力に圧倒。 チームに貢献できたかを苦慮するよりも、チームに何ができるかを考え行動し続けること。目的をヒトではなくコトに置く重要性を学んだ。 人の評価を気にしないためには、上記も然ることながら、徹底的にバカになるか、徹底的に自信を持つかの二極で半端はない。 日本では人に迷惑をかけず、自分でできることは自分でする文化だが、人の助けを借りて、少しでも前に進むのが人間としてあるべき姿ではないのか。 respectとappreciationを忘れず、勝ち続けることは完全に両立可能。 南場さんや守安さんはお会いしたことがあるから、文字以上に伝わるものがあった。 ほんとに考え方が清々しく、素晴らしい人だと思う。
0投稿日: 2016.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場さんがいかに組織をまとめ、成長させてきたかの様子がわかりました。 IT系で様々な人種がいる中で脱落者を出さず、組織を束ねてきたのはさすがです
0投稿日: 2015.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に薦められて読んだ。南場さんをはじめとするDeNAの方々はやっぱり賢いのだと思うけど、それだけでやっていけるほど経営は甘くないのだなぁと思う。行動を起こすタイミングが大切なこと、その好機を逃さないための敏捷さ、行動力に驚き。経営にもテクニックなどがあるのだとは思うけど、結局核になっているのは会社を成長させようという情熱や熱意、人との信頼関係などという汗臭いものなのだと感じた。また、経営術だけでなく、どういう人間が会社に求められているのかを知れたのも、この本の良いところ。
2投稿日: 2015.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログDNeAの南場さんの本。 普通経営者の本はとても綺麗にかかれておりかっこいいものだが、この本は違う。 とても泥臭い失敗も含めて面白おかしくかかれていて一気に引き込まれた。 「人の向うのではなく、ことに向かう」という言葉はとても深い。
4投稿日: 2015.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ自伝的な内容だが、ユニークに書かれていて面白く読めた。マッキンゼー出身とは言え、集まった社員は個性的な人物が多く、だからこそこのようなまとめる人が居ることで会社が大きく成長できたと感じた。特にコンサルティングと経営者の視点の違いが興味深い。
1投稿日: 2015.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ社長の仕事 意思決定。決定的な重要情報が欠落していない場合は、迷ってもその場で決める。もっと情報を集めて一週間後に結局また迷うだけ。決定的な重要情報が欠落しないように、どのような情報がポイントか大まかにすり合わせしておくこと。案件の決定を委ねる場合は、期限をつけて明示し、結果には口を挟まない。 外部との折衝、関係づくり、情報収集。社内の状況も把握するため、社員と直接接点を持つ。ただし、その情報は断片的であると自覚を失わないこと。 採用活動。競争力の源泉は人材の質。最高の人材を採用し、その人材が育ち、実力ある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、だから、辞めないというような
1投稿日: 2015.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
起業家の本というのは単なる成功体験だけを自慢するものが多いが、この本は成功がいかに苦しいことかを教えてくれる。そして、コンサルタントの薄っぺらさをここまで痛快に書いてくれた本を読んだことがない。「選択に正しいも間違いもない。選択したことを成功するようにするだけ。」名言だ。
0投稿日: 2015.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAがうまくいくまでの紆余曲折が非常にわかり面白かった。マッキンゼー、IBM、オラクルなどの優秀な方々がいたからこそできた事だとも正直思った。ただ、その優秀さがあっても、簡単にうまくいくわけではないという事はわかった。PDCAサイクル、スピード感、やり切る感は半端じゃない。
1投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNA 創業から現在までのヒストリーを、南場さんの目線から語ってくれます。 とても面白かった。 仕事の勉強になるところもチョコチョコはあったけれど、この本の醍醐味は、なんといっても魅力的な社員。 南場さんの社員への愛や尊敬の念がよーく伝わってくる。 熱い想いで各エピソードを語ってくれていて、彼女と仲間達が全力で仕事に取り組み、挑んできたことがよくわかった。仕事がんばろう、と思える本!
1投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログベンチャー企業として立ち上がったDeNAの女性創業者・南場智子氏が、3人で創業してから夫の看病のために社長を退くまでの出来事を、自社社員の中から印象深いキーパーソンと自身の経営者ぶりから振り返った本。
0投稿日: 2015.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとしたジャイアン,しずかちゃん的要素はない。マッキンゼー→DeNA起業→成功(失敗や危機はたくさん)を成し遂げた人なんだから思考がマッチョなのはステレオタイプに一致する。 話し好きなアニキが思い出話をしているような感じ。
0投稿日: 2015.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく良い本だった。何よりも仮に間違いな選択をしてもそれが正解だったように行動する、この言い回しがすごく好き。 パワフルで、でも時に慎重な南場さんの人柄も素敵だ。
1投稿日: 2015.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAの立ち上げから現在まで、初代社長の南場智子の手で書かれたエッセイ。 業界のスピードに食らいつき、全力を尽くし切る社風は、自分の会社のぬるさを実感させられた。 目標を高く、それぞれが自分の仕事に自信を持ち、自分が正しいと思うことをやり切る力、正しい選択をしたかどうかではなく、自分の選択を正しくさせる根性。それが、DeNAの社風だと感じた。
1投稿日: 2015.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「正しい選択肢を選ぶ」ことは当然重要だが、それと同等以上に「選んだ選択肢を正しくする」ということが重要となる。 一番刺さった言葉。自分の中になかった考え方。 ところどころジョークを織り交ぜているためか、とても読みやすい。 南場さんのおちゃめで人間愛に溢れた人柄も伝わってきてよい。
1投稿日: 2015.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DeNAを立ち上げた女性。ここまでになるための困難を、どう乗り切ってきたか。働いている同僚・会社がどういう心で働いているか、が書かれています。 こういう考え方のトップがいるのは羨ましい・・・。
0投稿日: 2015.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。資金や人は比較的恵まれているように見えても、これだけ苦労するのだなぁ。泥臭さは渋谷ではたらくの勝ち。
1投稿日: 2015.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大きな宇宙の営みの中で少しの時間だけ存在することが許されている、はかない生き物の私たちだからこそ、一緒にいられる喜びや、人の気持ちの温かさ、皆が元気に何か一生懸命になっていることなどが、とても尊く感じられるのだ ①最高の人材を採用し②その人材が育ち、実力をつけ、③実力のある人材が埋もれずにステージに乗って輝き、④だからやめない 人は人によって育てられるのではなく、仕事で育つ
0投稿日: 2015.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい本。その人が「チャーミングであるかどうか」がどこまで伸びるかを決める、という一節が印象的だが、「すべて自分で書いた」という文面からは、南場氏自身がもっともチャーミングな人物なのだと伝わってくる。
0投稿日: 2015.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ失敗を繰り返しながら成長していくベンチャー創業ストーリーとしても面白いが、何より軽妙でユーモアに溢れ無駄がない文章の素晴らしさ。ロジカルとヒューマニティが両立する著者の人柄が文才として現れている。
1投稿日: 2015.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は面白く、楽しく読ませて頂いた。 ビジネス書に分類できるかどうかは別として、 この手の本は、読みやすいと思う。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ金ぴかの経歴を持つ著者の成功物語と思い、あまり気が進まなかったが、読みながら、笑いや涙を誘うほど、面白い。 タイトル通り、チームDeNAの良さが伝わってくる。 こんな職場なら楽しいだろうな、と思ってしまう。 毛嫌いせず、一度、読んでみてよい本。
1投稿日: 2015.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログDeNAという会社について、というよりは南場智子物語として優秀な人でも起業には困難がつきまとうということを示した本。 社員向けに書かれたのではと思うくらい、社員への愛が感じられる。
0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ横浜DeNAベイスターズの親会社に興味があったので読んでみた。 面白い人材が作っているエネルギーあふれる会社だと思った。 DeNAがベイスターズのオーナーになってから野球観戦が飛躍的に楽しくなった。 これからも新しいアイディアをたくさん見せてほしい。
0投稿日: 2014.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ痛快かつ平易な言葉で書いてあるのでとても読みやすい。でもコンサルタントから事業家への転身など参考になる話は多い
0投稿日: 2014.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログアプリ作って起業したいな~と、ぼんやり考え、以前立ち読みした本書を改めて精読。リクルートとソネットに出資してもらって起業...レベルが違う。人をヘッドハンティングしたり、社長の人脈大事なのね。あとタイミングも。南場さんはとても謙虚で色々な人を尊敬し、お客さんの姿を真摯に見つめ、学んでる。こんな仕事したいわ!!と大満足で読了しました。
0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ父親に薦められ読んでみた。もちろん本作は以前からしっていたが、ベンチャー特有の成功論、どこか宗教じみた啓蒙論ばかりが語られているのではないか、と食わず嫌いであったが、実際に読んでみると爽快であった。著者の語り口やユーモア、所々にでてくる悲壮感は成功したビジネスマンのそれとは思えないほど軽快であった。また、ビジネススクールやコンサルという職業を経験して得たことをとても冷静に分析していると感じた。前者においては、国籍や性別が違えどみなが同程度の学力、理解力があるからこそなりたつシステムであるということが実際のビジネスとは大きく異なると指摘。後者はコンサル特有のエリート意識、あくまでも他人目線であり、事業を生み出すことがないという点が経営者になる上では邪魔になったと著者は言う。これは以前よんだ『申し訳ない、御社を潰したのは私です』よりも深くコンサルのマイナス面をつついていると感じた。
1投稿日: 2014.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ南場智子のブログも大好きだったが、この本は南場イズムに溢れていた。 マッキンゼーのパートナーまで務めた人でも、事業を起こすのはこんなに大変なことなのか。 そして、チャーミングであり、愛に溢れた人なのだと思う。こんな人と一緒に働きたい!
0投稿日: 2014.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ生々しい文章がとても好感が持てた。 「コンサルタントと実際の経営の現場は違う。」という話を体験を交えて書かれているところがとても刺さったかも。読んでよかった。
0投稿日: 2014.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログかっこいいなあ、南場智子。 大学行くのも、留学するのも、大前研一に喧嘩売るのも、起業するのも、社長を辞めるのも。 自分のやりたいように。
0投稿日: 2014.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ【不格好経営】 DeNA創業者の南場智子さんの著書。創業期からの山あり谷ありの経営を余すことなく綴っている。創業時から優秀な人材の確保に力を注ぎ、現在でも採用には南場さん自ら赴く。本書でも個人名でエピソードを描き、南場さん自身が本書を通じて感謝の気持ちを述べたいということが伝わる。本書を読んだ若い人はDeNAで働きたい!と強く感じることだろう。 そういった創業期のストーリーも面白かったが、勉強になるのは南場さんの経営者としての考え方だ。失敗を繰り返しながら学んでいく姿は、決して賢い人が経営者にふさわしい訳ではないことを気づかせてくれる。厳しい状況でも、逃げずに仲間と話し、前に進めることがどれだけ大切か、考えさせられた。
0投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでて泣きそうだった… こんな仕事できたらいいなぁ、といううらやましく思う気持ちと、今自分は何をやってるんだ、という自責の気持ちが半々。
0投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ創業されて間もないころ、南場さんとは何度かお会いし、食事も一緒にさせていただいたことがありました。 その後の成長、更には一線からの引退。時代を思い出して懐かしく読ませてもらいました。
0投稿日: 2014.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な局面での南場さんや設立メンバーの考え方、捉え方を知ることができる本でした。 また、苦しい辛いと思われる事も後々に貴重な体験だったと言えることが素晴らしいなと感じました。
0投稿日: 2014.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆3(付箋11枚/P264→割合4.17%) 面白かった。DeNAのことはそれ程多く書かれていなくて、本当に“チームDeNA”を書いている印象。 成功の方法は同じようにやってもうまくいくとは限らないから、失敗したことをきちんとたっぷり書いたそう。 元、マッキンゼーのコンサルなのでとっても厳しいお父さんの次に怖いと思ったのが、大前研一さんだそうです(^^ ただ、起業したい人がコンサルやるのは、タイガー・ウッズになりたい人がレッスンプロを目指すくらいトンチンカンだそうで、うん、そうかも知れない。 南場さんの人格というか、成長も素敵。 旦那さんが癌になって、生まれて初めて家族モードに切り替わって。 “病はこれまで経験したことのない苦しみや悲しみを突きつけた。 けれども、いくつかの大事な拾い物をした気がする。 私は人に喜びを伝えるのは下手なほうではないが、「今年も家族で桜が見られてよかった」という喜びは、なかなか伝えるのが難しい。 同じ桜なのに、こんな気持ちで見ることができ、また、だからこそ開花が待ち遠しくわくわくできることは、私の人生に新しい彩りを添えた。蝉の声もそう。満月も。自然には、人間や企業のすったもんだに惑わされず、きっちり刻むリズムがある。” 文章も読みやすくて、お勧めです(^^ ***抜き書きは以下** ・信國さん(当時リクルートのウェブサービスリーダー)はじっくり時間をかけて吟味した後、3つの指摘をした。 1、インターネットサービスをつくったことがないのに、よくここまでできたね、の褒め言葉。まあこれは次の2点が耳に入りやすくするための枕詞のようなもの。 2、ユーザーの理解度を高く評価しすぎている。つまり複雑すぎる。 3、ユーザーから見た場面のみを考えられていて、バックエンドがない。オークションに不適切なものが出品されたらどうやって削除するのか、クレームメールが来たときにどうやって対応するのか、そういった裏側の設計が表側と同等に重要だが、そこの設計が抜け落ちている。 ・パニック状態、というのは人生2回目だった。 マッキンゼーの1年目。朝9時からクライアントの社長へのプレゼンだというのに、9時半に秘書の電話で飛び起きたことがある。資料は朝4時までかかってひとりで製本したため、全部私が持っていた。一刻でも早く資料だけでも届けるべきところ、パニックした私はあろうことか母に電話し、「第四銀行、第四銀行、新潟に帰って第四銀行に転職するってお父さんに言ってください」と(特に第四銀行さんにとって)意味不明なことを繰り返し、あっ、と我に返ってマンションを飛び出した。 このときの経験で、パニックは人間の能力を極端に下げることを身をもって知ったが、今回のパニックはそれをはるかに超えていた。 ・わが社は声の大きいユーザーに左右されないように、サービス改良の指針としてリピート率や離脱率などの数字を最も重視することを徹底しているが、インターネットサービスの黎明期、ノウハウが確立していないこの時代に、ユーザーと徹底的に対話することでサービス業の本質を手探りでつかんでいったことは、その後のDeNAの姿勢の基礎となった気がする。 ・社長という立場は一瞬にしてものをつくり出すことはできないが、一瞬にして破壊することはできるので、気をつけなければならない。管理部門を中心に1年がかりで積み上げた地道な作業を私が台無しにしてしまわないように気を引き締めた。 ・当社が身を置く業界はとても競争が激しいために、マスコミからもよく競合に対する意識を尋ねられる。けれども、真の競合は「ユーザーの嗜好のうつろいのスピード」だと私は認識している。それより半歩先に適切に動かなければならないのだ。このときは遅れ、そして方向を誤った。 現状のアバターが飽きられたなら、新しいアバターを導入しよう。2次元が飽きられたなら3次元だ。動かないアバターの次は動くアバターだ、と新しいアバターの開発を急いだのだ。 成功のモデルは壊される前に壊さなければならない。しかし企業は往々にして成功の復讐にある。我々は、アバターという勝ちパターンにこだわり、新しいトレンドを見失っていた。 ・病はこれまで経験したことのない苦しみや悲しみを突きつけた。けれども、いくつかの大事な拾い物をした気がする。私は人に喜びを伝えるのは下手なほうではないが、「今年も家族で桜が見られてよかった」という喜びは、なかなか伝えるのが難しい。同じ桜なのに、こんな気持ちで見ることができ、また、だからこそ開花が待ち遠しくわくわくできることは、私の人生に新しい彩りを添えた。蝉の声もそう。満月も。自然には、人間や企業のすったもんだに惑わされず、きっちり刻むリズムがある。 ・こう言うと、経営コンサルタントという職業を評価していないと受け取られることがあるが、そうではない。経営コンサルタントは経営者に助言するプロフェッショナルであり、高度な研鑽が必要な、とても奥深い職業だ。コンサルタントになるなら、その道の一流のプロとなるよう、努力し、とことん極めてほしい。また、コンサルティングを「虚業」と言う人がいるが、価値を認め対価を払って利用する企業が存在する以上、実需を伴う実業である。私が言っているのは、事業リーダーになりたいからまずコンサルタントになって勉強する、というのがトンチンカンだということにすぎない。ゴルフでタイガー・ウッズのようなトーナメントプロになりたいから、まずはレッスンプロになろう、というのと同じくらいトンチンカンだ。 ・よく学生から、優秀な人の特徴や、性格上の共通点は何かと問われる。そんなことを訊いてどうするのだろうかとも思うが、実際、この質問は考え出すと面白い。 最初は個性がバラバラなので、共通点は考えられないなどと答えていた。実際ひとつのパターンは見出しにくい。ただ、自分が接したすごい人たちを思い浮かべると、なんとなく「素直だけど頑固」「頑固だけど素直」ということは共通しているように感じる。 たとえば新規事業が行き詰まっているとき、誰々に会って話を聞いたらどうか、××という他国のサービスを使い込んでみたらどうか、などというアクションに関するアドバイスをすると、必ず素直に、徹底的にやる。ところが、ターゲットユーザー層をずらしたほうがよいのではとか、機能を思い切って半分に減らしてみたらなど、結論に関するアドバイスをしても心底納得するのに時間がかかる。 ・南場さんについていきます、と言われたら、全力で断る。 …DeNAでは、「誰が言ったかではなく何を言ったか」という表現を用いて、「人」ではなく「コト」に意識を集中するように声を掛け合っている。 ・たくさんの失敗をしながらも、何度も挑戦の機会を与えてくださったことに何よりも感謝しています。「与えてくださった」という言葉を使いましたが、「失敗してへこんでいるときに、鉄球のような次の“挑戦の機会”を平気で投げつけてくる」という表現の方が正しそうです。優しいのか厳しいのかわからない、DeNAのそんなところが大好きでした。これからは、自分自身で挑戦の機会を探しに行かねばなりません。 先日、大学時代の知人たちに「退職して文筆業に専念する」と伝えると、皆から「お前、大丈夫か?」と言われましたが、笑って聞き流しました。7年前、DeNAに就職することが決まったことを告げた時も、彼らは同じように言っていました。「お前、大丈夫か?」「将来をちゃんと考えているか?」と。 “選択”に正しいも誤りもなく、選択が正しかったものにする行動があるかどうかだけだと信じています。この考え方は、DeNAで学んだ多くのことのうちのひとつです。 ・「…46億年の地球の歴史のなかでDeNAの歴史はまだたったの数年だ。 これからこの会社がどんなに長生きしようとも、 地球や宇宙の時間のなかではほんの瞬間の存在になる。 けれどもなにか宇宙に引っ掻きキズみたいな証を残したい。 私たちの大きな夢とてんでバラバラの個性で、 DeNAが生まれる前とその後では、きっと違う時代になる。」 私たちは夢に近づけただろうか。これからもっと近づけるだろうか。
1投稿日: 2014.10.09
