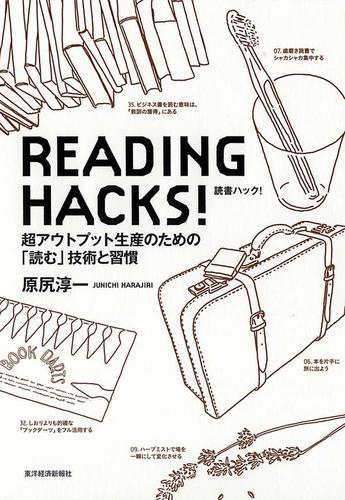
総合評価
(363件)| 60 | ||
| 151 | ||
| 114 | ||
| 15 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1188 本を読むときに著者という人に注目することで本の行間が読めるようになるって分かるな。本を読む前にやることは念入りに著者について調べることだから。読書とかも人について知りたくてしてるから内容とかはもはやサブなんだよね。記憶法としても内容として覚えておくよりも人として覚えておく方が記憶に残りやすいから。 原尻淳一 マーケティング・ジェネレーター。Harajiri Marketing Design代表取締役。一般社団法人みつかる+わかる共同代表。龍谷大学 客員教授。『IDEA HACKS!』等、東洋経済ハックシリーズ、『マーケティング・フレームワーク』(日本経済新聞出版社社)の著者。龍谷大学社会科学研究所共同研究員。龍谷大学経済学部アドバイザリーボードメンバー。日経ビジネススクール講師。リクルートマネジメントスクール講師。環境省家庭エコ診断推進基盤整備事業検討委員 他。クリエイティブやプロモーションにつなげる触媒としての役割を自覚し、アーティストやタレント等、人のブランディングを得意とする、マーケティングマン。現在、そのノウハウを一般人に応用し、個人の価値を高めるワークショップや学校を主催している。 □01 ウィキペディアで著者のエピソードをたくさん読む 本を読む、資料を読むことだけに限ることではありませんが、何事においても、まずはその対象にのめりこむことが上達のはじまりと言えます。しかし、こののめりこむというのは大変難しいことで、はじめから何にでも興味を持てる人はいないでしょう。ことに活字で書かれているものは苦手な人が多いのではないでしょうか。たしかに、全く興味のない分厚い本を読むことほど苦痛なものはありませんよね。 しかし、ビジネスマンにはいつ、何が起きるかわかりません。突然、違うセクションに部署異動ということも現実に起きうる話です。その場合、嫌でもその移動先の資料や専門書籍にあたらざるをえなくなります。全く未知なる情報にのめりこむ技術がビジネスマンには必要不可欠なのです。 さて、本章では、本にのめりこむハックに、とことんこだわっていこうと思いますが、実は本が苦手だという人には悪い癖があります。それはテキストだけに頼りきっているということなんです。つまり、文字だけですべてを理解しようとしているわけです。だから、疲れてしまう。しかも、もともと興味があるわけではありませんから、集中力も続きません。これでは駄目です。 さきほど、上達のはじまりは対象にのめりこむことだ、と言いました。テキスト自体に興味が持てない。それならば、本や資料そのものから若干離れたところに興味の対象を探してみることからはじめましょう。たとえば、この文章を描いた著者が一体どのような人物か、いきなり本を読まずに、著者のバックグラウンドを探ることからはじめてみる。 そこで面白おかしいエピソードを見つけることができたらしめたものです。読むに読めなかった本が、気になりだした著者を知る手がかりに早変わりというわけです。 要は、興味の対象をテキストではなく、人やテーマなど周辺にずらしてみること。そして、そこから興味のカケラを見つける。これが、全く興味のなかった対象が気になる「きっかけのマネジメント」の基本形です。 わたしは本を読む時、まずウィキペディアで著者名を入れて検索し、その人の経歴やエピソードに眼を通します。また、人脈にも注意してみます。なぜなら、その人脈が著者の思考や人格形成に影響しているからです。 さらに、一歩深く知ろうと思えば、ビジネスマンなら日本経済新聞で連載されている『私の履歴書』がお薦めですね。この『私の履歴書』のおかげで、わたしのピーター・ドラッカーのイメージは、「経営の神様」というお堅い印象ではなく、「ロンドン・ピカデリーサーカス駅の長いエスカレーターで妻となるドリスと劇的な再会をした博士」★1というロマンティックなイメージが強いですし、GEのジャック・ウェルチに関しては、「肝っ玉母さんに育てられた負けず嫌い」★2という印象が強く残っています。 こういう愛すべきシーンやバックグラウンドを垣間見た後に本を読むのと、全く知らないで読むのとでは、その本に対する愛着度合いや継続性が全く違ってくるのです。 □02 本にのめりこむには、まず著者の声を聴く これまで本のなかのテキストだけに頼らず、著者自身に興味を抱くことで、本に対する関与度を深めていく方法をいくつかあげてきました。しかし、著者に関して、最も人となりを教えてくれるツールを忘れてはいけません。ブログです。ブログこそ、リアルに著者自身が今の心境や本をアピールする最良のツールとなっています。 もう1つは、著者のプロフィールと人付き合いに関わる日記の内容に注意する★6。これはその人を知る上では基本情報であって、著者の思考や人格形成を探る手がかりになるからです。本というのは、著者の人生経験から生まれ落ちるしずくのようなものです。したがって、ブログにこそ、ホットで生々しい情報があり、それを押さえておくことは非常に大切なことです。 著者のバックボーンを知らずして、テキストだけから行間を読むということなど不可能な話で、だからこそ、この本を読む前に著者に着目するという作業は読書意欲を加速させる有効なハックだと言えます。 それからも先輩の本棚はよく覗きに行きました。本棚というのは、不思議なものでその人の性格や思考を表すんですね。それで慣れてくると、今度はその人が何に興味を持っているのかがわかってきます。これをさらに続けていくと、波長というか、自分の志向性と合う人、合わない人がわかってきます。それで見ていく本棚も自ずと淘汰されていきます。 このページでは、書評サイト、ブックレビューサイトから書評情報を横断検索することか可能です。また、関連情報として掲示板や、日記・ブログサイト、各種データベースの検索機能も提供します。 http://book.cata-log.com/review/ 読書を持続的に行う点で、わたしが一番良いハックだと思うのは、著者と話すこと。これに尽きます。最近では、著名な著者の方々の多くは自分のブログをお持ちですから、そこにコメントを書き込んでしまうのが最も手っ取り早い方法でしょう。 わたしが著者の方とはじめて手紙でやり取りしたのは、大学生の時です。当時のわたしの研究分野はNPO(非営利組織)やボランティア活動で、ある時、わたしは永六輔さんのボランティアに関するエッセイを読んで、生意気ながら感想と自分のボランティア論を出版社に送ったのです。すると、永さんから直筆のはがきをいただき、とても感動したことを覚えています。 今自分でも本を出版するようになって、mixiでコミュニティを持ち、多くの方から感想をいただくことがあります。これは著者としても大変うれしいことで、これには必ず返事を書いています。著者本人が言うのもなんですが、著者とコミュニケーションを取るのは簡単です。敷居はそれほど高くありません。うそだと思うなら、読者のみなさまは是非わたしに感想をください(笑)★9。 読んだ本の感想は著者にまっさきに伝える。著者と簡単に直接会話ができる時代だからこそ、これを習慣にしてみることをお薦めします。著者から返信が来ると、やはり素直にうれしいですし、このうれしさが持続可能な読書に弾みをつけてくれるのです。これは確実に癖になります。 □29 読書投資基準=70:20:10モデル 本を選ぶ時にはどうしても無意識に好きなカテゴリーばかりを選んでしまい、ついつい偏りが出てしまうものです。ある分野の専門家になることは大切なことですが、それだけしか知らない人を「専門バカ」と言います。これはいけません。生きるということは、もっと全体的なことですよね。 税金に腹を立てることもあれば、おいしい料理を作りたい願望もある。栄養の知識がなければ、食品のバランスに偏りが生じますし、病気の知識がなければ健康であり続けることは難しくなります。自分の生活を改めて見つめなおすと、生きるということは専門分野だけで完結していないことは明らかです。そこで、読書には恒常的に「専門外の知識」を取り込んでおくようにしたいもの。よりよく生きる手段として、読書の目的を広く持てば、知りたい欲求は果てしなく広がるはず。 では、どうすべきか。最も簡単なのは、読書に対して「70:20:10モデル」と呼ばれる投資基準を持つことです。これはグーグルの社長エリック・シュミットさんが自社の投資基準比として掲げているもので、グーグルでは、既存サービスの充実に70%の金と時間をかけ、20%は既存サービスの周辺サービスの充実に、そして10%は全く新しい未知の領域に投資するという黄金比率があります。 わたしはこの基準を読書に持ち込んでいて、既存ビジネス領域への書籍投資に70%、既存ビジネスをサポートしうる、あるいは新しいビジネスになりうる領域の参考文献に20%、そして全く未知の書籍に10%を割くように意識しています。決して機械的にきっちりやっているわけではありませんが、この基準値を持っているだけで、「ああ、今ちょっと専門分野ばかりに偏っているなぁ」と修正意識が働きます。 わたしはこの基準を読書に持ち込んでいて、既存ビジネス領域への書籍投資に70%、既存ビジネスをサポートしうる、あるいは新しいビジネスになりうる領域の参考文献に20%、そして全く未知の書籍に10%を割くように意識しています。決して機械的にきっちりやっているわけではありませんが、この基準値を持っているだけで、「ああ、今ちょっと専門分野ばかりに偏っているなぁ」と修正意識が働きます。 そこで、10%を全く専門外の(あるいは全く興味のなかった)分野で面白そうな本を探すのです。これが案外楽しいものです。たかだか10%ですが、新しい出会いが演出されているわけですから、読書の楽しみが計画的にデザインされているわけです。しかも、その専門外情報には、偶然に自分の専門にフィードバックされる有益な情報が含まれている可能性もあります。 独断と偏見:わたしの生涯読書ランキングTOP10 1位:阿部謹也 『自分のなかに歴史をよむ』(ちくま文庫) 2位:三木成夫 『胎児の世界』(中公新書) 3位:エッカーマン 『ゲーテとの対話(上・中・下)』(岩波文庫) 4位:幸田文 『父・こんなこと』(新潮文庫) 5位:網野善彦 『無縁・公界・楽』(平凡社) 6位:鶴見良行 『ナマコの眼』(ちくま学芸文庫) 7位:佐藤雅彦 『佐藤雅彦全仕事』(マドラ出版) 8位:三枝匡 『戦略プロフェッショナル』(日経ビジネス人文庫) 9位:中村尚司 『人びとのアジア』(岩波新書) 10位:齋藤孝 『身体感覚を取り戻す』(NHK出版) さて、図書館で問題なのは、当たり前ですが本を返さなければならないことです。読み終わったら、自分の手元から情報がなくなってしまうのです。しかし、今は読んだ本の痕跡をウェブ上に残すことができますね。つまり、重要なのは図書館で本を借りた後、脳内の読書情報をウェブ上に可視化させておくことです。なぜなら後々になって、ビジネス構築なり、論文研究なり、企画書作成なり、何か形にする時、大変効力を発揮するからです。 借りた読書情報を可視化させるツールはウェブ上にたくさんありますが、いくつか紹介しておきます。その1つが「ブクログ」★16です。このツールを利用すれば、本の表紙がスキャンされていますから、ウェブ上にあたかも自分の本棚を再現することが可能です。しかも、評価の☆とコメントが書けますから、後で読んだ時にも大変便利です。さらにいろいろな並べ替えが可能で、「おすすめ順」で並べ替えれば、自分の「生涯読書のランキング」が再現されることにもなります。 □48 著者が書いているすべての本を読んでみる とにかく、わたしはE・H・カーと阿部謹也にゾッコン惚れてしまいました。大学入学時は比較的時間がありますから、徹底的にこの2人の著作を読んでみようと思ったのです。 まず大学図書館に行って、2人の著作の全リストを出力してもらいました。それを手がかりにして、図書館にある論文やエッセイをすべて見つけていきました。ちょっとした探検気分です。劣等生ですから、劣等生らしく、読みやすいものだけをコピーして読むようにしました。この過程でわかったのは、当時のわたしにはE・H・カーを読みきる実力がなかったことです。それで思い切ってターゲットを阿部先生1人に絞りました。 さて、そのリストのなかに面白いものがありました。たしかNHK市民大学の『よみがえる中世ヨーロッパ』のテキストと映像のセットです。これはしめた! と思いました。劣等生は読むことより耳で聴くほうが楽ですから(笑)。それでいきなり阿部先生の講義をビデオですべて見る幸運に恵まれたのです。既に『自分のなかに歴史をよむ』でバックグラウンドは知っていますから、今度は阿部史学の思想そのものをつかまなければなりません。 これは難しいと思っていた矢先、映像で本人の声を聴いて、短時間でサクッとポイントを理解することができたのです。これをきっかけにして、わたしは気になる著者の講演会がある時は必ず行くようにしました。ライブから入って著作につなげれば、読むことがすごく楽になることがわかってしまったからです。 もちろん阿部先生の講演も聴きに行きました。ちょうどわたしが大学生だった頃、京都では平安建都千二百年記念行事で「世界賢人会議★2」が行われ、その時イリヤ・プリゴジン博士が参加するシンポジウムの司会を阿部先生が担当されていたのです。学生時代の友達と2人で席取りに並んだことを覚えています。ここまで来ると、アイドルの追っかけに近いですが、少なくともほとんどすべての著作を読み、本人の肉声を聴いていくと、ぼんやりですが劣等生でも何が言いたいのか、わかってくるものです。「ははぁ…ある学問分野を理解するには、その道の大家を決めて、読みやすいエッセイのようなものから徐々に読んでいくと、1つの思想、1つの体系がだんだん見えてくるんだな。わかったぞ」。 この時、ようやく読書のコツのようなものがわかりだしたのです。 まさに大江さんが言うように、わたしの読書は阿部先生の本を軸に、横に広がっていきました。Sに導かれてはじまったわたしの読書歴は、「人」が軸となっています。人に惚れて、人を知り、その人の書物に引用される人にまた興味を持ち、横に広げていく。そんな読書をしてきました。その結果、わたしの本棚は著者の人脈によって、書脈をなし、それが帯となって広がっていったと言えるでしょう。 自分のパッションを呼び覚ます。それが効果的なのは、意外と漫画なのではないでしょうか。わたしが最近「座右の書」として読むのは、夢枕獏原作、谷口ジロー画『神々の山嶺』(ビジネスジャンプ愛蔵版)です。これはエベレスト登頂に命をかけた山男の物語で、大自然の猛威に果敢に挑む人間の精神の限界をリアルに描いている名作です。 この漫画のなかにも出てきますが、エベレストでは7000メートル地点と8000メートルの地点では世界が全く違うのだそうです。ベースキャンプを張り、天候を見ながらアタックをかけるわけですが、7000メートルまでは多くの人たちが行ける世界。しかし、8000メートルから上は神の領域。運の世界とも言えます。 これを読むたびにビジネスに近いなぁと思うんです。8000メートルから上というのは並外れた体力、精神力の持ち主でないと到達できない世界です。そのために登山家はどういう気構えで、どういう準備をするのか、そこに注意しながら読むと、自分がビジネスに対してそこまでの姿勢で臨んでいるか、参考にもなり戒めにもなります。 さまざまな困難を限りなく自分のこととして捉え、それをストーリーのなかで追体験していく。そういう気持ちの持っていき方もある意味、自分に活を与えるリーディング・ハックなのです。 本章では、恥ずかしながら、わたしのお粗末な読書歴を書かせていただきました。なぜ、書いたかと言えば、わたしのような読書の劣等生でも、読書のコツさえつかんでしまえば、誰でも年間300冊くらい読めることを示したかったからです。わたしは市販されている「読書術」は学ぶべき点もありますが、かなり問題が多いと思っています。 つまり、わかるということは、知ることで得た知識を自分流に変換でき、その結果、態度変容にまで行き着くことなんですね。しかし、読書というのは知る作業でしかない。ですから、いくらたくさん知識があったとしてもそれだけでは駄目で、「他人の教訓を変形させて自分だけのノウハウ」に昇華させることが重要なのです。 一見関係のないミュージシャンや映画と仏像に補助線を引いて、意外な視点を提供してくれる。これが知的な面白さの根源なんですね。 知の面白さというのは、こういう全く違った領域を跨いで、意外な共通点を発見することだと思います。 □64 アウェーからの学びが専門をより強くする 専門ではない領域の読書が意外と新しい視点を提供してくれることがあります。たとえば、登山家の登頂の準備はビジネスにおいても大変参考になりますし、サッカー監督の視点はチームプロジェクトのコツにも重なりますし、温泉宿の女将の対応は、お客様に対する営業コミュニケーションの鏡とも取れます。そこから学ぶことは大変大きいのです。 やや学問的に捉えたとしても、文化人類学者のフィールド・リサーチは、マーケティングにおけるターゲット分析の方法論にもなりますし、心理学はターゲット・インサイト(消費者心理)を分析する重要な視点を与えてくれます。脳科学における強化学習の話は、ブランド・ロイヤルティを形成する上で大変有用な示唆を与えてくれます。 自分の専門外でも、そこから示唆を得ることはたくさんあります。そういった「意味ある偶然」を読書計画のなかにも忍ばせておくのは重要なことです。先にあげた読書投資基準「70:20:10モデル」は、20%の領域で専門に関係する分野に投資するというものでした。さらに残りの10%では未知の領域にチャレンジするもので、合計した30%の領域で、いかに新しい視座を持ち込むかがアウェーから学びを得るチャンスなんです。この30%分の投資領域から、自分のビジネスにフィードバックできるものが見つけられれば、それは新規ビジネスの種にもなります。 1つの専門性(思考のホーム・グラウンド)を体得したら、積極的に外に出て、大いに刺激や示唆を得て、自分のビジネスにポジティブ・フィードバックを引き起こすことが重要です。ここで言う外へ出るとは、専門の外に出ること、行動範囲をはみ出してみること、読書も積極的にはみ出してみること、部屋にいるより外へ出ることです。読書で言えば、垂直型読書から水平型読書へ移行すべき段階と言えます。そこでの刺激を思考のホーム・グラウンドで考え、醸成できれば、さらに高い思考にレベルアップしていくのです。 ハブとなるブログ ハブ(Hub)・・・車輪(ホイール)などの中心部のことを指す言葉です。 そこから転じて、物事の中心や中核、集約点という意味で使われるようになりました。 たとえば、各地からさまざまな航空路線が乗り入れ、重要な中継地としての機能を持つ空港は「ハブ空港」と呼ばれます。 アイデアファイルとは、自分の好きなものだけを集める秘密のファイリング・データベースです。極めて個人の好き嫌いに左右されますが、それはそれでOKです。なぜなら、アイデアやクリエイティブは、その人の好きを極めることから生まれるものだからです。元電通のクリエイターで、現在、東京藝術大学の教授をされている佐藤雅彦さんは、クリエイター時代、自分の好きなものや気になるものを集めて、そのなかから共通するものをルールとして明言化し、広告制作を行っていたそうです。 たとえば、1つの事例として「濁音時代」というルールがあります。これは佐藤さんが気になる言葉を集めて分析したら、濁音がつくものばかりだったそうで、そのルールに基づいて作ったのがなんとNECの「バザールでござーる」。なるほど、佐藤さんは自分の好きというものに潜んでいるルールや法則を見つけて、アウトプットに結び付けていたわけですね。 わたしがアイデアファイルに集めている素材は、圧倒的に雑誌の切抜きです。なぜなら、雑誌は写真や記事やグラフなど、アウトプットが美しいものが多く、ビジュアル的に刺激になるものが多いからです。そこで「おっ」と思ったものは迷わず破ってしまいます。ほとんどの人が雑誌を破るという習慣がないため、はじめは躊躇しますが、迷わず破ると気持ちがいいものです。 こういう複眼的問題解決のアプローチは、専門書ばかりを読んでいるだけでは生まれてきません。むしろ、専門外に眼を向けつつ、「おっ」と思うものを自分の仕事に取り入れていく作業にこそ、新しいクリエイティブが生まれてくる可能性がある。大げさかもしれませんが、演劇の表現方法にプレゼンテーションのコツがあるかもしれませんし、チームスポーツの練習のなかに、業務プロジェクトをまとめるコツがあるかもしれません。ですから、自分の好きな領域だけにとどまらず、全く未知の領域へ積極的にチャレンジし、そこでの学びを持ち帰るリバース・モードがリーディングにも必要なのです。 □82 直感を信じて、「好きな」文章も集めよう わたしが声を大にして言いたいのは、自分の好きなものへの感覚を信じろということです。アイデアというのは、その感覚的経験から滴る雫のようなもの。だからこそ、アイデアを発想したければ、自分の好きな情報をストックしておくことが大切です。これは雑誌のビジュアル情報だけにとどまりません。本から好きな言葉を集めるというのも大事な作業です。 つい数年前に明治大学の齋藤孝さんによって開発されたユニークな「3色ボールペン読書」。この方法は著者が言いたい一番大事な箇所には赤で傍線を引き、まあまあ大事な箇所には青、自分がオモシロイと感じた箇所には緑で傍線を引くというものでした。一番大事な箇所に赤で線を引くというのは、誰もが共通する点を見つけることであって、著者の結論やメッセージを的確に見抜くという点では、この赤線の作業がビジネスマンには重要かもしれません。 しかし、アイデア発想という観点からすると、わたしは「緑線」の部分こそ重要だと断言します。なぜなら、赤線や青線のようにある種客観性を帯びる文章は、企画や文章をまとめ、説得する際に使われ、緑線のような主観性の強い文章はアイデア発想につながる傾向が強いからです。「おっと、これはオモシロイ」という文章は、既に自分のなかに芽生えているアイデアに身体がうずいているわけです。ということは、自分に呼応するオモシロイを集め、そのオモシロイの本質や法則性がわかれば、それがクリエイティブの方法論になっていく。これは写真だけでなく、文字情報も同じでしょう。 この時ちょっとしたコツですが、オモシロイ箇所に傍線を引いた後、その理由を本の余白に書いておくようにしておくことです。Reason/Whyが整理されていると、後で見直した時、本を読んだ頃の課題や背景がはっきり見えてきます。そのメモはアイデアが急激に形になることを手助けし、既に必要のない情報になっているかもしれないことを教えてくれるはずです。 では、この読書における「オモシロイ」をどうデータベース化していけばいいのでしょうか? □83 ブログを「個人データベース」として活用する わたしの場合、読書情報はすべてブログ「Life Hacking Life」に集約していきます。ブログを単なる日記としての役割にとどめず、ビジネスに使えるデータベースとして構築するのです。情報のセレクトショップを運営しているようなものですね。『IDEA HACKS!』や『PLANNING HACKS!』でも書きましたが、わたしは鶴見良行先生のフィールド・ワークの技法を仕事においても応用しており、ブログにおいても次の3つの要素に分けてデータ蓄積をしています。 読書カード……これは京大式カードに参考となる文献の文章・ページ数・著者名・書籍名を記載しておくというもの。鶴見先生は4万枚のカードをお持ちだった。 日記……フィールド・ワークに出て、その日のうちにフィールド・ノートを作成する。ノートの左ページには、出会った人の名刺や地図を貼り、右ページにはその日の出来事を克明に記し、そこで考えた仮説が描かれる。 写真……鶴見先生の写真の腕前はプロ級で、雑誌にも掲載されるほど。数十年というフィールド・リサーチで歩いたアジア・オセアニア各国の写真が数万枚、保存されている。 鶴見先生は、この3つのパーツを再編集するだけで、著作のほぼ8割ができ上がってしまうという、とてつもないデータベース・システムをお持ちでした(現在、この資料は埼玉大学共生社会研究センターで誰でも見ることができます★3)。しかし、時代を経て、最新のネット技術を駆使すれば、これらはすべてウェブ上に集約することができ、ほぼ無料でデータベースを構築することができます。 わたしはこれまで自分のパソコン内に上記の構造を意識してデータベースを作っていましたが、最近になって、徐々に、ウェブ上に情報を移植し始めました。なぜなら、2つの利点を見込んだからです。まず、携帯電話でも見られるため、いつでも、どこでも簡単に必要情報にアクセスできること。これは急いでセレクト情報を確かめる際にかなり便利なツールとなります。 さらに読書カードに言えることですが、mixiの書籍評価などは、自分の参考文章や意見だけではなく、他の方々の意見や評価を見渡せるという点で、かなり付加要素がありますし、書籍に対して複眼的、かつ客観的に見ることができるからです。 ブログを単なる日記としてではなく、アウトプットのための情報データベースと捉えなおし、必要情報をネット上に公開し、さまざまな人の意見をも取り入れる編集装置として機能させれば、ビジネスマンとしてかなり有効な武器を手に入れることになるはずです。 わたしの会社の先輩に、残業は朝することを習慣にしている方がいました。たしかに、ウェーバー的習慣の有効性から見ても、ビジネス環境から見ても、朝残業のほうが夜の残業より効率性が高いのは確実です。なぜなら、早朝の会社は誰もいないからです。電話も鳴らない最も理想的な集中環境なのです。
0投稿日: 2024.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書が好きになるための入門書 まず、 「ハック:こんがらがった問題をサクッと解決する」 とあります。 読むことに取り組みたい方の問題を解決するための書であることが冒頭にしめされます。 冒頭に読書成長モデルA~Dの概念図があって、以後の流れがのっています あと、ガイドブックがいくつか紹介されているので、興味のあるかたはご参考にされるのはよいかとおもいます。
3投稿日: 2021.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ■ジェネラリスト的視点を深める読書 自動車、消費財、ハイテク、金融、エンタメ、流通、通信、運輸、コスメ ■スペシャリスト的視点を深める読書 営業、マーケティング、セールス・プロモーション、研究開発、クリエイティブ、人材開発・人事、ファイナンスなど
0投稿日: 2021.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎的な内容多し。ブクログを使用しているような人(=読書好き)には、あまり得るものはないのではないか。 ただ、以下は参考になった。 ------------------------------------------------------ ・「読書キット」でちょっとした隙間を逃さない 要は筆箱の拡大版。中に最近読んでいる新書や文庫が二冊入っている。さらにフィルム素材の三色ポストイット、数色の色ペンと書き込み用のボールペン、小さなスケッチブック、iPodと充電コード、これらが一式入っている。 一式にまとめておくと、そこにすべて詰まっているので、漏れがないのがいい。 ・「まず、はじめに最後を考えよ」 レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉。 ・まとまった思想を自分で生み出そうとする思索にとって、これ(読書)ほど有害なものはない。 ショウペンハウエルの『読書について』より。 「読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。(略)だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。自分で思索する仕事をやめて読書に移る時、ほっとした気持ちになるのも、そのためである。(略)ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、次第に自分でものを考える力を失って行く。」 ------------------------------------------------------ ショウペンハウエルの言葉は重い。 ビジネス書を読むのも、良いことを学んだような気になって、安心しているだけではないのか? 著者が苦労し身につけた経験を、(本を読むだけでは)自分が追体験できるわけでもない。 やはり、自分で考える、行動に移すことが大切である。
0投稿日: 2019.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の効果的なアウトプット方法を知りたくて読書術系の本を探す。たまたま図書館にあってよさげだったので。 ◯読書術関係の豊富な紹介 ◯検索方法として❶書評メタ検索、❷webcat plus。❶は、主にアマゾンで書評レビューを見てたので、色んなレビューを一気横断できるのはよい。❷は、気になったことをグーグルで検索しかしてなかったので、関連ワードが調べられるツールもよい。 ◯ある教訓を別で試せないかという視点。教訓だけでなくアウトプット資料もそういう視点でみる。横断的に知ってルールを探すっていうのは、抽象化というものか。最近読んだ本とつながった。
0投稿日: 2019.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログもちろん著者もそう思っていることだろうが、ここに書かれている「ハック」のすべてが読者に当てはまるわけではない。 が、「やり方を変えるきっかけ」になるヒントはいっぱい書かれている。 あと、ずーっと探していて見つけられずにいた文具の名前が「ブックダーツ」だというのがわかったのは本当にありがたかった。(やっぱりあれ使いやすいんだよねー。本をたくさん読む人はぜったい重宝すると思う) 何年も見つけられずにいたけど、名前さえわかればあっという間にインターネットで注文できちゃうわけだ。便利な世の中だ。
0投稿日: 2019.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アウトプット型読書を基本とすることがより本当に必要な情報を素早くできるコツ、読書のためプチ家出をする。本は家では読まない。本当にじっくり読むべきウェブ情報は印刷して精読する。
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「みんな、もうインプットで終わっちゃう読書はやめようよ。何かを生み出すアウトプット型の読書に切り替え、自分だけのシステムを構築して周りを出し抜いちゃおうぜ」という筆者の言葉に全てが集約されているような気がする。有用なWEBの情報などもありきわめて実践的
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・たまたま 【期待したもの】 ・「読書は1冊のノートに」を読んだ直後で、類似本をサラッと読んでみてもよいかなという程度。 【要約】 ・ 【ノート】 ・テキトーな流行りのハック本かと思ったら、意外と深いぞ。HACKSシリーズはISISシンジケートに牛耳られているのか? ・かなりセイゴオスタイルが散見される。物理的環境が読書やモチベーションに与える影響についても言及されてるし。しかもそれって、直前に読んだ「読書は1冊のノートにまとめなさい」の「作業興奮」との関連が強い。 ・Chapter5の「キャリアを作るリーディング・ハック」は、ほっほう〜という感じ、いい意味で。あまり自分で考えたことのないフィールドだったということもあり、特に興味深かった。もう少し読み込みが必要な感じ。 ・「教訓ノート」って「読書ノート」とはどう違うのか? ・しかし、図書館の電子書籍にはメモもマーカーも使えないとなると、電子書籍の特性がかなり低下しないか? 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書ハックとあるが、アウトプットにつなげる読む技術が詰まった本。この本に載っていることを実践できることがあれば、是非実施してみよう。取っつきやすいものから、難しそうなものまで網羅されている。読書成長レベルを4つに分けて、各レベルにあった技術を紹介している。何のために読むのかを意識して、アウトプットのレベルを向上させることを目指した本である。
0投稿日: 2018.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ【この本のターゲットは?】 ビジネス・リーディンにおける1つの基本モデルとなることを目標にハックという形で大量のドキュメントを効率良く読み、良質なアウトプットを生産するための準備を解説した本。忙しいビジネスマンや学生がターゲット。 【この本から学びたいこと】 効率の良い、読書とそこから導き出されるアウトプット力の強化方法を学びたい。 【この本から学んだこと】 ・著者についてウィキペディアなどでエピソードを調べる ・著者の声を聞く TOP BRAINなどを活用 ・著者のブログで話をする ・ipodで、ビジネススクールを耳学する iTunesUなど ・自分の部屋を図書館にする ・読書投資基準=既存ビジネス領域70%:既存ビジネスのサポートor新規ビジネス領域20%:未知の書籍に10% ・読書キットを持ち歩く ・本をノートとして書き込む ・ビジネス資料をアウトプット用にファイリングする ・教訓ノートをつくる 【新たな疑問、学びたいこと】 ・出版されたのが、2008年ということで今ならファイリングをEvernoteにまとめたりクラウドをつかう事が中心になるかと思う。ブログだけでは無くなってきているので、そのあたりを紹介してもらいたい。 ・読書術の本では、本をノートの様に活用する・・・とあるのだが、私はどうしても出来ないんですよねぇ。(^^ゞマダマダなんです。 ・読みやすく、HACKSというだけあって、すぐにでも活用できる内容だったので、著者の他の本も読んでみたい。実際のアウトプットの方法をもう少し知りたいので・・・。 【今後読みたい本】 ・『IDEA HACKS!』 ・『PLANNING HACKS!』 ・『自分のなかに歴史をよむ』 ・『胎児の世界』 ・『ゲーテとの対話』 ・『父・こんなこと』 ・『無縁・公界・楽』 ・『ナマコの眼』 ・『佐藤雅彦全仕事』 ・『戦略プロフェッショナル』 ・『人びとのアジア』 ・『身体感覚を取り戻す』 【この本を読んで次のアクションは?】 ・ウェブ書評「千夜千冊」で紹介されている本を読んでみる。 ・フィルム素材の三色ポストイット買う。 ・読書キットを持ち歩く。 ・読書のとき本をノート代わりに直接書き込む。 ・楽しむ読書とアウトプットのための読書をごっちゃにしないように、区別して本を読む。
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読む際に、いかに時間をかけずに効率よくその中身から自分の役に立つ部分を抽出できるか、というところに重点を置いた読書法。共感できる部分は多いが、本は捨てるという部分は心理的に抵抗感が大きい。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読む習慣がなかった人から、ぜひとおすすめされた本。実践書をいかに効率的に読み、いかにアウトプットするか。 何のために本を読むのか。自分は小説など楽しむための本書でいう「楽読」の比率が高いけれど、実践のための「実読」としての読み方も、使い分けていきたいと思った。 2008年出版でmixiなど古い例もあるが、(ブクログも紹介されていますが)、今に通じるインターネット時代の実践書の読み方マニュアル。自分に必要なものを取り入れていきたいハック本。
0投稿日: 2018.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んできたハウツー物(読書関係)の集大成として読む。程よく概括できた。ネットツールの使用はまだ自分には敷居が高いが、他のツールはあらかた実施していた模様。アウトプットベースで読む、ということをまだまだ実践できていないことを知る。つい、試す、実験する手間を惜しんでしまう。これを自覚したことが収穫。以前TVで見た、ひたすらA4ノートにメモる、という手段はつづいているので、これに読書メモやらなんやら、本書で得た方法を追加してみる。 後は洋書をいかに効率よく、都合よく読むか、ですな。和物でできるようになれば英語でもできるだろう。
0投稿日: 2018.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むことに関しての本というのはたくさん読んでます。 その中でも2008年発刊のこの本はかなり好きな一冊ですね。 ざっくりどんな本かと言うと アウトプットを前提としたビジネス系読書のノウハウ本。 読書に対する考え方という大きなところから、 どんな状況で読むか?という細かい小技的なものまで かなりの量の提案が一冊に収められています。 【小技的ノウハウ】 ①読む前にWiki,ブログなどで著者の情報、インタビューなどを読み その後に本を読み始める。さらに本で描かれている場所へ実際に行ってみる。 ↓ 時間があればこの方法はかなり有効。 ②音楽を聴きながらの読書は、ジャンルも大事だが、ヴォリュームの大小の影響が大きい。 ↓ 実際に試してみたところ、ジャストフィットしたヴォリュームだと かなり読書は捗る事が判明! ③歯磨きしながらの本を読む。 ↓ どーも、自分はよだれがだらだら口からこぼれるので却下(笑) ④付箋の貼り方→赤ー著者が強調したいところ。青→自分の課題に対応しているところ。 黄→文章表現として参考になるところ。 ↓ 齋藤孝先生の三色ボールペン方式もそうだけど、ついつい面倒になってしまうんですよね(笑)kindleの場合のハイライトで色変えられますけどこれは結構使える。だけど、やはり読書というのはスピードというか勢いみたいなものも大事ですよね。 ⑤④とかぶりますがラインを引く場合、(付箋も含め)なぜ気になったのか?という理由もその場で書いておくと後で役にたつ ↓ 確かに、あとでなんでこの箇所気になったんだろう?という謎の場所は多発しますね。 【考え方】 ①ビジネス書を読む目的→他人の獲得した教訓を現場検証し、自分のビジネスの規則として作り変えること。取捨選択し、自分のためにアレンジする事。 ↓ 確かに! 自分は目的を求めない楽しむためだけの読書肯定派だけど、 まービジネス書に関しては著者の主張通りだと思う。 切り分けですね!! ②本には恋愛適齢期みたいなものがある。 ↓ むかーしあんなに感動したのに、読む返してみると全然!という事はありますね。 ということは以前理解できなものが今読むと面白いというのもあるかも。 ③読書は著者と読者のプロレスのようなもの。学生時代は無制限一本勝負だったが、大人の勝負は30分一本勝負だったりする事を意識する。 ↓ そーですねー、きままに好きなだけ本を読める なーんて一日なんてなかなかないですからね。 時間を意識する。 30分以内に自分の得意技でその本をKOする!(ちと違いますね 笑) で、読書は著者と読書のプロレスだ! 理論から面白い例が書いてありました。 自分の得意技(得意ジャンル)で関係ないものを表現する達人として あのみうらじゅんさんの言葉が引用されていました。 『アメリカとかイギリスからロックは生まれたと思っていた私は ある日法隆寺の伽藍配置図を見たときハタと気がついた。 この配置はまるでステージのミュージシャンの並びと同じでは無いかと 四天王寺色はジャニーズ系の配置釈迦3尊像は松竹芸能系のルーツ!』 参考 http://d.hatena.ne.jp/mmm000mmm/20150125/p1 『空也上人は偉大なラッパー』 参考 http://www.kuniomi.gr.jp/togen/iwai/kuuya.html 関係のないミュージシャンや映画と仏像に 『思考の補助線』を引いて意外な視点を提供してくれる これが自らの得意技を使って著者と戦う?ための ひとつの有効な戦術だそうです。 うーーーん。みうらじゅんさんはやっぱり凄いなあ(笑) という事でこの本の結論はみうらじゅんを目指せ!! という事ではありません(笑) 本当の結論が気になる方は本書をご覧ください(笑)
2投稿日: 2017.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ<実践したいアクション> ・書店の近くに行きつけの隠れ家を開発する 本を買った時、その瞬間が読みたい!と言う思いが一番熱い時。その思いが冷める前に、書店の近くにあるカフェやら隠れ家で読書をする。そのための隠れ家を開発すること。 ・本を片手に旅に出る 小説にはよく実際の土地を描いた内容がある。その時に実際に出向き、本を読む。現実世界と本の世界を照らし合わせながら読むのも読書の楽しみかた。 ・生涯読書ランキングをディスプレイする 本棚には背表紙を正面に詰めつめで並べるのではなく、ランキングに入る名作は表紙を見せてディスプレイする。一度、自分の本棚を書店の本棚に見立てて、魅惑のディスプレイをしてみては? ・ブクログに自分の本棚をつくる ・アウトプット型読書を基本とする 「読書はレポートを書くための手段なんです」この考え方は他のアウトプットの仕方にも応用できる。例えば、仕事の生産性を上げるための手段なんです。人と楽しく会話するための手段なんです。 ・読書の7割を垂直型読書に投資する ビジネスマンが今やるべきことは、「今、所属している部署のスペシャリスト」になり、手っ取り早く、そこで「ホームグランド」を作ること。そのためには、読書の7割を専門的な分野の本に投資すること。
0投稿日: 2017.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ・読書の意義を教えてもらえた(アウトプットに繋げる) ・数あるハックから必要なものを選ぶ必要アリ ・実際にやろうと決めたこと (匂いで集中ゾーン、速読術、ポストイット、薄い本、ノウハウ実験、必ず携帯、朝はアウトプット)
0投稿日: 2017.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ多読の恐怖を知った。自分で考えるということを忘れてはいけない。 だけど、その前に本を読まないと、この意見は語れない。(笑)
0投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ図も多く、必要な部分は太字となっている。 アウトプットの仕方だけではなく、速読の練習にもなる本書は良書と言える。 文房具のおすすめもされているので、一緒に購入すべし。 さらには、ネットの利用の仕方までさりげなく乗っている。 おそるべし。
0投稿日: 2016.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログネット活用で革命的に本の読み方が変わる!スマートでポップな「ライフハック」式読書術。 (BOOKデータベースより) これまでのハウツー本よりは斬新な感じがして面白かった!
0投稿日: 2016.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がこの本から何を得ようとしているのか、 問題解決の意識をもって読むことで集中力を上げることが大事。
0投稿日: 2016.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログアウトプットを生み出すための思考の本質 まず、はじめに最後を考えよ 脳は極力処理に使い、記憶は外部に携帯しておく
0投稿日: 2016.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
意外にも学校では学べない「本の読み方」を様々な工夫をこらして教えてくれる本。著者の背景を深堀りする事で理解を深めたり、現実と本の内容とをリンクさせてより興味付けを与えたり、なかなかに面白かった。ショウペンハウエルの警鐘を用いて、読書の危険性なども書かれている。
0投稿日: 2016.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだ本を糧にして、自分の生活の中に活かしていく事。チャレンジするもまだ体得出来ていない。これからはきちんと記録に残し、アウトプットできる形で整理をしていこう。
0投稿日: 2015.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書の仕方について図入りでわかりやすく書かれていた。 アウトプットすることで読書は実になるという王道を行く本。そのための読書の方法について書かれている。 シントピカル読書、垂直型・水平型読書の仕方が参考になった。
0投稿日: 2015.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ほとんど丸一日を多読に費やす勤勉な人間は次第に自分でものを考える力を失っていく」ショーペンハウエル アウトプットのための読書をするためにはアウトプットのための読書だと思って本を読むこと。 まずはじめに最後を考えよ。
0投稿日: 2015.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログただの濫読ではなく、「アウトプットのための読書」という響きがいいですね。ブクログを始めるきっかけになりました。
0投稿日: 2015.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を知る・読む楽しさを味わうための様々な方法・ツールが紹介されており、気になる項目は幾つかメモしました。 どれもすぐに実行できることなので、良いです。 自宅を図書館化したいと思いました。が、現実には難しいですが...。
0投稿日: 2015.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログほとんど参考にならなかった。 読んで面白くないと思った本はそのときに必要な本じゃないので思い切って読むのをやめた方がいいと書いてあったので、今この本は私には必要でないと判断して6割読んだところでやめてしまいました。
0投稿日: 2015.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報過多の現在で、自分にとって有益な情報を掴み、どうアウトプットに繋げるのか?という事が難しいと感じていた矢先、この本に偶然出会いました。 やはり、自分の武器、引き出しを多く持つには読書は必要で、読書は今まで苦手な方の自分にとっては、参考になる一冊でした。 目的に合った本と巡り会う打率を高める方法や、速読の一種の紹介など比較的わかり易く書いてあると思います。
0投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書から仕事の資料まで、情報を処理したり知識や考え方を吸収する目的での読書テクを紹介する本。最近読書の機会が増えて、本の選別眼と知識定着率を向上させたくなり、読書論系の本に興味を持った。これは30分程度で読めるハウツー本だけど、私がふむふむと思ったポイントは以下。 ・imagine book search ・ブログで著者と対話する ・読書投資基準 (既存ビジネス領域 70 : 新しいビジネス領域 20 : 全く未知の書籍 10 )
0投稿日: 2014.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり、アウトプットは大切だな、と感じた。 今まで目次は読むという感じではなく、サラーっと流す程度だったけど、目次を読み込む事は基本だそうだ。以前、松岡正剛の読書の仕方をテレビで見たとき、やっぱり目次を見て大体どんな事が書かれているか、想像すると言っていた気がする。 巻末の「読書論」ナビゲーション・リストを参考に読書を続けたい。
0投稿日: 2014.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「図書館の側に引っ越す」 「書斎を作る」 ……等々は今すぐ実行できないけども、本の購入費の比率や、ノウハウを丸呑みにしない事などは為になった。 卒論を書いている時に知りたかったな……。
0投稿日: 2014.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【読書へののめり込み】 ービジネスマンのリーディングは目的が情報収集のため多読が基本。自分のビジネスネタを探すといういみでたくさん読む事が基本。 ▶︎アウトプットも重要だけど、アウトプットを出そうと思えばインプットの量も大事というふうに解釈。雑誌等でのネタ集めもしないと。 ー読書の欲しいものリストは管理 ▶︎ブクログで管理。 ー読書感想は友人と共有 ▶︎ブクログ、Twitterで発信。要点はチームメールで発信。アウトプットを意識するので効果的。 【速読】 ービジネス書を読む最重要課題は「他人の経験から紡ぎだされたスキーマ(物事の法則性)を獲得すること」。大切な事は獲得した教訓を現場検証して、自分のビジネスの規則として作り替える。つまり実践で試して本当に使えるか取捨選択し自分向けにアレンジする。この作業を繰り返し、使える教訓を蓄積していくサイクルができていればビジネスがどんどん加速する。 ▶︎とにかく、読んだら教訓をメモ。そして試す!このサイクルを高スピードでまわして行く。読みっぱなしは読書ではない。 ー速読のコツは問題意識をもち、ヒントを見つけてからそこをフックに高速で読む。目次を読んで自分にとって必要箇所を特定していく。 ▶︎本の構造を理解し、その部分を深く、何度も読み込む。逆に言えばその他の部分はほぼ読み飛ばしてもOK。そこまで読んでいる時間はないはず。同様に索引を読んでから本文に目を通しても著者が何に興味があったのか分かるから使える。 【アウトプット】 ー実読とはその読書を糧にしてアウトプットにつなげる読書。ビジネスマンにおいて重要なのは実読。 ーノウハウ本は実験して自分にあったものだけを吸収する。 ーアウトプットまで落とし込む読書は集中して身につける事が必要。やや緊張感のある環境で読む方が良い。 ▶︎アウトプットの重要性はここでも。とにかく読んだらAction!読むために喫茶店もどんどん活用。終業後、週に3日は喫茶店活用したい。 ービジネス資料は今見ている資料が今後の自分のアウトプットの参考になるかを考える ー資料には市場データ、顧客データが満載 ▶︎これらのデータは一括でevernoteにでも保存していく ー脳は極力処理に使い、記憶は外部に携帯しておく。読書で感じたネタはその場で本に書き留める、後日メモを作成。 ▶︎データのevernote保存は徹底させる。 ー教えてもらうよりも教える側にたって初めて理解が進む。 ー読書データはすべてブログに集約しアイデアを生み出す自分だけのデータベースを作る ▶︎アウトプッターは表層的な表現のもとに潜むルールや本質を見抜き、自分の表現方法に転化させ価値あるものに生み出せる人。大量の情報を選抜しながらそこから自分流の方法を体得する。 ▶︎インプットで終わる読書はやめよう。何かを生み出すアウトプット型の読書に切り替え自分だけのシステムを構築して周りを出し抜いちゃおうぜ! 【要点・まとめ】 ーアウトプットがやはり重要。教訓を現場で検証して自分のメソッドに置き換える。このサイクルをいかに回していくか。結局ここに尽きる。 ーアウトプットが重要といっても多読が必須。情報のネタは仕入れてナンボ。読む環境作る為にも喫茶店はどんどん活用。 ーデータのevernoteへの保存は徹底していく。脳は極力処理に使い、記憶は外部で提携。これは参考んなる! ▶︎最後の一文がすべてだと感じる。つまり、インプットで終わる読書はやめよう。何かを生み出すアウトプット型の読書に切り替えて自分のシステムを構築、周りを出し抜こう!という点。その為のメソッド・ハックは参考になる。メモ作成:アクションに落とす、がやはり重要かな。
0投稿日: 2014.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログCh.1 読書のめりこみハック!ー本に恋する、きっかけのマネジメント Ch.2 楽しいビジネス読書ハック!ーリーディング・ハック Ch.3 超速読ハック!ースピード・リーディング・ハック Ch.4 読書体質になるリーディングハック! Ch.5 キャリアを作るリーディング・ハック!ービジネス・マルチ・リーダーを目指して Ch.6 ドキュメントのリーディング・ハック! Ch.7 超アウトプット生産のためのデータベース・ハック!
0投稿日: 2014.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ楽しく本を読みたい、ただ読むだけでは面白くない、という思いに答えてくれる一冊です。 本を読むことに関してのアイデアが詰め込まれており、実践してみるとなかなか面白いものがいくつもありました。
0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスマンではないが、読むコトでもアウトプット部分をもう少し意識した方がいいと知った、ブログやココに書くために読むというのは正直意識していたが、カードやノートにまとめはしていなかった。 あ、あと読書キットはつくろうと思った。
0投稿日: 2014.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
副題の通り、正に、『超アウトプット生産のための「読む」技術と習慣』の為の本。 持続的読書ライフに入りやすくするきっかけから、最終的にはアウトプットの為のデータベース構築アイデアまで体系的に紹介されている。もちろん各々のTIPSを適宜参考にしても使える。 速読的な方法論は、他の色々なモノとほぼ同じような感じ。 個人的には2章の良書選抜の為のWEBツールの部分に感動した(知らなかった!)。2008年発行の本なのでクラウド的なツールは無し。 自身の軸、核となる「思考のホームグラウンド」確立や、本から得られる教訓という、奥に潜む法則性、抽象的な概念、本質を知り得る事が重要、などの点がより意識化された。 結局、何はともあれ読書は単なる手段であり、 アウトプットや目的を常に意識する事が重要であるという点が心に刻まれた。 追記:他のHACKシリーズでは、文庫本で再発され加筆改筆されており、この読書HACKSも文庫本が再発されているので、そちらの方が情報的に新しいかもしれない。(未確認。そちらを買えば良かった・・)
0投稿日: 2014.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の基本を再確認させてもらった。 いろいろとハックがあったけど、ホームグラウンドの話や、「まず、はじめを考えよ」とかは、当たり前のことだけど、つい忘れてしまいそうなことなので、しっかりと肝に銘じておきたいなと。 あと、時間を見つけて、最後のオススメ本も読んでいきたいと思います。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ単なる速読を薦める本ではなく、心構えから具体的な方法まで読書に対する取り組みが書かれている。 アウトプットをすることを常に頭にいれて読書が重要である。 HACK本は初めてだが、他のも読みたくなった。
0投稿日: 2013.10.13いかに読書の時間を充実した時間にするかのHACK!
HACKシリーズとして、さまざまな方法・工夫を提示してくれるシリーズの読書術版。 自己啓発本に分類されていますが、概念的な抽象論や感情論ではなく、 具体的な方法が様々な角度から紹介されているので、雑誌感覚で読めて楽しいです。 ビジネス向けなので、実用書を対象としていますが、特定のジャンルに限らず便利な方法が様々紹介されています。 便利なツール(ブックダーツなど)のHACKから、読み方のコツなどいわゆる読書術の部分、 そして、読書タイムを有意義にする方法、本の内容を活用する方法まで、本を読む前から本を読んだ後まで、 いろいろなHACKを見ることが出来ます。 読書術系の本を一冊は見てみたいなというひとにはおすすめです。
1投稿日: 2013.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ長続きしない→罪悪感→ハックで払拭 勉強法→インプットを最大化する技術 ビジネス アウトプット。結果を出したもののみが評価される。 知的生産の技術 知のソフトウェア 集中ゾーンに入るマネジメント→儀式を持つ。集中スイッチ。 欲しいものリスト→携帯のメモに入れておく。 Webcat Plus 想Imagine Books Search 知的興奮をどう演出していくのか。→読書体質 高速で何度も目を通す。目次読書法。 歴史とは何か 自分のなかに歴史をよむ 高校まで→インプット重視 大学→レポート,アウトプット ノウハウ本→鵜呑み× 実験○ 行動中心の読書,準備 アウトプットにこだわる→読書欲 思考のホームグラウンドをつくる→困ったらそこに戻って考える。→思考が整理 教訓ノート ダヴィンチ「まず,はじめに最後を考えよ」 ビジネス資料→解剖→見本?デザイン?説得材料? 誰かに説明する前提で読む
0投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「重要なのは、レビュアーの意見ではなく、自分が抱えている問題を自覚し、少しでもそれに対応するヒントを探せるか」p56 「目覚めて脳が高速回転し始めるタイミングこそ、アウトプットにつなげる読書にあてていくべき」p205 「ホンモノに触れて知的喜びを知る、と言いましょうか。「座右の書」に出会う。わたしは、これに勝る読書の原動力はないと思います。」p120 アクション 朝起きたら30分以内に読書をする。
0投稿日: 2013.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ゴール】 自分の読書スタイルを確立する知恵を5つ得る 【得た知識】 ●本の読み方 1.まえがき・目次を良く読み、この本を読む意味(ゴール設定)を意識する 2.ゴールに対するキーワードを意識しながら、気になるところにバンバン付箋を貼りながら高速読書(時間設定)を行う 3.付箋部の前後をじっくり読みながら、読書ノートを作成していく 4.隙間時間には、本を読むのではなく、読書ノートを読み返す 5.実践できることはすぐに行い、PDCAを回しながらしっくりするまで自己流にアレンジしていく 6.読んだ内容はブクログにアウトプット 【気づき】 ・歯磨きしながら読書:小説などを読むときには有効かと。『コンクール・ジェルコート』で実践してみよう ・ブックナビゲーション 想 IMAGING BOOK SEARCH:書籍検索に活用していきたいと思います 【総評】 経済的・政治的環境により必然的に図書館本での読書中心の私の読書スタイル確立に試行錯誤している中、また新しい知恵をいただいた。 時間的制約のある中で、いかに多読を行えるかが一つの課題でしたが、そのヒントをいただけたと思い、早速実践しPDCAを回しながらアレンジしていきたいと思います。 そして、早くからこのブクログに本棚を持っていたのに、活用しきれていなかったことを恥ずかしく思い、アウトプットのためのデータベースと捉え、本棚の充実にも気をつけていこうと思いました。
0投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ『読書ハック!』 原尻淳一 「ハック」というのは、何かの対象にのめりこむ「きっかけのマネジメント」と「仕事を効率的にさばく技術」が共存しながら、閉鎖したビジネス環境にスマートさとポップさを注入する方法と言えるかもしれません。(p2) ★ハックについての説明。ハックシリーズは多くあるので概念として覚えておきたい。 この文章を描いた著者が一体どのような人物か、いきなり本を読まずに、著者のバックグラウンドを探ることからはじめてみる。(p21) ★一つの手段とは思う。軽く見るぐらいのレベルで十分だろう。タイミング的には本を選定する時点で確認しておきたい。 書店に入ったら、まずこのリストをチェックして、このなかから今日の獲物を探します。(p59) ★時間の節約には必要。チェックリスト更新しなければ。 書店では毎月課題となる獲物をゲットして読んでいくわけです。(p83) ★毎月は厳しいかもしれないが、課題、目標が必要。 速読術のコツは、わたしが無意識でやっていたように「高速で何度も目を通すこと」……速読術とは、キーワードをあらかじめ意識し、その隙間を高速で埋めていく技術なのだということです。(p97) ★速読についての言及だが、これは著者のやり方である。自分なりの方法を見つける必要がある。 目次を読むことは読書の基本中の基本です。……本の構造と要点をつかむのに最も有効な読書術なのです。(p99) ★読んでいる内に忘れてしまうんだけどね。もう少し続けてみたい。 スキミングとは、簡単に言ってしまうと「飛ばし読み」です。本全体にざっと目を通し、その本の内容を簡単に把握する方法です。(p104) ★ここまで流れを把握する。 1目次読書 2飛ばし読み+杭打ち 3じっくり読み 4仮説/アイディアメモ 1と2でざっくり把握する。3でじっくり読む。杭打ちとはポストイットを3色使い目印をつけること。 手間なので杭打ちは出来そうにない。新書、ビジネス書オンリーの読み方だろう。 これは本にある索引をじっくり読んで、必要な言葉、面白そうな箇所を選んでよんでいるというもの。……辞書を引くようなリーディング法です。(p105) ★丸谷才一『思考のレッスン』で紹介されている方法らしい。古典、しっかり中身のある書籍でなければ対応できないだろう。 何のためにこの本を読んでいるのか、読む前にしっかり認識しておけば、何気に本をよんでいる時間より格段にスピードは速くなる。(p108) ★目的を持って本を選び、読む。目的地を設定しておくのだ。 ……本当の知的興奮をきっかけに知の体系を理解し、かつそれを形にする「アウトプット型読書」を基本スタンスとしているからに他なりません。(p125) ★アウトプットを意識して行いたい。読書ノート以外にも必要かな? 現在の自分の思考をまとめておきたい気もする。 ノウハウ本は実践をして、自分に合ったものだけを吸収する。……方法は人によって向き不向きがあるからです。(p129) ★他の書でもよく言われていること。自己アレンジが一番長続きする。 行動があって、それを高めていくために読書を手段としてフル活用する。これこそビジネスマンに必須の読書スタイルでしょう。(p133) ★まさに。正論。 「意味ある偶然」を呼び寄せ、壁を乗り越える方法が、このブレーン・ストーミング読書です。(p193) ★テーマとか目的をもってると何気なしに、そのテーマがふっとテレビや本屋などで目につくようになる。アンテナが張れているんだろう。面白い。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ*要点:アウトプッターというのは表層的な表現の下に潜む「ルール」や「ものごとの道理や本質」を見抜き、それを自分の表現方法に転化させ、価値あるものを生み出していく人です。~中略~「みんな、もうインプットで終わっちゃう読書はやめようよ。何かを生み出すアウトプット型の読書に切り替え、自分だけのシステムを構築して、周りを出し抜いちゃおうぜ」ということに尽きるのです。p209~p2010 *参考になったこと:①筆者の情報を知るという行為(ウィキペディア・TOP BRAIN)が理解度を深める②図書館で借りた本を可視化するのに「ブブログ」が使える。③素早く読むために必要なのは「目的意識」。これこそが、「必要でない箇所」を見極めるフィルターになる。④憧れの文体と理想の論理展開を見つける。⑤「本を読む本」M・Jアドラー他 4つの読書スタ イル ⅰ初級:読み書き取得のため ⅱ点検:制限時間内で出来るだけの内容を把握するため ⅲ分析:取り組んだ本を徹底的に読みぬき、血肉とするため ⅳシントピカル:一つの主題について何冊もの本を関連付けて読むこと ⑥レオナルド・ダ・ヴィンチ「まず、はじめに最後を考えよ」
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログインプットだけではなく, アウトプットに重きを置いた読書ハックが紹介されている。 「HACKS!」シリーズではあるが 『整理HACKS!―1分でスッキリする整理のコツと習慣』『TIME HACKS!』 の著者である小山龍介さんではない。 雑感としては,小山さんと比べると質が低い。 「面白くない本は読むのをやめる」というハックがあったのだが, そのハックに従って, 本書を途中で読むのを止めてしまおうかと思ってしまった(汗)。 終盤に入ってから,多少,盛り返した感はあったけど。 「本を本格的に読むのが大学に入ってからなので遅咲きだ」と書いているが, 30歳を越して本を読み始めた私は,「超」遅咲きですなぁ…。 ただ,咲くこともない人もかなりの数いるとは思うけど。 「待ち合わせの場所は書店が最も適している。 待たされても苦痛にならないから喧嘩にもならない。」 これはハックとしてではなく,脚注として書かれていたものだけど, 他のハックよりも,物凄く説得力があるハックだと思われる(汗)。 本書で紹介されていた本(備忘録として)。 『歴史とは何か』E・H・カー 『自分の中に歴史をよむ』阿部謹也 『神々の山嶺』(コミック版)谷口ジロー,夢枕獏
0投稿日: 2013.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ブクログの存在もこの本で知りました。 検索のWEBCAT-PLUS,想 IMAGE BOOK SEARCHもこの本で知りました。読書術として読んでためになることが多かったです。
0投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書その16】最近本を読むのが停滞している自分の読書を活性化するために手に取った本。かなり自分自分で実践していたものが多かった。ブクログの活用もその一つ。やはりアウトプットを意識した読書が大事なのだろう。読むものをすべてを理解するようにするのではなく、メリハリをつけて、何を得るのかを意識して読むことが大事。
1投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ7:2:1のリソース配分は採用。飛ばし読み、速読はいずれ身に付けなければいけないと思うけど、何か気がひける。
0投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ真面目に本の読み方がわからない人の為の良い入門書。読みやすく、本の検索の仕方は今すぐ使えるものばかり。
0投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書習慣の無い人間から熟練者まで、読書を楽しみ実用に活かすためのアイデアが詰まった一冊。 垂直型読書・水平型読書・ブレインストーミング読書・多読の罠など、新しい視点を提供してくれた気がする。 1~2時間あれば読める平易な本で、初心者でも読みやすい。 私がブクログを開始するきっかけを与えてくれた本でもある。 自分の業界内で「読書をしている」というと、決まって「偉いですね」とか「勉強されているんですね」と言われるが、その度に少しの優越感と、フィットネス業界の狭さや浅さを感じる。 周縁産業の事や世界の事も知らずに、集客手法は相変わらずの安売りのみ。 価値を上げる事も考えず、会員数が増えたか減ったかも気にしない現場。 今求められている価値は何か、を知る為にも、読書や旅を通じて、鋭い感覚を磨いていかねばならないと感じた時間であった。
0投稿日: 2013.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ◎1200円 読書に関するアイデアの考えかたはおもしろい。 ●ひとつの事を深く考えるとたんさんの事を考えざるを得ない ●生きるという事は本来、総合的で統合的なもの
0投稿日: 2013.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書のためのハック本。 インプット術、アウトプット術の実用的なものでテーマ毎に掲載されているため、読みたいところだけ読んでもプラスになる本だと思います。 こんだけ、世の中に本がたくさんあると、どのように選択するかといった重要になってきます。 読書のためのブックガイドもありと、次の本を探すのにも楽しめちゃいます。 対象はビジネス書メインであるため、小説などでは、活用できないものもありますので、注意が必要です。
0投稿日: 2013.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本棚に出会うきっかけを与えてくれた、アウトプットリーディングのためのハウツー本。アウトプットを前提にして読み進めて、知識の定着化、応用化をいかに行うかについて読書好きへのマネジメントや速読の方法を紹介しながら見やすく読みやすくまとめられている。
0投稿日: 2012.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログハックシリーズは過去にも何冊か読んでいるが、その中でも一番参考になったのがこの本だ。 「本」というツールは「読む」だけでなく、そこから今後に「活かす」ものだと思った。そのための方法を丁寧に紹介してあるように感じた。 自分は本を読んでいるが、「本を活かす」ことはできていないと気づかされた。私も「本」としっかりと向き合って自分を成長させるツールにしたいと思う。
2投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むのが苦手だった自分が、最近になって本を進んで読むようになった。 ただ、読んだ後に自分なりに噛み砕く事ができないのが悩みで、より本が好きになるための1歩としてこの本を読みはじめた。 読み進めるにつれ、ビジネスの立場からのビジネス書の読み方、捉え方、とあまり関係のない内容も多いかなと思ったが、最終的に「本を読む」という事を超えた「いかに効率良くインプットし、どうアウトプットに繋げていくか」という、まさに整理のつかない自分にうってつけの本だった。 たくさん読めば自分の知識になるかというわけでもなく、逆に本をたくさん読む(だけ)人は自分で考える力が衰えてしまうという。 一度読んだら終わりではなく、その本から学んだこと、学べることは繰り返し見返して自分のものにする姿勢を持とうと思う。 アウトプットも大事。 読み始め当初の自分の悩みに直結する解決方法を見出せた、さらにそこから多くのプラスの要素も得られる良書でした。
1投稿日: 2012.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
HACK本2冊目 本の選択に役立つサイト ・千夜千冊 ・amaztype 美しい! ・webcat 連想機能 ・想IMAGINE Book Search 複数のDBから検索 読書投資基準 70:20:10=既存のビジネス:(既存ビジネスのサポートor新しいビジネス):未知 持続可能な読書の極意 1)知的興奮 (著者とコミュニケーション、友人と共有) 2)おまけ的欲望 環境整備を楽しむ(喫茶店を探す、書斎を作る) 3)検索技術 読書キット 本、ポストイット、マーカーペン、スケッチブックをワンセットにして携帯 行動を高めていくために、読書を手段として活用する 垂直型読書(スペシャリスト)と水平型読書(ゼネラリスト) 思考のホームグラウンド(専門分野)を作る ホームグラウンドの共通点と相違点考える 教訓ノートを作る 自分向けに言葉や法則をアレンジして、スキーマ(知)集を作り、教訓として貯蓄していく 「まず、はじめに最後を考えよ」レオナルド・ダ・ヴィンチ アウトプットのためのインプット(読書) 誰かに説明することを前提に資料を読む 超アウトプットのためのハニカムDB 1)アイデアファイル 2)携帯電話メモ 3)データファイル 4)ブログ 5)教訓ノート 6)名作ファイル
0投稿日: 2012.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ20120730ウェブ書評千夜千冊 ブクログ→脳内の読書情報をウェブで可視化 ビジネス書を読む意味→教訓の獲得。他人の経験から紡ぎだされたスキーマを獲得する事 常に現場検証する。→本当につかえる教訓を取捨選択し自分向けにアレンジ ビジネスマンがいまやる事は、所属している部署のスペシャリストになる 多読型の人は、自分でものを考える習慣を忘れるな
0投稿日: 2012.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読む」を学ぶッ!という観点から本を読むッ! なかなか面白い発想だと思ったッ! この本でこのサイトを知ったので、 このサイトを知っている人は読む必要はないかも? 読書に飽きた時や、読書が嫌な人が読む本…ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ まさに読書の仕方を教えてくれる一冊なのッ! ※ジョジョ語風味に変換しています※
0投稿日: 2012.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の幅を広げるおすすめ本、良書を選択するための検索方法など、活かせる情報がいっぱい。7対3対1の比率で読め、というお話はこれからの指針になりそう。
0投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事を効率化するためのちょっとしたノウハウをまとめた"HACKS!"シリーズの読書版。 このシリーズの良いところは、ただ無味乾燥に効率化を追い求めているのではなく、そこに"楽しさ"が注入されていること。 そもそも"ハック"には、楽しみながら仕事をやろうという思想が根底に流れている。 ”目的をハッキリさせる”、"目次を読んで本の構造をつかむ"、"自分に必要な箇所だけを集中して読む"など、他の速読術本にありがちな技術が紹介されているが、それが何故必要なのか、目的をはっきりさせるにはどうすればよいか、といっ最も難しい動機付けの点までに言及している。 個人的には読書術本の決定版ともいえる一冊。 ---------------------------------------------- ・重要なのは、レビューアーの意見ではなく、自分が抱えている問題を自覚し、少しでもそれに対応するヒントが探せるかです。 ・わたしはこの基準を読書に持ち込んでいて、既存ビジネス領域への書籍投資に70%、既存ビジネスをサポートしうる、あるいは新しいビジネスになりうる領域の参考文献に20%、そして全く未知の書籍に10%を割くように意識しています。 ・簡単に言ってしまえば、速読術とは、キーワードをあらかじめ意識し、その隙間を高速で埋めていく技術なのです。 ・これは本にある索引をじっくりと読んで、必要な言葉、面白そうな箇所を選んで読んでいくというもの。 ・何のためにこの本を読んでいるかのか、読む前にしっかりと認識しておけば、何気に本を読んでいる時より格段にスピードは速くなる。 ・つまり、ビジネスにおける読書は、業務が中心の読書であって、それはビジネスにおけるパフォーマンスの精度を高めていくためのもの。 ・しかし、重要なのは、この教訓をアレンジして自分の仕事にフィットさせることです。 ・そして、多読で一番怖いのは、無意識に本に頼りきって、自分で考えるという行為をやめてしまうことなのです。
1投稿日: 2012.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書論の本が紹介されているので読んでみた。 著者の主張⇒アウトプット@読書の本であった。 主張はどの著作でも、同じようだ。多読、本をたくさん読む、本の中の情報整理方法。インターネットを上手に使っている。読書カードをブログにする手法は改めて感心した。 今回の一番は、例えば、読書論の本を探すときに書店では売れ筋が並んでいるが、図書館では過去の本も系列的に並んでいる、という点。まさにその通りであると思った。 なぜ、情報発信を続けなければならないかが、よく理解できないところである。
0投稿日: 2012.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に30代ビジネスパーソンを想定読者としていると思われる読書本。副題の通り、参考になる読書の方法(多読、ブログの活用、ふせん)のようなTipsも沢山紹介されているが、大人の読書=『アウトプットのための読書』を説いたことが本書の最大の意義かと。今後の読書の参考にしたい。
0投稿日: 2012.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書をする体質になるにはどうすればよいか、そのきっかけとは、そして、読書によりインプットしたものをどのようにアウトプットすればよいかといったことが89という項目に分けてまとめられている。 書かれている内容としては広く知られていることも多く、特に目新しいということはないが、1つの項目について1~2ページという小単位でまとめられているため、非常に読みやすくなっていると思う。 一般の人でも活用できるが、特に多くの情報を必要としてるビジネスマンは読んでおいて損はないと思われる1冊。
1投稿日: 2012.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本でブクログを知りました。 これまで、読書感想を手帳に書いていたのですが、断然便利ですね。 ブックダーツ、ブックストッパー購入します。便利グッズ、あるものですね。
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
導いてくれた本。 ●アウトプットして自分自身の能力としていく。 ●即実践、即行動。 ●自分の思考のホーム・グラウンドを作る。 とても勉強になりました。
0投稿日: 2012.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読む習慣はあったのだけれども、 全くそれが活かせていなかったので読んで見ました。 大学時代に読めば良かったと、今更ながら後悔してます^^; ただ今からでも意識的に読書してみようと思わせる一冊でした。
0投稿日: 2012.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
インターネットで「探して、のぞいて、並べて、比べて取ってくる。そして、これを「読む」ときはすでに編集に入っている。(本文227ページ)」今の時代で「読む」ことの意味を考える。 以下、雑記帳。 「フィールドリサーチ」 高瀬舟 「想-IMAGINE BOOK SEARCH-」 便利な検索サイト。アウトプットを効率化できる。 「読書「70:20:10」モデル」 グーグルの社長、エリック氏が自己の投資基準比として提唱。既存ビジネス70、新ビジネス20、未知の領域10。読書も然り。 「スキャニングとスキミング」 スキャニングは検索読み、スキミングは飛ばし読み。 「最初は薄い本から読む。」 頭が固まってしまったとき、その分野の本を読まなくなってしまったとき、あえて薄い本を読む。 「ポイントを理解するのには、音声や映像も効果的」 今の時代、オーディオや映像は簡単に手に入る。 「自分の最初の本を見つけたら、それらをつなげて、一つの台のような平面をつくる。その上に、これらの本が呼び寄せる別の本を持ってくればいいんです。それはこれらが呼び寄せる人間を持つ、ということでもあります。そして本当にそういう人間が師として友としてあらわれてくるものなんです。(大江健三郎)」 どの本にも必ず参考にした文献がある。その本一冊で完結するものなどほとんどない。 「石の上にも三年」 ビジネスも一人前になるには三年かかる、とのこと。 「まず、はじめに最後を考えよ。(レオナルドダヴィンチ)」 インプットの究極目的。
0投稿日: 2012.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ何のために読書をするのか。 この質問に自分なりの答えを持っていない人は、読んでみるといい。 自分としては、次の3つが参考になった。自分の中では思考が未分化だったところが整理された。 hacks 53. パッションを維持する読書 hacks 59. 「思考のホーム・グラウンド」を作る hacks 68. アウトプットを生むために読む
0投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ元々あまり本を読まない人に、本を読む習慣をつけさせるところから始める内容になっており、すでに多読の人にはその部分はあまり有効ではない。 ブレインストーミング読書はやってみる価値ありそう。
0投稿日: 2012.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
スキーマ これまでの経験から獲得している知識や経験によって裏付けられた物事の法則性 多くの人の共通な普遍的なメッセージが見えてくる。それを見つけるのが喜び 無意識に本に頼らないで自分で考えること。 ルール、ものごとの本質を転換→自分なりの表現→価値のあるものを提供する。 理論の本は事実 実践の本は方法
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方を少しずつ、精度の高いものに変えていかなければと思っている際に読んだ本。 参考になることも多かったし、ネットを使うことで楽しくなったことも多い。 このサイトに辿り着いたのも、この本よりである。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【目的】 ・本を読む際に気を付けるポイントを見つける。 ・アウトプットにつなげる工夫を見つける。 【結果】 ・本の裏表紙に目的、得られたアイディア等を記入していく。 ・得られた内容をデータベース化する。 ・気になる箇所のページをとりあえず折る、線を引く等、しるしを付けておく。 ・いつでも線を引けるように、本に小さいペンを付けておく。 ・線を引いた箇所を本の裏表紙にまとめていく。 ・気になったキーワード「Webcat Plus」「Imagine book search」
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとネタが弱い気がします。 残念ながら、ありきたり感が強いんですけど 最後に有名な本を紹介してくれているのは いい感じ。 これをふくめていい感じかな。
0投稿日: 2012.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に印象的なのは、 読む前に何でその本を読むか、明確にしないといけないこと、 自分の職業のスキルを高めうる本を7割選んで読むこと、 著者がブログもたくさん読むこと。 すぐ実験あるのみ!
0投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログP157:本の情報は自分と照らし合わせる。情報にリアリティを持たせる。 P159:テーマを1つに絞る。1つのテーマを深く考えると色々なことを考えざるをえなくなる。
0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ【Summary】 ビジネスマンの読書はアウトプットの為に行っている。アウトプットを出す為には、多読が基本となる。また、読書はinputであり、outputへ備えなければならない。その為に内容をデータベース化する必要がある。 【Sharkisland's Memo】 ①ビジネスでのoutputは、レシピ(ノウハウ)、素材(データ)、盛り付け方 (プレゼンテーション)に分けて保存しておく。 ②気になることは想-IMAGINE で調べる。千夜千冊で調べる。 ③速読の基本は、目次、流しながら重要箇所をpickup、重要箇所を精読
0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕がブグログを始めるきっかけとなった本 本=読み物 という概念を覆してくれた! 本=読む+アウトプットしなければ、その知識が活用される事はない。 アウトプットする事で自分の頭の中で内容が整理され、その後もその本の知識は、自分の血となり肉となる。 本を娯楽としてではなくその後の仕事や人生に効果的に役立てたいという人には是非とも呼んでほしい!
0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本をさらに楽しくさせる本 著者が網羅した本の読み方、活用方法、情報整理の方法をこの一冊にまとめている。 本はアウトプットしなきゃ意味がない。さらにその情報を整理しておく事で後々の仕事の役に立てるなど本を役立てるノウハウが満載。
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「目的意識の大切さ」は理解していたが、「不必要な情報を切り捨てる勇気の大切さ」を気づかせてくれた。 ノウハウ本は実験して、自分に合ったものだけを吸収する。 P129 この点は、共感できるが、もう一歩踏み込んで、自分に合わないモノを自分流にアレンジすることを提案したい。 まずは、ノウハウ通り → アレンジ で学んだノウハウを進化させることも大事だと思う。
0投稿日: 2011.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログライフハックが好き+速読できるようになりたい、というバックグラウンドから手に取った本。 一番重要な気づきは、速読における読書の捉え方。 通常の読書では一冊の本と向き合い、注意深く読み進めていくのが普通だ。つまり、当たり前だけど【対象は一冊の本】となる。 対して速読では、読書を通して如何に重要な知識を如何に効率的にインプットするか、という考えの元に立っていて、一冊の本という概念が希薄。つまり【読書を通して得られる知識全体】と考えていい。 この感覚を持てただけで読んだもとが取れた気がする。 単なるハック本としても豊作。 「ポストイットハック」「思考のホームグラウンドを作る」「インデックス・リーディング」など、簡単に実施できて効果がありそうなハックがあり、ためになる。 また、「70:20:10の法則」「垂直型読書・水平型読書」など考え方に関する示唆も得るものが多かった。
0投稿日: 2011.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本の中での読書は、主に「実学」としての読書~要するに仕事やキャリア、スキルをアップするための読書を想定して書かれている。しかしながら、一部では松岡正剛さんの「千夜千冊」など読書そのものの楽しみ、醍醐味を享受しうるようなサイトも紹介されている。 まずは著者の声が録音されている媒体(web, CDなど)から、生の声を聞いて、その人の人柄や人生観を感じた上で、読書してみる、、ということから始まる。 その後、「書評・ブックレビュー検索エンジン」「想ーIMAGINE Book Search」など、読書生活を進める上で役に立つサイトなどがたくさん紹介されてくるので、そういう”情報”も楽しい。 キャリアの築き方として著者は、「まず所属部署のスペシャリストとなるべく垂直型読書を続け、専門的知識を体系的に体得すること。その後に専門の外に出て、あるいは業界の外に出て議論をし、そこでえた知識を自分の思考のホーム・グラウンドにポジティブ・フィードバック」せよ、、と訴える。 そのための読書~それにかける時間割合として著者は、自分の専門:その周辺:未知の分野=70:20:10としている。 そのほか、自分用の読書セット(ボールペン、マーカー、ポストイットなど)を作ることなど、読書ハックならではの小道具的楽しみも忘れない。個人的には、読書メモをPCで作る際に、本のページを押さえておく「BOOK STOPPER」(トモエそろばん)が重宝している。
0投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログただ「読む」というインプットだけの読書ではなく、読んだ内容を効率よく形にする"アウトプット"としての読書法を紹介したビジネス本。 30代のサラリーマンを対象とした内容ですが、文献を読んでその内容をアウトプットすることは、大学生にとっても大切な技術。インターネットを活用した方法も多く紹介されています。ブクログのことも書いてありますよ(笑)。 話し言葉で書いてあるので、さっくり読めますし、重要なことは太字になっていますので、時間のない忙しい学生さんも、レポートを書く参考に読んでみてはいかがでしょう? ※引用した「書店」と「図書館」の違いについての話は、図書館を利用しない人にぜひ知って欲しい内容。学生さんの中には、本を探してこいというと、書店をざっと見て「レポートに役立つ本がなかった」と言うとお嘆きの先生も多いとか…。 【今月のおすすめ/2011年11月】
0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログよいアイデアを得るための 最も手軽で、安価な方法は 読書だと思います。 いろいろな情報が、 いろいろなメディアで発信されていますが、 「書籍」は、1つのテーマに関して、それなりの情報量を 分かりやすく体系立ててまとめられています。 一方、雑誌、TV、WEBなどでは、断片的な情報が多く、 全体を把握しにくい傾向にあります。 勉強会やセミナーは、内容のいいのもが多いですが 高価格で比較的しきいが高くなります。 本日ご紹介する本は、 いいアイデアや結果を得るための読書、 つまり、インプットではなく アウトプットに向けての読書について書かれています。 ポイントは 「自分で考える」 読書というと、 一通り読んで、”ああ面白かった” で終わってしまうことが多いのではないでしょうか。 しかし、これだと何も自分で考えたことにならず アウトプットにつながりがりません。 アウトプットするには”自分で考える”ことが必要です。 「何度も眼を通す」 本は1度読んで終わりではもったいないです。 なぜなら、人間は必ず忘れるからです。 ざっくりでもいいので、 何回か目を通すことで、記憶に残る確率が上がります。 私の場合は、最初にざっと目を通して気になったところに付箋を貼ります。 それから、付箋部分を見直してマインドマップにまとめていきます。 そして、マインドマップを見ながらメルマガを書いていきます。 これを一気にするのではなく、日を開けて、できるときにしています。 これだと、少なくとも日をあけて3回は見直していることになります。 「構造図」 企画書は重要なアウトプットの一つです。 企画書作りで最も大切なのは、 相手にこちらがやりたいことを 図解化してわかりやすくみせることです。 文書だけでなく、分かりやすい図を書く ということも重要なスキルになります。 本の中で分かりやすい図を見つけたら 参考にしましょう。 「朝はアウトプット」 最近、歳のせいか、 夕方から夜にかけては、 考える仕事をしようとすると 頭がまとまらないことが多いです。 逆に朝は、いろいろ考えることに抵抗を感じません。 目覚めて脳が高速回転し始めるタイミングこそ、 アウトプットにつなげる作業に向いています。 夕方以降はできるだけ単純作業をしましょう。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 理論、技術は道具。それらを駆使して、アイデアを形にし、結果を出す者のみが評価される 重要なのは、自分が抱えている問題を自覚し少しでもそれに対するヒントを探せるか 読書投資70:20:10モデル=既存領域=70%、領域拡大=20%、未知の領域=10% 10分以上の時間があれば、本を取り出して、短期決戦で読み始める ちょっとでも読書をしたいのであれば、思い切ってプチ家出をする 「意味ある偶然」=自分の専門外でも、そこから示唆を得ることはたくさんある 「まずはじめに、最後を考えよ」=アウトプットを生み出す思考プロセスの本質 常に資料は必ず誰かに説明するという前提に立っておく 「朝はアウトプット」=目覚めて脳が高速回転し始めるタイミングこそ、アウトプットにつなげる読書に当てるべき 本は原則として忙しい時に読むべきもの。まとまった時間があったらものを考えよう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ 1 読書のめりこみハック!―本に恋する、きっかけのマネジメント 2 楽しいビジネス読書ハック!―リーディング・ハック 3 超速読ハック!―スピード・リーディング・ハック 4 読書体質になるリーディング・ハック! 5 キャリアを作るリーディング・ハック!―ビジネス・マルチ・リーダーを目指して 6 ドキュメントのリーディング・ハック! 7 超アウトプット生産のためのデータベース・ハック! appendix 最強の『読書論』ナビゲーション・リスト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆マインドマップ◆ http://image02.wiki.livedoor.jp/f/2/fujiit0202/de18bc4cfa9946e6.png
0投稿日: 2011.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【再読】『本屋さんに行くと、何を読んでよいか分からなくて途方に暮れる』『本を読みたいけど、何を読んだらよいか分からない』という人は手に取るのをおススメします。読書論、知的生産の方法についての本や著者の理論を網羅的にまとめてあり、読書論の解説みたいな本。本を読むテンションが下がったら読むと、本を読みたい!と思えるかも。 ビジネス本なので、1テーマごとに短くまとめてあり読みやすい。重要なところは太文字(最近こういうの多いけど、苦手・・) 共感!したところ ◆清水幾太郎『本はどう読むか』の中で 面白くない本は読むのをやめる。 面白くない本は縁がない本。 これは、私が思っていたこと!同じことを考えているとはねぇ。 というか、読書に対してハードルが低い人はみんなそうかもしれない。 取り入れよう ◆著者のブログを読む ◆勝手に読書キャンペーンを展開する。 今月は環境学を頑張ってよむぞ!とか。 ◆読書投資基準 10パーセントは全く専門外の本を読む ◆検索サイトを活用 Webcat 書評ブックレビュー検索エンジン ◆著者が書いている本を全部読む 読もう 丸谷才一 思考のレッスン 小ペンハウエル 読書について
0投稿日: 2011.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「アウトプットを前提にした読書」という著者の視点は勉強になった。 また、自分のデータベース(著書のなかではハニカム・データベース)を作るということは、最近自分が何となく実践し始めたことであったので、大いに共感でき、また参考になった。 これからは、そのデータベースを如何にアウトプットに繋げるか、そのためのデータベースの基盤やルール創りが自分にとって大切になってくると思う。 あと、なにげに本の装丁が好き。
0投稿日: 2011.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書に使える様々なネット上のツールや、インプットではなくアウトプットに重きをなすこと、7-2-1の配分で専門、周辺、そして専門外の本へ投資する、「読書投資基準」などのアプローチ。理路整然としていてビジネス書を読むのに役に立つハック満載。
0投稿日: 2011.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログを知るきっかけをくれた本です。アウトプットをどのようにしていくか考えて行きたいと思います。 難しいことは言えませんが、本を読む方法として、色んな方法があるんだな~と参考になった本でした。
1投稿日: 2011.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログbooklogを知るきっかけになった本。 これを機に,インプットだけでなく,アウトプットをするための読書に切り替えたい。
0投稿日: 2011.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログbooklogを知るきっかけになった本 ビジネス書を読むのは限られた時間内で最大のアウトプットを出すための読書であり、その方法論や考え方などが記している。
0投稿日: 2011.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログを知るきっかけになった本。今までは読んでおしまいだった私。これからはアウトプットを生むための読書に切り替えていきたい(o^^o)
0投稿日: 2011.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むのに、考えてしまった人に、アウトプットを出したいヒトに。 個人的に面白かったのは、ブックダーツ、これ、Amazonで買う予定です。 これは、しおりよりも、いいよ。
0投稿日: 2011.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ■面白かったこと ・ブログで著者と直接話をする ・自分がこれまで行なってきた仕事を一度総括して、気づきを得る ■次に読む本 ・本を読む本 ・知性の磨き方
0投稿日: 2011.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログを始めるきっかけ本。本を片手に旅に出る、図書館の近くに引っ越す、書店の近くに行きつけの隠れ家を開発する、はじめは薄い本から読み始める、面白くない本は読むのを止める、「教訓ノート」をつくる、ブログで著者と対話する・・・などなど、本の多様な楽しみ方を提案。ひとつの読書術に固執してないので、自分にあった方法を取り入れればいい。使える!
0投稿日: 2011.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これは、今までに読んだことのある読書法の本の中でもかなりユニークな切り口の本で、とても面白かった。 特に出だしから、インターネットを活用してしまうところが、現代的であり、さすがHACKSシリーズの著者!!と衝撃!! また、きっかけマネジメントは「アンカー」と「トリガー」をうまく使って集中状態を作り出す手法であり、とても参考になる。 本とは関係ないが、自宅図書コーナーがうらやましい。 自分も作りたいと思った。
0投稿日: 2011.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのシリーズ、結構楽しみにしていて、シリーズが発売されるたびに読んでいます。 今回「読書」ということでしたが、 ネタ的にちょっときついかと 思わずにはいられませんでした。 それなりに、なるほど っということあるのですが。 でも、考えさせられたのは、読書(インプット)して、それからどうするのという点ですね。 アウトプットしなければ、意味がない。 ううん。確かに。 と少し反省材料となったのは良かった。
0投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆現代のビジネスマンが時代においていかれないための、アウトプットに直結した読書術。 ◇ビジネスの現場に出て気づかされるのは、理論も技術もすべては道具で、それらを駆使して、アイデアを形にし、結果を出した者のみが評価されるということです。 ◇文章の行間からにじみ出てくる質感というのは、著者本人の生まれや人間関係や生き様を知っていて始めてつかめるもの ◇読んだ本の感想は著者に真っ先に伝える。著者と簡単に直接会話ができる時代だからこそ、これを習慣にしてみることをお薦めします。 ◇既存ビジネス領域への書籍投資に70%、既存ビジネスをサポートしうる、あるいは新しいビジネスになりうる領域の参考文献に20%、そしてまったく未知の書籍に10%を割くように意識しています。 ◇大切なのは、獲得した他人の教訓を常に現場検証すること。そして、その結果を自分のビジネスの規則として作り変えることです。 ◇会議でも資料でも、自分が作成した資料でも何でも、その資料を必ず誰かに説明するという前提に常に立っておくと、内容把握の度合いが格段に違ってきます。
0投稿日: 2011.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログを知るきっかけになった本。 ターゲットはビジネスマンのようだけど、読書を楽しむ人にも参考になる。 なるほどなぁと思うことがたくさんあって、 私の中の読書欲を刺激してくれた。 特にブクログを始め、読書のために使えるツールが紹介されているので、 今後大活躍しそう★ 情報リテラシーを学ぶ第一歩になるのではと思うので、 大学の新入生や新社会人にぴったりな本だと思う。
0投稿日: 2011.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むための本としては分かりやすかったと思う。 著者がメディアに精通しているせいか手に取りやすい表紙や分かりやすい文章などが印象的。
0投稿日: 2011.03.31
