
ユートピア
トマス・モア,平井正穂
岩波文庫
どこにも無い国
著者トマス・モアが、船乗りラファエル・ヒスロディに語らせたユートピアというところは、自由な精神と自己規律でもって正しく生きている人々の国でした。 都市は国中に均等に散らばって存在し、都市間はわざと間隔が開けられています。それは、農村部を配置し、自給が可能なようにと配慮されているようです。 農村部の農場に、都市部から人が2年ごとに交代で集められ、農耕が営まれています。これは旧ソ連時代の集団農場を想起されますが、旧ソ連の指導者たちがユートピアをモデルにしていたとしても不思議なことではないと思いました。 ユートピアは島国であるが、他国との貿易によって莫大な利益を上げています。しかし、ユートピア人は財産の私有制を取っていないため、特定の個人に財が集中することは無く、またそういう野心を抱くものもいません。貿易で得られた利益は、金として国内に蓄えられるが、一部については他国へ借款として与えられ戦時の交渉材料として使われます。 金銀に対して国民が野心や邪心を抱かないように、金銀を汚らわしいものとして扱う、つまり金は便器として使われたり、奴隷を現す印に使われたりしている。 現実と理想の折り合いをつけようと真剣に考えていたことは、戦争に対する嫌悪感や戦争に対する現実的な対応方法の記述に強く感じられます。戦争による名誉こそ不名誉なことは無いのである。従って戦争は可能な限り回避されるように試みられますし、戦争が始まったときでも流血なしで解決されるように策が打たれます。貿易によって得られた莫大な資金を使って、敵対国と戦争回避の交渉が行われます。あるいは、敵対国の叛乱分子に資金を提供して、相手国を混乱に陥れます。いざ、戦いが始まると、初めに前線に向かうのは、お金に物を言わせて集めた傭兵たちです。ユートピア人の損害をできる限り最小化しようという思惑が働いています。しかし、傭兵をしても相手を打ち倒すことができない場合に、ユートピア人は戦争に嫌悪を感じつつも逃亡という不名誉は考えず、自らが相手との白兵戦に勇気を持って立ち向かうのです。それは家族とて同じで、前線での戦いに家族も同行し、戦士と生死を共にするのです。 ユートピアとは、ラテン語を使ったトマス・モアの造語で、どこにも無い国という意味だそうです。西暦1500年前後のヨーロッパの実情を見て危機感を抱いていたトマス・モアが、理想の国として描いたものだそうです。最小限の法律で国が円滑に運営される国、徳が非常に重んじられている国、物が共有されているためにあらゆる人が物を豊富に有している国、それがユートピアであした。トマス・モアが現実世界を直視して問題の根源を洞察したとき、財産の私有が認められ金銭が絶大な勢力・権力を振るうようなところには、正しい治世と社会的な繁栄はありえないという意見に辿り着いたのでしょう。
1投稿日: 2014.06.08
方法序説
デカルト,谷川多佳子
岩波文庫
良識から出発して哲学原理へと至る
デカルトは、「良識はこの世でもっとも公平に分け与えられているものである」という考えに立脚して、彼の偉大な思想を展開しています。良識とは、理性あるいは理性の働きのことで、知識ではなく判断力のことを指しています。 人が遍く(あまねく)良識を持っていることはどうやって知ることができるのでしょうか。それは、何も学問を修めたことの無いような市井の住民をみればわかるのだとデカルトは言います。市井の住民にとって判断を誤ることは、その結果によっては自分自身への重大な罰が下ることを意味し、従って文字通り真剣な判断が要求されるし、実際に自分自身に害が及ばないような判断が正しく行われている事実からも知ることが出来るのです。 では、人が皆充分に良識を持っているのに、何故人の意見は様々に異なり、意見の違いが生じるのでしょうか。それは、良い精神を持っているだけでは充分でなく、それをよく用いることが大切であり、人は正しい思考の道筋を辿っていないから誤った答えに辿りついたり迷って答えが出せなかったりするのだとデカルトは言います。精神を正しく用いなければ、「大きな魂ほど、最大の美徳とともに、最大の悪徳をも産み出す力がある」のであり、周囲に災厄さえもたらすのです。また、誤った思考の道を足早に進むことよりも、思考の正しい道をゆっくりと確実に進む方が、はるかに目標に向かって前進することが出来るのです。精神が正しい道を歩く方法、それをこの著作でデカルトは説明しています。 デカルトは、この考え方に既に若い頃(23歳)に到達していました。しかし、彼は、哲学において自分が速断による誤りに陥るのを危惧して、数十年もの間修練を積み、自らの成熟を待ち、自分の考えに誤りがないことを確かめるのです。「全生涯をかけて自分の理性を培い、自ら課した方法に従って、できうるかぎり真理の認識に前進していく」。そして、デカルトの哲学原理へと導かれたのです。 私は考える、ゆえにわたしは存在する(ワレ惟(おも)ウ、故ニワレ在リ) 当時の学問書がラテン語によって書かれていたのに対して、この著作はデカルトの信念によってフランス語によって著されています。学問を修めた人たちは古い書物に書かれたことだけを妄信しており、理性を働かせていないのに対して、市井で生きる人々は理性を自然に働かせており、デカルトの思想を正しく判断することが出来ると考えたからでした。 この著作は、精神が正しい道を歩む方法を与えてくれます。他者の知を盲信せず、自らの理性だけによって思考し、答えを導き出すことです。原理としては簡単ですが、実践することの難しさを知るとき、デカルトという人物が一生を掛けてこの原理を徹底的に実践した事実に畏敬の念を禁じえません。
3投稿日: 2014.06.08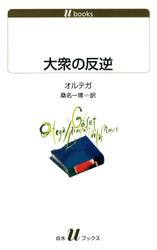
大衆の反逆
ホセ・オルテガ・イ・ガセット,桑名一博
白水Uブックス
近代科学と大衆化の力
オルテガは、社会で大衆が完全に社会的権力の座についている事実を指摘し、大衆は自分自身を指導することもできず、まして社会を支配することなど到底無理なのだから、この事実は社会が危機に見舞われていると警告しています。 オルテガは、大衆という言葉を「平均人」という意味で使っていますが、今の社会に生きるほとんど全ての人はこの部類に含まれてしまうと思います。オルテガは社会を構成する人々を優れた少数者と大衆とに分けて考えています。優れた少数者は自らに多くのことを課して困難や義務を負う人々であるのに対して、大衆は自らに特別なことは課さず、与えられた生をただ保持するだけで自己完成の努力をしない人々です。これは、貴族と平民という分け方とも異なっています。 世が大衆化するまでは、政治は優れた少数者によって舵取りがなされてきたのです。しかし、大衆化した世界では大衆が政治の座に就いています。大衆は自ら社会を支配することは無理だというのに、社会の中心に就いているのです。 大衆とは何者でしょうか。オルテガは、大衆の典型を近代の知識人の代表である科学者に見るのです。科学者は大衆人の典型とされていますが、それは偶然のせいでもなければ、科学者の個人的欠陥によるものでもなく、科学(それは近代文明の基盤であるが)そのものが、科学者を自動的に大衆に変えていくのだとオルテガは主張しています。 科学者は近代の原始人、近代の野蛮人になってしまっています。ガリレオなどの数世紀前の科学者は別として、近代の科学者は、良識ある人間になるために知っておくべきことのうち、ただ一つの特定科学を知っているだけで、しかもその科学についても、自分が実際に研究している分野にしか通じていないのです。近代は科学によって物質的な豊かさを実現したのですが、同じ科学によって人が大衆化されてしまったのだというのです。深い洞察によって導き出された鋭い意見だと思います。
1投稿日: 2014.05.10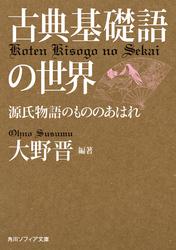
古典基礎語の世界 源氏物語のもののあはれ
大野晋
角川ソフィア文庫
源氏物語の言葉と宮廷人の精神世界
源氏物語を読むことは日本文化を愛する人にとっての憧れですが、原文で読むのは研究者にとっても難しいことですから、一般人にはいかに難解なことでしょうか。実は古典語には未だに言葉の意味が不明なものが数多くあり、中には、紫式部がその言葉に込めた重要な意味を、研究者でさえ捉えきれずに見過ごしてきたものもあるそうです。本著で扱う「モノ」も、研究者達に見過ごされてきた言葉の一つです。 「モノ」というと現代では「物体」のことを指して使われますが、これとは異なる用法として、「彼はモノの分からない人だ。」というような例もあります。これは、「世間の道理が分からない人」ということを意味していますが、実は古典の世界で「モノ」は「物体」とは異なる意味で使われているそうです。 古典の世界で、「モノ」は個人の力では変えることのできない「不可変性」という意味をもちます。運命、人が動かしがたい事実という意味にも取れます。「もののあはれ」というとき、「人の世のさだめのあわれさ」を伝えています。特に源氏物語は男と女の恋の物語でありその成り行きを語るものですから、「男と女の出会いと別れのあわれさ」という意味に重心を置いて使われています。源氏物語に於いて、人生とは男と女の相逢うことと相別れることに他ならなかったということでしょうか。 「モノ」の意味を正確に把握していくと、「平安時代の宮廷人たちがいかに規則・儀式などの社会的制約に縛られて生活していたか、人生あるいは人間の運命の不愉快や深い恐怖感をもって日常を生きていたかなど、当時の宮廷生活をそこに生きる人々の精神の世界を垣間見ることができる」のです。
1投稿日: 2014.04.20
遠野物語・山の人生
柳田国男
岩波文庫
人間の根源に関わる事
遠野地方に住む人がその地方に語り継がれている話として語ったものを、柳田国男が記したものです。素朴で簡潔な文体で、脚色などなく、なるべく語られたままを伝えようとしてあります。山男や山女の話、マヨイガと言って山中に現れる富の館の話など、様々なものがあり、一つ一つの話を丹念に見ていくと、物語としても面白いものが並んでいます。 柳田国男によれば、伝説や俗信には必ずや深い人間的意味があるはずで、柳田国男はそれらを根気良く収集し、掘り起こして行ったのです。これらの話を単なる田舎者に伝わる他愛もない話と片付けるのではなく、話が長い年月に渡って伝わっているからには何らかの意味がそこに隠されている、それは何だろうかと著者は問うています。 現代の科学的な基準で、切り捨てられてしまった世界が、当時の遠野にはまだ残っていました。科学的な視点で見たときに、合理性がないと切り捨てられた世界の中に、何か心の中の世界に、実は人間の根源に関わる事柄が潜んでいるのではないのでしょうか。科学的合理性からいうと、幽霊などは全く見向きもされない存在となっていますが、しかし、深夜の山奥に一人取り置かれたとしたら何か得体の知れない恐怖を感じるでしょう、それは幽霊という説明とは違うかも知れませんが、我々が実体験する何かの現象を現していると思います。そのような科学的には分析できないけれども、確かに人間が経験している世界が存在しているのではないでしょうか。そういうことを、遠野物語のような本を読むときに改めて考えさせられます。
1投稿日: 2013.12.28
茶の本
岡倉覚三,村岡博
岩波文庫
「不完全」を崇拝する
岡倉覚三(岡倉天心)は、日本美術院を創設した、明治日本における美術の開拓者です。本書は、岡倉天心が英語で書いた"The book of tea"を村岡博が訳したものであり、茶会のことに触れながら人の道を語り、芸術鑑賞にまで広く及んでいきます。 茶には不思議な魅力があって、人はこの味を愛さずにはいられないのですが、真に茶を愛でるには、深い精神性が必要なのです。 古代中国において茶は飲む薬とされていましたが、茶が粗野な状態から洗練された域へと達するには、唐の時代精神を必要としたのだそうです。8世紀に出た陸羽という人が茶道を開き、著書「茶経」に於いて茶道を体系立てました。 宋代には抹茶が流行し、新しい茶の流派が生まれましたが、茶道として確立するには、道教や禅宗の教えを必要としました。茶道の中心には、本当に大切なことは完成に至る過程であって、完成したものではないという思想があります。宋代の流派は、モンゴル帝国による侵略で中国では失われてしまいましたが、日本に受け継がれていきます。 茶は、南宋へ禅を学びに行った栄西禅師によって1191年日本へと伝えられました。禅とともに茶の儀式も日本中へと広がっていきます。中国ではモンゴル襲来で、茶道を追究する文化は中断しますが、日本において継続発展されます。茶は単なる飲む形式の理想化という枠を超え、生きる術に関する精神性を追究する道となっていきます。 岡倉は茶道の奥義を「不完全なもの」を崇拝することだと言い切っています。 「茶道の要義は『不完全なもの』を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから。」 「不完全なもの」とは何でしょうか。それは、茶会に於いて、参加者たちによって何か完全に近いものを成就しようと試みられることを指しているようです。道教に於いては、「完全そのもの」ではなく、完全を求める過程に重きをおいています。 ここで「不完全なもの」という時には、完全を目指していることが暗に含まれています。もし、「完全そのもの」を目指していなければ、それはただの混沌でしかありません。岡倉は「不完全」について次のようにも言っています。 「真の美はただ、『不完全』を心の中に完成する人によってのみ見出される。」 茶室に入った人は、その精神世界において、茶室の造り、掛け軸、花などと一体となり理想世界を瞑想します。「不完全」を成就するために日本人によって追及された精神性の現れです。完全を追い求めて、「不完全なもの」を一期一会に成就すること、そういうことを語っているように感じました。
0投稿日: 2013.12.23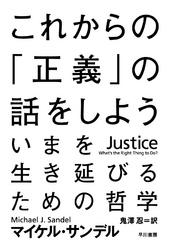
これからの「正義」の話をしよう ──いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル,鬼澤忍
早川書房
幸福、自由、美徳から考え直す正義
正義とは何でしょうか。書斎の中で思弁的に正義を語ることはできるかもしれませんが、実際に社会に起きている複雑で泥臭い毎日の事件に即して、正義とは何かを考えるのは難しいと思います。本書では、幸福、自由、美徳という正義の基盤となる考え方を道標(みちしるべ)としながら、読者は正義とは何かを探る旅へと導かれます。 世の中では、社会の最大幸福を追求すべきだとか、自由を尊重すべきだとか、言われるような気がします。しかし、自分を振り返ってみると、ある問題では皆が幸福であるべきだと考えているのに、別の問題では自由を尊重する立場に回ったりして、一貫性に欠けた幸福や自由を尊重していることに気がつきます。改めて、正義とは何かを考えさせられます。 幸福の最大化はわかりやすい考え方ではありますが、この考えを追求すると、人は大多数のために少数者の権利さえ犠牲にするという考えに陥りがちです。果たして、人権をそういう形で侵してもいいのだろうかということが問われます。 そこで人権を尊重する自由という考え方が出てきます。ところが、自由が拠って立つ基盤となるのは自己を所有しているという考え方ですが、この考えを突き詰めると、自分が同意さえすれば自分の命を絶つことが許されるという議論に陥ってしまいます。果たしてそういうことは許されるのでしょうか。 これらの考え方に対して、カントは自己所有とは異なるものに基盤をおいて彼の理論を作り上げたそうです。それは、人間は誰でも理性を持っていて、理性によって自ら行動することができますが、理性こそが人間の尊厳の基盤でもあるということです。さらに、人間は尊厳ある存在であるのだから命を絶つことは許されないというのが、カントの考え方です。 しかし、サンデルは、この確固としたカントの考えにも満足しません。カントの考えは余りにも理想的過ぎて実際の人生で立ち向かう現実との乖離がありすぎるということでしょうか。理想的な考えで正義が論じられるときには、人々が属している文化の美徳のようなものは無視されますが、果たしてそれでいいのでしょうか。自らのアイデンティティを形成してくれた社会から切り離された正義、ある意味非常に抽象化された正義に従うことが正しいのでしょうか。サンデルは、自らの人格形成に大きな影響を与えたコミュニティの道徳的な重荷と重要性を担いつつ、自由と向き合うことができる道を探しているのです。深い洞察と思索によって裏付けられた確固とした考えで、強い感銘を受けました。
5投稿日: 2013.11.24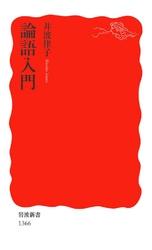
論語入門
井波律子
岩波新書
孔子の魅力
論語は、主に孔子とその弟子達との対話が書かれていて、孔子自身の著作ではないですが、孔子の思想がよく現れています。入門者でも読みやすいですが、奥は深いものです。思想は定義してしまうと、言葉に固定されてしまい、形骸化し勝ちですが、対話の形で語られる思想は形が完成していないからこそ、いつまでも生きた力を有しているのだと思います。読む者の器に応じて書物が話しかけてくれる、そのような書が論語なのかもしれません。 本書は、著者による視点、「孔子の人となり」、「考えかたの原点」、「弟子たちとの交わり」、「孔子の素顔」によって、収録した構成となっていて、孔子の人物像が浮き彫りにされます。 孔子が生きた春秋時代後半は群雄割拠する戦乱の世でしたが、孔子は仁愛と礼法を中心とした節度ある社会の到来を目指していました。孔子は弟子を引き従えて諸国を巡る遊説の旅に出ましたが、孔子の唱える理想主義を受け入れる君主はいませんでした。それでも、著者が言うように、孔子は「理想社会の到来を期して弟子たちを励まし、不屈の精神力を以て長い旅を継続した。恐るべき強靭さというほかない」人物でした。 孔子の魅力は、「身も心も健やかにして明朗闊達、躍動的な精神の持ち主であった」ことや、「いかなる不遇のどん底にあってもユーモア感覚たっぷり、学問や音楽を心から愛し、日常生活においても美意識を発揮するなど、生きることを楽しむ人だった」ことでした。 本書で紹介されているのですが、弟子の1人曾子が論語に残している言葉があります。 士以不可不弘毅。 任重而道遠。 仁以為己任。 不亦重乎。 死而後已。 不亦遠乎。 君子たるものは大らかで強い意志をもたねばならない。その任は重く、道のりは遠い。仁愛の実践を自らの任とするのだから、なんと重いではないか。生涯をかけて完了させるのだから、なんとはるばる遠いではないか。 高邁な志の力強い言葉ではないでしょうか。孔子が、弟子の言葉を通して、真正面を向いて人生の道を堂々と歩く者を励ましてくれているような気がします。
1投稿日: 2013.11.10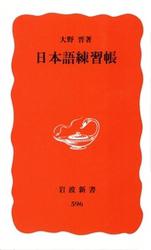
日本語練習帳
大野晋
岩波新書
日常の言葉を深く理解する
日本語をもっと理解して使いこなしたい、そう考える人たちの為に書かれた日本語勉強の本です。理論の説明ではなく、練習問題を解く形式で勉強をしていきます。問題を考えてみて、答えを書いてみて、日本語の基本的な考え方が身についてくる本です。 難しい言葉や漢字は出てきません、代わりに、日頃使っている言葉や文章が問題になっています。簡単なようで、よく考えると答えられず、自分の理解が曖昧なままであったことに気付かされます。(十分に理解していなくても、それなりに使えるのが母国語なのかもしれません。) 基本的な単語や、意味が似ているものを比較すると、それぞれの単語が根幹に持っている意味を理解することが、単語の意味を掴むのに重要なことだと改めて教えられます。 多くの言葉や文章を知っている人は、文章の良し悪しを的確に判断できるそうです。それは美術品の目利きにも似ています。良いと感じる文章を熟読すること、良い文章と評判のものを多く読んでみることがいいそうです。
1投稿日: 2013.10.19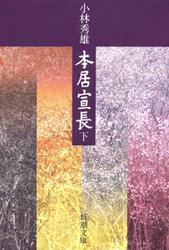
本居宣長(下)
小林秀雄
新潮社
古事記のこと
本居宣長の大きな業績のひとつである古事記研究についても書かれています。 古事記は神代について書かれたものであり「源氏物語」のような物語とは違いますが、この点が古事記を読む者を混乱させます。理性で理解できない神代の伝説(つたえごと)をどう扱うべきか、あるいはどう折り合いをつけるべきか、宣長と同時代の学者にとっても大きな問題でした。 宣長は、源氏物語研究を通して得られた道(方法)を真直ぐに歩いて、行ける所まで行ってみたのだそうです。次のように書かれています。 「忍耐強い古言の分析は、すべてこの『あはれ』の眺めの内部で行われ、その結果、『あはれ』という言葉の漠とした語感は、この語の源泉に立ち還るという風に純化され、鋭い形をとり、言わばあやしい光をあげ、古代人の生活を領していた『神(あや)しき』経験を描き出すに到ったのである。」 それは、古事記を頭で解釈することなしに、ありのままに読んでみて、自分の精神世界に映ずる情景を描き出したのではないかと思います。同じように、小林秀雄が本居宣長の精神世界に奥深く分け入って、我々に偉大な精神を描き出してくれています。
2投稿日: 2013.10.19
マンデリンさんのレビュー
いいね!された数90
