
木曜日だった男 一つの悪夢
チェスタトン,南條竹則
光文社古典新訳文庫
詩人の冒険活劇
ある日の夕暮れ時、それはこの世の終わりが来たような夕焼けで、ロンドンのサフラン・パークで詩人ガブリエル・サイムはルシアン・グレゴリーと詩的な会話をしていました。グレゴリーには誰にも明かされなかった秘密があって、サイムは誰にも言わない約束の下、その秘密を聞くことになりました。そしてサイムの冒険が始まります。 荒唐無稽ともファンタジーとも言えるような冒険活劇が続き、次から次に新しい事実が現れては状況が一転します。息をつかせぬ展開に身を委ねると、一気に巻末まで読み進められます。 物語の中央は冒険活劇なのですが、初めと終わりは詩的で思想的な雰囲気に満ちていて、何かを暗示しているようです。一通り読み終わった後に、冒頭に置かれた友人ベントリーに宛てた詩を読み返してみるとき、著者の心の底にある気持ちが微妙に伝わってくるように感じました。 ベントリーは、著者チェスタトンの幼いころからの友人。チェスタトンの幼少や青春の(本人にとっての)暗黒時代に心の支えとなってくれた友人らしいのです。詩を読み返してみると、この冒険活劇は、チェスタトンの孤独な青春時代を象徴的に表現したものに思えてきました。楽しくも少し考えさせられる物語です。
2投稿日: 2014.11.22
ソクラテスの弁明 クリトン
プラトン,久保勉
岩波文庫
真直ぐに生きる
哲学者プラトンは、彼に対して強い影響を与えた師ソクラテスがいかに断固とした決意で裁判に臨み力強く自己の信念を貫いたかを書いています。ペロポネソス戦争に関連してアテナイ(アテネ)市民から告発されたソクラテスは、裁判において毅然として反論し、自分自身が一生を賭けて貫き通してきた信念を曲げようとはしません。ソクラテスの弁明の言葉のみが記されているだけなのですが、読む者の目の前には、ソクラテスという傑出した人物の確固として揺るぎない人格やその人生までもが現われるのです。 目の前の困難から逃げて生き延びようと思えば国外への逃亡もできたはずなのに、ソクラテスは裁判から逃げようとはしませんでした。裁判において自己を辱めて惨めな命乞いをすれば助かったかもしれなかったのに、ソクラテスはそれもしませんでした。安全に隔離された書斎において哲学を考えることはできるかもしれないですが、人生の最大の危機において自分の哲学を貫き通すことは難しいけれど、ソクラテスはそれができる稀有な人格を持つ者でした。真直ぐに生きること、それがソクラテスの生き方でした。一つ一つの言葉ではなく、全体を俯瞰して初めて明らかにされるソクラテスの真直ぐな生き方には感動を覚えずにいられません。
3投稿日: 2014.11.15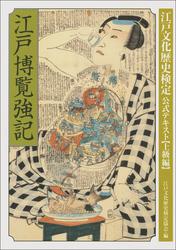
江戸博覧強記 改訂新版 江戸文化歴史検定公式テキスト【上級編】
江戸文化歴史検定協会
江戸文化歴史検定
将軍から地方武士まで それぞれの生活
全体的に江戸時代や江戸の町で生きた人々の生活が詳細に説明がされていて面白いのですが、特に、将軍、大名や旗本・御家人、幕臣など、文学や落語などにも出てくる支配階層の人々のことを知ることができました。 例えば、大名の中でも老中など幕府体制の中枢を担う職へ就く者の動向がどうであったとか、大名の家格がどういうしきたりによって扱われていたか、などは、なかなか知りえない話で面白く読めました。 旗本や御家人の家屋や家来の構成、江戸市中を往来する際のしきたりなどを読むと、落語の「かぎや」に出てくる旗本の背景がわかってきて、江戸を扱う文芸作品の理解に深みが出るように思いました。 大名の参勤交代に同行して江戸詰めをしていた地方の下級武士達の様子も面白いものです。職務の休みを利用して、歌舞伎や江戸見物を楽しみ、規則や門限を破ってまでも執拗に外出をしている武士の記録などが紹介されていて、こういう部分からも、当時の武士階級の意識を知ることができます。また、武士以外の町人の暮らしぶりも詳しく書かれています。
2投稿日: 2014.11.01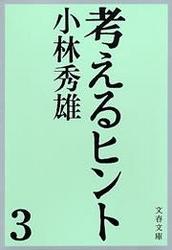
考えるヒント3
小林秀雄
文春文庫
信じることと知ること
現代人、とりわけ理性的な人は、科学的なもののみを思考の対象としていますが、では、世の中で経験される合理的・科学的でないものをどう考えるべきかが問題提起されています。 現代人は、合理的精神で説明がつかないものをナンセンスだと言って、思考から捨て去っています。合理的であることは、近代社会の中で効率的に生活していくうえでは重要なことですが、果たして捨て去ったところにあるものをどうすればいいのでしょうか。確かに、科学で説明できないことが、我々の周りでは経験されているのではないでしょうか。 小林秀雄が強い影響を受けた哲学者ベルグソンのことが引用されています。ある講演会にてベルグソンが聴講していたときに、超自然現象に関する話題で質疑が行われました。ある婦人は、夫が戦死した時刻に、夫の死ぬ様子を夢に見たと言ったのに対して、ある医者がその婦人の事例に直接触れず、世の中には他に幻を見たけどそれが誤りだった事例がたくさんあると答えました。それを聞いた別の若い女性が「先生のおっしゃることは論理的には正しいかもしれませんが、何か先生は間違っていると思います。」といったそうです。ベルグソンもその若い女性が言っていることが正しいと思ったのです。 その医者は、婦人の話を直接扱わないで、別の問題にすり替えてしまったわけです。しかしその婦人は自分が実際に経験したことを話したわけです。科学者は経験を尊重しますが、それは我々が普通に経験しているものとは違う科学的な経験に置き換わっているわけです。科学は、我々が生活の上で行っている広大な経験を合理的な経験に置き換え、計量化できるものだけを扱っています。科学はその計量化された経験だけに集中したが故に、大きな成功を収めているのですが、反面、切り捨てられている経験がそこにはあるはずです。 ベルグソンや小林秀雄は、普通の意味で理性的に話していますが、しかし、それは科学的な理性ではないのです。科学の狭い方法では扱えないものがたくさんあるのではないのでしょうか。 合理性の外側で広大に経験される世界に話は広がります。柳田国男の「遠野物語」の話に触れて、山の生活は我々平野人には忘れ去られた深遠なる経験の世界が残っているのだというのです。 合理的であることという現代人にとって極当たり前な考え方に縛られて、あまりにも合理的に現代社会を生きることだけに注意を凝らして、この世の中を見たり聞いたり感じたりしていなかったのではないのだろうか、そういう反省が心のうちに自然と湧き出てきます。
1投稿日: 2014.10.05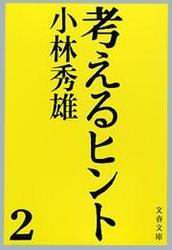
考えるヒント2
小林秀雄
文春文庫
天という言葉と人生の意味
小林秀雄の随筆は、深い思索に裏打ちされた、水墨画の筆致のような一度限りの作品だと感じます。文章はすらすらと流れて、著者が築き上げた思想が沈む精神世界の海底から表面に浮き出てくるものを下絵なしにさらさらと白い紙に描いているような印象を受けるのです。 さらさらと文章は流れていくのですが、書かれている内容は難しい。天という言葉が出てきます。天とは何かとは定義もしませんし、説明もしていません。天という言葉についてどういう思索をめぐらしたかという、思考の過程が垣間見られるだけです。そこに現れている文章は一閃の輝きを持っていて、読者の心を掴み、読者自身による思索へと誘います。著者の文章には定義も説明も無いのですから、読者は自分で考えるしかないのです。しかも、著者の思索は、著者の器の大きさを現すがごとく、あちらこちらへと大きく移り行きます。 我々現代に生きる者は、天というと、世界のことだとか、宇宙だとか、そんな事物的なものを考えます。しかし、古来から天はそんな浅薄なことを現すために使われてきたのではないそうです。我々はひどく無頓着な意識でもって生きていることになります。 天という言葉は、人生の意味について問う者が、人々の内的な生活に横たわっている何か言い表せない微妙な心情を表現したものであると、著者は言います。この言葉ほどに、うまく表現できた言葉が他にはないのです。それは何を表しているのか、それは定義できなくて、うまく言い表せないものなのです。だから各人が自身で考え捕まえるしかないのです。 「天という言葉が象徴的だったという意味は人生の意味を問おうとした実に沢山な人々の、微妙な言い難い心情に、この言葉は、充分に応じてくれたし、その点で、これ以上鋭敏な豊富な表現力を持った言葉は考えられないと誰もが認めていた、という事なのであり、従って、この言葉は、自覚の問題が、彼等の学問あり教養なりの中心部に生きていたことを証言していると、そういう意味だ。」 表面的に言葉を使い、言葉を便利な道具としてしか認識せず、言葉を弄していないか。言葉の意味、人生の意味を感じる鋭敏さを失い、鈍重な精神で生きてはいないか。人生の意味について自問する者は、言葉についても鋭敏な精神を持っているのでしょう。
2投稿日: 2014.09.07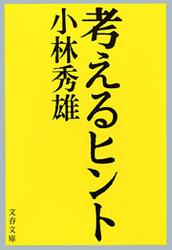
考えるヒント
小林秀雄
文春文庫
追体験して初めて「歴史」は存在する
「考えるヒント」の中の「ヒットラー」や「歴史」は、読んでいて非常に考えさせられて面白いものでした。 「ヒットラー」については、ヒットラーの人生観や思想の根本が鋭く見抜かれていて、改めて考え直しました。それは、自分のヒットラーに対する考えが表面的なもので、世間の普通に流布している意見をそのまま受け売りしていただけで、ヒットラーに対して少しも思索をしていなかったことを小林秀雄の文章は思い知らせてくれました。 特にヒットラーが、人生は闘争である、というときに、それは議論や思想でなく事実であるということには驚きを感じました。しかも、簡単だからといって軽視できないということにも眠りから目を覚まさせられたような感じを受けました。その実に単純で軽蔑すべき思想であるにも関わらず、しかし軽視できない現実世界からの体験に裏付けられていること、それらを深く考えていないということは非情な現実から安全な書斎へと逃避してぬくぬくとしている自分がいること、それらに気がつき戸惑いを感じました。 「歴史」では、フロイトの「自伝」を読んだ話が出てきます。フロイトの研究によって、意識と無意識の関係が明るみに出たわけですが、無意識の大きな海の上に浮かぶ小さな波のような意識というイメージは、その関係が複雑であるだけに、混乱をもたらしているようだと言います。何故なら、根本にある無意識を説明するには、無意識の上に浮かぶような小さな意識によってしか理性的に説明ができないのですから。 また、フロイトによると、無意識の世界の探求には強靭な自我がないと耐えられないのだと言います。我々が抱えている心の世界は、それを覗こうとすると、他のものとも比べようもないくらいの重量で以って我々の精神にのしかかってくるからです。 最後の方に歴史的な意識という言葉が出てきます。現在に生きる我々は、歴史との間に個人としての係わり合いを断ち切って、客観的に歴史を見るようになっています。歴史上の事件を、外側か眺めて、今の自分とは切り離された単なる事実として扱っています。しかし、それでいいのかと著者は問いかけるのです。それは、我々が自分自身の精神世界で過去を振り返り、自分自身で追体験できて初めて歴史は存在するといっているのではないかと思います。我々の生活は歴史の中で脈々と続けられているのですから、それを無視していいのかというのです。 うまく表現できないのですが、確固とした自分自身が存在できて、その基盤の上で初めて歴史は存在できるのでしょう。歴史という大きな流れの中に存在する我々個人が、個性的に生きるという問題にも答えを出せずにいるのに、歴史という流れを見ることはできないです。まずは自分を見よということでしょうか。
3投稿日: 2014.09.07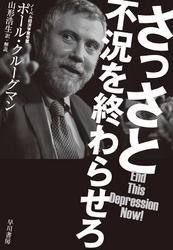
さっさと不況を終わらせろ
ポール・クルーグマン,山形浩生
早川書房
経済停滞と「子守り協同組合」
クルーグマンは、2008年金融危機を端緒としたアメリカの長期経済停滞をいかに脱してあるべき経済成長へと回復させるべきかを説いています。 経済停滞は様々な苦痛をもたらしますが、もっとも深刻なものが失業問題です。職が無い人は、所得が無いだけでなく、職業に就けないことで自分の価値の低下を感じることから、非常な苦しみを強いられるのです。人は職業を通じて、自らの社会における存在価値を確認して生きています。だからこそ、大量の失業は、大きな悲劇なのです。 本人の問題でなく経済停滞が原因であったとしても、長期の失業は、職業的なスキルを低下させ、また長期に職に就いていないという理由から雇うに不適当な者と見做されてしまうこともあります。特に若者の失業は深刻です。長期経済停滞で、一度も職に就けないまま、スキルを身につけることもできず、雇うに不適当な存在と見做され、これが一生続くのです。好況と不況の時期に社会に出た若者の人生を調査すると、好況の時期に社会に出たものの方が出世し経済的にも裕福な生活を送っているのです。 では、長期経済停滞の理由は何かというと、それは消費者、事業者、政府が十分なお金を使っていないことからきているのだそうです。対策はというと、需要を十分に大きい規模に増やせば、社会全体は技術も生産能力も有しているので自然に回り始めるという主張です。需要を増やすのは政府の役目なのです。これは、ケインズが20世紀初頭に説いた話と同じだそうです。 この意見に対する態度は様々で、当たり前すぎて不況への解答になっていないとか、不十分な需要で世界全体が苦しむのはありえないと否定するのが多いそうです。そもそも人々は自らの所得を何かに使わざるを得ないのであるから、需要不足が起きる筈が無いというのです。 この意見に対して、クルーグマンの出した「子守り協同組合」のアナロジーは、社会経済構造の要点を的確に説明しており面白いです。社会全体の心理が悪化すると需要が不足する仕組みを説明しています。: 若い議会職員(約150組)が、ベビーシッター代を節約するために、交代でお互いの子供の面倒を見る仕組みを作りました。互いが公平に子守を受け持つように、クーポン制にしてありました。子守をしてもらうときにクーポンを相手に渡し、自分が子守をするとクーポンを受け取る、そして、初めに受け取るクーポン数を脱退するときに返すのです。ところが、クーポン制にしたせいで、手持ちのクーポン数を気にするようになりました。いざという用事にクーポンを取っておきたいために、それまでであれば頼んでいた子守の依頼を控えるようになったのです。皆が子守の依頼を控えることで、クーポンが回転しなくなり、手持ちのクーポン数が少ない者は一層子守の依頼を控えるようになります。こうして、子守協同組合が機能しなくなったのです。この子守協同組合は、クーポンを増刷して増やすことで、参加者の心理を変化させ需要が出るようにしたところ見事に改善したそうです。 この実例は、以下のわかりやすい主張を説明しています。 「あなたの支出はぼくの収入であり、ぼくの支出はあなたの収入になる」 単純明快なことですが、現実の社会経済で世界規模にやるとなると難しいと思います。現実には、事業者も消費者も不景気な状況でお金を使いたがらないので、需要を回復するには政府が大きな支出をするしかなくなります。政府は普通政策金利(公定歩合)を下げることでお金の流通量を増やしますが、政策金利が0%に近いと、0%を切って金利を下げることができなくなります。ですから、もっと広範囲に金融緩和を行い、政府支出を増やすべきだというのです。非常にわかりやすい説明で、かえって本当にこれだけでいいのだろうかと迷ってしまうところに問題の本質があるのかもしれません。
0投稿日: 2014.08.23
アメリカのデモクラシー 第一巻(上)
トクヴィル,松本礼二
岩波文庫
平等の偉大な思想家
アレクシ・ド・トクヴィルは、1805年にフランス貴族の家系に生まれた政治家・政治思想家で、フランス革命やナポレオン帝政とその後に現れる王政復古など、フランス政治体制が激動に大きく波打った時代に生きた人です。貴族制から民主制へ進む時代の流れは変えられないと早い時期から認識し、民主制の時代に貴族の末裔としていかに生きるべきかを真剣に考えた人でした。 しかしながら、当時のフランスは革命によって民主政へ移行した経緯やその後の動乱の影響もあり、階層間の激しい憎しみ合いや政治的な混乱などがあって、フランス社会における民主制の先行きは不透明でした。 一方、まだ建国から数十年しか経たないアメリカは繁栄への道を着実に歩んでいました。トクヴィルは民主制の行く末はアメリカにこそ見出せると見抜き、友人ギュスターヴ・ド・ボモンとともに数ヶ月のアメリカ視察を行い、当時のアメリカ著名人のほとんどとも会談をして、まだ20代前半でしたがが、この名著を著しました。(因みにボモンも名著を著しているそうです。) 第1巻では、アメリカの繁栄に対して、境遇の平等がいかに大きく影響しているのかをいくつもの例を挙げながら丁寧に説明しています。トクヴィルは貴族制社会の中で貴族の血筋を受けた人であり、民主制を外から観察するように分析しています。 民主制がいかなるものかということを改めて認識し直すと同時に、併せて、貴族制とはいかなるものかということも初めて分かったような気がします。 第2巻は、平等が精神にいかなる影響を与えるかということが分析されます。第1巻では、アメリカ視察から帰った後の興奮が間近に感じられる位に、アメリカのことが好意的に書かれていましたが、数年後に書かれた第2巻では、アメリカ・イギリス・フランスの冷静な比較分析が行われています。 例えば、貴族は生活の心配がないから名誉を獲得できる大志を望みそれを実現することに専心します。貴族は家系こそが偉大さの源泉であり、家系の名誉を守るためには生命をも犠牲にささげます。民主制の人民は、常に生活の心配をしているから大志を抱く余裕がなく、民主制の時代には偉大な人物は現れなくなります。自分の生命が大切で、他人のことは全く気に掛けなくなります。そういった比較分析がなされているのです。 第1巻は読んでいて楽しく大変面白いですが、第2巻は地味ではありますが、深く考えさせられる内容に満ち溢れています。 アメリカは、西部開拓という大きなフロンティアを持っていて、国内だけでも成長していけた時代がありました。その期間は特に高度成長を遂げていて、活気に溢れていました。トクヴィルはそうした様子も伝えています。 民主主義は良い仕組みかもしれないが、ある社会にいきなり適用してうまく民主主義が回り出すとは思えません。それは、モラルの低い民衆からなる社会に民主主義を導入しても無政府状態に陥ることも大いにあるからです。 北アメリカの初期植民地でうまく民主主義が立ち上がったのは、ボストンなどのニューイングランド地方のようです。この地方にはピルグリムファーザーズと呼ばれる人々が殖民しました。彼らはイギリス社会でそれなりの地位にあったのですが、宗教上の理由でアメリカへと移民したのです。彼らには社会的な地位があり、彼らには社会集団としての秩序やモラルが備わっていて、それに平等が結びついて民主主義が、挫折せずに、立ち上がったと分析しています。 トクヴィルはアメリカの平等社会を評価していますが、成功の裏に不平等が存在していることもかなりのページを割いて記述しています。それは、先住民アメリカインディアンのことと、黒人のことです。 トクヴィルは、当時の民主制の国や人民の話をしているのではなく、民主制の国ではこういうことが起きるであろうという分析をしています。そうであるから、どちらかというと、民主制の国について予言をしていることになります。そして、この予言が多くの点で当たっていることが多く、非常な驚きを禁じえませんでした。 例えば民主制の国では、人民が政治に次第に無関心になり、僭主が現れて専制政治を行う危険性が高い(、貴族制では貴族が僭主に対して反抗するのでその危険性は小さい)、と述べています。後にヨーロッパや南米、アジアなど世界各地で起きる専制的な国家の危険性を早くも見抜いていたことになります。各国の専制体制を非難することによって単純に片付けて思考停止するのは安易すぎて、もっと民主制に関して深い考察が必要なのではないかと改めて考えさせられました。
4投稿日: 2014.06.22
神聖ローマ帝国
菊池良生
講談社現代新書
英雄たちの歴史
神聖ローマ帝国とは何かという問いに答えるのは非常に難しいです。神聖ローマ帝国を定義しにくいからかもしれません。そもそも「神聖」とは何に由来するのか、国土がドイツにありながら「ローマ」が国名に冠されているのは何故でしょうか。これらの素朴な問いへ解りやすく答えようとする一つの試みが本書です。軽いタッチで、史劇のように描写されていて、神聖ローマ帝国と呼ばれた地域の歴史の大きな流れを把握することができます。 19世紀後半のドイツ歴史学派によると、古代ローマ帝国の後継国家である「神聖ローマ帝国」は、962年オットー大帝によって開かれ、千年に渡りドイツ民族が支配してきた輝かしい国であるとされたそうです。19世紀後半といえば、多くの小国家や自由都市に分裂状態にあったドイツがプロイセンによって統一されようとしていた、ドイツ民族主義の高揚していた時期です。その背景には、政策的なものもあったかもしれません。 ところが、ドイツ歴史学派による主張は誤りであるという批判が20世紀初頭に起こりました。ツォイマーという学者が「神聖ローマ帝国」における帝国称号の変遷史を丁寧に調べたところ、歴史学派の主張がいかに非歴史的であるかを明らかにしたのです。 そのような経緯があったにしても、神聖ローマ帝国が歴史学派が言うような確固とした国でなかったとしても、神聖ローマ帝国の歴史を辿ることは、ドイツを中心とした中央ヨーロッパを知る上で重要なことだと思います。 神聖ローマ帝国の歴史を本書に従って辿っていくと、国政の変遷というよりも、国王に名を連ねた幾人もの英雄達の苦闘を見ていくことになります。神聖ローマ帝国の前身の時代から、重要な人物だけを数えただけでも、ピピン(カロリング朝)、カール大帝(西ローマ帝国復興)、コンラート1世、オットー大帝、ハインリッヒ4世(カノッサの屈辱)、フリードリッヒ1世(バルバロッサ)、フリードリッヒ2世、カール4世(金印勅書)、カール5世(ハプスブルク家)などが挙げられます。いずれも歴史に名を残している英傑ばかりです。 本書にておいて「王の霊威」という言葉が紹介されています。王位を継ぐ者には神が与えたもうた「王の霊威」が備わっていなければならないという考え方が中世には広く信じられていたのです。たとえ優れた英雄が出現したとしても、「王の霊威」を持たない者には王位は授けられないですし、実力だけで王位に就いたとしても簒奪者とみなされ臣下が従わなかったのです。さらに「王の霊威」は個人に授かるものではなく、家系、王家に授けられるものとされました。神聖ローマ帝国の皇帝は、「王の霊威」を持つとみなされた家系だけが受け継ぐことができたのです。選帝侯によって皇帝が選ばれたとしても、選帝侯は「王の霊威」を持たぬ者を指名することは事実上できなかったのです。そういう意味では、神聖ローマ帝国の歴史は、「王の霊威」を巡る歴史と言えるかもしれません。ヨーロッパの歴史を深く知ろうと思う人にはお勧めです。
2投稿日: 2014.06.22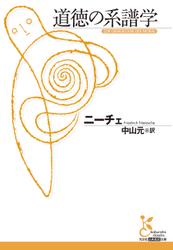
道徳の系譜学
ニーチェ,中山元
光文社古典新訳文庫
道徳という価値観
ニーチェは、我々が行為をなす際に価値の基準とするもの、つまり道徳という価値観を批判的に考察しています。人間は認識する者ですから、認識することと判断することは、哲学の中心的問題となります。認識して判断する際に、人間が持つ価値観は重要な役割を果たすのですから、道徳を批判的に評価することには意義があります。 ニーチェの師ショーペンハウアーは、「非利己主義的なもの」、つまり同情の本能や自己否定の本能、自己犠牲などを美化し神化したために、ショーペンハウアーにとって「非利己主義的なもの」は価値そのものとなってしまいました。このため、自分自身を見つめその中に存在する生が如何にその価値から離れた存在かを理解していた彼は、生に対して、自己自身に対して、否と言ったのだといいます。しかし、ニーチェにとって、「非利己主義的なもの」による価値は、人間を自己否定へと追い込むもので、虚無へと誘い込むものに見え、ニーチェは道徳という価値観に懐疑的な態度を取ります。ニーチェから見ると、道徳という価値観は人間によって疑うことなく判断の基準とされており、哲学者といえどもその呪縛から逃れられていないのです。ニーチェは、道徳の起源を探究することで道徳の価値という問題に迫っていきます。こうした批判の裏では、道徳が否定された後に、大胆にもニーチェは新しい価値観の創造を目指そうとしているのです。 ニーチェは、道徳における価値の逆転に触れて、ルサンチマン(怨恨の念)という考え方を出して説明していきます。高貴な者(ローマ)が作り出した価値は自己肯定の言葉でしたが、逆に低い者(ユダヤ)たちが作り出す価値は自己ならざる者を否定する言葉となっていました。この否定の言葉が彼ら(低い者)の創造(価値の逆転)となるのです。それは、キリスト教がローマ帝国の国教となり、ローマ帝国滅亡後はヨーロッパ社会の価値の基準となっていきました。 ニーチェ思想の基礎を知る上で、本著は重要な作品だと思います。
2投稿日: 2014.06.15
マンデリンさんのレビュー
いいね!された数90
