
女のいない男たち
村上春樹
文春文庫
哀愁漂う短編集
文学的小説を読むと、何かもやもやっとした感じになる。 だから何なの? だからどうしたら善いの? どうしてそうなの? 自分と重なる部分がある場合など、特にそう思えてくる。 男と女の心の中、自分心の中でさえ分からないときがあるのに、性別が別の他人の心の中が分かるよしもない。 秋の夜長、そんな世界に入ってみるのも、いいと思う。
1投稿日: 2016.10.16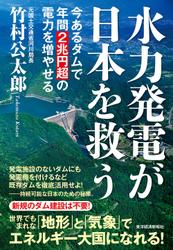
水力発電が日本を救う―今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる
竹村公太郎
東洋経済新報社
国土の7割を占める、山間地を利用してのエネルギー発生は理に適ったソリューションだ
環境問題を考える上で、単に自然を守ろうという言葉は、すでに時代遅れの考え方であろう。 と言うのも、少なくとも高度経済成長期においても、自然環境破壊は理解され、それと経済的メリット発展のバランスをとろうとしていたのである。残念なことに、その時代は経済発展を優先することが多かったのである。 上記も軽く触れられながら、本誌では何よりも日本の地形を最大限活用するためには、水力発電を活用することが望ましいことを、様々な面から説いている。 説明されている内容は実に納得がいくもので、国土の約7割が山間地域で有り、年間降水量が3000mmmという条件は正に水力発電に向いているといえる。 水力発電を広げていくためには2つの課題があると思える。 1.水は誰のものでもなく共有財産であるという理解を構築すること 2.共有利用できるための法整備 3.これまでのダムの改修 これらが一部でも解決出来ると、そこからできる改善策を打つことができるはずである。これから、永遠には無いと分かっている、地下埋蔵資源に頼り切るのではなく、どこにでもある水力発電を活用することが良いと考えています。
1投稿日: 2016.10.01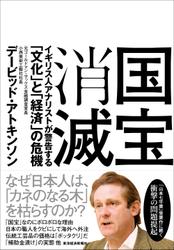
国宝消滅―イギリス人アナリストが警告する「文化」と「経済」の危機
デービッド・アトキンソン
東洋経済新報社
日本が経営していくと言うこと。
作者は小西美術工藝という、日本の古くからある建築物などの修理などを手がける会社の社長で、この本に書かれているような内容を複数の書に記している。 うがった見方をすれば、衰退している伝統工芸としての建築メーカーのアピールであるのかもしれないが、昨今しきりに騒がれているインバウンド、海外の方が日本に旅行にいらっしゃることについて、再度考えてみることができた。 というのは、海外の方が何故日本に?と考えると、分からなくなってくるので、私たちは何故、そこに旅行するのだろうか?で考えてみたら良いのだと考えた。 私は行ったことが無いが、ハワイや、グァム、ラスベガスなどのリゾートに行くのは、現在を忘れて別世界で夢の世界に浸ることだろう。そういえば、ディズニーリゾート、USJ、ピューロランドもそうなのかもしれない。 そのような体験で言うと、人が少ない大自然を訪問するというのも同じ感じではないだろうか。であれば、私は後者の方が好きかもしれない。 それに対して、京都、鎌倉、日光、または各地の城、城下町、はたまた寺社、仏閣を訪れたいというのはどういう思いからだろうか? それは、今の歴史を積み上げて人たちが、どのような暮らしをしていたのか?その地域の文化、その時代の文化に触れてみたいからではないだろうか?となると、それができるだけわかりやすく、当時の面影を残した状態で見せてもらえると、あらがたいものとなるのであろう。 翻って現在のそれらの保存状況を見てみると、果たしてそれらができていて、公開されているかというと、案外そうでも無かったりする。また、写真撮影禁止となっているところも多く、現代であればSNSでここに行ってきたよ、素晴らしかったとアピールすることすらできない。 ヨーロッパに行くと美術館に行く日本人は多いだろうが、日本に来て歴史的建造物を訪問したいと思っているヨーロッパの方も多いと思われる。その時、安価に入場してもらうのではなく、見合った代金を頂き、しっかりと見ていただけるという建物の容姿、サービスも付加させていくことが今後必要になるだろう。 私たちも、海外で有名な観光名所に行って、えっ、てことがあると、もう2度と行こうとは思わないでしょうから。
1投稿日: 2016.09.25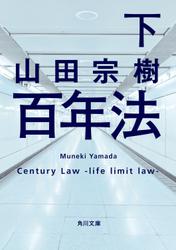
百年法 下
山田宗樹
角川文庫
人間が老化しないとどうなるか?
現在の人口減少問題が解消されるのはもちろんだが、多くの人が経験している、上の人がいなくならないため、いつまでたっても上に上がれないということが発生するのだ。 また、日々同じことの繰り返しに、人々は一体何年耐え続けることができるのか?これも大きな課題になるのだろう。私たちは、定年を60年として会社でも長くても40年しか同じ仕事をすることはない。とはいえ、40年同じ仕事をするということはまずないだろう。しかし、老化しないとなった場合一体どうなるのか? この物語は今の社会現象を、かなり織り込みながらストーリー展開されていく。 1回だけではなく、2回、3回と読める、2冊である。
0投稿日: 2016.09.19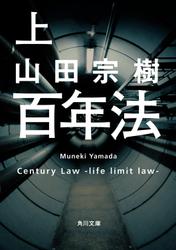
百年法 上
山田宗樹
角川文庫
場面の設定から圧倒された。
現代であるが、過去からの設定が大きく変更さている。 何と、第2次世界大戦では日本に6発の原子爆弾が投下されており、今から約20年後には中国と、韓国が圧倒的に日本を追い抜いているということになっている。 過去の話については、フィクションであるが、未来の話についてはノンフィクションの様に感じさせる。 その中で、人間が老化しないウイルスが発見されており、多くの国々でそのウィルスが利用されているという設定で話が進んでいく。 これが、下巻まで続いていく。読み応えある1冊である。いや、上下2冊である。
0投稿日: 2016.09.19
ストーリー・セラー
有川浩
幻冬舎文庫
一気に読んでしまった。
本を書きたいと思ったことはある。が、それは小説ではなく、知っている知識を広めることが主題である。 そんな中、小説家についての本に出会った。それも、少しややこしい、小説家は女性、そしてパートナー、または本人が病に倒れる(?)という2つの話がサイドA、Bと2つの話として書かれている。 パートナーとの出会いからドキドキしながら読み始め、安定期があるのか無いのか、そして結末に繋がっていく。そして、結末って? この一連の流れが、楽しくおもしろく、一気に読んでしまった。
0投稿日: 2016.09.19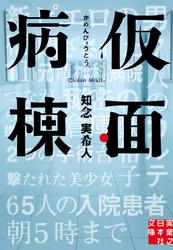
仮面病棟
知念実希人
実業之日本社文庫
3連休、またミステリーを読みたくなり、
読み進めていくと、だんだんと予想ができるところもあるのだが、最後まで予断を許さない、期待を裏切る、楽しめる1冊だった。 やはり、推論を進めていきながらも、それを裏切る大どんでん返し。これが、ミステリーの醍醐味なんでしょうね。
0投稿日: 2016.09.19
すばらしい新世界
オルダス・ハクスリー,黒原敏行
光文社古典新訳文庫
80年前に書かれたSF作品とは思えない。
書籍は新しければ良い訳ではないことを、改めて感じさせられた一冊だ。 今から80年前に書かれた作品であることから、現在を詳細にイメージできていたかというと決してそうではない。 詳細にイメージされているのは、人間の行動そのものだ。 このイメージを読んでいくと、80年という時代が経過したにもかかわらず、人間の進歩はないのではないかと思ってしまう。そのことから考えると、もしかして進歩が必要だと思っている我々が可笑しいのかもしれない。 日本では想像できない、気づいていない階層社会を、明確に記し、それにらについてどの階層が幸せで、不幸せであるかと言うことはないと記されている。 非常におもしろい、変かがないと言うことは、多くの人にとって幸せなことであり、それを上記のように記しているのだろうかと思えた。 何にせよ、この80年間を、そしてこれからの歴史を考える上でも読んでみると為になるSF作品だ。
0投稿日: 2016.09.19
ちょっと今から仕事やめてくる
北川恵海
メディアワークス文庫
えっ、なんてタイトルだ。
世の中のブラック企業、足を引っ張り合う風土というものは、あるんだ。と再認識すると共に、何よりも感動したのは、人と人のつながりだ。 それほど厚い本ではないので、さっと読んでもらいたい。最後には心がほっと、温まっていると思う。
0投稿日: 2016.09.19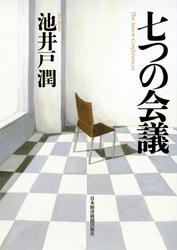
七つの会議
池井戸潤
日本経済新聞出版
企業内偽装
最近手にするのは、企業での偽装本が多い。それは、そのような本が増えているのか、今の仕事柄なのか、どうなのか統計を取っていないから分からないが、よく手にする。 企業ぐるみでの偽装というのは、後を絶たない。 これは、メーカーだけの話では無く、金融、サービス業も同じである。 この小説の中では、タイトル通り7つの会議がそれぞれの役割を持ちながら開催され、決断がなされていく。 その中では、様々な思惑が入り乱れ、繰り広げられていく。当然実社会でも同じであろう。だからこそ、小説とは思えない。 もしかすると、今そこにある危機、いや現実かもしれない。
0投稿日: 2016.09.19
ecotさんのレビュー
いいね!された数8
