
十三番目の王子
岡田剛
東京創元社
魅力的なのにな
主人公たちも舞台も魅力的。 国のあり方に宗教が大きく影響しているのも ヨーロッパの国々みたいで説得力がある。 はずなんだけど、そのあたりの説明が足りなくて 世界のありようが見えてこない。 だからその中で鬱屈を抱えてもがいているらしい主人公たちが 全く理解できなくてとてももったいなかった。 突然弟にナイフを投げつけたり、友人を殺す勢いで殴ったり ホントみんな病みすぎててついていけないし。 病んでる人を書きたかったのなら舞台は違う方がよかったし、 ファンタジーを書きたかったのならもっと主人公と世界を くっつけてほしかったな。
0投稿日: 2015.05.14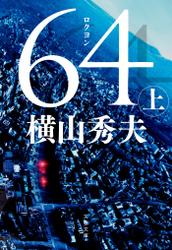
64(ロクヨン)(上)
横山秀夫
文春文庫
仕事って大変
ドラマ化されるので慌てて読んだ。 男性版お仕事小説、というにはちょっと仕事が物騒か。 横山先生作品ではおなじみの、警察官が主人公だけど現場で捜査する いわゆる刑事さんではない人が主人公。 今回は警察と外とをつなぐ広報官。 マスコミ対応とかするところです。 一気に読まされました。 最後は予想よりも一捻りあって満足。 ただたくさんの登場人物とその肩書き、退職した人まで出てくるもんだから 整理しきれずちょっともったいなかった。 パワーバランスが頭に入ってるほうが確実に楽しめます。 ドラマではこの人の多さは混乱せずに見れるかな。 あまり堅苦しく昭和のおじさんドラマにならないことを祈る。
2投稿日: 2015.04.14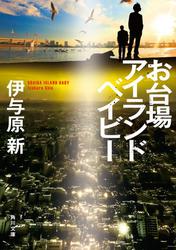
お台場アイランドベイビー
伊与原新
角川文庫
日本って平和じゃないんだね
この著者は始めて読んだ。タイトルの印象よりずっとハードボイルドだった。 舞台は地震によって壊滅的な被害を受けた東京。 その様子は今の私たちには容易に想像できるけど、これが書かれたのは震災前。 主人公の巽が気が置けないキャラなので、状況は厳しくて悲しくて理不尽だけれど 読み進むのは苦じゃなくむしろさくさく読める。 この作品で初めて無国籍児というものを詳しく知った。 日本は昔から言われているような豊かで平和な国とは言えなくなって いるのかもしれない。 最後のほうのシカケ(?)と終わり方だけが自分の好みではなかったのが残念だったけど。 この著者を知ったのは「ルカの箱舟」という本を見て面白そうだと思ったのが最初。 どんな作家だろうと著作を検索してみると、まったく印象の違う書影が並んだので ますます興味がわいた。 次も期待大です。
1投稿日: 2015.03.29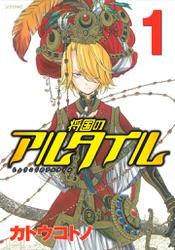
将国のアルタイル(1)
カトウコトノ
月刊少年シリウス
なかなかいいぞ
主人公が見た目小学生かって感じなのに将軍という国の要職に就いているのが 不安だったけど、本人がいたってシリアスだからか大丈夫だった。 漫画でありがちな年齢設定の低さはもちろん読者に配慮してるからだから 文句を言う筋合いはないけど、それだけで嫌煙すると面白い漫画を 見逃してしまうのよね。ううっ、ムズカシイ うまいタイミングで力を抜くので、作者やるなぁとうならされる 老将軍のキャラもいいね この後どう話が展開していくのか楽しみです
0投稿日: 2015.02.18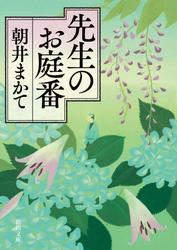
先生のお庭番
朝井まかて
徳間文庫
すこーし地味なので星3つ
忍者の話かと思ったら違った 派手さはなくてもなぜかページをめくる手が止まらない、そんな作家だ。 舞台は幕末、植木商で働く熊吉は出島のオランダ人が作った薬草園の園丁となる。 オランダ人の名前はシーボルト。植木商としてはまだ半人前の熊吉はやったこともない薬草や 珍しい花や木の栽培に精を出す。ひとえに“しぼると先生”の役に立ちたくて。 しかし徐々に幕末の混乱が出島にも影を落としはじめ・・・ この人の描く人物は100%善人とか悪人とかではないのがすてき。 とくに今回シーボルトは重要な人物なのに話の中心に持ってくることはせず、 さらに会話も少ないため、彼が何をどのように考えていたのかが示されず、 でも最後まで彼が何を考えどう思い、そして周りが彼をどう思ったかが話の全てと 言ってもいいので、そのあやふやなわからなさが当時の空気感を見事に伝えてくれている。 私たちは本当に分かり合えているのか。もしかしたら勘違いや思い込みで大事なことを 見誤っていないか。そんなことを考えさせられる。 今回物語の中で重要な役割を果たすアジサイ。その学名に秘められた秘密も見どころ。 最近知ったけど、いちょうの木は幕末に日本からヨーロッパへ渡ったらしい。もしかしたら 熊吉やシーボルトの仕事のひとつだったのかも。 ところで出島って幕末の時すでに築かれてから200年近くもたってたんですって。 それなのに日本人に外国人への畏怖や恐怖があれほどあったなんてなんだか不思議。
5投稿日: 2015.02.17
みなさん、さようなら
久保寺健彦
幻冬舎文庫
小学生がうまいなぁ
最初はちょっと変わった少年のちょっと現実離れした物語だと思っていた。 たしかに主人公は普通まわりにはいなさそうな破天荒な少年だけれども、その人物造形の背景がただの舞台設定になっていないところにすごく好感が持てた。 最近気になっていたんだが、物語をつくるために主人公をかわいそうな生い立ちにしたり、現在の不幸な状況に説得力を持たせるためだけに背景にいじめや、震災や事件などの実際に起こった出来事を使うことが増えている気がする。 当然その物語の主題がいじめや震災そのものであればいいのだが、実際はまったく関係なくストーリーはそれらを無視した形で違う方向へと進んでいく。 たとえば実際にいじめにあったことのある人にとって、いじめをよくある不幸な出来後などと思えるわけがない。体験していないからこそできる非常に安易で思慮に欠ける小説の書き方だと思う。 話がそれた。 思った以上にヘビーな話だった。 突拍子もない設定に思わせてきちんと読者が納得できる話になっているのはさすが。 でもそれを自分って不幸、と自己憐憫にひたる話でもなく、どかんとそれらを吹き飛ばすありえないヒーロー譚でもなくやってみせるのがこの作者の面白いところ。 だから主人公に全面的に同調できるかというと、それはちょっと保証できない。 現実でも好きでも嫌いでもないって友達がいるように、彼のことも特別好きじゃないけど「これからお前どーすんだよ」って聞きたくなるくらいには気になる友人の物語として、どうか最後まで見守ってやってほしい。
1投稿日: 2014.12.04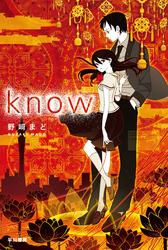
know
野崎まど
ハヤカワ文庫JA
かなりSF
表紙の印象から低年齢向けのライトノベルなのかと思ったけど違った。これは表紙でかなり損をしてると思う。 若くしてエリートと呼べる地位を手にしている青年や特殊能力(とはちょっと違うけど)を持つ美少女などキャラはライトノベルだけど、話はすこぶるSF。 頭に電子葉を入れた人々が暮らす未来は携帯端末を使わずにネットとつながり、なんと街を作る建材にも情報を取得する機能が備えられ、現代よりもさらに情報にあふれた世界になっている。 著者の情報の捉え方が、よくあるSFの設定より一歩踏み込んでいて面白い。 こんなにキャラが立っちゃってるのにそれに引きずられないのもすばらしい。 今はネットに流出する個人情報やどこに蓄積されているかわからないプライベートな履歴に戦々恐々としているけれど、さらに情報があふれる社会になるとたしかに考え方もこんな風に変わっていくのかもしれない。 師と仰ぐ教授と青年の会話、青年と少女のなんかずれてる会話、いつまでも聞いていたくなる不思議な感じだ。 ラストはそこだけ取り出すとファンタジーにしか思えないが、物語を読み終えてその一文に出会うとしみじみとした感動を味わえるだろう。
1投稿日: 2014.09.30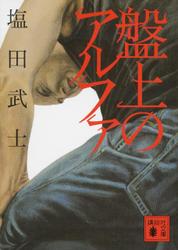
盤上のアルファ
塩田武士
講談社文庫
おしい でも次も読みたい
珍しい棋士の話です。デビュー作ですね。 著者は賞を受賞した時は新聞社で働いていたらしく、会社で受賞の報告をしたら、じゃあその記事書いてと言われて自分で自分の受賞記事を書いたそうです。 達者な書き方でデビュー作とは思えない読みやすさでした。 でもあちこちがおしい感じ。 初めに事件記者だった秋葉が将棋担当にまわされ不満たらたらで将棋の世界に触れるところから始まるんだけど、最初のエピソードが女流王位戦の、でも盤外での女の戦いを、たぶん棋士といえども普通の人ってことを書きたかったんだと思うけど三流小説のような展開で描く。下世話すぎてちょっとひいてしまった。 将棋はどこへ・・・ 2章目で主人公が変わりプロへの夢をあきらめきれない真田が登場。やたらアンダーグラウンドな生い立ちの真田と将棋のつながりが描かれるんだけど、あれ、連作短編なのかな?と思いきや3章目で秋葉と真田がやっと出会って本筋が始まる。 こんなにぶつ切りに構成しないで二人の話を最初から描けばよかったのに。 そして将棋の面白さはどこへ・・・ 何しろコミックでだったけど素人でも将棋や碁の戦いの面白さを感じることができるのは体験済み。 なのに素人だったはずの秋葉はいきなり専門用語を使い始めてこちらは置いてけぼりだし、棋士の心情には踏み込みきれてないしでもったいない。 ほんと、繰り返すけど、おしい。 でもなぜか、ほかの作品も読みたくなる。きっと登場人物が熱いからかな。これからもっと成長してくれそうな予感。
0投稿日: 2014.09.21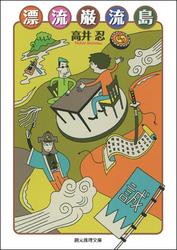
漂流巌流島
高井忍
東京創元社
歴史ものの小説ができるまで、みたいな
佐々木小次郎と宮本武蔵の巌流島の決闘、年末恒例忠臣蔵など日本人なら誰もが知っているこれらの話の真実は通説通りなのか。 テレビドラマの企画で、有名なチャンバラモノをオムニバスで作るという話が持ち上がり脚本家と監督がまず本当のところはどうなのか、それはどこまで信用できるのか、そして真実はどこにあるのかを話し合っていく。この過程を描いた短編集なのですが、さてしかし、こんな有名な話になぜそんなに検証が必要なのか。 それはこの企画の頭に「実録」とつくから・・・ 現代までこれらの事件がドラマになるほど知られているのは、そもそも昔から講談や芝居、草紙となって親しまれてきたからだ。なのでもちろんそこにはたくさんのアレンジが施されるわけで、通説となっていることはそのまま史実ですとはいかない場合が多い。 「小次郎敗れたり」の名台詞を本当に言ったのか、そもそも佐々木小次郎とは何者なのか。 忠臣蔵の敵討ちは忠臣ゆえだったのか?新選組はなぜ単独で池田屋に乗り込んだのか。 脚本家が資料を調べて監督にレクチャーするわけだけど、もちろん文献は研究書ではないから読むほどに矛盾や疑問が出てきて、はっきり書かれていない部分もあれば文献ごとに内容が違ったりとこの辺りは歴史ものを書く作家の苦悩がのぞけるところ。 そして監督が言うのだ。それはつまりこういうことだろう、と。 本格ミステリーのような謎解きがされて膝を叩くことしきり。さてあなたならどう読み解きますか?
1投稿日: 2014.08.17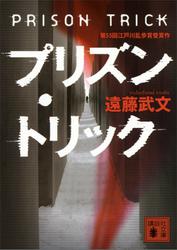
プリズン・トリック
遠藤武文
講談社文庫
この著者は初 違うのも読みたい
交通刑務所内で起こった殺人。物語は受刑者の一人称で始まるのでその男が犯人なのはわかっているが、殺人のシーンはカットされているので読者に詳細は明かされない。 次の章からは三人称になり、刑務官や刑事や保険会社の人間が入り乱れて脱獄した犯人を追っていくことになる。 トリック重視の本格かと思ったら動機も結構凝っていて、でもちょっと懲りすぎだった気がする。その上重要人物ではないキャラも書き込んでしまうため無意味に煩雑になっているよう。 事件の裏に隠された過去の犯罪に関わり苦い思いをした人物、刑務所内の殺人という前代未聞の事件にあたってしまった警察官の葛藤など犯人以外のキャラにも厚みを持たせたのはいいが、それを描き切れていないのももったいない。主人公というほど扱いが重いキャラがいないせいか全員の人間ドラマがぼやけてしまい物語全体もなんだかすっきりしないのだ。 とはいえ、交通刑務所の内情は面白かったし犯行の手口が明かされていく過程は十分楽しめる。読んでいくとちょうどいいタイミングで新しい事実が明かされて驚かされ、ページをめくる手が止まらないスピード感のあるうまい構成と文章。書き慣れた安定感があって安心して読めます。 書き切れていない感がするので星は4つ。
0投稿日: 2014.08.10
レビューネーム未設定さんのレビュー
いいね!された数56
