
古市くん、社会学を学び直しなさい!!
古市憲寿
光文社新書
平易で明快な視点で「社会学とは何か」を問いかける
テレビのコメンテーターとして、一風変わった切り口で社会現象を切り取る古市憲寿さんが、名だたる社会学者との対談を通して、「社会学とは何か?」という問いに始まり、社会学の存在意義や、先人の社会学者の足跡を明らかにしていく。 本書で登場する宮台真司さんや山田昌弘さん、本田由紀さんの本は、一般人向けの書籍ラインナップが充実していることもあって、これまでに何冊も読んでいるが、本書を通じて社会学への研究動機など、一人間としての研究者像が明らかにされていて読みごたえがある。 一方で、本書をきっかけに「あとで買う」リストに入れた本も一気に増えた。古市さんが一般人にもわかりやすい問いかけを行っているため、橋爪大三郎さんの俯瞰的視点や、逆に福島の問題から日本社会の構造的な問題を見つめる開沼博さんの視点など、知的好奇心を大いにくすぐられる。 社会学の「入門書」にはならないかもしれないが、教養としての読書のネタ探しにはうってつけの本だと思う。
0投稿日: 2017.10.07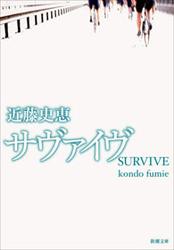
サヴァイヴ(新潮文庫)
近藤史恵
新潮文庫
「サクリファイス」「エデン」を既読の方は必読の短編集
近藤史恵の自転車ロードレース小説シリーズ:「サクリファイス」、「エデン」に登場した人物のスピンオフ短編集です。 「サクリファイス」、「エデン」を読んでない方も楽しめますが、両作品を既読の読者にはたまらないエピソードばかりです。 主人公の白石誓とヨーロッパ戦線のレーサーたちの物語は短編でありながらも自転車ロードレースの醍醐味を伝えるに充分の力作。誓の日本時代のチームメイトで、エデンではともにヨーロッパで戦うことになる伊庭和美のエピソードも読ませます。しかし何といっても誓に多大なる影響を与えた石尾と赤城の若き日のエピソード、「サクリファイス」の読者には必読といってもいいでしょう。
0投稿日: 2017.10.06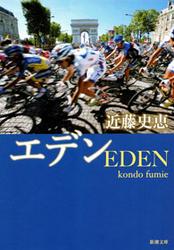
エデン(新潮文庫)
近藤史恵
新潮文庫
前作「サクリファイス」を超える傑作!
「サクリファイス」の続編です。登場人物は多いが、文体が極めて明快なため、すいすい読めます。読み始めると眠れなくなることは間違いありません! 自転車ロードレーサートとして様々な人の思い背負って、本場ヨーロッパへ渡った白石誓は、アシストとしての能力を評価され、フランスのチームへと移籍。チームのエース:ミッコ・コルホネンのアシストとして、世界中のロードレーサーが憧れる楽園(エデン)である、ツール・ド・フランスへ出場する。 三週間で約三千キロを走破するという、極めて過酷なレース。ツアーで勝利するための戦略と駆け引き、エース同士の争いからチーム内での争いなどレーサたちは様々な葛藤と思いを抱え、人間模様を描きながら楽園を疾走する。 最後で語られる誓うの言葉が印象的。 「ここはこの世でいちばん過酷な楽園だ」「楽園に裏切られる者も、楽園を裏切るものもいる。楽園を追われる者も、そしてまた舞い戻ってくる者も」
0投稿日: 2017.09.18
未来の年表 人口減少日本でこれから起きること
河合雅司
講談社現代新書
人口減少の問題点を年表形式にまとめた、たいへんな労作
国立社会保障・人口問題研究所が、全国の消滅可能性都市について公表して以来、人口減少をテーマにした書籍が多数出版されるようになった。 一方で、それらの書籍の中には具体的にどういったことが起こるのか、という視点については論点が錯落としていて、恐怖心や不安ばかりが煽られたり、逆に人口減少に伴うメリットが過度に強調されたりするものも多い。 その点、本書は人口減少に伴って起こると予想される膨大な問題点を整理し、年表形式で述べられているため、読者はその年に自分は何歳になっており、社会的な立場がどのようになっているのかを落とし込むことができる点でたいへん優れている。 問題点の指摘だけでなく、合計特殊出生率が回復しても人口は回復しないメカニズムなど、政府の取る対策が成功したとしても人口減少を止められない、その「しくみ」の部分についても詳しい。 解決への処方箋も示されているが、現在の社会制度や社会常識では対応しきれない抜本的な解決策が多く、公的資金で補てんされている部分の年金資金を死後に返済・循環させる方法や、居住地域を「戦略的に縮む」方法については、確かに効果はあるものの、財産権や税制、場合によっては憲法の改正まで必要になってくるかもしれず、この人口減少の問題の深刻さと、現状での手詰まり感を浮き彫りにしている。 人口減少の問題は、都市部に居住している方々には、まだ実感がわかないだろうが、私のように地方都市で生活している者にとってはすでに切実な問題である。若年労働力の不足、介護・医療現場の崩壊、「限界」集落を超え、続出する消滅集落と荒れ果てた里山がもたらす土砂災害の深刻さ…。これらの問題はいずれ日本人全員が向き合わざるを得なくなる。一つのシナリオとして本書を読んでおくことは有効だと思う。
4投稿日: 2017.08.15
もしアドラーが上司だったら
小倉広
プレジデント社
アドラーの「目的論」をはじめとする考え方がよくわかる本
タイトルだけ見ると、ドラッガーの「マネジメント」の解説本の二番煎じか?と思ってしまいますが、買って読む価値はあると思います。 アドラーの心理学の「目的論」の考え方は、その本質を理解するのが意外に難しい。この本は、アドラーの心理学をレクチャーしてくれる上司(ドラさん)と主人公のリョウとのやり取りを通して、アドラーの心理学をやさしく紐解いていく。 アドラーの心理学には、目的論以外にも共同体感覚や善の選択、ライフスタイル(自己と世界についての意味づけ)といった鍵概念が多くありますが、この本は『社会に出て数年、伸び悩む若者が、自己の成長のために何をなすべきか』という焦点に絞り込んで解説しているため、極めて解りやすいです。特に、大学生から20代の若い世代の人が読めば、大げさではなく生き方が変わるかもしれません。
0投稿日: 2017.07.03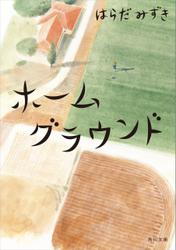
ホームグラウンド
はらだみずき
角川文庫
読みやすい文体の中に息づくはらだみずきさんの世界を堪能
「お父さんたちが子供の頃は、家でゲームなんかせずに、外へ出て遊んだものだ」しかし、現実はどこの公園もボール遊び禁止。そんな問題提起から始まるストーリー。 老人と社会人になって日が浅い孫が主人公:圭介のホームドラマ。はらだみずきさんの文体は本当に読みやすく、これなら小学校高学年ぐらいから充分読めます。前半では比較的淡々と進むストーリーが、後半になると登場人物の人生模様が変化していき、あっと驚く秘密も明かされていきます。はじめは電車の待ち時間などスキマ時間に読んでいましたが、後半はまとまった時間に一気に読んでしまいました。
1投稿日: 2017.03.20
空飛ぶタイヤ(上)
池井戸潤
講談社文庫
圧巻のリアリティ
凄いボリュームと、まるでノンフィクションを読んでいるかのようなリアリティ。 三菱銀行にお勤めだった池井戸さんが実際に見聞きしたエピソードも多分に含まれているのでしょう。出来れば週末にじっくり腰を据えて読むべき小説です。 他の皆さんが素晴らしい感想・レビューを書かれているので、私の出る幕はないのですが、一言だけ。 私の住む町は三菱自動車の企業城下町のようなところで、現実のリコール隠しに関わる影響で、地域経済は大打撃を受けました。原因個所と無関係の部品を担当した、たいへんに技術力のある下請けでも発注減による経営危機だけでなく、「三菱と取引があった」というだけで差別的な扱いを受けて、倒産した会社もあります。 大企業の論理に振り回させれるのはいつも無関係で善良な庶民や、ヒエラルキーの最下層の人々。戦争も原発事故もそうですね。 池井戸さんには、何年かした後には原発事故をテーマにしたフィクションも書いて頂きたいな、と思います。 余談が過ぎました。
4投稿日: 2014.09.05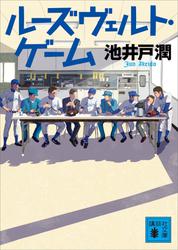
ルーズヴェルト・ゲーム
池井戸潤
講談社文庫
平成ヒト桁代までには存在した、こういう世界が懐かしい
「半沢直樹シリーズはヘビーすぎる」と思われている方にオススメです。 企業の業績不振や銀行からのリストラ要求、株主への対策、業界大手から仕掛けられるM&A、下請け製造業の悲哀。起死回生の新技術の開発。それらの経営上の色々なドラマが、社会人野球チームの成績低迷とチーム内の不和、エースと主峰の引き抜き、監督の交代と新エースの成長というドラマに密接にリンクし、同時進行でストーリーが展開されます。野球チームを中心に再び心が一つになった青島製作所。 現実は変わりませんが、最後は野球というスポーツの面白さが全部を洗い流してくれる。 私の会社でも社内運動会や社内旅行的なイベントが無くなって久しいですが、なんだか平成ヒト桁代までには存在した、こういう世界が妙に懐かしくなりました。
1投稿日: 2014.09.05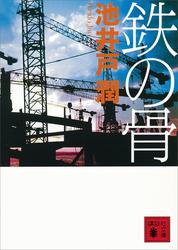
鉄の骨
池井戸潤
講談社文庫
後半は息つく暇もない展開に痺れます
中堅ゼネコンの現場で充実した仕事をしていた主人公の平太が、突然『談合課』と揶揄される業務課へ異動、現場とは全く異質な世界にカルチャーショックを受ける。会社や仕事に対する疑問や社会の「必要悪」に流されそうになる自分、恋人の心も自分から離れ、それらをどうすることも出来ない自分の未熟さを思い知る平太。。 しかし直属上司の西田、尾方常務、談合のフィクサーの三橋ら池井戸さん一流のキャラの立った登場人物たちとの痺れる ようなやりとりが見ものです。「現場にいたんじゃ十年かかっても経験できないようなことが起こるだろうよ。お前は運がいいんだよ」この西田の言葉がこの小説のテーマなのでしょう。 ストーリーは最後に向かえば向かうほど息つく暇のない密度の濃い展開に、平日前の夜に読み始めるのは危険です(笑)
1投稿日: 2014.09.05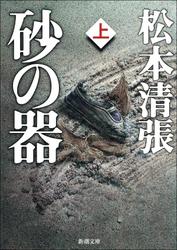
砂の器(上)
松本清張
新潮社
現代においても燦然と輝く存在感
昭和40年代に書かれた推理小説で、登場人物もほとんどが戦前生まれ。コピー機もなく、あらゆる情報は手帳に書き写し、大家と店子の関係が密接だったり、と現代とは全く環境が違うが、推理小説の肝のトリックの部分は本当に読ませる。今西巡査部長もスーパー刑事というわけではなく、地道な作業を積み上げて犯人を追い詰めていく。現代においても燦然と輝く傑作です。やっぱり松本清張は凄い
8投稿日: 2014.08.25
ラピスラズリさんのレビュー
いいね!された数57
