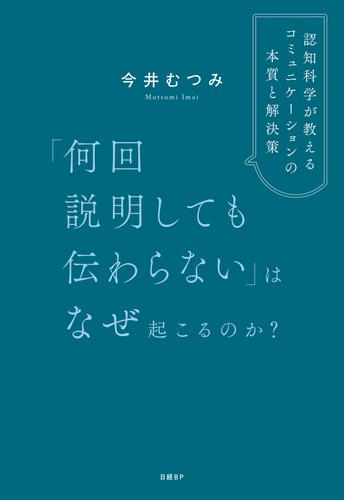
総合評価
(204件)| 44 | ||
| 77 | ||
| 64 | ||
| 7 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
個人的に今1番の推し。今井むつみ。 その新刊買わないわけない。 内容は今までの本と大差はないが、大きな違いはビジネスパーソン向けということ。 1番、心に残ったのはバイアスの話で出てきた流暢性バイアス。確かにあるよなー。喋りが上手いから、なぜか説得力ある人。 分かり合えない前提で、どうスキーマを見取り、克服していくか。その秘訣はシステム2の思考で、多くの経験を積んでいくことにしかない。 具体と抽象を行き来しながら。 ポッドキャスト、超相対性理論でも同じことをしている。 こういう本を手に取らない人は、つまり、自分のコミュニケーションに問題意識が無い人にはどうアプローチするのがいいんだろう? 地道な自己開示と寄り添う言葉掛けしかないのだろうな。人生に近道はない。
1投稿日: 2025.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネスにおける認知科学の知識の必要性が書かれている。(自分に必要と思ったことだけ書き出し) ・理由を伝える ・相手の感情に寄り添う ・悩みを共有する ・感情をぶつけても、問題は解決しない 上手な説明→具体と抽象を行き来する 具体…分かりやすくなる 抽象…全体を捉えられる ・忖度の問題点は、仕事の成功ではなく人の気持ちへの配慮を優先してしまうこと いいコミュニケーションとはなにか、と常に考えながら人との関係を築いていきたい。 ・失敗や間違いを認める ・バイアスの存在に気をつける ・説明する ・暗黙の了解に頼らない ・相手をコントロールしようとしない ・聞く耳を持つ
3投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログスキーマ(ものの捉え方)が人それぞれ異なるので、完璧に意思疎通することは非常に難しい。 その中でも、何より「相手の立場を考え寄り添う」ことが、コミュニケーションを取る上で重要であり、日頃から意識したいと感じた。 とは言っても、失敗はつきものなので、そこから反省し糧にすることを意識していきたいと感じた。
0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと怒りが強い性格ですが、他人のことで自分の機嫌が悪くなることが勿体無いと思うようになり、アンガーマネジメントや自分のご機嫌をとる方法を色々と試していました。 プロのカウンセラーさんにも相談したところ、こちらの本をお勧めされました。 結局は伝わらなくて当然な理由は至極納得ですが、 どうしても伝えた方が良い場合にどうするかが知りたいところだったので、 こたけ正義感さんが弁論で言ってた裁判での擦り合わせを夫婦の話し合いに横展開する方法の方が実際に役に立ちそう。
1投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった! 構成が分かりやすく、そして「分かり合う」「分かるように伝える」という簡単ではないことをそれでも工夫して実現するには、というスタンスがとても好きだった。 「伝わる」までの壁や仕組みを順を追って説明しながら、定期的に認知バイアスの種類にはこういうのがある、と例をまとめてくれるのが構成で分かりやすかったな、ありがたかったな、と思うところ。 内容面では、まず冒頭での「我々は言葉のやり取りを過信しているのではないか」という言葉から、言葉を扱うことが好きな自分としては刺さって引き込まれた。 読みながら納得したりハッとしたりしたのは、「理由があって結論を出しているのではなく、価値観に基づいた結論を出してから理由を後付けしていることがほとんど」、「感情に配慮した方が合理的」、「我々は異なるスキーマ(考えるときのベース)を持っており、察する力がない、経験能力の優劣と思われがちなものもスキーマの違いによることがある」、「相手をコントロールしようとする限りいいコミュニケーションは取れない」、「直観は天から降ってくるのではなく、長い道のりをかけて養うもの」、などなど。 そして「おわりに」のメッセージが個人的に胸アツで大好きだった!
1投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知心理学の視点からコミュニケーションにおいて受け手伝え手それぞれの立場で何が起こっているのかを丁寧に解説している良書。基本的な概念や考え方が多いが俯瞰してコミュニケーションを見つめ直す良い機会になった。
1投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書なので、実践のヒントがたくさんあるのは良い。ただし、明日使える技術と言うよりも、「こう言うことに気をつけて、頑張って」と言うタイプの本なので、その点は注意が必要。 どんな人と話す場合でも前提とするもの(スキーマ)な異なるので、分かり合えないのは仕方がない。ではどうするか、と言う点を丁寧に説明している点は好評価。異文化コミュニケーションの話もあり、外国語を学ぶ大学生も学ぶことは多いと思う。就職する前に読むのも良し、就職してコミュニケーションに悩んでから読むも良し。
1投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
以前、私が話したことが何か別の解釈で社内で伝わっていたことや私自身も元から察しの悪いところがあり、相手の発言を曲解した結果失敗する。ということがあったためこの本を読んでみた。 わかりきったことだが人は皆異なる人生を送っており、それぞれが異なる人生観を持っている。他にも様々な要因があるけど、なんらかの偏った考えを持っている我々が完璧に話を伝えることがそもそも不可能だという大前提を認識しよう!ということのようなので、お互いにただ日本語が通じる人くらいに考えて「話は正確には伝わらない」と割り切っておけば気が楽だしストレスにならないかもしれない。 じゃあ伝えるにはどうすればいいのか?この部分は内容がちょっと薄かったように感じたけど、基本的には伝わらない原因について詳細に語られているので、原因がわかれば対処法も自ずとわかるでしょ?ということなのかも…… それと内容とは全然関係ないけどカバーの手触りが気持ちいいので、本屋で見つけたらとりあえず手に取ってみてほしい。
6投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日々思っていた、なんで伝わらないんだろう?という理由を教えてくれる本。 解決策より、その本質を丁寧に教えてくれる。 解決策としては、理由をちゃんと言う、日々コミュニケションをちゃんととるということ。
1投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が人に対して言葉を伝える時いったい何が起こっており、なぜ意味が伝わらないのか。認知科学を通じて伝達時に起こる現象とその対策が解説されている。そもそもなぜ人間が言葉というプロトコルの情報量で伝達が可能になっているのかという当たり前の前提に疑問を感じられる様になった。善いコミュニケーションを取るために必要なのは、そのプロセスを絶えずアップデートしていくリベラルな態度自体にあると感じた。
1投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ私のコラムではおなじみの、コミュニケーション障害の部下を想起しながら読んだ本。 いや、発達障害者だけでなく、すべての人がこのタイトルと同じ言葉を発することだろう。 伝わらないのだ。 私は部下にいつも「相手の立場に立って考えてからコミュニケーションをとるよう」指摘していた。 でもその私自身、部下が発達障害である、ということは全く思い浮かびもしなかった。 何回か訓練をすれば学習して、きちんと報告できる、わかりやすいメールが書ける、と思い込んでいた。 そうして3年。 さすがにおかしい。 そう思って色々調べて、もともとの彼の特性であろうことを把握、 対策を「学習」から「事後対策」に切り替えた。 まだその成否はでていないけれど、、、 そう、この本でも「相手の立場に立って」はキーワード。第3章。 でもこれだけではない。 システム1とシステム2 という概念が重要であると捉えることができた。 ノーベル経済学賞受賞者 ダニエル・カーネマンの理論。 ファスト&スロー あなたの意志はどのように決まるか?(ハヤカワ文庫) ...読んでみよう システム1 ファスト思考 直感による意思決定 システム2 スロー思考 時間をかけて熟慮する知的活動 大半の意思決定はシステム1で行う、というのだ。 効率がよくおおむね正しい、という。 ただ、私の部下は1でたいてい間違える。 だから2によって補正するしかない。 でも頭の中では補正できない。 外部記憶装置、チェックリストを使って補正する、というのが今考えている対策。 その意味で対策の方向が間違っていない、と理解した。 最後のほうで映画「ハドソン川の奇跡」の話が出てくる。 機長はとっさの判断で川に不時着し、乗客全員が助かった。 管制塔の指示でも助かったのでは?と裁判にまでなったが、最後は機長が正しいことが証明された。 この判断はシステム2。それを咄嗟にやり遂げたのだ。 昨年1月2日の羽田空港自衛隊機の接触で大火事になった空港機も、一人の死者も出さなかった。 これもシステム2、日頃の訓練のたまもの。それを瞬時にやり遂げた、、、 これらのことを部下に臨むことはない。時間をかけてもいいから、「正しい」コミュニケーションがとれるよう、 ツールを作ってほしいものだ。 いやいや、深い本だ。 はじめに 認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策 第1章 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない 「人と人は、話せばわかり合える」ものなのか? 「話せばわかる」とはどういうことか? 「話せばわかる」の試練――記憶力の問題 人の記憶はどこまで「曖昧」なものなのか 「相手にわかってもらえる」を実現する方法を考えよう 第2章「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、 いったい何が起きているのか? 「言えば伝わる」「話せばわかる」を裏側から考える 言っても伝わらないを生み出すもの①「理解」についての2つの勘違い 言っても伝わらないを生み出すもの②「まんべんなく公平に見渡す」ことはできない、視点の偏り 言っても伝わらないを生み出すもの③「専門性」が視野を歪ませる 言っても伝わらないを生み出すもの④人間は「記憶マシーン」にはなれない 言っても伝わらないを生み出すもの⑤言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく 言っても伝わらないを生み出すもの⑥「認知バイアス」で思考が止まる 様々な思い込みと認知バイアス 第3章「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには? ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか 「相手の立場」で考える ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「心の理論」 ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「メタ認知」 「相手の立場」に立てる人のコミュニケーション 「感情」に気を配る 感情を味方につけるコミュニケーションのコツ 「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ 「伝わる説明」を、具体と抽象から考える 「意図」を読む 第4章 「伝わらない」「わかり合えない」を越える コミュニケーションのとり方 「いいコミュニケーション」とは何か? 「コミュニケーションの達人」の特徴① 達人は失敗を成長の糧(かて)にしている 「コミュニケーションの達人」の特徴② 説明の手間を惜しまない 「コミュニケーションの達人」の特徴③ コントロールしようと思わない 「コミュニケーションの達人」の特徴④ 「聞く耳」をいつも持つ 終章 コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために ビジネスの熟達者とコミュニケーション ビジネスの熟達者になるための「直観」
3投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の今の仕事は、「保健指導」をすること。 年上の方々に対して、その方の職場で30分ほど健康課題について話をする。 相手は医療職ではなく、 自らの意思で(病識があって)受診したのでもなく、 何ら健康上の問題意識はなく、保健指導も希望しておらず、忙しいからなるべく短時間で!というケースもある。 「聞きたくない」と思っている方が相手だと、仕事の難易度は増す。とはいえ、その方の今後がかかっているので、簡単に仕事の対象から除外することもできない。 今後の健康のために行動変容を促し、面談後にも定期的に電話でお話しすることもあるが、 まさに、「何回説明しても伝わらない」、と感じることもあり、本書を手に取りました。 なるほど、その方と私の「スキーマ」、「フィルター」が全然違う。 「メタボ」だの「動脈硬化」といったワードが、どのように理解をされるか? 抽象と具体を行き来しながら、説明。 人は忘れる、という前提も大事。 私は忘れる。相手も忘れる。 「神聖な価値観」の話も、なるほどなーと。 笑っちゃうくらい、人は「神聖な価値観」に基づいて行動している。そのことを覚えておきたい。 感情も大事。。 遅刻厳禁。服装や雰囲気、挨拶で好印象を与え、敬語の使い方、スピード、間の取り方に気をつけて、、 嫌いになられたら、話を聞いてもらえない。 逆に、この人嫌!ってこちらが感じちゃったら、良い提案もできない。。 なぜAIではなく、生身の私が保健指導をするのか? 自己開示をして良い関係性を。 直感力を鍛えたい。 メタ認知で振り返ると凹むから、やめようかと思ってたけど。 向上心を忘れずに! …聞きかじったことを、さも自分の知識かのように話すことだったり、流暢に説明して相手を信頼させることだったり、私のことかと思わせられる事例もあった。 もうすでに結構内容を忘れてるっぽいので、随時また読み返したいです。
1投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ後輩の指導でまさにタイトルの事象が発生したため、参考になればと読み始めた。 結果、相手だけが悪いのではなく、自分の伝え方が悪い、想像力が足りない、との気付きを得ることができ、年明けからの仕事の進め方を考えるうえで、大変参考になった。 本の内容も、具体的な例とともに認知科学、心理学の観点から、分かりあえない理由と、どうやったら伝えられるようになるかの説明が分かりやすかった。 この内容もすぐ忘れてしまいそうなので、時間をおいてまた読んでおきたい。
1投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コミュニケーションとは、言語を理解する力、文脈を把握する力、記憶する力、思い出す力、想像する力などに支えられた「認知の力」。 伝えたいことが上手く伝わらない原因は、個々人のあたりまえの違いを乗り越えることができなかったり、認知の力が上手く働かなかったりすることにある。すなわち、間違っているのは言い方ではなく、「心の読み方」で、「何をどう聞き逃し、都合よく解釈し、誤解し、忘れるのかを知ること」が不可欠。 相手に正しく理解してもらうことは相手の思い込みの塊と対峙してくことで、すなわち自身が持つ思い込みに気が付くことである。 意見がすれ違った時に必要なのは、丁寧に説明することではなく、それぞれがどんな視点からその意見を言っているのかを考え、聞き取り、それぞれの懸念を払拭していくことである。 メタ認知を上手く働かせることのできない人は、自身が作った資料などを見直すことや指示通りに自分が動けているかを見直すことが苦手。
2投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は聞き逃し、都合よく解釈し、忘れる…ということを認知科学の視点から解説している1冊。 なによりタイトルが秀逸。 「何回説明しても伝わらない」は本当に日常によく起こる出来事だ。 ただそれを解決できる方法を期待していた分、期待外れの内容。 半分以上が、なぜその現象が起きるのか?を解説している。たしかにタイトルはそう書いてあるからその通りなんだけど、それを解決する方法がもっと的確に書かれているかと思ったら、他の本でも良く書かれているようなことばかりで、新しい発見はなかった。 ・人は忘れる生き物 ・言葉や感情が記憶を書き換えていく ・さまざまな認知バイアス ・相手の立場で考える ・メタ認知が重要 ・具体と抽象を上手く使う ・感情に気を配る(理由を伝える、共有する、感情をぶつけても解決しない) ・コントロールしようと思わない ・聞く耳をいつももつ などなど。 結局は「人は伝わらないものだという前提で、相手に気持ちに立ち、丁寧に説明する」程度の話。 本当に解決を求めるのであれば、「伝わらない理由」をメインにした本ではなく、具体と抽象の練習やメタ認知の本を読んだ方が役に立つかなと思った。 期待しすぎた自分の問題。
2投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ我ながら(珍しく)実践できている内容が多かったかな。。 読む前に想像していた・期待していた内容とは違ったのでそこも残念。 でも、今まで本書の内容が実践できていたからこそ、これから心の余裕がなくなった時にはつい心がけるのを忘れてしまいそうなことではあるよなと改めて思わせてくれた本ではあった。
2投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなくそうだろうなと日々思っていたことが言語化されており、考えが整理された気がする。コミュニケーションは双方向でのやり取りがあって初めて成り立つものであり、双方向での理解の一致性が客観的レベル、主眼的レベルどちらも等しいもしくは近しい状態になることだと改めて感じた。相手のコンテキストをどれだけ見られているか。捉えようによっては、デザインの世界でいうところのUXデザインそのものがここにあるように思われる。 書内途中にコメントあったが、認知科学の世界は産業と直接結びつきにくく、学会運営も大変だと。一方で認知科学の世界は人間中心の真髄とも考えられ、社会生活やビジネスの本質をついた学問なのかもしれない。 「おわりに」を読むと本書のポイントがそこに凝縮されているように思われる。
1投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすく、サラサラ読めた。 人間にはスキーマがある、いうこと知っておくだけでも職場でのコミュニケーションエラーに寛容になれると感じた。 うちの会社にはいろんな人がいるので、会話に困ることが多い。今後の自分のメンタル維持のためにも、読んでよかった。結局相手の立場になって考えることってどんなシーンでも重要だと思う。どんなベテランでもそれが苦手な人っているよな〜。 人間関係で困ったときにまた読みたくなる一冊。
1投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言葉を発している人と、受け取っている人では、「知識の枠組み」も違えば「思考の枠組み」も異なるため、仮に全ての情報をもれなく伝えたとしても、頭の中を共有することは出来ない』この枠組み、スキーマという物を知れただけでも自分にとって大変価値があった。子どもに対してなど常に意識できるようになりたい。
1投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手に話が伝わらない、と感じていたときに、その人の独自の文脈が強すぎる、という感想を持っていたが、それは枠組み(スキーマ)ということらしい。一歩引いてコミュニケーションを取るヒントになる。
2投稿日: 2024.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族との会話、仕事での会話でなんでそうなるかなぁ、とため息しかでない今日この頃。コミュニケーションエラーが起きたり、相手の言ったことを捉えられている自信がないという強迫観念でメモを取ったりするものの、うまく理解できてないのか相手に言い負かされるように押し切られたり。会話をする際に相手の言ったことを記憶、理解して対話するということに自信がなくなってきたので、どうしたものかと思っていたらこの本の宣伝を目にしたので読んでみた。 この本を読むと意思疎通で伝わることってすごいことなのだとあらためて思う。人類みなコミュ障なんじゃないかと思えてきた。伝わらない仕組みを詳細に細分化してどこからどこで伝わることが阻害されるのか、伝わらない要因になるのかをすごく丁寧に教えてくれる。それもけっこうシステマティックに。重要な概念がいくつか紹介されているので、キーワードを抑えると読みやすいかもしれない。人がそれぞれもっている「スキーマ」が異なることとか、送り手と受け手のそれぞれにある「バイアス」、「記憶」の違いは、読んでいてなるほど、と思える。あまり意識していなかったことをあらためて読むと本当にしみじみ再認識させられる。書かれている内容は、意思決定科学や心理学を勉強し人ならなじみのある話が多いと思う。それでも気が付くと配慮を怠ってしまうのだから、コミュニケーションの達人は相当すごい努力をした人なのだろう。 相手とのコミュニケーションの改善には、改善策を考えるための丁寧な分析が必要でそのやり方はこの本でかなり学べる。ときどき会話がうまくいかなかったときに見返すようにしたい内容だった。
2投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手を思いやったコミュニケーションを取りましょう、という話。「そうは言ってもね」という感想がフツフツと……
1投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ後半に向かってスッキリしていく。昔から人の常識は違うというけれど「なるほど」と思える内容であった。知識や思考の枠組み(スキーマ)が同じ人はいない。なぜなら育ってきた環境が違うから。ここで思い出されるのはアインシュタインの「常識とは18歳までに身につれた偏見のコレクションのことをいう」である。近いスキーマになるようお互いの歩み寄りが不可欠なのは言うまでもない。本書の内容も教育現場で伝えられないものだろうか。
1投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容をまとめると、 どんなに丁寧に説明してもみんな違う環境で育った為、受け取り側は解釈が異なるよね。 という話。 新卒の私からしたら、上司が専門用語で説明してくるたびに意味が分からず悩んでいたが、分からないことが普通であると肯定してもらえたようで嬉しかった。みんな、解釈が違うことを念頭に置いてすれ違いが起こなさないよう気をつけたい。 コミニュケーション能力が低いので、この本にも書いてあったけど職場の人ともうまく行くようコミニュケーション能力は身につけていきたい。
1投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中で何度かだれてしまったけど、基本的に人に対して気をつけた方が良い内容や教訓がまとめられていて良い教科書本だった。 自分が気をつけて周りの人のことも考えることも大事だけど、周りの人も同じ意識になって貰うことも大事だと思うのでそこの巻き込み力が難しい気はした。
1投稿日: 2024.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手と自分とで、価値観・固定概念が違うからこそ「伝わらない」が生まれてくるものである。 相手の話も聞いてあげる、理解してあげることが打ち解けることへの近道だと思った。 ビジネス書というより読み物として面白い内容。 余談ではあるが、4歳まで子どもは他者の目線の感覚が無いことは勉強になった。
1投稿日: 2024.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログとても興味深い本でした。 「コミュニケーション」と一言でまとめられるこのワードの奥深さを考える良本だと思います。 スキーマの概念とか、なんで相手に分かりやすいように情報を伝える工夫をしないといけないのか、改めて考えるきっかけになりました。 当社の現場配属者、プロジェクトマネジメントを担当する社員の必読書にしたらいいのでは、とも思いました(笑)
1投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも情報の受け止め方のスキーマが人によって違う これは言い方を変えたり何度も言ったり、で変わるものではない 人間の記憶容量は1GB 大切なのは失敗コミュニケーションの分析 直感は日々の準備と訓練から でもそれが生成AIの登場で奪われる? 流暢性バイアス 生成AIが答えを出すプロセスは人間と異なる
2投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手に伝わらない理由の構造がよくわかった。 ・相手の視点と自分の視点は様々なので、すれ違いが生じる ・自分の視点で聞くと、様々な認知バイアスがかかり記憶が歪められることもある 相手との接し方で気をつけること ・常に相手がどう捉えるかの視点を気にかける ・抽象と具体を上手くバランスとって説明する
1投稿日: 2024.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログすっかり今井むつみ先生のファンになってしまって、この書き下ろしも早速読みました。認知科学の成果をもとに、人の認知(スキーマ)の仕組み、記憶の仕組みを紹介しつつ、良いコミュニケーションをいかに実現していくかを説き、優れた研究者が、優れたビジネス関連書籍を生み出すことを証明した一冊。直観を磨くには意識を向けた、メタ認知を働かせてよ弛まぬ歩み、努力を10000時間続ける必要がある、とする部分も納得できる。 あと、どれだけ時間があるのかはわかりませんが、直観を磨くために努力を続けていきたいと思いました。
1投稿日: 2024.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと認知科学の話がメインだと思っていたので、少し拍子抜けした。非常に読みやすかったし、コミュニケーションの認識を改めるという点ではタメになる部分もあった。
1投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログチームメンバーに対して言ったことがうまく伝わらない、伝わったと思ったことがそうではなかったことがあり、本書を手に取った。人は考える時にスキーマ(知識や思考の枠組み)を元にしていること。人の記憶は曖昧で、忘れることで新たなことを記憶するなど認知科学の基礎を学べる良質な本です。相手と良い関係性を築くために学んだことを活用し、チームメンバーが成長できるようにサポートしたい。
1投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人と人はわかりあえない、と主張する本はこれまでも他の本で見てきたが、「わかりあえない要因は何なのか?」「その前提が合った上でどうすればいいのか?」と踏み込んだ内容に言及していたのはこの本が初めてだったと思う。スキーマの存在を理解していれば、他者に優しくできるような気がした。
1投稿日: 2024.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何回説明しても伝わらない」場面は嫌と言うほどある。結局諦め妥協するのがオチだ。 そんなモヤモヤを解消したく楽しみに読んでみた。 そもそも丁寧に伝えれば理解してもらえるものではない。 人それぞれスキーマを持っており、同じワードでも感じ取り方が異なる。 しかも、その時の感情も理解を左右する要素とのこと。 少しでも意図したことを伝えるためには、相手のスキーマに思いを寄せその時の感情を推しはかり、ワントーンではなく具体と抽象の振幅を加えることが求められそう。 要は一方通行ではなくしっかり聞くことで相手を慮る姿勢が必要だろう。決して論破するのではなく。理性よりも直感の大切さも教えてもらった。
3投稿日: 2024.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。人はそれぞれ持っている価値観や考え方の枠組みが違うから、話せばわかってもらえるという考え自体が伝わらない要因の1つである。けっこう目からウロコの話で面白かった。相手がどう考えてるのか考えないとダメだよなぁと改めて思いました。
5投稿日: 2024.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井むつみ氏による著作の中では、インパクトが弱いと感じた。できるだけ分かりやすく丁寧に、具体例を交えながら著した結果だからかもしれない。 AIやデジタルが主流になってきた時代にとって、コミュニケーションは必要な技術であり、それは相手をコントロールしたり、押さえつける技術ではない。この本は、円滑にことを進めることを目的とするならば、コミュニケーションにはどのような方法があるかを教えてくれる。著者の作品を読んだことがない方にはおすすめできる。
1投稿日: 2024.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分と相手の前提知識が異なることを理解した上で、どうすれば伝わるのかを考えることの大切さを学びました。 相手に効果的に刺さるように、具体と抽象を上手に行き来して共通認識を得るという、すごく難しそうなことが、なんだかできるような気がしてくる本でした。
1投稿日: 2024.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログまさにこの書籍自体が「具体と抽象を行き来しながら」わかりやすい言葉で説明されていてよかった。今井先生の他の書籍、特に「ことばと思考」など読んでおけばより理解が深まると思う。
1投稿日: 2024.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションの難しさ(何度説明しても意図したとおりに伝わらない)を、コミュニケーションの本質を押さえながら説明した本。 人間の思考には意識されずに使われる枠組み(スキーマ)があり、知識、経験によって人それぞれ違う。スキーマが違うと同じ言葉でも理解が異なる。このコミュニケーションの本質をひとつ理解出来ただけでも、自分にとっては大きな習得だった。 常に相手の立場にたち、相手のスキーマにあったコミュニケーションを心がけて、なるべく誤解を生じないやり取りを行っていきたい。
1投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
間違っているのは言い方ではなく、心の読み方=相手が持っている当たり前(スキーマ)を理解して、それに合わせて話す。
1投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスキーマが違えば伝わらないというのは参考になった。年齢の高い人はガチガチに固まったスキーマで話すことが多く、自分のものの見方から絶対出ないみたいな人が多いように思う。結局、伝え方や聞き方をメタ的に認知して修正できる人と、それが出来ない人では大変な差が開いていって、結局そうした態度がある程度噛み合う人同士でしかコミュニケート不能なのではないかと思った。全員認知しているものがバラバラだというのは、仏教の「業界(ごうかい)」に通じる話だと思った。
2投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションの齟齬はなぜ起きるのか。 お互いに、違う環境、違う考え方が前提であれば同じことを話していても、捉え方は人それぞれ。 だから、世の中には詳細なマニュアルも存在する。 AIはあくまで、言葉を考えることはない。言葉や何かを習得するのは、具体と抽象化を繰り返した先にあるもの。 相手の立場に立って考えると言うけど、それがなかなか、難しいと思う。忍耐力も必要だろう。 私なんかも思い込みが激しい方だと思うので、なかなか他人と話が噛み合わないことがあるけど、それでも、今こうしていられるのは、幸いにも、コミュニケーションの高い人たちに恵まれた結果でしょうか。 脳の記憶容量は1Gバイトらしいですが、言葉の裏にある意味を理解できる人は、相当、高性能なcpuを積んだ人でしょうか。
3投稿日: 2024.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「話せばわかる」は「幻想」かも、から始まる潔さがいい 人の気持ちや考えは、そもそもわからないもの その前提の上で双方から難しい努力を積み重ねて、ようやく良好なコミュニケーションが成立するし できているつもりで、できていないことも多い 工夫しても反省して視野を広げても寄り添っても どうしても会話が通じない人は実際いるけど 努力を試みる側の人間を目指したい 私は正直、もういいやって諦めて極力関わらないを選択してしまいがちな性格なので自戒
1投稿日: 2024.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書らしく、流暢に読みやすく、忙しいビジネスパーソンも短時間で、コミュニケーションに関する即席的アドバイスを摂取できる。今井むつみ先生の書籍としては物足りないが、これはビジネス書というスキーマであることを前提に読むことが重要である。本書籍は、とにかく相手の立場になり考えることが論じられているためだ。
1投稿日: 2024.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大体何となく知っている話がおおかった。 人はそれぞれの認知スキーマを持っていて、そのスキーマによって世界を見ているし、人の話を理解する。そのスキーマーに対する理解なしには本当に伝わる話はできない。 「相手の立場を考えて」という昔ながらの箴言がやはり有効。 p294 直感を鍛えることが必要。 長期に及ぶ真剣で工夫を凝らした訓練 「なぜ直感の方がうまくいくのか?「無意識の知性」が決めている。」ゲルト・ギーゲレンツァ その他 ・流暢性のバイアスがある。 流ちょうに話す人を信用しやすい。 ・p198 理由になってなくても理由を述べているように見えれば説得性が増す。
1投稿日: 2024.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学の観点からコミュニケーションの本質を知ることができる。 【概要】 ●人は、何をどう聞き逃し、都合よく解釈し、誤解し、忘れるのか。 ●言っても伝わらないを生み出すもの ●具体と抽象のよくあるエラー ●「コミュニケーションの達人」の特徴 【感想】 ●スキーマを理解すれば、言葉だけでは他人と頭の中を共有することができないことを理解できる。 ●様々なバイアスに関しても説明されているため、認知科学に関する学びにもなる。 ●最後に結論が示されているが、これを実行するのはなかなか難しい。聞き手の能力には限界があるため、その点をどう折り合えばいいのかが真に悩む点である。ここは他書に委ねることにしたい。
3投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書を謳っているだけあり、専門性は薄く、非常に読みやすい内容でした。テーマはスキーマ。人はみな、異なる枠組み(スキーマ)を持っているため、同じ事柄も同じようには受け取れない。言われてみたら当たり前に感じますが、このスキーマ精神を持ち続けて、人と関わるのは簡単ではないですね。わかりやすい説明をするためには、上手な説明の仕方を身につけるよりのではなく、聞き手のスキーマを考えることが大切である、というのは、逆説的で印象的でした。
46投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は物事を認知する時、その人それぞれ異なった仕方で行っている。それは人の脳がそれほどハイスペックではなく(記憶容量に関しては1GB程度らしい)、受信したものをそのまま取り込むのではなくいわば「圧縮」のようなことをして行うのだが、人はそれぞれの知識や教養や考察力や応用力や識見などなどが異なっていて人によって偏りがあり、それを土台としてあるいは道具として認知や理解をせざるを得ないからだ。すなわちすべての人間は人それぞれ認知の仕方におけるバイアスを避けることができない。その土台や道具をスキーマ(枠組み)といい、人間同士の伝達とは、データがそっくり移行していくような類いのものではなく、発信者のスキーマと受信者のスキーマを介して圧縮・解凍という具合に変換されながら行うもので、そもそもが完全に正確には伝わらないということが前提であり、正確に伝えたいと思うのなら、自分と相手のスキーマの在り様とその違いを知ることが何より大切ということだ。さらには人間の脳は圧縮したものをいつでも正確に再展開することができない。なぜなら記憶そのものが正確でなく情報が欠落する(忘れる)ことはもとより、違った内容に上書きすらしてしまうようにできているからだ。本書は副題にあるようにコミュニケーションの本質を明らかにすることから始まるいわば基礎研究みたいなもので、タイトルからすぐにでも成果につながるハウツー本を期待して読むと肩透かしを食うかも。
17投稿日: 2024.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の認知な記憶の仕組みの説明があり、続いて直感に関する考察が書かれている。人は自身のスキーマ(思考のフィルター)を持っているので相手の立場を理解してコミュニケーションを取ることが求められる、は納得する。ただ、まま聞く話だなと思って読む。後半に記載されている達人の関する考察は興味深かった。 「ハドソン川の奇跡」で乗客全員の命を救った機長を例に取り、「すばやいけれども精度が低い思考」だある脳のシステム1を熟考が得意な脳のシステム明日2を使って長年の訓練の積み重ね、「すばやくて。しかも精度が高い、最高の判断ができる思考」に昇華させる。という件は深く納得する。知識と経験を繰り返すことで成長することを改めて確認できた。ちなみに生成AIへの警鐘もあり、著者の常識的な感性に安心した。
1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログひとはそれぞれに思考の枠組みとなるスキーマを持っていて、それによって考えたり話したりするので、相手に正しく理解してもらうことは難しい。 なるほど。自分なりに解釈すると、これは色眼鏡みたいなものかな、と。みんなそれぞれ、いろんな色の眼鏡(フィルター)をかけて世の中を見ているので、わたしが思ったこと(感じたこと)と他者が思ったこと(感じたこと)は当然違う。 で、完全に理解することは不可能を前提として、だけど分かり合うためには、〇〇さんの色眼鏡はどんな感じかな?と想像してみる、歩み寄ってみる、自分の色眼鏡が伝わる工夫をしてみる。 そこに出でくるのが、具体化と抽象化を行き来する能力。うーん、、、。 これなぁ、細谷功一著「具体と抽象」読んだんだけど、いまいち分からなかったんだよなぁ。 難しい。 もう一度、具体化と抽象化について、考えてみよう。
1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ当たり前の内容は人それぞれ違う。 その為解釈が変わり伝達内容が伝わらない事がある。 1,話合えば分かり合えるわけではない 心理学的言語でスキーマという、人それぞれがもつ思考の枠組みが違うからだ。 また話した側は覚えている、言われたら側は忘れているとう状態が多いのでズレがでる 2,本書のメインではないかもしれないが、人は意思決定する時1時回答を直感で行い、2時回答で熟考する。 この2時がメタ認知と呼ばれる事らしく、これができていないと、配慮が足りないや雑な仕事になってしまうようだ。自分はこの2時が全然できていないなと非常に思った。 3,話手の意図を掴む事がコミュニケーションとしては大切。その為、相手がどこまで理解していて、どこまでが共通認識なのか理解した上で話さなければ、いくら上手く話しても伝わらない事を理解した。 4,直感力を鍛えるには2,で書いたメタ思考、深く考え続ける事が重要で、その積み重ねが正しい直感力を養うと学ぶ事ができた。 これは経験上理解できる。直感が働く人は結局常に対象の物事を考えている人で、だからこそ即座に答えが出ると思った。 まとめ この本はただのコミュニケーション向上本ではなく、なぜコミュニケーションが上手くできないのか理由を説明してくれていて、個人的には非常に面白かった。 一方この本の内容をベースにコミュニケーションを上手く実施する為に自身で創意工夫が必要そうだ。
1投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログメタ認知のところやコミュニケーションの達人のところが特にわかりやすかった。冒頭のスキーマから人によくある認知のクセ等の説明もあり、スッと入ってくる。自分自身はまだまだ他者をコントロールする為の手段としてコミュニケーションを取っているなぁと反省した。
1投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝わらない理由があたり前で絶望的なことを論理的に説明した本。 ・伝わらないことを前提に、それでも本当に必要ならあきらめずにコミュニケーションをとる。 **他人と完全にわかり合うことは論理的に不可能だ。** たとえ100%の情報を伝えたとしても、知識や思考の枠組みが異なるため、同じ理解には至れない。この現実を受け入れた上で、コミュニケーションの目標を設定する必要がある。つまり、100%の共感をゴールにしてはいけない。実現できない目標だからだ。 **次に考えるべきは、理解を得る必要があるかどうかだ。** もし理解が不要なら、そのための努力は不要である。一方、相手に本当に理解してもらいたいならば、少しでも100%に近づけるよう工夫するしかない。そのためには、相手に実際の体験をしてもらったり、具体例を複数提示するなどの方法が有効だ。 **言葉には限界がある。** 言葉はあくまで記号であり、伝えられる範囲には限界がある。たとえば、お金を概念で説明する代わりに実際に現金を使わせたり、理科の新しい知識を実験を通じて学ばせたりする方法が有効だ。こうして、体験を通して伝えることで、理解が深まる。 **AIの限界もこの文脈で捉えられる。** 現時点でのAIは記号を処理するに過ぎず、人間のように記号の意味を解釈することはできない。したがって、記号操作が必要なタスクにはAIは便利だが、それ以上の理解や解釈を求めるタスクはAIには向かない。こうした限界を理解した上で、AIをうまく活用することが大切だ。
1投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログドッグイヤー50個程‼️非常に勉強になった。何となく理解していたものを抽象的に具体的に学ぶことが出来た。アドラー含め今年の読書は心理学の当たり年だ!
1投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人が各々持つスキーマが認識を歪める。正確には情報が伝わらない。経営方針の説明も様々な解釈をされてしまう。また、人間のメモリーは1Gバイトしかないというのも驚き‼️
1投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋で平積みされ、日経ビジネスでも紹介されていた本。コミュニケーションを図る上での認知に関する考え方を平易な文章でまとめた良作。 ひとつひとつが目新しい内容というものではないが、改めての気付きを得るにはちょうどいいボリューム。 いかに自分中心で楽な見方を変えるか、変えることが難しいかを改めて考えさせられた。
1投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆる話し方のスキル系書籍の類ではない、 認知や記憶の仕組みについて述べられた本。 言い方ではなく、心の読み方なのだと。 思いと解釈は一致しないこともある、 と知っていること。 人間の認知能力はあやふやである、 という前提に立って考えること。 人間の記憶容量は1GB程度であること。 これらは極めて肝要な知見だと思う。
2投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログぼんやりとはわかっていることだけれど改めて整理してもらえた感。ぼんやりとではダメなんだな、意識しないと。
1投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は大きく分けると 1章-現状のコミュニケーションの問題点 2章-それが起きている理由や構造 3章-うまく伝達するための方法 4章-実際の具体例 が書かれており、特に以下の2点が大きな学びとなった。 ○われわれ人間が物事を捉えるために使っているスキーマやバイアスの存在を理解すること ○感情が先に意思決定を行い、あとから根拠を結びつけている この2点を知ることで、自らの意見やSNS上での行き過ぎた意見をひとつ引いた位置から見ることが出来るだろうと感じた。 本書は単純な方法論的なコミュニケーションの上達法というわけではなく、上記以外にも脳の認知科学を基にした示唆に富んだ内容が様々あった。 メディアやSNS上には玉石混交の情報が飛び交い、多種多様な人とコミュニケーションを取る必要性が増えた今こそ一読をおすすめしたい1冊。
1投稿日: 2024.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、「コミュニケーションは難しい」と思うことが多々ありました。それで手に取った本が「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?です。この本のサブタイトル「認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策」から分かるとおり、著者の今井むつみさんは、認知科学と言語心理学を専門とする研究者さんです。 この本を読んで「自分が持つ偏見や認知バイアスを見つめることの重要性」に気づくことが出来ました。この本は「コミュニケーション」に悩むすべての人が読むべき本だと思います。 この本でおすすめしたいポイントを2つ紹介します。まずひとつ目のポイントは、「私たちが相手の言葉を理解するときに裏で動いている基本的なシステムがある」ということです。それは、認知科学用語で「スキーマ」と呼ばれています。 「スキーマ」とは、これまでの学びや経験、育ってきた環境、興味や関心から形成される「枠組み」のことです。人の話はすべて自分の「スキーマ」というフィルターを通して理解されます。「スキーマ」を「思い込みフィルター」と言い換えても良いかもしれません。 「自分が言ったことが、意図したとおりに伝わらない」ということが起こる理由は、その人のスキーマを通して理解されてしまっているからです。ここで重要なことは、「自分も相手の言葉を自分のスキーマを通してしか理解できない」ことを忘れてはいけないということです。 そしてふたつめのポイントは、私たちの選択や意思決定の仕方についてです。 ほとんどの人が「自分は合理的に判断し、意思決定している」と思っていますが、実はそうではなく、「好きか嫌いか」で物事を判断し、その後「論理的な理由」を後付けしているだけということです。要するに、すべての判断を「直観や感情」で決めているということです。 ただ、直観で決めることが悪いという話ではありません。直観による意思決定は、効率がいいし「おおむね正しい」からです。ここで重要はことは、「おおむね正しい」ということは、「時々間違っていることがある」ということです。そこで必要となってくるのが「メタ認知」です。メタ認知の典型的な事例が「テストの見直し」です。自分が今出している答えが正しいと思いこまず、たまに振り返り、見直してみることの重要性に気づくことができるのではないでしょうか。なにせ直観や感情で決めただけなのですから。 誰でも、「何回説明しても伝わらない」と悩んだり、つい「許せない!」とか「あの人と話をしてもムダ!」と切り捨てたくなった経験があると思います。 そんな時に、この本を読んでおけば、別のスキーマをもった人の立場や考え方を理解しながら、なんとか折り合いを付けたり、自分の中にある偏見に気がついたり、メタ認知を働かせて自分の出した答えを修正しながら、誰とでも上手にコミュニケーションをとれるようになるかもしれません。 とくに周りに自分と違う価値観や考え方を持った人たちが多いなと感じている人におすすめです。ぜひ読んでみて下さい。
11投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
分かりやすく伝えたつもりでも相手は全く理解していないことがよくある。 自分の説明が下手なのかと落胆したり相手の理解力のなさにイライラしたり、コミュニケーションを取る度に心労が絶えないが、こういった認識自体そもそも間違っているのではと気づかされた。 当たり前は人それぞれで、自分にとっての当たり前が相手にとっては当たり前じゃないこともある。 そのため言語力以前に双方の価値観の相違が根本にある。 人はどうしても自分の都合のいいように解釈してしまう。 説明する時は誤解や曲解が介された上で相手に伝わっている、と肝に銘じておきたい。 なるべく円滑な伝え方をするには相手の立場になって自分の言葉を多角的に捉えてみることが大切。
13投稿日: 2024.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ誤解が生まれるわけについてなんとなくわかっていることをしっかりと言語化したような本。 所感としては、結局は伝え方だよね?っていうこと。ただし、万人に通じる伝え方はなく、同じ伝え方をしても伝わる人と伝わらない人が存在する。つまり、伝える相手に合わせた伝え方にする必要がある。 伝える相手の専門性や物事に対する認識、また記憶違いをしてないか、誤って理解されてないか、などを考えてコミュニケーションしないとうまく伝わらない。
1投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学をベースにコミュニケーションについて学び直せる一冊。ビジネスをはじめ学校や家庭、SNSなどあらゆる場面でわたしたちの言語コミュニケーションにはどんな落とし穴があるか、現実の事件事故や興味深い心理実験の結果などの具体例を交えながらとてもていねいに親切に説明している。 言葉による情報の伝達は意外とあいまいで複雑で、人の認知にはいろいろな偏りやクセもあり、「(必ずしも)わかりあえない」をベースにしたコミュニケーションをという着地点は私にとっては新しくはないが(視点はまったく違うが、平田オリザ「わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か 」講談社現代新書をずいぶん前にとてもおもしろく読んでいる)、この本を読んではじめて目を開かれる人も多かろうと思うし、著者の提案する姿勢を心がけたコミュニケーション(それは必ずしも楽でも簡単でもないけれど)を実践する人が増えることであちこちの関係が少しでもスムーズになるといいなと思う。 個人的には、認知科学の国際学会はその道で一流の専門家が集って運営しているだけあってお金も上手に作って使えるし意思決定もうまいという話が興味深かった。 第1章で何回も言及されていたスローマン+ファーンバック『知ってるつもり 無知の科学』(ハヤカワ文庫)はずいぶん前に手に入れて積んであるはずなので、近いうちにちゃんと読もうと思う。
5投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは管理職の人には読んでもらいたい本。何度言っても伝わらないという相談や、どうしたら相手のモチベーションを上げられるのか、よく質問をいただくけれど、まずはしっかりと相手の話を聞き、相手の立場、相手の価値観を想像した上で、伝えることが大事だということが理解できる内容になっている。
1投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログわかる、がその人のスキーマ=枠組みを通したものである以上、自分と同じ考えに至った訳ではないと考えて過ごしたほうが良さそうです。メタ認知が出来て、自分を客観視すれば、相手のスキーマに寄せた提案ができそうで、日々訓練が必要です。
1投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【著者】今井むつみ 【出版社】日経BP 【感想】 ゆる言語学ラジオの準レギュラー的なポジションでも知られる、今井むつみ先生らしい満足度の高い本だった。 私が仕事で抱えている「子どもに伝わらない」問題と向き合うきっかけとして、本を購入した。 今井先生の本では頻繁に耳にする「スキーマ」が今回の主たるキーワードだ。 このスキーマの違いがディスコミュニケーションを生み出している。
1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学✕ビジネス書というのが新しい視点だったのかもしれない。障害の前に人は個人で認知の段階にかなり差があるからそこを配慮して根気よくコミュニケーションをとる、PDCA回すしかないのですね。
1投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言語の本質』が良かったがこちらも良かった。個人的に「話せばわかる」を全く信用していないが それを認知の観点から腹落ち感のある説明になっているのが良かった。 実生活やビジネスの中でこれらをどう落とし込んで活用していくのかを考えるのは自分自身だがそのためのヒントが後半の章に具体的に語られているのが良かった。
1投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で、タイトル通りのことで悩んで困っていたタイミングで、著者の方の話をYouTubeで視聴する機会があり、それでこの書籍の存在を知りました。 話し方の技術というかノウハウの話ではなく、「相手の立場になって考える」ってつまりどういうことか説明できますか?という内容です。 読み終わって私がどうなったかというと、なんと「おわりに」の著者のメッセージで泣いてしまいました。 ラクではなかろうとも、書かれているような生き方をしたいし、そういう人になりたいし、そう見られたいなと思います。
5投稿日: 2024.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログp.178 上司という立場、あるいは先生と呼ばれる立場になると、周囲から「確認してください」と言われることが多くあります。しかし、それは本当にその人が確認しなければならないものなのでしょうか。もしかしたら確認を頼んだ当人が、自分ですべき判断を避けているのかもしれません。 上司や先生と呼ばれる立場ならば、「確認してください」と言われた際には、ときには厳しく、 「これは『確認してください』という内容のものではないよね」 と伝えることも必要です。こうして、互いには見えない心の内を擦り合わせていくことで、「相手の立場に立つ」ことに近づいていけるのではないでしょうか。 ビジネスで頻繁に使われている「確認してください」という言葉は、非常に曖昧で、甘えのある言葉です。この言葉を使う場合には、「誰かに責任を押しつけることになっていないか」ということを、確認を頼む側も、頼まれる側も意識したほうがいいでしょう。 「相手の立場で考える」ことに関連の深い、「メタ認知」についても見ていきましょう。 「メタ認知」という言葉は、マインドフルネスなどの分野でも使われることも多いため、最近では聞いたことのある方も多いと思います。平易にいうと、「自分自身の意思決定を客観視すること」です。 ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの著書「ファスト&スローあなたの意思はどのように決まるか?」(ハヤカワ文庫)によると、私たちは意思決定の大半を「直感」で行っているといいます。 カーネマンは、この直感による意思決定を「ファスト思考」、別名「システム1」思考と呼び、時間をかけて熟慮する知的活動を「スロー思考」「システム2」思考と呼んでいます。そして私たちの意思決定は大半が実はシステム1思考に委ねられていること、そしてシステム1思考による意思決定は人間にとって効率がいいだけでなく、「おおむね正しい」ことが、本書では指摘されています。 システム1思考による意思決定は、「おおむね正しい」。それは、裏を返せば、ときに間違っていることがある、ということです。この間違いをシステム2思考によってチェックすること。これが「メタ認知を働かせる」ということです。 p.189 ①Excuse me, I have 5 pages. May I use the xerox machine? 「すみません。5ページだけなんですが、コピー機を使わせてもらえませんか?」 ②Excuse me, I have 5 pages. May I use the xerox machine, because I have to make copies? 「すみません。5ページだけなんですが、コピーをしなければならないので、コピー機を使わせてもらえませんか?」 ③Excuse me, I have 5 pages. May I use the xerox machine, because I'm in a rush? 「すみません。5ページだけなんですが、急いでいるので、コピー機を使わせてもらえませんか?」 これらのお願いに対する成功率は次の通りです。 ①60% ②93% ③94% 3 gas ①は、「because (一ので)」というような「理由」を伴わないお願いの仕方でした。 この場合は、60%の成功率で、割り込みをさせてもらえました。 一方、す%と一番成功率が高かったのは、急いでいるので(becauseTm in arusb)」と理由を示した③のお願いです。 ただ、ここで注目したいのは、②のお願いです。このお願いには確かに「理由」と思われるものがありますが、それは、「コピーをしなければならないので(becauselhave to make copies)」。コピーをしている人も、並んでいる人も、誰もが同じです。本来ならば割り込む理由にはならないはずなのに、①とほぼ変わらない成功率だというのは、驚くべきことでしょう。 188ページでも理由の大事さには触れましたが、改めてこの実験から、いかに「理由を伝えること(because)」が大事かということがわかります。 p.275 部下は会社員である前に、1人の人間で、生活者です。 仕事の場を一歩離れれば、別の話題で盛り上がることができる。プライベートが大変な時期には、少し仕事の加重をコントロールできる。こんな関係性が心理的安全性につながり、自発的に貢献し合える職場がつくられていくのかもしれません。 p.280 プラスのフィードバックで、不測の事態を防ぐ 「どんなときにも話を聞く」といっても、上司も人間である以上、自分に都合の悪い話を聞く際に「イヤだな」と思ってしまうのは、ある程度、仕方のないことかもしれません。私たちの思考や行動と感情は切り離せないということは、これまでもお伝えしてきた通りです。そのため、聞きたくない話を聞いた瞬間に、無自覚のうちに顔をしかめてしまった••・・というようなことは、誰にでも起こり得ます。 この一瞬が、相手に与える影響は多大です。「先生に注意された」という事実が、「先生は声を荒らげて怒鳴りつけた」という記憶に変わってしまうように、そこにネガティヴな感情があると、相手の些細な行動もネガティヴに脚色されてしまいます。 そしてその脚色を含んだ記憶が、現実に起きたことのように記憶されてしまう恐れがあるのです。 部下が失敗の報告をするときには、すでにそこに「ネガティヴな感備」があります。 ですから上司は、自分の態度にいつも以上に注意深くあらねばなりません。 無意識の表情の変化すら、相手に影響を与えてしまうのですから、上司としては、「イやな報告を受けたときこそ、相手をめる・感謝する」くらいの心づもりが必要です。 「リスクを早く報告してくれたから、早めに手を打てて助かった」「君の報告のおかげで、何とか取り戻せたよ。ありがとう」こうした「部下のホウレンソウ(特にネガティヴなもの)に対してめる」というフ イードバックを続けているうちに、「失敗を報告したら、選めてくれた」という話が、部下の間に広まるようになります。そうすると、ポジティヴサイクルが回り始めます。 ミスの報告に対するハードルは大きく下がり、部下は小さなミスでも報告をしてくれるようになるはずです。取り返しがつかなくなる前に、皆があなたに報告をしてくれるようになる。このサイクルを生み出すことができれば、現場の把握は驚くほどラクになるはずです。 p.294 工夫を凝らした訓練(deliberate practice)」だと述べています。実は人のデフォルトの思考はシステム1。直観的思考です。でも、訓練しなければ精度が低く、どちらかといえば「いいかげん」なものなのです。 メタ認知を働かせて自分を振り返り、自分の課題を分析し、その課題を解決し、向上するための訓練を考える。この「真剣で工夫を凝らした訓練」はまさに、システム 2の訓練です。目安は1万時間。システム2による集中した訓練を長期間行うと、自然に知識が身体化し、考えなくても頭と身体が連動するようになる。それが「達人の直観」の正体なのです。 言い換えれば、最初は「すばやいけれど精度が低い思考」だったシステム1を、システム2による長年の訓練によって、「すばやくて、しかも精度が高い、最高の判断ができる思考」に変える。これが達人になるために必要なことだと言えます。
1投稿日: 2024.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言語の本質』で新書大賞2024を受賞した著者の新刊。コミュニケーション齟齬という人類永遠の課題を認知科学から紐解いていく。序盤でスキーマを説明してそこを立脚点に「なぜ伝わらないのか?」が展開されていく。非常に面白い一方、いわゆるハウツー本ではないので「読んでる最中の納得感は高いが、いざ本を閉じたら自分の言動に何か具体的な変化を起こせるかというと…」という読後感は正直あるかも。それは必ずしも本書が悪いわけではないのだけど。行動を変えるのは難しい。
3投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者が今井先生なので、信頼がおけると思います。 内容はビジネス書という感じで、平易な表現が多いと感じました。 一発で伝えるにはこれ、と言ったような方法論が提示されている訳ではないです。 認知科学などに興味が無くても読めると思います。
1投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『言語の本質』による今井センセーのコミュニケーション本。 この手のコミュニケーション本は何冊か読んできたんだけど、その全てが共通しているのが「他人の考えはすぐには変えられないし、本当の意思疎通には莫大なコストがかかる」ってことだね。本書に沿っていうなら「スキーマ」があるからこそ、人は簡単に物事を理解し誤解する。 「犬」という言葉を聞いてアナタがチワワを想像していたとしよう。でも話者はダックスフンドを想像していて話を進める。この時点ですれ違っているのだけど、会話をする上で矛盾はない場合はすれ違ったまま了解される。「犬」という言葉のブラックボックスは、ある種の会話の中で開かれる必要はなかったんだな。 これが名詞なんかだと簡単なんだけど、「嬉しい」みたいな感情だったり「敬語」のような印象が関わってくると難しい。確たるものがないからこそ、本書のいう「スキーマ」に大きく左右されてしまうからだ。 自分の考え、あるいは物事の捉え方が唯一の答えではなく、そこから他者へ歩み寄ろう…という言語を生業にした人らしい誠実な本でした。
3投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ長年の訓練が必要で超一流の達人だけが持ち得る「優れた直観」が、生成AIの登場で危機に瀕しているという話がとても印象的でした。
1投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一章:「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない、第二章:「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、いったい何が起きているのか、第三章:「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには?第四章:「伝わらない」「わかり合えない」を超えるコミュニケーションとり方、終章:コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるには。話しても伝わらないのは、お互いのスキームが違うから。分かり合えないことを前提に、相手の立場に立つことが大事。
3投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ日々さまざまな立場の人とコミュニケーションを取っていて、「私の言いたいこと、あまり伝わってないな」と思うことはよくある。 伝わらなくても構わないことであれば受け流すが、仕事だとか重要な内容であればそうはいかない。とは言え「話せば伝わる」というのも幻想で、実際は「話しても伝わらない」ことも多々ある。 同じ言語を使う同士なのに、なぜこういったことが起こるのか? 文中に「天動説を信じている人に地動説について何度説明しても伝わらない」というような一節があるのだが、答えはこの一節に集約されていると思う。 人は経験から得た物事を捉えるときの枠組み(スキーマ)を通してコミュニケーションを図っている。個人的にそれを「それぞれの常識」や「偏見」という風に捉えたのだけど、他者の言うことを受けて自分なりに考えて意見を出すという流れの間にこのスキーマを通すわけだから、「うまく伝わらない」が発生する。 そして人が持つ認知(バイアス)も関係してくるわけだから、ますます「人それぞれ」になる。 元々柔軟である人ならば他者には他者のバイアスがあるということを理解してコミュニケーションが取れるけど、認知が強固であればあるほど伝えて理解してもらうということが難しくなる。 そのバイアスが「天動説を信じている」ということなら、「地動説」という別の考えを受け容れるのは簡単ではないということだ。 この本は指南書というよりは理解を深める参考書のようなもので、具体的にこんな風に対処しましょう、という内容ではない。 実際相手によって変わってくるから、対処方法をひとつにまとめるというのも無理だと思う。 ただ人間にはそれぞれ別の「スキーマ」や「バイアス」というものがあり、それを通して他者と関わっている、ということを理解することで、「伝わらないのは当たり前」と前提を持ち、その上で「説明することを惜しまない」という対処を取ることができる。 それがわかっただけでも、他者との付き合い方が、多少は変わる気がしている。
2投稿日: 2024.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10278885
0投稿日: 2024.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ余計な摩擦を起こさないようにするために知っておいた方がいいこと。コミュニケーションの達人は何度も失敗を繰り返した先に体得している。達人は世の中にそう多くない。だから知っておいた方がいい。
1投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ他人の記憶力や認知能力を信用してはいけない。そして自分のも。だから結局「話せばわかる」「言えば伝わる」を達成するのはめちゃくちゃ難しいよね、という結論。でも、「相手の立場に立った上で」という前提はやめてはいけない。
1投稿日: 2024.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知について感覚で感じでいたことが、理論的に理解ができた。仕事上の難しい人間関係において、認知バイアスや、スキーマを意識、認識すれば、より目的にしたがって円滑な行動ができるようになると思った。
1投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスにおける基本はコミュニケーションだ。 これはどんな仕事やその中の人間関係にも当てはまる。大事なことだ。 本書は科学的に相手を理解すること、認知の力を念頭においている。 だから、本書を読む前提として、目の前にいる人、人ひとり違うのだから、その求めている答えが必ずしも正解とは限らない。 だからこそ、本書に書かれていることの理解が必要になる。 またじっくり読みたいものだ。
1投稿日: 2024.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていたのとズレた内容だった。自分はありもしない「魔法の杖」を求めていたのだ、と思い知らされました。相手をコントロールする魔法はない。そもそも完全に分かり合えることはない、という前提からいつもスタートする覚悟を問われている、と読み解きました。
57投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログそうよね。人は皆異なるスキーマを持っていて、かつ様々なバイアスに囚われているから同じことを聞いても理解の仕方が違うのよね。そりゃわかっちゃいるけど、「あいつは一体何考えてんだ!」みたいなことが日常的に起こるわけよ。相手の立場に立って(=相手のスキーマを想像して)伝えることがいかに難しいか。発達障害だか何だか知らないが、自分は幼少の頃からこれが滅法苦手だ。死ぬまで修練を積み重ねていくしかないんだろうな。
6投稿日: 2024.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのタイトルにある、説明しても伝わらないということを切り口に、メタ認知、抽象と具体、直感などのことが学べる。どうすれば伝わるようになるかの解決策は形式的ではなく、本質的なものなので簡単に身につくものではないが、示唆に富む良書。
2投稿日: 2024.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間には育って来た環境や文化、特に言語に基づく「知識や思考の枠組み」=スキーマがある スキーマがあることで、お互いにお互いの意図を完全に理解することは不可能 まずはその伝わらないという前提に立つこと 人の脳は、忘れる、曖昧、嘘によって、分かったつもりが生じる 認知バイアスがあることを心に止める 伝えるために、相手の立場に立つメタ認知や、感情に気を配ること、具体と抽象を行き来する説明、意図を読むこと コミュニケーションにあたっては、失敗・分析・修正をセットで考えること、説明の手間を惜しまないこと、コントロールしようと思わないこと、聞く耳をいつも持つことが重要 ビジネスの基礎はコミュニケーション 真剣に工夫を凝らした訓練で直観を身につける
2投稿日: 2024.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ類書はいっぱいある。それでも認知科学の専門家であり、一般向け解説書にも既に定評のある「今井むつみ」のネームバリューを損なわない、きちんと編集された内容だと感じた。 最後の方に書かれている「AIの利用拡大が、人間の「直観」の能力や、「直観を涵養するために努力する姿勢」を損なう可能性についての提起は、印象深い。
8投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすくコミュニケーションの問題を指摘している。 誰もが同じものを見て同じように判断できるわけではない。それはこれまで経験し、学び、置かれた環境が違うことでそもそものバイアス、フィルターが存在するからである。 コミュニケーションは不完全であることを認識することがまず、コミュニケーションの第一歩。 そして伝えた内容が、相手の理解で咀嚼され、忘れられうることもまた、忘れてはならない。 フィルターをなくすことができない以上、そして認識の齟齬を否定できない以上、伝わるように手間を惜しむことなく日々の反省をしなくてはならない。 そして何より相手の立場に立ち伝えること、成長したい気持ちに寄り添うことが、次への一歩なのだろう。 備忘録 認知のシステムは直感的なシステム1と、改めて考え直すシステム2がある。
2投稿日: 2024.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コミュニケーションを取り上げたビジネス本であり、認知科学論。人は誰もが異なるふぃるた、つまりスキーマを無自覚にもっており、それをベースにしてしかコミュニケーションは取れない、という事実を理解することが重要。イヤな報告を受けたときこそ、相手を褒める、感謝する、くらいの心づもりが必要。言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく。「神聖な価値観」→「根拠のない自信」、信念バイアスに注意。ということでどうでしょう。
1投稿日: 2024.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと人間の記憶力はいい加減なところがあるし、育った環境によって言葉の捉え方が違ってくるし、価値観も違ってくる。スラスラ話されると信じてしまう認知バイアスがあるのには納得した。 相手をコントロールしようとせず、いい関係を保ちながら、相手の目線に立って、共通の具体例を挙げながら説明する。 失敗を検証し、シュミレーションしながら直感力を磨く。
1投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味がある題名、職場でも家庭でもよくあり得る出来事。とくに日本語は主語がなくても成り立つし、同じ音でもニュアンスで違う意味があったりするので、特有なこともあるのでしょう。 内容は大体想像していた通り、人が持っている認識(スキーマ)や経験、専門性、曖昧な記憶、またバイアスによって全然違う内容に捉えてしまうことは多々あるとのこと。 対策としては、「相手の立場」に立つ(俯瞰した視点)、「感情」に気を配る(感情を味方につけるには、伝えたい理由を添えると良い)。 最後はやはり、人と人の関係性になるのでしょうね。
1投稿日: 2024.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事向けと思って手に取ったのですが、家族とのコミュニケーションでも気をつけたいことがたくさん書かれていました。 様々なエピソードや研究、文献などをまじえていて、わかりやすいですし、 ところどころ、AIについて触れられているのも面白かったです。 〈キーワード〉 人間の認知能力というものののあやふやさ スキーマ 認知バイアス 感情 具体と抽象 (達人の)直感
1投稿日: 2024.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1、2章では、タイトルにある「何回説明しても伝わらない」の前提となる考え方や事実を述べる。第3、4章は、伝わらないことを回避するための考え方について論じる。 理解は解釈を含むこと、解釈はバイアスや感情を含むこと、それを避けるためにコミュニケーションが必要なことなど、全体的に見れば馴染みのある主張ではあるのだが、具体例を都度上げながら話が進むので、大変読みやすい。1時間半程で読了した。ただし、最後はコミュニケーションについて論じる都合上、具体的な方策というよりかは考え方の話が中心的になってくる印象。 以下はかなり個人的な話。 本書は職場の上司から紹介された。いつも「ちゃんと考えて行動しろ!」「自分の都合のいいように解釈するな!」と叱られることが多いのだが、なるほど、本書の「伝わらない」人物像に自分がピッタリ当てはまるような気がして、特に第1、2章は読んでて辛かった。(しかも、「誰にでも起こり得ることで、簡単に回避するのは難しいよね」という温度感で書かれている印象をうけ、それがむしろ絶望感に拍車をかけた笑) ただ、後半になるにつれて、それが個人の資質能力のみでなく、環境や普段のコミュニケーション、伝える側の性質にも影響されているのだ、と感じることができ、少し胸が軽くなった。 同じことを言われている社会人は、全国に多くいるはずだ(と信じたい)。本書は、伝える側が悪い!と主張するでもなく、聞く側が悪い!と主張するでもなく、非常にフラットな視点で「伝わらない」という問題にスポットライトを当ててくれている。「自分ってなんでこんなに物わかりが悪いんだろう」と、失意の中にいる人たちに、一度手に取ってほしい。
1投稿日: 2024.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに今、こういう事を知りたかった。 目から鱗が落ちるってこんな感じか。 「どれだけ言い方を変えても伝わらない」と頭を抱えていた昔の自分に読ませたかったな。 認知科学と心理学の視点で語られるコミュニケーションの本質には驚かされる。 と、同時に「やっぱりな」とも思う。 メカニズムを知ると冷静に物事を見られるから良い。 特に、スキーマの話が分かりやすかった。 まずは『人は自分の都合が良いように誤解する生き物』という前提でコミュニケーションを図る必要がある。 それにしても、相手の意図を読むなんて日頃からしているつもりだったけど…案外出来ていないのかもしれない。
2投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログとても分かりやすく、読み進めやすく、するすると最後まで読むことができた。 中高生であっても読めるのではないか、私もその頃に読みたかった気がする。 色々なバイアスに自覚的になること、諦めずに悩み続けることを大事にしたい。
1投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井むつみさんの本はどれもとても有用だが、本書では組織のパフォーマンスにまで敷衍できるような射程の広さを実感した。 今井さんの本は言語という見地から、社会的に人が生きるとはどういうことかという本質にまで迫ってくる。これからも注目していきたい。
2投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「話し方」のスキルよりも「心の読み方」のスキルを身につけたい。 話し方や表現の仕方などのスキルを磨くよりも、前提を理解した上で、「相手のスキーマを理解するスキル」を身につける能力を磨くことに徹する。 ⇛具体的には相手のフレームを知るようにする。 同じものをどのように見ていて、どう考えているのか?を常に意識してコミュニケーションを取る。
1投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学の専門家による、ミスコミュニケーションの解説。まず、人はどのように物事を理解しているか、からスタート。似たようなものをセットにすることで覚えやすくなることがあるが、同時に理解したからこそ間違えることがある。バイアスもそう。自分の聞きたいように聞く(つまり、相手は、相手の聞きたいように聞き、理解しているということ)。相手の目的を理解しようとすること。専門家でもないのに、専門家のようになはしてはいけません。流暢性バイアス、自信たっぷりに流暢に話していると信じやすくなること。神聖な価値観。それぞれの優先順位に基づいて理解、解釈されるということ。一つ一つとても参考になった。
1投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 相手の立場に立つ?具体的にどうすれば良いのか。相手のフレームを知ること。同じものをどう見ているのか。それをどう思っているのか。
1投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学を元にしたコミュニケーション齟齬の原因と対策の話。前半は科学的知見の話で、後半はビジネス現場への応用っぽい話。 あっさりしていて、すらすら読める。入門書として良いと思う。(この手の本を何冊か読んだ身としては、やや物足りないが。) ビジネスコミュニケーションにおいては、相手の立場に立って考えることが大事な場面は多い。でも、それができている人は少ない。関係者が認知の幅を広げて、相手のスキーマを意識していけば、もっと効率よく、品質高く仕事が出来るのになあ、などと思いながら読んだ。
2投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ300頁ある本書の227頁目に、こう書いてある。 「ここまで本書を読んできた皆さんも、文書の一言一句を覚えているわけではないでしょう。一言一句読んでいっても、その具体的な言葉は読んだそばから忘れていき、だいたいの内容だけをつかんで、読み進めているはずです。」 今まで読書が上手くできずに悩んでいた私の目から鱗が落ちた。忘れてしまう事に罪悪感を覚えていたのだ。 記憶にまつわる脳の仕組みを丁寧に解説したうえで、だから、コミュニケーションにはどう気をつけるか、どう訓練するか、といったことが書かれている(と記憶している)。目次だけ見て手っ取り早く第3章から読みたくなる気持ちをおさえて、はじめから読んでみて良かったと思う。
8投稿日: 2024.05.26
