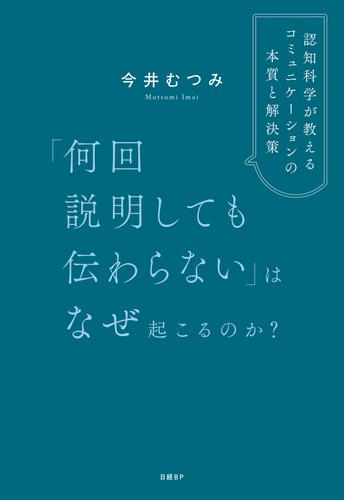
総合評価
(204件)| 44 | ||
| 77 | ||
| 64 | ||
| 7 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学の観点から、自分と他者との物事の捉え方や考え方の違い、意思疎通の難しさについて書かれていた。 基本的に人は理解し合えない。 そのことを前提に関わらないといけない。 内容としては面白さもありいろいろ考えさせられた。 いろんな側面から『何回説明しても伝わらない』はなぜ起こるのか?について書かれていたのだと思う。 が、タイトルから想像していた内容とは違ったため星3。
0投稿日: 2025.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分と相手が持っている言語や文化、認知の「スキーマ」(枠組み)は異なっていると言うことを前提に生きていこう、と言うお話。 例えば「丁寧にやろう」と言う発言で、どこまでが丁寧なのか?何が丁寧の定義なのか?曖昧さがあることはもちろん、人によって認識にばらつきが出るのは当然。家族でも認識が異なっており時たまアンジャッシュのコントのようなすれ違いが起きたり、重大なコミュニケーションエラーがおきるのだから、いわんや職場でをや。 マニュアルからは一切の曖昧さを排除すべきだし、指示を出す時は「これくらいわかるだろう」を取っ払って発信しなければならない。 また、専門性があるがゆえに発信できる内容が異なってくると言う尾身会長のエピソードもなかなか面白かった。確かに経済のプロ、感染症のプロ、政治のプロと色んな立場があって、責任を持って発信できる内容と「発信すべき」内容はそれぞれ異なっている。これらを調整していた当時の厚労大臣の加藤さんは大変な心労だったろう… 語り口調が優しいので、サクサク1時間くらいで読めます。 様々なバイアスが紹介されていたが中でも「信念バイアス」には大きく頷けた。 ネトウヨの両親を持つが、彼らにどんな反論をしたところで信念を曲げることはないし、信念を相手にも押し付けようとしてくる。こういった手合いと議論することはそもそも無駄なのだとよく分かった笑 色々あるけれど、相手の立場になって聴く・伝える、が結局大切ってこと。
14投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読みやすい。そして、例えがわかりやすい。 認知科学に興味が湧いた。 相手に何かを伝えたい時、受け取る側の枠組み(スキーマ)が違うから同じように説明しても受け取り方はそれぞれ。 枠組み(スキーマ)は学びや経験、育ってきた環境、興味関心で変わる。 それを踏まえた上で、相手を知り相手の心に耳を傾けて、相手の思考に辿り着いた上で、伝える努力が必要だと感じた。 なかなか難しいですね。でも頭の片隅に置いて意識はしていこうと思う。 あと、人の記憶は曖昧だと。頭に残っている記憶が「事実」とは限らないと。本人ですら気づかず記憶がすり替わることはあるということ。 ここで突然ですが、私の気になる子どもの頃の記憶が蘇りました(笑)どーでもいい話です。 私は子どもの頃、何かを食べて「ほっぺが落ちる経験」をした記憶があります。何を食べたかは思い出せない。でもほっぺが落ち、頬が重力に逆らえず地面に引っ張られるぐらい落ちてとっても痛かったのです。本当にほっぺが落ちたのです。ほっぺの筋肉が強く下方にひっぱられたのです。そしてほっぺを落ちないように抑えてたという、まんが日本昔ばなしのようなことがあったと記憶しています。でもいま、みんなにそのことを話すと「そんなことないない〜」「比喩」だと言われて終わります。そうだよね、そうなりますよね。 でも私の中では本当にあった話なのです(笑)私の記憶は嘘ものなのかなぁ〜。どこかのタイミングで記憶がすり替わってる?そんなことを考えてしまった。
127投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ代表性バイアス:一部の情報がすべてだと思い込むバイアス →そこから代表的な事例をすべてに当てはめて考える過剰一般化に陥りがち →情報を受取り理解・記憶する際は何かしらの偏りが必ず生じる スキーマによって捉えるものは人によって変わる →他者から指摘されるまで気づかない
1投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ何故相手に伝わらないかを説明している本。 凄く整理されている本だとは思うが、自分にとってはあまり新しい情報が少なかった。 基本的にスキーマが違うから伝わらない、だからそれを整えるためにどうするかという話。 人は見たいものしか認知できないのと同じかな。 相手の立場にどう立ち想像するか、それに基づいて攻略する必要があると。
1投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の方は、なるほどと思うところが多かったが、途中からコミュニケーションの重要性についてのはなしに変わっていってしまったのが残念
1投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は、育ったバックボーンは異なるし、時代や文化が異なる。でも、互いに同じと考えてしまうことによって、伝わらない、という現象か発生してしまう。 そう理解することによって、コミュニケーションが円滑に進められるといいな。
12投稿日: 2025.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、慶應義塾大学教授で認知科学等を専門とされている先生が執筆されたものです。以前、図書館で予約してようやく回ってきました。「うまく伝わらない」ことに対して、言い方を工夫したり何度も繰り返したりでは解決しないようで、人は自分の都合がいいように解釈するため起こるそうです。では、自分の考えを正しく伝えるにはどうすればよいか、認知科学と心理学の視点から本質と解決策を解説されています。本書ではそのようなことを事例を踏まえながら丁寧に説明されていて、私にもわかりやすく、興味を持って読み進めることができました。本書を読み、よく理解して実践することが大事なのではと感じました。返却期限がきてしまったので、また今度読み直してみたいと思います。 1. 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない ・人はそれぞれ異なる「知識・経験の枠組み(スキーマ)」を通して解釈する。 2. 「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、いったい何が起きているのか? ・専門家である以上、何らかの立場にいる以上、「視点の偏り」は必ず起こる。 ・偏見や先入観等の認知の歪みを認知バイアス(代表性バイアスもこの一種)という。 ・認知バイアスにとらわれず、「自分の頭で考える」ことは重要である。 3. 「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには? ・「相手の立場で考える」ための「メタ認知(自分自身の意思決定を客観視すること)」※参考『ファスト&スロー』(分量は多そう) ・感情を味方につけるコミュニ-ケーション→(相手の立場で)理由を伝える、相手の感情に寄り添う、悩みを共有する 4. 「伝わらない」「わかり合えない」を越えるコミュニケーションのとり方 ・人それぞれのスキーマというフィルターが違っても、伝わるように伝える。 ・コントロールしようとしない。 ・いい関係性(信頼関係の構築)、相手の成長、聞く耳、プラスのフィードバック(褒める、感謝する) おわりに ・この世界で生きていくこと→自分の芯を持ち続けながら、別のスキーマを持った人々の立場や考え方を理解し、折り合いながら暮らしていくこと ・相手の中にも自分の中にも存在する認知バイアスに注意 ・メタ認知をしっかりと働かせる
7投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本大学図書館生物資源科学部分館OPAC https://brslib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1000347743
0投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・理由を添えることで相手の納得を得られやすくする ・相手の感情に寄り添う ・具体と抽象を行き来する ・コントロールせずに相手を動かすには 関係性を築く、相手の成長を意識する
1投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「話せばわかる」とはどういうことか? そもそも「話せばわかる」というとき、私たちは何をもって「わかった」としているのでしょう。 「相手の話がわかる」ということを、段階を踏んで表現すると、 ①相手の考えていることが ②言語によってあなたに伝えられ ③あなたが理解をすること といえます。 ここで問題となるのは、それぞれの頭の中をそっくりそのまま見せ合ったり、共有したりすることはできない、ということです。 それは単に「言葉によってすべての情報をもれなく伝えることはできない」というだけではありません。 言葉を発している人と、受け取っている人とでは、「知識の枠組み」も違えば「思考の枠組み」も異なるため、仮にすべての情報をもれなく伝えたとしても、頭の中を共有することはできない、という話です。 記憶は曖昧・・・ならば「言い切った者勝ち」なのか このように、「記憶は非常に頼りないものだ」ということを知っていると、役に立つことがあります。なぜなら、相手の言うことがあやふやでも、ときに間違っていても仕方ないと許すことができますし、それでイライラすることも減るからです。 また自分の記憶に頼らず、様々なことをダブルチェックするようになりますから、 ミスも減ります。自分が間違っていたかもしれないと、素直に非を認めて歩み寄ることもできます。 私たちが知識や情報を受け取り、理解し、記憶する際、何かしらの偏りが必ず生じています。自分に合わない情報は、そもそも頭に入ってきません。また、スキーマによって、捉えているものは人によって変わります。だから、指摘されるまで気づかないのです。 その点では、マーケティングの担当者が、同業他社がまだやっていない、高い効果が見込める施策を提案したときに、別の部署の人が、 Aさん「今すぐやりましょう」 Bさん「準備に1カ月は必要ですね」 Cさん「できませんね」 などまったく美なる意見を出し、平行線をたどってしまうのは仕方のないことといえます。 視点が違う状態でただ同じ議論を繰り返していても、お互いまったく相容れないことになります。何かを信じれば信じるほど、自分が論理的であると思っていれば思っでいるほど、他の人の意見が「間違っている」と思えてしまう。相手を攻撃してしまうこともあるでしょう。「なぜそのように考えるのか、まったく理解できない!」ということになってしまうからです。 このときに必要なのは、新しい施策を、手を変え品を変え魅力的に、あるいは丁寧に説明することではなく、それぞれがどんな視点からその意見を言っているのかを考え、聞き取り、それぞれの懸念を払拭していくことです。 まずは自分がマーケティング担当者として、何を目的に提案をしているのかを明確にすることです。そして一歩踏み出して、「相手の視点の偏りはどこにあるのか」を考える。 そうすることで違う考えに対して寛容であることができますし、今より少し自分の枠組みから距離を取って、相手の意見に耳を傾けることができるようになるはずです。 こうしたプロセスによって、Bさんの発言が物流面での懸念を踏まえたものであり、 Cさんの発言がコストへの懸念によるものである、など、それぞれの考えがわかれば、「言っても伝わらない」「話してもわからない」を越えていけるのではないでしょうか。 意図を読むとはどういうことか 「意図を読む」ということを辞書的に解釈すると、「相手の、こうしようという考えや思惑、狙いをくみ取ること」となります。視点はあくまで、「相手」です。 つまり、これまでお話ししてきた「(非認知能力や性格の問題ではなく、心の理論やメタ認知に基づいて)相手の立場で考えること」が、意図を読むためには必須といえます。 また、こうしようという考えや思惑、狙いは、直接は教えてはくれませんから、推測したり推論したりする能力も求められるでしょう。 さらに、そうした考えや思惑、狙いの背景にある感情もまた、意図に影響を与えているはずです。 つまり、意図を読むためには、「相手がどういう視点で、どういうスキーマを持って状況を捉え、状況に対してどういう感情を持っているのかを推論すること」が求められ、それには相手の感情も大きく関わっているといえるでしょう。 「コミュニケーションの達人」の特徴 ①達人は失敗を成長の糧にしている ②説明の手間を惜しまない ③コントロールしようと思わない コントロールせず相手を動かすポイント ・関係性 ・相手の成長を意識する ④「聞く耳」をいつも持つ おわりに 本書をここまで読んでくださった皆さんは、向上したい、成長したいという気持ちが強い方だと思います。そしてその気持ちは、人が働く上で、大きくいえば生きていく上でとても大切なものです。 強い思いを持ち続けられることは、それだけでひとつの大事な能力です。「明日は今日よりもっとよくなりたい」「今やっている仕事より次の仕事はいい仕事にしたい」。 そう思えること自体が才能なのです。 本書では、「話せばわかる」「言えば伝わる」を切り口に、人の認知や記憶の仕組みについて、幅広くお話ししてきました。また、直観についても考察し、失敗の意義についても紙幅を割きました。日常の生活の中で私たちの認知機能がどのように働いているかについて、その一端をつかんでいただけたのではないでしょうか。 私自身、本書を書き終えた今、理解し合うことの難しさを改めて感じています。世の中にこれだけの対立があるのには、理由があるのです。 この世界で生きていくということは、自分の芯を持ち続けながら、別のスキーマを持った人々の立場や考え方を理解し、折り合いながら暮らしていくことです。相手の中にも自分の中にも存在する認知バイアスに注意しながら、物事を一面的ではなく様々な観点から評価し、判断する。自分の所属する、帰属する集団の価値観を、一歩引いて見つめてみる。メタ認知をしっかりと働かせることを意識していく。しかし自分の芯はぶれさせない。 これは決して簡単な生き方ではありませんし、ぼんやりとしてつかみどころのない生き方のように思われるかもしれません。 そんなときは、逆の生き方を想像してみるとわかりやすいかもしれません。 自分の芯を持たず、様々な立場の人を許容することなく、物事を自分の考えのみで判断し、所属する集団の中の価値観を正しいと信じて発言する。そういう人があなたの周りや言論空間にもいるかもしれません。 思い込みにとらわれたそのような生き方は、実はラクな生き方でもあります。 相手の意図を考える必要も、情報を精査することも、知識や教養を得ることも、自分を外から見つめ直すこともないからです。自身を見つめ直し、自己を批判することで痛みを感じることもありません。自分が思ったことが正しいし、情報は自分が思ったように解釈すればいいからです。 自分の認知のバイアスに埋没し、心地よいところだけで生きるのは、とてもラクな生き方でもあるのです。 その道を選ばなかった皆さんは、これからの日々も探究しながら生きていくことになるでしょう。1つの問題だけを取り出しても、相手の立場や信念に思いを巡らせ、 それにまつわる知識を学び、自分が持つ偏見を見つめ、その背景を探り・・・・・・。多くのことを俎上に載せてうなりながら、自分なりの結論を出していくのだと思います。 自分とは相容れない相手に対しても、「許せない」と切り捨てたり、「人それぞれ」と突き放したりするのではなく、「そういう考え方もあるのか」「そういう捉え方もできるかもしれない」と建設的にすり合わせをしていくことでしょう。 大変な世の中です。 自分のこと、家族のこと、仕事のこと、社会のこと。考えなければならないことはたくさんあります。そのような中、人の認知について知るためにこの本を手に取り、 その知識を持って物事をより深く考えようとする皆さんの前には、長く果てしない道がのびていることでしょう。決してラクな道ではありませんが、その探究の道のりがよりよいものであることを、心から願っています。
1投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス本のレベルを超えた認知科学。 質の良い大学の授業を受けている感じだった。良本。 オススメです。
1投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
話し手と聞き手は、それぞれ異なる**常識や思考の枠組み(フレームワーク)を持っているため、コミュニケーションの際に「わかりづらさ」**が生じる。 このギャップを埋めるためには、双方の歩み寄りが必要となる。 • 話し手:聞き手がどのように内容を理解するかをシミュレーションしながら話す必要がある。 • 聞き手:話し手の意図を汲み取る努力をすることで、コミュニケーションの行き違いを防ぐことができる。
1投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井先生の本や認知科学の本を読んだことがない方、「スキーマ」という言葉を聞いたことがない方にオススメ。 言語コミュニケーションですれ違いがなぜ起こるのか、その理由を認知科学の専門家がこれ以上なく平易な言葉で説明してくれる。 「相手の立場に立って考えよう」と子供の頃からよく言われたが、それは倫理や優しさの問題じゃなくて、異なるスキーマを持つ相手とコミュニケーションするために必要だからなんだな。 生成AIと、人間の「流暢性バイアス」が、僕たちから「生き生きとした直感」を奪う説は、リアリティがあって怖い。 タイトル最高。
9投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間に抱いていた一切の甘えや期待を捨てることができる本。結果、コミュニケーションのもどかしさは激減した。人間の脳みそって適当なんだ。みんな適当なんだ。細かいとこにネチネチこだわるのはやめよう。1GBに私のことを保存していてくれてありがとうの気持ちでいよう。 似たような経験を積んできた人と関わるのはとても楽だし安心する。ただ、「何となくみんな伝わってるし、分からない少数派が合わせにくればいい」という考え方でやっていると自分の成長も止まるし相手も組織も確実に腐っていく気がした。 “空気を読む”以前に、考えを伝える力というか責任のようなものを教わって世に出ていかないといけない気がした。受け取る脳みそは適当なんだから、せめて伝える方になった時は頑張ろう。
1投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションの齟齬が生まれる原因を正しく理解することを促す本。 人は事実を自分のスキーマ(枠組み)を通して認識することから、自分にとっての重要性と相手にとっての重要性が異なることや、印象が変わることが起きるのは当然である。 また、記憶を保持するためにも忘れることや、無意識なバイアスによって判断する可能性が十分にあると正しく認識することが意思疎通をはかるうえで、大切である。 日本人のようなハイコンテキストの文化で育った者にとって、他国に居住した際、どこまでが共有すべきコンテキストなのか(相手と比べてコンテキストの認識が違うのか)は分かりにくく、それによって意思疎通に齟齬が生まれることがある。それだけではなく、上記のようにそもそも人間は自分のスキーマを通じて事実を認識する上で違いがあることは当然であると理解した上でコミュニケーションを取ることが必要だと教えてくれる。
3投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ職場に何回説明しても噛み合わない人がいて読んでみた。まさに、だった。 ものすごく簡単にまとめると「人それぞれモノの捉え方(スキーマ)は違うから相手の立場に立って考えよう」ってことなんだけど、その困った職場の人は自分のスキーマしか見えていないのだ。 こちらも相手の立場や前提知識、常識、大事にしているものを想像して歩み寄った説明をすることが必要だが、頭の中を丸っと見れるわけではないので、完璧にすることは難しい。説明される側にも人それぞれモノの捉え方が違うということを知ってもらいお互いが歩み寄り合うことが、この問題には必要だと非常に感じた。 その他にも、記憶やバイアスなど認識が人によってズレてしまう原因など専門的な事柄について、初心者にも非常に分かりやすく書かれているので、「なんでアイツはいくら言っても通じないんだ?」と感じている人は読んでみると原因が解明されてスッキリするかも。性格が悪いんじゃなくて、認知の仕方がズレていると分かれば腹立たしさも少しはマシになりますしね。 そこから本当に解決に向かうのは中々骨が折れそうだけれど…
0投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
認知科学、言語の心理学の著者が、コミュニケーションの齟齬が起きる理由、言ったつもり、聞いたつもりで、理解していない、されない理由を、誰しもが持っている思い込みやバイアスといったものを解説しながら、主にビジネスパーソン向けに書いたもの。 言語学とかに興味があると著者はとても有名な人で、よく岩波新書とかで名前を見る気がするし、昔おれが生成文法とか勉強したりしてたので、なんか前から名前見たことある人だったけど、著作を読んだのは初めてだった。 それこそ伝わりにくさ、コミュニケーションについて説いている本なので、この本が読みにくいというはずはなく、それこそ著者が読者を想定しながら易しく、かつ本書でも述べられているように具体と抽象を行き来しつつ述べられている。とても読みやすいので、読むのも時間がかからず読める。でも結論は、「人はそれぞれに考え方が違うし、人間特有の認知のエラーもあるから、説明したから分かるということにはならないし、相手を責めるわけにもいかないということをまず理解しましょう」ということだと思う。だから、どこかにも書いてあったが、こうすればいい、みたいな安易なハウツー本でもなく、人間の認知の性質を分かりやすく一般向けに説明した本、という感じ。おまけとして、「生成AIは人の直観を育てない」という話が挟まる。 あとは気になったところのメモ。おれは英語の教員なので、それこそ何度教えても伝わらない、出来ないというのは山ほど経験しているが、それにしても本当におれが中高生だった頃だったらもうちょっと出来ないヤツでも出来た気がするけど、と常に思っている(のだけど、これもバイアスなのだろう)。でも最近本当にその傾向が強いと思ってしまっているが、平面図形を教えるという話のところで、「あることを覚え、使おうとする強い意志がない限りは、教えられてもなかなか記憶には残りません。自分にとって重要でない物事が記憶に残らないのは当然です」(p.41)という、もちろん当たり前なのだけど、でもスマホとゲームと生成AIで面白くて便利なコンテンツが昔より溢れている今の時代、相対的に学問に興味を持ちにくい環境なのではないかと思う。まして英語なんて生成AIでいくらでも翻訳してくれるし、なおさら面倒な英語をやる重要性、って昔より感じにくいのではないだろうか。とすれば、英語を教えるというのは昔より遥かにチャレンジングなことなんじゃないか、と思う。あとは記憶や認知の歪みについて。「銃口をつきつけられたとき、人は、銃を凝視することがわかっています。それも、犯人の顔はいっさい記憶に残らないくらい、銃だけをひたすら見続ける」(p.54)ということで、だから犯人の顔は記憶に全然残らない、というのはすごい理解できた。他にも認知の歪みを引き起こす現象として、「エコーチェンバー現象」というのがあるらしく、「SNSなどで同じような意見を見聞きすることで、自分の意見や思い込みが強化される」(p.99)、つまり「さまざまな情報の中から、自分に都合のいいものだけを無意識にピックアップして、それがすべてだと思い込んでしまう」(p.100)ような現象のこと。じゃあ、これは危険だからもっといろんなことを相対化しないといけません、と教養ある感じのことを言ったとしても、そこには「相対主義の認知バイアス」というものがあって、「相対主義の考え方を突き詰めると、独裁者の存在や戦争も、『それなりに理由がある』として受け入れることになってしまうことになりかねません。自分にとっても、社会にとっても非常に重要な課題に対してこのようなアプローチを取ると、『多様性の中でどれが合理的か』と考えることを放棄してしまう」(p.163)ということで、「一見理にかなっているように見える相対主義的な言説を披露する人はけっこういます。このような相対主義の罠には気をつけなければなりません」(同)ということも考えないといけないので、やっぱりそんな単純なことではない、ということが分かる。あとは自分の考え方のスキームというのがあって、これに縛られるので、あとは聞く耳を持たない、というのも、コミュニケーションの基本だなと思った。似たようなやつで「英語学習のビリーフ」というのがあるけど、ここでは「神聖な価値観」として説明されている。さらに「『神聖な価値観』による物事の単純化を、私たちは日常生活の中で、頻繁に、無自覚に行なっています」(p.141)というのも、何というか、興味深い。だから話は通じない。要するに色々理屈をつけたとしても、最終的には「好き嫌いの話」として、おれは諦めることもよくあるんだけど。でもこの感情に合理性を見出している養老孟司の話(pp.193-4)も面白いと思った。 あとおまけで時々出てくる生成AI、Chat GPT関連の話は、やっぱり自分も生徒も周りの人もいっぱい使っているから、いくら当たり前のことだと思ってもやっぱり興味を持って読んでしまう。「Sさんはクライアントから委託を受けて特許や商標登録を国内・海外に出願する業務をしていますが、最近、クライアントから法的に間違った主張を堂々とされることが増えた」(p.64)ということで、「生成AIの返事の『もっともらしさ』」(p.65)に騙される、「『言い切った者勝ち』のような現象」(同)って本当に恐ろしい。これが罷り通るなら、生成AIに支配される世の中、というのはSFじゃなくなってくる。そしてこの裏にあるのが、「流暢性バイアス」。「誰かがスムーズにわかりやすく説明をしていると、その内容を信じやすくなる」(p.165)ということで、テレビショッピングとか、これもあるんじゃないかな、と思う。確かにChat GPTって何でもスラスラ答えてくれるよな。おれなんかは、授業ではとにかく流れるようにテンポよくやってナンボ、という面もあると思っているんだけど、おれ自身の流暢性バイアスをおれが活かした結果、ということになるのかも。「相手が流暢に話していると、内容が薄くても、ときには間違っていても、信用してしまうというバイアス」(p.296)ということで、おれの汚い考えでは、教員もとりあえずスラスラベラベラ喋ったらある程度「良い授業」として認識されやすいということだよな、とか思った。あと関係ないけど、p.223に分数の大小比較がChat GPTは2023年の時点では出来ない、って書いてあったから、Chat GPTに聞いてみたら、そんなことはなかった。今はできるらしい。 ということで、読みやすいビジネス本にもなりうる本で、認知のバイアスについて自覚されてくれる良い本だと思う。でもやっぱり結局相手の気持ちに立って、あるいは自分の気持ちをもっと相対化して相手と接するしかない、という、コミュニケーションの達人と言われる人はものすごい高度な能力を持っているんだな、と思った。でもたぶん、こういうことに加えて非言語コミュニケーションの力も大いにあると思うので、とにかくコミュニケーションが総合的に難しく、その中でおれは何が出来るんだろう、何が苦手なんだろう、ということを自覚することが出来た。(25/08/22)
2投稿日: 2025.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で結構待って借りた。多少急ぎ足で読んだけど、いい本だった。 人間の認知の仕組みについて知ることって大事。いかにそれぞれのスキーマの中で思考しているか。
0投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「同じものを見たり聞いたりしても、誰もが同じような理解をするわけではない」。なぜなら、思考において無意識に使われる枠組み=スキーマは、それを形成する学びや経験、育ってきた環境、興味関心が1人ひとり皆異なるから。 全体的に斬新な感じはなく、そうそうという納得感。 元より、仕事でコミュニケーションを取るにあたり、相手は伝えたい事の半分も分かってない、と思ってこちらは対応すべきとはこれまでも考えてたし、会社でさんざん言われたのは「コミュニケーションの問題は伝える側の責任」という事。相手が理解納得して行動して貰える迄伝える側が確認対応すべき、という事だった。 直感に基づく判断に救われた事例でハドソン湾の奇跡や羽田空港の奇跡(JAL機と自衛隊機接触事故でのJAL機乗員乗客全員脱出)が出され、そこで「達人の直観」を育てるのは「長期間に及ぶ『真剣で工夫を凝らした訓練』で、ここは生成AIには代替出来ない、との説明にはどこか安心した。 外国人との共生社会において、「代表性バイアス」「過剰一般化」は要注意だ。
0投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ例に出てきている記憶の中の犯人は、まったく別人というのに驚いた。 人間の記憶って簡単に変わってしまう。 けれど、それがあたかも正しいと感じてしまう。 本当に恐ろしいと思った、 また、言葉として伝えられたことでも 一人一人の映像としての捉えが異なることによって 伝わらないということが起こり得ると思った こう言ってるんだから伝わって当たり前だよね っていう自分の考えの押し付けにならないように 違う捉えもあるかもしれないと考えられるようにしたいと思った。
0投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなんか当たり前のことを、いかにも、って感じで書いてある。いろんなバイアスがあるので、気をつけましょう。って感じ。正解がある話ではないから、こういう書き方しかできないっていうことかもしれない。いろんなケースを知っておくことは役には立つ。
0投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の帯に「間違っているのは言い方ではなく心の読み方」とありました。 「心を読む」 本書を読み進めると「相手の立場に立って話を聞くこと、理解に努めること。」のことだと思いました。 よく耳にする言葉ですが、それだけではないのが本書のいいところです。 まず相手には過ごしてきた背景があり、そこから得た専門的な知識と経験「認知的スキーマ」があるので、そこをよく知った上で伝えること。伝えるにも「丁寧さ」が必要であるとありました。 日本と海外工場の作業マニュアルが比較されており、納得しました。 「普通」「みんな」もその範囲は個人的なものであり、誤解と洗脳とも思える巻き込みにもなりかねないため、そこには注意を促してました。 相手のスキーマには、「話を聞くぞ!」と意識しないと気づけないため、かなりの時間と鍛錬が必要そうです。 スキーマの仮説、失敗、修正を繰り返して、自分にかかってる「信念バイアス」に気づく作業になりますが、その作業に価値を見出してないと続きそうにないです。 著者がインタビューしたコミュニケーションの達人達もこの過程の繰り返しているとのこと。 個人的に伝わらないときは、「精神的に、体力的に余裕がない」時が当てはまってます。 時間がない、疲れているなどで説明が面倒くさくなっていることがほとんど。 よくするには、時間と体力に余裕が持てるよう準備(バッファ、体力作り、休暇など)が必要だと感じました。 余裕がない時は、無理しないのが得策かなと(無理すると余計こじれそう。)
1投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に注意しておきたいのが、この本は「何回説明しても伝わらない」時にどうしたらいいか?を解説する本ではない。 あくまで、「何回説明しても伝わらない」はなぜ起きるのか?ということの解説本である。 なぜ伝わらないのかを知りたい人、伝わらなくてイライラして居る人は、この本を読んでみると、伝わらないのがこういう理由だったのか!となるが、伝わらなくて困って居る人が読んでも、解決策は書いてないので、残念な気持ちになるだろう。 それはそれとして、人間の記憶がいかに脆弱なものか、ということがいくつもの社会実験や実際の事件などを通じて書かれており、読んでいて面白くはある。 ただ解決策がほとんど書いていないので、片手落ちという印象である。
0投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「当たり前」は人によって違う。 これはかなり人間の本質を表しているのではと思う。 身近であれば、仕事の内容の伝わり方やコミュニケーションののズレなどがそうかな。 マクロで見ると、戦争が代表的かな。 それぞれの正義が、それぞれにあって当たり前を押し付けている。 一方で、日本人の当たり前と海外の人の当たり前も違う。 日本の中でも違う。同じ職場でも違う。 人間難しすぎるって!!! だからこそ何回も失敗する。 その失敗を修正して、改善して、行動に移す。 失敗を失敗で終わらせない!
18投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ認知科学の第一人者の著書を購入 コミュニケーションでは、代表性バイアス、過剰一般化、エコーチャンバー現象、専門家の視点の偏り、信念バイアス、知識の錯綜(他人の知識=自分の知識バイアス)、相対主義の罠、流暢性バイアスに留意しつつ、相手の立場に立って考えること、また、具体と抽象の使い方を工夫して理解を促すこと、経験に裏打ちされた直感は大事だが論理的思考のメタ認知も重要、相手に理由も加えて説明することが効果的など、認知科学に基づいたコミュニケーションこあり方を学ぶことができた。 我々は一人ひとりが異なる「知識と思考の枠組(スキーマ)」を持っているのだから、なるほどよい一冊だった…
0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が認識している内容が多かった。 その中でも今回読んでみて、改めてそうかと思ったことしては、 ①直感の磨き方 179ページ、ファスト思考とフロー思考 293ページ、直感は天から降りてくるものではなく、そこへ向かってたゆまず歩き続ける中でやっと手に入れられるものだ。 ②AIがその直感を奪う。 AIをこの本で言う基礎ができていない人が使い続けたらどうなるか?やっぱり、留意して使用する必要があるのか。 ③楽に生きるのは文字どおり楽ではあるが成長はないんだなあ。 最後に経験学習が大切ということか。
0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1〜5章で構成 1〜3章は、「伝わらない」ということの具体例や考えが書かれていた 4章で、伝わらないことに対する対応法とかが記載されてたイメージ 5章では、4章の内容を踏まえた上での例や生成AIによる「伝わらない・自分の考え方や知識としてのインプット」に対する危惧が書かれてた
0投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度言っても伝わらないなぁ…という状況を思い浮かべるとき、何人の顔が浮かぶだろうか。 たとえば制限時間、10秒で。 私の場合は、夫、子どもたち、職場のあの人とあの人。 5秒程度で5人。よく顔を合わせる人ばかりだ。もっとよくよく考えると、もっとたくさん思い浮かべることになるだろうから、5秒でやめておく。 考えてみれば、 「なんで(言われないと)わからないんだ!」 と、怒られる側から、いつの間にか怒る側になっている。 私が年を取ったからだ。 会社でも、誰かに業務を教えたり、説明することがいつの間にか多くなった。 「あり得ない…」 と思うような間違いを、平気な顔でやらかす同僚もいる。 しかし、ここでキレてはいけない。 「こちらの説明が足りなかったですかね…」と言ってみる。 「そうですよ!」とマシでキレ気味に返ってくる。 さすがにこちらもキレそうになる。 こういうヤカラをどうするか。 「何度言ったらわかるんだっ!!」 と、夫は子どもたちに日常的に怒鳴っている。 夫の言いたい気持ちはわかる。 わかるが、夫が子どもに合わせて説明しているとは思えない。「なんで俺が下に引きずられないといけないんだ」「できないヤツが悪いんだろーが」と思っている。 そういう人と、 「だってパパの言ってる意味がわかんないんだもん」 と言う子どもとの間に入って、両者の怒りをかわしながら通訳するのは正直ツライ。 【命題】 何らかの立場にいる以上、「視点の偏り」は必ず起こる。 そのコミュニケーションの難しさの中で、私たちはどう振る舞うべきなのか? これに対する解答を探しながら読んだ。 この本は、とても読みやすい文体で書かれている。なのに読み終わるのに思いの外、時間がかかった。 「まぁそうだよね」「それはわかるんだけどさ」と思いながら、メモを取っていたせいではある。 ここからはネタバレになるが、結局のところ、この本では「なぜそうなるのか」は学べても、「どうしたらいいか」対処法はいまひとつ学べなかった。 「スキーマが違うから仕方ない」 「違うということを前提にするしかない」 「年長者や立場が上の人が合わせる」 「諦めずに建設的にすり合わせる」 やっぱりこれに尽きるのか…? え、いやいや…えーっと…それって… 1人で改善するのって、相当ムリじゃない? そんな手間ひまかけてる余裕も時間もないんですけど… というモヤモヤを抱えたまま読み終わり、メモを読み返してもいまひとつスッキリしない。 私の読解力の問題だと思うが、一方で、まぁそんなもんかもな、とも思う。 だって、コミュニケーションって、そもそも1人じゃ成り立たないから。 本書で改めて思ったが、 「あなたもわたしも間違えるから」という前提があると、気持ちが優しくなれる。 それぞれがどんな視点からその意見を言っているのかを考え、聞き取り、それぞれの懸念を払拭していくのが、コミュニケーションの上で大事なのは間違いない。 「とにかく言語化するチカラをつける」 今のところ、私にとっての対処法はこれに尽きるように思う。 この本は、本屋のレジ前に平積みされていて、タイトルをひと目見て「これは興味ありすぎる」と、とりあえずいつもどおり図書館で予約していた。気づけばちょうど1年。去年の私より、今年のほうが「何度言ったらわかるんだよ…」というシチュエーションが確実に増えている。 子どもたちが、それだけ大きくなった、とも言える。 「言えば伝わる、ハズ」と、自分の中で子どもたちにうっすらと期待していた。 「言わなくてもわかる、ハズ」と、夫や同僚に期待していた。そういう自分に気づくことになったのは、この1年での私の成長だと思いたい。 もしかすると私も誰かにとって「何度言っても伝わらない人」かもしれない。 たとえば、娘にとって。 大人同士のコミュニケーション齟齬をどう乗り切るか、ということがメインなので、子どもとの関係をどうしたらいいのかは、同じ著者の、別の本で読んでみたい。
26投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の認知能力がどれほど低いかよくわかった。 人の認知や記憶に期待しなくなった。 人が何かを認知できなかったりしても、全く自然なこととして捉えられるようになった
0投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ約300ページ、平易な言葉で書かれており、とても読みやすかった。自分と他人は元々の価値観、背景が違う。だから話し方も受け取り方も違って当たり前と思って、コミュニケーションをとらなければ、分かり合えない。ホントにその通りと思った。
0投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 コミュニケーションにおいて誤解が起こる原因になる、認知バイアスの諸々を図解と共に解説している。 「人間の認知能力のあやふやさ」を理解するための本。 根本的な原因を解消するのがこの本の主題ではない。 「話せばわかる」はありえない…… 相手が聞く耳を持たない(「問答無用」だ)から、ではない。 そもそも人間は“相手の話した内容をそのまま脳にインプットするわけではない”から。 冒頭から、2024年1月にあった羽田空港での衝突事故のやり取りの話が出てきて震える…… こうした齟齬が起こるのは何故か? 人の思考には、それぞれ「スキーマ(知識、物事の捉え方、考え方の枠組み)」があること。 人の記憶は曖昧であり、忘れること、意図せずとも「記憶のすり替え」、「嘘」をつくことがある。 そして曖昧であやふやなものを、その誤った情報や思い込みなどを自信満々に「こうだった!」と言う人に押し切られ、「断言したもの勝ち」になってしまう…… 生成AIについても言及。によってこれら「記憶の曖昧さ」に基づいて誤った情報を吐き出してしまう。そして生成AIは責任を持ってくれない。人間だけでなくプログラムまでも「断言したもの勝ち」を助長する、と。 「理解」とは「記憶力が良い」とは関係ない。(理解しているからこそ記憶違いをする、すり替わる) 「視界に入った=見えている」ではない。 「過剰一般化」問題とエコーチェンバー現象……人は自分の見たい、知りたいものしか認識できない。 認知バイアスがある。 「コミュニケーションの達人」となるには、メタ認知の力が必要だった。 ①失敗を成長の糧にしている ②説明の手間を惜しまない 自分と他人のスキーマ(物事の捉え方、考え方の枠組み)は違う。 ③コントロールしようと思わない 相手と良い関係を築き、相手の成長を意識する。 ④「聞く耳」をいつも持つ 「イヤな報告を受けたときこと、相手を褒める・感謝する」くらいの心づもりが必要。
0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【なぜ】著者の出演ポッドキャスト回で良い印象があったため読んでみる 【ここだけ】 スキーマを埋める、バイアスを忘れない。これらを忘れない。 【感想】 認知科学ならではの視点であり、日常の分析がなされ納得。半分まで読み、コミュニケーションをそつなくこなすのハードモードすぎるこれこの本でちゃんと解決してくれる?と恐怖体験。 ちゃんと回収してくれました。 やはり具体抽象とメタ認知だよなー。 【メモ】 p110 偏った視点や考え方を持ったものが集まって仕事は進んでいく。→自分が大切にしていきたい方向性と合致する p112 その言葉の裏にある意図を見るようにする p128 カルタのプロは忘却の能力が必要 p146 信念と信念バイアス。前者は自分が「こうしよう」と思うもの。後者は、それを他人にもさせよう。 p162 気が利くの価値は文化に依存する p162 相対主義の認知バイアス…過度な多様性の受け入れは、どれが合理的かの考えを放棄しうる p164 流暢性バイアス…詐欺につながるようなもの p180 ファスト&スロー…ファスト思考は"概ね"正しい p190ホウレンソウの重要性を部下が気づいていないことに上司が気づいていない、と言う二重の問題 p199 コピー機割り込みの検証…①普通に伝える②コピーをしなければならないのでを加える③急いでいるのでを加える、で②③はほぼ同じ成功率 p204 悩みを共有すると感情を味方にしやすい p255 コミュ達人の特徴①…失敗から得ることがある
3投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
認知科学って面白いけど難しい ・相手の立場(気持ちや感情、スキーマ)で考える →相手の置かれている状況に思いをはせる ・メタ認知で自分の伝え方を振り返る →その内に直感が養われ、極めた先に「大局観」が身につく ・理由(なぜ?)や背景を伝えると、感情に働きかけて相手の納得を得やすい ・言葉は抽象な記号だから、具体例を交えて伝える →抽象と具体の紐付けは注意しないと勘違いを生む →具体と抽象の間を積極的に埋める意思が大切(分析、仮説、検証の反復) 筆者の考えを私は正しく理解できないかもしれない 私の考えはあなたに正しく伝わらないかもしれない それでも思いを伝えたいと願う気持ちから この本が生まれたのだろう
0投稿日: 2025.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人はそれぞれの背景によってスキーマ(偏り、バイアス)を持っている。相手の言っていることを自分のフィルターで捉えるから認識の差が発生すると。 判断は直観的な好き嫌いで決めてしまう方が良く、決めた判断のあとから、合理的なロジックを組むプロセスになっているケースもある。「合理的に判断できるまでデータを集めないと判断出来ないは最高に非合理」 そして、直観とはファスト&スローのシステム2思考によってメタ認知した思考で訓練を積み重ねたことによって身につくと言っていて納得感がある。
0投稿日: 2025.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝えたいなら相手の立場に立て、 それができないから悩んでるんだけど〜? 現代文とな苦手な私には この本は難しかった
1投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ●本書はコミュニケーションのハウツー本ではない。認知科学を専門とする著者が、「言っても伝わらない」メカニズムを認知科学の見地から解説し、その上で伝わるコミュニケーションの考え方を述べている。
0投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「コミュニケーションのスタートは相手の話を聞くこと」。わかっちゃいる。いるんだけれども。「聞く/聴く」がいかにむずかしく奥深いことなのかは、傾聴ボランティアを始めた時からの課題でもあり、興味が尽きないテーマだからこそ、認知科学の視点はすごくおもしろい。話が伝わらない“他人”と折り合いをつけながら生きていくためには「1GBの記憶容量」を駆使して、これからも試行錯誤するしかない。
9投稿日: 2025.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ行っていることが伝わらないのは、各人が持っているスキーマが異なるから。 人は自分も相手も忘れるという前提で物事を考えるべき。 期待したほど面白くなかった。
0投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ細谷功さんの『具体と抽象』を読了後に、「この概念を理解している人としていない人の間で、上手くコミュニケーションがとれるのだろうか?」と疑問に思い、この本を手に取ってみた。 やはり、『具体と抽象のよくあるエラー』として記載があった。 また、この本で人それぞれが異なる『スキーマ』を持ち、その枠組みを使ってコミュニケーションを取っていることを知り、やはり相手にこちらの意図を正しく理解してもらうのは簡単ではないのだな、と痛感した。 少しでも円滑なコミュニケーションが取れるように、努力していきたい。
0投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ慶應大学教授・今井むつみ氏の『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』を読了した。2024年5月の出版で2025年6月の今日現在でAmazonのレビューが670件、総合評価4.2の高評価が付いている。 私もその一人だが、他人とのコミュニケーションに悩んでいる人がいかに多いかがわかる。 人はそれぞれ独自のスキーマを持ち、バイアスを持っている。話の前提になるスキーマが異なれば、「阿吽の呼吸」のようなコミュニケーションは難しい。 となれば、①スキーマを合わせるか、②スキーマの違いを乗り越えるかの2択になるが、①は難しいので、②しかない。 そのためには、偏りなく相手の考えに耳を傾けることが大事になるが、「偏りなく」というのが難しい。そもそも、スキーマという偏りがあるため齟齬が生じているのだから、容易ではない。 しかし、相手のスキーマを理解することはできるはずだ。そして「偏りなく」相手のスキーマを聞くこともできる不可能ではないはずだ。 仏法では、偏りがない生命を「仏」と呼ぶ。ありのままを見て、ありのままを聞く。本書はそれがいかに困難であるかを示している。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログハイコンテクストな世界にいると、ついつい目の前の相手を自分と同じと思ってコミュニケーションしてしまいますよね。相手が外国人だったりしたら、フィルターが外れるのにね(笑) どんな人でも認知のフィルターをできるだけ外し、ありのまま接しれるよう精進します♪
4投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログコミニュケーションについて再考するにあたり、とても参考になる内容でした。 正しく伝えるための方法について実践した上で再考したいと思います。
0投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大切だと感じたことです。 スキーマ(理解する際に裏で働いている基本的な知識や思考の枠組み)の違い→認知の歪みを起こす、理解というプロセスを経て認識し、記憶違いなどを起こす 記憶のあやふやさ、塗り替え1GB位しかない。 感情(好き嫌い)が、判断のはじめになることが多い。 判断は即時性のものとゆっくりするものの2種類。即時性のもので大体は間違いがないが、ゆっくり判断するものでチェックをかける。 説明には、理由をつける、具体と抽象をうまく使うなど、一番は相手の理解に配慮して伝えること
0投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションや言語について,認識を新たにすることができた。 自分の中のバイヤスやそれぞれが持つスキーマのことも改めて気付かされる事がたくさんあった。 知人や子ども達にも勧めたい。
0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログITエンジニア本大賞2025のビジネス部門大賞ということで気になっていたので読んでみた。 コミュニケーションにおいてかなり重要なことが書いてあったように思う。 言っても伝わらないということはあると思って接したほうがいいよね。 うちの会社にも、口頭でいろいろいわれて、全然伝わらないのに、「なんでこの説明で分からないか分からない!」と言ってくる人がいる(一度、「その言い方やめて」と言ってからはやめてくれたけど)。 相手が「わかった」といってもそこには齟齬がある可能性があるということは、意識しておいたほうがいいのだろうと思う。だから、どう理解したかを聞くのがいいのだろうけど、その伝え方が悪くうまく伝わらなかったら、分かっているのか分かっていないのかが分からないという。 「自分の記憶が正しいと信じられた人の勝ち」というのは確かにあるよなと思うことがある。自分は、昔から自分の記憶を信じられないので、「そんなこと言ってたっけ?」とか「そんなこと言ったっけ?」となるので、相手のいうことを信じるしかなくなることがある。 極力そうならないために、せめてメモの習慣はつけたほうがいいのだろうな。 コロナ禍によくメディアにでていた感染症の専門医の尾身茂さんについての話も書いてあって、かなり理解されなかったり、曲解されたりしたこともあったよう。確かに、よく叩かれてるとこみたなと思う。 後、そもそも人間は忘れる生き物なのだから、覚えていないことなんて当たり前のようにあると考えたほうがいいとのこと。そのためには、メモの習慣とリマインドが重要なのだと思った。まあ、それも忙しい時には忘れてしまうことはあるけど。 理由を伝えるというのは、大事だよなと思う。うちの会社でも、「○○しといて」といってなぜを伝えない人がいて、なぜそれをやるのかがよく分からず、多分こうだろうなと思って進めると求めていたものと違うなんて言われることがあった。 自分は、極力、依頼する時や、質問する時は、なぜかも伝えるようにしている(まあ、そのなぜかの説明だけに着目されて、質問に答えてもらえないなんてこともあるのだけど)。 他人は別の生き物と思ったほうがいいということがあるけど、まさにそう考えたほうがメンタルもコミュニケーションも楽になるのだろうなと思う。
1投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言い方を工夫したり、言い変えてみたり、わかってもらえるまで何度も繰り返し説明したりしても、相手に伝わらないのはなぜかを、根本的なものから解決策まで書いた本だった。 ところどころ分かりにくい部分があったが、要するに、相手の立場に立って話す・理由をつけて説明する・相手の感情に寄り添う・悩みを共有する・感情をぶつけない・具体的に伝える・相手の話をしっかり聞いて、お互いに話しやすい環境を作ることで、相手に伝わるコミュニケーションができると書いてあった。 なるほどなと思った。
1投稿日: 2025.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ間違っているのは、 「言い方」ではなく「心の読み方」 ビジネスで 学校で 家庭で …… 「うまく伝わらない」という悩みの多くは、 「言い方を工夫しましょう」「言い換えてみましょう」「わかってもらえるまで何度も繰り返し説明しましょう」では解決しません。 人は、自分の都合がいいように、いかようにも誤解する生き物です。 では、都合よく誤解されないためにどうするか? 自分の考えを“正しく伝える”方法は? 「伝えること」「わかり合うこと」を真面目に考え、 実践したい人のための1冊です。 目次 はじめに 認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策 第1章 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない 「人と人は、話せばわかり合える」ものなのか? 「話せばわかる」とはどういうことか? 「話せばわかる」の試練――記憶力の問題 人の記憶はどこまで「曖昧」なものなのか 「相手にわかってもらえる」を実現する方法を考えよう 第2章「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、いったい何が起きているのか? 「言えば伝わる」「話せばわかる」を裏側から考える 言っても伝わらないを生み出すもの①「理解」についての2つの勘違い 言っても伝わらないを生み出すもの②「まんべんなく公平に見渡す」ことはできない、視点の偏り 言っても伝わらないを生み出すもの③「専門性」が視野を歪ませる、言っても伝わらないを生み出すもの④人間は「記憶マシーン」にはなれない 言っても伝わらないを生み出すもの⑤言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく、言っても伝わらないを生み出すもの⑥「認知バイアス」で思考が止まる、様々な思い込みと認知バイアス 第3章「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには? ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか「相手の立場」で考える ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「心の理論」 ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「メタ認知」 「相手の立場」に立てる人のコミュニケーション 「感情」に気を配る 感情を味方につけるコミュニケーションのコツ 「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ 「伝わる説明」を、具体と抽象から考える 「意図」を読む 第4章 「伝わらない」「わかり合えない」を越える コミュニケーションのとり方 「いいコミュニケーション」とは何か? 「コミュニケーションの達人」の特徴① 達人は失敗を成長の糧(かて)にしている 「コミュニケーションの達人」の特徴② 説明の手間を惜しまない 「コミュニケーションの達人」の特徴③ コントロールしようと思わない 「コミュニケーションの達人」の特徴④ 「聞く耳」をいつも持つ 終章 コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために ビジネスの熟達者とコミュニケーション ビジネスの熟達者になるための「直観」
0投稿日: 2025.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策 著:今井 むつみ 出版社:日経BP 良書。本書は、コンピュータの関係者にとって、戦慄の書である。 なぜなら、文章(ドキュメント)のお城に住んでいる我々コンピュータ関係者の中で、完全なコミュニケーションが成り得ないと言い切っている書であるからである。 企画、要件定義、概要設計と工程が下るにつれて、膨大なドキュメントを生産する情報システム開発はまさに人と人とのコミュニケーションになりたっている仕事である 「伝えたい物事が正しく伝わらないのは、言い方や説明不足のせいだけではないのかもしれない」 が本書のテーマである。 コミュニケーションという動作を深く掘り下げ、ヒューマンエラーを様々な角度から眺め、どうすれば防げるかを考察する。 当然ながら、どんな仕事でも独りで完結するようなものはない、かならず、人と人とのコミュニケーションの上になりたっている。 その中で、齟齬が知らぬ間におきて、そのチェックをして、確認を進めていく。テストは、コミュニケーションの必要な段階で必ず必要になると、認知科学は告げている。 おおむね、正しい。 人の感情を配慮しての対応も必要 となると、いずれ、生成AIが主要な部分をカバーしてしまうかもしれない 目次 はじめに 認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策 間違っているのは「言い方」ではなく「心の読み方」 第1章 「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない 「人と人は、話せばわかり合える」ものなのか? 「話せばわかる」とはどういうことか? 「話せばわかる」の試練 ー 記憶力の問題 人の記憶はどこまで「曖昧」なものなのか 「相手にわかってもらえる」を実現する方法を考えよう 第2章 「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、いったい何が起きているのか? 「言えば伝わる」「話せばわかる」を裏側から考える 言っても伝わらないを生み出すもの① 「理解」についての2つの勘違い 言っても伝わらないを生み出すもの② 「まんべんなく公平に見渡す」ことはできない、視点の偏り 言っても伝わらないを生み出すもの③ 「専門性」が視野を歪ませる 言っても伝わらないを生み出すもの④ 人間は「記憶マシーン」にはなれない 言っても伝わらないを生み出すもの⑤ 言葉が、感情が、記憶をどんどん書き換えていく 言っても伝わらないを生み出すもの⑥ 「認知バイアス」で思考が止まる 様々な思い込みと認知バイアス 第3章 「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには? ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか 「相手の立場」で考える ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「心の理論」 ビジネスで「相手の立場に立つ」ための「メタ認知」 「相手の立場」に立てる人のコミュニケーション 「感情」に気を配る 感情を味方につけるコミュニケーションのコツ 「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ 「伝わる説明」を具体と抽象から考える 「意図」を読む 第4章 「伝わらない」「わかり合えない」を越えるコミュニケーションのとり方 「いいコミュニケーション」とは何か? 「コミュニケーションの達人」の特徴① 達人は失敗を成長の糧にしている 「コミュニケーションの達人」の特徴② 説明の手間を惜しまない 「コミュニケーションの達人」の特徴③ コントロールしようと思わない 「コミュニケーションの達人」の特徴④ 「聞く耳」をいつも持つ 終章 コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために ビジネスの熟達者とコミュニケーション ビジネスの熟達者になるための「直観」 おわりに ISBN:9784296000951 判型:4-6 ページ数:304ページ 定価:1700円(本体) 2024年05月13日第1版第1刷発行
18投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会でマネジメントする際や家庭でも応用することができよう内容である。 本著では、心理学、認知心理学等の視点からコミュニケーションの改善と解決法を教えてくれる。内容は伝え方や相手の心の枠組みまで捉えてから、伝えることが必要と説く。私なりに補足をするのであれば、「相手の心を知ることや理解する姿勢は大切だが、機嫌を伺うようなことはしてはいけない。」それでは、部下が育つことはできない。どこかで必ずしわ寄せが来る。 本著では相手の心の在り方の理解が必要だと述べており、それはとても重要だと私も思う。だが、現場の実践に落とし込むとなると中々難しいという現実もある。それでも、心の在り方は人それぞれなので、全ての人を理解しマネジメントすることから、私、あなたという自分という人間をまず心の在り方を理解し、受け入れた上で、対人間として(男女年齢関係なく)向き合うことがマネジメントの土台として必要だと言えよう。合わせて、この本は一つの人間関係理解の解釈と実践としての相手の心と人間性と自分に向き合う姿勢を試みる内容といえるだろう。
0投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人にはそれぞれの「スキーマ(枠組み)」があり、それに応じた理解になるため、お互いに齟齬が生じることがある。 また、人間は「記憶マシーン」にはなれず、言葉や感情、時間の経過がどんどん記憶を書き換えていく。さらには自分の中の「神聖な価値観」によって思考が止まってしまう。 そうならないためには、相手の立場に立って、互いの心の内を擦り合わせていくことや、具体と抽象の往還をすること、メタ認知の大切さを事例とともに紹介している。
11投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ言ったのに、話したのに伝わらないことがあり何とかならないかなと思って読んでみた。 まず前提として人が相手とは違うスキーム、バイアスを持っていることに気づけた。これを踏まえた上でどう伝えるかが大切と分かったことが大きな一歩。素敵で楽しいコミュニケーションめざしてがんばる。
1投稿日: 2025.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テーマはスキーマ。相手の、そして自分が持っている枠を考えること。 個人的ヒットはどんな理由でもあるだけで感情が楽になるという話。実感がありよくわかるし、振り返ると実践していた。とても納得。
0投稿日: 2025.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログコミニュケーションについて、認知科学の視点から紐解き、より良いコミニュケーションを取るための考え方を示している。コミニュケーションを単なる言葉のやり取りではなく、その背景にある認知の枠組み(スキーマ)や認知バイアスから捉えている。この本を読むと他者と意思疎通を取ることが奇跡のように思えてくる。スキーマの異なる人との認識の擦り合わせはタフな作業だが、そこから逃げずに向き合う人がコミニュケーションに熟達した人になれると感じた。
0投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人と人は分かり合えないという前提で話す必要がある。この本を手に取った時点で、向上心があり成長したいという思いが強いはず。それも才能のひとつだと書かれていて、少し自信になった。 思い込みにとらわれた生き方は実は楽な生き方 自分の認知のバイアスに埋没し、心地よいところだけで生きるのはとても楽な生き方でもある 私の母がそのタイプ そのためかいつも話しても話にならない 母は自分の考えに固執し、話を理解してくれず、私はイライラする 母のようにはなりたくないという強い気持ちが、私の向上心の原動力となっていると感じた
1投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手の当たり前と自分の当たり前は違うもの。話せばわかる、言葉を尽くせばわかるのは、共通の言語があるから。ものすごく大雑把に言うとそういうことなのかなと、雑に理解した。 そこをスキーマと言われると、途端にわかりにくくなってしまうんだけどな‥一般人としては。スキームと語感も意味も何となく似ているせいで。何かぴったりな日本語はないかな。
2投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
突飛な気づきを与えるというよりは、コミュニケーションにおけるあるあるがなぜ発生するのか、と言ったタイトルについての深掘りが為されている本。 具体的に何をすればいいのかでなく、「そもそも、この前提があるからすれ違いが起こるということを頭に入れておくのが大切だ」というのが言語化されていて面白かった。 仕事・家庭・友人、コミュニケーションに迷う瞬間がある人には一読してほしい本。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて「ある ある」って、自分自身に置き換えてよく分かりました。実際に第一人者目線の発言をしてるだろうし、同じ思考回路だと思った伝えてる。 しかし、「思考の枠組み」は環境、立場、時などいろいろあるから、全く個々のスキーマは違うのだ。 伝えたいを叶えたいなら、より相手側になり発信する事が大事だと深く感じた。 また、直感が大切で一番の正解かもには、笑えた。やはり自分を信頼しないとね。モノゴトを忘れちゃう自分が一番怖いのに(笑)
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はタイトル通り 「なぜ起こるのか?」 を認知科学、心理学の観点から説明がされている。 というよりほぼその説明で、全体を占めており だからどうすればという具体的な解決策の説明は 種類として少なく幅広い層に当てはまらないのでそこは期待しないほうが良い。 本質を理解して、実践するには自分の環境をよく理解しそこに合わせた解決法を自分で見出すことが必要不可である。その手助けとして読んでおきたい一冊。
0投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手の立場に立って想像力を働かす、という昔から何度も擦られた表現が、「人はみな異なるスキーマ(枠組み)を持っている」という時代に合ったものに言い換えられ進化していた。
10投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んだから、他人が自分の説明をわかってくれるようになるわけではないが、そりゃそうだよねとはなる。
2投稿日: 2025.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝える側と伝えられる側のギャップがわかりやすい。それでいて、具体的なので、この手のビジネス書の中でも印象的だった。 エビデンスを羅列するだけでなく、実用的な一冊と感じられた。 シーンも、あらゆる仕事や業種だけでなく、プライベートでも、まあ相手が老若男女、どんな人でも役立つと思う。 1日でサクサク読み切れる本にもかかわらず、深みもある。
0投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションギャップがよくわかるし、それを円滑にするためが書かれており、読みやすく、実践しやすい。
0投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策。今井 むつみ先生の著書。何回説明しても伝わらないは自分のせい?何回説明しても伝わらないの相手のせい?自分は悪くない、相手がバカで理解できないだけ。そんな風に上から目線で傲慢に振る舞っても伝わらないだけ。相手がバカで理解できないわけではなくて自分が悪いと反省しないと。
0投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ教職に就いている身なので、「何回説明しても伝わらない」という悩みは日常茶飯事である。 より円滑な、相手と分かりあうためのコミュニケーションに必要なヒントを1つでも得たくて、本書を手に取ってみた。 印象に残ったキーワードの一つが、「認知バイアス」。 偏見、先入観、歪んだデータ、一方的なおもいこみなどを生み出す我々の認知の傾向のことを言う。 特定の価値観による物事の単純化や、根拠のない価値観の押し付け、他人の知識と自分の知識に差があることに気づかないことなど、多くの人が知らず知らずのうちにコミュニケーションを阻害する認知の偏りを持ってしまっている。 伝えることや理解してもらうことを達成するには、相手の立場に立つことや「感情」に配慮すること、具体と抽象のバランスなどが大切らしい。 また、コミュニケーションの達人は失敗を成長の糧にしており、手間を惜しまぬ説明を心がけ、相手の成長を意識したり「聞く耳」を持つ意識が高いそうだ。 結びにあった「直観」についての文章も大いに学びになった。 学校では、生徒に対して自主性を要求しがちである。 しかし、教員側が具体と抽象を上手に使い分けた指示・説明の技術を持っていないとしたら、自主性の要求は教員側の怠慢と言えるのではないか? 自主性とか忖度というものについて考えさせられました。 いったい、人は他者の行動に対してどこまで要求する権利があるのだろうか?
1投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルのごとく、伝わらないのを解消する内容というより何故伝わらないのかという原因メインだった印象。新しい知識はあまり増えなかった気がするが、サラッと読めて認知に関する大まかなことは学べると思う。 ・別の人間とは、違う背景・違う視点で物を理解しているため、同じ話をしても同じ理解をするとは限らない ・言葉とは既に抽象的なものであり、言葉を聞いた時にそのまま受け取る訳ではなく、自分の中で再構築している→そのため背景が違えば齟齬が生まれるのは必然 ・できるだけ齟齬を無くすためには、具体例を多く入れるなどの工夫に加えて、相手の立場に立って話す意識が重要 これから意識したいと思ったこと ○人は忘れる生き物だという前提でいること ○自分に都合の悪い話でもネガティブな感情を出さない ○仕事以外のことでも、話しやすい相手であれるようできるだけ多くコミュニケーションを取る ○システム1(大体の判断に直結する直感的思考)で良い判断ができる力を身につけるには、その物事に向き合い、極めること
2投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ職場での悩みや疑問がかなり解決した本 でも解決して終わり!じゃなくて相手の意図や感情を汲み取れるようにならないと根本的な解決にはならないんだろうな、それが難しいんだろうけど 私はメタ認知システム2の熟考の力が弱い気がする… 深く考えないところがある自覚がはっきりした 今度はそういう思考力的な部分をどう伸ばすが、みたいな本を読んでみようかな 枝葉のように広がる読書、たのしい… この本は序盤からコロナや空港爆発の時事ネタを例にして話していて、それがすごく分かりやすいと思った そしてそれこそが抽象と具体の具体例だったんだと最後まで読んで気付いた そういえば、中学高校の英文法のテキストも必ず抽象と具体で構成されてたな
22投稿日: 2025.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ・相手に正しく理解してもらうことは相手の思い込みの塊と対峙していくこと。そしえ相手を正しく理解することは自分が持っている思い込みに気がつくことでもある。 ・人は誰もが異なるフィルター、つまりスキーマを無自覚に持っており、それをベースにしてしかコミュニケーションは取れない、と言う事実を理解することが重要 ・選択や意思決定の多くの場合、人は最初に感情で、端的にいえば「好きか嫌いか」で物事を判断し、その後「論理的な理由」を後付けしているに過ぎない これらの事実を知っているだけでも、コミュニケーションのすれ違いによるストレスが減り、より円滑にやりとりすることができると感じた。 今まで他人といざこざがあった時に自分の性格などに自責の念が生まれていたが、それもあるかもしれないが、そもそもの認知の仕組み上、起こりやすかったのかもしれないと視野が広がる一冊だった。 自分がわかったと思った時、本当に自分は相手が意図しているように理解できているのか?人の話はすべて自分のスキーマというフィルターを通して理解される
17投稿日: 2025.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の理解は、発言の内容そのものよりも、発言者の態度や発言された状況等、そして発言を聞く人の理解力の背景にある知識に大きく影響される。 正しくコミュニケーションをするためには、そのようなバイアスがあることを知った上で、そのバイアスを補正するような努力が必要、というように要約してみたのだが、さて、どの程度、この本の内容を上手く伝えられているのだろうか?
1投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ周囲の人が薦めていたため手に取りました。 自分の行動を反省させらる1冊。 どうして相手に伝わらないのか認知学の観点から物事の考え方を教えていただけます。 そうだよなぁ、コミュニケーションだよな。 相手のことを考えて話さなきゃなぁ。
1投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログで?結局どうしたらいいの?みたいな気持ちで読んでる時間が長かったかな。 最後の方にあった、嫌な報告をしてもらえる雰囲気をつくる→小さいリスクも早めに共有できる→手を打てるっていうのはなるほどなと思った。怒られると思うと、やばい事あっても1人で解決できたら言わなくて済むからって抱え込むもんね。
4投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションの本質のようなものを学んだ。話せば分かるは幻想で、メッセージの出し手も受け手も相手を慮り丁寧に接するのが良い。場合によっては自分のスキーマを手放し、寄り添った解釈をするべきと感じている。
1投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルについての回答はしていないと言いながら、最後にはその解法を説明している。ハドソン川の奇跡の機長の話を引用して、直感は訓練の賜物という説明である。AIについてもその観点で批判している。 東日本大震災ので釜石の奇跡においても、ただ津波が予想を遥かに超えて高くなったにもかかわらず、99%以上の人が助かったのは、直感でより高台で逃げたからたすかったのではなく、絶え間なく訓練していて、それから直感を働かせたので助かったということが言える。単に訓練していて訓練した避難場所に逃げて安心していたら被災してしまう。
1投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ話者は受け手に対して、言葉を介して、考えや思いを伝えるけれど、それがまったく正確に等しく伝わっている保証はない。どう捉えられるかを考えながらの発言が大事。受け手側もそれを分かったうえで、何を言いたいのかを汲み取る。
3投稿日: 2025.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ後輩の教育をしていて、説明したのに伝わらず、苦労を感じることが多かったので読みました。 相手はどこまで理解できた上で話を聞いているのか、こちらもしっかり考えた上で説明していくようしたいと思います。
1投稿日: 2025.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ構成 1.話せばわかるではなく、相手にわかってもらえることが大事。 2.話してもわからないとき、何が起きてる? 3.言えば伝わるを実現するには? 4.いいコミュニケーションとは?
1投稿日: 2025.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コミュニケーションのズレは、各人が持つスキーマの違いから生じる点にあることを知ることができた。とはいえ、日常のコミュニケーションの中で、スキーマの違いを意識し、プラス方向にチームを作っていくことは、言うは易く行うは難し、と感じる。 ✔︎「イヤな報告を受けたときこそ、相手をほめる、感謝する」くらいの心づもりが必要
1投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログパートナーとの生活の中で、自分の苛立つ感情をどうにかしたいと思っており、ふと目に入ってあまり深く考えずに購入。 「人間は前提として、わかり合えないものである」 認知科学の観点から、研究や実験、事例、体験を交えて、とても分かりやすく読みやすかったです。 筆者が子どもの言語発達の研究などもしているので、大人が当たり前のように思っている事柄を、子どもが認知する過程で取り上げているのも面白い。 日本語⇔英語の違いはその言葉の成り立ちを考えることで認識の違いが見えてくる。 認知バイアス、メタ認知、具体と抽象 一朝一夕でどうにかなるようなものではないが、多様性の時代において大事な何かを考えるきっかけにもなる本。 個人的には、ドミニク・チェンさんの「未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために」にも繋がる本。
1投稿日: 2025.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館新刊コーナーより。 若い人向けの本として紹介されていたリストにあり、気になっていた。 タイトルから「ライトなハウツー本」という印象を受けていたけど、単純なハウツーに収まらない本だった。 気軽に読めることは読める。 人が「聞き逃し、都合よく解釈し、誤解し、忘れる」ものだという前提のもとで、どうコミュニケーションをとればいいのか、という内容。 とても共感する。話が食い違っていたら「前提が違うんだな」とよく思う。 人はそれぞれ、思考の枠組み(スキーマ)を持っている。 他人から聞いた言葉はスキーマを通して解釈される。 相手も別のスキーマを持っているので、「わかり合えた!」と思っていても、ズレていることがある。 そのため、結論に焦点を絞った話し方をする必要があるというのは、味気ないけど適切な方法だと思う。 コミュニケーションの失敗を成長の糧にしたり、説明の手間を惜しまないとか、相手をコントロールしようと思わないとか、「聞く耳」を持つなどの心掛けが必要とのこと。 なんだかざっくりしているけれど、「これだけやれば大丈夫!」みたいな、単純な解決方法は無いということなのかな。
1投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ【学んだこと】 ・人とそれぞれのスキーマーが違うから分かり合えなくて当たり前 ・小さな村バイアスが家庭内モラハラにつながるのでは ・人は覚えてられないということを前提に話す
1投稿日: 2025.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ伝わらないのか??というメカニズムがとても分かりやすく色々な角度から説明されていて、なるほどと思うことがたくさんあった。 一方で、だからどうすれば良いのかと言う部分がちょっと薄く感じた。解決策をもう少し具体的に掘り下げてほしかったかな。
1投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が他人の本をさらっと紹介するくらいの表面的でエネルギーの低い本。引用としてきちんと書いてあるわけでもないので、伝聞の読書感想文のような。 認識の枠組みを「スキーマ」と呼ぶのだな、というのは初めて知ったけど、そのほかは知っている話というかどこかで聞いた話。 心理学の対話スキルへの応用解説としてはこないだ読んだ『話が通じない相手と話をする方法 哲学者が教える不可能を可能にする対話術』の話が深かった。
0投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なぜ説明しても伝わらないのか」を認知科学の視点で原因と対策を述べている。 一般的に人は「伝わらない」と感じると、説明の仕方や表現方法に問題があると、思ってしまう。 なので、分かりやすい説明の仕方や、正しい表現方法を学ぼうとする。 本書はHOW(どのように)を変えることで、伝わるようになるのかに焦点を当てている。 結論は、人は今まで経験や学んだことで形成されたスキームにより、言葉を理解している。 相手にどんなスキームがあるのかを理解すること、 どんな認知バイアスがあるのか知ることで、伝わる言葉を選ぶ必要がある。
1投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルにあるように、「なぜ起こるのか?」がよくわかりました。 結局は、人との関わりにおいて楽な道はなく、コミュニケーションをとるうえで、根気よく人と向き合うしかない。しかし、この本を読みながら、その必要性が理論とともに、自分の中にストンと入り込んできた感覚がありました。 多くの人に読んでもらいたいです。そうすれば、「意図を読まない部下」や「部下を思う通りに動かそうとする上司」も変わっていくのかな。 私は、職場では中堅。後輩もいるし、先輩もいる。どちらの立場にも置かれているので、著者の今井先生の言うように、「多くのことを俎上に載せてうなりながら、自分の結論を出す」ことを、諦めずにやっていきたいと強く思いました。 「おわりに」で、著者の今井先生が「本書をここまで読んでくださった皆さんは」と、読者に向けて、励ましの言葉をくださいます。それも読んだ後の充実感に繋がったように思います。
2投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログはいはい、気を付けますよ いやー失敗した またもや失敗した ついこないだもおんなじこと思ったんだっけ はい、よいコミュニケーションを生むための考え方というか、そんな感じのやーつなんだけど、最終目標は考え方を変えてコミュニケーション能力を磨きビジネスシーンで役立てようってことみたいなんよね わい、ほんともう出世とかしたくないし、今さら部下とか持ちたくないんで、ただただ毎日ヘラヘラしていたいので、ビジネス書とか読んでもぜんぜん感銘とか受けないんだわ よし!頑張ろう的な気持ちにならんのよ じゃあ読むなよってね だから失敗した言うてるやん 日経なんちゃらとかは、ほんと手にするのやめよう なんかごめんなさい でもちゃんと最後まで読んだから許す!
53投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ何回説明しても伝わらない理由について、「スキーマ(人がものごとを理解する枠組み)がみんな違うから」を軸に、丁寧に説明してある本です。 少し前に、今井氏の『学力喪失』を読んでいたこともあって、その内容との関連性も適度にあったため、個人的には、非常に読みやすかったです。 ちなみに、個人的に最も衝撃を受けたのは終章。 自分が最近考えていたことが、立て続けに的確に言語化されていて、感動を覚えました。 ここ最近、「10000時間の法則」や「システム1の思考とシステム2の思考(とそれらの関係)」「AIをはじめとする機械を使った学習の危うさ」あたりのことをずっと考えていて、何となく、思考がまとまりつつありました。 本書の終章では、その思考の結論とも言える内容をズバッとまとめてあり、しかも、そのまとめが、自分が考えていた方向とピッタリ合っていたのが、感動を覚えた理由だと思います。 本書で得た考え方も参考にしながら、いろんな人たちと一緒に、これからの仕事の進め方を考えていきたいな、と思っているのですが、その中には、スキーマが自分とはとんでもなく異なる人がいて、その人を相手にしなくてはならないことが見えているので、そこをどう乗り越えていくかについても、本書で得た知見をもとに、進めていきたいと思います。
1投稿日: 2025.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ生き残るために得た思考の能力が影響していて、言う側も言われた側もその思考のフィルターを通しているから伝わらないことが起きる。それは人それぞれ違うフィルターがあるから当たり前なこと。また実際に起きた出来事に関しての証言が不正確になる原因など、本質的な部分に触れている。思考フィルターがあることを踏まえてどう人と接していくかにも書かれているので親切。一歩引く目線を持たせてくれるきっかけになる本だと思う。
3投稿日: 2025.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の発言を100%理解してもらえるはずがない! だって、人それぞれ育った環境や趣味嗜好のが違うんだもの。 認知バイアスだってあるし… 他人とうまく意思疎通なんてできっこない。 なかなか厳しい現実です。 でも、人間は戦うのです笑 相手を慮って、寄り添って、手を尽くしてわかる努力をする。 爽快な解決策ではないけれど、努力あるのーみ!
34投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で若手の頃「言った言わない」になることがあり、具体と抽象や記憶については気をつけて対処するようにしてきた。 でも本書を読み、話が伝わらない要因としてはそれだけでなく、様々なバイアスがあることをしる。それぞれ説明されていて、「こういうことも気をつけないといけないなあ」と気付かされた。 論理的に説明することに注力しすぎて、相手の感情への配慮が足りていないことを改めて認識した。コピーの割り込みの話には非常に驚いた。本当なのかしらと思うほど。 「具体と抽象のよくあるエラー」はとても面白かった。気にせず生活しているけれど、人はとんでもなく難しいことを苦もなくやってのけるのだなあ。
3投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後にビジネスマン向けに書かれたと知ったが、(なるほど出版社が日経BPである)幅広い人にとって有益だと思う。例えば、カウンセラーにとって、接し方のスキルを学ぶにも、本書を読むことでかなり腹落ちするのではないか。各自が持つスキーマの違いにより相手に伝わらない、自分の判断を客観視するメタ認知を鍛えること。経験により直感力を磨くこと。AI偏重になりつつある今、本著の存在は大事である。わかりやすく読みやすい。2.25.2.15
3投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝わるとは、言っていることが伝わり、こちらの意図通り理解してもらえること。 人間は必ずバイアスがかかるため、「意図通り」理解してもらうためのハードルは高い 相手の立場になって考え、 人は感情によって意思決定をしていることに注意し、 具体と抽象を意識することが大事。
2投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。日々のコミュニケーションにおいて他人は自分とは異なる思想・思考を持っているという前提は、当たり前だけど当たり前として生きてない我々。良い小説を読み終わった時のような爽やかな読後感です。
2投稿日: 2025.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログバイアス、色々あると知った。 それまでの人生の土台が違うのだから、思った通りに伝わっているというのがそもそも無理な話。 というのは常に心に留めておく。 忖度、本来は他人の心をおしはかり、それに配慮することと言ういい意味なのだけど目的がすり替わると事件になる(仕事の成功ではなく、人の気持ちへの配慮のほうを優先してしまうと問題がある)なるほどと思った。
2投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの書籍を読んで勉強になったこと。 ◯人はそれぞれ育ってきた中で独自のスキーマ(考え方)があるため、無意識にそのフィルターを通して理解する。 その前提でコミュニケーションを取る必要がある。 ◯具体と抽象をうまく使い分けて、説明するのが大事。 ◯自身にスキーマのバイアスがかかっていると言うことを理解した上で、相手とコミュニケーションを取る必要がある。 ◯自己開示してコミュニケーションを取りやすくする。 これらを意識して、他者と関われるように心がけたいと思いました。
1投稿日: 2025.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体を通して、身に覚えがあることが誰でも一つや二つはあるはずの、 とても耳の痛い鋭い内容の本ですが、 それだけに座右に置いておくくらいの価値のある一冊だと感じました。 「言った」「言わない」の類いの不毛な言い争いや、お互い誤解してしまうこと、話が噛み合わず平行線のまま終わってしまうこと等、 誰もが日頃から頭を抱えるような悩みについて、 認知科学の観点から、根本的な人間の脳の認知の構造として鮮やかなに紐解いてくれています。 本書を読めば、目から鱗が落ちて、 延々と不毛に悩み続けることが無くなることも 大幅に減ることと思います。 認知科学の専門家が書いているだけあり、 全体的にとても読みやすく、わかりやすい表現で書かれています。 一気に読み終えることができました。 コミュニケーションについて少しでも悩んだことのある人にとっては、 必読の一冊だと感じました。
1投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーションの失敗の本質を科学的に解説 ・人にはそれぞれ思考、知識の枠組み「スキーマ」があるため、伝わらないのはしょうがない ・記憶のすり替えは簡単に発生する ・捻じ曲げられた記憶を本人は真実と思い発言する ・仕事が出来る人は「相手も自分も忘れる可能性がある」ということをわかっている ・バイアスに気をつける ・結論から遡り、バイアスを考える 《気をつけるべきバイアス》 ・信念バイアス(〜べき) ・他人の知識=自分の知識バイアス(専門家のように振る舞う) ・相関を因果と思い込むバイアス(結果が出ないのは努力不足) ・小さな世界の認知バイアス(エコーチェンバー現象) ・相対主義バイアス(それぞれ違ってそれぞれ良い) ・AかBかバイアス(賛成でなければ反対) ・わかりやすいと信じてしまうバイアス ・直感は正解率が高いが、絶対ではない ・メタ認知を働かせる(見直し機能) ・相手の立場に立つ ×あのグループのせいで遅れて困る ⚪︎あのグループのために出来ることは何だろう ・何で出来てないんですか?というほとラクな事はない →相手と一緒に課題を解決しようとする ・説明が上手い人は「具体」と「抽象」を行き来する
1投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今井むつみ著の『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』に関する感想を述べると、特に第4章で強調されているポイントが非常に重要です。以下にその要点をまとめます。 ■重要なポイント ・失敗を糧にする: 失敗は成長の一部であり、そこから学ぶことが重要です。失敗を単なるネガティブな経験として捉えるのではなく、次に生かすための貴重な教訓として受け入れる姿勢が求められます。 ・説明の手間を惜しまない: コミュニケーションにおいては、相手に伝わるように丁寧に説明することが不可欠です。相手の理解度や背景を考慮し、必要な手間をかけることで、誤解を減らすことができます。 ・コントロールしようとしない: 他者をコントロールしようとするのではなく、相手との良好な関係を築くことが大切です。相手の成長を意識し、サポートする姿勢がコミュニケーションを円滑にします。 ・「聞く耳」をいつも持つ: 自分の意見に固執せず、他者の意見や感情に耳を傾けることが重要です。特に、ネガティブな報告や意見に対してもオープンな姿勢を持つことで、信頼関係を深めることができます。 ・他者との関係を諦めない これらのポイントを実践するためには、他者との関係を諦めない姿勢が必要です。コミュニケーションは双方向のプロセスであり、対話がなければ誤解や摩擦が生じやすくなります。時間をかけ、誠意を持って接することで、必ず改善の道が開けると信じることが重要です。 このように、今井むつみの著作は、コミュニケーションの本質を理解し、実践するための具体的な指針を提供しており、非常に有益な内容となっています。 ■本書の要点の抜粋 ・「話したら伝わる」という幻想: 本書では、単に話すことが理解につながるという考え方が幻想であると指摘しています。人は自分の経験や知識に基づいて情報を解釈するため、同じ言葉でも異なる理解を生むことが多いのです。 ・記憶力と理解力の関係: 記憶力が良いことが必ずしも理解力の向上につながるわけではありません。人は情報を忘れる特性を持っており、これがコミュニケーションの障害となることがあります。 ・視点の偏り: 各人の視点は異なり、専門的な知識があるとその視野が狭まり、他者の理解を妨げることがあります。特に、専門用語や業界特有の言葉を使うと、相手が理解できない場合が多いです。 ・感情と記憶の関係: 感情は記憶を強化する一方で、時には記憶を書き換えることもあります。感情が高ぶると、情報の受け取り方が変わるため、冷静なコミュニケーションが難しくなることがあります。 ・認知バイアス: 認知バイアスは、思考を固定化し、柔軟な理解を妨げる要因となります。自分の先入観に基づいて情報を解釈するため、誤解が生じやすくなります。 ・相手の立場に立つためのメタ認知: 他者の視点を理解するためには、メタ認知が重要です。自分の思考を客観的に見つめ、相手の立場に立って考えることで、より良いコミュニケーションが可能になります。 ・感情の取り扱い: 感情には適切な取り扱い方があり、相手の感情に寄り添うことや、理由を伝えることが重要です。また、感情が問題解決に役立たないことを理解することも大切です。 ・「勘違い」と「伝達ミス」: 具体と抽象のエラーが、コミュニケーションの中でしばしば発生します。具体的な事例を挙げることで、相手に意図を伝えやすくなります。 ・「意図」を読む: 相手の意図を理解することが、効果的なコミュニケーションには不可欠です。相手が何を求めているのかを察知することで、よりスムーズな対話が実現します。 ・「直感」を磨く: 最後に、直感を磨くことが重要です。経験を通じて得た直感は、コミュニケーションの質を向上させる助けとなります。 ■結論 本書は、コミュニケーションの複雑さを理解し、改善するための具体的な方法を提供しています。特に、相手の立場に立つことや、感情の取り扱い方を学ぶことで、より良いコミュニケーションが可能になると感じました。これらのポイントを意識することで、日常生活やビジネスシーンでのコミュニケーションが大きく改善されるでしょう。
1投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログさっと読めて、子どもたちや友人達とする、コミュニケーションを円滑に進めるためには?どうすればよいのかと、考える機会を与えて頂きました。 話し方、接し方、考えさせられましたね。 2日くらいで読めるので、時間無い方々にもお勧めです。
1投稿日: 2025.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
何回説明しても伝わらないのは、「あなたと私の知識や思考の枠組み(スキーマ)は全く違う」という前提がなく伝えられているから。 その前提となるフィルターの違いを受け入れ、偏見や先入観、歪んだデータ、一方的な思い込みなどの認知の特徴をそれぞれが理解し、配慮し合って、初めていいコミュニケーションが成り立つ。 多くの人は選択や意思決定の場合、まず感情(「好き」か「嫌い」)で物事を判断するので、相手と自分の感情に配慮したコミュニケーションを心がけたい。
1投稿日: 2025.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログゆる言語学ラジオ(YouTube)で今井先生を知りました。 伝わらない原因が知れて、子供とのコミュニケーションが楽になりました。今までは前言ったでしょと思う事が多々ありイライラしていましたが、分かってなくて当たり前だなと思うようになりました。
1投稿日: 2025.01.28
