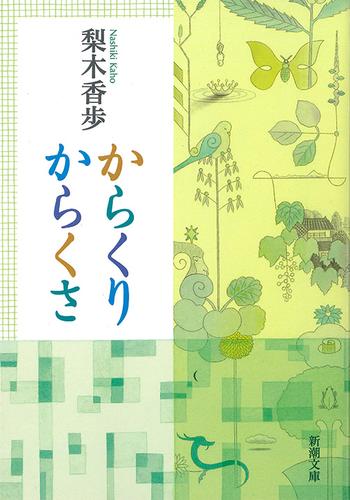
総合評価
(340件)| 100 | ||
| 117 | ||
| 71 | ||
| 18 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ(借.新宿区立図書館) 途中不穏な血縁の因果の話になるのかと思ったが、そこまでではなかった。クルドの話などあちこち寄り道して、どうもいろいろな問題がうまく収拾できていないように感じられる。まだ書き慣れていないときの作品ということなのか? とりあえず前日談の『りかさん』から読み進めていってみよう。
0投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログふむ…といった感じ。 面白かったとは思うんだけど、起伏があまり感じられず、話の軸も何本かあったおかげで、結末もなんかよく分からなかった。 ただ、すごく綺麗なお話だったと思う。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ全容を理解できなかったけど、共感できること、心に落ちてくるものがあった。四人の女性たちも互いにそうなんだろうと思う気がするから、分からなくていいとも思えた。
0投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ4人の下宿生と一体の人形が暮らす家を中心に物語は進む。 登場人物は、染織、機織りなどの手仕事に関わっていて、自然や手仕事を通して、人の生きることに対しての心持ちと言えるようなことが語られる。 機を織る。布を織る。 様々な色の糸を縦横に使い、一枚の布を織る。 簡単には織れない、地道な作業。 織り上がった布には表裏があり、様々な顔を見せる。 至る所で機織りはされ、たしかにその土地に根付いている伝統はあり、脈々と伝えられてきた。 自分の気持ちや境遇、良い時も悪い時も、ただ機を織る。 そうして手仕事をつないできた歴史があるということを知ることは、少しだけ人生を豊かにしてくれると思う。 物語の途中、様々な場面で、草木から色を出していく。 そしてその糸で紬が織られる。 名を残すのではなく、作った物で残っていく。 名は残らないけど、たしかにそれを作った誰かがいて、それは他の誰かの為に作られたもの。 手仕事が紡ぐ歴史は美しいと、改めて思う。 人が生きるということは、様々な縁という糸で織り上げられていくものなのかもしれない。 その織り上げた布は、自分は最後に見ることはできるのか。 見られず、誰かが見て「ああ、あの人はそうやって生きたのか」と思うものなのか。 そんなことをぼんやり考える。
2投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ染めや織り、能、植物の知識もなく、それぞれのルーツや情報量が多すぎてなかなか読むのが難解だったけど途中で読むのをやめようと言う気持ちにはならなかった。古民家で丁寧な暮らしをする日々や、だんだんに謎が解け繋がっていく感じがよかった。『りかさん』を読んだらまた読み返してみようか…
10投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなかに複雑だけど面白い! 登場人物も意外に多いし 染め物の知識からお家騒動 クルド人の置かれた文化的背景などなど 単独でピックアップされても充分な お話が唐草のように絡みあって からくりが解けるように終わって... じっくり知識を持って読むと もっと面白いかなと思いつつも 知識薄くても読み応えあって 素敵な物語だった!
11投稿日: 2025.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
難しかったです。ずっと前に読んで、どうにもこうにも自分の中で「読めた」という感触がなかった記憶があり、今回はもうだいぶ歳も重ねたし、「読める」と思ったのですが・・・(以前、全く楽しめなかった「村田エフェンディ滞土録」は、数年後に読んで大好きになったという経験があったのですが、今回はそうはいかなかった・・・!) 草木染めの修行をしている蓉子は、亡くなった祖母の家に住むことにし、学生の下宿として部屋を貸すことにします。集まってきた下宿人は、同世代である美大の学生の紀久、与希子とアメリカ人のマーガレット。紀久は紬、与希子はキリム織りの研究をしており、マーガレットは東洋医学を学んでいます。4人に共通するのは今では「タイパ」や「コスパ」という点から嫌煙されがちな「手仕事」が好きというところでしょうか。その4人ともうひとり「りかさん」という蓉子の市松人形が、網戸もない古い日本家屋で、庭で摘む草花を食卓に出したりと、なんとも俗世離れした共同生活を送ります。「りかさん」を軸に下宿人たちの宿世の縁がだんだんと明らかになっていきます。 染物の話、織物の話、能面や人形の話、そしてたくさん出てくる植物の名前。なんだか作者の興味の深さと知識の豊富さに圧倒され、そのどれにも詳しくないのに、こう、飲み込まれていく感覚が少し息苦しかったです。それにしても、マニアックすぎませんか。こんなマニアックな話、どれだけの人に受け入れられたのかと要らぬ心配をしながら読んだのですが、そこはさすが梨木香歩というべきところでしょうか。どうやらたくさんの人に読まれ、評価されているようでした。かくいう私も、今回も「読みきれなかった」という思いは強いものの、「嫌い」にはなれず、またいつか、とリベンジを誓ったのでした。 たくさんの人がレビューで書かれていましたが、とにかく相関図がないと関係が複雑で、もうこんがらがっちゃいます。途中からネットで拾った相関図をチラチラ見ながら読みました。「りかさん」からこんなふうにつながるとは、まさに「宿世の縁」でした。 ふと出てくるマーガレットの過去の話で、ピーナッツバターとジェリーのサンドウィッチの話は胸に迫るものがありました。日本語が母語ではないマーガレットが、端的に語るこのセリフは、漠然とした表現になりますが、梨木香歩さんにしか書けないと思いました。梨木香歩さんにしか、マーガレットに語らせることはできないというか。 竹田という与希子が惹かれている青年が、共通の知人の神崎についてその人となりを語るところがあるんですが、こんな表現力ある大学生がおる?!と変なところで深く感心してしまいました。しかも、すごく説得力があるんです。神崎ってそういう人よね、と納得してしまうところと、そういう類の人っているよね、と一般論的にも納得してしまうというか。神崎がこの4人の共同生活にもたらしたものは大きすぎますが、なんだか本質はそこではない気がしました。神崎の件は、あくまで支流というか。うまく言えないのですが。 神崎といえば、トルコに渡り、自身の危険を顧みずにクルド人の奥深いところまで入っていこうとします。唐突に出てきたように感じるクルド人というトピックはマーガレットとつながりがあるのですが、梨木香歩さんがどうしても避けて通れないことなんだろうな、と思いました。ここも作者の「書かなきゃ」という感じが胸に迫ってくるようで、息苦しいような、でもやはり必要なんだろうなというような・・・ 最後、作品と大事な家が燃えあがってしまうところは、登場人物の芸術的感覚に全くついていけませんでした。が、先述したように、決してこの小説を嫌いだとか無理だとか思えないものがありました。 それぞれの暮らしや興味や過去からのつながりが、縦糸と横糸になって織り込まれた一枚の織物のように壮大な物語でした。 それにしても終始、主人公である蓉子自身が私にとってはなんだか不思議な人でした。浮世離れしたというか、何か特別な力を持っていそうな、つかみどころがないのに、一番地に足をつけて生活しているような。自分とは対極にある人のように感じられ、羨ましさが勝ったのかもしれません。 次は「りかさん」を読みたいと思います。これは、どうやら本書より前の蓉子とりかさんの話らしいです。この二冊をどの順番で読むか悩みましたが、出版順に読むことにしました。
36投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ここにはないなにか」を探そうとしないで。ここが、あなたの場所。 祖母が遺した古い家に女が四人、私たちは共同生活を始めた。糸を染め、機を織り、庭に生い茂る草が食卓にのる。静かな、けれどたしかな実感に満ちて重ねられてゆく日々。やさしく硬質な結界。だれかが孕む葛藤も、どこかでつながっている四人の思いも、すべてはこの結界と共にある。心を持つ不思議な人形「りかさん」を真ん中にして――。生命の連なりを支える絆を、深く心に伝える物語。 「新潮社」内容紹介より ちょと染色をする機会があって、それを友人に話したらこの本を紹介してもらったので読んでみた. 染色をするにあたっていろいろと調べてみたのだけれど、まぁ、奥の深いこと.この本にも書かれているように、こういう色が出るだろうというのはある程度分かっているけれど、材料の状態によって焙染剤によって思ったような色にならないこともある.こういう素材の場合はこういう反応が起こっているだろうというのは、化学的に分かってはいるのだけれど、様々な要因によって、色は変化するのだ.思ってたのと違う.この感想はたぶん染色をやっている人が誰しも経験することなのだろうし、きっとそれを楽しんでもいるのだろう. 染色と織物はとても深い関係にある.この本を読んでいて改めてそれを認識した.この本で描かれる4人(5人)の女性たちの共同生活は、それぞれ異なった色をもつ各人が一つ屋根の下で共に織る布のようだと思った.きっと各人の個性とその時々の感情が時間とともに様々な色を織りなすのだろうな.
12投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」の現実感あふれる作風好きだっただけに、若干ファンタジー要素があって期待と違った。あらすじ読んでから手に取るべきだった。
2投稿日: 2024.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い女性4人の古民家共同生活の中で発覚する意外な繋がりのお話 以下、公式のあらすじ --------------------- 祖母が遺した古い家に女が四人、私たちは共同生活を始めた。糸を染め、機を織り、庭に生い茂る草が食卓にのる。静かな、けれどたしかな実感に満ちて重ねられてゆく日々。やさしく硬質な結界。だれかが孕む葛藤も、どこかでつながっている四人の思いも、すべてはこの結界と共にある。心を持つ不思議な人形「りかさん」を真ん中にして――。生命の連なりを支える絆を、深く心に伝える物語。 --------------------- 以前読んだ時は誰が誰の先祖だって?と色々と混乱しながら読んだけど 今回は若干は頭の中で整理しつつも十分には把握しきれてない やはり読書ノートをつけるべきだったか…… おばあちゃんの家で同居する4人 主人公の蓉子、鍼灸の勉強のために日本に来ているマーガレット、機織りの歴史を調べている内山紀久、織物の図案に興味がある佐伯与希子 たまたま同居を始めたのに、人形の「りかさん」をきっかけにした過去の繋がりが発覚し…… 染物の不思議 植物を煮出して染めるという単純な作業なのに 元の植物からは想像できないような色になったり、同じ素材を使っているのに同じように染まらなかったり これだからあてにならないのか、たまらないのか このやりとりは前に読んだときの記憶が今回も残ってた 思った通りにならなくとも、それを面白がれるかという事なのでしょうね りかさんの存在がかなり思わせぶりではあるんだけど あの結末で本当によかったのかな? 以前読んだときは、「りかさん」を先に読んでいたので、りかさんはいつまた話し始めるのだろう?と思いながら読んでいたのだけどね この作品の後に、蓉子さんが子供の頃のりかさんとの出会いを描いた「りかさん」があって、それにはこの物語の後日談になる「ミケルの庭」も収録されている どっちを先に読む方がいいのでしょうね? いっそ、りかさんの収録作をバラして時系列が一番いいのかもしれない あと、トルコのクルド人のエピソードも入っている 梨木香歩さんとトルコと言えば「村田エフェンディ滞土録」を思い浮かべてしまう トルコ、何か繋がりがあったりするんですかね?
3投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神世界と物理世界が絡み合う表現に編み物を使うというのがいい。美しい世界。一つ気になることは、妊娠は嫌だ。その話題は読みたくない。気持ち悪いのだ。
1投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「りかさん」の前日譚。 発売日的にはこちらが先。 ただ、先に「りかさん」を読んだほうが、理解しやすいと感じた。 むしろそうじゃないと、「?」となる部分が多い。 4人の女性の同居を通じて描かれる物語。 「容子」は前作の「ようこ」が大人になった姿。 唐草模様のように、縦横無尽に絡み合っている様は、なるほどタイトルどおり。 人形主体であった「りかさん」に対し、こちらは人間主体のよう。 ただし4人以外の人物関係の把握がなかなか難しい。 背景や世界を思い浮かべながら読むと、牧歌的な雰囲気を感じられた。
1投稿日: 2024.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
‣ 命は旅をしている。私たちの体は、たまたま命が宿をとった「お旅所」だ ‣ 古今東西、機の織り手がほとんど女だったというのには、それが適正であった以前に、女にはそういう営みが必要だったからなのではないでしょうか。誰にも言えない、口に出していったら、世界を破滅させてしまうような、マグマのような思いを、とんとんからり、となだめなだめ、静かな日常に紡いでいくような、そういう営みが ‣ どれだけ共同体に溶け込んでそれに自分を捧げられるかで女の評価は決まるのよ。そこから飛び出してしまうと評価の対象外になる。ということはほとんど人間扱いされなくなるわけ。彼らは自分たちの範疇外にあるある女が恐ろしいのよ。自分たちの存在の基盤まで揺るがされるような気になって ‣ 何百年とはいかなくても、ずっと続いてきたものが変わるときというのは、犠牲になるもんが要るんです。たまたまそのときは私だったわけで…… ‣ 私、いろんなこと勉強して、いろんな人に会った。強く生きていけるように見えた女の人が実は内面に脆さを抱えていて、それが男の人に支えて貰えると錯覚したときにあっというまに崩れていくのも見てきた。彼女は錯覚した。人が人を支えきれるなんて、幻想です ‣ 慈しむってことは、思い立って学べるもんじゃない。受け継がれていく伝統だ ‣ 自分の信条とするところのものを、それも生理的なものに裏打ちされた信条を裏切った行為をすることは、おおげさでなく、自分自身の魂を汚していくようないたたまれない思いだ ‣ どうしてもっと、大声で怒らないの?どうして人間が出来ているようなふりをするの?あなたは何も悪くないのにどうして反省なんかするの? ‣ 私はいつか、人は何かを探すために生きるんだといいましたね。でも、本当はそうじゃなかった。 人はきっと、日常を生き抜くために生まれるのです。 そしてそのことを伝えるために ‣ 一枚の布。 一つの世界。 私たちの世界 ✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ 女性たちの手によって古くから受け継がれてきた染色や織物の技術と、 そこに秘められた抑鬱とした思い。 20年以上前に発行された作品ですが、女性が抱える悩みや葛藤は現在でも根本的には変わっていないのかもしれません。 穏やかな日常、手仕事の尊さ、人との絆、女としての葛藤… 物語に登場する女性たちが、それぞれの思いと共に生きようとする姿に心動かされました☺️ 梨木さんが描く現実と非現実が織り交ざったような世界観はクセになりますね✨
0投稿日: 2024.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ生活を共にする四人の女性。それぞれの先祖や関係が一つの模様のように複雑に織られる。彼女達は自ら自分達のルーツを知ろうとする。それは作中で語られる手仕事を営んできた女性達のようでもありながら異国からの手紙で語られるアイデンティティーを剥奪されまいとするクルド人のようでもある。連続しながら変化すること。私もまた何かを引き継いで何かを残すのだろうか。
0投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者さんの作品、今回も難しかったです。 本のカバーに書かれているのを読んでこれならと思いましたが。 女性4人の共同生活の物語です。 この作品にも沢山の草花について書かれていて、そのつど調べながら読みました。 知らない言葉についても同様に。 読んでいると彼女達の過ごす家が浮かんできます。けれども共同生活の物語としてだけではなく、世界情勢まで話は広がります。 それだけではなく…次々と。 きちんと理解出来て読めたかはわかりませんが、読んでいる間は心地良かったです。
32投稿日: 2023.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔懐かしいおばあちゃんの家を思わせる、古い日本家屋。住んでいるのはイマドキではない、勉強熱心で深い思いやりを持つ表現者達、かつ草木や生き物、織物、染色に専門性がある。 空気感が心地よく、夏の終わり、西陽の入る縁側などを思い起こさせる。個性的な4人は二十歳そこそこ、プラス神秘的なリカさんが居る。 謎解きミステリーのような感じもするが、国際問題や大学や社会の理不尽、古い街や家のしきたりなど、盛り込まれている。彼女たちの前向きな好奇心と素直な性格がホッとする。 ストーリーは複雑だが、世界観はすきです。
1投稿日: 2023.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ蓉子の祖母が亡くなり、その家に4人が同居することになった。染物修行中の蓉子、東洋文化を学びにきたマーガレット、紬(つむぎ)専門の紀久、キリム(中近東の図柄)に興味を持つ与希子の4人である。蓉子が大切にしている日本人形、りかさんを中心に、蓉子・紀久・与希子の関係が明らかになっていく…。 日本人形が元々苦手だったから恐る恐る読んでいった。染織に関する専門用語や、複雑な人間関係が話を難しくさせていて、具体的に細かいことを想像するのが困難だった。
1投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ描写が美しいだけに、私の理解力不足で親戚縁者の関係が分からず読んでいて非常に疲れる点が残念。ストレスが溜まる読書体験だった。 織物や草花に知識造詣のある人、メモ片手に家系図を書ける人におすすめです。
0投稿日: 2023.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ丁寧な共同生活が目に浮かぶ私の好きな世界観の本だった。ただ、植物や染色、織物の知識が、特別有るわけではないので、世界観の半分もイメージしきれなかったように思う。個人的には、いろんなエッセンスが散りばめられすぎていて、結局どうなったの?と言うこともあり、消化不良な感じが残った。
0投稿日: 2023.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体と個のぶつかり合い。 地域から世界まで同じ問題はある。 設定が複雑で満員電車で押されてるような時に読むような本ではなかった。ゆっくりしっかり咀嚼しながら読みたい。
0投稿日: 2023.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梨木香歩さんの不思議な世界、最近、彷徨っていますw。「からくり からくさ」、2002.1発行。命のある人形、りかさんをテーマにした物語。全442頁。残念ながら、93頁で失速しました。
0投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ古民家で自然と共にのんびりと暮らしている女性たちの物語りかと思いきや、りかさんにまつわる過去や彼女たちの内に秘めた激しい思いが淡々と描かれていて、心にぐっと刺さりました。 能面にまつわる過去のつながりがイマイチ理解しきれなかったのですが、伏線がちゃんと回収されていたのでだいたい分かりました。
0投稿日: 2023.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ女の子4人が住んでいる雰囲気や関係性は好きだけど、話が難しい、言葉が難しい、最終的な終わり方がわからない、、読むのにものすごく時間がかかった、、
0投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ亡くなった祖母の家で4名の女性の同居。 描写が薄いベールで包んだような情景で独特の世界観。 このまえに、 りかさん、を読んでいたので、 りかさんの登場を楽しみにしてました。
0投稿日: 2022.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人なあなたは、同世代の友人の家で食事をしようとなった際に、そこに『人形』のための席が用意されていたとしたらどう感じるでしょうか? 人はさまざまな価値観をもってそれぞれの毎日を生きています。それぞれがこれが正しいと思うことを信じて生きています。しかし、表面的な付き合いの中では、そんな価値観はある意味オブラートに包まれて見えにくくもなっています。一方で関係が深くなればなるほどに、そんなオブラートの内側が垣間見えるようになってもいきます。それぞれの住まいを訪れるという行為は、訪問を許した側が、そんなオブラートの内側への侵入を許すことでもあり、そんな訪問はその人の、より素の姿を見ることのできる貴重な機会だと言えます。さらに一歩進んでその人と共同生活を送るようなことになったとしたら、素と素のぶつかり合いの中に関係性はより深まっていく、もしくは深めていくことのできる機会が生まれたと言えます。 そんな場において、テーブルを囲むのは『計六人になるはずなのに』、何故か『しつらえられた席』が七人分だったとしたら、”何故?”という思いが浮かぶのは当然です。そんなあなたが、そのプラス一人分の席が『人形のためのもの』だと知ったとしたらそこに何を思うでしょうか?あなたが抱く疑問に対して、『小さいときからこれが我が家の習慣』と言われたとしたら…。 この作品は、あることがきっかけで一つ屋根の下に暮らすことになった四人の女性の暮らしを描く物語。そんな四人の暮らしの中に一体の『人形』が確かな存在感を放つ物語。そしてそれは、そんな四人の暮らしの中に、『人はきっと、日常を生き抜くために生まれるのです』という言葉の意味を噛み締めることになる物語です。 『今日は祖母が死んで五十日目だ。昨日が四十九日だった』という日に、祖母が暮らした家の鍵を開け、掃除を始めたのは主人公の蓉子(ようこ)。『久しく人気のなかった家の畳はうっすらとほこりを積んでいた』という中、雑巾もかける蓉子は、一通りを終え、『さあ、次はりかさんだ』と、二階にある『祖母が「お人形部屋」と呼んでいた』部屋に入ります。『長持のような桐の箱を引っ張り出し』、『りかさん、起きて。開けるわよ』と、蓋を開けると『柔らかい羽二重の生地に包まれて』『りかさんは眠ってい』ました。『いやだ、りかさん、どうしたの、人形みたい』と声をかけるものの何の反応もないのを見て『りかさんはまだ帰ってきていないんだ』と蓉子の心は沈みます。そして、『祖母の家からりかさんを抱えて帰』った蓉子に『何も変わったことなかった?』と母親の待子が話しかけます。そんな待子は『いつまでもあのままにしておくわけにはいかない』と祖母の家のこれからのことを話します。『女子学生の下宿はどうかしら』と言う待子に『いいわ。私もその下宿人の一人にしてくれるんなら』と提案する蓉子。そして、父親の了解も得られ、『蓉子の独立』が決まりました。『昔から染めものが好き』という蓉子は、『二階を下宿人の個室に、一階の一部を蓉子の工房にすれば両方のニーズが満たせる』と考えます。一方で『あの古い日本家屋に喜んで来てくれる若い娘さんがいるかどうか』を心配し、ため息をつく待子。そんな母親に、『アメリカから鍼灸の勉強のため日本に来てい』て、蓉子とは、英語と日本語を教え合っている仲のマーガレットのことを提案する蓉子。下見をしたマーガレットはすぐに住むことを決めます。そして、残りの二人も『案外早く見つか』ります。『蓉子の通っている染織工房』に通う美大生の内山紀久(うちやま きく)と、佐伯与希子(さえき よきこ)です。『機を織る音』と『織機を置くスペース』に困っていた二人。そして、『四月に入って大学が始まる前に引越しをすまそう』と、相次いで引っ越してきた三人。そして、『荷物も運び入れて一段落した夜』に、『蓉子の両親がささやかな歓迎の宴を開』きました。『蓉子とその両親、下宿人の三人で、計六人になるはずなのに』、場となる居間のテーブルに『しつらえられた席』は七人分であることを不思議に思う『紀久と与希子』。そんな残りの一席は『蓉子の人形のためのもの』でした。『蓉子が小さいときからこれが我が家の習慣』と言い訳する両親。そして、席に座った人形を見て『りかさんっていうの?このお人形』と訊く紀久に『そうです』と『生真面目に答える』マーガレット。そして、『最初にりかさんがきたのはね…』と、蓉子が『りかさん』との出会いを語り始めました。そして、そんな女性四人と『りかさん』が一つ屋根の下で暮らす日々が描かれていきます。 “古い祖母の家。草々の生い茂る庭。染め織りに心惹かれる四人の娘と、不思議な人形にからまる縁。生命を支える新しい絆を深く伝える書き下ろし長篇”と内容紹介にうたわれるこの作品。すべて平仮名で「からくりからくさ」と書かれた書名が和の雰囲気感を強く醸し出しています。では、そんな内容紹介に上げられたポイントを順番に見ていきましょう。まずは、蓉子たち女性四人が暮らすことになった家の”草々の生い茂る庭”です。『町中ではあるけれど…ほら、庭がわりと広いじゃない』という蓉子に『ジャングルみたいよね』と与希子が茶化す庭にはさまざまな野草が繁茂しています。そんな『野草のアクのとりかたや料理』のコツを掴んできた四人は『タンポポ、ノゲシ、ヨメナなど』『多分キク科と見当がつくだけの名も知らぬ雑草でも、平気で食べてしまう』ようになります。『カラスノエンドウ、スズメノエンドウなどのマメ科の植物』は、『あえ物にでも油いためにでも使う。菜飯にもする』と利用します。一方で『てんぷらは一番おいしいけれど、結局その野草の持つ風味が薄くな』ると思い至り、『次第に面白味がなくなった』と繰り返し食べるが故の感覚も生まれてきます。そんな風に庭の植物を食用に楽しむ中で『全部摘んじゃうのは、惜しいくらいね。根っこごとひっこぬく、なんて蛮行はできないわ』とまさかの感覚が生まれる一方で『さすがに野草園にしておくつもりもない』と意見が分かれる四人。結局、『庭を四等分してそれぞれの管轄に』することを決めました。この植物に対峙する感覚は梨木さんの代表作でもある「西の魔女が死んだ」にも感じられるものです。とても梨木さんらしい雰囲気感がよく出た場面だと思いました。 次に”染め織り”です。そもそもが『染めもの』が好きで、その工房を設けたいと引っ越してきた蓉子、そして美大生の紀久と与希子が暮らす中では、『染めもの』の話題が出るのは必然と言えます。幾つもの場面が登場しますが、『植物園で、桂の大木が切り倒されることになった』というその木をもらって染めていく様はその工程が素人にも分かりやすく表現されています。『枝葉を払って車に詰め込んできた』という桂を手にした三人。『枝葉をざっと洗い、細かく切り刻む準備にかか』り、『割合に早く事が進み、大鍋に煮出すところまでい』きます。そして、『ステンレスの大鍋の様子を見、染め棒でかきまわす』蓉子は、タイミングを見計らい『火から鍋を降ろし、ざるにあけた。漉した染液に、糸束を浸け、ゆらゆらと染め棒で染み込ませる』と工程を進めます。そして、『鉄媒染で、多分、紫黒色』という『媒染液を用意』し、布を浸け、引き上げます。しかし、それを見て『ああ、どうも、これは…』と落胆する蓉子は、『紫黒というよりは、闇に近い、迷妄のような紫だった』という染め上がりを見て『おかしいわ、前、桂でやったときは…。これだから植物は…』と思います。そんな言葉の後に『あてにならない』と続けようとしたところを、その場にいた神崎に『こたえられないね』と言葉を括り上げられる蓉子。そんな会話の中に、思わず『にっと笑って神崎を見た』蓉子…と続くこの場面。『染めもの』の難しさと面白さを読者に絶妙に垣間見せてくれる場面だと思いました。 そして、そんな物語で欠かすことのできない存在、それが、”不思議な人形”という『りかさん』の存在です。『りかさんは、もともと蓉子が昔、祖母から貰った人形だ』と紹介される『りかさん』。その経緯は「りかさん」の中で存分に堪能できますが、面白いのは「りかさん」単行本の刊行が1999年12月にも関わらず、この「からくりからくさ」単行本の刊行はそれに遡ること7ヶ月前。1999年5月という点です。刊行順に読まれた方はこの作品の衝撃的な結末を先に読んだ後、『りかさん』の過去を遡るように、蓉子との出会いを読むことになり、何とも不可思議な読書を体験されたことになります。また、「りかさん」文庫本の後半には〈ミケルの庭〉という短編が収録されていますが、これは実はこの作品の後日談になっています。この辺り、説明なしに順不同で読むと全く意味がわからなくなります。この辺りなんとかならないものかと思いますが、これから読まれる方のために、ここに読む順番を記しておきたいと思います。 ①「りかさん」: 幼き蓉子(ようこ)がおばあちゃんから『りかさん』をプレゼントしてもらう物語。 ②「からくりからくさ」: おばあちゃんの死後、おばあちゃんの家に友人等三人と四人で暮らす蓉子の物語。『りかさん』も一緒。 ③〈ミケルの庭「りかさん」に同録〉: 一歳になったミケルを置いて”中国に短期留学に行ってしまった”母親の代わりに育児をする蓉子たちの物語。 ④「この庭に ー 黒いミンクの話」: 〈ミケルの庭〉のさらなる続編。 ということで、流れからするとこの作品は『りかさん』四部作?の中間にあたる物語となります。そんな物語では、前作「りかさん」と大きな違いをもって『りかさん』が存在します。それが、『りかさんはまだ帰ってきていないんだ』と、蓉子の心が沈んでいく様が描かれるように、前作「りかさん」と異なり、会話をしない、蓉子と心を通わせることのない『りかさん』の存在です。前作を読まれていない方には何を言っているのか意味不明かもしれませんが、実は人形の『りかさん』は、主人公・蓉子と会話をするのです。そして、「りかさん」での会話の光景がこの作品ではこんな風に説明されます。 『りかさんの声は、耳からではなく、蓉子の目と目の間、つまり顔の正面から入ってくる。父母はりかさんの声が聞こえないようだった』。 「りかさん」の中で二人が会話をする場面は幾度も描かれますが、その情景を詳述するこの記述は、「りかさん」を読んだ読者に、そういうことだったのか!と貴重な”解説書”の役割りも果たしてくれます。 『りかさんと祖母と蓉子は、秘密結社のような濃密な時間を共にした』という蓉子の幼き日々。そして、『蓉子の学校生活が忙しくなるに連れてその濃密さは薄れていったが、それでもりかさんの存在は蓉子にはかけがえのないものだった』と補足されていくそれからの蓉子と『りかさん』の関係性の描写はとにかく貴重です。そして、そんな『りかさん』が今作でしゃべらない原因がこんな風に語られます。 『人形は傍らに人間がいなくなると、「冬眠」のような状態になるのだそうだ。今回はどうだったのだろう。そういえばりかさんは「お浄土送り」をするとは言ったが、帰ってくるとは言わなかった。けれど別れの挨拶もなかったのだ…』。 おばあちゃんの死により『りかさん』に起こった大きな変化。その先に描かれていく物語は、『りかさん』という存在がただの人形にすぎない現実を見る物語が描かれているとも言えます。しかし、それを読む読者がそこから感じるのは『りかさん』の確かな存在感です。『りかさんは人形だけれど、命がある』というその存在はおばあちゃんの家で暮らす三人にとって、そして当然ながら蓉子にとって、一人の人間の存在同等の大きさで語られていきます。そして、この存在感の大きさこそがこの物語の読み味を決定付けます。世界観は全く異なりますが、四人の女性が一つ屋根の下で暮らす物語というと、三浦しをんさん「あの家で暮らす四人の女」が思い浮かびます。そんな物語にも人ではない”カラスの善福丸”が登場し、この存在が物語の印象を間違いなく決定付けていました。人間四人という安定感のある構図ではなく、人間四人+αの構図が物語を面白くしていく、そんな構成の妙をこの作品にも同様に感じました。 そんな物語は、上記した、庭の植物を食す、染めものに執心する、そして存在感のある『りかさん』についてさまざま場面で言及がなされるという構図の中に一つ屋根の下に暮らす四人の女性の日常生活が描かれていきます。それで結末までいけばこの作品はある意味書名の和の雰囲気感の上に平穏な四人の女性たちの日常が描かれた物語となるのだと思いますが、実際には後半に進むに従ってどんどん不穏な空気が差し込み始めます。どの点を衝撃と捉えるかは人によると思いますが、私が呆気に取られたのは、 『トルコ政府がクルド人に対して彼らの言葉の使用の禁止をはじめ… 民族アイデンティティを抹殺し去ろうとしている…』 唐突に登場するまさかの『クルド人』問題が俎上に上がる衝撃的な展開です。それは、ある人物の手紙の中に登場するものですが、その手紙全文がひたすらに続くその後に『長い手紙だった』という一行から次のパラグラフが始まる通り、それまで読んできた作品の世界観を一気に変えてしまうだけの文章量をもってこの『クルド人』に関する物語が全体の雰囲気を支配していきます。その一方で、物語は、これまた予想だに出来ないまさかの展開をもって、不穏な空気感の中にスピードをどんどん上げて一気に幕を下ろします。この幕の下ろし方は衝撃的であり、これには度肝を抜かれました。ネタバレになるのでこの詳細に触れることはできません。しかし、この作品のブクログのレビューを見るとその評価は完全に二分しています。もちろん人によって受け止め方は異なるとは思いますが、少なくとも私には特にこの『クルド人』問題の登場は、広い意味で作品のテーマに結びついているとわかった上でも、それでも最後まで異物感が拭えませんでした。 『人は何かを探すために生まれてきたのかも。そう考えたら、死ぬまでにその捜し物を見つけ出したいわね』と言う紀久の言葉に『本当にそうだろうか。それなら死ぬまでに捜し物が見つからなかった人々はどうなるのだろう』と思う蓉子。そんな蓉子が『私が探しているのは、隠れているりかさんなのだろうか』と自問する姿が描かれていくこの作品。そんな作品では、蓉子を含め、おばあちゃんの家で暮らす四人の女性の日常が描かれていました。前作「りかさん」の強い印象から読者もそんな『りかさん』の姿を物語の中に探してしまうこの作品。 さまざまな要素が盛り沢山に書き記されていく物語の中に、『人はきっと、日常を生き抜くために生まれるのです』という梨木さんの拘りを強く感じた、そんな作品でした。
142投稿日: 2022.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの場景描写力は素晴らしい。 日本語の美しさ、日本の自然や四季の変化の美しさを、改めて深く丁寧に教えてくれます。 4人の女性が共同で暮らす古い家。 丁寧に、真剣に生きる女性達が魅力的に描かれています。静かだけど情熱的な作品です。
4投稿日: 2022.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ裏庭で挫折したので、今回も挫折するのだろうかと思いながらも梨木香歩氏の独特の世界に入りたくて購入。りかさんを最初に読んだのがよかった。 大人になった蓉子さんは変わらずりかさんと一緒にいる。話すことはできなくなったけど、価値観も違う下宿人らとの生活の中心にりかさんがいてそして何よりも日常を大切にしている、そんな話になっている。 内容は難しいが機を織るトントンという音が聞こえるような小説でした。
0投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログを始めるよりずっと前に読んだ大好きな本(梨木香歩の作品の中で5本指にはいる)。 新潮社のPR誌「波」で続編の連載(不定期掲載らしいけれど、とりあえずPR誌は定期購読を申し込んだ)が始まったのを機に再読しようと思って本棚から探し出してきた。巻末解説は鶴見俊輔。
2投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「りかさん」を先に読んでいたので すんなりと物語の世界に入れた。 大人になった蓉子は染織の世界へ。 祖母の家での同居人は機を織り、 織物の研究をし、針灸の勉強とそれぞれ。 庭の植物や穏やかな暮らしのなかに 人の思いや現実があり 人形や織物が過去を物語る。 3人の合作の最後の様子は圧倒され 一瞬の芸術というのもあるのだなと 思った。
2投稿日: 2022.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
テーマは“宿世の縁”。 その媒体となっているものは“一枚の布”。 布を織ること。 古代より脈々と受け継がれてきた手仕事。 “布”は、俯瞰でみると一つの“物”だけれど、元々は紡がれ染められた“糸”であり、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が丹念に織り上げられて、模様になっていく。 紡ぎ手の思い、染め手の思い、織り手の思いまでもが織り込まれている、一枚の布。 『からくりからくさ』 梨木香歩 (新潮文庫) 梨木さんの書く物語は、どこかしっとりと湿り気を帯びている。 自然にくるまれ守られて、朝霧の中で静かに呼吸をしているような感じ。 染色家を志す「蓉子」、機織りを学ぶ大学生の「紀久」と「与紀子」、そして、鍼灸の勉強のため日本に来ている「マーガレット」の四人の女の子たちが、心を持つ不思議な人形「りかさん」とともに共同生活を始める。 蓉子の亡くなった祖母が住んでいた、冷房も網戸もない古い日本家屋で、彼女たちは自然の営みとともに生活する。 庭を造り、草花を食し、糸を染め、機を織る。 「結界が張られているような家」と神崎に言わしめた、世の中の変化の外の、何かに守られているかのようなこの家で、過去の小さな出来事の一つ一つが布を織り上げるように繋がっていく。 その繋がり方がまたすごいのなんのって。 ややこしすぎてとても書けないけれど、まさに宿世の縁、定められた運命、断ち切れない何か。 りかさんを中心にして、蓉子も紀久も与紀子も、本人たちの与り知らぬ地下水脈のような歴史の深みで、実は繋がっていたのだった。 彼女らの合作が火事で燃え上がった時、定められていた運命とでもいうべき一つの作品が完成するのだが、その場面は凄まじい。 梨木さんは、“人間の業”を描くのがうまい人だと思う。 普段は隠れている人の醜い部分を、決してごまかさずストレートに描く。 時々目をそむけたくなるほどリアルに、心の闇を描き出す。 マーガレットと神崎の関係を知った紀久が、蓉子に黒を染めてもらう場面は怖かった。 草木に悲鳴を上げさせてまで色を出したくない、と普段、自然の媒染剤しか使わない蓉子に、紀久は、劇薬の「重クロム酸カリ」を使って黒を出してほしいと言うのだ。 その、心の闇を染め出したかのような黒糸は、紀久の織る紬の一部となり、そして一枚の布になっていく。 すべてのものは、一枚の織物のように永遠に繋がる連続模様であり、人はその中を生きている。 何かすごい物語だったな。 横に広いというよりは、下に深いという感じ。 ただ、神崎さんのやりたかったことが、あそこで終わってしまうのはもったいない気がした。 蓉子、紀久、与紀子と竹田君は魅力的に描かれているんだけど、神崎とマーガレットのキャラクターが少し薄い気がしたな。 神崎はトルコから、クルド人たちのことを日本にいる彼女らに伝えたのだし、マーガレットは、子供を産むことで破壊の後の再生の役割を担ったのだから、役割は十分に果たしているのに、肝心の人物像がうまく結べなくて、そのあたりがちょっと残念だった。 ところで、人形の着物の柄の「斧(ヨキ)と琴と菊」が、「ヨキコトキク」だということに、読み終わってしばらく時間がたってから気付いた! へーそういうことなのか。 なぜ作者は、作中人物にそのことについて一言も語らせていないんだろう。 言っちゃえばただの言葉遊びで終わってしまうからかな。 まあ、りかさんがいることによって、何が起きても不思議ではない世界が現実にそこにあるわけで、例えばテーブルの上の唐草模様とか、マーガレットの倒れた音が二回したとか、その時には気付かないおかしなことが、後から見えてきたり、きっとこれもそういうことの一つなのだろう。 「りかさん」という作品があるらしい。 読んでみよう!
1投稿日: 2022.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
りかさん、の主人公のようこが大人になった蓉子としての新たな物語。 祖母が亡くなって、かつて祖母が住んでいた家を下宿にすることになり集まった若い女性たち。 孫の蓉子は染色、アメリカ人のマーガレットは鍼灸師を目指し、紀久は機を織り、与希子は機と図案の研究。 4人とも手仕事を共通にしながらの共同生活。 蓉子の大切な市松人形のりかさんは 祖母の喪にふしたまま、ひっそりとしたままだった。 4人で協力しながらの生活 紀久の故郷で墓の中から見つかったりかさんそっくりの人形。 それを辿っていく中でわかる与希子の家系と遠い親戚だったという事実。 紀久が必死に書いた機織りの原稿を大学教授に横取りされそうになる騒動。 マーガレットが身籠った子供、その相手の神崎が滞在しているトルコ、クルド人のこと。 4人の手仕事が集結した作品をお披露目した日。 与希子の余命僅かの父のタバコの火によって燃えていったりかさんの最後。 書ききれないほどの話の内容の濃厚さ。 りかさんの最後、ありがとうだ。
1投稿日: 2022.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの本はどれも好きなのだが今回は情報量が多すぎて疲れてしまった。また少し時間を置いて再読したい本。
1投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生で読んだ際は、自分の好きなワードがたくさんあるはずなのに、どうしてか内容が頭に入らずもやもやしていました。 再読してみて、紀久の心情を通し物語にすんなり入り込めるようになっていました。 物語がゆったりと進行しているので、一読してから長い時間を置いてみて、また読んだのが良かったのかもしれません。自分の中で上手く消化できた気がします。 古民家、人形、染織といった日本的なワードが散りばめられていますが、マーガレットの存在や中近東の話題、クルドのことが違和感なく語られていて、織物の縦糸と横糸を丹念に編んでいくような小説です。
1投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ同居する四人の女性と人形のりかさん。染色と機織りの話や人形師の話やクルドの話まで絡んできて読むのに疲れた。
1投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人形りかさん 三人の下宿人と祖母から家を引き継いだ女性 それぞれが染織などに打ち込んでる 古い因縁話 たてにも横にも拡がってしまった物語
3投稿日: 2021.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい梨木さんの世界。 「りかさん」という本の続編だと、読み終わってから知りました。 祖母の遺した家に住む蓉子とアメリカから日本の鍼灸の勉強をし蓉子とランゲージエクスチェンジをしているマーガレット、機織りをする紀久、テキスタイルの図案を研究している与希子の4人の女性の共同生活。 草木染め、機織り、紬、能面、人形と日本の伝統文化とクルド人の背景も交えながら生きることの意義を教えてくれる。 これも大切にしたい一冊になりました。 手元に置いていて何度も読み返したい一冊です。
68投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常のことなのに、不思議な世界観を纏っているように感じる。 出てくるものが、少しずつ近づき繋がっていく。 日々の変化や、知ることが辛いこともあるけれど、乗り越えると違うものを得たりできるというようなことをなんとなく読んでて感じた。、
2投稿日: 2020.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログふしぎな物語だ。時間が止まったような一軒家で共同生活を始めた若い女たち。容子は染色、紀久は日本の紬織り、与希子はキリム織と、それぞれが伝統的な手仕事に打ち込んでいる。 それに鍼灸を学ぶマーガレットを加えて4人、と言いたいところだけれど、この家には実はもうひとりいる。それが、容子が祖母から受け継いだ人形の「りかさん」だ。容子が子どものころから会話を交わしてきた「りかさん」は、いろんな女の子たちとともに長い時間を過ごしてきた記憶と知恵をたくわえているようだけれど、容子の祖母が死んだ時から、その魂はどこかへ出かけているらしい。 つまり、この若い娘たちは、気が遠くなるほど多くの、ひとりひとりの名前を超えた何かを織り続けてきた女たちの営みを、自ら引き継ぐ者たちであるわけだ。さらに、紀久の祖母の墓の中から、「りかさん」にそっくりな人形が現れるあたりから、彼女たちが受け継ぐ歴史は、まさに蔦のつるのように、互いにいっそう複雑に絡み合うようになる。どうも、江戸時代に「りかさん」を作った非業の人形師とその周辺の人々は、彼女たちの親戚関係の中で、みなつながっているようなのだ。 これがふつうの小説ならば、過去の数奇な因縁によって結びつけられた現代の女たちは最後に真相を知ることで、すっきりとした近代的個人に立ち戻るところだけれど、もちろん梨木香歩の小説だから、そんなことにはならない。人形師の打った面が引き起こしたとされる大名屋敷内で起きた陰惨な事件に端を発する因縁で結ばれたつながり、さらには、彼女たちの周辺にいる男をめぐるつながり、そうした、個人の意思を超えたつながりによって結びつけられている関係を、彼女たちは厭うどころかむしろ積極的に確認するようなそぶりで、共同制作へと進んでいくことになる。 「生き物のすることは、変容すること、それしかないのです。…追い詰められて、切羽詰まって、もう後には変容することしか残されていない」。 手仕事からしだいに遠ざかって、自分を超える大きな流れが見えなくなってきているわたしたちのために、蔦唐草の模様の中に織り込まれてきた智慧を差し出してくれる作品だ。個人とは、わたしひとりのぶんだけではないということ。つないでいくためには、変らなくてはならないという智慧を。
4投稿日: 2020.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
10代、20代のころにこの本を読んでもおそらくあまり響いてこなかっただろう。確かに毎日を生きることは機織りのようであり、ふりかえってみると人生はその織物のようだ。 変化はしんどいものであり、代償を払うものなのだと筆者は書いているが、織物から人形そして家が炎に包まれた瞬間、悲劇的な場面をそれは美しい情景として描かれているのが印象的。 そうか。人の死も同じなのかもしれないと感じた。
1投稿日: 2020.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ何冊か彼女の長編小説を読んでいるが、いつもその重層的な構造に、もしくはその絡まり合う要素にいつも目眩がする。考えてみれば、初めて読んだ「ピスタチオ」からしてそうだったのだが、その後の「沼地のある森を抜けて」など、複数の作品に共通している。そして、あえて共通項を探せば、女性、手仕事、自然、時代ということになるのだろうか。 そして、最後にカタルシスを伴うような圧倒的な事象が起こることも共通か。 などと分析されることを望んではいないのだろうが・・・
2投稿日: 2020.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ登場人物たちの大切にしているものが、興味のない分野過ぎて読むのにたいへん時間がかかってしまいました。 手仕事が主であった昔の方が、物事に対して非科学的な解釈をしたり、そういう感覚を常に持っていたのかなと思いました。 そういう言葉に表しづらい感覚を見事に文章で表現されていると思います。 りかさん は不思議と楽しく読めました。 ただこれは、長いです。壮大ですし。好きな人は好きだと思います。
2投稿日: 2020.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不思議な作品 ファンタジー要素が混じりつつも、日常を描いてるような それがだんだんひとつの事件(?)を追究していくことになっていく おつたさんとか赤光たちと、与希子とか紀久たちの関係性が混乱してきたので、もう一度読み直しておきたい 文庫本の解説に、国内と国外を分けてみている作品というような話があったんだけど、実際4人で暮らしているのにマーガレットの存在だけ異質である点もおもしろい 「りかさん」という本も出していることを知ったので、あとから読んでみたいです
1投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
同じく梨木さんの「春になったら苺を摘みに」の次くらいに思い入れの深い小説。 小学生の時に図書館で借りたハードカバー版で読んだのが最初だったんだけど、その解説に子供には分からない話、みたいなことが書いてあってすごくムカッとしたのを覚えてる。その時の私なりに感じることもたくさんあったし、でも図星であることもなんとなく分かっていた(笑)。その後年を重ねながら何度も読み返して、そのたびに新しいことを考えた。今回もまた、今自分の抱えている問題に先回りされていたような部分があって、かなわないなあという気持ち。 受け継がれるもの、伝えていくもの。その中で否応なく変容を迫られる、その瞬間のエネルギー。植物との丁寧な暮らしも含めて梨木さんの思いのたけがぎゅうぎゅうに詰まっている、と感じる。 紀久の帰還のお祝いの時の彼女たちそれぞれの微妙な心の機微、その空気の中でマーガレットがマーガレットらしくなる瞬間、そういう柔らかく繊細な描写が好き。でもこれは優しい小説ではなくて、同時にたくさんの女たちの「誰にも言えない、口に出していったら、世界を破滅させてしまうような、マグマのような思い」を内包してもいる。 それらが絡み、業火の溶鉱炉と水脈とでつながり、伝わり、大きな一枚の織物になり、続いていく。 私が一番近く感じてしまうのはマーガレットで、ジェリーとピーナッツバターのサンドウィッチのエピソードは彼女の気持ちに自分の中にも心当たりがあって子供の頃から読んでいて胸が苦しかった。 あらかじめ欠けているもの、受け継いでいないものを一生追い求めないといけないということの苦しさ。それをいとも簡単にやってのける人を目の当たりにした時の焦燥、悲しみ。 子どもを産んで、一層そういう事が浮き彫りになっていく中で「淵」を歩いて、生きて、つなげていかなくてはならないマーガレット。 「断ち切れないわずらわしさごと永遠に伸びていこうとするエネルギー。それは彼らの願いや祈りや思いそのものだったんだ。自分の与り知らぬ遠い昔から絡みついてくる蔦のようなものへの嫌悪といとおしさ。」 「呪いであると同時に祈り。憎悪と同じぐらい深い慈愛。怨念と祝福。同じ深さの思い。媒染次第で変わっていく色。経糸。緯糸。リバーシブルの布。一枚の布。一つの世界。私たちの世界。」 呪いのように身に絡みつく因縁も、怒りも苦しみもすべて飲み込んで伸びていくエネルギーへの、生きていくことへの目の覚めるような賛歌。身を焼くような苦吟でさえ、祝福を同時に宿しえる、日常の中に織り込んでいくことができる。 変容を迫られながらも受け継いで伸びていくことをやめられない、そうしかできない私たち。 大好きな小説です。
6投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ祖母の残した古い家が痛まないようにと、20代の女4人と 人形のりかさんが共同生活を始める。 決して楽しいだけの繋がりではなく、それぞれの 心模様にも激しい葛藤を与えながら、また、親戚や 先祖達まで繋がっていく。 今を生きながら、遠い昔を覗き見る。 緩やかに頑なに脈々と繋がる蔦のような物語。 梨木さんの作品は何作か読んではいるけれど こんなに激しい執念や感情は初めてでした。 優しいだけの作品と思って読むと、苦しいかもしれない。 「りかさん」→本作→りかさんに収録されているミケルの庭を読むといいかも。
1投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログりかさんのその後のお話。りかさんの持ち主、容子は亡き祖母の古い家で女性4人の共同生活を始める。染物、織物、西洋のキリム等が織りなす穏やかな日々。赤の他人のはずが、人形を通じてつながりがあることがわかっていき。 かなり深い話なんだと思う。ただ、私にはちょっと難しかった。家系図が複雑すぎて一度読んだだけでは理解ができない。正直、なかなかページが進みませんでした。頑張って読み終えた感じ。もう一度読んだら理解できるかもしれないけど、ちょっと疲れっちゃっいました。 「りかさん」の方が好きだったな。
1投稿日: 2019.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログあんまり面白いと思わんかった、自分には難しすぎたのかも、、専門用語とか難しい言葉が多すぎたのと、家系図が複雑すぎて理解が追いつかんかった。 でも、共同生活をしていくことで絆が生まれていくのは分かった。人は蔦みたいに繋がっていくことが言いたかったこと(???)
1投稿日: 2019.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。の、はずなんだけど、初めて読むような気持ち。 『りかさん』とつながる、というか『りかさん』の完結編というか。 現実的な部分と非常に不可思議な部分が融合して、なんだか酔いそう…。
1投稿日: 2019.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ『りかさん』の主人公「ようこ」が大人になり、「蓉子」として描かれていた。小さい頃から好きだった染物を続けていたり、人を慈しみ包み込むような暖かさが、「ようこ」だと分かる要素だった。 『りかさん』はようことりかさんの物語で、最後にマーガレットの娘と三人の共同生活が描かれていましたが、読んだ時点ではなんで共同生活なんて送ってるんだろう、なんでこんなややこしい関係なんだろうと思っていたことがやっと繋がりました。 『からくりからくさ』ではたくさんの植物の名前が出てきて、スマホを片手に調べながらじゃないとなかなか情景が浮かばなくて大変でした。 「色は移ろうものよ。花の色は移りにけりな、いたずらに、ってらいうじゃない。変わっていくことが色の本質であり、本質とは色である」 この与希子の言葉は花と染色の関係だけではなくて、人間関係や人の心情も表してるんじゃないかなぁとも思いました。四人の共同生活の中でそれぞれに抱える問題があって、でもそれが関わりあうことによってまた違う色が出てくるような…。 この本は情報量が多かったけど、その分考えることも多くて、特に龍神と蛇の関係は私が大学時代に研究したことにも通ずるところがあったので面白かったです。 能の講義も受けていたので能面に関しての話もすごく興味深かった。 作家さんってすごいなぁと思ってしまう。 知識もたくさんあるし、それを物語に取り入れてより内容の濃いものにできるからすごい。 何回読んでも飽きなさそうだし、読むたびに新しい気づきがでてきそう。
4投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんシリーズ。 染色や織物の世界を通して、唐草模様のように連綿と受け継がれ、伝えられてきた、女達の抑鬱と幸福を描く。 染色、機織り、パターン作家、中東にルーツを持つ外国人鍼灸師の4人の若い女性と、1体の人形の共同生活。「おばあちゃん」が住んでいた一軒家を下宿にすることになり、たまたまそこに集まった4人は、実は数奇な運命の糸で結び合わされていた・・・。 オレが読むとどことなし女女(おんなおんな)していて生々しく感じるけど、静かな中にも存在の切実さというか生の迫力というかがすごく迫ってくる。凄いお話だと思う。 能面の「般若」は知っていたけど、このお話に出て来る「生成」「真蛇」というのを先に見ておいたらもっと面白いかも。
1投稿日: 2019.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
亡き祖母の家に女性4人と人形の「りかさん」が共同生活することになる。 初めはりかさんの存在に戸惑うが、徐々に家の中心的存在となっていく。 庭に茂る草花を調理したり、草花で糸を染めたり機を織ったりと手仕事を丁寧にしながら心穏やかに暮らす4人。 世間離しているかに思えた4人も、いつしか各々の問題にもがいていく。 正直、私は人形が苦手…。 でもこの4人にとってのりかさんは「物」ではなく「人」なんだろうな。 様々な経験を経て成長する4人は、りかさんの不思議なエネルギーに守られ絆を深め、各々の世界から踏み出せたように思う。
3投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。染や織や紋様といった魅力的な世界の描写に絡めて、生と死、愛情と憎悪、連続と変化といった相反するものが混じり合ったり混じり合わなかったりして流れていく、美しい世界。梨木さんの小説を読むたびに、こんな世界に身を置いて生きていきたいと思ってしまう。
1投稿日: 2019.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ管理人を兼ねる染色の外弟子をしている蓉子、鍼灸の勉強のために日本に来ているマーガレット、美大で紬を専門に織物をする紀久、同じく美大で中近東の遊牧民が織るキリムを追う与希子 の、女四人と不思議な日本人形「りかさん」の過ごした季節を描く物語。 今だったら「シェアハウス」って言っちゃうんだけど、平成十四年の作品らしく。 物語の軸とはずれてしまうけど、「メールしたらいいのに」とかおもってしまったり、今ならすぐスマホで調べたり写真撮るよな、ってシーンがちょこちょこありました。 そうやって、失われてしまった情緒みたいなものが、たっぷり描かれた作品ともいえるかもです。
2投稿日: 2018.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い家に肩寄せ合って暮らす女が4人。ただそれだけでも神秘的なのに、4人には共通点がある。手仕事。手で仕事をすること。気の遠くなるような仕事を。現代では、むしろ廃れていく仕事でありながら、私はこういった仕事に惹かれてやまない。草木染めをしている蓉子。キリムの図案にはまり、自分で織りもする与希子。紬を織り、全国の織り子たちの話をまとめる紀久。外国から来て、鍼灸大学に通うマーガレット。「ヨキ コト キク」のキーワードにつながる名前を持った4人。そして、彼女らと一緒に住まうもう一人「りかさん」。人形だけれど、それだけではない。彼女らを結びつける糸、その象徴。りかさんを中心にして、数えきれないほどの伏線が張られ、恋愛、妊娠の話もあるのに、不思議と生臭くなく、しかし女性の感情を余すところなく伝える部分は、すごみを持って迫ってきた。物語がクライマックスに達したとき、言いようもない感情に襲われた。快感、やるせなさ、せつなさ……。その感情の行く末は、読んだ本人に任せられている。静かに澄んだ湖面を見るような、久しぶりに、幾度も読み返してみたいと感じた作品だった。
1投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ適度に手が入った自然に囲まれた家屋に集った4人の若い女性の田舎暮らしの話と思いきや、家つきの人形が4人を呼び寄せ、4人の結びつきを明らかにし、自分を作った人のもとに帰っていく物語だった。 なぜこの4人が不便な家に集まって生活を共にしようと思ったのか、しっくりしなかったのだが、”りかさん”が呼び寄せたのだと考えると、納得できる。
1投稿日: 2018.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梨木果歩の有名どころを今更読んでみた。 前半は「西の魔女…」等、俺の思ってた梨木作品感があって、「うんうん、これこれ」と思ってページを繰って行ったのだが…なんだか、話がこみいってくる。 女4人のシェアハウス生活、それぞれの想いや生き方が折り重なって、丁寧なタペストリーを編み込んで行く。そのパターンや模様を眺めつつ「人間関係って運命て縦糸と横糸を紡いでできる大きなテキスタイルやな」…とかそういう読後感で締めくくられるものと思い、その体で読み進めると、エラいことになる。 この話は、そんなもんじゃない。読み進めて行くうちに、そんな安易な読書感想文で先生に及第点もらえるような感想で済む話じゃない。上っ面の手作り大好きとか森ガールとかそういうもんとラップさせてた俺が悪い。もっと心の深層えぐってくるよ、この話。 後半クライマックスにドキドキする、こんなことするんや。芸術に溺れたヤツとか、権威に淫したヤツはどうしようもない。そのどうしようもないヤツが作品の仕上げをやってしまう理不尽。 主要登場人物たち以外の個性が分かりづらく、途中で見分けがつかなくなったり、あちこちに飛ぶ話に疲れてしまったり、荒削りな部分は否めないが、生きていくことの土着的な力強さを感じる作品。なるほど「ヨキコトキク」か…。
2投稿日: 2018.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年2月9日~10日。 時間と空間。 まさに織物のように経糸と緯糸が交差している。 唐草の概念は連続すること。 連続模様のパターンが変わるとき……火事と完成。 生と死。 火と水。 炎の中のりかさん、水の中のりかさん。 天と地。 憎悪と慈愛。 永遠に交わらないもの。 すべては繋がっている。 読み終わってすぐに感嘆の声をあげたのは、いつ以来だろう。 最初はこれを読み終わってすぐ「ミケルの庭」を読み返そうとした。 でもやめた。 しばらくはこの余韻に浸っていたい。 他の方がこの作品をどう受け止めようと知ったことではない。 物凄い作品。
1投稿日: 2018.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮大なテーマ、家守綺譚シリーズや裏庭や西の魔女にも通底する壮大なテーマがより具体的に顕現したような作品でした。 ハシヒメやミズグモなど裏庭と共通するモチーフもでてきてそういうところも楽しく読めます。 作者の膨大な、多岐にわたる「伝えたいテーマ」が凝縮されていて読み応えがあります。 何度も読み返したくなる本がまた増えました。
1投稿日: 2017.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ素敵な作品。最初の方は「西の魔女」のような読みやすさよりは、「家守綺譚」のような古風な印象を受けましたが、半分過ぎからは一気に読みたくなるような展開で惹きつけられました。込み入った舞台や背景の設定が少し混乱させられましたが、「裏庭」や「西の魔女」に通じる喪失と獲得の物語で、読み終わった後の余韻は素敵です。
3投稿日: 2017.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自然と触れ合う手仕事が素敵な生活を作る。 その描写と並行して、みなの先祖の来歴がミステリ式に明かされていく。 その中心にはりかさんの存在がある。 機織りに、名もなき女性が支配されながらも続けてきた営みを見たり、 愛着と恨みは同根だと気づいたり、 祝福と同時に呪いでもあるという真実に逢着したり、 東でも西でもない人類の根に思いを馳せたりと、 とにかく視座が広い。さすがユング。 (そのため妙に説明的……なのは仕方ないのかも。「村田エフェンディ」や「f植物園」の簡素な文体のほうが個人的には好きだけど)
1投稿日: 2017.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
りかさんの主人公、蓉子のその後のお話。 登美子ちゃんとの再会が嬉しかった。 正直なところ、紀久さんと与希子さんがごっちゃになってしまって話が度々よくわからなくなってしまった。 もう一度読んでまたりかさんを読み直そう。
1投稿日: 2016.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度となく読んでいる本。 蓉子のつくる暮らしの基盤や家に流れる包み込むような空気に触れると丁寧に暮らしていくことへの憧れが強くなる。 1番共感したのは紀久。 それまで自然の作り出したものを受け入れ好んできた作り手たちだったのだけど、どうしても自然からは出来上がらない底の見えない黒を必要とする様はここのところ経験した黒い闇にとても似通っていた。 人が生きていくということは綺麗なだけでは済まされないことがあり、それでも何世代も後に消化してしまえる強さが人にはあるのだなぁ。 梨木香歩さんの小説は始まりから全てが繋がっていて、それは物語が始まる前からずっとずっと繋がっているというテーマでもあると感じる。 紡いでいくということ。 そして暮らしの丁寧さや言葉、自然の描写の美しさにたまらなく惹かれるのでした。 うう、レビューは苦手だけど頑張ろうw
2投稿日: 2016.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ草木を集めて染料にしては糸を染め、作品を織り上げる・・・ 自然を身近に感じる生活。 純粋に憧れます。
1投稿日: 2016.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性4人の共同生活と聞くともっとドロドロしたものを想像するけれど、確かにドロドロしそうな部分もあるんだけれども何となくカラッとして終わってしまう。それは登場人物それぞれが、個人の事情や恨みつらみよりももっと大きな、人が延々と営んできた生活の連なりの方に興味の対象をもっていってしまっているから。だから何となくみんな目の前のことには無頓着というかぼんやりしているというか 女性というのは(自分も含めて)えてして目先のことに囚われすぎなところがあるので、そのくらいの方がちょうどいいかもしれない。
2投稿日: 2016.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログどうやら梨木さんはかなり私の好みらしい。 「西の魔女~」の作家さんだから、それも当然だけど。 もう少し児童文学風の作風なのかと思っていたら、全然違った。 途中、誰のおばあちゃんとだれのおばあちゃんがどうなって、おばちゃんがどうなるのかこんがらがったので、もう一度読んでよく整理したい。 でも、こんな共同生活いいなぁ。
1投稿日: 2016.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者さんが草木染めをするようになるノンフィクションの本を前に読んで、またこの本でも草木染めのことがあるので興味がわきました。 まだ読み始めたばかりです。 また読了してから追記します。 追記:「りかさん」は未読です。 最初ほんわか優しい雰囲気が、途中から暗雲たちこめる感じになり、最後は壮絶な芸術となり、次へつなぐ。 そんな風に感じました。 「完全な闇が欲しいのだ」というところは、本当に怖かった。 紀久とマーガレットがお蔦騒動と同じ結果になるのではと恐ろしくなった。 そして、生理的に受け入れられないことをやるしかない辛さや、「内側から衝動のように出てくる義務感」によりやりたくないけどやりたいとなる複雑さ。 全員に感情移入して、読み進める気持ちが重かった。 女の人の強さだけでなく、弱さも醜さも、優しく包み込むようなお話でした。 ただ、赤ちゃんの精神は、胎外へ出る瞬間ではなく、受精の瞬間でもなく、もっと太古の幻想的かつ神秘的なところで誕生していると私は思っているので、この作品に限らず、生まれ変わり的な考えはなかなか受け入れがたいところもあります。 神崎の手紙の内容も、織物を学ぶ人たちに向けたものとしては必然なのかもしれないが全く知識のない私には難しくて、流し読みしてしまった。 それでもいいのかもしれないけれど。 みなさんのレビュー見て: 与希子と紀久 斧琴菊 !! わぁ、変わった名前だと思ってたけど、そういうことだったのかぁ~
1投稿日: 2016.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「りかさん」の続編、と言っても、単なる話の続きではない。 ようこが「蓉子」に成長して、紀久、与希子、マーガレットの三人の女性たちとの暮らしを通し、深みを増していく。 物語も、それぞれの人物の過去や祖先の時代まで遡り、今と思いがけない結びつきを露にする。 マーガレットやクルディスタンで行方不明になっていく神崎の存在のために、東西の往還も含まれる。 複雑で、いろいろなものが混然一体となって、それでもひとつの統一体として、この物語は立ち上がってくる。 その厚みに圧倒される。 この物語ではもう死んでしまっているおばあさん。 蓉子に残した、手を洗った後、しっかり水気を拭き取ればあかぎれなんかにならない、という教え。 これを今私も実践中。 これがなかなかいい調子なのだ。 すごい。
1投稿日: 2016.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ心の奥深いところ、本質を書いたんだと思う。少し難しかったけど、読みやすくはあった。言葉では言い表せないような、壮大な話だった。 何年後かにもう一度読んでみたいと思う。
1投稿日: 2016.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
お話はあちこちに広がり、絡み合い、複雑な紋様を織りなしていく……。 けど、結局何が言いたいのかわからない作品でした。 女の内面や嫉妬、それに人形や能のお面はやっぱり怖いな、という感想です。 読んだ後に知ったけど、前作として「りかさん」、続編として「ミケルの庭」という短編があるらしいですね。図書館にないので私は読めませんが、この三部作をきちんと順番に読んだら、また違うものが見えてくるのかもしれません。
1投稿日: 2016.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性3人が古い家で暮らす。たまには波風も立つが穏やかな暮らし。そんな本かと思っていたが、なかなか難しい。
1投稿日: 2015.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性4人の共同生活。 庭の草を使って草木染めをする人がいて、その糸で機を織る人がいて。テキスタイルを考える人がいて。庭の野草や野菜で慎ましい食事をして、生きる。 共同生活も、こうした自立した人々との生活ならば、楽しいかもしれない。依存はしないが、影響を受け合う存在。 その根底には、りかさんがいて、りかさんからすべてのものを慈しむ気持ちを育んだ蓉子がいる。その精神を見習いたい。 博学で、それでいてそれをひけらかさずにじっと見つめる、梨木香歩さんの眼差しを感じられる作品。 ――――――――――― 女たちは機を織る。 反物という一つの作品に並行して、彼女たちは自分の思いのたけも織り上げていった。 古今東西、機の織り手がほとんど女だというのには、それが適性であった以前に、女にはそういう営みが必要だったからなのではないか。 誰にも言えない、口に出していったら、世界を破滅させてしまうような、マグマのような思いを、とんとんからり、となだめなだめ、静かな日常を紡いでいくような、そういう営みが。 p.95
1投稿日: 2015.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこういった丁寧さの中から美しさは生まれると思う。 登場人物とか背景にある人形の歴史とかに関する記述は名前がぐちゃぐちゃになってしまって読みづらかった。
1投稿日: 2015.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み返し。 やっと児童文学以外も読むようになった頃に読んだためか、頭に刻み込まれてる作品なのですが、今、出版された月をみると、りかさんとの差が7か月しかないことに驚く。もっと経っていると思ってました。 うーん、真剣に読んでた時期だったんだなぁ。
1投稿日: 2015.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作『りかさん』に続く、お話。主人公の蓉子は、高校を卒業した後、染色家の道に。亡くなった祖母宅で、女ばかり4人の共同生活が始まる。りかさんは、祖母を見送りに行ったのか、不在。主に共同生活を送る4人とそれを取り巻く家族や友人、そして日々の出来事や心情の変化が主たるストーリー。りかさんを作成した人形作家や生い立ちなども、少しずつ明らかになってくるが、当のりかさんは、ほとんど登場しない。そして、結末は・・・・。 個人的な感想としては、前作『りかさん』ほどのインパクトはなく、なかなか読み進まなかった。
1投稿日: 2015.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「生きて命があるって、異常事態なのよねぇ」 『誰にも言えない、口に出していったら、世界を破滅させてしまうような、マグマのような思いを、とんとんからり、となだめなだめ、静かな日常を紡いでいくような、そういう営みが。私の曾祖母も機を織ることを知っていたら、少しは楽だったかもしれません。』 「もしかすると家の中の全員他人の方が理想的な家族ができるのかもしれない」 内容も勿論好きなんですが、文字を辿っていって気分が良くなる本でした。
1投稿日: 2015.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初は、『女四人がレトロ感溢れる家屋で共同生活』で、爽やかそうな話だと思っていたのだが。 ページをめくるごとに、段々ドロドロとしていき……。 というか、あれですよね。やり逃げ……?
1投稿日: 2015.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれを読んでから機織も草木染もやりたくなってしまって。 ものづくりする人間の創作意欲を爆発させます。 穏やかな語り口。嘘の無い表現。そこからは考えられない意志の強さ。 梨木香歩さん、ほかも読みたいです。
1投稿日: 2015.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ5年以上ぶりに再読了。以前はよく分からなかったところも少しは理解しやすくなった気がする。草木染めと能という、この小説の中の重要な二つの要素に、私自身が興味を持ち続けてきたことも興味深い。何度でも読み返したい作品。
1投稿日: 2015.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ『りかさん』から数年経て、主人公の蓉子は染色を仕事にするようになっていた。祖母が遺した家で3人の下宿人を置き、共に暮らすこととなる。 鍼灸を学ぶためにアメリカからやってきたマーガレット。美大の学生で、機織りをしている紀久とテキスタイルを研究している与希子。 4人の共同生活の日常と人間関係の機微を梨木さんらしい筆致で描いていく。 この作品の発表の方が『りかさん』よりも先なので、こちらから読んだ方がよかったのだと思う。というのは、『りかさん』に収録されている『ミケルの庭』が本作の数年後を描いており、私には状況がわかりにくいところがあった。ようやく今になって、背景はこうだったのかとつながった気がする。後で読み返しておこうと思います。 それにしても、梨木さんの書く小説は、登場する人たちの配置が絶妙だといつも思う。何らかの弱さや苦しみ、傷ついた過去を抱え、自分を解放できないつらさを常に味わいながら生きていく人。人との距離感を上手にとれなくて迷っている人。自由で無邪気な子どもっぽいところが見え隠れする人。穏やかでありながら、しっかりとした芯を持ち、いろいろな困りごとも淡々と受け止められる不思議と頼りになる人。 どの人も決して一面的な良し悪しを切り口にすることはなく、弱さと強さを併せ持ち、互いを補いあうような関わりを見せている。 読んでいると、「誰にでも、あなたの中の良さを見つけ、大切にし必要としてくれる人が必ずいるのですよ。」と梨木さんが語りかけてくれているように感じられる。人や人に起こるすべてのことをあるがままに見つめて、そのまま肯定してくれる世界が広がっているように感じるから。 この作品の登場人物も、家族関係の中で感情のすれ違いを解決しないまま今日まで持ち越していたり、自分のありったけの時間と労力を費やして書き上げた研究成果に対して横槍を入れられたりする。自分の感情を持て余すことも。。読者が苦しさを共有し、一緒になって腹を立てることでしょう。 それでも、4人の女性たちは考え方の異なる仲間の存在に大いに影響を受けて、また自分自身で考えを整理しながら、道筋をつけていく様子が好ましい。 そして、りかさんに待ち受ける結末。 目の前で突然起こる出来事に読んでいる私も、もう今では会えない人に対して「ああ、こうすればよかった。こうしていたなら・・。」という抑え込んでいた気持ちがあったことを思い出した。 読んでいると 苦しいのになぜだか許されるような 哀しいことなのになぜだかいつか癒えると思えるような 辛いのは自分だけではないと思えるからなのか・・・。 もうしばらく梨木さんを追いかけていこうと思っている。
14投稿日: 2015.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
作者がユング、河合隼雄に影響を受けていると本で読んだ。竜の描き方がいい。ミケルの生まれた事情が分かった、りかさんに載っていた短編を読み返したい。
1投稿日: 2014.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ積読だったが、読みはじめた。 祖母の残した古家で「りかさん」と言う人形を中心に 娘4人が生活していく・・・ 私には何か苦手な内容かも。 悪い言い方かもしれないが ”だらだらして何か内容が はっきりしない” やっと半分まできた。 :::::: でも このゆっくりした状態を体感させているような気がする、少しスピードを落とすことを教えているのか。 能(歌舞伎なども)とはどのようなものだろう。 読み終わったフゥー。 最後は説法みたい・・・・。
1投稿日: 2014.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
そもそも女の人の共同生活がとても苦手で、あんまり入り込めなかった。内容もどろどろしていて、なんで一緒に暮らしているんだろうと思った。そのドロドロの犠牲になるのが小さなミゲルであるところが、また嫌な感じだった。 草木染や織物の描写はきれいだし、人形が燃えると場面はきれいな風景が脳裏をよぎったが、好きな小説ではなかった。
2投稿日: 2014.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログしれっとものすごくフェミニズムやった。さまざまな方向で。だからか分からんけれども、男性キャラが胡散臭くてどうにも好感持てんかったなあ。神崎あいつはいかん。 それにしてもこの人は季節感のある自然の情景の描き方が素敵よね。まだこれ読んだの3冊目やけども。 庭に季節の野草が生えたのを摘んで食べるとかもうね、あこがれよね!庭なら犬のおちっこも心配ないし。 ごちそうさまでした。
2投稿日: 2014.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ縦糸と横糸がまじりあってそれぞれの色を殺さずにまじりあう、っていうのを人生とかにも例えててそれがすごく説得力あった!本当に梨木さんは天才だなあすごい
1投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の無知さを感じます きれいな話ではないけど、深遠な話です 勉強したり、何かを作り出そうとする人は人より追い詰められて切羽詰まって日々を生きるときも必要なんだなと思いました
1投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
神崎からの手紙のくだりで私が感じたことを、この物語の中で唯一の第三者と言ってよい竹田が、終焉近くで言葉にしていて、好感を覚えた。 きっと一枚の織物なんだ。 それはあらゆる人と時空を覆い尽くすほどの織物だろう。 何のつながりもないはずの女性たち。彼女らは経糸。 連綿と受け継がれてゆくもの。それは旧き因習であれ民族の歴史であれ、異端のものに触れてしまえば、変わることを避けられない。それを頑なまでに拒み切れるか、折り合いをつけて変化に身を委ねつつも変わらぬ部分を遺してゆくのか。 そんな息が詰まるような瞬間を何度となく経験しながら、この世界を構成するあらゆる生命とモノたちが繰り返してきた、変わる時の苦闘、苦痛、苦悩。それが緯糸。 変化のたびに避けることができない代償を払いながらも、人も人形も、民族も遺跡もそのいのちを長らえてきたのだろう。 四人を繋いできたあらゆるものの焼失、そして一つ…いや、あるいは二つかもしれない生命の消失が、その凄絶な変化が、新しい生命の誕生に繋がってゆく。 必然…そうして宿縁。その場に居合わせた者たちの胸をよぎる、同じ思い。そのあとに訪れた穏やかな安らぎ。 織物は絵とは違い、用いた色が溶け合うことはない。それぞれがそのままに、しかし織りなされたものの醸された深みは底がない。 …なんという作品だろう。私は呑み込まれてしまった。もっと早くに読むべきだったと思う。 よき、こと、きく。りかさんとその姉妹人形に贈られた着物の紋様。この謎染は、犬神家の一族にも関わっていた。 良きこと聞く…という縁起を担いだだけではなく、未来への暗示。 与希子と紀久への祝福…か。 深い物語でした。憎しみや恨みと愛は、同じマグマから産まれる情念なんですね。
6投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのタイミングでこの本に出会った不思議 と、思いたくなる内容でした。 作品内の会話に出てくる 『偶然は偶然』『偶然は必然』なんてよくあるコピーみたいなことはない… そう、そんな陳腐な表現は嫌だけど そう言いたくなる繋がりがあるように思えてきた。 つながりについて、現れ方には、事例4つ挙げているようだ。 人は、今、現在も、過去も未来も一人では成り立つことはなく、 だからと、繋がらなくてはいけないのでもない。独りを見つ、なんとかしよう、その受け入れる力。 『でも傷を持たない人なんていないでしょう。問題のない人も少ないと思う』 『そうなんだけれど、彼と関わることになる人って、独特の暗さのある人たちなんだ、…』 何処かそんな一端を持つ4人の女性 それに、これまでの女性の社会的立場や土地とのつながり、芸術と職人技の境とつながり 名もないひとたちが作っている この今を生きる、生き方に それも良いでしょうと伝えているようだ。 後半、そしてラスト前は鳥肌のスピード感が また、前半の影から綺麗に光らせている
2投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ連綿と続く人の営みは、普段見えていないだけでいつでも存在し、紡がれているんだ、と空を仰ぎたくなった。 織られている時には、全容は分からない。今、ここ、は、いずれどんな模様になるのだろう。 自分に流れてる川を辿ったら、水脈までの道のりはどれほどのものなんだろう。 ぐるぐる頭の中にいろんなことが巡る。 しばらくの余韻を、蝉の声とともに過ごすことになりそう。
2投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作者さんの作品は、数年前に「西の魔女が死んだ」を読んだ時にリタイアしたのだけれど、この作品は染色や機織りといった興味のある分野を扱っていたので手にとってみた。 人形のりかさんをめぐる、ファンタジー要素を含むあれこれの部分はやはり少し苦手。 それでも、植物の描写が上手くて、浮世離れした生活も羨ましく、読み進めることができました。 浮世離れした生活の割には結構ドロドロした恋愛関係もありるが、さらっと解決するあたりもファンタジー。
1投稿日: 2014.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ祖母が亡くなった古い家で共同生活をする芸術家女性の4人と『りかさん』といぅ人形のお話し。 大きな事件が起こっている風でもないのに気付くと大きなコトで、運命ってこんな感じに回ってるのカナ?と思わせるお話しで好きでした。 彼女達の慎ましやかな、でも季節を感じて生きていくのにもとても共感と憧れを持てました。こぅいぅ風に優しく時間を生きていきたい。
1投稿日: 2014.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは...何というか....(^ ^; 本当に「分類不能」な本だなぁ...(^ ^; 主人公の亡くなった祖母の家で共同生活を営む 4人の「芸術家の卵」の女性たちと、 主人公が大切にしている人形のりかさん。 さらに彼女らの家族や師匠、ボーイフレンドなど、 登場人物の幅はそれほど広くはない。 舞台も、共同生活する旧家と庭を中心に、 それほど広くはない場所が中心。 それでいて、世界が、扮装が、国家が、民族が、という 人類共通の大きなおおきな問題を提起しているような。 また、どちらかと言うと「地味目な」主人公たちが 芸術とは、人の心とは、生きるとは、血とは...という 深く大きなテーマに絡め取られて行く。 りかさんにまつわる歴史と、血と、業と、呪いと... 思いもよらない繋がりと、祝福と... 複雑に絡まり合う人間関係と、 どうしても受け入れられないもの、 抗えずに受け入れざるを得ないもの、 運命とは、死とは、芸術とは、変革とは... 重く大きなテーマを読者に突き付け、問い、 この作品の中で「ある一つの結論」も出しつつ、 読者の心の内に想起させられる問題意識は、 読後もきっと色褪せることなく自問を強いてくる。 で、自分は... 最後のエピソードは、かなり強引な印象も受ける。 が、それを呆然と見つめるしかなく、かつ 不謹慎にも「美しい」と思ってしまう心情は、 私にも分かるような気がしなくもない。 具体的に考えると、いや、そこはまさか... となる部分もなくはない。 で、これからどうすんのよ、というのも 「放り投げて」終わっているし(^ ^; が、そんなことはどうでもよくて、というか この本の本質はそんなところにはなくて。 とにかく、読んで面白いことは面白いのですが、 テーマが重く、大きく、深く、さらに過去のしがらみや 人間関係が複雑に絡まり合っていて... 会社の行き帰りにちょこちょこ読んでいると 途中で話について行かれなくなる(^ ^; これはいつかもう一度じっくり読みたい本である(^ ^;
1投稿日: 2014.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
引用文に書いた言葉は、梨木果歩の作品全部に共通して言えることだと思う 「りかさん」で張った伏線を全部回収してくれて有り難いけど、銀じいは結局何者なのか分からなかったな りかさんのかよちゃん説はもっと掘り下げたかった 染め物やってみたい それにしても、りかさん行っちゃやだ!
1投稿日: 2014.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていたイメージとは違いましたが良かったです。 機織りをして暮らすというと穏やかで優しい感じがしますが、読んでみると儀式的で隙のない印象を受けました。 機織りや織物の歴史を理解しながら読むのはなかなか疲れましたが、読みきって良かったときっと思えるはずです。
2投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「りかさん」から十数年?後のお話。 というかこのお話があって、ようこのお話が描かれたのか。 順番を間違えたので、最初から寂しい始まり。 あのおばあちゃんが亡くなって、おばあちゃんのお家で共同生活を始めた、蓉子、与希子、紀久、マーガレット、そしてりかさん。 機織りの音、草木染めの煮出す匂い、庭の野草の調理など現代社会から隔離されたような生活。 沈黙するりかさんの謎とは。 マーガレットの率直さ、与希子の素直さにヒヤヒヤしたり、微笑ましく思ったり。 蓉子の無意識に物を慈しむ様子に嫉妬してしまう。 「慈しむってことは、思い立って学べるもんじゃない。受け継がれていく伝統だ。」 糠漬けもおいしくならない私の手。この台詞にドキリとする。 紀久の闇の深さ、蔦を全身に絡めるような様子が他人事に思えず、それを振り払うように機を織るという行為がうらやましい。 私の機織はなんだろう。雑巾縫い? 能面、お蔦伝説、唐草模様、蛇、水蜘蛛、クルド人。 蔦が絡み合うように、縦糸と横糸が絡むように話がすすんでいく。ルーツ、対立、対比、融合。 隔離されたような彼女達の生活が外の空気に触れるとき、少しづつ平穏な日々に亀裂が入る。 何時の間にかいろんなものが絡まって、身動きが取れなくなって息苦しいくらい。 最後はこれしかないのかもしれない、でもとげを強引に抜かれたような痛みが残る。 「残った部分は潰さないわ」という蓉子にホッとしたような痛々しいような。
12投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ関係性があまりに込み入っていて、紙に全部書き出して、なるほどと理解したけど、また忘れた。だから何度読んでも面白い。児童向け作品「りかさん」を先に読むことをお勧めします。
1投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログまったくの個人的なものだが、この手は苦手だ。 まず登場人物たちの浮世離れしたプチセレブな感覚。 興味をひかれない物語の中心部。 リアルではなく、かといってファンタジーに徹するでもなく、上品で優しく、軽くて。 私には無縁の美しい世界。 やれやれ、読み終えるのに努力が必要でした。ぽいっ。
3投稿日: 2014.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
祖母が残した家で4人の女性が共同生活をします。おもいがけない縁で結ばれていた4人の関係と、不思議な人形の里香ちゃんの存在がとても素敵です。
1投稿日: 2014.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
祖母が遺した古い家での、染色家の孫と二人の美大生、外国人の四人+「りかさん」という「人形」の同居生活を描く。自然の物を使った染色や機織り、龍・蛇・唐草といった東洋・西洋で普遍的に共通する模様の記号分析など、四人の生活は丁寧というか、浮世離れした雰囲気。途中からは「りかさん」がつなぐ宿縁も明らかになっていくなど謎解き的な面もあり、それがアクセントになっています。 私としては、これまであまり読んでこなかったタイプの作家さんですが、嫌いではないですね。他の作品も読んでみようかと思います。
0投稿日: 2014.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ手仕事感は、すばらしくさえわたっています。ただ、込み入り過ぎていて、一気に入り込んで読まないとわからなくなるかも…
1投稿日: 2013.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ魔女の次は意思のあるお人形か…と嫌な予感がしながら読み進めたけど途中で断念。西の魔女もこの本も雰囲気と文章の感じが私には合わなかった。梨木さんの本まとめ買いしてしまったのに。
1投稿日: 2013.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ祖母の遺した古い一軒家で共同生活を始めた4人の女性。 最初は、彼女達の持つ雰囲気や口調が あまりにも上品過ぎて、何だかこそばゆい感じがしました(笑) 今時こんな子達いないんじゃないかなぁ??…と。 でも読み進めていくうちに、あら不思議。 4人の適度な距離感やゆったりとした時間が心地良く感じてきます。 慌ただしい時代だからこそ、この本を読む意義があるのでしょう。 決して優しいだけの物語ではありません。 でも読んだ後には、しっとりとした温かさが残ります。素敵な本です。
1投稿日: 2013.12.01
