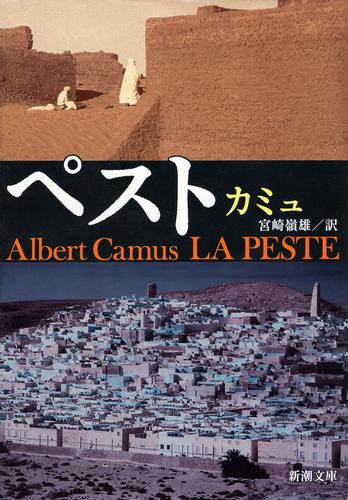
総合評価
(355件)| 86 | ||
| 104 | ||
| 90 | ||
| 21 | ||
| 4 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題は、法律によって規定されるソチが重要かどうかということじゃない。それが、市民の反芻が死滅させられることを防ぐために必要かどうかということです。 そいつは問題の設定が間違ってます。これは語彙の問題じゃないんです。時間の問題です。 命令なんて!それこそよっぽど頭を動かさなきゃならないときなんだが。 疫病はみんな一人一人の問題であり、一人ひとりが自分の義務を果たすべきであること。
2投稿日: 2020.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ人よりも小説好きと自任しているはずなのに、そもそもこれを未読で、新型コロナウィルスで俄かに注目を集めている状況で読むというのもなんだか気恥ずかしいが、実はこの一か月以上、大切に大切に読んでいた。 通読し、読み直し、登場人物別に思いを巡らせ、筋を書き出したり、人の感想を漁ったり。 また信州読書会の音声を聞きながらランニングしたり、NHKで再放送していた「100分de名著」を見たり、ブクログのタグ検索で小林秀雄や内田樹に手を伸ばしたり。 書き出した筋はネタバレなので非公開読書メモ行きにするが、作品全般について言えば。 ・キャラクター小説、というか、それぞれの人物設定が各々の思想性を代表している。 だからペストの推移よりも重要なのは、会話や議論の場面。ドストエフスキーに近い。 ・個人的にはグランにぐっとくる。というかグランのような人物が作中にいてくれて、よかった。 ・ペストに対する人の反応がリアル、というわけでは決していない。 むしろ対話が主眼の舞台劇を成り立たせるためのギミックでもある。 議論をするための思考実験とも。 ・不条理=「異邦人」と思いがちだが、むしろ「異邦人」はモラルの話であって、不条理度は「ペスト」の方が高い。 が、不条理な状況を描くというよりは、不条理下だからこそ際立つ実存、と重点を置きたい。 (カミュをキャッチフレーズ的に語るときには、不条理、実存、モラル、人間中心主義、抵抗、いろいろあるが。) 人はそもそも死の時限爆弾を内包した有限の存在なのだから、すでにペスト状態なのだ。あとは時間的に早まるかどうかというだけで。 最大の不条理=不条理を見据えて(死が運命づけられているからこそ)、それでも抵抗して生きる(を意識する)、そこに実存が生まれる、そのとき必要なのはモラルであり、そのような生き方をユマニスムという。 なんて図式化したら、間違いも生じるし、零れ落ちるものも多いが、まずはこういうざっくり理解で行きたい。 ・(科学力・人災は、コントロール可能……)戦争<ペスト・放射能<地震など天災(……自然はコントロール不可能。形がないので常に現在。不安は募り続ける) という構図も念頭に置くとよさそう。 ・またペスト=世界の否定性=自分の人生への疑念、と個人の生き方に引き付けてもいいし、ペスト=ファシズム=ナチスドイツと引き付けてもいい。このあたり、小説としての美味しさにもかかわる。どちらにしても、非現実的な災厄である・特殊な状況であると同時に、決してペストが去れば忘れ去ってもいいというわけではない。すでに生に内包された災厄であり、すでに自身に内包された暴力性である、と。こう考えれば村上春樹も連想できる。 ・「ダブル語り手」だが、リウー=見極めること=果てしなき敗北。タルー=記録し理解すること=倫理・行動様式。このふたりの関係性は一言でいえばエモい。 ・実は「異邦人」を読んだ高校生当時に手を伸ばして、挫折した経験あり。理由は悪い意味での翻訳調。今こそ光文社古典新訳文庫などでアップデートするべきだと思うが、宮崎嶺雄(1908-1980)の1950年翻訳をあえて擁護するなら、原文の生硬さをあえて移したものなの、かも、しれない。 ・数十年後に、あのとき大変だったなーみんな雰囲気おかしかったなーそんなときに座右にあったなーと懐かしく思い出したい。 連想を広げていく。 ・疫病文学……澁澤龍彦が構想していたのだとか。 ・オトン判事の息子フィリップの死を看取るあたり、「燃えあがる緑の木」のカジ少年の死を思い出す。。 そういえば初期大江健三郎の「芽むしり仔撃ち」も、疫病を恐れて村人が逃避した村に少年たちが居つくという話だった。 大江は自ら渡辺一夫に学ぶために大学に進んだというくらいでユマニスムから出発し、実存主義文学へ進んでサルトルに影響された(その後は構造主義へ?)だけあって、カミュの影響がないはずがない。 ・ガルシア=マルケスが、舞台をコロンビアに移して映画脚本を書いたものがあるらしい。YouTubeにも。「ペストの年」EL AÑO DE LA PESTE (Dir. Felipe Cazals, 1979) Gabriel García Márquez. Película completa ※小林秀雄『Xへの手紙・私小説論』新潮文庫に収められた「「ペスト」Ⅰ」「「ペスト」Ⅱ」はぴんと来ず。 ※内田樹『ためらいの倫理学 戦争・性・物語』角川文庫に収められた「ためらいの倫理学」のカミュ論。 01 「異邦人」とレジスタンス活動参加は同時期。「ときには、条件さえ整えば、私たちは人を殺すことができる」という「異邦人のモラル」がレジスタンスのイデオロギーと親和する(不条理よりもむしろ)。これが本稿で扱う第一。解放後、対独協力者の粛清を前に、立場を放棄し、減刑嘆願に同意する。「暴力は不可避であるということと、暴力は正当化できるということは違う」という「正義のためらい」が「ペスト」から「反抗的人間」に現れている、これが第二。 02 ムルソーは、戦うときは同じ条件という「ベルクールの男のモラル」つまり「暴力における平等性」「平等性のモラル」に忠実だったに過ぎない。平等性さえ確保されれば、暴力は免責される。みずら死のリスクを冒す用意のあるものには「人間を殺す権利がある」。 03 フランス人の意に反してドイツ人が始めた戦争。先に傷を負ったものは、加害者に対して等量の痛みを請求する権利がある。 04 しかしこの「異邦人のモラル」を、解放後、対独協力者の粛清裁判に直面したとき、カミュは助命嘆願書に署名することで、放棄する。 05 もとより戦争には「異邦人」の「判事」のような上位の裁定者は存在しない。また粛清裁判は、一対一の「決闘」ではなく、多数対一の「処刑」で「平等性のモラル」に馴染まない。粛清裁判に勅命することで、「異邦人のモラル」には脆弱性があると気づいたのだろう。 06 多くのフランス知識人は、報復の権利という平明なロジックによって、階級闘争・民族解放闘争に支持と連帯を表明した。その中で、ためらい、柔弱、疚しさ、のカミュのあいまいなスタンスは「中途半端」。二正面の敵……歴史の名で革命暴力を正当化するマルクス主義者、全的自由を要求するシュルレアリストやイワン・カラマーゾフ的なニヒリストたち……と戦った。暴力は不可避だが、正当化することはできない。「反抗的人間」の中で肯定的に書かれたのは、ローマ暴政に反逆した剣闘士指導者スパルタカス、19世紀ロシアの「心優しきテロリスト」たち。どちらも「異邦人のモラル」。 07 「異邦人のモラル」」を追認するだけでなく、「反抗」という倫理的契機を書き加えた。言葉の印象からロマン的な行動原理のように見えるが、むしろ柔弱な、優柔不断な、「何かをするため」ではなく「何かをしないため」に発動する内的な抵抗感。何かにいらだつ、なんdかいやな感じがしてたまらない、と。「私自身」が「正義のテロル」の執行者になりうる。暴力をなすとき「相手の顔」を見てしまう、そのときに感じる「動き」。相手の顔から感じる「殺すな」という訴えは、神の戒律ではないし、立法者の命令でもなく、内から湧く「ためらい」だ。ためらいが暴力を「限界づける」。現代において暴力を制御するのは、信仰でも階級社会廃絶でもなく、この「ためらい」を思想に高める理性の努力ではないか。 08 ムルソーは灼けた大気、影、汗でアラブ人の「顔」を見ていない。あるいはみずから目を閉じて「ためらい」を振り切る。 09 確かに「反抗的人間」は整合性に達していない。しかしこの「収まりの悪さ」が、絶えざる前言撤回による命題の揺らぎこそが、「反抗の倫理学」の本来的な語り口だ。これは思想書よりも小説で立体的に差し出せる、それが「ペスト」のタルーだ。「ペスト」とは外部から来る悪ではない。「私」の「外部」のあるものにすべての「悪」を凝縮させ、それと「戦う」主体として「私」という話型に取り憑かれることが「ペスト」の症状だ。「ペスト」とはエゴイズムの別名。生きているだけで、すでに他者に害をなしている可能性がある。人間が「より人間的になる」ためには、自らへの倫理的負荷を「他者よりも高く」設定する、それをタルーは「紳士」と呼ぶ。 10 タルーとムルソーという二人を同時に見つめることで、はじめて「反抗的人間」の立体的肖像が見える。一人では表現しえなかった。レジスタンス時代、カミュはムルソーのモラルに馴染んだ。しかし粛清のとき「カミュの中のムルソー」は「カミュの中のタルー」による異議申し立てにさらされた、分裂を生きる思想家。 また内田樹ブログに、 (以下引用) カミュの著作でもっとも評価されていないのは『反抗的人間』である。 これははっきり言ってタイトルの訳語が適切ではないせいもある。 Homme révolté は「反抗的人間」というようなわかりやすい存在ではない。 いちばん近い訳語を当てれば「むかついている男」である。 フランス語の動詞 se révolter には「反乱する、反抗する」という意味もあるけれど、「気分が悪い、むかむかする」という意味もある。そして、カミュがその著作で繰り返し言及したのはこの「なんだかわかんないけど気分が悪い」という心的状態の方なのである。 例えば、自分の掲げている政治理論が正しいと思っていて、相手に絶対的な非があると思っていても、「じゃあ、こいつ殺しちゃおう」という局面になると、「ちょっと待ってね」と腰が引けるということがある。 別に宗教的理由から「どのような極悪人にも慈悲をかけねばならない」と思っているからではない(それならすっきりしている)。 そうではなくて、たしかにすげー悪いやつで、いくら殺しても殺したりないくらい憎いのだけれど、でも殺せない・・・という「抵抗」が不意に訪れることがある。 カミュの言う「反抗的人間」は、この「抵抗」に直面して、どうしていいかわからないまま状況が切迫しているために決断せざるを得ない人間のことである。 (以上引用) そこそこの長編でも、ここまで噛み続けられる、素晴らしいスルメ作品。
10投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔々積読していた記憶があったので探して見ましたが、既に処分していたようなのでこの機会に再度購入して読みました。この物語の舞台になるのは、当時フランスの植民地であったアルジェリアのオランという港町、街の臭いがしてきそうな程の描写に思わず引き込まれます。死んだ鼠を前振りにペストが蔓延し街が封鎖され、医師リウーらによる必死の治療にも関わらず不条理な死が人間を襲い、生きている人々は打ちひしがれます。そしてそれは終息し、街は開放され、生き残った者には日常が帰ってきます。献身的な働きをした医師リウーの妻が亡くなったのもまさに不条理な死です。今回のコロナ禍ではこのような不条理な死ができるだけ少なくなるように祈りたい。
6投稿日: 2020.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ海水浴の場面で表出する心の繋がりが素晴らしく、この世の不条理は全てあの瞬間のために存在しているのではないかとさえ思わされた。
1投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族がいるもの、1人もの、老若男女、どんな職業かも関係なく、襲いかかる見えないウィルス。まさに、現代コロナ以上の破壊力。最後は、自然抗体の末か?そして、進化もしそう。
1投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年春、新型コロナが席巻する世界において、改めて読み直されている不朽の小説。 アルベール・カミュはこの小説の成功で1957年にノーベル文学賞を受賞している。 その卓越した着想と構想、洞察力により、現代の社会生活を送る人々に対しても一定の普遍性を持つ内容となっており、忍び寄る新型コロナの恐れに対し実体験として多くを共有できるものである。 本書のテーマである「ペスト」は「悪」の象徴であり、「戦争」であったり「いじめ」であったり「全体主義」であったりと寓意として様々な事象に置換できるものという解説もあるが、閉鎖された空間における不条理への対応ということで、やはり感染症に侵される行き場のない人々というテーマがもっともしっくりとくる。 フランス領アルジェリアの都市オラン。ねずみが大量死することから事は始まった。 不気味に思う人々。そして、人間にも症状が出始める。やがて広がる人々への伝播。症状から病名はペストと判断される。 都市封鎖。感染病棟の大幅拡充。濃厚接触者の大規模隔離施設。大量死による墓地の飽和。 閉鎖された空間の中で人々はどのように振る舞うのか。不条理な状況下に突然おかれた人間たちの想いと行動が交錯する・・・。 この作品は主人公である医師リウーの視点を通底としているが、ときおりリウーは同志ともいえるタルーの手記を引用するという体裁をとっており、タルーの視点を多分に組み入れるという構造となっている。さらに、リウー自身を描く作者の視点と、タルーが見る人々の諸相は当然作者の掌中にあるため、こうした四重ともいえる複雑な構造が小説全体を難しくしているのではないだろうか。 さらに、作者が描写する背景や風景、説明部分が割と長いのに加えて、文章自体が冗長的であるためこれも少し小説を読みづらくしているところである。 また、宮崎嶺雄の訳がおそらく大部分が1950年当時のものと思われ、格調が高く重厚的な反面、現代としては少々古くなっている。 こうした「読みづらさ」というハードルは多少あるものの、再度ベストセラーとなっているということは、あらためてカミュの描く不気味で恐ろしい社会が世の人々の実感となっているということなのであろう。 登場人物としては先の主人公である医師のリウーと、民間の保健隊をいち早く編成し彼を助けることになるタルーがいるが、その他はひとりひとり、作者が熟考吟味した登場人物になっており、作者の思想を体現しているとも言える。 新聞記者のランベールはたまたま都市に居合わせて都市封鎖に遭遇してしまった者である。外部の世界にいる恋人に逢いたいがため、都市の有力者を巡り自分への特権を与えてくれるよう努力するのだが、それが不可と知るや闇業者に根回しを行うのだが、合い間にペスト対策一員としての作業をしているうちに心変わりしていく。 イエズス会のバヌルー神父は、初期ペスト禍の段階では大勢を集めてこれは神を背いた人々の報いであるとした。しかし、都市封鎖下で大量死を目の当たりにし、しかも少年が死に至るプロセスを間近で見ることでペスト対策の一員として身を捧げることになる。神への愛は困難な愛であるが必要なものであるとし、「司祭が医者の診察を求めるとしたら、そこに矛盾がある」というジレンマを抱えながら。 予審判事のオトンもその職業柄、上から目線の人であったが、息子が死に濃厚接触者として長期隔離され家族と離散することで、社会貢献の意志により隔離施設の事務手続きを行う役をかって出る。 グランは役所の下級役人でリウー医師と親しくしている。役所での仕事の傍らで保健隊にも属し、また自分を見限り捨てた妻を想いだし、小説の出だしの文章をずっと考え続けている。 コタールは謎の犯罪者。今回の非常事態下で犯罪捜査が緩み、その存在を当局から黙認されている状況をほくそ笑んでいる。タルーからはそれが彼の唯一赦しがたい罪だと断定されるが、その非常事態が解かれた後、彼がとった行動は反社会的なものであった…。 唯一、ペスト禍の都市封鎖の中においても、世の中から隔絶し喘息に病みながらも豆を移動させ達観の境地にいる老人。タルーが「これは聖者か?」と自問する対象となる。 そして、タルー。ある意味、作者が最も思い入れを深くしている人物像と思われる。死刑制度に反対し、そうした団体に属すも孤高の存在として不幸な人々のうちに入ることを望む。あくまでも理不尽なもの不条理なものと闘う反抗姿勢を見せる。 この小説ではペスト発生当初においては当局はそこまで深刻なものとせず、あまつさえ言葉の定義ややり方などの形式論にとらわれて出だしは大きく遅れることになる。 様々な意見が噴出しなかなかまとまらない対応策。そして、次第に市民に明らかになる状況と都市封鎖によりパニックとなる人々。そして迎える多くの死。 作者が登場させる多くの者が死に、また死に至る事細かな描写が何度も挿入される。 様々な立場の人々が次第に連帯する姿。 現代のコロナ禍と重なる部分も多く、多くの者の共感を得るゆえんである。 だが、主人公のリウーは多くの死に直面しそのプロセスや処理を多く見ており、さらに本書の終わりの方では彼自身の不幸も多く重なることになるのだが、彼はあくまでも淡々とこれに接し、超人的な精神と働きを見せる。「おそらく、罪を犯した人間のことを考えるのは、死んだ人間のことを考えるよりもつらいかもしれない。」と考え、タルーの思想が乗り移ったかのように社会的に前向きな姿勢をみせるのである。 神へのすがりを断り、都市封鎖を追放と捉え、自発的な連帯を期待し、感情を排除して超人的に不条理なものと闘う姿勢。 これはコロナ禍にある現代の人々にはある意味、理想的で酷な姿勢とも思えるのだが、当時の社会情勢下、カミュが孤高に生きることを宣言した狼煙が、現代に至ってもわれわれに強く突き刺さるものとなっているといえよう。 最後はペスト禍が終息し都市が開放される。多大な困難を乗り越えた人々は様々な歓びと感慨を抱くことになる。 われわれもこのような時期はいづれやってくるであろう。 しかし、本書の最後はこう綴られる。 「ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴蔵やトランクやハンカチや反故のなかに、しんぼう強く待ちつづけていて、そしておそらくはいつか、人間の不幸と教訓をもたらすために、ペストがふたたびその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差向ける日が来るであろうということを。」
36投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ新型コロナ感染症の拡大に関するテレビの番組内で紹介。NHK「100分 de 名著」で紹介されたらしい。 #外出自粛 #都市封鎖 #隔離 #極限状態 での人間心理。時代が変わっても変わらない。 しかし昔の翻訳は読みにくい。
1投稿日: 2020.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コロナウイルスの感染拡大により、感染症に対しての関心が高まる中、その時流に乗って購入。 物語は、194*年フランスの植民地であるアルジェリアのオラン市を舞台に、鼠の変死に端を発してペストが蔓延し、死の恐怖と共に隔離された住民たちの戦いの記録であり、最後に明かされるある語り手の手記という体裁をとっている。 登場人物には、ペストと戦える唯一の方法は誠実さだと考え、終始一貫して自分の役割を全うする医師ベルナール・リウー、殺人を正当化するようなものを一切拒否するという信念を持ち、後にリウーと友になるよそ者のジャン・タルー、愛する恋人と引き離され、隔離からの脱走を画策する新聞記者のレイモン・ランベール、ペストの発生は人々の罪のせいであると説教する博学で戦闘的なイエズス会のパヌルー神父、殺人を犯したことを内心是認しているにも関わらず、逮捕されることや孤立することを恐れながら生活している犯罪者コタールなどがおり、それぞれの性格が、リアリスト(リウー)、イデアリスト(タルー)、ヒューマニスト(ランベール)、クリスチャン(パヌルー神父)、クリミナル(コタール)という異なった立場を象徴していた。 彼らの掛け合いには意味深なセリフも多く、その深意を正確に理解できたとは思えないし、翻訳の影響もあるが、そもそも前半は話し手がどちらかさえ分からない場面も多々あったが、物語の内容はとても興味深く、現在のコロナウイルス感染拡大と重なる点も少なからず見受けられた。 例を挙げれば、当初住民たちは原因不明の熱病として懐疑的な姿勢を保っており、権力者たちもまた同様で対策が遅れ、被害が拡大してしまう点。 医療従事者への賛辞は意味を持たず、結局のところ安全圏の人々の自己満足でしかないということ。 疫病との戦い自体が免疫力の低下や、またその疲労によって思考の停滞を招き、住民の軽率な行動等により感染リスクを高めてしまうこと、などがある。 そして更に、その先に待ち受ける都市封鎖から、住民が希望を失っていく様をリアルに描いている。 ペストとは菌による感染症のことだが、作中で「人は誰もが自分の内にペストを持っている」と書かれているように、「毒」や「悪」の暗喩として用いられる場面もあり、そういう意味では警備隊が正義の名の下に脱走者を射殺することも、人の死という結果はペストのそれと何ら変わらないものであり、射殺した側の人間は、怨恨という名の感染症を蔓延させるペスト患者なのだと感じた。 個人的に最も印象的だったのは、犯罪者のコタールという人物。彼は殺人を犯して逮捕されるはずが、ペストの騒動で難を逃れていた。そのためか人間不信と孤独を恐れる気持ちとが共存していたが、それもまたペストによる都市封鎖により、皆と同じ境遇にいることで心は満たされていた。つまり彼にとってペストの終息は、逮捕へのカウントダウンであり、彼は終息を望まない稀有な存在であったのだ。 ペストに関して、人類共通の敵という認識を持っていたが、立場が違うとそれを望む者も一定数いることに気付かされた。 本作は「不条理」をテーマにしているが、ペストによる無作為な死のみを不条理と捉えているのではなく、それによる無慈悲な都市封鎖や、脱走者に対する発砲、錯乱した住民による放火などの人為的な行為、そして善悪の定義や信仰の矛盾などの問題も含め、多角的に構成されているように思えた。 抗うことのできない不条理に立ち向かう人間の可能性と無力さを、様々な立場や視点で描いた価値のある作品だった。
5投稿日: 2020.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年12冊目。 このコロナの現状と重なるディストピア小説だと思って読み始めたら、それどころの作品ではなかった。執拗とも思えるほど緻密な描写のなかに多くのテーマが織りなされている、稀にしか見ない化け物のような小説だった。 この作品に描かれているのは、アルジェリアのオランという街でペストが蔓延しはじめ、街が封鎖され、それが解除されるまでの約1年間の物語。街の様子の推移がいまの世界の現状と多分に重なることにはもちろん引き込まれる。けれどそれ以上に、登場人物たちの心情描写の徹底ぶりに度肝を抜かれた。 蔓延しはじめた病が恐ろしい「ペスト」であると認めたにもかかわらず、それでもなお思考がその現実についていかない医師リウーの様子は、新型コロナウイルスの脅威の度合いが判明してきてもなおなかなか行動を変えることができなかった自分たちと重なる。「彼らは決して災害の大きさに尺度を合わせることができない」という言葉からは、大きな危機に対する人間の適応力の課題を突き付けられる。 街の人々が徐々にその人らしい思考を失っていき、感情が平坦になっていく様子は他人ごとではない。その感覚に浸り過ぎ、ペストの時代が終わってもなお相変らずペストの基準に従って暮してしまうという描写に、病そのものではなく「病の周辺」にある痛みや苦悩の重大さを思い知らされる。その影響は一時的なものではなく、たとえ世界が戻っても自身のなかの世界観は戻らないというのはとても恐ろしい。 それでも、この小説が描き出すものは暗いことだけではない。街で結成された有志の保険隊のヒロイズム精神に食ってかかるある人物に対して、医師のリウーが次のように語ったシーンは、コロナの現状と向き合う上での自分の姿勢を固めてくれた。 ----- 今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかしペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです(中略)一般にはどういうことか知りませんがね。しかし、僕の場合には、つまり自分の職務を果すことだと心得ています(p245) ----- 大きなヒロイズムを目指して自身の無力さを嘆くのではなく、足元の誠実さ、つまり「自分の職務を果たすこと」に注力すること。この教えに強く励まされた。どのような状態にあっても、リスクは冷静に見極めつつも、光りを探す姿勢を忘れたくない。 ----- 天災のさなかで教えられること、すなわち人間のなかには軽蔑すべきものよりも賛美すべきもののほうが多くあるということ(p457) -----
7投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
外出自粛期間中に非常に臨場感を持って本著を読み終わったが、まず最初に「コロナ」が「ペスト」級の感染影響を持つレベルではなかったことがこの状況下での救いではないかと、この本を読んで考えるところである。 コロナの影響は2020年5月初旬時点で感染者350万人、死亡者25万人弱(今後増加しても恐らく感染者1000万人、死亡者100万人以下でしょう)であるのに対し、ペストは過去3度も世界的パンデミックを巻き起こし、14世紀に起きた「黒死病」と呼ばれるペストは世界全体で8000万人以上(最も被害が出た欧州では人口の1/3以上、そして世界大戦の戦死者以上)も死亡したと言われている。 我々はペストがもたらした無慈悲さと不条理性(ある意味で戦争体験)を実感することは不可能だが、まさにそれを実感した著者が本著を通してペスト(パンデミック型感染症)に対する政治の無力さ、人々の感情変化、個人的背景による感受性の差異などを、現実逃避する宗教性の問題、冤罪リスクをはらむ死刑制度の問題を絡めて忠実に描写し、歴史上類稀なる体験をした当時の人々の想いが込められている事が、ノーベル賞評価ととも伝わる作品である。 そういう意味でも現代に生きる我々はこの歴史的名著から多くを学び、教訓としなければならないが、残念ながら、人間の本質的課題とでも言うべきか、人間社会の宿命とでも言うべきか、「人間の無情なる忘却」から脱却できてない。 特に、今回のコロナ問題で特筆すべきは、本来であれば最もその警鐘を早期に迅速に世界へ発信し、毅然とした態度を示すべきだったWHOがその役割を果たせず、まさにカミュが本著で指摘する「誠実さ」というべきものが損なわれてしまった点である。(これについては今後評価が下されると思うが、問題は世界各国への迅速で正確な情報開示が毅然とした態度で行われたか否かである) 本著者のカミュはその強烈な人生経験から、宗教に見られる超越的存在(神)を否定し、個の存在を縮ませる全体主義に反抗し、社会的な不条理性に痛みを伴ってでも抗うヒューマニズム精神を奨励したが、まさにこの姿勢を改めてコロナ後の世界で考え直さねばならない事を示唆している様に思う。
3投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ20年以上ぶり?くらいの再読。もちろんコロナウイルスからの連想で本棚から取り出した。 前回読んだ時の記憶はあまりない。夜の海水浴のシーンだけがうっすらと記憶にあったくらい。かなり新鮮な気持ちで読んだ。 テーマは疫病というよりはカミュらしい人生の意味づけ。ペストは象徴でしかなく、その意味では今のコロナ禍で読むことはきっかけとしては有りだけど何か答えがあるわけではない。 シーシュポスのようにただ落ち続ける岩を持ち上げるようにペスト患者を見続けるリウーがカミュの追い求める道であるけどランベールもグランも喘息持ちの爺さんも生きる人は生きる。タルーのように世界を理解した、と思っても死ぬ時は死ぬ。パヌルーが象徴する宗教に逃げるのも人生に対して誠実ではない。 やはり印象に残ったのは夜の海水浴の場面。リウーとタルーは言葉を交わすことなく一緒に帰っていく。決してわかり合っているわけではないが、互いに生きていこうとする。
2投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーを読むことはないのだけど,コロナ騒動には困り果て,読む. 戦後間もないアルジェリアのオラン.ペストに襲われ都市封鎖.その中で淡々と誠実に職務を果たすことでペストと戦う医師リウーを中心とした群像劇. 訳が悪いという評価が多いが,訳は古いが難しくはないのではと思う.もとのカミュの文章が思索的でもって回った表現が多いのだろう. 表面的に見ればコロナよりずっと怖いはずのペストに襲われた都市は今の東京よりも開放的.映画館もレストランもカフェも夜までやってる. ペストはカミュ的倫理における悪のメタファーというのが定説らしいし,エピグラムも,そしてこの本の核心をなすタルーとリウーの海水浴に先立つ会話のシーンでもそれは裏付けられる.それを現代のコロナ禍のもと即物的に読むのは無理があるのではないか. 実存主義全盛の頃ならともかく,今の世の中,本の描かれた時代背景や社会情勢を知らないと何を言ってるのかわからないところがある.そういうところは解説の役目だろうが,こういう思想的な小説は読まれなくなるのも早いのかなと,少し思った.
3投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
源一郎さんやらあっちゃんやら激推しで、なにやら売れているし、現在の状況とかぶるところもありなにか思うところがあるかしら、と思い買ってみる。 が、まあ予想はしていたが私の苦手分野。 1ページの文字数が多すぎてつかれる。 とりあえず頑張って最後まで読んだことは読んだが、咀嚼しきれてはいない感じ。 でも後半、ランベールが残ることを明言したあたりから結構ちゃんとそれぞれの人物が立体感をもって読めるようになってきた。ようやく、であるが。 幼子の苦しむさまをずっと見守り続けるシーンが一番衝撃的。そこ、助からないんだあ、と。 無慈悲、無条理に全ての人に降りかかる病。 そこにある意味での平等を感じ幸福感を得るもの、あまりの無条理に絶望をみつつ、それを乗り越えようとするもの、受け入れようとするもの抗い続けようとするもの。 ただ、それらの人々が行動としては対立するのでなく協力していたことに人間の小さな希望があるのかも、とも思ったりする。 今コロナに罹患した人を責める風潮があって、その気持ちは実は私の中にもある。それはどうやら人間が自分を守ろうとする心の動きであって自然のものらしい。 だからこそ、自然にまかせるのではなく、理性で私はそれを抑えるべきなのだろう。もっとおおきな自然に抗うために。
2投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ緊急事態宣言が発令される前、この作品が、コロナウイルスの感染が拡大する現代社会と重なる描写が多く、今かなり売れているらしい、というのをおそらくフォロワーさんのレビューで目にして、3月中旬から、「ペスト」探しの旅に出た。 その頃は、2月上旬から4月上旬までの2ヶ月でこれまでの30年分の増版がなされたことなんてつゆ知らず、まったりとブックオフから探し出していて、あとは歩いていて目につく書店すべて訪れて探し回って、紀伊国屋書店本店で一冊もなかった時に、思っているよりもものすごい勢いでみんな「ペスト」を購入しているんだなと、少し焦る。どこかで、なんの根拠もなく、「自分だけが今『ペスト』が話題なのを知っている状態」だと思っていたので、ものすごく恥ずかしくなった。大人しく近所の本屋で予約購入。 わたしがこの本を入手できたのが4月16日。そして、この作品で舞台となっているアルジェリアのオラン市で、ペストが発生したと思われるのが、4月16日。 思いがけないこの偶然に、とても、いやだいぶ運命的なものを感じてしまって、一気読み… と言いたいところですが、一気読みには程遠く、半月かかってしまいました。翻訳にだいぶてこずってしまった、のが一番の理由です。物語が進むところはそれなりにすいすいと進むのですが、哲学者でもあるカミュが考えていることが難しいのか、訳が難しいのか、「彼」というのが誰を指しているのか、当時の時代背景の知識不足からくるものなのか、とにかく何度も躓いた。それでもこうしてなんとか最後まで読んで、なぜこの作品が、たった2ヶ月で30年分も増版することになったのか、どんな風に描かれているのか、そういったところを中心に、かつ、100分で名著を同時進行で見ながら、読み進めた。 作品の中で描かれているのはペストという疫病だけれど、テーマとなっているのは不条理。そして、最も描きたいのは、戦争という不条理だろう。 100分で名著で伊集院光さんが、この不条理を「いじめ」とも捉えることができると言っていた。巨大地震、災害、貧困問題、そういった事象にも置き換えられる作品だと思う。 ここからは引用しながらなので長くなります。 P55天災というものは、事実、ざらにあることであるが、しかし、そいつがこっちの頭上に降りかかってきたときには、容易に天災とは信じられない。この世には、戦争と同じくらいの数のペストがあった。しかも、ペストや戦争がやってきたとき、人々はいつも同じくらい無用意な状態にあった。 最初、日本ではそこまで脅威とは感じられていなかったコロナウイルス。日本人が本格的に危機感を持ったのは、志村けんさんが亡くなったあたりではないか、と個人的には感じている。 P73諸君がこれをペストと呼ぶか、あるいは知恵熱と呼ぶかは、たいして重要なことではありません。重要なことは、ただ、それによって市民の半数を死滅させられることを防ぎとめることです。 P74問題は、法律によって規定される措置が重大かどうかということじゃない。それが、市民の半数が死滅させられることを防ぐために必要かどうかということです。あとのことは行政上の問題ですし、しかも、現在の制度では、こういう問題を処理するために、ちゃんと知事というものが置かれているんです。 上に立つ人は、いつの時代も発言におそるおそるだ。何かを決めて行動する、それはものすごい決断力が必要だし、責任が伴う。いつの時代も、みんなそこから逃れたい。でも、国民の命を守らなければならない。安倍首相が急遽決定した、全国一斉休校の措置。最初はみんな戸惑った。文句もたくさん言った。でも、最近の報道を見ていて思う。継続して学校へ行っていたら。もしかすると、もっともっと今よりも感染が拡大していた可能性だってあったのではないか。卒業や入学シーズンと重なり、とても急に、大切なものを奪われたような気持になった人もたくさんいるはず。でも、命は守られた。 P95「ペストチクタルコトヲセンゲンシ シヲヘイサセヨ」 P96この瞬間から、ペストはわれわれすべての者の事件となったということができる。 そしてその後発令された、緊急事態宣言。ステイホーム。 P101事実上、われわれは二重の苦しみをしていた―まず第一にわれわれ自身の苦しみと、それから、息子、妻、恋人など、そこにいない身の上に想像される苦しみと。 この点は現代、オンラインがあって本当によかったと思う。そして、コロナウイルスの感染拡大によって、なかなかすすまなかったテレワークが進んだ人だっているし、オンライン授業だって可能になることだって気付かされた。オンライン飲み会、オンライン帰省、意外といいなって思った人は結構いるはず。 P103この病疫が六ヶ月以上は続かないというなんの理由もないし、ひょっとすると一年、あるいはもっとかもしれない 長引きそうな緊急事態宣言。もしかすると、6月以降も継続するかもしれないですよね。 P116ある朝一人の男がペストの兆候を示し、そして病の錯乱状態のなかで戸外へとび出し、いきなり出会った一人の女にとびかかり、おれはペストにかかったとわめきながらその女を抱きしめた、というようなうわさが伝わってきた。 ここを読んでいる時、ちょうどそんなニュースを観たもので、カミュの鋭い洞察力と想像力に感服。いつの時代にもこういう人っているんだろうか。 P174頻繁に、ただの不機嫌だけに原因する喧嘩が起り、この不機嫌は慢性的なものになってきた。 「コロナ離婚」という言葉がささやかれるようになったくらい。DVや虐待の悪化を、ただただ懸念しています。 P257すべてはまさに最大限の速度と最小限の危険性をもって取り行われた。 P260すべての作業のためには人員が必要であり、そしてしょっちゅう、まさにそれに事欠こうとする状態にあった。最初は正式の、後には間に合わせの職員であったこれらの看護人や墓堀り人夫も、多くのものがペストで死亡した。どんなに用心してみても、いつかは感染してしまうのであった。 P280恐怖にさらされた、死者続出のこの民衆の中で、いったい誰に、人間らしい職務など遂行する余裕が残されていたであろうか? P282病毒に冒された家へ行かねばならぬことを、最後のぎりぎりのときになって知らされたりすると、どこかの消毒所まで引き返して、必要な薬液の注入を受けることなど、やらないうちからもう疲れ果ててしまうような気がするのであった。 患者さんと毎日向き合っている医療従事者の方には、本当に心から感謝と敬意を表します。何もできないで家でくさくさしていることを申し訳なく思いますが、今わたしにできることは、自粛くらいです。 P268市民たちは事の成り行きに甘んじて歩調を合わせ、世間の言葉を借りれば、みずから適応していったのであるが、それというのも、そのほかにやりようがなかったからである。 P376りっぱな人間、つまりほとんど誰にも病毒を感染させない人間とは、できるだけ気をゆるめない人間のことだ。しかも、そのためには、それこそよっぽどの意思と緊張をもって、決して気をゆるめないようにしていなければならんのだ。 今のわたしたちは、このあたりにいるんでしょうかね。 一人一人がそれぞれ自分の方法で戦っていても、マスクや消毒液はないし、液体せっけんも品薄。それでもスーパーには行かないと生活できない。スーパーには、びっくりするくらい人がいる。なんとか、スーパーの丁寧な対応によって、消毒済のカゴを持ち、間隔を空けて並ぶことができたり、飛沫感染を防げたり。 自分と他人を守るには、やはり、できるだけ家にいるしか方法はないんでしょうね。 作品の中には、「内なるペスト」の話が出てきます。誰しもみな、心の中にペストを抱えているという。例えば、100分で名著では伊集院さんがペストをいじめに例えていたとお伝えしましたが、これだって、いじめを見て見ぬふりをしていた人だって、ペストを抱えていることになる、というもの。なるほどと思った。P362以降のタルーとリウーの会話、特にタルーの語りは興味深く、ページをめくる手が止まりませんでした。タル―が抱えるペスト、とは。 また、引用は疫病の部分にフォーカスしましたが、この作品の哲学的な描写や、パヌルー神父の変化、などにもフォーカスして読むとおもしろいと思います。パヌルー神父は当初「ペストは神からの罰」的なことを言います。以前、東日本大震災があった時に、前の都知事が同じようなことを発言され、かなり批判を浴びました。それと同様のことを発言していたパヌルー神父。かなり衝撃的な運命をたどります。 ちなみに、背景としては神が不在なので、無宗教である日本人には刺さりやすいのかな、という感覚を持ちました。 100分で名著がなければ、これほどきちんとは理解できなかったように思います。今の時期に読んだからこそ、ペストという疫病の方にばかり注目してしまったけれど、今読まなかったらわたしはどの部分に注目していたんだろう。ペストという疫病を、自分自身においては何にあたるのか、自分の人生における不条理とはなんなのか、もっともっと、掘り下げて考えただろうか。 ※こちらのレビューは、noteにも記載しております。(https://note.com/tattychannel/n/n345b056fcf74)
80投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのご時世、気が滅入りそうで避けていたのだが、あまりにもブレイクしているのでやはり読んでみた。 「ペストはナチスを象徴している」という予備知識だけはあったものの、日々ニュースにさらされている立場で読む限り、(少なくとも終章の一節を読むまでは)おもいっきり疫病の話として読んだ。私の整理ではこんな感じ。 第1章、病気の存在そのものを疑っている段階 第2章、流行が他人事の段階 第3章、事の重大さを理解する段階 第4章、蔓延、現場の苦悩、終息の統計的兆候の段階 第5章、終息 もちろん症状その他を混同してはいけないが、一般的な流行の経過や隔離などの対策については、1940年代と今とでほとんど何も変わらないことにまず驚く。 立ち向かうのは、医師リウーを中心とした無名の人々。 そこに居合わせてしまった市民が、みずからの職業的、宗教的、あるいは人間的なモラルである意味淡々とやるべきことをやっていく姿に心打たれる。 そして、たまたまロックダウンに巻き込まれ、手練手管で脱出しようとしていた新聞記者のランベールも、脱出決行のまさにその日に街に残ることを決意する。 「現に見たとおりのものを見てしまった今では、もう確かに僕はこの町の人間です、自分でそれを望もうと望むまいと」(P307)。 天災だらけの日本においても、こうした名もなき人が常に必要な場所にいたのだろう・・・ 注:それにしても、翻訳がさすがに生硬すぎ(古すぎ)やしませんか・・・??
8投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログヨーロッパを襲ったペストについて,ノーベル文学賞作家が書いた小説。事実を淡々と語っているような物語の展開が面白い。 本書の解説にはこうある。 本来ならば一般の読者には取つきにくいと思われるこの作品が、こんな爆発的な成功を収めた理由はなんであろうか? それはこの作品の簡潔なリアリズムが、さまざまの角度からきわめて明瞭な象徴性をもっていて、読者の一人一人がその当面の関心を満足させるものをそこに見いだしうるからだと、カミュ研究家アルベール・マケは言う。 登場人物が個性的で,医師のリユーを始めとして,司祭パヌルー,判事オトン,新聞記者ランベール,犯罪者コタールなど…そうそうタルーも忘れちゃいけない。 カミュは,この小説をとおして,何を狙ったのか。これまた,解説を書いた宮崎氏は言う。 しかもここには明らかな敵性人は一人もなく、コタールさえも憐れまれている。そして、誠実の 人リウーを中心に、神を信じるパヌルーから理性を信じるタルーにいたるまで、できるだけ広く人々の立場を糾合して,「人間」のための強力な人民戦線を結成しようとしているように見える。コンミュニスムとキリスト教とのあいだに、より人間的な第三の道を求めようとしているカミュの立場を、これほど遺憾なく表現しえている作品はない。 カミュ. ペスト(新潮文庫) (Kindle の位置No.5751-5752). 新潮社. Kindle 版. 本書では,ペストという感染症をとおして世の不条理を描くとともに,それでもなお人間への信頼を感じさせる。アルジェリア独立戦争の際に,第三の立場に立って行動した(両者から見れば行動しなかった)姿は,その後,彼の存在を返って浮かびあがらせることになった。
2投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むなら今しかないと思い、珍しく購入して読む。なんとか終わりまでたどり着いた。ラストの段落の文章にはゾッとさせられるけれど、物語としてそこに至るしかないだろうし、実際、現実でもそうなのだろうと思う。小説としては(それほど登場人物が多いわけではないけれど)やはり登場人物票がほしいところ。物語は重厚で、歯ごたえありすぎ。1/4くらいの分量だったら読みやすかっただろうな。すっかり内容を忘れているけれど『死鬼』『夏の災厄』『アウトブレイク』を連想。
1投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今のこの時期(コロナ禍)だからこそ、一度読んでみようと思った一冊。 ペストに襲われた街、オラン市の人たちは、それぞれどのように行動し、災厄に立ち向かうのか。今の世界情勢と照らし合わせ、この事態は現実世界ではどのようになっていくのか考える一助にしたくて読み始めた。 この本、個人的に良かった点をあげるなら、①オラン市の人たちの反応、②リウー医師とタルーの交流と友情、③リウー医師の医者としての姿勢の3つである。 まず①について、これがまあ、現代の私達とほぼ同じで、人は少なくともこの小説が発行された1947年、今から約70年前には今とほとんど変わりない思考や反応をしていたとわかって面白かった。ざっくり言うと、なかなか動かない政治家、宗教に救いを求める人、心を殺して頑張る医療者、金もうけしようとする悪党等々…今も昔もあまり変わりない。 ②について、この小説、基本第三者視点でたんたんとオラン市民たちの様子を年代記風に書いてるので、最後の方まであんまり感情移入はしにくい感じになっている。でもその分、最後の最後で描かれるリウー医師と、彼に協力する市民タルーの交流と友情と喪失に心を持っていかれた。 ③、これは個人的に一番グッときたポイント。ずっとペストを何とかしようと頑張っているリウー医師の医者としての姿勢について。毎日何百人と死んでいる状況で、結局どんなに頑張ってもあなたの勝利は一時的なもの(人は最後は死ぬから)だろうと言われた時に「知っている。それだからといって、戦いをやめる理由にはならない」と応えていて、同じ医療関係者として「せやな!」と思った。 最後に、☆3つのした理由であるが、途中まであまりにたんたんと書かれているので、いわゆる小説的に読者が感情移入するという点では取っつきにくい感じがしたから。ただし、良かった点②に書いたように最後の最後に感情移入させられて心を持っていかれたので、本を読みなれている人ならぜひ一度読んでみて欲しい。特にこの時期だからこそ、きっと普段よりも興味深く読めると思う。
3投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍の今読んだら面白そうだと思い購入したものの、翻訳がすんなり頭に入ってこず。 それでも、今の状況と比べて読むと面白い部分もあり、なんとか読了。 新しい翻訳版出ないかなー。
5投稿日: 2020.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ骨の折れる読書だったけどあっちゃんの授業を聞きながら読破。緊急事態宣言の今だからこそ読めた。 リウー先生の誠実さを目指したい。
1投稿日: 2020.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳が古くて読みづらかった。 物語というわけでもなく、時代の情勢を書ききっているわけでもなく、 何も進展しない、何も得ることのない、 結局何を伝えたいのかさっぱり分からない本だった。 むしろ、別に何も伝えたくないのかもしれない。 その割に6700ページと長く、 周りくどい表現や、意味の分からない翻訳で、 時間を無駄に費やしたと思ってしまった初めての本。
2投稿日: 2020.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログペストに襲われ封鎖された町。そこで悪疫と戦う市民たちの記録。 人生の悪とも感じられる害毒は果たして、私たちに何を連想させ、どんな象徴を感じさせるのだろう?病気、死、苦痛、あるいは貧困、戦争、政治悪??? 淡々とした文章がかえって彼らの人生やその変わりゆくさまを劇的にさせ、その不条理を浮かび上がらせている。 登場人物も多くなかなか難しい文章でもあるけれど、奇しくも、この新型コロナウイルスに悩まされる暮らしの中、時間だけはたっぷりあるので、ゆっくりと噛み砕きながら読んだ。 私たちはいま不条理と戦う毎日。それでも笑って暮らしていけるように。 「天災のさなかで教えられること、すなわち人間のなかには軽蔑すべきものよりも賛美すべきもののほうが多くあるということ、をただそうであるとだけ」だって言える世界でありますように。
2投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ新型コロナウィルスの流行中の今の世界に通じるものがあると言われていたのと、NHKの「100分de名著」で紹介されていたので読んでみた。 番組ではすごくわかりやすく解説されていたんだな~ って、作品を読んでみて思った 外国人の名前が苦手な私としては「あれ?この人誰だった?」とか何回も前に戻って読み返してたので読み終わるのにものすごく長い時間がかかったのよね。 それはさておき…内容。 アルジェリアのオランという商業町。医師のリウーの前で1匹のネズミが死んだ。ペストという疫病が街の生き物を殺す中、政府はオランを封鎖。残された人々はペストという抗えないものに対峙した時に、改めて自分の生き方や考え、自分の中に潜む人間性や宗教性に対峙する… 疫病という抗えないものに遭遇した時の人々の様子は今も昔も変わらないんだな~。 閉鎖された町であるものはなんとか街を脱出しようとし、あるものは酒で恐ろしさを忘れようとし、あるものは性愛でその場の快楽に身をゆだねる。そしてあるものは神に助けを求め、あるものはこの閉鎖されたからこそ生きて行けるという暗いラッキーにほくそ笑む。 絶対的な危機に瀕した時に現れる人の本質とそれを直視しないといけないという恐ろしさ。 コロナ禍で、マスクを求めて争う人々の姿、自分は桜の花見に行っても大丈夫だろうとか、これ見よがしにせきを人にふきかける人や、ヒマだからと言って行楽地や歓楽街に繰り出す人など… 人は時代が変わってもやはり人間中心主義(ヒューマニスト)なのだろうか。 不条理な小説と言われているこの小説はラストにも悲劇が待ち構えている。決して「よかった」と思わせるラストではない。でも、だからこそ読み終わった後にもう一度考えさせられる。1度目よりは2度目、2度目よりは3度目…何度読んでも発見があり、また深く考えさせられる。 この作品に出会ってよかったと思う。
14投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解できない部分も幾箇所かあったが、随所のエピソードは心に迫るものがあり、色々な生き方や人間性がよく描かれている作品だった。ピックアップされて描かれている人間は、1人1人にはっきりとした個があり、ペストという共通の問題に対する取り組み方の違いや紆余曲折に読み応えがあった。 登場人物の中で最も親近感が湧き、こうありたいなと思う人物はリウーだった。人格はさておき、思想の面で最も自分に近しいと思う。一度不条理の世界に浸ってしまったら平然として不条理の存在を無視することなどできない、存在しない神を信じることは出来ない、人間を愛することを大切にしたいから。リウー以外にも不条理に浸かった人間が多く登場するが、皆、ニヒリズムを志向しているのではなく、不条理を受容しつつも何か希望を求めて続けているというのが、今自分に必要で、手探りしていることそのものだと感じた。 世界はいつでも不条理に満ちているが、ペストという不条理の強烈な具現化によって、読者全体をその世界線に一度沈め、思考の開始点を揃えているのが素晴らしいと思った。この小説に非常に多くの要素が詰まっていると感じたが、ペストというものを持ち出すことによって、要素をうまく集約していると思う。まだまだ消化しきれない部分ばかりなので、時間を置いてから要所を再読したい。 物語の中で特に印象に残ったのは、パヌルーとリウーのやりとりだ。神を信じようが信じまいが、目下行うべきことは同じであるし、思想は違えどそれは自分たちを引き離すことはできない。相手の思想の違いを尊重しつつ、でも自分はそれを信仰しない理由を持っているし、自分が信じていることをはっきり認識している。そんなリウーに心惹かれた。 翻訳の問題だと思うが、表現が婉曲しすぎて、文体に関してはあまり好みではなかったかな…。読むのに時間がかかってしまった。それにしても、これが架空の話で、登場人物も架空の人物であるなんて信じられない…。本当に読む価値のある作品だと思う。ずっと積読していたけれど、手放さずに読んで良かった。
6投稿日: 2020.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ愛のないこの世界はさながら死滅した世界であり、いつかは必ず牢獄や仕事や勇猛心にもうんざりして、一人の人間の面影と、愛情に嬉々としている心とを求めるときが来るのだということを。 ◯不条理な世界に生きる我々にできることは、絶望しながらもなすべきことをすることしかないのかもしれない。 ◯この小説に描かれる混乱、絶望、悲しみは、小説とは思えないほど実感がある。 ◯コロナの収束を待ちながらも、小説を、とりわけ今この世界を描いたような小説を読み、普段では味わえない共感や感情移入することで乗り切っていきたい。
13投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログペストに象徴される不条理へと向き合う人間劇。新型コロナウイルスにより半ば自宅隔離が続くなか、ふと古典でも読んでみようと書斎から取り出す。面白い。不条理に襲われ閉鎖された街のなかでの人間模様が淡々とした筆致で描かれる。医者、小役人、罪人、老人、知事、通りすがり、神父と、多彩な登場人物の生き様は肉々しい。心を揺さぶる特別な煽りがあるわけではない。しかし読者を引き込む独特な筆致は、その場の空気感と匂いすら感じさせる観察眼とリアリズムによって支えられている。死者数が数百人、数千人と膨れ上がっても、どこか現実味がなく他人事のように思えてしまう。皆と一緒に耐えねばという集合的感覚のなかでも失われることのないエゴイズム。語り尽くせぬ生を引き受けながら、人の生が終わるのはとかく儚い。パンデミックを目の前にして、テレビを通して目にする映像よりも、よほどリアルな世界がここにあった。不条理のなかでいかに生きるか。私は、リウー医師が初めてペストに正面から向き合う際、身をゆすぶって感じたことを出発点としたい。 「そこに、毎日の仕事のなかにこそ、確実なものがある。その余のものは、とるに足らぬつながりと衝動に左右されているのであり、そんなものに足をとどめてはいられない。肝要なことは自分の職務をよく果たすことだ。」 特別なことではなく、まずやれること、やるべきことを。不条理のなかに生きる指針をみた。
2投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不条理に対して友愛の力を知ったランベールと孤独のママで居続けたコタールの対照的な終わり方から愛の大切さを知った。
1投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まさに起きていることと重なる。 政府の有り様。問題に立ち向かう立ち日による違い。離れ離れになっている人々。 美しい文章の中から、私たちが学んでいかなけれびならないことが満載です。
1投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
不条理に対する人間の向き合い方をリアルに描いた作品。 神をも超えた疫病という存在に対して、個人や全体主義的な葛藤や考え方の変化といった状況を描写している。 人や国がどういう考えでどのように行動するのか、これは今も昔も本質は変わらないのかもしれない。
1投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ今、この時期、読んで良かった。 ペスト、病気の話?いくら名作でも、そんなの読みたくないな。 今までそう思っていた。 でも、今、新型コロナが広がっている中、Kindleで試し読みしたら、続きが読みたくなり、今こそ読む時だと思って買った。 胸に静かだけど、ずしっとくる。 名作だった。 恐ろしいペストの症状、残酷さ、死。不条理。 あらゆる不幸が突然襲いかかる。 それなのに、美しい文体で静かに染みてくる。 さまざまな共感できる人物が登場する。 自分は今どの立場か? 新型コロナと比較してしまう。 同じような道のりを辿る小説内のペスト。 政治家の判断の遅さ、閉鎖される町、別離、死。 死の描写は臨場感があり、苦しい。 なんてひどいんだろう。残酷だ。 なんで、ペスト菌は現れて人や動物を苦しめるんだろう? いつになったら、外に出て愛する人に会えるのだろう? いつペストは収束するんだろう? 同じように、 新型コロナはいつ収束するのかなぁ? そんな日は来るのかな。 1日に何回かそんなふうに思う。 在宅で仕事し、子供は学校が休みで家で勉強、スーパーやドラッグストアは週1回、ジョギングはマスクをして人の少ない道を走る。
1投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語は複線で進んでいくので、少し異なる物語を追っていくのが難しかった。普段は小説などはすらすら読んでしまう方だが、これはとても時間がかかむた。 感染症という圧倒的な不条理に対して個人が、または都市全体がどのように反応するのかを淡々としたタッチで描いていく。突然やってくる災厄、当初の楽観的見通し、突然の戒厳令、違反者に対する容赦ない厳罰、強制的隔離や脱出者の射殺、抜け道、危機を利用した商売、抜け道、懇願、諦め、狂気、無関心、慈悲、偽善的ボランティア、日常的な死、、、これらは今のコロナ拡大によって自分たちが経験してきた、あるいは経験することになることなのかもしれない。印象的なのはペストによる死そのものではなく、これらに対して人間がどのように受け入れるのか、抗するのか、にフォーカスがあることだ。 個人的に面白かった点は、解説で指摘されていたこの作品が第二次大戦直後に発表されたもので、ペストは世界大戦という不条理に関連されているということ。圧倒的な支配に対して、個人の反応と都市全体の連帯や全体主義の間で視点が移り行くのが面白い。
3投稿日: 2020.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わって分かったこと ・いつの時代も感染症は、別離の苦しみと病の痛みをともなうものだということ ・終わりは唐突にやってきて原因不明であること ・忘れているようだが、常に人類は滅亡の危機に瀕しているということ カミュの時代のキリスト教の考え方がいまいち分からなかったので、理解に苦しむところが多かった。 コロナウィルス対策に何かヒントを探したけれど、物語の時代背景を勉強して、理解を深める必要がありそう。
2投稿日: 2020.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際、ペストが、その語の深い意味において、追放と別離とであったことを物語っていたのである。… 本当は、病だけでなく、宗教や哲学にも触れられた一冊です。が、今回はとにかく話の結末を知りたい一心で読みました。ネズミやノミ、ダニを媒介に、じわじわと人々を蝕むペスト。現在、コロナウィルスと闘う医療関係者と、「チームリウー」と呼ぶべき登場人物らが重なります。1940年代のアルジェリアを舞台に、淡々とした筆致で描かれていますが、闘う医師リウーの結末と、多大な犠牲を払いながら解放された街で喜びを享受する市民の姿とのコントラストは、淡々としているが故に胸に迫ります。 今この瞬間も闘っている患者さん、医療関係者さん、そのどちらものご家族、この生活で不安になっている全ての人、今生きていることに感謝しよう。しにくいけど、自分も人も解放を待ち望む一人の人間だと自覚しよう。
3投稿日: 2020.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恐らく一番リアルに内容を理解できるであろう時期に読了。 ペストに襲われ突然封鎖された街で起こる人々のパニック、悲観、困憊など不条理な出来事を淡々とした筆で綴った作品。 黙々とペストに立ち向かう医師リウー、タルー、グラン、たまたま立ち寄った街で閉じ込められ必死に抜け出す手段を探すランベール、逃亡者でペストで封鎖された街に安堵すら感じている様なコタール…等様々な人物が登場する。 突然襲ったペストはまた突如収束してゆく。 翻弄される人々や社会の変容がとてもリアルだった。 「ペストが終わったらこうしよう、ペストが終わったらああしようなんて……。彼らは自分でわざわざ生活を暗くしてるんですよ、黙って平気でいればいいのに。」 まさにコロナ禍の中、強烈な図星を刺されたようだ。 時代を経た名著だが、現在にそのまま通ずるものがある。
4投稿日: 2020.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ新型コロナウイルスが蔓延している今、この本にたどり着けて良かった。世界というのはまぎれもなく「不条理」なもので、それは突然襲いかかってくる。 そして、そこで経済活動ができなくなった時にどう対応するのか。多様な登場人物でそれぞれの対応が描かれているのが興味深い。現代にも十分通じる。 さて、2011年は天災だったし、2020年は疫病。 その中で人はどう考え、どう行動するか。 私自身も問われている。できることをやろう。
3投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちを脅かすコロナ。世の中は日に日に増える感染者の数と比例して恐怖感を強めていく。過去にも世界の歴史の中でペストやスペイン風邪といったものが今と同じような状況を経験している。私たちは何をしなければならないのか考えさせられた。主人公リウーやランベール彼らそれぞれの目線でペストに対する向き合い方や想い、そして人生の喜怒哀楽が大いに感じられる作品です。ホントに今が旬の本ではないでしょうか。多少表現が昔風になっているのでそこが読みづらいところが難です❗
9投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カミュはサルトルより好きだった。だから、怖い話でも、なんとか読み進もうとした。ちょっと頭でっかちの読み方。今、感染症が流行るなかで、読み返すのが多い本の上位3冊の1冊らしい。もう1冊は1984。最後の一冊は、、、。
5投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログペストがひろがり、町が隔離され人々が生活していく中でその人それぞれの本質が見えていた。リウーやタルーの様に最後まで戦うもの、神を信じるもの、この状況のおかげで金儲けをするもの。それは現在のコロナウィルスでも同様である。マスクを高値で転売する人などがいる。また隔離されることで心境の変化もでてくる。最初はここから出たい気持ちが高まり、そして出る手段を考えることに没頭することで離れた人のことを考えることがなくなる。ウィルスはいつ終わるかわからないので、感染が失速しても希望だけでなく不安もついてくる。
2投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかったが、とてもおもろかった。 今の時代にも当てはまることは多いという意見が多いが 確かに示唆に富んでいることが多いと感じた。 一つの疫病を前にして、人がどのように生きるのかを表している。その現場で自分の職務と淡々と果たそうとするもの、自分の個人の目的のために生きようとするもの、安堵(むしろ喜ぶ)もの、皆実際にこのような人たちはいるがその人たちがお互いに批判するという権利はないのではないかと思った。 私も初めは、ある人物には批判的に見ていることもあったが、途中でそのようにできなくなっていた。 きっと思考し、同情し、ということが徐々にできなくなっていくのかもしれない。そして、私もそういう状況になるのかもしれないと、少し恐れてしまった。 絶望的な状況の中で生きるとは、どういうことなのか、淡々とした文章ではあるが、どこか大きな主張が根底に流れていて、それを感じずにはいられない作品だった。
2投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ続くのか。 というより、終わらないのか。 不気味だ。 2020/4/17 の今日、読み終えてよかった。 終わりがない。 とても怖い。
2投稿日: 2020.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『抽象と戦うためには、多少抽象に似なければならない』 カミュの哲学的な言葉が沁みる。カミュの正義は白黒の明確な勧善懲悪の正義ではない。どこまでが許容され、どこからは拒否されるのか。それはもしかすると「許容され得る」「拒否され得る」と表現されるべきものであるようにも思うが、その可能性を決定する主体は非常に曖昧でもある。神の存在は希薄であるし、絶対的な存在、すなわち絶対的な善を信じているようではないが、何もかも自分自身の価値観で決めるようでもない。誰と約束した訳でもないことを律義に守ること。それが全てであるように見える。 『自分がいっている全的な受容という徳は、普通に考えられているような狭い意味に理解されるべきではなく、それは月並みな諦めでも、困難な自己卑下ということでさえもない』 全くの受容が「徳」であるとする前提には、受け入れ難いことに抵抗する気持ちがある筈だ。しかしそこに善悪の基準を挿し込まないでいるためには強い精神力が必要であろうと思う。それは「何故受け入れ難いのか」と問うてみるとはっきりする。それに対する答えを善悪の基準抜きに答えようとすると、上手く言葉にならない。カミュは主人公に受け入れ難い状況を受け入れさせつつ、その状況にただ手をこまねいて傍観することも許さない。その立ち位置に恐らくカミュの正義はあるように思う。 『だが、まあ、そういうもんだね。ほかの連中はみんないいまさ──《さあ、ペストだ。ペストにかかったぞ》なんてね。もう少しで、勲章でもほしがりかねない始末でさ』 結局、誰かに自分の行動を認めてもらうために行動するのではないのだ、とカミュは言うのだ。正義の御旗の下に立ち上がるから善なのではなく、自分自身が身体感覚として感じるところに従うこと、それだけなのだ、と。それは単純なことでありつつも、自分の行為を抗弁しないという茨の道でもある。しかしこんなカミュの言葉をしっかりと胸に刻んでおくのがいいのだろう。 『これは誠実さの問題なんです。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかしペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです』 それはもちろん、比喩としてのペスト以外と戦う唯一の方法でもあるのだから。
7投稿日: 2020.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログただただ続く不幸や不条理の連続に、まるで延々と暗がりの部屋で読んでいたような感覚に陥ってしまいました。 オーウェルの『1984年』や、映画『コンテイジョン』『復活の日』などのディストピア系の作品が近頃流行り始めているのは、迫りくる現実を客観的に見て、 どうすることが「正しいこと」なのかを考えるために読んでる人がいるのかもしれません。 この物語は、 『四月十六日の朝、医師ベルナール・リウーは、診療室から出かけようとして、階段口のまんなかで一匹の死んだ鼠につまずいた。』 という、当たり前の日常の、少しの違和感から始まります。 ただの1匹の鼠の死骸が、日に日に夥しい数になり、やがて、人間にも感染していくようになりました。 感染者は増え、街を封鎖しましたが、本当の恐怖はこの、封鎖した中で広がっていくこととなります。 まるで未来予知のごとく、今起こっている現実にものすごく近くて、ページをめくるのが怖くなりました。 きっと、フィクションであれば、すぐ読めたのですが、そうもいってはいられない現状で、何度も読むことをやめて、また読むことを繰り返し続けました。 作者は1人であるにもかかわらず、物語の中では、さまざまな考えを持つ人がいます。 何となく自分はこの人に近いかもしれない、と思うこともあるかもしれません。 設定上では、この物語を書いているのは、登場人物の中の1人です。それは誰かは書きませんが、想像を膨らませながら読むのも一つの楽しみ(?)だと思います。 物語の最後をどう捉えるか。僕は、物語終盤でリウーの感じたことが、まさに的確な意見に思えました。 向かい風が吹き荒れる現実に、立ち向かうにはどうするべきか。まだ風が弱いうちに、少し考えてみるのもよいのかもしれません。
39投稿日: 2020.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナウィルスの混乱をありのまま物語っている小説だった。 自粛生活でモヤモヤした気持ちの正体を言語化してくれる。反省の意味も込めてまさに今読むべき本だと思った。肝心なことは自分の職務をよく果たすこと。 読み進めていく中で登場人物達の心の変化に目が離せず感情移入した。何が正しいかではなく自分は今どうあるべきか改めて考えさせられる。
5投稿日: 2020.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログフランスの作家カミュによる1947年発表の作品、コロナ騒動により世界各国で読み直されている一冊。フランスの植民地のアルジェリア・オラン市で伝染病のペストが蔓延、市が閉鎖される中での、市井の人々の葛藤を描く。物語は医師のリウーが死んだネズミに気づくところから始まり、死者が出て、メディアが持ち上げ、市は閉鎖、最初は楽観的だった市民も次第に恐怖の渦に飲み込まれていく。今のコロナ騒動との共通点がいくつも描かれているし、学べる教訓もたくさんある。世の中は変わったが今も昔も人の行動・思考はあまり変わらないなと感じた。
5投稿日: 2020.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生の頃買ったこの小説を、現在起きつつあることの内実が抉り出されるのを見る思いで読みましたが、それによってかろうじて落ち着きを保てた気がします。封鎖された街で人々が結びつきながら、かつ生き方を変えながら疫病と向き合う様子は、現下の状況をどう生き延びるのかと問いかけます。
2投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ騒動に触発されて再読。と言っても、何十年かぶりで内容は殆ど覚えていなかった。 作者が描きたいのは世の中の「不条理」さで、現在の人間が勝手に今のコロナの状況と重ね合わせているのは本意でないかもしれない。 ただ、間違いなくこの本で描かれている人々の心の動きや葛藤、社会的状況は大なり小なり当てはまるだろう。故に、本書もまた、今の世の中により一層の現実味を持って受け入れられている。 終わり方が怖い。
5投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログアルベール・カミュ(1913~1960年)は、フランス領アルジェリア生まれの作家、哲学者。第二次世界大戦中に発表した小説『異邦人』(1942年)などで「不条理」の哲学を唱えて注目され、1957年にノーベル文学賞を受賞。1960年に自動車事故で46歳の若さで死去。 本作品は第二次世界大戦後(1947年)に発表された、代表作のひとつである。 物語は、フランス領アルジェリアの港湾都市オラン市(現存する)をペストが襲い、感染拡大阻止のために街は封鎖され、人びとが次々と命を失っていく絶望的な状況の中で、医師のリウーを中心に、よそ者(旅行者)のタルー、下級役人のグラン、新聞記者のランベール、パヌルー神父、密売人のコタールなどの様々な登場人物が、それぞれの立場で無慈悲な運命と立ち向かう様を描いている。 この作品は、ナチス占領下のヨーロッパで実際に起こった状況の隠喩だといわれる。逃げるところのない過酷な状況下で、同胞同士の相互不信、愛する人びととの別離、刹那的な享楽への逃避など、カミュ自身が実際に目撃した人間模様が描かれているのだ。本作品は、戦後間もない時期に発表されたが、民衆はそれを理解しベストセラーになったという。 さらに、この作品に込められているのは、カミュの人生観・哲学でもある。罪なき人びとの死、世に蔓延る悪、自分の力では変えようのない状況。。。人の人生は「不条理」に満ちている。しかし、いかに不条理であろうとも、我々はその人生を生きていかなければならない。そして、そのために最も大切なことは、本作品で描かれているように、人びとがそれぞれの役目を果たし、人びとが連帯していくことなのだ。 そして、作品の最後では、感染がほぼ収束する中で、それまで医師リウーを支えてきたタルーがついに発病し、「今こそすべてはよいのだ」という言葉を残して静かに死んでいく。。。世界はどこまでも「不条理」なのだ。 今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴って、本作品はヨーロッパのほか、日本でも広く読まれるようになっているという。カミュのメッセージは上記の通り幅広く普遍的なものであるが、今の世界、我々を取り巻く状況に引き寄せて解釈することは、もちろん有効だろう。そして、そこで示唆されるのも、やはり、リウーやタルーのように、目の前のことに対して自分のできること(多くの人びとにとっては、外出を自粛すること)を精いっぱいに行い、皆で連帯していくことが最も大事ということだ。 今、このカミュのメッセージを大切にしたいと思う。
5投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログフランス領アルジェリアの港町オランで、突然ネズミの死骸が街にあふれ、人々は正体不明の病に倒れていく。病名はペスト。町は封鎖され、外界から孤立した住民たちは、それぞれの立場や信念でこの未曾有の災厄に向き合う。医師リウーを中心に、苦悩と希望、葛藤と連帯が交差する中、人々の本性と生き方があらわになっていく。 アルベール・カミュの『ペスト』は、単なるパンデミック小説ではなく、人間の本質をあぶり出す哲学的な物語だ。舞台は閉ざされた町・オラン。突然訪れた死と混乱の中で、人々は選択を迫られる。逃げるか、残るか、信じるか、絶望するか。 登場人物たちの選択はさまざまだ。病に倒れた妻を別の都市に残し、医師として使命を全うしようとするリウー。死刑を宣告する父を持ち、死とは何かを問い続けるタルー。帰郷できず孤立したランベール記者は当初脱出を望むが、やがて他者のために残る決意をする。また、パンデミックによって逮捕を免れたコタールのように、この異常な状況が終わらないことを願う人物もいる。 そして、信仰の立場から人間の罪を説いていたパヌルー神父は、無垢な子どもの死を前にして言葉を失う。彼の姿から、「正義とは何か」「神とは何か」「意味のある死とは」といった問いが読み手に投げかけられる。 この物語には、絶対的な正しさはない。カミュは登場人物のどれをも批判せず、読者に判断を委ねている。それぞれの信念、それぞれの恐れと希望があり、誰もが何かしらの「正しさ」を抱えている。だからこそリアルで、読み手の心に突き刺さる。 ペストの終息は唐突に訪れるが、リウーは「ペスト菌は決して消え去ったわけではない」と語る。それは病気だけでなく、人間社会が抱える問題、差別や暴力、戦争や不条理にも通じる。カミュは警告する。災厄はいつでも、どこでも、再び現れるのだと。 コロナ禍を経た今読むと、よりいっそう身につまされる。「正義」は一つじゃない。だからこそ、自分なりの正しさを持って、他者とともに生きることの大切さを感じさせてくれる一冊だ。
3投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【内容メモ】 ・ペストという不条理が襲う世界。閉鎖され、外界との接続が断たれる街。別離や死別。 ・人々は自らの苦しみと、愛する人の苦しみの、二重の苦しみに苛まれる。 ・最初は恐怖と不安で錯乱する市民たちも、次第にその感情すら失い、希望の無い生活を送るのみ。 ・ただ、ペストの衰退=街の解放によって、ラストでは、民衆は、それまでの事は何もなかったかのように歓喜し、愛する人との時間を味わう。リウーはそれを見て、その人間らしさを、それを良しとする。 ・リウーは誠実な人間、医師としての職務に絶望を感じようとも、健康の問題だけを考え、一人でも多くの命を救いたいと考える。この人の強い意志は、予断を許さない疲弊の中で切れそうになっても、挫けない。 ・新聞記者ランベールも、最初はパリの恋人の元へなんとしてでも帰ろうと=個人の幸せだけを考えていたが、「自分はこの街の人間だ」という思いに至り、脱出せずに町の人々を救う活動を手伝い始める。 ・この物語の登場者たちは、自暴自棄にならずに、人間的な形で、この巨大な敵に立ち向かおうとしている。 ・医師リウーをはじめとして、登場人物たちはこの異常な状況下で、苦しみながら、人間として生きていく術や希望を見出そうとする。 ・ペストで人々が得るのは、知識と記憶。 友情や愛を知り、また、それがあったことを思い出す。 ・人々は、そばにいない人の肉体の温かみや、愛情や習慣をずっと求めていた。 ・物語の結びに、リウーは、 ペストは消滅することは無く、またどこか幸福な街に死滅を与えにくるときがくるだろうと書いていて、いつなんどきそうした不条理が襲ってくるかわからないということを暗に示している。 【感想】 実際、今回のコロナもそうだけど、いつ不条理に襲われるか分からない。日々の中で、愛する人にはその気持ちを伝えないといけないなと思った。月並みだけど。 読む前は、人々が恐慌状態で錯乱して、お互いを疑い憎み合い、地獄絵図のような世界になっていくストーリーを想像していたので、すごく人間らしく、慎ましくこの恐ろしい敵に立ち向かう人々の物語だったことが意外だったし、なんだか人間の善の部分を信じたいと思った。絶望の中でも一縷の希望を見出す、人間的に生きていく、そういう思考を持ちたいと思った。
5投稿日: 2020.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020/4/5読了。世界的に蔓延している新型コロナウイルス感染者数102万人。死者5.39万人。 (3日時点)日本国内感染確認数約3000人、死者 75人。今日4日首都東京では、連日急増していた感染者数が、危険水域とされた三桁の119人になってしまった。政府は、ギリギリに推移していると経済的打撃を恐れて『緊急事態宣言』を発動出来ないでいる。もはや、水面下ではこの数字の十数倍もの 感染者がいると言われているのに。だれもが、楽観的に見たくなるが疫病はそれを嘲笑うかの様に蔓延して我々小市民の日常生活を破壊していく。第二次大戦後のカミュの作品ながら、そんな極限で生きる人間を冷静に見つめる眼差しが現代に生きる私に違和感なく伝わる。難解な部分もあったが読了。解説も参考になりました。
5投稿日: 2020.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ちょうどコロナが流行り、学校も休校になった頃に読んだ。 ペストの流行後に起こったいくつかの出来事が現実でも起こっているのには驚いた。 ペストの兆候を示した男が、錯乱状態で戸外にとびだし、いきなり出会った女に「俺はペストだ」と言いながら抱きついた→コロナに罹った人がフィリピンパブで「俺はコロナだ」と言っていた事件を思い出させる。 不測の感染を予防するためにハッカのドロップをしゃぶるようになった。薬屋からハッカドロップが姿を消す→マスクとアルコール消毒液が買えないことを想起する。 マスクが何かの役に立つのか、という疑問に「そんなことはないが、つけていると向こうが安心する」という答え。 街が封鎖され、死者数が増えて行って葬儀が間に合わない、という事態になっている国も実際にある。 この本の病気の始まりが春なので、その点も絶妙だ。 暗いクリスマスを現実が追従しないよう切に願う。 リウーは最前線でずっと治療に当たって、睡眠時間も4時間でくたくたに疲れながら頑張ったのに、友達になったタルーも奥さんも失ってしまってかわいそうだった。
3投稿日: 2020.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ不条理なこの状況、人間はどうあるべきか。新型ウイルスが猛威をふるう2020年のいま、この書にわたしたちの救いはある。終息に向かうまではこの書を片手に。
3投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ新型コロナウィルスが流行し始めてから、改めて注目されている名作です。フランス人作家カミュ(1957年にノーベル文学賞を受賞)による1947年の作品です。舞台は1940年代、アルジェリアのオランという県庁所在地。4月に突然発生したペストにより、市が封鎖されてから解除されるまでの約9か月間の物語です。ペストという「不条理」(ペストは戦争、災害、不当な権力などに置き換えることができます)に対して、人々の弱さが描かれると同時に、様々な立場の人々が連帯していくさまも描かれています。キリスト教信仰の強い地にあって、神に頼るのではなく、また人間の理性を過信することもなく、ひたすら誠実に、かつ子どもをはじめ弱い立場の側に立つ作者の立ち位置が胸を打ちます。文章は決して読みやすくはありませんが、わずか33歳で書かれたその内容の深さに感銘しないではいられません。
8投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ194×年、フランス領アルジェリアのオランを襲ったペストの脅威に慄く人々と、目に見えない邪悪なウイルスに果敢に挑む人間の行動と心理を克明に描いた、ノーベル文学賞作家【アルベ-ル・カミュ】の代表作です。感染拡大するペストの災禍によって日常生活が失われ、人間の尊厳までも奪い去られる無慈悲で不条理な世界が露呈します。教会の神父は、罪を悔い改め、信仰を深めよと説きます。ペスト終息を前にして町医者のリウ—が呟く警鐘〝人間に不幸と教訓をもたらすために、再びどこかの幸福な都市にペストが差向けられる日が来るだろう・・・〟
1投稿日: 2020.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ新型コロナウイルスが猛威をふるう現在、この小説がまさに旬でしょうと思い、読みました。なかなかおもしろかったです。が、思ってたのとはちょっとちがってたかも。ペストが流行って、まちが封鎖されてしまって、いろんなひとは困るし、絶望的な状況も多数生まれる。でも、なんだか、現在の私の周囲にたちこめている閉塞感のほうが息詰まり度は高い気がして、むしろこの本のほうが、みんな昼間は出歩きまくってお酒飲みまくって、映画館もいっぱいになって・・・、なんて、なんだか楽観的に感じられたりしました。私の読み違えでしょうか。あと、やはりなんかだらだら長いのね。描写。フランスって、哲学もそうだけど、なんだかダラダラ長いよね。それがフランスの知識人の文章の作法なんでしょうか。なかなかついていけません。【2020年2月23日読了】
7投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログアルジェリアでペストが流行し、街が隔離、閉鎖される、という設定の小説。第3者の目線で記録体で記述されている。 戦争の体験を背景に、ペストはそれらの隠喩として書かれた作品のようだが、新型コロナの言われる今の状態ではペストをそのまま、感染症の脅威として捉えることに実感が湧く。 極限状態の中、悲観的な考えを持つ者、無根拠に楽観論に走る者等、今の世相にも合う部分があり、人間の本質は今も昔も変わらない、と思わざるを得ない。
5投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログペストによって街が封鎖される。疎開は許されず、境界をはさんで別離も生じる。たくさんの人々がそれぞれに重苦しい空気の中で病気と戦い、生き方を見直し、あるものは敗れて死に、あるものは生き残る。伝染病の感染と言う災害と、どう共に生きるかを問う災害文化の物語。 フランス語らしい端正な文体で綴られる。 2019年の暮れから世界的に流行した新型コロナウィルスの騒動の中で、多くの人々が改めてこの本を手に取った。 この本が書かれ、世界的なベストセラーとなったときには、別段伝染病が流行していたわけではない。ペストは当時の世界を覆ったある種の重苦しさのメタファーとして理解されていたのだろう。 今日のウィルス禍は、文字通りのウィルスによるものなのだが、ウィルスそのもの、病そのものよりも、科学的な調査を意図的に避け政治日程を優先するような愚かな政府、あるいは市井の人々の過剰とも言えるような反応、その連鎖によるある種の茶番こそが、苦しみの中心になってしまっている。 人々はペストに勝ち、門は開かれ、花火が上がる。 人間はこう見えてなかなかにしぶといから、新型ウィルスにも、やがて我々は勝つであろう。しかしその時の社会の傷が、致命的にはならないようにしておかなくてはならない。
0投稿日: 2020.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュ『ペスト』新潮文庫。 新型コロナウイルスの感染拡大のニュースに本屋で目にして思わず手に取った古いフランス文学。大概の有名な作品は読んでいるが、この作品は若い頃にも読んだという記憶は無い。 伝染病の始まりというのは僅かな日常変化なのだろう。1940年代、アリジェリアのオラン市で医師のベルナール・リウーが鼠の死骸を発見したことから物語が始まる。次第にペスト感染者が拡大し、オラン市を封鎖し、ありとあらゆる施設を感染者の待機場所にして感染を封じ込めようとするところはまさに中国の武漢市と同じで、市民が不条理に苛まれる姿も現在の日本の状況と同じであることに驚いた。 我々の生きているこの時代は阪神淡路大震災、東日本大震災、台風、竜巻、そして新型コロナウイルス感染拡大と死と向き合わざるを得ない自然の猛威を見せ付けられる特殊な時代なのだと改めて思う。 本体価格750円 ★★★★
61投稿日: 2020.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年越しかで読了。緻密な記述でリアリティがあるが、それだけに逆にページが進まなかった。語り、論説の部分が特に厳しかった。
2投稿日: 2020.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現実の世界で、人類にとって未知のウィルスとの対峙を余儀なくされている。新型コロナウィルス肺炎COVID19。 これまで、人類は様々な病原体と戦ってきた。歴史上で取り上げられる病原体との戦いの様子を知りたくて、『ペスト』本書を手にした。 1940年代、第二次世界大戦が終わって間もない、フランスの港町で起こる出来事を年代記風につづっている。ペストが猛威を振るう前兆から物語が始まり、死が徐々に町を覆っていく。 想像してみてほしい。通信手段が電報しかなく、交通機関も未整備である時代に、ある日突然町が閉鎖されるときの心情を。本書は、ペストを医学的な視点で語るのではなく、対処方法が明確ではなく致死率の高い病気に直面した人々の行動や心理をつぶさに描いている。 目の前で愛する人々が、苦しみ命を落としていく日常が繰り返されたとき、日常と変わらぬ心情で病と対峙する人々がいる一方、心情、行動が大きく変わる人々もいる。 司祭の苦悩は、想像を絶する迫力があった。目の前に繰り広げられる不条理に対して、全てを受け入れなさいという教え、受容することで、信仰を失わずに正気を保つ様は心が揺さぶられた。 この二週間、外出を控え感染拡大を防ぐ大切な期間と言われている。この時期に読む本の候補に上げてほしい一冊だ。
4投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、売れてるみたいですね。 不条理に直面した時、どのように行動するのか。いろんなパターンが出てきて興味深いです。 どうか、現実が本書を凌駕しないことを祈ります。
2投稿日: 2020.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間性を蝕む「不条理」と出合ったときに人々はどうするのか?どうなるのか? 「ペスト」という疫病が「不条理」に設定されていますが、それを置き換えても当てはまります。「災害」「戦争」もちろん喫緊の課題「新型肺炎コロナウイルス」にも。 そのようなわけで再読しました。といってもすっかり忘れていますので、初めて読んだようになりましたけど。 ノーベル賞作家であり古典ですから当たり前なのですが、ストーリーが半端なく、うまいなあと思いました。リアリズムというか、映像を見ているように描かれ、平明な文章と文脈で淡々と綴られている、文学らしい文学を味わいました。 アルジェリアのオラン市というところでペストが発生、市が封鎖され、閉じ込められた人々が疫病という困難に立ち向かう人間模様(深刻ですが)に共感します。中世のペスト時代のことは想像でしか分かりませんが、これが書かれたのは1940年代、小説の時代設定も同じで、近代的な状況での災禍なのです。電話もあれば自動車もある文明の都市における非常時の人間たち。 始めの小さな兆候、次第にわかる状況におびえる市民、行政の不備に怒る人々が現れ、専門家の意見は分かれ、ゆっくりした整備、数字は跳ね上がり、社会生活の不自由、別れの悲嘆、宗教の介入、あきらめと通過への希望。そして絆。嵐が過ぎ去る。地味にとんだ普遍的な文学だと思いました。 今、に示唆があるか?この描かれた70年前のように、現代の疫病はそんなに簡単ではないという気はします。世界がつながってしまっていますもの。封鎖はあってないようなものですから。カミュさんも真っ青。いえ、予言はしていらっしゃいます。超現代の試練です。
12投稿日: 2020.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだか人々の反応が、今世界で起きていることとあまりにもぴったりきすぎて驚いてしまった。カミュの洞察力がすごすぎる(←ボキャ貧。。
4投稿日: 2020.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログペストが蔓延し、隔離されたアルジェリアの港町で、人々の不条理な現実への態度を描く。この不条理というのは説明しがたいが、人間の思い通りにはならない過酷な現実といえると思う。カミュの作品にはこういう人間のあり方を題材にしたものが他にもあるが、この小説の特色は、群像劇風に、不条理な状況下にある様々な人間にある。ペストに遭遇し、普通の生活を奪われた人間が示す様々なふるまいや感情、美徳、信仰が語られていく。 この本をどう読むかと問われれば、一つにはこの本の解説のように、小説の人物群を、不条理な現実を直視した「不条理人」とそうでない人に分けて理解し、カミュの不条理の思想を読み取ろうとする読み方がある。しかし私はむしろ、不条理を直視して生きる人にカミュの思想があるとみなすよりも、何人も逃れることのできない不条理な現実とそこから逃れていこうとする人間の切とした欲求の純粋さ、現実とその欲望との葛藤をこの小説に読みたい。 「抽象はランベールにとって、およそ彼の幸福と相反するものであった。そして、じつをいえばリウーもランベールがなるほどある意味においては正しいことを知っていた。しかし彼はまた、抽象が幸福にまさる力をもつものになることがあり、その場合には、そしてその場合にのみ、それを考慮に入れなければならぬ、ということを知っていたのである。」(p107)恋人に会いたいがため、ペストの町から脱出を試みる記者ランベールと、ペストへ効果の乏しい治療を続ける医師リウー、ランベールはペストの拡大防止のための町の封鎖措置を「抽象」と呼び逃れようとした。この文章はリウーの独白で、ランベールの幸福への情熱にたいする思いである。「不条理人」リウーがランベールへ向けるこの理解は、カミュがただただ不条理の哲学を書いた小説家であるわけではなく、人々の普通の幸せへ関心を寄せることができた人間であるのだと感じた。
0投稿日: 2019.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログアルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。(e-honより)
0投稿日: 2019.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログQ.あなたにとってペストとはなにか? A.際限なく続く敗北です。 それでも治療を続けるリウーさん。かっこいい!
1投稿日: 2019.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
やっと読んだ。異邦人どまりのカミュ読者だとこんな文章の人だったっけと思うけど抑制を効かせつつ後半にかけて感情の昂まりが見事に表された筆致だった。閉鎖された街にはゲットーを思うし、バタバタ人が死んでいく状況を機械的に処理する毎日はナチス強制収容所から着想を得ているのだろう。 ペスト蔓延、毎日の医師の奮闘、友が斃れていく日々、無垢な子供の無意味な苦しみ、その極限状態の果てに見出したもの、得たものがただ「知識と経験」のみだったというのはあまりに不条理で、それを今後も受け入れていくのはまた一種の地獄かもしれない。知らなかった頃には戻れないのだ。
0投稿日: 2019.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書会の課題本。ペストのパンデミックを描くことで、限界状況に置かれた人々を丹念に綴られている小説。世界滅亡をテーマにしたSFなどにも大きな影響を与えたことで有名。「自分が同じ状況に置かれたら、どうするだろう?」と想像しながら楽しめた。著者の戦争体験から想起された本作だが、近年に起きた災害の被災者に重ねて読むことも出来ると思う。
0投稿日: 2019.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むのに1ヶ月かけてしまったけど、読後感は充実。 不条理の文学と言われる所以が感じられたし、想像よりも前向きな雰囲気の作品だった。 一番共感できるのは、ランベールかな。
0投稿日: 2019.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年は名作を読んでみよう(毎年思っているような気がする。。。)と思い、図書館で借りてみた。 ペストが流行して隔離された市の中で、医者のリウーをはじめとした登場人物たちが格闘する。 中盤、リウーやタルーが対ぺストのための医療・衛生組織を立ち上げた際に、それを当たり前のものと捉える事によって、人間の良性・可能性を肯定しようとする著者の記述を読んだ時、それまでは人間のネガティブな面をクローズアップし、それを肯定して弱者に寄り添うような小説を読む事が多かった気がするので、「おや?なんか真面目だぞ?」と少し違和感を覚えたものの、特にそれで集中力が途切れるような事もなかった。 最後まで読んでみて、個人の幸福を追い求めるのではなく、医者としての職務を全うし、最終的には極度に理不尽で過酷な状況下での知識とは、死んでしまった大切な者たちの記憶と、今は存在する愛するものたちもいつかはいなくなってしまうという事を認識する事だととらえ、かつそれはペシミズムではないリウーや、死刑執行を見てしまった時から究極の理想を追い求めるタルーには、今の私とはかけ離れすぎている崇高さがあり、読んでいて情けなる思いだった。
0投稿日: 2019.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ"彼らの姿は、あらゆる明証をものともせず、われわれがかつてあのばかげた世界、人間を殺すことが蝿を殺すことと同じ程度に日常茶飯事であった世界ーーを経験したということを、悠然と否定していた。" 最初は会話を挟んでは、毎回リウーが町並みを見ては、沈鬱な町の雰囲気を描写している場面が、多く、すごく長ったらしくてうんざりした。 文脈が、繋いで、繋いでなので、どこを指してるのかわからなくなるシーンがあった。 後半の友人の描写は、すごい。そこだけでも、読む価値はあった。
0投稿日: 2019.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界史でチラッとだけ触れた黒死病について、史実として触れるだけでなく物語として触れてみたいなと思って読んだ。 患者の話というより、その周りの街や人々の話だった。 正直怖いもの見たさで読んだのもあって、会話よりも状況説明がえらく長くて初めは物足りなさを感じた。でも世界史の教科書では触れられない部分のことを考えるきっかけになったのは良かった。 「大粒の涙が〜鉛色の顔面を流れ始め、…」 鉛色の顔面ーーーー‼︎‼︎‼︎ フィリップ少年が死ぬ場面が印象に残った。
0投稿日: 2018.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災後の状況をこの作品になぞらえた文章をたまたま2つも別々に見つけた。そこで読んでみる事に。 日常をむさぼっていた都市が、徐々に不条理な事態に直面する(徐々に、というのが地震と異なるが、原発や電力の問題が当初の予想を超えてエスカレートしていく様は少し似ていないか)様子を淡々と描く前半から、そのペストと言う事態の只中で、確たる希望もないまま闘う人物の姿が描きこまれていく後半へと盛り上がっていく。主人公のリウーやともに保健隊で働く仲間たちは、彼らを動かす原動力こそ違えど、ヒロイズムでなく平凡に自分の職務と思うところを果たしていく。世界は圧倒的な力で人間を打ち負かすことがあるが、それでも抗うことに人間の人間たる所以があるのだろう。 しかし、フランス人が書いたせいか、60年の隔たりのせいか、翻訳と言うフィルターのせいか、単に趣味の問題か、どうもセリフや叙述がまだるっこしく思える(これでも簡潔な文体と訳者は言うが)。それに主題も、ボクにとってスッと腹に落ちるものなのだが、スっと落ちすぎて引っ掛かりが足りない感じ。読みきれていない部分もあるのだろうけれど。
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュの代表作のうちの一冊。 原題:La Peste NHK、Eテレで放送中の「100分de名著」で取り上げられていた。 災厄の始まりは小さなものだった。 ネズミの死骸、それは一般の人は気にも留めない小さな予兆。 しかし、市内全土に広がっていくのに、多くの時間は要らなかった。 恐怖と、悪と、戦うこととは一体どういったものか。 理不尽なことと向き合うこととは。 物語は淡々と綴られていく。 どんなに悲惨な出来事であっても、どんなに不条理な出来事であっても、生きている我々は歩みを止めてはならない。 ペストと、戦い、抗うのだ。 ペスト=悪があることを知り、それを思い出し、友情を知り、思い出し、愛を知り、思い出し、それが唯一の、我々がペストに勝ちうる方法なのだ。 「知識と記憶」(431頁)だけが。 なぜならペストは死ぬことも、消滅することもないからだ。 「人間に不幸と教訓をもたらすために」(458頁)それはあるのであり、たとえ一度は恐怖から逃れられたとしても「この嘉悦が常に脅かされている」(同)ことを忘れてはならない。 我々は、理不尽な恐怖に直面した時、何をなすべきか? いやそもそも、それが来る前に何ができるのか? 私たちにできることはそう多くはない。 過去の災厄を、今まさに来んとするそれを、見なかったこと、なかったことにして忘却の彼方に追いやるのではなく、正面から対峙し、ありのままを認めなければ、後手に回った対策は何の意味もなさない。 そしてそのことだけが、ペストに立ち向かう方法なのだ。
7投稿日: 2018.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュ 「 ペスト 」 ペストとの戦いを描いた不条理文学。 ペストは ナチス支配を暗喩するものとして 読んだ。カミュの反抗とは「死を意識しつつ死を拒否することに 生の価値を見出すこと」と捉えた ペストが意味するもの *盲目的態度→ナチス支配下の市民生活? *ペストが与えるのは 追放の状態、単調 *ペストが奪うものは 愛の能力(愛は未来) ペストの影響、効果 *同情がムダである場合 人は同情に疲れてしまう *町の全生活=一人一人の幸福とペストの陰鬱な戦い *ペストと戦う方法は 誠実さ〜自分の職務を遂行する *ペストとの戦いで 人間が得られるものは 知識と記憶 「悪は〜ほとんど無知に由来する〜善き意志も豊かな知識がなければ 悪意と同じ被害を与えることがある」 著者の宗教観、死生観 *人生の後半は 下降期であり、下降期において 人間の一日一日は 彼のものでなく、どうすることもできない *死は何ものでもない。それは一個の事件 *この世の秩序が 死の掟に支配されているかぎり〜神に目を向けず〜あらんかぎりの力で 死と戦った方がいい
1投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「100分で名著」を観て。 どうにもならない地道な戦いを続けながら、パンデミックの嵐のある夜に海で泳ぐシーンの、静謐な美しさが読後一番印象に残っている。 人智を超えた災害において、ひとの在り方、心の持ちようなど、ドラマチックな感情の起伏はありがちだけど、この本が他と違うのは、その、静かさにあるように思える。 日常の時間は、ただ、淡々と過ぎるのだなと思った。
0投稿日: 2018.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュは初めて。いわゆる不条理文学の代表作。商業都市が突然ペストに見舞われ、町が閉鎖・隔離され、残された人々がこの死の伝染病と向き合う様を描いたもの。ペストが蔓延していることを認めたがらない市長や医師会長のせいで対策が後手後手となること、絶望的な状況を神の怒りとして思考停止してしまう人々、不法手段を使ってでも町を出ようとする人々、淡々と己の役割を果たすことで病気を戦う人々などが淡々と描かれている。過酷な状況に人々は慣れてしまうし、解決の目を見たときにはこれまでの状況をあっさり忘れてしまうもの。ヒーローが現れて市民を救うでもなく、画期的な治療法が見つかってハッピーエンドになるでもない。戦争や伝染病、自然災害だけでなく交通事故や事件に巻き込まれるなど、不条理なことはむしろ日常にあふれていて、自分の身に降りかかったときにどう振る舞うのか考えさせられる。
0投稿日: 2018.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「すっかり削ってしまいましたよ、形容詞は全部」 フランス文学ってみんなこんななの? もっと文章、削れるだろ、推敲しろ推敲、伝わるもんも伝わらんわ、と思いながら読んでました。ほんとつらかった……。訳文が悪いのかなぁ。それか絶望的なまでにフランス文学か、カミュの文章と合わないか。文章見直せばこれ、半分くらいの量にできませんかね。最後のグランを見習って修飾語を削りなさいよ。 話の内容、ストーリィについてはうーん、ペストが起こって収束するまで。結局なんで助かったのか分からないひとも多いし、偶然なのか。収束した理由もないし。最後リウーもペストにかかって死んじゃうのかなと思ってたら、タルーのほうが死んじゃうっていう。頑張ったんだからゆっくり休んでほしいです。
0投稿日: 2018.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ知人から「今読むべき本」として勧められた。 海外小説なのと古いのとでかなり読みづらく、時間がかかった。登場人物を忘れてしまいがちなので、表を用意しておけばよかったかも。 なるほど、「今」と重なる部分が多々。
0投稿日: 2017.04.252011年4月の読書メモより
震災後の状況をこの作品になぞらえた文章をたまたま2つも別々に見つけた。そこで読んでみる事に。 日常をむさぼっていた都市が、徐々に不条理な事態に直面する(徐々に、というのが地震と異なるが、原発や電力の問題が当初の予想を超えてエスカレートしていく様は少し似ていないか)様子を淡々と描く前半から、そのペストと言う事態の只中で、確たる希望もないまま闘う人物の姿が描きこまれていく後半へと盛り上がっていく。主人公のリウーやともに保健隊で働く仲間たちは、彼らを動かす原動力こそ違えど、ヒロイズムでなく平凡に自分の職務と思うところを果たしていく。世界は圧倒的な力で人間を打ち負かすことがあるが、それでも抗うことに人間の人間たる所以があるのだろう。 しかし、フランス人が書いたせいか、60年の隔たりのせいか、翻訳と言うフィルターのせいか、単に趣味の問題か、どうもセリフや叙述がまだるっこしく思える(これでも簡潔な文体と訳者は言うが)。それに主題も、ボクにとってスッと腹に落ちるものなのだが、スっと落ちすぎて引っ掛かりが足りない感じ。読みきれていない部分もあるのだろうけれど。
3投稿日: 2017.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹氏の本かなんかで出てきて興味を持って買ったが、しばらく放っておいたのをやっと読了。異邦人やシーシュポスは、どこか中二臭さのある作品だが、ペストは徹頭徹尾大人な小説だと思った。最初は少しダラダラした感じで入り込めなかったが、ランベールが脱走をやめたあたりから最後まではここの登場人物の変化に胸がうたれる。特に、解放後の描写、喘息持ちの爺さんのなにも変わらない感じなんかが印象に残った。構成も含めてドラマがあり、長い映画を一本観たようなそんな感じ。いつか再読したいな。
0投稿日: 2017.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログペストが蔓延した町での人々を描く。 カミュも読んだことの無かった作家のひとりで、最初は「異邦人」を探していたのだが見当たらず、こちらを読んでみた。 医師リウーを中心に淡々と書かれた作品で、ペストによって翻弄される人々の様子が伝わってくる。 こういった感染症は現代でも多くあり、その度に人々の反応は様々で、過剰なまでに恐怖に取り乱すひとから、何ら変わらない日常を送るひとまで正に千差万別というところだ。 物語の中でキリスト教の考えが司祭の言葉を通して書かれているところがある。 神が人間に反省と信仰を促すためにペストを蔓延させた。 こういう考え方は日本人には理解しづらいところだと思う。 聖書の中でも神はしばしば人間に、深い愛による厳しすぎる試練を与えている。その結果生命を落とす者の中には、何も悪いことをしていないだろう幼児なども含まれている。一部の人間の目を開かせるために生命を落とす子供は不憫としか言えないところだが、人間は生まれながらに罪を背負っているという考えもキリスト教にはあるわけで、考えはじめるととても難しい。 ただ、キリスト教徒のひとりであるわたしとしては、人間の抗いきれない運命に接したときにこそ心の拠り所となるのが信仰であるはずなのに、結局信仰だけで恐怖や悲嘆をなくすことができないのであれば、信仰に意味はあるのか。こんなことを考えたりもした。 それでも信仰を捨てようとは思わないのだけれど。 この作品はきっと読み返すたびに感じることが変わっていくと思う。 次に読み返したときに何を思うのか楽しみにしたい。
0投稿日: 2016.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ分量としては全く多くないが、中だるみしてしまって、展開を忘れてしまいながら読了した。 すばらしい指摘・観点からのレビューがたくさんあり、自分の理解の浅さに恥じ入るばかりである・・・ 是非再読したい本となった。
0投稿日: 2016.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログペストの極限的現実を通して、権力、心理、宗教、哲学、医学を重層的に語りつつ、最終的には全ての生がペスト性=人の不幸の上に自分の幸福を築いている事実を切実に暴く。 一人として不必要な登場人物はいなかった。 タルーの「共感すること」という一言。リウーと二人で海水浴をするシーンがクライマックスか。
0投稿日: 2016.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ命というものの卑小さ,報われなさを感じた.しかしこの小説から結局何を受けたのか自分の中でまだよくわかっていない.時間を置いてまた読もう
0投稿日: 2015.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ感情的にならない、抑制された文章が良かった。 タルーの過去の話には感銘を受けた。自分では気付かぬ内に殺人者の側にいるかもしれないということ。犬や猫を可愛がりながらも、毎日のように牛や豚を平気で殺しているのが人間なのだ。ペスト菌が人間を殺したとしても、それ自体が何か間違ったことであるわけではない。人間から見てそれが脅威であるだけのことで、人間だって他の多くの生き物を大量に殺し続けている。人間同士でさえ殺し合うくらいなのだ。 「ペスト」は何を意味しているのか。それは、病気や戦争、災害、そういうすべての不幸だ。人間にとっての不幸。忘れた頃にやって来る、不幸。 それに立ち向かうにはどうすればいいか。もちろん、立ち向かわない、という選択肢もあるだろう。どうしても人間が生き残らなければならない、という理由は無いのだから。そのまま絶滅に一歩足を踏み入れるのも、もっと大きな目で見れば悪くない選択だ。 それでも生きたいならば、必要なのは「知識」だ。無知ほど怖いものは無い。無知な人間は往々にして視野が狭く、その狭い視野の中で思考するので、間違った結論を下す。それなのに、自分は万能であるかのような思い違いをする嫌いがある。すべてを知ることは出来なくても、知ろうとすること、世界には自分の知らないことが無数にあることを知ること、一つの物事も複数の視点から眺めてみること、そういう努力。それを怠る者は、人間自身にとっても脅威になる。 人間は決して生きることを優遇されているわけではないのだ。
0投稿日: 2015.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ『異邦人』(歌の名前ではないですよ)で有名なフランスの作家による寓話的小説ですが、いろいろな災害と重ねて読めます。
0投稿日: 2015.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログロビンソンクルーソーの作者による16世紀にイギリスを襲ったペストの大流行を描いた作品。 これを読んでも、ペストには詳しくなれないし、どのような病気で、どんな対策を取れば良いのかは明らかにならない。 しかしながら、ただ、淡々と、単調とも思える筆致で、羅列されてゆくペストに係る悲劇の圧倒的物量だ。ノンフィクションでは無い が、圧倒される。 そして、この時代の病の知識の無さを笑えない。 今の私もペストについて「死の病」と言うことくらいしか知らないし、ましてや未知の病気が大流行すれば同じようなことをするに違い ない。いやむしろもっと酷いことになるかもしれない。 私には、過去の無知さを笑えない。
0投稿日: 2015.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
単なるペストとオランの人々との戦いでないところが非常に興味深い。しかし相性が悪いのか、自分の理解力が足りないのか所々分からない、もしくは分かりにくい部分があったのが残念。時間をおいて再読しようと思う。
0投稿日: 2014.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュということで カミュの筆致を尽くした思考実験。 巻頭に引用されているデフォーの言葉にある通り、存在するものを存在しないもので表現することでしか、ひとは現実を共有するすべがない。 今回の思考実験では、たまたまペストという形をとったに過ぎないが、これはあらゆる監禁状態にあてはまるはずだ。現代はケータイやインターネットがあるから状況は当時とは違うと思うかもしれないが、電波塔がなければ電話もできないし、先の地震で見たとおり電気がなければ連絡はできない。通信規制がかけられる可能性だって十分にありうる。それに仮に使えたとしても、監禁状態にあるという事実は変わらないし、苦しみを共有することなどできはしないのだ。時代によって状況が変わるような、そんな小さいことをカミュは考えていない。真理はどの時代であっても、どんなひとであっても正しくなければ真理ではない。 この一連の監禁状態を語る「筆者」は、ただ歴史の語り手として、かなりシンプルで淡々と叙述を進めているにも関わらず、描かれるひとびとへの冷淡さをどこか感じさせない情熱が見られる。 名前を与えられた人物たちは皆、監禁下における様々な人種の代表として、各々のやり方でペストに立ち向かい、そして、きっちりとその役目を果たし、死んでいったり、辛うじて生き延びたり、狂気に落ちたり、その彼らの生き様すべてを以て、自分という存在を力強く伝えてくる。 あとがきではカミュは当時の時代から、第三の道を探しているとか、神は無用だと考えているとか、書かれているが、彼は「反キリスト教」であって、神を否定などしていない。彼の掲げる反キリスト教とは、わけもなく祈りにすがろうとするそこにあるのだと思う。祈りの本質、神を考えるというその行いをしない「教」を彼は嫌うのだ。 巻末で語られている通り、「ペスト」はどこにでもあって、その牙はいつむかれるかわからない。どこにでもあって、どこにもない。人間から見ればそれは「不」条理なのかもしれない。だが、そもそも存在するということ自体に理由はない。存在そのものが不条理なのだ。そうである一方、事実として今ここに存在しているということは、やはり条理である何物でもない。ひとの力ではその本質はどうにも掴み得ない。掴み得ないからこその不条理。だからこそ彼は、不条理としてのペストに立ち向かう人間の力強さを描き出し、その本質に迫り続けようと善く生きるひとの姿を描き出したのだ。不条理をどうにかできるとか、不条理の前ではひとは頭を垂れて諦めるより他ないとか、こんな不条理だらけ世の中なら死んだ方がましとかそんな下衆なことから彼は書いているのではない。 彼は「わかってしまった」という点で、やはりサルトルよりもずっと優れた作家であると感じる。
1投稿日: 2014.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ鼠の媒介によってペストが流行し、街全体が閉鎖される中での人々と、医師がペストに立ち向かう姿。ナチスに対抗した人々のレジスタンスの比喩なんかじゃないなと思う。旅先に持ってきた一冊なのだが、飛行機の出発情景が浮かぶ。子供が大泣き大暴れして、親や乗務員が必死に宥めていた。さして大きくもない飛行機で折角の旅立ちに弱った。でも電源を切れと案内されてるのに、ギリギリまで携帯で通話していたオヤジの方がよほど迷惑だった。頑是無い子供にモラルを提示することも出来ない大人。閉じた空間の非日常とは、実は日常にゴロゴロしてる。 エボラ出血熱やデング熱に右往左往する世相にコミットする。ダニエル・デフォーの同名作品の引用で始まる。鼠の大量死から最初の犠牲者が出てあっという間にパンデミックとなったペスト。ここに至って当局は街を封鎖する。ソドムとゴモラの故事を持ち出すパヌルー神父の説教を真に受けて疫災が通り過ぎるのを待つ人、それでも自分だけは逃げようとする人。風が更に病気を街中に行き渡らせ灼熱酷暑の封鎖された街で懸命に治療に当たるリウー医師は、別の病気での療養の為に妻を転地させたばかり。 子供の死さえも神の意思と説くパヌルーを、分裂と矛盾のなかに生きてきたタルーは、とことんまでいくつもりなのだと評する。街から脱出しようとしたランベールはリウーやタルーと一緒に懸命に働いた。タルーが発した臨終の言葉は「悪霊」で殺されたキリーロフと同じ。リウーは嘆いたね。コタールは当に鼠男。ペストが蔓延して封鎖された街で典型的人間のダイナミズムを見て、笑ってられるのも怒ってしまうのも僕らは部外者だと安心しているからで、震災や伝染病や戦争と隣り合わせのリスキーな社会で、安穏は未だに許されていない。現代への警笛の書だ。
8投稿日: 2014.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこちらも再読。 今読んでみると、ペスト発生~蔓延するまでの展開が非常にサスペンスフルだと感じる。 最初に読んだときは何やら小難しいことを考えていたような記憶があるが……。
0投稿日: 2014.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログカミュの本を久しぶりに読んだけど相変わらずおもしろかった。なんていうかすごく不条理な話を誠実にちゃんと書いている。こういう文体書ける作者とか現代にいるのかな。なんとなく読んでいてカフカの「審判」にもそういった誠実さを感じたのを思い出した。 ペストによってある町が封鎖され、絶望を味わいながらその町の中で生きていく人々の心理や行動を詳細に描いた内容。(最終的には希望を持つが) 一見こういった絶望的な状況でも、コタールのように幸福を感じる人間もいるのは納得。日々の生活に絶望を感じている人間は、そういった絶望的な状況になると逆に幸福を感じ、ほとんどの一般人のように日々の生活に絶望を感じていない人間は、そのような状況に陥ったら絶望を感じるのだろう。 自分の住んでいる町がそのような事態に陥ったらいったいこの町の人間たちはどうなるのだろうと少し想像した。 「人間にはいろんな病気をかけもちすることはできない」というのは確かに(笑)
0投稿日: 2014.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルどおり、空前の「ペスト」禍に見舞われて、ほとんど町に閉じ込められてしまった人人の物語。一見、このような状況下には絶望感しか漂っていないように感じられ、じっさい本作にもそのような感情を示す場面が多数登場するため、けっして間違った感想ではない。ただ、本作が描き出しているのは、絶望というよりはむしろ希望の本質なのではないか。その象徴的な例が、新聞記者レイモン・ランベールの行動である。「部外者」としてたまたまこの騒動に巻き込まれてしまったランベールは、当初さまざまな手を尽くしてこの町を脱出することを画策する。しかし、しだいにこの考えは変わり、最後にはこの町に留まり続けることを決める。なぜか。やはり、こういった困難な状況にこそ、かえって希望を見出したからではないか。思えば現代の日本においても、3年前に凄まじい災禍が国内を襲ったが、そこで盛んに喧伝されたのは、流行語となった「絆」をはじめとする前向きな言葉の群れであった。逆説的なようだが、希望は絶望のなかから生じてくるのである。そのもうひとつの例が、イエズス会の神父・パヌルーである。神父といえば、絶望したときに縋るなど、どちらかというと希望を感じる存在であるとは思うが、ここでは病没した少年すらも罪業によるものと断定してしまっている。当然反撥も喰らうのだが、このような発言にはもはや希望はない。最後のよすがとなりうべき存在なのに、そこには満腔の絶望が描き出されている。ここでもやはり逆説が生じている。この小説はナチスに対するレジスタンス運動のメタファーとして読まれることも多いようだが、むしろわたしには希望と絶望の本質を描いているように読めた。
0投稿日: 2014.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログペスト細菌兵器を含め、人類自らが伝染病の要因を築きつつあるとはあまりに愚かしく、さすがにカミュも想定すらしなかったろう。
0投稿日: 2014.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ20世紀フランスを代表する小説家・劇作家アルベール・カミュ(1913-1960)が第二次大戦直後の1947年に発表した長編小説。アルジェリアの都市オランがペストに襲われて封鎖されてしまいオランの人々が病禍に抵抗するさまを描いた本作品は、発表当時、第二次大戦中ナチス・ドイツの支配下にあったフランスに於けるレジスタンス運動の比喩として読まれたが、カミュ自身はこうした固定的な読まれ方をよしとはしていなかったようだ。ひいては、自らの作品を「実存主義文学」として括られることも拒否していたという。 物語の叙述は、舞台となっている北アフリカの都市の気候のように重苦しい暑さと、困憊した不安な陰鬱さと、そこで登場人物たちが自らの生をその都度創っていこうとするところの「絶望」と、そうしたものによってべたりと貼りつかれているようだ。ペストという〈悪〉に反抗する人たちは、決して〈善〉の奥行きの無さを以ては描かれていない。カミュは、〈善〉を定型的に実体化することを意識的に拒んでいる。 「今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです」「どういうことです、誠実さっていうのは?」「一般にはどういうことか知りませんがね。しかし、僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています」 「英雄」など現れることはない、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】、彼らは抗った。「特効薬」など無かった、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】、彼らは抗った。「奇跡的救済」など起こり得べくもない、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】、彼らは抗った。 □ 「不条理」と「反抗」、これはカミュの文学に於ける最も切実な主題であると云っていい。 では、カミュ云うところの「不条理」とは如何なる事態を指しているのか。彼の哲学的エッセイ『シーシュポスの神話』(1942年)によると、彼の考える「不条理」とは、一応は以下のようなものであると云える。人間には世界を理性(logos)に基づいて意味付けしようとする本質的な志向性があるが、世界の側は人間の理性を一切受け付けずこの志向性を常に裏切る。このように人間と世界とが相対立した状態、人間と世界を結ぶ唯一の関係性が、「不条理」である。 生は、生の前には、何も無い。全て在ることどもは、生の後に続くものである。生それ自体以外に在り得ないという事態にあって、我々が我々自身以外に在り得ないところで、全てを選んでいくのだ。まず初めにあるところの生、そこでの生による選び。そうした、人間存在のそれ以上遡及することが不可能な突端・縁とでも呼ぶしかない次元を、カミュは何とか描き出そうとしたのではないか。この次元に於いて問題になることだけが真の問題なのだと、それ以外は擬似的・副次的な問題に過ぎないのだと、そのことがこの作品の中で反復変奏されている。そしてこの次元に於いてこそ、≪連帯≫が可能になるのである。 世界が意味を峻拒する不条理、その無-意味の只中に投げ出されただけの何者でもない"現"存在であることに絶望しながら、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】、そこから無を超越して生を創り出していく、他に始める場所など無い。所詮は、いつと知らず何望むべくも無く、ただ何処でもあって何処でもないところの"そこ"に投げ出されただけの"現"存在である。「神」や「幸福」や「生の意味」などの形而上的なるものは、日常的・即物的なるものと同列に、生の後に在り得る副次的存在者の一つであり、その前後関係を転倒させてはいけない。 生は何ものにも束縛されない。生は自由である。生は何ものをも選ぶことができる。生は、生の後に続くあらゆる概念的規定を、常に/既に如何様にも超越し得る可能態である。それゆえにこそ、生は全ての責任を負う。この絶対的自由と絶対的責任に耐えられなくなると、先に述べた前後関係を逆向きにして、仮構された超越者への依存へと陥る。これが、不条理を不条理として受け止めずにいられる自己欺瞞、絶望を絶望として向き合わずにいられる自己欺瞞、則ち頽落である。「・・・絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである」。 さて、生は、世界という無-意味に於いては何者でも在り得ないと述べた。また、人間存在は、あらゆる概念的規定を超越し得る可能態であると述べた。ところが、この事実的世界にあって我々は何者かとして在る以外に無い、何らかの存在者としての在りようを負うしかない。そこで我々は自らの実存を賭けてその「何か」としての存在者を選ぶ。 「いったい選んだんですか、あなたがたは? そうして、幸福を断念なさったんですか?」 こうして可能態としての実存は、不可避的に「何か」という存在者として限定される。世界に意味付与しようとした当の人間存在が、却って言語的概念的に規定されてしまう。ところが、自己が規定されてしまえば、それに応じて世界は意味付与されてしまう。ここに欺瞞が生じる、そこにあっては世界はどこまでも虚構に過ぎない。しかし、実存が上に述べたような可能態である以上、常にこの限定を峻拒することができる。これは、世界と人間とのあいだの唯一在り得る関係としての「不条理」という事態と表裏一体である。そして、自己は、次の瞬間にはまた別の「何か」としての存在者に限定されてしまう。こうした実存の無際限の運動は、ロマン主義的アイロニーとも呼ばれる。 このようにして、人間存在は、必然的且つ不可避的に二重の敗北を負い続けることになる。それは無際限の敗北である。世界への意味付与の闘争と、自己への概念的規定からの逃走と。この、敗北が予め定められている闘争・逃走に、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】、赴かずにはいない、これが「反抗」だろう。如何ともし難い「不条理」への、赴かずには在り得ない「反抗」。これが人間存在の自由、不可能性の内にあるしかない自由の在りようだ。それは追放者の自由である。そもそも追放される場所すら無い者の自由である。則ち、帰る場所の無い者の自由である。そして、何者でもないという根源的-無、則ち自由によって、その無条件性によって、人間は他者と≪連帯≫が可能となるのだ。 「とにかく、この世の秩序が死の掟に支配されている以上は、おそらく神にとって、人々が自分を信じてくれないほうがいいかもしれないんです。そうしてあらんかぎりの力で死と戦ったほうがいいんです、神が黙している天上の世界に眼を向けたりしないで」「・・・。しかし、あなたの勝利は常に一時的なものですね。ただそれだけですよ」「つねにね、それは知っています。それだからって、戦いをやめる理由にはなりません」・・・「際限なく続く敗北です」 生は、【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】という反語の内にしか在り得ない。 このように、「不条理」に対する予め敗北が定められていながら【にもかかわらず/それでもなお/それゆえにこそ】無際限に繰り出される反語としての「反抗」、そこに生は自由であるのであり、この生の自由こそ、そして自由であるがゆえにこそ可能となる他者との≪連帯≫こそ、カミュが手放すまいとして何とかして表現しようとしたものだろう。ところで、「不条理」、則ち世界の在りようが根源的に無-意味であるということ、これを意味付与の手段である言語によって表現しようとする企ては、それ自体が矛盾を孕んだ不可能事である、「不条理」である。カミュにとって、書く行為それ自体が、まさにこの「不条理」への際限無き「反抗」だったのだろうか。 「僕が心をひかれるのは、人間であるということだ」
0投稿日: 2014.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この小説は、架空の話です。 アルジェリアのオラン市でペスト(黒死病)が流行した。その市内で超人的努力する医師「リウー」や牧師などいろんな個人が登場しますが、最初のうちはそれぞれの意見がぶつかり合いますが、それでも協力し合います。その結果ペストは終息しますが、これに関わった人物のその後が多少書かれています。
0投稿日: 2014.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ町がペストに侵されて行く様子、町がふたたび開かれるまでの人々の様子を緻密に淡々と綴られる文章は意外にも不思議と心地良く感じた。訳の古さはけっこう読みづらくもあったが、読み応えたっぷりの一冊だった。読んで良かった。素晴らしい傑作だと思う。異邦人よりも面白いかもしれない。
0投稿日: 2014.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ西欧の、特にフランスの文学は「構築美」であるなと思う。加えて本作は、長編ながら一分の無駄もない文章が驚異的。さながら、鍛えられた競走馬の筋肉のよう。一文を書き出す上で、どれだけの言葉が捨てられたのだろうか。
0投稿日: 2014.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ7年ぶりに読んだ。ガツンとやられた。 作品のパワーに圧倒されてうまく言葉が出て来ないけど、人生で何回も読んでいきたい作品。人間のあらゆる側面が詰め込まれていて、中でも誠実さの力を絶対に信じているところに惹かれる。 大好き。
0投稿日: 2014.01.19
