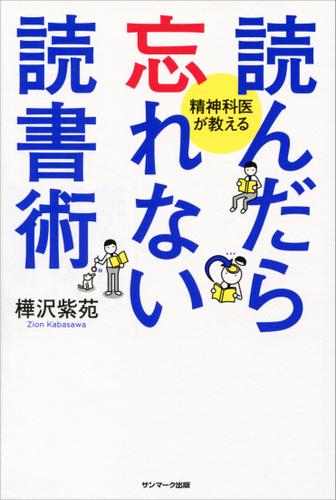
総合評価
(877件)| 212 | ||
| 354 | ||
| 176 | ||
| 35 | ||
| 9 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みたい、で登録してたのは「読書脳」 だったんだけど、図書館になかったので、 同じ著者のこちらを。 月に7冊読めば、読書量で 日本人の上位2%に入れるんですってよ? 読書量と収入も比例するんですってよ? ブクログに登録してる皆さんは、 頭が良くてお金持ち?ほんとに? 命名がお得意な方だな、と思いました。 鉄は熱いうちに打て読書術、とか 温泉採掘読書術、とか。 転スラかっ!リムルかっ! 楽しいから読む。大賛成。 読みたい、に登録した本の中に 思いがけない気付きがある瞬間が感動的なので、 すんません、我流でしばらく続けまーす。
2投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ通勤時間、スマホを見る時間が減りました。記憶力がない自分を嘆いていたけど、たぶん本を読むことを義務化していて楽しめていなかったので、記憶するモードになってなかった。あと、読んだら読みっぱなしで、本の中身を頭の中で反芻してなかったのも要因。このブクログを活用していきたいと思います。
1投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の目的は「読んだ後に行動が変わること」という言葉に感銘を受けた。 ただ、漫然と読むだけではいけなくて読んだ後の行動変容が重要であると痛感して、このアプリを始めてみた。 アウトプットによって、内容を自分の血肉にしていきたいと思う。
1投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ※一部内容に関する記載あり 「何かを『変えたい』と思ったら、まず本を読むことをお勧めします。」(p.56 第一章より) 読書初心者である私が本を読みはじめた際、「自分がよんだ本は果たして私に身に付いているのだろうか?」と思い購入。 題名から分かる通り、読んだ本の内容を確実に自分の物にする読書の手法が書かれているが、それだけでなく、「なぜ読書は有意義なのか」、「自分にとっての良書を買うにはどうすればいいのか」、「Kindleをどう使いこなすのか」など、読書術というより「読書論」に近いような興味深い内容もあり、実に読みごたえのある一冊だった。 実はブクログを始めたのも本書の影響である。 おすすめポイント: ①思わず実践したくなる読書術が満載 目次を見るとわかるが、○○読書術という文言と共に読んですぐに実践できるノウハウがたくさんあり、権威ある科学的根拠が説得力を持たせている。 ②読書のテクニックだけじゃない! 自分の読書に導入できる技術だけでなく、読書によって得られるメリット (↑これを読むとますます読書をしたくなる) 本をどう選びどう買うか 電子書籍の特徴など 読書自体の効果、本を読むとき以外の本にまつわる状況についても充実した知識が得られる。 ③読書時の先入観が改善するかも 私は読み方(速読や精読など)を意識して行う的なことも書いてあるのかと思っていたが、筆者は速読でも精読でもない意識すべきことを私に教えてくれた。 ④科学的読書論+読書術が格安で読める 上記の充実した内容が、中古市場ではほぼ500円以下で取引されており、これから読書を始めるという人も手に取りやすい。これからの読書を有意義にするために購入することを私は勧める。 ⑤著者の本当のねらい 本書は表紙を見て分かるように精神科医がわざわざ読書についての本を書いている。なぜ医者が読書術についての本を書くに至ったのか? 読書に対する著者の想いと願いが本書において触れられている。
6投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログきっかけ↓ YouTubeを垂れ流す毎日に飽きてきたこの頃 急に「本を読もう」と思いました。 同業の先輩に 「本を読み出したけど、内容をすぐ忘れてしまう」 という相談をした際、紹介してもらったのがこの本です。 ↓感想 読みながら なぜ、読書の方法を学ばずにここまで来てしまったのか。と感じる内容でした。 読み切ることを目標としてしまい、1週間後にはほとんどの内容を忘れる。 そんな今までの自分をぶん殴りたくなりました。 読書をすることによるメリットや、忘れない方法、作者の思いが詰まった素晴らしい本でした。 とりあえずマーカー引いてアウトプットしまくります!!!
1投稿日: 2025.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読んだら忘れない読書」にするために著者が勧めているのが、「アウトプット」をすること。 その手だてのひとつとしてSNSへの投稿について書かれているのだが、私はこの点を詳しく知りたくて本書を購入したので、もう少し具体例などを挙げて教えてほしかった。
1投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前に一度読んだのですがブログを書くために再読 読み流していましたがしっかり読むべきでした。 本に「マーカーは引かない派」なのは変わりませんが レコメンド機能や論文のGoogle Scholarは教えてくれてありがとう と思い ブグログに投稿することにしました。 読書の良さを見つけたい人におすすめの本です。
5投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだ内容をしっかり記憶、脳に定着させるためのポイントは次の2つ。 ①アウトプットする ②スキマ時間で読む アウトプットは次の4つがおすすめ ・読みながらマーカー、メモする ・人に話す ・SNSでシェアする ・レビューを書く スキマ時間で読む方法は、まとまった時間で一気に読むのではなく「15分×4」のように短時間を複数回に分けて読むのがいい。特に最初の5分と、最後の5分が集中力が高まるため。
1投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは入門書から読むというのは、そのとおりであると思う。いきなり高度な内容の本を読んでも理解できず、嫌になるだけだ。スキマ時間を利用して読んだ方が効率よく読書できるというのは、脳科学的に良いし、楽だと思った。著者に会いに行くのも、東京住まいなら進んですべきだ。
0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の中に、(当時の)日本人の読書量は年間12.3冊とあり、日本人が1か月に読む本の量で、7冊以上と答えた人は3.6%らしく、月8冊読めば、あなたは日本の上位4%にはいると書いてあったのを見て、俄然やる気が出ました。笑 (28歳ベンチャー勤務初期に読了)
0投稿日: 2025.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
抜き書き集 ・1年たったら古くなるのが「情報」、10年たっても古くならないのが「知識」 ・大切なもの「お金」「時間」「情報・知識」「人(つながり)」「健康」 ・新しいことは、試行錯誤してくれた先人から本で学ぶ ・スティーブン・キング「作家になりたいなら、たくさん読み、たくさん書くこと」 ・文章力を鍛えるには、インプットとアウトプットを繰り返すこと ・最初のインプットから7~10日以内に3~4回アウトプットすると忘れない ・寝る前に情報をインプットすると、熟睡したあと整理されている
0投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本では、月に本を読むのが1、2冊と答えたのが34.5%、3、4冊が10.9%、5、6冊が3.4%、7冊以上が3.6%になるらしい。ということは月に7冊読むだけで日本人の上位4%にはいるということを教えてもらった。さらに月に10冊読む人は上位約2%にはいるとのことだ。もちろんこの本で学んだ通り、記憶に残らなければ多くの本を読んでも意味はないのかもしれない。でも、月に10冊、つまり3日に1冊読むならきっと多くの良い本に出会うことができて、自分の人生を少しは変えれるのではと思った。 だから、本を読むことを続けたい。
0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読書脳という本わ読んでからの読んだら忘れない読書術に辿り着きました。やはりインプット、アウトプットを回していくことが大切で、読書をする際はマーカーなどを引きながら読んでいくのがいいそうです。他にもホームラン本との出会い方や隙間に読書をして記憶力を上げるなどはじめて知れたので良かったと思いました。すでに読書脳で知った内容が多かったですが深める読書がしたかったので古い方も読みました。書いてあることは変わらず知識を深めることができて良かったです。
0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、本を読み始めて読書時間を有意義な時間にしたいと思い、この本を手に取りました。 本は、沢山読んでも自らの知識になり、それを活用できないと意味がいという事を再認識させてもらいました。 マーカー読書法、アドレナリン読書法など、エビデンスをもとに本の内容を10年忘れない読書法がわかりました。 その中で、一番大切なのは、いかにアウトプット回数を増やす(SNSに感想を投稿、人に本を勧める)かとの事だったので、初めて感想を書いてみました。
0投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書しても記憶に残らず、字面を追う感じになっていました。あとから感想をと言われても言えない自分に正直がっかりしてました。 この本を読むことにより、1週間に3度触れる、アウトプットする(人に話す、SNSのアップするなど)、本に書き込みをしたほうが覚えやすい等と自分にもできるやり方を学べました。ここで感想を述べるのもアウトプットの一つだと思います。 後半でKindle活用について書かれてましたが、あれ?書き込みやパラパラ読書法できないじゃんと思ったところ、すかさずフォローの記述がありました。Kindle欲しくなっちゃいました。
0投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識として役に立つ、記憶に残る読書がしたいと思って読みました。 アウトプットとスキマ時間の活用、から始めてみたいと思います。
2投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ40代になり、今更ながら本を読むようになった。 本を読む事により脳が鍛えられ、こうやって読んでいる事が無駄ではない事を、この本を読んで知ることが出来た。 肯定されたようで嬉しかった。 忘れない為にはアウトプットするのが良いそうだ。 人に話す、SNSに投稿してみるetc
2投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は本の読み方、本との出会い方、本の内容を知識として身につける方法が書かれており、大変役立つ一冊となりました。 本を読んでも、すぐに内容を忘れてしまったり、誰かに内容を上手く説明出来なくて、時間の無駄だったんじゃないか…そう思っていました。 読んではいるけれど、知識として身についていないなと感じていた。 インプットしたものをアウトプットすることで、自分の知識となり、忘れないものとなるんですね。 スキマ時間、スマホではなく読書で知識をつけ自分の世界を広げていきたいです。
1投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の素晴らしさがとても伝わる本だった。 読んで忘れない為の読書術 メモを取る 人に話す、薦める、SNSなどに感想を投稿する この本を読んでから、読んだ本をこのアプリに感想を書いていくことに。
0投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に読書を始めたタイミングなので、今読むべき本だったと思う。なんとなく文字を追ってわかった気分になるのではなく、この本で読んだことを実践して読書の質を上げたい。
4投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識や語彙力、言語化力、コミニュケーション能力等ビジネスで活用するために読書を始めましたが、中々実践したり読んだ本の記憶が思い出せなかったりと悩んでいる中でのこの1冊。 本を読むことでのメリットが多く書かれており、モチベーションはアップしました。 やはりアウトプットしていくことが大事であり、読んだ本を週に3回アウトプットすることで記憶に残る本となるそうです。 また、本を読む上で、1冊につき3カ所気になる文章(マーカーや印などを付ける箇所)を見つけるとその本の元が取れたと言っても良いと記載があり、1冊の本からたくさん知識を得なけれぼと思うハードルが下がり、気楽に読めるようになりました。
1投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近時間に余裕ができた為色々なジャンルの本を読み始めましたが、中々自分の中にうまく取り込めていないことが多くせっかく読んだのに勿体ないどうしてこんな記憶力がないんだろう・・・!と思っていました。 そんな時に本屋で見かけたのでこれだ!とすぐさまレジへもっていきました。 すぐ実践できるものも多くとても勉強になりました。 マーカーを用いての読書や15-45-90の法則読書法などは今後取り入れていきたいですし、就寝前のスマホを触ってしまう時間を読書に置き換えていきたいと思います。
0投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
▷重要な点 ⭐︎よく使われる情報、感情が動く情報が記憶に残る ・一週間に3回アウトプットする →マーカー、思い出し復習、感想 自分にとって重要な点にマーカー、3つあれば良い本 ・隙間時間の締切効果(15分の隙間を無駄にしない) ・寝る前は記憶に残りやすい ・目次を見て重要な点を見定める、ワープする →興味のある内に重要な点をインプットでき、さらに記憶に残る、深く読む部分を見定められる ▷メリット ・ストレス2/3、リラックス ・論理的思考力、集中力、共感力(特に小説)、読解力。仕事で特に重要なのは共感力 ・インプットで勝ち、アウトプットで勝ち、行動を変えられれば圧倒的な差をつけられる ▷その他 ・文章力を鍛えるにはたくさん読んで書くしかない ・選択肢が広がる(例、年収1000万達成方法) ・3日に1冊目標 ・Kindle ・買ってすぐ、好奇心のある内に読むと記憶に良い
1投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読んだ本の内容を忘れちゃう。そんなことが私には往々にしてあります。 この本を読んで、それを軽減できる気がしました。 記憶に残すためにはSNSへの投稿、人に話すなどを通じてアウトプットすることが重要であり、その時に、議論できるレベルにすることが鍵だと理解しました。 読書で得られる知識は、ザルに水を注いでザルに残る水量程度だとどこかで読んでいましたが、実際はインプット、アウトプット次第で変えられそうです。 どうせ読むなら残したい。
0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報は1年で使えなくなり、知識は10年後に使えるというのは「なるほど…」と… 特に守破離に分類して読むというのは、今後やっていこうと思います。 自分のステージに合わせた本として、 守:基礎を学ぶ本 破:他人の応用されている内容の本 離:自分に落とし込むブレイクスルー本 仕事でも応用に目が行きがちになるんですよね… 他人の成功体験とか、めっちゃ輝いて映りますし、そのままやったら出来るんじゃ?となるんですけど、やっぱり根幹大事です。 自分の各知識がどのステージにいるかと言うのを、考えながら本は選んで行こうと思いました♪ でも悩むのは1分だけで、決断は中々難しいですね… この本は学びが多かったです。 著書で紹介されている本も読んでみようと思います♪精神科医の方で、ユングの心理学とか書いてますけど、心理学がそもそも分からないのでアホでも分かる本から行こう!
0投稿日: 2025.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の考える「本を読んだ」の定義は、「内容を説明できること」、「内容について議論できること」であり、忘れてしまっては意味がない。 アウトプットとスキマ時間読書を推奨しており、アウトプット大全に通ずるところがある。 自分のノートに感想書くだけに留めず、SNSへの投稿も積極的にしていこう。
0投稿日: 2025.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の内容をすぐに忘れない読書習慣をつけたいと思い手に取る。 読書のメリットを改めて確認。 スマホを見るスキマ時間を読書に充てていきたいと思えた。 本を読み終えた翌日に、SNSで感想を投稿する。 本の内容を元に友人と会話できるようになる。 アウトプットを意識して読書していきたい。
0投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書をすると幸福度が上がる。 こういう実験結果をよく見かけるしこの本にも書いてある。 でも、私は読書しすぎの弊害で頭が重くなったりぼーっとしてしまったり、読みたいがあまりに人との交流を避けてしまったりする。 本当に読書っていいことなのかな。 この本を読んで、私のやってきた読書はインプットしすぎなのかもしれないと感じた。 アウトプットするには人と関わる必要が出てくる。 本好きな人であれば、私のアウトプットに付き合ってくれるだろう。 もしかしたら、同じ本を読んで感想を話し合うことができる関係の友達やパートナーができるかもしれない。 多読×アウトプットで読書のよいところを最大限受けられるようになりたい。
6投稿日: 2025.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだら忘れないようにするにはどうすればいいか? それを一番に知りたくて読んだ。 私は読む前に 「丁寧に読んで、アウトプット」 という予想を立てたが、概ねハズレてはいなかった。 ということは、まあ他の似たようなタイトルの書籍と、そこまで違いはないかなというところ。 目次の項目は多いので、人によっては参考になる部分もあるとは思う。 個人的には、最後の方のおすすめ選書が参考になった。
0投稿日: 2025.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術入門者向けの本。 私は読書術の本は、何十冊も読んでいる。ほとんどの本に共通して書かれているのは、以下の3点についてである。 1.読書の効用(読書のすすめ) 2.どう読むか(読書術) 3.何を読むか(本の選択) 本書もこの3点について書かれているので、概要を書いておく。 ◾️読書の効用について 「読書によって得られること」は、下記の8点を挙げている。 1.結晶化されて知識を得る 2.時間短縮 3.仕事力アップ 4.健康(ストレス緩和) 5.頭が良くなる 6.人生の変化 7.成長 8.喜び ◾️読書術について 本書の「記憶に残る読書術」の要諦は、下記の2点。 1.スキマ時間に読書した方が記憶に残りやすい 2.本を読んで「1週間に3回アウトプットする」 3回アウトプットは、下記の4つのうち、3つを行う。 1.本を読みながら、メモをとる、マーカーでラインを引く。 2.本の内容を人に話す。本を人に勧める。 3.本の感想や気づき、名言をFacebookやTwitterでシェアする。 4.Facebookやメルマガに書評、レビューを書く (p81-82) ◾️何を読むかについて 「自分の今のステージに合った本」を読むことが強調されている。 読書は「たくさん読む」よりも「何を読むか」のほうが、10倍重要です。(p151) 自分がその分野で「守破離」のどのステージにいて、どこを目指すのか。そこを見極めた上で、自分が買おうとする本が「守破離」のどの部分を重点的に説明しているのかを照らし合わせれば、あなたにとって「最も必要な本」が自ずと明らかになります。(p155) 類書には書かれていない、本書だけの独自性は見られなかった。読書術の本としては、標準的な内容だ。類書に比べて特に優れていることはない。大きな欠点もないようにみえるが、1点だけ気になったことがある。スキマ時間についてだ。 樺沢氏は、月30冊本を読むが、全てスキマ時間だけで読んでいるという。(p85) 「スキマ時間」というと、10分、15分程度の時間を想像するのではないだろうか。だが、本書で想定しているのは1時間のようだ。 東京に通勤するサラリーマンの通勤時間は、平均1時間。往復で2時間。(p85)。 車通勤の人は、1日あたり2時間のスキマ時間は捻出できないだろう。 樺沢氏が、すべてスキマ時間で読書しているというので、まとまった時間で読書する方法については書けないことになる。自分で行っていないことを書くのは、机上の空論になるからだ。実際に、まとまった時間の読書について書いていないので、誠実といえる。 しかし、王道は、読書の時間をあらかじめ予定して、集中して読書することだ。私は、ほかのことをする時間は捨てて、優先的に読書をしている。読書家の多くはそうだろう。こういった王道について書かれていないことは指摘しておく。 多読家で、読書術の本を多く読んでいる人は、新たに得られることは、ほとんどない。読書入門者にとっては有益であろう。特に、樺沢氏の他著が気に入った人にお勧めしたい。ただ、先述したように読書するのがスキマ時間のみでは偏るので、本書だけでなく、類書もあわせて読んだ方がいい。
2投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭に残る読書法を学びたく購入 これまで、本を読んでも内容が頭に残らず、結局読書を楽しめることはなかった。 読書により得られることがたくさんある。 他人と差をつけることができる。 楽しんで読むこと≫自己成長のため。本は汚くして良い。蛍光マーカーとボールペン最初は、パラパラ読みし、読み方を決める。知りたい部分を先に読む。自分のステージあった本を読む。本を買うのは即断即決で!本を読んだ後、記録したり、内容を人に話すなどのアウトプットも必要。 マーカー、メモをとりながら、読書をしていきたい。読んだ後に、必ず読書記録を残したい。
4投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ記憶に残っていない→知識として定着していない、何の役にも立っていない。 圧倒的なインプット→圧倒的なアウトプット 記憶に残る→自己成長、人生を変える。 本は結晶化された知識 他人の経験はお金で変える。 本を読む人と読むない人の差→文章力 先に7冊→日本人の上位4% 解決法を知るだけでストレスは軽減する。 楽しむとこじゃなければ、自己成長は得られない。→感情を動かせ 読書術3つの基本 ① 1週間に3回アウトプット 何度も利用 心が動いた出来事 ②隙間時間だけで月30冊も読める。 ③本は「議論できる水準」で読む。 1冊の本で産業大切なところを見つける。 レビューは翌日以降に書く。 集中できる15分を上手に活用する。 アウトプットをし読書する。 メモ、書く、SNS 何度も繰り返してみる。 議論できる位深く読む。 大事なところを1つに絞る。 本質を捉える。 一言でまとめる力をつける。
12投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログインプット大全、アウトプット大全に続いて読み切りました。 本を読んでも頭に残ることが少なかった私、まず読書術を読んで、頭に残る読み方を学ぼうとして読みました。インプット大全、アウトプット大全と繋がる部分もあって、理解が深まりました 基本 1.1週間に3-4回アウトプットする 2.隙間時間に読む(最初の5分と終わりの5分は集中力が上がる→記憶に残りやすい) 3.多読ではなく、まず深読できるようにする その本についての内容を話せる、議論できるレベル 実践 1.パラパラ読みで大幅な内容を掴み、この本から何を得たいか、読む目的を決める 2.読みたいところを最初に読む 3.読む本の難易度、制限時間を設定することでプレッシャーをかける→記憶残りやすい 4.ワクワクしながら読む 5.著者に会いに行くことで、人となり(非言語情報) が分かることで更に深く理解できる 今後実行すること 前書き、後書き、目次、パラパラ読み をして大体の内容を掴む 制限時間を設定して、何を得たいかを明確にする 読んだ後、1週間以内に感想を書く、人に話す、内容の実行 を3回する 響いた言葉 読書を自己成長のためにするのではなく、 読書自体を楽しむことが大事 どの本を読むのかの基準は自分で持つ 脳が覚えていられる情報は、 何度も利用された情報と心が動いた情報
3投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ▼人に説明、人と議論ができなければ、読書による学びが身についていない。 ▼読書による学びはSNS等、アウトプットにより身につく。 ▼少しでもスキマ時間かあったら読書。 これからの時代にも、人生に読書は必要不可欠。
2投稿日: 2025.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからやってきたいこと ・15分を読書集中時間とし、繰り返し読んでいきたい ・アウトプットと隙間時間の有効活用を習慣づけ、自身の血肉となる本を読んで行きたい ・ベストセラーを選ぶのではなく、自分の求めているものと自分の守破離を意識して本をえらびたい 本を読む習慣を今までつけてなかったことを反省した。本は苦手だからと逃げてきた昔の自分に喝をいれたい。
3投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ多読というより深読のススメ。 年間300冊以上読書する著者の多読の秘訣や本選びのコツについて軽快な比喩表現とユニークな語り口で惜しみなく書かれている。 具体的には スキマ時間の活用。15分✖️4セット アウトプット前提でインプットしろ。 スマホは持ち歩かない。本を持て。 一日一冊と覚悟を決めて緊張感と意思を持って読め。 汚して読め。 知りたい部分を先に読め(ワープ読書術) 鉄は熱いうちに一気に読め。 著者に会いに行け。 などなど。 Kindle欲しくなった笑
0投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書をする意義や、読んだ内容を記憶するための具体的手法を示した入門書。 読みやすく、読書へ向かうモチベが上がる一方で、タイトルの割には、読書の効果を説明する部分が半分以上を占め、読んだら忘れない具体的な手法は3割程度の印象。
0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとってとても意味のある内容でした。 私は読書が好きで周りの人よりは読むのですが、内容をはっきり覚えていない事が多い。 インプットしたらアウトプットする。感想をシェアする。楽しく読書をするノウハウが詰まった1冊でした。
7投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから読者を習慣にしたい考える人におすすめです。読書をすることで得られるメリット、読んだ内容を自分の血と肉にするためのノウハウが説得力のある書き方で書かれています。特に"本は汚く読む"という話は私の読書概念をガラリと変えるものであり、その場で初めて折り目とマーカー線を引いてしまいました。 大事なのは ①1冊の本から線を引くのは3箇所のみ ②本を読んだらレビューを書く
0投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ本は最高の娯楽。ワクワクして読むのが良い 本を読む日数を決めて目標設定することでドーパミンが出て記憶に残りやすい。 ラインマーカーで線を引くと記憶に残りやすい。 全体をまず読んで速読か精読かをきめる。 その本でなにを学びたいかをきめる。 その本を何日かで読むか目標を定める
0投稿日: 2024.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ振り返ってみると読んだら読みっぱなしで、内容を覚えておらず実践もしていない本が多く、本の指摘が心に刺さった 本を何となく綺麗なまま読みがちだったが、これからは書き込みやマーカーを使い1冊の本を使い倒していきたい 忘れない方法として載っていることをまず実践するべく本のメモと付箋、感想、フレーズ選びなどを行った これからも度々読み返して今後の読書のサポートとして側に置いておきたい1冊だった
0投稿日: 2024.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書録「読んだら忘れない読書術」5 著者 樺沢紫苑 出版 サンマーク出版 p178より引用 “ 実は、最新の脳科学で、直感を生む「基 底核」というJ部分は、大人であっても成長を 続けるということがわかってきました。 つまり、訓練によって基底核を鍛えること で、「最善の一手」が直感的に思い浮かぶよ うになる、訓練によって正しく判断できる直 観力が養われる、ということが脳科学的に支 持されたわけです。そしてそれは、今からで も遅くないのです。” 目次より抜粋引用 “なぜ、読書は必要なのか?読書によって得 られる8つのこと 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 3つの基本 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 2つのキーワード 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 超実践編 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 本の選択術” 精神科医で作家である著者による、しっか りと記憶に残すための読書の方法を記した一 冊。 読書の利点から自分に必要な本の選び方ま で、著者の経験と実践に裏付けられた具体的 なやり方が記されています。 上記の引用は、本の選び方について書かれ た項での一節。 人生の折り返しをとうに過ぎた、私位の年代 の人達にとって、衰えるばかりではない残り 時間があるというのは、大きな希望になるの ではないでしょうか。 死ぬ直前まで、一歩踏み出しながら生きてい たいものです。 読んだ本の全てを憶えておくのは無理でも、 少しでも多く自分の身に付けたいと考える人 にお勧めできる一冊。 書かれている事を始めるにあたって、大金が 必要そうではないところも、より多くに人が 試すことが出来て良さそうです。 私もそこそこ続けている、読書録を投稿す ることですが、良い方法だったようです。 ーーーーー
1投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログここ最近、スマホでゲームをしたりSNSを見たり、自分の時間が溶けているのを感じていた。人には見せられないような怠惰な生活を送っていたので、この本でそんな生活をリセットしたいと読んでみた。 内容はどこかで聞いたことがあるような、知っているようなことなのだけど、きちんとした理由や著者の経験談が書かれているので、素直に腹落ちした。こんなふうに自分の時間をコントロールできたらなぁ。まずは意識することだけでも、違ってくると思うので、できるところから始めてみよう。 寝る前にスマホは見ないぞ! 適度に運動するぞ! 8時間睡眠をとるぞ! 遊びの時ToDoリストをつくるっていいなと思った。楽しいや好きはたくさんあった方が毎日ハッピーだものね。 20241112
0投稿日: 2024.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本を読めば、何千、何万人の先人の知恵を借用できる」と書かれており(強く共感です!)、その上で「貯金をするな!知識を貯金しろ!」、「知識は、最高の貯蓄である」と読書を力づく、後押ししてくれます。これからは、「アウトプット」と「スキマ時間」を意識しながら、本を読むことを楽しんでいこうと思いました。“心が動くと記憶に残る”というフレーズが、読書に限らず、まさにそうだな!と思い、心に残りました。 巻末に、著者が勧める珠玉の31冊も読みたくなりました。 また、この場で、皆さまにいろいろな本を紹介していただけるのも、大変ありがたく、励みになります。
48投稿日: 2024.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログネットで何でも調べられる時代だからと言って、本の存在をあなどってはいけない。 何を始めるにもとっかかりとして本を利用すれば、土台がしっかり固まる。 読書を日常的にしていると幅広い知識だけでなく、突然の出来事にも対応できる姿勢も身につく。 ただし読んで終わりではなく、積極的なアウトプットが重要 。 アウトプットしなかったら将来的に「だいぶ昔に読んだから覚えていないな…」とすっかり内容を忘れてしまう。 それはつまり 一過性の満足しか得られない無駄な読書ということ。 アウトプットを前提としてインプットし、インプットしたらアウトプットをする。 自己成長につなげられるような読書術を身につけていきたい。
21投稿日: 2024.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書についての入門書 自分は読書を始めたいと思いましたが、けど本って読んでもつい忘れてしまうところがあるし、そもそも文字ばっかりだと飽きてしまう。って悩んでました。 そこでこの本を読んでみようと手に取って、読み始めて読書の大切さや読書の色々な方法が書かれていました。 忘れないためにはアウトプットが大切と言う事で アウトプット大全も購入しました。 読書のモチベーションが低下したらまたこの本を読み返していきたいです。
1投稿日: 2024.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりの小説じゃない本。(ジャンルはなんだ!?)この本は学校の図書館出タイトルに惹かれ、運命的な出会いをした本です!私はブクログに感想を書いているくせにあんまり内容を思い出せない時が割とあるんです。本は内容が頭に入らないと意味がないのでしっかり記憶に残したいと思い読んでみました。 さすが精神科の先生!信用できる。こまめにちょこちょこ読書したりすると忘れないのか! それに、この本には忘れないための説明だけではなく、本をたくさん読めば読むほどよいという事が書かれていてますます読書したくなりました! 月に7冊以上本を読んだら日本人の上位4%に入れるのです!!ブクログのユーザーさんのようにこんなに本を読んでいる人はなかなかいないそうです。しかも、日本人の読書を全くしない人の割合はなんと約半分! ブクログユーザーさん、読書しましょー!エイエイオー
84投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ·月7冊本を読むことで日本人の上位数%の読書家になれる。 ·読み終えた本について一週間で3回アウトプットすると記憶に残りやすい。 ·スキマ時間に本を読むことでより集中して読書できる。
5投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1336 251P ★4・・・1947 樺沢紫苑(かばさわ・しおん) 精神科医、作家。1965年、札幌生まれ。1991年、札幌医科大学医学部卒。2004年からシカゴのイリノイ大学に3年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。メールマガジン「精神科医・樺沢紫苑 公式メルマガ」など15万部以上を配信している。その発行部数は国内でも屈指。Facebookページの「いいね! 」数は14万を超え、個人では最大規模のFacebookページ運営者として知られている。Twitterフォロワーは約12万人。こうしたインターネット・メディアを駆使して、精神医学、心理学の知識や情報をわかりやすく発信している。「日本で最もインターネットに詳しい精神科医」として雑誌、新聞などの取材も多い。また、過去20年間の読書数は6000冊以上にものぼる。その脳科学的な裏付けのある「記憶に残る読書術」により得た知識や情報をSNS上での紹介や執筆活動を通じて広くアウトプットしている。著書に『メールの超プロが教える Gmail仕事術』『ツイッターの超プロが教える Facebook仕事術』『SNSの超プロが教える ソーシャルメディア文章術』(いずれも小社)、『もう時間をムダにしない! 毎日90分でメール・ネット・SNSをすべて終わらせる99のシンプルな方法』(東洋経済新報社)、『頑張らなければ、病気は治る』(あさ出版)などがある。 読んだら忘れない読書術 by 樺沢 紫苑 先述しましたが私は、だいたい年に3冊のペースで本を出版しています。さらに、毎日、Facebookに記事を投稿し、メルマガも発行しています。毎日、原稿用紙で 10 枚から 20 枚、多い日で 30 枚以上の文章を書いていることになります。 私はよく、「どうしてそんなにたくさん文章を書けるのですか?」「どうしてそんなに速く文章を書けるのですか?」と聞かれます。 答えは簡単です。たくさん本を読んでいるからです。 本を読む人と読まない人の決定的な違いは、「文章力」があるかどうかに表れます。 仕事に限らず、友達との交流や恋愛、さらに夫婦や親子の交流、連絡も「メール」「メッセージ」なしでは考えられません。つまり、自分の考えを文章で的確に表現できる人は、仕事で成功する。また、自分の思い、気持ちを文章で的確に表現できる人は、友人や恋人、家族と上手にコミュニケーションができ、友情と愛情に包まれた生活が送れるのです。 インターネットの時代では、「文章力」は絶対に不可欠な「仕事力」だといえます。 そして、「文章力」を鍛えるほとんど唯一の方法は、キングの言うように「たくさん読んで、たくさん書く」ことしかないのです。 本を読まない。文章も書かない。それでいて、文章力を鍛えることは不可能です。 言い換えると文章力を鍛える方法とは、インプットとアウトプットを繰り返すことです。アウトプットを前提にインプットを行い、インプットをしたらアウトプットをする。それをフィードバックして、また別のインプットをしていく。本書でお勧めする「アウトプット読書術」を実践するだけで、文章力は確実に鍛えられます。 仕事力にもいろいろあります。営業力、コミュニケーション力、決断力、問題解決力、時間管理力、プレゼンテーション力、指導力、リーダーシップ……。 実は「本」を読むことで、これらの仕事力全てをアップさせることができます! なぜならば、これらのスキルをアップさせる本は書店に行けば、それぞれ 10 冊以上並んでいるからです。 本を上手に活用できる人は、ストレスが緩和され、「悩み事」でクヨクヨすることから解放されます。しかし、この事実は、ほとんどの人が知りません。 なぜなら、読書家は問題や悩み事に直面しても、「本」を参考にして、早期のうちに解決してしまうので、大きなストレスや厄介な悩み事に煩わされること自体がないからです。 一方で、滅多に本を読まない人は、「悩み事」を抱えたとしても、「本を読んで問題解決をしよう」とは思いません。 過大なストレスに支配され、大きな「悩み事」を抱えたとき、人は「視野狭窄」に陥ります。目先のことしか考えられなくなり、頭に思いつく選択肢が減っていくのです。普段から本を読む習慣がない人は、「本を読んで問題解決しよう」という発想すら浮かばないということです。 人間の悩み事というのは、だいたい共通しているものです。人間関係の悩み、仕事上の悩み、恋愛の悩み、金銭のトラブル、子供の教育、成長の悩み、病気や健康に関する心配や悩み……。こうした悩みに対する解決法は、ほとんど全て既刊の本に書かれています。 本に書かれている通りの方法を忠実に実践すれば、ほとんどの場合、悩みは解決するか、少なくとも軽減するはずです。 しかし不思議なことに、悩みの渦中にいる人は、問題解決のために本を読もうとしません。悩みの渦中にいる人が本を読まない大きな理由は、「それどころ」ではないから。 「悩み」や「ストレス」を抱えた場合、心理的に余裕がなくなってしまいます。普段から滅多に本を読まない人が、そんな心理状況で本を読めるかというと、読めないのです。 精神科の患者さんは、自分の病気について山ほど質問を投げかけてきます。精神科の外来には、いくつかの病気ごとに「患者さん向けにわかりやすく書かれたQ&A集」が置かれているので、… 次回、「小冊子は読みましたか?」と聞くと、多くの方は「読んでいません」と言います。「なぜ読まなかったのですか?」と聞くと「それどころじゃなかったからです」と。それで結局また、小冊子に書いてあることと同じ質問を、何度も繰り返し聞いてきます。 自分の病気について心配があれば、1冊本を読むだけで、その疑問のほとんどは解決しますし、病気に対する不安や心配もとりのぞかれます。しかし、自分から書店に行って病気の本を買って読んで勉強する、という人は非常に少ない。それどころか、小冊子を渡… つまり、「どうしていいかわからない」状態において、最もストレスが強くなる。 対処法、解決法を調べて「何とかなる」(コントロール可能)とわかっただけで、状況は全く改善していなくても、ストレスの大部分はなくなるということです。 言語情報が不安を消し去ってくれる 解決法を知るだけでストレスや不安が軽減される。もう1つ、科学的根拠を示しておきましょう。 不安というのは、脳の「 扁桃体」という部分と関連しているということが脳科学の研究でわかっています。「扁桃体の興奮」=「不安」という図式です。 医者からただ「この薬を飲んでください」と言われても不安なままですが、きちんと薬の説明をされるとそうした不安は軽減します。 「情報」は、人間の不安を和らげてくれるのです。 「脳への言語情報の流入」というのは、「話す」「聞く」「読む」などさまざまなパターンがあります。その中でも人に相談する、人から情報を得るのが最も効果的なのですが、「話す」「聞く」には相手が必要です。 しかし、「読む」のに相手は必要ありません。本1冊分のお金があれば、誰にでも、自分1人で、すぐに実行可能です。 心配事があれば、その対処法について書かれた本を1冊買ってきて読めばいい。「言語情報」によって不安は軽減し、「解決法を知る」ことでストレスも軽減するのです。 本を上手に利用すれば、不安やストレスのかなりの部分を減らし、そしてコントロールできるようになります。 私は元来、頭が良いとはいえない人間でした。少なくとも高校、大学くらいまでは。高校の同級生たちは、今私がこうして 10 冊以上も本を出していることや、講演活動をしていることを知ると、みんな驚きます。 ただ、大学卒業時と今を比べると、圧倒的に頭が良くなっている自負があります。思考力、分析力、集中力、文章力、発想力、問題解決能力など、比べものにならないほど進化しています。 その理由は、月に 30 冊の読書と、毎日文章を書くことを、 30 年以上継続してきたからです。 文章を書き続けるためにはインプットが必要ですから、「文章を書く」ことと「読書」は表裏一体となっています。読書と文章を書くことの訓練を続けてきたことによって、他の人にはできないような発想で新しい切り口の本を書くことができるようになりました。 「頭が良くなる」といっても、それは「知識」が増えただけでしょう? と多くの人は誤解します。 しかし、 読書は私たちを「物知り」にしてくれるだけではありません。読書によって「地頭が良くなる」「知能が高くなる」「脳が活性化し、脳のパフォーマンスが高まる」 ということは、多くの脳科学研究が示しています。 では、人間の能力を伸ばすために何をすればいいのか? それは、「運動」と「読書」です。「運動」すると頭が良くなる。これはとても重要なことなので詳しく述べたいところですが、本書の内容とはズレてしまいます。それについて知りたい人は、運動と脳についての研究をまとめた決定版ともいえる『脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方』(ジョンJ.レイティ、エリック・ヘイガーマン著、野中香方子訳、NHK出版)をお読みください。この本を読むと猛烈に運動がしたくなります。 苫米地英人氏は『 15 歳若返る脳の磨きかた』(フォレスト出版)の中で、「IQの高さというのは、じつは読んだ本の数にほぼ正比例しています」「たくさん本を読めば読むほど(IQが)高くなる」「読書はIQを高める一番の手段」と断言しています。 自分の頭でいくら状況を打開する方法を考えても、限界があります。しかし、「本」を読めば何千、何万人もの先人の知恵を借用できるのです。 自分1人で解決できない問題も、乗り越えられない壁も、先人の知恵を借りれば簡単に乗り越えられる。現状を変えることは、そう難しいことではないのです。 何かを「変えたい」と思ったら、まず本を読むことをお勧めします。 本を読むのは嫌いだとしても、読書をすれば収入が増えるとするならば、 俄然、読書に対するモチベーションは上がりませんか? 実際に、読書量と年収は、比例するのです。読書量について多くの調査がなされていますが、ほとんどの調査で、年収の高い人は読書量も多いという結果が出ています。 成功している経営者のほとんどが、「読書家」である、というのです。 では、成功している経営者で、本を読まない人はいないのかというと、当然そういう人もいるそうです。しかし、本を読まない経営者で、 10 年、 20 年と継続的に結果を出す例は極めて 稀 なのだそうです。つまり、本を読まない経営者は、結果を出せたとしても「一発屋」で終わる可能性が高い。連戦連勝は難しいのだと。 ■喜び〜「読書エンタメ理論」 結局、楽しければいいじゃないか! 「なぜ樺沢さんは、そんなに読書するのですか?」と質問されることがあります。 「自己成長のため!」と答えるとカッコ良いかもしれません。 確かに、「自己成長のため」の読書が私の最終目的ではあるのですが、日々の読書で本を開くたびに「自己成長するぞ!」と意気込んで読むことは、まずありません。 私がこれほどたくさん読書する理由は、「楽しいから」です。これがまず基本です。 1冊、たった1500円です。電車の中でも、カフェでも、ベッドの上でも、どこでも場所を問わずに楽しめる。1年間、毎日でも楽しめる。 時間と場所を選ばず、楽しいだけではなく自己成長にもつながり、こんなにも安価な娯楽が、他にあるでしょうか? 私は、「映画」が大好きで、映画評論家としての仕事もしていますが、映画は劇場でしか見ないので、見る「時間」と「場所」が制限されてしまいます。いつでも、どこでも楽しめる娯楽ではありません。 小学校、中学校、高校と、私の一番苦手な教科は、「国語」でした。全教科で「国語」が一番苦手。「一体、どうやって文章を書けばいいんだ?」「国語なんか大嫌いだ」と思ったものです。結局今考えると、小学校、中学校の頃は、ほとんど本を読まなかったので、「国語」が苦手だったというのは、実に当然のことだったのです。 その「運命の1冊」との出会いによって、読書嫌いが、読書好きに変わる。 本を全く読まなかった自分が、読書が楽しくてしようがない人間へと変わった。 その瞬間に無限の可能性の扉も、同時に開かれたのでしょう。 「私は月 30 冊本を読みます」と言うと、「凄いですね。よくそんなに本を読む時間がありますね」という反応をされます。「読書したいけどその時間がない」というのは、読書ができない人に最も多い「言い訳」です。 文化庁が発表した「国語に関する世論調査」(2013年度)の結果によると、読書量が少ない理由の第1位は、「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」で、 51・3%と過半数を占めています。つまり、「時間さえあれば、読書したい」と考えている人は非常に多いのです。 私は月 30 冊本を読みますが、全てスキマ時間だけで読んでいます。 スキマ時間といってもいろいろありますが、私の場合は「移動時間」がほとんど。「電車に乗っている時間」と「電車を待っている時間」です。 自分の家で仕事をしているような人を別にすれば、ほとんどのサラリーマンは、通勤時間、移動時間、約束の待ち時間などのスキマ時間を合計すると、1日「2時間」近くあるはずです。1ヶ月で 60 時間。 そのスキマ時間の 60 時間を読書に使えば、読書のスピードが遅い人でも、スキマ時間だけで月 10 冊読むことは可能なのです。 私は電車の中でスマホを見るのは、最大の時間の無駄だと思います。 なぜならば、1日 10 回もメールやメッセージをチェックする必要はないし、スマホでメッセージを返信するよりも、パソコンで返信したほうが、何倍も早いからです。スマホで 15 分かけて打った長文メールも、パソコンなら3分で打ち終わります。 そんな「スマホやSNSにかけている時間の無駄を極限まで減らして仕事を効率化しましょう」というコンセプトで書いたのが、『もう時間をムダにしない! 毎日 90 分でメール・ネット・SNSをすべて終わらせる 99 のシンプルな方法』(東洋経済新報社)です。 実は、私は電車の中でスマホを見たことは一度もありません。 なぜなら、私はスマホを持っていないからです(笑)。 私がスマホを持っていないというと、多くの人は驚きます。「樺沢さんのようにネットに詳しい人がスマホを持たないなんて」と。 私がスマホを持たない理由は、必要ないからです。 スマホというのは、移動時間やスキマ時間にチェックする人が多いと思います。 目の前に自分のパソコンがあるのに、わざわざスマホを使って検索したり、スマホでメールチェックしたりする人は少ないでしょう。 前述した通り、私はスキマ時間のほとんど全てを「読書」に費やしており、電車の待ち時間も、ランチで食事が出てくるまでの待ち時間も、本を出して読書をします。座れる場所では、ノートパソコンを開いて仕事をします。立っている場所ではほぼ読書しているので、スマホを見る時間が全くないのです。 毎日、2時間、電車の中でスマホを使ってゲームやメールをしても、あなたの収入は1円も増えませんが、毎日、2時間の読書で月に 10 冊の本を読めば、年に120冊の本を読めます。 10 年で1200冊です。ここまで本を読めば、あなたの人生に革命が起きることは間違いないでしょう。 たくさん本を読める人は、時間管理が上手な人。 読書術は、時間術そのものといってもいいくらいです。 著者に会いに行って、好きになる 本をたくさん読んでいくと、必ず好きな著者、お気に入りの著者ができるはずです。そんな「好きな著者」ができたなら、著者に会いに行って欲しいと思います。 例えばその著者が登壇するセミナーや講演会に参加するといいでしょう。新刊の発売直後は、多くの著者が「新刊発売記念講演会」などを開催しています。小説家は別として、ビジネス書の作家の場合、多くの方が講演活動を行っています。 有名な著者の場合は参加費が高い場合もありますが、書店と提携して行われる場合などは、「本を購入すれば無料」という講演会もたくさんあります。その著者の公式ホームページをチェックすれば、そうした講演会情報は、簡単に得られます。 ではなぜ、著者に直接会いに行くといいのでしょうか? それは、直接会うことによって、その人の書いた本の内容が、スポンジに水が染み込むように、自分の中に浸透するからです。 コミュニケーションには、「言語的コミュニケーション」と「非言語的コミュニケーション」があります。表情、視線、眼差… 仮に、その人と言葉を交わさずとも、その人の前にいるだけで、非言語的な多くのメッセージを受けとることができるのです。言葉にはならない、言葉を超えた理解。心と心の対話……。直接会うことで、そうした非言語的対話が可能になるのです。 本で文字として書き切れなかった非言語的… そして、単に理解できるだけでなく、それは何倍も記憶に残ります。実際、私もよく著者仲間の出版記念講演会に参加しますが、講演で聞いた話は、5年たっても忘れません。 「百聞は一見にしかず」ということわざがありますが、本を100回読むよりも、著者に1… そして 何より重要なのが、講演で話を聞くことで、すなわち著者と会うことで、実際に「著者の人となり」が理解できるということです。 「人となり」がわかると、なぜその著者がその本を書いたのか、あるいは、どういう「思い」でその本を書いたのか、といった本を読むだけではわからないことを、直感的に理解することができるのです。 会う前と比べて、その本の内容を圧倒的に深い… そして、その著者をより「好き」になるはずです。 この「著者に会いに行って、好きになる」というのは、その後もその著者の本を読むたびに、記憶増強効果を発揮してくれるはずです。なぜならば、「好き」「楽しい」は、脳を刺激し、記憶に残りやすくするからです。 おそらく、あなたも「大好きな著者」に関しては、その著者の本を全て議論できる水準で読み込んでいるのではないでしょうか? 「好きな著者」が「大好きな著者」になることで、その後もその著者の新刊… 好きな著者に会いに行こうというのが、「百聞は一会にしかず読書術」です。「それって、読書術じゃないじゃないか」というツッコミも入りそうですが、「読書」を「本を読む」ことだけに規定… 先ほども述べましたが、読書しない人ほど「入門書」よりも、「本格的な1冊」が好きな傾向にあります。「基本」をすっ飛ばして、いきなり「奥義」を知りたがる。「わかったつもり」にはなるかもしれませんが、実際に「身につくレベル」「人と議論できるレベル」で読むことは難しいと思います。 その点でいえば、自分の友達や知り合いが勧める本を読むと、失敗する可能性が低く、それらはヒット本やホームラン本である可能性が高いのです。友達から直接勧められた場合はもちろん、ソーシャルメディアも本選びにおける貴重な情報源となります。 「ホームラン率」を高める〜「1万5000円読書術」 私は、読んだ本の感想や書評をFacebookやメルマガにアップするようにしていますが、「これは読んだほうがいい!」と強くお勧めできる本というのは、実はそんなに多くはありません。おそらく、自信を持って「これは読んだほうがいい!」と言えるのは、月に数冊でしょう。 月に 30 冊読む中で、強くお勧めできる本は数冊。つまり、自分が読んだ 10 冊の中のベストワンを推薦しているというイメージです。 言い換えると、1冊を紹介するために、1500円の本ならば1万5000円ほどを投資しているわけです。1万5000円を投資した中でのベストワンですから、いうならば「1万5000円の価値がある」ということになります。 自分でゼロから良書を探して巡り会うためには、自分で1万5000円払わないといけません。それが、私がお勧めした本を買えば、1万5000円の投資なしで、最短でホームラン本に到達できる可能性が高いのです。 他の人が「本気でお勧めしている本」というのは、普通に書店に並んでいる本の、何倍もの価値があると考えるべきです。 「本のセレンディピティ」というのも、間違いなくあると思います。 本との偶然の出会い。しかし、偶然に出会っているようで、それは実は偶然ではないのです。 どの本棚の前を歩き、どこに目を光らせているのか。私たちは何もしていないようで、無意識に注意力を働かせて、「選択」しているのです。 人間の脳というのは、自分にとって必要な情報、重要な情報を積極的に集めてきます。一方で、自分が興味のない情報や知らない情報は、脳を素通りする仕組みになっています。これを心理学用語では、「選択的注意」といいます。 最後は「直感」を信じる! 自分はどの本を読めばいいのか? どの本を買えばいいのか? 最後は、「直感」だと思います。「この本は、おもしろそうだ」「この本は、自分の役に立ちそうだ」という直感を信じるしかない。たくさん本を読むことで、そうした「本を選ぶ直感」も研ぎ澄まされてきて、本の選択で失敗する確率は減っていきます。 読書の場合でいえば、本をたくさん読めば読むほど、自分にとって「良い本」「役に立つ本」についてのデータベースが充実していくわけですから、直感で正しく判断できる確率が高まっていきます。 たくさん本を読む読書家の直感は正しいことが多いので、たくさん読んでいる方は自信を持って、その直感を信じて本を選びましょう。 例えば、1ヶ月の間に、全く異なるジャンルの本を5冊読む場合と、同じジャンルの本を5冊立て続けに読んだ場合、どちらが記憶に残るでしょうか? 「固め読み」したほうが圧倒的に記憶に残りやすくなります。 同じジャンルの5冊の本の間で相互に関係性が生まれるので、意識しなくても比較・対照しながら読むことになります。 これは、いうなれば温泉採掘のようなものです。温泉採掘には、「試し掘り」と「本掘り」の2つがあります。温泉が出そうな場所を予想して、試しにそこを掘っていく。いきなり温泉が出る場合もあるし、出ない場合もあります。何箇所か「試し掘り」を繰り返して、ようやく温泉が出る場所を発見します。その後、安定的に温泉を供給するための太い穴を「本掘り」していくことになります。 温泉というのは、あなたの興味や関心、そして好奇心をくすぐる領域です。そうした領域にこそ、あなたの「適性」「個性」「特性」「長所」、あるいは「才能」「隠された能力」が埋もれているのです。 あなたの可能性を引き出すための読書をする。そのためには、「試し掘り」を繰り返し、「ここだ!」と思ったなら、徹底的に「本掘り」していくことです。 これが、最も効率がいい自己成長につながる読書術です。 一番もったいないのは、「試し掘り」をして温泉が微量にわき出ているのに、あっさりと次の試し掘りに移動してしまう場合です。 例えば、大ベストセラーとなった『嫌われる勇気』を読んでみて、「おもしろい! アドラー心理学って凄いなあ」と思った。でも、それっきりにしてしまう。「アドラー心理学って凄いなあ」という興味のアンテナが反応した、つまり「ここに温泉はある」という反応が出ているのに何もしない。これは、非常にもったいないことです。 アドラー心理学に興味を持ったのなら、アドラー心理学に関する別の本を何冊か読んでみるのです。「本掘り」することで、さらに知識は深まり、記憶にも残り、アドラー心理学を普段から実践できるようになるでしょう。 もう1つのよくある失敗パターン、それは、温泉が出るかどうかわからないところを、いきなり「本掘り」してしまうことです。これは、大きな時間の無駄になります。 例えば、これまであまり本を読んだことがない新人ビジネスマンが、先輩から「ビジネスマンなら、ドラッカーくらい読んでおけよ」と言われて、「よし、勉強しよう!」と一念発起し、『マネジメント』(上田惇生訳、ダイヤモンド社)を買ってきて読み始める。しかし、この大著を最後まで読むだけで一苦労ですし、これまでビジネス書を読んだことがなければ内容の深い部分まで理解するのは難しいでしょう。これが、最初から「本掘り」して失敗する悪い例です。 月に何十冊も本を読む人は、本の購入費がかさみます。 「本は、できるだけ安く読みたい!」と、誰もが思っているはずです。 しかし、特に今日発売された紙の書籍の「新刊」を安く購入することはできません。 一方、電子書籍の場合は、今日発売された「新刊」でも、安く購入することができるのです。 サラリーマンの平均時給は、約2000円だといわれます。ですから、単純に考えて 10 分迷ったら、330円の損失です。年収の高い人は時給4000〜5000円の人もいるでしょう。そんな人が、 10 分悩んだら600〜800円ほどの損失ですから、文庫や新書の値段になってしまいます。
2投稿日: 2024.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読んだらアウトプットしましょう」を理論的に説明した一冊。 特にビジネス書は読むだけで満足してはダメ。実践してなんぼ。
0投稿日: 2024.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までなんとなく本を読んでいたがまず読む方法から改めて学ぶことができた。情報ならネットでいいが知識として定着させるなら読書をする。読書を自己投資であるため書き込みをして、ノートみたいに自分なりに作って行くことが大切。そしてこのような感想を書くなどアウトプットいてくことで記憶させる。読書の仕方を学ぶのならとてもオススメだと思う。
0投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書を読んだ目的:読書をする習慣は身についてきたが、読んでいても頭に入ってきている自覚がなかったり、読んでもすぐに内容を忘れてしまう実感があった。そのため、長期に記憶に残り、自分のスキルになるような読書の仕方を知りたかったため、本書を読んだ。 感想:非常に記憶に残る読書をするための実践的な方法が記載されており、さっそく実践してみたい。主な学びは下記の通り。 1.本の選び方 読みたい本を読む。わくわくしながら、楽しむながら読むことが最も重要。自分で良書に出会うのは難しいため、自分が尊敬している人や有名人のおすすめを読むのが良い。ただし、自分の本を読む目的や興味と合致する本を選ぶべき。やらされ感で読んでも身に付かない。 2.本を読むとき 隙間時間とアウトプットを意識する。隙間時間の15分を利用すれば、長時間読むより始め5分、最後5分はより集中できて記憶に残る。また寝る30前の読書は記憶に残りやすい。アウトプットは週3回すべし。本を読んでいるときはメーカーを引き、メモを取り、1回目のアウトプットする。 また、ゆっくり丁寧に読めば良い訳でなく、ある程度負荷をかけて読む方が記憶に残る。本の難易度によって読むスピードを変えて、調整すべき。本を読む期間も目標として設定するとなお良い。 3.本を読み終えた後 本を読み終えた次の日に2回目のアウトプットをする。マーカーの箇所を見直し、重要部分を再度メモする。(SNSでの発信も良い)。2回目のアウトプットをした次の日にレビュー等を書き、3回目のアウトプットするのが個人的に良いと感じた。 まとめ:本書に記載の通り、人の悩みのほとんどは本が解決してくれると思う。過去何千人の成功談、失敗談を参考にすることで、悩みの解決方法が必ずといっていいほど見つかる。焦らずしっかりと着実に本を読み、使える知識を身につけていきたい。
0投稿日: 2024.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びと気づきを得る読書は、自己成長と行動の変化につながるとあった。たくさん本を読んで、たくさん文章を書くという、インプットとアウトプットを繰り返すことで、読書が身につくようだ。読みやすい読書術の本だった。
1投稿日: 2024.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人になって読書をしようと思いこの本を手に取りました。 本を読んで満足していることが多くその本について何も語れないことがあり2回目。 精神科医の視点で読書術が書かれており、「1週間に3回アウトプットをする。」どんな方法でもいいのでレビュー、SNSなど文字に起こしておくことが大切。
1投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医樺沢紫苑先生の読書術の本。普段から樺沢先生の動画を見ることが多く、普段から見ていた内容が多かった。 それでも読書のメリットや、具体的な読書の方法、本の選び方などは非常に参考になった。 この本を読んで1番良かったのは、1500円の価値感の認識を変えられたことだ。普段からKindleやブックオフで安い本、中古の本を中心に購入しているが、1500円以上の価値を得られるのであれば新刊でもどんどん買っていこうと思えた。100万円あったら、貯金するより全部本を買った方が、自己投資により収入が増える、という考え方。素晴らしい。 自分もトップ数%の読書家になって、生涯年収を上げていこうと決意を固めた。 残念ながら面倒くさがりな所を治す必要があるが… あまり共感できなかった所 本を汚すということ…綺麗な状態で持っておきたい、汚れた本は後から読む気がしない 人にあげると喜ばれる…人に勧めて読まれた試しがない
14投稿日: 2024.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ記憶に留めるためにも最近このレビューを書くようにしてる。本は買わなくても図書館でも十分だと思ってるけどね。時間も意識して読書してるからあまり新しい発見はなかった。 オススメ本も紹介されてるのはありがたい。
2投稿日: 2024.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから読書を始めようと思い手に取った本。 私は読書が苦手という意識があり、読んでもすぐ忘れてしまう。 スキマ時間を使い読むことで、高い集中力の中読書ができるということ。さらにアウトプットすることで記憶に残りやすくなること。これらが大切であると知った。 また、自分のレベルに合わせた本を選ぶこと。ホームラン本に出会うためにはたくさん読むしかないということ。日本人の半分は月に1冊も読書をしないということ。様々な読書をするこに対する知識が書かれている。 私のような読書初心者にぴったりの一冊。
1投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログビフォー この本を読む前の私は、本を読むけど内容を覚えていないことが多かった。 気づき この本を読んで、これまでの本の読み方が記憶されにくいものだと知った。特に、本を頭から読むのは知りたい情報まで時間がかかり、モチベーションが下がりやすい読み方だった。また本に書き込みせず、折り目もつけずに読むのは振り返りがしにくく、自分の気づきを取りこぼすことになるのだと感じた。 TO DO 今後は「ワープ読書術」で読みたいところ先に読んだり、書き込みや折り目をつけて自分の記憶に残る読み方をしていく。
1投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
忘れないためにはアウトプットが重要。 ⭐️感想をシェア ⭐️名言を投稿してコメントを加える 私は電車で紙の本を読むことに抵抗があるため、電子書籍について興味を持った。両手が塞がらないのが自分的1番のメリット。 私はいつも本を選ぶ際悩んでしまうが、次からは「直感」信じて購入しようと思った。
1投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読もうと思ったきっかけの本 『アウトプットとスキマ時間』 予めアウトプットするという気持ちで読むと 理解度や集中力が違ってくる。 最近読書できていなかったので 本への投資をケチらずやっていこうと 改めて考え直しました。
0投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書に対するモチベは上がる。 大学までは頭悪いって言ってるけど、医学部行って頭悪いはないやろ笑 それはともかく、このようなレビューを書く事でアウトプットをし、また人間の脳内部室を刺激する事で覚えるということもわかった。 何となく今まで実践してきた事が科学的にも悪くなかったと裏付けできたのが、この本で学べた。 最後まで読みやすかった
0投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしたら忘れない読書ができるか、精神科医が教えてくれる。ロジックに説明してくれるので、いくつかは今後も使えそう。 他の本とも重複はあるものの、本を読む。ということを再考させてくれる一冊。
0投稿日: 2024.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書をしても時間がたったら思い出せないのでこの本を購入しました。自分がいかに勿体ないことをしていたのか実感しました。 今までアウトプットを意識してこなかったので、この機会にブクログをはじめました。 以下学んだこと ◾️なぜ読書が必要なのか 本には何千人の成功体験と失敗体験が載っている。自分の頭でいくら状況を打開する方法を考えても、限界がある。しかし、本を読めば先人の知恵を借用できる。 ◾️1週間に3回アウトプット アウトプット方法 ①本を読みながらメモを取る、マーカーを引く ②本の内容を人に話す。本を人に勧める。 ③本の感想、気づき、名言をSNSでシェアする。 ④書評、レビューを書く。 ◾️心が動くと記憶に残る アドレナリン、ドーパミン、エンドルフィン、オキシトシンなどの記憶力を高める脳内物質を意識的に分泌させる。 ◾️スキマ時間に読書 初頭努力:最初の5分 終末努力:最後の5分 この時間は集中力と記憶力が高くなるので、15分のスキマ時間に読書をすると良い。 ◾️速読より深読 内容について議論できる水準にする ◾️本の選び方 自分のステージにあった本を読む
0投稿日: 2024.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。速読よりも深く理解する深読や、1週間に3回アウトプットしていくのが良いなど、なるほどなぁと思いました。ちょっと自分には合わないなと、思う部分もありましたが興味惹かれたのはやってみようと思います。この投稿していく事も良いようです。
3投稿日: 2024.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本を読んでる私、かっこいいし偉いやん」 という自己満を恥じたい。 自分の糧にしていくための読書が大切。 自分が求めていた読書法はこれだったと、ドンピシャ感を味わえた。 不定期に本を読んでいる人におすすめの本。 本を読むことに少しでも価値があると感じる人ほど、その時間や読書を生きる糧にすべきだと気付かされる。 ・アウトプットをする ・隙間時間を使う努力 ・全ての本がホームランじゃないからこそ、たくさん読むべき ・精神科医の視点だから、人間の脳の仕組みも分かって腹落ち感がある
1投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログどのような本を、いつ、どれくらいの時間で、どのように読むべきか について一通りインプットすることができた。 それらを実践しつつ、本書にもある通りアウトプットを積極的に重ねたい。
0投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医・樺沢紫苑 流の読書術 どう読めば、読書による効果を得られたり、多くを忘れずにいられるか、 というノウハウを脳科学や経験などをもとに、読みやすく書かれている。 ちょっとした、エッセイ要素もあるので、樺沢紫苑さんの過去も知れて 肩ひじ張らずにに読めるビジネス書と言えます。 ビジネスにおける読書術的な側面が強いので、 小説メインに読む人には、ちょっとばかし違う気もしますが、 基本的な読み方としては、同じだと感じました。 電子書籍に関しては、賛否両論あるでしょうし、 老眼の人に良いという考えは、光刺激の観点から賛同はしかねるかな。
0投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて購入。 著者の作品である「アウトプット大全」を先に読んでなければもっと面白かったと思う。 学んだこと 感想は次の日以降に読み返しながら書く 目的をもって本を読む 本は楽しみながら読む 読みたいと思ったその時が1番頭に入る この4つはこれからも意識して読む
8投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書方法と本の選び方が色々書いてあります。 速読法は書いていません。 この本を読んだのはYouTubeで10分で読書する方法という動画があったような気がして、それが本で詳しく説明してあるかと思いましたが探しても見つかりませんでした。 動画も後から探しても見つかりませんでした。 完全に勘違いかな? 本を選ぶ際は守破離を意識するなど役立つことは色々書いてありましたが、私が一番知りたかった本をどんどん読めるようになる読書法はあまり書いていませんでした。 そもそも読んだら忘れないをテーマにしているのでそれについて書いているから当然だね! まず本の選び方を間違えないようにしようと思いました。
1投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルから期待する「読書術」に触れている部分は少ないが、まぁ筆者が「広く様々な人に伝えたい」という思いで薄い内容の本にしているのだろう(と、肯定的に捉えてみる)。 なぜかKindleの営業みたいな一節もあり、なんか主観と客観が混ざった、クリスタライズされていない、おっさんのあんまり面白くない話を聞いている気分にもなった。その分、人間臭くて読みやすい。 ・とにかくたくさん読め。インプットとアウトプット。 ・脳内物質(ドーパミン、エンドルフィン、オキシトシン、、、)を出して読むと覚える。面白かった昔の漫画は忘れない。 ・マーカーと書き込み。 ・速読、深読、精読をつかいわける。 ・目的を持って読め。この本から何を得たいか? ・固め読み、一気読みした方が記憶に残りやすい。
1投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、読んだ本の内容を忘れないための読み方や習慣について紹介しています! 私が読んでいて特に印象に残った2点について感想を書きます! 【本を読みながらアウトプットする】 本を読みながら気になった箇所にラインマーカーで線を引いたり、余白に気づきや疑問を書いたり、要約するなどアウトプットすることをオススメしていました。これらのアクションを起こすことで、単に本を読んだ時と比べて、「知っている→理解できる→説明できる→実践できる」という認知プロセスにおいて「理解できる・説明できる」あたりの深い段階に到達できるのではないでしょうか。よって本を読みながらアウトプットすることで、深い理解や記憶定着がより期待できるのではないかと感じました。 【スキマ時間を活用する】 人間の集中力は、活動の初めと終わりが最も集中している状態になるため、長時間同じこと続けるよりは、短い時間でも複数回に分けて行う方が、集中力が高い状態の割合が増えて、効率が向上すると述べられていました。私だけかもしれませんが、学習や読書をする際はまとまった時間を取りたいと思いがちだったので、電車の待ち時間や食事提供までの時間などのスキマ時間を見つけて行動することの大切さを知ることができました。また、時間の管理の向上や時間を有意義に使う意識を持つようになり、時間に関する改善も着手できそうだと感じました。
1投稿日: 2024.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の樺沢先生は、月に30冊本を読むらしい! しかも、全てスキマ時間の移動時間に読んでることに驚いた。 ★人生の1割に相当するスキマ時間を「浪費」に使うのか、「自己投資」に使うのか。 この時間の使い方次第で、あなたの人生は変わる。 ★出かける前に今日読む本を決めると1日1冊読み切れる。 「今日1日でこの本を読む!」と目標設定して、制限時間を決めることで、緊迫感が出るので集中力が高まり、記憶に関係する脳内物質が分泌され、読んだ内容が記憶に残りやすくなる。 何か物事を行う場合、制限時間を決めると集中力がアップし、脳が高いパフォーマンスを発揮する。 ★60分連続した読書よりも、15分のスキマ時間4回で読書するほうが、記憶に残りやすい。 高い集中力が維持できる限界が15分。 普通の集中力が維持できる限界が45分。 「45分」の間、少し休憩をはさめば、90分の集中も可能。
1投稿日: 2023.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んでもっと読書したい、と思いました 著者が、人生で初めてハマったファンタジー小説の作者(推し)のイベントに実際に出向いて握手して色紙にサインもらった話が愛おしすぎる ただの勉強になるだけでなく心がほっこりする話もあってとても読みやすかったです
0投稿日: 2023.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・読書とは、学んだ知識を記憶しそれを人生に活かすためのもの ・まず全体像を把握し、何を学びたいかという目的を設定する ・目次を見て、1番知りたいことの結論が書かれているページを見つけて読む、深掘りしたいところがあったらまた目次を見て見つけて読む、そこからはじめて最初から読み始める ・学んだ知識を忘れない方法 1メモにまとめたり人に内容を話したりSNSで感想をシェアしたりして1週間に3回アウトプットする
0投稿日: 2023.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内容の流れとして ①本を読むことの意義 →自己成長やストレス緩和、幸せになるための糧になるのが本。 ②具体的な方法3選 →アウトプットをする、隙間時間に読む、深読する。の3点が重要。 アウトプットするというのは脳科学的にも裏付けがあり、「1週間のうちに3.4回アウトプット」が重要となる。 具体的には、感想を書く、人に話す(おすすめ)、レビューを書く。メモを取ることが重要。 他人に見られるSNSなどに記載することはなおさら効果的。 隙間時間に読むということは、本を読む習慣を作り上げる。そして、何よりスキマ時間に読むことで多くの本を読むことができる。 しかし、人間の集中力には15.40.90の法則があって90に関しては途中に休憩があれば保つことができる人間の最大集中力のこと。 ひたすら読み進めることは集中力の観点から難しいからそういった意味でもスキマ時間は効果的。 深読というのは樺沢さんの造語で、質よく読むようなと、重要なのは本を読む目的が字を読むや、量を読むということではなく、自己成長のために読んでいるということを忘れてはいけない。 そして、その際にやらさている感ではなく、楽しんで読むことができれば脳内物質的にも効果的に記憶される。 深く読む、ことの重要性を知りました。 他には細かいことが記載されていて 脳内物質による記憶 本の読み方→目次から読みたいとこだけ読む 選び方→自分のレベルにそう、直感を信じる、芋蔓式に読むなど。 日本人の読書量について この本を読んで改めて本を読むという行為の意味が重要だと痛感しました。ただ読むだけだなく、何のために読むのかを常に考えながら読むとより内容が入ってくると感じました。 また、本を読んで終わりではなく、それをアウトプット、行動に移すことでより内容を自分のものにできるので、積極的に取り組むことで自分のものにしていこうと思います。 本は将来への自己投資であって、貯金をするならお金ではなく、知識が大事。 どんどん、蓄えて将来の自分への投資を行っていこうと思いました。 本を読むことがあまり得意でなく苦手だった私が、ワクワクして最近は読むことができているのでドンドンこの感覚を大切にして読み進めていこうと思った1冊です。
0投稿日: 2023.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の後にはアウトプットが必要。わかっていても中々できない。筆者はマーカーを引くだけでもアウトプットになり、記憶に残るという。また、このように記録に残すことでも定着するため、今後なるべく感想や気になった点を書き込むようにしたい。
0投稿日: 2023.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・スマホ使ってる時間あるなら本読め ・感想をアウトプットしろ ・とにかく本読め という当たり前すぎる方法論。 しかも病気によって好きだった本が目が滑って読めなくなるという現象を読書家の医者のくせに知らないのか、とか、この本を取るたいていの人間は読書の有用性は理解しているのだからさっさと本題に入ってほしい、とか突っ込みどころ満載。 極めつけは進路を決定づけた運命の一冊がドクラマグラって・・・。ドクラマグラが悪いわけじゃないんだけどさ・・・。
0投稿日: 2023.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の量と年収は比例する。 ただ読書するのではなく、頭に入れる為にアウトプット前提で本を読む、本を読む目的を決めてから本を読むなど、年間300冊読書をする樺沢先生ならではの読書をするときにしている工夫が、書かれている本でした。 とても勉強になる1冊で、定期的に読み直したい本です。
0投稿日: 2023.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだ本を自分のモノにしたい方はもちろんのこと、 本が苦手…積読ばかり増えている…という方にもオススメしたい一冊です。目次を読むだけでも意識が変わるかもしれません。 樺沢紫苑先生の別の本を探していた時に、たまたま図書館で見つけて手に取ったことがきっかけでした。 タイトルの通りさまざまな読書術が端的明瞭にまとめられていて、すごく分かりやすかったです! ちなみに本筋と外れますが、前半に綴られていた読書の良さや効果の部分が私には一番刺さりました。 元々活字を読むことに対して苦手意識があった私が、最近読書好きに転換した理由が腑に落ちました(笑)
0投稿日: 2023.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだ本は読んだ気になっていた。内容は覚えておらず自己満足だと感じた。 アウトプットが大切❗これからはアウトプットして自分の側頭葉の金庫に保管する(¬∀¬)
2投稿日: 2023.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書全般についてではあるものの、ビジネス書読者や、読書を仕事に活かしたい、成長したい人向けの話が中心なので自分とは方向性が若干ズレる。 のだけど、まさに「読んだけどどんな内容だっけ…」が多発しているので…というのが読んだ理由。 やはり決定打はアウトプット。そうだよね…と(重い足取りで、でも影響を受けたい気分のうちに)久々に感想を書いている。 あとは興味がある、わくわくする、ドーパミンが出てる状態で読むこと。鉄は熱いうちに、一番興味がある時に。 意外だったのは、隙間時間の読書について。私は物語中心の読書が念頭にあるので、読書はがっつり邪魔の入らない時間をとりたい、とったほうがいい読書になる、と考えていた。 でもこの本だと、人間の集中できる時間や、制限時間や目標がある方がドーパミンが出る…という理由で、隙間時間読書を積極的に推していた。 言われてみれば確かにそうなのかもなあ。物語については自分の意見は変わらないけれど、最近はノンフィクションの方が読むことが多いし、これは参考にしたい。 しばらくは読書記録をつけてみよう。
2投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の習慣を付けたいと思い、読み始めたこの1冊。 「読んだのはいいものの、少し時間が経つと内容を忘れてしまう」という悩みを抱えていました。 お金と時間をかけて読んだのに、学んだことを身につけることが出来ていない、、、 この本を読んで、今まで自分が「読んだ気・学んだ気」になっていたことに気付かされました。 記憶に残すためには「アウトプット」と「スキマ時間」が鍵となる。 普段SNSは「見る専」ですが、アウトプットをしていくために、本アプリを用いて感想を投稿していくことにしました! まずは月7冊を目指していきたいと思います! 読むと猛烈に読書がしたくなる一冊です。 読書習慣がない人にはとくに読んでいただきたいです✨
2投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログちょくちょく本は読むが、その内容がしっかり頭に定着しないため、アウトプットとしてブクログに感想を書いていた。しかし、それでも数週間前に読んだ本の内容を忘れてしまうことが悩みだった。 心理学の専門家である著者の非常にロジカルな読書術は参考になり、真似てみようと思った。 キーワードは「アウトプット」と「スキマ時間の活用」。 ★最初のインプットから7〜10日以内に3〜4回アウトプットすると、脳内で知識が短期記憶から長期記憶に移動されて定着する 1冊読み終わった後は以下でアウトプットするようにしてみる。 ①すぐブクログで感想を投稿し、②2〜3日後にTwitterで感想・要点投稿、③6〜7日後にブクログの再読記録に投稿
1投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさん本を読みたい!と思わせてくれる一冊でした。読んだらまずは感想を書かなきゃと思いながら初めての感想を書きました。
1投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
要約 ・記憶に残らない読書は何の役にも立たない自己満足読書だ。本は何千人もの経験をたどれることができ、時間術・仕事力・脳の活性化・健康を手に入れることができる。だからこそ記憶に定着化させるために週3回のアウトプット、そして4日に1冊のペースで読むインプット、それを可能にするスキマ時間の活用、15分という高い集中力を保てる制限時間を設けることで記憶に残す方法が記されている。さらに失敗しない本選びとして守破離から自分に合ったステージの本を選び、より多くのことを本から吸収するコツを教えてくれる。 「記憶に残らない読書は何の役にも立たない自己満足読書だ。」 読了後に忘れたくないと思っても忘れてしまう私にとって、一番響いた言葉。なんとか記憶に残したいと思い読み進めたが、序盤は筆者の話ばかりで早く方法を教えてくれ!とモヤモヤしながら読み進めていったが、実体験や共感できるエピソードやエビデンスを元に方法を伝授され、実践せずにはいられなくなりペンでどんどんラインを引き、この読書アプリをインストールするまでに!方法自体はそこまで難しくないことと、本で人生を変えることができると思わせてくれるところが魅力的だと感じた。 初めてのレビュー・要約なのであまり参考になさらずに笑
0投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の人柄になんとなく面白く惹かれるものを感じた。 今度からの読書の仕方が変わるようなそんな予感が今、自分の中にある。 本にLINEマーカーは日ごろからしていたことだけれど、余白に書き込みはあまり意識していなかったから、今度からは余白も意識してメモとして活用してみようと思った。 また自分が何気なくしていた本の読み方。この本で言うと、ワープ読書術を私はよくやっていたなぁと改めて実感。 ワクワクするような自分の知的好奇心を満たす読み方もまたありだなと思った。 様々な本の読み方を紹介してくれていたからとても参考になったし、今後活用しながら読書をしてみようと思う。
3投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ【きっかけ】 『アウトプット大全』で紹介されていたから。 『読書脳』が新版として出てしまいそっちを先に読んだけど、せっかく図書館で取り寄せてもらったので。 【心に残ったところ】 ◉キーワードは「アウトプット」と「スキマ時間」 ◉月10冊読む人は、日本人の上位2%に入れる! ◉「読書エンタメ理論」読書はなぜするのか?楽しいからに他ならない!安いし、どこでも読める! ◉「1週間に3回アウトプットされると記憶される『三度目の正直読書術』 ◉「スキマ時間だけで月30冊も読める」 ◉「電車でスマホを触るのは最大の時間の無駄である」 【感想】 これは2015年に書かれた本だけど、今でも十分通用するぐらい有益な本だった。 著者も言っていたが、新版とあまり内容が変わっていないからすごいと思う。 スマホいじるなら読書。 自分に言い聞かせて本を読む時間を増やしたい!
3投稿日: 2023.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ今後読書する上で実践することを時系列でまとめる。 ①「なぜ読書をするのか?」 →好きな作家の小説でワクワクしたい(A) →実用書から仕事のテクニックを学びたい(B) →哲学的な本から考え方について学びたい(C) (A)の場合 "好きな作家の本"は既に好奇心が高まっており記憶に残りやすい。→③ (B)(C)の場合 "守破離"を意識した本選びが重要。→② ②「学びたい内容における自分の知識レベルはどうか?」 →その手の本は読んだことがない...入門書レベル(守) →ある程度理解していて知識を深めたい...専門書レベル(破) →更に専門的な知識や応用編について知りたい...超専門書、論文など(離) ③「何で読むか?」 →紙の本(全体をパラパラ見たり、読みたい箇所にすぐ飛んだりしやすい) →Kindle(安く買える、持ち運びが便利、マーカー機能や検索機能が便利) ④「いつ、どのように読めば良いか?」 スキマ時間(電車移動中、休憩中)や寝る前に 制限時間を設けて、 知りたい結論を先読みしてから読み返す。(B,C) 読み返す前に先に全体をパラパラと読み全体像を把握する。(B,C) おもしろいと思ったら一気読みして良い。(A,B,C) 大事な文には印を付けること。 またKindleも活用すれば読みたい本を読みたいときに読めるため、記憶に残りやすい。 ⑤「1週間以内に3回アウトプットする」 印をつけ、人に話しおすすめし、レビューを書く。 ただし、レビューや感想は読み終わった翌日以降に実施すること。興奮冷めやらぬまま書いても、楽しかった!とか、良かった!しか出てこないため。 ★おすすめしたい人 ・読書が続かず悩んでいる人 ・速読ばかりで記憶に残らず悩んでいる人 ・少しでも記憶に残る読書法を知りたい人
1投稿日: 2023.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだら忘れないようにするためには、「1週間に3回アウトプットする」という原則を実践するとよいとのこと。 さらに、具体的な方法が、本書の中に示されているので、まずは、アウトプットをするということを意識して読むようにしたい。 そして、読んだことを、行動に移す!
0投稿日: 2023.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 知識をつけるのに最適な方法。他人からもらうこと。もらったら自分のものになっているか確認する。別の人に伝えられるか。
0投稿日: 2023.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ★3.6 読書の「量」より「質」を高めたいあなたへ。 最近読みたい本が多過ぎる。伴って、出来るだけ再読はせずに新しい本に時間を費やしたいという気持ちも強くなってくる。 そんなわけで手に取った本著。 ビジネス書を読む人に向けて、という傾向が強いが、小説を多く読む人にも得られるものはあるだろう。 「速読」ではなく「深読」。 読んだら忘れない、のテクニックは勿論、そもそも読書の価値を再認識できた。 鉄は熱いうちに打て、と言うように、本はワクワク感がある内に読め。
12投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今まで読んだ本の内容をすっかり忘れてしまっていたり、本当にこのままの読み方でいいのかなぁと常に不安というかモヤモヤしたものがあったので、この本は本当に読んでよかったと思った! まず私は小説を読むのが好きだけれど、小説は啓発本や実用書と比べて、ただの娯楽なのでは…と小説以外も読まなければと思っていた。でも、ただ楽しむことで得られる効果や、小説は「共感力」が鍛えられると書かれていたのが、とても嬉しかった。これからもたくさん小説も読む。 この本のキーワードは「アウトプット」と「スキマ時間」。アウトプットの力を上げる、内容を頭に定着させるため、このブクログを始めることにした。一応誰かに読まれるかもしれないというプレッシャーにより、少しドキドキしている。今、脳内記憶物質ドーパミン出ているのでしょうか。 響いた言葉↓ ●たくさん本を読める人は時間管理が上手な人 →時間ができたら読書しようとか、今忙しくて本が読めないとか、恥ずかしくて言えなくなりました。 ●「財産を奪われても、知識だけは奪えない」 知識は最高の貯蓄 →ほんとにそう。知識をたくさん貯めて、実生活で知性として生かしたい。 ●将来にたくさんの不安があっても、あなたが自己成長すれば、たいていの問題は解決する。 →そうだよなぁ。不安なのは勉強不足や準備不足だからだと思いしらされた。 脳科学に裏付けられたものなので、説得力が大きかったし、著者の読書術にアレンジしながら、これからの自分の読み方を確立していきたい。大好きな読書、本。せっかく読むなら自分の身になるように読みたい。そしてそれを習慣化する!
0投稿日: 2023.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ他人の知識は買えるというフレーズが印象に残った。弓道をしていた時に、自分で一から考え我流で引くことが遠回りで、先人の教えを吸収することが大事だと感じたことを思い出した。 月7冊で日本人の上位6%になれるなら読むっきゃない! 読まないと、と思って読むことが多かったけれど、楽しみに意識的に変えて読もうと思った。効果あげたい。 本を読んだの定義が、内容を説明できること、内容について議論できることと書かれていて今まで読んだ本はただの自己満になっていたことがもったいなかった。 これからは読んだらその日か翌日には簡単な感想、1週間以内に詳しい好評レビュー的なしっかりとした記事を書きたいと思って描き始めた。 文字の大きさや太文字でスラスラ読めた!今後の読む時参考にしたいと思った。
1投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ本が好きだけど、ほとんどの本を忘れてしまっていると思い、この本を読んでみました。 この本で一番印象に残ってるのは「1週間に3回アウトプット」 今まではかなり気に入った本以外は人に紹介することはありませんでした。 頭に浮かんでいることを言語化して説明するののが得意ではないですが、 まずはその第一歩のアウトプットとして今回初めて感想書いています。 こうやって読んだら行動することの大切さを改めて実感できました。 他にも「生グレープフルーツ読書術」や「結論から読む」など本の読み方変えていこうと思いました。 私にとって、この本は新たな行動に繋がる大切な本となりました。
2投稿日: 2023.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の仕方はもちろん、本の選び方、買い方、紙と電子とどのように使い分けるかなど、幅広い範囲を網羅して記載している。 個人的には、 ・スキマ時間を活用して本を読むことで読書量を確保する。 ・読書した内容を複数回アウトプットすることで定着させる。 ・守破離を意識して、難し過ぎる本や本格的な本ばかりを読んで「分かったつもり」にならないよう、基本的な入門書から読む。 ・様々なジャンルを同時進行するのではなく、特定の分野を固めて読むことで深掘りする。 ・参考文献の部分にも目を通し、「数珠繋ぎ」のようにして専門分野の知識を取り入れる。 などの部分は身に積まされるものが多く、早速実践しようと思った。
1投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いろいろな読書術があって、それぞれユニークなネーミングが付いて、とても親しみやすい方法がたくさん掲載されています。しかも、すべてが脳医学の観点から説得力のある説明があるから「やってみよう」と簡単に着手できる方法に目からウロコが落ちる思いでした。 しかも中には「すでにその方法、やっていた!」っていう内容もあって読書の方法は間違っていなかったんだなぁって思いました。特に印象に残った読書法はスキマ時間を使った読書方法でした。ぜひ挑戦してみてください。 ちゃんと記憶に定着していましたから。
0投稿日: 2023.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これから本を読んでいく中で、やはり記憶として定着させていきたい。そのためにこの本を手にとった。 精神科医の視点から、どのようにしたら忘れない読書をできるかが書かれており、読書習慣化を目標にしてからの2冊目の本としてはとてもよかった。 この本は一章で読書をすることのメリットをまとめており、その中でも私の心に響いたのは日本人の読書量の話である。月に7冊以上の本を読んでいるのが日本人の3.6%であり、本を7冊読むだけで上位4%に入ることができると述べていた。私はこの本の感想を書いている現時点で一ヶ月7冊の読書を終えている(本のページ数に差はあるが…)。約半月で7冊読めるということは10冊読んで上位2%に入ることもそこまで難しくはないと感じる。そんな風に読書量としてのモチベーションをこの章の中で身につけることができたと感じる。 二章では本題の忘れないための読書術を教えていただいた。一つ目としては一週間に3回アウトプットするということ。アウトプットの方法として、書評・レビューを書くことを勧めており、私が今実際に実行していることである。他にもスキマ時間を読書に充てることや速読よりも内容を理解する「深読」をするということを読書術としている。 三章、四章ではアウトプットの方法をさらに深掘りしている。マーカーやボールペンをつかって汚く読むことが記憶に定着させるために不可欠であることや本の内容を要約して相手に伝える大切さ、15分の時間で本を読むと集中力が最大になること、睡眠前や起床後すぐに読書すること、自分の興味のある分野でありレベルに合った本を選択する重要さを教えていただいた。 最後の章では、本の選び方と樺沢先生のおすすめの本を紹介されていた。是非私自身のの興味のあるものを見つけ読んでいきたいと思う。 このように読書のやり方を説いてくれたこの本を私は時々読み直して自分の中に定着させたいと思った。
0投稿日: 2023.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な読書術が記載されているので、 とても参考になります。 せっかく読書をしているので、身につけたいと思いました。 『アウトプット』『インプット』『スキマ時間』『ワクワク感』 お勧めの本屋さんまで紹介されていて行ってみたくなりました。
4投稿日: 2023.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと読書を続けているが、読んでいても身になっていないなと思い読みました。 正確には読み直しです。 読んで得たもの(インプット)を発信する(アウトプット)ことを改めてやっていこうと思いました。
1投稿日: 2023.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログインプット大全、アウトプット大全を経て、この著書を読んで、個人的な見解だが、より具体的な著書から得られる知識を血肉にするためのハウトゥーが記されている著書。 以前より速読ができるようになり(1分に1.5ページ読むのは速読なのか…知らんけど)、多くの著書に出会えるようにはなったものの、本の概要を大まかに理解できるがあまり具体的な部分を忘れてしまっており、悔しい想いをしてしまっていたところで、この本に出会った。 こうした「評価と感想」を描くのも一種のアウトプットの一回に数えられるが、今後はさらにフェイスブックでも感想を外に発信することで、脳の海馬に中身を刻み込んで行きたい。
1投稿日: 2023.06.13
