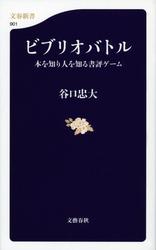
総合評価
(93件)| 18 | ||
| 28 | ||
| 24 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読んだ本にビブリオバトルの話が載っていたので興味を引かれ手に取りました。 興味を引かれたといってもバトルに出てみたい とかではなく、皆が読みたくなるような「本のプレゼン」の仕方についてです。 なので思っていた内容と違っていたのですが、いろいろ知ることが出来ました。 本書の著者がビブリオバトルの発案者であり大学の理系研究室の勉強会が発端ということに驚きました。 てっきり、書店や図書館が先頭に立って行なっていたと思っていたからです。 本書は「ビブリオバトルの遊び方」、「ビブリオバトルの生い立ち」、「いい本との出会い」、「ビブリオバトルの現在と今後」、 プロローグとエピローグにビブリオバトルの短編小説がユーモアを交えて描かれています。 ビブリオバトルとは、本を通して人と人、人と本を繋ぐコミュニケーションゲームです。 ビブリオバトルの開催レポートで面白いビブリオバトルが掲載してありました。 なんと、「妖怪ビブリオバトル」 妖怪好きによる妖怪好きのためのビブリオバトル。 本のプレゼンを聞いているだけでも面白そう。 妖怪のコスプレして来る人とかいるともっと盛り上がりそうだ。 ビブリオバトルの副産物として、コミュ力やスピーチ能力、プレゼン能力の向上等がみられいろいろなシーンで役立っているようです。 なので、会社や学校、図書館、書店等に幅広く普及されています。(私の周りではまだ耳に入らないけど) 特に小中学校の授業に取り入れるのは素晴らしいアイデアだと思う。ゲーム感覚で楽しく学べるし読書離れの解消や本を通して人を知ることにも繋がる。意外な一面を知って仲良くなるかも。 面白い本や人と出会うきっかけにもなる。 それがきっと楽しいんだと思う。 このブグログもそうですが読書の楽しみをたくさんの人で共有できる場所が増えるのは嬉しいし楽しいことです。 全国大会やいろいろなビブリオバトルがあるようなので機会があれば見学してみたい。
24投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近になり、ビブリオバトルを知りました。 本書の著者は、そのビブリオバトルの考案者です。 著者、谷口忠大さんは、ウィキペディアによると、次のような方です。 ---引用開始 谷口 忠大(たにぐち ただひろ、1978年6月24日 - )は、日本の情報工学者。立命館大学情報理工学部教授をへて、京都大学情報学研究科教授。パナソニックシニアテクニカルアドバイザー。ビブリオバトルの考案者として知られる。専門は人工知能、記号創発ロボティクス、記号創発システム論で、環境との相互作用を通して、人工知能やロボットが自律的に内部表現や認識を構成する仕組みを研究している。 ---引用終了 で、本書の内容は、BOOKデータベースによると、次のとおり。 ---引用開始 おすすめの一冊を持ち寄り、本の魅力を紹介し合う書評ゲーム「ビブリオバトル」。たった4つのルール、5分間の熱いプレゼン。ネット時代の新しい本と人との出会いを生む“つながる読書”の全貌を、ゲーム発案者が描く。 ---引用終了
46投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ152〜160ページ辺りにビブリオバトルの本質が書かれている。バトルを通して、人を知る。そうしてコミュニケーションをとることで、豊かな時間を過ごすことができると思う。
1投稿日: 2024.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトル、面白いですよ! やり方を知りたい人は、 本を読むよりHPを覗いた方がいいですね。 本書は、ビブリオバトルの歴史が綴られ、 それを味わうための本。
1投稿日: 2023.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ838 学校で読書感想文じゃなくてビブリオバトルやった方が100倍良いと思う。読書好きな人で読書感想文好きな人見た事ないし、読書感想文こそが読書嫌いにさせる要因だと思う。 【公式ルール】 1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 2.順番に一人5分間で本を紹介する。 3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2〜3分行う。 4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加 者全員一票で行い、最多票を集めたもの『チャンプ本』とする。 本との出会いは「縁」だ。その本が自分にとって面白いかどうかは実際に本人が中身を読ん でみないとわからない。とはいっても、本屋さんに並んでいる本を、左上から順に棚ごとに大 人買いして、片っ端から読んでいくということはできない。自分のポケットに入った財布の中 身を考えても難しいが、それよりも時間だ。実際問題として、冷静に計算してみよう。お金は なんとかなるかもしれない。もし僕が何かで財をなして大富豪になったら、全ての本を購入す るだけなら可能であるかもしれない。しかし、時間は誰にとっても平等であり、有限だ。 一冊を一時間で読める速読術を学んだとしても、一日に読めるのは、せいぜい八冊程度だろ う。これを八十年間続けたとしても、一生に読めるのは約二十三万三千冊。 人に本を薦める、薦められた本を読むというのは、一つのコミュニケーションとして重要で あるし、そういうことを通じて、お互いを知り合う機会にもなる。「この人も読んでいるなら、 面白いに違いない」という、人に依存した選択は意外に正しい場合も多い。また、間違ってい たとしても、人から薦められた本だからこそ、読んだ後のコミュニケーションが弾むこともあ る。 「読書はどちらかというと一人で読んで一人で納得するものだったけど、ビブリオバトルなら 読書をみんなで分かち合える。公共図書館だからこそ、『みんなで分かち合える』という面が 大事なのかなと思います」 ビブリオバトルの後は、上下関係や部署などの枠を超えて、今までにないコミュニケーションが起こるそうだ。秦社長はまた「設立五十年目から百年へという会社の歴史の中で、ビブリオバトルによって、会社の未来のクオリティが変わったと思っている」と、話された。僕自身にとっても、これほど嬉しい言葉はない。ビブリオバトルを様々な会社内のインフォーマルコ ミュニケーションの活性化に役立ててもらえれば本望である。
1投稿日: 2023.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルのルール、成り立ち、目的、効果効用、世間への浸透具合が説明された本 最近、初めてビブリオバトルに参加してみてイメージしてたより楽しかったので読んでみた 読書会にはよく参加するけど、ビブリオバトルはやったことがなかった 「チャンプ本」を決める、という行為が本に優劣をつけているように思っていた 本はあくまであるだけで、それを読んでどう感じるかは人それぞれであって、どんな本でも特定の人にとっては唯一無二の本 なのに、限られた集団の中で発表の内容も含めてチャンプ本を決めるのは乱暴な気がしてた でも、実際に参加してみると、チャンプ本に選ばれるのはその本を面白いと感じて他の人にも伝えたいという想いが伝わってくる発表をされた本 なるほど、確かに本を知ると共に人を知る事ができるなぁと思った ビブリオバトルの発祥は工学部の情報系研究室の輪読会の選書からとのこと 著者が所属していた研究室の輪読会 発表者以外は読んでこなかったり、自分の担当意外の部分は理解は浅かったり、そもそもどの本を選ぶかという最初の問題がある そこで、次に読む本を皆で持ち寄ってプレゼンし合い、一番得票数の多かった本を次回まで読んでくることにしたのが始まり その後、本について話したい人は研究室内で話すし、読みたい人は勝手に読むという事で、チャンプ本を決めるだけの形式に落ち着いたらしい ☆ビブリオバトルのルール 1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる 2.順番に一人5分間で本を紹介する 3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う 4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする 基本ルールはこれだけ 他には、テーマを設けても良いとか、質疑応答は4チャンプ本を決めるための参考となるような質問にするとか、審査員等を設けずに参加者の投票で決めるとか あと、紳士協定として発表者は自分以外の本に投票するとかくらい その他の決まりは特になく、順番の決め方やタイトルの発表方法などは適宜決めて良い レジュメや原稿の使用を禁止していないのは、チャンプ本に選ばれるためにはそういった物を使わない発表が必要になるため、必然的になくなるとのこと ビブリオバトルの意義としてはいくつかあって その一つは「本とどうやって出会うか?」という事 リアル書店で買うか、ネットで買うかといった議論よりも前に、その本を買おうと思ったのは何がきっかけか? ネットでのレコメンドなどいくつかあるものの、自分の好みと類似したものがオススメされるので意外性がない 他の人に薦められるという経験はなかなかない そこで、ビブリオバトルでの本の出会い あと、ビブリオバトルは 「人を通して本を知る。本を通して人を知る」 という行為 そもそもチャンプ本を決める意義としては ささやかな心理的インセンティブとしてのチャンプ本という動機づけ 発表者はチャンプ本に選ばれるように、発表するコミュニティに沿った選書になる そこで聴衆への理解というコミュニケーションが発生する 聴講参加の人は、チャンプ本を決める一端を担うという責任感で発表を真剣に聞くようになる だからこそ、単なる本のプレゼンだけで終わらずにチャンプ本を決めるルールが必要 チャンプ本に選ばれるため、チャンプ本を選ぶため、参加者は本をううじてお互いを理解しあう ビブリオバトルの効果効用としては まずは、本と出会える 本の内容を共有できる お互いの理解が深まる スピーチの訓練になる 著者としては、ビブリオバトルをもっと気軽に楽しめるようなもとして普及させたいとのこと 固有名詞ではなく一般名詞になるくらいになってほしいらしい 今はビブリオバトルがイベントとして行われていたりするが フットサルやドッヂボールのように、気軽に人が集まって行われるようなもの 例えば、家族内でもいいし、最少人数3人でも開催できる 私は冒頭でも書いた通り、読書会にはよく参加するけどビブリオバトルの経験はまだ少ない でも、小説や「BISビブリオバトル」、藤野恵美「ふたりの文化祭」でのビブリオバトルのシーンなど、何かと影響を受けて本を読んでいるわけで 普通の読書会だけじゃなくて、もっとビブリオバトルにも参加してもいいかもしれないと思った
1投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルというものがあるというのは聞いたことがあったけど、起源が明確なものとは思わなかった。京都大学の輪読会が発祥というのはなんか納得できた。 書籍情報共有、スピーチ能力向上、良書探索、コミュニティ開発、いろんな効果があるんですね。
1投稿日: 2022.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルという書評ゲームの奥深さを知れた本です。 これまでビブリオバトルのルールなどは、他の物語形式の本を読んでわかっていたけれど、ビブリオバトルができた経緯、存在意義などについて知ったのは初めてで、感動しました。 私もこんな風に何かを作りたいなと思います!
0投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ書評紹介なら、勝ち負けはいらないと抵抗感があったが、観客を意識して本を選び、プレゼンの仕方を工夫するというところで、闘争心をあおるきっかけとしての勝ち負け。そのうちに技術論、ビブリオバトルの勝ち方なんて言う事にならないだろうか。
0投稿日: 2020.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの創設者による、ビブリオバトルについての本です。 ビブリオバトルが大学の研究室で生まれた経緯などが書かれています。 一つ一つのルールの意味を知れるので、なるほど、そこは参考になりました。 とにかく、本を紹介すれば、その紹介者の人柄がわかる、ということ。 私も生徒にやらせてみたけれど、本の紹介そのものは楽しんでいたように思います。 ビブリオバトルの小説チックな内容は読むのが辛かったかな…。
0投稿日: 2019.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は深い。ビブリオバトルは深い。 単にビブリオバトルのやり方を書いてある本と思って手にしたが、いやいや、OMOの時代に大切なことや、最新のコミュニティマーケティングの肝になる部分もしっかり分析して伝えてくれる。理系の研究者の言葉の説得力は素晴らしいものがある。
0投稿日: 2019.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの目的、よさについて理解できた。 ・書籍情報共有機能 ・スピーチ能力向上機能 ・良書探索機能 数え切れない本の中から、良い本を選定するためのフィルター的機能がある。 ・コミュニティ開発期間 紹介する本を通してその人を知ることができる。コミュニケーションの場づくりがビブリオバトルの本質である。 ☆チャンプ本を決めることの意味 本を紹介するコミュニティに対して良書を選ぼうという動機付けのため、一方的でなく聞き手に一生懸命伝える努力をうながすために、チャンプ本を選ぶという仕組みか必要である。チャンプ本を決めるために投票する側もしっかり聞くようになる。
0投稿日: 2019.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトル、面白そう!ってのがとりあえず一読の感想。プレゼン下手の治療にはもってこいだろうし、どうしても独りよがりに陥りがちな読書っていう営為に、思いも寄らない自己的ブレイクスルーをもたらしてくれそう。職場とか家庭で取り入れてみたい!っていう欲望が沸々。という意味では、本書の目論見は見事に果たされているってことですね。というか、本書そのものをビブバトしてみたい、って感じ。既にどこかではやられているんだろうけど。ただ、最初と最後の小説風パートは完全に蛇足。最終的には読み飛ばしたけど、何でこんなもの混ぜたんだろ?頁数(=収容スペース)の無駄です。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者でビブリオバトルの発案者である、谷口氏は京大出身で立命館大学情報理工学部准教授。こういう「遊び」を考えつくあたりはさすが京大だなぁと感心。
0投稿日: 2017.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの起こってきた背景、本来目指しているものについて丁寧に書かれており、単なるビブリオのノウハウ的なものではなく、一読に値する内容。 情報検索という視点からのビブリオの有用性について述べている部分や、研究室での勉強会を活性化させるところに端を発しているところなど、とても納得がいく。確かに読書会でみんなが本を読んでくる状況を作るのは難しい。ただ、学校でビブリオをやってみようとすると、どうしても「本を知る」方に力点が行っしまい、本来のコミュニーケーションの視点が抜けてしまうのが残念・・・。
0投稿日: 2017.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内容は、読書に関して非常に面白い取組み、ピプリオバトルの紹介。これは、数名が自分の紹介したい書籍を5分程度で紹介し、その中で優れた、あるいは良かった、あるいは読みたくなった紹介本をトップと認定する書評ゲームである。◇単なる本の紹介だけでなく、紹介者の人となりが開陳されるし、友人関係や信頼関係を作り上げるツールとしても、プレゼンテーション能力向上のツールとしても有益。また、大学生のみならず、中学高校、社会人、果ては小学生まで可能なはず。◇なお、読メも文章によるビブリオバトルの趣き。◆著者は立命館大学准教授。
0投稿日: 2017.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ発案者によるビブリオバトルの解説本である。その公式ルールから、発案に至った経緯、そのルール設計の工程などが詳しく説明されている。 この本を読めば、公式ルールの重要性やその意図するところはハッキリとわかる。なぜチャンプ本を決める必要があるのか、なぜ5分なのか、そうした公式ルールを破ることでビブリオバトルが意図する部分が損なわれる(可能性がある)ことが理解できるだろう。 イベントとしてのビブリオバトルが紹介されている一方で、物語仕立てで実際の実施する風景が著述されている点も、実施する上では参考になるだろう。 発案者の意図するところでは、家庭単位で行えるくらい身近な知的スポーツであるようだし、この本を読んで仲間内で始めるくらいの姿勢が望ましく思える。 某テレビ番組では「自分のお勧め本を紹介するなんて、××(下ネタ表現のため自主規制)を見せてるようなもんですよ」と、そうした考え方もあるため、ビブリオバトルそのものが万人に受け入れられるかというとまた別ものだろう。 そうした方への啓蒙としては機能しないが、より正しい形でビブリオバトルを行う上での教書としては適切な一冊である。内容に不足はなく、ここでは星五つで評価している。
0投稿日: 2017.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、好きな本を1人1冊5分間で紹介しあい、どの本を読みたくなったかを投票で選ぶゲーム「ビブリオバトル」の創始者で、ルールや歴史が紹介されている。キャッチコピーは「人を通して本を知る。本を通して人を知る」。本との出会いの場となるだけではなく、参加者のコミュニケーション能力が高まり、学校、職場、地域などで行えばよいコミュニティを形成するのに役立つという。とても面白そうだ。
0投稿日: 2016.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルというゲームのルールは今の時代にあっていて、発明だと思う。 知識は人に結びついていうこと。文章は人(その人のバックグラウンド)により読まれ方が違う。 人格を持った一個人に知識が結びついてるからこそ、ダイナミックな活動の中でしか、人が人を理解したり、人が人を通して知識を得られない。
0投稿日: 2016.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ巷で話題の「ビブリオバトル」の発案者である立命館大学の谷口先生が書かれた本。 「ビブリオバトル」が生まれた経緯、この本を読むまで完全に勘違いをしておりました>_<谷口先生が立命館で教鞭を取られるようになってから生まれたものだと・・・。京大のポスドク時代に研究室で新しく勉強会を立ち上げようと試行錯誤する中で生まれたものだったのですね。このアイデアを思いつき、形にしたのがすごいなー。 ビブリオバトルの4つの機能(書籍情報共有、スピーチ能力向上、良書探索、コミニュティ開発)にも、納得です。実際にやらせてみてどれも実感できました。 あと公共図書館でビブリオやることについて、「ビブリオバトルは、もっぱらの公共図書館でなかばタブー視されている二つの要素をはらんでいるからこそ、人々を惹きつけているのではないだろうか」(p184)という考察にもハッとさせられました。たしかに、ビブリオバトルは今まで公共図書館になかった「人を通して本を知る。本を通して人を知る」という視点、また「賑やかさ」をもたらしていると感じます。 あとビブリオは情報推薦の分野でも難問タスクとされる「『意外な本』だけど『読みたくなる本』を推薦する機能」に秀でているという研究結果も面白い。(p151)
0投稿日: 2015.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本を通して人を知る。人を通して本を知る。」という筆者の理論に感銘を受けました。ビブリオバトルは、読書活動だけでなく、コミュニケーション力やプレゼンテーション能力の向上にも繋がり、また、人と人との関係づくりにも繋がるなど、あらゆる可能性を感じました。
0投稿日: 2015.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯文:”学生から社会人までもっと本を語りたくなる!「つながる読書」革命!” 目次:はじめに ビブリオバトルって何? プロローグ そんな日常の「ビブリオバトル」、第1章 ビブリオバトルの遊び方、第2章 ビブリオバトルはどうして生まれたのか? 第3章 本と出会い人を知るためのテクノロジー、第4章 広がるビブリオバトル、エピローグ いつか会えたら「ビブリオバトル」の話をしよう、あとがき
0投稿日: 2015.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きな本を持ち寄ってそれを推薦する5分のプレゼンを行い、それを競い合って一番を決めるというビブリオバトルの考案者による案内書である。世間に横溢する出版物はすでに読書歴を共有することが困難であることを示している。このゲームは自分の知らなかった本と出会うきっかけを与えてくれるという点で興味深い。 本書のサブタイトルが「本を知り人を知る書評ゲーム」であることが端的に示すように、筆者はこのゲームを通して人と人との深いコミュニケーションを図ってもいる。学術的な評論ではなく、アドリブを含めた5分間のパフォーマンスを軸としたのも、より人間的な要素を引き出す工夫になっている。 実は私は読書活動推進策の一つとして中学生にビブリオバトルを紹介することを考えている。これを完成させるためには、まずは自由に自分の意見を表現できる雰囲気をつくらなくてはならない。本書は京都大学などの大学生や院生といった「大人」の例が大半であるが、中等教育に導入するためにはそれなりの下地づくりも欠かせないと思った。
0投稿日: 2015.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書好きであったが、本を使った「ビブリオバトル」なるものが旭日とは知らなかった。興味を抱き読んでみる。 各々が好きな本をアピールして、その発表を聞いて読みたくなった本一位を決めるもの。なるほど、発表、ディスカッション等の練習にもなるし楽しそうだな。 小学校高学年位からできるそうな。 ルール、一連の流れを説明すれば充分だと思うが、本にするためか、意義や歴史など蛇足的な文章が多く読みにくい部分も。 ・小学校高学年位から参戦できる ・有名な本よりあまり知られていない本の方が勝てやすい 【公式ルール】 1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 2.順番に一人5分間で本を紹介する。 3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。 4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。
0投稿日: 2014.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトル。 私は知らなかったのですが、最近各方面で普及が進んでいる書評を題材にしたゲームの事で、そのルールは ・参加者は持ち時間5分でおすすめ本のプレゼンを行う ・プレゼン後、2~3分程度の質疑応答 ・すべての参加者のプレゼンが終われば、投票にてもっとも読みたいと思った本、チャンプ本を選出する と言う簡単なものです。 本書は、このビブリオバトル考案者その人によって執筆されたビブリオバトル解説本で、ルール解説やビブリオバトルが誕生した経緯、その後の普及過程、 そして、ビブリオバトルを行う事によってどの様な効果が期待できるのか等が記されています。 冒頭で述べた通り、私はビブリオバトルの事を知らず、その存在は本書によって初めて知りました。 しかし、例えば公立図書館や書店でのビブリオバトルの開催の他、東京都後援でビブリオバトル首都決戦なるビブリオバトルの全国大会も開催されたとの事で、正直、「知らぬ間にこんなに普及していたのか・・・」と驚くことしきりです。 尚、ゲームだけあってルールは厳守。 プレゼンの持ち時間5分を過ぎると、例え途中であっても容赦なく打ち切られますし、また時間を余らせてプレゼンを終えることも出来ません。 その場合には、何とかして空き時間を埋めなくてはいけないとの事です。 ビブリオバトルは楽しんで行うものだと思いますが、しかしあえてそのメリットを考えてみると、 自分のお気に入りの本を5分間で売り込む。 チャンプ本に選ばれれば良し、選ばれなかった場合には、チャンプ本に選ばれた本のプレゼンと自分のプレゼンと比べ、自分のプレゼンを客観視できる。 また、他の参加者のプレゼンを通し、この人、こんな事が好きだったのか等と相手の意外な側面を知る事ができ、相互理解に役立つ。 等となり、結構自己啓発や人間関係の円滑化に役立ちそうですね。 機会があれば、ちょっと参加してみるのも良さそうです。 ちなみに著者によれば、書籍の中身を消化し、それを5分間のプレゼンに作り替えるビブリオバトルには漫画・アニメの世界ではよくある二次創作的な側面もあるとの事で、その点も興味深い所です。
0投稿日: 2014.11.02公式ホームページでは読めないビブリオバトルの世界
ちまたで流行りのビブリオバトルについて知りたい人。発案者が書いた本書を読むのが一番だろう。 が、実は公式ホームページもかなり充実しているので、本書を読まなくても特に問題はない(笑) ・・・と身も蓋もないことを書いてしまったが、それでもやはり、本書は一読に値する。 つまり、「ルールを知る」以上の、読み物としての面白さがあるのだ。 本書の最初の方と最後の方は小説仕立てで、実際にビブリオバトルをやってみたら・・・? という設定で描かれている。この部分とコラムの部分は何が面白いって、 実際に本が紹介されていること(笑)。 相手に「読みたい!」と思わせる。 これが勝負のゲームなのだから、本の紹介パートは面白い。 読んでみたくなる。そして、こういうレビューを書くときの参考にもなる。 真ん中の部分はちょっと真面目なお話。 コミュニケーションって何だろう、というような、 ホームページには書き切れないような踏み込んだことが語られている。 ビブリオバトルを発案した著者、文系だと思われがちらしいが、 実は理系で、修士課程・博士課程ともに、「人間とコミュニケーションするロボット」 について研究していたという。 ソニーのAIBOを素晴らしい存在だった、と思う一方で、 「何を実現したら、人間とロボットがコミュニケーションできたと言っていいのだろうか」 という根本的な疑問を持つようになる。 人と人、人と本の新たなつながり方を提示した著者。 ビブリオバトルのルールは小学生でもすぐに理解できる、シンプルなもの。 しかし、その必要充分なシンプルさに行きつくまでに、 ロボットとの葛藤、人との葛藤が数多くあった。 それが、ホームページでは読めない、本書の面白さ。
5投稿日: 2014.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった!!実例がラノベ調で挟まれてるからイメージしやすい。 しかし勉強会のネタ探しが原点とは恐れ入りました、、こんな院生生活送りたかったです 楽しく素人らしく、でも相手をみながら好きなことを伝えるってのは面白いもんだなあ、と ぜひやりたくなっちゃった 実は生徒がやりたいやりたい言うから、いっちょ勉強するか、と思って読み始めたけどわたしも参加したくなったわ やろーっと
0投稿日: 2014.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく早くビブリオバトルがやりたくなった。そこで、1か月後の祝日にやろうと思って企画することにした。職場で、子どもたちや保護者や講師たちも巻き込んでできればよい。それとは別に、自宅でもやってみたい。近所の人たちを誘って、ビブリオバトル×ホームパーティー、大人だけ?子どもも入れる?何かシバリを付けようか?初回はとりあえずフリーでいいか。数年前、齋藤孝さんの偏愛マップを持ち寄って飲み会をしようと提案したことがあったが、誰も乗ってこなかった。近所に本好きが何人かいるから、今度はうまくいくかもしれない。だいたい私自身がコミュニケーションが苦手で、2、3人の中なら話ができるが、5、6人になると聞き役に回ってしまう。10人以上とかになると、隣の人と2人で話したりはできるのだけれど。盛り上げたり、誰とでも気軽にできる共通の話題の持ち合わせがない。即興で臨機応変に話をするのが苦手というのもある。このビブリオバトルなら、自分の好きな本をある程度事前に考えて紹介できるからうまくいきそうだ。そのあとの、質問タイムなどでは上手に話せないかもしれないけど、5分内で熱く語れるはず。自分がいっぱい出せそうな気がする。やってみたい。でも、他ですごいことやってる人がたくさんいそうなのでその様子も勉強しないといけないなあ。YouTubeも見てみよう。 久しぶりの図書館で偶然見つけました。なぜ見逃していたのだろう。出版された当初、名前を知らなかったからだと思う。半年ほど前の新聞紙上で初めて出会い、その後、ブックカフェで実際に見た。最近なぜしてないのだろう。
0投稿日: 2014.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ簡単なルールでだれでも始められるビブリオバトルですが、輪読会の欠点を補う形で作られたなど、経緯を知るとなるほど!と思います。
2投稿日: 2014.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【つながる読書、ビブリオバトルの魅力とは?】おすすめの一冊を持ち合い、本の魅力を紹介しあう書評ゲーム「ビブリオバトル」。ネット時代の新たな本と人との出会いを提案する。
0投稿日: 2014.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログやってみたいなぁ。 この本をよんで、思っていたよりもハードルは高くないと思えた。 更に、思っていたよりも色んなメリットがありそうだと。 いいな。多くの人に本で楽しんでもらう仕掛け。
0投稿日: 2014.09.01読書好きから話し上手に
「趣味は読書です」「最近何が面白かった?」「ええと・・・」 本ばかり読んでいるので、知識は増えていくけれども、自分の中で完結してしまってコミュニケーションが下手という読書家さんは多いと思います。 何とかしたいとは思っていても、いわゆるビジネス書の類は二の足を踏んでしまって、「まあ、いいか」と諦めてしまっている、そんな人におススメの本かもしれません。 「書評ゲーム」というタイトルから、面白い本を知るきっかけになればと思い、手に取った一冊。早速読んでみたいと思う本もありましたが、それ以上に「本を通じて人を知る」というコミュニケーションの広がりを期待させてくれる一冊になりました。
4投稿日: 2014.08.31単なる書評ゲームではない
巷で噂のビブリオバトル、気になっていたので発案者の本を読んでみた。 ルールはいたって単純。 1)発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 2)順番に一人5分間で本を紹介する。 3)それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。 4)全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員で行い,最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。 のみと参入障壁は低い。読む前は、自分の気に入った本を紹介して一位を争う競技だろうと単純に考えていたがいろいろな効果が期待できそうでやってみたくなった。 1)参加者で本の内容を共有できる(書籍情報共有機能) 2)スピーチの訓練になる(スピーチ能力向上機能) 3)いい本が見つかる(良書探索機能) 4)お互いの理解が深まる(コミュニティ開発機能) 設計思想は「知識は人に紐付いている」であり、その人が人を介してもしくは理解して知識を得たり、得られたりする「コミュニケーションの場づくり」を行うのがビブリオバトル。あなたもやってみてわ。
4投稿日: 2014.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ巷で話題のビブリオバトルの概要を一冊にまとめたもの。 そもそも、ビブリオバトルとはなにか。一言で言えば、「本を紹介するプレゼン大会」といえる。 何より、ビブリオバトルのルールは非常にシンプル。 ・お気に入りの本を持参する ・順番に一人5分で紹介する!(+2~3分のディスカッション) ・「どの本を一番読みたくなったか?」で投票を行い チャンプ本を決める プレゼン力も上がるし、みんなでワイワイ話して楽しめるなと思った。個人的にはこれを機会にやってみたいと思う。
0投稿日: 2014.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ビブリオバトル」自体を知らなかったんですがタイトルに惹かれて読んでみた。 「本を通して人を知る」というのはホントに素晴らしい発想だと思う。私も本棚見れば友達になれそうか分かる。 ビブリオバトルは面白そうではあるが参加してそこで面白そうと思った本を読む時間が世の中の人にはあるのだろうか? 暇人の私でも年200冊程度でいくら頑張っても300冊は読めない現状を考えると、個人的にはビブリオバトルに参加するのは難しい。 「面白かったよ」の一言だけで回って来る本を読むのが会話が少なくて一番ホッとするかも。
0投稿日: 2014.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの考案者による、ビブリオバトルについての本です。発端は、著者が所属していた研究室で読書会を始めようとしたこと。従来の読書会では発表者以外読んでこなかったり、レジュメを読み上げるだけで退屈だったり、そもそもどの本を読むべきか判断できなかったりと、問題が多いと感じていたそうです。そこで、みんなが読むべき本をそれぞれプレゼンし、「チャンプ本」を改めて研究しようと考えた――それがビブリオバトルにつながったと知って驚きました。 研究室というコミュニティで始まったため、コミュニティ構成員によるビブリオバトルでは、回を重ねるごとに互いを深く知ることができます。コミュニケーションを深めることは目指していなかったにせよ、人を知るツールとして役立つことになりました。最初の思いつきがそのままの形で実現しなくても、思いつくことが重要なのだと感じます。 ちょっとした短編小説も挟まれ、ビブリオバトルの様子が具体的に描かれているだけでなく、ビブリオバトルがその後の人生にどう影響を与えたかも書かれており、楽しみながら読むことができました。
0投稿日: 2014.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこれ、見るからに楽しそうです。 仕事で使えないか、検討中。 まぁ、あとは上司の頭がどれだけ柔らかくて、いろくなところにアンテナを伸ばせるかどうかですよねぇ。 今日、ちょっと話したらルール崩せ的なことを言ってました。 うーん、それではあんまり意味がない……というか、楽しくないなぁ。 まぁ、最終的には、上司関係なく、環境を無理矢理作って、やりたいことをやるというのが、わたしのスタイルではあるのですが。 まぁ、できることなら、楽しくやりたいですねぇ。 あと、前後の小説部分は、ちょっと蛇足かなあと思った。 この部分があるから、この本を手に取らない層もいるのではないかと思った。
0投稿日: 2014.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルとは、集まった人でオススメの本を紹介し合い、その中から一番読みたくなった本を決めるゲームです。この本は、そのビブリオバトルのルールや歴史から、なぜこのようなルール設計にしたかなどについてビブリオバトルの考案者が解説されているものです。 ビブリオバトルを通して新しい本に出会えるだけでなく、本の紹介を聞くことで相手の考えや背景を知ることができる、「本を通して人を知る」側面を考えてルール設計されている点が驚きだった。まだビブリオバトルは観たことしかないので、「本を通して人を知る」側面に触れるためにも発表者に挑戦してみたいと思いました。
0投稿日: 2014.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館より ビブリオバトルとは自分の本をプレゼンしあうゲームのことです。自分がこの言葉を初めて知ったのは1、2年ほど前、確かダヴィンチで紹介されていたからじゃないか、と思います。 この本では、ビブリオバトルの紹介はもちろんのこと、それがどうして生まれ、世間に認知されていったか、という過程も書かれています。個人的に意外だったのが、理系の教授の方の研究室から始まった企画だという事でした。 読書って一人で楽しむ側面の強い行為だと思っていましたが、ビブリオバトルやもちろんこのブクログも、そうした一人で楽しむ読書の楽しみとは一線を画した「読書によるコミュニケーション」によって成り立つ世界だと思います。 ビブリオバトルがこの本の最後に書かれていたように、一つの普通名詞となるまで認知されていくのかは分かりませんが、一人の本好きとしては、いろいろな形で読書の楽しみを共有できる機会が増えていくのは楽しみだなあ、と思います。
3投稿日: 2014.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログKさんのお勧め。 巷ではビブリオバトルという、 好きな本をプレゼンしあって賛同の数を競いあうのが 流行りつつあるらしいので、 読んでみた。 読書会というものにも参加したいことがないので、 何とも言えないが、 人が勧める本には興味があるので とりあえず聴きに行ってみたい。 バトルの開催レポートに出てきた書籍を 思わずメモってしまいました。
0投稿日: 2014.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ参加者がおすすめの一冊を持ち合い、それぞれ本の魅力を紹介して票を競うゲーム「ビブリオバトル」。 著者はこの考案者で、ビブリオバトルがどのように生まれたか、その魅力などがよくわかった。 紀伊国屋などでやっていることは知っていたので、なんとなく取り上げられるのは小説かと思っていたのだが、もともとは大学の研究室で輪読会の本を選ぶために始めたこととわかって目から鱗。プレゼンの練習になるし、本を通してその人を知ることにもつながる。大学や企業の勉強会としては輪読より面白いのではないだろうか。
2投稿日: 2014.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かこの本を初めて知った時はビブリア古書堂の事件手帖のドラマが放送されているぐらいの時季だったので、流行に便乗した本だと思ってたけど、このビブリオバトルという概念自体は2008年ぐらいからあったらしい。検索したら隣の市の市立図書館で隔月でビブリオバトルのイベントをやっているということが分かった。この本を読むまでそういうイベントがあるなんて知らなかったのだけれども、本当に広まってるんだなぁ。 この本を読む前にゲーミフィケーションについての本を読んだのだけれども、このビブリオバトルというものは書評をゲーム化したゲーミフィケーションの一つといえるのかもしれない。 ところで、野宿ビブリオバトルというイベントの話に思わず噴きそうになった。『諸般の事情で流れてしまった』と書いてあったのでさすがに野宿は無理だったんだなぁ。と思っていたら、『野宿のみをされたという』とつづいたので電車の中で噴きそうになった。 ところで、紀伊國屋が営業で大学に行くって、いったいどういう営業だったんだろう。
0投稿日: 2014.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログとても簡単で、本と人となりを知れる強力なツールだ。実例も載っているが、チャンプ本は読みたくなる。 【公式ルール】 1 発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 (テーマ設定しても可。コミュニティ内なら自然と絞られることも。) 2 順番に一人5分間で本を紹介する。 (5分ちょうどでタイムアップ。早く発表が終わってしまっても何かしゃべること。メモ程度なら良いが、原稿を読むととてもつまらなくなる。) 3 それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う(質疑応答)。 (批評では無く、4の投票の為の追加質問の時間。) 4 全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。 (紹介者は他の発表者の本に投票する。審査員を設定せず全員投票とすること。) ・大学には面白い学問があります。面白い研究もあります。ですが、キャンパス内をふらふら歩いていてもなかなか出会うことができません。そうした中でビブリオバトルは能動的に「面白い学問や面白い人に出会える場」を作っていけると思います。 ・ビブリオバトルはルールが簡単で、他のイベントとの融合も可能なので、〇〇かけるビブリオバトルという掛け算がやりやすい。例えば、船で水辺探索×ビブリオバトル、お寺で朝のお勤め×ビブリオバトル、浴衣でバーベキュー×ビブリオバトル。
2投稿日: 2014.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ビブリオバトル」という言葉を聞いたことがあるだろうか。バトルとつくからには戦いであり、ビブリオとは書籍を表すラテン語由来の接頭語なので、「本の戦い」、つまり「本の紹介ゲーム」である。著者が発案者となり2007年に京都大学の理系の研究室で始められたものだが、現在では大学内で、会社の研修として、中学高校の読書仲間で、公共図書館や書店などのイベントで、本好きの仲間たちが集まってと日本中に広がりつつある。公式ルールは次の通りの極簡単なゲームだ。 1.発表者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 2.順番に1人5分間で本を紹介する。 3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。 4.すべての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員1票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。 ビブリオバトルが単なる「本の紹介」や「書評の発表」と大きく異なるのは、勝敗がつくバトルだという点である。参加するからには自分の紹介する本を「チャンプ本」にしたいと思うだろう。その為には「自分が好きな本」というだけではなく「参加者の皆に読みたいと思ってもらえる本」という視点でメンバーを考慮して本を選ぶ必要がある。そしてその本の魅力を十分に伝えられるように紹介の仕方を工夫する。ただあらすじを述べるだけではとても「チャンプ本」にはできない。聞く方も自分の清き1票を投じるに相応しい本を選ぶのだから真剣になる。また、発表者は本の紹介を通して自分の解釈や考え方を述べる事になるので、その人となりが表れる。ビブリオバトルは「人を通して本を知る」と同時に「本を通して人を知る」コミュニケーションの場なのだ。 ビブリオバトルの成り立ち、理論、社会への広がりなどを紹介した本書から、本と人、人と人を結ぶビブリオバトルが大変魅力的なものであることがわかる。ルールは簡単、費用もかからず3、4人集まればできるビブリオバトル。友達同士で気軽に楽しんでみてはどうだろうか。
3投稿日: 2014.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ≪目次≫ はじめに ビブリオバトルって何? プロローグ そんな日常の「ビブリオバトル」 第1章 ビブリオバトルの遊び方 第2章 ビブリオバトルはどうして生まれたのか? 第3章 本と出会い人を知るためのテクノロジー 第4章 広がるビブリオバトル エピローグ いつか会えたら「ビブリオバトル」の話をしよう ≪内容≫ 4つのシンプルなルールの基に、書評合戦をするゲーム「ビブリオバトル」。その発案者の著書。第2章はやや専門的な部分も見られるが、始める勇気があれば、だれでも始められるこの遊び(ゲーム)。第1章や第4章のゲームのやり方や実例を読みながら、実践してみたいと思った。 また、プロローグやエピローグの「ライトノベル」が実にいい味を出している。わかりやすさをより深めているのではないか?
0投稿日: 2014.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルが生まれた背景と、ルールができるまでの過程が記される。なるほど、今のルールがあるのは、そういう経験を積んできたからなのだと納得できる。
0投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの紹介・解説本.平易な文体で読みやすい.簡単なルールで効果が多様で大きそうで「開催してみたい」と思わせる.ゲーム自体も興味深いが,黎明期の試行錯誤や情報技術との関連性といった分析が更に面白い.あと,趣味丸出しのラノベパートもね.
0投稿日: 2013.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログつい最近知った言葉で興味を持ち概要理解。仰々しい大会形式に意味があるとは思えない。何らかの集まりで、アイスブレイク的な自己紹介ツールとして使うのがよいのではないだろうか? また、学校や職場等々で人を知るツールとしても有効ではあると思う。 要はコミュニケーションツールという手段としてはいいと思うが、バトル自体が目的になってしまっては、これだけ情報が溢れる中では、見知らぬ数名の本紹介では、コスト・スケールメリットでネットには勝てないし、本選びとしても有効だとは思えない。 あとはプレゼンスキル云々というのは社会人では低レベルで使えないし、学生の教育目的になってしまうと権威が入り込んでどうなのかな?という疑問が出てくる。勝敗つけてゲーム化するのも、目的がなんなのか?わからなくなってしまう可能性もあるような。結局ウケを狙う事になり、どうしても権威や人気にベクトルが向かうような気がするのだが。
0投稿日: 2013.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルとはお薦めしたい本1冊を持ち合い、その魅力を紹介し合う書評ゲーム。本書では発案者である著者がルールやゲームの目的、魅力を伝える。 「人からの紹介が、新しい本を手に取る最大のきっかけである」。 本や雑誌のブックナビ、本屋さんのポップに惹かれて、ブクログの新着レビューを見て…確かに棚に並んだぼう大な数の本から1冊を探すより、簡単なあらすじや読んだ人からの感想をもとに本を読もうと思うことがほとんどだ。 本を薦めることは自分を知ってもらうことであり、コミュニケーションにもつながる。“本と人”以上に、“人と人”をつなぐのがこのゲームの目的なように思う。 最近は本屋さんや図書館、学校のイベントとしても採用されて、その規模を大きくしている。
0投稿日: 2013.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの入門書。やり方や 楽しみかた、そして、いまビブリオバトルが起こしている現象をまとてた本。 字が多かった!
0投稿日: 2013.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人に本を薦める、薦められた本を読むというのは、一つのコミュニケーションとして重要であるし、そういうことを通じて、お互いを知り合う機会にもなる。ビブリオは書籍を表すラテン語由来の接頭辞であり、バトルは戦いを意味する、つまり、「本を使った戦い」というのが直訳だ。ビブリオバトルは、簡単に言ってしまえば「本の紹介ゲーム」だ、もう少しカッコ良く言えば、「書評を媒介としたコミュニケーションの場づくり手法」である。発表者は自分で面白いと思った本、みんなに紹介したいと思った本を持ってきて集まる、基本的に本のジャンルは問わない、小説でも専門書でも、漫画でも詩集でも、写真集でも円周率百万桁表でも構わない。ちなみに決めるのは『チャンプ』ではなく『チャンプ本』である、偉いのは本の方だ、「どの本が一番読みたくなったか?」という基準での投票を行い多数決でチャンプ本を決定する。
0投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな読み方で一生かけたって、日本で1年に出版される本の3年分しか読めない。こんな事実を突き付けられた。 ではどうやって読むべき本と出会うか、そのためのひとつがビブリオバトルということだ。 本書は、冒頭の「3年分」の事実を僕に突きつけながらも、ビブリオバトルの説明ばかり(当たり前だ、その本なのだから)。第三章の「本と出会い人を知るためのテクノロジー」が、僕にはとても面白かった。コミュニティはフィルタリング装置であり、ビブリオバトルもその一つ。やっぱりそこへ行くか。 イベントとしては面白いし手軽だけど、単に本と出会うコスト、としては高すぎる気がするのだけどなあ、どうなんでしょうか。副題にもあるように「人を知る」の方に重みがあるのかな。まあ、僕は一人でヒソヒソやりますよ…。う、うらやましくなんかないんだからね!
0投稿日: 2013.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際に参加したことはなく、どんなものか知りたかったので、興味深く読みました。 おもしろそう! 普段、自分が手に取らない本に出合えそうです。
0投稿日: 2013.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題通り、ビブリオバトルを語った本。 途中、図書館や書店に広がっていく様はドキドキした。 いろいろ面白いことを考える人はいるが(新聞にもよく紹介されている)、それが根付くのが難しい。そう感じていたので、全国に広まったビブリオバトルは興味をそそられる。
0投稿日: 2013.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ビブリオ」っていまいち英語っぽくない。 もともとスペイン語? 教員として、この試み、くいつきたく。 で~も~な~、この「ビブリオバトル」って呼び方が、いまいち気持ち悪い。この気持ち悪さってなんだろう。いかにも「仕掛けてます」感がするからなんだろうかなあ。 試みそのものは面白いんだけどさ。
0投稿日: 2013.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年はビブリオバトル中心で仕事をしているのだもの,これは読まないと。ビブリオバトルのバイブルだからね。 ビブリオバトルを始める時に,たにちゅー先生の論文はいくつか読んでいたのですが,やっぱり本一冊になると,まとまっていてよくわかります。 なぜ,私がビブリオバトルいいなと思ったか。なぜ,一緒に講義している先生方が,熱心に普及をすすめるのか。 ビブリオバトルは,大学図書館業界ではやっている「ラーニング・コモンズ」ととても親和性がある。能動的な学び,自分とは異なる価値観との出会い,という機能が共通していると思う。そして,それが今求められているからこその隆盛なんでしょうね。 ただ,ビブリオバトルは色んな属性の人が色んな楽しみ方を見つけられるようになっているゲームであり,私のこの捉え方は大学図書館職員ならではの視点ですので,念のため。 以前,うちの図書館で似たような書評プレゼンイベントをしたけれど,それほど浸透しなかったのは,この「ルール」を遵守する「ゲーム」性がなかったからだなあ,とあらためて思う。こういうことをうまく設計できる,というのが創造性ですねえ。 あ,最後に一つ。ラノベ部分がなんだか,かわいかった。
3投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ20130810 やってみたかったビブリオバトルの解説本のようなもの。 始まりから現在まで。 やり方については、ラノベ風小説があり、わかりやすくはある。最初読み飛ばすとこだった… やってみたかったのは、ゲームっぽい方が楽しそうかな、と思ったのと、比較するために覚えるから、記憶に残りやすいから。やっぱり楽しそう。 以前、一冊の本について感想を言い合う会やったり、持ち寄りで本を紹介し合う会に参加したりもしたけど、後者はそれにプラスしてどれが読みたいか、を最後に選べばビブリオバトルだったかも。笑 向き不向きはあるのかな?本が好きなら誰でもできそうだけれど。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログだれかに読んでもらってビブリオバトルしたい。布教活動したら参加してくれるかなあ。ビブリオバトルについてラノベ風に紹介してるんで読みやすいよ!
0投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルのはじまりは大学の研究室ですが、着実に、公共図書館や中高の学校図書館に広がっていると実感します。人を通じて意外な本との出会いが新鮮な感じを出していると思います。私も挑戦してみたいです(o^^o)
0投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
019 ちょっと前から気になっていたビブリオバトル。 少年マンガ風に 好きな本を紹介して、トーナメントで勝ち上がってゆくものかと思ってました(^_^;) 著者 谷口忠大氏は、大学の研究室で ビブリオバトルがどのようにはじまったか、そして、進化してきたかを解説。 ビブリオバトルのルール ①発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 ②順番に一人5分間で本を紹介する。 ③そけぞけの発表後に参加者全員でディスカッションを2.3分行う。 ④全ての発表後「どの本が一番読みたくなったか?」を基準に投票を行い、チャンプ本を決める 敷居を低く、ルールで縛りすぎない、 でも自分が好きで、集まるメンバーに教えてあげたい良書をもってゆく。 本を通して 本の事も、その人の事も知る事ができるビブリオバトル。 本書にもあるように、 ゆくゆくは、ドッチボールやフットサルのように 気軽にそこここではじめられるゲームになったらいいですね。 本がより身近なものになるのに。 ビブリオバトルをする大学生たち生活を ラノベっぽく描いていたり、読みやすい本でした。
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近話題に登る「ビブリオバトル」 いつどこで誕生したか知っていますか? この本は、ビブリオバトルが誕生した経緯などが掛れた本です。 知れば知るほど、興味が沸くビブリオバトル! その本質に触れてみませんか?
0投稿日: 2013.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ持ち寄った本で「この本面白いですよ」と参加者にアピールし、たくさんの人に読ませたくさせたら勝ちというバトルで1冊本を書いてしまっている。 すげえ。ネーミングも好き。 読みたい本を探す手段として、ブクログの★や本屋大賞とかあるけど、友達がこれ面白いという紹介もある。 視野をぐわって広げるにはやっぱり紹介かなあって思う。 Amazonの「この本買った人はこれも買っています」とか趣向が偏っちゃうもんな。 それにポチポチネットサーフィンして、本書に出てくる「「場所」論」という本に出会ったとしても題名からして手に取らない。本書からその本の内容を聞いて興味が湧いたんだけど、やっぱ本はタイトルが6割。 「場所」論とオロロ畑でつかまえては読んでみようと思う。
2投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近にわかに知名度を上げている書評ゲーム「ビブリオバトル」の説明本。筆者はビブリオバトルを作った人物である谷口忠大さん。 ビブリオバトルのルール ①発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 ②順番に一人5分間で本を紹介する。 ③そけぞけの発表後に参加者全員でディスカッションを2.3分行う。 ④全ての発表後「どの本が一番読みたくなったか?」を基準に投票を行い、チャンプ本を決める 本書はビブリオバトルがどのように作られたのかという歴史を解説し、そして現在のビブリオバトルの広がりがどのような状況かを考察しています。 こういう取り組みって面白そう!
0投稿日: 2013.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルはイベント会場で見たことがある程度だけど, 実際に興味が出て買った本はなかった。 もともと研究室で人となりが分かった状態で行っていたものだと知り, それならばその人のツボに合ったプレゼンを用意できるし, 発表者への理解を深めることができるというのだろうなと感じた。 本が大量に出版されるこの時勢に,人からおすすめされた本というのは読む原動力としては強い。 自分も興味があるけど,周りでビブリオバトル知ってる人はいなさそうだし自分から積極的にやりたいとも言い難い。 なかなかジレンマ。
0投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今朝の朝日小学生新聞に「ビブリオバトル」が1面で紹介されていました。というぐらいに急速に普及している書評ゲーム。ルールは単純。ネタバレになるので公式ホームページで確認を。本を通じたコミュニケーションであり、プレゼン能力を高めるのにも有効と思います。誰かやりませんかね。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013 6/19読了。Amazonで購入。 出たと知ってすぐに買い、なかなか読み始める時間のなかったたにちゅー先生の、ビブリオバトル紹介書。 中身はビブリオバトルの発想に至る話+ビブリオバトルの紹介+その後の諸々とかを書いていて、ビブリオバトルに至る前のあたりは「本の紹介」とかを考える上でかなり参考になりそう。 あと、最初と最後にまさかのたにちゅー先生自らによるラノベが入っていて吹いたw でも、最初のライトノベルが一番、「ビブリオバトルおもしろそう!」ってイメージを伝えている気がする。これは良い物だ。
2投稿日: 2013.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京都知事の猪瀬さんも『解決する力』の中で推奨されていたりと、 ここ最近、意外と耳にすることが増えてきている、「ビブリオバトル」。 ルールは至極単純で、、 ・参加者が読んで面白いと思った本を持ち寄る ・順番に1人5分で本を紹介する ・それぞれの発表後に、参加者全員で2-3分のディスカッションを行う ・全ての発表終了後に、「どの本が一番読みたくなったか?」を基準に、 参加者全員1票で行い、最多票の本を「チャンプ本」とする と、人と本が集まれば、どこでも誰でもできる内容です。 ドッジボールやフットサルのようにすそ野を広げたいとは、なるほどと。 本の魅力を伝えるにも、相手の琴線に触れないと意味が無いので、 プレゼンやコミュニケーション能力等の「伝える力」を磨くのにも、いいなぁ、、と。 また、定期的に開催することで、読書に対するモチベーションの維持にもなりますしね。 実際に企業でも取り入れているところもあり、効果も出てきているとのこと。 個人的には、ちょっと前に「西荻夕市」でやっていたのを横目で見た位なのですが、 機会を見つけて是非一度、参加してみたいところ、、選書に悩みますけども。。 ブクブク交換なんかとも相性がよいのでしょうか ビブリオに特化した朝活なんてのも面白そうかなぁ、、とも。 そんなに大規模なものでなく、4-5名で一時間程とかでも小気味よく行けそうです。
11投稿日: 2013.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの考案者がビブリオバトルができたきっかけなどを記している。 ビブリオバトル自体は面白いんだけれど、この本は微妙である。 ビブリオバトルのルールは以下のとおりである。 ①参加者が面白いと思った本を持ってくる。 ②1人5分間で本を紹介する。 ③発表に関するディスカッションを2~3分行う。 ④全員の発表が終わったら「どの本が一番読みたくなったか」を投票する。 ビブリオバトルの機能は次の4つ。 ①参加者で本の内容を共用できる ②スピーチの訓練になる ③いい本が見つかる ④お互いの理解が深まる →発表者の人となりや個性、知識、背景に関する相互理解が深まる。 (まっちー)
0投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて。 今年のGWにたまたま訪れた広尾の都立図書館で、ビブリオバトルの企画展をやっていたので、初めてこの単語を知りました。 過去のバトルの映像も流していたのでその会場や発表の様子を知ることができたけれど、ぜひ生で見てみたい、できれば参加してみたいと思いこの本を借りてみました。 この本では、ビブリオバトルのルールなどの説明はもちろん、ビブリアバトルができるまでのなりたちや、このバトルの効果などがさすが新書という感じで説明されています。理系の研究室から始まったとのこと。びっくり。 もともと大学から始まっただけあっていろいろな大学や学校、企業などでも取り入れられているようだけれど、一般の人が気楽に参加できるようにならないかなあ。ブクログに登録をしている人たちは、きっと大好きだと思うんだけど…みなさん、一緒にやりませんか??
0投稿日: 2013.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近各地で広がりを見せている「ビブリオバトル」の誕生の背景、その意義、展望を語ったもの。ビブリオバトルは極めてシンプルなルールであるが、著者の大学の研究室の体験に基づいた制度設計の緻密さに改めて驚かされる。 本書の後半部では草の根から徐々に幅広い展開を見せるビブリオバトルの可能性が述べられているが、「ビブリオバトルを一般名詞に」という著者の目標への挑戦はこれからも続くであろう。 この手のバトルものは得てして広がれば広がるほど勝利至上主義やプロモーション目的のためにいつの間にかコンセプトが歪んでしまう危険性をはらんでいるが、こんな時こそ本書に立ち返り「人を通して本を知り、本を通して人を知る」というコミュニケーションこそ本質であることを再確認すると良いのではなかろうか。 一介の乱読者としてビブリオバトルの可能性と将来の展開に大いに期待したい。
0投稿日: 2013.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 2.順番に一人5分間で本を紹介する。 3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。 4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員で行い,最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。 たった4つのルールで行われる「書評ゲーム」 ビブリオバトルを知ったのは、昨秋、大阪市東成区にある八坂神社で行われるというビラを見たのが最初でした。 本を媒介にゲームをするというのが全くイメージできず、時間を合わせて見に行こうと思っていたのに結局行けずじまいで、それからモヤモヤとした思いが残っていたのです。 と、いう状態で巡り会ったこの一冊。 ……即買いでした。 京都大学大学院情報学研究科で「新しい勉強会」のつもりではじまったこの仕組み。 単なる本の書評サイトやAmazonなどのレコメンドでは出来ない「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」ということを誘発できる興味深い試みだと改めて知ることができました。 本好き、書店好きだと言っても、自分自身が選ぶ本っていうのはやっぱり限られてくる訳です。 好きな作家さんだったり、興味を持っている物だったり人物だったり出来事だったり、表紙を見て「ジャケ買い」だったり。 本が好きだからこそ、本を媒介「本と人を知る」ことができる面白そうな仕組み……あぁ、ちょっと参加したくなっちゃったなぁ。
0投稿日: 2013.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は読書は好きだが、書評は嫌い。 先行研究のために本を読んで、それをたたき台として更なる高みに行くのは良いが、書評は、評しているだけでしょ。生産性ゼロだよ。 この本自体は面白くもなんともない、筆者の思いで話と自慢話だけだから、読む価値なし、と書評はこうなる。
0投稿日: 2013.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白かった本を 持ち寄る。ひとり5分間順番にしゃべる。2,3分全員でディスカッション。多数決で読みたくなった本を選ぶ。 この4つのルールーで、ビブリオバトルが成立し完結する。 今まで、確かに図書館や詩人のプロフィールなどでビブリオバトルという語を見た覚えがある。 でも面白そうと思ったような出会いではなかった。 だから、この本を読もうと思って手に取ったことが本当によかったと思う。 さっそく奈良県立図書情報館のビブリオバトルに申し込んだ。 イベント型でテーマが「結婚」とあった。もう何でもいい。ただただ実物を見たい聞きたい。 もし曲がりなりにも「結婚」の話しでときめくことが一瞬でもあるなら儲けもんだ。期待はずれは悲しいので、何も期待しないで出かけますわ
2投稿日: 2013.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ近所の書店さんたちで見当たらず、やっと買えた。まさかのライトノベルつき(笑)帯の女子大生がかわいいのですが画像ないですね… 耳をすませば的な出会いをするのが今の図書館では難しくなったのですが、これはよい取組み。市民の方から図書館への要望で「出会いたい(恋愛的な意味で)」なんてのがあったので、ぜひ出会う場を提供したい。
0投稿日: 2013.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書を中心としたコミュニティから、ツールとして図書館や町興しに役立てたりと、ひとつの会の広がりの軌跡がとても面白いと感じました。人から本を、本から人を知るという感覚に共感できたのが、面白いと感じた大きな要因かもしれません。
0投稿日: 2013.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの本質がよくわかった。『人を通して本を知る、本を通して人を知る』なんとワクワクさせられる言葉だろうか。ルールは4つだけ、と誰でもできる遊びで、すぐにでも始められそう!
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読んだ本の面白さを伝える力を身につけたい」と思って読んだので、ちょっと私の求めていた内容とは違うなぁと思いました。 でも「ビブリオバトル」という言葉さえ知らなかったけど、面白そう♪問題は自分のコミュニティにどう取り入れるか…
0投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう本の探し方もあるのね。 レビュー読むより、聞く方が楽だし、 書店でやってるの見たら、確かに買っちゃうかもしんない。
0投稿日: 2013.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人5分の制限時間の中で、自分が選んだ本の書評を戦わせ、チャンプ本を決めるという、書評ゲームである「ビブリオバトル」が紹介されています。 本との出会い方を分析している入り方は面白かったのですが、それをバトルという形式に持って行く過程で、本との出会いからコミュニケーション力へと重点がシフトしている様に感じました。 ビブリオバトルが「人を通して本を知る」のみならず「本を通して人を知る」場であるということには非常に魅力を感じますが、やはりバトルと言う形式により本の内容が軽んじられるのではと危惧してしまいます。 仲間内で本を紹介し合う程度の方が私には合っているかな。 しかし、機会があれば紀伊国屋書店等で開催されている、ビブリオバトルを見学してみたい気もします。
1投稿日: 2013.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当にビブリオバトルだけで一冊書いてしまうなんて、たにちゅー先生すごい…。しかもラノベ付き。 ここに書かれていることを目撃していたので、感慨深し。 ビブリオバトルはシンプルな設計とキャッチーなネーミング、メディア露出のタイミングや人脈がうまくいった好例ですよね。 普通名詞になるまであと一歩。「朝読」みたいなかんじで学校現場には受け入れられやすいと思うけど、街でオフィスで盛り場で、どれだけ市民権を得られるか。 「草野球」にたとえてらっしゃったのがしっくりきました。
0投稿日: 2013.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビブリオバトルという、本の紹介ゲームについて説明している本。 5分間で、自分の好きな本をプレゼンし、その本を読ませたいと思わせるというゲームらしい。 ビブリオバトル自体はとても面白そうだなと思った。 ただ、自分は本書に、その実例の紹介や、そこでのプレゼンの面白かったところとかの内容を期待していたが、そこらへんはほとんど触れられてなくて残念だった。 この本自体は、ビブリオバトルの始まりやその意義、やり方、などについてがほとんど述べられているだけだ。途中で実例も少し紹介されているが、できればその現場の写真みたいなものがほしかった。 だが、その実例とかを書いた本がまた今度発売されるそうなので、そちらを読むだけでもよさそうかな^^;
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログというか著者ですがww 自分でも新書になった本書を改めて 二度ほど読んでみた 新書って読みやすいんだね 校閲原稿でやってた時から比べて圧倒的に読みやすくさらさらいきます ビブリオバトルもいろんな場所で遊ばれるようなことが増えてきて いろいろ質問を受けるけど、いわゆるFAQのほぼすべてが本書を読めばするっと融けるように書き上げたつもり ビブリオバトルってなに? って人から帯のキャラクターが出てくるライトノベルを読むだけでも手にとって欲しい
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルの歴史と将来を展望する.その意図が,人を通じて本を知る.本を通じて人を知る,である点に得心し,深遠さを理解する.
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時間制限有り、本番内に使用できる資料はなし。 自分の紹介した本の投票率が最も高ければ 「その本」が優勝― この本ではゲーム感覚で楽しめる会である 「ビブリオバトル」の紹介がされています。 シンプルだけど厳格かつ合理的な ルールも規定されていて、 公式の大会まである模様。 プレゼン能力も自然と高まりそうで なかなか興味深いです。
0投稿日: 2013.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を買う前にオフィシャルサイトを結構読んでしまったので、この本自体に読み物としての魅力はさほど感じなかった。けど、「ビブリオバトル」は面白そう。早速、サイトで最寄りのイベントを探し、とりあえず観覧を希望した。(まだ返信なし) 5分間で自分の好きな本を紹介し、質疑応答の後に「決を採って」、チャンプ本を決めるというルールのシンプルさがいい。 とりあえず見てみたい。
0投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本との出会い、大量の情報をフィルタリングする方法の分類というくだりで、原始的には「権威・人気」しかなかったものが、web, SNSで多角的に広がっているという表現があった(その後「場所性、創造性」という著者の本論に入る)。 そこで連想したのが、web, SNSでも結局情報の多さ故に、皆が同じ事しか考えなくなってるんじゃないかという実感。 知人のリツイートに共感した直後に、全く別の関係性の知人が同じものをリツイートしてて興醒めした経験、好きな著名人の意見に無条件に同意しそうになる感じ。 大量の情報から自分にとって有益なものをいかにして抽出するかという奮闘は、回り回って原始的な情報操作に陥ってる気がする。 【以下抜粋】 p.153〜 本の読みとは本来読み手に委ねられた創造的な活動なのである。読者は意味のクリエイター、ビブリオバトルにおける語りは二次創作、創作活動。 p.190 ビブリオバトルを語学教育の場に持ち込むことで、授業の中のテストで重要視される文法的に「正しい」「間違っている」という尺度ではなく、より伝わるように話せるかどうかという尺度を、言語教育の中へと持ち込めるかもしれない。
0投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今日買ってきました。 何しろプレゼン下手が悩み。 読書は大好き。 これらが組み合わさったら、楽しくプレゼン力伸ばせるんじゃないかと思って。 参加してみたいな~。 面白そう。 =========== ビブリオバトルには興味があるけれど、正直その発祥とか歴史とかどうでも良いです。 書いていらっしゃる方、いかにも働いたことのない院生上がりの方で、 何となく世間とズレがあります。 たとえて言うならば、日経新聞に出ている経済学部の大学教授の論文を読んでいる気分です。 「本の面白さを上手に伝えるスキルを見に付けられるかも!」と思って買ったので求めてたものと違った、といえばそれまでかもしれませんが。。。 けなすばかりでは申し訳ないので、 ビブリオバトルを、ストーリー仕立てにしてたのは読みやすくて面白かったですね。
0投稿日: 2013.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでもらいたい書籍を5分間で紹介して競うゲーム、ビブリオバトルについての本。 最初と最後にビブリオバトルを題材にしたライトノベルがあり、その間にビブリオバトルの解説が書かれているという珍しい構成。 ライトノベルの他に、実際のビブリオバトルの様子も何パターンか紹介されているので、その場に自分が参加している感じでわかりやすい。 特に興味があったのは第3章で、「テクノロジー」としてのビブリオバトルが解説されている。「ワード検索」「カテゴリ検索」「購入履歴をベースにした推薦機能」と並ぶ情報システムとしてのビブリオバトルの側面はとても興味深く、特に人を介することによって生まれる「書籍のメディアとしての二重性」の提示は、「人が本を読む」という行為がこれまで過小評価されてきたのではないか、と思わされた。
2投稿日: 2013.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルは本離れがすすんでいると言われる昨今、本の良さを広める新しい形の宣伝方法になる。これが学校などでも普通に行われるようになれば、多くの人が本を好きになり読む習慣が自然に広がる可能性が高い。それだけではなく、自分の好きな本を5分間のスピーチで表現することでプレゼンテーション能力が飛躍的に向上する、ゲーム感覚で楽しい、まさにいいこと尽くしのイベントのように思える。 この本はビブリオバトルが生まれた経緯などを紹介した本。
0投稿日: 2013.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログビブリオバトルは2007年に京都の大学のとある研究室で生まれて、その後日本中に広まっていった。P104
0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログすぐにやってみたくなる書評対決ビブリオバトル。小説仕立ての挿し絵は「?」って思うけど楽しく読めます!
0投稿日: 2013.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ職場にかなりの読書好きかつ若手教育に熱心な上司がいる。よくこんなの読みたまえとあれこれ薦めてくるが周りに実際それらを手に取る人は少ない。おそらく一方通行過ぎるんだと思う。 この本で紹介するところのビブリオバトルは人のコミュニケーションを全面に押し出している。本の良し悪しもだが勝利には心象が重要となるため自然に聴衆の関心を得るための話術が要求されるし、そのことにより発表者の人物にも本にも興味がいや増す。シンプルだが無駄がない。 新たな本との出会いもいいが、何よりも内向的趣味の代表格のような読書にコミュニケーションツールとしての大きな可能性を感じさせる。
0投稿日: 2013.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログお勧めの本と人とタイマーだけあればどこでもできちゃう書評ゲーム、ビブリオバトル。 生まれてから普及までの経緯と著者の信条がコンパクトにまとめられています。 読書推進というより、コミュニケーションが出発点になって発展したから、ここまで受け入れられているのではないかなと感じました。 本は本屋だけのものではないし、人によって感じかたが様々なのが面白いところ。 人柄が見えたり、コミュニケーションのきっかけになるツールとしての本という考え方が、もっと広まったら素敵だろうなぁ。 実際のプレゼンの再現もたくさん収録。 いい意味で、「あれ、これ私たちもできるんじゃね?」と、ノリ気になってきます。 うーん、やってみたいぞ、ビブリオバトル!!
0投稿日: 2013.04.23
