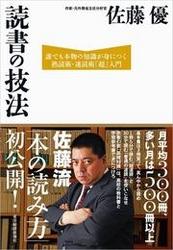
総合評価
(410件)| 90 | ||
| 157 | ||
| 103 | ||
| 17 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術の本で何回も読み直しているのが、齋藤孝さんの「読書力」とこちらの2冊。 多読、熟読、速読の方法について述べられている。レベルが高くて私には無理かなと思う方法もあるけれど、熟読を実践して読んだ本については、読了から何年経っても主要部分を覚えている。 以下個人的な覚え書き 熟読→1回目は線を引きながら読む。2回目は線を引いた部分を中心に文章を囲みながら読む。ただし囲みは全体の10分の1まで。3回目は結論部分を3回読む。 速読→超速読は1冊5分程度。基本、線は引かずに読む。普通の速読は1冊30分から1時間。こちらは線を引いたり付箋を貼ったりしながら読む。
6投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ凡人の私にはとてもじゃないが佐藤さんの読書法は真似できないかな。 読書が苦行のように感じられるところもあるので、気軽な感じで読むと痛い目を見るかもしれない。 ただ、読書ノートを作ることについては、気になった部分を本から抜き出して自分なりの感想やコメントをまとめているので、自分のスタイルはあながち間違いではなかったと少しホッとしています。
1投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読とは、熟読すべき本を選別するためのものであるという内容は納得です。 ・目的意識を持って読むこと ・自身の知識の欠損部分を知った上で、基礎知識を身につけること ・他者に説明できるレベルの知識を身につけること ・読書ノートを作成し、知識の定着と整頓を図ること まずはこのあたりを念頭におきつつ、実践したいと感じました。
11投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
3回読みや自腹で買った本には書き込みを入れて 抜書きノートを作る等面白い技法が書いてあった 合うかどうかは個人差があるだろうが新書で試したところ知識が身につきやすくなったように思う。
0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「月平均300冊」のタネは熟読と速読の使い分けにある,基礎知識の重要性についても多数の事例から示す。著者の生活スタイルや思想までは真似できないのでその辺は軽く読み流しておく。
0投稿日: 2025.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の帯に書いてある数字には誰もが驚くだろう。 「月平均300冊。多い月は500冊以上」 だが、この数字にはカラクリがあった。それは下記の記述を見ればわかる。 目を通している300冊のうち、熟読している本は月に4~5冊。1冊5分程度で処理する「超速読」が240~250冊。30分から2~3時間かけて読む「普通の速読」が50~60冊。(p26を要約) 超速読の目的は2つ。 1. 「自分にとって有益な本かどうか」、「時間をかけて読むに値する本か」の仕分け作業 2. 「一部分だけを読めばいい」、「この箇所を重点的に読めばいい」と当たりをつける (p78を要約) つまり、約8割の本はさっと見ているだけ。時間をかけて読むに値しないと判断された本だ。時間は無限にあるわけではないので、読む本を選別するのは大いに賛成だ。しかし、普通は、選別で落とした本を「読んだ」とは数えない。 梅棹忠夫氏は『知的生産の技術』の中で、次のように書いている。 本は、「はじめからおわりまで読む」ものである。はじめからおわりまで読んだ本についてだけ「よんだ」という。ななめよみで一部分だけ読んだ場合には「みた」ということにしている。 この定義に従えば、佐藤氏が「読んだ」本は、月に4~5冊だけだ。多少あまく見ても、「読んだ」という言葉の範疇に入るのは、約50~60冊だろう。 以上のことを知ったうえで、本書を読むか読まないかを判断した方がいい。 副題に『速読術「超」入門』とあるが、本書に書いてあることを完璧にマスターしても、月に平均300冊「読める」ようなるわけではない。多くの本が読めるようになりたいという目的では、読まない方がいい。 本書は3部に分かれているが、重要なのは第1部である。それは、カバーの折り返し部分に書いてある要約で把握することができる。下記に引用しておく。この記述に興味を持たれた方、もっと詳しく知りたいと思った方は読むことをお勧めする。 ■佐藤流「熟読」の技法 1. まず本の真ん中くらいのページを読んでみる【第一読】 2. シャーペン(鉛筆)、消しゴム、ノートを用意する【第一読】 3. シャーペンで印をつけながら読む【第一読】 4. 本に囲みを作る【第二読】 5. 囲みの部分をノートに写す【第二読】 6. 結論部分を3回読み、もう一度通読する【第三読】 ▶熟読の要諦は、同じ本を3回読むこと 基本書は最低3回読む 第1回目 線を引きながらの通読 第2回目 ノートに重要箇所の抜き書き 第3回目 再度通読 熟読できる本の数は限られている熟読する本を絞り込むために、速読が必要になる ■佐藤流「超速読」の技法(1冊5分程度) 1. 5分の制約を設け、最初と最後、目次以外はひたすらページをめくる ▶超速読の目的は2つ 本の仕分け作業と本全体の中で当たりをつける ■佐藤流「普通の速読」の技法(1冊30分程度) 1. 「完璧主義」を捨て、目的意識を明確にする 2. 雑誌の場合は、筆者が誰かで判断する 3. 定規を当てながら1ページ15秒で読む 4. 重要箇所はシャーペンで印をつけ、ポストイットを貼る 5. 本の重要部分を1ページ15秒、残りを超速読する 6. 大雑把に理解・記憶し、「インデックス」をつけて整理する ▶普通の速読は、新聞の読み方の応用
1投稿日: 2025.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とにかく基礎知識。 これは熟読でしか身に付かない。 熟読は手順を踏んで3回読む。 基礎知識を身につければ、読むべき本・内容に素早くたどり着ける。 また、本筋とは違うが重要な人との関係を構築したい場合、1ヶ月以内にに3回会い、その後は3週間に1度は会うと考え方が参考になった。
0投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の経験から読書に対しての技法、読み方が書かれている本。読書ノートをまとめたり、本に線を引くなどの読み方が合いそうだなと感じる人にはお勧めできる。個人的には、読み方より終わり方を意識するという考え方が参考になった。
5投稿日: 2025.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏流の読書方法とアドバイスや事例。 ノートをとる意義 速読する意義 基礎をかためる意義 これらが特に学びとなった
4投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本をどう読むか、というのはためになりますが、それ以上に、著者の一日のスケジュールが紹介されていて、それがとても興味深かったです。
0投稿日: 2024.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書によって得られた知識を血肉化して教養にまで高める方法には、王道はないということがわかる。 彼ほどのエリートでも、努力を惜しまず勉強するしかないのだ。
0投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログほんの読み方について改めさせられる良い本だと思う。超速読など一見早く読む為の本に思われそうだが、本質的に読者自身の学力や読む力をまず鍛える必要性があると著者は繰り返し伝えている。つまりどれだけ早く読めても内容を理解できる頭脳がなければただペラペラ本をめくるだけで意味がないのだそう。コレには世の中の速読本を完全に一掃した発言で私はすごく納得した。私自身勉強も必要だと学ばされたし、読む力不足だと痛感したが、この本の内容自体は30%くらいしか理解出来なかったように思う。熟読も必要だが、この本を理解する為にこの本に紹介されている本を先ずはよんでいこうと思う。
0投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術についての本を数冊読んだうちの1冊。 ちょっとハイキングのコツが知りたいな、と思って読んでみたら、 いかにしてエベレストに登るかの本だった、 というような意味で合わなかった。 けれども、読書のヒントは得た。
0投稿日: 2023.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書評 読書レベル 初級 ボリューム 270頁 読みやすさ ★★★★ 知識・教養 ★★★★★ 理解度 ★★★★ 実現度 ★★★★★★! 影響度 ★★★★ 一言感想:月300冊から500冊のビジネス本を読む人の技法を学びたい方、仕事で大量の資料を読まないといけない方、学生の方で国語数学社会が将来の何に役立つんだ!と疑問に感じてる方にオススメです。 ビジネス書の読み方、向き合い方が変わりました!そして、知識が頭や体に残せます!ビジネス本を読まれる方はとにかく早めに知っておくべき内容だと感じました。
21投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は読書について極めていると思う。 なので言っていることは正しいのだろうけれど、ついていけなかった。 人生は有限だから無駄な本を読んでいる暇はないというような主張があり、その通りだけど私の場合はその前にネットサーフィンしている時間を減らすべきだと思った。
2投稿日: 2023.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書への興味が湧き上がった。 速読の習得目的で手に取りましたが、 「読書」の根っこを教えてもらった思いです。 速読する効果と、実行のために必要なことを 知ることもできましたが、 それ以上に、読書で得られること、 本の内容をより理解するために何をしたら良いかが 分かりやすく具体的に書かれています。 読後、たくさんの本を読んでみたい衝動に駆られています。 また、高校の教科書が読みたくなりました。 本に興味がある幅広い層に薦めたくなる良い本でした。
0投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の基本を教えてくれる一冊。基礎知識がいかに重要か教えてくれる。基礎知識の重要性はある程度分野について詳しくないと気づけなくて軽視してしまいがちだが、知識の巨人の佐藤さんが語ると説得力が増す。読んで満足せずに、佐藤さんの読書方法を実践していきたい
1投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法というタイトルだった為、読書慣れしていない人向けかと思ったが、古参者向けだった。哲学、特にロシアの政治経済等の基礎知識がないと、例えが理解できない。 政治への主義主張が強い。 また、ロシアでの滞在体験については、ロシアとウクライナの戦争前なので興味深い。
0投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
筆者の本の読み方を具体的に書いてくれている本。 基礎知識がないと速読はできず、基礎知識は熟読でしか得られないという、至極当たり前のことに改めて気がつかされた。またいきなり難しいことを身につけようと欲張らず、自分の学力を客観的に捉える必要があるという指摘には、耳が痛い。基礎知識は我慢して時間をかけてつけないといけない。 (やり方は本書を読んでいただくとして、)超速読(1冊5分)で熟読するか、速読(1冊あたり1時間)するか、超速読だけに済ませるかを仕分けする方法を紹介している。 が、超速読で切り捨てる本をどれだけ持てるかは、それまでの知識量によるのだろうなと思う。速読と熟読の本を仕分けることや、読書ノートをつける(記録をする)ことは真似したい。
1投稿日: 2023.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の読書を含む「時間」に対する考え方に圧倒される 全ての時間を自分の考え方に当てはめて無駄に過ごさないことを徹底しているように感じた 最後の部分にそれらに関する著述があり、熟読や速読の方法が書かれた最初の部分より印象に残った
1投稿日: 2022.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤氏は、言います。 「なぜ、読書術が知の技法のいちばん初めに位置づけられなくてはならないのだろうか。 それは、人間が死を運命づけられている存在だからだ」。 私は、この一文がどうも気になり、購入しました。 佐藤は、続けて言います。 「そのために、時間が人間にとって最大の制約条件になる。」 「正しい読書法を身につければ、人生を2倍、3倍豊かにすることができる。 読書によって数十人分の経験を身につけることができる。」 この読書の技法の目的が明確に書かれた一文です。読書で、人生を豊かにすることができる。 しかし、人生はいつか必ず終わる。 佐藤氏は、さらっと書いていますが、なんとも考えさせられる一文です。 読書を通じて、仕事でアウトプット力を身につけるとか、 論理的思考を身に付けるとか以前の原理原則から始まっている所が、 この本を価値あるもの、佐藤氏の哲学が反映させている書籍だと思います。 佐藤氏は、この書籍で、正しい読書術を身に付けるためには、 高校教科書レベルの基礎知識をつけておくことを強調しています。 奇をてらった方法ではなく、王道だなと感じました。 手に取ってみることを、強くすすめます。
0投稿日: 2022.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家で元外務省主任分析官だった佐藤優氏による読書指南本。 「月平均300本」といったワードに度肝を抜かれるが、本文を読むと 「月平均300本以上に『目を通す』」 「『熟読』している本は月に平均4〜5冊」 ということが書かれている。 つまり「いかに数多の書籍の中から読まない本を判別し、目を通すだけの本には最低限の関心を払い、熟読する本に時間をかけるか」が大事だということが書かれている。 超速読や速読についても、書籍や本の中の情報を判別するための技術として見ると、自分にも可能なように感じる。(実際に私はこの本を紹介されていた超速読と速読のやり方を行ってこの本を読んだところ、こうして感想を書くぐらいには読むことができた) 数々の教養書として紹介されていたものは正直、ピンとこなかった。 ただ、一般書や漫画も紹介されており、佐藤氏からの視点で読むと『クレヨンしんちゃん』はこう読める、といった視点を得ることができる。 読み終えると、付箋とペンを横に置いて読書してみたくなる一冊。
2投稿日: 2022.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の冒頭にも書いてあるが、読書の技法ではない勉強の方法と理解すべき本。速度イコール読まない本を選別することと概ね理解。出口先生の現代文講義が取り上げられているのは興味深い。その他は雑多な経験談とも読める。
2投稿日: 2022.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際にやっていたら、ノートへの書き写しは、時間がかかる・・。。 そのために、速読をマスターする必要あり。 全体的に、インプット方法として参考になる。
0投稿日: 2022.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ立花隆が自身の読書について語った本を読んだことがあり、その勉強量に驚いたことがあるが、この佐藤優の本にも驚いた。月平均300冊、多い月には500冊以上を読む。その佐藤優が、自身の勉強法について語ったのが本書である。 すごくロジカルで、かつ、基本に忠実だな、というのが第一印象。 ある分野の本を理解しようとすれば、その分野についての基礎的な知識・素養を身に付けている必要がある。逆に、ある分野についての深い専門知識を身に付けていれば、その分野の本を読む時間は短縮できるし、更には自分にとって新しい知見でなければ、その部分は飛ばし読み、あるいは、読む必要はない。 そういった基礎知識の分野として、佐藤優が本書中で薦めているのが、高校レベルの勉強をもう一度、きちんとすることである。世界史・日本史・数学・国語など。このような広い分野の基本的な知識や考え方を身に付けていれば、本を読むスピードは速くなるだろうと思った。 もう一つ驚いたのは、佐藤優の仕事量・勉強量だ。一日のほとんどの時間を執筆または勉強にあてている。こんなことは不可能であるが、参考になる部分の多かった本だ。
11投稿日: 2022.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者でも、熟読できる本には制限があると書いてあってなぞに安心。そりゃそうですよね。 NEW出口の現代文講義の実況中継が気になりすぎる!
1投稿日: 2022.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優の読書法がひたすら書いてある本。第一章の文章がまとまっていた。「基礎知識は熟読によってしか身につけることはできない。しかし、熟読できる本の数は限られている。そのため、熟読する本を絞り込む、時間を確保するための本の精査として、速読が必要になるのである。」 以下参考になった点 基本書は奇数。初読はシャーペンで線引き・囲み、結論を自分なりにまとめる(今やってる作業) 速読は気になる点だけ印。 高校の基礎知識は超大事!! 漫画は「代理経験」「人間関係の縮図」 読書録を付け始めて一冊への向き合い方が真剣になったし、エッセンスも頭の中に残りやすくなった。自分は速読は好きではないが、知識獲得としての手段ならしょうがない(これからそういう場面がでてくる)ので頑張りたい。 とりあえず受験勉強は知への近道 2021/12
1投稿日: 2022.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★一度読んだ本は二度と読まないつもりで、何かを得られるように読む。 1.読書目的・課題意識 ・読書の効果向上。読んだ本の内容を覚えておらず実践に生かせていない現状を打破する示唆を得る。 2.takeaways ・読書目的に照らして「熟読」「速読」「超速読」を区別する。ただし、速読・超速読は基礎知識がある分野のみに適用可能。 ・ゆるい形で本を読む習慣が身についてしまうと・・・頭の中に定着していかない。「あっ、自分も知っている」という感覚は味わえても、「では、どう知っているのか」には答えられない(知識が定着していない証拠)。 ・だらだら長時間勉強をしても学力はつかない。 3.todo ・読書時に「熟読」「速読」「超速読」を区別し、実践する。すべて時間制限も明確にする。 ・ブクログに記録をつける(ノートの代替、ただし熟読時はノートも併用する)。 4.要旨および重要と感じたフレーズ ・上級の応用知識をつけようと欲張らない:難関大学の卒業生で、学生時代の成績がそこそこよかった人にこういう例が多い。読書法を根本的に改めない限り、こういう人が知識を集積していくことはできない。(p56) ・基礎学力をつける段階で客観的な自己評価ができないと、間違った読書法をしてしまう。大切なのは、自分の知識の欠損部分を知り、それを補うことだ。(57p) ・重要なことは、知識の断片ではなく、自分の中にある知識を用いて、現実の出来事を説明できるようになること。そうでなくては、本物の知識が身についたとは言えない。(p58) ・熟読方法(10時間~):基礎知識習得のためには3冊選定(多数決)。まず本の真ん中(内容薄弱になりやすい)を読んで充実しているものから読む。(p59抄訳)3回読む、1回目は興味深い点・疑問点の目付(鉛筆・ポストイット等)、2回目はそれらのうち重要なものをノートに転写、3回目は目次構成を読んだうえで結論部分を3回読み、最後に再度通読。 ・第1回目の通読を漫然と行ってはならない。実はいい加減な仮読みのような手法で一度本を読んでしまうと、その後、重要事項がきちんと頭に入らなくなってしまう。 ・超速読(~5分):速読の目的は、読まなくてもよい本をはじき出すことー一生で読める本の数は限られている。(p51) 基礎知識がある分野が前提(そうでなければ単なる指の体操にしかならない)。ページ全体や強調部分のみ目を通して、結論部分を読む。(p78抄訳) ・速読(30分(新書・ビジネス書)~3時間(専門書)):超速読同様基礎知識がある前提。明確な目的意識を設定し読む。完璧主義は捨て、新聞を読むように重要部分以外は超速読、重要部分も1分未満で読む。(p88抄訳) ・ノート:読書後30分程度で対応。ノート等で振り返りまたは深堀しなければ、自分な得意分野の知識しか身につかず、それでさえ中途半端なレベルのため応用問題は解けない。(p100抄訳) ・ゆるい形で本を読む習慣が身についてしまうと・・・頭の中に定着していかない。「あっ、自分も知っている」という感覚は味わえても、「では、どう知っているのか」には答えられない(知識が定着していない証拠)。(p101抄訳) ・知識は一定の熟成期間を置いた後にしか身につかない。・・・本当の意味で身につくのは3~6か月後。(p113) ・世界史の勉強は1日4時間以内にする。だらだら長時間勉強をしても学力はつかない。(p137) 5.読了時間 ・1時間程度(再読時)
0投稿日: 2022.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法というよりも、大人の勉強のやり直し方法を記載してる感じた。引用が多分に含まれてて著者の主張がものすごい圧を感じるがそれはそれで、はぁ賢い人はすごいなぁと思いながら読み終わった。
0投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人生の時間制限を考えるとで時間をかけて読める本は意外と少ない」という危機感が根底にあるがゆえにとても現実的な読書術になっていた。 月に〇〇冊みたいなものは胡散臭いものが多いが、この著者は ・熟読できる本は多くても月に親書で10冊程度 ・速読で熟読するかどうかを見極める 等、実践的で地に足の着いた読書量を提案している点がとても好印象。 また、読書後のアウトプットの方法として読書ノートの作成法を提案してくれている点も実践につながってよかった。 「知識は効率的に手に入れて、実生活で使えてなんぼ」という実践性に主眼が置かれた読書法でまさに求めていたものだった。
0投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ《熟読の技法》 ☆読むきっかけ 自分の読書というものをより鍛えるためにはどうすれば良いか考えた結果、他人の読書術と比較して、自分に足りないところがあれば、それを吸収すれば、良くなるだろうと判断した。 ☆内容の自分なりの要約 著者は月に300冊以上の読書をすると言うが、全ての書籍をじっくりと読んでいるわけではないという。 時間は限られており、生涯で読める書籍は意外と少ないため、読むに値しない本を排除するために「速読の技法」を使い、じっくりと読むに値する本を「熟読の技法」で読み込む。 速読をするためにはある程度知識が必要だという。知識がないまま速く読もうとすると、ただ字面を追うだけになり、その文章の意味まで理解しないまま通り過ぎてしまう。そのため「その本ってどんな事が書かれていたのか?」と尋ねられても上手く答えられない、という事が起こる。 では、速読をするために必要な知識とはどうすれば身につくのか。著者いわく、一番簡単に基礎知識を手に入れる方法は「高校レベルの教科書と参考書を読む」事だという。 多くの人は「受験で得る知識など実社会では役に立たない」というが、それは著者に言わせれば、知識として定着しておらず、しかも日常生活や仕事で活かそうとしないからだという。きちんと使おうとすれば、役に立つ知識が詰まっている、それが教科書と参考書だと主張している。 しかし、教科書と参考書をゼロから読むというのは効率が悪い。まずは自分の知識の水準がどの程度なのかを把握する事が大切であり、そのために役立つのがセンター試験などの入試試験であるという。センター試験を使って、自分はどこが分かっているのか?どこが分かっていないのか?を明確にして、分かっていないところを重点的に学べばいいという。8割の点数が取れれば、基礎知識がついていると判断してもいいとの事だ。 著者は読書をする際、常にノートを近くに用意しているという。熟読する時は「少なくとも3回は読む」という。一回目は読みながら重要だと思っているところに線を引いたり、よく分からないところには疑問符をつけて通読する。二回目は重要だと思ったところをノートに書き抜き、それに対して自分なりのコメントをつける。三回目はもう一度再読する。という手順を踏んでいるという。 著者の考えでは「現実の出来事を説明できないならば、本当の知識は身についてない」との事だ。例えば歴史の年号や出来事、人物を暗記しているだけでは不十分で、「そこからどんな教訓が見出されて、それが日常生活や仕事上でどのように活かす事ができそうか?」というレベルまで深められていないと本物の知識とは言えないという事だろう。 また、小説や漫画にも触れていて、大きく分けると3つの効用があるとする。「娯楽として楽しむ」「何かを学ぶためのモチベーションとなる(三国志の漫画を読んで、中国史を勉強しようと思うなど)」「社会や人間関係に関する理解を深める寓話」という3つの効用があるという。 要するに「自分の基礎知識を客観的に把握しながら、膨大な書籍を速読術で見極め、じっくりと読むに値する書籍を熟読して、自分の知の領域を拡張していこう」という事ではないだろうか。 著者は前書きにおいて、「読書の技法というタイトルになっているが、物の見方・考え方、表現の仕方まで視野に入れているので、知の技法についての入門書と考えていただきたい」と書いている。そのため、読書術の本としては珍しく、単なる読書の方法論だけではなく、「第二部:何を読めばいいのか」において、世界史や日本史、政治、経済、国語、数学などの学び方の参考になりそうな項目を追加しているのだろう。
0投稿日: 2021.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ買って本棚に置いて読み終えた気がするが、内容を忘れてしまい再読。多くはまた忘れると思われるが、筆者の不断の努力、プロ意識(そんな表現は、安っぽいんですが)に、素直に感心させられます。不器用そうな生き様が見れる点も良いし、個人的には数学を学ぼうとする姿勢に好感が持てます。
0投稿日: 2021.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ1度では全てを理解できないので何度か読み返し、必要な部分だけをまた読み直す作業を繰り返し行いました。 すぐに参考になるところ、今はとてもついて行けないところなどあり、今後の本との向き合い方のベースのひとつとしています。
0投稿日: 2021.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本それベースの知識を身につけてから取捨選択する能力を使って熟読速読超速読をしていくと言う内容 途中から読書技法というよりは、高校の歴史の教科書の復習のようなパートがあってすごく読みづらかった
0投稿日: 2021.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ぶ事が多くあった。 自分は思考力があるわけではないから、本を読んでせめて知識ぐらいはつけようと思う。
0投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ20代の頃、佐藤優さんを社会の先生だと思って信奉していた時期があったのですがそのきっかけになった一冊。 なぜか「世界のエリートとの会話では世界史の教養は必須」という言葉に憧れて半年ぐらいかけて学び直したこともありました。 世界のエリートと接する機会?ないですよ? でも本書の中で紹介されている『青木世界史B講義の実況中継』を使った世界史の学び直しの経験のおかげで自分なりの通史観ができたのは今の読書や映画を観る際にも役に立ってます。
0投稿日: 2021.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変、参考になりました。 著者は書き込みができないため、図書館を利用しないそうです。私は図書館で読んだものを気に入ったものだけ購入しています。 本から得る知識はたくさんあることに異論はありませんから、人それぞれの本との付き合い方を見つければ良いと思います。
0投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じ本を3回以上反復して読むことが大切 大学入試で8割(全科目)様々な学問の基礎知識として必要である
1投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ月平均300冊を読む多読家の佐藤優氏による読書法のノウハウ本です。筆者の持つ膨大な知識量が裏付けとなっているので、書かれている内容にも説得力があります。哲学的な論調は理解が追い付かず、素通りした部分もありますが、効率よく読書から知識を吸収し、定着させるための技法が分かりやすくまとまっていて、とても参考になりました。 難しい内容の部分は読み飛ばして、実践的な読書の技法だけでも理解し、実践するだけでも十分価値のある内容だと感じました。
0投稿日: 2021.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識量からくる考察の深さが見れる。読書のまとめ方も方法論だけでなく、例題を多く記載していて良いと思った。ただ、その例題として記載しているまとめの内容が難しすぎるため読み進めていくのがキツイ。 教養に関する部分は、自分が勉強するタイミングで一つずつ読んでいかないと無理だと思った。 正しいと思っていることが刷り込みであることもある。基本書は3、5冊読むようにする。 読書のまとめは、30分や60分など時間を区切って行い、それ以上は時間をかけないようにする。 自分の意見や感想を追加する。〇〇の言説と対立している、など。 小説は自分で経験できないことを経験してる人の心理や誘惑を知るための代理体験として読む。 夜中や疲れているときは、基本書の読み直しや復習のために使う。
1投稿日: 2021.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ正解的なものを提示するのではなく、著者自身の読書法を具体的に提示して、読書判断で参考にできる部分を参考にするという主旨かと思う。 私自身は、佐藤氏のように博覧強記の怪物ではないため、ここまで突き詰めることはできない。 超速度と普通の速読についての説明が興味深い。巷でイメージされてるような、一種で写真のように記憶するマジックのようなものではなく、「基礎知識があるからできるものであって、その目的は熟読すべき本を選別するためのもの」という考え方。 良書を繰り返し熟読することでのみ使える知識となるというのは、おっしゃる通りだと思われ、カルチャースクールでフォトリーディング講座を嬉々として学ぶような愚行は避けたいところである。
0投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学を出ていても高校レベルの基本を押さえていない学生が多いという記載があった。 私も大学時代は全く勉強していなかった為、ビジネスシーンにおいては不利な戦いを強いられた。 この佐藤さんの読書の技法を読むことで抑えるべき歴史の転換点の出来事や読書するために必要な基本というものが理解できたのでこれを生かして今後の知的活動に力を入れていきたいと思います。
0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ●基礎知識がなければ読書にならず、指の運動p27 ●重要なことは、知識の断片ではなく、自分の中にある知識を用いて、現実の出来事を説明できるようになること,P58 ●基礎知識は高校教科書で学ぼう
0投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログノートに文を写すという部分は時間がかかりすぎるのでは?と思ったが、能動的に取り組むという意味では大切なことであると感じた。 本をどう選ぶかという点については私自身が適当に行っていたこともあり非常に参考となった。 最初の基本書は網羅性を中心に選びたい。
0投稿日: 2021.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み手に一定の知識を要求される。 読書によるインプット、アウトプットの面では多くの人にとって役に立つ方法が書かれており漏らさず読み込むことをおすすめする。 速読に関しても、技術うんぬんを言っているあまり合理的でない本を読むよりも遥かに有益なメソッドを知る事ができる。 しかし、例などで挙げられているものは著者自身がモスクワに赴任した経験からロシアに関するものや、政治に関するものなど、ライト層にとっては堅苦しく敬遠しがちなものが多く、疎外感を持ってしまい、深い理解求めると挫折してしまう読者が多そうだとも感じた。 読者の知識レベルを問われる本であるが、確かに有益な事が書かれていたのは理解できた。 知識レベルをあげた上で再度読み返すと決めた。 その時にはぜひこの本を熟読したい。 拙い文章を読んでいただきありがとうございました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 自分用メモ ・簡単に読める・そこそこ時間がかかる・ものすごく時間がかかる の3つに本を分類する 知りたい分野の本は3〜5冊読む 下手に間違った知識を入れてしまうとステレオタイプになりかねず、その後深い理解に苦しむ事になる 1番クオリティが落ち込みがちな真ん中を読む 熟読は3回読む 1,線を引きながら (シャーペンで後々直せるよう書いた方がいい) 2,ノートに重要な所を抜き書き(10日程度かけ線を引いた所からさらに重要な所を線で囲み書き写す。囲みはどれだけ多くてもテキストの10分の1にとどめる) 3,もう一度読み返す(まず目次で構成を理解した上です結論を3回読む
0投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本書を3回、結論3回、3冊読んでベースを作る テレビのニュースを見ても、わからないことがある。特に、海外情勢や貿易、為替の話題になるとちんぷん、かんぷん… その理由は、高校までの政治経済や歴史の知識が足りなかったからなんだと痛感。あいたたた…今から、基本教科の底上げを図りたいところです。自分の子供には二の舞を踏まぬよう、先を見て道標を作ってあげられるかもと、ちょっぴりワクワクもしています。 本書は、0からでも世界史の学力を上げる方法が具体的に書いてあり、やる気を起こさせてくれます。 また、著者の睡眠についての記述を参考にしたところ、睡眠時間が6時間くらいに収まり、高い集中力をキープできています。 読みたい本ややりたい事が沢山あり、時間が足りないと感じる方は、一読の価値があると思います。
1投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んで良かった。読書以外にも、ビジネスパーソンとして必要な知識や教養等について、具体的な勉強方法も紹介されており、非常に学べることが多い。 後は、実行するかしないかである。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログきっかけ 某メンタリストさんのオススメからの入り口 ただ本を読むのではなく、読んだ先に何があるのかが知りたくて、手に取った 感想 政治の話とか、自分の基礎知識のなさが露呈した そんな中、読み切ったことが、一つの自信にもなった気がする 歴史や政治について、知らなさすぎるところは、本書にて勧められてる勉強をやってみるのも面白そうだと思う 近いうちに、本のピックアップの後始めるつもり 本の読み方に対しても、 付箋 三度読み に関しては取り入れようと思っている
0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書は他人の経験、知的努力を自身のものにすることができ人生を今以上に豊かにできる。 月平均300〜500冊は目を通すという佐藤氏の読書術が本書には書かれている。 時間に制約があるなかで自身にとって必要な本がそうでないかを自己選択するのが大事であり、「熟読法」「速読法」「超速読法」の3種類に分けて説明している。 上記の読書法で私自身も実践をしたいと思ったことは重要な箇所にはポストイットやシャーペンで印をつけ情報を整理すること、読書ノートを作成することである。 また知の道を極めるには高校レベルの基礎知識を身につけることが近道とされ、歴史政治経済国語数学の教科がビジネスパーソンという目線でどう活用できるのかということも詳しく書かれている。 本書を読んで自身の読書の価値観が変わった一冊である。 印象に残ったことば 「知は力」であり「力は知」である。
0投稿日: 2020.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んでから、1冊のノートに読書メモを取ろうと思いたち、ノートを購入した。 本の内容が分からないのは、前提知識が足りないからか、デタラメな本だからだという指摘はもっともだと思った。 知識が足りなければ高校の復習をする、という堅実な方法が書かれていて、やはり楽して知識をつける方法というのはないのだな… 無駄にタラタラ書かれている割に情報量の少ない読書法の本とはひと味違う。一読すべき本。
0投稿日: 2020.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者は今まで沢山本を読んできて多くの分野に通暁しているから本が速く読めるようになったらしい。自分も小手先の速読術をかじって本を沢山読めた気になるのではなく、知識が不十分なのだから本が速く読めないのは当たり前だと割り切って、毎日少しでも本を読み、継続することが1番大切であることを常に意識してしていきたい。 これから食後の消化タイムに必ず本を読むことを習慣づけていきたい。 速読する本と熟読する本を仕分ける技術を身につける為に、これからは目次→はじめに→終わりに→気になる単語・文節を拾い読みをして熟読に値すると思った本だけもう一度通読することにする。
0投稿日: 2020.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ方法論に関する本はあまり好きではないが、これは大変参考になった。 超速読・速読・熟読・ノートにメモの4つを上手く自分なりにアレンジして実践している。おかげで一読するだけの習慣がなくなり、再読する重要性に気が付けた。 「良い本だった!」という印象が残っている本を改めて手に取ると全く覚えていないという経験もさせてもらった。だから特に記憶に残しておきたいものはノートに記す。 ちなみにこの本は2回読みました。笑 自分の読書習慣を見直す機会になるだけでなく、大学受験の勉強の大切さが書かれているので、勉強欲も刺激してくれるいい本だった。
0投稿日: 2020.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門 (和書)2013年03月18日 22:57 佐藤 優 東洋経済新報社 2012年7月27日 この本を本屋で見つけたときは、速読とか基礎知識の習得法ぐらいの本でぱらぱら眺めてこれこそ速読で済ませられる本だと判断していた。ボクはカネがないから基本的に本は立ち読みか図書館だ。 図書館で見つけた時も参考書の確認程度の認識で借りてみた。しかしそれはとんでもない間違いだった。いくらか読み進めていくとこの本がそんなハウツー本ではない非常に優れた政治思想の本であることが解ってきた。 人間がどのように連帯するか、その相互扶助の政治思想が読書法の仮面の下に隠れていた。 ボクは一度、紀伊国屋ホールで佐藤優さんの講演を聴きに行ったことがある。その時、彼は「自分は保守である」と語っていたがそれは方便であるということが解ってきた。 この本こそ速読で済ませられる本ではない。 あと、本は購入し手を入れるべきとのこと。出来ればそうしたい。しかし本を買う金銭的余裕はない。だから図書館でしか基本的に本を借りない。それで最近、ノートを取る習慣をつけようと心がけている。そこら辺は自分の現状との摺り合わせでやっていくしかない。 かなり読みやすく有益な本だと思う。オススメします。
0投稿日: 2020.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読法について、全く知識のない分野の本をいくら早く読もうとしても無駄。全くロシア語を理解していない人がいくらロシア語の本を早くページをめくっても理解できないのと同じ。 熟読する本と、時間をかけるべきでない本を見極める。 本は熟読するなら借りるのでなく買って書き込み、メモし、四角で括り、汚くするものだ。 基本的な知識がなければ難しいテーマを読んでも理解が進まず、時間の無駄になる。 基本をよく理解し、自分に合った知識レベルの本を選ぶ。 二度寝はしない。著者は昔からのショートスリーパーで3時間くらいで大丈夫な体質だが、昼寝はしても、少しハッと目が覚めることがあればすぐ飛び起きて、時間を無駄にしないようにしている。 語学と数学は体で覚える。 歴史は暗記するのではなく体系的な理解を心がける。歴史を学べば現在起きている事柄を理解しやすくなるが、体系的な知識がなければ、理解できない。
0投稿日: 2020.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ月に300冊から500冊という「とんでもない量」の本を読む、佐藤優さんの読書法。 そのポイントは本を3つに分けること。 「超速読」だけで終わる本、「普通の速読」をする本、「熟読」までする本、というもの。 これだけ読む人でも、普通の会社員が熟読できるのは月にせいぜい5、6冊程度と書いてある。 大切なのは、その「熟読すべき本」をしっかり選べるようになること。 つまり、出会いのために多読が必要だということで超速読や速読をする、というのが著者の主張になる。 ちなみに、「速読」「超速読」といってもいわゆる眼筋を鍛えるとかフォトリーディングとかそんな魔法みたいな読書法ではない。 慣れれば誰にでも可能な方法だと思うので、やってみる価値はある。 「超速読」で本の選定をし、「普通の速読」を基本として読む。これは!という本のみ「熟読」する。 佐藤優流の読書術がこの一冊におさまっている。
0投稿日: 2020.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読、速読、超速読と三種類の技法 またそれにかかわる詳しい説明がきさいされていた 筆者の言う通り時間は有限であるため 超速読などにより、読む必要のある本と必要のない本の選定は非常に説得力のあるものであった また、本は買って読むについては非常に同感 ノートは記録ではなく記憶のためにつける 意見やコメントをつける 書き写しというところは自分の定着になるだろうなあと感じました メモ程度ですが参考までに
0投稿日: 2020.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ月平均300冊以上の書物に目を通している佐藤優氏の読書術がこと細かに描かれています。 熟読・速読・超速読の3つに分類し、それぞれの目的と具体的な実践方法が分かります。 どのような本をいつどこでどのように読めば良いか、具体的に分かるので、できるところは真似してみたいです。
1投稿日: 2020.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ超速読、速読、熟読に分けてそれぞれ方法や意図を教えてくれる本日。 超速読とは5分で行い最初のページと目次のみ読みひたすらページをめくる。気になった点のみシャーペンや折るなどしてわかりやすいようにし、最後の結論ページのみ読む。最初のページと目次を読んだ後は真ん中から読むことで本の水準を知ることが出来る。 これによりまず超速読のみにとどめるか、速読するか、熟読するかを選択する。また超速読も速読にも、一定の基礎知識が必要である。基礎知識は高校までの勉強で培うべし。 速読とは30分で1冊読む方法だ。これは既知の方法で、大体出来ているため割愛。 熟読は囲みで抜き出して、自分のコメント、意見、賛成or反対 理解できるorできない 一言などを付け加える。 またどの方法の際もシャーペンを用意して印をつける必要があることを推している。 まずは基礎知識習得のために高校の現代文の勉強からやり直す。
1投稿日: 2020.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優が自らの読書の技法について語る。 懇切丁寧である。 どういった本は熟読が必要で、どういった本は速読・超速読で済ませるかといったアドバイスもさることながら、読書の際に用意する道具。シャープペンシルや鉛筆、消しゴム、ノートといったものを紹介しながら、シャープペンシルの芯の濃さまで指定している。。 しかも、満員電車では本に線を引く作業を行わない方がいい。他人に気遣いができる人間のほうが出世するなど、細かい配慮も怠らない。 やもすれば「佐藤優のようなエリートだからできる読書術だ」と考えがちだが、そのあたりはごく普通のサラリーマンでも対応できるような方法でアドバイスしてくれている。 自分もこの本を読んで、もう一度読書というものを考えてみようと思った。
0投稿日: 2020.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「知識を得るために、いかに本を読むか」という読書指南。 著者の地道で真摯な読書・勉強スタイルに尊敬するばかり。 簡単ではないけれど、ぜひ真似したいと思えるものだった。 他に読書術の本は読んだことがないが、佐藤氏の真摯で緻密な読書法は勉強の基礎の基礎を実践されているようで、これを目指せばきっと間違いないように思える。 昨今は本の要点をまとめたサービスもあるようだが、きっとそれでは知識は身につかないだろう。限られた人生の中で読むべき本を見極め、知識を会得できるような読書ができるようになりたい。まだまだ自分には長い道のりにも思えるが… 熟読法はなかなかすぐには真似できないが、まずは積読を処理することから始めてみたいと思う。
0投稿日: 2020.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本をはやく読む方法を知りたくて読み始めたので、思っていた内容と少し違ったが、読み進めるうちに興味深くなっていっきに読んでしまった。 ビジネス書や仕事関連の本をなかなか読む気になれなかったが、読む際の着眼点や理解を深める方法が参考になりそう。
0投稿日: 2020.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・月平均300冊 ・多い月は500冊 これだけの量を読んでいる、 佐藤流の「熟読術」「速読術」を知れるということなので読んでみました。 正直、誰でも簡単にできる技法ではないと感じます。 読書初心者にとっては難しい。 読書の虫ってくらい本が好きな人でないと実行できない技法です。 本を読むのが苦手だから「読書術」を学びたいって人にはおすすめできない一冊です。
0投稿日: 2020.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
有限な人生において読むことができる本の数は限られている。佐藤氏は月に300冊の本に目を通すが、熟読するのは4, 5冊。 読むべき本の精査のためには速読が必要になるが、読もうとする本の分野の基礎知識がなければ速読はできない。基礎知識は基本書を熟読することでしか得られない。 超速読では1冊を5分で読む事を目指し、本を読む必要がああるかどうか、読むべき箇所がどこかを見極める。はじめにと結論、目次以外は読まずに流し見するだけ。 普通の速読では1冊を30分 ~ 数時間程度で読む。新聞を読むときのように、見出しなどから読む場所と飛ばす場所を判断しつつ、自分が必要としている未知の情報だけを拾い読みする。 熟読する本は3回読む。線を引いたり、気になる箇所を囲ったりしながら繰り返し読む。 小説や漫画は娯楽としての読書として有益。
0投稿日: 2020.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書に関する佐藤さんの行っている様々な技法がまとめられた本。 他の読書術の本に書かれているのと違う点は、「ただ早く読む」という点に焦点を当てるという訳ではなく、1つのジャンルを極めるために読む技術が書かれている。 なので、入門書の精読の仕方からかなり詳しく書かれている。 速読は基礎知識がないとできない、だからその土台を作る精読。 というのは、分かるんだけど正直時間もかかるし何より面倒。しかし、この本を土台に自分なりにカスタマイズして利用することは出来ると思う。 本を読むけど、ただ読んでるだけで頭に入ってこない人理解できない人なんかにはオススメ。
0投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書習慣をつける為、まずは読み方から学んでみようと思いこの本を選びました。 読書をする上での基礎知識の重要性や、速読は熟読する本を見つける為の行為という考え方など学べたものはあったかと思います。 しかし政治の話や著者の読んだ本の引用等、 読書法とは離れたところでの難しい内容が多く、 読書入門で読むものではなかったのかなと感じました。 読書の技法を学びたい人におすすめ!とは言えませんが、何冊か読む中の1冊としてはアリだと思います。
0投稿日: 2020.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ超人。真似のできるわけもない。2時に寝て、5時に起きる。でも読書、気になる。月平均300冊。 読書ノートは作るべし。ゆるい本を読む習慣が身につくと、読んでも、頭の中に定着しない。
0投稿日: 2020.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優さんの、その名も「読書の技法」。 大量の情報を入手していることは自明で、それをどうやっているのか、ノウハウを知りたくて、手にしてみました。 どんな情報を必要としているか、にもよるので、方法論として知っておくのはいい。「何を知るために」そして「それをどうやって活かすのか」については、当然自分自身の頭で考える必要はあります。 ある程度の年齢になってきて、リベラル・アーツから学ぶことって、結構あるなと思うようになってきたのだけれど、昔詰め込んで、しかも好きだと思っていた知識も、結構忘れているのですね。その意味では、テクニック的に参考になったのは、以下です。 以下、抜粋: 1. 『基礎知識を高等教育までで徹底的に詰め込むからこそ、大学入学後、驚くほどの速度で大量の本を読みこなすことが出来るのである。・・・なかでも、『岩波講座 世界歴史』と『岩波講座 日本歴史』を通読し、世界史、日本史についての基礎知識を強化できたことは大きい。・・・』 2. 『大学入試の標準とされるのは先ほど取り上げた佐藤次高他『詳説 世界史 改訂版』(山川出版社)だ。しかし、この教科書を読んだだけで、内容を記憶することは出来ない。そこで、通史については、わかりやすい青木裕司『NEW青木世界史B 講義の実況中継』(全5巻、語学春秋社)を通読することにした。・・・第二段階として次の課題を指示した。鈴木敏彦『ナビゲーター世界史B』(全4巻、山川出版社)を読み、その後、前出の『実況中継』第5巻(文化史)を読んだ。・・・そして、塩田徹/永井英樹編『各国別世界史ノート 重要事項記入式』(山川出版社)に取り組んだ。この教材は、教科書を読むだけでは理解しにくい各国史、地域史を把握するのに最適だ。ビジネスパーソンが国際政治を理解する基本書として用いることもできる。』 こんな時だからこそ、時間を大切にして、なかなかインプットすることのできない知識に集中的に向き合うのもいいと思います。
0投稿日: 2020.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の本ばかり最近読んでいるが彼の人生で求められた読書の身につけ方を纏めた本。 相変わらず読みやすい文体。 速読と熟読はちがう、身につけなければならない知識をどう定着させるかというとこである。 使えなければ読書の意味はない、その技法を経験を交えて説明してくれている本だ。
0投稿日: 2020.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分に使えそうな部分をかいつまんで読了。読書ノートだけじゃなく自分の思考や行動を書き記しておくのも面白そう。再現性の高い身になる読書ノートを作りたい。
0投稿日: 2019.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分は転職のために高校時代の教科書を読み直す勉強法を取ったが、この時初めて教科書を面白い読み物だと思った(国語は当初から面白かったが)。そしてこれさえ読めば事足りると確信した。専門書以外の参考書は、一般教養問題集1冊しか買わなかった。 それくらいに高校の教科書は優れている。これを論理的に説明しているのが本書である。この本の影響なのだろうか、山川出版社から続々と「もういちど読む教科書」シリーズが売り出されるようになったのは。 当時の鳩山政権の失敗を、「偏微分」で分析しているところが面白い。鳩山元首相は数学者でありバリバリの理系学者であったから、これまでの文系政治体系とは異なる論理を組み立てていた。その数式が分からない人は「宇宙人言語」と揶揄した。だが数式を分かる人が身内にいなかったのだろうか、結局政権は瓦解した。理系首相の失敗を分析する重要性を著者は説く。あれから9年後、分析どころか世の中はますます理系のレベルが下がっていないか?「数学IA」から読み直そう。
1投稿日: 2019.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ”本を読むための本”を読むのは時間の無駄のように思えてやめようと思ったのだが、ついつい読了。 一生に読める本、身につけられる知識は限られているから読むべき本を見極めて読むという筆者の考え方に触れ、そういえば人生もう半分終わってしまった、と改めて思う。 筆者が紹介する超速読、速読、熟読、という読書法は、仕事で読む論文の読み方にも取り入れることができた。 読書にとどまらず歴史や数学、現代文、哲学などの勉強法もおすすめ参考書とともに解説されており、非常に刺激を受ける。 自身の勉強以外でも、親が何の予習もなしに子供の勉強を見てられるのは小学校低学年まで、というのはその通り。 学び続けて、ちゃんと内容を理解して教えられる/一緒に考えられる親でいたいから頑張ろう。
0投稿日: 2019.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
メンタリストDaiGoが「読書に関する本はこれだけ読めばいい!」と勧めていて、読みたい本が多いのに積読だけがどんどん溜まっていくので、参考になればと思い読んでみた。 筆者の体験・経験をベースに本の読み方について解説してある。 速読、多読、熟読と章分けされており、参考になる部分は多かった。 本にはそれぞれの役割があり読む順番があることは、新たな気づきだった。 しかし、紹介されている本が個人的には専門的過ぎて一読しただけでは消化不良感があるため、★マイナス1とする。 ただの本好きが、単純に今より多く本を読みたいから速読を学びたいと思って読むものではない。 内容をしっかり咀嚼して自分の知識として、自己の成長を望んでいる人には、大変役に立つと思う。 定期的に読み返して筆者の技術を身につけ、今より多くの本をスムーズに読んで知見を広げたいと思った。
1投稿日: 2019.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者の本の読み方や、読み取り方のコツなどを書いた一冊。 速読や熟読法などは非常に興味深く、参考になった。 しかしながら、中間部の教科書の読み解き部分が個人的には多すぎるかと、、
0投稿日: 2019.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭のどこかでずっと気にかかっていた本。たぶん、本屋で見かけた表紙の著者の目線と表情が気になっていたのだと思う。2012年出版だから、そこから現在までのどこかで見かけて数年経っていたはずだ。市の図書館を使いはじめたついでで借りてみた。 「ちゃんと論述してある」ので読む価値はあるし、紹介されている本の何冊か(主に高校教科書と参考書)は気になった。それは自分が政治・経済への興味の高さと知識に低さに理由があると思う。 市の図書館の電子図書を試そうと思って借りてみた似たことを主張する本よりはずっと価値があった。こちらはなんとなく論述して色々な”アート”(科学啓蒙書、思想・哲学、映画、マンガ、文学、芸術作品など全般)を列挙するタイプだったので、良くも悪くも通りすぎる以上の価値はなかった。それよりも電子図書の動作確認の方が価値があった。 それに対して本書はノートを残しておこうと思えるものだった。それは学者という自分は頭が固いし頭でっかちだし屁理屈をこねるからだと思う。 とは言うものの、本書の場合は基本的に私的な文脈に基づいた地に足のついた論述がなされていたから、面白く読めたのだと思う。改めて自分の興味を広げ、視野を広くする姿勢を思い出させてくれた。 手元に置いておいて、何度か読んでみてもいいと思った。 「第I部 本はどう読むか」はその方法を真似するかはともかく、何をもってその方法を採用しているか、それによってどういう経験をしてきたかなどがきっちり書かれているので参考になる部分も多い。賛同する部分も多いし、新に考えさせてくれる部分もあった。 「第II部 何を読めばいいか」は著者の経験に基づく具体的な事例を使った論述。著者の専門とビジネスパーソンの需要を考慮して世界史、日本史、政治、経済、国語、数学と網羅。基本的には高校の教科書(と参考書)をマスターせよ、ということ。教科書の何が良くて何が悪いか、全く同意する。また、国語と数学は最も近い”科目"であるという自分にとってもほぼ自明であることが、ちゃんとわかりやすく、良い本(参考書)を引用しながら主張してあるところが素晴しい。自分は良い受験生(中高生)ではなかったので、そのときにちゃんと知っていたかったとも思う。……いや、当時だったらやっぱりかぶれるだけかな。 「第III部 本はいつ、どこで読むか」たぶんこれまでよく質問されてきたことに答えながら本書を終わりに向けるために設けられた部分。自身の経験を踏まえながら回答していくような論述になっていた。軽く読んでいける部分。 広く一般的な話題を扱う第I部から事例にはいる第II部への繋がり、最後を締める第III部ということで構造もとても入ってきやすいし、参考になる部分も多かった。
0投稿日: 2019.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先日読んだ池上彰さんとの共著「僕らが毎日やってる最強の読み方」が面白かったので、佐藤さんの読書術をもう少し詳しく知りたく出版から結構経った本ですが手に取ってみました。 で…実は途中で読むのをやめました。今「-最強の読み方」を読了していたらこの本は必要ないなと感じたからです。 ビジネスパーソンやこれから社会に出る大学生には具体的で有効かと思いましが、自分には「-最強の読み方」だけで充分でした。こちらを先に読んでいたら良かったのかな。 まさに、佐藤さんのおっしゃる通り自分に必要な本とそうでない本の仕分けで「速読」して終了しました。 佐藤さんの本で即実践することになるとは思ってませんでしたが、おかげさまで少しは今までよりも早く必要な本が読めそうな気がします。
2投稿日: 2019.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「熟読」「普通の速読」「超速読」を使い分けて、本から知識を学び取る方法を教えてくれる本。 速読のハウツー本は何冊か読んだけど、どれも試してはみたけどしっくり来なかった。 本書でも「速読のやり方」についての記述はあるけど、結局のところ「速読」で全てを理解するのは不可能、本気で熟読できるのは月に数冊という、至極当たり前の結論に辿り着く。 読むべき本と、そうでない本を見極める。自分にとって必要な本にはそれ相応の時間をかける。完璧主義に陥ってしまうと、結果として有限な時間を無為に使ってしまうことになる。 「高校の教科書は結構使える」「小説、漫画は興味の入り口、娯楽として」「本は出来るだけ買った方が良い。書き込みできるし、金を使うと元を取ろうと考える」といったあたりも、当たり前って言えば、当たり前。それだけに腑に落ちる。 唯一、意外性があったのは、鳩山由紀夫元総理への著者の評価くらいか。 という事で、アレンジやチューニングは必要だけど、これは実行可能なノウハウな気がする。
0投稿日: 2019.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの書物を読みこなす著者の読書アカデミー講座。本の読み方では、速読を身に着けるためには熟読法を身につけなければならない、というものが印象に残っている。 また、教科書と学習参考書を使いこなすの章では、世界史、日本史、政治、経済、国語、数学と学び方を丁寧に解説しているので、この章を読むだけでも、知識と心構えが身につく。 とても真似できるようなものではないが、一歩でも近づく努力をしたい。
0投稿日: 2019.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログボンボン本を出している、元外務省分析官による実用書です。 いわゆる教養人がこうあるべし、とか言って指南書を書くのはよくあることだし、別にそれはいいのだけれど…。 アラが目立つよなあ。いい点は語り尽くされてるので、気になった点を。 まず、帯に書かれた月500冊の読書量について。 全盛期のニーチェが日に200冊、某メンタリストさんが日に30冊、ジャイアント馬場さんが年間200冊なので、割と多い部類です。 種明かしすると、読みを分けておくことで効率化を図っていました。 氏が超速読と呼ぶ、パラパラめくって内容をざっと掴む読み方による読書も含めての500冊でした。 献本された書籍でもこの超速読による選別は行なっているらしい。 というわけで、端から端まで読んでの500冊ではありませんでした。世の中手品のタネは退屈なのです。 あとは、おいおい追記します。
26投稿日: 2019.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白くて一気読み。 じわじわと売れているようですが、それは、本書が他のビジネス書にありがちな、誰でもできる読書のノウハウ本とは一線を画するからでしょう。 単純な読書のためのノウハウ本というわけではなく、知識人らしい奥行きのある内容で、読書の有用性について、筆者の読書歴といった話も楽しめる。 インテリジェンスがいかに知を磨き上げ、見識とものの見方を広げているのかがうかがい知れる。 ふわふわした読書ではたどり着けないような、腰の座った読書の仕方が提示されています。 知識の深め方、自分の血肉とする方法を具体的に示している。とても参考になりました。 ある分野について知るには基礎的な知識が不可欠、熟読対象の読み方の提示、速読の意味、高校レベルの知識と論理力がいかに必要かという話から、高校レベルの教科書、参考書を使った学び方も提案されています。 ビジネスパーソンだけではなく、どんな仕事の人でも自分の専門分野の学びについて参考にできる部分があります。
2投稿日: 2019.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ12.8.1 こんにちは、土井英司です。 本日の一冊は、月平均300冊、多い月は500冊以上を読むという 博覧強記、元外務省主任分析官の佐藤優氏による『読書の技法』。 一冊を30分程度で試し読みし、熟読するかどうか、読書ノート を作成するかどうかを決める「普通の速読」と、5分で本を仕 分け、読むべき箇所のあたりをつける「超速読」。著者はこの 2種類の速読技法を併用することで、驚異的な読書量を可能に しています。 とはいえ、実際に熟読する本は月に4〜5冊で、本書にはそれ らの本をどう熟読するか、そのポイントが書かれています。 ・まず本の真ん中くらいのページを読んでみる<第一読> ・シャーペンで印をつけながら読む<第一読> ・本に囲みを作る<第二読> ・囲みの部分をノートに写す<第二読> ・結論部分を3回読み、もう一度通読する<第三読> 囲みを作る、という発想はこれまでなかったので、さっそく参 考にしてみようと思いました。 (確かに、普通に赤ペンを引くより見栄えがきれい) ほかにも、「自分の本棚にあえて『積ん読』本のコーナーを作 り、5〜6冊たまった頃合いを見て、超速読をしてみる」など、 大量の書籍情報を処理するノウハウが満載。 そして何より本書が優れているのは、読者に「自分の知識の欠 損部分を知」ることを推奨している点でしょう。 高度な本を読みこなすために必要な【世界史】【日本史】【政 治】【経済】【国語】【数学】の基礎知識と、おすすめ本のブ ックガイドがついており、社会人の学び直しに最適の一冊とな っています。 私立文系出身で、「知識の欠損部分」の存在を意識している人 は、ぜひ本書のブックガイドを見て、参考書を買い漁りましょう。 表面的な読書をやめ、本気で「知」を身につけたい方に、ぜひ おすすめしたい一冊です。 --------------------------------------------------- ▼ 本日の赤ペンチェック ▼ --------------------------------------------------- 「熟読できる本の数は限られている」というのは、読書の技法 を考えるうえでの大原則である。読書に慣れている人でも、専 門書ならば300ページ程度の本を1カ月に3〜4冊しか熟読で きない 新たな本を読むとき既知の内容に関する部分は読み飛ばし、未 知の内容を丁寧に読む。このように速読を行うことによって時 間をかなり圧縮することができる 基礎知識があるからこそ、該当分野の本を大量に読みこなすこ とができるのだ なかでも、『岩波講座 世界歴史』(全31巻、岩波書店)と 『岩波講座 日本歴史』(全23巻、岩波書店)を通読し、世界 史、日本史についての基礎知識を強化できたことは大きい 大切なのは、自分の知識の欠損部分を知り、それを補うことだ 現実の出来事を説明できないなら、本物の知識は身についていない 1回目に線を引いた部分で特に重要と思う部分をシャーペンで 線を引いて囲む 「普通の速読」とは、400ページ程度の一般書や学術書を30分 程度で読む技法である ◆超速読の技法 5分の制約を設け、最初と最後、目次以外はひたすらページをめくる 高校段階での数学に不安があり、行列、数列、微分法、積分法 がまったくできないのに、近代経済学や統計学の知識を身につ けようとしても、無理である。その際は数学の基礎力をつけて 再チャレンジするしか、知識を着実に身につける道はない 歴史小説で歴史を勉強してはいけない 恐慌の結果、本格的なリストラに耐え抜くことができる大資本 だけが生き残り、老舗財閥の力が強化された。そして、社会的 格差が拡大し、貧困層の不満が強まり、「世直し」の気運が出 てきた 改革運動は不遇の知的エリートが起こす くれぐれも漫画で基礎知識をつけようとしてはいけない
1投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優さんの読書のノウハウ、速読から熟読精読まで書かれているのだが、大半は彼がいかに賢い、優秀か、経験豊富かと言うことを誇示しており、また彼の主義主張が多く、読んできて気分がよくない。その一方でノウハウ的なことはあまり書かれていない。
2投稿日: 2019.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読 真ん中を読む 基本書奇数冊 超速読 目次 まえがき 全体ページめくるだけ 普通の速読 1ページ15秒 定規
1投稿日: 2019.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はあとがきに書いてある通り、技法というより、読書の有用性を訴えている 年間4000冊を読む人の技術集 まず、じっくり読む本とそうじゃない本の区別のために速読があると言っていた。 また、熟読する本選びのためにも超速読というものも有効であると説いている。 本書は作者が文系であることから外国語や歴史について主にふれて、読書というものもを紹介している。ただ、自分は文系教科に馴染みがないため、頭に入りにくかった。 筆者の膨大な読書した本の中から、本題目に沿った引用が数多くある。 こんな本があるんだという、知の追求、知的好奇心の刺激に最適。自分の無知の知を再認識する ただ、この本の内容はエビデンスを他の本にしているため、最新の論文などによる科学的に根拠が薄い部分もある。だけど、自分の知らない分野の知に触れられて良かった
0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
速読についての良書ということで流し読みしたが、他の方のレビューを読めば充分内容を取ることが出来る。あえて追記するならば以下のふたつ ・ノートを取らないと自分の得意な分野の知識しか身に付かない ・小説は時代の雰囲気を掴んでいるので、現実とリンクさせながら読むとよい
1投稿日: 2019.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間が人間にとって最大の制約条件。速読は読まない本を早めに選別するための手段。 現実の出来事を説明できないなら、本物の知識は身についていない。 読書ノートには抜書きとコメントを記す。 社会人になってから教科書と学習参考書を使いこなす。 読書では完璧主義を捨て、目的意識を明確にする。 学ぶことに対する姿勢に刺激を受けた。
1投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の知に迫りたくて読んだ。結局、ボリュームかなぁというのが感想。速読の技術は個人個人でベストな方法が違うので、自分なりに佐藤氏並のボリュームをこなすにはどうしたら良いか、それを考えることが必要だと改めて思った。 速読とは直接関係ないが、基本書を熟読すること、微分積分の勉強し直しについては非常に参考になった。数学も語学と同じで、練習あるのみであるという示唆には目を洗われた。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎的な知識がないと、いろいろな分野の本を本当に理解するのは難しいということがわかった。数をこなせばそのうち理解できるようになると思うのは甘いし、時間の無駄。近いうちに、世界史と数学の高校レベルの復習を始めたい
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年87冊目 朝活アウトプット読書会で頂いた本です。 著者の佐藤 優氏は元外務省分析官。ロシア外交の最前線で活躍していたが、背任などで逮捕され執行猶予付き有罪判決確定後外務省を失職し、今では多くの著書を出した作家でもあり、ジャーナリスト。 月平均300冊。多い時は500冊以上も本を読んでいてその読み方を紹介。 本の正しい読み方を学ぶ事で多くの本を読む事ができる 前提は難解な本をいかに多く読むかという方法論をベースにしており、 著者が読んでいる本の専門性と幅広さに驚かされる。 そして、難解な本を理解するには正しい基礎知識が重要ということを主張。 社会人は基礎的な知識に欠落があることを指摘しており、 その欠落を埋めるために高校の教科書や参考書をすすめている。 本書では教科書の読み方にかなりのボリュームを割いている。 面白い尾のは、学術書だけでなく、たとえば村上春樹の1Q84からも鳩山由紀夫の政治手法を結びつける考え方なども説明しており、著者の物事を読み取る力に驚かされるばかりだ。 また、知識の定着方法として読書ノートをどうつけるかなど参考になる点も多かった。 非常に参考になる一冊であった。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログmmsn01-288 【ノート】 ・MediaMarkerで。どうも、適当そうな本っぽいので、図書館で。 ・いやいや、そんな「適当」な本ではなかった。ちゃんと真摯に書かれている。なので購入。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディオブックにて視聴。 いや、佐藤さんすごいっすわ。 ちゃんと体系だって学びたかったのでKindleも購入。 またKindle読んだら読書メモ書きます。
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外出張中に読んでいた本。 以前読んだ『獄中記』でもエッセンスは述べられていたが、本書ではより直接的に、著者の読書方法にフォーカスしたものである。 教科書や参考書を読むというのは、同著にもあったが、本書では、より広いジャンルでの方法が紹介されている。 私は本を汚すのが嫌いなので、そのまま真似することはないが、紹介されている本のいくつかは読んでみようと思う。 [more] (目次) 【第I部 本はどう読むか】 第1章 多読の技法――筆者はいかにして大量の本を読みこなすようになったか 第2章 熟読の技法――基本書をどう読みこなすか 第3章 速読の技法――「超速読」と「普通の速読」 第4章 読書ノートの作り方――記憶を定着させる抜き書きとコメント 【第II部 何を読めばいいか】 第5章 教科書と学習参考書を使いこなす――知識の欠損部分をどう見つけ、補うか 【世界史】【日本史】【政治】【経済】【国語】【数学】 第6章 小説や漫画の読み方 【第III部 本はいつ、どこで読むか】 第7章 時間を圧縮する技法――時間帯と場所を使い分ける 【特別付録】本書に登場する書籍リスト
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の知識のなさに愕然とした。恥ずかしい。学生時代に、受験のためじゃなく自分のために、もっとちゃんと勉強しておけば良かった。今からでも学び直そう。この本の熟読術・速読術を駆使して。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手の本はあまり読まないことにしているのだけれど、佐藤優が気になって読んでみた。でも高校の教科書や参考書は大人にも有効という話は参考になるかな。だからといって、もう一度勉はしないと思う。ハウツー本というよりは、著者の読書法拝見本か。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログとても真似できないが,得るところは多々あり. ・「何をしないか」「何を読まないか」も大切な知の技法のひとつ. ・時間が人間にとって最大の制約条件 ・場所を変えると効率も変わる ・細切れ時間をどう活用するか? ・完璧主義をすて目的意識を明確にする
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論から言うと一般的なビジネスパーソンが読書術を学びたいという目的には適していないと思う. ただし,筆者の文筆には一般的ビジネス図書の方法論を遥かに超えるほどの秀逸と深みを感じさせた. 冒頭に自分が作者という職業についた理由,またあゆみきた教育履歴からの文化,経済,歴史,政治さらに宗教に関する深い洞見の原因がわかる本だった. 一般の方が佐藤優さんの熟読は3回論で,速読は良い本を出会わせるための効率的な手法で目的ではないということは実用的なノウハウになるかと… ただ,実際に紹介した図書が私のような歴史,政治に詳しくない人にとても難しく,熟読に大量の時間がかかる本で,もうすこし基礎知識をつけてから読もうと言い訳をつけて断念することにしました.
0投稿日: 2018.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の読書していかに知識を積み重ねていくかが書いてあり、読書に取り組む姿勢が変化するほどの刺激を受ける本であった。 佐藤優氏が 「基礎学力がないと知識が積み重ならない。」と言われるが、その言葉に毎回ハッとさせられる。 読みっぱなしはいけない。本当の知識にならないと痛感した。
0投稿日: 2018.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家・元外務省主任分析官、「知の怪物」とも呼ばれる佐藤優氏の読書術についてまとめた本。メインとなるのは第2章の「熟読の技法」。本の3回読み、線引き・書き込み、ノートへの転記とコメントなど、読書の理解を深め記憶に定着させるための技法を具体的に紹介している。また熟読する本をセレクトするための「超速読」、ポイントをすくい取る「速読」の技法や、これらの技法を下支えするための基礎体力としての教科書・参考書の活用についても言及しており、本書に書かれている内容をマスターすれば、さまざまなジャンルの本に対応できるだろう。 ただし、基本的には著者の経験ベースによる技法である部分が強く、必ずしも万人に受け入れられる方法ではないと思う。
0投稿日: 2018.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ多読速読について知りたくて読書。 読書の目的を明確にすることの重要性をリマインド。情報、知識を得るための読書と娯楽のための読書を明確に分離させる。 速読の目的は、熟読するべき本を探すための選別作業。 感想を残すること、まとめることで知識を定着化させる。 『クレヨンしんちゃん』などを真面目に評論している下りが面白い。 基本的に著者がしかめっ面で腕組んでいるような表紙の本は手に取らない(もろもろ理由あり)が、著者の本は初めて読ませてもらった。 率直な感想は、超人過ぎて真似できない。自分にとっては再現性は低いものが多数だったが、著者でも毎日4~6時間も読書へ当てているのがすごいと驚嘆した。 速読を応用して外国語学習を再開したい。 読書時間:約45分
2投稿日: 2018.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。なんだけどすごく楽しめた。この人のこの系統の本は、読んでいて仕事ができるようになりそうだ、とか頭が良くなりそうだと感じさせてくれる。教養エンタメだね(笑)。目的に応じて、本を読む速さは変わる。それは俺自身、やっていることだけど、目的に応じた速読、熟読の技法など、あれこれ参考になった。もっとも、この本出た当時に読んでるわけだから、その後の今に至る俺の読書に活かされている、ということかもしんないけど。
0投稿日: 2018.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法と世界情勢(ロシア情勢)を学べる書物。 正直、ロシアの話を蛇足と捉える人もいるかも? でも筆者が効率良く情報を集める過程の一例なので参考になります
0投稿日: 2018.06.01
