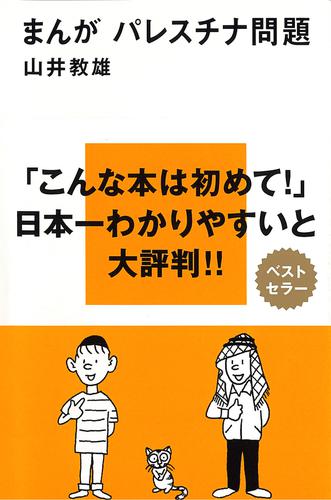
総合評価
(141件)| 43 | ||
| 54 | ||
| 26 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教のエホバ、キリスト教、イスラム教のアラーはみんな同一の神なんだ!!! って初めて知った!!!! ブッダは違うよね? いやーそうなんだ! そして、今まで戦争やらなんやらで問題になっているパレスチナ人とか、ユダヤ人とかそういうのの問題をまんがでわかりやすく解説してくれて、完全にはわからないけども、、、 えぇ、それは、、、あんまりだ。 って思ったよね。 ユダヤの人々やパレスチナの人々、、、、ちょっと、、、あんまりにも虐げられすぎでは、、、、 そして、同じ神なのに、信仰の仕方を統一しようとして、他宗教を制限するキリスト教。 すでに、そのやり方が神への冒涜になるんじゃ。 と、思ったり、パレスチナ人が入ってこないように壁を作ったイスラエルのくだりは、進撃の巨人を彷彿とさせたよね、、、、 日本。 はたまたアジア。 こちらは仏様の宗教、こちらにもそう言った宗教問題があるんだろうか? ビンラディンの名前が出てきたあたりで、だからこうなったのか!と思った。 このやりとり、どっかで終わらせないといけないんだろうけど、、、、腹の探り合い、嘘のつき合いで、ずーっときて今もまだ決着つかず。 これは、、、解決の糸口が見つからないのも、、、無理はないと思ってしまった、、、、、 #パレスチナ #戦争 #イスラエル #イスラム教 #ビンラディン #キリスト教 #ユダヤ人 #地理 #宗教 #元は同じ神 #なのになぜ #強引
0投稿日: 2025.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナもイスラエルもどっちもつらい。欧米諸国に翻弄されて、ややこしいことになってしまっている。歴史のあの時点まで戻れたらと思っている人は多くいるだろう。今からでもやれることはありそう。
0投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題というとても難しい内容を、子供でもわかるように、イラストと風刺漫画で解説した本です。旧約聖書から今日までの歴史の中で、パレスチナおよび中東がどのような変遷を辿ってきたのかが説明されています。 ニュースで見聞きする程度の知識しかない私には、歴史や政治的な背景など、とても勉強になりました。 今日のパレスチナ問題はより深まっており、その解決は、未だ遠いように思われます。 皆が本書のアリとニッシムのように、未来のために生きていける日が来る事を願うばかりです。
5投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題について知りたくて読みました。中東に関する歴史が豊富なイラストとともに丁寧に説明されていて良かったです。
1投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神はみな同一の神様であるというところから始まり、ザッと歴史的な出来事をおさらいしてくれた。2005年発刊の本で、当然続編がある。 先日「イスラエルについて知っておきたい30のこと」を読み終えたばかりだからか正直言ってさほど勉強にはならなかった。イスラエルの犯す戦争犯罪の非道さに心を痛め、怒りが噴き上がるというほどの内容ではなかったということ。 続編に期待する。必ず読む。
8投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログとるに足りない細部と映画『ノーアザーランド』見て、その理由を知りたいとおもって。旧約聖書の神の声で整地が決まったとあった時はついていけないかもしれない…ト思ったものの、その後は人間味のある話でよかった。 キリストが死刑になるきっかけを作ったのがユダヤ教の偉い人で、それゆえにキリスト教圏からユダヤ人が迫害されている、というのはなかなか理解しづらい(キリストもユダヤ人なので)のだけど、結局彼らは差別してもいい理由が欲しいだけでしょう。
1投稿日: 2025.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログガザ地区への攻撃がまったく止まない時期に、もらって読んだ。(「まんが」というほど漫画中心ではない。) 長い歴史の部分は、一度勉強したことのある人にはおさらい程度で、どちらかというと最後の数ページの内容がこの新書の核心だと思う。本当の平和的な共存を考える上で、難しいのはわかっているけど、とても大事なこと。 2005年に発行されたこの本の歴史的事実は2004年で止まっているので、20年経った今の人間としては、続編も気になっている。
1投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ紀元前にまで遡って今に続く紛争の根を解説。 常に「はざま」に位置付けられ、大国の思惑に晒され続けるパレスチナ。辿ってきたその歴史。
2投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初ユダヤ教、キリスト教、イスラムの宗教の始まり、宗教観の理解が難しくてわかりにくかったけど、戦後の史実に沿った流れは分かりやすかった。 巻末に中東の地図などがあるともっと理解しやすかったと思う。 各国の勝手な思惑、資本主義の歪みがこのパレスチナに寄せられているように思う。 自国の利益のためにパレスチナ問題を放棄しているのは日本もそうなんだろう。 国際司法機関が全く機能してないのと、シオニズム派の権力や賄賂に忖度して強く非難できない各国の政治家にがっかりする。 ファック民族至上主義。
1投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ聖書の時代から2000年代初頭まで、パレスチナが置かれた状況を概観出来る書籍。イスラエルとパレスチナの2人の少年が案内人となり、努めて客観的に書かれたことが分かる。 特に1960年代から中東の問題は複雑になるので、見返して整理するためにも役立つと思う。 続編もあるので読みたい。
1投稿日: 2024.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題の大まかな流れがわかってよかった。 ユダヤ人とアラブ人の少年からそれぞれの主張を聞ける構成になっており、どちらかに偏った見方になりにくくなるので良いと思った。 イラストは多いが文章はわかりにくく感じるところもあった。
0投稿日: 2024.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログバビロン捕囚中のユダヤ人は、奴隷として悲惨な生活を送っていたのかと思っていたけれど、この本では豊かな都市バビロンに連れて行かれたユダヤ人は繁栄していたと書かれている。他の本でも確認したかったけど、この本には参考文献リストがないのが残念だ。 https://worldheritagesite.xyz/contents/wailing-wall/ 嘆きの壁はソロモン王が建てた神殿の一部だと思っていたら、現存しているものはヘロデ王が建てた神殿だと書かれていたので調べてみると、ソロモン王が建てた神殿跡にヘロデ王が建てた神殿のことらしい。 ヘロデ王が建てた神殿は数年後に破壊されたが、壁だけが残っていて、その壁が嘆きの壁と呼ばれているとか。 反ユダヤ主義の始まりは十字軍だったのか。 イスラエルの歴史教育では、「無人のパレスチナの地にユダヤ人が入植した」と本当に教えているの? イスラエルにも問題はすごくたくさんあるけど、やはりパレスチナ独立は無理がある。パレスチナ人にゼロから国として必要とされる制度作りは無理だろう。
0投稿日: 2024.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
パレスチナの歴史を概観できた。争いの歴史的な理由は分かるが、解決策は分からない。本書は2005年に出版されたが、さらに問題が深まっている。 この本に登場するアリとニッシムみたいに融和できればいいのに。
0投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本のエピローグの部分を読んでいた時、少しだけ涙ぐみそうになりました。 ユダヤ人の少年とパレスチナ人の少年が、それぞれの歴史や宗教を辿る一冊。紀元前から9.11の影響についてまでの歴史がまとめられています。タイトルには「まんが」とありますが、まんがというよりかは挿絵くらいの理解の方が近いでしょうか。 少年二人の対話と、解説役のねこの説明を中心に進んでいき語り口は平易で読みやすかった。それに近現代の歴史だけでなく神話や紀元前、三大宗教の話もあり、パレスチナに関する情報も網羅されていて、これ一冊で2023年のイスラエルとガザの問題の根源にあるものはある程度理解できるのではないかと思います。 神話から9.11までたどっていくため、情報量が非常に多くかったので自分には一読ですべてを理解するのはちょっと難しかったです。ただ先に書いた通り平易で読みやすい語り口なので、なにかわからないことや、忘れたことがあれば気楽に読み返すことができるのもいいと思いました。 オスロ合意というのは、名前はなんとなく知っていたけどこの本を読んで、この時のパレスチナの人たちの希望を想像してしまいました。そして2024年5月現在のイスラエル・ガザの現状を見ていると、このオスロ合意のときにもっと何かできたことはなかったのか、と少し思ってしまう。 報復の連鎖と絶望で過激派に走るガザの若者たち。ホロコースト以降、自衛のため強硬になっていくイスラエルの右派たち。そしてつくられたヨルダン川西岸とガザの壁は、進撃の巨人よろしく、人間を壁の中に閉じ込め天井のない監獄を完成させてしまいました。 この本は、最後に二人の少年に関する意外な事実が明らかになり閉じられます。自分はこのフィクションの部分の希望と美しさと、日々流される現実のあまりの救いなさに苦しくなったのだと思います。 今回のイスラエルの侵攻が終わった時、世界各国は何を思い、イスラエルは何が変わるのか。過去にも、いま起こっていることにも何も関われないけど、そのことを注視することだけは忘れないでいたいと思います。
7投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年の7冊目。 パレスチナの問題についてテレビでやっててもよくわからなかったので、こちらで勉強。わかりやすかったですが、まんが、と言うか挿絵付きといったほうが適切かも。
0投稿日: 2024.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログp9 ペルシャ湾近くのウルに住んでいたユダヤ人の祖先は、BC19世紀頃カナンの地(いまのパレスチナ)を約束するヤハベの声を聞いたアブラハムに導かれてカナンへやってきた。 p12 BC17世紀、飢饉にみまわれてユダヤ人は、衛士ぶとに避難 p15 400年して、預言者モーゼが現れ、エジプトを脱出し、パレスチナに変える 60万人以上 海が2つにわれて、ユダヤ人だけ通した p23 BC1000年頃 イスラエル王国が成立 2代目王 ダビデ ソロモン(3代目)が死ぬと、国は分裂、バビロニアに滅ぼされ、捕虜としてバビロンにつれていかれる バビロン捕囚 バビロニアはペルシャに滅ぼされる。ユダヤ人はパレスチナに変えることを許される p49 パレスチナ ユダヤ総督によって治められていた。ユダヤ人は2度反乱を起こすが、鎮圧される。エルサレムにユダヤ神殿が残っている限り、反乱は収まらないと考えられたものだから、ヘロデ王が再建した神殿は完全に壊された。ユダヤ人はエルサレムに立入禁止となり、ユダヤ人のディアスポラ(離散)の始まり p69 十字軍の時代に、異教徒のユダヤ人は汚れだから浄化しようという反ユダヤ主義がヨーロッパに定着する p72 スペイン イスラム教徒、キリスト教徒共存していた 十字軍に影響されてカトリックのレコンキスタ(国土回復運動)がおこり1492年に最後のイスラム王国がカトリック王国に滅ぼされる グラナダにあるイスラム王国最後の御城 アルハンブラ宮殿 p92 1984 フランス ドレフェス事件 p98 エドモンロスチャイルド アラブの不在地主から、パレスチナで一番肥沃な土地、戦略的に重要な土地を買い上げた p115 英 パルフォア宣言 1917 ユダヤ人たちが戦費を賄ってくれるならパレスチナにユダヤ民民族のホームランドの建設を認めようといった 英 独立させる約束で、アラブ軍がロレンスと一緒にオスマン軍と戦う 大戦後のオスマン帝国はイギリスと、フランス、ロシアで山分けにする密約ができていた 1916 サイクス・ピコ協定 三枚舌 p119 スエズ運河や油田など、イギリスの利権をアラブ人から守るには、パレスチナにユダヤ人が大勢いたほうが都合がいいから、無制限の移民を認めた。 p125 マクドナルト白書 10年以内にパレスチナ国家を樹立する。ユダヤ人移民を制限する。ユダヤ人の土地購入を制限するというないよう。 アラブ人に有利な提案だったが、この提案をうけいれなかった p138 ロシアでもユダヤ人に対する集団暴行事件 ボグロム p141 1948/5/14 イスラエル建国 p145 イギリスは1948/5/15をもってパレスチナ問題を国連に丸投げ 国連はパレスチナを、ユダヤ国家、アラブ国家、それにえるされむ(国際管理地域)の3つの分割する案を採択 1947/11/29 国連案の分割案が通ると、アラブ人が起こって、パレスチナは内乱状態となる ユダヤ人の軍事組織はエルサレムの補給基地路がアラブ人に攻撃されないように、道沿いの村を攻撃して、破壊した。 ディールヤッシン村 パレスチナ難民のはじまり 1948 第一次中東戦争 アラブ連合国軍はイスラエルに負ける 1952/7 エジプトでナセルや差だとなどの自由将校団がクーデター 1956/10/29 第2次中東戦争(スエズ戦争) ナセルは戦争に負けたが国際世論を味方につけて、政治的には勝利 1967 第3次中東戦争 ナセル、イスラエルにたった6日間で完敗 イスラエルは領土を4倍に拡張 ヨルダン料だった東エルサレムも20年ぶりに取り返した エジプト、シリア、ヨルダンに頼っていてはパレスチナの領土は永久に戻ってこないと考え、パレスチナ人が主体となって、イスラエルと戦い、自分たちでパレスチナ国家を建設する以外にないと 1968/3/21 パレスチナゲリラはイスラエル軍を追い返した アラファト PLOの疑徴になる 1970/9/16 ヨルダンがPLOに宣戦布告 まけたPLOはレバノンに逃れた レバノンは1943 フランスから独立 中東にはめずらしく、キリスト教徒が多数派 1982/8 1.5万のパレスチナゲリラをつれてアラファトはチェニジアへ 第4次中東戦争 エジプトのサダト 日本は非友好国に分類され、1974 戦後始めてマイナス成長 1979/3/26 キャンプデービッド合意 カーター、ペギン、サダト エジプトがイスラエルの存在を認め、国交を持つ代わりに、イスラエルはシナイ半島を変換し、ガザ地区、ヨルダン川西岸のパレスチナ人に行政自治権を認める 1979 イランイスラム革命 パーレビ王朝が倒される 指導者はホメイニー イラク サダム・フセインが大統領になる 1980 イラク・イラン戦争 アメリカがイラクを支援 パレスチナのイスラエルの占領に対する抗議運動 インティファーダ p214 イランイラク戦争でフセインは戦争に買ったといいふらしたが、獲得領土や賠償金もない。借金で首がまわらず、復興も進まない。100万を超える兵隊の処遇にこまた そこでクエートに目をつけた。オスマントルコ時代、クェートはイラクの一部だった サダム・フセイン 国連決議に反して、パレスチナを20年以上専用し続けているイスラエルになんにも制裁を加えず、イラクがクェートを占領ばかりを避難するのは不公平。 1993/9/13 オスロ合意 PLOがイスラエルの生存権を認めて、テロを止める。イスラエルもPLOをパレスチナの代表と認める。調印後、ガザとエリコのパレスチナ人暫定自治を認め2年後から難民帰還の問題、エルサレムの貴族、入植地の処理などの問題を話し始める 1994/7/25 ヨルダンとイスラエルは和平協定 1995/11/4 和平反対派の男がピストルでラビンを撃った 1996 ペレスはパレスチナ過激派ハマスの指導者の一人を暗殺 ハマスは報復として通勤バスに次々と自爆テロ 和平反対派のネタニヤフが勝つ p238 2001/1 再開された和平交渉で、バラクが占領地の96%を変換すると提案したのに、強気になったアラファトはまたけってしまう。 2001/2 シャロン政権が生まれると、過激派のハマスやイスラム聖戦はイスラエルに対するテロをさらに活発化 2001/9/11 2003/6 ロードマップ ほとんどオスロ合意と同じ p250 ヨルダン川西岸の壁 2004/11/11 アラファト死亡
0投稿日: 2024.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ十字軍物語を読んでいたり、昨今のパレスチナ情勢の背景を知りたかったので手にとりました。 ひとつひとつの事件や出来事(歴史ではバビロン捕囚や十字軍、近年ではナチスのホロコースト、イライラ戦争や湾岸戦争などなど)などは目や耳にする機会はあっても、一つの流れとして把握できてなかったのでとても勉強になりました。 ユダヤ人という考え方が民族(人種的なもの)ではなく、宗教的なものだったというのは新鮮でした。また著者も語ってますが、民族という単位で括るのは危険な考え方な気がしました。本来、ヒトの心を救うはずの宗教が争いの原因になってしまうのは悲しいことだと思いました。
17投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログニュースを見ていても、ずっと理解できてなかったパレスチナ界隈の問題を、わかりやすく解説してくれたと思う。
0投稿日: 2024.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
家内が図書館から借りて来たのだが、漫画のストーリーではなく、活字でパレスチナやイスラエルの歴史を簡潔に聞き書かれており、それを補う形でイラストが、あるどという体裁の本である。メソポタミア文明から20世紀末までの歴史が簡潔にまとまっている。19世紀末から20世紀が詳しいのは多分現在に近いからであろう。いわゆるユダヤ↔︎パレスチナ問題が実はイギリスやフランスやアメリカ 播いた問題であることがよくわかる。2000年も国を持たなかったユダヤ民族に金銭を介して国を与ええた(パレスチナから土地を買った)結果、色々な軋轢が出て来た経緯がよくわかる一冊となっている。イスラエルにいる反パレスチナも少数でパレスチナにいる反ユダヤも少数であると聞くが、国際政治の狭間に両国は位置してしまっている。アメリカ、ロシア、イギリス、イスラエル、アラブ諸国の意向がせめぎ合うおしくらまんじゅうとしてのパレスチナ問題が、あることがよくわかった。ぎゅうぎゅう押されて餡が出ると問題が表出する。 分断するのではなく共生する緩衝地帯を設けるべきなのではないだろうか?
0投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログイスラエルやパレスチナ問題のニュースを観ていて、そもそもの問題は何なのか?というところを紀元前から現代のトピックスまでをザッとイラスト付きで簡潔に理解できる良書。読んで改めて問題の根深さを痛感できる。ただ、タイトルにあるいわゆる「マンガ」ではないけども。
0投稿日: 2024.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログいくら調べてもよくわからなかったことがすべて!涙 大国に翻弄される国々の現実と、本当にこれまで同じ事を繰り返していることがよくわかる。。 ところどころキーワードを押さえ直してくれたり 概念の違いを根本的に解説してくれるのありがたい
0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすい。地名や人物名と物事の結びつき、流れが理解できるように物語的に解説されてる。ただ、ユダヤ人的/パレスチナ人的視点を両方示すため、一部には便宜上架空のキャラクターである「アリ」と「ニッシム」の感情と目線がかなり濃く反映されてることを頭に入れながら読んだ方が良い。いずれの考え方をそのままアダプトするよりも、両方の視点を踏まえた上で(日本人の)読者である私がどうあるべきか考えた。
0投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近良く聞くパレスチナ問題というものについて、恥ずかしながら本当に全く分かっていなかったのですが… まんがならまだいけるか、と思い読み始めたところ、やはり絵が多いのとそれに伴って文量が少ないもんで、するっと読める。んですがだからといってボリュームが少ないなんてことはなく。 それこそ聖書の時代、紀元前から続くまさに歴史! というようなストーリーが展開されてまして、この問題、こんな根深いもんだったのかと。 また、まんがパレスチナ問題、というタイトルのまんがの部分。ストーリーについてもエピローグで意外な展開を見せてまして、そこに作者の思いのようなものも感じられ、そこもまた感慨深かった。 パレスチナ問題についてだけでなく、そもそも歴史ってジャンルはこんな面白かったのか、という気付きがあり、ちょっと学び直してみようかなぁなんて気になりました。 次は続〜の方も読んでみようかと思います。
0投稿日: 2023.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にわかりやすい。 漫画と思って軽く読み始めたけれど、一気に引き込まれました。 複雑なパレスチナ問題をここまで易しく、問題意識を持って読める本は他には存在しない。 そして、最後まで読めば分かることですが、この本は単に歴史を伝えるだけのものでは無いのです。 一番素晴らしいのは民族の問題を乗り越える方法は分離する事ではなく、共存して行くことだと強く訴えている点です。 おススメ致します。 素晴らしい本です。
1投稿日: 2023.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ4日間の戦闘休止… そんなさなか、ようやくちゃんと学ぼうとしている。 あるワイドショーで「ガザでの戦闘について自分には何ができると思うか」というアンケートをとったところ、48%が「歴史を学ぶ」と回答したという。過去に読んできた本でイスラエル・パレスチナ問題に触れたものはあったが、正直説明できる自信がない。 歴史すらしっかり学べていなかったことになる。 タイトルの「まんが」はコマで分けられたものではなく、各ページイラストを使って解説していくスタイル。 ユダヤ人のニッシムとパレスチナ人のアリ少年、エルサレムに住むネコがタイムトラベルをしながら解説役にまわり、時にはその時代の代表者も話に加わったりする。 この2人と1匹がとにかく優秀! 解説は簡潔明瞭でありながらきめ細やかであるため、出来事が順番にインプットされていく!「日本一わかりやすい」と帯に書いてあったけど、自分も忘れた時にはまた本書を読み返せば良いと思っている。 アリ君はちょっぴり激情型だけど、美辞麗句でごまかすよりもあれくらい赤裸々な方が逆に信用できる。「これが彼らの本音なのかな」って。 古代エジプト王朝が各地の部族を征服・統合してもファラオは彼らの部族神を抹殺しなかった。 しかしユダヤ人は自分たちの神(ヤハベ)以外を認めず、遂にはモーゼと共にエジプトを脱出した。ニッシム少年曰く、ユダヤ教には選民意識がありユダヤ人でなければヤハベの恩恵は受けられないとのこと。 上記を知るまでユダヤ人を悲劇的な民族の代表格みたいに思っていたけど、パレスチナ人も相当理不尽な目に遭っている。 第一次大戦が終わりイギリスがユダヤ人を無制限でパレスチナに移民させて以降、パレスチナ人はヨルダン川西岸やガザ地区で難民生活を強いられている。挙句の果てにはイスラエル入植地を守るという名目で、パレスチナ側に大きな壁まで造られてしまった。(流れがアメリカ先住民と入植者みたいで、どこでも似たようなことが起こるんだな…) 隣国同士の少年を解説役にあてた理由が、この辺でよく分かった。 「テロリストを作るのは貧困じゃないんだよ。絶望なんだ」 「(民族的憎しみが)まるで歴史的事実で、人の力ではどうにもならないもののように思われてる。だから、世界のどこかで民族紛争が起きると、[中略]民族を引き離すことしか考えない」 平和への鍵は各民族が共存できる世の中。 エジプトの多神教社会も他の神を受け入れ、中には習合させたりもした。スペインのイスラム王国である後ウマイヤ朝でも国民の60%は異教徒だったという。 風通しをよくすることで人も国も豊かになるというのに、何故わざわざ絶望させる方を選ぶのか。 鍵の形は分かっているのに誰も先へ進もうとはしない。 歴史はある程度学べたが、何故足踏みするのか疑問が後を引いている。ここは<続>に託そう。
53投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界史を習ったことがない、何も知らない27歳です。今世界で起こっている現状を少しでも知っていきたいと思い、この本を手に取りました。 非常にわかりやすいですが、なにせ何の知識もないので、まずは宗教というもの自体を学ぶところから今は始めています。『教養としての宗教入門』や『はじめての聖書物語』、『ホロコースト』、『物語 フランス革命』、『物語 エルサレムの歴史』、『世界史の中のパレスチナ問題』を同時に読み進めながらですが、まだまだ最初の方の章で止まっています。 十字軍やインディアンの歴史、ローマ帝国についてもさらに知りたくなりました。始まりは全て同じ宗教であったはずなのに、なぜこうも歪んでしまったのか。絵が可愛くて読みやすいですが、この裏にある沢山の残酷な歴史を思うと、これくらい可愛くないと心が潰れてしまいそうです。
3投稿日: 2023.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023年のイスラエル・パレスチナ間の問題について勉強・知識不足故に背景が全くわからず問題の理解が進まないため、少しずつでも知っていくためにまず、読みやすそうなこちらを手にしました。 まんがとタイトルにありますが、コマ割りの漫画ではなく挿絵がたくさんあるもので本以上漫画未満(絵が入っているという意味で)という感じです。 挿し絵があることでイメージしやすく、一通り流れを追って読むことができました。 また、語り手がパレスチナ人、ユダヤ人の少年と不思議な猫という複数の視点のものであるから偏りすぎずに読める点も良かったです。 長い今までの歴史があり、そして今なお続く因縁関係における出来事の一つが最近の報道なのだとわかりました。 ガザ地区への攻撃、子供の被害など胸が痛むもので何故こんなことを?と不思議で全く理解できませんでしたが、この本を読んで、大まかな経緯はわかりました(共感できる、納得できるという意味ではないです)。 対岸の火事のようにただ他人事のようにみていて火の粉がかからない位置から平和を祈るだけ、というのは何もしていないのと同等ではないか?とロシアのウクライナ侵攻についての小泉さんの本を読んで思い至りました。 ガザ地区への攻撃をやめてと言って止まるのなら、とっくに止まってますよね。 声を上げることが意味がないとは思いませんが、それを言うだけ、というのは安全地帯から憂いて平和を願う大人が行う行為としては力がない気がします。 イスラエル、パレスチナ間の和平交渉の場を設け、話し合いを進めていくことも大事なのは、この本で語られる過去の和平交渉の機会やノーベル賞受賞などからもわかりますが、話が進んでも、パレスチナ側に民主主義的視点から国を率いることができるリーダーの資質を持つ人材がいないこと、絶望が蔓延して諦めてしまっていることなどから、学問の教育だけでない政治の指導が必要なのではないかと思えました。 またイスラエル側の暴力に対して暴力で対応する姿勢について、それを止める倫理観の教育が必要なのではないかと思うのですが。信仰する宗教故に価値観倫理観は変え難いのでしょうか。 多様性尊重が叫ばれる世の中で、それに従わないとキャンセルカルチャーが蔓延してる西側諸国。 多様性尊重の気配がないイスラエル・パレスチナ問題、と思ってしまいました。 そもそも、、、最初の神話的な話って、作り話なのではと、無宗教の人は思うのではないでしょうか。 罪のない人を殺してまで尊重する価値がある神秘とは思えないです。 その根本的な聖書の話に突っ込むのは、またイスラエル・パレスチナ問題とは違うと思いますが、疑問に思わずにはいられませんでした。 自爆テロをする人に対して理解できませんでしたが、この本を読んでその行為に至ってしまう絶望の引き金、理由を知ることができました。 帰る家どころか国もない未来もない、と思って、自分の行動で天国に行け、家族にお金が入るから、敵は殺して良いと吹き込まれ続けたら、病んだ心はそれに傾いてしまうのだろう。とんでもなく悲しいことだ。 そんな人たちがいたなんて。 民族紛争解決のポイントは「憎しみや恨みを忘れて、テロと報復の連鎖を断ち切ること」と、「隔離や分離をしないで他民族が平和に融合した社会を目指すこと」(P.263) 確かに、と思う反面、自分の国で自分の周りで、と考えた時に果たして多くの外国人を受け入れられるかと思うと複雑である。日本の未来を考えて、受け入れなければ難しいと言うのはわかっていても、価値観倫理観は日本ベースであって欲しい。かといって、外国人の人たちそれぞれの母国の文化を貶したり無くしたい訳でもない。だけど、、日本では日本を優先して欲しいって言うのも、衝突になるのかな。 同じ人間だから、もっと大雑把に?ってなるのかな? でも、同じ人間でもバラバラの性格、考えを持つ人たちで協力して社会を作っていく中で協調性とか勤勉さとか、日本の考えは効果的と思うこともある。悪いところもあるけれど。色んな国の良いところ、を混ぜてがいいのかな。 でも国のトップはそういう悠長なことは考えずに、利益と外交で決めていくのだろう。 映画は政治的なものと常々思ってはいたが、映画が所々に引用されているのをみて改めて映画は政治を描いてきたのだなと何だか映画好きとして誇らしくなってしまった。
1投稿日: 2023.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題に関して無知である自分にとって、最初に読む本としてベストだった。 ただ、この本を読んでパレスチナ問題が何重も何重も何重も複雑であるため、一度読んで「理解した」と言える問題では無いと感じた。 2000年の間、迫害や離散を迫られたユダヤの人が、パレスチナに戻り、やられた事をやる側に回った(回らざるを得ない感情)のは複雑。 この本を読み、テレビとかで見る戦争の問題に対して、 暴力が起きている背景(宗教、環境、感情など)を踏まえないといけないと感じた。
1投稿日: 2023.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ少しだけアカデミックに現在進行形の時事問題の背景を理解したくなり、この本を購入しました。合わせて続編も手に入れ一気に読了。(「まんが」で手短に理解しようとしたのは大きな間違いでした。やはり難しい。) 中東の問題といえば、宗教絡み、石油絡み、そして第二次対戦後米国主導で国連決議の下に建国されたイスラエルという国が大きく絡んでいます。 今、テレビニュース等で報道されているガザのハマスとイスラエルとの争い。今のニュースだけを切り取ってみると、ガザのハマスがイスラエルの一般市民にロケット弾を撃ち込み、イスラエルが反撃し市民を巻き添えに!というもの。しかし、国連で、「とりあえず停戦しろ」といっているが、米国は拒否権を発動。イスラエルはハマスを根絶やしにすると息巻いている。一方、道徳的な観点から、、、、 このイスラエルvsハマスの対戦は今に始まったことではなく、十年以上前から同じような攻防戦が何度も何度も定期的に繰り返されているのですね。ガザの極貧生活もイスラエルの閉じ込めによりすでに何年も続いています。イスラエルもハマスからのロケット弾攻撃を何度も被っている。イスラム過激派の名前は色々と出てきて複雑ですね。ハマスの前にはPLOのアラファトが有名でした。他の地域ではタリバン、アルカイーダ、今勢力を伸ばしているのはイスラム国(IS)でしょうか。 根本的には何が問題なのか?今もニュース解説等で説明されていますが、もう一つ腹落ちしない。そこで、この本を読めば何らかの知識を得る事ができるかもしれない、と思い手にしました。(本屋さんには見当たらず、ブックオフにもなく、ネットで正規購入。しかし2週間ほどかかりました。なかなか手に入らないのですね。需要が多いのかもしれません。) しかし、この本を読んで全ては理解できませんでした。あまりにも多くの争いが出てきて、その前後関係や背景を理解しようとしても歴史のスパンが長く、関係する地域が広い。そして宗教が絡んできます。完全には理解し難い。多くの国々の関係性がその時代時代によって変わってきます。 解明しようとしても、ほとんど人類の歴史そのものになってしまう。ナイル文明、チグリスユーフラテス川のメソポタミア文明の頃から理解しないといけない。そして宗教的な背景が入ってきます。(十字軍から石油ショック、湾岸戦争、ニューヨークの9.11を全て根本から説明するのは難しいでしょう。) 元々、一神教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教。これらの宗教が崇めている「神」は同一なんですね。「元々ユダヤ教徒であったイエス・キリストはパレスチナ人」なのだということからも良くわかります。全て紀元前の話。イスラム教は紀元後6世紀ごろ出来上がります。そもそも同じ地域の人々。ノアの方舟のことは昔々どの宗教の皆さんにも共通の宗教的背景があったことのようです。モーゼの「十戒」あたりはユダヤ教になりますが。「三大宗教」の「聖地」が「エルサレム」にあるということも皆さんの出自が同じだということを象徴的に物語ります。 アレキサンダー大王、ギリシャ、エジプト、ローマ、オスマントルコ。それぞれの時代の移り変わりとともに宗教の広がり方や内容、他宗教との関係性も変わってきます。部族・民族の多様性も複雑。そして、欧米の列強が石油の利権を求めて様々な国々、民族をぐちゃぐちゃにして憎悪だけを残して去っていった。(未だに裏では操っていますが) 2000年に渡って争いの歴史がある。理解しようとしても一筋縄では行きません。 なので、いま現在の状況においてどちらが悪いとは軽はずみには言えません。難しい。まさしく人類の歴史そのもの。 ただ、現時点において言えることは(極めて個人的な見解ですが)、 ・長期にわたる独裁国家(独裁者)は国民に真の情報を開示せず、他国へ侵略することにより政権の存続を求めがちである。(現時点ではプーチン、習、金、ルカシェンコのように) ・宗教を根拠として出来上がった国家・集団は他宗教への攻撃を政治の目標としがちである。 ・傀儡政権による民主国家らしきものは中枢から腐敗し多くの弱者が生まれて、国民は絶望してしまう。 ・軍部を力の根源とする政権は力で国民をねじ伏せる。 ・極貧、絶望の中から難民やテロが生まれてくる。 ということぐらいでしょうか。 幸い私は比較的平和な時代の日本で生きてきました。この私の感覚が世界規模で見るとかなりズレているのかもしれませんが。 第2次大戦後、日本も様々な浮き沈みを経験してきましたが、かろうじて戦争に直接巻き込まれておりません。今の所は。 何とか日本を含め全世界の人々が安心して生きている世の中になってほしいと願うばかりです。
32投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログTwitterでたまたま見かけて気になったので読んでみたが、本当にわかりやすい。 パレスチナ地方を巡る争いの大元は旧約聖書の時代まで遡り、やがて列強による利権争いが絡んでくる。もとは同じ神を信じた人たちがなぜこんなことになってしまうのか。しっかりとその歴史を知って考えたい。そして、私たちの周りでも人種や民族、宗教の違いなどから諍いが起こらないように学んでいきたい。 それにしても、いつの時代もどこの国でも「神」と「金」というのは使い方によっては厄介なものにもなるんだなあ。
2投稿日: 2023.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと分かった 「世界中に民族は約3000、言語は約5000あると言われています。でも国の数は200しかありません。どう考えても、各民族の自決、分離独立は不可能です」
2投稿日: 2023.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあることは複雑だ。 なぜならこの問題は”簡単に”することで取りこぼしてしまう要素が多いから。 それを複雑性を保ったままで、あくまで書き口を可能な限り簡易に、そして風刺画も交えながら、なぜこの問題が生まれ、世界がどう対応してきたのかを書いている。 この1冊だけですべてを理解できるわけでもないことはわかっているけど、いまのこの状況で無知ではいられない、でも何から学べばいいのかわからないという人にはうってつけだと思う。 センセーショナルでわかりやすさだけに特化した解像度の低い本やネット記事を読むよりも明らかに正確だ。 読んでよかったと思う
3投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画 とあるがイラスト多めなだけ 二人の少年と猫が会話しながら歴史をわかりやすく語る。って昔の学習漫画によくあった形式。 猫がかなりメインで語るのだが文末や文章の途中でニャとかニョとかむりやり入ってて最初その部分が名詞なのかと混乱した。 文末だけにしてほしかった。
2投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログまったく知識がない自分が読んでも非常にわかりやすかった。 日本人にはあまり馴染みがない(?)宗教問題。 まさか始まりが紀元前とは… この本から始めて、もう少しパレスチナ問題を学んでいこうと思った。
3投稿日: 2023.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段は漫画をほぼ読まないのだが(鬼滅の刃など話題になった物は読んだ)、漫画とパレスチナ問題という、一見相容れないタイトルに惹かれ読んでみた。漫画と言うが2人の主人公+猫の会話を中心に挿絵を織り交ぜながら、パレスチナ問題の根本原因となる二つの宗教の成り立ちに始まる。モーセの出エジプトを機に世界を彷徨い続け(ディアスポラ=離散)、時にナチスドイツのホロコートに代表される様な悲惨な目に遭うユダヤ人。彼等はどこの土地にいてもその他民族の嫉みや恨みの対象となり迫害され続ける。そんな彼等を救えるのは最早自分たち自身しかない。辿り着く先それはユダヤ回帰シオニズムによるパレスチナでの建国。一方パレスチナには元々土地に住んでいたパレスチナ人がおり、勝手に入ってきて建国されてはたまらない。そこへ第一次世界大戦への流れとなる。当時パレスチナを支配していたのは弱体化したオスマン・トルコ帝国だが、イギリスはアラブとはアラブ独立国家を約束する「フサイン-マクマホン書簡」、フランスやロシアとはオスマン帝国両度分割を約束する「サイクス・ピコ協定」、そしてユダヤ人からの資金援助の代償としてユダヤ人のパレスチナ移住を約束する「バルフォア宣言」と見事なまでの三枚舌外交を演じる。直接的には現代のパレスチナ問題へと繋がる、それぞれへの根拠ときっかけを作ってしまった。結局大国フランスとの領土分割だけが守られる事に。 その後も第一次〜第四次中東戦争では、エジプトやイスラエル、ヨルダン、レバノン、そしてアラファト率いるパレスチナ解放戦線(PLO)など周辺諸国を巻き込んだ紛争地域がすっかり板についてしまう。ガザ地区に押し込められた民衆の間でもイスラエルに対する放棄(インティファーダ)として投石・火炎瓶が投げられるシーンはニュースや報道番組で何度となく目にした。一時期活発化した和平交渉もイスラエルがタカ派のネタニヤフである現在、問題解決に向かうかはわからない。聖域完全奪取に向け、軍事力に任せたイスラエルの威圧は暫く続くだろう。 本書のラストでは会話をしてきた主人公の2人がこの先のパレスチナの未来を共に手を取る事を約束するエンディングへ向かう。然しながらキリスト教含む様々な宗教と政治の思惑、民族の交差点にあるパレスチナという土地柄が複雑な問題の解決を難しいものにしている事は間違いない。千年以上前から続く民族個々の事情がそう簡単に解決するとも思えない。 ここでも最終的には平和で自由な暮らしを求める民衆個々人の努力、お互いの尊重、隣人を愛する気持ち、他者への献身など各宗教が持ち合わせる本来の教義や思想に答えを求めるのが1番ではないかと感じる。 責任はイギリスは勿論、アメリカにもロシアにも日本にもある。イラク、イランもそうだ。いい加減、他人事のように眺めて、自国の利益になる時だけ上手く問題を利用しようとするのを止めて、世界が解決に向けて手を取り合う必要があると強く感じる。
0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ複雑な歴史がある中東・ヨーロッパ。 中東にいる以上、触りだけでも知っておかなくてはと思い読んだ本作。 非常にわかりやすく解説してくれています。 日本の歴史とはまた別次元の、非常に各大陸の思惑に振り回されているパレスチナ問題。 本作だけ理解するには無理があるが、全体像は掴めます。 大変勉強になりました。 全体像を掴んだ今、中東で働く日本人としてどのような動きが必要か、そしてどのようにこの問題を捉えるかが自分に与えられた課題だと思ってます。 本作で学んだことを、日頃の振る舞い、言動に落としこんでいきたいものです。
0投稿日: 2022.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ中東の歴史や宗教についてわかりやすく、読みやすく、まとめられています。 なんとなく、ボンヤリとニュースで聞いていた内容が輪郭を持って浮かびあがる話しとなってきます。 宗教や土地の為に戦争をするなんて、と思いますが、そうせざるを得ない事情や感情、あるいは政治的思惑があるのだと改めて思い知らされた。
4投稿日: 2021.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦ナチスドイツホロコースト後60万人のユダヤ人が敵意に満ちた400万アラブの土地のど真ん中に1948年イスラエル建国。アメリカ寄り国連に反発しアラブ5か国による中東戦争勃発もなんとかイスラエル勝利し100万人近いパレスチナ人が難民となり今日へ。
0投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログイラストと文章で、わかりやすく パレスチナ問題を解説してる。 若干、端折ってると感じる部分もあった。 あと、数冊読めば理解出来そう。
0投稿日: 2021.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログまんがというより、イラストが多用された絵本あるいは紙芝居的な作りですが、複雑かつ長い歴史的背景を持つパレスチナ問題の経緯をざっと概観理解あるいは理解を今一度整理するのに最適。 「民族」という人間が作り出した概念を乗り越えた共存の可能性を訴える著者の想いが込められたエピローグが良いですね…。
0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後のエピローグで涙ぐんでしまいました。 イスラエルとパレスチナの歴史をマンガで学ぶことができます。 筆者のあとがきで、「民族主義が争いの原因になっている」ということが語られますが、まさにイスラエルとパレスチナの問題は民族主義の悪い部分をなぞるような歴史を歩んでいると思いました。 その悪い部分とは「視点の固定化」だと思います。「私たち」と「あなたたち」という分け方をして、「私たち」側の視点で物事を捉えて判断してしまうことです。 日常生活でもこの捉え方や考え方が人間関係において大きな誤解を生みがちだと感じています。 理想主義に過ぎるかもしれないけれども、確かに民族に根差した捉え方を辞めることが、人には必要かもしれないと考えさせられるエピローグでした。 とはいえ、現在進行形で苦難に直面しているパレスチナの方にどうしても同情的にはなってしまう読後感はありました。(イスラエルも相当に悲惨な背景がありますが…)。言行不一致ではあると思いますが、少額の寄付やパレスチナ製品の購入で貢献できたらと思います。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログまんがというよりイラスト。 ユダヤ人ってだれ?イスラエルってどこ?エルサレムってなに?あやふやな知識を大きな流れにのせて分かりやすく掴める一冊。 宗教的にきわどいことは全て猫に発言させていくスタイル。世界情勢の見方が変わる。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早く読めば良かった。ずっと読みたいなと思いながら、積読したままになっていた。 パレスチナ問題の起源だけでなく、歴史上の出来事を時系列で示しながら、その過程や変容をわかりやすく解説してくれている。 イラストも豊富で、とても読みやすい。子ども向けかと思っていたが、ある程度の知識があったほうが理解が深まり、勉強になると思う。 特に、現代史までカバーしてくれている点、人種と民族の違いや社会主義と共産主義の違いなど、わかりやすく説明されている点、民族問題を解決するための糸口が示されている点がとても良かった。 続編も是非手にとってみたい。
2投稿日: 2020.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のなかで気が向いた時に開催される、”普段読まない分野を読んでみよう”シリーズ。前知識なく選んだけど非常に分かりやすくまとまっていて良書。 パレスチナ問題といいながらも歴史的には英国や米国がかなり絡んでおり(近年はそれらの権力争いそのもの)、にもかかわらず報道ではこれらが常識又は不要として意図的に省かれたりする。 中東ニュースは勧善懲悪な報道になりやすいけど、どんな情報が省かれたのか、”何を伝えたくないのか”を注意して見るようになった。 イギリスの3枚舌外交やアメリカの手のひら返しには「このクソがっ」となるよ、そりゃ。
0投稿日: 2020.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログヨルダン、イスラエルに行ってきました。 イスラエルの経験はかなり衝撃で、アラブ地域の問題に無頓着すぎた私は、まずは、、ということでこの本を。(実は旅行前に買っていたが、読めていなかった。。。) 行ったからこそ何となく地理感がつかめて、身近に感じられて、聞いたことある言葉が出てきて、読み進められたと思う。 こんな大人になるまで知らないなんて、ほんと無知で恥ずかしいが、だからこそ、やっぱり旅は、世界を平和にする。 人を無関心や他人事から、関心、知ってる人がいる、知ってる土地であるから大事にしたい、と言う気持ちに変えさせてくれる。と、改めて。実際に行くって大事。 パレスチナ問題について知る、とっかかり本。
0投稿日: 2020.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人から「パレスチナ問題」の関心が薄れている気がする……。そんな状況でも、この一冊がロングセラーとして書店の棚に陳列され 続けていることは、希望と言えるかもしれない。エピローグで主人公の少年二人(パレスチナ人・ユダヤ人)が手を取り合うシーンに心を動かされた。
0投稿日: 2020.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログNetflixのメシア1話を観て、 中東問題無知だったため購入 漫画かと思ったらまんがではない笑 知識0の私には結構難しかった。 少しだけなんとなーくわかった程度なのでもう少し勉強してからまた読みたい。
0投稿日: 2020.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀末までは1/3、迫害され続けたユダヤ人はトルコ帝国で一応の居場所を得た、アラブ人の攻撃には無干渉。ナポレオン戦争以降の国家意識形成、トルコ帝国没落・崩壊でユダヤ人は本国を持ちたいという“シオニスト”運動を起こし(当時は領土概念が希薄)新たな迫害の口実となった…シオニズム運動へのロスチャイルド家の金銭的支援、イギリスの3枚舌外交(1915年のフセイン-マクマホン協定、16年のサイクス-ピコ協定、17年のバルフォア宣言)、1922年からのイギリスによる委任統治→ナチスによるユダヤ人迫害を国際社会は放置…「ユダヤ人はたび重なる差別やポグロム(無説明だがロシア語。大虐殺19~20C)に反撃しないできた…あげくナチスの600万ホロコーストだった。イスラエルは最後の安住地、ここから逃げる場所はない、から反撃することにした」1947年の国連でのパレスチナ分割案承認、1948年の委任統治の放棄とイスラエル建国、米ソのイスラエル即時承認、相次ぐ中東戦争、テロの横行と報復…1981年オシラク原発爆撃。本書には書いていないが、「売るほど」エネルギー源があるイラクが敢えて原子力発電所を持つ意図は(売ったフランスもどうかと思うが)核開発としか考えられない。核燃料が入れられる直前を狙った爆撃は「自衛的行動」と言っておかしくない。イラク側は、イスラエルが発表するまで、「誰がしたか」もわからなかった。 オスマン・トルコ帝国においては、婚姻・葬儀・相続などの問題はイスラム教徒はもちろん導師に、ユダヤ人は彼らのラビに、キリスト教徒は彼らの宗教裁判所にそれぞれ委ねられていた。現代のイスラエル居住の非ユダヤ人にも各集団の裁定が認められている(らしい)。前半で十字軍の野蛮や中南米でのコレキスタドールを語る文脈で傍観者の猫がp83「宗教って伝染病みたいなものだニャ(ユダヤ教は布教しません)」「本当に宗教って人間に必要ニャのか?」と問いかけるが、その考えを推し進めると「ユダヤ人でなくなれば殺されなかったのに」になる…
0投稿日: 2020.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ井上ひさしさんの名言 「むずかしいことをやさしく、 やさしいことをふかく、 ふかいことをおもしろく、 おもしろいことをまじめに、 まじめなことをゆかいに」 を 「まんが」という道具を 使って 見事に この「パレスチナ問題」を 読み解いた一冊です。 これは ぜひ若い人に届けたい一冊です。
0投稿日: 2019.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前の本です。過去の歴史の評価は時代によって変わりますが、十四年位ではまだまだ変わらないはず。しかしながら激動の世界情勢の中、パレスチナの問題は悪化しているとしか言いようがないでしょう。 この本は何千年か前からの成り立ちから分かりやすく書かれていて非常に有意義です。旧約聖書の時代から、キリストが現れ、ユダヤ人に対する迫害が始まり、時代は進みホロコーストへ。 そして国を作ったユダヤ人は、過去に民族離散で苦難の道のりで寛容さを持つのではなく、未来を脅かすものには武力で徹底的に叩き潰す方向に進みました。 殺戮を繰り広げるイスラエルは、その財力と影響力で世界の国々の口を塞ぎます。 繰り返される民族的、宗教的ないがみ合いや殺し合い。2014年にはイスラエルの爆撃にてガザ地区のパレスチナ人たちは2000人亡くなりました。痛ましい事です。
0投稿日: 2019.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ中東問題の根源はパレスチナ問題にある。 というのが本当に正しい認識かどうかはだんだんわからなくなってきた今日の中東情勢なのだが、もう一度、頭を整理すべく読んでみた。 旧約聖書のノアやモーゼの話などから始まり(それらが史実かどうかは別として、物語としての真実ではある)、十字軍、シオニズム、イスラエルの建国と中東戦争、インティファーダ、オスロ合意、アラファト死まで、2004年くらいまでの4000年の流れをとてもわかりやすく説明してある。 4000年の歴史といっても、パレスチナが4000年間、中東の問題の中心であったわけでもない。 今日の状況にいたる流れは、長めにとらえても19世紀からの200年くらいの歴史であり、もっと直接的に影響しているのは、第1次大戦後の100年くらいの歴史なのだ。 もちろん、3つの宗教にとって重要な聖地エルサレムの問題はあるものの、宗教的な対立をパレスチナ問題の原因に求めてはいけないと思った。 ヨーロッパの植民地政策や反ユダヤ主義の矛盾が、このパレスチナ問題として現れ、それが宗教や文化の違いによる対立というかたちで表現されているのだ。 そして、パレスチナ問題が、改善されているわけでもなく、より一層状況は悪くなっているにもかかわらず、中東問題のなかでは、比較的マイナーな問題になってしまうほど、他の問題が大きくなっている現状。 ここからみると、パレスチナ問題は、「アラブの大義」ではあっても、今、起きている中東問題の直接の原因はまた違うところにあるのだ。 というのは、わたしの理解であって、この本がそんなことを直接主張しているわけではない。 シンプルにとてもわかりやすいパレスチナ問題の解説だと思う。
0投稿日: 2019.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在までつながる一連の問題の流れが分かりやすくまとめられている。「アラブ・ゲリラだろうが、サダム・フセインだろうが、アメリカと敵対している国と戦う奴なら、アメリカは見境なく支援して、ガンガン武器を与える。そいつらがアメリカにもらった武器で、次はアメリカに戦いを挑んでくる…。 アフガン戦争でも、イラン・イラク戦争でもいつも同じパターンじゃないか。こんな単純なことを、どうしてアメリカは学習しないで、性懲りもなく繰り返すんだろう。」(p204)
0投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ユダヤ教の成立からアラファトの死まで、世界史の中からパレスチナ問題に絡む所を取捨選択、分かりやすく並べている。 ユダヤ系とパレスチナ人の少年に語らせる設定上、このエピローグは必要だったとは思うが、ちょっと唐突。だけど素敵な未来図だ。
0投稿日: 2018.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ三大宗教が始まった昔々から、現代の中東問題まで、分かりやすく流れに沿って解説してある。 また、ユダヤ人とパレスチナ人の男の子が常に登場し、どちらの立場からも発言させることで公平性を保たせている。
0投稿日: 2018.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読み終わった途端、トランブ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認定し、大使館もイスラエルへ移す、というニュースが出て、あまりのシンクロぶりにびっくり。本書のおかげでこのニュースの重大性がすごくよく理解できた。 ちなみに、「まんが」と銘打っているが、イラストレベルのものに文章がミックスされたもので、通常のコマ割りされたマンガを期待するとがっかりします。
0投稿日: 2017.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログまんが パレスチナ問題 山井教雄 2005年1月20日第1刷発行 2017年9月24日読了 まんがとあるけど挿絵を入れたわりと普通の読みもの。 旧約聖書のノアの箱船の話からスタート。 ノアの息子、長男セムの子孫がユダヤ人、アラブ人、パレスチナ人となる。そこからユダヤ教、キリスト教、イスラム教の説明があり、十字軍、フランス革命を経て、第一次世界大戦、第二次世界大戦、イスラエル建国。 そして中東戦争。9.11へと歴史を追いながら優しく解説した本。 概要を掴むには良いかと思います。 ローマ帝国と戦争し、負けてからユダヤ人のディアスポラが始まる。その後2000年もの間ユダヤ人は迫害され自分たちの国のない放浪が続く訳だけど、第一次世界大戦のバルフォア宣言によりパレスチナにユダヤ国民のホームランド建設を認めようと約束。しかし結局は反故された事が遠因となり、今のパレスチナ問題の原因になってる。この辺はざっくりと掴めて分かりやすかったです。 かつて迫害され、虐待され続けてきたユダヤ人がイスラエルを建国して自国のためとはいえ同じ暴力を持ってイスラム教徒やアラブ人を攻撃していることは悲しい現実ですね。 でもそれには宗教観の違い、民族意識、政治が絡みとても複雑になってしまってる。お互い信じる神は同じで聖地も同じなのに、信じる宗教観が違う。それは経済よりもっと難しい問題となって今も解決されることなく悲しい現実を生み出している。 お互いの多様性を認める社会は出来ないのか。違う宗教観があっても良いのではないか。でも今度は民族意識、人種問題が立ちはだかる。それがミャンマーのロヒンギャ問題。 日本は恵まれている。一つの国に一つの(ほぼ同じの)民族。宗教観だけは多様かもしれないけれどバランスが取れているとも思う。 引き続き関連本を読んで色んな知識を身につけたい。 ざっくりすぎるので、一番初めに読むよりもう少し詳しい本を読んでからおさらい位の感覚で読むと良いかもです。
0投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ夫が読め読めと言うので・・・随分前の本ですが読んでみました。 ちなみに、「まんが」と書いてあるけど全くまんが本ではありません。挿絵入りの、普通の本でした。 絵の分だけ文字数は少ないですけどね。 パレスチナの複雑な歴史をわかりやすく簡潔に書かれた本です。 ユダヤ教の始まりから、2000年続いた民族差別の歴史、報復攻撃を行ってしまう悪循環の歴史がよくわかりました。 ちょっと思ったのは、ユダヤ教の頑なさ。 イスラムは多神教でユダヤ教に歩み寄りがあったのに、ユダヤ教は一神教で偶像礼拝も認めず選民意識も強く、このままじゃあ共存は難しいのかなと感じてしまいました。 著者が語っていますが、経済が原因の戦争ならばお金がなくなれば終わるけれど、宗教や民族のアイデンティティに関わる戦争だと戦争が正当化されて終わりがない、と。 民族主義に拘るかぎりテロと戦争は無くならないと。 民族の壁を越えて、平和に共存できる方法を、当事者同士だけでなく世界が考えなければいけない時代なんだと実感しました。 ただ、無知な私はこの本を読んで著者の考えに引っ張られてる感じがするから、別の本も何冊か読まないと、自分の考え自体がよくわかってないかも・・・ 勉強しなきゃ。
0投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと知りたかった「なぜユダヤ人は流浪の民になったのか?」の答えがはじめて分かった。 繰り返し大国から侵略され続けてきたのは災難だが、何より戒律を絶対に守ろうとする頑固さが原因のようだ。その2000年前から現代までの過程がよく理解できてスッキリした。 とはいえ、現代のイスラエルと先進国との関係に関する説明が物足りなかった。 これからは、現在起こっている問題とアメリカとの関係を中心に調べていきたいと思う。
0投稿日: 2017.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログアラブ人とユダヤ人の2人の少年、ネコ、歴史上の重要人物の対話を通して、「ノアの方舟」から刊行時点(2006年1月)までの複雑なパレスチナ問題の経緯を大変わかりやすく解説している。
0投稿日: 2017.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教、キリスト教、イスラム教と元の神は同一。 ただしユダヤ教、キリスト教はヤハベ(エホバ)であるのに対し、イスラム教はアラー。 最初にユダヤ教、律法の複雑さに疑問を感じキリスト教ができ、 その後モハメッドがイスラム教を説いた。 そのこともあり各聖典は、ユダヤ教では旧約聖書、キリスト教では旧約聖書・新訳聖書、 イスラム教では旧約聖書・新訳聖書・コーランとなっている。 ときは流れ、現代。 遥か昔、ユダヤ教の人たちはパレスチナがあるところは、 ユダヤ教の人たちのために神が与えた土地となっていて、自分たちの土地だと思っている。 ある時にユダヤ教の人たちがパレスチナに戻ってきてイスラエルを建国した。 当然もともと住んでいたパレスチナの人たちもいて、問題になる。 今もなおこの問題は続いている。 (以下抜粋。○:完全抜粋、●:簡略抜粋) ○旧約聖書の律法がどんどん複雑になって、神がなんでそんな決まりを与えたのかまでわからなくなる。律法学者が力をもって偉そうに振る舞う。そんな風潮をおかしいと思ったイエスは、「そんなに律法ばかりにこだわらずに、もっと神を信じなさい。神の愛を信じなさい」と説いたんだ。(P.41) ●ユダヤ人:ユダヤ教人、あるいは母親がユダヤ人 アラブ人:アラビア語を母国語とする人 パレスチナ人:パレスチナに住んでいる、 あるいはイスラエル建国前にパレスチナにすんでいた、あるいは父親がパレスチナ人(P.132) ○PLOってのは、1964年に色々なパレスチナ・ゲリラ組織や、 労働組合なんかをまとめてできた組織ニャンだ。 だから、穏健派から過激派までいろんなグループがある。(P.173) ○アラブ・ゲリラだろうが、サダム・フセインだろうが、アメリカと敵対している国と戦う奴なら、 アメリカは見境なく支援して、ガンガン武器を与える。 そいつらがアメリカにもらった武器で、次はアメリカに戦いを挑んでくる・・・・・・。(P.204)
0投稿日: 2016.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ民族も言語も国境も文化もすべてが同一の日本人にとって、パレスチナ問題はそれらが入り組んでいて、理解するには容易ではない。 本書はまんが(風刺画や挿絵)をふんだんに用いて、ざくっと4000年の歴史を解説する。個々の事象をしっかり理解するには物足りないが、全体像を捉えるにはとても分かりやすい。
0投稿日: 2016.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ中近東のややこしそうな問題を少しでも理解したいと思い、読んでみた。 イギリスがやっぱり悪かったような・・(笑)。 ISがのさばりだして、余りこちらのニュースは聞こえてこなくなったけど、依然としてこちらの問題も未解決なんだろうと思う。 ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も実は同じ神を信仰していて、モーゼの十戒を規範としているはずなのに・・。 「汝殺すなかれ」・・・全く守られていない。 さぞや神は嘆いていることだろう。 宗教戦争かと思っていると、案外経済闘争だったりすることもある。何かいい解決案はないものだろうか?
0投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごくわかりやすい! 旧約聖書から、現在のイスラムゲリラ戦激化に至る流れが1冊で簡潔にわかる良書。
0投稿日: 2016.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ人とアラブ人、イスラエルと周辺国家の軋轢や戦争をイラストと話し言葉で分かりやすく解説する。 知識ゼロで中東の歴史や内情をざっくり知るにはうってつけ。 常に迫害され続けたユダヤ人の心情や、突然に住処を奪われたパレスチナ人の言い分も理解できた。 エピローグで述べるように、民族としてのアイデンティティがいかに流動的で、それに固執した時に暴走を助長するかも考えさせられた。
0投稿日: 2015.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
必要最小限の事項がイラストとともにまとめられている良書。 もともと同じ神から派生したユダヤ教、キリスト教、イスラム教の間で、十字軍だったり、ジハードだったり、エルサレムを取り合ったりしてることは、実際にその「神」が現れたら何というのか聞いてみたいところだ。 ナチスのユダヤ人迫害の反省もあって、イスラエルが作られた、とか、一次大戦後の列強による中東分断が中東問題の根源である(アラビアのロレンスによりアラブが統一されていた可能性もあった)、とか知らないことも多かった。 ある意味、石油がこれらの国を狂わせたのかもしれないが、昔の大文明国が他国にかき回され、骨抜きにされた感はある。これらの国をまとめる思想が、イスラム教なのかどうかはわからないが、同じ「神」の教えならそれほど大きな違いはないはずなので、共存できる素地はもっているはずだと思うのだが・・・。 イスラエル建国により漂流するパレスチナ人やもともと漂流していたクルド人、内戦で余儀なく漂流しているシリア人も、漂流先で幸せな人生が送れれば、それはそれで良かったと思えるようにしてほしい。民族は所詮過去の記憶にすぎず、こだわりすぎては本末転倒になる気がする。イスラエルをはじめ、受け入れる側にも当然それは言える。(パレスチナ人からすれば、イスラエルの方が勝手に入り込んできて壁をつくった訳ではあるが・・・)。テロに対する戦争よりも、移民、難民が幸福な人生を送ることの方が重要だし、結局それがテロを撲滅する第一歩となるはずだから。
0投稿日: 2015.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと部族宗教であったユダヤ教から、キリスト教・イスラム教という世界宗教が生まれた。宗教人口はキリスト教が22.54億人(33.4%)でイスラム教が15億人(22.2%)、ユダヤ教が1509万人(0.2%)となっている(百科事典『ブリタニカ』年鑑2009年版)。米調査機関ピュー・リサーチ・センターによれば、2070年にはイスラム教徒とキリスト教徒がほぼ同数になり、2100年になるとイスラム教徒が最大勢力になると予測している(日本経済新聞 2015-04-06)。 http://sessendo.blogspot.jp/2015/04/blog-post_25.html
0投稿日: 2015.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ神話の時代からアラファトの死去に至るまでのパレスチナを巡る歴史を、平易な言葉で分かりやすく教えてくれる入門書的な一冊。 まんが、とありますが、実際にはイラストや地図を多用した解説本です。 パレスチナ問題についてはニュースなどで頻繁に情報が入ってくるものの、そもそも紛争の原因やこれまでの経緯については曖昧な理解にとどまっていました。 本書はそのあたりを包括的にさらさらっと理解するには最適です。 もっと深く知りたいという方は、この本を皮切りにより専門的な書籍へと進むのがよいかと思います。 どうでもいいことですが、進行役となるユダヤとアラブの少年にはちゃんと名前がついているのに、マスコット的に頻繁に登場する猫には名前がなく、単なる「ねこ」どまりなのが個人的にはツボでした。
0投稿日: 2014.12.08読後感は、民族問題に対して何ができるか、自問自答せざるをえなかった
本書は、パレスチナ問題を考える入門書ですが、読後感は、民族問題に対して私には何が出きるか自問自答せざるを得ないものでした。 本書が生まれる背景となったのは、著者の山井教雄氏が、1991年、ユーゴスラビアで行われた国際漫画会議に出席したときの体験です。 当時、ユーゴスラビアは、人口2300万人、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字を持つ1つの国家でした。 しかし、国内では内戦が勃発し、アジテーターに各民族意識が掻き立てられた結果、自分はユーゴスラビア人だ、という人は5%しかいないとのことでした。 これは、1984年にユーゴスラビアのサラエボで冬季オリンピックが開催されてからわずか7年後のことです。 このとき山井教雄氏は次の3つのことを考えたとのことです。 『①民族および民族意識はその時の政治の都合により、人工的に作られるものだ。 ②民族は命をかけて戦い、護るほどの確固たる概念でもないし、崇高なものでもない。 ③今後民族主義は国際的に広がり、人類にとってはガンになるだろう。私は反民族主義の漫画を描き続け、この流れに抵抗しよう』 このような背景があり生まれたのが本書です。 本書の最後に、南アフリカの黒人解放運動のリーダーで後の大統領、ネルソン・マンデラ氏の行動を振り返る形で、民族紛争解決のポイントが2つあげられています。 ・憎しみや恨みを忘れて、テロと報復の連鎖を断ち切ること ・隔離や分離をしないで多民族が平和に融合した世界を目指すこと この2つはあまりにも当たり前のことですが、しかし、パレスチナ問題の歴史1つをとっても、この当たり前なことがどれほど困難なことかと考えさせられてしまいます。 世界は、例えばEUのよう既存の国家の枠組みを越えた政治、経済の統合の動きがある一方、パレスチナに限らず、ロシア、中国、中東でも見られるように民族独立の動きもあります。 特に後者の動きは、先のスコットランドの独立の住民投票のような平和的な手順で進むのはまれで、テロや内戦などで、時の国家や国際社会と武力衝突が多く発生しています。 平和とは対極の事態をもたらす民族問題に、私には何が出きるのか、正直、容易には答えを見つけられません。 ただ、ひとつ実感としてあるのは、民族問題を遠い世界の出来事ととらえず、身近な問題としてとらえることによってでしか、自分なりの答えとやるべきことは見つけられないだろう、という思いです。
0投稿日: 2014.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近でもガザ地区の無差別攻撃が行われて、多くの人が死んだ。その割にはニュースでの取り扱われ方が少ないように感じる。 パレスチナ問題を知るためには、その歴史を知る必要があるが、そのためには手っ取り早い本だと思う。 ユダヤ教、キリスト教、イスラム教それぞれの聖地でもあるイェルサレムの地図を見ると、本来ここは各宗教が同居する象徴的な地になっていたのかもしれないと思う。また、それらの宗教が一神教の世界宗教として同根であることも、あらためて分かる。 「まんが」と書いてあるけれど、まんがではないからね。
0投稿日: 2014.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ言うだけあってすごい分かり易い。やはり物事の導入に漫画は有用。 浅くザックリと把握するのにもってこい。 漫画にするからにはまずこんな感じでザックリした知識だけでもつけさせて欲しい。
0投稿日: 2014.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画というか、挿絵の多い新書。長い歴史物語を一冊にまとめる以上、やむを得ないことではあるけど、ページ毎に登場人物が目まぐるしく入れ替わるから、なかなかついていくのも大変。でも、巻末の年表だけ見ても無味乾燥だから、やっぱり漫画付きってのはそれなりの意味があったってこと。ざっと学ぶのには適している新書でした。
0投稿日: 2014.01.22分かりにくいということがよく分かりました
現在イスラエル-パレスチナ間で起きていることの背景には歴史上のあまりにも多くのことが関係しているということが分かります。このことを分かりやすく書いてありとても良い勉強になりました。西欧のある国に住んでいた時、ユダヤ人の友人が何人かおりました。私にとって、肌の白い彼らは他の白人と同じに見えました。普通の白人からは、私をマイノリティーとして見下したり積極的には関わろうとしないそぶりを感じことがありましたが、ユダヤ人の友人たちは私たちに親しみを持って接してくれました。彼らが他の普通(キリスト教徒)の白人とは距離をとっていることを不思議に感じていましたが、この本を読んで彼らの背後から感じた何か説明のできない空気の背景が分かったような気がしました。
2投稿日: 2013.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題を思い出すのによかった。 30分もあれば読めるか? パレスチナに同情してしまいます。 関係ないけど、ロスチャイルドの陰謀などは都市伝説何でしょうか?
0投稿日: 2013.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログざっくりと理解するには丁度よかったです。 三枚舌のイギリスが悪いかと思ったけど、イギリスがいなくてもいずれはあの土地にイスラエルは建国されただろうし、この土地と宗教戦争はユダヤ教とイスラム教が存在するかぎり何百年経っても解決しないとも思えてきた。他国が干渉せず両国で納得いく形で解決するしかない。 もっと理解するにはイスラム教、ユダヤ教のことを知ったほうがいいし、きっと知るとまた別の見方ができると思う。
0投稿日: 2013.11.12分かりにくい問題を分かりやすく解説した良書
世界的な問題で、大きな問題が起こる度に幾度となくニュースとなってきた“パレスチナ問題”。 大きくざっくり言えば、パレスチナという土地を巡るユダヤ人とイスラエル人の争いのことですが、各国の利害関係、各宗教の相容れない信仰問題、各民族の勢力関係等、あまりに様々な要素が絡まったのがこの問題。 紀元前のユダヤ教成立にまで遡り、その後のキリスト教、イスラム教の成立から、2004年のアラファト議長の死まで、西洋の歴史と並行して常に関わり続けた問題を、ユダヤ人とイスラエル人の少年ふたりを案内役にイラストでわかりやすく解説。 どうも争点が整理しきれないこの問題を、通史的に解説することで全体像をかなりわかりやすく掴むことができます。 結局誰が悪いという単純なことでは済まないのが人間の歴史の複雑なところ。今が常に歴史の途中の“今”であることを考えるための、俯瞰する知識と知恵が学べます。(スタッフY)
5投稿日: 2013.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ去年、イスラエルに行った。 パレスチナ自治区、ヨルダン川西岸地区にも行った。 パレスチナ人居住区の上に住む、ゴミや糞尿を投げ入れてくるユダヤ人入植者。 パレスチナ人からユダヤ人を“守る”ために常にマシンガンみたいな大きい銃を携えて闊歩するイスラエル兵。 イスラエルとパレスチナ自治区を隔てる高い壁と、まるで国境のような厳重なイミグレーション。 雇ったパレスチナ人ガイドに最後に言われた言葉、「見に来てくれてありがとう」 あの日見た光景、聞いた言葉にある壮大な背景を、分かりやすく説明してくれる一冊でした。 みんな過去なんて忘れてしまえればいいのにね。 そしたら誰も恨まずに済むのに。
0投稿日: 2013.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界史を結構細かく勉強していたので、何となく背景や固有名詞は知っていたのだけれど、そもそもの「ユダヤ」の根源とか本質とかを自分が理解できていなくて、そんな状態で読むと「で、それは遡ると根本の意図や理由はなんなの?」みたいなことを節々に感じてしまって消化不良だった。
0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ中東は、歴史も地理も宗教も、 色んな要素を絡めないといけないので、 どっから手をつけていいのやら状態でからっきし弱い私ですが かーなりスッキリとまとめられていました。(しかも図つきなのでわかりやすい) ぼやぼやっとしていた中東の様子が 多少なりとも輪郭づけられたような。 とにかく全部が芋づる式につながっていて 芋の原点がなんと旧約聖書まで遡ってるって・・・ 奥が深すぎるぜパレスチナVSイスラエル・・・
0投稿日: 2013.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題をわかりやすく纏めた本。 2004年の本なのでその後の10年もきちんと勉強したいと思いました。 『テロリストを作るのは貧困じゃないんだよ。絶望なんだ。将来に希望があれば貧困だって耐えられるし人を愛することだってできるんだ』
0投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ複雑な中東問題を歴史からわかりやすく、簡潔に解説した書。小学校高学年くらいから読めるだろう。私が中学生の頃から既に中東問題は地理の授業でもわかりにくいものだった。当時の先生が「中東戦争を理解しようと思えば、発端までさかのぼらないとわからない。『今』だけ見ていても理解できないよ」とおっしゃっていた。確かにそうだ。当時この本があればもう少し中東問題も理解しやすかったかも。 未だ、中東では世界各国の利害や思惑も加わり、戦火が絶えない。当事国以上に関連列国の思惑に振り回され、そこで生活する市井の人々は常に貧困と生命の危機を感じながら過ごしているのだろう。一朝一夕にはいかないのだろうが、利害を超えてなんとかならないものなのか。
3投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログアブラハム、モーゼからアラファトの死までの大きな歴史、周辺史を交えて流れがつかめる。特に、第4次中東戦争以降の理解が断片的になっていたので役立った。 善悪、正邪に踏み込んだ部分が鵜呑みするには危険であったり、オーソライズされているのかちょっと首をひねる数値もあるように思えるが、あとがきの「反民族主義の漫画」が示すように意欲作。
0投稿日: 2013.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログイスラエルの建国やそれに伴う宗教について書かれた本。世界史の中で宗教に関係することを説明しつつ、今のパレスチナ問題について述べている。普通の解説書と違って、話し手がいるという点で、ある立場をとりやすくなっている。宗教間の対立という物を経験したことがない私でも、その立場にたって歴史の出来事考えることができた。
0投稿日: 2013.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書みたいでちょっと読むの大変だったけど、すごくまとまっていて勉強になった。宗教は人を幸せにするために作られたはずなのに、戦争するなんて悲しいね。
3投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵と一緒にすごくわかりやすく解説されていた。 テロリストをつくるのは貧困じゃない絶望なんだ。という言葉が印象に残った。
0投稿日: 2013.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログイラストで読み解く、パレスチナのいままで ユダヤ人とアラブ人の少年2人とネコを登場人物に、神話からイスラエルの壁建設まで。 立場の異なる両者がユダヤ人の歴史を中心のパレスチナ地区の動乱を解説する。 「正史」にはまだまだ遠いパレスチナの歴史。一方から見た正義が他方の悪事なんてザラにある地域で、この2人は相手の意見に物申しながらも喧嘩になる事なく進めていく(そりゃそうか)。 元来ユダヤ教徒とイスラム教徒は中東地域で善き隣人として共存していた国がいくつもあった。 それが、イスラエルの建国もだが、それ以上にソ連やアメリカの介入によって、互いに憎み合うようになってしまった事が悔しい。 確かに、各国は自国の利益のために動くだろうが、それは他国を情勢不安に陥れる程の影響力を行使すべきではないと思う。(こんな事を言っても、私も日本が働いている悪事を全て把握している訳ではないし、今の自分の生活もその犠牲の上に成り立っているものだとは思うけど。) 最後にまとめられたように、ほんの些細なきっかけで人生は大きく分かれてしまう。 本当はこの場に居るのは私ではなく、他の誰かだったのかもしれない。 今の幸せは当然ではなく、偶然の賜物だ。 同じもので固まる方が安心するかもしれない。 でも、実際には全てが同じもの同士で集まるのはほぼ不可能だし、自己と他者は必ず違う。 そして何より、違う事が世界を広げる。
0投稿日: 2013.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は東京外大出身。 すごく読みやすい!わかりやすい! 中学生でも読めるかも。 こんな難しい問題を、こんなわかりやすく書けるなんてすごい! ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の説明から始まり、 紀元前の旧約聖書の話から、21世紀の9.11事件に至るまでの歴史。 高校の世界史で習ったことがたくさん出てきます すごく根深くて複雑で理不尽なことだらけなんやね。 宗教だけでなく、政治や経済も絡んでて。 利権を独り占めしたい各国の王や大統領たちと、 理不尽に虐げられ希望を見出せず、ゲリラやテロに向かう民。 やっぱ争いって、自分のことしか考えないから起こるんだと思った。 自分が一番かわいいよね。まず守りたいのは自分や家族やんね。 パレスチナ問題全然知らんかったけど、もっと知りたくなったょ。
0投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治学関連の講義で中東問題が扱われたことから、参考のため入手。 所謂、中東問題のコアの部分が、この書のタイトルの「パレスチナ問題」である。 この問題の発端は第2次世界大戦にあると思っていた。 政治的にはそうなのかもしれないが、ユダヤとパレスチナ、あるいはアラブというキーワードで考えた時、それは歴史的にはさらに前に、宗教的な観点も含めて理解されなければならない。 そのように考えると、この書の内容は宗教やそれぞれの民族がたどってきた歴史を端的に、それでいてわかりやすく述べている。 また、タイトルに「まんが」とあるが、所謂「劇画調」ではなく、ひとつひとつの説明を文章とイラストでまとめているような形であり、これなら中学生でも頑張れば理解できるのではないかと思われる。 自分だけの理解、というのは人に説明する義務がないから、どうとでもなるし、どうでもいいことだともいえる。しかし、人に説明したり議論したりする際には、自分の持つ知見を相手に理解させる必要がある。 そういう点でも、この書は理解しやすく説明するのに便利にだと思われる。 ただ、現在も解決されていないこの問題をどのようにしたら解決すべきかという点については、理想的な話に留まり、具体的ではないかと思う。問題の淵源を知ると、解決も容易ではないことがわかる故に、この点は読後よくよく考えさせられる。
0投稿日: 2012.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ今月発生したハマスとイスラエルの衝突をきっかけに11年ぶりに再読。まんがというよりもイラストでパレスチナ問題を解説した本。ありがちなパターンの本ですが、シャロン・イスラエル首相までの似顔絵、地図や図版も豊富で、視覚に訴えたわかりやすい構成になっています。 本書では、少なくとも以下の疑問に対する説明がなされています。 -なぜ、ユダヤ人は今のパレスチナの土地にこだわるのか? -なぜ、ユダヤ人は嫌われているのか?また、ユダヤ人差別のきっかけはなにか? -同じ神を持つにも関わらず、なぜキリスト教はローマの国教になったのに、ユダヤ教は広まらなかったのか? -なぜ、ユダヤ人は2000年近くも迫害と放浪の生活を送ったのか? -なぜ、アラブ人とユダヤ人はパレスチナを巡って争うようになったのか? -そもそも、ユダヤ人、アラブ人、パレスチナ人とは、どんな民族なのか? 本書がカバーするのはBC13世紀の脱エジプトから2004年のアラファトPLO議長の死去まで。したがい、「アラブの春」以降のパレスチナ情勢については続編に譲ることになります。 それでも、本書はパレスチナ問題の入門書としては最適。自分の断片的な知識がページを追うごとに有機的にまとめられてゆく感覚は快感です。
0投稿日: 2012.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本人にとって、歴史的なかかわり合いが浅く、あまりよく知られていないパレスチナの問題をマンガでわかりやすく説明した書籍。世界三大宗教がの起源から始まり、現代の中東問題にまで続くストーリーを、重要な歴史的人物を登場させつつ、それぞれの立場で物を言わせている書き方が非常にわかりやすかった。結論として、誰が良いとか悪いとか言えるものではないが、和平への近道には我々日本人のようなあまり関係性のない世界中の第三者への理解も必要であるのではないかとこの本を読んで感じた。
0投稿日: 2012.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後まで理解できず… どっちかの考えに、偏ってしまう感じはある。 パレスチナ問題…もっと分かりやすく説明されているものがあるか、探し中…
2投稿日: 2012.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
パレスチナ問題の歴史を簡単に学べる本。(なはず・・・・) ちょいちょい入るユダヤ人とパレスチナ人の子どもの会話が面白い。歴史って面白い。
0投稿日: 2012.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログパレスチナ問題は宗教とが交錯していて、戦争、軍事組織、指導者、国連等が入り混じって一つの問題ができているので概観が少し難しい。 これは漫画というよりかはイラストが理解を助けてくれる本なので勘違いしないように。専門的でなく初級者向けだが、これだけ知ってれば十分だろうというくらいのボリュームはあるので、パレスチナ問題初心者向けの本として推薦できる。
0投稿日: 2011.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログまんがと言うほどマンガはではなく、挿し絵と図解が入っていて、会話形式をとっているイメージ。 そのためか、文章が読みにくく、一気に読めないので内容が入ってきづらい。
0投稿日: 2011.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
パレスチナの歴史を漫画で説明した本。イスラエル側、パレスチナ側の視点があって面白かった。ただ、問題は根深く、いつ解決できるのか。
0投稿日: 2011.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に分かりやすかった。 この先もパレスティナ問題は勉強していきたいと 思っているが、 基本知識の辞書として今後も活用していくことになると思う。
0投稿日: 2011.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログいい本でした。小難しく説明してくれる本はいっぱいあるんでしょうけど、これくらい簡単に説明してくれた方が、よっぽど為になる気がします。なかなか作家専業になられてない方の説明より、よっぽど「わかりやすい」し、「そうだったのか」です。
0投稿日: 2011.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2011.09.21読了)(2011.09.18購入) 旧約聖書の時代から2004年までをイラストを主とし、文字を従としてパレスチナ問題に関する話題をわかりやすくまとめてくれた本です。 「まんが」となっていますが、ストーリーのある物語となっているわけではありません。 パレスチナ問題について既にわかっている方には、頭の整理や復習に、初心者には、入門書として利用できると思います。 さらに詳しく勉強したい人のための、参考文献を挙げてくれるとよかったけれど、残念ながら、ついていませんでした。 目次は以下の通りです。(いつ頃のことかを記入しておきます) ユダヤ教(BC19世紀~) キリスト教(BC4世紀~) イスラム教(6世紀~) 十字軍(1096年~) フランス革命(1789年~) 第1次世界大戦(1914年~) 第2次世界大戦とホロコースト(1933年~) イスラエル建国(1945年~) 第1次、第2次中東戦争(1948年~) 第3次中東戦争とPLO(1967年~) 第4次中東戦争とサダト(1973年~) キャンプ・デービッド合意(1978年~) インティファーダ(1987年~) 湾岸戦争(1990年~) オスロ合意(1993年~) 第2インティファーダ(2000年~) 9.11(2001年~) エピローグ(2004年~) ●モーゼ:十戒(19頁) 1、神はひとつである 2、偶像を崇拝してはいけない 3、神の名をみだりに唱えてはいけない 4、安息日を守れ 5、父母を敬愛せよ 6、人を殺すな 7、姦淫するな 8、盗むな 9、偽証するな 10、貪欲になるな ●ローマのキリスト教(51頁) キリスト教がローマに入ってきて、ユダヤ教とは違う宗教だって示すために、盛んにユダヤ教を攻撃した。その時、「ユダヤ人は、せっかくこの世にあらわれた救世主、イエス・キリストを殺しちゃった罪人なんだ」って宣伝したんだ。本当はローマ人が殺したのにね。 ●イスラム教徒の5つの義務(64頁) 1、信仰告白 2、礼拝 3、喜捨 4、断食 5、メッカ巡礼 ●反ユダヤ主義(69頁) 十字軍の時代に、異教徒のユダヤ人は汚れだから浄化しようという「反ユダヤ主義」がヨーロッパに定着する。 ユダヤ人たちは、ひと目でユダヤ人とわかる服を着せられ、色々な職業から閉め出され、ゲットーに隔離された。ユダヤ人差別がキリスト教社会で制度化されちゃったんだ。 ●2003年6月の和平会談(248頁) パレスチナ自治政府首相アッバス、イスラエル首相シャロン、アメリカ大統領ブッシュ、3人でヨルダンのアカバで会談を開いた。 ロードマップの構想 第1段階(2003年5月末まで) パレスチナ側はイスラエルの生存権を認め、テロを停止する。イスラエル側は、パレスチナを主権国と認め、ガザ地区やヨルダン川西岸から軍を撤収。入植活動を凍結する。 第2段階(2003年6月から12月まで) パレスチナが憲法を制定、暫定的な国境線を持つ独立国家を樹立する。 第3段階(2004年から2005年) エルサレムの主権などの問題を解決して、関係を正常化する。 ●アラファト(254頁) 2004年11月11日、アラファトがパリの病院で死んだ。12日にラマラの議長府に遺体が帰ってくると、何万人ものパレスチナ人が広場に集まって、最後のお別れをした。 アラファトは権力を一人占めにして、後継者を育てなかった。お金も一人占めにした。世界からの援助金はたくさんあったはずなのに、彼は学校も病院も作ってくれなかった。 (2011年9月23日・記)
0投稿日: 2011.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログまんがでよめるが、著者が若干左的な思想であることが気になった。 もちろん、平和で争いがないことが理想だが、これもまた実現は難しい。 その意味では他書を並列して読んだ方がよいかもしれない。
0投稿日: 2011.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすい。 漫画としてよめる。 今中東で起こっている聖戦の歴史や起源にさかのぼって解説してくれていて、タイムラインに沿って説明してくれてるので読みやすい。
0投稿日: 2011.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ聖地エルサレムを巡る、いわゆるパレスチナ問題を非常にわかりやすく書いた一冊。まんがというタイトルだが、正確には教科書にイラストを入れて漫画っぽくした感じ。パレスチナ人とユダヤ人の子供を語り手にすることで両方の利害や立場をわかりやすくし、中立の立場のねこのキャラクターが補足する。内容は非常に濃くてユダヤ人の誕生から現代まで網羅している。特に地図がわかりやすい。筆者のパレスチナ問題を理解してもらいたいという気持ちが伝わる良書。
0投稿日: 2011.04.11
