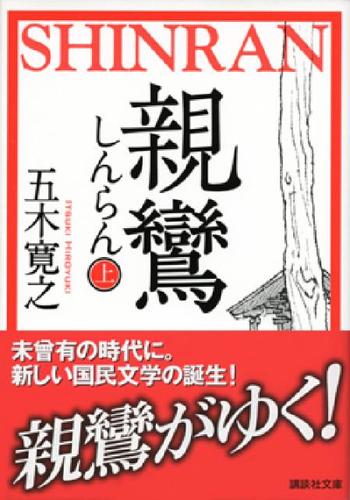
総合評価
(90件)| 23 | ||
| 38 | ||
| 16 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之が親鸞を書き始めた頃、年取るとこんな世界(宗教)に行くのかと冷ややかだったけど、読み始めると流石、大菩薩峠みたいな面白いさ。
14投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
浄土真宗を開いた親鸞上人を描いた大河小説。上人が仏教と向き合う苦悩だけではなく、歴史小説、ミステリー小説、冒険小説などあらゆる要素が詰まっていて、読み進むのに倦むことはない。
1投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2010/5/28) 学生時代、歴史小説を読み漁った。 巨人の星(梶原一騎)、心技体(二子山勝治)に続いて人生に影響を与えた宮本武蔵を皮切りに、吉川英治の長編は全部読んだ。新書太閤記、私本太平記、新平家物語、三国志、新水滸伝、そして親鸞。 ついでに司馬遼太郎の坂之上の雲、竜馬が行く、国取物語、山岡荘八の徳川家康。 話がそれた。そう。学生時代以来の「親鸞」を五木寛之で読んだ。 ヒーローのいる小説と比べ、親鸞は理解しにくかった覚えがある。俗っぽいお坊さん、程度の認識だったかもしれない。「善人尚もて往生をとぐいわんや悪人をや」の意味も十分理解できなかった。 今回の五木親鸞はまず、楽しい。冒険活劇のように、まだ親鸞と名乗る前の11歳の忠範少年を活躍させる。史実ではないのだろうが、暴れ牛が目に浮かぶようだ。続いて比叡山で修行する29歳の範宴。俗から離れた僧のあり方に疑問を感じ、市中に身を置き始める。女性と出会い、、、ってところで上巻は終わり。 楽しく読ませてくれる。 下が楽しみ。
4投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ平安から鎌倉に変わる動乱期に、日野忠範として生を受ける。 御白河上皇の助けもあり、叡山に入山し、範宴として修行を積む。 そんな中、法然に出会う。叡山の修行は研究に似ていると思った。 黒面法師になぜ狙われるのか不明。ようやく山を降りる決意をする。
4投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「この世に生きることは苦しい」 苦しい上で、どう生きるか。 どう生きれば喜びを感じれるのか。 よろこびを探して、見つけていくということが「人生」というものなのかなと思った。 この本は親鸞の幼少期(忠範8歳)〜範宴29歳の時のお話。
0投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ浄土真宗 宗祖の親鸞聖人のことを知りたくて図書館で借りてきたが、さすがに五木寛之が描くとグイグイ引き込まれる面白さがある。 半面話を作りすぎのような気もするが、読み易いのでゆるす!
1投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白く読みました。はじめは、時代小説なのに文体は普通で違和感を感じていましたが、最後にはすっかりなれてのめり込みました。下巻が楽しみです。
1投稿日: 2021.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都に転勤となって,六角堂を訪れる機会があり,親鸞を再認識しました。で,手に取ったのが五木寛之のこの本です。さらっと読んでしまいました。下巻に期待です。
1投稿日: 2021.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと積読だった本を読みはじめた。さすがに五木寛之の本は面白い。平安末期から鎌倉時代にかけて多くの宗派が乱立するわけですが、今ひとつよくわからなかった。 この本は、そこいらへんのことを整理してくれる。
1投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之の本は初めて読んだ。歎異抄を読もうと思ったが、その前に親鸞とは何かを読んでおこうと思って。凄い本。怒涛の展開で一気に読んだ。平安から鎌倉という舞台でしかも仏教の話だから、退屈な展開かと思ったがとても引き込まれて読み進めた。親鸞の仏教に対する真摯さは分かるな。どんな分野でも同じような悩みはあるはずだ。突き詰めると狂っちゃうような。次巻以降も楽しみ。しかし人の命が軽い時代なんだな。
2投稿日: 2020.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人はみな平等である。身分や職業の高下などない。この世に生きることは苦しい。心と体が痛む者を助けなければならぬ。よりよく生きる道をさがそう。そしてよろこびをもって生きよう。それ以外に何がある?いってみろ」河原者法螺房弁才の言葉に藩宴は・・・。
1投稿日: 2020.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ1173年4月1日は親鸞上人の誕生日、と歴史カレンダーにあり、日本版宗教革命というべき人の事跡を読むにはこの古典か、と思い手にとった本。 9歳で出家した親鸞は、比叡山で20年修行を積みます。浄土教の先輩の法然も天台僧であったらしく、2人とも、比叡山で総合教学と各種の行を学んだ結果、念仏を選んだ訳です。特に親鸞については、底辺の人々の生き様に触れ、驚き、後の悪人正機の悟りに繋がっていく伏線が描かれています。 このような宗教者の小説にありがちなのですけど、宗教者としての足跡を追いかけようとするあまり、歴史小説としての考証が弱くなることがあります。宗教者の奇蹟と悟りなら、その教団が出す本を読めば良いのですから。 ということで、この上巻で一旦置くことにしました。自分の中でもう少し熟してから、むた考えようと思います。
1投稿日: 2020.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
発刊された時から読みたくて入手したものの、ながく手をつけずに寝かせていた一冊。 今が読むタイミングだったのだろう。 不思議とそんな気がする。 感想は下巻を読み終えてからとし、上巻では評価のみ。 説明 内容紹介 馬糞の辻で行われる競べ牛を見に行った幼き日の親鸞。怪牛に突き殺されそうになった彼は、浄寛と名乗る河原の聖に助けられる。それ以後、彼はツブテの弥七や法螺房弁才などの河原者たちの暮らしに惹かれていく。「わたしには『放埒の血』が流れているのか?」その畏れを秘めながら、少年は比叡山へ向かう。 内容(「BOOK」データベースより) 馬糞の辻で行われる競べ牛を見に行った幼き日の親鸞。怪牛に突き殺されそうになった彼は、浄寛と名乗る河原の聖に助けられる。それ以後、彼はツブテの弥七や法螺房弁才などの河原者たちの暮らしに惹かれていく。「わたしには『放埒の血』が流れているのか?」その畏れを秘めながら、少年は比叡山へ向かう。 著者について 五木 寛之 1932年福岡県生まれ。朝鮮半島より引き揚げたのち、早稲田大学露文科に学ぶ。PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、76年『青春の門』(筑豊篇ほか)で吉川英治文学賞を受賞。81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学んだが、のち文壇に復帰。2002年にはそれまでの執筆活動に対して菊池寛賞を、英語版『TARIKI』が2002年度ブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門を、04年には仏教伝道文化賞を、09年にはNHK放送文化賞を受賞する。2010年に刊行された本書は第64回毎日出版文化賞を受賞し、ベストセラーとなった。代表作に『戒厳令の夜』、『風の王国』、『風に吹かれて』、『百寺巡礼』(日本版 全十巻)など。小説のほか、音楽、美術、歴史、仏教など多岐にわたる活動が注目されている。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 五木/寛之 1932年福岡県生まれ。朝鮮半島より引き揚げたのち、早稲田大学露文科に学ぶ。PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て、’66年『さらばモスクワ愚連隊』で小説現代新人賞、’67年『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞。’76年『青春の門』(筑豊篇ほか)で吉川英治文学賞を受賞。’81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学んだが、のち文壇に復帰。2002年にはそれまでの執筆活動に対して菊池寛賞を、英語版『TARIKI』が2002年度ブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門を、’04年には仏教伝道文化賞を、’09年にはNHK放送文化賞を受賞する。2010年に刊行された「親鸞」は第64回毎日出版文化賞を受賞し、ベストセラーとなった。小説のほか、音楽、美術、歴史、仏教など多岐にわたる活動が注目されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019年11月27日読了。 ★P331 ・忠範→範宴 ・河原坊浄寛、ツブテの弥七、法螺坊弁才「蛸法師」 ・後白河法皇 ・伏見平八郎(六波羅王子) ・慈円、音覚法印、良禅 ⚫️「浄土をひたすら恋う気持ちが分からなければ、 念仏は分からない。頭で浄土を思い描いているかぎ り、法然房のもとに集う人びとの心は理解できないだ ろう。そのこころは、心ではなく情(こころ)なの だ。浄土は情土なのだ。唯識で心はとけるが、 情(こころ)はときあかすことはできぬ。 」 放埓(ほうらつ)… 傀儡(くぐつ)… 隠遁(いんとん)… ⚫️草にも木にも、土くれにも仏性が宿るという伝教大師・ 最澄さまの教えからすれば、世間の弱き者たちに慈悲の 光をさずけるのは当然であろう。その当然のことを、 われらがながく忘れて、朝家、権門、富者にのみ奉仕し てきたのじゃ。そこに法然房のつけ入るすきがあった。 ⚫️法然 「知恵を捨てて愚者になれ、そしてただひたすら念仏せ よ」 ⚫️<人は目にうつすすべてを見るのではない>と、 範宴は考えている。外界のさまざまな現象のなかで、 人は自分が期待するものを選んで見ているのだ。 ⚫️聖徳太子は、家族をもち俗世間に生きつつ真の仏法を この国に築かれたではないか。 末法の世とは、本当の仏法がすたれて、形式だけが残り すっかり変わってしまった時代をいう。だからこそい ま、釈尊の教えの第一歩に戻って出なおすことが必要 だ。仏法二千年の垢を洗いおとして仏陀の初心に戻るの だ。すなわち人はみな平等である。身分や職業の高下な どない。この世に生きることは苦しい。心と体が痛むも のを助けなければならぬ。 よりよく生きる道をさがそう。そしてよろこびをもって 生きよう。
1投稿日: 2019.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログフィクションの世界 山口晃画伯の挿画集と並行して読み進めた。 挿画とその作成過程が手助けになる。 親鸞と言う存在、浄土真宗の租が少しだけ分かる気がした。 その他はエンターテイメントだった全6巻。
1投稿日: 2019.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ詳細は、あとりえ「パ・そ・ぼ」の本棚とノート もご覧ください。 → http://pasobo2010.blog.fc2.com/blog-entry-1777.html 東京新聞に連載された 「親鸞」、「親鸞 激動篇」。 2013年7月1日から、新聞小説「親鸞 完結篇」五木 寛之、画/山口 晃 が東京新聞に連載。 その挿絵が面白い! と聞いて 興味がでてきました。 せっかくだから、最初から読んでみようかな! 読んでみると、さすが 面白くてグイグイ読み進める。 次は下巻です。 『 五木寛之氏の朝刊連載小説「親鸞 完結篇」が七月一日から、本紙に登場します。 第一部にあたる「親鸞」(二〇〇八年九月一日〜〇九年八月三十一日)は京都に生まれ、法然に師事し、弾圧を受けて越後に流された若き日の親鸞像に迫りました。 続く「激動篇」(一一年一月一日〜同年十二月十一日)は、赦免(しゃめん)の後、関東に招かれた壮年期の親鸞が、布教しながら思索を深める様子を描きました。 今回の「完結篇」で、親鸞は京都に帰還します。「教行信証(きょうぎょうしんしょう)」の完成など多くの業績を残し、九十歳で没するまでの晩年を、八十歳を迎えた著者が円熟の筆致でつづる予定です。 挿絵は、第一部、第二部と同じく山口晃さんが担当します。ご期待ください。 』 2013/7/4 予約 7/10 借りて読み始める。7/14 読み終わる。 内容と著者は 内容 : 馬糞の辻で行われる競べ牛を見に行った幼き日の親鸞。 怪牛に突き殺されそうになった彼は、浄寛と名乗る河原の聖に助けられる。 それ以後、彼はツブテの弥七や法螺房弁才などの河原者たちの暮らしに惹かれていく。 「わたしには『放埒の血』が流れているのか?」その畏れを秘めながら、少年は比叡山へ向かう。 著者 : 五木 寛之
1投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最終的に浄土真宗を広め歴史に残る僧となる親鸞、そうなることがわかってその幼少期や青春期を読むのがとても興味深い。あまり記録が残っていないとされているからほとんどフィクションの世界かもしれないが。 平安末期から鎌倉時代の話とは思えないほど、現代と通ずるところもあり面白く読めた。
1投稿日: 2018.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語の進み方がすこし駆け足な感じもするけれど、ポイント毎の出来事がじわりじわりと人の思想を染めていくのが分かる。下巻が楽しみ。
1投稿日: 2018.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上下巻を通しての感想。 簡単にいうと幼い頃から、親鸞という名に至るまでの話。 後白河上皇、平清盛やら歴史上よく知られている人物が登場し、末法の世としてその頃の世情が描かれる。 そんな中、世俗の民と心安く語らい、ツブテの弥七や法螺房など無頼の徒と出会い、彼らと固く結ばれる。没落貴族の出である幼い親鸞が出家を決意し、比叡山に登り、座主に贔屓にされる中、仏教を極めようとするが、途中から聖徳太子に導かれ法然上人の念仏に帰依し、比叡山を去る。そこで法然からも格別の期待をかけられ念仏にを進化させて行く。途中、紆余曲折はあるものの、法然から受け継いだ信念を曲げずにひたすら突っ走って行く。 最終的に弾圧され、京都を去ることとなるが、その際の妻のありようと弥七の別れの挨拶は何ともカッコいい。 親鸞そのものに焦点が当たっているので仕方ないのだが、周囲の弥七や犬丸、敵役の良善や平四郎も魅力的なキャラクタとして物語を盛り上げている。 物語として面白く読めた。
1投稿日: 2018.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
伝説の人親鸞の、激動の人生。比叡山を降りる決心をするまでの上巻。生まれながらにして才能を持っていたとはいえ、幼少期での偶然の出会いが運命を大きく変えていく過程が丁寧に描かれている。ロマンス要素や大事な人の救出劇等、見所が髄所にある。身分を不要とし、動物がごとくものに執着しない心持は自分の生き方において指針になり得ると考えた。 人間本来が持つ様々な欲を抑制しつつ悩む過程は他の宗教偉人小説に必ず出てくる要素ですね。
1投稿日: 2018.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ友情、勝利、努力、愛情、争い、裏切り、悲劇的な別れなど、色々あり大変スペクタクルで面白かった。まだ親鸞は親鸞ですらない段階ですが。 親鸞、とても優秀で努力を怠らない上に周りの人望も熱い割に世俗的な悩みに囚われていて好感が持てる。
1投稿日: 2018.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと坦々と語られるのかと思ったら、かなりドラマチックに親鸞の少年時代が描かれています。 「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」親鸞といえば……という歎異抄の一節ですが、小説もそこを軸に語られています。
1投稿日: 2018.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ幼少期からその間様々な経験と思念により成長する姿を描く。他の人より感受性が高い分、行動も異なってくるのだろう。2017.12.14
1投稿日: 2017.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ若き日の親鸞は、馬糞の辻で行われる競べ牛を見に行き、怪牛に突き殺されそうになります。 その時浄寛と名乗る河原の聖に助けられ、以後、ツブテの弥七や法螺房弁才などの河原者たちと知り合い、彼らの暮らしに徐々にひかれていきます。 叔父の家から寺に出されようとしたとき、親鸞は比叡山へ行くことを決意します。 若き日の親鸞の葛藤も描かれ、読み進むにつれ、どんどん引き込まれていきます。
1投稿日: 2017.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ終わりに鴨川で弥七?が言い放った「こんな世間を変える為に僧になったんちゃうか」みたいな台詞がこれからをワクワクさせる。
1投稿日: 2017.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでが実話?すべてが物語?よくわからないが、引き込む力はすごいと思う。これから、どうやって浄土真宗が興ってゆくのか先が気になるが、単なる青年僧の成長物語として読んでも面白い。
1投稿日: 2016.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ忠範の頃から比叡山に入って範宴となり、比叡山を出ると決意するまで。 難しい本なのかと思ったら、すごく読みやすいし面白いし、登場人物の魅力がすごくある! 下巻も楽しみ。
1投稿日: 2016.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ活劇色が強すぎて、リアリティが無い。親鸞は、期待に反し普通人であった。なるほど、親鸞とはこの様な人物であったかと、納得する人物像を描いて欲しかった。
1投稿日: 2016.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ固い本かと思いきや、坊主の青春物語。 非常に読みやすい。 におい。平安時代末期のにおいが伝わってくる。 ドロドロしていて、生臭い。でも、かすかに良いにおいもする。 下巻を早く読みたい。
1投稿日: 2016.07.15親鸞の少年時代から越後に流刑になるまでの波乱の人生
親鸞の少年時代から越後に流刑になるまでの波乱の人生を劇画調に描かれる。 後白河上皇が賭場に現れたり、使用人が実は賭場の胴元だったり、つぶての弥七が絶体絶命の時に必ず救ってくれたりと、荒唐無稽ではありますが、躍動感に溢れダイナミックに時代を描く筆力はさすがです。 勿論、時代考証はしっかりしており、親鸞の求めた極楽浄土の道も余すことなく表現されています。
1投稿日: 2016.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家が廃れ源氏の世になろうとしていた時代 後白河法皇は武力ではなく歌の力で世を治めたいとしていたとか 忠範は口減らしで出家し、比叡山の僧となり、範宴となった。己の煩悩に悩み、仏とは何かという根本的な問いに悩み、今の仏道が弱き者の為にという本来の姿ではなく、貴族などの為にあることに疑問を感じていた。 比叡山を下り、世俗の中で仏道を、己を見つめ直すことにした。 意外と読みやすい。
1投稿日: 2016.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「念仏をとなえて浄土へうまれる」修業、学問、悟りを求めること不要と法然は説くのだった。彼は範宴(若き日の親鸞)と同じ比叡山で修業し、将来を約束されたがなぜ下野へ下ったのか、その教えが多くの民衆に受け入れられる意味とは・・・下巻につづく
1投稿日: 2016.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之さんの小説は大河の一滴に共感できず、それ以来読まずにいた。でもこの小説は痛快に面白く、止まらない。続、親鸞も読みたい。
1投稿日: 2016.04.02親鸞
浄土真宗の宗祖親鸞の比叡山での数々の修行、でも見いだせなかった自分の生き方。そして比叡山を出た後の苦悩。 今ゲーム三昧の多い若者現代人にもぜひ読んで欲しい文庫本で有る。
1投稿日: 2016.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログひょんなことから友達から借りた本。 何の気なしに読み始めたけど、第1章からものすごくテンポが良くて、次が気になる書き方。 ここまで次が気になった本はあまりないかも。 というわけで星5つです。
1投稿日: 2015.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の家の宗派が浄土真宗ということもあり、昔から気になっていたが、この前お坊さんの話を聞いて、さらに知りたくなり読んでみた。 親鸞という名前しか知らなかったが、彼がそこに行くまでの経緯。誰を慕っていたのかなど、過去に学校で学んだことが蘇ってきた。
1投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ多分に創作も含まれるんだろうけど、なかなかに興味深い親鸞聖人の話。小学生の頃からその名前は知ってるけど、その生涯については全くの無知。暗い闇を宿した目とか、破天荒な人間との付き合いとか、意外に人間くさいところが色々と垣間見れて、楽しく読み進められる。しかし、”検非違使”って響き、久しぶりに聞きました。
1投稿日: 2015.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログほとんど予備知識のないままに読んだので 物語として楽しめた。 「生きとし生けるものはすべて心に闇を抱えている。善だの悪だのと簡単に区別できるものではない」 だから誰でも、自分の闇や悪に気づくたびに念仏を行っていくしかない、 というような教え。 聖書の「罪びと」の考え方と同じだと思ったし、 久しぶりに聖書を読んだり教会に行きたくなった。
1投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ全2巻。 ただ、続篇で「激動篇」が2巻あり、 現在「完結篇」が連載中。 坊さんだけどそんなに抹香臭くない。 特に序盤の本著は、幼少時代から始まることもあり、 冒険したり仲間に助けられたり戦ったり、 素直にワクワク読み進められる。 吉川英治版より、より「冒険活劇」なイメージ。 ただ、執筆年数、物語内の年数ともに長いので、 序盤で活躍したキャラ、 キーになるだろうと予想されたキャラ達が、 どんどん影が薄くなり、 使い捨てられてる感じがある。 まだ完結してないので何とも言えないけど、 すっきりしない感じが残りそうで不安。 何はともあれ完結を待っています。
1投稿日: 2014.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ『他力』(講談社文庫)や『蓮如』(岩波新書)などの著書があり、浄土教に造詣の深い著者が、若き日の親鸞をえがいた小説です。 のちに親鸞となる忠範少年は、八歳のころに両親をなくし、伯父である日野範綱の家に引きとられます。ある日彼は、馬糞の辻でおこなわれる「競べ牛」の見物に出かけ、河原坊浄寛という聖や、ツブテの弥七、さらに法螺坊弁才といった、個性の強い男たちに出会います。さらに、日野家の召使いの犬丸から、忠範には彼の祖父・日野経尹と同じ「放埓」の血が流れていることを教えられます。 そんなある日、犬丸が「六波羅王子」という異名をとる伏見平四郎に捕らえられるという事件が起こります。浄寛たちとともに六波羅王子の屋敷に向かった忠範は、戦いの末、犬丸を救出することに成功します。無事に忠範と再会した犬丸は、後白河法皇の命を受けて世間の動きを探っていたことを明かします。そして忠範は、犬丸の推挙を受けて、仏門に入り比叡山の慈円のもとで学問と修行をすることになります。 忠範は、慈円から範宴という名前を授かり、やがて吉水の法然の説法を聞いてくるように命じられます。そのとき、まだ範宴は、法然の教えを受け入れ彼のもとに推参する期が熟していませんでした。しかし若い範宴は、自分のめざす学問と修行は、浄寛たちのような闇に生きる人びとに救いをもたらすのだろうかという悩みをいだくようになります。そんなある日、弁才と再会した範宴は、弁才が病に苦しむ貧しい人びとのために尽くしていることを知り、自分の進むべき道について考えを変えることになります。 前巻では、若き日の親鸞の苦悩が描かれています。ストーリーそのものもおもしろいのですが、ここからどのようにして、親鸞の宗教的な思索が織りあげられていくのかということが、一番気になります。
1投稿日: 2014.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ坊主エンターテインメント。初の五木寛之作品で、ほぼ装丁が気になって買ったので、読むまでどんなもんかと思ってたら、意外におもしろい。危機が意外とすんなり切り抜けられたりするけど、それはそれ。
1投稿日: 2014.05.14まさしく講談
河原者とのエピソード。平清盛の部下との死闘。恵信との恋。かしこまった所は少しもなく、まさしく講談。新聞小説だけあって、テンポもいい。
0投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ僧も生きていくための単なる職業で、多くは財や権力を求めていたのだろうと思う。そんな中で、親鸞はそこから飛び出し仏とは何かと心に問いかけ続けていた。真に苦しむ者に寄り添ってこそ仏なのではないかと思う。親鸞自身決して恵まれた境遇で育ってきていなかったことが彼を作り上げる一つの要因だったのではないかと思う。人間は良い心だけを持っているわけではなく、常に悪い心と戦いながら一生を終えるのだろう。
1投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之が 小説をかくのをやめ 仏教大学にはいった というのは,実に新鮮だった。 そして また物語をつむぎだした。 なぜ、五木寛之が 仏教に行ったのかを 理解する上で、『親鸞』という作品を書いたのは 重要な意味があると思い 読み始めた。 忠範という少年の物語から始まって、 若くして 決然と方向性を決める少年に 清々しさを 感じたのであるが。 慈円より 範宴という 名前をいただき 9歳から 修業を始め、12歳で 比叡山で修業を始める。 どんな荒行をしても 人間の煩悩を消すことをできない。 玉虫という女性に会うことで 生々しい感覚を 自分の中に しまい込む。 10年後に 玉虫が 大きな変化をしていることに 範宴の 人柄の感染として存在する。 紫野が 登場したが 下巻で絡み合うのだろうか。 範宴は 比叡山の最澄の仏教よりも 聖徳太子に 魅かれていく様が 実に面白い。 そして、その頃のはやりである 法然の持つ魅力に圧倒される。 救済とは 階級制ではなく すべてのものに 平等である という 考え方は 宗教のあり方として 重要。 聖として 無戒 をうけて 市井での悟りを開くのだろうか。
1投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログすっかり活劇になっていて笑った。本当の悟りを求め迷いさまよう親鸞。その命を狙う黒面法師。ピンチの時に風のように現れるツブテの弥七。まさにクエスト・オブ・アバター。話がRPGちっくで楽しい。しかし比叡入山から越後流刑までの流れは判りやすくて勉強にはなった。 この本ですっかり悪役になっていた法然の弟子の安楽房、この人ゆかりの寺が哲学の道沿いの安楽寺で、法然院のすぐ傍にある。紅葉が綺麗。ここを訪れた時に和尚の法話を聞いたのだが、この安楽房の辞世の句がダサ過ぎてこけた。「今はただ 云う言の葉も なかりけり 南無阿弥陀仏の み名のほかには」
1投稿日: 2014.01.20時代劇チャンネル
宗教の難しい話というよりは、時代劇チャンネル。 激動編の続きもあるのかな。
1投稿日: 2013.12.17浄土宗と真宗の違いは?
上巻下巻全二巻の構成。私事、実家が浄土真宗なので、宗派の説明本を読みたかったのですが、開祖である親鸞の人物像に迫ってみるのも宜しかろうと、この本を選びました。でも、やはり文学ですね。個人的には高僧で堅苦しい御仁のお話かと思っていましたが、ごく普通の煩悩だらけの人だったとは意外でした。ちょっとサスペンス仕立ての場面などもあって、楽しめました。 自分ではこれまでに無い、かなりのスピードで読み耽ってしまいました。法然に弟子入りし、そこから浄土教とどこがどう違う宗派になっていったのかが分からないまま終了しているのが残念でした。
2投稿日: 2013.10.12親鸞の描写が明確
一気に激動編まで読んでしまいました。残念なのは親鸞がハッキリしている割に、こちらの時代背景の知識が足りないので、親鸞が浮いてしまいます。こちらの知識不足を痛感してしまった作品です。それでも読まずにいられなくなるのは作者のなせる技なのでしょう。続編を早く読みたいです。
4投稿日: 2013.10.06親鸞
五木寛之の書、若き日の親鸞の修行と苦悩を描く、親鸞の人となりを理解するのによい、
0投稿日: 2013.09.26一気読み
さすがは五木文学。親鸞についてそんなに興味があったわけでもないのに、読み出したら引き込まれるようにして一気読みしました。 すかさず下巻も買いました。 すべての世代の方におすすめです!
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ表紙のイメージから、もっと難しく取っ付きにくいかと思い込んで読んでみたら、意外とエンタメが入っていて、まだ上巻ですがワクワク面白いです。親鸞がまだ8歳のタダノリ(忠範)と呼ばれていた頃から比叡山へ上がり範宴という名で修行に打ち込む日々までの過程に、随分キャラの立った面々が加わって飽きません。ここではそれ程深く後白河法皇について描かれませんが、大変興味深い法皇様ですね。
1投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんとなく気になって読んだ。 宗教云々はよく分からないけど、読みやすくて面白い。 蛸のごとく吸って飲み込んでしまったとこがやたらとリアルに感じてしまって気持ちが悪いような寒気がするような、なんともいえない気分。思い出してもウッとくる。 下巻読み中。
1投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之氏の本は最近は随筆しか読んでいなかった。久しぶりの小説。五木氏らしい、いかにも物語風になっている。登場人物が皆、不思議な力を持っているのもそのひとつ。少し現実離れしているため、親鸞の生き方が十分描かれているのか疑問も湧く。しかし、親鸞について私達よりもずっと詳しい五木氏のこと、親鸞を描くにはそのような不可思議な力の働きが必要なのかもしれない。
1投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
宗教小説でなく、歴史小説として読める。上下巻。 親鸞が誕生する(親鸞は、俗名に始まり、法名も4度変えている)までの「創世篇」と言える(「創世篇」とは名付けられていないが。そして「激動篇」へと続いていく)。
1投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の幼少期から青年期まで。 まだまだ話は盛り上がりの途中、今後の展開がどうなるか気になるところ。
1投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ意外にエンターテインメント性たっぷりで、面白く読めた。 想像していた感じではなかったけれど、よかった。 「浄土真宗」確立から晩年までの続編もあったらいいなぁ。
1投稿日: 2013.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ実家が浄土真宗なので読んでみようかと手に取った一冊。どれだけありがたい教えが述べられているかと思いきや、アクション満載の面白い歴史小説風になっている。上巻は、親鸞の青年時代までの物語。修行僧時代の記録などほとんど無いだろうから、おそらくは、ほとんど著者の創造であろう。80歳になんなんとする年齢で、よくここまで面白くかけるものだと思う。 続きも思ったより楽しく読めそうだ。
1投稿日: 2013.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞のことは名前しか知らなかったけれど、浄土真宗をいう仏教の中でも大きな宗派を開いた偉人が、悩み多きふつうの人だったというのはすごく親しみが湧く。 最初からいろんな災いが降りかかり、ハラハラドキドキ。 まだまだいろんな苦難が待ち受けてそうで、目が離せない!! 下巻も一気に読んでしまいそう! ちなみに大河ドラマ「平清盛」を観てたので、だいたい時代背景がわかりやすかった。 後白河法皇や六波羅王子や今様のことなど。 史実をだいぶ脚色してあるだろうけど。
5投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログうちも浄土真宗だから親鸞には馴染みがあるなー、と思って読んだ本。 あとはO木医師のおすすめもあり。 あとは京都一人旅の道中に買った思い出もあり。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教を通して、自分自身そして社会と向き合うことでなぜ生きることは苦しいのか?救われる道は?を問い続ける主人公、親鸞の物語。
1投稿日: 2013.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
親鸞、どこかのお坊さんということしか知らない状態で読み始めた。平清盛が栄華を極めているときに生まれ、ある程度の身分があるのにもかかわらずやくざもののような人々に魅かれ、ある程度の悪をしなければ生きられない時代に、たとえ悪をしても浄土へ行く道があるのかを探すために比叡山に入り修行をするタダノリ(のちの親鸞?)を描く。 タダノリが修行する時代の比叡山は仏門をはなれ、身分を求め、権力闘争をしている、それに背を向けひたすらに仏を求めるタダノリ。やがてその生真面目さから比叡山を降り、町の聖として生きることになる。 僧として捨てねばならない欲をすてきれず、またその生真面目さゆえに他の僧のように適度に欲と付き合うことができず、ひたすらに自分を責める姿が描かれている。
1投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログがつながっていなかったので、今年初の投稿になるが、なんと9冊め。かなり良いペース。 親鸞がジョー・ストラマーに思えた。浄土宗はブルースで、浄土真宗はパンクだ。
2投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄く面白いです。 親鸞に対して以前から興味があって、ほんの少しだけその教えも知っていました。 けれど、想像した以上に、親鸞は人間臭い感情と常に向き合っていたのだと思いました。 もちろん史実そのものではないのでしょうが、人にいわれたことを鵜呑みにせず、自ら悩み抜く力があったからこそ、親鸞の教えが今も生きているのだと思います。
1投稿日: 2012.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたま訪れた西本願寺で親鸞聖人入滅750年の法要をやってたんで…読んでみようかと。小説としてもそれなりに楽しめたけど、エンターテイメントではないな。
1投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い!いつの時代も改革は狙って始めるものではなく、おかしい、おかしい、の連続から生まれるんですね。ポジティブなネガティブ目線、重要です。加えて、いつの世も時代背景は違うけど、根本問題に違いは全くないですね。この後の展開が楽しみ。
2投稿日: 2012.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ忠範の幼少期から天台の仏門に帰依して範宴となりやがてお山を降りる決心をするまでのエピソードが描かれた上巻。さすがに新たな国民文学というだけのスケールはある。面白い。
1投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とても面白く、興味深く、読めました。 忠範に弥七から託された石ころを渡すとき 「・・われら悪人ばらのためにお山で修行なさるのだ。だから忠範さまに伝えてほしい。もし、運よく物事がはこんで、自分がなにか偉い者でもあるかのように驕りかたぶった気持ちになったときには、この石を見て思いだすことだ。自分は割れた瓦、瓦の小石、つぶてもごとき者たちの一人にすぎないではないか、と。・・・」 忠範が悩み苦しみながら、成長し、自分の信ずるところに妥協せず、もがき、迷いながら進んでゆく姿が とても身近に人間らしく感じられ、 いとおしく感じました。
1投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ人として生きる上で大事なことは、何なんだろうか? そんなことをふと考えてしまう一冊、続編を読まねば。
1投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
念仏とは人生という夜道を照らす灯りである、 親鸞が町人にたいして説法をしている際に町人から「念仏となえると病気が治ったり、暮らしが楽になったりするのか」と問われ、そうではないと答える。 親鸞曰く、修行時代に暗い夜道を重い荷を背負いくたくたになりながら歩いていると、ふと民家の明かりが見えた。それはつまり目的地が近い事を意味し、体が軽くなった気がした。 ゴールが見えたからといって荷物が軽くなった訳でもなく、目的地が近くなった訳でもない。でも体は軽くなった。 念仏とはその灯りのことだ。 僕は以前から自分の心の中にある、もやもやしたなんともいえない不安のような物が何なのかよくわからなかった。ただ、この本を読んでわかった事は、僕の人生には灯りが無かったって事だ。
1投稿日: 2012.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) 馬糞の辻で行われる競べ牛を見に行った幼き日の親鸞。怪牛に突き殺されそうになった彼は、浄寛と名乗る河原の聖に助けられる。それ以後、彼はツブテの弥七や法螺房弁才などの河原者たちの暮らしに惹かれていく。「わたしには『放埒の血』が流れているのか?」その畏れを秘めながら、少年は比叡山へ向かう。
1投稿日: 2012.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012.06.25 上巻読了 2012.06.29 下巻読了 おもしろかった。 ただただ法然の教えを自分の意としいら
1投稿日: 2012.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでが史実なのかはわからないですが、幼少からのエピソードなどから興味深く書かれています。他が認める行をなし、才能を持ちながら、欲や出世を捨てて、あくまで自らの信じる、求める道を進むため、俗世間に身を置く、その覚悟が読んでいて心にしみます。下巻につづく。
1投稿日: 2012.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ浄土真宗の親鸞がどのようにして出来上がっていったか、ということを読みやすく書いてある。 取り巻く人々は、史実的にどうなんだと思わないでもないけど、気楽に読めてよし。
1投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説を読もうと思って最初に手にとった本。とんだ冒険活劇でした。少しだけ親鸞のことがわかった気になります。
1投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと書店に並んでいたのが目についていたので何気に手に取った。幼少期、比叡山での修行までは淡々と読んでいたが、六角堂への通い修行あたりから親鸞の煩悩や自己嫌悪、形骸化した仏教体制への不満など熱い思いが次第に膨らんでいく過程では胸を打たれた。底辺とされる人々との交流の中で自らを見出し、仏教を生きた教えとして伝えていくことを決心した親鸞の人生はこれから真骨頂を向かえるというところで終了。熱いストーリーを後編にも期待したい。
1投稿日: 2012.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年67冊目。(再読) 激動編購入のため、読み直し。 やはり一気に読み通してしまう面白さがある。 「民の目線」を大事にする姿勢をもう一度学ぶ。 ==================== 2012年3月23日(初読:27冊目)。 難しい用語はところどころにあるものの、ノンストップで読める読みやすさのある歴史小説。 「仏とはそういうものだ」という暗黙知に、「仏とはなんだ?」と真正面から誠実に迷う親鸞(この時の名は範宴)の姿に共感を覚える。 お山から降りて一般大衆に近づこうとする姿勢が、今の世でも通じるリーダーシップ像を思い描かせる。 続きに期待!
1投稿日: 2012.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変、読みやすい。 物語として軽い感じで楽しめつつも、仏とは何なのか、という本質的問題を投げかけてきたりもして、まだまだ序章ではあるけれど、この先のお話が気になって仕方がない。 下巻が楽しみ。
1投稿日: 2012.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の幼少期から比叡山に入山、俗世間での経験をきっかけに、比叡山を下りる事を決意したところまで。仏とは何か?の問いを求めて苦行に励む親鸞。今と通じるような世の中の構図がこの時代にもあり、共感出来る。
1投稿日: 2012.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログじわじわ面白い。 続きが気になって次から次へと読み進める感じではないけど、自分も一緒に修行して成長してる気になる。 仏教的な難しい話かと思ってたら、意外と青春物語。恋もするし反抗もするし。仏教用語は多く出てくるが、読者に向けてか話の流れか、噛み砕いて話してくれてるので読みやすいし勉強になる。 範宴(親鸞)の考え・悩みは現代にも通じることで、自分も深く考えさせられる。 日本で飢えることはほとんどない今も、人は争い苦しんで生きるし、極楽浄土を目指すんだよなぁ。
1投稿日: 2012.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ浄土真宗、浄土宗の人は必読!?親鸞と法然という「人間」に焦点を当てて書かれているので、仏教に非常に親近感が湧きました。鴨川に死体を捨てていた、死臭が漂っていたというのは、今京都に住んでいる自分にとって衝撃。昔の京都の街が妙にリアルに想像できてしまいます。なーもあーみだんぶ。。。
1投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に読みやすい。流れるように読め、それでいて歴史の変遷を随所に感じられる良作。本当に歴史を知りたい!という人には物足りないが、ちょっと歴史的な雰囲気を味わいながらの暇つぶし本としてはおススメだ(といったら失礼なのだろうが)。 親鸞といえば浄土真宗および「悪人正機説」。何となく奇抜な人なのかなあというイメージを持っている人は多いと思う。だからこんなにひたむきでまじめな少年・青年だったのか!と驚いた。叡山に入ったのか、などいろんな発見がある。 現代日本において仏教のなんたるかなど答えられる人など少数だと思うが、平安時代・鎌倉時代の人々は違う。死体が転がる日常で求めたのは浄土への扉だった。だが仏教の門は開かれていなかった。そんな中で求道者となる範宴(親鸞の比叡山での名前)がこれからどうなって行くのか楽しみだ。
1投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ五木寛之の本はだいぶ前に「戒厳令の夜」を読んで以来、たいへん面白いものの、壮大な物語の結末が非現実的になり過ぎてあっという間に終わってしまうという展開に物足りなさを感じていました。しかし、「大河の一滴」で作者の違う面に触れ、仏教との関わりという視点から興味を持っていました。この本は、まさに仏教を題材にしてたいへん面白いという話は聞いていましたが、単行本を買う気にはなれずにいました。単行本になったのを知り、すぐに買って読みましたが、あっという間に引き込まれてたいへん面白く興味深く読みました。ただし、かなり史料に基づいて書かれているのだとは思いますが、やはりちょっとリアリティに欠ける部分もあります。
1投稿日: 2012.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログいや、面白い。 つってもお坊さんの話でしょ? と、説教臭い地味目な内容を予想してたら どっこい序盤からドラマチックな展開で飽きさせません。 むしろエンターテイメントに徹しながら、 折々で仏教の考えや、現代にも通じる人の内面、社会の有り様を 嫌味なく置いていく感じ。 スーパー草食系の主人公が、 持ち前の内向性と空気の読めなさを発揮しつつ、 あっちに行ったりこっちに行ったり。 しかしまっすぐな姿勢が周囲に好かれるもんだから、とにかく世話になりっぱなしで。 ええい、しっかりしろ。 とつい感情移入してしまう。 基本的に読者の目線を一手に引き受ける主人公は、 「で、仏って結局なんなの?」「なんでみんな念仏唱えるの?」「それで誰が救われるの?」 と、こちらが気になる所にちゃんと引っ掛かってくれます。 まあそうなると坊さんとしては異端の道をゆくことになるんだろうなあ。 巨大なものを相手にしても自分で考え、理解しようとする姿は美しいです。 上巻は幼少期から青年になるまでのどこか青臭さの残るお話でした。 厳しい修行を重ねても女子と話すと途端に舞い上がる普通の青年。 分かる分かる。
1投稿日: 2011.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログお坊さまは、じっと忠範の顔をみつめて、ため息をついた。 「この子の目にやどる光は、ただごとではない。なにものをもおそれず、人の世の真実(まこと)を深くみつめようとするおそろしい目じゃ。こういう目をした子に、わしはこれまで一度だけ会うたことがあった。京の六角堂に詣でるために紀州から上京してきたという母子じゃったが、その幼い子が、やはりこのような思いつめた深い目をしておった。いま、そのことをふと思い出していたところじゃ。たしか、法師、とかいう名前であった。母親が六角堂に万度詣でをして授かった子だとか。その子の目が、忘れられずに心に残っていたのじゃが、同じ目をした子にふたたび会うとはのう。このような目に見つめられると、悟りすましたわが身の愚かさ、煩悩の深さがまざまざとあぶりだされるようで、おそろしゅうなる。一歩まちがえれば大悪人、よき師にめぐり会えば世を救う善智識ともなる相と見た。心して育てなされ」 この言葉は忠範(のちの親鸞)の心にずっと残る。或いは「自分には放埓の血が流れている」という意識をずっともっていたということになっている。 この坊さんの言葉に出てくる母子はおそらく法然とその母親のことだろう。この前私は岡山県美咲町の誕生寺に行った時、「旅立ちの法然像」を見た。上巻では、親鸞(この時はまだ比叡山修行僧の範宴)は法然の説教を聴いているが、まだピンときていない。本当の出会いは、おそらく範宴が世の様々な「罪」「煩悩」に出会って以降になるのだろう。 「親鸞」に初めて出会ったのは、中学二年のときだったと思う。吉川英治を読み始めて、初めて自分で買った文庫本だった(文庫本の吉川英治全集が出始めて直ぐだったと思う)。それ以降、その本は擦り切れるほど読んだ。何か自分に引っかかったのだと思う。 今回の五木版はどうやらその「親鸞」の数倍はある長さになるようだ。視点も、吉川版よりもずっとずっと庶民の視点に近づいている。私が何に引っかかったのか、暫らく付き合って行きたい。
3投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「もし運良く物事が運んで,自分がなにか偉い者であるかのように驕り高ぶった気持ちになったときは,この石を見て思い出すことだ。自分は割れた瓦,河原の小石,つぶてのごとき者たちの一人にすぎないではないか,と。そしてまた,苦労が続いて自分はひとりぼっちだと感じたときは,この河原の小石のようにたくさんの仲間が世間に生きていることを考えて欲しい,と。」 「浄土をひたすら恋う気持ちが分からなければ,念仏は分からない。頭で浄土を思い描いている限り,法然房のもとに集う人びとの心は理解できないだろう。そのこころは心ではなく情なのだ。浄土は情土なのだ。唯識で心はとけるが,情はとかすことはできぬ」 「仏の道を国の教えとして確立されたから尊敬しているわけでもない。立派な憲法をつくられた偉い方だからでもない。身分というものをこえて,世間の人びとにわけへだてなく生きる技を教えてくれたおかただからこそ太子を慕う者たちがいる。人びとが法然棒を慕うのも,同じであろう」 「真実の仏に会おうとすれば,当然,なみの覚悟では出来ぬ。狂うところまでつきつめてこそ,真実が掴めるのじゃ。しかし…狂うてしもうてはだめなのだ。その寸前で引き返す勇気が必要なのじゃ。命をかけるのは良い。だが,命を捨ててはならぬ。」 「法然房はのう,こういわれたそうな。酒は飲まぬ2こしたことはない。しかしそこは,世のならいなれば,と」
1投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めてすぐに思い浮かんだのが、陰陽師だった。 なんだかワクワクしてきた。 忠範がなんとも可愛い。 河原坊浄寛 ツブテの弥七 法螺房 この三人がまた魅力的 昔観たことがある漫画が浮かぶのだけど、なんて漫画だったかなぁ・・ 牛若丸と弁慶も思い出した。 仏の世界のことはわからないけど、厳しい修行にあえて挑んで行く忠範、まだ小さいのに切なくなる。 そして、この三人の関わりが面白い。 病室にて読了
1投稿日: 2011.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ親鸞の幼少期から比叡山での修行時代を描く。 初めて五木寛之の本を読んだが、さすがに読みやすくて引き込まれる。 いろんな仲間に出会ったり、悪い奴をやっつけたり、女性に誘惑されたり。。。。。 もう少し堅めで説教じみていて、読むだけで仏教の教えを多少勉強できるようなことも期待しつつ読み始めたが、予想に反して単純に面白い小説。 下巻ではこの面白さを維持しつつ、もう少し仏教的な内容にも触れたい。
2投稿日: 2011.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに『小説』とちゃんといえるような本を読んでる気がする。 今週末、家族総出で祖母の納骨に京都の大谷祖廟にゆくのです。 そこに、この『親鸞』の文庫化。 歴史物は苦手故、読めるか不安だったが、どんどん読める。はまる。 範宴の苦悩が、なんだか心に染みます。 つぶての弥七が、範宴に渡した小石に添えた言葉、この世も地獄、あの世も地獄と覚悟する者たち、罪を犯していると自認し、そうでなければ生きていけない身で、だけど、それでも地獄には行きとうない、と嘆く人。 んー。それぞれのエピソード、言葉が素直に入ってくるのは、さすが五木寛之か。 親鸞が近くに感じる。 週末までに、下巻読み終えたい。 大谷祖廟に行く前に。 「身分や職業の高下などない。この世に生きることは苦しい。心と体が痛む者を助けなければならぬ。よりよく生きる道をさがそう。そしてよろこびをもって生きよう。それ意外になにがある?」
1投稿日: 2011.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直この小説で涙するとは想像していなかった。仏教界が、世俗にまみれた時代に生きた親鸞の少年時代を描いたこの上巻では始終若き親鸞は、悩みに悩む。仏とはなにか?信仰する主に対して悩む姿は、他の坊さん達には理解されず、狂ったのではないかと思われる。仏教界と世俗との間で、常に悩みながら生きる姿は、数百年前の話とは思えないリアリティがある。これが五木寛之の力かと唖然とさせられる。
1投稿日: 2011.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教の教義とか出てきて難しい本かと思いきや、ユニークな人物たちが脇を固めていて、十分楽しめる本だ。 作者が五木寛之なので、親鸞の思想を分かりやすく、解いてくれるだろうと期待する。
1投稿日: 2011.10.23
