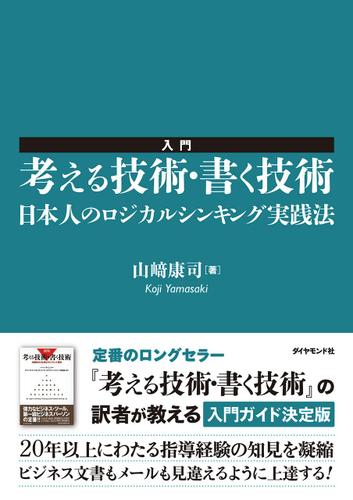
総合評価
(220件)| 77 | ||
| 86 | ||
| 35 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングの技術、それをライティングする技術書です。 良本です。 10冊買って、会社の社員に読んで貰いました。
0投稿日: 2026.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・読み手は何に関心を持ち、どんな疑問を抱くかをまず考える。 →OPQ分析(読み手の視点で考えること) Objective:望ましい状況 Problem:現状とobjective とのギャップ Question:読み手の疑問 Qに対するAnswerがそのまま文書の主メッセージになる。 ・考えを組み立てるプロセスは2種類 ①複数のグループ化されたメッセージから要約メッセージを探す ②メッセージのグループをつくる ・「が」は順接にも逆説にも使われるため、注意して使わないか最小限に。 ・ピラミッド作成が何よりも大事(主メッセージとグループ)
0投稿日: 2026.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、わかりやすい文章を書くためには書き方以前に「読み手の疑問を起点に考える力=ロジカルシンキング」が重要であると説いている。 OPQ分析やピラミッド構造を用いて結論を先に示し、理由や根拠を論理的に整理することで、説得力のあるビジネス文書やメールが書けるようになる。 日常的にメッセージを構造化する訓練を重ねることで、コンサルタントとしてクライアントに価値を提供できる思考力と表現力が身につく。
0投稿日: 2026.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログAI時代だからこそ、文章力を体系的に高める必要があると考えた際に見つけた本です。 わかりやすく、新入社員への推薦にも適しているとのレビューを見て拝読しました。 中堅社員となった今、慣れによる思考停止や惰性が文章に表れがちであることに気づき、改善のきっかけを得られた点が良かったです。特に第4章(接続詞)は、日常業務のコミュニケーションや資料作成においても即活用できる内容だと思います。 分量は多くないものの、じっくり考えながら読み進める本であり、教科書に近い印象です。新入社員はもちろん、中堅層にとっても一読の価値がある一冊だと思います。
6投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・読み手が何に関心があるを想定して、文章を書きなさい。 ・書きたいことを書いていては、伝えたいことが伝わらない。 ・帰納で文章を仕上げ、演繹で伝える。
0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書、論理的思考の基礎本。後輩に、文書は読み手の視点で書いてと指導したが、この本を読んで貰えば良いなと思った。 以下、引用。 ー日本語の主語のなさ、接続詞を気安く使えるなど、日本語特有の問題が、考える行為そのものの足を引っ張っている。これはそう感じてきた部分もあった。 ーメッセージ構成を文章上、一目でわかるように表現するには、文章を書き始める前に、伝えたい考えを明快に組み立てる必要がある ー感謝の言葉にPDF。1日1回ピラミッド×4ヶ月のトレーニング。
0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理的思考を身につけ、仕事のコミュニケーションを改善したくて読んだ。 印象に残ったのは「まず問い(Q)を立てる」ことの重要性。考えるための“レール”がないと、思考が迷子になると気づいた。 また、「ピラミッド構造」で結論→根拠→具体例と整理する方法は、話の伝わりやすさにも直結する。自分の曖昧な思考を“見える化”できる点が役立ちそう。 論理的思考はセンスではなく型で鍛えられるというのが大きな学び。今後はOPQ分析を意識して、メールや会話でも問い→答え→根拠を意識してみたい。(感謝のPDF)
0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログざっくり、基本的に伝える時はロジックツリーの通りに伝えればOKみたいな感じだった気がする。 頭の中でロジックツリー描けてるかの方が重要そうな気はした。
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手が知りたいことは何か? それに対しての解は何か? またその解の根拠は何か? これは常日頃から意識したい
0投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントの方は挫折したが、こちらは内容が分かりやすくすらすら読めた。 OPQ分析を用いて読み手視点に立つことを習慣づける。 また、メールを書く際には「感謝の言葉にPDF」を意識し、1日1回ピラミッドを本気で続ける。
0投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構良かったです。 何が良かったとか言語化するのは難しいけど、ライティングって大事なんだろうなって気持ち。 (言語化できてないからライティングできてないですね)
0投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が何を伝えたいかではなく、読み手のことを一番に考える。 読み手の疑問は何でその答えこそが、ビジネス文書で考えるべきメッセージ。 事実をグループ化し、その中から要約メッセージを作る。 要約メッセージとは同じグループ内のメッセージに共通する「特定の意味」を拾い出すもの。 メールの基本 「感謝の言葉にPDF」 ①まずは日頃の感謝を述べる ②その後にP(Purpose Statement)目的文 主メッセージのこと。 ③D(Detail)詳細 主メッセージの理由や判断根拠、内容説明、具体案など。 ④F(Follow-Through)フォロースルー 結びにあたるもの。 今後のアクション
1投稿日: 2024.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ・しりてが接続詞を使わないように気をつける ・ピラミッドを作る時は、縦横の関係を意識しないと、ロジックが崩壊する
0投稿日: 2024.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ問い ロジカルな人と思われるにはどうすればいいか (ロジカル→話がわかりやすい→仕事ができる、説得力が増す) 答え 自分ではなく相手の関心や疑問に対して結論から答える 根拠 ・仕事は相手があって成り立つ。お金がもらえる。 ・忙しい相手は自分の関心があることしか聞かない。 ・そもそも資料作成や説明は相手の疑問を解決するため、相手に動いてもらうために行う。
8投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングの初学者にはとてもおすすめできる。 既知のことかもしれないが、なぜそうであるのかが、単に理解しやすいだけでなく、本書を通じて自分なりに飲み込みやすいと感じた。 日本語の曖昧な表現、特に著者の言う「しりてが接続詞」については改めて気付かされたところもあった。
0投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログレポートやメールを分かりやすく簡潔に書くためのメソッド。ライティング用技術でありながら、書く前に自分の考えを整理することが出来る。 言ってることは簡単なので真似しやすい(ハウツー本で重要なところ)。さっそくピラミッドの練習をしてみたい。 著者の例文で腑に落ちないところはあるものの、目をつぶれば良い程度のことだと思う。
0投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は良いと思うが、個人的に著者の語り口や見本として挙げられていた文章が好きになれなかった。人に読んでもらえる文章を作るためのスキルに関する本なのに、なんとなく好きになれないという読後感が残るのはちょっとな、という個人的な感想です。
0投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・前に会社の上司が「下位者に教える際の参考になる書籍がないかと思い、探して見つけた」と言っていた本 ・内容は分かりやすく興味も持てるが、簡単な内容なので苦手意識があまりなければ優し過ぎる印象 ・改めてインプットする機会という意味では良かった
0投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手の立場で相手が知りたいことを端的に書こうとするべきと学んだ。OPQ分析 望ましい状況とその問題点、飲み手に対する答え主文のメッセージ ピラミッド構造化は頭の中で即座にできるように、普段からトレーニングしたい。
0投稿日: 2024.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本家の後にこちらを読みました。こちらの方がコンパクトにまとまってていてわかりやすく、より実践的だと思いました。日本人向けにハマるポイントを解説しているのも好感が持てます。 この文章も「しりてが」接続詞禁止ルールに従って書かないとと意識できました(笑)。
0投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「このスライドは何を伝えたいものなの?」 「このメッセージは結局どういう意味?」 「このスライドの重要な部分はどこ?」 ここ数ヶ月、社内の経営陣に向けた提案書を作成している中で上長から上記のような質問を受け、自身の提案書作成スキル向上の一助とするために読んだ本。 テキストライティングのみならず、パワーポイント等で図解しながら提案書を作成する方にとっても参考になる考え方だと思った。 おもに参考になった点は以下。 ・資料を構成する前段階から「しりてが」といったあいまいな助詞を意識的に使わずにピラミッドを構成する ・主メッセージ(結論として言いたいこと)がうまく言語化できない場合はそれ以前の根拠やロジックそのもの、またはそれらの関連性に誤りがある可能性が高い ・主メッセージの体言止めの原則禁止 →何について言いたいのかはわかるものの、何を言いたいのかはわからないため
3投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ•ミントの『考える技術•書く技術』の訳者による日本人向けのジェネリック版的な本。 とはいえ、原著のエッセンスを日本人向けに平易な言葉で解説していることに加え、例文や実践のためのアドバイスなどが分かりやすいため、原著よりもタメになる。
0投稿日: 2023.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ■評価■ ★★★✬☆ ■■概要・感想■■ ○ピラミッド構造を主軸として、文章の書き方について述べた本。 ○導入編としてはいいと感じた。 ○深掘りするところでは、書く技術・伝える技術のほうが、より具体例が多く個人的には好みだった。 ○それでも入門書としては、十分に有用だと感じた。
0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ備忘録 ・読み手のOPQをを意識した文章を書く。 →読み手が目指すありたい姿、それに対する現状、gapが何故生まれるか、それを解決する手段 ・メールの場合は感謝に加えたpdf。 感謝の言葉を述べる、メインメッセージ、詳細、今後のアクション ・ピラミッド構造は帰納法、演繹法でまとめる。 →帰納法の場合はなぜならば、演繹法の場合は前提が本当に正しいかを確認して、論理構造を確かめる ・しりてがは使用しない。しりてがではロジカルな接続ができない →しりてが言葉はロジカル接続詞に置き換える ・ピラミッド構造のパターンを意識 →状況のwhy、方法のwhy、行動のhow、主題に対するhow、howに対するwhyの三段論法
2投稿日: 2023.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ簡潔な分かりやすい文章を書きたいと考えている人に勧めたい。 ロジカルシンキング・ロジカルライティングにおいて私が読んだ中で最もわかりやすかった本。 読み手の疑問にたち、相手の立場に沿って分かりやすい文章を書くための考え方・手法が分かりやすく解説されている。 https://self-methods.com/introduction-to-thinking-and-writing-techniques/
0投稿日: 2023.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
プレゼンテーション、報告書、ビジネスで何らかの文書を書く。その機会があるなら読んでおくべき。 本書はピラミッド構造で、演繹法、機能法を図示して考える。また、OPQ分析、O:Objective 望ましい状況、P:Problem 問題(現状と望ましい状況のギャップ)、Q:Question 読み手の問題、A:Answer 文書の主メッセージ、で考える。これかが基本となる。 また、4つの鉄則がある。ここには書き出さないが特に「しりてが」接続詞は使わないは秀逸。確かに見た目は良いが意味がない。
0投稿日: 2023.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラミントの著作が原点であり有名ではあるが、内容が難しいと言われてることもあり先にこちらを読んでみた。平易な文章で書かれていて分かりやすいので、まずは本書を繰り返し読んで実践していきたい。
0投稿日: 2023.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ書く技術と言っても、つまるとこ考え方、思考法がすべてであるということ。その点を分かりやすく解説している。伝わる文章の書き方を教える本だけあって分かりやすい。
0投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章力強化の教材として、会社の先輩から紹介され読む。「これはすでに知っているし、できている事」と自分では思っていたけれど、そうではなかったと、ようやく分かり始めた。 自分の作る文章を客観的に見ると、ここに書かれている注意すべき事がことごとくできていない。「知っている」のと、「できるようになる」事は、全く違う次元なのだと理解できた。(読んだだけでは分からなかったが、その先輩からの指摘ポイントを聞いて、自分のいけてなさを痛感した。 これから実践する上で、何度も読み返して確認したい教科書。
2投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすくロジカルな文章を書くために、どんな手順が必要なのか全体像と共に、各手順のコツやポイントをわかりやすく示していた。 ピラミッドストラクチャーは構造を理解しているつもりだったが、まだ活用できるまで落とし込めていなかったと気づくことができるくらい、学びになった。次は実践できるようにしたい。
1投稿日: 2023.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語の欠点を明記しながら、具体例を多く揃えてくれているので、視覚的にとても分かりやすい。 文書を書くのが苦手な私にとって、ピラミッドは最高の出会いに感じた。1日一回、感謝のPDFとピラミッドを習慣にできるよう努力したい。
1投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ●=引用 ●レポートを受ける立場になって読んでみる メッセージ構成を文書上、一目でわかるよう表現するには、文書を書き始める前に、伝えたい考えを明快に組み立ててお必要があるのです。考える作業で大切なのは、最も重要な考え(主メッセージ)を見つけることです。(略)主メッセージを明確にした後は、それを説明するメッセージ(下部メッセージ)との関係を整理します。(略)このような一連の考えを構成を一目でわかるよう、ピラミッド型に配置したのが、右ページの「メッセージ構成」です。ここまで来れば、あとはできあがったピラミッドを文書に置き換えるだけです。 ●読み手は何に関心を持ち、どんな疑問を抱くのか つまり、読み手の疑問に対する答えこそが、ビジネス文書で伝えるべき考え(メッセージ)なのです。厳しいようですが、それ以外の関心のないテーマについて、いくらあなたが手間暇かけて書いたところで、その文書は読まれないのです。したがって、読み手の理解こそが、説得力あるビジネス文書を書くための再重要ポイントとなります。 ●読み手の関心を呼び起こすには 書こうとするテーマが読み手の関心から離れている場合、読み手の立場に立って考え、関心を引きつける努力をすることが重要です。 ●読み手の疑問を明らかにする「OPQ分析」 ●以上のように、レール(トピック)の設定が異なればOPQもまったく異なるものとなります。実践では関係者と可能な限りのヒアリングを行ない、読み手が本当に問題としているレール(トピック)は何なのか、読み手が抱えているOPQは何なのか、最も適切と思われるOPQを発見します。そうでなければ、見当違いのレポートに終わってしまいかねません。読み手の立場に立つことがなぜ重要なのか、おわかりいただけると思います。 ●このOPQでは、比較のレール(トピック)が在庫なのか売上なのかが明快でないために、読み手の疑問を明確にできていません。比較のレールをごちゃ混ぜにしてしまうというよくある間違いです。読み手の疑問が曖昧だったり、違うトピックが混在していたりすると、具体的な答えを導き出すことができません。 ※別紙・抜粋あり
0投稿日: 2023.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ来年から社会人になるため、バーバラ・ミントの著書を読もうと手に取りましたが、評価を見ていると難しそうなので、手始めにこの本から入ろうと思い読み始めました。 メモを取りながら読み進めると、あっという間に2時間ほどで読み終えてしまいました。手が止まることがなく、充実した2時間半でした。これをきっかけにして次はバーバラの方も読んでみたいと思います。 これは感想なので、結論ファーストで簡潔な文章になっていないことをお許しください笑
0投稿日: 2023.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ○OPQ分析で読み手の疑問を明らかに ○しりてが接続詞は使わない ○ビジネスでは帰納法でロジックを展開する 資料作成の際に気をつけるべきことを知ることができた。段落表現の大きめな行間は読みやすさに繋がると思うので、取り入れたい。また、感謝の言葉をはじめにいれることで、入りが柔らかくなるとおもうので、定型の言葉を考えたい。
0投稿日: 2022.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ■目的 思考や文書作成の”型”を覚えて、ゼロスタートをせず楽できるようにしたい。 ■要旨 ・社会人のレポートライティングには問題がある、それを学ぶ機会が無い ・相手の望んでいるものを考え、相手の立場で書く★ここがめっちゃ大事 ■参考になった点 ①考えるときの技術 ・OPQA分析→相手のことを考えながら O:望ましい状況(object) P:問題(problem) Q:読み手の疑問(problem) A:答え・メッセージ(answer) ・体言止めの使い方について ○メールなどの見出しならオッケー ✕相手に伝えたいメッセージとしては NG ・曖昧言葉を使わない 早急に、増大、適切な、見直し、など。 ②書くときの技術 ・接続詞「しりてが」を無くする ・全てに主語を入れる ・曖昧言葉を無くする ③メールの技術 ★感謝の言葉にPDF P:主メッセージ D:詳細 F:今後のアクション でかく。Dは・を使った段落でもOK ================== ④報告の技術 これはこの本に記載されていたことではないが、知識として知っていたので書く ↓ CREC法(人に報告するときはこの順番がいいよ、という型) C:結論(Conclusion) R:そう考えた理由(Reason) E:根拠(Evidence) C:再度、結論(Conclusion) ■感想 こういった方は同じ目的でもいくつかあるが、とりあえずこの本で取り上げられたものを真似していきたいと思う。素早く使えるテクニック集としては有効。
0投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ第12回アワヒニビブリオバトル「誰かにオススメしたい本」で紹介された本です。 出張特別編@もりのみやキューズモールエアトラック 2016.04.29
0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ■文書を書くときは、読み手のことを第一に考える。 ・複数人いる場合は、だれに焦点を当てるか? ・読み手が不安に思っていることは何か? →その不安に答えることを第一に考えるを ・不安に思っていることがわからない場合は、OPQ分析を使う Objective:望み(あるべき姿) Problem:問題(現在の姿とあるべき姿のギャップ) Question:疑問(問題の解決に向けて読み手が抱くであろう疑問点) Answer:疑問点に対する答えがレポートの内容になる ・読み手が関心のないことを報告するときは、関心を惹くための工夫が必要 →関心のある内容から始めたり、関心のないことを伝えることがわかるような枕詞を入れる。
0投稿日: 2022.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスでのシチュエーションに絞ったロジカルシンキングの本。 ロジカルな文書とそうでない文書では何が違うのか理解できた。 ロジカルシンキングの基本となる考え方を学べた。
0投稿日: 2022.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングは興味があったため、6割はベースができている状態で読んだ。 学びは、読み手主観、OPQ、しりてが接続詩とロジカル接続詩、感謝の言葉とPDF。
0投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・O objective 読み手の目標、P problem 問題、Q question 解決に向けた読み手の疑問、A answer 書き手の答え ・読み手を理解する為に: 報告に何を期待するか聞く機会を作る。顧客と接する+食事共にする ・帰納法では1対1のピラミッドはない(その前提は自明ではない証拠) ・帰納法の目的は、ダブりなく、モレなく作ること。読み手がモレがないか判断する ・主メッセージ後に置く場合: 社内偉い人、社外顧客など読み手の反応がわからない人。異論反論を唱える人 ・英文ではand 使用禁止
0投稿日: 2022.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントのピラミッド・ストラクチャーの翻訳者による入門書。 日本の文脈を踏まえながら、説明になっているのは言うまでないが、面白かったのは、日本語の特質を踏まえてのアドバイスがなるほどであった。 たしかに、外国向けのプレゼン資料を作るのに、日本語でまず資料作成して、それを英語にしようとすると翻訳できず悩んでしまうことがあるのを思い出した。 つまり、主語がなかったり、文章と文章の間のロジックが明確でなかったり、行動が具体的でなかったりなどなど。 そこは日本語の奥ゆかしさというか、情緒なのだけど、それはやっぱビジネスには合わない性質なのかな? 日本的な事例もあるし、ピラミッド・ストラクチャーの考えの基本部分を簡潔に確認することができた。
0投稿日: 2022.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的に沿った文章を書くための途中過程である考えを組み立てる過程について解説した本。 当たり前なことが書かれていますが、本文で指摘されていたあいまい語の使用や関連づけの甘い文章接続 (and接続詞の使用) は意識せずに使ってしまいがちです。 本書では悪い例と修正案がいくつも挙げられていたため、実践的な内容でした。
0投稿日: 2022.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ例外の場合とかも理由付きで書いてあることが珍しいと感じた。 分かりやすい型にこだわりつつ、本来の目的に照らして不自然になる部分に関しては型に頓着しないような姿勢が好き。
0投稿日: 2022.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書におけるロジカルライティングの基本を学べる本。 ピラミッド原則についての解説本、とも言える。 シンプルで、わかりやすく、実践的で、読みやすいです。
0投稿日: 2022.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ理論と実践の両方を網羅されている良書だと思います。 自分はバーバラミントの著作を読まずに、今回の著書を読んでみましたので、前提知識ゼロで読んでみました。難しいかなと不安になりつつも読んでましたが、読者に伝えやすいように考え書く「OPQ分析」、そして日々実践できる「感謝の言葉にPDF」や「1日1回ピラミッド」を例と問題を交えながら懇切丁寧に提示してくれており、初学者にわかりやすい構成となっています。
0投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ新入社員は特に読んだ方が良い本。もともとはバーバラミントの『考える技術書く技術』であり、著者が翻訳を担当していた。翻訳を担当したからこそわかる、日本語へのビジネス文書のコツを分かりやすく網羅して、課題解決の考え方まで示してくれる。面白い上に、役に立つ。ぜひ読んで欲しい。
0投稿日: 2022.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書の書き方の基礎が書かれた1冊。 ●「読み手の理想とする状況・問題・疑問」を正しく読み取ることの重要性 ●日本語表現の曖昧さ の2点は今の自分になかった視点。 知らない間に、書き手側の都合しか考えていない文章になっていたかもしれない。 できる限り、簡潔で一文一義の文章を書くことを心がけたい
0投稿日: 2022.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』の訳者の方が書かれた入門書 内容としては1部、2部を分かりやすくまとめたうえに、「しりてが」などの論理的に曖昧な表現など、日本語話者ならではの注意点も記載されているため入門書としては十分な内容と思われます。 ビジネス文章を書くことに関しては、割と得意な方だと思ってたんですが、色々考えが足りてなかったことが分かったので、4カ月間ピラミッドチャレンジしてみようと思います。
0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文書を書くための考える技術、書く技術が書かれている本。 「ビジネス文書では何について書くのかを決めるのは読み手。 読み手の知りたいこと、関心に向けて書く必要がある。」 と本文に何度も登場するのが特徴。 そのため本家の考える技術・書く技術以上に、読み手を意識させるのが本書。恐らく相当に重要な部分なので、入門編として読み手を意識させることに注力したのだと受け取った。 意識させるだけでなく、具体的に読み手のOPQ分析を始め、ピラミッド(演繹法や帰納法)の決定要素や感謝のPDFといった、読み手を意識するフォーマットをいくつも提示してくれている。 もっと言えばビジネス文書だけでなく、ビジネスをする上で、もっと言えば人とコミュニケーションを取る上で読み手は常に存在している。 その相手を意識することで円滑に進むことは多くあると思う。(あえて無視する際も意識はしている) そして今は自分の中では意識することが習慣化できていない。習慣化するまではしっかり実践しながら参考にしていきたい。 具体的には1日1ピラミッド、1日1感謝のPDFは実践していく。
0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ【考える技術】 OP Q分析 鉄則 1.名詞表現、体言止めは使用禁止とする 2.「あいまい言葉」は使用禁止とする 3.メッセージはただ1つの文章で表現する 4.「しりてが」接続詞は使用禁止とする 【書く技術】
0投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすい文章を書くために読みたい1冊。 あなたの文章は読みにくい、わかりにくいと言われたときはぜひこの本を読んでほしい。 なぜ読みにくいのか、わかりにくいかがこの本を読めばきっとわかるはず。 自分も最初は文章が読みにくい伝わらないということが幾度もあった。もう少し読みやすく書いてほしいと言われてもどのような文章が読みやすいのかもよくわからなかった。 テクニカルライティング系の本を何冊か読んで、何を意識して書けばいいのかがだんだんと理解できて始めて読みやすい文章がわかるようになった。 そのようなことがこの本には1冊にまとまっており最初に手に取るには適切であると思われるのでおすすめです。
4投稿日: 2021.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に読みやすい内容だったが、文章を作るという上での本当の基礎で重要な考えがまとまっていた。高校や大学の勉強で満点を目指すにはまず小学生で習得するものを完璧に習得しなきゃいけないというような感じ。 なんとなく感覚でやっていたことを大人になった今この本を読み返すと勢いでやっていた書くという行動をより良いものに昇華させるための小さい気付きや改善すべきポイントを読みやすい文章の中から見つけ感じることができた気がする。
0投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人4年目・女性です。 正直、当たり前のことが書かれており、読み応えはなかったです。 サラッと読めたので、初心に立ち返る意味で節目節目に読むのは良いかなと思いました。 平易な文章と分かりやすい例で構成されているため、ビジネスコミュニケーションの経験がない学生さんや新社会人にはぴったりかもしれません。 こちらの元となった『考える技術・書く技術』も購入したので、比較して読んでみます。 ■参考になった考え方 ・演繹法/帰納法 ・OPQ ・so what?
0投稿日: 2021.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝わる文章の書き方と考え方がまとめられた一冊。 自分の考えを相手に伝えるのが難しい。 この本はその問題を解決する考え方や書き方を説明してくれている。 10年前に出版されている本にも関わらず、今でも充分に通用する内容。 1日10分ピラミッドを習慣化していきたい。
0投稿日: 2021.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキング本はいくつも出ているが、本書の良かった点。 ・薄くて文字も少ないので読みやすい。 ・一つの例に対して悪い例、改善例が記載されている。
0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想:ページ数は少ないが読みやすく、内容は凝縮されていた。特に、書く技術は学校では教えてくれない重要なスキルだと感じた。 ●文書は、相手方の立場になって書かなければならない。書き手が言いたいことをどんどん書くのでは相手は動かない。文書は相手に何かしてほしくて書いてるはずだから。 ●文章はピラミッドである。結論がきて、それらを証明する根拠、詳細を持ってくる。文章を書くことは何度もあるので、ぜひ1日一回は勉強として意識したい。 ●「しりてが」は使用禁止である。接続詞は文章を上手くまとめた気になる使いやすいワードであるが、主語述語、文書のつながりをわかりにくくする。 ●感謝の言葉にPDF、わかりやすい。感謝をまず伝えれば、相手にも動いてもらいやすいはず。あとは簡潔にメッセージを伝えればスムーズに業務が進むのではないかと思う。
0投稿日: 2021.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門とある通り、日頃からライティングを意識していない人に向けた本です。 私は社内へのメールこそスラスラ書きますが、社外に出す時は書き苦しさを感じていました。おそらく、ロジカルに文章が繋がっていないためでしょう。 社内宛では気にしていなかっただけ、そう思います。 同じような経験がある方は、読むと勉強になります。 ・読み手を意識して文章を書くこと ・ピラミッド原則を守って文章を書くこと ・so what?を繰り返すこと ・接続詞を意識すること 全てをいきなり吸収することはできませんので、ひとまずこのあたりに書いてあることを意識して文章を書くようにしています。 私はnoteを書いています。この本を読んでライティングを意識することで、PVに対するスキ率は上がりました。 ロジカルな文章はまだ習得できていませんが、読みやすさは格段に上がったのだと思います。
0投稿日: 2021.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ0 読んだ理由 (1) 本家を読める基礎が欲しいから。 (2) ロジカルシンキングのコツと技法を学びたい。 (3) 本家を読んで理解できる状態になりたい。 1 どんな本? ビジネスライティングの入門書であり決定版。定 番のロングセラー考える技術・書く技術を読む前の 基礎を固めるのに最適。コンセプトはビジネスを前 提にした読み手視点の文書での伝える技術。平易に 分かりやすく書いていると感じた。 2 構 成 序章、1〜4章、終章構成で付録有り。日本人のラ イティングに関する誤解の件から始まり、読み手視 点、考えるプロセス、文書での表現、日々の練習方 法で終わっている。付録で考えるプロセスのテンプ レを4パターン紹介している。 3 著者の問題提起 欧米ではライティングという科目が普通に有るが 日本では国語止まりである。したがって読み手視点 の文章を書く力が低い。ビジネスシーンでの弊害に なっている。 4 命題に至った理由 入社間もない頃の著者は文書を上司にダメ出しさ れるほどビジネライティングが出来なかった。そん な著者がライティングの教育を受けて問題は英語や 日本語では無く「考え方」にあると気がついた経験 から。 5 著者の解 ビジネスライティングを学んで、読み手視点、帰 納、演繹、ピラミッド、ロジカル接続詞を使った考 えるプロセスを学べばビジネスシーンで文書を書け るようになる。 6 重要な語句 (1) OPQA(目的、問題、疑問、答え) (2) レール(文脈、何の話をしてるか) ⭐︎(3) ピラミッド原則(考える過程と書く過程を分け る) (4) グループ化 (5) SO WHAT (6) 帰納法(結論は推論) (7) 演繹法(下文が正しければ上分も正しくなる) (8) しりてが(and) (9) 感謝の言葉でPDF(目的文、詳細、求めるアクシ ョン、自分のアクション) (10) 1日一回ピラミッド (11) 状況判断のwhy、解決方針のwhy、解決行動の HOW、whyとhowの三段論法 (12) ロジカル接続詞(論理関係を明確にする接続詞) 7 重要な文 (1) 主メッセージはQに直接答える。 (2) 人間は何かを認識するときグループ化する。 (3) グループを象徴するメッセージが要約メッセー ジ (4) 一つのメッセージから根拠や説明になるメッセ ージのグループを作る。 (5) 考えるプロセスは曖昧な言葉で妥協しない。 (6) 帰納法は同じ種類の考えかチェック (7) 演繹は第一前提文と2文の主語か述語はバトン パスをしているか。 (8) 段落の冒頭にその段落のメッセージをいれる。 8 感 想 この本を読んでいて頭の筋トレをしている感覚に なった。もうやめたいけど成長したいという気持ち で読み進めた。図が沢山あったので分かりやすいは ずが私のレベルではギリギリだった。1番刺さった 箇所は終章の一日一回ピラミッド。これなら出来そ うと言うかやりたいと感じた。人に薦めるなら最初 からかな。 タイトル通りの本だと思うけど本家を読んで確認し たいし、ピラミッドの理解も深めたい。 9 TODO 感謝のメールPDFと一日一回ピラミッド
0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスライティングの入門書にして決定版 相手に伝わる文章を書くためにの「考え方」と「書き方」の技術がコンパクトにまとめられています。もともとはコンサルタント向けの内容ですが、幅広く実用文章全般に応用できる内容です。特に、「読み手」の視点を重視する姿勢の大切さは大変勉強になりました。図解や文例(訂正前→訂正後)も効果的に用いられていて理解しやすいのもうれしいポイントです。
0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に、分かりやすいビジネス文書の書き方を教えてくれる本。 「明確なメッセージにするための鉄則」はかなり役に立つと思う(「あいまいな言葉」を使用禁止にする、など) 読めば、自分の文章の見え方が変わる
0投稿日: 2021.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログマスターするには演習あるのみ。 1日1回ピラミッド×4ヶ月か。まずチャット、メールを意識して書いてみよう。
0投稿日: 2021.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと分厚い一冊もありますが、まずは入門編を読んでみました。 ピラミッド構造で考えを構造化し、分かりやすく書く技術がまとめられています! 日本語ならではの注意点や練習問題も記載されており読みやすいです。 自分の「書く技術」が原則に従っているか、見直す機会になりました。
0投稿日: 2021.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで、レポートや文章の書き方の本を何冊も読んできた。結論から書くことはどの本にも書かれていた。 この本では、ピラミッド型など今まで読んだことのない書き方や伝え方がこの本には書かれていた。相手の立場になって考えることはどの分野であっても大切だということが分かった。 私は文章を書く能力がまだ低い。これから大学のレポートや就活で使えるように書く能力を高めていく。そのために毎日特訓していく。
0投稿日: 2021.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章を正しく書く事の重要性を感じ、本書を手に取った。 考え方や文章の書き方について、重要な内容のみに絞り込んで、具体例を踏まえて、丁寧に解説してあった。 読み手のOPQ分析、キーメッセージと下部メッセージの構造とルール、感謝+PDFがわかりやすかった。時折振り返って文章力の筋肉を維持しようと思う。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ【星:3.0】 ロジカルシンキングをベースにライティング技術を解説している。 どちらかといえばロジカルシンキングがメインといった印象である。 ただ、シンキング・ライティングの両方を解説しようとしているため、どちらの説明もやや深みに欠ける。 この本を読むよりもロジカルシンキングに特化した本を読む方が得るものが多いと思われる。
1投稿日: 2021.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯こんな人にお勧め 仕事で相手に説明する場面が多い人 ◯理由: 相手にわかりやすく説明するコツをつかめば、同じ内容でも結果が大きな差につながる。本書はそのグローバルスタンダードのコツを学べる。 ◯要約メッセージの鉄則 ①名詞表現、体言止めは使用禁止 ②曖昧言葉は使用禁止 ③「しりてが」の接続詞は使用禁止とする ◯英文に翻訳してもらう時の注意 ①メッセージを表現する文章は『and』は原則禁止。ロジカルな接続詞で繋がるように意識をする。 ②すべての文章に主語をいれる ③「見直し」などの曖昧なことばをなくす ◯今後実施すること OPQ分析:望ましい状況→問題→読み手の疑問の後に答えを書く 一度に覚えられる数には限度があるので上手なグルーピングを実施。マジックナンバー7±2を忘れない アウトプットの前に考える時間を確保(ライティングの上達はレポートを書いた回数に比例するのではなく、考えるプロセスをどれだけこなしたかに比例する)。構成さえきちんとしていれば、書く時にあれこれ悩むことはない。逆に途中で止まってしまうなら、それはきちんと考えられていない証拠
0投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングを何かしら齧ったことがある方にも、初めて触れる人にもオススメです。 なぜなら、最初に言及している「OPQ分析」という手法は社内外問わず、提案・報告・プレゼンなどをする上で欠かせない大前提の考え方だからです。 また、考えの「ピラミッド」を作るための注意点を、例題を用いながらとても丁寧に説明されているので、 基本の復習という意味で非常に良い本だと思います。 量も多くないので、気張らずに読めるので、時間がない方にもオススメです。
0投稿日: 2021.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
演繹法は「つなぎ言葉」でチェック。 なぜならば、なぜそう判断するかというと、たとえば、具体的には。。。という言葉でつながるのであれば演繹ロジックが成り立つ。 演繹の下部のメッセージ(事実)が同じつなぎ言葉で説明できるのであれば、概ね問題ない。 1つの考えを短く明快に! 1)名詞表現、体言止めは禁止 2)曖昧言葉禁止 3)メッセージは1つの文章で表現する 4)しりてが、接続詞は禁止 しりてが、とは、接続詞ANDでメッセージを2つ繋げないようにする。 ~し、~であり、~だが、~せず、~なく、など逆説と捉えるのか、因果を表しているのか曖昧になる。 ロジカルで分かりやすい文章は接続詞が重要! 英文ではANDをなくすと読みやすくなる。 ピラミッド構造は縦・横の関係性が重要であり、構造を紙のスペースなどに合わせて勝手に変更してはならない。
0投稿日: 2021.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手の立場での発信 複数いる場合は誰かにはターゲットを絞る OPQ分析→読み手の objective,problem,question ピラミッド原則 全体的に非常に分かりやすいです!
0投稿日: 2021.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス文章の改善のために学ぶには良書です。 ロジカルシンキングを先に学んでから本書を開くとグッとわかりやすくなります。 接続詞について述べている箇所が非常に参考となった。
0投稿日: 2020.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログあいまいな表現を使わない。 (見直し、問題、再構築) メッセージはただ一つの文で表現する。 改行のときに、一文字さげない。 しりてが、を使わない。 ロジカルな接続詞をつかう。
0投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文章を書く前に、考えるプロセスや構成を重視すること。 入門書として、ポイントを押さえてよくまとまっている本だと思います。 まずは読み手の関心を引きつけるという点、とても重要だと思います。ここを忘れがちな書き手が多いと感じることが多くあります。 章ごとに文章を書き上げるまでのステップをまとめているので、わかりやすい構成になっています。 このごろ何を言っているのかよくわからない人が多いように思います。文章を書く人だけでなく、最低限の会話を円滑にするためにも、伝えたいことがある人は一読すると良いのではないでしょうか。
0投稿日: 2020.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジネス文書は読み手の関心と疑問に沿って書かなければならない。 ポイント ・OPQ分析で読み手の疑問を確実に捉え、Qに対するAを主メッセージにする。 O…objective(望ましい状況) P…problem(問題) Q…question(OとPを受けた読み手の疑問) ・ピラミッド構造で要約メッセージを探しながら、各メッセージをグループ化する。 体言止め、曖昧な言葉、「しりてが」接続詞は使用しない 「だから何?」で要約メッセージを具体的にする 「縦に論理の繋がりがあるか」「横が同じ種類の考えか」で構造を確認する ※帰納法の場合、下部メッセージに同じ繋ぎ言葉を入れる 演繹法の場合、前提が「絶対的に正しいか?」を考える ・メッセージ文を冒頭に置いた上で、1段落1メッセージを視覚的にも表現する 今後のアクション ・感謝の言葉にPDFでメールを書く P…purpose statement(目的) D…detail(詳細9 F…follow through(今後のアクション) ・1日1ピラミッドを作る
0投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手の疑問・関心を意識して書いているか?ロジックピラミッドを作っているか?「しりてが」接続詞を使っていないか?勉強になった。
0投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログリモートワークが主流となったことを受け、文で人に伝える重要性が従来以上に高まったと感じ、読みました。 とても良書で、人に伝わる文書にはどのようなことに気をつけるべきか、気づけました。 OPQ分析、感謝の言葉にPDFですね。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ転職とリモートワークで文章を書く機会が増え、上司に勧められて。 シンプルな理屈に纏まっていて、理解しやすかった。読んでから書いた企画書は上司から文章自体の直しがなくなり、如実に効果を感じた。 ただこの本を読んでも読書した〜って楽しみや文章を読む楽しさはなかったので、わかりやすい文章と面白い文章はトレードオフだなと実感。
0投稿日: 2020.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人になってすぐ買って、読まずに本棚で眠っていた本。 この本の考え方のピラミッドを理解すれば論理的に考えられるようになり報告書も分かりやすく書けるようになる。 社会人なら知らずにやっている人も多いと思うが、考えたことがごちゃついてしまう人には一読することをおすすめする。
2投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手の立場で考える。 当たり前のようでなかなかできない、というか忘れがちなこと。 基本的なことですが、お陰で頭が整理された気がします。
0投稿日: 2020.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も読んでピラミッドを作り続けて自分の技術にしたい。 ライティングは相手が何を知りたいのかを知ることから始まる。よく仕事でも読み手を意識しろと言われるが、その方法を系統立てて教えてくれるのがこの本。 日本語は曖昧な表現が出来てしまうしそうなりがちな言語だからこそ自分の考えを整理する段階では曖昧な言葉(見直し、問題、再構築、、etc)や曖昧な接続詞(しりてが)を絶対に使わないようにする。
0投稿日: 2020.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ思考力の高まる本として、ネットで勧められていた本。 シンプルなタイトルと表紙からは想像できないほど、具体的、かつ、有効な内容が記されていた。 ビジネスマンの必読書です。 部下が出来たら間違いなくお勧めする本です。 出会えて良かった。
0投稿日: 2020.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ請求記号 336.55-ヤマ 資料番号 300521804 新潟医療福祉大学図書館 蔵書検索(OPAC) https://library.nuhw.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=1000095370&opkey=B158884036426005&start=1&totalnum=2&listnum=0&place=&list_disp=50&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=00
0投稿日: 2020.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社での書類を書く際に、読み手にわかりやすい文章を書きたくてこの本を読んだ。 読み手の疑問を明らかにするOPQ分析。 OBJECTIVE 望ましい状況 problem問題すなわち現状とOBJECTIVEとのGAP question読み手の疑問 answer答え 文書の主なメッセージ メッセージを絞りグループ化 ビラミッドの基本 帰納法でロジックを展開する 接続詞が大事! しりてがはなるべく使わない メールのポイント 感謝の言葉にPDF 感謝の言葉 purpose statement Detail follow trough
0投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
■感想 迷っているなら、読むことをお勧めします。 簡潔に纏まっていて、実践的な内容です。また、分量も少ないので半日で読めます。 本家バーバラミント女史の本をより日本人向けに、プラクティカルにした内容です。実は私は本家の方は挫折しているので、このような入門編を手に取ることができて大変助かりました。 ■要諦 入門 考える技術・読む技術 第1章 読み手の関心・疑問に向かって書く OPQ分析 Objective: (読み手の)望ましい状況 Problem:(読み手の)問題、すなわち現状とObjectiveのギャップ Question:(読み手の)疑問 Answer:(読み手への)答え/文書の主メッセージ OPQ分析のコツ 全て読み手視点で表現する 比較のレール(トピック)を外さない 文書の主メッセージはQ直接答える 第2章 考えを形にする メッセージ構造:グループ化 何かを認識するとき=読み手が情報を受け取るとき、僕たちは物事を様々なグループやカテゴリーに仕分けする。 なお、グループ化は帰納法のチェックで後述。 キーメッセージ キーメッセージは一般論にならないようにあうす 例:①天気予報は雨といった、②今朝早く、カエルがうるさく鳴いていた、③西の空には黒い雲がある→「今日は雨になるだろう」というのが要約メッセージ。「天気を予想するためには様々な自然現象の考察が必要である」では内容としては正しいが、要約にはなっていない。 要約メッセージを文章にするときの「4つの鉄則」 鉄則①:名詞表現、体言止めは使用禁止とする 例:「東南アジア市場の推移」のような体言止めだと、何について言いたいかはわかるが、何を言いたいかという中身には触れられていない。 鉄則②:「あいまい言葉」は使用禁止とする 例:「営業組織の見直しを提案する」→「東京大阪など大都市圏での営業人員を増大させる」/「営業戦略の再構築が必要である」→「営業戦略を、東京・大阪など大都市強化型に変更する必要がある」。あいまい表現とは、「見直し」「再構築」「問題」「適切な・・・」である。 鉄則③:メッセージは1つの文章で表現する 例:文章が2つあるならメッセージが絞られていないということ。 鉄則④:「してりが」接続詞は使用禁止とする 例:メッセージは1つの主語、1つの述語がベスト。日本語の特性上「してりが」は違和感なく聞こえるが、メッセージが2つになってしまう。「してりが」とは「・・・し、・・・」「・・・であり、・・・」「・・・して、・・・」「・・・だが、・・・」「・・・せず、・・・」「・・・なく、・・・」 BeforeAfter A社は倒産し、B社は黒字になった。 A社は倒産したにもかかわらず、B社は黒字になった。(逆説) B事業は赤字であり、今後も黒字化は期待できない。B事業は今後も黒字化は期待できない。(赤字であることは自明) あのマンションは、1000万円も値下げしてようやく売却できた。あのマンションは、1000万円値下げすることにより、ようやく売却できた。(因果関係) わたしの貯金目標は300万円だが、あと3ヶ月で達成できそうだあと3ヶ月で、300万円の貯金目標を達成できそうだ。(単文へ) 役員に若い人がおらず、ネット事業への取り組み意欲が低い役員に若い人がいないために、ネット事業への取り組み意欲が低い。(因果関係) So What?を繰り返す これは具体的なメッセージを出すために行うもの。 例:A事業は多くの問題を抱えている→A事業から撤退するべきだ 第3章 ピラミッドを作る 帰納法と演繹法 ビジネスの世界では絶対的に正しい前提があまりないため、一般的に帰納法の方がよく使われる。演繹法が使われるのは、「過去や現在の事実」に「正しい法則」や「妥当な仮定」(一般的に正しい)を適用して将来を予測する場合。 帰納法のチェック方法 「つなぎ言葉」をメッセージ文の冒頭に入れてやる 「なぜそう判断するかと言えば」「なぜならば」「例えば」「具体的には」をつけ、音読する。グループ内で同じ「つなぎ言葉」でいけそうなら、7割型問題ない。違和感があるなら、そこが論理的に問題。 演繹法のチェック方法 「前提」をチェックする。「本当に正しいと言えるか?」 ピラミッド作成のコツ コツ①:1つの考えを短く明快に 書き方は要約の4つの鉄則に従う。主メッセージとそれを直接支持するキーメッセージを早い段階で決める。ピラミッド内には1メッセージにする。文章化は別のステップで実施。 コツ②:縦と横の2次元を意識する 縦の関係は、結論と根拠・説明の関係になっているか。帰納法はつなぎ言葉チェック、演繹法は前提チェックが有効。 横な関係は、帰納法は、グループ内のメッセージに仲間外れがいないか。演繹法は、第1前提文の主語か述語が、第2前提文にバトンタッチされているか。 ピラミッド作成の罠 1対1ピラミッドの罠。 ビジネスには不確定要素が多く、ある前提を自明だと思い込んで、1対1のロジックを作ったが、前提が自明ではなかった。不安定な前提ではロジックにならないし、説得力も出ない。 一方、「大丈夫、前提は自明であり、疑問の余地はない」というのであれば、わざわざ1対1のピラミッドを作るまでもない。1つのメッセージの中で、ロジカル接続詞(後述)を用いた複文で表現すれば十分。 前提が間違っているケース ↓は設備投資したら、固定費増するので、必ずしも黒字になるとは言えない。 同じメッセージの繰り返しになっているケース 1対1のピラミッドで結論・根拠で同じ内容のメッセージになっているのはよくある。 例外:イメージによる説得 事例を取り上げて、キーラインを支持する場合は、1対1でも良い。が、論理関係はないので、線で繋がないこと。 読み手にとって既知なことは書かない OPQ分析においては、読み手目線なので、既知のことはノイズになる。特にキーラインでは書かないようにする。 第4章 文書で表現する 概要 メッセージごとの固まりが一目で分かるようにする メッセージごとに見出し、段落、箇条書きにするなど。 基本、各メッセージ文を固まりの冒頭に配置する ピラミッドのメッセージをそのまま形にする 主メッセージの位置を決める 冒頭か、最後 目次をどのようにつけるか 内容を匂わせる目次か、内容を匂わせない目次か。主メッセージの位置が前なら匂わせる方、最後なら匂わせない方。 文書のわかりやすさ ロジカル接続詞 ロジックの種類日本語英語 時間・・・する時にWhen ・・・する前にBefore ・・・した後でAfter ・・・するまでUntil ・・・して以来Since 対照・対比・・・である一方While, where, whereas ・・・であるけれどAlthough, though, even though, however 原因・結果・・・であるがゆえにBecause, since, as ・・・の結果So…that, such…that, as a result ・・・であるにもかかわらずDespite that, in spite of ・・・するためにはIn order that, so that 条件もし・・・ならばIf, in the event that もし・・・でなければUnless ・・・になるという条件でProvided that 「しりてが」接続詞の部分的な解禁 ピラミッドやメッセージ文には使用禁止だが、メッセージを支持・説明する補足説明文に限り、2つか3つまでなら見逃し可。日本語とは切ってもきれない関係なので。 英訳依頼時のコツ 「しりてが」を排除する、全ての文章に主語を入れる、あいまい言葉の排除 読み手を惹きつける「導入部」 OPQ分析を使って導入部を作ること。つかみなので、OPQ全てを網羅する必要はない。端折り、統合、表現変更、順序を変えてもいい。読み手を本文に向かって効果的にガイドできれば良い。 「結び」で今後のステップを示唆する ★3つのサンセットマークを使用するか、行間を取り、デッドラインとタスクを書く。 終章 メール劇的向上術 感謝の言葉にPDF 日頃の感謝、Purpose statement(目的), Detail(詳細), Follow-through(今後のアクション) 付録 ピラミッドの基本パターン
0投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログピラミッド形式でロジカルに主メッセージを伝える方法を非常に分かりやすく書いてくださってます。 バーバラミントの本筋の方で挫折した方にオススメです。
0投稿日: 2020.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ(心構え) ・読み手の「疑問」に答えること ・ピラミッド化→文章化 (実践すべきこと) ・感謝とPDF ・ピラミッド化の練習(4ヶ月)
0投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
バックグラウンド問わず必読。 個人的にはESに四苦八苦している就活生が読むと効果大。 明快な「発信術」のノウハウの全てが 豊富な具体例と共に記載されています。 以下、私的重要事項のメモです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●相手が求めている結論を最優先に書け ビジネス文書読む意図は何らかの課題を解決したいが故。 上手い文章ほど「相手視点」を大事にしている。 ●相手視点の獲得にはOPQ分析を用いよ O : Objective … 相手の望む理想状態 P : Problem … 理想状態と現状のギャップ(隔たりの要因) Q : Question … OとPから当然の様に予測される問い → Qに対するAnswerこそが主メッセージ ●主メッセージと下部メッセージの関係性に留意せよ 下部メッセージに求められる条件は2つ。 ①全て並列の関係である ②主メッセージの下支えである ●以下の様に読み進め、ロジックが通るかチェックせよ 主メッセージ→ロジカル接続詞→副メッセージ 【ロジカル接続詞の種類】 ①Why型 … なぜかというと〜である、その根拠は〜である ②How型 … 具体的には〜をすべき、そのためには〜が必要だ ●メッセージから曖昧言葉を徹底的に排除せよ。理由は2つ。①結局言いたいことが分からない ②理解に齟齬が生じ得る 【曖昧言葉の例】 適切な処置、〇〇が問題だ、検討の余地がある →So whatを繰り返し、曖昧言葉を明確な表現に。 ●メールは感謝 + PDF 感謝 → Purpose massage → Detail → Follow through 言い換えると、感謝→主メッセージ→根拠→今後のアクション
0投稿日: 2020.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の研修で薦められたため購入し、本日読了。 例文も豊富でサクサク読めた。 メールのPDFの流れで簡潔に表現すること。Purpose Detail Follow 文章構築の際、読み手のOPQにきちんと意識を向けること。Object Problem Question この2つを改めて意識をしていこう。
0投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み手を動かせる、読みやすくロジカルな文書を書くためのエッセンスがコンパクトにまとまっている。 すぐにできはしないので、実践が必要。その方法も提案されている。
0投稿日: 2019.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の文字数は少ないが、内容量は非常にボリューミー。 自分が何かを相手に話すというシチュエーションの全てに適応しうる手法だと感じた。ピラミッドを意識する訓練を今日からでも始めたい。
0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のためにメモ ・ターゲットとなる読み手を具体的に設定すること。 ・OPQ O: Objective 相手が目指している望ましい状況。 P: Problem 現状とOとのGap、解決すべき問題。 Q: Question 問題Pに直面した読み手が、その解決に向けて自然に抱くであろう疑問。 ・読み手を中心として「書く目的」を考えることにより、考えの中心軸を読み手にセットする。 ・考える時には、 名詞表現、体言止めは使用禁止とする。 「あいまい言葉」は使用禁止とする。→見直し、再構築、適切な、問題 メッセージはただ一つの文章で表現する。 「しりてが」接続は使用禁止とする。 → ~し、~であり、~して、~だが、 ・つなぎ言葉で機能的な論理的接続の矛盾をチェックする。 「なぜそう判断するかと言えば」 「なぜならば」 「たとえば」 「具体的には」 ・「前提」の後に、本当に正しいと言えるか?」と自らに問いかけることで 演繹的な論理的接続の矛盾をチェックする。 ・感謝の言葉にPDF 感謝の言葉 P:Purpose Message D:Detail F:Follow-Through -> 今後のアクション ・一日一回ピラミッドの薦め
0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ今日から実行しよう、「感謝の言葉にPDF」、「1日1回ピラミッド」。具体的な練習方法を、ハードル低く提唱してくれる良書だと感じた。しかも、前半の説明部分も、書き方の本だけあって、分かりやすい。基本的には、問題のある書き方と、何が問題か、どう修正するかを示している。 何かを書くときには、読み手の関心・疑問に向かって書く。 考えを形にする、ロジックを明確に。 日本語にありがちな問題点は、主語が曖昧だったり、抜けていること。それから、不明確な接続詞。 これを意識して精進しよう。実践が大切。
0投稿日: 2019.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ入門書としては良いと感じた。特にメールについてのことは役に立ちます。できる限りピラミッドを作りたいと感じました。
3投稿日: 2019.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログロジカルシンキングはピラミッド構造とかMECEばかりに目がいっていたが、まずOPQ分析。MECEは確からしさを見せるためのもの。納得できれば良くて、何も完全な漏れだぶりをなくすことが目的ではない。 接続詞に気をつける(しりてが)
0投稿日: 2019.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログピラミッド原則について分かりやすく書かれている。 まずOPQ分析で読み手の疑問を明らかにするという流れも、当たり前ながら日々できていないことを痛感する。 OPQ分析とピラミッドを癖づける。
0投稿日: 2019.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読んで、メールがいかに自分都合になっていたかを反省しました。 OPQ分析 感謝の言葉にPDF など、例文を多く含み、大変わかりやすく説明してくれている。 インプットするだけでなく、文書やメールが上達するには日々の練習が重要。
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ直感でしか喋れない自分にはほどよく勉強になりました。 訓練しないと自然にはできなそう。 手元に置いて時々見返したい。 <考える> ・読み手を主語にして「書く目的」を考える ・OPQ O:望ましい状況 P:問題 Q:読み手の疑問 ・「考える」上での日本語ならではの注意事項 1)名詞表現、体言止め禁止 2)あいまい言葉禁止(見直し、再構築、問題、適切な・・・) 3)メッセージはただひとつの文章で表現する 4)「しりてが」接続詞の禁止 ・帰納法 →結論が先でその下に前提がくる →前提(下部メッセージ)は必ず複数になる ・ピラミッド内に文章を書こうとしてはいけない <書く> ・ピラミッドをそのまま形にする(書く過程で考えない) ・いい目次は見ただけでピラミッド構造が目に浮かぶ ・ロジカル接続詞 時間 …する時に when …する前に before …した後に after …するまで until …して以来 since 対比 …である一方 while,where,whereas …であるけれど although,though,however 原因結果 …であるがゆえに because,since,as …の結果 so...that …であるにもかかわらず despite that 目的 …するためには in order that 条件 もし…ならば if もし…でなければ unless …になるという条件で provided that ・★★★=結びの合図(サンセット) ・メール:「感謝の言葉にPDF」 P:目的(Purpose) D:詳細(detail) F:今後(follow-through)
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章はいかに読み手を意識して、的確に述べられるかにかかっているかわかりました。そのための手段としてOPQ分析を用いるといった具体例を交えて説明されていたので、とてもわかりやすかったです。 またいい文章は自然とピラミッド構造が見えるというなので、私も文章を書く時はそれが見えるように意識しながら書くべきだと実感しました。 文章スキルはビジネスに限らず身につけておいて損はないと思うので、この本はとてもおすすめです。
0投稿日: 2018.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログバーバラ・ミントさんの考える技術・書く技術を実践するための日本人向けノウハウを凝縮した本。特に、最後の「感謝の言葉とPDF」は、わかりやすいメールを書くための必携のツールと思う。早速、明日から実践したい。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ提案書・報告書・ビジネスメール…書き方で評価が全く変わる! 投稿者 masnet (兵庫県) 世界中の一流経営コンサルティング会社でレポートを書く手法として広く採用されている「ピラミッド原則」(邦訳「考える技術・書く技術」バーバラ・ミント著)。 これを訳者自らが、日本語特有の落とし穴などを指摘しながら、日本人向けの入門篇として分かりやすく解説しています。 私たち日本人はついつい順を追って説明し、最後に結論を伝えたくなりますが、いかに読み手の視点に立って的を射た論理的な文章を書くか…その方法が非常に実践的に、事例・図解・練習問題などで示されています。 この薄さでこの内容の充実ぶりは素晴らしいと思います。 すべてのビジネスパーソンに必須の「使える」一冊です。
0投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「しりてが」接続詞使用禁止や、体言止めの使用禁止など、おそらく常識的なことなのでしょう。私にとっては目からうろこでした
0投稿日: 2018.11.04
