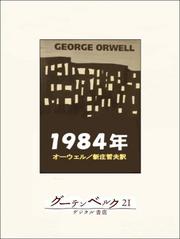
一九八四年
ジョージ・オーウェル,新庄哲夫
グーテンベルク21
様々なフィクションに影響を与えた、不朽の名作。
本作「1984」は、以後の多くの作品に影響を与えた非常に意義深い名作です。 基本的には、未来の全体主義国家において抑圧を受ける市民の生き様を描く物であり、当然ながらそのような国家像に批判的です。 20世紀からの贈り物として、21世紀を生きる我々が受け取る価値のある作品でしょう。 無論、1940年台の小説ですから、古くさいと思ってしまうかもしれませんが、本書から感じ取れるテーマは決して古くなく、今現在でも十分通じる内容です。あまり多くを語るつもりはありませんが、是非一度読んでみて下さい。
7投稿日: 2013.11.01
マリア様がみてる1
今野緒雪,ひびき玲音
集英社コバルト文庫
間口の広い少女小説。老若男女にお勧め。
本書は「マリア様がみてる」シリーズの第一巻です。 「マリア様がみてる」シリーズはアニメになり漫画になり実写映画にもなっておりますし、何より長期シリーズとして続いています。当然内容の面白さは折り紙付きです。 この、「マリア様がみてる」はコバルト文庫から出ていますので、少女小説になります。少女小説というと、なかなか敬遠する方も多い方と思いますが、実際にはこのシリーズは男性の読者も多く、それで居ながら特に男性に迎合している内容というわけではないので、男女どちらの方にもお奨めできます。 また、内容的にも特に過激でもなければ、妙にキャピキャピしたものでもありませんので、中学生から大人までの皆様にお勧めです。 人生で少女小説を一冊も読んでない、あるいは気軽に面白い物を読んでみたい、と言う方なら誰にでもお奨めできる、間口の広いエンターテイメント小説です。
5投稿日: 2013.11.01
脳が冴える15の習慣 記憶・集中・思考力を高める
築山節
NHK出版
言われてみると当たり前、だけど言われなければ意外と見過ごす。そんな忠告。
「定年退職してからは、毎日ゴロ寝してテレビを見てばかり居る高齢者」や 「いつも夜更かししてパソコンに向かう学生・社会人」 を見ると、『頭の動きが鈍ってそうだな』と思いますよね。そういう『頭に良くない行動』を指摘し『生き生きと生活出来るための行動』を教えてくれるのがこの本です。 というと「そんな魔法のようなテクニックがあるのか?」とお疑いでしょうが、本書で上げられているのは決して突飛なアドバイスではなく、比較的皆が納得しやすい物です。そして、その大半が「言われると納得だが、意外とやってない行動」だと思います。 単なる読み物としても面白かったですし、雑談のタネとしても良書です。また、著者は「高次脳機能外来」を担当されるお医者様なので、医学的な面でも内容に問題は無いと思います。 これから頭を使う機会の多い学生や社会人、そして頭の動きを若々しくしたい中高年の方にお奨めしたい本です。
5投稿日: 2013.11.01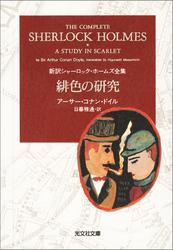
緋色の研究
アーサー・コナン・ドイル,日暮雅通
光文社文庫
日暮雅通 訳 のシャーロック・ホームズ シリーズ 最初の1巻
日本を代表するシャーロッキアンの日暮雅通氏が翻訳されたシャーロック・ホームズ シリーズの長編第一巻が本作となります。 シャーロックホームズを読んだことがない。そして、なにから読んだら良いか判らない。と言う方には、本作を自信を持ってお奨めします。 残念ながら、私は全てのシャーロック・ホームズ シリーズの邦訳版を読んだというわけではありませんが、私の読む限り、日暮雅通氏の訳は非常にこなれて読みやすかったです。 また、シャーロッキアンである日暮雅通氏の注釈が数多く入っているため、「19世紀末から20世紀初頭のロンドン」という今の我々には貨幣価値すらよく分からない世界が、身近に感じられること請け合いです。 少なくとも、私はこの本に出会えて最高にシャーロックホームズを楽しめました。あなたもいかがですか。
2投稿日: 2013.10.25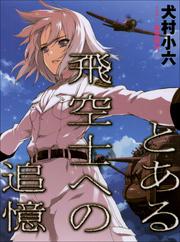
とある飛空士への追憶(イラスト簡略版)
犬村小六,森沢晴行
ガガガ文庫
身分差のあるボーイミーツガール。その結末は意外かもしれない。
「とある飛行士への追憶」ご存じの方も多いかと思います。 ご存じでない方のために言うと、これは、 犬村小六先生の「飛空士」シリーズの最初の作品になります。また、本作は映画化もされました。 ということで、お分かりの通り、シリーズ化され、映画化もされているので、つまらないはずなど無いのです。状況証拠的には、最高に面白いはずです。 このレビューは推理小説ではないのでハッキリ言いますが、状況証拠通り最高に面白いです。 身分差のあるボーイミーツガール物語ですので、他のライトノベルでも良くある設定かもしれませんが、結末はちょっと珍しいタイプのオチかもしれません。 試合に負けて勝負に勝った型の爽快な読後感を味わえます。 ライトノベルをほぼ読んだことない人、ちょっと変わったライトノベルを読みたい人にお勧めです。
1投稿日: 2013.10.25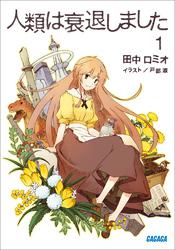
人類は衰退しました1(イラスト簡略版)
田中ロミオ,戸部淑
ガガガ文庫
ゆるいSFラノベ。初ライトノベルとしては無難な選択。
タイトルの通り、人類が衰退した世界を描くライトノベルです。といっても、人類衰退系世界観の他の小説等と比べると、比較的明るい描写が多く、決して暗い気持ちにならずに読みすすめる事が出来ると思います。 ライトノベルを読むことの多い人向けに言うと、「キノの旅」が好きな人などは、楽しんで読めるかもしれません。 ライトノベルを読んだことのない人に向けて言うと、いわゆる「美少女が出てきて、エッチなことがあったり、よく分からない超能力バトルをする」みたいな作風ではないので、そういうのを期待してる人には向かないでしょう。 どちらかというと、「イマドキの児童文学」とでも言うつもりで読むと、楽しいかもしれません。 ライトノベルを読むのが初めてと言う方には、比較的オススメできる部類の作品です。
3投稿日: 2013.10.19
氷菓
米澤穂信
角川文庫
爽やか青春ライトミステリー。本作と一緒に次作「愚者のエンドロール」もオススメ。
この<古典部>シリーズ、ライトノベルとして生まれ、このように通常の角川文庫からも出て、さらに漫画やアニメにもなっていることでお分かりの通り、かなり面白いです。 漫画やライトノベルやアニメは苦手、という方も居るかもしれませんが、どちらかというと、NHK教育のドラマの原作になってもおかしくない爽やか青春ライトミステリーなのが本作です。 ですので、比較的多くの人から受け入れやすい内容になっていますし、実際読者・視聴者層向けに多数のメディアミックスが為されています。 本作に関して言えば、個人的には古典部シリーズの中では、それほど出来が良いと思ってません。(あ、言い切っちゃった) でも、次作以降ドンドン面白くなってくるので、ここは我慢して本作「氷菓」を買いつつ、一緒に次作「愚者のエンドロール」を購入してはいかがでしょうか。 それに、本作が次作以降に比べて劣ると言っても、次作「愚者のエンドロール」が99点なら本作「氷菓」は80点ほどです。実際、本作もかなり面白いです。 是非本作「氷菓」を……と言うより次作「愚者のエンドロール」以降を楽しむために「氷菓」を手に取ってみて下さい!
1投稿日: 2013.10.19
ループ
鈴木光司
角川ホラー文庫
「リング」「らせん」シリーズの完結編。世界観が前作から大きく変わるが面白い。
「貞子」は2013年の今でも映画になったりして、かなり長生きしているキャラクターですので、皆様もご存じでしょう。 その「貞子」が出てきた「リング」「らせん」の完結編が本作「ループ」になります。 実は、この作品「リング」や「らせん」と大きく世界観が異なります。どう異なるか書いてしまうとネタバレになりますが、とにかく違います。世界観どころか、小説のジャンルまで違うと言って良いでしょう。 それに本作は、「リング」「らせん」と異なり、映像化されていません。というと、なにやら本作が駄作であるかのように聞こえると思いますが、決してそうは思いません。 私も、本作を読んだとき大変驚きましたが、つまらないとは思いませんでした。「リング」「らせん」とは異なるおもしろさが確かにあります。 「ホラー小説以外は一切読みません」という人にはオススメできませんが、「ホラー小説が好きだが、他のも読む」とか「いろいろなジャンルの小説を読む」という人なら、凄く楽しめることは間違いないです。 是非、「リング」「らせん」を読んだ上で、それとは趣の違う楽しさを本作「ループ」から味わって下さい。オススメです。
1投稿日: 2013.10.19
日本沈没(上)
小松左京
光文社文庫
日本を舞台にした、最高のパニック小説
「日本沈没」このタイトルを聞いたことの無い人はいないでしょう。 タイトルを聞くと「なんと荒唐無稽な」と思われるでしょうが、作中では何とも綿密なロジックにより、この無鉄砲な展開に岩山の如き説得力を持たせています。 そして、リアリティがあるのは沈没のメカニズムだけでなく、「日本沈没」という決定的破滅に向き合った日本人たちの生き様、これにも大変な現実感、生々しさが見られます。 タイトルがネタバレになっている以上、ハッキリ言いますが、確かに日本は沈没します。しかし、日本人たちは作中で何とか生き延びようとします。彼等の生存への闘争・努力、そして希望を得る姿を追体験できるという濃厚なひとときを楽しみました。
5投稿日: 2013.10.18
バカの壁(新潮新書)
養老孟司
新潮新書
10年立っても色あせない、養老先生のエッセイ
養老孟司先生は、医学的な専門知識を元に社会やココロを語るエッセイを多く書かれ、一度は皆様も名前を聞いたことがあると思います。 控えめに言って、「20世紀末から21世紀初めの、文理横断的な大衆向け読み物を書く知識人」と言ったら、多くの人が思い起こす人でしょう。 もし、養老先生を知っていて本書「バカの壁」を読んだことがないなら、是非読んで下さい。(恐らく)養老先生の著書の中では一番売れていますし、実際楽しく読めるエッセイ集です。 逆に、養老先生を知らない、著書を一切読んだことない、と言う方は、是非これを機会に読んでみてはいかがでしょうか。 無論、エッセイ集ですので重厚な知識の獲得等には向きませんが、「そう言う考え方もあるか!」「それは知らなかった!」という楽しみは、必ずあると思います。
8投稿日: 2013.10.18
アトムヘアーさんのレビュー
いいね!された数61
