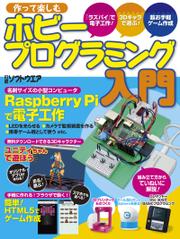
ホビープログラミング入門(日経BP Next ICT選書)
日経ソフトウエア
日経BP Next ICT選書
いろいろ遊べる内容が満載
紹介文の1部〜7部の内容を見てわかる通り、幅広い内容を扱っている。 ラズベリーパイやSphero、さらには3Dプリンタといったハードウェア色が濃い部と、Unity 3Dなる総合開発環境使った3Dグラフィックコンテンツの作りかの紹介まで読むだけでも楽しめた。 どの部でも、PC一台とモノがあれば実際の演習を出来るようになっているので興味のある内容については実際に自分で試すことが出来る。 個別の内容については、どうしてもそれを詳しく扱った書籍よりも情報量は少ない。でも載っている内容が少ないからといって薄いわけではなく、上手く美味しいとこ取りをしていると感じた。 プログラミングの覚え始めくらいの人でも、遊び感覚で出来ることがいっぱい載っているので楽しめた
0投稿日: 2016.05.15
サッカー データ革命 ロングボールは時代遅れか
クリス・アンダーセン,デイビッド・サリー,児島修
辰巳出版
ゴールの価値は一定では無い!!
サッカーで、ゴールの価値が変動すると言われて、興味を惹かれた本。 ゴールの価値は、1点で価値は必ず1点だと信じていましたが、「サッカーの目的はゴールを決めて勝利をすることであり、シーズンでの成績を残すことだ」と言われれば、なるほど1点目と4点目のゴールの価値が異なると予想できる。 そのほかにも、シュート数は多ければ多いほど良いのか? 成績の上がらない監督はなるべく早く更迭すべきなのか? 高額のストライカーは無理をしてでも雇うべきなのか? といった疑問に対してデータ分析によって事実を明らかにしてくれる。 統計学の手法を用いた分析で、サッカー界で常識とされていた事実に鋭く切り込んでいく。 ゴールの価値を分析することで、メッシの様なスターストライカーの働きとディフェンダーの働きが勝利に対してどう影響を及ぼすかを考えることが可能になり、勝つ為には、多額のお金を積んで、スターを揃えるか、ディフェンダーの補強をするか?選手の育成をするか?クラブ運営に関わる問題にまで、ピッチ上の分析を通して鋭く切り込んでる。 基本的にはサッカーに関する本だけれども、サッカーの監督がどうチームのマネジメントを行い、それがピッチ上でどう現れたかについても分析を行っている。監督のマネジメント分析ではサッカーの枠を超えて、ほかの競技にも共通する示唆が多く含まれていた。 例えば、プレーでも人格的にも優れた選手が、他の選手に与える影響は大きく、優れた選手が他の選手の能力を引き上げようと努力した場合、チームが負けなくなる確率が上がる。逆に、プレーだけに優れていても他者を引き上げる努力をしない選手のいるチームは、負ける確率が上がってしまうのだ。監督は、そういったことを踏まえて補強の判断をする必要がある。 こういったマネジメントの影響を数字を元に明らかにしている点で、この本はサッカーに関心のある人だけでなく、ラグビーなどの他の競技者、さらにはビジネスマンも興味深く読めると思う。
0投稿日: 2016.04.23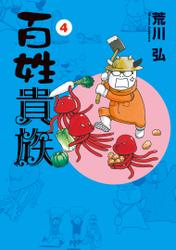
百姓貴族(4)
荒川弘
ウィングス
酪農あるあるは普通こんなに面白いものなのか?
どうしてこんなに笑えるのか?腹がよじれる。 酪農あるあるネタで、農家の結婚式あるある、作者のオヤジさんの不死身あるある?。などなど。 そろそろネタが尽きてくるんじゃなかろうか?なんて心配をよそに大爆笑の渦に巻き込まれた。
1投稿日: 2016.04.10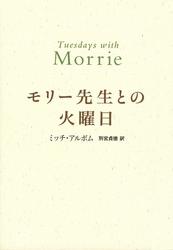
モリー先生との火曜日
ミッチ・アルボム,別宮貞徳
NHK出版
ラグビー日本代表HC エディ・ジョーンズお勧めの一冊
ラグビー日本代表の躍進をさせたHC エディ・ジョーンズお勧めの一冊。 内容については、特にラグビーや勝負に関わる話ではないが、人生の意味について考えさせられる。 著者とALSの老教授とのやりとりを通して通して、幸せな人生がどんな人生なのかを諭された。 自分の意見を持ち、それを自分で考えながら実行していく事が大切だという事を教えてくれる。
1投稿日: 2016.04.09
工具の本 総集編
ル・ボラン編集部
学研
好きな人にはたまらない
車で使用される工具についての内容が多い。 いろいろな工具メーカのすぐれた工具を眺めるだけでもなかなか面白いが、各社のコメントも自分たちの道具をどんな設計思想で摂家しているか?何を目指しているのかなどのコメントから滲み出る誇りが渋い。 世界ラリー選手権(WRC)メカニックの工具の内容が面白かった。
2投稿日: 2016.04.09
遠い太鼓
村上春樹
講談社文庫
ローマの縦列駐車は1日に見ていても飽きない。らしい。
ヨーロッパの国々に暮らしている人たちの生活は、それぞれ少しづつ時には大きく異なっていてその一つのエピソードにイタリアはローマでの縦列駐車のくだりが出てくる。 ローマでの縦列駐車は日本でのそれとは大きく違っていて、とても入らないんじゃないかと思うようなところに入れると拍手が起こったりする。そういう日常のなかの感覚のズレを著者の視点を通して分析しているのがとても面白い。 縦列駐車が面白いだなんて日本にいたら絶対に思わないのではないか? そういうどうでも良いエピソードを通しての考察は抱腹絶倒モノ。
0投稿日: 2016.04.03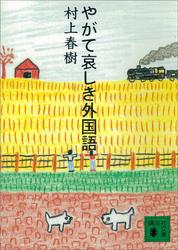
やがて哀しき外国語
村上春樹
講談社文庫
海外に長く住んだ著者にしか分からない、日常の微妙な変化について
やっぱり、マラソンでいろんな場所を走っているんですね、村上さん。 マラソン一つとっても、日本とアメリカだと違うし、ボストンとプリンストンだとこれまた違ったりするらしい。マラソンなんて走るだけなんだから、日本の大会でもアメリカでも一緒でしょ?理屈上はそうです。一緒なんですよね。 でも、走るという単純な行為を42.195km続けるという意味では世界中どこにいても同じだけれども、開会式からスタートの仕方、給水所の運営方法、一緒に出場しているランナーの服装や走り方をとってみると大きく違ってくるというのは確かにそうなんだろうと思う。 日本の当たり前なマラソン大会と、アメリカの当たり前なマラソン大会は大きく異なるし、どちらかのマラソンに慣れてしまうと別の大会に出た時は大きな違和感を抱くことになる。 そういう違和感についての分析がとても面白かった。 そういう何気ない違いが、著者の創作システムに影響を与えているらしいというのも興味深かった。
2投稿日: 2016.04.02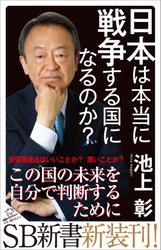
日本は本当に戦争する国になるのか?
池上彰
SB新書
事実ベースで何処にどんな問題があったのかが面白く読めた。
今年の夏に問題となった安全保障関連法案。 そもそもなぜ安全保障関連法案の整備をしなければならなかったのか?賛成派と反対派はそれに対してどのようなアクションを取っていたのか? 新聞を読んだだけでは知らなかった事実があることを初めて知った。 賛成派、反対派、報道それぞれに問題があったことが分かる。 2015年の夏にどんな事があったのかを知りたいと思った時に読みたい本
1投稿日: 2015.12.12
走ることについて語るときに僕の語ること
村上春樹
文春文庫
走ることの意義について、肯定的になれる
著者は小説家で仕事はランナーではない。 しかし、走ることにたいする熱量はかなり大きく、サブフォーをやっと達成している私から見るとかなり偉大なことを実現しているように見えた。 ごく個人的な長距離競技の話のはずなのだが、その心構えやランニングに対する考え方は多くの人が共感し、参考になる。 ランニングをしているときに、何故こんなことをしているんだろうという気分になったら、この本の事を思い出したい。 自分が納得するまで努力したという手応えは、人生に何らかの良い変更をもたらすように思えた。
2投稿日: 2015.09.13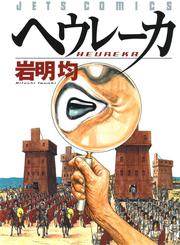
ヘウレーカ 1巻
岩明均
ヤングアニマル
アルキメデスの生きた時代の見た事もない戦争。
アルキメデスが生まれたのは紀元前287年らしい。 私が想像する紀元前の戦争といえば大きな丸い盾と長い槍を持った屈強な男たちが戦う姿だったが、この漫画ではアルキメデスの発明した兵器が大活躍する。 紀元前の技術で実現される兵器を見るだけでも楽しめる。 そこに岩明均の描く人間ドラマが展開されるので、読み応えがありとても面白かった。
0投稿日: 2015.09.11
oka_1008_jさんのレビュー
いいね!された数15
