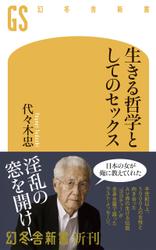
生きる哲学としてのセックス
代々木忠
幻冬舎新書
「監督、女をわかってないわね。」
本書は御歳八十歳のAV監督が記した自叙伝?のような本です。 著者はその筋では有名な人、なのかな。 カマトトぶるわけではないですが、当方野暮天ゆえ著者の本業の世界についてはあまり明るくないのでござる。 いや本当。 わたくしとて男子のはしくれ、AVぐらい観たことはあります。 でも、著者の監督作品を観たことがあるのかと問われれば、正直よくわからんちんです。 本書の内容はというと、永年AVの現場にたずさわってきた者としてそこで得られた知見を通して、性について、男女の仲について語っています。 構成としては、一つの方向に向かって話が進んでいくというわけでもなく、どこか散文的というか、ある種徒然草のようなまとまりのなさが感じられます。 「徒然草のような」とは、徒然草ってあっちとこっちで言ってることが真逆だったりする箇所が多々散見されますが、それがマイナスにはなっていませんよね。 整合性はないけど妥当性はあるというか。 要はアレです。あの感じです。 また、おじいちゃんの自慢話のような、時代錯誤のような箇所も正直あります。 そもそも、本書そのものがAVの現場で出会った人たちを通して性について語っているわけで、そりゃああなた、ある特殊な人たちを例にあげて普遍的一般的なことを語ろうとしても無理があるでしょう、てなハナシでもあります。 ただ、そういったマイナス面を責める気にはなれません。 読み手である当方がそこを差し引いて読めばいいだけのこと、そう思います。 あくまでここで表されているのはこの著者がその生涯をとおして手にした知見なのですから、無理にきれいにトリミングする必要はありません。 このままで全然結構です。 とはいえ、はてさてこの本をどう評価したらいいものか。 誰かに勧めたくなる本、というものではないような気がします。 同時に誰かにこの本を読んでもらいたいな、という思いもあります。 あいつとあいつにはこの本読んでもらいたいな、そうすれば風俗通いなんかやめてもっと奥さんのこと大事にするんじゃないかな、そんな思いも浮かんだりしました。 でもどうでしょうか。この本を読んで何かを得る人はそれ以前にもうそれを得ている人のような気もします。 また、エロにつられてこの本を読んで、何かを得たつもりにだけなって本当は何も得ていない、そんな人も出てきそうな気もします。 どうなんでしょうね。 なんだか奇妙なプレゼントを受け取ってしまったような、そんな感じです。 これをボクにどうしろというんですか。 どうもしなくていいんですけどね。 あと女の人はこの本を読んでどう思うんだろう。 やっぱり今も「監督、女をわかってないわね。」って言われちゃうんでしょうか。 なんだかそんな気がしないでもないです。 ちょっとだけ気になります。
0投稿日: 2018.11.01
クルマを捨ててこそ地方は甦る
藤井聡
PHP新書
羊頭狗肉である。
タイトルに興味をもち購入しました。 しかし結果としては、「羊頭狗肉」と呼ぶにふさわしい著作でした。 本書の内容をまとめると 「地方の中核都市レベルの都市であればクルマ利用の抑制について対応をするといいことがあるかもしれないが「負け戦」で終わることも覚悟しておく必要がある。あとそれとは別に、一般論として、あまりクルマに頼りすぎた生活をしているとなんらかの支障がでるかもしれないので注意すべし。」といったものです。 以上です。 本当にこれ以上のものは含まれていません。 タイトルが悪いんですね。 だって「クルマを捨ててこそ地方は甦る」というタイトルですよ。 そういう内容を期待しちゃうじゃないですか。 でも実際には タイトルでは「クルマを捨ててこそ」といっていますが、実際には「クルマとかしこくつきあう」ことを推奨しています。 タイトルの「地方」は、本書では、一般的な「地方」のことを指しているのではなく「県庁所在所レベルの地方都市」を指しています。 「地方は甦る」というものの、その効果は実は疑わしいものであることを著者自身が自覚しています。 第5章の中で「・・・そのために、地方政府や地域社会は、京都市や富山市のように、半ば「負け戦」を覚悟の上で戦う心持ちで、一つひとつの交通まちづくりの取り組みを最大の戦略性を持って展開する姿勢を、持続しなければならない。」とあります。 「負け戦」を覚悟の上で。 何をかいわんや、です。 タイトルは著者ではなく、出版社の人が決めたのかもしれません。 そう考えれば、タイトルと中身との解離をとやかく責めてもしょうがないのかもしれません。 しかし、中身についても少々、いや大分お粗末であるといわざるをえません。 最終章(「おわりに」)の中で、20代後半に留学を経験して以来、自分の中での最も大きな研究テーマの一つだったのが、本書で論じた「かしこいクルマの使い方」の問題であった、とあります。 著者略歴をみるに、1968年生まれとあります。 二十年余の研究の成果がこの内容なのでしょうか。 本当にそうですか。 「やっつけ」で作った本なのではないか、なんとなくそう感じます。 人とクルマの現在の関係についてある種の危機感を持っている。 それはわたくしも著者の方と思いを同じくするものです。 でもそこで感じている危機感の本質やその解決に求めるものはちがっていたようです。 老婆心ながらですが、もしこの本の購入をお考えでしたら、著者のファンの方ならしらず、そうでなければおやめになったほうが宜しいかと存じます。 おそらくはそのほうが著者の為にもなるかと存じます。 紙の本ですが「<小さい交通>が都市を変える」大野秀敏、佐藤和貴子、齊藤せつな著(NTT出版)という本があります。 これは有益な本でした。 個人的にはこちらをお勧めします。 読後のあと味が悪すぎたのでつい毒舌になってしまいました。 著者の藤井聡さん。 いろいろとご活躍の方で著書も多数おありのようです。 優秀な方なのでしょう。 今回たまたまハズレをひいてしまっただけで、他の著作では有益なものもあるのかもしれません。 ただ個人的にはもういいです。 さよなら。
0投稿日: 2018.09.12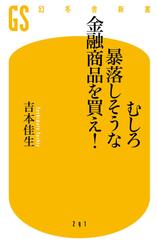
むしろ暴落しそうな金融商品を買え!
吉本佳生
幻冬舎新書
あなたが働かないのにおカネが働いてくれることはない。
平成24年11月刊行の本です。 内容が古いかというと、そうでもありません。 タイトルこそ乱暴ですが内容はいたって真っ当なものです。 「長期投資」「分散投資」は今となっては有効でなくなったこと、ここをメインに話が進みます。 本書はお金儲けの指南本といっていいでしょうか。 ん~どうでしょう。 わたくし的には指南本と言ってよいように思いますが、人によってはちがう感想をもつかもしれません。 「第3章 分散投資ではもはや資産は守れない」での分散投資についての現状分析は、なんとはなしに感じていた点であり、そこを論理的かつ周到に説明してもらって、目からウロコかつ我が意を得たりとの感想をもちました。 また、長期投資について、おそらくですが今(2018年9月)から10年くらいにさかのぼってみてみれば、このスパンでの長期投資で成功している人は、実は多いかもしれません。 そういった人たちにとっては長期投資はいまなお有効な投資方法であると感じているかもしれません。 いまの経済がバブルだとは思いません。 でも油断は禁物です。 あるいはそろそろ暴落を迎えるのかもしれません。 これは杞憂かもしれませんが、そのような危機意識をもつことの重要性を、本書は主張しているようにも思えます。 「第6章 『暴落しそうで不安だ』と思う資産のほうが安全?」のおしまいのほうに、 「徹底してリスク管理を考えながら投資を続け、致命傷を避け、いつかバブルに乗って大儲けをするチャンスを狙うのが、今の世界の金融市場に適した投資だと、筆者は考えます。」 とあります。 わたくしも同意いたします。 なおまったくの余談ですが、読みながら、ナシーム・タレブの「ブラックスワン」や「反脆弱性」を思い出していました。 その主張に類似性があると思います。
1投稿日: 2018.09.05
なぜ皮膚はかゆくなるのか
菊池新
PHP新書
頭の中はカユくなるのか?
はてさて、これは困った本です。 いや、ほめるところがないということではありません。 中身が不明瞭であるというわけもありません。 その逆で、たいへん明快ですしおもしろい内容です。 ただなんというか、どうほめたらいいのかわからない本なのであります。 この本は「かゆみ」についての本です。 おそらく、対象としている読者層はアトピーで悩んでいる人やジンマシンで悩んでいる人たちなのだと思います。 そういった、一般の本好きというよりも切実な問題意識を抱えている人向けの本だと思います。 そして、そういった人たちにとってこの本はたいへん有益な本だと思います。 でも、決してそれだけではない、もうちょっと広くて深いものをこの本は含んでいる、そんな風にも思えるのです。 それがどういうものであるかとというと、ちょっとまとめにくい。 気になったエピソードはたくさんあるけどどれか二つ三つ挙げてみてといわれると、どれをどう伝えていいか迷ってしまいます。 アンポンタンな話です。 たとえるのならそう、脳科学の本にすこし似ているような気がします。 脳科学についての本は世にあまたあります。 興味深いエピソードがたくさんあって、身につまされたり考えさせられたりします。 みんな大好き脳科学といった感じで、一般の本好きが普通にそれを楽しむことができます。 この本もそんな脳科学の本に似た、そこからふくらませてちょっと哲学的なことまで考えてみたくなるような、そんな本であります。 もちろん著者の方はそういう読み方楽しみ方までを想定しているわけではないと思うですがどうでしょうか。 中島らもさんのエッセイ集で「頭の中がカユいんだ」という本があります。 タイトルだけお借りしてなんですが、この本はまさに頭の中がかゆくなる、そんな本です。 (追記) 目次(章立て)をあげてみます。 この本の射程範囲(?)がだいたいわかると思いますので。 <以下目次> はじめに 第1章 かゆみの本能と感覚 第1項 ”掻くと気持ちいい”の本能を考える 第2項 かゆみは特殊な感覚 第3項 「かゆみ」と「痛み」の微妙な関係 第4項 「痛み」は素早く、「かゆみ」はトロい 第5項 「心」がかゆみにおよぼす影響 第6項 掻くとさらにかゆくなるもの 第2章 ”無性に”かゆくなる皮膚のしくみ 第1項 原因がわかるもの、わからないもの 第2項 かゆみの主犯格、「ヒスタミン」と「マスト細胞」 第3項 アレルギーの最初におこること 第4項 どのようにして脳に伝わるのか 第5項 掻くとさらに、かゆみを感じやすい体になる 第6項 かゆみを増幅させる装置 第7項 掻かずにかゆみを抑える 第8項 異常な知覚と、どう向き合うか 第3章 医者にかかる前に知っておきたい治療法 第1項 現実には知識のない医師もいる 第2項 虫刺され・かぶれ・日やけは、表皮のダメージ 第3項 じんましんのかゆみは、ヒスタミンが原因 第4項 乾皮症や乾燥肌は、かゆみ過敏状態になっている 第5項 慢性湿疹・金属アレルギーは、まず原因の除去から 第6項 アトピーは、ステロイドだけでは治せない 第7項 ヘルペス(単純疱疹・帯状疱疹)には外用薬はあまり効かない 第8項 かゆい水虫もかゆくない水虫も、治療の基本は同じ 第9項 しもやけは異常感覚 第10項 目のかゆみには抗ヒスタミン剤が効く 第11項 むずむず脚症候群は、中枢性のかゆみか? 第4章 かゆみにまつわる実際の症例 第1項 実際の皮膚科診療の現場では 第2項 症状1 アトピー性皮膚炎[30代 男性 二人の例] 第3項 症状2 金属アレルギー[42歳 女性] 第4項 症状3 慢性じんましん[56歳 男性] 第5項 症状4 子どもが抱える皮膚トラブル[0歳児] 第6項 症状5 毛染めの薬品にアレルギー反応[70歳 男性] 第7項 症状6 ひどい掻きぐせ[8歳 女児] おわりに 参考文献
0投稿日: 2018.06.22
仕事に効く、脳を鍛える、スロージョギング
久保田競
角川SSC新書
とりあえず今日からちょっとだけ走ってみましょう。
ボリュームもそう多くなく、文章も読みやすいです。 そうですね、2・3時間くらいででさくっと読めます。 奥付をみると、2011年11月5日第三刷を底本として2012年1月1日に電子書籍として発行、とあります。なのでいま(2018年)からみると少々古い本です。 とはいえ内容的に時代遅れという訳ではありません。 ゆっくり走るといいことあるよ、走るときはフォアフット走法で走るといいよ、こういったことが書かれています。 「Born To Run」(クリストファー・マクドゥーガル著 NHK出版)や「脳を鍛えるには運動しかない!」(ジョンJ・レイティほか著 NHK出版)を本文の中で紹介・引用しています。 上記の出版時期からいって、この辺の話が話題になっていたころに、これらの内容を若干希釈して読みやすくし、そこに本著独自の視点や解釈を加えている、そういった本づくりをしているのだろうなとの印象を受けました。 子供のころの体育の授業にいやな思い出がある人は少なくないと思います。 運動なんて疲れるししんどいしなんか嫌だな、といった人も多いと思います。 でもそういいつつ、体を動かすことは楽しいことだ、ということをわかってもいます。 スポーツもそうだしダンスもそうだし、音楽に合わせて頭を揺らしたりするものそうです。 なんだかんだいっても体を動かすことは楽しかったり気持ちのいいことだったりするものです。 そんななか、ゆっくり走るあるいは無理なく走る。これが一番手っとり早くて一番人に適した運動なんだろうな、そう思わす内容でした。
0投稿日: 2018.05.15
脳は回復する―高次脳機能障害からの脱出―(新潮新書)
鈴木大介
新潮新書
井上陽水は「氷の世界」の頃、アフロヘアーでした。
本書は、不幸にも脳梗塞を引き起こして高次脳機能障害を負った方の体験談です。 前著に「脳が壊れた」という本があります。 前著もそうでしたが本書は、内容はかなりシリアスなものですが読みやすい文章で書かれています。 著者は本書において、脳梗塞からのサバイバーとして発言・提言されています。 個人的な体験をベースとして、自分が抱えることとなった様々な障害や症状を分類し、その特徴を説明し、その対処法や解決法を探っています。 言ってみればこれらは「切れば血の出る生身の言葉」です。 ここに本書の主眼があります。 また著者の職業は取材記者であって、これまで職業上取材対象者として多くの貧困者や種々の被害経験者に接してきています。 彼ら彼女らから感じることのあったある種独特のパーソナリティと、今回自分が抱えることとなった障害・症状との間に、類似性があることを見いだしました。 ここも慧眼だと思います。 もっともこの、取材対象者に関するくだりについては、読んでいて息苦しいというか、気持ちが揺れるところもありました。 著者は本書の中で、みずからの障害・症状からの回復に必要だったものを挙げています。 ただし、それすなわち上記の取材対象者たちが決定的に持ち合わせていないもの、だったりします。 この点において著者が、この場で共に語らんとする取材対象者との間に解離というか溝を作ってしまっている、そんな気がするのです。 あるいはわたしが頭でっかちで、誤読や曲解をしているだけなのかもしれません。 ただ、著者のいう「助けなきゃいけない人たち」(「助けなきゃいけない人たちが、助けたいと思えるような人たちだとは限らない」のだ。)の中にはこのような誤解や曲解をしてしまいがちな人もいるのではないでしょうか。 そんな気がして、微妙に気持ちがヒリヒリしながら読んでいました。 そんなこんなで個人的には著者に対して、今は「あれもこれも」とは考えずに、脳梗塞からのサバイバーとしての発言・提言に主軸を置いた方が良いのではないかな、と感じました。 結局はそれが、著者が求めているものの全てにつながるような気がします。 アトゥール・ガワンデの「予期せぬ瞬間」(みすず書房)という本があります。 この本の中に「厄介事が起こると、私たちはそれを悲劇と呼ぶ。しかし、ひとたび誰かが書き記せば、それを科学と呼ぶ。」(原註 まえがき1)とあります。 高次脳機能障害をもつ当事者からの発言・発言はまだまだ少ないのが現状のようです。 より多くの当事者の声が書き記されることを望みます。 そして、より多くの厄介事が科学に還元されることを望みます。 (本当は著者の奥さんについても書いてみたかったけど、なんか力尽きてしまった。) いい本です。読んでみてください。
0投稿日: 2018.04.11
死を迎える心構え
加藤尚武
PHP研究所
老齢者の処世訓?否、当事者研究本である。
むかし、この著者の生命倫理学に関する著作を何冊か読んだ記憶があります。 1990年代の中頃だったはずです。 内容は正直まったく覚えていません。 ボンクラ丸出しです。 しかし感銘を受けたという記憶はあります。 だからこそ著者の複数の著作を読んだのです。 ちゃんとした記憶はないものの自分の気づかぬところで、みずからの血肉となっているのでしょう(そうあって欲しいものです)。 本書は著者80歳を目前に書かれたものです。 学者として生き、老齢期に入り、来し方を見やって、今の自分の考えを理知的論理的に、そして可能な限り率直に述べようとしています。 本書は、学術的な記載であるべく様々な引用が用いられています。 それらは、もちろん見るべき知見であり聞くべき言葉であります。 しかしながら、そして僭越ながらですが、それらの引用よりも著者ご本人の「なまの声」こそが、説得的で貴重だと感じられました。 わたくし的には二つの見るべき点がありました。 ひとつは、「お年寄りあるある」的な、老いの実感を表現しているところです。 たとえば、歳をとり記憶を手繰りよせることがままならないことを、図書館と出納係のたとえで説明するくだりがあります。 また、未来がなくとも未来があるふりをすることや好好爺ぶって芝居することの大事さを語るくだりなどがあります。 共に上手なたとえであり、老いてからの処世術としてとても説得的だと思います。 ただ、若干表層的かもしれません。 講演受けする、共感を得られやすい話なんだろうな、とも思いました。 もうひとつは、パーソナルで切実な、老いの実感を綴っているところです。 著者は「息子には自殺する権利はない。なぜなら、息子が自殺したら父親である著者はみずからの同一性を保持しえないから」と言います。 また、「夜中に悪夢から醒めたとき、ふたたび悪夢を見るのではないかと恐れたときは、『おとうさん』と何度か唱える。今でも父の言葉に支えられて生きている。」とも言います。 身内への愛情の回帰というか愛情の再強化というか、そういったものが感じられます。 こころの深層に迫るもので、身につまされます。 本書は、老齢者自身による「老いに関する当事者研究」の本であって、あるいはそこにこそ眼目がある、そう言ってよい本であると感じました。
0投稿日: 2018.03.20
テロ
フェルディナント・フォン・シーラッハ,酒寄進一
東京創元社
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。
シーラッハの作品は好きで一通り読んでいます。 どれもそんなに長くなく、そのせいもあってか一度読んでいてもたまに読み返したくなります。 この作品もそんな一つです。 本作品は法廷劇で舞台用の戯曲です。 おそらくは観客が参審員となり被告人に対して有罪または無罪との評決を下す、そこに眼目が置かれている作品なのだと思います。 なので判決文(本作品では有罪の場合の判決文と無罪の場合の判決文の両方が用意されています。結末が二通りあるというのは奇妙といえば奇妙ですが、当然といえば当然ですね。)は読んでも読まなくてもかまわないのかもしれません。 第二幕までを読んだらあとは本を閉じてしまって、自分で結論を下せばそれで物語は完結する、そういう読み方もできると思います。 本作品の面白さは、ページをめくる手が止まらないといった面白さではないです。 立ち止まって吟味して、深く考えながら読み進めると味わいが深まる、そんな面白さです。 最初に読んだときは被告人であるコッホ少佐は無罪であるしそれしかないと思いました。 次に読んだときはこれは有罪以外にはありえないのではと思いました。 真逆の結論ですね。 今は正直どちらとも決められません。 でもそんな中途半端な思いを楽しんでいます。 ずるい楽しみ方ですよね。 でも、そんなずるい楽しみ方をしている自分に安心しているところもあります。 この作品を読んで、有罪なり無罪なりの判断をしてそれでこと足れりとしてしまうこと、それができる人に自分はなりたくないし、それができる人とはあまり友だちにはなりたくないな、と感じます。 そんなに簡単に、一筋縄ではいかないものですから。 でもどうしても有罪か無罪か決めなければならないとしたら、こちらに票を投ずるというのが何となくですが決めてはいます。 それがどちらかは言いませんけどね。 詳しくは、まあ読んでみてくださいな。
0投稿日: 2018.02.21
柔らかなこころ、静かな想い 心理臨床を支えるもの
村瀬嘉代子,中井久夫
創元社
タイトルに偽りなし
中井久夫先生の著作から巡り会った一冊です。 挿絵を中井久夫先生が担当されています。 このような本との巡り会いは、地方に住む者にとって、まちの本屋さんでは少々難しいです。 どうしても品揃えが少ないので、村瀬嘉代子先生も(中井先生であっても)そうそう本屋さんで見かけることがありません。 今となっては当たり前のこととなったと言えるのでしょうが、電子書店ならではの巡り会いであり、そして、巡り会えてよかった一冊です。 心が洗われると言うのでしょうか、リラックスして読める文章です。 もっとも最後の方の数章は背筋の伸びる、ピリッとした内容になっています。 好きな章は 「芽吹き、花開き、結実のとき」 「二羽の鶴-林隆行先生ご夫妻を偲んで」 「家族力」 「手紙」 「入り日を惜しむこころ」 といったところでしょうか。 とりわけ「家族力」のおわり近くは気になる内容でした。 曰く、 虐待されたり親から拒否された子どもは、しばしば親を庇い親の批判をしない。 昨今トラウマを再現し言語化させるという治療技法が受け入れられているが、いたずらに辛い体験の再現や言語化を求めるべきではないのではないか。 なぜなら人間にとって父母とは自分の存在を生物学的にかつ精神的にもかなり基底の部分で大きく規定している存在であり、自分の親をいたずらに否定すると人は自分自身の存在をも受け入れがたくなるのではあるまいか。 とのこと。 身の回りの人を見て思い当たる人あり、はっとさせられる内容でした。
0投稿日: 2017.07.06
漫喫漫玉日記 四コマ便
桜玉吉
月刊コミックビーム
読もう!桜玉吉
2009年11月から2013年までの作品です。 いちおうコミックビームの販売促進のテイですが、身辺雑記の四コマ漫画です。 タイトルも同じだし、「満喫慢玉日記 深夜便」とワンセットと考えるべきでしょうか。 O村さんとの対談があいだに挟まれています。 これがあってよかったです。 二人のやり取りから、玉吉さんの当時の状況がわかります。 玉吉さん、苦労されてますね。 収められている作品から、その作風というか描画の線をみるだけでも、玉吉さんのその時の精神状況をうかがい知ることができます。 ともあれ復活おめでとうございます。 子どもの頃のチンチンのムズムズは共感です。 思い出しました。 当方とりわけブランコにのっているとき、おしっこをしたいようなでも出ない、気持ち悪いようなでも気持ち良いような、そんな感じがありました。子どもだったので、性的なるものとのバイパスが形成されていない、その時期ゆえのムズムズだったのでしょうか。 謎です。
0投稿日: 2017.07.05
shiroyagi03さんのレビュー
いいね!された数8
