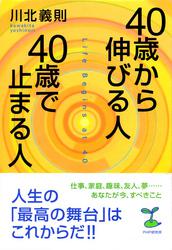
40歳から伸びる人 40歳で止まる人
川北義則
PHP研究所
30歳の時に発売された本を、40歳の時に読む
自分は昨年(2013年)40歳になりましたが、その年に中小企業診断士の資格取得を志し、合格することができました。 今年5月に正式に登録を受け、実際に診断士として活動することはできますが、当面はシステム開発者との二足のわらじで、資格は「武器」となるよう常に磨いておこうと考えています。 80年の人生なら40代は折り返しの時期ではありますが、40代になっても学ぶことはいくらでもあるし、まだまだ成長を止める気はありませんし、折り返すつもりもありません。 本書は、そういう考え方の自分の背中を押してくれる1冊になります。 仕事の成果で他人に貢献することを自分の喜びと考えているので、「いい人と呼ばれないように」には違和感がありますが、そういう考え方もありだろうと思います。 私の考え方だと、他人の評価を常に意識してしまうので、窮屈になることもあります。ただし商品でも自分でも、売り込むにはマーケット・イン、つまり世間が求めるものを提供しないと売れないわけで、バランスが大事ですね。 そして最も心をえぐられたフレーズがこれ。 「中小企業診断の資格を取っても、顧客を獲得する段階で苦労して投げ出してしまう人が多い。」(41 資格取得は「役に立つ」ではなく「好きな道」を選べ) ……そうなんです。 実績をあげられず消えていく中小企業診断士はごまんといるわけですが、これが書かれた2003年は試験制度の見直し前なのに、10年後の現状を見通している達見にも驚かされます。
1投稿日: 2014.06.03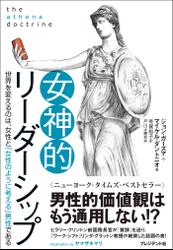
女神的リーダーシップ ~世界を変えるのは、女性と「女性のように考える」男性である
ジョン・ガーズマ,マイケル・ダントニオ,ヤマザキマリ,有賀裕子
プレジデント社
「性差」では何も語れなくなった
少なくとも自分の感覚では、「男らしく」「女らしく」といった性別役割分担は、前世紀や昭和時代の遺物になってしまったのだろうと思います。 確かに女性の社会参加は遅れており、この分野では日本は最後発国となっていますし、先進国でも女性の管理職の割合などを義務化して何とか状況を進めている段階です。 それでも、私たちの生活レベルで男女の役割を見ていくと、支配や競争に疲れてしまい、奪うよりも分け与えるほうが利益が大きいということに、ようやく気づき始めました。競争を成長の源泉としてきた自由主義や資本主義の転換点でもあるかと思います。 余談になりますが、いまだに「支配」のフレームワークで生きている人が、総じて自分は権力の支配に虐げられている不幸な人間だ、と自らを規定しているのは、非常にもったいないと思います。支配・被支配の構図から抜け出せば、自分がどれだけ自由なのか気づけると思うのですが。 前置きが長くなりましたが、世界のあらゆる地域で、男女問わず「協力」や「共感」で新しいものを作り出し、成長していくことが起こっています。本書で最も印象的だったのが、アイスランドの事例です。 同国は経済成長を謳歌していましたが、2008年の金融危機で財政破綻、2011年には過去の反省を踏まえた新たな憲法草案を作ることとなりましたが、国民参加でソーシャルメディアを活用した議論が行われたとのことです。 経済成長の時期は競争社会、財政破綻後は共感と協同の社会と、全く異なる側面を見せていますが、人々にとっては後者のほうが居心地が良いのではないでしょうか。その中で作られた憲法は、自分たちが作った新しいアイスランドの象徴になりうるでしょう。 日本でこれをやるには国の規模が大きすぎますし、そもそも世界で最も制定(改正)からの時間が長くなってしまった憲法はある意味でブランドになってしまっていますが、より身近なところで共感と協同の社会が作られています。 インターネットを通じて、人々は関わり合うし、助け合います。言葉の表面上はいがみ合っているように見えても、奥底では通じ合っているのではないかと思うこともよくあります。助けたり助けられたりするのを拒絶しているようでも、単に恥ずかしがっているだけでしょうし、それでいいのではないでしょうか。
6投稿日: 2014.02.27
コンサルタントの「現場力」 どんな仕事にも役立つ! プロのマインド&スキル
野口吉昭
PHPビジネス新書
経営コンサルでもITエンジニアでも必須の能力です
長年ITエンジニアを続けながら、昨年(2013年)の中小企業診断士試験に合格し、経営コンサルタントとしても活動していきたいと考えているときにこの本を読みました。 「現場力」とありますが、これは現場で発生している問題点の本質をを即座に見つけ出し、解決していく力と説明できるかと思います。この力は経営コンサルタントでは当然必要ですが、ITエンジニアでもユーザーの現場である顧客との折衝や要件定義、あるいは開発現場側でも設計や実装において、それぞれの立場で必要な能力となります。 経営コンサルタントは問題の分析にあたってSWOTや集約・発散の蝶ネクタイ図など、フレームワークを使いこなしますが、誰もが必要なレベルで求められるのは仮説を構築し、検証し、修正する力のほうが重要と言えます。 問題の原因を説明できる仮説を作るだけなら誰でもできますが、その仮説が適切かどうかを高いレベルで検証し、修正していくのは、その意識と訓練を伴わないとできないですし、自分もまだまだだと感じます。 そして意外に、とはいえ実は最も重要なのは、提案した解決方法を実際に受け入れて実施してもらうことです。上から強圧的に指示を出してやらせるわけにはゆきません。相手にこちらの提案を正しく理解していただき、納得いただいた上で初めて実施することができます。 この部分はロジックではなく、人間としての情熱であったり、巻き込む力のようなもので合ったりします。性格や器質によるもので変えられないと思っていましたが、これも意識や訓練次第、あるいは一度成功体験を得られさえすれば、大きく成長する余地があるのだと考えを変えつつあります。
2投稿日: 2014.01.18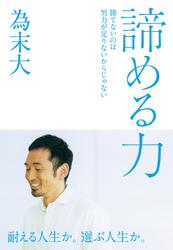
諦める力~勝てないのは努力が足りないからじゃない
為末大
プレジデント社
「諦める」と「逃げる」の違い
為末さんのツイートでも、自分の限界を知ることや、成果に結びつかない努力が無駄に終わる危険性を何度か指摘されているのを見ました。 これは、「諦めなければ夢は叶う」と信じさせて別の道に移るのを許さない風潮に対する警鐘でもあります。 どちらの考え方にも理屈はあり、自分もどちらが正しいのかはわかりませんし、おそらくはケースバイケース、あるいは言い方は悪いですが結果論の部分も多々あるでしょう。 ただ、為末さんの言う「諦める」と、「逃げる」とを混同してしまっている人が少なくないように感じます。 ここで言う「諦める」は、自分の夢や目標を達成する手段を変えて、別のもっと可能性の高い方法を選ぶことであって、夢や目標の達成自体から「逃げて」しまうことではないはずです。 本来、個人個人の夢や目標は相当抽象的なものであり、その達成手段はいくつもあるはずです。 自分自身の話をさせてもらうと、昨年(2013年)、中小企業診断士の試験に合格し、システム開発の仕事と経営コンサルタントの二足のわらじを履くことになります。 開発者としては周囲の期待に応えたとはいいがたいのですが、努力の軸足を経営コンサルタントのほうに移していくことも考えています。 自分の夢が「顧客や勤め先、社会全体に貢献したい」というところにあるので、その手段がこれまでやって来たシステム開発でも、これから挑戦する経営コンサルタントでも、夢を達成する手段であるということに違いはありません。システム開発で夢を実現するのは「諦め」ても、夢そのものから「逃げ」ているとは思っていません。 新しい挑戦もしていきますから、これからも何度も壁にぶつかると思います。その壁を壊すのか、乗り越えるのか、あるいは回り込める別の道を探すのか、ともかく夢を叶えるために諦めないこともあれば、諦めることもあるだろうと思います。
5投稿日: 2014.01.05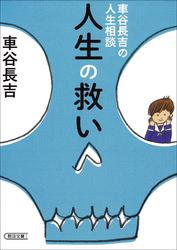
車谷長吉の人生相談 人生の救い
車谷長吉
朝日新聞出版
人生は最大の挫折をもって初めて始まる
朝日新聞で連載されていた読者投稿の身上相談とその回答をまとめたものです。 正直なところ、すべてに共感できるということはありませんでしたし、参考にできない回答もいくつかあったのですが、著者の考え方を知ることはできました。 全体を通して感じるのが、著者特有の人生観です。 「最大の挫折を通じて初めて、真の人生が始まる」「真の人生が始まらないまま、一生を終える人が9割」という言葉は、自分の心にも痛切に響きました。 そして、著者の考え方に従えば、私の人生も始まらないのだろうと。 常識や世間体で自らの首を絞めている人であれば、そういったものを投げ捨てても生きていけることを教えられるし、背中を押してもらえる一冊になるだろうと思います。 ただ、何もかもを捨てて世間から後ろ指を指される(著者の言い方をすると「阿呆になる」)生き方ができるかというと別問題ですし、できなくても――楽にはなれないかもしれませんが――やはり生きていけるわけです。 そのあたりは、著者の生き方もひとつの考え方と受け入れて、自分の生き方、考え方を選んでいきたいと思いました。
7投稿日: 2014.01.02
リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす
エリック・リース,井口耕二,伊藤穣一(MITメディアラボ所長)
日経BP
単なるスモールスタートではない
ブームになった頃には読めず、今頃(2013年末)読了となりました。 ネットで見聞きしていたのと違っていたのは、リーン・スタートアップが単なるスモールスタートではなく、スモールスタートからいかに事業を軌道に乗せるか、そのためにはどのような基準で事業の成長を評価すれば良いのか期待通りに成長していない場合、何を変えていくべきなのか、といったその先の方法論について深く分析されていました。 とくに事業の方針転換である「ピボット」は、失うものも大きくなかなか決断できないことも多いだろうと思うのですが、決断を鈍らせる原因を取り除く1冊でもあるといえます。 また、リーン・スタートアップの源流はトヨタの生産管理にあると言われていますが、それだけにとどまらず、日本で生まれた運営管理がいくつか採用されており、私たちにもなじみ深いやり方が出てくるのでうれしくなりました。 とくに「なぜなぜ5回」は、トラブルの真因を探るのに重要で、原因を個人の資質や意識に求めるのではなく、業務プロセスの不備や改善点の発見につなげていく上で重要な方法です。 自分もあるプロジェクトで「なぜなぜ5回」を行ったことがありますが、最終的には仕様認識の不備、情報共有不足といったところにたどり着くものがおおかったです。単なるミスであっても、ミスが起きても対応できる仕組みだけではなく(こちらも大事ですが)、そもそもミスを起こさせない仕組み作りができるのだということも気づきました。 実際にリーン・スタートアップを成功させるのは、方法論の知識とピボットの決断、そして市場の声を聞く謙虚さが必要になります。とはいえ難しそうだと逡巡してしまっては、スタートアップ自体を諦めてしまうことになり逆効果なので、まずは何らかの形で動かないと始まらない、ということも意識しておきたいところです。
3投稿日: 2013.12.28
僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか 絶望から抜け出す「ポジ出し」の思想
荻上チキ
幻冬舎新書
考えるべきことを考えない私たち
本書の見所、すなわち私たちがもっとも意識しなければならないことは、前半部に詰まっていると感じました。 大きなところでは日本の財政問題、小さなところでは生活保護の不正受給問題などに焦点を当てています。感情論に流され、自分と考え方や立場の異なる者を叩いてよしとするのではなく、「根拠(エビデンス)」「解決策(ソリューション)」「倫理(エシックス)」の3つの観点から冷静に理論を組み立てることの重要さが示されています。 この3つの観点から、当然のことが淡々と述べられているだけなのですが、その当然のことをいかに自分たちが考えてこなかったか、痛感させられます。 怒りや諦めなどで、冷静な議論ができなくなっている部分もあるだろうと思いますが、やはり考えることを放棄して、思考停止に陥ってしまった部分が多くを占めているでしょう。 後半は政治への参画について。中盤の族議員批判で、圧力団体の利益誘導を行っていることを指摘していましたが、結局のところ自分たちが圧力団体になることで政治を動かせる、という結論はどうなのだろうと思いました。 とはいえ、自分の1票で政治が動くようには思えないし、都市部や若年層を中心に投票率低下が実際に起こっています。実際に政治を動かしたいなら投票よりも、事業を立ち上げて規制に立ち向かうほうが、効果は高いですよね。 起業のような大きなことでなくとも、またデモや集会、署名活動に参加するなど直接的な行動でなくとも、自分の身近な問題(社会のバグ)に自分のできる範囲ややり方で関わっていく、というのが第一歩になるだろうと思いました。
2投稿日: 2013.11.28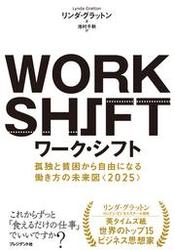
ワーク・シフト 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図<2025>
リンダ・グラットン
プレジデント社
【漫然と迎える未来】を生き抜くために
2025年の未来像として、著者は2つの方向性を示しています。どちらがよりありうるかと考えると、悲観的な方向、【漫然と迎える未来】だと言わざるを得ません。 グローバル化とネットワーク化が進んだことで、先進国に住む私たちの収入は発展著しい国々との競争で頭打ちになり、「常につながっている」社会は容易に「常に監視されている」社会になります。 その中で私たちはどのように生き抜くことができるのでしょうか。社会は変わらなくても、自分の意識や行動は変化させることができますし、そのヒントが本書の「3つのシフト」にあると言えます。 いまの自分の生き方、働き方も、「3つのシフト」にある程度即しているように思いました。 ひとつめ、連続スペシャリスト。自分はITベンチャーでシステム開発者として働いてきましたが、中小企業診断士の資格を取ってコンサルタントになろうとしているわけですし、両者の特性を生かした働き方も想定しています。 ふたつめ、みんなでイノベーション。勉強会や読書会に頻繁に参加することで、仕事でもプライベートでもない人脈を広げ、何かのときに役に立てられるかもしれない、と感じています。 さいごに、金銭的収入から価値ある経験へ。もともと「お金のために働く」という意識は薄いほうでしたが、仕事を通しての新たな発見、成長、挑戦を楽しむことを経営理念としている会社に勤めたことで、働くことの意識がもう一段あがったように感じます。 このような働き方は、相当の成果を出さない限りは、外部からは評価されにくい働き方かもしれません。ですが外部からの評価以上に、自分が成長している、貢献できているという感覚を持てることによって、より充実した働き方ができるのではないかと思いました。
7投稿日: 2013.11.11
承認欲求―「認められたい」をどう活かすか?
太田肇
東洋経済新報社
仕事のモチベーションとして
この本が紙で出版されたのは、自分がこのレビューを書いている(2013年の)6年前になりますが、その6年の間にも「承認欲求」のあり方が大きく変化してきたように思います。 まず、<認められたい><評価されたい><貢献できていると感じたい>という日常の中の欲求として考えられてきたのが、<目立ちたい><注目・脚光を浴びたい><他人のしないことをしたい>という方向に変容し、実際に限度を超えた悪ふざけをする人たちも現れてきました。 また、ニコニコ動画やTwitterの利用者が増え、悪ふざけが手軽に公開できるようになり、同様に手軽に拡散されるようになっています。その結果「承認欲求」という言葉自体がネガティブな意味を持つようになってきています。 自分の中にも(前者の意味での)承認欲求があり、仕事のモチベーションにも直結しています。システム開発の仕事をしていますが、自分が携わったシステムが実際に使われ、よい評価をもらえれば、それだけで仕事を続けてよかったと思えますし、<貢献したい>という気持ちがとくに強いのかもしれません。 ですが、そういった欲求を表に出しづらいのが日本社会の特質でもあり、近年はその傾向がより強くなったように感じます。個人情報の自己防衛とも絡んでいるのか、とにかく自分を消してしまうような活動や、社会の中に埋没して傍観者然としていることが最善であるという考え方が増えているのではないでしょうか。 本書は仕事のモチベーションを保つ方法論として読んでいました。仕事の達成感や有能感を得るには、あるいは上司の立場から部下を褒めて伸ばすにはどうすればよいか(部下はいませんけれど)など、個人を埋没させるのではなく、一人一人別々の人格を持った人間としてどのように承認し、モチベーションを高めていくかを考えていければと思います。 このレビューを書いている時点では試験の結果が出ていませんが、中小企業診断士として様々な企業にアドバイスする立場になることを考えていますし、その中では従業員のモチベーションを高めるため、言い換えれば承認欲求を満たすため、どういった働きかけが有効かも、あわせて考えていきたいです。
3投稿日: 2013.10.23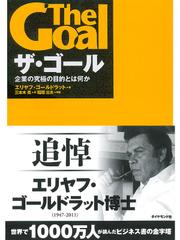
ザ・ゴール
エリヤフ・ゴールドラット,三本木亮,稲垣公夫
ダイヤモンド社
定番ですが名著です。ちなみに小説です
中小企業診断士の資格取得の講座で、講師の方から本書を紹介されました。 以前から本書の存在は知っていたのですが、これを機に読み始め、そこで初めて小説だということを知ったのですが、楽しんで読み進められました。 当たり前のことではありますが、企業の究極の目的(ゴール)は、利益を上げること。利益を上げるには売上を増やしてコストを下げること。本書は工場を舞台にしていますが、工場における利益とは、コストとは、といった根本的な問題に切り込んでいます。 小説の体裁であるため、工場運営以外のシーンも描写されており、その中にも運営改善のヒントを見つけることができます。ネタバレになりますが、子供たちとのハイキングから、ボトルネック以外の部分での稼働改善が必ずしも利益を生むものではないと気づくなど、主人公の洞察の深さにも気づかされます。 最後に、本書の舞台は1980年代の米国。日本がカイゼンやJITで大きな成果を上げていた裏で、米国が凋落したといわれた時期でした。 本書の設定が事実であったとすれば、そりゃあ当時の米国は日本に勝てなくなるよなあと思う反面、現代では日本と新興国の立場に置き換えられるかと思いますが、日本が新興国と製造業で戦っていくには何をすればよいのか、考えさせられる1冊でもあります。
4投稿日: 2013.10.12
たまご915さんのレビュー
いいね!された数127
