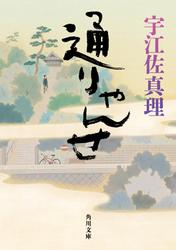
通りゃんせ
宇江佐真理
角川文庫
的確な時代考証を土台にしたSF時代劇
25歳の若手サラリーマンである大森連は、失恋の傷を癒すために休日になるとマウンテン・バイクで走りまくっていた。ところが小仏峠周辺で道に迷い、滝の裏に墜落してしまう。目が覚めると、なんとそこは天明6年の武蔵国中郡青畑村であった。 連は時次郎とさな兄妹に助けてもらいながら、連吉と名を変えて時次郎の百姓仕事を手伝うことになる。さらに忙しい時次郎に変わって、領主である江戸の松平伝八郎のもとを訪れるのだった。 宇江佐真理と言えば、吉川英治文学新人賞を受賞したり、何度ともなく直木賞候補に挙がっている時代小説の旗手である。ところがなんと本書は、現代っ子の若者が江戸時代にタイムスリップして、川の氾濫や天明の大飢饉で苦しむ村人たちを助けるというSF絡みの時代小説だったのだ。 ただしSF時代劇と言っても『戦国自衛隊』や『戦国スナイパー』などのように未来人が未来の知識や武器を使ってヒーローになるような大それた話ではない。せいぜい汚れた井戸水の簡易ろ過装置を創ったり、整体やストレッチの知識を生かして感謝される程度の活躍をするだけである。それより何と言っても、主人公・連の優しさと誠実さが脈々と流れてくるような清々しく凛としたストーリーに心を奪われるだろう。 またさすが本格時代小説家だと感じさせる的確な時代考証を土台にした、現代と江戸時代の風俗や社会構成の比較描写は実に見事であった。それに加えてワームホールなどのタイムスリップ理論や、過去の改変によって引き起こされるタイムパラドックスについても言及しているところに著者の真摯な勉強熱心さを感じた。 ただ高校時代の友人坂本賢介の存在や行動が、説明不足かつ中途半端だったところだけが唯一気に入らない部分だったような気がする。またラストでの早苗との遭遇はよくある映画のパターンで、ほぼ私の予想通りであったのだが、ずっと暗く苦しかった連にそのくらいのご褒美はあげてもいいかな……。
0投稿日: 2023.12.06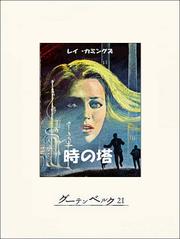
時の塔
レイ・カミングズ,川口正吉
グーテンベルク21
冒険SF小説の古典
作者のカミングスは、1887年ニューヨーク生まれのSF作家であるが、なんとあの発明王エジソンの秘書を5年間務めたという。本作は1929年に書かれた古典SFである。 「時の塔」と呼ばれる塔の形をしたタイムマシンで未来からやって来た少女が、悪人ターバーの病院に監禁されてしまう。それを主人公のエドと親友のアラン、そしてその妹のナネットが救い出すのだが、その代償にナネットがターバーに捕まってしまう。 なぜかターバーもタイムマシンを所持しており、地球征服の野望に燃え、以前からナネットと結婚しようと目論んでいたのだ。ところが主人公のエドとナネットは相思相愛の仲であり、ナネットを取り返すべくエドとアランの長い旅路が始まるのであった。 はじめはSFというよりも、こじんまりとした冒険小説のような佇まいであった。ところが太古の時代から超未来へ、そして未来でのターバーとの戦いが始まると、俄然スケールが大きくなってくる。映画にしても良いのではと思ったが、現代では古典SFとなってしまい、かなり古臭いストーリー展開なので、現代風にアレンジする必要があるかもしれない。 またタイムトラベルものとしても、まだまだ単純でタイムパラドックスなども考慮されておらず、単に冒険を広げるためにタイムマシンを利用しただけに留まっている。まあこの時代のSFなので仕方がないと言えばそれまでであるが、タイムトラベルファンには、ちょこっとばかり物足りないかもしれない。
0投稿日: 2023.12.06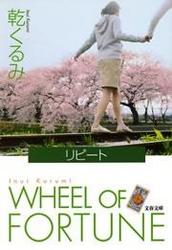
リピート
乾くるみ
文春文庫
ブラックパズルのような悪魔的展開
主人公は、一人暮らしの大学4年生・毛利圭介で、夜は歌舞伎町のスナックでバイトをしている。ある日、風間という見知らぬ男から電話がかかってくる。なんと要件は、過去に戻るリピートツアーに参加しないかということだった。余りにも荒唐無稽な話なのだが、その信ぴょう性を証明するために告げた地震予知が的中し驚いてしまう。その後にまたもや、再度正確な地震予知が大当たりし、このリピートツアーは本物かもしれないし信じ始めるのだ。 このリピートとは、タイムマシンなどに搭乗するのではなく、ある一定の日に現れる黒いオーロラに突入すると、記憶だけが10か月前の自分の中に上書きされるというものだった。そこで人生のやり直しをするのだが、もちろんそこでは未来の記憶を利用して、競馬や株で儲けることも自由自在だ。 リピートツアー参加者は風間を含めて10人、その中には一人だけ若い女性が参加していた。この女性の存在が、毛利にいろいろなプレッシャーを与える原因になるのだが、とにかく彼は女性にモテモテなのである。ただこのモテモテが最大の災いを生むことになるのだが……。 このような記憶だけのタイムトラベルといえば、すぐに思いつくのがケン・グリムウッドの長編小説『リプレイ』である。ただ本作が僅か10か月前の自分に戻るだけなのに対して、『リプレイ』の主人公は25年前の18歳の青年に戻れるのである。さらに43歳になると自動的に心臓発作を起こしてまたまた18歳に戻れるのだ。 そしてそれが何回も続くのである。それに比べると本作では、もう一度リピートするためには、ある一定の日に現れる黒いオーロラに再突入しなければならないという点が異なっている。 また『リプレイ』では主人公が、未来の記憶を利用して大儲けしたり、つきあう女性たちを変えてみたりと、「もしもあの時こうしていれば良かった」を次々と実現させてゆく。だが本作ではそんな『リプレイ』のような痛快さは余り楽しめない。どちらかといえば、リピートしたために起こった記憶にない数々の嫌な事件に翻弄されてしまうのだ。そしてなぜそんな事件が起きるのか、犯人は一体何者で何のための犯行なのか、ということがメインテーマとなってくるのである。 それにしても著者の巧みなブラックパズルのような悪魔的展開にはいつも脱帽せざるを得ない。中盤からはなんとあの『罪と罰』のラスコーリニコフのような心情に堕ち込んでしまったではないか。まさに乾くるみは天才としか言いようがないね、と思い込み続けてどんどんページをめくっていったのだが、ラストが余りにもあっけなく、無理やり感が残ってしまったのが非常に残念であった。
0投稿日: 2023.12.06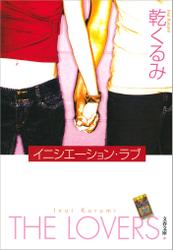
イニシエーション・ラブ
乾くるみ
文春文庫
二回読みしたくなる傑作ミステリー
イニシエーションとは「通過儀礼」のことである。従ってタイトルの『イニシエーション・ラブ』とは永遠の恋ではなく、大人になる前の一時の恋ということになるのだろうか。また本書はバリバリの恋愛小説だと思っていたのだが、実は「必ず二回読みしたくなる」と絶賛された傑作ミステリーであった。 本書の裏表紙にある内容紹介文には、「甘美で、ときにほろ苦い青春のひとときを瑞々しい筆致で描いた青春小説----と思いきや、最後から二行目(絶対先に読まないで!)で、本書は全く違った物語に変貌する。」と綴られているのである。 これは一体何を意味しているのだろうか、ネタバレになるのでここでは解説は避けることにするが、いくつかのヒントだけ紹介しよう。第一のヒントはこの小説のタイトルである。そして第一章、第二章という区分ではなく、かつてのカセットテープのようなside-Aとside-Bという区分も意味深ではないか。さらにside-Aではしつこいくらい細かくじっくりと丁寧な描写に終始しているのだが、side-Bではテンポの速い展開に変化しているのだ。また本作はタイムトラベル系の小説ではないのだが、時系列をゆがめて描いているため、二度読みが必要だということ……。まだほかにも矛盾することがいろいろあるのだが、これ以上記すとネタバレになってしまう恐れがあるのでこのへんで止めておこう。 なお本作はなかなか映像化し難い部分があるのだが、なんとそれを巧みに凌ぎながら2015年に映画化されているようである。ちなみに監督は堤幸彦で、主演は松田翔太と前田敦子になっている。機会があったら是非観てみたいものである。
0投稿日: 2023.12.06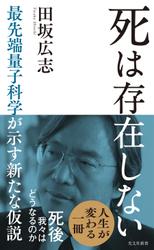
死は存在しない~最先端量子科学が示す新たな仮説~
田坂広志
光文社新書
ゼロ・ポイント・フィールドの謎を解く
著者は東京大学卒業後に同大学院を修了し、工学博士(原子力工学)号を取得。その後、実業界・学界において大活躍している人物である。 そんな唯物主義の塊のような著者が、なんと死後の世界観を科学的に分析し、SF映画や小説なども交えて分かり易く解説してくれるのが本書なのだ。従ってサブタイトルは、ちょいと気取って「最先端量子科学が示す新たな仮説」となっているのであろうか。 書店の店頭で本書を見かけたとき、もうそのタイトル・サブタイトルだけで、どうしても本書を読みたくなってしまったのだ。さらに細かく分離した小見出しや、ゆったりとした文章間スペースなど巧みな編集の妙も加わって、実に読み易い環境を創りあげているではないか。従って350頁以上の新書本であるにも拘わらず、遅読の私でも、僅か3日間であっという間に読破してしまったのである。 ただし本書の中身は、タイトルから想像していたような「死後の世界」の在り様などを解説したものではなく、どちらかと言えば宇宙論と死をドッキングさせたような仮説を展開しているのだ。その中でも著者が執拗に語る『ゼロ・ポイント・フィールド』とは、直訳すると零点エネルギーということであり、量子力学における最も低いエネルギーで、基底状態のエネルギーと言いかえることもできる。つまり宇宙が誕生する前から存在する量子空間の中に存在している『場』のことであり、「何もないところに全てがある」という禅問答のような場所らしい。 そしてこのゼロ・ポイント・フィールドには、宇宙が誕生してから、現在、さらには未来の情報までもが波動として記憶され、時間と空間を遥かに超越した情報の保持が可能になるというのである。ちなみに宗教の世界でも、不思議なことにこのゼロ・ポイント・フィールドと酷似している思想が語られている。 仏教の「唯識思想」における「阿頼耶識」と呼ばれる意識の次元では、この世界の過去の出来事全てや未来の原因となる種子が眠っているという。また古代インド哲学の思想においても、「アーカーシャ」と呼ばれる場のなかに宇宙誕生以来の全ての存在について、あらゆる情報が記録されているというのだ。 さらに著者は、ゼロ・ポイント・フィールドに蓄積される全ての情報は、「波動情報」として記録されていると付け加えている。つまり量子物理学的に見るなら、世界いや宇宙の全ては「波動」であり、情報は「波動干渉」を利用した「ホログラム原理」で記録されているというのだ。別の言葉で説明すれば、波動の干渉を使って波動情報を記録するということになるのだろうか。 この解説を読みながら、私の脳裏をかすめたのが、最近話題になっているチャットGPTである。チャットGPTとはインターネット上にある全ての情報を収集し、AIがそれを学習して様々な仕事をこなしてゆくシステムである。ところでこのインターネット上の全ての情報という部分が、なんとなくゼロ・ポイント・フィールドと似ていないだろうか。チャットGPTが有形のデジタル仕様なのに対して、ゼロ・ポイント・フィールドは無形で無限大のアナログ仕様という感覚がある。 さてゼロ・ポイント・フィールドの話にばかり終始し過ぎたが、それではタイトルである『死は存在しない』とはどういうことなのだろうか。現実社会での死とは、肉体が滅びることであり、心臓の停止やら脳死によって判断される。また意識とか想念については、脳とともに消滅していると考えられているようだ。ところがもし意識や想念の存在が、脳とは別物だと考えると「死の定義」そのものが覆ることになる。 本書では死によって私という『自我意識』が、ゼロ・ポイント・フィールドに移動し一体化すると、徐々に消滅してゆきエゴから解放された『超自我意識』に変貌してゆく。その後国境を越えた『人類意識』へ拡大し、やがては地球自体も巨大な生命体と考え、地球上の全ての意識である『地球意識』へと変貌してゆくのだ。そしてさらに究極の意識である『宇宙意識』へと昇華してゆくというのである。 つまりは宗教的に表現すると、「神の領域」に到達するということなのだろうか。またゼロ・ポイント・フィールドとの一体化ということは、ある意味で唯我論にも通じる思考ではないだろうか。だからこそ「死は存在しない」と言い切れるのかもしれない。まだ100%理解できないのだが、なんとなく生と死の意味が、朧げに見え始めてきた気がする。「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」
1投稿日: 2023.12.06
徳川家康 弱者の戦略
磯田道史
文春新書
巧みな人心掌握術と悪運の強さ
2023年のNHK大河ドラマは、松本潤が演じる『どうする家康』で、弱虫だった家康が少しずつ成長して、天下人になるまでを描いてゆくようである。本書ではその弱虫だった家康を歴史学的に検証しながら、逆境に学び続けた天下人の実態に迫ってゆくのである。 家康は強力な超人パワーと実行力に満ち溢れていた信長や、権謀術数と巧みな人心掌握術に優れ、さらに膨大な兵力と資力を誇る秀吉のようなカリスマではない。だが己が経験したことや見聞きしたことをひとつひとつ地道に積み上げ、信長や秀吉が成し遂げられなかった15代にも及ぶ長期政権の礎を築いた努力と辛抱の人だったようだ。また優れた家臣に恵まれていた……というより家臣の使い方が非常に巧みだったのである。 また当然のことながら、家康が天下人になるまでには、いくつかの障害と選択肢があった。まずは今川を裏切って織田と同盟を結んだこと、もしこの選択肢を誤っていれば、天下人どころか今川とともに滅んでいたことだろう。さらに武田信玄急死による武田軍廃絶や、本能寺の変で無事伊賀越えと成し遂げたという運の良さ、さらには天正大地震で秀吉側が莫大な被害を受けたことなど数え上げたらきりがないほど悪運に恵まれていたようだ。 さて今回の大河ドラマでは、家康の正室である築山殿をかなり美化しているのだが、歴史学的にはそもそも今川出身の築山殿にしてみれば、家康が今川を裏切った時点から恨み続けていたようであり、嫡男・信康においても、気性が激しく日頃より乱暴な振る舞いが多く、家康とは反目しあっていたとも言われている。従って単に信長の命令だけで、築山殿と信康を処断したわけではなく、家康の意向も含まれていたと解釈されているようだ。 また秀吉による関東転封も、家康自身はさほど不服だったわけではなく、むしろ秀吉との棲み分けや石高の大幅増加、関東平野や江戸湾などの地勢にも惹かれて積極的に受け入れたようである。 本書ではこのような話を織り込みながら、歴史学者的観点を踏まえながら分かり易く家康が天下人になれた経緯を描いてゆく。また190頁という新書版の薄さも手伝ってか、遅読の私でもたった3日であっという間に読破してしまった。寝苦しい夏の熱帯夜を忘れるためにも、是非手軽に本書を手に取ってみようではないか。
0投稿日: 2023.12.06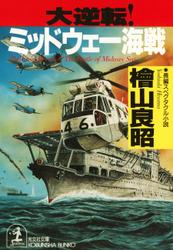
大逆転! ミッドウェー海戦
檜山良昭
光文社文庫
自衛隊護衛艦が太平洋戦争中にタイムスリップ
ミッドウェーとは日本とハワイの間に位置する2つの島と環礁のことを指す。また『ミッドウェー海戦』とは、太平洋戦争中にミッドウェー島周辺で行われた日米海戦のことを言う。 またその海戦において、日本海軍機動部隊は米国海軍機動部隊との航空戦に敗れ、空母4隻と搭載機約290機の全てを喪失してしまう。そしてこの敗北によって、戦争の主導権を米国に握られてしまうという、まさにターニングポイントとも言える戦いなのである。 ただ日本海軍の戦力のほうが、米国海軍より遥かに上回っており、簡単に勝てたはずなのになぜ負けたのかと主張する人も多い。そして巷では、「日本海軍の暗号が筒抜けだった」とか「山本長官の作戦自体がおかしかった、または南雲艦長が無能だった」とか、「レーダーの性能が不完全だった」とか「零戦のパイロットが未熟だった」とか、数え上げればきりがないくらいの理由が論じられている。 本作ではミッドウェー海戦直前に、突然UFOが出現して米国を有利な状況に導いたという荒唐無稽な設定となっている。そしてその謎を解明するために、現代(1988年)の米国軍隊が時空移動兵器を使って1942年のミッドウェー海域に調査隊を送り込むのである。ところが時空移動兵器の発動により巨大な竜巻が生じて、近くを航海中であった日本の自衛隊護衛艦4隻も巻き込まれて過去に送り込まれてしまうのだ。 このあと自衛隊護衛艦が最新ミサイルを使って、1942年時代の米軍戦闘機・爆撃機を次々に撃ち落としてしまい、結果的にはタイトル通り『大逆転!ミッドウェー海戦』となり、歴史を塗り替えてしまうのである。不謹慎かもしれないが、このあたりの描写は、日本人ならきっとスカッとすることだろう。 またここまで書くと、かわぐちかいじ氏の長編マンガ『ジパング』を思い出してしまった。ただジパングのほうが本作よりずっと後に発表されているので、本作から何らかの影響を受けたのかもしれない。 それにしても著者の檜山良昭氏の、戦争や兵器に対する造詣の深さには脱帽せざるを得ない。本作のほかにも『日本本土決戦』、『アメリカ本土決戦』、『大海戦!レイテ海戦』、『大逆転!戦艦大和激闘す』など、数々のシミュレーション小説を世に送っている。タイムトラベルものとしては、やや物足りないかもしれないが、過去をひっくり返してスカッとするためにもう数冊読んでみようかな・・・。
0投稿日: 2021.01.12
敵の名は、宮本武蔵
木下昌輝
角川文庫
面白すぎる武蔵の話
武蔵と戦い敗れ去った剣豪たちは数多い。本書は彼等の視点から見て、宮本武蔵の実像を語っているところがユニークである。345頁の長編であるが、読み易く天下無双の面白さのためか、あっという間に読破してしまった。 著者の木下昌輝氏は、ハウスメーカーから脱サラしてフリーライターとなり、2012年に『宇喜多の捨て嫁』でオール読物新人賞を受賞している。また同作は直木賞候補になり、その他数々の文学賞も受賞している。 さらに本書『敵の名は、宮本武蔵』でも、直木賞・山本周五郎賞・山田風太郎賞の候補作になっているという。 本書は7つの話に分割されているのだが、決して時系列順ではないところが、本書のミソとなっている。まず鹿島新当流免許皆伝の有馬喜兵衛が、13歳の少年武蔵と戦うことになった経緯に始まる。 そして第2章は、牛馬同然に売買され蔑まれていたシシド(吉川英治の小説では宍戸梅軒)が、鎖鎌の達人として山賊の頭領になり、武蔵により成敗されるまでの儚く悲しい物語となる。 さらに第3章では4代目吉岡憲法こと吉岡源左衛門が、武蔵との試合を通して「憲法染」と呼ばれる黒褐色の染物を発明し、家伝の一つである染物業に専念するまでを描いている。このあたりは吉川文学には登場しないが、こちらの成り行きのほうが史実らしい。そして武蔵も憲法との戦いを経て、剛力だけだった剣に優しさを匂わせるようになるのである。 その後武蔵は神道夢想流杖術の流祖である夢想権之助や、自身の弟子である幸坂甚太郎との戦いを経て、巌流津田小次郎との試合へと導かれてゆく。なお吉川文学の佐々木小次郎は架空の人物であり、古文書によると巌流島での決闘相手は、津田小次郎という年老いた剣士のようだ。本書は史実に沿って巌流津田小次郎として、架空の物語を創りあげているところが面白いのである。 さて本書がさらに俄然面白くなるのはこの辺りからである。まず巌流津田小次郎の出自というか、その悲運に満ちた生涯に心が痛む。そして武蔵の父・無二のさらに悲しき生き方に遭遇し、ここではじめて本当は彼が裏の主人公であることを確信する。 これだけでも、嫌というほど面白いのだが、このあたりで今まで少しずつ疑問に感じていた部分が、時間を遡って順次完全解明されてゆくのだ。まさにこれはミステリー小説の収束技法だと言っても良いだろう。それにしても、緻密に調査した事実をベースにしながら、これだけの嘘(創作)を捻り出した著者の力量は計り知れない。
0投稿日: 2021.01.12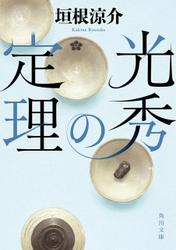
光秀の定理
垣根涼介
角川文庫
『本能寺の変』が省略されている明智光秀本
明智光秀が主人公の歴史小説なのだが、どちらかというと架空の人物である愚息と新九郎の視点で語られるところが多い。愚息とは世の中のしきたりに迎合せず、辻博打で生計を立てている破戒僧の名である。そして彼が信じるのは手垢のついた仏教ではなく、釈迦の直接説法だけだというのだ。 また若き兵法者である新九郎は、剣の道を志すも金に困り辻斬りに身を落としていた。そんなある日、辻博打をしている愚息と運命的な出会いを果たす。さらに若き日の光秀を辻斬りしようとしたが、新九郎との実力差を認めた光秀が刀を差し出すのを見ていた愚息に光秀の勝ちだと言われてしまう。こんなことが縁となり三人の奇妙な付き合いが始まるのであった。 このほかにも光秀の妻煕子の聡明さや、光秀が世話になっている細川藤孝のしたたかさ、そして織田信長の残虐さの中に同居する器の大きさなどを分かり易く描いている。それだけならよくある歴史小説との差別化は果たせないのだが、本作では愚息の辻博打で使われている「3つの定理と確率論」が大きく関わってくる。そこが実に興味深いというか、他の歴史小説にはあり得ない構成となっているのだ。 さらに面白いのが、光秀を描いておきながら、あの『本能寺の変』の描写が一切省略されているのである。ただなぜ光秀が、その暴挙に走ったのかという謎解きだけは、光秀が没した15年後に、愚息と新九郎の酒の肴として語られる。まさにそれが『光秀の定理』であり、まるでミステリー小説の結末を探り当てるように一気にむさぼり読んでしまうだろう。
0投稿日: 2021.01.12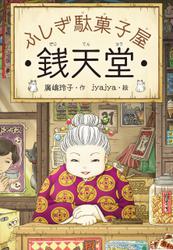
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 1
廣嶋玲子,jyajya
偕成社
笑うセールスマンのようなふしぎな駄菓子屋さん
ときどき思い出したように町の路地裏に佇む奇妙な駄菓子屋さん。そこで店番をしているのは、和服を着てどっしりとしたお相撲さんのようなおばさんである。真っ赤な口紅を塗りたくり、色とりどりの大きなガラス玉のかんざしを何本もさしている派手な彼女は「紅子」という名で、古いお金を集めているようである。 また店に置いてあるものは、「猫目アメ」、「骨まで愛して・骨形カルシウムラムネ」、「闇のカクテルジュース」、「妖怪ガムガム」、「ぶるぶる幽霊ゼリー」などなど、見たこともない摩訶不思議なお菓子ばかりである。そしてこれらを食べることによって、魔法のような不思議な現象が起こるのである。 本書では「型ぬき人魚グミ」、「猛獣ビスケット」、「ホーンテッドアイス」、「釣り鯛焼き」、「カリスマボンボン」、「クッキングツリー」、「閉店」の七短編が掲載されているが、読み易くて面白いので遅読の私でさえ1時間程度で読破してしまった。 好評につき、現在13巻まで出版され、アニメ映画化されたようである。なかなか面白い小説だが、なんとなく藤子不二雄の『笑うセールスマン』を思い出してしまうのは私だけではないだろう。
0投稿日: 2021.01.12
KENTさんのレビュー
いいね!された数12
