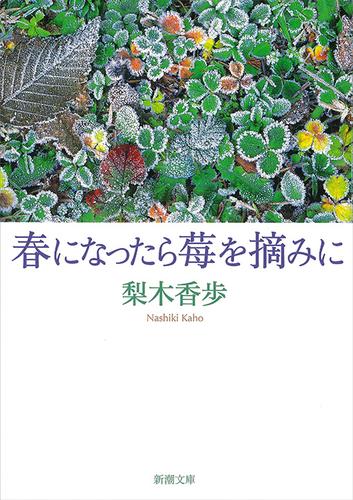
総合評価
(244件)| 78 | ||
| 86 | ||
| 49 | ||
| 4 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説?と思ってしまうくらいドラマチックですが、梨木さんの英国での体験を書いたエッセイでした。彼女のエッセイを初めて読みましたが、かなり好きな感じ。しみじみと、この人の考え方・感じ方にはすごく共感できるなあと感じました。自閉症の考え方にもすごく共感。だからこの人の書く小説も好きなんだなぁ。 梨木香歩さんの作品でとくに共感した小説は『僕は、そして僕たちはどう生きるか』でした。このエッセイを読んで、『僕は~』はこういう体験をしてきた人が書いた物語なんだなあとしみじみ納得できた次第。 他者の押しつけがましさに抗おうとする。いちいち言葉にしないさりげない親切に、心の中でそっと感謝する。そんな筆者の心の機微が感じられて、とても心地よいエッセイ。手元に置いておいてなんども繰り返し読みたい、そんな本でした。
2投稿日: 2013.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近ずっと梨木果歩作品を読み直している。 このエッセイを読んで、何故この人の書くものに惹かれるのかが少し分かった気がする。 人のバックグラウンドに興味がある。 だから人の基底になる、宗教や、家族や、育った環境の話を聞くことが好きだ。そういう惹かれるものの方向性が重なる部分があるのだと思う。 ウェスト夫人の「自分の信じるものは他人にとってもそうなるはず、と独り合点するところはなく、また人の信じるところについてはそれを尊重する、という美徳」 すべてを理解したり受け入れたりしなくても寄り添うこと、手をさしのべること。難しいけどそういう在り方に憧れる。 2013/12/15
2投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ価値観や倫理観の違う人間同士の間でどこまで共感が育ち得るか… について真摯に考えさせられるエッセイ。 梨木香歩さんは洞察力の深い方だと思う。
1投稿日: 2013.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの作品は、本当に心地よい。 人として魅力的な人が多く登場して、 直に会いたくなる。 素敵な人生を歩んでいる方なんだな~。
1投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人の作品は、どちらかと言えば物語の方が好きなのだが、こんな風なエッセイも捨てがたい魅力がある。ほんとうに感性が豊かな人なのだろう。今回は、いわゆる「異文化接触」が基調テーマなのだが、彼女が最初に巡り合った、ウェスト夫人とS・ワーデンのコミュニティの人々は、最良の英国であったように思う。ことにウェスト夫人は、彼女の物語作家としての師でもあり、この出会いがなければ、今の梨木香歩はなかったかも知れない。このエッセイの読後感は、ウェスト夫人を核とした、連作の小説を読んだかのようだ。
1投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもチャーミングで魅力的なウエスト夫人との 長年の交流をとおして、日本と諸外国の 感じ方や行動の違いや、根底に流れる「人間」として お互いを思いやり尊敬する気持ちに触れることができた。 筆者の常に控えめであり、人に対し真摯に向き合う姿勢が 人との長い関わりをもたらすのではないかと思った。
1投稿日: 2013.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読んだ。 硬派で気高いひとだなあと思う。 ところどころ、エピソードのあったかさや切なさに泣きそうになった。 著者のようにストイックにはとても生きられないけれど(どちらかといえば私はモンゴメリのように閉鎖的な偏愛性質)、人間って意外とそんなに悪いもんではない、かも、とちょこっと思えてくる随筆集。
3投稿日: 2013.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの文章がとても美しい。 自分がこれまでおっかなびっくりしていた気遣いやふるまい、価値観と同種のそれを 美しい言葉で取り出してくれるので、ああこれは良いんだって肯定された気になる。 すごく面白いけれど、場末のファストフード店などで読むと雰囲気の差に悲しくなるので 紅茶を入れて優雅に読みましょう。
1投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕草ともいうべき微細な動きをしっかりと受け止める。エッセイと言っていいのだろうけど、個々に歴史と文化の重みを感じ、心にずしりと響いた。ここでも国家というものの理不尽さ、幻想が期せずして感じられた。孤独に生きることはそんなに悪いことじゃない。そう思えた。
1投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログウェスト夫人、素晴らしい!こんな人がいるんですね、広い世界の中には。 著者の、日本語を心から大切に思っていることも表されていて、良かった。 これから、簡単に「国際交流」なんて言葉を発するのが恥ずかしくなりそう。
0投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国での生活を味わえたような…そんな読後感。 梨木さんの性格が表現されており、だからこそ「西の魔女が死んだ」や「裏庭」などの作品がうまれたんだなと納得。 関わり合う人達を客観的にとらえているあたりも梨木さんの性格がうかがえる。 ほっこりできた一冊だった。 ただ、エッセイを初めて読んだので読みづらさはあった。もう少し慣れたらまた読みたい。
0投稿日: 2013.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ただひたすら信じること、それによって生み出される推進力と、自分の信念に絶えず冷静に疑問を突きつけることによる負荷」「彼らのことをわからないと言う人がいるけど、自分の論理を押しつけて来るという点では、僕にはみんな同じだな」「理解はできないが受け容れる」
0投稿日: 2013.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理解はできないが、受け容れる」裏表紙に書いてあるこの言葉は梨木香歩さんの本に共通して流れている意識だと思う。ただひたすらに受け容れるのではなく対象をよく見て飲み込み消化をし、適切な距離をとる。尊重をする。 彼女の言葉は私にとって、よりよい方向へ進むための道標みたいだ。
3投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のイギリス滞在記 印象に残った話はいくつかあったが、「夜行列車」は特に。タイムリーというか... 歴史問題で人々が互いに反感をもつことについて、ある面からの本質がわかった気がした。
0投稿日: 2013.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説を読んでいても深いなあと思うけれど、エッセイはさらにその人柄の向こうに見える人生が垣間見えて、その深さに心フルフル・・・。 梨木さんの作品には、障害者が自然に、もう、本当~に自然に、登場人物のひとりとして出てくることがあるのだけど、このエッセイにもごくごく自然に登場しています。 「自然に」と構えすぎて、自然さが失われてしまうことが多々あるこの手の話題でこのナチュラルさ。やはり、とても深い方なんだなあと思うのです。
1投稿日: 2013.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ英国S・ワーデンの ウエスト夫人のもとを出入りする、国籍や人種を超えた多種多様な人達。 ウエスト夫人が持つのは 理解する愛ではなく、 受け入れる愛。 作者と、ウエスト夫人をはじめとする様々な人達との出会いや交流が綴られているエッセイ。 嫌みがなく、洗練された深みのある作品。 *** 読むと世界が広がって、 もっとたくさんの人と交流をもってみたくなります。 個人的には最後の2行がとても印象的。読んでいる側でも、なんだか5年の歳月を感じてしまいました。
2投稿日: 2013.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログたんたんとしていながら静かに情熱的で、決して押し付けがしくはなく自分の思いを伝えている。読み終わったあとじわじわ〜と良さが染み渡って来る滋養にいいエッセイ。もっと早く読んでおけばよかったなぁ。子供部屋とクリスマスが特によかった。近いうちにこんな雰囲気、空気感を感じにイギリスとか訪れてみたい。
2投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんがイギリスに留学していた時の 出来事を綴ったエッセイ。 かなり変わった下宿人達を、英国人のウェスト夫人が 寛大な心で受け止めている。 改めて、世界は広く、生き方は様々だということを 気づかせてくれる。
1投稿日: 2013.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログなんともグローバルな話にびっくり。エッセイなんて読んだことなかったけど、こんな感じのならいくらでも読みたいと思った。 梨木さん、すごいアクティブです。まだ「西の魔女が死んだ」しか読んだことないけど、もっと読みたい。
0投稿日: 2012.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイというかドキュメンタリーというか…。腕のいい料理人の自宅のキッチンでの動きを見せてもらった感じ。なるほどここから「からくり〜」や「村田〜」や「ピスタチオ」が作られるんだな、と妙に納得しました。ところで何で苺じゃなくて莓?
0投稿日: 2012.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログあ~こういう人だからああいう作品ができるのだと納得。 清冽で深慮あり。 私的経験を語っていながら私に埋没していない。乾いているのに温かい。心地よい距離感。 世界の情勢を固まり・潮流ではなく、あくまでも個人の身の上に何が起こったのかでとらえるというところが、新鮮だった。
0投稿日: 2012.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ三浦しをんさんがエッセイで絶賛していて、図書館で借りて読んでみた。 アウトドアができて、ワールドワイドで一人旅ができて、別荘を持ってて、外国人の友達がたくさんいて、西の魔女が死んだを書けるなんてとんでもない御人。 憧れます。
0投稿日: 2012.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【内容】 梨木香歩さんのエッセイ.主に,筆者が英国に滞在した時にお世話になったウェスト夫人や下宿人について. 【感想】 梨木香歩さんのフィルターを通した,英国での生活や,様々な文化,周辺の出来事・会話は読んでいて楽しかったです.ウェスト夫人が彼女の知り合い総出で「筆者をニューヨークへ連れていきたいという」想いと筆者の「行きたくない,英国の片田舎で羊の群れの分にまみれている方がマシ」という主張の張り合いにはつい吹き出してしまいました. また,その折に出てくる慎ましい主張,思考にはっとさせられます. 例えば, 夜行列車の予約席とは全く異なる席に案内された時の,車掌の蔑視感情,誤解を解こうとすれば感情が波立つ.解決できても納得がいかない.だからといって,表面的な怒りに身を任せて訴えるのは不毛である.本当に自分が感じたのは…. 筆者は本当の感情を理解するのは難しさ,ましてや従軍慰安婦問題といった国家レベルの問題や,犯罪の被害者側の感情といった,他者の感情・尊厳を理解する難しさと必要性を訴えます. 国家間の領土問題やいじめ問題など,今も「他者」への想像力・共感能力を努力する必要が(意識的に努力する必要が)あると思います. 私も筆者のように,少し立ち止まって考えられたらと,自戒します.安直に想いを吐き出すのではなく.
5投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作家の本はまだ数冊しか読んだことないものの、エッセイまで小説と同じ雰囲気を漂わせていることに驚き。真面目すぎる女性?
0投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログまるで小説のようで、 文の節々が温かくて、 読んでいてなんだか和やかな気持ちになりました。 優しさの溢れた素敵なエッセイです。 ちょっとした休憩時間にローペースで読むと良いと思います。
1投稿日: 2012.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこういうのを随筆っていうのかしらん。エッセイというと軽い感じがする。 イギリスの庭園や、町並み、いなかの雰囲気をありありと思い浮かべることができる。 理知的で、かつ受けとめてくれるウェスト夫人と梨木のおだやかな関係が心地よい。
0投稿日: 2012.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012.8.26読了。 他人の原風景を知るというのは、覗き見をしているようで落ち着かないけど…「西の魔女が〜」の根っこが知れたようで嬉しい。
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の頃に「西の魔女が死んだ」を読んで、とても面白かった。 その後、「からくりからくさ」「りかさん」を読んだら、全然面白くなかった。 今読み直したら面白くなっているだろうか。 このエッセイはとても面白かった。 女性のエッセイは酒井順子、さくらももこくらいしか読んだことがない。 あとは雑誌にちょっと載っている「オシャレでしょ」系とか「スノッブでしょ」系、「季節感に敏感でしょ」系とか。 女性のこんな知的なエッセイは始めて読んだ。 米原万里とちょっと似てるけれど、米原さんは大概どぎついことを言うが梨木さんはどぎついことは全く言わない。 常に極端にならないように生きていると言うか、絶対に他者を否定しないようにしているようだ。 一番最初の「ジョーのこと」なんて、くらたまのだめんずウォーカーに載っていても引けを取らないエピソードだと思うが、著者はジョーの選択を否定しない。 しかし、「カッコつけてないで止めてやれよ。馬鹿じゃないの?」とは思わされないように書かれているんだから、すごい。 悲劇と喜劇は紙一重と感じた。 解説にもあるように、外国の素敵な友人との交友なんて鼻につくに決まっているのに、気にならない。 下世話でないのに嫌味がない。 とても素敵な手元に置きたい本だった。
4投稿日: 2012.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解はできないが受け容れる。ということを、観念上だけのものにしない、ということ。 言葉の上ではいくらでも人は無限に可能性を広げていくことができるけど、それを行動に移すことは難しい。 理解できないけど、受け入れる。そのために感情ではなく、知識を手に入れること。 異文化の人だけじゃなく、身近の人にもそれをしなければ。
1投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外の人とは価値観が違う。 誰でも知っているけれど、 この事実を本当に知っている人は、 実際にぶつかり合った人だけなのだろう。 海外での暮らしを経験したら、 毎日どれほど刺激があふれることになるのだろう。 「価値観が違う」なんて簡単な言葉では表せないほどの経験をするのだろう。民族としての尊厳・宗教・差別など、一人の人間の歴史よりも、もっと深い深い歴史がついてくる。 こういう経験があってこその、 梨木香歩の作品達なのか。 自然の描写がとても綺麗なのは、 イギリスの豊かな自然を見たからかもしれない。 幻想的なこともさらっと描いてしまうのは、 アフリカからの留学生が猫の呪いを信じている事を目の当たりにしたからかもしれない。 海外での暮らしをしたいと思った。
4投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩のエッセイ イギリスでのホームステイ ウエスト夫人 過去・現在と視点変換が激しい どう生きるべきなのか 受け入れる、とは? すごく綺麗な文章 色々と考えさせられる 読後感は爽やか
0投稿日: 2012.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスに留学した体験を描いた物。 丁寧な文章で、真摯で独特な視点でとらえられた情景に、なんだか今まで動いたことのない悩の部分を刺激されます。 ユーモラスな出来事や、人の暖かさが心地良い。 おもに、下宿先のウェスト夫人との交流。 素敵な人ですね。 学校教師で児童文学作家でもあった。 どんな人にも手をさしのべようとするホスピタリティに満ちているため、面倒な相手の世話を背負い込むことにもなるのですが。 著者がイギリスに半年滞在していたとき、20年前の学生時代に下宿していたウェスト夫人の元を訪れる。 そこはロンドンよりも北のエセックス州、S・ワーデンという町で、まず語学学校に通うためだった。 「ジョーのこと」では14年前に滞在したときにウェスト夫人に紹介されて知り合ったジョーという女性の思い出。 地元のグラマースクールで教師をしていたジョー。大家族で育ったが、ほとんどが聴覚障害者。 ジョーは信じられないぐらいドラマティックなことが起きる身の上だとウェスト夫人が称していた。若い頃に事故で一人だけ生き残ったとか。 ジョーは快活で有能で、著者が手こずる子供達の世話も楽々とこなした。 著者は先生の子供達のベビーシッターを時々していて、楽しいのだが、やんちゃなので疲れ果てるのだ。 後にジョーの元彼が舞い戻ってきて、ウェスト夫人は心配して長い手紙を寄越した。元彼のエイドリアンは知らないうちにインドで結婚もして妻子有りらしいと途中で知れたのだ。それを知った著者も具体的には触れることができずに、ただジョーを応援する手紙を書く。 が、エイドリアンはふいに姿を消し、ウェスト夫人の小切手帳が持ち出されていた。 ジョーも消息が知れなくなってしまう。 「人間には、どこまでも巻き込まれていこうと意志する権利もあるのよ」と彼女なら言いそうだと思う著者。 「王様になったアダ」はナイジェリアのファミリーに困った話。 わがままで傲然としていて、お礼も言わない。 身分が高く、後に一家の父親アダは本当に王様になったのだった。 どこへ行くにもお付きがぞろぞろついてきて、まるで囚人のようだと本人はウェスト夫人に情けない顔で語ったとか。 それまでのことも「名誉に思うべきです」という態度だったらしい。 「ボヴァリー夫人は誰?」は近所に越してきた脚本家の女性ハイディが、うっかりした発言で反感を買う。 反核運動が盛んな頃で、著者も近所の人と共に参加したりしていた。 大人しそうに見える老婦人も驚くほど活発にアムネスティの活動をしたりしていて、知的で公共心の強い人が多い。 そういう土地柄なのに、ボヴァリー夫人の現代性を語るときに、「地元の女性のほとんどが専業主婦で有り余る時間をもてあまし幼稚化している」と書いてしまったのだ。 反論されて、その後すっかり大人しくなったハイディを気の毒に思って、ウェスト夫人はさりげなく和解の場を設ける。 「子ども部屋」は一人で旅行中の出来事と、その時々に思い出した出会いの話。 ウェスト夫人の元夫のナニーの話が印象深い。 元夫はヨークシャの裕福な地主の家柄。 ドリスという女性は子守りとして8歳から奉公に来て、家事一切をするナニーとして88歳まで独身でその家に仕えた。 ウェスト夫人はお茶も入れられない若妻として、家事を教わったのだ。 字も読めないが、忠義者で、家事のエキスパート。 離婚後もウェスト夫人は老いていくドリスを訪ね続け、著者も同行して一度会う。 ウェスト夫人は、もとはアメリカ生まれ。 3人の子をもうけた後に、夫とは離婚。 親がクエーカー教徒だったわけではないが、途中で共感して自らそうなった。 ウェスト夫人の父親は、戦争で銃を持つことを最後まで拒否した人だったという。 夫人の3人の子はインド人のグルに傾倒して、グルに付き従ってアメリカへ渡ってしまう。ある意味、親に似たのでしょうか。 その数年後に出会った著者。 空いていた子ども部屋には、児童文学の蔵書がみごとに揃っていた。 他に出会った人たちも個性豊かで、いきいきしています。 2001年末のウェスト夫人からの手紙で締めくくられています。 春になったら苺を摘みに行きましょう、と。 著者は1959年生まれ。 映画化された「西の魔女が死んだ」など、作品多数。
8投稿日: 2012.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者である「梨木香歩」氏の、学生時代すごした英国での日々を、シンプルな筆致ながらも、登場する様々な価値観を持った人物たちと織り成す濃密なタッチで描かれたエッセイ。 こういう人との付き合い方が、今の著者の精神性を養ってくれてるんだね。骨太な人間関係。日本人にはあまりなじみがないかも。
0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイです。英国での人々との交流を書いています。 あまり好ましくない人のことでさえ、梨木さんの文章表現、人間性で、何故か愛すべき変わった人になってしまうのが不思議です。 自分の信念を貫く強さ、出会った人々には、どこまでも寛容な作者。 いろいろな国の人、人種の人と出会い、戦争問題、反核、信仰の違いなどについても書かれてあり、とても深い、良いエッセイでした。 これを読めば、英国に行きたくなります。
0投稿日: 2012.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人の感性が、そこから紡ぎ出される言葉が、好き。エッセイはその、作家の作家たるエッセンスが凝縮されてるように思うよ。
0投稿日: 2012.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの言葉の「着地点の選別作業」はいつも素晴らしい。終始温かな雰囲気を纏った文体から、時折垣間見える情熱や鋭さもいいエッセンスとなっていて、客観的視点を一貫していないところもじっくりと文章を読ませるのに一役買っているように思えた。いいエッセイ集でした。
0投稿日: 2012.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ清廉、とか、瑞々しい、とか、、、「透明感」という言葉が似合いそうな言葉が光るエッセイ。 英国を軸に、滞在先で体験した出来事や、出会った人々について淡々と語り続ける、という内容。その中に、時折、自分の内面をさらけ出すような、あるいは逆に、内側を見つめすぎて閉じこもってしまったかのような、静かで鋭い表現が顔を出し、そのたびに胸を突かれる。 外国で、住み続けるのではない旅人の外国人として生活する中で感じる違和感を、どんなに些細なこともひとつひとつ生真面目に足を止め、ジッと見つめる視線はとても繊細。たとえば、庭先を走るリスの色にも気づくことができるような時間の過ごし方。 直接にはそんな内容でないにも関わらず、大人になる過程でやり過ごしてきたものたちを拾い集めるような印象を残す一冊だった。
2投稿日: 2012.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ『西の魔女が死んだ』で梨木さんのファンになり大分読んできたが、最高の本。というか人生の中で出会った、私上最高の本。全然押しせがましくなくて、すーっと心に染みわたりほっこりさせてくれる、そんな優しいお話です。
1投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ英国に滞在していた著者がその滞在中に出会った人たちとの関わりを描いています。 エッセイとはいっても各章が比較的長いので読みごたえがあります。外国人と関わることで、または外国で過ごすことによって経験する事柄を敏感にとらえその時の思いを深く考えていく著者の姿勢が全編を通して見られます。 この本を読んで人間(または人種?)の多様性を理解することの難しさとアイデンティティを持つことのバランスについて考えました。 多様性を理解する、なんて簡単には言えるけれど本当のところどこまで理解できているのか?と自分に疑問は残りますがそのための一歩としては違いを認めることが大切なんだなぁと思いました。そしてその違いはまず自分があるから、自分というものを知っているからこそ見えてくるものなんだろうなぁと感じました。 もう一つ感じたのはアイデンティティを強く持ちすぎると、自分とは違う人間を受け入れることができなくなってしまう可能性があるということです。 色々な受け取り方が出来る本です。でも読後感は何かしら考えさせられる本でもあります。秋の夜長、こんな本はいかがでしょうか。 *表紙が星野道夫さんの写真で、とても美しいものです。
1投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイです。梨木香歩さんのバックグラウンドがわかる1冊。 こんなふうに物事を見たり聞いたりしてきたから あんなお話が書けるんだなぁ、と思った。 道理で凛とした言葉とお話を作る人だ、って納得。
1投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の過ごしてきた人生が、物語のように語られる。 彼女の作品に流れる空気がそっくりそのまま出ている。 精神を落ち着かせたいときに読むとよい。
0投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんなところへ行っていろんな人と触れ合った経験が書かれたエッセイ。 ほんとこの人はいろんな経験をしてるなぁと思うんだけど、たぶん経験以上に感じていることが人よりも多いのかなぁと、読んでいて思った。 静かに、淡々と書かれている感じが、好き。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内定先から読書感想文を提出するように言われており、参考図書の一冊として挙げられていたのがコレ。参考図書のリストの中で一際目立っていた。それもそのはず、参考図書のリストには「ザ・リーダーシップ」とか「働く君に贈る〜」などのビジネス本や自己啓発本が連なっていたのだから。 私は梨木香歩さんの作品をすでに何冊か読んでおり「なんとなく手にとってなんとなく読める本」として彼女の作品を認識していたが、本作も期待を裏切らぬ心地の良い文体で私をウェスト夫人と過ごす日々へといざなってくれた。 しかし彼女のエッセイを読んでいると、私は彼女の体験に激しく嫉妬してしまう。なんて羨ましいのだろう、と。私には英国に行ったことも、下宿に滞在して様々な人と出会ったこともないし、友人が海外から日本にいる私に会いに来ることもない。エッセイに書かれた彼女の体験の全てが羨ましくなってしまう。 それでも、彼女が体験したことと彼女が抱いた感覚に何か近しいものを私も感じる。 以下に、印象的だったフレーズを引用しながら、私の体験を綴ってみる。 p.100 ---神を信じているかと単純に尋ねられれば今でもそのたび真剣に考えこみ、それは「あなたの定義する神という概念による」とまじめに答えてしまう。--- 私が初めて海外に行った時、それは中学3年の夏のことなのだが、タイとマレーシアでそれぞれ一週間ずつホームステイをした。マレーシアは多民族国家であるのに対し、タイはまさに仏教国であり、各家庭にミニ仏像があるような国である。タイでホストファミリーから「あなたは、仏教徒?」と聞かれ、「イエス」と答えた。また、二度目の海外経験であるオーストラリアでのホームステイでは、「あなたは神を信じている?」と聞かれ、「ブディズム」と答えた。 これは、単に私が自分を説明する手間を省き、都合のいい返答をしたに過ぎないということは重々承知していた。高校1年生では宗教に関して小論文まで書いたが、それでも宗教に関する質問にはいつもどのように答えたらよいのか考えこんでしまう。 p.149 -----あなたが私の言うことを信じてくださらなかった、あの時。 -----私は本当に悲しかった。 この彼女の言葉は、予約したはずの列車の座席にスムーズに案内されず、「軽い東洋人蔑視の気配のようなもの」を感じた時に相手に伝えたものである。 私が友人と2人でインドに旅行した時、何やら日本語で話しかけてくる少年がいた。私たちはあまりその少年の相手をせずに歩いていたが、少年はそれにめげずずっと私たちについてきた。彼は近くでお店をやっていると言う。私たちはガイドブックに記載されているお店に行こうとしており、少年は親切にも「その店ならこっちの道だよ」と教えてくれた。私はどうも人を信じやすい質なので(ただし、それが原因でスペインではスられているのだが)少年の言うことを比較的信じていたが、友人は「見ず知らずの人なんて信用できない、本当にそっちの道なのか」とかなり疑い、少年が教えてくれた道ではない道も確認し始めた。その時、少年は「なぜ僕の言っている道に行かないの!信じてくれないなんてひどい」と怒っていた。当然である。人に親切にして、信じてもらえなかったら、そりゃ悲しい。同情する。その後結局、少年の教えてくれた道が正しいことがわかり、目的の店にたどり着いたのだが、少年は「信じてくれなくてとても悲しかった」と私たちに言った。とても申し訳ないことをしてしまったと思う。 おそらく、日本で(もしくは生粋の日本人が)「その店ならこっち」と教えてくれたたなら、迷わずその道を行っただろう。しかし、彼がインド人であったこと、が少なからず...と、いうかかなり大部分かもしれないが、彼の発言を信じられなくしていたのではないかと思う。ガイドブックには「日本語で話しかけてくるインド人に注意しろ」と散々書かれていたのだから、無理もなかったとも思うが、そういう先入観や偏見を強く持ってしまった自分自身を恥じている。 そして何より、「信じてくれなくてとても悲しかった」と素直な気持ちを打ち明けてくれた少年の純粋さを尊敬する。 p.127 価値観や倫理観が違う人間同士の間でどこまで共感が育ち得るか、という課題。 おそらくそれは永遠の課題であり、人類が平和への道を歩めるかどうかの答え。私は、この課題にずっと直面していたい。そう思っている。
2投稿日: 2011.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ深くて、正直なところ、私の中でまだ未消化なところが多い。 だから、うまくことばにできないのだけど、 ウェスト夫人の博愛精神、 梨木さんの感受性、 幸せなことばかりがつまっているわけではないし、 ときには少し悲しみを帯びた部分もある。 でも、決して暗い気持では終わらない。 もう少し、日常でアンテナを張ってみたい、 自分の感性をしっかり持ちたい、 そんな気持ちにさせられた。 もう一度、ゆっくり向き合ってみたい本。
2投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の外部に対する無関心さとナルシシズムを思い知らされる。 受容さえ拒絶して裏を読もうとするのは、歪で未成熟である事だけが理由じゃない。
0投稿日: 2011.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ前に一度読みかけて、途中までしか読めなかったのが、今回はひきこまれてすんなり読めた。イギリスが少し近くなったからか。ウェスト夫人の受け容れる姿勢について。
0投稿日: 2011.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ彼はそれから、言いにくいことを言うかのように、ちょっと俯いて、 ――K・・、You are not capable…… と呟いた。その言葉が一瞬虚をついたように私に迫って、私は、……I am not capable of what? と、質すべきか、それとも I know と認めて、それから押し黙るべきか、どちらとも分からず、ただどちらも口にしかねて、視線をそらして微笑むしかなかった……。 イギリスでの滞在経験を主としたエッセイ。
0投稿日: 2011.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最後の部分、 You are not capable・・・・・ "You are capable."を「あなたならやりかねない」と考えて、そのnotなので、「あなたであってもできない」という解釈をすることにしました。 日本を訪れた友人が、「人と人が本当に相互理解して、お互いを認め合ったり助け合ったりして生きることや、違う国に住んでいて文化が違ったとしても人が分かり合うことは、頑張ったらできるんじゃないかと考えている(ように予てから見えていた)」作者に対して、「文化の違いは大きいと実感した。アフリカとかに比べれば受け入れやすいだろうと考えていた日本でもこんなに差がある。君がどんなに分かり合おうと思っても文化が違う人に相互理解を押しつけるのは無理だ。そういうのを取り除くのはできないよ。しょうがないよ」 という半分あきらめ、半分慰めの言葉だったんだと思います。 あくまで私の解釈です^^
3投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしは外国に行ったことがないから、いろんな国を渡り歩いた人の書いた話を本質的には理解できていないと思う。この本も、様々な国で様々な人に著者が出会い、いろいろなことを考えているけれど、もしわたしがこの立場だったらどうするか?と考えたら自分の主張のなさというか空っぽさに虚しくなった。わたし自身が経験をもっと積んで知識を得ないとこの手のエッセイは楽しめないと思う。しかし彼女の細かな心情の描写は本当に綺麗。
1投稿日: 2011.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
異なる神を信じる者同士で、仲良く平和に暮らせないものかと「研究」をしている知人がいる。 不勉強な私は、「それは政治がやることではないの?」 と思ったのだけれど、 異なる文化を持つ人々の考え方をさぐり、 昔にさかのぼって歴史を紐解いていくことで、 答えを導き出そう、という「学問」なのだそうだ。 自分が正しいと思っていても、他の人にとってそれはその人の信念に反することだったりする。 それは同じ人種間にも生じることなのだから、 異なる神を信じる者同士の「落としどころ」を探るのは容易ではないに違いない。 本書は、異国の地に降り立った日本人である著者が、 異なる人種の人とかかわりを持つ中で、 感じ取ったことがつづられているエッセイ。 『価値観や倫理観が異なる人間同士での間で、どこまで共感が育ち得るか、という課題』。 人種の壁。 宗教の壁。 思想の壁。 文化の壁。 そして、9・11の日を境にできた、それまでの世界とその後の世界にたちはだかる「壁」。 人の数だけ考え方があって、 そのすべてを受け入れることはとうてい不可能。 だからこそ、「壁」はいつまでも人々の間にたちはだかる。
1投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的にはかなりインパクトがあった本。近日中に再読します。 以下ネタバレ。内容は梨木さんの自伝的私小説、らしい。 テーマは多様。宗教感、人種の問題、生命について、などなど。 今まで「物語」の中に折り込まれていた梨木さんの世界観(感)が、「物語」を介さず、ダイレクトに読める。 かなり好みが分かれる作品だとは思うけど、私はかなり好きです。 押し付けるわけではない、あくまで私感という感じで書かれてる印象を受けたし。 読み込みが足りないのでざっくりした書き方しかできませんが、もっと読んでいこうと思います。
0投稿日: 2011.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの目には、すべてが(良い意味で)フラットに映っているのかもしれない。 好き嫌いの激しい私は、考えさせられることばかりです。 梨木さんが書かれる小説の持つ雰囲気はやはり、彼女の生きてきた人生、 そして人間性が現れているのだな、と思えるエッセイでした。 私も、もっと、経験を積もう。
0投稿日: 2011.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイは苦手だったけれども、物語の文体をしている。プライベートなんだけども、インフォーマルな装い。
0投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が本を読むきっかけとなった梨木香歩さんのエッセイ。 優しくも芯の強い本であり、こんな考え方をもって生きていけたらなと思う。
0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読んだエッセイです。エッセイと言うと私のなかでは芸能人の波乱万丈の人生を赤裸々に語ったものと言う勝手なイメージがあり、ずっと嫌煙していましたが、梨木さんのエッセイだけは、どれもすっと自分の心に入ってきて、読んでいて心地よいです。この本は特にお気に入りの一冊。 読んでいるうちに、コレがエッセイなのか、梨木さんの書いたフィクション小説なのか、一瞬分からなくなってきます。それくらい、この方が書かれる小説の原点ともいえるものの考え方やエッセンスが要所要所にちりばめられています。 梨木さんの言葉を読んでいると、「ああ、その感覚、そういう気持ち、なんだか分かる。わたしも持っている。」と思うことがよくあり、自分の中でずっとモヤモヤしていたものが言葉になった感覚があって嬉しくなります。共感とでも言いましょうか…。
0投稿日: 2011.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイは基本的に苦手なので敬遠しがちでしたが、好きな作家さんなので、手を出してみました!もともと異文化交流には興味があったので、内容に引き込まれてしまいました^^
0投稿日: 2011.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんのことば、考え方、全てにふるえる。 同じ人間とは思えない。その眼にこの世界はどのように映っているのだろう。 この愛すべき、ろくでもない世界を。
0投稿日: 2011.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログへたな書き方をすれば鼻につく留学自慢になりかねないところですが、梨木さんのエッセイにはそんな危険はまったくない。 内容の深さと筆力のなせる技なのでしょう。何度読んでもすべての登場人物が愛しい。
0投稿日: 2011.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作家のエッセイを読むのは初めてだけど、なぜか初めてという感じがしなかった。もしかしたら、「村田エフェンディ滞土録」と似ていると感じたからかも知れない。 「ボヴァリー夫人は誰?」が1番好きだなあ。ウェスト夫人のは強引なところもあるけれど、繊細な気遣いや救済をすることにも長けていて、溜息が出るほど魅力的な人物だ。 この本を読んだだけで自分の世界がかなり広がったように感じたけども、やっぱり著者のようにいろんな世界へ足を踏み入れていろんな人々と関わらないと、自分の考えは深まらないんだろうなあ。
0投稿日: 2010.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ書かれていること、使われていることばが、あまりにも心の内側にぴったりと寄り添う わたし こんなふうに生きていこう
0投稿日: 2010.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の留学時代を振り返るエッセイです。私自身の留学体験を思い起こして楽しかったです。昔ながらのイギリスを感じられて素敵です。
0投稿日: 2010.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩が大好きなので、こちらのエッセイを読んでみました。 著者がイギリス留学中のお話です。 とても心温まるストーリーが多く、イギリスに行きたくなります。 ああ、イギリスに留学したかったなあ。
0投稿日: 2010.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩のイギリス滞在中に始まった交友関係を中心にしたエッセイ。日常生活に密接した人種についての感覚とか、差別とか、人間性とか。 この人、大人だな~、なんて思いながら読んだ。
0投稿日: 2010.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わるのが残念な本だった。この本の世界観が好き。主人公が学生時代を過ごしたイギリスで出会った人たちもそれぞれに魅力的。特にニューヨークで過ごしたクリスマスのエピソードが好き。やっぱり人生の基本はファミリーだ。血がつながっていなくてもファミリーになれるカルチャーが素敵。
0投稿日: 2010.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは小説ではなくエッセイなのですが、 凄く・・・・良くて、どの物語よりも好きです。 イギリスでの留学、アメリカやカナダへの旅行等での経験が主で 様々な人種や考え方の人々と関わる中で著者が考えてきた事が淡々と語られていたのですが・・・ うーん、本当考えさせられる本でした。 「理解はできないけれど、受け容れる」 これが特に印象に残ってる。
0投稿日: 2010.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理解はできないが、受け容れる」 さらっと書いてあるこの言葉は人間にできる最大限の寛容の精神の行動パターン。 KiKi もね、もっとずっとず~っと若い頃は「人は言葉を操ることができる知的な動物なんだから、心をこめて、時間をかけて、じっくりと話し合うことさえできれば分かり合えるはず・・・・ 今は時代が忙しすぎて時間をかけてじっくりと話し合うことができないのが問題」だと思っていたようなところがあります。 でもね、ある年齢を過ぎてからそれが幻想に過ぎないということに気がついたんですよね~。 だいたいにおいて「分かり合える」と思うこと自体が不遜・・・・というか、自意識過剰なんじゃないか? そんな風に感じ始めたのは、このエッセイの中で著者が経験されたのと似たような海外の人たちとの接点を持つ機会を得てからのことでした。 でもね、当初はそれでもしつこく「いやいや、食文化も精神文化も異なる国の人たちとはなかなか分かり合えない部分も多いけれど、似たような食文化・精神文化のアジアの人たちとなら・・・・・」「いやいや、やはり国が異なれば似ているといっても限界があるから、同じ日本人同士なら・・・・・」「いやいや、世代が違うと体験してきた文化レベルが違うから日本人の同世代人となら・・・・・」というように少しずつ、少しずつ、そのエリアが狭まっていきました。 でも、今の KiKi は「同じ国に生まれ、同世代で、同じ地域で似たような環境で育ってきた人であってさえも、分かり合えるというのは錯覚にすぎない」とさえ思っています。 あ、別にその努力を放棄しようと思っているわけではないんですよね。 ただ、「分かり合えるはず」という思い込みは危険なもの・・・・・と捉えているとでも言いましょうか・・・・・。 この本を読んで最初に感じたこと。 それは著者の梨木さんは KiKi とは違って「分かり合いたい」という気持ちは強いものの、どこかで最初から「それは幻想である」とわかってしまっていた人のような気がしました。 どちらかというと不器用で、常に「一般的」と呼ばれる何か・・・・とはほんの少しだけ距離を置いてきた(というより距離感を抱えていた)人だったんじゃないか? ある種、現代の普通の日本人社会にどこか違和感を持ち続けてきた人だったんじゃないだろうか?と。 そして、そこから這い上がりたいが故に、諦め切れないが故に、生き様として「深く生きる」という方向性を志向されていらした人だったのではないか?と。 (全文はブログにて)
1投稿日: 2010.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者さんの下宿先ほか、いろんな国のいろんな人が集まる場所からのエッセイ。 日常の中の、人との関わりについてあれこれ考える内容が多いかな。 だけど主張は激しくなくて、作者さん本人よりむしろ下宿先のご主人さんが中心になってたり。 とても淡々としているので必要以上に沈んだりはしないで済みます。透明感のある文章も上々すてき。 迷走を続ける社会だけど、春になったら苺を摘みに出かける生活ができたらいいな、ってお話でした。 エッセイってジャンル自体の好みで星-1だけど、エッセイ本としては素晴らしいものだと思います。 小説本だと思いこんで買っちゃったのはないしょなのさ!(←
0投稿日: 2010.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」を読んだときも感じたことだけど、この作家さんの考え方やものの感じ方は私と似てると思う。時々はっとさせられたり、痛いところを突かれた気分になったり。 本文中の「ボーダーというよりグラデーションで考えよう。」という一文が好きだった。 「好きではなかったがその存在は受け容れていた」も。
0投稿日: 2010.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイ。 梨木さんの小説のルーツになってそうなエピソードだらけ。 異文化の受容についての捉え方に共感できる作品。 人の名前とか土地の名前が多くて多少読むのに苦労したけど面白かった。
0投稿日: 2010.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログほんわかな話かと思ったら意外にシビアな話だった。 人種と戦争に対する作者の視点が興味深い。作品を作る上で、人との出会いや様々な経験は大切であり必要なのだと感じた。 一つ一つの話に勉強になるところや、ハッとするところがあって、定期的に読み返したいと思った。 世界にはいろんな人が存在し、その分だけ価値観が存在する。 無骨な人は愛しい。
0投稿日: 2010.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログどれも著者の身近でおこった、あるいは近しい人が体験した話なのに、 著者とはどこか薄くて透明な膜がはっているように読み取れる。 多分、著者は自他の境界線をはっきりとひいている人なんだと思う。 だからこそ様々な人とコミュニケートできるんだとも思う。
0投稿日: 2010.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報科教員MTのBlog(『春になったら苺を摘みに』を読了!!) https://willpwr.blog.jp/archives/51119848.html
0投稿日: 2010.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ春になったら読みたくなる一冊。 未来が見えなくてただただ暗い気持ち出歩いているとき、この本を広げると抱えていた悩みが春の日差しによって徐々に溶かされてゆくように思えて来る。 思い悩まなくてはならないことは本当にたくさんあるし、 身を切る風はまだまだ冷たいけれど、水はそのうち温み、空の色も明るくなって日差しもどんどん強くなってくる。 そうしたら、このくじけた心もう一度しゃきっと仕切りなおすんだ。 一人で悩んでいるとつい見えなくなってしいがちな周りの人たちに笑顔をむけて歩いていきたい。 そんな気持ちにさせてくれる読むクスリです。
1投稿日: 2010.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの文章はとても優しい。 ひとつひとつの言葉にこだわって書いていることがよく伝わってくる。 出会った人たち一人一人に真摯に向き合い、考えていることが、文章の端々から分かる。 吃音という障碍を持った男性と話している時、彼がどもって一つの単語を発音するのに時間がかかっても、梨木さんは「言葉本来の意味を考えさせられる」と書いている。 色々と考えさせられる本だなぁと思った。
0投稿日: 2010.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログまず、タイトル! タイトルが可愛らしすぎます! 加えて、この表紙! 手に取らずにはいられません。もうここから個人的にツボ。 留学中のお話や海外を旅行した折など、広い視点からの著者の考え方が窺えるエッセイ。でも、エッセイと呼ぶにはあまりにも多くの物語と土地土地の匂い、人々とのふれあいに満ちあふれていて、文章自体もすとんと入ってくるので、御伽話の世界に足を踏み入れたようなそんな気分が味わえます。 月日が過ぎてまた読んで見たい、そのとき自分はまた新しい発見や感じ方ができるのではと楽しみな本です。 『分かり合えない、っていうのは案外大事なことかもしれないねえ』
0投稿日: 2010.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんのエッセイ集。 梨木さんの深い文というのは、深い体験から来ているのだと思う。 そんな梨木さんの過去をちらりと覗くことができる。 海外でのいろんな人との出会い。 そしてそれに対する梨木さんの視点。 そして、夫人の「理解できないが受け入れる」という姿勢がとってもしみる。
0投稿日: 2010.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんがイギリスにいる間にあった出来事をまとめたエッセーです。ホームステイ先のウェスト夫人との交流が主に書かれていますが、個人的にはお蕎麦とお風呂の話が印象的でした。
0投稿日: 2010.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスにホームステイしていた時の女主人、ウェスト夫人のことを中心にしたエッセイ集。 「理解はできないが、受け入れる」この寛容さが、全てを貫いている。 これって、なかなかできることじゃない。 ウェスト夫人は、しなやかに強い。できれば、こういう年齢の重ね方をしたものだと、自我の乏しい私は思う。 そして、夫人を描いている梨木香歩の視線も、やさしく、つねに公平である。 批判はしない。不愉快になることもあるけれど、それは不愉快になったということだけであって、その人のそれ以外を損なうものではない。という視点って、なかなか通せるものじゃないと思う。 ウェスト夫人の影響の結果なのだろうか。 いいエッセイだった。
0投稿日: 2010.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ― 私たちは人の内界を本当には知らない。分かってあげられない。 理解はできないが受け容れる。ということを、観念上だけのものにしない、ということ。 世界と関わるとはこういうことか、と‥ 海外や留学などに興味があれば、ぜひ読んでみてください。
0投稿日: 2010.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解できないけれど、受け入れる。そんなこと、できるのか?できればいい、できるようになりたい。 再読したい本。
0投稿日: 2010.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ【内容】 「理解はできないが、受け容れる」それがウェスト夫人の生き方だった。「私」が学生時代を過ごした英国の下宿には、女主人ウェスト夫人と、さまざまな人種や考え方の住人たちが暮らしていた。ウェスト夫人の強靭な博愛精神と、時代に左右されない生き方に触れて、「私」は日常を深く生き抜くということを、さらに自分に問い続ける―物語の生れる場所からの、著者初めてのエッセイ。 【感想】
0投稿日: 2010.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイ。 これを読んで、ものすごくイギリスに行きたくなって、行ってしまった。 もちろんお供に連れていきましたとも。 旅行者とは違う視点で書かれているけども、「異邦人の視点」であることは間違いなく、共感できたり新発見・再発見できたりする本。
0投稿日: 2009.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイというより、一つの小説として読みました。あとがきにもありましたが、嫌味になってしまいそうな日記を、こんな風に仕立ててしまう文才は素晴らしいです。ウェスト夫人からの最後の手紙は、本当に素敵で涙が出そうになりました。
0投稿日: 2009.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで本当にたくさんの本に出遭ってきたけど、そのTOP3に入るくらい大好きな本!! 「西の魔女が死んだ」で有名な梨木香歩さんの、イギリス・カナダ在住時代のエッセイ。 きっと、この時期に感じたこと、考えたことが全ての著作の根底に流れているんだと思う。 梨木香歩好きとしては、外せない、たまらない1冊。 毎日をていねいに暮らす。 すごく大変なんだろうけど、梨木香歩さんはそれを自然にしてる感じがする。素敵だなー!
0投稿日: 2009.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ引き込まれる文章。 理解は出来ないけど、受け入れる。 そんな生き方は素敵だと思う。 そんな風に生きられるかな・・・。 受け入れることが出来るかな・・・。
0投稿日: 2009.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家のエッセイはかなり苦手な方なのだけど、この方のエッセイは作品の雰囲気と乖離がなくて大変読みやすかった。 英国の空気や人柄をしっとりと感じられる不思議。
0投稿日: 2009.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ表紙の素敵な写真といい、タイトルの温かさといい ほんわか優しいエッセイかと思っていたら 研ぎ澄まされた言葉達に少したじろいでしまった。 でも内容はイギリス(S・ワーデン)カナダ(トロント)アメリカ(ニューヨーク) での描写が梨木さんの目線でしっかりと伝えてくれていて 観光雑誌と違う海外の魅力を感じさせてもらった。
0投稿日: 2009.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの考え方や周りの人のやさしさが素敵でした。彼女の書く物語の文章から感じる雰囲気の謎に触れたかんじです。たまにむしょうに読み返したくなるエッセイ。
0投稿日: 2009.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな作品に至る作者の道が見えるような、エッセイ。 感情と言葉を、日本と外国を、行き来するように自分の立つ場所を 見つめているような本。 中に、 ー恨みも悲劇もない、ごく普通の市井の人々が正直に生きてきた 跡というのは大好きだ、幽霊だってその秩序の一部に組み込まれて いるのなら、愛さずにはいられない。ー というのがあった。 わたしも、そんな梨木さんが書かれる作品を愛さずにはいられないなあ、と。
0投稿日: 2009.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあー、すごく優しい作品だ。エッセイだけど、完成された作品と思う。 色んな人々との出会いがあり、それぞれの価値観を知る。 そうした出会いと向き合う梨木さんのまなざしも温かい。 時間を置いて、何度も読み返したいエッセイ。
0投稿日: 2009.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。初読2007 友人が勧めてくれて。 読んで泣く記憶の残る大切な本。 「理解はできないが、受け容れる。」 押しつけがましい、不気味で理解不能な「愛」とは違う、さっぱりした現実味のある愛情。 そもそもよくわからないながらも、宗教と世の中の等身大の繋がりをのぞき見たような。 イギリスの風景を想像して読めたことが有り難い。 そうだ 共感してもらいたい つながっていたい 分かり合いたい うちとけたい 納得したい 私たちは 本当は みな
0投稿日: 2009.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログウェスト夫人が、イギリスでの生活が、梨木さんの原点なんだなと思った。理解できないけど、受け入れる。言葉にするのは簡単だけれど、実行するのはとても難しいし、意識してしまう時点で実行できてないんだろう。優しくて柔らかくて、エッセイなのに物語みたいな一冊。でも決して、物語にしてはいけない一冊でもある。
0投稿日: 2009.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「 -----君はいくつだね。 -----六歳。 -----よろしい。いいかね、我々の祖先のそのまた祖先もずっと暑い国で暮らしてきた。そこで適応するためにこういう色になったんだ。 -----わかった。でも、なぜ、あなたの手のひらはピンクなの。それからあなたの口の内側もピンクだ。なぜ? -----・・・・それは、そいういうものだからだ。 -----ねえ、ものすっごく強い風が吹いたら、その色、飛んでいっちゃう?ものすっごく強い風だよ・・・・。 」 p.56 l.6-14 歴史や偏見にとらわれず、相手の違いを認め、うけいれることの大切さ
0投稿日: 2009.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの本は随分前に読んだ『西の魔女が死んだ』以来。 この本は著者初のエッセイ。 イギリスに留学(おそらく児童文学の)していた際の 下宿先の主人、ウェスト夫人を中心とした人種を超えた交流が描かれている。 ウェスト夫人は博愛主義のクウェーカー(キリスト教の一派?)で、 彼女の周りにはイスラム、アラブ、アフリカ、そして日本人(梨木さん)と さまざまな人種が集まっている。 そんな彼女自身がアメリカ人であるのに、読んでいるとそうは思えず、 「イギリス女性」を感じさせる。 昔の回想だろうというのに、鮮やかな描写は、 どれだけ彼女が日々を大切に過ごしているかがわかる。 (日記を書いていたのだろうとは思うけど。) 決して心温まるとか、なまあったかい話ではなくて、 文化の違いや人種差別、 パールハーバーや、イスラム圏の抗争、9.11などシリアスな話題もあるけれど、 ウェスト夫人(と梨木さん)の「理解はできないけど、受け入れる」という姿勢があれば なんとかなるのかな、と思わせてくれる。 これって民族間だけではなく、身近な人でもそうだ。 そして、彼女の周りには特別な人が集まっているわけではなくて、 ウェスト夫人や彼女が深く関わっているからなのだと思う。 (もちろん、ウェスト夫人や梨木さんの人柄が人を集めているのではあるけれど。) だから、感じる力があれば、考える力があれば、 自分も周りからもっといろいろ学べるし、感じられるのだと思わせてくれる。 女性作家のエッセイというと、軽薄なものが多いイメージだけれど、 このエッセイは硬質で精緻な文章。 そして、男女問わない内容だと思う。 名前の印象や著書のタイトルから若い方かと思うけれど、今年50歳の女性で、 世界各国を旅されているようで、”考える”ということに真剣に取り組んでいて、 児童作家というより哲学者とか、心理学者みたいだなぁと感じた。 だけど、やっぱり女性独特の柔らかさや温かさにあふれていて、 読みやすくて、涙がこぼれる文章やエピソードがいくつかあった。 文庫本の帯には そうだ 共感してもらいたい つながっていたい 分かり合いたい うちとけたい 納得したい 私たちは 本当は みな ほんとにそうだなぁって思います。
1投稿日: 2009.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がイギリスへ滞在していた間お世話になった下宿にて、女主人のウェスト夫人を中心に起こったことを綴ったエッセイ。 梨木果歩さんの本って、日本の良さを大事にしてるイメージがあったので、これほどに場所というものにコダワリ、執着・・なんて言ったらいいんだろう、縛られずに世界を見てる方だと知って、本当に目からウロコのようでした。縛られて見ていたのは、私のほうだ。 ああ、でも、そうだなぁ。例えば「からくりからくさ」のときの世界観ってすごく、もっと、なんていうか、この世界全体の繋がりを感じさせるものでしたものね。 バックグラウンドは違うとしても、彼女たちはお互いを大切に思ってる。 自分の大事なものが相手も大事だと思い込まない。また、そうあって欲しいと望まない。違いを受け入れる。 そういうことが普通に行われている場所が、この世界にあるんだなぁと思うと、本当にびっくりしました。 宗教的な意味でも。 ウェスト夫人は自分の子供たちの信ずるところに関しても、全てを尊重するのです。 もちろん、人それぞれ受け取り方は違うでしょうし、ウェスト夫人のやり方を良しとしない方もいるでしょう。でも、そういうところも楽しめちゃうのが彼女なんでしょう。 どんな人種でも、どんな経歴を持つ人でも下宿人を選ばないウェスト夫人みたいに、グローバルな問題ではないにしても、私たちが普段過ごす上で訪れる生活のあらゆることの中で、ウェスト夫人みたいな考え方になれたら、たくさんの問題が片付いちゃう気がします。 分かっているつもりだったけど、言われてみて初めて気づいたような、そんな瞬間がたくさん訪れるエッセイです。
0投稿日: 2009.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「けれど人間にはどこまでも巻き込まれていこう、と意志する権利もあるのよ。」 のくだりが私を前に向かせてくれる
1投稿日: 2009.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩自身が、若かりし頃に学生時代を過ごした 英国の下宿時代の追想と、 そこから生まれて、今なお続く下宿屋の女主人ウェスト夫人を 核にした人々との交流を描いたエッセイ。 「人は出会う力を持っている」 折に触れ、そんなことを思うが、 この本を読んでその思いを強くした。 出会う力に導かれて、人と出会い、 出会いの中で、自力では感じ得ないことを感じ、 学びきれない、様々なことを学ぶ・・・。 梨木香歩は、まさに、そんな力を秘めた人なのかもしれない。 この本の中には、 白人、黄色人種(である梨木香歩)、 そして象徴的に出てくるアラブの人々といった 異文化、異人種とのふれあいに 関するエピソードが数多く登場する。 その“異”なるものと、 どう向き合い、どう接していくのか・・・。 大きな歴史と文化の壁があるものを、 『理解はできないが受け入れる。 ということを観念上だけのものにしない』 という言葉で書き記されている一文を読んだときに、 その意味が、胸に落ちていくような気がした。 外国人と暮らしたことも、深い接点も持ったことが無い私が、 この言葉に反応するのは、 やはり、9.11にはじまる一連の世界の動きを 経験したからだろうと思う。 読み進むうちに、 私は「リベラル」という言葉の意味を考えていた。 リベラルという言葉の持つ、本当の深さを この本は、改めて考えさせてくれたような気がする。 こんな風に書くと、 堅い思想的な本のように思われるかもしれないが、 そんなことはない。 美しい英国の地方での暮らしや、 そこで出会った人たちとのエピソード、 既成概念に囚われない、梨木香歩本人の価値観などが 描かれていて、ゆったりとした気持ちになれる。 ゆっくりと読了し、 さらにその後、好きなエピソードを読み返す。 そんな風に時間をかけて味わった一冊だった。 そして、きっと、これから、何度も読み返す本になる。 そんな予感がする。
0投稿日: 2009.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれに異なる国籍、言語、文化的背景、考えを持つ人たちを、適度な距離感で受け入れるウエスト夫人の生き方に、あたたかい感動を覚えた。 彼女の家に滞在した梨木香歩さんが、さまざまな人と出会い、話し合いながら、人の思いに共感し、それぞれの人の生き方を尊重する姿勢を深めていくことにも憧れる。 外国に出ていって暮らすことは、一見華々しくうつるけれど、本当は派手な社交性よりも、文化が違う人たち誰もが傷つかないようにする心配りや、人が大事にしているものを守る思いやりを育てていく、そういうことが本質なんだろうと思う。 ウエスト夫人の暮らすイギリスの街が、偶然にも私が高校時代に滞在したEssexのSaffron Waldenであり、ウエスト夫人はそのときに通ったBell語学学校の教師であったことにも感激。 この本をプレゼントしてくれた友人にそのことを伝えるのが本当に嬉しかった。
0投稿日: 2008.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイはあまり好きじゃないけど、梨木さんのはさくさく読めた。 エピソードのひとつひとつが物語のようで、 でも自然で。 考えが前面に押し出されているような暑苦しい本じゃないのに、言いたいことがしっかりわかる。 海外で暮らしてみたくなる本。
0投稿日: 2008.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理解はできないが、受け入れる」 文にすれば簡単なことに思えますが、これがどれだけすごいことか。この本を読んで、私は「自分には絶対無理だ・・・!!」と思ってしまいました。 たとえば同じ日本人同士でも、どうしても理解できない人って必ずいますよね。私はそういう人とは、たいていの場合苦手意識か嫌悪感からあまり関わらないようにします。それが当たり前だと思っていたけれど、そうではないのだということをこの本を読んで思い知らされました。 ウエスト夫人の家には様々な人種や考え方の人々が入れ替わり立ち替わり暮していて、そういった人たちとの話を紹介したり、自分でほかの国へ行って出会った人たちの話が語られるのですが、一つ一つが考えさせられる話ばかりです。 ウエスト夫人との話を読んでいると、私は知りもしない人なのにまるで間接的に癒してもらっているような気持になります。優しくて暖かくて、少し(かなり?)強引な時もあって、お茶目心もある。なによりも「理解はできないが、受け入れる」これを実践できるなんて、器が大きすぎます、ウエスト夫人。こんな素晴らしい人に出会えた梨木さんが、私はとてもうらやましいです。 最後の方に、ウエスト夫人からの手紙がいくつかのせられています。9.11後について語る手紙もあります。そのことについて胸を痛め、時には憤って。そして一番最後の手紙、題名の通りの、「春になったら苺を摘みに――――・・・私たちは、そういうことを続けてきたのです。そういうことを、これからも続けていくのです」の部分が、私はとてもとても好きです。心に沁みて、胸が熱くなって、今にも会いに行きたくなるような。 この本を読むことができて、本当に良かったと思います。1人でも多くの人に読んでいただきたいです。
0投稿日: 2008.11.14
