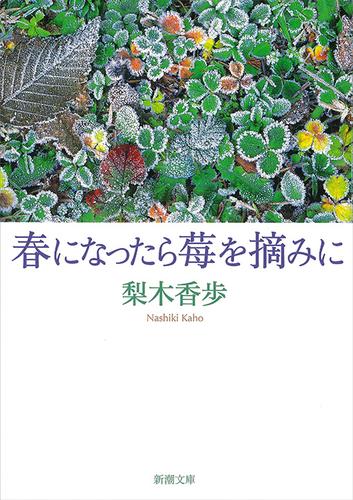
総合評価
(244件)| 78 | ||
| 86 | ||
| 49 | ||
| 4 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんのエッセイ初読。英国に下宿していた時の女主人ウェスト夫人と、様々な人種の人たちとの交流や文化、考え方の違いなどに驚かされたり共感したり。日本に帰って来てもその時の経験が生きたり、梨木さんの人生の深みを垣間見ることが出来て面白かった。
0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった!世界中の色んなバックボーンを持った人たちと心から関わり合えるのって素敵。個人的なことから人種やらのことまで幅広いエピソードがあって楽しかった。
0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ遠い国イギリスで出会った人々との日々の出来事。 作者の芯がある性格に好感を持つ。 英語が話せると、こんなにも多種多様な人々と深くかかわりあえることを羨ましく思う。自分の怠惰をうらめしく思う。 出会いが出会いを繋いでいく。
0投稿日: 2025.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
メルヘンなタイトルだけど、イギリスでの一筋縄ではいかない生活を綴った、芯の通ったエッセイ。ウェスト夫人の人柄が素晴らしい。
0投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログカタカナが多く難しかったけど、人との繋がりとか、世界の文化、差別とか色々と考えさせられる作品だった。
0投稿日: 2025.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログむ、難しかった。登場人物が多い、ローマ字表記、そして知らない言葉が多くて読み終えるまでに時間を要した… とは言っても、外国の文化や、梨木さんの想いがよく伝わる文章で良書。もう少し言葉を知って読み返そうと思う。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」の著者、梨木香歩さんのエッセイ。本書では、他国の人々の出会いや触れ合いが書かれている。文化の違う国で出会った人々との忘れられない思い出。おもしろかった。
6投稿日: 2025.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の季節にあった題名である。都会より自然のある生活を愛する著者の大学出たてで英国Sワーデンの下宿先を二十年後訪ね湖北地方を旅し、山を登り土地の人たちと交流して自分のアイデンティティを確かめながらまた、ニューヨークに渡りニューヨークの刺激に魅了し反核運動に参加したり、クリスマスパーティーに参加した話、カナダトロントに滞在してプリンスエドワード島での旅での老車掌とのやりとり、自閉症児との話など、爽やかな読後感のエッセイです。 季節は今、題名の通りの時期ですが著者の温かな感性がただよう本でした。
0投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルのイメージより複雑難解。聞き慣れない地名や人名が多いのもあるけどなにより異文化!しっくりこない部分も多々ありつつ、そんな人たちやそんな考え方があるものなんだなあと蚊帳の外から眺める感覚で読んだ。1回では消化できないけどちゃんと読めたら楽しいんだろうなと思った。このエッセイがちょっと難しくて心が折れかかっているので、積読の『ピスタチオ』と『海うそ』が楽しく読めることを祈るばかり…
0投稿日: 2025.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ家守奇譚などを読んでいて和風のイメージがあったため、梨木さんが海外で暮らしていたことを知らず驚いた。 クリスマスの話が好きです。 ゲストをたくさん呼んだり、各々料理を準備したり、ネームプレートを用意したり、みんなでツリーの下にプレゼントを積んだり… そんな文化祭みたいなイベントが日常に組み込まれていることが羨ましい。 それと、最後の章の、マイ箸を機内食で使用した後に客室乗務員の方が「お洗いしましょう」というところ。ホスピタリティがすごい。 「自分が彼らを分からないということは分かっていた。好きではなかったが、その存在を受け容れていた。 理解はできないが受け容れる。ということを、観念上だけのものにしない、ということ。」
0投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理解は出来ないけど受け容れる。」 さまざまな意味での「異邦人」を受け容れることは、今の日本社会を生きる私たちに必要な姿勢なのだと思う。理解が出来ないものは受け容れられない、そんな価値観が蔓延るなかで、ウェスト婦人の受け容れる姿勢には気持ちが暖かくなった。 理解出来なくても受け容れていいんだ、と安心感すら覚えることのできる、素敵なエッセイだった。
0投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログまるで物語のようなエッセイ! こういう体験(留学)を バックボーンに 小説を描いてるんだなぁ〜 細やかな心情や情景 ふっと気配を感じる描写 梨木さんの作品 引き続き読んでいきたいと思う
7投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の時に読んでからずっと忘れられない一冊。 価値観が違う人・もの・出来事を、理解できなくても自分の中に受容する姿勢の大切さを今でも語りかけてくる。
0投稿日: 2024.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とても良質なエッセイだった。梨木さんと親交がある方々のお話を伝えたいのではなく、それを用いたお考えがとても素晴らしかった。 烏滸がましい限りだけど、人種差別問題に関する見解や相容れない相手に対する考え方に通ずるものがあって、嬉しく思った。 といっても私は梨木さんやウェスト夫人その他エッセイに出てくる人々ほど賢くもなく、成熟した人間ではないけれど、考えていること、想いは少なくとも一緒だ。 特に理解はできないが、受け入れる。 私が信念としていたのはまさにこれだと思う。 この考えを少しでも多くの人が取り入れてくれたら少し世界は変わってくるのではと思ってしまう。 理想主義的な考え方かもしれないが、過去の歴史の暗い部分を繰り返さない為にも、必要だと思う。 受け入れられないから排除するという考えがないといられないような状況にいる人もいるかもしれない。 でも、梨木さんの言葉を借りれば、できないとどこかでそう思っていても諦めてはならないこともある。 理解できないが受け入れるということは諦めてはならないことな気がしてならない。 最もトロントのリスのジョンの言葉を借りればこの考えも自分の論理を押しつけていることにすぎないのかもしれないが…。 何気なく図書館で借りた本だったが、手元に置いておきたい一冊。 そして、この本を少しでもたくさんの人に読んでほしいと思った。
0投稿日: 2024.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログKの経験すること、出会う人たち、全てがわたしに新しい考えと見方をくれました。魅力的な世界を生きていることをうらやましく思い、わたしも世界へ行って経験をしたいという気持ちになります。
0投稿日: 2024.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ〈再登録〉梨木香歩さんの初エッセイ。「裏庭」の風景描写や異国情緒はイギリスの町、S・ワーデンで過ごした日々がルーツなのでしょうか。様々な人種が集まる土地で感じた価値観の違いに真摯に向き合う姿が印象的です。 若い時にウェスト夫人という慈愛に満ちた人と共に過ごしたこと、彼女と変わらぬ友情を築いてきたことは一生の財産なのでしょう。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「西の魔女が死んだ」も好きでしたが、こちらは英国好きの私には堪えられないエッセイでした。 旅行で行くのと暮らすのでは違うとわかっているけど、私も暮らしてみたい。久しく訪ねていませんが、また旅行したくなりました。 ウエスト夫人の飾らない、でも暖かい人柄に惹かれます。こんなふうに歳を重ねたいものだと思いました。
1投稿日: 2024.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
エセックス州S・ワーデンでお世話になった下宿の女主人、ウェスト夫人を中心とした友人たちとの交友記。梨木さんの小説(それがもとになった映画はみたような)読んだことがないが、友人がいたイギリスの北部を思わせる風景や、人びとの様子がとても興味深い。解説の人が書いているように、梨木さんの感性、好きだ。
0投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
理解はできないが受け容れる。相手を完全に理解することはできないけれど、相手を否定せず理解しようとする姿勢は持ち続けたい思った。 「それが文化である限り、どんなことであろうと私はそれを尊重する。文化である限りは。」 日本人の蕎麦を啜る音に驚いたナイジェリア人女性のこの言葉が印象に残っている。
0投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分とは異なる考え方や感じ方を肯定するでもなく、否定するでもなく、受け入れるにはどうしたらいいのかと思って、手に取った本。 どんなに自分では理解できなくても、好きになれなくても、人が感じたことを尊重できる自分になりたいと思った。
0投稿日: 2023.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ異国の地での暮らし、人との出会いはその後の人生を変えてしまうくらいの影響力があると思う。 人との関係、距離感がいい。 エッセイではないような重さがある。
12投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイなのに物語のような1冊。 ウエスト夫人の人柄に惚れ惚れしてしまう。 こんな素敵な経験が梨木香歩さんを作ったのかなと思うと彼女の柔らかくも強い文章に納得する。
1投稿日: 2023.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」が大好きでこれを書いた方ってどんな人だろう?と思って手に取った。 エッセイと言えば気軽に読めるもの、という思い込みが吹っ飛ばされ、思った以上に難しかった。 ウエスト夫人の人間性に感銘を受けた。
2投稿日: 2023.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ異国の土地での出会いがどれほど素敵で、一緒に過ごした時がどれだけかけがえのないものだったか伝わります。 梨木香歩さんが好きなのとタイトルに惹かれて手に取りました。 想像よりもご友人たちへのメッセージが強く、その方達へ書いているのかな?という内容でした。 またハッピーな内容ばかりでなく、朝の苦痛な通勤電車で読むには少し負担になってしまい、途中で挫折してしまいました。 時が来たらまたリベンジしたいと思います。
1投稿日: 2023.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ寒さが少し和らぎ、花粉が飛び始めてムズムズし始める時期が旬のエッセイだと思う。 あらゆる人々との出逢いが、この250ページに詰め込まれていて、現実の出会いを億劫に思う気持ちを撫でて解いてくれる気がする。 暮らしの中で問を見つけては真摯に思考を重ねる著者の姿には、なぜだか、エッセイに出てくる車掌や駅員寄りのイメージを重ねていた。
3投稿日: 2023.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は読書は同じ著者のものを続けて読んでしまうクセがあります。(またこの著者さんの本の感想かと思った方がいればすみません) こちらの書籍は、大まかに言うと人と人、過去と現在の問題や、日常のエッセイかと思います。様々な話題が取り上げられていました。 一部の内容について、私自身、戦争はもちろん差別されるような環境にも置かれたことがない(認識してないだけかもしれないが)ので自分には難しい話だった。 そうであっても、心によく入ってきて感情が揺り動かされて、初めてこういった話題は今まで理解はしようとしていても深く感情まで動いたことはなかったのだなとこの本で気付かされた。 改めて世界の平和を心から願う。
5投稿日: 2023.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も何度も読んで、カバーがぼろぼろになってきたけど買い替えず持っている本。やりきれない、わかり合えない、けど誰かとつながっていく。
4投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
静謐な文章。静かでしかも日本の冬の空気のような張り詰めた清々しさがある。読んでいて須賀敦子さんの文章を思い出した(解説も言及)。「…覚悟を決める瞬間は、外から見てどうであれ、個人の体験としてはいつでも自力で思いドアを押して向こう側の空気に身を晒すような清冽なものだ。」印象に残ったところ(解説も言及)。
0投稿日: 2023.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログウェスト夫人の人柄と、著者の地に足ついた観察眼に、ホッとする読後感。「西の魔女が死んだ」の背景には、著者の人間性があることに納得した。 自分の周囲にそのような人がいない理由を逡巡し、おそらく私の知性の不足だろうと思い至る。著者の思慮深さを前に、必然謙虚になる。そんな本。 図書館では閉書となっていた。残念でならない。
1投稿日: 2023.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解は出来ないけど、受け容れる。分かってあげられないけど分かっていないことは分かっている。この考え事や姿勢がとても好きだなぁ。色々な人がいて、価値観や生き方が違って家族でも衝突することがあるけど、こんな風にお互いの考えもうまく受け容れていくことが出来るようになれたら…と思った。自分の中で人との向き合い方に悩んだときに、読み返して確認したくなる大事な本だな…と思う。
0投稿日: 2022.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人種や性別を感じさせない、作者のフラットで真っ直ぐな視点とその表現力が素晴らしいエッセイ。 軽く読み進めることができるのに現代を生きる私達へのメッセージ性も充分にあり非常に満足しました。 “相反するベクトルを、 互いの力を損なわないような形で 一人の人間の中に内在させることは可能なのだろうか。” “あれはドリス(人名)そのものよ。 全て青天白日にさらして、何の後ろめたいこともない。” 上記2つのフレーズが、特に印象的。 周囲の友人に自信を持って勧めたくなる一冊でした。
2投稿日: 2022.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ家守綺譚を読んで、同じ作者の本を読みたくなりました。 家守は日本的な話だったので、イギリスに語学留学されていたことに驚きました。 梨木さんに更に興味が湧いてきました。
0投稿日: 2022.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの初めてのエッセイ。 家守奇譚や村田エフェンディ滞土録を読んで、一体どんな人がこんな話を書くんだろう、って独特の世界観に思ってた。少し納得。 また他の本も読んでみたいと思った。 2022.10.07
3投稿日: 2022.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしには少し難しかったかなあ。でも作者の出会ってきた様々な人達との時間など、とても大切な時間をイギリスで過ごしてきたんだろうなと感じた。
1投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「分かり合えないを受け入れる」 最後に伝えてきたこのメッセージは、中々すぐに上手く飲み込めないほど重く、難しく、そして大切なメッセージでした。 色々な人と繋がることをある種強制される現代の中で、「違うもの」と沢山出会います。でも、私は否定されたくないから、そういった「違うもの」を敵として戦ってしまいたくなります。 ウェスト夫人のように「違うもの」にすら愛をおくれる人になることができるのでしょうか。そもそもなりたいのでしょうか。 正義をぶつけ合うこの時代に多くの人と悩みたいです。
1投稿日: 2022.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログできること、できないこと。 ものすごくがんばればなんとかなるかもしれないこと。初めからやらないほうがいいかもしれないこと。やりたいことをやっているように見えて、本当にやりたいことから逃げているのかもしれないこと。 けれど、できないとどこかでそう思っていても、諦めてはならないこともある。
0投稿日: 2022.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログいい本を読んだなあ…と思った。 著者とその周りの人々の交流とかその景色が、外国の小説を読んでいるようで、エッセイという感じがしなかった。 その一方で、人が何かを考えている時、こういう風にするすると思考って流れていくよなあ…と思えるような、頭の中を覗いたような文章だった。 「理解はできないが受け容れる」ことって、理想ではあるけど体現するのは難しいことだと漠然と思っていた。 けどウェスト夫人のような人がいると知れて、人との交流は新しい価値観をもたらすものだと思ったし、人との交流をもっと広げていきたいと思った。 外国の風景も魅力的だった。この本自体が、英国の田園風景を想像させるような雰囲気を持っていると感じた。 2025/3/16 再読 外国に行って人種や文化の違い、経験の違い、信仰するものの違いを避けず、受け止めて考えていく経験が、自分にはないと感じた。
0投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫の内容紹介は「『理解はできないが、受け入れる』それがウェスト夫人の生き方だった」から始まっている。梨木作品は「家守奇譚」「ピスタチオ」を読んだ後だったこともあって、てっきり「不思議への理解」のことと思きや(そういうシーンもなくはないが)、「他人への理解」「異文化への理解」という意味だった。 差別、戦争、宗教などの問題に踏み込んではいるものの、「社会派」というのとも違う。あくまでも、焦点は「社会」ではなく、「具体的な誰か」である。冷静な文章でありながら、これだけの熱量を感じるのは、実際に触れあった、生の人たちの体温だろう。 可愛らしいタイトルのエッセイだ、などと油断できない読み応えである。
3投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスでの下宿生活をメインに、様々な人との出会いや衝突(良いものも悪いものも)が描かれたエッセイ。 色んな土地の情景を想像しながら読むドラマティックな話の数々は小説を読んでいるよう。K...の尖った感性に触れるたび、共感したり、そんな風に感じる?と懐疑的になったりと、自分の感覚と比較しながら読み進める感覚が気持ちよかった。 イギリスの風景の、もの悲しいけどどこかノスタルジックな感じ、に強く共感。 少し色褪せたというか、淋しい色合いの街並みが1番イギリスらしくて好きだなと思う。 特に好きだった、というか自分にない考えだなと思ったのは日英人間で政治的な話題に触れていた時の話。 日本人の英国人に対するコンプレックスは当事者なので想像しやすい。でも英国人の日本人に対するコンプレックスなんてないだろう、ないからこその差別偏見があるのだろうと今まで何となく思っていた。けれど違った。嫉妬の概念が英⇨日の方向にもあると想像したことがなかった。面白いなあと思った。 "あなた方は本当にそのことを話したいの?ーーそういうことを語らせているエネルギーが、「敗戦国のくせに経済大国にのし上がった」国民への嫉妬と黄色人種への嫌悪の混ざったコンプレックスであったり、一方では白色人種とその文化への劣等感であったりするのなら、そこから離れた場所でいくら議論したって互いの合意点になんか到達できるはずもない。"
0投稿日: 2022.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログカタカナの名前を覚えるのがすごく苦手で、読むのに時間が掛かってしまった。これはほんとにエッセイ?と思うほど物語のような経験をしてる作者にびっくり。ウェスト夫人の「理解はできないが、受け容れる」は簡単なようで普通できないことだ思う、、一つ一つのエピソードがもう寛大という言葉じゃ薄っぺらいくらい素晴らしくて、ボヴァリー夫人は誰?のウェスト夫人の行動はあっぱれ過ぎて感動した。
0投稿日: 2021.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解はできないけれど受け止める、受容する。すごくシンプルではあるがなかなかできないこと。言葉にすると一言だけれど、その実現を作者は英国で体験し、実践しているのだとおもった。
1投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログモンゴメリにも人種的な偏見があったことに触れていた。他は全体的にあまり頭に入ってこないが、そこだけ妙に印象的だった。
0投稿日: 2021.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の豊かさって、人との出会いなんではなかろうか?と、思えるくらいの本であった。 作者の作品は、動植物、自然を強く感じる作品が多いが、このエッセイは「人」を感じる作品で特に、「人の行動」がクローズアップされているように思える。人の行動は、十人十色であるが、それぞれの個を受け入れる(個に合意するとか、納得するという意味ではなく、いい意味で受け流すというか…)優しさを感じる。それがこの作者らしい透明感に繋がっているのではないかと、作者を垣間見た気持ちになる一冊であった。 特にイギリスには、3カ月くらい滞在していたこともあったのでとても懐かしかった。私いたところはブライトンからさらに西のボーンマスというところで、イギリスのリゾート地で、海が近く町がとても綺麗なところだった。当時は日本人がいなくて(今ならいるのかというのも知らないが)、ホストもはじめての日本人でなにかと気にかけてくれた。 そんなことを回想しながら読んでいると、ちょっとした描写に、そうだこんな感じだったと、こんなふうに接してくれたなぁと懐かしく感じる。 そして羨ましいのは、作者がそこで出会った害のない(?)個性的なキャラクターの人たち。特に古い友人であるウェスト夫人は、『受容する人』 と絶賛できるのいい。 こんな人たちとの出会いが、作者自身のあの独特な透明感を生み出したのではないかとまで思ってしまう。 本作を読んで、作者の今までの作品で『だからか』と納得するのと、これからの読む作品に対する予備知識ができたような気持ちになり、今までとは違った異なった感じ方ができるような予感がする。 そして自分の心の持ち方と放ち方について、とても参考になった。
48投稿日: 2021.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ10数年前、学生の時に初めて読んで、ウェスト夫人や梨木さんの人との関わり方にさわやかな共感を覚えた。理解はできないが、受け容れる、まさにその感じが、卑屈でも傲慢でもなく自分を相対的に認識するということだと共感した。 以降、社会人になって人づきあいとか自分の振る舞いについて考えさせられたり、グローバルとかインターナショナルとかの言葉を聞くたびにこの本を思い出していた。 で最近、多様性という言葉を頻繁に聞いたり意識するようになって、なんとなくまた読みたくなって手に取ってみた。 深すぎる。 今でも他者と関わる際の理想として完全に共感するけど、自分の日常を振り返ると、身近な人でも受け容れていない自分がいる。なぜだろうと考えると、身近な人ほど理解はできるし相手にも理解することを期待するから違いを受け容れることが難しくなるのかもしれない、と思った。 ここらへんは三浦綾子さんの本を読んだ時もいつも考えさせられるけど、永遠のテーマだと思う。 もう少し歳を重ねて円熟できれば受け容れられるようになるかもしれないという期待もある。自分を顧みる反省し続けることが大事だと思う。
2投稿日: 2021.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ雪崩れるような、思考の奔流のなかを、ゆっくり足場を選んで歩いていくようなエッセイ。梨木さんの留学時代からのエピソードがいろいろ詰まっている。家を借りるとき、買い取る家主になるのに無視され紹介者に話をされていたときでも「このくらいで怯むようでは外国で「外国人」はやっていられない」というユーモア交じりの柔軟さが好き。
0投稿日: 2021.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」の梨木香歩さんのエッセイ。 文化的な背景や個として歩んできた道の違いから生まれる様々な価値観を、「理解できないが、受け容れる」生き方をするウェスト夫人。 その夫人の下宿先に著者も滞在していた時の記憶を中心に、人生の節々で感じた様々な想いが綴られる、というよりも、文を通じて内省されている。 アイルランドの荒涼とした景色に吹く風や、カナダで痛いまでに冷たく輝く雪景色を胸に、「全く理解できない」という煩わしさと、「けれどもわかりたい、繋がっていたい」というさびしさと恋しさ、あたたかさを感じた。 著者の本はこの本以外に「西の魔女が死んだ」と「裏庭」の2冊しか読んでいないが、その本に表れる風景の原体験を感じ取れる本。 個人的には描写されている風景・景色が非常に好きなのだが、何故好きなのか、ということを著者に言語化してもらったようで少し嬉しかった。 宗教観も含めて内省しているので、合う人には合うし、合わない人には合わないだろう。 ****** ”けれど、できないとどこかでそう思っていても、諦めてはならないこともある。 After five years have past. 世界は、相変わらず迷走を続け、そして私もその中にいる。”
0投稿日: 2021.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木さんの世界観にドップリとハマってしまい、普段はエッセイはあまり読まないのですが、梨木さんを知るために是非読みたいと手にした一冊。 海外でお世話になったウエスト夫人についてのエッセイ。 ウエスト夫人が素晴らしい。 「理解は出来ないが、受け容れる。」というのが夫人からきているとは。 人生の中で、とても大切な出会いがある。 まさしく梨木さんにとって、ウエスト夫人こそその人。 この本を読んで梨木さんのことが少し理解できたように思います。 そして、やはり梨木さんは素晴らしいと思いました。 この本の表紙の写真、なんと星野道夫さんの写真。 この本も大切な一冊になりました。
60投稿日: 2020.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文章がきれい! 語彙がきれい… でもイギリスの人名入ってこず、内容入ってこず… いつかじっくり読んでもいいかも
2投稿日: 2020.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ・クウェーカー キリスト教プロテスタントの一派であるキリスト友会に対する一般的な呼称。清教徒革命の中で発生した宗派で、教会の制度化・儀式化に反対し、霊的体験を重んじる。
0投稿日: 2020.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者英国留学時代に、さまざまな人種、価値観を持つ人との交流を通して、ものごとの本質を問い続けた経験が書かれたエッセイ。 この本の口コミで、「ともすれば自慢話になってしまいそうな題材だが、まったくそれを感じさせない」と言った表現を見たが、ああ、たしかにそうだな、と思った。 海外留学系のエピソードは、下手すると「意識高い系」と捉えられそうだが、このエッセイはまったくそんな雰囲気がない。自然体で、出来事ひとつひとつを大切にしている筆者の穏やかさがにじみ出ていて、読んでいて癒される。 「理解はできないが、受け容れる」。多様性が進むまさに今の時代に必要な考え方の詰まった一冊と感じた。何度も読み返したくなる素敵なエッセイ。
1投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ゲート・ナンバーはB10だった。けれど税関も過ぎてそのゲイトに辿り着いてもどこにもラガーディアの文字はなかった。係員も誰もいない。不安になって…』というトロントからニューヨークへと向かわれる梨木さん。私もピッツバーグからトロントというマイナー路線に乗った時に似たような経験をしました。ゲイトに行っても薄暗く誰もいないその空間。時間が迫り来る中、たまらない不安感の中、10分前になって係員がようやく登場。そして超小型機が目の前に。結局乗客4名という衝撃的なフライトでした。他の人たちも特別な感情を持ったのでしょう。その中の一人の方が、『俺たちは選ばれた4人だ!行進していこう』というので降機してから一列に並んで歌を歌いながら行進したのを覚えています。外国人のノリのよさって凄いな…と、あの時を思い出しました。…と、書くとこれもエッセイみたいなものでしょうか。まあ、そもそも私のことなどどうでもよくて、早速ご紹介しましょう。「春になったら苺を摘みに」という不思議なタイトルのついたこの作品、これは梨木さんが初めて書かれたエッセイです。 ロンドンの南方にある南サリー州に半年間滞在することになった梨木さん。『三人の子どもがあり、上二人が女の子でアンディとサラ、一番下がビルという男の子だ』という二十年前学生時代を過ごしたウェスト夫人の下宿を訪ねます。『ウェスト夫人のキッチンの窓からは、スイカズラやアイビーが絡まる生け垣を通して、サリー家のサンルームが見える』と生活の中にもまず植物に目がいくのは如何にも梨木さんらしいところです。 そんな中、梨木さんはある時旅に出かけます。人は旅に出ると色々なことを考えるものですが、『山の方にひたすら歩いていくと道は砂利道、次第に細くなっていく』という道のり、『さっきから後方を歩いていた男性二人組にここで追い越される。「ハロー」「ハイ」しばらくいくとまた別の一組に追い越される』という段で梨木さんは『西洋人と自分との差を徹底的に感じさせられるのは、こういうときだ。がっしりした肩幅。厚い胸板。のっしのっしと迷うことなく確実に長い歩幅で進むその安定感とスピード』と感じ次のようにまとめます。『この調子で古代から次々に厳しい自然に挑んできたのだろう。また征服できると錯覚するのも無理はない気がする』。う〜ん、ここまで考えることが大きいと単なる山歩きが哲学の道のりになりそうです。そして、大きな岩で休む梨木さん。遠くに『動く黒い点が見える。双眼鏡で見るとやっぱり羊だ。その横でもう少し長い影が動く。双眼鏡でようやく人らしいことを確認する』。何がどうということのないあまりに普通の行動です。それを梨木さんは『まったく人間というのはなんでこんな必要もないことをせずにいられないんだろう』と書かれます。こんな普通の行為にそこまで意味を考えられるとは、もう梨木さんの前では人間のあらゆる行為が意味なしでは許されなさそうです。もっと気楽にいきましょうよ、と声をかけたくなります。でも、こういう風に考えていく感覚があの独特な作品群を生み出す原動力になるのでしょうか。 また、ウェスト夫人が語ったこんなエピソードへの言及もありました。ミーティングの途中に急に気絶して床に倒れてしまった女性を見たウェスト夫人。『その時、まあ、なんと鬘(カツラ)が外れてしまったのよ。誰も知らなかったんです。みんな息をのんだわ』という場面。そのとき、『ジャックが助け起こしたんだけれど、彼が駆け寄ってまず最初にしたことは何だったと思う?』と梨木さんに聞きます。『黙って鬘をさっと彼女にかぶせたんです。それが最初にしたことよ。それから助け起こしたの』と答えます。『すてきだと思わない?ジェントルマンよねえ』と言うウェスト夫人。う〜ん、これも日常のワンシーンですが、自分だったらどうするだろう?と思いました。こんな咄嗟の場面にこそ文化の違いというか、その人がベースで持っている考え方が自然に出るのかもと思いました。英国人男性はみんなジェントルマンなんでしょうか。 今まで何名かの作家の方のエッセイを読んできました。圧倒的にインパクトがあるのは三浦しをんさんだと思います。三浦さんの場合、読者がいることを前提にショータイムのようにエッセイを展開される印象を受けます。一方で梨木さんのこのエッセイは、イギリスやトロントで過ごした日々のことをそのまま淡々と記されています。見たまま、聞いたまま、そして体験したままの事ごとを梨木さんならではの表現に置き換えて淡々と文字にしていく、そして出来上がったのがこの作品だと思います。人によって好き嫌いはあると思いますが、私には少し入っていくのが難しく感じてしまいました。少し近寄りがたいというか。ただ、前述した三浦しをんさんは自著の中でこの梨木さんのエッセイを高く評価されているので、やはりこれは好き嫌いの問題なのかなとは思いました。 直前に「村田エフェンディ滞土録」を読みましたが、舞台となる国は違えど異国を表現する感覚に両者の中に似たような雰囲気感を感じました。特にウェスト夫人とディクソン夫人は私の中では同一人物なくらい重なりました。このエッセイを書かれた経験があったからこそ「滞土録」が生まれたんだろうなと感じました。そう、観光するだけでなく異国で生活する感覚、すれ違うだけでなく異国の人と交流する感覚、そして感じるだけでなく異国を理解しようとする感覚。「滞土録」のあの異国留学の奥深さはこのエッセイの先にあった世界なのだととても納得しました。 梨木さんの独特な世界観から生まれる作品たちが根差す土壌の感覚に少し触れることができた、そんな印象を受けた作品でした。
34投稿日: 2020.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ西の魔女が死んだでおばあちゃんが住んでいるところと同じ匂いがして、やっぱり人が生み出す物語はその人の経験の中から紡ぎ出されるものなんだなと思った 雄大な、というよりは、ささやかで時間がゆっくりと穏やかに流れていくような、そんな自然に囲まれた環境が好きなところ、わたしもそうだしもしかして似たような感性なのかも いわゆる健常者(この表現は適切ではないかもしれないが)の延長線上に自閉症やアスペルガー症候群があるという話が印象的だった なぜだか私はエッセイが苦手なので小説としてはそこまでだけど、この雰囲気はとても好き この人の本をもっとたくさん読んでから読み返したらまた違う感想になるのかな
0投稿日: 2020.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ時として著者と同じ目線になり、その物語を存分に味わった。 普段は第三者的に傍観しているものが、本エッセイは著者の目線と重なってとても深いところで理解した気がする。 もしかしたら私の中に著者の感覚と似ているところがあるのかもしれない。 人の心に敏感で、さり気なく優しい。 そんな著者の人柄にも触れることができる。 装丁の星野道夫氏の写真がとても素敵で、本書にもピッタリだ。 切なさと優しさ、そして温かさを感じられる一冊。
0投稿日: 2020.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ梨木香歩さんの本は、本当にすごい。単なる児童文学者では絶対にない。世界を旅した経験もあり、むしろ社会的な人であるように思う。「ピスタチオ」ではそこを目指していたように思うが、経験として積み上げたきたものがあったのだということが分かる。
0投稿日: 2020.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常を丁寧に、周囲の人や自然、歴史や食べ物に目を向けて生きると、人生は素晴らしいものになるのだと思えた。
0投稿日: 2020.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ0033 2018/05/29読了 風景と色んな国の人のことを想像すると楽しい。イギリスでのんびり過ごしたくなる。楽しいだけじゃなく、色んな国の人といるからこそ人種や歴史のことも出てくる。これが現実かと思うこともあれば笑い話になることも。全てそうなればいいのにね。 梨木香歩の本、初めて読んだ。 初めてだけどエッセイだから、小説も読みたい。
0投稿日: 2019.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリス、カナダ、アメリカ、日本で過去に経験した回想録(?)。丁寧に綴られていて、空気まで感じられそうな文章だった。特に、イギリスではどのような思いで過ごされていたのか知りたかったので、当時の様子を少し垣間見れたようで楽しめた。別のエッセイも読んでみたい。
0投稿日: 2019.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ウェスト夫人は私の見た限り、彼らを分かろうと聖人的な努力を払っていた、ということは決してなかった。彼らの食べ散らかした跡について、彼らのバスルームの使用法について、彼らの流す大音響の音楽について、いつも頭を抱え、ため息をつき、こぼしていた。自分が彼らを分からないことは分かっていた。好きではなかったがその存在は受け容れていた。 理解はできないが受け容れる。ということを、観念上だけのものにしない、ということ。
0投稿日: 2019.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ表紙の良さに惹かれて購入。 外国人の名前の登場人物が沢山出てきて、 また時間が行ったり来たりするので、 多少混乱しつつ、頁を行ったり来たりしながら、 時系列を整理してどうにか読み切った。 エッセイなので、著者の人柄や主張が強く表れており、 その点では読みごたえがあった。 外国人とのやり取りの中で生じる価値観の違いや それぞれの生き方、環境や空気感の違いが 海外に行ったことのない私にも伝わってきたのも良かった。 イギリス、カナダ、アメリカ、ナイジェリア等様々な国の人達・国の様子が出てくるが、違いはちゃんと伝わってきた。 時々、事件や重い話題も出てくるが、 変に嘆いた文章ではなく、落ち着いているのがいい。 よってノスタルジックな雰囲気もリアルに感じられる。 ウェスト夫人と著者のような関係は憧れるし、 ウェスト夫人と著者のそれぞれの人柄も好きだ。 私も外国人の友達が欲しくなる。旅に出たくなる。
0投稿日: 2019.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家梨木香歩氏の、エッセイ。小説は3作品読んだが、エッセイは初めてである。本書は、著者が2回にわたり英国サリー州で下宿していた家の女主人、ウエスト夫人や他の下宿人たちとの交流や出来事を中心に、体験したことや考えたことを綴っている。 とても気前が良く、どんな人でも受け入れるウエスト夫人はアメリカ人だが、離婚後英国で下宿屋をしている。私もサリー州に住んでいたので、著者の表現するイギリス人の特徴や、イギリスのもやがかかったような風景が、実感できた。著者は素晴らしいホームステイ先に出会い、かけがえのない経験をしたと思う。本に出てくる人たちも様々だが、皆いい人である。 著者はアメリカに住んだことが無いので、その部分は多少誤解というか違和感がある。また、イギリスでの暮らしの部分はとても良く書かれているのだが、やはり小説家が政治的思想に言及すると、難しいのだと思った。作者個人の見解なので、正しいとか間違っているとかではないが、従軍慰安婦問題や同時多発テロについて、こういうふんわりとしたエッセイの中で読むのは不思議な感じがした。
0投稿日: 2019.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」の著者で有名な梨木香歩のエッセイ集。 梨木香歩の作品は、「西の魔女が死んだ」と「海うそ」を読んだのみである。 あまりにもタイプが違う作品でありながらそれぞれが素晴らしい内容の小説であり、こんな小説が書ける梨木香歩というのはどんな人なのだろうと興味があった。 このエッセイ集にを読んで、彼女がどのような人たちと触れ合い作家としての感性を育んだかその一端が垣間見えた様な気がした。 驚いたのは、彼女のベースになっているのは海外での生活と様々な国の人たちとの交流にあった事であった。 梨木香歩という作家に興味があるならば間違いなくお勧めの一冊である。
0投稿日: 2019.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者のイギリス留学時代以来の知人(大家さん)や、取り巻く人々とのやりとりが軸。 最初、あれ、エッセイだよね? え、小説? と迷子になったような気がするほど、登場人物たちの心の動きまで写し取るような観察や感情移入がすごい。 タイトルの意味は最後に出て来る。懐かしい人との思い出の深さに胸打たれた。
0投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読。随筆。まるで小説なのかと思うような章で始まった。素敵な人々と出会い、思い出と関係を積み重ねていく。それでも戦争、人種差別、テロ、文化の多様性、自閉症といったきついテーマに対して、揺るぎない思いがさらりと挟み込まれていく。声高に叫ぶことなく、柔らかく沁みこませるように。異質なものに一斉攻撃して襲いかかるような世の中で、こういった静かな声に巡り合うと、良心に触れたようで安心する。 p.210「優しく落ち着いた声の、少し吃音のある彼の英語は、辺りの空気の質まで変えてゆくようだった。同じ単語が。少しずつ繰り返され立ち現れてくる気配は、言葉の持っている本来的なセンスをゆっくりと私に味わわせるゆとりを与えた。早口の英語に少し疲れていたのかもしれない。もともと、吃音のある人と話すのは好きだった。一つの言葉がその本質を露わにしていくような空気の振動のようなものが感じられるから。」 久しぶりに会った友は加齢のためか酔いのためか吃音が強くなっていた。そのときの私の楽しかった気持ちを見事に表してくれた一節。
0投稿日: 2019.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2018.11 図書館 筆者留学中のエッセイ。 村田エフェンディ滞禄期に通ずるものがある。 相変わらず、短いのに読みにくい。 エッセイだけれど、物語のような内容。 木梨果歩の賢さやひととなりがよくわかる。こんな自由な人生をおくってみたかった。
0投稿日: 2018.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の留学中に世話になった英夫人を中心に添えたエッセイとは知っていた。田舎の賢夫人の暮らしぶりがテーマと思ってたら、随分違った。一篇一篇が結構な長さがあるし、色々騒動も持ち上がるし。 イギリスでの生活が舞台だから、「玄関ドアの高さをフルに使って入ってきた彼は、」なんて表現になるのかな。判り易いけど、チョッと面白い。 レディー・ファーストは「甘やかし」と思い、心地良く感じながら「トウゼント オモッテハ イケナイ」と自分に訓戒を垂れる。 本を読むこともなく働き通しの家政婦の生活、敬虔なクウェーカー教徒の暮らしを思いやり、日常を深く生き抜くことを問う。 神への信仰にひたむきな女性が先住民の精神文化を侵略したことに対し、信仰心とそれに対する疑念を一人の人間の中に持ちうることが可能かと自問する。 テクテク歩きながら、水の流れに足を捕われながら、相反する方向性を保つ無意識のコツ、方法がなにかあると考える。 こういう処が、梨木さんらしい文章だなと思う。 気位の高いナイジェリア人の家族、「道徳」を知らずに育ったコソボ出身の姉弟、女性の人格を認めないイスラームの留学生、…。 色々のエピソードが満載だったが、読後は彼らを理解が出来ないで、頭に来てたりしながら、それでも、受け入れようとするウエスト夫人の姿が立ち上ってくる。 日本人の殻に閉じこもっている自分。お前、それでいいのかと問われているように感じた。
3投稿日: 2018.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解はできないが受け入れる、はすごく納得できる。 だから家守綺譚の主人公はああいう感じだったんだなと。
1投稿日: 2018.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ私はいつもこの方の持っている表現の的確さ圧倒されてしまう。 「人の纏っている気配の核心的なことの性質」 「相反するベクトルを、互いの力を損なわないような形で1人の人間の中に内在させる事は可能なのだろうか。その人間の内部を引き裂くことなく。豊かな調和を保つことは。」 こういう表現に出会ってしまうと、いかに自分が適当なところで妥協して言葉を選んでいるかを突きつけられているような気になる。 本当にしっくりくる表現を選びとるまで粘る頑固さ? そして、ウエスト夫人という方が、梨木さんの作家としての仕事、否、生きていく上での深い部分に刻印を残していることを知り、梨木さんの作品を味わえる者として夫人に感謝したいと思う。
1投稿日: 2018.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段狭い視野で生活している自分の世界が少し広がった気がした。 人と人との向き合い方、いろんなバックグランドがあるなかで、たとえ理解できないものであっても、尊重する姿勢を持っていたいと感じた。
1投稿日: 2018.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ三浦しをんさんの三四郎~より至。 梨木さんにとっての人生の宝物が、この一冊に集約されているのかなと、タイトルの意味を知って深く感じました。英国、北米など描かれている情景も綺麗で、想像の中で楽しめました。この本を通じて一緒にまだまだ旅したいと思えるような一冊でした。
2投稿日: 2017.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がイギリスで経験した多くの人との交流を,素晴らしい筆力が書き留めた楽しめる文章が満載だ.ウェスト夫人のキャラクターは凄いレベルの包容力が醸し出すものが基本になっているようだ.それにしても,多くの人との交流をうまくこなすのは,大変な苦労があったと推察するが,一人でやってのけるバイタリティーは特筆ものだ.イギリス社会の奥深さを実感する場面が多くあったが,未だに訪れたことがないので,機会を作りたいと思った.
1投稿日: 2017.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が学生時代に英国へ留学した先で出会った人々やそこでの交流、感じたことを綴った初エッセイ。 梨木香歩さんの作品は好きで何冊も読んでいます。フィクションからも感じ取れるのですが、鋭い観察眼や落ち着きある文体は、このような常日頃からの視点や海外での経験があったからなんだと腑に落ちるようなエピソードが多く描かれていました。 梨木さんの留学先であるウェスト夫人がきりもりする下宿所。ここには様々な国籍の学生たちが異なるルーツ・文化・思想を抱えてやってきます。 いわゆる“違う者同士”が集まる一つ屋根の下で、ウェスト夫人は彼らを等身大で受け入れ接します。来る者を拒まず、去る者を追わず。一人一人を気に掛けながらも適度な距離をたもつウェスト夫人の人との接し方や振る舞い、さりげない気遣い、優しさとユーモアを併せ持つおおらかさは読者としても気持ちの良いものだし感心することばかりです。そんなウェスト夫人と、彼女のもとに立ち寄り去って行った多くの下宿者たちの様子を、梨木さんは大局的に、鋭くも優しい眼差しで切り取っていきます。 全てを捨てて犯罪者である恋人の背中を追ったジョー、気さくに交流していた日々が一変し一国の王となったアダ、一夜にして町中の嫌われ者となったベティなど。ウェスト夫人はそんな彼らを前に困ったり、傷ついたり、不快に感じたりしますが、「理解はできないが受け容れる」姿勢を崩しません。彼らの考えをまるっと受け容れ寄り添います。 全体を通して感じたのは「違い」。 親友でも、恋人でも、家族だとしても、自分自身とは違う人間です。自分には自分のルールがあるように、他人には他人のルールがあります。会話によって埋まる溝もあれば、歩み寄りの域をとうに越えた深い深い溝もあります。深い深い溝に対峙したときにどう対処するか。このエッセイにはそのヒントが書かれていました。 狭い世界でも広い世界でも、ギスギスとした緊張が続く毎日。自身と相容れない思想に対し壁をつくり、反発し、敵視し、ついには排除しようと躍起になるのは簡単ですが、「なぜ?」という疑問を常に抱えながら一度立ち止まる冷静な姿勢が、今後ますます必要な世の中になってくるように思います。 柔らかなタイトルと留学先の日常という舞台に反し、深く考えさせられる内容が詰まっていました。 ================== 「世界は、相変わらず迷走を続け、そして私もその中にいる。」 「理解はできないが受け容れる。ということを、観念上だけのものにしない、ということ。」
9投稿日: 2017.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本の田舎に閉じ籠っている私に、ちょっぴり刺激的でふんわりとした優しい風を吹き込んでくれた! 梨木さんが若い頃下宿していた英国の女主人と、その下宿先等で出逢った人達との交友記。 色んな国の老若男女との異人種交流。 楽しいことばかりではなく、時に緊張に満ちていて、価値観や倫理観の違いに驚かされる。 世の中には人種や障害の有無等様々な境界が存在する。 自分とは「異なる」相手の全てを理解することは限界があり「理解はできないが受け容れる」の考え方に共感した。 梨木さんの描く物語の礎がここに詰まっている。
3投稿日: 2017.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり、梨木香歩さんのエッセイが好き。 丁寧で、物事をよく見て、人の話をよく聞いてる。 中学生のときに読んで感動した「西の魔女が死んだ」、どうやったらあんな本が書けるんだろうと思ってたけど、このエッセイを読んでなんか納得。 イギリスの郊外で毎日丁寧に大切に日々を過ごしていたんだなぁと。 私は1年間ロンドンに暮らしてたけど、こんなエッセイ書けないわ。笑
0投稿日: 2017.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ理解できないが受け容れる、 異文化間で感じるのは生きるうえでの究極みたいなところ。 一番好きなのはここ 「ただひたすら信じること、それによって生み出される推進力と、自分の信念に絶えず冷静に疑問を突きつけることによる負荷。 相反するベクトルを、互いの力を損なわないような形で一人の人間の中に内在させることは可能なのだろうか。その人間の内部を引き裂くことなく。豊かな調和を保つことは。」
1投稿日: 2016.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の学生時代の英国での下宿話を中心としたエッセイ。 その中では様々な人種・考え方の人と暮らしていく中でみにつけた(もしくは本質的な本人の性質としての)、ウエスト夫人の生き方から 著者が感じたこと・学んだことが描かれている。 英国人の気質・外国で外国人として生きるということ・日本人とは、、、など 随所に考えらせられることがたくさん。
0投稿日: 2016.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中にはいろんな人がいるんだ、ということ。たとえその人をどうしても理解できないし受け入れられなくても、その人はただ世界中にたくさんいる‘いろんな人’の1人でしかないことをしっかり理解すること。 世界をしっかりと見つめ、理解するにはまずそこから始めなければならない。ものすごくエネルギーが要りそうだけど、ものすごく淡々と描かれているのがかっこいい。
0投稿日: 2016.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ英国、米国、カナダにおいて、日本人の著者が様々な人々と出会い、その土地ならではの体験を綴ったエッセイ。旅をすること、異文化に触れることは、その人に多くの発見と気づきを与え、感性を養い、人生を豊かにするものだ。
0投稿日: 2016.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「西の魔女が死んだ」以来の梨木香歩。知的な言葉選びと端正な文章が印象に残った。特に「子供部屋」の中にある、「日常を内省的に深く生きる」という言葉が頭から離れなかった。他にもあっこの言葉いい!という箇所がいくつもあって購入してから何度も読んだ。解説者がこの本から須賀敦子を連想していたが、私は須賀敦子も好きなので、なるほどと納得した。どう生きて行くか、と考える際のヒントが詰まっている、そんな本。ブックカフェのレビューを見て購入したけど当たりだった。
0投稿日: 2016.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文庫化を楽しみにしていたエッセイ。 >>ピースフルで静かで思いやりに満ちた美しい生活。 そういう生き方に憧れる。
0投稿日: 2016.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい梨木香歩だった…。 どうやったらこんな、凛として透明な空気を言葉で作れるのか?何も起きてないのに、泣きそうにさせる。 たぶん、自分がいる所から遠い場所だと感じるから。御伽の国みたいだもん。 だがしかし、カタカナ名は頭に入ってこないなと改めて感じた。
0投稿日: 2016.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞で紹介されていたので手に取った。 この本を読むまで梨木香歩さんを知らなかった。 著者が学生時代に暮らしたイギリスの下宿を再訪し、その下宿や、下宿を通じて知り合った人達、下宿のオーナーたちの間で起こる出来事をつづったもの。 日本語がとても丁寧で、読み始めたときは翻訳本かと思ったほど、長い形容詞が特徴の文体で、人物描写や情景描写が素晴らしい。 梨木さんの他の本も読んでみたい。
0投稿日: 2015.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ重い。でも好きなところもある。子供部屋とか。 とても読みにくいエッセイで、何を、誰を、いつを指しているのか読み取るために苦労したところが結構あった。 それでいいのか?
0投稿日: 2015.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
梨木さんの作品の根源のようなものを感じるエッセイでした。 「理解はできないが、受け容れる」 「私」が学生時代を過ごした英国の下宿先の女主人ウェスト夫人の生き方。 さまざまな人種や考え方の住人たちや時代に左右されないウェスト夫人の生き方に触れ、「私」は日常を深く生き抜くということを問い続ける。 心に響く言葉が、出来事がたくさん書かれており、よくわからないのに泣けてくるお話がたくさんあった。 何度も読み直したいと思った。 「できること、できないこと。 ものすごくがんばればなんとかなるかもしれないこと。初めからやらないほうがいいかもしれないこと。やりたいことをやっているように見えて、本当にやりたいことから逃げているのかもしれないこと。―いいかげん、その見極めがついてもいい歳なのだった。 けれど、できないとどこかでそう思っていても、諦めてはならないこともある。 After five years have past. 世界は、相変わらず迷走を続け、そして私もその中にいる。」(p.247) 最後のこの言葉にはっとさせられた。
11投稿日: 2015.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイ…それも、作家さんの書くものは極力読まないようにしている。それなりの理由はあるのだが、それは私的なこととして。 エッセイなのに、この本には梨木香歩さんの物語が吹き渡る。 理解はしないが受け容れる。ウェスト夫人の振る舞いを評したこの言葉、梨木氏の言葉選びの正しさに唸ってしまった。 理解しようとしたけれど理解できない…ではないのである。妥協点を見出そうとしたのではなく、あくまでも能動的な自己主張として、理解はしない。それがウェスト夫人の態度であり、全編を吹き渡る風…梨木氏のモラルなのだ。 異文化理解、多文化共生は流行り言葉として多くの人々が口にする。しかし、ジョンとの会話の中で、梨木氏は何気なく本質に触れている。 「分かり合えない、っていうのは案外大事なことかもしれない」 世界の隅々まで心地よく吹き渡る風。 梨木香歩さんの体の中には、それがある。
2投稿日: 2015.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好きな梨木香歩さんのエッセイ本。 結構難しかった…。 私にはエッセイ本は向いてないのかもしれないと思った…。でもやはり言葉選びが美しくて好き。
0投稿日: 2015.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだのは10年くらい前だったろうか。 梨木さんはフィクションだけじゃなくエッセイも素敵。 瑞々しく色彩豊かな文章が強く印象に残っている。 いずれ再読したい。
0投稿日: 2015.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『夜行列車』が特に良かった。例外を除き、海外での体験が語られていた。それにしても梨木の記憶力のすごさには舌を巻く。その人生への覚悟とも言える潔さは尋常ではない。
0投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「王様になったアダ」の少年との会話、「トロントのリス」が好き。 ジョンと話してみたくなりました。 behold,look
0投稿日: 2015.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人を受け容れる気配にあふれた温かさ、かといって必要以上に好奇心をあらわにしたりしない適度の親密さ。この絶妙な距離感が心地よい。」
0投稿日: 2015.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに知性があり、思慮深く、魅力的な女性の生活の一部を知れることは私にとってもありがたいことです。 巻き込まれる、意思の権利 子供部屋の風 本当に伝えたいこと クウェーカー たくさんのキーワードがあって、いろいろと読み進める途中に考えにふけって進まない部分もあったりと、何重にも楽しめる素敵なエッセイです。
0投稿日: 2015.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。ふと読みたくなって手に取った本です。梨木さんはエッセイであっても、小説のように物語を感じさせてくれる不思議な作家さんです。私が、ときに梨木さんの小説よりもエッセイの方が面白いと感じるのは、それが「私小説」のように思えるからかもしれません。 淡々と語られるそれぞれのひとたちのことば。それを注意深く聞き取っている梨木さん。そこに生まれる物語。 本をいつも手元に置いておきたい作家さんです。
0投稿日: 2015.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログエッセイらしいけど、読み終わってなお現実とは思えない外国の童話のような非日常感が余韻として残っています。 同時代の日本人女性にこんな人生を送ってきた人がいたなんて… どうりで彼女の作品には他の作家にはないテイストが詰まっているはずたわ。
0投稿日: 2015.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ心に留めておきたい言葉が多い作品だった.滞土録もそうだけど,梨木さんの作品は自慢みたいなものは感じなくて,だただた憧れるような人生経験が描かれていて,なかなか自分はその体験を実際にはできないので,こうやって本を通して得ることができるのは有りがたいなぁと思う.ちょうど今の自分や周囲の迷ってる友人たちに送りたい考えが多くて,こうやって今のタイミングにこの本に出会えてことに運命すら感じました.なので,今読んで欲しい!と勧めるのではなく,ふとしたときに手に取って欲しいような作品でした.
1投稿日: 2015.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスの田舎町の風景が目に浮かぶ素敵なエッセイ。第8章「トロントのリス」にある、モシェと重い自閉症の子のエピソードに涙。
0投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログカウンセラーの先輩お勧めの本で、これも結構前に読み終わっていた ブログに感想アップ待ち状態で数カ月・・・ すっかり読んだ時の記憶がない・・・ 梨木さんと言うと「西の魔女が死んだ」が確か映画化された気が・・・ その程度の記憶で、正直、梨木さんの小説を読んだことがなかった この本は梨木さんの初エッセイだそうです イギリスに留学されていた時、ホームステイされていたお家の ウェスト夫人や、ウェスト夫人をめぐる人達との交友記となっています 正直、ヨーロッパに興味がない私が読んでもピンとこない風景や生活の描写 「失敗したか?」と思いましたが、なんだか最後まで読んでしまいました それはきっとカウンセラーの先輩からの「カウンセラーが読んだ方が良い本」という 言葉が引っ掛かっていたからかも知れません 「夜行列車」というエピソードがあります トロントから赤毛のアンで有名なプリンスエドワード島に列車で行くというエピソード 詳細は伏せておくけど、最後の方に書かれてある文章に「あぁぁ、ここだ」って ハッとしたところがあったのでご紹介します 「そうだ 共感してもらいたい つながっていたい 分かり合いたい うちとけたい 納得したい 私たちは 本当は みな」 (p161) やっぱり、この本、もう1回読んだ方がいいな・・・
0投稿日: 2014.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに乙女チックな響きやノスタルジックなものを感じますが、英国で留学生活を送った作者の下宿先での交流を中心とした日々の様子や旅先での出来事などを綴ったエッセイです。 作者の精神性を形作ったものがこの中にあるようなので、梨木さんのファンには見逃せない1冊でしょう。 先日読んだ「渡りの足跡」の中にこの本の内容が一部あったので、詳細が分かりすっきりしました。旅先での思わぬ出逢いを書いた場面ですが、こういうことは出逢うべくしてあることなのでしょう。 「嵐が丘」の舞台のヒースの野とかプリンスエドワード島に行く途中の出来事、赤毛のアンの作者のモンゴメリのことなどに触れた箇所もあり興味深く読みました。 外国での日本人としての矜恃に触れた場面や、コスモポリタン的な内面などを読むにつけ日本以外では暮らしたことのない私は、梨木さんの行動力に憧れつつ、共感できる部分も多くありました。 アスペルガー症候群についての記述もありました。引用しますが、‥ここからは自閉症、ここまではそうでないという線は、だから、実はどこにも引けないのだ。先に述べたようにその傾向は大なり小なりあらゆる人々にうちに偏在する。ボーダーというよりグラデーションで考えよう。‥ この考え方は至極しっくりきました。
0投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ他人にも、自分にも厳しい人だと思った。 最初は、イギリスの田園生活を優雅に描いたエッセイとしか思わなかった。 イギリスの小さなコミュニティの中での軋轢。 太平洋戦争時にアメリカで強制収容された日本人の重い経験。 イスラエルからの移民で、小児麻痺の子どもを抱えながら多くの障碍を持つ人のために献身的に働く夫婦などなど、人種や歴史の折り重なったところの、人々を静かに描いていく。 厳しくも、人間らしくあろうとする筆者の姿に、感動を覚える。
1投稿日: 2014.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
英国留学の経験を持つ著者の、下宿先の主人であるウェスト夫人とその周りの人々との交友録。梨木さんの小説に漂う 独特の雰囲気のバックグラウンドをうかがえる事が出来る一冊です。
0投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が学生時代を過ごした英国の下宿、その女主人ウェスト夫人をはじめとした、様々な人種や考え方を持つ住人たち。 色々な国、色々な民族、色々な宗教、色々なイデオロギー。 その違いに振り回され、時に理解に苦しみながらも、多くの下宿人を受け入れ続ける夫人と下宿人たちとの日常を通して見えてくるもの、生まれる問い。 共感してもらいたい つながっていたい 分かり合いたい うちとけたい 納得したい 私たちは 本当は ウェスト夫人の下宿は、民族対立が先鋭化しつつあった時代の中においてまるでサンクチュアリのよう。 数々の梨木作品の根底に流れるもの、物語の生まれる土壌はここにある。
1投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説のようなエッセイ。 梨木さんの作品はまだあまり読んだことが無いけれど、「西の魔女が死んだ」のまいの感受性の強さやおばあちゃんの受けとめる力、「家守綺譚」の人々の姿勢は梨木さんの考え方と経験によって出来たものなんだなあ、と思った。 たくさんの人が出てくるので、ちょいちょい誰が誰だか分からなくなってしまって混乱。カタカナの名前はなかなかしっかりと覚えられない……。
1投稿日: 2013.12.23
