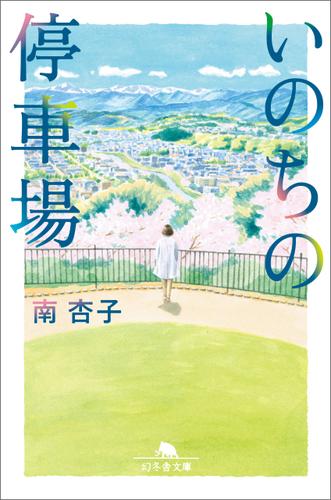
総合評価
(167件)| 66 | ||
| 70 | ||
| 17 | ||
| 2 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私自身が総合病院の病棟看護師として勤務していたこともあって、「あるある!」と共感できる状況がたくさん出てきた。 その中でも印象に残ってるのは、佐和子の父が、家で転倒し骨折したことをきっかけに、ADLが低下し、「教科書通りの経過」を辿っていくエピソードだ。私も今までたくさんの患者に関わってきたが、この「教科書通りの経過」を辿る患者は少なくなく、毎回どうするべきだったのか、長期入院は避けた方がよかったのでは、と思うことが数え切れないくらいあるからだ。主人公の佐和子は、その問題の中でたくさんの葛藤がありつつも、最終的に父の「家に帰りたい」という願いを聞き、在宅での看取りを選んだ。 佐和子のような葛藤を抱える人が、この先もたくさん出てくるのだと思う。そのときに、患者とその家族の思いを尊重し最大限にサポートしていける看護師でありたい。
2投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療について考えさせられる一冊。 人生の最期をどこで迎えるか。 高齢化が進んだ日本で、病院で死ぬことが当たり前だった時代は、もう終わりを迎えているのだと思う。 国の財政も逼迫し、人的資源も限られている。 終末期医療を考えさせらる本だった。
5投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ重かった。自分に置き換えて、親を自宅で看取ることが出来るだろうか?家族は自分が自宅で逝くことを許してくれるだろうか?どちらもハードルが高いと思う。萌ちゃんの章は辛過ぎて読むのが苦しかった。
7投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ生とは何かということについてとても考えさせられる作品だと思います。命があるだけでは生きていることにならないということが痛いほどわかりました。その人によって生の概念が違うし、生きている目的それぞれだからこそ、迎えたい最期の形もそれぞれなのだと感じました。最期を望んだ形で迎えられる人の方が少ないのかもしれませんが、最期を迎えようとしている家族がいるとき、その人の人生の中で大切にしていたものを少しでも多くあの世に持っていけるように支えていこうと考えました。
4投稿日: 2022.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は病院勤務の看護師です。 地域で働くのもいいなぁと改めて思えた本でした。 スタッフ同士の良い関係性があるから患者、家族も安心できるのでしょうね
3投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉永小百合主演で映画化されて気になっていた本。 救急救命センターの第一線で長年働いてきた医師・佐和子が故郷の金沢に戻ってきて訪問診療医になる。 在宅医療、そして終末期医療について考えさせられて深かったです。 特に終末期に家族は1分1秒でも長く生きてほしいと思う。それは当然の感情と思っていたけれど、患者本人に耐え難い苦痛や痛みがある場合、生きていてほしいと思うのは酷なことなのではないだろうか。本人も残される者のためにそれを耐えるべきなのだろうか。もう楽になりたいと思うのもまた当然ではないのだろうか。両者の思いをすり合わせて納得できる形で最期を迎えられるといいよね。 小説の中のいくつかのケースを読みながら本当に考えさせられました。自分が家族なら、本人なら…と立場を変えてみると相反する思いが理解できる気がする。立場は違えど、お互いのことがかけがえのない大切な存在だからこそ、また難しく。 私は痛みに弱いから苦痛はとりのぞいてほしいなぁ。
2投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこの年齢になって知人とのお別れや自分自身の事を思い手に取って見たくなったタイトル。在宅医療、延命措置、安楽死等、考えされる内容でした。
4投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログリアリティ溢れる作品で、何度か涙しました。 在宅医療、身近な人の死などを扱い、いつかは自分の身の回りにも訪れるであろうことを深く考えさせられました。 ラストは本当に、ドキドキしました。読後もまだ思い出してはドキドキが止まらず、、自分がさわこの立場だったら、お父さんだったら、仙川先生だったら、、、と色々な立場を想像してみるものの、なかなか答えは出ません。いつかはこの誰かの立場に立つときが来る、という覚悟みたいなものができただけでもありがたく思います。
7投稿日: 2022.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年末の大掃除で発掘した本です、この本は2021年の間に読む本の様ですね。読みかけになっていたために、評価は「★一つ」にしております。内容が不満足だったわけではありません。 2021年12月29日作成
0投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ救命救急センターで働いていた医師・咲和子。 とある責任を取り辞職。故郷金沢へ帰り、在宅医療をメインで行う診療所で勤めながら、終末期医療の在り方の是非を問う6遍からなる物語。 著者の作品は3作目。 現役医師の視点ならではの、命の取り扱いが丁寧に、とてもリアルに描かれていて、深く深く考えさせられた。 また、石川県は私の親父の故郷であり、少年期は毎年のように家族で田舎へ帰っていたこと、金沢や能登には思い入れもあって、より感情移入に拍車をかけた。 特段、6章「父の決心」は、親の立場、子の立場、日本の死に対する法の在り方など、多角的な観点から読者へ問うてくる。 兎角、本作の主人公の設定が絶妙過ぎる。 命を救う以外の選択肢などない一刻を争う救命救急のベテラン医師から一転、命の終い方に寄り添う新米医師へと遷移する。 そして60歳を過ぎた主人公の咲和子先生が、出会いと別れを繰り返しながら、どんどんと成長していくではないか。 ありがとう、南杏子。 貴女の視点に賛同するともに、物語から放たれるエネルギーを確かに受け取った。 ただのおじさんだと、常日頃俯瞰視しつつあった自分自身にも、まだまだ伸びしろがあるのではないかと。 命ある限り、やればできることがまだまだあるのではないかと。 別段、わたくしごとで恐縮。 来春に、とある資格を取ろうと決めた。 目的は今の私に必要な知識の習得と、取得のエビデンスとなる肩書きを持つことだ。 昨年の合格率が40%と私からすれば難関だ。 よって当面、小説読書をちょいと控えようと思います。ちょいとですよ。 いかんせん私はシングルコアスペックゆえ、勉学集中対策を講じる必要があると判断。 ただのおじさんから、有知識兼有資格のおじさんに。 ちょいと頑張ってみます。ちょいとですよ。 読書、鑑賞を愛される同士のみなさん、引き続き素敵な読書鑑賞ライフを。 みなさんが感情を揺さぶってくれる作品に、これからもたくさんたくさん出会えますように。
261投稿日: 2021.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ紐解いたのは映画を観て、ラストにどうしても納得いかなかったからです。原作を読んで確かめてみたかった。ラストまでは大変素晴らしい作品でした。吉永小百合は少し年寄りすぎる気はしたけど、それさえ目をつむれば、広瀬すずも松坂桃李も西田敏行も田中泯も、それぞれの患者もたいへんな熱演でした。観客は年寄り層を中心に大勢詰めかけロングランになった。もしかしたら、私の思い違いかもしれないとさえ思った。 以下ラストについてのみ書きます。ネタバレです。 主人公咲和子(吉永小百合)の父親(田中泯)は神経性の異痛症になり、治療不能、死ぬような痛みに襲われるようになる。願うのは、「積極的な安楽死」。まともすぎる医師である咲和子は当初は当然断る。それは殺人であり、法に触れるという意識もある。でも、父親の冷静な度重なる懇願と、金沢に帰ってずっと終末医療に携わってきた咲和子に、心変わりが訪れ、父親の願いを(点滴の投与という形で)受け入れることにするのです。 映画では、訪問介護専門のまほろば診療所の所長(西田敏行)にだけは真実を話すけど、情熱を持って続けてきた診療所も辞め、父親と2人になるところで終わるのである。 私はこのラストはダメだと思った。 いくら診療所を辞めても、ことが公になれば、必ず「元まほろば診療所医師」ということで、せっかく軌道に乗ってきた診療所に大きな迷惑をかける。そんなこともわからない咲和子さんなのか?私は納得できない。 原作の方は、いろんな面でそのリスクに免責を与えていました。 ひとつは、所長含めて同僚にもしっかり説明していた。安楽死場面に(第三者の見届けという理由で)2人も同僚を呼んでいる。 ひとつは、1962年に出た高等裁判所の特別に安楽死を是認しうる6つの要件を紹介し、咲和子さんがそれを全てクリアする様に段取りをつけたことである。 ひとつは、父親がさあこれから点滴投与を行う直前に死亡するというハプニングが起こる。よって、おそらく咲和子さんは殺人罪が問題になるようなことはないだろう。 しかし、それでも咲和子さんは警察に連絡をするということで、小説は幕を閉じる。「積極的な安楽死」を、是非とも認めるべきだ、論議の一石を投じるべきだ、という作者の強い想いがそういうラスト描写になったと思う。 映画は、あまりにもラフ過ぎた。成島出監督という好きな監督なのだけど、尺の関係か、裁判所判例も一切出てこない。私はやはり映画は、お勧めできる作品になっていないと思う。 小説は、それでも警察に連絡する時点で、診療所に迷惑をかけると思う。それでいいのか?と思う。 理論的には、「積極的な安楽死」について、実は私はなんとも言えない。私は、過去3度も、臨終場面で「消極的な安楽死(延命治療をしないことで死亡すること・合法)」を直ぐには選ばなかったことで、後々まで後悔している。未だに、私は良くなかったという想いだけはあるけど、どの時点で、何をするのが1番Bestだったのか分からないでいる。 思えば、私の最初の選択から13年経つけど、昨日のように後悔の念が起きる。 安楽死問題、とても難しい課題である。
71投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家であり医師でもある南先生だからこそ書ける医療小説だと思います。 必ず向き合わなければならない身近な人の死について考えるきっかけになりました。 高齢化社会の日本でこれからもっと増えるであろう在宅医療について知ることができて良かったです。
15投稿日: 2021.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ高齢化社会でもある今、在宅医療を必要とする患者さんも増えてくると思われます。第二章で描かれているように専門医と訪問医との連携が重要である事も痛感。現代のITの技術を活用して、より多くの患者とその家族にとって最良の治療が受けられるように専門医からアドバイスを受けられたら心強い。現実には難しいところもあるのでしょうけど。
2投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ救急救命から訪問診療へと変わることになった主人公咲和子。その体験を物語を通して看取ることの大切さを教えてもらいました。 今後きっと直面するであろう看取りに対する考え方を知りました。難しい問題ですが、考えるきっかけになりました。
10投稿日: 2021.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログわたし自身が医療従事者ということもあり、現場の切迫感や、やむを得ない決断を迫るシーンはリアリティが伝わり、想像しやすくて物語に入り込めました。 その反面、在宅医療の現場のあくまでも、理想論に感じてしまう所もありました。 純粋に物語として楽しめば、感動する場面が多く、 命のあり方や、家族の看取り、自分の命の終わらせ方に向き合える作品です。 日本の医療の現状と課題も描かれ、考えさせられるものでした。 また、作者自身が医師だったからこそ描けるリアリティがあり、他の作品では味わえない緊張感がありました。 この作品は作者の考える医療なのだと思い、その思想に共感、賛同しました。 だからこそ、最後のシーンの白石先生の行動とその行動に繋がった考えに、現在の日本の安楽死における問題が直面し、切なくジレンマを感じて涙が出ました。とても苦しかったです。 重いテーマを取り扱っていることもあり、色々な考え方、感じ方ができる作品だと思います。 ぜひ、この作者さんの他の作品も読んでみたいと思いました。
8投稿日: 2021.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍で変わる医療に対する意識。病院よりも在宅での良さはきっとたくさんあるし、人々の考えはどんどん変わっていく。人の死に立ち会ったことの無いひとがたくさんいる中で、向き合い方を教えてくれる作品でもあると思う。映画は吉永小百合さんかぁ。ハイヒールのイメージが無いんだよなぁ。 2021/9/28読了 2021年の62冊目☆
6投稿日: 2021.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ終末期の状況がいくつかのエピソードと医師の葛藤がわかりやすく表現されている。尊厳死を考えさせられた。 作者の南杏子の本は、最初の1冊だったが、今後も読んでみたい。
2投稿日: 2021.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現代の医療の問題点をきれいに洗い出して作品にぶつけてる良作で、医療に関わっていない者でさえいろいろと考えさせられる。 在宅医療も散々いわれているが現実問題としては依然病院死が普通だし、自分の親父もそうだった。緩和ケアなら自宅で、といいたいが、誰が面倒見るの?家族?家族のつながりって小説ほどきれいじゃない。相方を最後まで愛情もって看取れるかって現世では苦行でしょ? この物語で出てくるケースはすべて看取る家族がちゃんといた、だから成立した物語なのであって、現実は死を受け入れられないとか直視できないとかそんな問題じゃなく、自分の時間を削って看病していられるほど看病側の生活も逼迫していてそれどころじゃないって言う家庭のほうが多い。 医療も崩壊しているが、生活も社会も家族も崩壊しているのが今の問題だ。もはや誰が総理になろうと、どこが政権を取ろうと解消はしない大問題。 ひとつ、解決策をあげるなら、医者の数も病院も減らせ、だ。 医療費はどこに嵩むか?医者の給料と病院だ。それを削ればあら簡単。問題すっきり解決だ。 なに?病人?諦めろ。 長生きしたい?お前の一年の経費で孫が何人生活できると思ってんだ? つまりはそういうこと。 で、小説の感想。すごくよかったが、最後の110番したってところで興ざめた。 どちらにしても積極的安楽死を認めない国は古生物以下文化としか言いようがない。
5投稿日: 2021.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ10月13日新着図書:【病気や死と向き合う患者やその家族。彼らを支える訪問診療所の医師が主人公。つらい現実。でも、亡くなってもどこかに光が残るような話が続きますが…。時々涙がこぼれ落ちそうに。家で読むことをおすすめします。】 タイトル:いのちの停車場 請求記号:910.26:Mi URL:https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/BB28193565
0投稿日: 2021.10.15少し重い作品でしたね
在宅医療の現実と、併せてま死について改めて考えさせられる秀作であると感じる。 ただ、後半の少女の話し以降は、それまでのリアリティーが徐々に薄くなり、ありきたりのストーリー展開で、後味として内容の重さだけが残るという感じであった。
0投稿日: 2021.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療現場の取り組み実情が生き生きと伝わってくる。末期患者が多いので死と常に隣合わせで、患者の家族と共に気が休まらない毎日でである。ゴミ屋敷、最先端医療へのアプローチ、静かな見取りなどいろいろあるが最後に父親の望む安楽死問題が描かれ心にズシーンと響いた。
2投稿日: 2021.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ夫の母が貸してくれました。患者一人ずつ話がまとまってるので読みやすい。読書初心者の方にオススメです。 「死」を考えさせられる一冊。延命治療とは、生きるとは、、自分の残り時間が短くなった時、私はどう判断するのか、もはや判断すら出来なくなるのか、人生のいい気付きになる本でした。
2投稿日: 2021.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ父が結構面白かった、と貸してくれました。 現実的にもっと厳しかったり悲惨な話が入ってくるので、そういう意味で言うと結構ライトな感じで軽く読めました。 60代女医さんが田舎に帰って在宅医療に携わる、というお話なので、まぁその為に帰る設定が必要なんだろうけど導入部がちょっと雑なような。全責任は私が取ります、って言ったからそうなったんだろうけど。でもなぁとちょっと思ったり思わなかったり。 後は、最先端医療とか、他の専門医療機関への調整がいまだにコネ頼りなんだなぁと思いました。まぁお話だからかもしれないけど。医学の世界もいまだに、学閥だの派閥だなんだのが幅を利かせていそうだな…と読んでいて思いました。 最後の決断ですが、その前に高齢の父親を半年病院に入れたままなのがちょっと?という感じでもあったり。まぁ家に連れて帰ってきても面倒見る人も居ないからそうなったんだろうけど。で、お父さんもそんな重大なことを娘に押し付ける?って感じでした。娘はまだ生きていかなきゃイカンのにねぇ。そういう問題提起をしたかったからのエピソードなんだろうけど。 この父娘は医学的な知識があったから判断が可能だけれども、何もわからない人は担当の医師の考えに左右されちゃうだろうなぁ…なんて思いました。ただ、自分だけは自分の意思で死にたいってのも、なんとなくですが医師の傲慢という気もしないでもないですけどね。延命治療に賛成している訳ではありませんが。
4投稿日: 2021.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常の生活では、当たり前のことかもしれないが、「死」を意識しない。それは、生きるという意思があることの証でもある。 でも、「死」を意識することは、生きる上でも大切なことだ。 どのように「死」に対峙するのか、その心の持ち様について考えさせられた。 古の人は、「死」を恐れ、宗教と関係つけたりし、正面から対峙していたと思う。 昔の人が、“強く”と生きていた、と感じるのも、「死」との向き合い方の違いからくるのだろうか。 武士は、死を美と捉えて、切腹など死に急ぐ、死を軽くみている、と評す人がいるが、そうなのだろうか? そこには、かけがいのない「生」、強い「生」があるのではないか? 「死」程、平等なものはない。 必ず誰しもに訪れるもの。 だからこそ、達観することが必要。心の持ち様如何で「死」の受け止め方が変わってくる。 そんなことをこの小説は感じさせてくれた。 貴重な疑似体験、だったのかもしれない。 舞台は金沢。 金沢は、以前から、日本で最も行ってみたい都市。 その金沢を、妄想的に楽しむこともできた。 この小説は、吉永小百合の主演で映画化され、予告編も見たが、映像を見せられると、その妄想が、現実に晒されるようで、興覚めのところがある。 この小説は、心の中の妄想として、大切にしていきたいと思う。
4投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ救急医療から在宅医療に場を移した医師が、患者の病気だけではなく、その環境、人間関係まで目を向けて調整していく様がすごい。 終末期医療で、避けられない尊厳死と積極的安楽死についても正面から取り上げて、本当に読み応えがあった。
2投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療医師の患者との向き合う気持ちや、死を迎える在宅患者の希望など、自分だったら…と考えさせられました。 医療系の物語は、父を看取ってから興味を持って読むようになった。 父の病気が分かった時には余命数日宣告されるくらい悪く残された命ももうわずか。 父に告知をすることも出来ず、在宅やホスピスの事にも未知過ぎて後悔ばかりが残ります。 父を亡くす前にこの物語に出会えていたらもう少し父の気持ちに寄り添ってあげられることができたのかなって思います。
3投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
南杏子作品はお初です。 吉永小百合で映画化されたということで まずは原作を手にした。 有名大学病院の医者として第一線で働いていた主人公 咲和子だが、62歳になり、救急での対応ミスの責任をとって辞めることになる。 実家の金沢へ戻り 訪問医療を行う「まほろば診療所」を手伝うことになる。 老々介護の夫婦、スポーツで脊髄損傷したIT企業の社長、高度ながん治療に見切りをつけて在宅医療を選択した官僚夫婦。 在宅での終末医療を選択する理由は様々だが、家族や本人の葛藤が生々しく語られて 主治医としての咲和子を通して 読み手に問題の難しさを投げかけてくる。 最後の章で 自分の父の看取りに悩む様子は 「仕事」ではなく「娘」として悩む咲和子の葛藤が辛かった。 ただ そんな重苦しいテーマーだが 登場する人々が優しく 病気に向き合い、(いま自分にできること)を考え患者と接していることに救われる。 文章は読みやすく 内容に引き込まれていくのは 作者が医師として現場で経験したことがベースになっているからだろうか。 だれもが一度は考えるであろう「死の迎え方」を考えさせてくれる小説だった。
3投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ徹子の部屋で著者の主婦から医者になりそしてカルチャーセンターで 本の著作を習い作家になったと言う驚きの人生に興味を持ち読む。自分が元看護師だったので、医療者には異常に興味あり、しかし深く考えさせるほどにはならずまあまあでした。
2投稿日: 2021.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ南杏子著『いのちの停車場』#読了 東京の大学病院を辞し故郷金沢へ戻った咲和子62歳は、在宅医療専門診療所の応援を頼まれた 妻の在宅医療に不理解の夫、ラグビーで四肢不随となった会社経営者、在宅医療を推進してきた厚労省高官、小児癌の6歳の少女 咲和子は患者と家族に寄り添いベストを尽くす
2投稿日: 2021.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ訪問医療の問題点が浮き彫りに。昔のような往診という制度が無い時代に、一人の医者が患者の生き死にを背負う難しさを知りました。
2投稿日: 2021.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療の話。 フィクションだけどノンフィクション。 決して他人事ではありません。 やはり高齢で入院してしまうと、どんどん弱っていくものなんですね。 自分の祖父母もそうでした。 自身の体験と重なる部分が多くて、色々と思い出してしまいました。 小児がんの章は終始泣きっぱなしでした。 ああ読むのが辛い。 医者にとっての延命治療は至極当たり前の事だというのはわかりますが、やはり尊厳死は認められるべきですね。
3投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段、あまりこんな感じの本は読まないのだけど、本も映画も評判良さげなので買ってみた。 丁度この本を読んでいる最中に、コロナ感染の入院対象者を重症者らに絞り込むとした政府方針が出たけれど、もし自宅療養で症状が重く変わった時にどうしたら良いのか、とても不安になる…。 東京の救急医療の現場で働いていたベテラン女医・咲和子があることをきっかけに故郷である金沢に戻り在宅医療の診療所に勤めることになってからのお話。 老老介護で妻の世話をする夫、在宅医療で出来うる最先端治療を望む半身麻痺のIT会社社長、ゴミ屋敷の中でセルフ・ネグレクトを続ける老婆、終末期を迎え故郷での在宅医療を選んだ高級官僚、小児がんで余命短い6歳の少女。 看取りの経験のない家族に死を見守らせる、看取る人に人が死ぬところを見るという覚悟を求めるという在宅医療の苛烈な現実がどの話でも描かれ、逝く者看取る者の思いが渦巻いて、切なく身につまされて、朝夕の通勤電車の中で読んでいて泣けてきて困った。 死に向かう人の変化が克明に書き込まれていて自身や家族の来るべき時のことを思うと怖くなるが、「アドバンス・ケア・プランニング」とか「レスパイトケア」ということについても初めて知って、準備して覚悟することの大切さを思った。 最後の話に来て、それまでの正統派の医療の話に人情噺を織り交ぜた作りから「積極的安楽死」について語る硬派の話へと入り込む。 ここまで各章の話にあわせて挟まれていた咲和子の父の病状が転げるように悪くなり、医師であった父は『俺は十分に生きた』と延命治療を拒否する。 私ももはや口から食べ物を受け付けなくなったとしても胃瘻とかして欲しくないと思っているけれど、とは言え、自然に弱って死ねたら良いくらいにしか考えておらず、耐えられない痛みに苛まされるようになった時どのように思うかは全く頭の中に無かった。 どの段階からが「余計な治療」なのか、患者の意思に沿い治療を止めることの是非について、法的倫理的かつ心情面から掘り下げて語られる話には考えさせられる。 折々に描かれる金沢の町の風情に旅の記憶が甦り慰められた。
7投稿日: 2021.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログサイレントブレスの作者南杏子さんの作品だった。一章一章が非常に重たかった。人形の願いでは幼い娘を失う両親の想いが綴られ、父の決心では医師としての佐和子の矜持と終末期医療に対する日本の制度が間接的に表現されていた。自分がその立場だったらどうだろうと真剣に考える時間でもあった。
2投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログテーマは終末在宅医療。 日本も早く「尊厳死」が認められる国になってほしい。条件はとても厳しくてもいいから。
2投稿日: 2021.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログkindleunlimitedで読了。 著者の南杏子さんは徳島出身で、医者の経歴を活かして様々な医療小説を執筆しており、今作は4作目の作品となる。 物語は、救急救命センターで主人公の咲和子が、大規模交通事故の過度の受け入れをしてしまうことから始まる。この件がキッカケで金沢の診療所に務めることになった咲和子が、患者、そして父とのやり取りを通じて、温かくもあり残酷でもある現実と向き合っていくストーリーである。 終末医療という難しいテーマを、医者の立場から描いているということもあって、下顎呼吸やアロディニアなど専門用語もオンパレードであるが、在宅医療や幹細胞治療といった様々なテーマが描かれており、生死について考えさせられる内容てあった。
2投稿日: 2021.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京の救命救急センターで働いていた医師が故郷金沢に帰り、訪問診療医となり、今までと違う環境で在宅医療とは何か、十人十色の患者との関わりから見つめるお話…だけじゃなかった。 積極的安楽死、尊厳死についてなげかける怒涛のラスト。それまでに丁寧な落ち着いた一人一人の患者の命との向き合い方を描いたからこそ問える「生き方」だけでなく、「人生の終え方」は鋭く突き刺さった。 真正面から人生と向き合う医療に実際に携わっているからこそ書ける小説だなと思った。 だからこそ、自分もいつか迎える「人生の終え方」の選択肢としての積極的安楽死についてもっとたくさんの人にこの本や映画を通して考えてほしいと思う。
14投稿日: 2021.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄く良かった。こんな在宅医療を受けれる人は幸せ。尊厳死とか色々考えるけど家族にとっては結論がでないのが本当のところ。父と同じ様な道を辿っているお父さんだったので、切なく苦しくなってしまい涙してしまった。
6投稿日: 2021.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
◆全体の印象 医療がテーマの小説を初めて読みました。「死」について学ばせてもらいました。 医者というのはすべての命を救ってくれる人だと思っていました。 ですが、白石パパが「絶対に助かる見込みがない状況で、非常に苦しい時間が死ぬまで続くと確定しているのならどうだ?」と言ったセリフで大きく考えさせられました。 僕も同じ状況だったら、白石パパと同じように積極的安楽死をお願いしたいと伝えるかもしれないです。 それを思うと、命を救うことだけが全てではないのかなと感じました。 とても深いテーマでした。 映画もやっているみたいなので、観てみたくなりました。 ◆印象に残った場面トップ3 ①死を学ぶ授業だと思ってください。 授業の内容が深すぎです。僕もこの授業を受けないといけない日がくるのかな。。。 ②生涯医療費のうち、終末期にかかる医療費は約半分。 半分もかかることに驚きました。 ③「はっきり言おう。積極的安楽死を頼む」 白石パパのセリフが一番心に残っています。
8投稿日: 2021.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【あらすじ】 医療小説。在宅での終末医療についてのお話。 主人公の白石先生は救急救命センターでの副センター長。62歳。ベテラン救急医。しかし、とある事故の処置でのミスを境に、故郷金沢に戻ることになった。そこで幼馴染である医師 仙川の「在宅専門 まほろば診療所」を手伝うことになる。老老介護や終末期を迎えた患者、末期癌を患う6歳の少女と向き合う日々が描かれる。 【感想】 「どのように死ぬか。」 死について、さまざま考えさせられる物語だった。 救急救命士時代は、医師として「患者の命を繋ぎ止めること」が仕事。しかし、在宅医療は必ずしも命を繋ぎ止めることが患者にとっての正解とは限らなかった。毎日の激痛にもがき苦しみ、死を願う人もいる。そのような患者に「1日でも長く生きて」という言葉は酷でしかないし、看取る側のエゴなのかもしれない。 同じ「医師」であるものの、必ずしも命を繋ぎ止めることだけが医師の仕事ではないように感じた。 -- その選択が患者にとって最適か?患者が求めていることは、必ずしも生きることだけであるか? -- 患者の意志に寄り添うことができるのが在宅医療であるのだなとわかった。 また、この物語は患者だけでなく、介護者にもスポットが当たっている。ゆえに、もし自分の親がそうなったら、自分も将来介護者になったら耐えられるのだろうか。感情移入せざるを得なかった。 死に対して生まれてくる感情は「恐怖」が1番にきてしまい逃げてしまいがち。しかし、必ず人間誰もが死を経験する。「私らしく最期に死ぬ」ために、逃げずに少しずつ考えて行けたらいいのかなとも思えた。
6投稿日: 2021.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この展開は多分こうなっていくだろうな、と言う予測は早くからつき、実際その通りの展開となっていきましたが、ラストがそう来るとは想像しなかった!そう終わるのか…と読了後しばし呆然。 ラストは、医師である著者の現場からの生の訴え、問題提起と捉えました。しかし今現在たくさんの苦しみの中にある患者さんがいる事実があってもここに描かれた患者の希望が法的に叶うようになるのはまだ難しいと思います。 まだ、と言いつつそもそもなるのかどうかも怪しいとも思われます。 この問題が「前向きに」もっと検討されるよう日本の情勢が今後進んでいくことを願います。
9投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ庇護を求めるか弱き存在の者のために自ら日陰を作って立つーそれが医療者というものだ これは私自身の人生の最終章、「死を創る」ための処置だ 最後の日まで、いかにその人らしく生きるか、
2投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を観てから読み終わりました。 配役もぴったりだと思いました。 終末期医療の状況が刻々と変わるようすが文章だけでも読み取ることができて、悲しさの中にも前向きにいのちと向き合う登場人物たちに考えさせられました。 いまこういう時だからこそ、より一層大切な人との時間を大切にしたいと思います。
5投稿日: 2021.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな在宅医療ができるなら!病院はもっと医療だけじゃなくて看護も質が高くないといけないなー。としみじみ。積極的安楽死ははじめて見た、海外ではあるけど日本は認められてないから、倫理的に通った後でも気になるところ。投与する前に亡くなったお父さんも最後まで神経内科医だったね。
3投稿日: 2021.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療の知識が全くなかったので、読んでいて衝撃を受けました。 特に老老介護、終末医療の内容は、読んでいて胸が締め付けられるくらい苦しかったです。 少しでも長く生きることだけが「生きる」ではないと、初めて気付きました。難しい…。 終わり方が意外な形でしたが、最後がすっきりするとは限らないのも生きることと似ているなと思いました。深く、考えさせられた本でした。
3投稿日: 2021.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログKindleアンリミテッドでまもなく終了!の文字に惹かれて読んだ。映画のポスターを見た覚えがあったようで、「いのちの停車場」のタイトルだけは知っていたが、普段このようなジャンルの本は読まないので新鮮な読書体験であった。私は今まであまり病院のお世話になったことがなく、まだ両親も健在なので医療との関わりは薄い。しかし、いつかはこういうことを考えないといけない日がくるんだなと思ってしまった。
3投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めてこの著者の作品を読みましたが、とても読みやすくておススメです。 この本では終末医療の問題も家族の問題も出ていて、引き込まれるように読みました。 ずっと患者の命を救う仕事しかしてこなかった先生が、終末医療の現場に行くお話で、先生がどんな考えになるのかよくわかるお話でした。 この本を読んでいたら、癌になったおじいちゃんをよく思い出して、泣きました。 おじいちゃんに癌が見つかった時は、とても元気で、歩くことも喋る事にも、痛みも無く、何にも問題がなかった。ただ咳が続いてる感じでした。 それでも、家族と医者の意向から治療が始まり、二週間足らずでおじいちゃんは一人で歩けなくなっていました。 この本を読んでいたら、治療なんかさせなければ良かったと思わせるような本でした。彼の人生の最後の時間がどれほど奪われてしまったのか。 延命治療の残酷さがこの本で痛いほど、響きました。
3投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療の観点から、様々な医療の課題をテーマとして取り上げていて、心が揺れ動いた。 医療用語などが多いが、スッと入ってくる文章で読みやすかった。 その時々の自分の年齢や置かれた状況で、どのように感じるかは変わってくるはず。またしばらく経ってから読み返したい。
2投稿日: 2021.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログスイスなど自殺幇助が認められている国もあるが、本人や家族には辛い問題。必ずしも自分には無関係な話ではない、起こりうる話。 弱っていく佐和子の父親が辛くて読み進めるのが苦しかった。
3投稿日: 2021.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle Unlimitedで購入。病院だけでなく、家で家族に看取られながら死ぬという死に方もあるんだと思った。家族と自分で延命するかしないかで分かれたときどうすれば良いのか考えさせられた。長寿化によって尊厳死の問題を孕むことが増えてきたので、興味深いテーマであった。そして私自身小説はあまり読まないのだが、たまには小説を読むのも良いなと感じられた。
3投稿日: 2021.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle Unlimitedで読破。 在宅医療について考えたことがなかったがとても考えさせられた。在宅医療ということは自宅で死を看取ることになるので介護者の気持ちとしても想像しきれないほどの感情が生じると感じた。 金沢についても少し詳しくなった気がする。天気が変わりやすいとか。
2投稿日: 2021.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle版で読了 義父母が高齢で在宅医療を受けている事もあり、興味を持って読み始めました。 主人公の医者 佐和子視点でストーリーが進みます。 主なテーマは、癌や難病の患者に治療を尽くし最早治る事がない段階に至ったとき、余生をどのように生きるか。 幸福とは?不幸とは?延命治療と積極的安楽死の間で揺らぐ感情、善悪の認識問題についてです。 それには患者本人、家族友人や医療従事者全ての私情感情が絡み合い何が正解かなんてわかりません。 患者は高齢者や6歳の女の子、会社経営者の男性、果ては主人公の父親と様々な立場ですが、共通して言えるのが、患者本人が覚悟を持って死を受け入れているという事です。 特に6歳の萌ちゃんには涙が止まりませんでした。 奇跡が起きてどうにか助かって欲しい、この状況は辛くて目を背けたくなる…という具合に祈るような気持ちで最終章まで読み進めました。 最終章の主人公の父親と佐和子のやりとりは、他人ごとではなく自分ごととしてこの先も考え続ける問題です。 苦しい場面が多いですが、診療所の仲間のキャラが楽しく、ほっと笑える場面もあります。 読了後は不思議とスッキリとした気分になり、読んで良かったな、今日からも日常を生きていこうとあたりまえながらも強く思わせてくれる一冊でした。
3投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療、安楽死について。 桜橋とか犀川、浅野川などが出てきて金沢の風景が目に浮かび親近感が湧いた。吉永小百合さんが演じているなんてイメージにぴったり。
2投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ積極的安楽死と向き合う場面での緊張感に、全身で慄く。 小説的な部分もあるけれど、リアリティもあるから、素直に読み進められるとおもう。
2投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ新作映画の原作ということで手に取ってみた。在宅医療をテーマにする珍しい話であった。死と隣り合わせの治療、生と死の倫理について考えさせられるところもあった。しかし、ストーリーとしてはありがちで、著者はここで涙を流させたい、というのがわかってしまい、なかなか感情移入できなかった。
2投稿日: 2021.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ父親が、骨折をきっかけにどんどん体が弱っていく様が恐ろしく、リアル感があった。自分の最期を自分で決めたい…その気持ちが痛々しいほど伝わってきて、また、家族の複雑な思いもよく分かり、答えが出ない問いだと思う。 生き物が命を終わらせる流れが詳しく書かれていて、勉強になったし、必要以上に怖がることはないんだと勇気が持てた。また読み返したい作品。
3投稿日: 2021.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログしっかり泣けます、 自分の親と話がダブったりして・・・ 特に6歳の萌ちゃんはガマンならんです おすすめです
2投稿日: 2021.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
映画も見てみたい。 お医者さん役が初めてという、吉永小百合さんにも興味がある。 ずっと救急で働いていたお医者さんが 救急の現場で医師の資格のない事務の子が医療行為を。絶対にやっちゃいけないことのわだけどなぁ。 でも、その子をかばうために責任を取り故郷の田舎の診療所で在宅医療の担当を。 そのかばった子が、追いかけて診療所に来てくれたとこはよかった。 絶対、先生への恩返しのためにもお医者さんになって欲しい。 老老介護→絶対に世の中にある現実、読んでて辛かった 脊髄損傷→最先端医療の在宅医療、成功して欲しい 精神疾患→完治したのかな?よかった 終末期→看取るの辛い、絶対に気丈に振る舞えない… 小児がん→読んでて一番辛かった。両親は子供の死を受け入れれないけど6歳の子供の方が死を受け入れてて泣いた。 最後は、自分の親(元医者)から楽にしてくれと言われ 医者としては、そんなことできない 家族としては、楽にしてあげたい という葛藤。
34投稿日: 2021.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
金沢での在宅医療の話。医師ならではの臨場感ある描写と、丁寧な情緒面の語りが絶妙。暗い話になりがちな終末医療。でも読後は悪くない。 ゴミ屋敷老人、老老介護、官僚、IT社長からの父親、6歳の女の子という進み方が、他人事から自分の事となっていくようでかなり感情移入してしまい、涙涙…。 3月に義父を癌で亡くしたところだったので重なる所も多く色々考えさせられた。終末医療、自分だったらどうしたいかは大体の方針は夫や親に伝えているけれど、そこまでたどり着く前までの目の前の苦しみに耐えられるかどうかは不安。 最後は物語らしく唐突な終わりでちょっとあれ?と思ったけれど、その選択肢が私にもあったらいいな。そうしたらもう少し死に対して明るく捉えられるような気がして。死は怖くないけれどそこに至るまでの不安や苦痛が怖くて嫌なので。 映画化するのかな? 観てみたいけれどそれより同じ作家さんの本をもっと読みたいと感じた。
5投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて読む南杏子さん作品。 在宅での終末医療の色々なケースがあり、どれも考えさせられる。自分の親も遠くない将来あり得ることだし。 最終章の患者の終わり方は読んでて鳥肌立った。 どう命をつなぐかではなく、どう最期を迎えるか。 これからの時代、医師が犠牲にならない患者の意志の尊重の仕方がより整備されて行ってほしいと思う。
7投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になっていて先日テレビにも著書がでていたので気になってよんだが、とても読みやすかった。 所謂死に際にどんな状態になるのか、何が必要なのか具体的によくわかった。 自分はどうするのか、考えた。 昔より人の死に向き合う機会が少ないので多くの人に是非読んで欲しい。
5投稿日: 2021.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ在宅医療現場の現実が読み手に迫ってきます 終末の様子の描写に手加減がなくリアルで 自宅で母を看取った時の何か月かの部屋の臭気がよみがえりました 思いがけない結末に作者の覚悟が読み取れました
6投稿日: 2021.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ命には限界がある。安楽死、終末医療、アドバンス・ケア・プランニングについて、現役医師の作家だからこそ描けた感動作。 勤務地の管内の病院に勤務する医師の方の作品ということをきっかけに手に取った一冊。 長く救命科の医師を務めた主人公、ある事件を機に大学附属病院を辞め故郷の金沢へ帰る。年老いた父。幼なじみがやりくりする小さな訪問診療所。救命科とは百八十度異なる在宅診療に携わることとなる。 出版社勤務を経て医師となったという筆者。数多くの人々の生死を見つめ、苦悩してきたことが本書から伝わってくる。命の大切さ、人生の素晴らしさ、そしてそんな美辞麗句を全てに無効にする、病に苦しむ患者の想像を絶する苦悩。 本書に登場する7人の患者。それぞれ終末医療の課題を表象している。 本作は吉永小百合主演で映画化。豪華キャストと舞台となる金沢の風景できっと良い作品に仕上がっていることだろう。 重い重いテーマを描いた作品。筆者の持つ苦悩はもっと思いことだろう。ストーリーの中に小さな未来はあるが、筆者の心の闇は未だ解消されていないように思う。切り離したラストの余韻が心に残る。
5投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ事情も病状も全て違い、それに対応する訪問診療の難しさについて考えさせられる。 第五章の小児がんに侵され死期を間近に控えた6歳の女児とその両親の悔いのない日々を描いた物語がとても心に響いた。 最後の日まで、いかにその人らしく生きるか そうした毎日を支える存在になろうと、「まほろば診療所」の皆がそれぞれに考えている。
10投稿日: 2021.05.31在宅診療は、新たな治療の道を開く?
在宅医療については、これまで様々な小説やルポが発表されています。この小説は、現役の終末医療に携わっている医師が書かれたと言うことで、リアリティがありました。 しかしまず、プロローグとして書かれている主人公が金沢に戻った理由に引っかかりました。娘が助かったにもかかわらずクレームをつける親がいるんですね。彼らもその時の病院の状況が判っているのにねぇ。結局そのことが問題となって彼女は故郷の金沢に帰ります。室生犀星の「ふるさとは遠きにありておもうもの」の金沢です。この舞台設定が見事でしたね。金沢には二度程行ったことがあります。戦災を受けていない美しき町並、犀川、浅野川、あの砂浜を車で走ったこともありますし、治部煮の美味しさは格別でした。小説の中にも、この治部煮が重要なアイテムとして登場しました。 小説は、終末医療ばかりではなく、大病院に入院するばかりではない新しい治療の方向も示しますが、すべてに結論をつけているわけではありません。また、終末期、特に幼き子供がそうなったとき、どう寄り添ったらよいかについての、ひとつのエピソードが出てきます。 そして、終末医療となれば、どうしても尊厳死、安楽死について目を背けるわけにはいきません。最近は、延命治療ではなく、緩和治療にベクトルが向いていますが、主人公の父親を、モルヒネ等この緩和治療が効かない患者に設定するところなんぞは、作者が医師であるところの面目躍如といったところでしょうか。これは犯罪なのかというとこで、物語は終わり、結論は読者に委ねるというスタイルとなっています。 正直私も、死ぬことへの恐怖よりも、痛み、苦しみへの恐怖の方が強い気がします。それもこれも、医療の進歩のなせるワザなのかもしれません。難しい問題ですよね。
0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を先に見たのです。 しっかりとこちらを読んでよかったです。 死について、死に方について考えさせられます。
3投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ祖父が死んだ日を跨いで読了。 人間の最後について考えさせられた。 延命治療の意義とは。生きるってなんだ。
5投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ同著者のサイレントブレスと同じように、在宅医療が題材。 死期が迫った人間の最期のときをいかに尊重するか。 そのために医療従事者は何ができるか。 患者の意思を尊重して苦しみから解放するために命の炎を消すことは罪なのか。 苦痛から逃れたい患者に生き続けることを強いることこそが罪なのか。 父も死の間際はずっと「苦しい苦しい」と言っていた。 早く解放してあげてって思った。自分がそうなっても、延命治療は行わず早々に死なせてほしいと思う。 いざ身内がそうなったとき、死の決断を下すことは難しいのかもしれない。 二度と話せなくなることに、家族の側が勇気を持てないのかもしれない。 永遠の課題だと思う。
5投稿日: 2021.05.23
