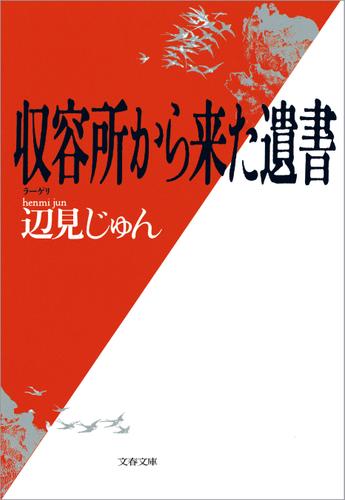
総合評価
(142件)| 84 | ||
| 30 | ||
| 13 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ極寒のシベリアに抑留された日本軍兵士達のノンフィクション小説です。 数十万人が捕虜にされ、11年もの長い間強制労働させられたという事実を忘れてはならないと思います。 映画「ラーゲリより愛を込めて」を観ることをお薦めします。映画では小説の半分も伝わらないかもしれませんが、良い映画だと思います。
12投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本当にノンフィクションなの?と疑うほどのストーリー 山本さんは「最後に勝つのは道義であり、誠であり、まごころである」と遺書に残しました。 しかし、現代の日本を見渡すと、道義に反した振る舞いをする人の方が得をして、生き残っているように思える瞬間があります。その現実は、とても皮肉で、やりきれない気持ちにさせられます。 けれども、時代を越えて語り継がれ、尊敬され続けるのは、やはり道義を大切にして生き抜いた人たちだと私は思います。山本幡男もその一人であり、その姿勢こそが後世の人々の心を打ち続けているのだと感じました。
1投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人捕虜が極寒の地、シベリアでどんな生活を強いられてきたのかがよくわかりました。やはり戦争は人を人として見なくなってしまうものなのですね。地獄のような日々の中で生きる希望を多くの人に与えた山本さん。このような日本人が当時は何人かいたんだろうな。戦争を体験しているご老人はやはり強い!!
0投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生きるために食べる、けど、食べる気力も無くなった時、さいごに生きる力を湧き上がらせるもの…そうですね、そうですよね!!と、胸が熱くなりました。
0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログおすすめ。 #戦争 #感動 #衝撃的 #苛酷 書評 https://naniwoyomu.com/31709/
1投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭は本の読み方で磨かれる で、紹介されていた! 1984年 という本と同じく、 今生きていて、この生活ができていることに 幸福を見出せる、 究極の幸福論の本だと思う!
0投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留のノンフィクション作品。 山本さんの人間性が素晴らしいし、その人の遺書をなんとか日本の家族に届けようと知恵を絞る仲間の絆に感動。 ちなみに遺書の持ち帰り方は、原作と映画で少し違っていた。 本当に尊い作品でした。
4投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ見事な作品です。 終戦後、シベリアに抑留された無名の男性・山本幡男の生涯を描いたノンフィクションです。しかし、まるで一個の良く出来た「物語」を読んでるような気持ちになります。 ラーゲリについてはソルジェニーツインの『イワン・デニーソヴィチの一日』で読んでいますし、実は亡くなった父もシベリア帰りで少しは話を聞いていました。その分、他の人に比べインパクトは小さかったと思います。 むしろ主人公の生き様が強く印象に残ります。「死せる孔明生ける仲達を走らす」というのは不適切な言い回しかもしれませんが、主人公を慕い、敬った仲間たちが、10年を超える抑留から解放され、シベリアから思わぬ方法で持ち帰り奥さんに伝えた遺書。それが、主人公の誠実で苦難にもへこたれず仲間を鼓舞し続けた素晴らし人間性を示しています。
2投稿日: 2024.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログGet busy livin’ or get busy dyin’. Remember Red, Hope is good thing, maybe the best of things and no good thing ever dies. 「ショーシャンクの空に」より
0投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「遺書」の文面を読んだ時、涙が止まりませんでした。 戦争という名の下にどれだけの犠牲があったのか…。 強制労働、粗食、収容所内にスパイがいるかもしれない、気が休まる事はなかっただろう。 アムール句会のみんなの俳句が、ときに切なかったです。
1投稿日: 2024.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留の方々が大変な苦労をされたことは知っていたが、理不尽さは遥かに想像を超えていた。捕虜となるどこの国でもこうなるのか? そんな状況下でも希望を持ち続ける山本氏らを支えていたのは句会や勉強会。自分がもし同じ状況でも、こんなに知性と感性、知識欲を持ち続けることができるだろうか?
2投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ貸していただいた本です。 遺書と題名にあるのだから、そうなることは分かっているのに、帰れることを願ってしまいました。
1投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ山本が遺書について何としても家族に届けてほしい、と懇願したのが、それまでの山本像とは異なるお願いだったので違和感があった。そういう私欲のために他人を使うということをしなさそうな人だったからだ。 しかし最後まで読めば、その違和感は勘違いだと分かる。山本はもちろん家族に届けてほしいという意向はあったが、それ以上に残された俘虜たちに生き延びる強い希望を与えたかったのだろう。遺書を届けてほしいというお願いは、「あなたは生きて日本に帰れるのだ」という山本のかけた強いマインドコントロールでもあるのだ。 残された俘虜たちは何としてもこの遺書を暗記し、生きて帰るのだ、という確かな信念を持つことができた。これが帰還までの生きる寄す処となったことだろう。死してなお希望を与え続けた山本の力に感嘆する。
1投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留の実話です。 想像を越えた10年を超える抑留生活の苛酷な様子を知り、言葉にならない衝撃と悲しみと苦しさでいっぱいです。 ソ連の強制収容所の厳しさは耐えられないほど辛いけれど、何よりも密告する同胞たちがいることに心が痛みました。 そんな身も心も痛めつけられてしまう地獄のような収容所の中ででも、シベリアの青い空を美しいと感じる心を持ち続け、俳句をよみ、文章を綴り、仲間を励まし続けて日本に帰ることを決してあきらめなかった山本幡男さん。 「ぼくはね、自殺なんて考えたことありませんよ。こんな楽しい世の中なのになんで自分から死ななきゃならんのですか。生きておれば、かならず楽しいことがたくさんあるよ」 私もずっと読みながら、 「苛酷な状況に置かれてもなお人間らしく生きるとはどういうことか」 ということを考え続けていました。 そして、山本幡男さんのご遺志を命をかけてでもご遺族に伝えようとした仲間の友情に心打たれます。 山本さんや収容所の俳句仲間の俳句、詩、文章。 本で読むと文字から想いが伝わってきます。 日本の地を踏むことなく、家族との再会も叶わず、シベリアの収容所で亡くなった方々の無念を思うととても悲しいです。 その方々のためにも、日々を大切にして良い生き方をしないといけないなと思いました。
0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を見たので、原作本思ったけど、私が読み進めるにはかなり厳しかった。 登場人物は多いし、歴史的説明も多い、俳句も入って来て、もはや歴史と国語の教科書的な感じで どうにもこうにも進まなかった‥ 普段ライトな小説ばかり読んでいるからか… 諦めずに読み切ろうとだけ思って頑張った。 山本さんの衰弱していく様子は辛かった。 しかし、クロがホントに日本にも来ていたなんて!そこが心底ビックリ。 あれこそフィクションだと思っていた… まぁ、なんとか読んだけど、やっと終わった…と思ってしまった。
0投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画やそのノベライズは、悲惨さが強調されていた。それに対して、この原作は、どのようにして色んな人の希望となったかに焦点を当てていて、前者よりも深みを感じられた。
0投稿日: 2024.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
山本氏の妻への手紙がとても印象的だ。「実によくやった!殊勲賞ものである!」と、彼女の奮闘を心から誉める。山本氏の実直さが感じられる。山本氏の妻は実際、子供達を大学に行かせ、大変尊敬に値する方である。
1投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大宅賞と講談社ノンフィクション賞のダブル受賞作品。 題名から、文書で届いた遺書に基づく作品かと思っていた。 しかし、強制収容所から出るときには、紙類など記録媒体は持ち出せず、何と抑留されていた仲間たちが頭の中に記憶し、あるいは小片に折りたたみ肌着に縫い付け、日本に帰ってから一字一句を文章化して遺族に届けたという。 彼らの巧まざる努力と知性に、驚嘆するばかり。 その遺書とは、ダモイ(帰国)情報で彼らを励まし、収容所生活に少しでも潤いをと俳句を主宰した山本幡夫のもの。 その彼自身が病に倒れ、帰国を果たせなかったとは。 著者による、帰国した人びとに対する綿密な取材が、リアリティに満ちた感動の傑作となっている。 遺書を託された人物が何度も書き写したという、山本の関心が日本の将来に向いていたという言葉。 「日本民族こそは将来、東洋、西洋の文化を融合する唯一の媒介者、東洋のすぐれたる道義の文化――人道主義を持って世界文化再建に寄与し得る唯一の民族である。この歴史的使命を忘れてはならぬ」 些か誇大的ではあるが、傾聴に値する言葉と言っていい。 重苦しい話が続く中、収容所に紛れ込み、彼らに懐いて、帰国の船を追って海に飛び込んだ犬のクロを救い上げたという逸話には、ホッとさせられる。
14投稿日: 2024.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は少し難しい。 タイトルからあるように、その人物自体は亡くなるのが分かっているのだけども、『収容所』という場所で あれほど希望を持って、新しいことをしよう、学ぼうと頑張っていけるものだろうか。 彼が居たからこそ、励まされ、もしかしたら栄養が足りず、精神的に追い込まれ亡くなっていた人もいたかもしれないところを生き延びえたのでは無いだろうか。 あとがきより、最後の遺書が届いたのが30年をも超えてのことだったと。 人を信じるとともに、この世界から早く戦争をなくしてほしい。
1投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログだから文学を学ぶことが大事なんだ アイデンティティを忘れないこと 希望を持ち続けること ジーンと胸に響くものがあって、考えさせられる作品
1投稿日: 2024.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログAudibleにて。 「ラーゲリより愛を込めて」でこの原作を知りました。(映画は未視聴) シベリア抑留ものは辛いシーン(寒さで鼻がもげるとか、遺体が凍るとか)が多いため、山崎豊子の「不毛地帯」以来読めていませんでした。 この物語にも、抑留による辛いシーンはありましたが(私は同胞による吊し上げが辛かった)、それ以上に希望に満ち溢れていました。 東南アジアの収容所ものはいくつか読んでおり、そちらはイギリスやアメリカの管轄のため、比較的人道的な待遇がなされており、文化活動が行われていたのは知っていました。 しかし、国際法違反の非人道的待遇が取り沙汰されることの多いソ連によるシベリア抑留で、そのような活動が行われていたのは知りませんでした。 アムール句会は読みながら心が洗われる思いでした。 創作は光だと感じます。辛い境遇にあっても、創作は心に光を灯してくれる。ダモイを信じ、創作活動を導いてくれた山本幡男氏。私も山本幡男氏?のような人物になりたい。ニーチェの言う超人のような人物だと思います。 V.E.フランクルは、「夜と霧」でどんな絶望の中でも希望を失ったらいけないと説き、キェルケゴールは絶望は死に至る病だと訴えました。 山本幡男氏は古今東西の先哲たちが考えてきたことを、まさに体現しながらいきた人物であるといえます。 氏が生きて、日本に帰ることができたならどんなにか良かっただろうと思いますが、もしそうなっていたらこの物語が広く人々に読まれることはなかったと思います。 ご遺族は本当に辛かったでしょうが、そういう意味で、山本幡男氏の死は意味があったと思います。 残されたモジミさんの苦労も、並大抵のものではなかったでしょうが…。(遠方まで行商の仕入れに行くシーン、「おしん」でそういうのありましたよね。本当に大変だったと思います。よく生きてこられたと敬意を表します。母は強し。) 作中に俳句・短歌も登場しますが、アムール句集も実現できたら良かったなぁと思います。ぜひまとめて読みたい! 素晴らしい作品に出会えて良かったです。取材協力者の名前を見たとき、ああ、この人たちは本当に実在していたんだ!と実感が湧き、改めて涙が出ました。 現在も、国際法違反と言われる戦争が起こっていますが、国際法を違反しても制裁措置がなく、是正はできません。シベリア抑留時代から進歩したのでしょうか。とはいえ、武力で制圧するのも、正解ではなく、山本氏がいう「人道」について、私たちは考えていかなければなりません。 ご長男の顕一さんは偉大なお父さんをもったことでご苦労された面もあるようで、顕一さんのご著書も読みたいと思います。
2投稿日: 2023.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
二宮和也主演の映画「ラーゲリより愛をこめて」の原作本です。映画、観ました。 原作となっている本書はずいぶん以前に書かれたようで、1989年に単行本が出版されている。解説では、1990年代の今、読むべき本とか書かれているけど、もちろん2023年の現在読んでも価値ある本です。 先に映画を観ているので、ラーゲリの厳しい寒さや、日本人の中にもスパイがいるかもしれないという緊迫感、やせ衰えて死んでいく仲間、懲罰房の恐ろしさなどが読みながら思い出された。映画でも山本が俳句を詠んだり、知的な部分が存分に描かれていたが、本書の中にもたくさん、山本やその仲間が収容所で読んだ俳句や詩が出てくるので、よくこんなに覚えている人がいるな、と感心した。多くの人の記憶と証言を集めて、時間をかけて取材して書かれたのだろう。そのことにも感動。 幼いころ「アンネの日記」を読んで漠然と感じたような感動を、本書にも覚える。人は、どんな厳しい状況にあっても、生きている限り心を失ってはいけない。自分で自分の心を守ることができれば強く生きられる。最後は心なのだと。 映画でも同じ描き方だと思うが、タイトルでもありメインとなるのは「遺書」なのに、ページのほとんどが収容所での出来事と山本と周囲の人たちとの交流に割かれ、遺書が書かれ始めるのはもうページも残り少なくなってからだ。「やっときたか」と思いながら読み進める。そして、遺書を記憶した人々が、ダモイの日を迎え日本の船に乗るシーンは本当に胸が熱くなる。船の中で句会をするなんて映画にはなかった気がするな。いい場面だと思いました。 クロも本当にいたんだな。 読んで良かったです。
10投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日、映画「ラーゲリより愛を込めて」のDVDを観た。 シベリアの収容所で帰国を果たせずに病死した男の遺書が、思いもかけない方法で家族に届けられる。 良作でした。 その原作本。 第二次世界大戦終結後、たくさんの日本人がシベリアの収容所に送られたことは聞いたことがあったが、巻頭の地図を見て、収容所の多さと収容者の人数に驚く。正確な数は今も分からず、およそ60万人だということだ。 無知であった。 映画では長くなる説明はされないため、少し背景に分からなかったこともあって、原作本はそれを知る手掛かりとなった。 抑留から2年半後、一般の捕虜の多く(一部?)は帰国が叶った。 しかし、ソ連側から見て「戦犯」に当たる者たちは、これより長きに渡る収容所生活に入る。 主人公・山本幡男はロシア語に堪能。 満鉄時代に調査員だったため、戦犯扱いとなった。 極寒と飢餓と重労働で、日本人捕虜たちは次々と命を落とし、白樺の根元に埋められていく。 「自分もいつかは白樺の肥やし」と言って虚無的になる(「白樺派」と冗談めかして言われた)風潮を山本は嫌った。 明日の見えない収容所生活の中でも、穏やかな笑顔で前向きだった。 彼の作った俳句の会は長く続いた。 俳句に「季語」があるのは日本に美しい四季があるため。 句会の折に山本は語る。 「ぼくたちはみんなで帰国するのです。その日まで美しい日本語を忘れぬようにしたい」 故国の、文化と風土を愛していた。 軍国主義由来の、押し付けられた愛国心とは全く異なる。 博識と、ユーモアにあふれた語りで、絶望の中に生きる収容者たちに束の間の笑顔と生きる希望をもたらす。 山本の人柄は収容者たちの心の拠り所だったのだろう。 過酷な環境の中でも彼らは人間らしさを失わず、友情を育んでいった。 山本亡き後の友人たちは、彼の遺書を家族に届けるという使命を支えに生き抜いたのかもしれない。 収容者の長期残留組の帰国がかなったのは、なんと敗戦から11年後のことでした。
4投稿日: 2023.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、私の周りにはキャラの濃い友人が多いと書きましたが、その中の1人に本人は読書をあまりしないのに何故か私の読書事情を把握したがる女性がいます。 そんな彼女に「そろそろ部屋で軍歌を流し出しそうやな、そうなったら絶対に遊びに行かへんから言ってよ。」と、あらぬ疑いを掛けられましたので暫く第二次世界大戦関連の本から離れようと思っていたのに、気付けばまた手を出してしまいました。 もういっそ大音量で『日の丸行進曲』でも流してやろうかと思う私ですが、本作は敗戦後にソ連軍に捕われ、極寒と飢餓と重労働で有名なシベリア抑留をされていた山本氏と、山本氏と関わった仲間達のお話です。(嫌な知名度ですけれど) タイトルでお分かりのように山本氏は残念ながら抑留中に病死をされてしまうのですが、6通の遺書を仲間達があの手この手を使って(この方法が本当に凄い…。こっちまで冷や冷やしました)厳しいソ連監視網をかい潜って持ち出し、遺族の元へ。 遺書すら持ち出させない徹底ぶりにやりかねないなと得心しつつも少し苛立ちましたが…。 これがノンフィクションだと言うのですから、畏敬の念が溢れるあまり敬礼しそうになりました。 本当に凄い。そして仲間をここまで駆り立てる山本さんのお人柄…。 いつも明るく前向きに、41歳の山本さんが「まだまだ若いから未来がある」と生きる希望も体力も失いかけている同胞に勇気を見せ、スポーツ大会では実況で皆を笑わせ、俳句の回を催して皆を癒し… これはフランクル著の『夜と霧』日本人バージョンだと感動しました。 人種が違えど、どんな時でも希望を失わず周りの同胞を慮り愛情を忘れずに接する。 私に同じ事が出来るとは到底思えません。 最近あまりにも本に泣かされるので、今回は泣くもんか!と耐えていたのですが、祖国に戻って瀬戸内海を見つめ、同胞であった野本さんが山本さんを想って彼に教わった詩を涙ながらに詠む場面で「もう知るかぁー!!悲しいもんは悲しいんやー!!」と軍歌の流れていない部屋で涙腺ダムを崩壊させました。 遺書が遺族の方に届いたのは山本さんが抑留されてから12年後。戦後もご家族の戦いは続いていたんですね。今後の長い人生において挫けそうになった時や人道を外れそうになった時は(そうならない事を切に願いますが)本作を思い出し、戦って下さったご先祖さまやご家族の方に恥じぬような生き方をしようと心に決めました。 手始めに私をおかしな目で見る友人達を笑って許そうと思います。(人間が小さすぎる) 最後に、山本さんの詠んだ句では無いのですが、句会で仲間の方が詠んだ詩があまりにも美しかったので置かせて頂きます。 『祖国近し 手にゆく雪の すぐ溶けて』
17投稿日: 2023.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争が終了した後も、過酷な北の土地で強制労働を強いられていた人達がこんなにもいたことを知らずにいたこと恥ずかしい。 ただこの本はそんな過酷な生活を嘆く内容ではなく、そんな中でも希望を捨てず皆の力になった人がいたこと、そんな人を中心とした人の絆を表現した作品。 今だからこそ、人の絆に触れる作品が必要だと思う
2投稿日: 2023.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画のpvで興味を持ち、映画は公開終了後だったので、原作を読んでみました。戦後、シベリアに捕らわれた俘虜の実情は想像もできないほど非情で、そのような世界が現実に存在していたことに驚きました。そんな耐え難く未来の見えない日々の中で、希望を持ち続けて、他人のために行動を起こし、支い支え合っていく登場人物達の想いに感動しました。本を読んだ後、もう一度映画のpvを見たら涙ぽろりでした。映画見たかったです。
11投稿日: 2023.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留の事を正直あまり知らなかったのですが、この本を読んでかなり胸にずっしりと来ました。 山本幡男の生きて帰ると言う強い信念が、周りを動かしたんだなと、色々考えさせられました。
5投稿日: 2023.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ見た目は普通の薄い文庫本だった。 読み進めるにつれ、どんどん重くなり、ページをめくるのも辛くなった。 でもみんなに読んでほしい。課題図書にしてほしいと思ったら、どなたかも書いてあった。 「夢顔さんによろしく」を読んだ時とはまた違う感情が湧き出た。それは、今の自分の環境もあるのだろう。
1投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を見て原作も気になり読みました。過酷な状況に負けず辛い生活の中にわずかな楽しみを見つけていく主人公が本当に素晴らしいです。 そんな主人公のために遺書を届ける仲間たちに感動します。
6投稿日: 2023.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争の悲惨さもそうだが、その後の十数年も収容所に入れられる悲惨さは筆舌に耐え難い。 フランクルの夜と霧にも似た感情を持つのは私だけだろうか。 どんなに苦しい時でも人に対して明るい影響を与えるような人に切になりたい。
3投稿日: 2023.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留の史実に基づいた話なので、覚悟して読みましたが、過酷すぎて何度も立ち止まりました。 極寒、飢え、重労働、次々と仲間が死んでいく、そんな極限状態でも帰国を諦めず、皆を鼓舞してきた山本幡男の人柄が素晴らしい。病魔に倒れた山本の帰国は叶いませんでしたが、仲間たちが危険を承知で遺書を分担し、暗記して、日本の家族に届けます。いかなる文書の持ち出しも禁止していたソ連当局の目をかいくぐり、ノート15ページ分の遺書が少しずつ遺族に届きます。 集団帰国が終了したのが1956年。そんな昔話でもない事実。ロシアがおかしくなっている今、平和ボケした日本人はもっと知るべき事実ではないかと思います。
6投稿日: 2023.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中眠くなるが、ソ連が日本人捕虜を石ころのごとく労働させたこと、そして今 ウクライナへの侵攻。他国に対する尊重の無さに怒りが湧く
1投稿日: 2023.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ梯久美子さんの「この父ありて」で角川源義と辺見じゅんの父娘物語を読んで、手にしたこの一冊、近時、映画化されてたんですね。 収容所で書かれた遺言を仲間たちが尋常ならざる方法で祖国に持ち帰り、遺族に伝えたという実話の辺見じゅんが描き切る。 感動で心が震えます。
3投稿日: 2023.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画『ラーゲリより愛を込めて』の記念展示を東京駅近くの『KITTE』で見て、その週末に映画を見て、原作も読んでみようと思って、今読み終えた。 どんな逆境にの中でも決して希望を失わなかった山本幡男の生涯。スパイ行為防止の為、文字による記録の所有が一切認められない中で、抑留生活九年目に没した山本の遺言を記憶で持ち帰る為に6名の仲間が分担して長い長い遺書を覚えた、という実話に感動する。 抑留生活3年目に帰国のためスベルドロフスク収容所からナホトカ港に向けて移動中、途中のハバロフスクで主人公他が列車を降ろされ、別の収容所に移送される際の絶望たるや。 映画を見た後に知ったのだが、私の妻の祖父は、この時の列車に乗っていたらしく、途中下車させられることなく、無事「永徳丸」で舞鶴港に帰国を果たしている。よくぞ、生きて帰ってきてくれた、とこの本を読んで、改めて思う。 以下、印象深い詩と短歌 指 わが指は 節くれだちて皺よりて 老いにけらしな 若き日は 品よく伸びて美しく 垂乳根の母はも 己(おの)が指に似たりと 愛で給ひしが 生業の筆もつ指に 筆胼胝(ふでだこ)生えし ニコチンの沁み入る指は 黄色く染まり この皺に鏝(こて)かけて延す術なし この手もて 親子 姉妹(はらから) 十人の 生活(たつき)ささえし現世(うつしよ)の 苦を刻みたる皺なれば うたても またいとほしく 時折は撫でて見つる 妻と幼子二人が平壌で発疹チフスで死んだことを中学生となった息子からの返信で知ったときの草地宇山の短歌 母逝くと吾子のつたなき返しぶみ 読みて握りて耐へてまた読む
9投稿日: 2023.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ恥ずかしながら、シベリア抑留が戦後10年以上も続いていたと言うことを知らなかった。しかもこれほどまでに過酷な環境で厳しい重労働を強いられていたことに、ただただ胸が痛くなる。 山本幡男さんと、彼と親しかった人々の話を中心に話は進んでいくが、これはシベリアの地で無念の思いで散って行った全ての人々の物語でもあると感じた。 本書の中心人物である山本幡男さんは、ロシア語が堪能なだけでなく、俳句や和歌にも精通した非常に博識な方で、前向きで意欲的、そして温厚でユーモアもあり、多くの人から慕われていたのは想像に難くない。辛い環境でも何か楽しみや目的を持つことの重要さを教え、皆に生きる気力を与えていたんだなと思う。 残念ながら、山本さんの生きての帰国は叶わなかったが、その死を以てしてなお、絶対に生きて祖国に帰るという目的と決意を仲間たちに与え、最後までつくづく立派な人だなと思う。 山本さんの遺書を皆で暗記して持ち帰ったというだけでも凄いが、山本さんが亡くなってから帰国までの間、3年以上も暗記し続け、しかも遺書だけでなく、生前の山本さんの句や詩までも暗記していたというのだから驚きである。それだけ皆の心の支えになっていたのだろう。 今、山本さんが望んだ日本にはなっていないことを恥ずかしく思う。
4投稿日: 2023.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクションと気がつかずに読んでました。途中、実名で登場する人がいて気がつきました。戦争の爪痕というか、理不尽な事を受け入れながらも自分の信念を曲げない強さを感じた。家族に残した手紙は心に染みる。
4投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化が話題になった、原作のノンフィクション。 戦後10年が経ち、「もはや戦後ではない」と言われていた時代に、極寒のソ連の片隅で必死に生きようとしていた日本人俘虜の生き様には、ただただ感服。 あの長文の遺書や大量の俳句、詩を暗記して祖国に伝えたとは…。 極限状態でも日本人としての誇りと矜持を失わない姿に感動すると共に、こうした方々の犠牲の上にできた平和な社会でのほほんと生きている今の自分たちの姿を反省した。
1投稿日: 2023.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後に勝つのは道義だぞ という印象的なメッセージを覚えておきたい。 理不尽で壮絶な環境の中で、希望を忘れず、周囲にも希望の光を灯していく生き方に感銘を受ける。 映画も本当に素晴らしかったけれど、小説では特に、文化的な豊かさやユーモアは人の心を支え、困難を乗り越える大きな力になるのだと知った。 また読み返したい一書。
5投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦の敗戦のあと、シベリア各地の収容所で12年もの長い年月を送らねばならなかった日本人捕虜たちの群像を、主人公である山本幡男氏の生涯を描いたノンフィクション。 著者によると、シベリアに抑留された日本人捕虜は60万人。収容所の数は1200ヶ所。酷寒と飢えと重労働のせいで亡くなったのは70000人超。 山本が書き残した遺書を記憶し、日本に持ち帰って遺族に渡そうとした元捕虜たちの物語である。 本書を通じて戦争について、また人間としての壮大な思想や友情、あらゆる事を考えさせられる作品でした。
26投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ二宮和也 主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』の原作本。 高校生ぐらいの課題図書にしてほしいぐらい、とにかく今だからこそ読んでほしいノンフィクション。 日本敗戦後のロシアにある収容所での12年間を語るノンフィクション作品。 明晰な頭脳を持ち、収容所に入られた捕虜たちに慕われた山本幡男さんを中心に語られる。 まさに『能ある鷹は爪を隠す』がピッタリな人です。 ロシア語が堪能で収容所でも通訳をしていた程の人が、スパイと見なされ理不尽な対応を受ける。 捕虜となった人々も様々な理不尽に遭い、過酷な労働をさせられる中、帰国の日を夢見て生き延びる日々。 自然環境も生活環境も過酷な中で日本へ帰還できる望みを決して捨てず、自身の持つ教養を活用して人々の心を救う姿に胸を打たれます。 やがて山本さんはガンを患い、日本への帰還を待たずに、この世を去ってしまう。 その前に書かれた遺書を、どうやって遺族に届けるか。 書面に残せば没収され、スパイ行為とされ監獄送り。 そんな厳しく理不尽な環境で、人々は自身たちの記憶を頼りに遺族へ伝えることを考える。 何年かかるか分からないし、自分たちか生きて帰国できるかも分からないのに。。 結果、捕虜とされていた人々は日本へ帰還。 遺書は山本さんの遺族に届けられ、最長で33年かかって届けられた書面もあったそうです。 遺書を記憶する人も選抜しないといけないところが、また辛い。。 遺書の存在がバレて、ロシア側にスパイ行為として密告される可能性もある。 覚書ですら、見つかれば没収・監獄へ。 まさに人が人を信じたからこそ起こった奇跡だと思います。 そして、その遺書は山本さんのお母さん・奥様・子供たちへと宛てられているのですが、子供たちへ宛てた部分は未来の日本人への願いだと感じました。 また、山本さんの行動からは教養の大切さを学びました。 自身の持つ教養を共有すること(句会を主催していた)で人々の心の慰めになり、人々の心を動かした。 柔軟さもありながら自分をしっかり持つ強さも見習いたい。 この本に携わった全ての方々へ、しきれない程の感謝を。
18投稿日: 2023.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化に伴ってノベライズ版も出版されているようだが、本書は1989年に出版された原作である。 日誌を読んでいるかのような淡々とした文章で、ラーゲリでの過酷な生活の中を日本人たちがどのように支え合い、生き抜いたかが描かれている。 30年以上前の作品であるため若干言葉が固く読みにくく感じる人がいるかもしれないが、戦争が起こっている今、一読の価値のある作品と断言できる。 山本氏の子供たちに宛てた遺書は、現代で豊かさを享受しながらなんとなく生きている我々にこそ響く珠玉の言葉たちであった。
3投稿日: 2023.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ信念を持つというのはどのようなことか、本当の楽観主義とはどのようなものなのか、文化や歴史、哲学はなんのため学び、何のために使うのか。人間はどこまで残酷になれるのか。日常が日常であることがどれだけ恵まれていることか。 これほど考えさせらる本になかなか出会えないと思った。 ノンフィクション小説というのが信じられないような、驚きの結末を迎える物語であり、登場人物たちの覚悟や葛藤、究極に過酷な状況下においても仲間を想い、立ち上がる純粋な心と勇気に心を動かさずにはいられない。 大規模な戦争が再び勃発している今、自分にできることは少ないかもしれない、ただこの本に出会ってしまった限りは学びを深めたい。
7投稿日: 2023.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
映画ラーゲリより愛を込めての原作(?) タイトルを変えたのはそりゃ出オチだから当然だよね ラーゲリ:地名かと思っていた シベリア抑留 の言葉は知っていたけど そしてそういう苦難の生活は数年、2-3年もすれば国家間の交渉 人道的なんとやらでどうにかなるものかと思っていた 現実はそんな甘い過酷な幻想をはるかに超える絶望的なものだった 風景を心情を歌い、歌を詠み、内にこもらず、そとに発し表すことで 帰国の希望、信念、過酷な生活な中でも人間性、感情を保つ、失わないよう 届いた ではなく 来た というのも 自らの一部を遺書と化した 人・生き残った人という
3投稿日: 2023.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉にし尽くせない酷い世界に光を灯し続けた主人公に、ただただ涙でした。昨今の、不要不急という言葉によって削がれた時間のなかで、文化芸術があっても、お腹は膨れないとも言われました。でも、この本を読んで、食べ物だけあっても、人が人らしく生きるのは難しいのだと、食べ物と同じくらいの生命のエネルギーになるのだと、改めて思わされました。
3投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を観て原作を読んでみたいという思いで読んだ。 映画とちょっと展開が違うんやな〜。 原作はアムール句会を中心に話が進んでいってそこで山本の日本にダモイすることを諦めない精神に周りが心打たれるっていう。 映画のホームページにも書いてたけど、コロナ禍っていう状況で山本幡男みたいな人物がいたら最初の深刻な状況もいつか元の日常に戻れるっていう勇気をくれたんやろうか。 登場人物多くて大変やったけど面白かった〜。
3投稿日: 2023.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画 ラーゲリより愛を込めて を見て、大きな衝撃を受け、原作を買って読んでみた。 実際の厳しさと共に、絶望の中でも日々と文化、ユーモアを大切にして、希望を失わなかった山本幡男と仲間たちの姿が、人間が立ち上がってくる。 聖人君主の物語ではなく、凡夫のままに生きる人間の勁さに圧倒される。 やっぱり、戦争はいかんという思いと、 人間の勁くいきる力への憧れと、 知性に裏付けられたユーモアへの信頼と、 長屋の隠居が理想ですという山本への共感と、 家族へ伝えようという友たちへの称賛と、 色々な思いが渦巻いている。 されど、その一方で、 アクチブに熱狂するもの、ソ連兵の走狗となるもの、軍の秩序にあぐらをかき続ける者、仲間を売るもの、絶望して死にいくもの、もいるという事実も突きつけられる。 それもまた、人間の姿であることを知る。 自分もああいう環境に置かれたら、後者のような反応をしてしまうだろう。 だからこそ、人間とは何かということを、もっとよく知りたいと思う。そのために、山本のいう、人道主義や、『最後に勝つのは道義だぞ』という言葉をもっと掘り下げて理解していきたい。 持ち帰られなかった、山本の『平民の書』が読みたかったと思う。 私の母方の爺様がシベリア抑留者だったので、興味を持って読んでみたが、本当に凄い人達がいたことをしった。 これから、 もっとシベリア抑留について調べてみたい。 夜と霧も読んでみたい。 こういうことをしながら、少しでも山本のいう人道とはなんなのか、考えて行きたいと思う。
11投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリアでの捕虜生活を想像し、滂沱の涙。ロシアに対して怒りすら覚えた。日々死活に怯える仲間達を俳句で癒し、励ます山本。山本の遺書を命懸けで暗記し、約束を果たした仲間達は日本の誇りだ。
2投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書が原作の映画『ラーゲリより愛を込めて』が昨年末公開され、映画ノベライズも刊行されました。私は未鑑賞・未読ですが、「ここはやはり原作を」と思い、本書を手にしました。 単行本は1989年刊です。まず本書の目次の次ページにある、見開きの「旧ソ連領内抑留日本人収容所分布図」を見て驚きを隠せません。広大な土地に記された夥しい数の収容所。そこに60万人が俘虜となった‥。唖然とします。 物語では、戦争が産んだ悲惨で過酷な収容所生活、仲間との絆、家族への想い等が描かれます。 読み進めるのが辛く感じるほどの重苦しさです。しかし、私たちはこの事実を知らねばならないでしょう。なぜなら、過去の歴史と多くの犠牲の上に生きているのですから。(偉そうですけど‥) しかし本書の肝は、戦争の悲惨さを背景にして、どんなに理不尽でも絶望せず、置かれた状況下で喜びや楽しみを見出し、それを他人へも波及させてしまう精神の強靭さと凄さを持ち合わせた一人の人物の生き様です。この山本幡男さんの存在を広く知らしめ、その崇高さを存分に謳いあげた物語と言えるでしょう。 山本さんの、(個人の遺書を超越し)亡き収容所の仲間を代表した、祖国日本人宛の願いに通じる遺書を、仲間が分担し「記憶」の形で届けるという、奇跡的な帰還を果たした事実に、涙します。 感動などという、ありふれた薄っぺらい言葉では伝えられないほどの深い感銘を覚えました。 戦争、極寒、飢え等のマイナスイメージから敬遠されそうですが、若い世代の皆さんにほど、おすすめしたい一冊だと思います。 ロシアのウクライナ侵攻からまもなく1年になります。一日も早い終結を願うばかりです。
48投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画の公開と同時にネットに掲載されたコラムに書いてあったので、読んでみたかった作品。 映画を観て、その足で本屋へ。 もっとルポタージュっぽい作品なのかと思っていたが、文章が小説のような感じで描かれているので、すごく読みやすかった。 第二次世界大戦後、満州に残された男性たちは捕虜となり、旧ソ連に連行された。 その中に元満州鉄道の職員だった山本幡男と言う人物がいた。 ロシア語が堪能で、ロシア人との通訳も勤めた山本だが、人柄が良く、重労働や極寒の中で疲弊していく捕虜たちを励まし、どんな状況でも「ダモイ」を諦めなかった。 しかし、元々身体が弱かった山本は「ダモイ」を前に癌で亡くなってしまう。 手紙を始め、文章など残せなかった山本の「遺書」を6人の仲間たちが11年越しに、山本の遺族に届けると言う実話。 正直、「ラーゲリ」と言う言葉を映画になったことで知ったし、たくさんの戦争関係の書物を読んで来たと思っていたが、旧ソ連の捕虜の方の話は無知であったことを恥じた。 山本は決して派手に何かをした人物ではない。 しかし、仲間たちがそれぞれ家族の元へ「遺書」を届けようと思うほどなのだから、きっと描き切れない優しさに溢れた人であったのだろうと想像するしかない。 元々の映画の原作である今作。 今作では「遺書」を届けるのは6人であるが、映画では登場人物を集約する為、4人となっている。 映画に登場する4人は架空の人物と言うことで、それぞれの登場人物のエピソードを組み合わせているとのこと。 どのエピソードが誰の物語になったか、考えながら読むとなかなか興味深かった。
13投稿日: 2023.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ1945年の敗戦で、ソ連軍に捕らわれ、不慮生活をおくることになる山本。 帰国(ダモイ)を信じ、希望を捨てずに生きる姿は周りにも影響を与える。 惜しくもダモイ前にがんで亡くなってしまうが、ある方法で遺書を家族に届ける。 まさに日本版「夜と霧」 日本にもこのような事実があったことに驚く。 自分の知識の無さにも。 「夜と霧」や「ショーシャンクの空に」同様、ここにも希望を捨てない男がいる。 そして、過酷な状況でも周りにきつく当たることはない。 とにかく丁寧。 家族や周りの人のことを考えている。 どんな環境でも反応の自由はある。 原作小説では、映画よりさらにいろいろなことが書かれている。 その分、分かりづらく、テンポが悪かったりするが・・・ 実際に日本人捕虜がラーゲリで強制労働をさせられていたり、10年以上も帰国できなかったり、さらには現地でなくなってしまう人も多くいたという事実は、日本人は知る必要があるのだろうな。 同じく、日本が朝鮮などを植民地化して同じようなことをしていたことも。
1投稿日: 2023.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ想像を絶するほどの過酷な収容所生活の中で、人としての心と希望を失わなかった、山本さん、その他多くの方々に、ただただ尊敬の念しかありません。 辺見じゅんさんの書籍は初めて読みましたが、丁寧でとても読みやすい文章でした。
9投稿日: 2023.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みながら、久しぶりに泣いてしまった。 涙無くして読めない。 決して希望を見失わず、常に仲間を励まし続けながら、力尽きた主人公の無念を思うと、胸が張り裂けそうだ。 極寒での過酷な強制労働そして長期に渡る拘禁、抑留生活を強いられたことは、敗戦国の悲哀では済まされないのではないだろうか? 現在のロシアのウクライナ侵攻もあり、益々ロシア為政者に対する怒りが湧いた。
2投稿日: 2023.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアがウクライナに侵攻したこのタイミングでの映画化に感慨深いものがある。 まず、これが戦争という事物のなかの事象であることを忘れてはいけない。ロシア人が特別に非情な人間だということではなく、人間は社会的規範にはその理由を考えることもなく従ってしまう、という特徴がスターリンの暴政で如実に現れた結果なのだ。 本編は、日本人俘虜として捕らわれた人々の日々に終始している。 スターリンの政治、朝鮮戦争、その他の世界情勢はなく、一貫して俘虜たちにフォーカスを当てている。 懲罰やソ連兵の惨さにもあまり言及していない。ただ、俘虜たちを支えていた山本の言動、帰国を信じて日々を強く生きようとする日本人俘虜たちが描かれている。 個人的に、日本人俘虜がラーゲリで可愛がっていた犬クロの話が強く印象に残っている。犬と人の絆にも涙した。 ホロコースト、戦争捕虜、原爆。 こういったことを経験した人で、 戦争は社会のためには仕方のないことだから、もう一回やろう、そんなことを言える人が一体どこにいると言うのだろうか。
4投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023.1.16 読了 『ラーゲリより愛を込めて』という映画の原作本。 映画を見た後にこの本のことを知った。 戦争の裏ではどのようなことがあったのか、学校では習わないシベリア抑留について学ぶことができた。戦争について改めて考えさせられる本だった。
3投稿日: 2023.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリアの荒野をろんろんと高鳴る風の響きに、千キロ彼方に広がる生まれ故郷の日本海の海鳴りを聞く。 生きて必ず日本に帰ること、家族と再会すること、それまでの間うつくしい日本語を忘れぬこと。終戦直後からソ連軍に捕われ、極寒と飢餓と重労働に苦しむシベリア抑留が続くなかで、同じ収容所(ラーゲリ)に捕らわれている人々に希望を与え続けていた山本幡男という人がいた。しかし彼は病に倒れ、生きて日本に帰ることは叶わない。 ところが彼が生前、家族にあてて認めた数通の遺書は、敗戦から12年目にして遺族のもとに確かに届けられた。シベリアで俘虜となった元兵士や、民間人たちがどんな仕打ちを受けていたか、真実の漏洩を恐れる厳しく執拗なソ連の監視網を搔い潜る驚くべき方法で、かつて山本によって心を救われた収容所の仲間たちによって――。 第二次世界大戦終戦後、武装解除され投降した日本軍捕虜や民間人らが、ソ連によってシベリアなどへ連行された。その数およそ60万人。死者は約6万人とされているが、アメリカの研究者によるとさらに多く、今もその実数は不明。長期にわたる抑留生活と奴隷的強制労働により、多数の人的被害を生じたこの一連の悲劇をシベリア抑留という。 いくら慕っていたとはいえ、自分自身が過労と飢餓と酷寒に苛まれるなかで、その遺書の長文を一字一句たがえぬように暗記して、それをいつか日本に帰ったあかつきには必ず彼の妻子のもとに会いに行って伝えて見せる。そこまで仲間たちに行動せしめた彼――山本幡男という人は、一体どんな人物だったのか。本書はその知性と人間性を、人々の記憶をつなげて再現していく。 実際に起き、生き残って日本に帰ってきた人々によってたくさんの証言が残り、おそらく、それ以上に口を閉ざさざるを得なかった人類の悲劇を、体験者や遺族への丹念な取材をもとに明らかにしていったノンフィクション。
1投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログラーゲリより愛を込めての原作。 シベリア抑留の過酷さ、当時の政治&世界情勢がよくわかる。 1人の男のために、みんなが命を賭して遺書を届けた。その思いに感動した。 映画がどのように切り取られてるかわからないが、映画もみたい。 これは、物語として単調に読めるものではないが、とても良い話。是非原作のこの本も読んで欲しい。
1投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
映画化ということで読んだ。 絶望的、過酷な環境でも生き抜く主人公には胸を打たれた。 その主人公に慕う仲間も一人一人色濃く描写されている。 遺書を仲間の記憶によって家族に届ける感動的な内容であった。ソ連への復讐や憎しみではなく、悲痛な内容が書かれるのではなく、遺された家族への幸せを願う。 私も愛や喜びを大事にし、そして道理を通すことの大切さを子供に伝えていきたい。と感じた内容であった
1投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留中に亡くなった男の遺書はある方法をによって厳しいソ連の監視網を潜って家族のもとに届けられた、真実の物語。 映画「ラーゲリより愛を込めて」を観てとても良かったので、原作を手にしてみました。 映画との違いに初めは戸惑いましたが、事実に迫る描写に捕虜生活の過酷さを読み取ることができました。 そして、俳句という日本の文化がこの捕虜生活の中でとても重要な救いであったことも強く伝わってきました。 家族のもとに届けられた遺書が全文残っており、涙なしでは読めない内容でした。 これらのことから、俳句をはじめ、日本語の表現や文化がこの過酷な捕虜生活を支えていたのではないかと感じました。 日本語という言葉の力の素晴らしさを再認識することができたと思います。
19投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ知らなかった世界をまた一つ知った。 日本史の教科書の「シベリア抑留」の言葉にまとめられた、その歴史の一片を知れた。 戦争がもたらすもの 生きること自体が目標になる生活 その中でいかに豊かに生きるか 豊かに生きるためにはどんな精神でいるべきなのか それを、仲間を巻き込んで一つの大きな渦を作り出したのが山本幡男さんだった 2022年に二宮和也が山本さんを演じた映画「ラーゲリより愛を込めて」が公開。 ラジオでこの映画の紹介を聞いて関心を持ち、原作を手に取った。 きっと、映画では、恋愛や、友情や、収容所での厳しい生活に対する衝撃などがクローズアップされて、もっと細かい部分は読み取れないのではないかと思って、原作を読むことにした。 (映画を見ることで、シベリア抑留を知るきっかけにはなるのだろうけど) 映画は、機会があったら見ようかな。 〜思い出して追加〜 祖国を思いながらも、日々の作業をこなすことで精一杯な俘虜 そんな俘虜たちが、 日本語に触れてホッとする それまでの人生で触れたことがなかった短歌や和歌に触れてのめり込んでいく これがラーゲリでの生活を豊かにする 人々に精神的に繋がりを生む そして、ようやく叶ったダモイの船の中で、重数年ぶりに触った箸に感動する… いま、私たちが求める「豊かさ」とはなにか。 家族で支え合うこと 日々の仕事に心を込めること 愛情を持って人に接すること 日本の文化を知ること 世界の文化を知ること 当たり前にすぎていく毎日を、いかに豊かに生きるか この問いは、現代社会でもラーゲリの中でも、同じかもしれない
2投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画化されると知り、すぐに購入。 やっぱり辛い、苦しい。 映画は夫婦や仲間の絆を軸に描いていたが、本は収容所の実態を詳しく書いており、映画のあのシーンの背景にはもっと過酷な出来事が起こっていたんだな、と想像しながら読み進めていた。 本の中で特に印象的だったのが和歌を楽しむ場面。映画ではあまり多く描かれていないが、本の中では沢山和歌を詠む場面が出てくる。これがまぁ難しい…読んでも読んでも頭に入らない… 和歌という日本語の美しさが詰まった言葉たちを理解できないとは、、彼らと同じように楽しめないとは、、日本人として悲しい気持ちになった。 学びを積極的にしたり、知恵を絞って娯楽を楽しんだり、和歌を皆んなで詠んだり…デジタルに囲まれた現代だからこそ、人間って本来こうあるべきだよな、と気付かされ、どこか羨ましい気持ちにもなった。 主人公が子供たちと若者に遺した言葉。 《日本民族こそは将来、東洋、西洋の文化を融合する唯一の媒介者、東洋のすぐれたる道義の文化、人道主義を以て世界文化再建に寄与し得る唯一の民族である。この歴史的使命を片時も忘れてはならない。》 グッとくるものがあった。 日本の文化に誇りを持って生きている人ってどのくらいいるのかな?親切心や礼儀正しさ、日本にいると普通のことでも世界から見ると凄いと言われる文化が沢山あると思う。そういう日本の美しい文化をもっともっと大切にしたいなと読んでいて思った。
3投稿日: 2023.01.01シベリア抑留は知っていましたが、こんな奇蹟的な話があったとは
映画化されると聞き、大急ぎで読みました。シベリア抑留についての知識は、歴史上の事実として知ってはいましたが、このような奇蹟的な逸話があったとは、全く知りませんでした。 実は、今は亡き、大正13年生まれの我が父は、工兵として満州へ行き、そこで終戦をむかえました。オヤジの話によれば、終戦後復員する前に、ずいぶん中国本土の復旧工事をさせられたと言っておりました。でも、ほんのちょっと運命が違えば、彼もシベリア送りになっていたかもしれません。もしそうなっていたら、お袋さんと結婚していないかもしれないし、昭和34年生まれの私はこの世にいなかったかもしれません。 この本はノンフィクションながら、かなり小説風に書かれてはいます。時の流れや描かれる場面があちこちにいって、ちょっと戸惑うことがありました。作者の想像で書かれた箇所もあるかもしせませんが、兎に角、よくぞこの本を出版してくれたと思います。 収容所生活の過酷さは、これまでも様々なところで紹介されてきました。過酷な状況に耐え抜くには、体力以上に、必ず故国へ帰るという強い意志が必要だったでしょう。でも極限状態となると、その人の本性のようなものが健全化してきます。また、日本人同士間のタレコミやソ連に迎合して、少しでも良い思いをしようとする人も出てきます。 そんな希望のかけらも見えない状況の中、どうして山本幡男さんは、いつも前向きに考えることが出来たのでしょうか。ただひたすらに、故国へ帰るんだという強い希望を持ち続けたからでしょうか。しかも、その振る舞いは、次第に周りの人々に影響を与えていき、彼の存在そのものが、過酷な生活の中で他の皆の希望になっていったんだね。しかし、病気が進行し、とても故国へは帰れないと自覚したとき、流石の彼も希望をなくしてしまいます。ところが今度は、周りの仲間が彼の希望を奮い立たせるわけです。それが、彼の遺言や彼の詩、彼の歌等の著作物を、彼の帰りを待つ故国の家族に届けると言うことだったんだね。しかも、帰国の際に持ち出せないからと、仲間とともに少しずつ分散して、すべてを暗記することによって。。。 昼間は過酷な労働を強いられ、疲労困憊の中、他人のコトバを一字一句間違えずに暗記するなんてことは、不可能に近い行為です。それに、帰国してからだって、大変な生活が待っていたはずです。最後の遺書が山本家に届けられたのは、昭和62年とのこと。こんなことが私たちの知らないバブル全盛期に起こっていたとは。 これは、収容所で共に艱難辛苦を味わった友情のキズナなんていう生やさしいものではなく、とても我々のコトバでは言い表せないモノが彼らの間にあった証でしょう。 ソ連の行ったことは、まぎれもなく戦争犯罪です。いやその前に、勝ち目のない戦争に突き進んだことが問題であることは、今となっては明らかです。でも、それ以上にこの本は、生きると言うこと、いや生き抜くと言うことは、どういうことかを読者に突きつける一冊でありました。
0投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ過酷な収容所での生活で、人間の醜い部分もたくさん目の当たりにしても、空を見上げて「シベリアの青い空」の美しさに気づくことができるのか。 全てを取り上げられても、古典や万葉集を引用し、詩や俳句を読むことができるのか。 そして、ノートや鉛筆を取り上げられても、人の記憶まで奪うことはできない。 文化、芸術、教養は、本当に人間の生命維持に不可欠なのだと思い知りました。真っ直ぐな希望と力強さに、日々を大切にして生きていきたいと思います。
1投稿日: 2022.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログソ連への捕虜となった日本軍の強制労働についてはいろいろと書かれているが、山本幡男という一人の人間をもとに、死亡した時の遺書を皆で分担して記憶して家族に伝えたという話はこの本が初めてである。 ノンフィクションとしてだけでなくフィールドワークの記録として価値がある。日本に帰ったのが1956年12月というのも驚かされた。
2投稿日: 2022.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で言うと、日本版『夜と霧』である。 シベリア抑留での過酷な生活の中で、絶望感に打ちひしがれる人が多い中、周りの人々を俳句などで励ました山本幡男さんの話である。 残念ながら顔『夜と霧』フランクルと異なり、山本さんは抑留先で亡くなり帰国出来なかった。だが、山本さんの仲間たちが、書き物が所持品検査などで収容所の人間に没収される状況下で山本さんの遺書をいつ帰国できるかわからない状況下で暗記し続け、帰国後に山本氏の遺族に遺書の内容を伝える。このエピソードでどれほど山本さんが慕われていたかがわかると思う。
2投稿日: 2022.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ胸が打たれた。小説だと思って読んでみたら壮大な遺書でした。 映画化と聞き読んでみた。初めは読み辛かったが、最後まで読み切って本当に、本当に良かった。初めてのノンフィクションは物語として満足できるか不安だったが杞憂であった。本当に実現したのだろうか、極限で死が身近な環境での山本幡男という男の生き様は、日本に生まれ平穏に暮らせる幸せを生きる自分の価値観では到底計り知れない。 とても大きく偉大だと読み終えて口に出た。 また作者の熱意にも感謝したい。当時ではこの作品を作り上げる苦労も凄まじいだろう。 作者も伝えているが、子供達へ宛てた言葉は現代の我々も真っ直ぐに受け止めねばならないと感じた。 映画は観させていただきます。
3投稿日: 2022.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画の原作ということで読んだけれど… これは、映画館で見れるのだろうか…配信されるまで待とうか…悩む(絶対号泣してしまうだろうから)
1投稿日: 2022.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログなんていう話や。唸った。 主人公が帰国した世界も見てみたかった。平和とは当たり前ではないと痛感する。 もうすぐ映画も上映されるということでそれも楽しみ。
12投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今度公開される映画「ラーゲリより愛を込めて」の予習として読みました。 読み始める前に作品の時代背景を把握するのが少し難しかったのですが、 1943年に満州に出兵していた日本軍が、1945年に第二次世界大戦が終戦した後ロシア軍に捕虜とされ、12年間収容された後に日本に帰国し、1957年にある手紙を遺族に届ける話です。 原作は辺見じゅんさんの『収容所から来た遺書』で、こちらは単行本で1989年に書かれたものです。 原作本は33年前に書かれたもので、本に書かれている内容は今から79〜65年(の14年間)前の話です。 自分は1990年生まれなので、この本が出た年の翌年に生まれています。 書かれていることは、祖父母が子どもだった時くらいで、つまり曽祖父母の時代の話という位置づけで読みました。 読んでいて面白かったのは、当時の思想的なうねりが生々しく生死に関わってくる時勢の中で、ロシア文学に心酔していた主人公山本が収容所の中で生きるということの意味を掴んでいく過程と、日本語の俳句や詩を収容所の中で作り続けながら自身の思想や生命観を磨き続けた後に親族に宛てて「遺書」を書いたことです。 そしてその遺書を、ロシア軍の検閲をかいくぐって(暗記して)仲間が親族にまで届けるという尋常ではない言葉の受け渡しのドラマです。 手紙、言葉、というものが、過酷な状況の中でいかに深まって行き、人間を鼓舞するかという壮大なノンフィクションだったし、絶望的な境遇の中で書かれた親族へのシンプルで希望に満ちた言葉を読んだ時の感動はちょっと言い表せません。 本当に圧巻で、震える一作でした。 現代では掃いて捨てるくらい大量の(そしておもしろい)エンターテインメントが溢れていますが、こういう色褪せないノンフィクションをじっくり読むのもおもしろかったです。
0投稿日: 2022.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログミセスグリーンアップルの大ファンです。 新曲『Soranji』が、映画の主題歌になるという事で、その原作である本書を読みました。 とても、壮絶な内容でした…。 山本さんの強さ。明るさ。生きることへの執念。 今の私と、真逆です…。 ぜひ、映画も見てみようと思いました。
1投稿日: 2022.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「人の世話にはつとめてならず、人に対する世話は進んでせよ。但し、無意味な虚栄はよせ。人間は結局自分一人の他に頼るべきものが無いーといふ覚悟で、強い能力のある人間になれ。」『子供達へ』の中のこの一文が強く心に残った。私は今まで、何事も中途半端で強みと言えるものがなかった。学生であるうちに1つでも強みを作りたいと思った。
0投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
映画を観にいく予定はないが、『映画化決定』、『大宅壮一ノンフィクション賞受賞作』の帯に惹かれ、タイトル買いした本書。 終戦後長らくソビエトのラーゲリ(強制収容所)に抑留された山本氏の物語。 本のタイトルや、筆者が山本氏のことを書こうと思ったきっかけは、戦後10数年かけて遺族に届けられた遺書であるが、物語の大半が山本氏が生きている間のこと、特に収容所での日常生活に充てられる。 あまりにリアルで、顔をそむけたくなるような、そんな日常生活である。 私が尊敬するノンフィクション作家の角幡唯介が、「ノンフィクションには必ず、フィクションが入っている」と言っていたが、この本ではそのことが明瞭に理解できた。筆者あが収容所での緩慢に進む日常にスポットを当てたことで、10数年後に届けられた遺書の重みがよりずっしりと感じられるなったと思うのだ。 手紙が届けられてこと自体は、エピロローグでさらっと触れられているだけである。
3投稿日: 2022.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログソ連軍に強制連行され、酷寒と飢えと重労働のシベリア抑留中に死んだ男(山本旗男)の日本の家族への遺書(ノート)は、彼を慕う仲間たちによってソ連の監視網を掻い潜って、驚くべき方法で遺族に届けられた・・・大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した感動実話。
5投稿日: 2022.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年(2022年)の年末にニノ主演で映画されるとのことで読んでみたが、私はこういう話はとても苦手。感情移入しちゃうからなあ・・・。しかし、こう云うことがなんで起こるかはともかく、何のお咎めがないのがおかしい。今もしてんだろうなあ、この国。好きにし放題だよな、いつも・・・ ところで作品の内容に全く関係ないが、筆者は角川春樹さんのお姉さんなんだ・・・
0投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ニノ始め北川景子、松坂桃李と言う主役級がそろった映画化と知って原作を読みたくなった。戦後ロシアが行った不法なシベリア抑留での主人公山本幡男たちの記録で、表題でも分かる様に山本は生きて日本に帰る事は出来なかった、しかしその遺書だけはロシアの検閲をくぐり抜けて人々の暗記によって持ち帰られると言う奇跡の物語。シベリア抑留は山崎豊子の「不毛地帯」等でよく知っており、そこには帰国後日本政財界で暗躍する瀬島龍三なんかも登場するが、本書では端役に過ぎない。ロシアは昔も今も一緒で日本人は決してロシアを許してはならない。
3投稿日: 2022.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦終戦後、国交のないソ連に俘虜として抑留された人達のことは知ってはいたが、実は全くわかっていなかったんだ。 極寒、重労働、空腹・・・過酷な状況に置かれても人間らしく生きるとはどういうことか。山本の存在が、如何に周囲の人々の生きる支えになったか。本当に強い人とは、彼のような人を言うのだろう。 映画「ライフ・イズ・ビューティフル」を思い出したのは私だけだろうか。 文句なしの星5つ。
2投稿日: 2022.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログお世話になっている社長から数年前に進められる。 終戦後、シベリア抑留された方々の実話。 映画化され12月に公開されると聞く。 読後の余韻が止まらない。 映画を観に行くかどうか決めていないが、無理して映画化しない方がよかったかも。 この物語は2時間程度で済むものではない。
1投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「辺見じゅん」のノンフィクション作品『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』を読みました。 「半藤一利」の『ソ連が満洲に侵攻した夏』を読んで、シベリア抑留された人の実態を知りたくなったんですよね -----story------------- 敗戦から12年目に遺族が手にした6通の遺書。 ソ連軍に捕われ、極寒と飢餓と重労働のシベリア抑留中に死んだ男のその遺書は、彼を欽慕する仲間達の驚くべき方法により厳しいソ連監視網をかい潜ったものだった。 悪名高き強制収容所に屈しなかった男達のしたたかな知性と人間性を発掘して大宅賞受賞の感動の傑作。 第11回(1989年) 講談社ノンフィクション賞受賞 第21回(1990年)大宅壮一ノンフィクション賞受賞 ----------------------- 第二次世界大戦敗戦後、ソ連軍に捕らわれ極寒と飢餓と重労働長い年月(最長十二年)をシベリア各地の収容所で送らねばならなかった日本人捕虜たちの群像を、その一人だった「山本幡男」の生涯を軸に描いた作品です。 ■プロローグ ■一章 ウラルの日本人俘虜 ■二章 赤い寒波(マロース) ■三章 アムール句会 ■四章 祖国からの便り ■五章 シベリアの「海鳴り」 ■エピローグ ■あとがき 三十三年目に届いた遺書 ■解説 吉岡忍 シベリアに抑留された捕虜は六十万人(『ソ連が満洲に侵攻した夏』では五十万人と記載があったかな…)にものぼり、そのうち、酷寒と飢えと重労働で七万人を超える人々が亡くなっています、、、 その絶望的な暗黒の生活の中で、仲間に光を与えた「山本幡男」の言動に勇気をもらうとともに、「山本幡男」の死後、その遺言を遺族に伝えるために驚くべき方法を実践した仲間達の行動に感動しましたね。 文字を残すことが禁じられていた抑留生活の中で遺書を分担して記憶… 帰国後、記憶を頼りに再現された遺書七通が遺族の元に届けられます、、、 最後に届いた遺書は、なんと昭和62年… 「山本幡男」が昭和29年に亡くなってから、実に33年後だったとのこと。 長い長い旅をして届いた遺書… 色んな人の思いの詰まった遺書だったんでしょうね。 こんな歴史を繰り返しちゃいけないな… という思いを強く感じました。
2投稿日: 2022.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公山本の言葉、人柄があってこそ、皆で日本に帰る強い希望を持ち続けたと思えた。また、彼の遺書を伝えたいという仲間たちの思いに胸を打たれる。
0投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
敗戦後シベリアの強制収容所に送られた日本人は五十七万四千五百三十人と言われている。 その中の一人に元満州の諜報部隊出身でロシア語の堪能な山本幡男さんがいた。トレードマークは丸メガネ。極寒で劣悪な環境の中、黒パン一個で重労働をする苛酷な状況下でも彼はソ連兵の監視を逃れながらアムール句会という俳句のあつまりを作り、俳句を作ることで遠い日本に思いを馳せた。また、彼はどんな状況になってもダモイ(帰還)を諦めなかった。それは周りの人びとの希望でもあった。しかし帰還を目前にして病魔に襲われてしまう。 仲間達がどのようにして山本幡男さんの遺書を持ち帰ったのかという部分で泣けた。あの環境下で他人のためにあそこまでできる彼らは本当に凄いし、山本さんのためなら、という部分が大きいというのが本一冊を通して伝わってきた。 山本さんが生前言っていた「生きておればかならず楽しいことがあるよ」という言葉は忘れないようにしよう。
0投稿日: 2022.04.16人は死んでも生きている
戦後シベリアで抑留され過酷な状況にありつつも、その中に生きがいや幸せを見出し、周囲の人たちの希望となった山本幡男とその遺書を記憶して伝えた男たちの話。泣けてなけて仕方なかった。人は死んでも生きている。亡くなっても人の心に存在し続けるように生きたい。
0投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中で頁を閉じる事が出来ず、一気に読了。塩からい水が呼びもしない私の頬を絶えず流れたまま。 ラーゲリロシアの収容所で俘虜として終戦後10年過ぎてもダモイ帰国する夢もついえたまま亡くなった山本旗男氏。故国を想い、妻と4人の子供、実母を想い、心ならずも癌で絶命する直前に自分の言葉で呟いた数通を仲間は日本へ持ち帰った・・無論、現物ではなく。文字を持ち帰ることは没収を意味し、すべて「記憶暗唱」 6通が妻モジミさんの元へ、そして7通目が届いたのは昭和62年。「もはや戦後ではない」どころか、バブルの残滓が国中を浮遊しているような浮かれた時間だったのは私が覚えている。 戦争、俘虜、収容所・・何も知らない、知らなかったではすまされない重いドキュメントだった。 著した辺見氏も今や、鬼籍に入り、この作品を残してくれたことに心から敬意と賛辞を。 山本氏が「居た」「輝いた」「他者の心に灯をかざした」ことが伝わって行く・・行かねばならぬ。 今、ロシア、ウクライナの行方を見守る時間の中で強く念じる。
0投稿日: 2022.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ノンフィクション、ドキュメンタリーに書かれているのかと思いきや、半ば小説で読みやすい。 戦後、ソ連の収容所へ送られた日本人たちの話。 山本幡男氏の、ダモイ帰国を信じ、周りの囚人達へ、句会や勉強会を通して美しい日本語を忘れないよう、また、日々の細やかな季節の変化や楽しみを作って前向きに生きていこうとする。 それでも山本の最後は病気を患い帰国できない。最後の力で書き残した遺書を仲間たちは、厳しい検問で文字を持ち帰れない中、記憶やさまざまな努力の末に持ち帰り、遺族へ伝える。その言葉は、遺族のものだけでなく、日本の未来へと語り継がれるべき、強く、美しい日本男児の言葉である。 凄まじい、過酷な状況下からの生還。ぽつりぽつりと届けられる遺書の数々。戦争を知らない世代に読んで欲しいとあとがきにあった。正にそう思う大切な一冊。
4投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後ソ連に抑留されていた元日本兵の遺書を戦友たちが記憶して持ち帰った、というあらましだけ知ってて、うっかり読む機会を逸するところでしたよ。読んでほんとに良かった。本当に重要なのは、遺書がどう持ち帰られたかではなく、この山本幡男という人物がどのように生きたかということなのでした。 ようやく戦争が終わったというのにその後10年以上も抑留され、過酷な自然と強制労働の重荷のために仲間は次々と死んでいき、いつになったら解放されるのかもわからない。その状況は想像するだに絶望的だが、特に山本氏の場合、大学在学中にはマルクス主義の洗礼を受けて退学を強いられたほどのソ連びいきだったにもかかわらず、かえってそのために収容所内においてはスターリン主義になびいた日和見主義者たちの激しい迫害を受けるという、なんとも皮肉な苦境を経験していたのだった。 そのような中にあって腐らず、生きて故郷に帰る希望を捨てず、「こんなに楽しい世の中なのになぜ自殺を考えるのか、生きていれば必ず楽しいことがある」と少しの皮肉も交えずに話し、何か月も続く厳しい冬の中でわずかな空気の色の変化に目をとめては句や詩を詠む。 周囲の人々が記憶していた遺句に見られる環境にそそぐ観察者としてのまなざしの透明さにも大いに感銘を受けるが、とくに深く感じ入るのは、密告が蔓延し、自らもその被害に遭って命の危険にまでさらされていながら、ひそかに句会を組織したり交流会で人々を楽しませるなど、自ら交わりを求めつくりだして周囲の人々を生き延びさせていった、その姿勢だ。彼がはじめた句会には、元憲兵や将軍さえもが参加していたという。どのようにして人間不信に陥ることなく、人のつながりに積極的な姿勢を保ち続けることができたのだろう。このような人でありたいものだと心から思う。そして無名の偉大な人の足跡をこうして伝え知ることができるように物語を伝え運ぶことの意味を思う。 もうひとつ、「シベリア抑留」を「戦後処理」という枠組みで見ることの不十分さにも気づかされた。スターリン支配のソ連で日本人俘虜たちは実際には戦争捕虜としてではなく他の多様な集団に属する者たちとともに体制への脅威かつ労働力として扱われていたのであり、冷戦構造下における国家秩序の再編によってその扱いは翻弄された。文中でも言及される朝鮮人俘虜たちは朝鮮半島における分断国家という現実によって大きく翻弄されたのであって、まだまだ知らないこと、考えてみることが多いことにも気づかされる。
0投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
3.6点 "置かれた環境での楽しみを見つけよ" 理不尽な状況下の中、ダモイという帰国を信じ生を全うした山本という男を主軸に描いた作品。 現在の社会に置き換えて考えることができる内容で、逃げることの出来ない過酷な労働下とまでは行かないが、精神的に追い詰められて自ら命を絶つ人たちも多い昨今。 今が恵まれているということを再確認もしつつ、俳句のような逃げ道を見つけて拠り所を見つけることも大事だと思う。 俳句に明るくない為、都度出てくる俳句を理解しきれなかった点がある。解説などつけてくれるとよりありがたい。
1投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦が終了し、多くの人々には「戦後」が訪れた。 だが、終戦後も長きに渡って拘束されたままの人々もいた。ソ連の強制収容所(ラーゲリ)に囚われた人々である。極寒の地で飢餓と重労働を強いられた日本人抑留者の数は60万に上り、死者は7万人を超えるとも言われる。 外交交渉により、抑留者の釈放が決まり、最後の解放者らを乗せた船が舞鶴港に着いたのは、1956年暮れのこと、実に終戦から11年が経過した後のことだった。 本書は著者が多くの人々に取材してまとめた、ラーゲリを舞台とするノンフィクションである。その軸となるのは、ラーゲリで病に倒れた男が記した遺書だ。厳しく生活を規制され、筆記具なども満足には支給されず、さらには解放時に文書や記録等の持ち出しも堅く禁じられたその地から、男の遺書は仲間により遺族のもとに送り届けられた。いったいどうしてそれが可能であったのか。 男の名は山本幡男。ロシア語が堪能で、収容所では通訳としても活躍していた。 一時はウラル地方のスベルドロフスクに収容され、その後、東に移送されて、ハバロフスクで長い年月を過ごした。 このまま帰れないと悲観する者もいる中で、山本は一貫して「ダモイ(故郷へ、帰郷)」肯定派で、いずれは解放され、自国の地を踏めると信じていた。 その山本が主宰したのが、日本文化の勉強会だった。左翼運動のため外国語学校を中退という学歴ではあったが、山本は学才豊かで、万葉集や仏教にも詳しく、そのわかりやすい話は収容所の皆を楽しませた。後にそれはアムール句会と称する句会となり、山本の話を聞くだけではなく、集まった参加者が俳句や短歌を作り、山本が選評を行う会となった。 「ぼくたちはみんなで帰国するのです。その日まで美しい日本語を忘れぬようにしたい」 単調で厳しい生活の中で、やがてそれは皆の心の支えとなり、日々を生きる糧となった。 著者は抑留者の多くを訪ね歩き、ラーゲリでの生活を聞き取っている。 食糧も十分ではない。寒さも厳しい。碌な道具もないのに、作業は重い。 それでも文化の火を灯し続けようとした山本の姿が浮かび上がる。多くの人々を励ました一方、それは彼自身の支えでもあっただろう。 しかし、山本を病魔が襲う。 仲間たちは病室を訪れ、時に足をさすり、時に苦労して手に入れた滋養のあるものを差し入れる。だが、病状は進み、長くないことは誰の目にも明らかだった。 1人の男が遠慮がちに、家族に向けて遺書を残すことを勧める。 瀕死の山本が必死の思いで書き上げたそれは、涙なくしては読めないものだった。 山本幡男、1954年8月25日死去。享年45歳。 山本の遺書はノートに記されていた。だが、書き残したものは下手をするとスパイ行為とみなされ、処罰されることもある。 原本が処分される可能性も想定し、仲間たちは手分けして遺書を暗記したり、書き写して隠したりした。 艱難辛苦の果てに彼らが帰郷し、遺族の元に遺書が届けられたのは1957年1月のこと。仲間の1人が封書を手に遺族を訪ねた。 しかし、届けられたのはそれ1通ではなかった。別の仲間たちから1通、また1通と遺書の一部、また山本の句や詩が届けられた。時を経て、全部で7通もの遺書が、山本の無念の言葉、そして遺族への励ましを伝えたのだった。 15ページにも渡る遺書は、家族全員へのものに加え、母、妻、子供宛てのものがあった。遺書を守った仲間の1人は、「これは山本個人の遺書ではない、ラーゲリで空しく死んだ人びと全員が祖国の日本人すべてに宛てた遺書なのだ」と思ったという。 山本の残した「海鳴り」という詩がある。 「耳を澄まして聞くと海鳴りの音がする ろんろんと高鳴る風の響き 亦波の音 (中略) 嗚呼 寒夜の病床に独り目を覚まして 私は ろんろんたる海鳴りの声を聴いてゐる 遠く追憶を噛みしめてゐる」 臨終の床にも、故郷の隠岐の海鳴りが聴こえていただろうか。 極寒の地で、彼らを支えたものは、故郷への思い、そしてそれを綴る言葉そのものであったのかもしれない。
7投稿日: 2021.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリアに抑留された元兵士たち。句会等を通じて人望を得た人物が帰国の願いを胸に病死。手紙、ノート等が禁じられた中、仲間たちは遺書を遺族に届けるために思いもよらぬ手段を取る。 シベリアからの最終引き揚げが昭和31年。長い戦後、故国に思いを馳せ無念の死を遂げた日本人も多い。 本書は絶望的な環境を持ち前の教養で句会、同人誌などで、仲間の心を支えつつ亡くなった男。その遺書を持ち帰る話。シベリア抑留についてはもちろん、戦争経験者が高齢化し記憶の風化する今日、貴重なノンフィクションであろう。 故国に家族に思いを馳せながら亡くなった人々の存在も他の戦争記憶と共に残しておきたい。国がしっかりしないと、その前提として国民が正しい判断をできる日本でないと、起こりうる悲劇。 家族や仲間との絆に感動する作品。何度も読み返してみたい。
0投稿日: 2021.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1945年の敗戦によりソ連によって捕らえられた日本兵の記録。シベリア抑留により収容所という過酷な環境で日々厳しい労働をして暮らす多くの日本人。そこで帰国(ダモイ)の実現を信じている山本幡男氏が中心に書かれる。衝撃的なのはやはり山本さんの遺書の内容を多くの仲間が各パートに分けて暗記し、遺族に伝えたところ。メモ類はスパイ行為の防止のため、収容所内などでは没収されてしまう。そこで安全な方法である暗記になるのはわかるが、ちょっと驚く。 日本が「もはや戦後ではない」と謳っているときに、シベリアから帰った人々がいた。戦争は終わっても、その影響は多くの人のその後の人生に重く長くのしかかる…と思う。
0投稿日: 2021.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ■あまり知られていないシベリア抑留者の実態、日本人だからこそ生まれた美しい実話■ まずソ連での俘虜生活の過酷さ、日本人の処遇の理不尽さに強い憤りを感じる。 抑留者は使い捨ての労働力、奴隷、あるいは共産主義に都合のいい道具として扱われた。終戦間際に南下参戦、日本人を捕虜として確保して以降、戦後10年以上にわたりである。 なぜこのようは非人道的な行為が許されるのか。なぜ日本は声を上げないのか。なぜ国際社会はこの蛮行を問題視しないのか。 戦勝国に意図的に植え付けられた自虐史観に悪乗りし、あることないことでっち上げたり、国民をあおって解決済みの問題を蒸し返して賠償請求したり、我が物顔で領土主張を繰り広げる国があるというのに。 それはさておき、本書の主題は山本幡男氏と彼の周囲の日本人の生きざまだ。 およそ人間が生活するに値しない環境にあっても、常にダモイ(帰還)への希望を捨てず、日本にいる家族のことを思い、俳句や短歌をとおして仲間と交流を続けることにより、あくまでも人間として生き、あるいは死んでいった。 こんなにも強く、思いやりにあふれた人たちと同じ民族であること、僕の中にも彼らと同種・同族の血が流れていることを誇らしく感じる。 今日この遺書が現存し、僕たちがそれを読むことができるのは俘虜が日本人であったからだと確信する。
0投稿日: 2021.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ極限の環境で、人としての尊厳を保ちながら生き抜いた。そして子供たちへの遺書のなんと素晴らしいこと。生きていくうえでの本当に大事なことは、いつの時代にも普遍だと思われる。 それも、命の危険を顧みずに届けた人たちがあったからこそ。 こんな人生が本当にあるのだと、心が震えるほどの感動だった。
0投稿日: 2020.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第二次大戦終戦後、俘虜(捕虜)として、収容所で強制労働を強いられた日本人達を描くノンフィクション小説。登場するご本人たちへの取材を行い、書かれた本だ。 戦争を知らない、ましてや捕虜になどなったことがない。 私は、この物語を通じて何を想うか。 語ることなど決して出来ようもない。 今はこの本から、知ることだけで精一杯だ。 山本さんの放つ生命力。国へ帰ることを決して諦めず、囚われの身ながらも前向きに生きた男だ。 最後に彼は、病のために生きて日本へ帰ることが、叶わないことを悟り、家族へ遺書を残す。 厳しい検閲を潜るために、遺書は複数の有志に託され、記憶として日本へ持ち帰られる。山本さんを慕った男達は、山本さんの妻モミジさんに、各々の方法で遺書を送る。こうして戦争の時代から、新しい時代へと一歩踏み出していった。 読了。
21投稿日: 2020.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ終わりの見えない過酷な収容生活の中、帰国への希望を持ち続け、周囲に生きる希望を与えた山本幡男。 ともに過ごした仲間たちが記憶として持ち帰った6通の遺書が、遺族へ届けられるまでを描いたノンフィクションです。
1投稿日: 2020.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次大戦が終わった後、ソ連・シベリアの収容所(ラーゲリ)に抑留された日本人は、約60万人とされている。その内の7万人の方々が、抑留中に、彼の地で亡くなられている。日ソ間に国交が成立し、抑留者の最後の方々が帰国し、舞鶴港に到着されたのは、1956年の12月のこと。1945年の敗戦から11年が経過し、この年の経済白書は、高度成長期の始まりを迎えた日本を、「もはや戦後ではない」と高らかに謳った。 抑留者の中に、抑留中の1954年8月に病気で亡くなられた、山本幡男さんという方がおられた。山本さんは、抑留者の中での人望も篤い人物であったが、無念にも、帰国が叶う前にラーゲリで亡くなることになられた。もう長くは保たないと悟った仲間から、遺書を書くことを勧められた山本さんは、末期の癌の苦しみの中、奥様、母親、子供たち、そして山本家全体に対して、の4通の遺書を一晩で書き上げる。 収容所内では、日本語の書き物は禁止されている。遺書は、見つかると有無を言わさず没収されるため、収容所の仲間が暗記をする。そして、暗記された遺書は、無事にご家族のもとに届けられた。 収容所は、酷寒、過酷な労働、栄養不足、といった過酷な環境下にある。 そのような過酷な環境の中ですら、人間らしく生きた山本さんの生き方に勇気をもらえる。希望を失わず、前向きに、かつ、他者への配慮と思いやりと優しさを持ち続けることが、どれほどのことか、と畏敬の念を覚える。 そんな山本さんの遺書を、暗記し、実際にご家族のもとに届ける、仲間の友情にも胸を打たれた。 山本さんは、収容所の中で、「アムール句会」という、俳句の会を設立し、自ら、指導をされる。また、ご本人は詩作もされる。 本文中には、収容所で編まれた、俳句や詩が多く紹介される。俳句や詩を創ることが、こういった過酷な条件下で、創り手にどれだけの人間らしさを与えられるものか、また、過酷な条件下で、短字数の作品が、どれだけ、研ぎ澄まされたものになるのか、ということについても、改めて教えられた。
10投稿日: 2020.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログもう何回読み返しただろうか。 著者があの角川書店を盛り上げた角川春樹だと後で知った。 シベリア抑留がどんなに過酷なものだったか、捕虜を酷使して開発を続けたスターリン下のソ連のこともきちんと描かれている。
1投稿日: 2020.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
シベリア抑留、ひとつの事実として知ってはいたが、きちんと知ろうとしたことがなかったので、読んでみた。 寒さと飢えと労働と、信じられないほどの苛酷さ。 その中で、希望を捨てず、仲間と集う機会を設け、句を詠み励まし続ける山本幡男という人物。 「ぼくはね、自殺なんて考えたことありませんよ。こんな楽しい世の中なのになんで自分から死ななきゃならんのですか。生きておれば、かならず楽しいことがたくさんあるよ」 ラーゲリの中にいながら「こんな楽しい世の中」とは。 つらいシベリアの生活の中で、それでも「空の青さ」を見出す。 いろんなことを諦めるしかないのかな、と思いたくなる社会だが、こんなことくらいで希望を捨ててはいかんな、と思った。 シベリアに比べれば、ということではなく、山本さんの、それでも世界を信じる強さに、心打たれたからだ。 シベリア抑留者は約57.5万人、死者は6万人弱。ほんの75年前の話。
5投稿日: 2019.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留中に亡くなったある男。 彼の「遺書」を、思いがけない方法で持ち帰った男たちがいた。 主人公は、生きるか死ぬかの過酷な収容所生活にあって、人間らしい感情を忘れなかったある人物である。密かに句会を開き、多くの仲間に慕われた。 「必ず生きて帰国できる」と、仲間を励まし続けた彼は、異国の地で果てることとなった。そんな彼の最後の思いがこもった遺書を、彼を慕う仲間たちがいかに苦心して持ち帰ったか。 過酷な収容所生活が身に迫ってくるような作品である。 「抑留者」と一口に語られるが、そこにはそれぞれの苦しみ、希望と絶望の繰り返しがある。そうした人々の苦難の年月があって、わたしたちの現在がある。
1投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
抑留中に亡くなった山本幡男氏を軸にした話。ロシア語が使え、共産党思想シンパの彼がなぜ抑留されたのか。句会や文芸活動などによってどのようにほかの抑留者を元気づけたのか。いまわの際で彼は日本にいる家族たちにどのような遺言を遺し、それをどのようにして仲間たちが持ち帰ったのかが語られる。うまくまとめてあるが、シベリア抑留とは何か。それを知りたくて読んだため、泣きの描写が邪魔に感じた。
0投稿日: 2018.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリアに長期にわたって抑留されたある日本人のノンフィクション。想像を絶する苦難の中、ダモイ(帰国)に望みをかけて生きていく人々、その逞しさ、悲惨さが胸を打つ。 国は何とかもっと早く救い出すことが出来なかったのか、全員の帰還が日ソ共同宣言まで時間がかかったことが悲しい。 帰国叶わず無念の中で書いた魂の遺書に心が震えた。日本人が戦後を謳歌していた中でこのような境遇の人がいたということを心に留めておくべきだと思う。
3投稿日: 2018.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ収容所で亡くなった人の遺書を日本に帰るまでの2年半以上、分担してそらんじて、遺族に、妻に届ける物語。 事実は小説より奇なり、と思わずにはいられません。
1投稿日: 2018.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋で見て惹かれ読んでみる。終戦後ソ連の収容所で強制労働させられていた日本人の話は他の本でも何回か読んでおり、最初は「そう言う話か、俳句の力は素晴らしいな」くらいな思いで読んでいたが「収容所から来た遺書」につながっていくとは。 俳句を通して皆を勇気づけてくれた山本幡男が遺書を残し死去し、仲間たちが(ソ連の監視に見つかると廃棄、処罰させられる中)分担し暗記したり遺書を隠したりして、日本に持ち帰り山本氏の家族に伝えた話。結局伝えられたのは戦後12年にもなった後であった。 リスクを犯してまで何人もの人が協力しようと思う、山本氏の人柄に心動かされる。皆に勇気付けする事の大切さ。 今に置き換えるとどうだろうか、何もなければやはり俳句・詩は頭と感じる心が有ればできるので、有用か。 私が空で(準備なし、材料なし)でできる勉強会は何があるだろうか。
0投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログシベリア抑留に関わるノンフィクションの傑作。 この本を読んで驚き、勇気づけられたことがある。 それは、文学、芸術が持つ底力だ。 今まで自分は、文学や芸術は、人間にとって、余暇、余剰を楽しむものとしての役割が中心と考えていた。 しかし、この本を読んでその考えを改めた。人間の尊厳(自らを信じ、生きていける事、他人を信じる事)が崩壊しそうな時に、文学がその尊厳を回復することをできる。非常に重要な役割を果たせる。 東日本大震災の際も、芸術に関わる方々が「自分たちは、このような大きな危機の状況に無力である」とショックを受けた発言を多々していた記憶がある。 その中で復興地に行き、芸術家が、例えば演奏すること、話をしにいくこと、映画をとることなど、現地の人たちと交流することで、現地の人々の心の支えになることができるということを感じていた。この本に描かれる話も方向性は同じ。そして、もっと深く、究極に切実な役割を文学(芸術)が果たしている。 シベリア抑留、収容所への収監。その期間は敗戦後12年間にも及んだ。日本では「もはや戦後ではない」と言われ、復興が進む中、シベリアに留めおかれた方々の壮絶な状況に絶句する。 物理的にも精神的にも過酷な環境。現代からは想像すらできない戦争が続いているような異常な環境が続いている。 シベリアの生活は、未来も見えなく、いつ死ぬかわからないような過酷な労働、常に栄養失調の中、人権も無視され、日本人内でも密告等でお互いを信頼することができない。 そのような極限状態の中、主人公は隠れて、俳句会を作り、収容所内の希望を生み出していく。 ソビエトから抑圧され精神的にも極限に追い込まれる中、俳句を媒介にして、自分たちのアイデンティティを確立する。(自分だけではなく、「自分たち」という連帯感、共同意識までもてる) 俳句、または短歌は、日本人の生活の中に息づき、長い年月(その時代ごとの過酷な状況)に耐えて、生き残っている。それは単なる芸術ではなく、「=生きる」事だからなのだと思う。 俳句の力は、 自分の感じたこと、状況を様々な視点で見れることであり、自分の属す世界への対し方が広がること。 少ない文字の中、行間を想像することで、自分の感じていること、他人の感じていることを、想像し理解できるということ。 であり、過酷な人生において、生きていくことにポジティブな意識を持ち、自己肯定するために役立つ。 俳句の力を最大限に発揮し、生きる希望にまで昇華できたのは、主人公「山本幡男」によるところが大きい。 山本は、どんなに過酷な状況であっても、ダモイ(帰国)を信じ続けたし、日本に帰って家族と再会することを信じていた。もともと楽観的な性格というのもあるが、信念があること、人間を信じるということができていた。 だからこそ、俳句を使って、周りの人間を理解できるように、未来を信じられるように、できていったのだろう。 抑留当時のソ連からの扱い、今から想像もできないような状況であり、家族が無事かもわからずに、必死に離ればなれで生き続けないといけない。生半可な苦労ではない。 ようやくやりとりできた手紙もソ連の検閲に合うため、正直に書けないことも多い。制限のある状況であっても、交流手段は間接的な文章での交流にならざるを得ない。 遺書は、最後の魂の交流として書かれたものであるからこそ、その無念さと、本当に伝えたかったこと、未来のある家族への、想いの深さに感動をする。 人間が、大きな社会のうねりに、政治に翻弄され、戦争の犠牲になること。人間の集団性の恐ろしさ。 一人の命がいかにちっぽけで、儚いか。 その中で、希望をもち、人、未来を信じることの、輝き 。 この本は、そのことをドラマチックにあおるのでもなく、主人公に寄り添うように、誠実に描きだしていく。
11投稿日: 2018.04.01
