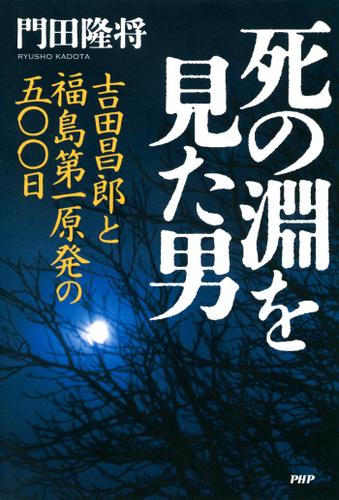
総合評価
(186件)| 104 | ||
| 53 | ||
| 14 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログあのとき、あの場所で何が起こっていたのか。 フクシマ50を見てから読みました。 当時のことはよく覚えているけれど、あの爆発の元、必死に事態収束のために命をかけていた人がいたことを知らなかった。 というか、自分自身も平和ボケをしていて、今の日本で、まさか放射線の危険がある中で作業をするまい、という思い込みがあった。 じつは、このときの福島原発はほんとうにやばかった。すでに起こったことそのものが、やばいのだが、あと少しのところで、避難区域は東京まで及び、日本は分断、首都圏が機能しなくなり、数年は経済的混乱が起こるとされていたらしい。 なんだかわからないけど、最後はうまく行ったのだが、人ができることが、冷却くらいしかないってことが恐ろしい。 自分も仕事となったら、この場に命を預けられるだろうか。 このとき、現場では東電の人々が命懸けで作業をしていて、その詳細を詳らかにしていくのが本書である。 吉田昌郎の人柄も興味深く、なかなかドラマチックにまとめられているので、読みやすい。 映画、ドラマの原作にもなった本書でしか知れない事実もある。 よく、事故は人災というが、最後には安全より利益追求に傾いたトップの判断をしてきする記述もある。
2投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ門田隆将さん著「死の淵を見た男」 3.11東日本大震災、福島第一原発が舞台。そこで生死をかけて原発事故を凌いだ東電の社員さん達のノンフィクション。 当時、14年前になるが自分は東京にいた。 15時Openの自分の経営する居酒屋の仕込み中で、営業開始前の慌ただしさの最中にあの地震が起きた。東京は大混乱に襲われ電話は繋がらず、その後電車も止まり帰宅困難者が溢れかえった。明日からの日常はどうなるのか?という不安が凄かった。 テレビでも再三津波の被害の映像が流れていて、翌日からは福島第一原発の映像が頻繁に流れていた。 その当時、原発事故の恐ろしさを知らなかった自分は調べれば調べるほど恐怖に駆られた。 はっきりと覚えているが、当時東京都知事だった石原慎太郎さんの有名な「天罰」発言、あれは自分に言われた言葉だと今でも思っている。石原慎太郎さんのその発言は都知事としての言葉として不適切だ、亡くなった人の事を考えて物を言え、とメディアから散々叩かれていたが、自分はあれで目が覚めた。 「なめてた」という言葉がピッタリと当てはまるくらい、あんな大震災が来るとは全く想像しないで暮らしていたのだから。 それから政治に関心を強く持つようになったし、震災天災には人一倍意識して気を付けるようになった。 自分自身の意識のきっかけにもなった東日本大震災。その時の福島第一原発。吉田所長をはじめ東電社員さんの方々の正に命がけでの復旧作業が描かれている。 凄まじい… なんて表現したらいいのか?言葉が見当たらない。 確実に言える事は生死をかけて原発の暴走を止めてくれた方々がいるから今でも自分達国民は生活できているのだということ。 逆にもし被害が拡大していたならば、東京は首都機能を失い、人口の半分くらいの人々が被曝し、東北及び関東圏は放射能汚染地帯となり誰も住めない土地になってしまっていたのだと思うとゾッとする。 自分達の現在と未来を東電の社員さん達が守ってくれたのだと…感謝しかない。 この作品、いくつものエピソードが描かれているのだが、描かれる方々の誰もが命懸けだからこそ心を震わされるし、目元が熱くなってくる。 14年の月日が流れ、被災地の復興もだいぶ進み経済の安定もある。だからといって過去の惨劇とは絶対に言ってはいけない。 多くの方々が命をおとし、多くの方々がその悲しみを胸に生きているのだから。 その中でこの作品に描かれた方々がいたことも同時に知っておくべきだと思う。 地震大国日本、またいつか南海トラフ、他のアウターライズ地震、群発、富士山噴火、色々と想定できるがその都度自分にできる最良で最大の貢献を心がけていきたい、吉田所長みたいに東電の社員さん達みたいに。
113投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011.3.11の日に福島第一原発では何が起こっていたか、詳細な内容が書かれていた。 震災から10年以上が経ち初めて知る内容であった。 東電の社員、自衛隊、消防士の方々は命懸けで日本を救ってくれた。いま、日本が、、東北が住める状態なのは、極限の精神状態の中、命懸けで頑張ってくれていた東電の職員や協力会社の人それぞれの勇気ある行動考えのお陰という事が分かる内容の本であった。 いろいろな立場の人の視点でストーリーが書かれていて、それが想像出来る内容であった。 読んでいて何度も胸が熱くなった❗️
2投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
▽何度も死を覚悟した福島第一原子力発電所所長【吉田昌郎 よしだ まさお】氏。▽我を忘れた“イラ菅”こと【菅直人】氏。▽2011.3.11の大津波による原発事故は、自然に対する「侮り」「驕り」が危機管理の甘さを露呈。▽「全電源喪失」「冷却不能」の事態に対処すべき安全指針の改定を見送っていた原子力安全員会の怠慢。▽世界唯一の被爆国でありながら、「原子力」に対する「畏れのなさ」と無責任なリ-ダ-たちの存在。
7投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログあのときの現場の人達が何を考えてどう行動したのか 文字通り命懸けで闘ってくれたことが分かった ただただ感謝 以下メモ 地震の揺れを感じている時にスクラム(欣喜停止)すると直感をした 実際に揺れのあとすぐスクラムした ちゃんとスクラムして逆に安心した 地震による停電で電源がなくなってしまった しかし 非常用電源があったので活用した そういう場合の訓練は頻繁に行っていたので 落ち着いて対応できた 非常用電源は海抜10m のところにあった 10m あれば絶対大丈夫と思われていた なぜなら 過去1000年以上 そんな大津波が来たことはなかったから しかし 津波はそこに来て なんと非常用電源もなくなってしまった 電源が全てなくなってしまって何もわからなくなってしまった 圧力などの監視システムが全て使えなくなってしまった 原子炉をとにかく冷やす必要がある 電源がないので水を直接入れて冷やす必要がある 消防車のホースを使うことを考えてすぐに消防車を手配した そして水を入れられるように弁を開けた すぐに この判断ができたことがとても良かった なぜかと言うと 数時間後には人間が近づくことができないレベルの線量なったので 格納機の圧力がどんどん高くなっていった 爆発してしまうので軽く ガス抜きをすること つまりベントをすることが必要になった ベントするために 原子炉に向かったが 線量計が振り切れてしまった その辺りで水素爆発が起きた そんなこんなでただでさえ 忙しいのになぜか 菅総理が現場に来ることになって説明しなくてはいけなくてさらに大変になってしまった さらに 官邸からなぜか海水注入を中止しろと言われた 塩が残る などの影響がありリスクがあるからだという しかし現場では冷やすためには 海水を入れるしか方法がないことが分かっていた なので 命令について分かったと言いつつ 実際には海水注入を続けることにした 現場の人は死ぬ覚悟で戦っているのになぜか 官邸には東電が撤退するつもりだと伝わってしまっている 伝言ゲームって怖い いよいよ 危なくなって現場の建物にいた 600人いたが そこから最低限の人数を残して退避することになった 幹部の人たち など50人ほどが残った そこで 悲壮感の雰囲気になると思いきや 意外と 和やかな雰囲気になった 死んではいけない人間がいなくなって死んでいい人間だけになったから 自衛隊の協力で遠くから 強力な消防車が来てくれて 水もたくさん来てくれてホースで水をたくさん入れて原子炉の 暴走を止めることができた もし 暴走してしまえば人間はもう近づくことができない なので福島原発は10個あるのでチェルノブイリ×10の被害がある そうなれば 東日本には人は住めなくなり人が住めるのは東北や 北海道 あとは 西日本になるはずだった 実はアメリカでは9.11のテロ 移行 原発が全電源停止することを想定したマニュアルを作った それは日本にも伝えられたのだが 日本ではテロは起きないと考えられ そのマニュアルは整備されなかった 原子力安全委員会は30分以上の長時間の全電源喪失について考慮する必要はない という指針を取っていた
1投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時の現場状況がよく分かリました。 筆者が指摘している慢心、日々の仕事でも教訓としたいと思いました。
0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなことがあったなんて。 想定外で済ませてしまうけど、原発は一度事故を起こしたら、国が滅ぶかもしれない。 こんなのはやめなくてはいけない。
0投稿日: 2024.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログフォローしてる方のお勧めで。Netflixでもやってるドラマの原作。 ただ、ここに描かれてるのは事実、とてつもなく重い事実と言う事で読み進めるのが怖くなる程。 放射能との戦いだけでなく、無策な政府、東電の幹部、、、命を賭して福島を守った男達に感謝。
10投稿日: 2023.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログあの時あの場所にいた人達留まった人達そして向かった人達。その覚悟と決意にただただ頭を下げるしかない。 何も知らずに電気を空気のように使う毎日。彼等の努力があってこそのこの毎日なのだと痛感した。ならばせめて福島の復興に役立つことがしたいと素直に思う。私にできることは微々たることだが…しないよりは私自身が救われる。 現場の話とは別にこの国の行き当たりばったり、採算性だけを考えて突き進んできた原発事業というものはおかしいと考えざるおえない。原発というものがどういうものなのか、一度暴走が始まったらどうなるのか、今も続く処理水などの問題。エネルギーを得たいという巨大な欲望は飽くことをしらない。私自身今電気がなくなったらと思うとどうしようもない不安しかない。どうしたらこの欲望と折り合い安全なエネルギーを生み出せる方向に向かえるのだろうか。
1投稿日: 2023.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずもがなですが、フクシマ50の原作。 映画を見たことがあったけど改めて手に取る。 映画では知り得なかった事実が色々あり、まさに人間の究極の状況における葛藤などの中、揺るぎなき信念で、たまたま私たちは救われたのだと思いました。 吉田所長をはじめ、みなさまの働きに 感動するとともに深く感謝いたします。
1投稿日: 2023.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログとても小説に入り込んで、引き込まれて読みました。特に最終部分の原発にて津波で亡くなられたご家族のお話には涙が出ました。門田さんは本当によく取材されてれいると思う。あの時福島原発で何が起きていたか。必死で原発を守った方々の勇姿が描かれている。 それにしても、政府の対応は良くなかっただろう。
1投稿日: 2023.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画「Fukushima 50」がなかなか興味深かったので、その原作である本書を読んでみました。 ちゃんと確認できていないのですが、本書の中での原子炉内の圧力の値(キロパスカル単位での表記)は、おそらくすべて間違っていると思いますので(正しくは、もう1桁大きい値になると思います)、原子炉内の圧力については「設計圧力の○○倍」といった記述のみを拾えばよいと思います。 上記の数値の件からも推察できると思うのですが、理系的な観点からは物足りない部分がありますし、この本の内容のすべてが真実だとは限らないものの、東北地方太平洋沖地震により、福島第一原発でどのようなことが起こっていたか(起こった現象とその対応など)を知るには、よい本だと思います。 当時の福島第一原発での出来事を美談にするのは問題だと思いますが、その一方で、吉田昌郎をはじめとして、命がけで対応に当たってくださった方が何人もいたことも事実。 本書は、今後の原発のあり方を考える上では、貴重な資料になりうるかもしれませんし、日本人としては、これぐらいは知っておいた方がよいかも、と思いました。 また、この本を読んで、スリーマイルとチェルノブイリについても、もっと知っておくべきだと反省しました。
1投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ好きな俳優の佐藤浩市さんと渡辺謙さんの共演で映画化されることになったと知り、この本を手に取りました。福島第一原発事故の事は、テレビや新聞などで報道されるような事しか知らなかったので、本当に衝撃的でした。現場で対処されてた方々の命懸けの行動には頭が下がります。自分の命を懸けてでも、家族を、福島を、そしてこの日本という国を守るという強い気持ちと勇気ある行動は、大平洋戦争の前線で戦ってくれた先人方と重なりました。最初から最後まで、ずっと涙・涙の読了でした。映画館でも号泣しそうです。
2投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災後に起こった大津波によって福島第一原発は危機に直面した。チェルノブイリの10倍の大事故に発展する恐れのあった原子力のメルトダウンを可能な限り事故を最小化しようとした人たちの生死をかけた仕事ぶり。生きているということは、人は何かに生かされていくこと、何かに引き寄せられるように生きていくこと、その中で自分の志を立て、次の世代にバトンを渡していくのだと思います。
1投稿日: 2022.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故で、北海道と西日本しか人が住めなくなる事態になるということが、最悪の事態としてあったということをはじめて知った。震災後アメリカが日本はもう終わりだと言ったらしいが宜なるかな。 当時は東京電力の本社の対応の遅さに不信感を覚えていたけど、現場の社員や協力企業の方々、自衛隊員の方々の決死の対応によって、何度も危機を乗り越えられたことを知りました。 大和魂はまだ日本人のDNAに組み込まれているのかな?命を賭けて闘った社員さんたちに敬意を表します。 日本もまだまだ捨てたものではないですね。 簡易便所の便器がずっと血尿で赤く染まっていたというのが印象的だった。 引き込まれて一気に読んでしまった。著者の文章力が巧みかつ読みやすいので、比較的楽に読めると思います。 他の著作も読んでみたくなりました。 オススメです。
2投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発に関する報道で、東京電力のイメージはあまりよくありませんでしたが、前線の社員の方々は、血尿が出るような極限の状態で、死の恐怖と戦いながら、事故を最小限に食い止めようとしていたことを初めて知りました。 その方々の頑張りがないと最悪、青森を除いた東北と関東の全部、新潟の一部という莫大な範囲が避難対象になる可能性があったと知り、そこまで深刻だったのかと、今更ながら、背筋が凍る思いでした。
3投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災の時の福島第一原発の様子を所長への取材を通して描く話です。次から次へと困難が襲うなか、命懸けで闘った人々の感動のドキュメンタリーです。オススメ!
4投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ慢心、安全対策の節約 起こらないだろう でも起こってしまった 誘致で街は栄え立ち入り禁止となった まだ終わっていない 大きい犠牲と損失 美談ではない
1投稿日: 2021.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ最悪の場合 日本は"三分割"されていたかもしれない。 汚染によって住めなくなった地域と それ以外の北海道や西日本の三つ。 日本はあの時、三つに分かれるぎりぎりの状態だったのかもしれない。 そんな最悪な事態さえ招きかねなかった原発を未だ利用し続けるのか。 映画「Fukushima 50」の原作本。
1投稿日: 2021.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画「FUKUSHIMA 50」を見たので、ノンフィクションのこの本も読んでみる。改めて衝撃だし、こんな事態に命を懸けて立ち向かった皆さんに改めて頭が下がる。しかし、この教訓、絶対に生かされてない国だよな。たとえ30mの堤防があっても絶対に安全なんてことはないし、いつテロの対象にされるかは分からない。過去は変えようがないが、未来は変えられるんだけどなあ・・・
1投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあの時現地で何が起きてきたのか。 地震、津波、そして原子力を前に、いかに人間がちっぽけな存在かを痛感。 一方で、絶望的な状況下で懸命に働く人々の姿に人間の持つ可能性を感じる。仲間との絆や家族への想い、強烈な使命感には、大きく心を揺さぶられる。 あの事故を風化させないためにも、ぜひ読むべき一冊。
1投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクションをちゃんと読むのは初めてだった。自分が小学生の時、故郷、日本を守るために命をかけて闘っていた人たちがいたという事実に気付かされた。原発に関して素人でも読みやすい本だった。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログすでに231人もの方々から感想が書かれている事に現れている通り、私にとっても衝撃の内容でした。 上梓から年月も経っていますが1人でも多くの方に手にとっていただきたい本でした。 著者に、取材に協力された方々に、あの当時懸命に取り組んでくれた方々に感謝申し上げます。
1投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
来年2021年は東日本大震災から10年。節目の年を前に原発事故の本を読んでみた。当時の状況はテレビ、新聞で見ていましたがこの本を読んで全然分かってなかったなと感じた。東電の若い社員が二人お亡くなりになった事。その二人に酷い誹謗中傷があったこと。東電の社長が言葉足らずに政府に状況に伝えた為緊急会議が開かれたこと。そもそも政府が良く東電に聴けよとか思い馬鹿馬鹿しいとすら思った。又菅首相の東電への心無い発言。現場で懸命に作業している東電社員の心が折れそうになるかと思う。迷惑このうえない電撃訪問。その結果東電や他の人が被爆したかもしれないこと。それに引き換え吉田所長をはじめとして自衛隊や名もない人々の献身的な作業本当に現場の人々のお陰で今平和な暮らしができているのだと頭が下がる。 これを教訓にしてテロと自然災害に対応できる原発になっているのか? それについての議論が国会で行われたのか? 行われていないのであれば亡くなられた方に申し訳なく思ってしまう。
2投稿日: 2020.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間が経ったので改めて。 本当にギリギリの状態だったんだなと。現場の皆さんには敬意を表したい。 でも、その一方で津波のリスクについては指摘が事前にあったことも知られている。 私は反原発ではないけれど、どうすればこの事態を回避できたのか、検証がきちんと終わっているのかが気になる。全てを稼働停止にして蓋をするのは、なんだか違うよなと。
0投稿日: 2020.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ衝撃・絶望・感動の作品。 東日本大震災により福島第一原発で何が起きていたのか、現場で起こっていたことを生々しく描くノンフィクション。 今まで日本がここまでの危機に瀕していたことを認識出来ていなかった。そして果敢に命を賭して対応した吉田所長以下の現場の人々に焦点を当てた物語に感動。 放射線量が上昇する中、電気が途絶えた中央制御室に踏みとどまった人達。最後の際まで「死」と隣り合わせで踏ん張った人達。 現場で自らの使命の元、仕事を全うする人々。 それと対比して、官邸、東電幹部のやり取りの虚しさ。十分な意思疎通がなされないまま、菅首相の現場に投げかけた残念な言葉。その言葉を振り返ったコメントもあるが、謙虚さと慎重さがあまりにも足りないように感じた。それ故の現場の空虚感と怒りであったように思う。 専門家でない官邸の判断の難しさはよく分かるが、本書に触れられている不測の事態に対する対応についての議論が圧倒的に足りていなかったことは重要な問題であるように感じた。失敗から学ぶべきことは多い。 そして意外なのが、最後の最後に残った人々は死ぬと思って残ってるわけじゃなくて、やることがあるから残っていた、と言う。過酷な環境下で黙々とやらなければならないことをやる。静かな闘志のようなものを感じた。 また津波で亡くなった若手二人に対する心無い情報の拡散に関する話があるが、無知であることの罪深さを思い知らされる。 それに対して彼らの仲間達が壮絶な事実をキチンと両親に伝え、仲間として仕事と責任を全うする姿勢に胸を打たれる。 日本を救ってくれてありがとうございます。 未来に負債を残し、今を生きる仕組み から、SDGs、持続可能な社会を作ることの重要性を強く感じた。
15投稿日: 2020.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容紹介 (Amazonより) その時、日本は“三分割"されるところだった――。 「原子炉が最大の危機を迎えたあの時、私は自分と一緒に“死んでくれる"人間の顔を思い浮かべていました」。食道癌の手術を受け、その後、脳内出血で倒れることになる吉田昌郎・福島第一原発所長(当時)は、事故から1年4か月を経て、ついに沈黙を破った。覚悟の証言をおこなった吉田前所長に続いて、現場の運転員たちは堰を切ったように真実を語り始めた。 2011年3月、暴走する原子炉。現場の人間はその時、「死の淵」に立った。それは同時に、故郷福島と日本という国の「死の淵」でもあった。このままでは故郷は壊滅し、日本は「三分割」される。 使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した男たちは、なぜ電源が喪失した放射能汚染の暗闇の中へ突入しつづけることができたのか。 「死」を覚悟した極限の場面に表われる人間の弱さと強さ、復旧への現場の執念が呼び込む「奇跡」ともいえる幸運、首相官邸の驚くべき真実……。吉田昌郎、菅直人、班目春樹、フクシマ・フィフティ、自衛隊、地元の人々など、90名以上が赤裸々に語った驚愕の真実とは。 あの時、何が起き、何を思い、人々はどう闘ったのか。ヴェールに包まれたあの未曾有の大事故を当事者たちの実名で綴った渾身のノンフィクションがついに発刊――。 関西に住んでいるせいか 同じ日本なのに遠いところの事のように当時は考えていたと思います。 この本を読んで 知らなかったことがたくさんあり 今こうしていられるのは この方達のおかげもあるのだなぁとつくつく感じました。
12投稿日: 2020.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田所長以下福島第一原発の現場でまさしく死を覚悟して最悪の事態(格納容器爆発して放射性物質飛散で北海道、西日本以外居住不可)に陥るのをギリギリのところで食い止めた東電社員、協力業者、自衛隊の人達の知られざる激闘の様子が、本人達の証言を基に時系列で語られていく。不眠不休の対応が続く地震から4日目の3月15日、遂に吉田所長から「各班は、最少人数を残して退避!」の指示が出される。最少人数とは?何の基準も無い中、思い浮かぶ家族や故郷と自らの役割との間で残るべきか退避するか、一人一人が壮絶な葛藤を強いられた筈。残った69人。海外ではこの人達をFUKUSHIMA50と呼んで称賛されていた事を映画「FUKUSHIMA 50」観て初めて知ったけど、この69人に限らない現場の人達の献身の実態はもっと知らしむべきと感じる。
2投稿日: 2020.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ菅元総理が現地に行って批判されたり東電幹部が無能な事や福島原発の所長以下現場社員が頑張っていた事は記憶があるけど、福島のみならず東日本全体が危機に陥っていた事はあまり知られていない。 福島の方には気の毒だけど、よくそれだけで済んだのは東電の現場社員たちのお陰だと思います。
0投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画「FUKUSHIMA50」を見て、その原作を読みたくなりました。 読みながら、映画のシーンと当時のニュース映像が頭の中を駆け巡り、あっという間に読み終えていました。 取材力に感嘆です。
0投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発で震災時にどんなことが起きていたか。想像を越えた極限状態で闘っていた人たちの姿を時系列で教えてくれる。 著者が最後に述べているように、911とスマトラ津波で安全性の見直しをするチャンスを逃したのは大きな悲劇。電源喪失や冷却不能を想定して対策を講じる必要性が明確なのは、後付けの理論などではないように感じる。 ミサイル攻撃やドローンテロなど、想定されるものを全ての対策を講じて始めて原子力のパワーに頼ることができるものと確信させられる
0投稿日: 2020.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画公開を機に9年たった今、初めて読みました。 この本が出版されてから随分経ちました。 当時現場で頑張っていただいた方達のお陰で最悪の事態は、免れた。しかし今の福島原発の現状を考えると、とても複雑な心境になります。 そして今も現場で頑張っている人達が居る。
0投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ現場の方々には 何をやらねばいけないのか また 行うことの困難さについて 驚くほど的確にわかってらっしゃった ということに 私は驚きと尊敬を感じました
2投稿日: 2020.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
当時、私も神奈川近郊の工場で働いており、バスに乗車して出勤中であったが、バスごと揺れる体験をしたのは初めてだった。震源地からそれなりに距離がある場所でもあれだけの揺れが生じたのに、あの未曾有の被東日本大震災による東電の原発緊急停止の現場はまさに修羅場だったと思う。その中で陣頭指揮をとった人が吉田所長であったことはまさに不幸中の幸いだったんだなという事が実感できる本である。 もし格納容器爆発が起きていたら「チェルノブイリの10倍の放射能被曝」が生じ、関東含めた東日本一帯に人が住めなくなり、日本が三分割される可能性もあったということはこの本で初めて知った事実であるが、それを瀬戸際のところで命懸けで防いで頂いた吉田所長を筆頭とした東電の現場の方々には感謝と敬意で頭が上がらない。 現場の意見や状況をしっかり把握し、焦らず着実に情報伝達をするという事が危機対策の鉄則であるという事が改めて理解できるし、平時にもっと危機意識を持って、今後の災害・危機対策を検討しなければならない。 コロナウイルスもまさに世界中で危機的状況に陥っているが、新型インフルエンザの特措法はあったが新型(コロナ)ウイルスは法律上想定していなかった事を考えると、まだまだ危機意識が不足しているということなのだろう。
0投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故の、考えられうる最悪の事態の中で、現場はどう動き、どう闘ったのか。福島第一原発所長として最前線で指揮を執った吉田昌郎のもと、使命感と郷土愛に貫かれて壮絶に闘った人々の物語。 映画「Fukushima50」の試写会を観て興味を持ったので図書館で借りた。 映画よりさらにいろんなドラマがあった。
0投稿日: 2020.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発の3.11を書いたもの。 当時は毎日出てくる情報を探しながら、ハラハラしていたが、上辺の情報だけしか知らなかったなと改めて思う。 必死に最悪のケースを回避しようと、自らの生死を顧みずに奔走する現場と、情報伝達がまずく、イライラする上。 最悪のケースも有ったのだなと思うと共に、現場での奮闘は心を揺さぶる。日本を守ってくれた彼等に改めて感謝すると共に、この本を読めたことを良かったなと思う。
0投稿日: 2020.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画公開に備えて読む。本書を元に作られたNHKの特集なども見てみたが、それでさえ伝えきれないことが多々あったようだ。地理上日本はある程度の災害を受けざるを得ないのは分かるが、東條英機や村山、菅など能力に欠けた者が政権に就いた時、特に激しい厄災に見舞われるようである、選挙は慎重を期さねばならないことを肝に命じよう。そしてその厄災をリカバリーしてきたのは市井の名もなき人々であるのだ。現在でも菅がまだ存在していることに腹が立つ。文庫本版の後書には朝日新聞によるフェイクニュースの事も書かれており、本当に朝日と毎日は狂っている。
2投稿日: 2020.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時の報道がどれだけ曖昧なソースで垂れ流され、誤解を生じさ出ていたか。 常日頃から、言えることをきっちり発言する勇気が大事なんだと改めて考えさせられました。きっとこれからも乗り越えていけると思います。
0投稿日: 2020.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログその時、日本は“三分割"されるところだった――。 2011年3月、暴走する原子炉。 現場の人間はその時、「死の淵」に立った。 それは同時に、故郷福島と日本という国の「死の淵」でもあった。 このままでは故郷は壊滅し、日本は「三分割」される。 使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した男たちは、なぜ電源が喪失した放射能汚染の暗闇の中へ突入しつづけることができたのか。 あの時、何が起き、何を思い、人々はどう闘ったのか。 ヴェールに包まれたあの未曾有の大事故を当事者たちの実名で綴った渾身のノンフィクションがついに発刊――。 この事故を美化するにはいかがなものかと思うけれど。 真実を知らないと、語ることもできないとも思う。 「原子力とは何か」を学ぶ上で、避けては通れない事実。 読んで良かった。
0投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わって「あー面白かった」と思ったものの、全てが実際に起きた出来事ということを思い出し、冷や汗をかく。
0投稿日: 2019.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011年3月11日 東日本大震災に伴って起こった福島第一原発事故の500日,とりわけ,最初の1か月間の経過を,当時所長吉田昌郎氏を中心に克明に再現していく.おそらく丁寧な取材がされた結果なのだろう,関わった人たちの心の動きまでが描き出されていく.またそこには,事実を忠実に記録するだけでなく,取材対象となった遺族を含む人々への人間味あふれる視線を感じとることができる.
0投稿日: 2019.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ不安だった日々を思い出し、読むのがつらかった。 でも読んでよかったと思う。こんなに懸命に頑張ってくれた人たちのことを、知ることが出来て。 吉田所長は大きい人だな。
5投稿日: 2019.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2011.3.11東北地方を襲った巨大地震。 その後の津波により福島原発も大きな被害を受け機能が停止。 その後起こった爆発によりチェルノブイリ以来の放射能漏れ事故を引き起こした。 あの時何が起こっていたのか。 そこで人々は大切なモノを守るために何をしたのか。 緊迫した状況を描いたノンフィクション。 同じ時代を生きた日本人として読んで良かったと思える一冊でした。 説明 内容紹介 その時、日本は“三分割"されるところだった――。 「原子炉が最大の危機を迎えたあの時、私は自分と一緒に“死んでくれる"人間の顔を思い浮かべていました」。食道癌の手術を受け、その後、脳内出血で倒れることになる吉田昌郎・福島第一原発所長(当時)は、事故から1年4か月を経て、ついに沈黙を破った。覚悟の証言をおこなった吉田前所長に続いて、現場の運転員たちは堰を切ったように真実を語り始めた。 2011年3月、暴走する原子炉。現場の人間はその時、「死の淵」に立った。それは同時に、故郷福島と日本という国の「死の淵」でもあった。このままでは故郷は壊滅し、日本は「三分割」される。 使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した男たちは、なぜ電源が喪失した放射能汚染の暗闇の中へ突入しつづけることができたのか。 「死」を覚悟した極限の場面に表われる人間の弱さと強さ、復旧への現場の執念が呼び込む「奇跡」ともいえる幸運、首相官邸の驚くべき真実……。吉田昌郎、菅直人、班目春樹、フクシマ・フィフティ、自衛隊、地元の人々など、90名以上が赤裸々に語った驚愕の真実とは。 あの時、何が起き、何を思い、人々はどう闘ったのか。ヴェールに包まれたあの未曾有の大事故を当事者たちの実名で綴った渾身のノンフィクションがついに発刊――。 内容(「BOOK」データベースより) 吉田昌郎、菅直人、班目春樹…当事者たちが赤裸々に語った「原子力事故」驚愕の真実。
6投稿日: 2019.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい本です。改めて、ギリギリだったんだなぁ、、、と。ちょっと劇画っぽく描かれているきらいもありますが、凄まじいです。涙が出そうになりました。
2投稿日: 2019.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発は、雪に閉ざされる農閑期の出稼ぎ労働から、地域に雇用を生み出すために建設された。東日本大震災の津波が、全電源を喪失させ、原発事故へとつながる中、核燃料の暴走を止めようと全力を尽くす第一原発・吉田所長と地元で採用された男達。東電の原発運営に批判が集中した感があるが、現場の男達は命をかけて最悪の事態から日本を救ったのだ。それに引き換え国策として原子力発電を推し進めた政府は何をしたのか? 当時の総理大臣が頼まれもしないのに現地入りなどして、復旧の足を引っ張るだけの印象が……
0投稿日: 2019.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故当時、最前線で指揮を執った吉田昌郎所長や当直長を中心に、菅直人、斑目春樹など、当事者たちにインタビューしたノンフィクション。 今まで何冊もの原発事故関連の本を読んできたけれど、これが現場を一番表現されているものではないだろうか。 地震後の停電、通信手段の遮断の中で、吉田や当直長らは自らの経験から最善と思われる行動を次々ととっている。後に本店や官邸とやり取りができるようになってからも、対策を考えているのは現場。思考停止している本店とは対照的だ。彼らこそ「プロフェッショナル」だろう。 巻末の「おわりに」に、斑目委員長の会見の弁が記されている。 -原子力安全を確保できるかどうかは、結局のところ“人”だと痛感している 原発再稼働へ向けて、新しい安全基準に適合するかの審査が続けられている。 どんなに頑強なタッパを作ったところで、それを管理・運用するのは人間。そして、現場に優秀な人材が揃っていたとしても、当時のような災害時に、離れた所から的確な指示を出せる人材や環境があるのか。 火力発電で事故が起きた場合、燃料が燃え尽きればそれで終わる。けれど、原発ではそうはいかない。 原発は費用が安いと言われているけれど、果たしてそういった安全管理や、一旦事故が起こった際の補償を含めて、それでも安いと言えるのか? 電気に依存しきった生活を送る身としては、原発即廃止が難しいことも理解できる。 再稼働は致し方ないのなら、タッパも、現場も、バックアップする本店も、プロフェッショナルになってからにしてほしいものだ。
2投稿日: 2019.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
先日、福島第一原子力発電所の見学をする機会をいただきました。予習をしたいと思い、行きの電車と、いわき駅前のミスドで読みました。 感動しました。強く心を動かされました。 すべてを他人のせいにして逃げることもできる状況で、自分の命をかけて原子炉を制御しようと全力をかけた人たちには、ただただ頭が下がります。 一方で、人が命をかけないと守れないものを、世の中にあってよいのか?という大きな疑問が、自分の中でさらに大きくなりました。原子力発電所がこの世の中にある限り、考え続けなければならないことと思いました。
0投稿日: 2019.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の時、本を読んでいると自分の周りから音もなくなり、色も消え、完全にその世界に吸い寄せられていた事があった。 大人になると徐々にそいういう経験はなくなり、ページ数やまとめを頭の中で管理しながら本を読むようになった。 この本は、久しぶりに意識が完全に持って行かれた作品。 本の内容からすると甚だ不謹慎な表現になるけど、「ゾクゾクする程刺激的で面白い」。 ドキュメンタリーである事、そして史上最悪レベルの原発事故であった事を考えると、本書からなんらかの教訓を得ないといけないと思うのだけど、それを考える間もないぐらい、強引に襟首をつかまれて作品の中に引きずりこまれる。 311直後からの福島第一原発の現場作業員の攻防戦の記録。 タイトルからすると、もっと感傷的な内容かと思っていたけど、文体はとてもソリッドで、それが独得のリズムを生んでいて飽きさせない。 複雑な状況化で、なおかつ膨大な量の関係者が登場するのに、読者の視点が迷わないのが印象的 原因は ・基本的に吉田所長の視点で書かれている事 ・生死という根源的で単純な問題がテーマである事 だと思った。 特に物語のドライな感じは、多分に吉田所長の宗教観(高校生から物理学と同時に仏教にとても興味があった)によるものだと思われる。 震災から2年以上経過した今でも、この書籍で描かれている内容は断片的にしか知らなかった。 いや、知っていたとしても文字情報としてしか理解出来ていなかった。 もちろん、インタビューで構成された内容である以上、それぞれの人物の主観ではあるのだけど、少なくとも読んでいる限り、それぞれが受けた主観を正直に作者に語っている。 たぶん、ドキュメンタリーで大事な部分はそこだと思う。 真実を追うのではなく、個々の人物の主観を積み上げて真実の輪郭を追うのだ。 今はこれ以上の感想を書けないので、またいつか二回目を読んだ時に、もうちょっと踏み込んだ感想を書きます。
0投稿日: 2019.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログその時、東日本大震災の時、福島原発で何が起こったのか。東京電力の職員や、消防隊、自衛隊、政府(民主党菅代表)はどう考えどう動いたのか。 インタビューを基に書かれた話。本人の言葉をそのまま読むので緊迫した状況が伝わる。地震、津波で制御不能となった原発を、命がけで守った人々。 ここまでになって原発は本当に必要なのかと再度考えさせられる貴重な一冊。
0投稿日: 2018.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を手に取る前から、かなり東電寄りの内容であると聞いていた。 (amazonのレビューは、一見しただけでかなりキモい) 世論の趨勢を見れば、それはそれで意義のあること思っていた。 しかし、著者はかなり過剰にそのスタンスを表明し過ぎている。 死を賭した名もなき英雄たち、ハリウッド映画化すれば嵌りそうなプロットだ。 だが、ストーリーテラーは、手を緩めない。 ・「想定外」で済ませる加害者意識のなさ ・こっちこそ犠牲者視点 ・ついには宗教者的な人物にまで持ち上げられる吉田所長 ・そして、チェルノブイリ10倍規模に拡大して日本が3分割になるところをこの程度に留めてやったんだという恩着せがましさ…。 ・被災した地元住民に拍手で慰労され贖罪を終える伊沢宿直長 (福島の方は、こんなに度量があるだろうか) どうなのだろうか? 「マッチポンプ」が、そこまで言うのか!と結局反発してしまう一冊だった。 原発推進、津波対策放置、その果てに、事故後の有効策って、ひたすら水をかけただけ?(1号機のベント(?)は、その後に水素爆発) そして、現在の汚染水漏れとさらに問題は続いている。
0投稿日: 2018.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあの極限状態でどのような判断をしたのか?門田隆将著の壮絶なノンフィクション.自分だったらどうするかとは軽々に言えないが,多くの教訓を得なければいけない.
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災当時福島第一原発所長だった吉田氏の名前がサブタイトルに含まれているが、登場するのは吉田氏だけでなく、震災直後に現場で奮闘した東電職員のインタビューをもとに構成されている。現場にいた人たちが、津波で電源を失ったあと、どのようにして最悪の事態を回避しようとしていたかが臨場感を持って理解することができる。原発事故については、民主党の福山氏の著書や検証委員会の報告も読んだが、現場の内実を知るという意味では、段違いに理解を深められた。 原発内で津波の犠牲となった、当時21歳の東電職員のご両親のことばも掲載されていたのだが、いたたまれない気持ちになった。原発内にいるに違いないのに、行方不明になってから遺体が発見されるまでに何と3週間も要したとのことだった。そんなにタイムラグがあったことも今になって気づかされたのだが、発見されるまでの間に、行方不明の二人が「現場から逃げた」という心ない情報が流れたこともあったらしい。 以下は父親の言葉。 「ついには、テレビに出演している人が”そんなやつは、捕まえて吊し上げりゃいい”ということを言ったんですよ。私たちはなにも希望のない中にいて、生きて見つかったほうがいいに決まってます。でも、祥希が仕事を放棄して逃げるなんてことがあり得ないことは、親である私たちが一番わかっています。だから、そういう話はショックでした」
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故での現場対応を克明に記した貴重な本である。あの混乱する、かつ国家首相からの横槍が入る中で、最善の策を次々と打っていった吉田昌郎氏の手腕に感謝する。まだ避難されている方が大勢いらっしゃるけれど、吉田氏がいなければ、日本は今頃、全国民が海外避難をしなければならなかったと思う。
0投稿日: 2018.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
原発事故の中で、最悪の事態を防ぐべく抗った男達の熱い話。 でも何より人の思いやりや使命感に心を動かされました。
0投稿日: 2018.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ20180103 東日本大震災に関する本は何冊か読んできたが、福島第一発電所でその時何が起こり、誰が何をしていたのかが、克明に記録されていた。 著者の精力的な取材の賜物だ。 これを読むと東電の現場で命を懸けて働いた人たち、自衛隊の人達の使命感に圧倒される。 安易に東電を批判する事なんて出来なくなった。 そして何度か涙無しでは読めないところもあった。 いずれにせよ、命より経済を優先させる訳には行かない。原発は無くして行く事を前提としたエネルギー政策が必要とあらためて感じた。
0投稿日: 2018.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/3/11 札幌でも揺れを感じ、テレビでは津波の被害を放映していた。そんな状況の中、福島原発では数百名もの人間が、それこそ死の淵に立ち、必死に戦っていた。そんな人たちの気持ちを深く感じ、彼らが何のために戦っていたのか、読むほどの深く感謝した。 彼らは、故郷を守るため、日本を守るため、そして家族を守るために、生死をかけて暴れまくる原子炉を鎮めることを行ってきたのだ。 放射能という目に見えない恐怖と戦いながら・・・ 今後、このようなことが二度と起きないように、あらゆるリスクへの対応策と、そして短期間の廃炉を可能にできる対策が確立するまでは、建設すべきではなく、そのために国民は、原子力のいらない発電環境を作るため、電気使用を考えるべきなのではないだろうか
0投稿日: 2017.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ辛かった。 戦争でもないのに、死に向かう覚悟をする人が出てしまったことが。 思いを言葉にするのは難しい。
2投稿日: 2017.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ約400ページを3日間で読み切ったのは、自分の中ではかなりのペース。 それくらいのめり込むほど、興味深い内容だった。
0投稿日: 2017.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ命をかけて現場で闘う男たち 現場を混乱させるためだけに大局観もなく現場に入る首相… 人は窮地に陥ると本性が現れます。 東電本店と官邸の無能ぶりが現場の男たちを際立たせます。 分厚い本ですが日本人ならあの時なにが起こったのか知るために一読したい本です。
0投稿日: 2016.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙無しには読めません。原発が、東電が、政府が…色々あるが何より純粋に人としての生き様について考えさせられます。
0投稿日: 2016.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発で陣頭指揮をとった吉田所長を中心に、原発が被災してから収束に向かうまでの期間にわたり、本人や関係者の直面した苦悩、課題、解決策などを克明に綴った書籍。吉田所長の生き様を感じた。当時の菅首相の稚拙さと比較すると、リーダーとしてあるべき姿がいっそうよくわかる。良書。
0投稿日: 2016.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ壮絶な現場、死をも覚悟した圧倒的な責任感、感動した。だからこそあってはならない原発事故。原発一律反対ではないがなくすべきことは必然。
0投稿日: 2016.06.13吉田昌郎さんへの感謝を込めて。
主人公は吉田氏だけではなくいわゆるFUKUSHIMA50と言われる人たち。東電本社はともかく現場の人たちは限られた条件の中で出来ることはした。よくあの状況の中で自発的に必要な判断を出来たと思う。 一例に挙げると福一を最悪の事故から救ったのは津波と全電源喪失直後に1号炉に冷却ラインを作り消防車の応援を呼んでいたことだった。事故直後の報道ではわからなかったが吉田所長の最悪の想定はチェルノブイリの10倍の規模の放射能漏れであり、班目氏はさらに福島第二と東海原発への連鎖まで想定していた。彼らは専門家でありその想定は重い。しかし、全電源喪失については防げる事故でもあったのが残念だ。 一号、三号が爆発した3月15日の明け方席に戻った吉田所長はゆらりと立ち上がり、机と椅子の間に胡座をかき目を閉じて座り込んだ。その時周囲の人間はプラントの「最期の時」を感じたのだが、吉田は腹を決めている。「私はあの時、自分と一緒に”死んでくれる”人間の顔を思い浮かべていたんです」「やっぱり、一緒に若い時からやってきた自分と同じような年嵩の連中の顔が、次々と浮かんで来てね。頭の中では、死なしたらかわいそうだ、と一方では思っているんですが、だけど、どうしようねぇよなと。ここまできたら、水を入れ続けるしかねぇんだから。最期はもう、(生きることを)諦めてもらうしかねぇのかなと、そんなことをずっと頭の中で考えていました」 その吉田にテレビ会議で管が言う。「事故の被害は甚大だ。このままでは日本国は滅亡だ。撤退などあり得ない! 命がけでやれ」「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる。逃げてみたって逃げ切れないぞ!」 逃げる?誰に対して言ってるんだ。いったい誰が逃げると言うのか。(なに言ってんだ、こいつ) 厳しい批判を受けた中では班目氏はどうやら限られた情報の中で想定される事態を把握していたようだ。少なくとも官邸に対しての助言は間違ってはいない。しかし、どうしようもなく当事者意識が無く官邸が自分の言うことを理解しなければどうなるか薄々わかっていながら怒れる管に何も言えないでいた。伝わらなければ正しいことを言っても意味が無い。 最終段階では出来ることはないとわかっていても残ろうとした若者もいた。残ってくれると信じていたが退避したものもいた(彼らを責めるのは筋違いだが)。そして新潟から応援に来てそのまま残った協力業者もいた。一旦退避してから戻って来たものも多い。「ヤクザと原発」によれば協力業者の中には必ずしも使命感だけで残ったのではなく、その場のノリで残ったものもいる。それもこれも含めて彼らに救われたんだろうと思う。 個人的には今でも使える原発は使うべきだと思っています。例えば原発安全神話と温暖化は怖くないというのは対象が変わっただけで構造的には変わらないし、石炭は私の理解では原発以上に明らかに健康や安全に対してマイナスだし(例え高効率の発電が出来、PM2.5が解決できたとしても採掘事故の問題は残る)、単純に燃料費が上がるという経済的な損失も人によっては直接健康や安全に危害を及ぼす。それでも原発を無くしたいと言う素直な感覚は理解できるし、それを否定する気はない。いろんな問題をイノベーションが解決するかもしれないがまだ時間はかかるし、その上で何を選択するかということだろう。今後日本で新しい原発が稼働できるとは思えないので当面は天然ガスに頼り再生可能エネルギーのイノベーションを待つというのは一つの答えだと思う。その間のトレードオフを理解した上で原発を止めるというのはそれも一つのもっともな選択だ。
0投稿日: 2016.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ良質のノンフィクション。ギリギリの状況を救った人たちの戦い。だんだん遠くなっていくフクシマだが、絶対忘れてはならない。 なぜ、再稼働が進むのか、私には理解できない。自然災害だけでなく、テロや北朝鮮の脅威もある。北朝鮮は原発攻撃もやりかねない不気味さがある。経済効率をだけを考えた政策は間違っている。 本書は、原発の有無を問うものではなく、極限状況の中の人間を描いたものだが、フィクションでは味わえない緊迫感とリァリティがありおすすめだ。
3投稿日: 2016.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ地震直後の福島第一原発で何が起きていたのか、何であのような大事故となったのか、当時の状況と事故現場で復旧作業にあたっていた人の勇気と苦労がわかりました。 それにしても本店トップの無能振りや、菅さんの衝動的な行動が如何に混乱をもたらしたかがよくわかりました。
3投稿日: 2016.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ覚悟が詰まった一冊であった。 この著書では、班目が割と良い人として書かれていた。 吉田所長がいたことは、偶然ではなかったように思う。 東電の人材力、配置の力があったのだと思う。 本店に関しては、大会社病があったのだと思うが、現場に関しては、それが無くいわゆる技術者のプライドがまだまだ残っていたために、日本は救われた。 今回の事故に関して、結果論からこの場合はこの判断をするべきだったといった検証をしていくべきである。 それがあらゆる防災につながっていくと思う。
0投稿日: 2015.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ考えられうる最悪の事態の中で、現場がどう動き、何を感じ、どう闘ったのか。所長、当直長、中操内運転員たち、経産省の現地対策本部長。菅首相、大臣、官房長官、安全委員会長。自衛隊の消防車隊員。一緒に死ぬ人間だけ残す。 現場の経験、知恵、ノウハウの蓄積あってこその技術。
0投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ津波による電源喪失。混乱する現場で必死に故郷を日本を守った男たちの記録。この戦いがあったことを忘れてはならない。 無策な上層部と使命感を背負った現場。特攻基地の跡地に建てられた原発で繰り返された悲劇。しかし、将来ある若者は退避させ現場責任者クラスが残ったのは、あの時とは違う。電車で読む際は、嗚咽注意です。
0投稿日: 2015.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非常によくかけている気がする。あと、吉田さんの仏教好きってのが気になる。それから、電話の通じた二人だけが津波で殉死ってところの不思議さとか。
0投稿日: 2015.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災の時、原発に何が起こったのか。そして覚悟を持った現場の方々の戦いが、緊迫感と共にびしびしきました。 現場すごい頑張ってる。そんな中、当時の首相のKY行動が際立って酷く……。 後日朝日新聞の、彼らを貶める記事掲載が問題になりましたが、こういう本が出ていたのにあんな記事出せたんだなぁ、と。当事者じゃないけど腹立ちますわ。 そして改めて、あの事故が最悪の事態に陥っていたらの恐ろしさが…。
0投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
門田さんのノンフィクションは何作か読んでいます。 こちらも気になりつつも多くの方も書かれていたようになかなか手に取る勇気がもてませんでした。でも先日、福島原発の被害者の方たちで結成された「福島原告団」のお一人の方の講演を聞く機会がありそれをきっかけに手に取りました。 単に講演を聴いたからということではなく、その原告団の方がこの吉田氏のことを「責任を負うべき立場であり、自分の不作為の後始末を自分でしただけ、決して英雄ではない」と語ったからです。 実際に吉田さんという人が、あの日から東電を去る日までどういう風に原発と対峙されたのか知りたいと思いました。 本書を読んで感じたことは、まず原発の被害に遭われた方々にとっては、まさしくその原告団の方の言った通りなのだということです。 吉田さんは責任を負うべき立場でありその責務を全うされたのでしょう。 英雄視されていることが許せない、納得いかない、というのも当然のことと思いました。 でも、それは「社会的立場視線」で視た場合のこと。 「人間的立場視線」で視たならば、いくら責務であったとしてもやはり誰でもここまで果たそうとするだろうか、できるだろうかと思ってしまいます。 吉田さんだけでなく、その部下の方々も。 ノンフィクションと言っても著者がいる以上、著者の感情や立ち居地が文章に反映されることは多いにあるでしょう。そこを考えたとしてもやはり私個人としては「よく吉田さんは、そしてその部下の方たちはここまでやってくれたな」と思わずにはいられませんでした。 確かに結果的には故郷を喪った方たちをたくさん生み出してしまいました。でも、ここに書かれた人たちが原発と文字通り必死に向き合って戦ってくれなかったら、今の日本は間違いなくありませんでした。 そのことを思うと、「責務を果たしただけ」というのは私には辛かった。これが他の仕事だったならと考えてみたら、命をかけても職務の責任を果たせ」とは今の時代、誰に対しても言えないのではないでしょうか。 命を落してまでしなければならない仕事などあっていいわけがないと考えます。 彼らを責めて良いのは原発の被害に遭われた方だけという風に私には思えてなりません。 これを読んだら、原発が存在すること、原発に頼ることがいいことだ、仕方のないことだなどととても思えないです。 原発稼動賛成、という人にこそ心して読んでいただきたい一冊だと思います。
8投稿日: 2014.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災は確かに大きな地震で、津波の被害も甚大だった。でも、今なお終息していないのは、原発問題が終わっていないからだし、自分が生きているうちは終息しない。 もう少しで東日本が人が住めない土地になっていた状態にあったのは、本当に恐ろしい。この人達の尽力でくい止めてくれた。吉田所長に合掌。
0投稿日: 2014.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログもう何度目の読破だろうか 毎回感情移入してしまい、涙がでてしまう 私も事故前のこの現場で協力企業社員として 3年間働いた経験があり 出てくる言葉、場所、 登場人物の一部に理解があるせいだろうか ホント、事故後の現場の方々はよくやっている 凄いの一言では片付けられない だから涙がでてくるのだろうか 読む人でも立場でも 原子力に反対でも賛成でも 何かを感じてもらえるはず、ぜひ読んでもらいたい一冊 吉田所長と福島の浜通りの方々 リーダーとして、エンジニアとして そして人間として 尊敬する そんな人たちです。
0投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ20141016読了 読んだ・・・凄まじすぎて休み休み数日かけて読んだ。●私は西にいたのでテレビに映し出される映像や日を追って明らかになる現地の状態にただただ呆然とするしかなく、東電や政府の混乱はともかくとして、こんなにも壮絶な現場で踏みとどまってくれた方々がいたとは知る由もなかった。状況判断して動く現場のすごさ、取り仕切る立場の重圧や葛藤。原発事故の最前線に、あのときこの人たちがいてくれて今がある。読んでよかったと思う。
0投稿日: 2014.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯文:”「あの時」を風化させてはならない。吉田昌郎の「遺言」は私たちに何を問いかけるのか。” ”吉田昌郎、菅直人、斑目春樹……当事者たちが赤裸々に語った「原子力事故」驚愕の真実。” 目次:はじめに、プロローグ、第1章 激震、第2章 大津波の襲来、第3章 緊迫の訓示、第4章 突入、第5章 避難する地元民、第6章 緊迫のテレビ会議、第7章 現地対策本部、第8章 「俺が行く」、第9章 われを忘れた官邸、第10章 やって来た自衛隊、…他
0投稿日: 2014.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ副題に500日とありますが、ほぼ原発事故直後に焦点を当てたもの。 そして吉田所長を始め、何人かのその後が紹介されています。 門田さんのノンフィクションはほかにも読んだことがありますが、偏りがなく、事実に忠実であろうという姿勢が感じられ、なおかつ読み応えもあります。 当時のニュースでは分かりにくかった原発事故の内実に、かなり近づけたのではないでしょうか。 事故当初のことから、原子力発電所建設にまつわる話まで、必要な情報がまんべんなく詰まっているように感じられました。 EG村という存在も、本書で初めて知りました。 情報に色はない、とは青木直人さんの言葉ですが、門田さんの本は色づけされることのない情報が提供されていると感じます。 どんな政治思想を持っているかにかかわらず、多くの人に読んでもらいたい一冊。 そして著者が最後に指摘しているように、原発事故により、火力発電所などで起こる地球温暖化等の環境問題を指摘する声がまったく聞こえなくなったことは恐ろしいことだと思います。 極端から極端に走りがちな日本人。本書が冷静に考えるきっかけとなってくれたらと思います。
2投稿日: 2014.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災。 TVには壮絶な映像ばかりが流れている頃、福島第一原発には福島を、日本を守るために自身の命をかけてまで戦った東電社員や協力会社社員、自衛隊隊員がいた。 メルトダウン、ベント、水素爆発…化学を専攻していた自分でもあの時あの状況ではよく理解してなく、ただ報道されることを鵜呑みにしてた。 実際に現地で間近でそれらと戦っていた方々の恐怖、使命感、勇気は計り知れない。 再現映像とはまた違うリアリティに涙が溢れた。 当時の菅首相が地震の翌日に福島へ、原発に向かった。ヘリから降りるところTVで見て、「今来て何するの?」とか「首相自ら危険な所に行かんでいいやろ」とか思ったけど、そんなの浅はかさすぎた。1分1秒を争う現場なのに、ヘリから降りる姿を撮影するための待ち、迎え入れるための準備、説明対応、見送り。何やらせてんだ、首相。 東電という会社にはもちろん大きな責任がある。国にも責任がある。簡単に許されるべきじゃない。 でも、あの日福島第一原発で戦った方々には敬意を送りたい。日本を守ってくれてありがとうございました。
0投稿日: 2014.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故の発生から、 その収束のための指揮を執った吉田昌郎所長が病気で退くまで、 その原因となったマグニチュード9.0の地震が起こったところから 綴られていくノンフィクション。 どうやって、あの原発事故は最悪の被害を免れたのか、 福島第一の現場の状況は当時どう流れていっていたのか、 そこでどんな人々がどう闘っていたかがわかる本。 どうしても、東電や政府は悪いものだというイメージがあったりする。 10mを越す津波はこないとする想定の甘さといい、 マスコミによる政府や東電側の「対処の遅さや悪さ」 を強調する報道などが一面的になされたからだ。 しかし、本書を取ってみると、 現場で働く東電社員と協力企業や自衛隊の人々の 決死かつ迅速な事故対応を知り、イメージが新たになる。 そこには、平和ボケする僕も含めた大勢の一般人のような日本人はいない。 緊急時に際しても力を失うことなく、 やれることを最大限にやり抜き、知恵を絞り、スピード感を持ち、 そして放射能の恐怖に負けない、強い責任感(なのか、日本を救わなければという気持ちなのか)を 読みながら汲み取っていくことになり、心が打ち震えてくるのである。 まるでハリウッドの奮闘物映画のヒーローのような人たちばかりがでてくるし、 それは脚色でも演出でもなく、生の事実だというそのことが、 彼らへの敬意と感激とねぎらいの気持ちを起こさせるのだ。 そこには数々の人生が交差している。 それぞれに家族がいて、自分の生がある。 大きな、「日本滅亡へのベクトル」というどうしようもない流れに抗して なんとか最悪の事態になるのには打ち勝った、その頑張りと勇気に 頭が下がってしかたがない。 それにしても、本書の書き方が偏った向きもあるのかもしれないけれど、 当時の首相の管直人さんの言動や行動にはあきれさせられた。 人間、怒りのパワーなどで人や物事を動かそうとしたって、 そんなのは逆によくない影響をもたらしたり、時間を無駄にしたりする。 そういう教訓として、管首相のところは読んだのだった。 「イラ菅」なんて呼ばれるみたいだけど、そんな人だったとはよく知らなかった。 福島第一原発事故はまだ収束しているとはいえないと思っています。 今だって避難している人たちはたくさんいるのだから。 そういう人たちそして、事故そのものを忘れないために、 そして、そこで闘った立派な人たちを知り、忘れないためにも、 (これは、原発推進、脱原発いずれの思想に限らず) 多くの人に読まれるといい本だった。 最近、朝日新聞の吉田調書での虚偽の記事が問題になりましたが、 本書では、そういうことはなく書かれている本だと思います。
0投稿日: 2014.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「入れ続けた水が、最後の最後でついに原子炉の暴走を止めたー福島県とその周辺の人々に多大な被害をもたらしながら、現場の愚直なまでの活動が、最後にそれ以上の犠牲が払われることを回避させた」英雄視するのは違うだろうけど、やっぱりすごい人。そして沢山の命をかけて使命を果たそうとしてくれた人達、忘れてはいけない。
0投稿日: 2014.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ自宅ソファーで読了(43) 壮絶…。そしてこれはノンフィクション。 世間を賑わした、朝日新聞の吉田調書問題きっかけでのセレクション。
0投稿日: 2014.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでが真実かは分からないけれど、今までの報道では知り得なかった緊迫感が凄く伝わってきた。読んで良かった。
0投稿日: 2014.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダーというのはどれほど重要かということ。 極限の状況においてひとの根っこの部分があらわれる。 その点において、国の存亡の危機であったこの事故の現場のリーダーが吉田昌郎氏であったこと、現場の人が日本人の持っている責任感と使命感をもち命を賭けてチェルノブイリ×10の事故になることを防いでくれたことに感謝しなければいけない。 そして今もその作業は現場の人々によって続けられていることも忘れてはいけない。
3投稿日: 2014.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ極限状態おけるリーダーシップ、また、それぞれの役割においての選択・行動が残酷過ぎる程に描かれていた。 危機に置いて曝け出される人間性の数々。 そしてこの本で知った数々の事実。 原発建設以前の戦時中は、特攻訓練所だった事。 不信の中、あり得ない現場介入を行った当時の宰相。 死の覚悟とプライドを持って任務を果たした現場作業員の“功績”。 多くの人に読まれて然るべき。
2投稿日: 2014.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは五百日となっているが、実際はほぼ1週間の出来事。あの時福島で何が起こっていたのかを克明に示している本。 「東電寄り」と書かれているレビューもあるが、実際のところは東電ではなく現場を描いた作品なのであって、その日に至るまでの危機管理はさておき、あの事態が起こった後に現場の人達がどれだけの状況下でどういう働きをしたかがよく分か流というだけでいいと思う。 より大きな組織論や政府とのコミュニケーションについては、ここでは力点が置かれていない。菅さんへの言及も、本人の直接のコメントを入れる等、中立的に書こうとしていると思う。 死を覚悟して刻々と変わる状況に対応していった吉田所長以下現場の方々には頭が下がる思い。 ただ、一点不可解なのはどうして津波について誰も思い至らなかったのかということ。わざわざ沿岸の建屋の地下の点検を命じ、結果2人の作業員が亡くなったことについては残念としか言いようがない。 ゴルゴ13の『2万5千年の荒野』でも指摘されているが、原子力発電は恐ろしい。でも100%の安全に近づけるよう、制度と運営を実施しなければきっと世界の何処かで同じ危機は繰り返されるのだろう。そんな地球の上に、僕らが生きているという事実。
7投稿日: 2014.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログあの日あの時あの場所で何があったのか、何を思いそこに居たのか、被災者でありながら、被害者になってしまい、それでも最悪の被害を避けるべく、懸命に、正に命を懸けて、制御できると過信した人間に牙を剥いた原子炉と闘い続けた現場の人間のドキュメンタリー。 何度、電車の中で泣きそうになったかわからない。 本当に多くの人たちがのただただ愚直に、職務に、責任に、使命に、道徳に、良心に忠実に従って、あの事故に必死に対応してくれていた。 ただ、決定権を持つ者たちだけが現場を知らずに権利を主張した事が混乱の原因だった。 後100年、廃炉までは掛かるだろう。それまでとそこから、人はどんな選択をするのだろう?あの時、現場で奮闘した者たちのように、ただただ愚直に、一心に、最悪を回避する事だけを考えた選択をしていえるのだろうか?
2投稿日: 2014.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがに門田隆将のノンフィクション小説は重厚な内容で読み応えがありますね!私の知らなかった福島第一原発事故後の現場での戦いの現場の人たちの使命感や責任感の凄まじさに感動しました。また吉田所長のリーダーシップにも感服しました。それにひきかえ政府の人間の無能っぷりにはガッカリさせられましたが。まさに真のプロフェッショナルな人たちというのはこのような人たちのことを言うのでしょうね!
3投稿日: 2014.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発推進派も反対派も、イデオロギーに関係なく読んでもらいたい。 原発事故があった事は事実であり、また、被害を拡大させない為に命をかけて守った人がいるのも事実です。 時の首相にも取材をしており、ドキュメンタリーとしての秀作。
7投稿日: 2014.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本が滅びるかも知れない」と大げさでなく、瀬戸際に立って奮闘した吉田氏とメンバーたち、そして菅首相も悪役のように書かれているがきっとそうであるに違いない。ただイラ菅が現場を刺激し反発心を招いたことは伝わってくる。正に日本を救った瞬間の驚くべきドキュメンタリー。果たしてこのような状況下で誰が逃げずに戦うことができるだろうか?「やるしかない」と割り切らざるを得なかった!とはそうなのだろう。第2原発から第1原発へ志願して戻る関係会社社員の阿部のことは心が震える。吉田が万事窮すと「最期の時」の雰囲気を周りに発信し、「一緒に死んでくれるのは誰だろうか」と瞑想にふけった瞬間(3月14日早朝)はこちらまで深い思いになる恐ろしい場面。家族への思いと責任感の間に揺れた男たちそして女性。日本を救った実話の衝撃の1冊である。
0投稿日: 2014.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東日本大震災以降に、福島原発の現場で何が起こったのか。誰が何をアクションしたのか。現場と本社、東電と政府の関係者にもヒアリングをしたルポタージュであり、単純に誰が良い、悪いという二元論で語っていない。 あの頃、とんでもないことが起こった不安感に一般の国民は襲われていたが、現場では、なんとか事故を食い止めるために、吉田所長以下のメンバーが決死の覚悟で仕事に挑んでいたことが手に取るように伝わります。 今も変わらずに、現場で作業にあたっている方々を忘れずに、しかも、この問題を防げなかったことに関しては、常に意識しきたいと思える一冊でした。
0投稿日: 2014.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ3.11東日本大震災にて福島第一原発に起こった事を、現場の人達の言葉から綴ったノンフィクション。 消えていく照明、原子炉の情報を示すメーターも消える。システム化された状況で全ての情報が途絶えるなか、原子炉の暴走を止めるべく戦っていた。 そこには、すごいプロ意識と使命感があった。 また、原子炉を冷却するため、各地から結集した消防隊。上空からのヘリ消火をした自衛隊。 現場のさまざまな人の力で、チェルノブイリ級の事故にならず、なんとか抑えこむことに成功した。 みんな家族がいるなかで、任務をまっとうした。 これは、後世に残すべき大接近な歴史だと思う。 災害とテロが起きた時に、全電源を喪っても原子炉を冷却する必要がある。必要な対策を、事前に施してなかったことは悔やまれる。
0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発の大事故を当事者たちの実名で綴った渾身のノンフィクション。原発の是非、東電トップや政治家の責任ということよりも現場ではどうだったかが知りたくてこの本を読んだ。非常電源までも喪失し、計器の読み取り困難な状況の中でベントのためにバルブを開ける様子。チェフノブイリの10倍で北海道、東北と関東の汚染地域、西日本という三分割という最悪の危機を救ってくれたリーダーシップあふれる吉田所長や使命感、責任感をもって対処してくれたフクシマ・フィフティや自衛官に感謝し敬意を払いたい。忘れてはならない。
0投稿日: 2014.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ副題に五〇〇日とあるが,ほぼ発災から一週間の現場ドキュメント。所長をはじめ,後に「フクシマフィフティ」と呼ばれることになる人々や,政権,保安院,自衛隊,地元の人間にも取材してあの緊迫の日々を振り返っていく。最後まで残ったのは69人だったということだが,彼らが死を覚悟していたというのは決して誇張ではないだろう。 4号機タービン建屋で津波に飲まれて亡くなった二人のうちの一人についてもむつ市の遺族に話を聞いている。地震直後に息子からかかってきた電話が最後の会話になったこと,ネット上で事実無根の中傷が広がったことなど,初めて知る事実が多かった。扱っているテーマのわりには,全体的に誇張や偏向などなく,しっかりしたノンフィクション作品だった。
2投稿日: 2014.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ3.11を、そしてその後の原発事故とこれからも続くであろう放射能の問題をリアルタイムで見聞きした身として読まなければならないと思っていた1冊。震災発生後ほぼ1Wの出来事で占められているが当時の切迫したフクイチを命がけで「最悪の状況」を回避するために電力喪失といった最悪の状況に全身全霊で立ち向かった現場従事者達を描いている。このフクイチの現場力ってのは凄いな、物凄い現場力だよ。そして当時の政権には改めて強い憤りを感じた。また当時、デタラメ委員長とまで揶揄された斑目委員長が実は当時の状況化において、政権に翻弄させられた一人だったってのも驚いた。原子力委員会という組織についても見方が変わったわ。この本に書かれている事をそのまま全て鵜呑みにするつもりも無いが、報道で知った内容と疑問・疑念を重ねあわせて読み進めた限り、ほぼリアルな状況を書き記したものであろう。そして改めて原子力と言うモノの恐ろしさを感じた。
0投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発事故の最初の1週間に、第一原発内で何が起きていたのかを描く。文字通り命懸けで限界状況に立ち向かっていった現場の”男たち”を”ヒロイック”に描く。その描写はまるでドラマのようだが、それは著者が取材した現場の人々に持った強い敬意の表れだろう。文章は非常に読みやすい。より多く読まれるべき本だろう。ただタイトルが内容をうまく表せていないように思う。副題に「吉田昌郎」の名だけがあがっているが、吉田氏以外の多くの人の活躍を描いており、紙幅の面でも必ずしも吉田氏だけがメインとは言えない。また、「五00日」とあるが、全375頁中、300頁ぐらいは3・11から一週間の出来事で占められている。(特に最初の3日間)。
0投稿日: 2013.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本に起こった重大な出来事。この本は読んでおいた方がいい。 福島第一原発を守った吉田所長と現場で作業に当られた方達に感謝の気持ちでいっぱいになる。沢山報道されてきたけれど、知らない事がまだまだ沢山あり、読みながら何度も涙がこみ上げる。 時間との闘い、情報の欠如、そして意思の疎通の難しさ。原発について、放射能についての知識の無さは、その頃の日本では普通の事だったと思う。終わってからは色々言えるけれど、その時、その場では、ギリギリの状況で最善と思われる判断が秒単位でなされていたのだと思う。
0投稿日: 2013.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田所長をはじめ、関係者へ証言を突き合わせて、取りまとめられており、マスコミ報道や一方的な記者会見ではわからない事実が浮かび上がってくる。全電源喪失という厳しい現場のなかで、あらゆる限りの知恵を絞って対応する人たちの努力は敬服するとともに、現場力というのものを改めて実感した。テレビに出ていた本店の人も東電なら、現場を支えたのも東電なのである。そんな東電を一緒くたにし罵倒し続けた菅直人をはじめ民主党政権には怒りさえ感じてくる。 デタラメ委員長とまで揶揄された斑目委員長もそんな政権に翻弄された被害者だと思えてくる。 最も感動したのは、4号機建屋で津波にのまれた若い運転員のご両親の証言。発見が遅れ、一時は、侮辱的な発言をしたテレビもあったらしい。耐える家族と復旧の仕事をしながら苦しむ仲間の思い。本当に涙が止まらなかった。 用語の使い方などに間違いもあるが、全般的には誰にでも読みやすく書かれているので、状況を知りたい人にはよいのではなかろうか。
0投稿日: 2013.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、東日本大震災が起きた2011年3月11日から約9ヶ月後の2011年11月頃までの時間軸の中で、福島第一原発の事故が悪化の一途をたどっていく状況とそのときの人間模様を物語調に描いた本である。 本書を読み、頭にパッと浮かぶのは”なんと、凄まじいことか”という想いだ。ここには2つの意味がある。 1つは”現場力の凄さ”という意味での凄まじさだ。管元首相のことが色々と取り沙汰されてきたが、誤解を恐れずに言えば、結局のところ、当時のトップが管首相であってもなくても、(多少の違いはあったかもしれないが)あの現場の人たちがいたかいなかったか・・・それが全てだったんじゃないかと思う。それほど現場力は凄まじいものだったと感じるのだ。 もう1つは”なんと過酷なことだったのか”という意味での凄まじさだ。海外からはフクシマフィフティと言う言葉でたたえられた現場の人たち。自らの命をも省みず、家族・・・いや、日本のために、必死で闘った人たちのことだ。本書を読むと、彼ら・彼女らに降りかかった肉体的・精神的な負担が、いかに過酷なものだったのかが、はっきりと伝わってくる。 原発の恩恵を享受する国民一人一人が、原発廃止の是非を判断する前に、当時報道されなかった”見えなかった犠牲”というものを知るために本書を手に取るべきだということはもちろんだが、加えて、組織のトップこそ、ぜひ読むべきだと思った。 なぜなら、本書を通じて災害時における組織のトップのあり方を理解することができるからだ。災害時には現場こそが一番機能する・・・これは9・11からも、3・11を描いた本書からも見て取れるが、組織のトップがその事実を改めてしっかりと理解しておくことで、自分のあるべき真の役割を見いだせるのではないかと思うのだ。たとえば私なら、トップは結局、「現場がより円滑に機能できるように後方からサポートをしてあげること・・・決して邪魔をしない・・・それにつきる」という答えを出すんじゃないかと思う。 こうした考察が正しい、正しくないは別にしても、過去を振り返り、こうした思考をめぐらせることは、非常に大事なことだと思う。その意味でも、本書の意議は大きい。 (書評全文はこちら↓) http://ryosuke-katsumata.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
2投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ簡単に書くと、2011年3月11日の地震とその後に、福島第一原発で起きていた出来事について、数多くの関係者(当時福島第一原発の所長だった吉田昌郎氏、原子力安全委員会班目委員長、菅首相等を含む)から聞き取り、まとめたものです。 出来事、関係者の思いや覚悟など、一言で表現できないものが詰まっていました。 班目委員長が「日本が汚染された地域・それ以外の東日本・西日本に3分割されいたかもしれない」と書いている状況の中、人のいろいろな感情が書かれている本だと思います。
0投稿日: 2013.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく、この本とじっくり対峙する時間と心の準備が出来て一気に読み上げた。 後に「フクシマ50」と呼ばれる大震災、津波後の極限状況のなかで、荒れ狂おうとする原発に命を賭けて立ち向かった人々の物語。 1000年に一度の津波への防御を尽くさなかったことを「人災」と断罪するのは容易い。 では、原子炉が完全に暴走して関東・中部に死の灰が降り注ぎ、日本が北海道、西日本、「住めない地域」に3分割されるギリギリのところで押しとどめた、吉田所長以下のサムライがいた僥倖をもっと認めてもいいのではないか。
0投稿日: 2013.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ3.11に引き続き発生した原発事故において、何が起こっていたか、責任感を持ち続けた現場が何を考えていたかが判る一冊。 死を決意した男たちの活動に泣かせられる。
0投稿日: 2013.10.13
