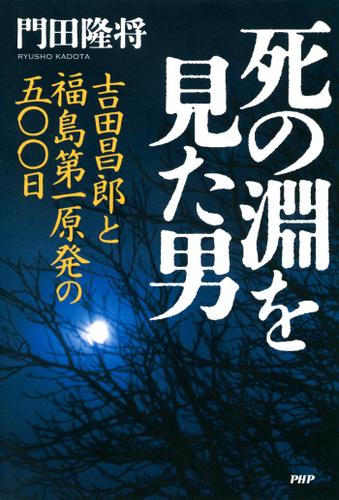
総合評価
(186件)| 104 | ||
| 53 | ||
| 14 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東電=悪者、という構図がぼくの頭にはあった。 たしかに、東電上層部の不信感は今もぬぐえない。 しかし、この本を読んで、吉田所長以下東電や関連企業の社員、その他の方々が、「決死の覚悟」でことにあたっていたことを知った。 皆さま、よくぞ逃げずに頑張ってくれた。ありがとう。 自分の仕事に責任を持ち、死を覚悟し仕事をし続ける。これぞまさにプロフェッショナリズムだろう。 逆に、原子力保安院の4名は、逃げた。あの災害時に、恐怖を感じ、逃げたくなる心理は当然だ。しかし、原子力を使う以上、誰かが責任を持たなくてはならない。保安院は、法的に責任を持つのに、逃げ出したということは、今後の緊急事態の行政の対応に不信感を植え付けるきっかけになったと思う。
0投稿日: 2013.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013/10/01-10/08 福島第二原発事故 班目前原子力安全委員長はこう言った。「日本が三分割されるギリギリの瞬間だった。放射能汚染で住めなくなった場所とそれ以外の北海道と西日本である。」が残る。 吉田所長 菅首相 班目委員長から見た原発事故の記録である。
0投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011年3月11日。 東日本大震災が起きたその日から、福島第一原発の最前線で戦い続けた男たちのノンフィクションドキュメンタリー。 内容は基本的には当事者インタビューに基づいて、極力著者の「意見」が挟まらないように、まさにあの時、現場で何があったかを著述するスタイル。 これは想像を絶する。 あの時は、東京在住の私としては、自分の身の回りもドタバタで、はっきりいってあの一週間で原発がどういう推移を辿ったかは明確には記憶から抜け落ちていた。 それだけに、現場で起きていたこと、現場の人間がどれほどの窮境に置かれていたかなどは、読む前の想像をはるかに絶した。 個人的に岩手に復興ボランティアに行ったことはある。 しかしやはり、原発事故というのは、それとはまただいぶ違った災害なのだなぁ・・・。
0投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災による福島第一原発事故に立ち向かった吉田所長をはじめとした原発職員たちの闘いをまとめたノンフィクション。 放射能という見えない敵と不眠不休で闘った現場の人たちの様子が綿密な取材で書かれていて、後世に語り継いで行かなければならない内容だと思った。 同時に当時の首相をはじめとした政治家、東電の経営陣の無能さ、無力さに怒りを覚えた。
0投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田所長だけでなく、東電の人は本当によくやってくれていると思う。 東電トップと官僚と政治家が東電をダメにしているのだ。 今後、危機が日本に襲ってきたとき、 日本は臨機応変に対応できるのだろうか。
0投稿日: 2013.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ全電源喪失・冷却不能などということは起こり得ない、という慢心から起こった原発事故は、本当なら日本の国土を、「北海道」、「西日本」、「汚染区」の3つに分割する事態を招いていた。基準を超える放射線量を浴びること、浴びさせることが許されない限り、これは不可避の現実だった。これが回避されたのは、本書で登場する事故現場で対応にあたったすべての人の、識見、判断力、勇気、そして使命感のおかげだった。つまり仕組みは早々に機能しなくなり、あとは現場で何とかしたのだった。その現場の人々が地獄の現場に真っ向から立ち向かう超人間的な行動と精神の強靭さに驚くとともに、そういう人々がたまたま現場の対応にあたっていてくれたという日本にとっての僥倖と、結局は現場しか仕事をしないという巨大組織の脆さというものを思わずにはいられない。
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ五輪の招致でも焦点となっていた福島原発の汚染水問題ですが、いまなお収束どころか不安定な状態であることを思い知らされた原発処理の現実です。本書はその発端である東日本大震災の直後に、現地で何が起こっていたのかをインタビューを基に再現したノンフィクションのドキュメンタリーです。 本書は福島第一原発の事故当時の所長である吉田昌朗氏を中心とした内容で進みますが、この吉田所長は当時から様々なメディアでも「所長が吉田さんであったのがせめてもの救い」と云われていた人物でもあります。 内容は恐らくはほとんどの人が知らなかったであろう福島第一原発の成り立ちや、初期にアメリカのGEの技術移転があったエピソードを皮切りに、当時の原発所員の視点で事故直後の緊迫した状況が描かれていきます。菅首相が現地に来た際の経緯や状況も可能な限り正確に再現されているようで、さまざまなメディアや本人の証言などの食い違いがいまなお話題になるものの、一定の解釈を提示してはいます。 最後のエピローグは、目の前が霞まざるを得なくなりますが、結局のところ、庶民が庶民のために命を懸けて、それを一番諒解していたのも国民である庶民だという描写に、いまなおだらしのない政府や東電への作者の強烈な批判と皮肉、そして救いと希望が見てとれます。 もっとも印象に残ったのは、当事者である原発職員や自衛隊の方々が、本書の中で何度も、「当然の事をしただけである」という感覚で当時も今もいることです。だから今になっても当時の真実が逆説的に見えてこないとも言えるのですが、第三者的なマスコミや学者連中、批評家がいまだに全容を解明できないポイントなのかも知れません。 なにせ当の本人達に「国を救った」とか「絶対絶命のピンチを自分のおかげで切り抜けた」などという大それた!?感覚は一切なく、「当然のことをした」だけなのですから。 著者の門田隆将氏が何度も念押ししているように、本書は反原発でもなければ責任を追及する暴露本でもなく、日本という国の国民庶民が未曾有の国難において「当たり前の行動を取った」ドキュメンタリーだけの本で、特に主張や見解を明示しているわけではありません。 ただし、本書の印象から敢えて 風呂敷を広げれば、過去の戦争を含めたいろんな歴史的な事件や話題も、当時の我々の先祖である日本人が、恐らくはほぼ間違いなく今回と同じように「当たり前の行動をした」のであれば、今なお真実が不明瞭な理由や本当の答えがどこにあるのかは、おのずと明らかではないのかという気がします。著者が暗に明示したいのも、日本人としての行動規範!?は今回も失われずに残っていてそれが国難を救ったと取れなくもありません。まあそんな大それた意図はなく、著者も同じように「当然のこと」として本書を上程したのでしょう。 ともかくも是非一読をお勧めするのと、さる7月に亡くなられた吉田所長のご冥福をお祈りしたいと思います。
0投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構専門用語は出てきます。 でも、言ってることは状況から分かるはずです。 所長、当直長、当直副長、作業員、協力会社等、関係者がどんな気持ちで福島第一原子力発電所の収束に当たっていたのか、これを読んでいるとその使命感の強さに頭が上がりません。
0投稿日: 2013.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ事実の重さをまざまざと感じさせられ、涙が出た。 まさに人の強さと弱さが大震災という非常時に本当の姿として現れるのだろう。 果たして同じような状況で、自分はどんな姿を曝け出すのか。日々の生き方が問われている。
0投稿日: 2013.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ過酷事故を題材にした人間物語で、それ以上でもそれ以下でもない。感動したくて手にとったが、期待は裏切られなかった。 原発で津波に襲われた21歳の東電社員の遺体に母親がようやく対面できた場面と、現場で命がけで事故収束に当たった職長が避難で散り散りになった地元の人たちの会合に出て拍手されて男泣きする場面は、泣けた。 危機は人間の底力を見せつけたり醜い実像をさらけ出したりする。現場にいた多くの男女が前者であった事に感謝し誇りたい気分にさせられた。
0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発のドキュメンタリー。 原発の是非について論じるでなく、まさにその現場で事故に直面した人達がどのように思い、行動したのかに迫った傑作。 これを読むと、事故初期の当直長を中心とした現場の方々の対応で事故の被害がかなり抑えられているとわかる。海外のメディアでは福島フィフティーという名の英雄として報道されたそうだが、悲しいかな、日本にいる私は、こんなにも果敢に事故対応してくれた人達の存在を全く知らなかった。 取り返しのつかない被害をもたらした今回の事故だが、「不幸中の幸い」に助けられた面が多々合ったのだとわかる。 前述の通り、現場の対応は正しかったし、事故の前線基地となる免震重要棟は事故のたった8ヶ月前に完成したそうだ。そして、最後の方で紹介される、吉田氏の生立ちいや人柄を知って、彼がこの事故のある時に福島原発の所長に就いていた事は日本の運命と言っても過言ではないだろう。 事故の当日に若いプラントエンジニア二名が命を落としていた事も今回初めて知った。放射能による影響ではなく、津波に襲われて命を落とし、その遺体は数週間も救出することができなかったそうだ。彼らもまた、放射能の危機から私たちを護るために行動した訳だが、一部では行方不明という情報が逃げ出したという噂に変わって、遺族の方に誹謗があったそうで、酷い話だと思った。 現場といえば、原発のサイトだけが現場ではなく、官邸には官邸の、東電本店には本店の現場が合った訳で、こちらの対応ときたら、情けないとしか言いようが無い。 特筆すべきは元首相の管氏。常軌を逸した態度で、その取巻きは情報をあげることもできなかった。彼へのインタビューも本書には納められている。彼の説明を聞けば、私は彼には彼の理屈としての正しさがあったと思う。しかし、私たちが政治に求めることは結果責任。今は非常事態。話す理屈は間違っていても良いから、現場を掻き回すべきではなしし、命をかけて戦っている人達に、「死ぬ気でやれ」と言い放って、気持ちを萎えさせることがあってはならない。 現場の人達の行動や思いにフォーカスしているわけだが、読者としては、最後には原発の是非について考えが及んでしまうだろう。 私が感じたことは、ここまでモラルと能力の高い現場を日本中の全ての原発に配置できなければ、いつかこれ以上の事故が起こると思わなければいけない、ということ。著者の指摘するように、想定以上の自然災害の可能性やテロの危険を消す事はできない。本を読んでいて、福島原発の人達の現場の能力やモラルは高かったと思うけど、そんな彼らですら10m以上の津波が押し寄せる事を全く考えらられず、なぜ電源が落ちていくのかわからなかった事実は大きい。 最後に、東電に対する不信感は拭えないが、事故当時にそこで果敢にも私たちを護ってくれたのもそこの東電の社員なのだと、そんな当たり前の事を思う。命懸けで戦った方々に、ただただ感謝。
9投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故に係わる、4つもの事故調の報告書に、 ルポルタージュに脱原発便乗本は、様々ありますが、 どれもこれもが、東京視点、ホワイトカラー視点で、 福島(現場)視点、ブルーカラー視点の書籍は、 意外とといぅか、ある意味、当然ありませんでした。 本書は、本年7月に、食道癌で亡くなられた 事故当時の所長であった吉田昌郎さんを始め、 現場で事故対応にあたられた方々へのインタビューを 元に構成された、現場視点、ブルーカラー視点での、 ノンフィクション(ルポルタージュではなぃな)です。 日本は、 ここまで、現場力、ブルーカラーの力によって、 経済大国へと成長してきた、技術立国ですが…、 現在、現場やブルーカラーは、むしろ虐げられ、 高層ビルの中で澄ましたホワイトカラーによる、 教科書的な政治や経営によって、競争に負けています。 しかし…、 人間は、極限の状態に追い込まれたとき、 その真価を発揮するものだ、と言われていますが…、 長く日本経済の成長を牽引したブルーカラーの真価と、 今の日本経済を操舵しているホワイトカラーの真価が、 その明暗が、くっきりとわかれた様子がわかります…。 もちろん、 遡って、吉田元所長が、原子力設備管理部長時代に、 想定を超える津波の可能性を示唆した評価を一蹴し、 その結果、津波対策が講じられなかったことも、 今回の事故被害の拡大の要因の1つでしょうが、 それらの問題点は、本書の中ではいいでしょう。 本書は、 あくまでも、地震(事故発生)から1週間…、 現場は、どのよぅな状況で、どのよぅに対応したのか、 といぅことを、日本人として「知る」といぅ意味では、 とても意義のある一冊であったと思います。 福井県出身の元土木技術者(自然災害・環境問題)で、 現在、ホワイトカラーの一人としてPCを叩いている 1個人としても、いろいろと考えさせられました…。 それにしても…、 福島の現場で、遺言や遺書を電話やメールに残して、 命がけで、事故対応にあたっている職員に対して、 東京の東電本店に乗り込んで、自分に悦に入って、 「命がけでやれ!」と演説ぶった、菅元首相や、 そぅ言わせた政府や東電幹部の無能が、哀れです…。 なお…、 副題は「吉田昌郎と」となっており、企画段階では、 吉田元所長を中心とした構成だったのでしょうが…、 病気療養との兼ね合いによる取材不足もあってか、 中央制御室の、伊沢当直長を中心とした構成であり、 吉田元所長の行動や証言は、肉付け的な内容でした。 また、副題は「福島第一原発の五〇〇日」ですが…、 内容は、事故発生(地震)から1週間が中心であり、 500日間の記録…ではなく、500日後の証言…、 といぅニュアンスが、正しいよぅに思います。 この点はちと商業的で、格を落としちゃってるかな。
0投稿日: 2013.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現場の人間の自己犠牲の精神に深く感銘を受けるとともに、改めて奮闘ぶりに感謝。絶対に忘れてはならない壮絶な記録。
0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011.3.11 東日本大震災による原発事故発生から数日間のドキュメント。原子炉を冷却するために戦った、東京電力社員・協力会社・自衛官らの活動を、彼らの心の葛藤とともに描いた。 「確かなのは、冷却のために水をぶち込むことしかなかったということです。電源復旧の道を探る一方で、私たちはひたすらそこを目指したわけです」(福島第一原発所長 吉田昌郎) 「東電というのは、”御殿女中”的な人間が多いと思っていたけど、吉田さんというのは、そういう人たちとは違う印象を持ちました。非常に個人としての考えがしっかりした男のように思えました」(原子力災害現地対策本部長 池田元久)
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログいや、すごい1冊だった。先日亡くなられた福島第一原発の吉田所長をはじめとした現場の人々と家族、東電幹部、首相、政府関係者、住民などの姿を通して描く原発事故の真実。細部にわたる取材とインタービューをもとにした文章は、簡潔でスリリングです。 たまたま同時に「小説太平洋戦争」を読んでいたのですが、太平洋戦争における日本軍と、今回の事故における政府、東電、現場の様子が、自分では予想もしていなかったほどシンクロして驚きました。上層部と現場の意志の疎通の悪さ、根拠ない楽観論、リーダーシップの欠如、そして上層部とは対照的な、現場の人々の目の前の仕事における強さ。近代日本が内在する根本的な特徴が、戦後約70年を経て、またしても現れたのでしょうか。 これから先も、不幸なことにまだまだ復旧には時間がかかりそうですが、猛烈な批判を浴びる原発事故の中にも、こういう現場の人々の壮絶な頑張りがあったことは、もっと記録されてよいことだと思います。
2投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ未だに汚染水漏れなど原発事故後の対応のまずさが心配で、東電のイメージは悪くなる一方です。 けれどもあの事故直後、原発と言うモンスターが最悪の状況に陥ることをまさに命がけで守ってくれた人々もまた東電の人達。 あの時何が起こっていたのかが克明に記されており、その過酷さを思い涙がこみ上げてしまいました。 その代表である当時の原発所長の吉田さんを始めとする職員のみなさん。そして関連会社、自衛隊、消防隊等々。懸命に闘ってくれたおかげで最悪の状況は免れました。感謝と共についに亡くなられてしまった吉田昌郎所長のご冥福を祈ります。
2投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2013.08.16読了)(2013.08.07借入) -吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日- 【東日本大震災関連・その125】 福島第一原発事故について、なかなか知ることの出来なかったことのわかるいい本でした。東日本大震災にともなっておこった福島第一原発の事故に関して、今までいくつかの本を読んできましたが、福島第一原発の現場の人たちはいったい何をやっていたのか、津波が来た時や発電所の爆発が起きたときにどうしていたのか、津波や爆発の際に被害を受けた人がどれくらいいたのか、といった事について、今まで読んだ本では知ることができずもどかしい思いをしていました。 この本には、福島第一原発であの時働いていた人たちに何があったのか、何を考え、何をしようとしていたのか、何をしていたのかということが詳しく書いてありました。 疑問が解消されて随分すっきりしました。 文句があるとすれば、本の題名です。題名からすると、本の大部分が事故当時の吉田昌郎さんの考えた事、命じたことで占められていると思ったのですが、逆にほとんど書いてありません。ほとんどが、第一線の現場で動いていた人たちの話です。 500日というのも嘘で、3月11日から3月17日ぐらいまでの1週間の話で99%が占められています。取材を開始したのが、震災から500日目ということのようなのですが、この表題から、そんなことが伝わるでしょうか? まいるなあ。 【目次】 はじめに プロローグ 第一章 激震 第二章 大津波の襲来 第三章 緊迫の訓示 第四章 突入 第五章 避難する地元民 第六章 緊迫のテレビ会議 第七章 現地対策本部 第八章 「俺が行く」 第九章 われを忘れた官邸 第十章 やって来た自衛隊 第十一章 原子炉建屋への突入 第十二章 「頼む! 残ってくれ」 第十三章 一号機、爆発 第十四章 行方不明四十名! 第十五章 一緒に「死ぬ」人間とは 第十六章 菅邸の驚愕と怒り 第十七章 死に装束 第十八章 協力企業の戦い 第十九章 決死の自衛隊 第二十章 家族 第二十一章 七千羽の折鶴 第二十二章 運命を背負った男 エピローグ おわりに 関連年表 参考文献 ●非常用電源オフ(57頁) もしかしたら、津波が来て、(四円盤の)非常用の海水ポンプのモーターに水がかかることがあるかもしれないと、考えていました。それでも、大きくても五、六メーターのものを考えてのことです。まさか、あんな十何メーターもの大津波が来るとは思ってませんでした ●午後四時五十五分(73頁) 原子炉建屋に入るところは二重扉になっていて、外と遮断されています。一つを開けて中に入り、それを完全に閉めないともう一方の扉が開かない形になっている。でも、もうその扉の前に来た段階で、持って行った放射能測定器が〝振り切れて〟しまったんです。 ●海水注入(100頁) 津波で散乱したおびただしい量の瓦礫やゴミをまず取り除かなければならない。しかも、原子炉建屋など重要な施設のまわりは、テロ対策のために厳重な柵で囲ってある。この柵を壊して、作業に必要な「道」を通すことが第一だった。 最初の水が原子炉に注入されるのは、明け方の四時頃のことである。 津波から十二時間余が経過し、ついに原子炉に水が注入されるのである。 ●菅首相、現地へ(158頁) もし、あの時点で、住民の避難が確認されてないからベントができないというんだったら、そういう理由をいえばいいじゃないですか。線量が高くて、なかなか作業が難しいんだとか、操作のマニュアルがどうしたとか、何らかの説明があるならともかく、そういうものが全然なかったんだ。 ●出るわけには(206頁) 「今、避難している地域の人たちは、われわれに何とかしてくれという気持ちで見てるんだ」 「だから……だから、俺たちは、ここを出るわけにはいかない」 ●海水注入(221頁) 「本店から海水注入の中止の命令が来るかもしれない。そのときは、本店に(テレビ会議で)聞こえるように海水注入の中止命令を俺が出す。しかし、それを聞き入れる必要はないからな。おまえたちは、そのまま海水注入をつづけろ。いいな」 ●死ぬ覚悟(274頁) 「円卓にいる幹部たちは、もう死ぬ覚悟をしていたと思うし、実際に、私は、彼らは最後まで残るべきだと思っていました。そういう気持ちで皆さんを見たので、吉田所長たちが死に装束をまとっているように見えました」 ●血尿(278頁) 免震重要棟のトイレは、真っ赤になっていた みんな、血尿なんです。誰もが疲労の極にありましたから ●フクシマ・フィフティ(278頁) およそ六百人が退避して、免震重要棟に残ったのは「六十九人」だった。海外メディアによって、のちに〝フクシマ・フィフティ〟と呼ばれた ●アラームが鳴ったら退避してください(300頁) 目の前には、不気味に浮かび上がった三号機があった。松井たちの線量計のアラームは鳴りつづけている。そんな中で、「外」に立って、自分たちの消防車を誘導している人間がいるのだ。 ●家族(317頁) 「お父さんは最後まで残らなくてはいけないので、年老いた祖父さんと、口うるさい母さんを、最後まで頼んだぞ」 「おやじ、何言ってるんだ。死んだら許さない」 ●チェルノブイリ×10(356頁) 格納容器が爆発すると、放射能が飛散し、放射線レベルが近づけないものになってしまうんです。ほかの原子炉の冷却も、当然、継続できなくなります。つまり、人間がもうアプローチできなくなる。福島第二原発にも近づけなくなりますから、全部でどれだけの炉心が溶けるかという最大を考えれば、第一と第二で計十基の原子炉がやられますから、単純に考えても、〝チェルノブイリ×10〟という数字が出ます。私は、その事態を考えながら、あの中で対応していました。 ☆関連図書(既読) 「原発労働記」堀江邦夫著、講談社文庫、2011.05.13 「緊急解説!福島第一原発事故と放射線」水野倫之・山崎淑行・藤原淳登著、NHK出版新書、2011.06.10 「津波と原発」佐野眞一著、講談社、2011.06.18 「前へ!-東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録-」麻生幾著、新潮社、2011.08.10 「亡国の宰相-官邸機能停止の180日-」読売新聞政治部、新潮社、2011.09.15 「官邸から見た原発事故の真実」田坂広志著、光文社新書、2012.01.20 「ホットスポット」ETV特集取材班、講談社、2012.02.13 (2013年8月18日・記) (「BOOK」データベースより)amazon 吉田昌郎、菅直人、班目春樹…当事者たちが赤裸々に語った「原子力事故」驚愕の真実。
0投稿日: 2013.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故で、現場で何が起き、現場が何を思い、どう闘ったのかを描いたノンフィクション。当時の吉田所長をはじめ、多くの関係者へのインタビューを通じて、地震直後からの事実が克明に書かれている。電源喪失がわかった時点で消防車による注水を想定した行動や、放射線が強い真っ暗な原子炉建屋の中にベントのために手動でバルブを開けにいく決死隊の行動、二号機の格納容器の圧力が高まる中での決断など、あとから知って驚くと共に、現場の人々の覚悟と奮闘に頭が下がる。官邸の様子も生々しく描かれており、そのお粗末な行動には怒りさえ感じられる。現代社会では極限状況に追い込まれる場面はほとんどないが、人間の素の姿がむき出しにされる場面も多く、興味深いものがある。
2投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙なくして読めない。特に終盤は。 吉田所長だけでなく原発処理に関わったいろいろな人が登場する。 進んで危険な所に突入する50代の当直長達。 命がけで作業している人たちに対し、「命がけでやれ!」と怒鳴り散らす当時の総理。 責任論ばかりで動こうとしない国の役人。 地下で津波に巻き込まれた21歳の若者と両親など。 吉田所長を中心とした福島第一原発の現場の人達は、物凄い執念で、時には政府の意見に逆らって原子炉と闘ったのである。 私達は「東電何やってんだ!」と言うばかりでなく、自分たちの問題としてどうするべきなのかを考えなくてはならないように思う。
0投稿日: 2013.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災と福島原発という絶望的な危機に文字通り命懸けで戦った人々の記録。そこには日本人の良い面と悪い面と両方を見ることができる。悪い面は主に後方にいる経営責任者たちだが。だからこそ、同じ日本人として現場で戦った人々に尊敬と共感を覚える。
0投稿日: 2013.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログよく「現場の作業員」と表現されていた人達。最前線で指揮を取った伊沢氏をはじめとし、多くの関係者の述懐で本書は構成されています。 あくまで現場に焦点を当てているため、政官業の責任を追求するような内容ではありません(ただ菅さんだけえらく悪者風に書かれてるようにも見えます)また現場の話も網羅的という訳ではありません。 あの日現場に残った人々の多くは、ただひたすらに事故を防ごうと、命を賭して闘っていた。彼らの執念こそが、最悪の事態を食い止めた。この本にはそういう事が書かれていました。死の恐怖をも乗り越えた、作業員の方々の誠の強さに、心から敬意を表すとともに、深く感謝します。
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「死の淵を見た男」というより「男たち」。吉田所長へのインタビューは2回4時間半とニュースで著者が言っていたので、本書でも本人の生の言葉の出番は少な目。90人もの関係者に取材して、事故直後から、福島第一原子力発電所の中で何が起きていたのか、電力会社の社員や協力企業、自衛隊の人たちがどういう気持ちで作業にあたっていたのか、遠く離れた官邸や「本店」で何が起きていたのかが描かれていた。 電力会社に入った人たちは、電力の供給を通して国や地域や消費者の役に立ちたいと思っていたと思う。その人たちが周辺地域を死滅させるような事故を、どう受け止めているのだろう、と思っていたので、気持ちが分かってよかった。 衝撃だったのは、吉田所長が事故直後すぐ、最悪の場合、「東日本」(福島だけじゃない)が「えらいことになる」と感じていたこと、作業員の拠点となった免震重要棟のトイレの小便器がずっと真っ赤だった(疲労でみな血尿だった)という描写、そして事故後4日後、必要な人員を残して撤退する場面、一度撤退してから再び現場へ戻る場面。残る、残らない、戻る、戻らないを任された人たちの究極の選択に胸が痛んだ。 決死の作業に感謝の気持ちしかわかないけれど、やはり現時点で、人間は原子力を高度にコントロールすることはできないのではないかと思う。また、現場から離れたところ、原子力行政、東電経営陣の動きや発言に「責任の所在」のなさを感じた。 門田節炸裂で、後半泣きっぱなし。労作でもあるけれど、現場の人たちの闘いに★五つ。事故はまったく終わっていないことを胸に刻みつつ。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田さんの判断が三分割になりそうな日本を救ったのだろう!更に前線で放射能に恐れながらも立ち向かった当直長、運転員に敬意を評します。
0投稿日: 2013.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログあの時、節電しながらも報道のテレビ番組は消すことができなかった、その時現場でなにが起こっていたのか。 本の名称にある吉田氏だけをフューチャーした訳ではなく、関係者からいくつかの視点のインタビューがまとめられたストーリー仕立てのルポ。 菅元首相も登場する。 知るためには、日本人として読むべき一冊ではある。 読み進めると、最後にいくつか筆者が論じる部分があったが、危機管理はされるものではなく、するもんなんだと改めて心に刻み込んだ。。そんな一冊。
0投稿日: 2013.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間ドラマとして表面的にはよくできているが,関係者から見ると分析があまいというかあまりに詳細の描写に欠けるのが残念である。 吉田所長のみにフォーカスをしてもっと深掘りしてほしかった。
0投稿日: 2013.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ東電福島原発事故、本当に多くの方々へのインタビューから当時現場で起こっていたことを明らかにするノンフィクション。 吉田所長を始めとする東電の社員、協力会社の社員、自衛隊の隊員。 普段あまり耳にすることのできない現場の方々の決死の努力と、死を覚悟した人間の強さや優しさを知ることができました。 切迫した場面での嘘偽りの無い言葉の数々に、何度も涙を流しました。 もちろんこの作品の情報のみで判断することはできませんが、官邸の過干渉とそれが現場に与えた悪影響は、当時言われていた以上だと感じました。 「一方が得をし、もう一方が損をする」状況で、大局的に判断をし調整するのが政治家だと思っています。 そうだとすれば、時の総理にその資質があったのか、甚だ疑問です。 この作品を読んでいる最中に、元総理が現総理を名誉毀損で訴えた、というニュースを目にしました。 この作品に書いてあることが事実だとすれば、なぜ訴えたのか理解に苦しみます。 まぁ、裁判の過程で事実が明らかになればよいですね。 高校卒業まで福島、以降ずっと東京にいる私は、この問題に関して正直抜群に微妙なポジションにいます。 意見を求められる機会もありますがいつも困ります、私もあそこで作った電気を使っていたわけですから。 しっかり勉強をして自分の考えを持つ、その考えに従って粛々と一票を投じる。 黙して語らず、が私のスタンスです。
0投稿日: 2013.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故での命を懸けた凄まじい現場の戦いを描いた一冊。 批判にさらされる東電のなかに吉田所長をはじめとした多くの人々が、国、仲間を思い自分の命がどうなるかなど顧みずに立ち向かっていたという現実を伝える素晴らしい本です。 奇しくもこの本を読んでいる最中に吉田所長がお亡くなりになりました。 国を守って頂いたことへの感謝とご冥福をお祈り申し上げます。
0投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田昌郎さんへの感謝を込めて。 主人公は吉田氏だけではなくいわゆるFUKUSHIMA50と言われる人たち。東電本社はともかく現場の人たちは限られた条件の中で出来ることはした。よくあの状況の中で自発的に必要な判断を出来たと思う。 一例に挙げると福一を最悪の事故から救ったのは津波と全電源喪失直後に1号炉に冷却ラインを作り消防車の応援を呼んでいたことだった。事故直後の報道ではわからなかったが吉田所長の最悪の想定はチェルノブイリの10倍の規模の放射能漏れであり、班目氏はさらに福島第二と東海原発への連鎖まで想定していた。彼らは専門家でありその想定は重い。しかし、全電源喪失については防げる事故でもあったのが残念だ。 一号、三号が爆発した3月15日の明け方席に戻った吉田所長はゆらりと立ち上がり、机と椅子の間に胡座をかき目を閉じて座り込んだ。その時周囲の人間はプラントの「最期の時」を感じたのだが、吉田は腹を決めている。「私はあの時、自分と一緒に”死んでくれる”人間の顔を思い浮かべていたんです」「やっぱり、一緒に若い時からやってきた自分と同じような年嵩の連中の顔が、次々と浮かんで来てね。頭の中では、死なしたらかわいそうだ、と一方では思っているんですが、だけど、どうしようねぇよなと。ここまできたら、水を入れ続けるしかねぇんだから。最期はもう、(生きることを)諦めてもらうしかねぇのかなと、そんなことをずっと頭の中で考えていました」 その吉田にテレビ会議で管が言う。「事故の被害は甚大だ。このままでは日本国は滅亡だ。撤退などあり得ない! 命がけでやれ」「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる。逃げてみたって逃げ切れないぞ!」 逃げる?誰に対して言ってるんだ。いったい誰が逃げると言うのか。(なに言ってんだ、こいつ) 厳しい批判を受けた中では班目氏はどうやら限られた情報の中で想定される事態を把握していたようだ。少なくとも官邸に対しての助言は間違ってはいない。しかし、どうしようもなく当事者意識が無く官邸が自分の言うことを理解しなければどうなるか薄々わかっていながら怒れる管に何も言えないでいた。伝わらなければ正しいことを言っても意味が無い。 最終段階では出来ることはないとわかっていても残ろうとした若者もいた。残ってくれると信じていたが退避したものもいた(彼らを責めるのは筋違いだが)。そして新潟から応援に来てそのまま残った協力業者もいた。一旦退避してから戻って来たものも多い。「ヤクザと原発」によれば協力業者の中には必ずしも使命感だけで残ったのではなく、その場のノリで残ったものもいる。それもこれも含めて彼らに救われたんだろうと思う。 個人的には今でも使える原発は使うべきだと思っています。例えば原発安全神話と温暖化は怖くないというのは対象が変わっただけで構造的には変わらないし、石炭は私の理解では原発以上に明らかに健康や安全に対してマイナスだし(例え高効率の発電が出来、PM2.5が解決できたとしても採掘事故の問題は残る)、単純に燃料費が上がるという経済的な損失も人によっては直接健康や安全に危害を及ぼす。それでも原発を無くしたいと言う素直な感覚は理解できるし、それを否定する気はない。いろんな問題をイノベーションが解決するかもしれないがまだ時間はかかるし、その上で何を選択するかということだろう。今後日本で新しい原発が稼働できるとは思えないので当面は天然ガスに頼り再生可能エネルギーのイノベーションを待つというのは一つの答えだと思う。その間のトレードオフを理解した上で原発を止めるというのはそれも一つのもっともな選択だ。
0投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災時に、福島第一原発の所長であった吉田昌郎氏へのインタビューをもとに、あの時の現場の状況を克明に記録したノンフィクション。吉田氏がお亡くなりになった今、我々が知りうる最も現場に近い状況を伝えてくれる本となりました。著者の門田氏も、7/9のNHKニュース9や、報道ステーションでコメントされておられましたが、あの時現場で指揮を執られた吉田氏にこそ、今後の原発の安全性など貴重な意見を発信していただきたかったと思います。「決死隊で臨む」、「一緒に死んでくれる人の顔を思い浮かべた」等の言葉が、いかに過酷な状況で発せられた言葉であったのか、この人の言葉であるからこそ我々にも伝わってきます。
0投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログフクイチは磐城飛行場跡地だったのか。◆◆吉田所長じゃなければ、うまくいかなたったかもという気もするが、事故前に打てる対策がどうだったのか。ドラマ仕立てになっているぶんだけ、割り引かなければならない。
0投稿日: 2013.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ苦難の場面で、吉田所長をはじめとする現場の管理職、若手、関連会社の職員、自衛隊員が、事故対応への覚悟や家族への思いをどのように抱いていたかを聞き取り、細かく描いている。だから、読者として、「自分がこの場面のこの立場におかれたら、どんなことことを思い浮かべ、どんな思い残しを持ち、その思い残しをどう断ち切るだろうか(あるいは断ち切れないだろうか)」といったことを、いろんな章の中で考えた。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ甚大な被害を出した3・11の地震、津波による原発事故の現場を描いたノンフィクション。 いったい現場で何が起こっていたのか。 現場の最前線で命がけで立ち向かっている人たちのこと。 その人たちを前線に送りださないといけない人たちのこと。 現場の極めて限られた情報の中で、懸命な計画し実行していったか。 東電本社と現場の温度差。 政府の対応。 総理の体たらく。リーダーとしての資質。 被災者、そして家族は。 いままで災害に対する準備と対応はどうだったか。 生死の間際でどのように人は考え行動するのか。 様々なことをこの本は自分にぶつけてくる。 日本人は絶対読むべき本だ。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇しくも第23回参議院選挙の公示の今日、この本を読み終えた。もしかすると「過去のこと」と思われている東日本大震災と福島原発の被害。我々日本人はその時何があったか、知り得るだけの事実を認識した上で選挙に望む必要があると考える。そしてこの一冊は全国民が読むべき書だと言いたい。 原発への関わりの有無にとらわれず、日々の信頼関係が構築された仲間と達成目標を共有できた絆の強さと、立場だけで発言する人々との繋がりの弱さを読み取った。果たして今の自分はどういう環境で仕事が出来ているのか考えさせられた。
0投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログふと古本屋に立ち寄ったら、目立つように置いてあり、そのまま吸い込まれるように手に取った本 脱・原発論(小林よしのり)以来、原発に関する本を読んでなかったし、吉田前所長らのインタビューから出来上がった本ということで非常に興味があった あの当時は知識もなくテレビの情報だけで、物事を判断していて東電何やってるんだという物の見方しか出来なかった 現場の人がどれほどの思いで行動をしていたかも想像出来なかったし、全ての責任が東電にあるような気がしていた けれど、実際に責任があるのは日本に住んでいる人全員なんじゃないかと最近やっぱり思う 知っておくべきことを知ろうとせず、我関せず…それが一番罪。 とりあえず、知ろうと思う気持ちのある人に読んでほしいと思った
0投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログつらいのか、苦しいのか、感動してるのか、または申し訳ないという気持ちなのかわからないけど、のどの奥から胸にかけて、痛くて痛くて泣けてしまう一冊だった。人間の、日本人の底力。生きる、働く、という意味。生と死の意味。家族、仲間。大切にしなければならないすべてのことが、ここにあった。そして最後に、福島原発で闘ったすべての人々と、この本の刊行にかかわったすべての人々へ。「ほんとうにありがとうございます」。
0投稿日: 2013.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故に立ち向かった、吉田所長を始めとする多くの人びとを通じ、あの時そこで何が起こっていたかを明らかにするノンフィクション小説。 不完全な安全対策のまま稼動している原発を地震、津波が襲った時から500日の間、そこにいた人々が何をしてきたか。そして、何をしなかったか。 そもそも原発を使うべきか、作るべきかという議論、充分な安全対策がとられていたかという議論は別にして、その時、その現場で事故対応にあたった人びとは、原発を救い日本を救うことだけを考え、最善の努力を果たしてきたのだと思う。 自分が死を覚悟し作業にあたるだけでなく、自分が命じる仕事が、死を意味する可能性がある。そのような決断を下す時、人間の覚悟が見えることがあるのだろう。 また、本書は図らずも福島の現場とは距離をおいて、既存の利益、企業を守ろうということだけに汲々とする東電関係者、政府関係者そして職場を放棄して逃げ出した保安検査官の姿も描き出している。それら犯罪者の罪は決して見逃されていいものでは無い。
0投稿日: 2013.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて、当時の政権および東京電力の上層部に対する不信感と、今もなお原発を推進しようとする自民党政権に敵愾心を持った。
0投稿日: 2013.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
原発事故の現場の様子を、実際の現場の方々に取材して文章化した作品。 原子炉に一番近い人たちの「見たこと・考えたこと・やったこと・感じたこと」が書かれていて、『矜持』という単語がふさわしいと思った。 大きな山火事とかがあって数日間も燃え続けるニュースを見たことがあるんだけど、火事は、一応、鎮火するものだ。 しかし、今回の福島原発で起きた「事案」は、まだ鎮火していないのだ。 どうも、鎮火したようなイメージがあったりするが、今でも「見えないナイフ」をまき散らしており、何十年先まで続く。 しかも、ちょっと何かあれば、そのナイフが膨大な量になって、日本の存亡を揺るがすかもしれない状況のままだ。 見えないからなのか、もう慣れてしまったのか、それとも大ごとではないように思わされているのか、ということはさておき、 あの時に感じた反原発の意識は薄まりそうになっている。怒りの気持ちを維持するチカラが低下している。 http://blogs.dion.ne.jp/kenrisa/archives/2013-03-1.html
2投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故の現場をその場にいたものたちのインタビューを元に描いたノンフィクション。あのときの現場の状況がよくわかる。吉田所長以下の現場社員の言葉が重い。 正確な情報がない中で、死を意識しつつ、最悪の事態を避けることを第一に考える。死を覚悟するというのではなく、ここで何かが起きるのであれば、自らは死ななくてはならない、という意志があったのではないか。 著者が「その時のことを聞こうと取材で彼らに接触した時、私が最も驚いたのは、彼らがその行為を「当然のこと」と捉え、今もって敢えて話すほどでもないことだと思っていたことだ」(P.373)とある。一方それは、分かるような気もする。 当事者であるということは、そういうことではないだろうか。
2投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログあの震災から二年が経った。いまだ収束への出口が見えない福島原発。震災直後の人々の奮闘、そしてそこにあった迫る危機を伝えている。 後半は、何度も涙が出てきた。
1投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も何度も、あふれてくる涙をふきながら読み終えた。正直言って、3.11の地震から生じた原発事故について書かれたこの本を、「迫真のドキュメント」とか「感動のノンフィクション」とか述べる資格は、体文自分にはないのだと思う。だけど、とにかく読んでおいてよかった、と心から思う本であった。 同じ立場であったら同じことができるだろうかと考えると、到底そうは思えない。だけど、心の中のかなりの部分が、自分に任された仕事を全うすると言うことについて、自分を確かめられるような気がする。能力としてできるかどうかはわからないけれど、気持ちとしては同じ何かを自分の中に思う。 だから、危険極まりのない状況の中であがき続けた男たちに対してと同じくらい、そこへ戻ることを30分かけて決意した若者に対してシンパシーを感じるし、心を打たれる。自分自身を振り返って、あれこれと考える。 野球選手だけではない、こういう人たちにこそ国民栄誉賞をと思う。でも、実際にそうしようと思うといろいろ難しいのだろうなってことはよくわかる。せめて、こういう本がたくさん読まれるといいなって思うのだ。
2投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発事故が大惨事なるのを体を張って食止めた壮絶な戦いの物語。 このまま生まれ育った故郷を更には国を捨てるか、それとも自分の命を懸けて事故現場に突入して、これ以上の災害を食止めるかの究極の選択となる。 その中で強い使命感の下、吉田昌郎氏、伊沢郁夫氏、消防員、自衛隊員のリーダシップと使命感に脱帽するばかり。 もし、自分が吉田あるいは伊沢の立場になった時に同様な命を賭けるような行動が取れるだろうか。
1投稿日: 2013.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
福島第1原発の事故に関する著書などは数多く存在すると思う。 しかし、この「死の淵を見た男」は小説風に仕上げられたノンフィクション・ドキュメンタリーで、今まで報じられなかった影の部分を巧みに描写している。 特にコントロールルームで繰り広げられる原子炉との攻防は、実話だけに関わった方々の苦悩を肌で感じることが出来た。 全電源を喪失したため照明はもちろん落ちている。 計器類が動作しないため、必要な情報はバッテリーを直接計器につなぎデータを取る。 普段は電動で動かすバルブ操作は、人間の手によりハンドルを廻して行われる。 爆発するかもしれない格納容器の恐怖におびえ、大量の放射線を浴び懐中電灯をかざして行う作業。 吉田所長以下、チーム一丸となって作業にあたるさまは頭が下がる思いだ。東電の職員のほか協力会社や自衛隊の皆さんの勇気がひしひし伝わってきた。 また亡くなった職員2名のことも今回始めて知った。 特にむつ市出身の21歳の若者の死には心が痛んだ。 地元の工業高校を優秀な成績で卒業し東電に入社、配属先は建設中の東通原発。 完成を前に福島第1と第2の原発で研修を受けていたとのこと。 たまたま低い場所で点検作業を行っていたら予想をはるかに上回る津波に襲われ、その若い命を失った。 もっとつらいのは、彼らが現場から引き上げられるまでの数週間ずっと海水に漬かっていたこと、そのことがネットでは「現場から逃げ立ち去った」と噂され誹謗中傷を受け、遺族や関係者に心の傷として残っていることなど、気の毒としか言いようがない事柄が綴られている。 この著書でも批判の矛先は菅総理(当時)に向けられるのだが、まぁ普通ではない総理の言動は読むに値する。 いずれ、今まで知らなかったこと、マスコミが報じていないことなど、多くのことを知ることができたし、多くの人に触れて欲しい本である。
1投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ3.11のあの瞬間からの現場での東電社員の闘いはネットで見聴きしていたが、消防団員や自衛隊員の必死の冷却が効かなければチェルノブイリ事故の10倍もの被害があっただろうことを、リーダーの吉田さんが仰っていたことに身の毛がよだった。 吉田さんの早い判断と、死ぬ覚悟を決めた人たちの努力は、今になれば報われたわけだが、一つ間違えば大惨事だった。 そんな中、当時の首相である菅氏の言動は、現場の人たちの足を引っ張っていたわけだからバッシングされて当然であった。 撤退したら東電は百パーセント潰れる。逃げてみたってみげきれないぞ! と仰った菅氏の言葉に、 なに言ってんだ、こいつ ・・・・現場の人々は、すでに命がけで格闘している。 撤退するということは、もうだれも制御する人がいなくなるわけで、 そんなことをする考えなぞ言語道断である。 亡くなった若い命もあった。 まだ21歳の青年のご両親の話は読み進めるのが辛かった。 人間が制御しきれないものを、人間は抱えている。 原発は、地球上からなくならないだろうと思う。 またこういうことが起きるような気がする。
0投稿日: 2013.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ・一号機は二日前に爆発している。今度は三号機での爆発である。「次」は二号機だというのは、誰しもが考えることだった。 「こっちも(線量が高くて)交代に行けないことが、苦しくてたまらない。それで、”ちょっと待ってくれ”とホットラインで言った時に、自分はどうなっちゃうんだという思いが向こうにはあったと思います。それで電話の向こうから、涙で声を詰まらせて、覚悟したように、”伊沢さん。交代、来なくていいですよ”って言われたんです」 来なくていいですよ――その言葉が、伊沢の頭に谺した。 「いや、いま行けないだけだから」 伊沢がそう言うと、電話の向こうは一瞬シーンとして、 「もう、いいですよ…いいですから、伊沢さん」 … 「まだ許可が下りてなかったんですけど、私、しびれを切らしちゃって、もう中操の人間が精神的に耐えられない、線量がどうのこうのじゃなくて、私は行きますからと言って、許可を得ないまま四人だったか、五人だったかで、中操に向かったんです」 四、五人で車一台に乗り込んだ伊沢たちは、中操に向かった。 「中操に入っていったら、そいつが、もう泣いてました。バツ悪そうに。私は、黙ってマスクの上からゴンって殴りました。なんていうか、やっぱり、交代に来てくれるって嬉しいんですよ。人間ですから」 ・ビン・ラディンは自然災害とは関係がない。彼がおこなったものは、テロである。だが、およそ三千人もの犠牲者を出したこのテロは、原子力発電に対しても、大きな警鐘を鳴らした。 予想を超えた規模のテロは、原発に対する最も大きな脅威であることを人々に知らしめたのである。アメリカの原子力関係者の動きは素早かった。 ただちに、テロ対策を強化し、その中で、「すべての電源を失った場合、原子炉の制御をどうするか」ということが、以前にも増して議論されることになった。 そして、五年後の2006年、アメリカの原子力規制員会が対策のための文書を決定し、それは日本にも伝えられた。 その中には、全電源喪失下の手動による各種の装置の操作手段についての準備や、持ち運び可能なコンプレッサーやバッテリーの配備に至るまで細かく規定されていた。 そう、読みながら、911のテロの事を考えていた。あれはアメリカの国に与えた衝撃だった。東日本大震災は特に福島悲劇を起こし、日本に与えた衝撃はとても大きいものだったけれど、多分にアメリカの911が自分のものと感じられないように、後の世代やアメリカを含む海外にとって、東日本大震災も、ヒロシマナガサキの原爆も、一つの知識でしかあり得ないのだ。 演劇理論のスタニスラフスキー・システムでは、自分の経験から役の感情を引き出し、役を生きる。それはジョーゼフ・キャンベルの言う、インドラの網だ。すべての網目に宝石があり、それが隣合う宝石のきらめきを映しこみ、世界を形作っている。 それにしてもというか、やはりと言うべきか。現場ではこんなに壮絶に死と、それよりももっと大きなチェルノブイリの10倍になるかもしれない大災害という絶望と、向き合っていたのか。東京電力の上層部は慙愧の念を持つべきだ。
1投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ何がいけなかったのか…。現場は命がけで対応した。現場はいつも懸命だ。利権…倒すべきものはその考えなのではないのか。
0投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や殆どなかった事にされているが、福島原発事故対応の真っ只中の3月25日に内閣府の原子力委員会が作った、いわゆる「最悪のシナリオ」という文書がある。 (http://www.asahi-net.or.jp/~pn8r-fjsk/saiakusinario.pdf) ここでは、水素爆発で1号機の原子炉格納容器が壊れ、放射線量が上昇して作業員全員が撤退したと想定。注水による冷却ができなくなった2号機、3号機の原子炉や1~4号機の使用済み燃料プールから放射性物質が放出され、強制移転区域は半径170キロ以上、希望者の移転を認める区域が東京都を含む半径250キロに及ぶ可能性があるとしている。 これを間一髪で防いだ、吉田所長と「フクシマ・フィフティーズ」と呼ばれた作業員のドキュメンタリー。 2号機が破裂寸前の絶望的な状況の中で協力会社と部下に礼を述べ避難を促す場面、本店に乗り込んだ菅元総理の演説が流れるテレビ会議のモニターに尻を向けてズボンを履き直す場面、この二つは吉田所長の人としての大きさを良く表した名シーン。 この人たちの命懸けの働きには、本当に頭が下がる。 しかし、ベント実施のための奔走に前半の多くのページを割いているにも関わらず、肝心の実施の瞬間が描かれていないのはどうしたことだろうか? このドライベントこそが、格納容器の破損を避けるためとはいえ大気中に放射能を人為的にばら撒いた行為であり、せめてこのとき適切な避難指示がされていれば飯舘村や浪江町の大量被曝は防げたというのに。 だからこそその瞬間に何があったのかをとても知りたいと思う。
0投稿日: 2013.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログあの時、福島第一で何が起きていたのか? 間違いなく後世まで語り継がれれるであろう、あの事件の全貌を知りたくて手に取った本。極限的状況下でベストを尽くしやるべきことを果たした人々の記録。 ノンフィクションとしては、筆者の心情が前に出過ぎていると感じられるところがあり、それが少し惜しまれる。これは、個人の好みの問題かもしれないが。
0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにボリュームのある本を読了。 みなさんの記憶にしっかりと刻まれている、3.11の東日本大震災での福島第1原子力発電所の事故に関する、当時の模様のノンフィクション。おもに当時の所長である吉田昌郎氏にフォーカスを当てて書かれたものだ。私は本書を読むまで知らなかったのであるが、事故から8か月後に食道癌(ステージ3)、その手術から7か月後に脳出血に見舞われており、その事故の対応たるや、想像をはるかに超える凄惨なものだったに違いない。 本書は、地震発生から暴走が止まらない原発に対して冷却をかけるまでのわずか1週間くらいの様子が克明に描かれている。筆者の取材力も相当なものだったろう。 本を通しての感想を一言で述べると、現場と本社(東電の場合は本店)・官邸との温度差である。とくに時の首相である管直人の愚行は、あるいは罪人である。詳細は本書を読まれたい。 印象的だったのは、原子炉に対する海水注入の意思決定プロセスだ。当時、マスコミでは本店の意見が報道されたことを記憶している。それは、「海水を注入すると、塩のせいで廃炉せざるを得ないから慎重に判断すべきだ」という内容の報道だ。しかし、現場では吉田所長(当時)が本店の意見を聞く前に海水注入を進めていたことである。これは彼が「全電源喪失のために冷却装置が動かないとなると、海から水を引っ張って冷却せざるを得ない。さもないと人間の力ではコントロールができなくなりチェルノブイリの10倍の被害につながる」と現場での肌感覚で独断で進めていたものだ。これがなかったらさらに大きな被害をもたらしていた可能性があることは否めない。 日常の仕事においても、このような大きな意思決定の際に、どうしてもトップダウンの力が大きくなることが多いように感じられるが、現場の意見に真摯に耳を傾ける姿勢というものを大事にしたいなと考えさせられた。 最後に、残念ながら事故発生直後に4号機の点検で地下に下りて行った若い命が2つ、亡くなってしまったそうだ。彼らの冥福をお祈りいたします。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災直後には原発事故を書いた本が多かったが、この本は1年半以上後に出版。その分だけ、当時の報道に頼らず、関係者の証言、思いを中心に書かれている。 原発の是非はともかく、このような命をかけた使命感を持った人間、そして自分の心の葛藤を感じながら、仲間の絆のために原発に残った人間がたくさんいたこと、そしてそのことで、原発の最悪の危機が回避され、今の日本、もっと言えば今の自分があるのだと感じた。 彼らを駆り立てたものはなんだったのか?軽々に赤の他人が論じることは失礼あたると思うが、プロとしての矜持と仲間を助けたい、役に立ちたいという絆なんだと思った。 そして、こういう事故やイレギュラーな事象が発生した時は、現場の第一線の人間の知恵や工夫が一番であり、机上の議論をしがちなお偉方では判断を間違うのだということを改めて感じた。
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ震災以来2年が過ぎ忘れかけていた当時の記憶がよみがえってくる。 極限状態の現場で、使命感と仲間への想いから決死の作業に取り組み、日本列島を破滅から救った人びとの行いは、これからも語り継いでいかなければならない。 不作為と怠慢によってこの危機をもたらした政府、東電経営陣の責任を厳しく糾弾すると同時に、先の大戦でも明らかであった、ありのままの現実を見ることなく、希望的観測と身内にしか通用しない論理を振りかざすことによって全体に対する多大な損害を及ぼす構造を、今後いかに変えていくかを相当の覚悟を持って議論していかなければならない。
2投稿日: 2013.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に多くの人にこの本を読んで欲しい。原発の是非ではなく、事故の背景にはどんな思いで、覚悟で闘っていたのかを知って欲しい。読めばきっと、軽々しく批判することなんてできないと思う。現場の命を懸けた行動を認めて欲しい。
3投稿日: 2013.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ最悪の事態を食い止められたことを成功と捉えており、原発事故の裏で行われていた対策について複数の人にスポットを当てて比較的淡々と綴られた記録的書。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ前代未聞の事故の現場にいた人たちの戦いを描いたもの。タイトルと内容が合ってなかったり、一つの読み物としてはまとまりがない印象があるが、これも病気悪化により吉田所長へのインタビューが途中となってしまったためだろう。 しかしそうした欠点を補ってあまりあるくらいの内容で、地震直後の混乱から事態が悪化するにつれ増す緊迫感が生々しく描かれいる。 誰もが勇敢な行動をとれるわけでもないなか、それでも覚悟を決めて事にあたった方々への感謝と尊敬の気持ちでっぱいになった。
3投稿日: 2013.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田昌郎 こういう男がいたのだ 52才(2011.3.11) 大阪教育大学付属天王寺 東工大 逃げない 184CM、85kg 追い込まれた時、あぐらをかいてすわった その後横になる 突き抜けた時に人間はどう行動するか 菅外貨に人間としてリーダとして最低の人間かよくわかる。 そもそもそういう資質のない人間が総理になる事自体おかしい しかしその資格チェックのあとで総理を選ぶということはできないものか 安倍もダメだ。今その資格のある人材が政治家にいるのか
0投稿日: 2013.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本を救った人たちが克明に描かれている。 現場の力は凄い。本当に頭が下がる。 自分はメーカーで勤務しているが、現場至上主義は行き過ぎはよくないが、逆に軽視される傾向もどうかと思うことがある。 震災時、自分は本社で精一杯のことをやり続けたが、皆も精一杯のプロフェッショナリズムを発揮したと信じている。 久々にラインが稼働したときの現場の方々の話を聴いたことをよく思い出す。 ホワイト、ブルー・・難しい。 いずれにせよ、身を削りながら日本を守ろうとしてくれた方々に感謝したい。 吉田元所長が一日も早く回復されることを心から願う。
0投稿日: 2013.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのタイミングでこの本を読む機会が得られたことに感謝を表したい。 震災から2年が経とうとしているが、僕の中であの日の記憶がもう薄れてきている。 不謹慎ではあるが、しかしこの本を読むと東電の従業員が自分の命を 犠牲にして僕ら日本人を守ろうとしてくれていたんだなと思うと、 僕はこんな生活をしていていいのかと自問せざるを得ない。 福島原発事故がどのようにして悲惨な事件へと変わっていったのか? 僕はこの本を読むまで全く知らなかった、あるいは忘れていた。 地震による影響というよりは、地震の後の大津波が甚大な被害をもたらした。 そして電源もまったく使用できない中で、原発プラントの中に優秀な、 本を読むまで知られることのなかったヒーローがたくさんいた。 メルトダウンという最悪の状況を避けるために彼らは最大限努力をしていた。 その中で若くして亡くなった従業員もいて、本当に胸が痛くなる。 あの状況がもし自分の前に立ちふさがった時、 僕は同じように命をかけて原発の暴走を止めようとしたのだろうか、何度も何度も考えた。 死の間際に人間が悩み、葛藤に悩まされながらでも懸命の作業をしていたのだ。 一方では東電の福島第一原発元所長の吉田さん、 原子炉一・二号機の中央制御室の当直長であった井沢さんのリーダーシップも見事だった。 難しい選択も自分で行わないといけない状況にあって、 でも決断するありさまは素晴らしかった。 対する国の最高責任者であった菅元首相のふがいないリーダーシップが あまりにも皮肉に写る。 いくら現場から情報が上がってこないとはいえ、見ていられない醜態だった。 首都圏の電力の大部分を供給してきた、福島原発。 地元経済を活性化させるために工場誘致を行って一時的には 経済が良くなった福島の地域も、あの地震で起きた負のダメージがあまりにも大きい。 原発を誘致した町長、絶対神話を貫き通した政治家・官僚のために 甚大な被害を受けたのは原発地域の住民だった。 これでいいのか?負担を彼らだけに負わせて本当にいいのか? 原発の廃炉に向けてこれから40年もあるはずだ。 使用済み核燃料の廃棄場所もまともに決まっていない。 一方で汚染水は今時を刻む一秒一秒も膨大な量で増えている。 ああ、僕には何ができるのだろうか?
0投稿日: 2013.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者が「あの時、何が起き現場が何を思いどう闘ったか、その事実だけを描きたいと思う」と書いていました。私もそれが知りたかった、そして知ることができた。
0投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログマスメディアでは報道されない、東日本大震災時に原発と戦った東京電力のスタッフ達の本当の話しがここにある。まだ終わったわけではないけど、ギリギリのところで命をかけて戦った現場のリアルな話しは知っておかなければならない。
0投稿日: 2013.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログあの福島の原発事故が甚大な被害をもたらしたのは言うまでもないが、それでもあそこで食い止めることができたのは、ひとえに、あの現場で、文字通り命を懸けて闘い続けた人々がいたからだ。 彼らがいなければ、今頃日本は、人間の住むことができない国になっていたかもしれない。 刻一刻と惨状が伝えられたあの現場の中、決死の覚悟で闘っていた人々がいたことはわかってはいたが、人間の限界を超える過酷な状況にありながら、こんなにもすべてをなげうって使命を果たそうと体力と気力の限りをつくしてくれていた、その事実を改めて目の当たりにして、胸が震えた。 原子力安全委員長の斑目氏が、委員会の廃止に際して語ったというこのことばを、決して忘れてはならない。 「原子力安全を確保できるかどうかは、結局のところ”人”だと痛感している」 どんな先進技術であっても、必ず最後は人の手に委ねなければならないなら、制御できないものに頼るべきではないと、やはり思う。 誰かがやらなければならない。その誰かは、ロボットでもなんでもない、家族があり夢があり思いがあり喜びも悲しみもある、命ある人間なのだから。 そのことを忘れてはならない。
1投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発事故の記録。世界最悪の原発事故に向かう巨大なプラントに立ち向かった人達の記録。原発の是非を考えるのも大事だが、地域の為、日本の為に自らの命を顧みずに働いていた人達の活動を知る機会になった。日本人の仕事に対する誇りの高さが印象的だった。
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災における福島第一原発の現場で、死 を覚悟しながら事態の収拾に全力を尽くした方々 のノンフィクション。実際亡くなった方も含め て、このまさに懸命な努力と賢明な判断、そして いくつかの運がなければ、日本という国は一体ど ういうことになっていたか。想像を絶する状況の 中で対応された方々に頭が下がると同時に、そら 恐ろしい。
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東電の対応を東電側の視点から描いたこの本。震災、原発関連の本を読むたびに心が痛み、自分の無力さを想いが、この本も例外ではなかった。一般的には原発事故で非難を浴びている東電だが、この本を読む限り、そんな東電の人たちを非難することは出来ないと思ってします。現場で命をかけて対応にあたってくれた多くの人たちがいたからこそ、今こんなところでのんびりとPCでレビューを書いていられる訳で、その存在を無視していけないと強く感じた。いけないのは東電の仕組みや、これまでそれを放置してきた行政などであって、当時の現場職員には落ち度はなかった、むしろその非難を一身に背負いながらまさに命がけで戦ったとうことがよく分かる。被曝された方、避難された方にとってみればそれを死闘だとか、命がけだとか思えないだろうが、少なくともそれを客観的に見ている自分には東電やそれに協力した人々、特に吉田所長に敬意を表したい気持ちになる。最後にこの事故の最悪の想定をチェルノブイリ×10と表現していたこと、日本は分断される可能性があったということが書かれている。可能性としてはその程度はあっただろうと思うが、現場責任者の言葉としてはとても重いものを感じ、背筋が凍る思いだった。まだまだ原発事故への対応は始まったばかりだが、こうした現場の一人ひとりに思いを巡らすことが必要だなと改めて痛感した。
0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発における、東電の現場の方に心からの尊敬と感謝。彼らが命を張って僕らを守ってくれたから、今の生活がある。暴走する原発という強大な敵に知恵と勇気で立ち向かい続けた、強靭で純粋な精神が彼らにはあった。
0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、福島第一原子力発電所の事故の発生直後から最悪の事態を脱するまでの、「【本書 はじめに より抜粋】現場がどう動き、何を感じ、どう闘ったのかという人としての姿」を当事者達への取材によりあきらかにしたノンフィクションです。 そのため著者は、「【本書 はじめに より抜粋】本書は、原発の是非を問うものではない。(中略)なぜなら、原発に「賛成」か「反対」か、というイデオロギーからの視点では、彼らが死を賭して闘った「人として」の意味が、逆に見えにくくなるからである。私はあの時、ただ何が起き、現場が何を思い、どう闘ったか、その事実だけを描きたいと思う。」とも著しています。 私は、この事故で「日本は故郷の一つを失った。故郷に帰りたくても帰れない。これがどんなにつらいことか。想像を絶する。」そう思っていました。 しかし、本書を読了してそれが誤りを含んでいたことを知りました。 日本はまだ、故郷の一つを失ってはいなかったのです。現場では、故郷を・この国を護るという強い意志を持ち、大きな被害を出しながらも最悪の中でも最悪の事態を命を賭して防いだのです。 そこに強い意志があるかぎり、必ず福島にも未来がある。そう感じずにはいられません。 また、「福島第一原子力発電所は紛れもなく戦場そのものだったのだ」ということも知りました。 ・死直面した状態での優しさ・思いやり・覚悟・迷い・使命感 ・自分たちが闘いに敗れた時には国が滅びるという重圧 ・死地に赴くためにリーダがくだす判断・人選と、それに応える部下 ・大切な人を・故郷を・母国を護るという自然発生的な思いと誇り ・土壇場で発揮される底力と信念 一人ひとりの取材で現場の人々の口から語られる言葉は、かの大東亜戦争での兵士の言葉と酷似していました。 今も目に焼き付いている水素爆発で建屋の屋上が吹き飛んだ映像。あの瞬間も、その建屋のすぐそばで、死地に赴く闘いが続けられていました。 【本書抜粋 福島第一原子力発電所所長 吉田昌郎】 (前略)単純に考えても、”チェルノブイリ×10”という数字がでます。私はその事態を考えながら、あの中で対応していました。 だからこそ、現場の部下たちの凄さを思うんですよ。それを防ぐために、最後まで部下たちが突入を繰り返してくれたこと、そして、命を顧みずに駆けつけてくれた自衛隊をはじめ、沢山の人たちの勇気を称えたいんです。 本当に福島の人に大変な被害をもたらしてしまったあの事故で、それでもさらに最悪の事態を回避するために奮闘してくれた人たちに、私は単なる感謝という言葉では表せないものを感じています。 --- そう語る吉田氏は、事故から八ヶ月後に食道癌の宣告を受けています。さらには、それから一年も経たないうちに今度は脳内出血を起こし、今も闘病生活を続けているそうです。 また、のちに”フクシマ・フィフティ”と呼ばれる人々を残して現場を去った最後の方が次のように証言されています。 【福島第一原子力発電所 防災安全グループ 佐藤眞理】 (必要最小限の人間を除いて退避の命令を受け、現場を離れた最後の人)私は、振り返りませんでした。神聖な雰囲気ですから、その円卓に座っている五十人ほどは、もう死に装束で腹を切ろうとしてる人たちですから、振り返るなんて、そんな失礼なことはできませんでした。 --- 国難において、自らの命さえも顧みず立ち上がる精神は、現代にも間違いなく受け継がれていることを彼ら・彼女らは教えてくれました。 本書では、当時の政権の現場における言動の一部も、取材により明らかにされています。 【本書抜粋】 (当時の日本国総理大臣 管直人の現場での発言について)「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる。逃げてみたって逃げ切れないぞ!(菅直人)」 逃げる?誰に対して言っているんだ。いったい誰が逃げるというのか。この管の言葉から、福島第一原発の緊対室の空気が変わった。 (なに言ってんだ、こいつ) これまで生と死をかけてプラントと格闘してきた人間は、言うまでもなく吉田とともに最後まで現場に残ることを心に決めている。その面々に、「逃げてみたって逃げ切れないぞ!」と一国の総理が言い放ったのである。(中略)緊対室は、怒りと虚しさが入り交じった奇妙な雰囲気に陥った。 --- 左翼運動家としての本質。自分がそうだから、きっとあいつもそうだろう・・・。責任と無関係で批判だけをしてきた人間の本質と言えるでしょう。 極限の状態でこそリーダに問われる資質。それは「人を信頼し、その人が最も力を発揮できる環境を用意し、責任は全て自分で負う覚悟」だと私は思います。自らが手を下すのは楽ですが、それでは組織を活かすことはできません。 私自身は極限の状態に放り込まれた時、どのような本質を曝すのか。 現場での事実を通して、様々な事を教え・考えさせてくれる良質のノンフィクションです。
0投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ何が起こり、どうなっていたのか。一人一人の苦悩や葛藤、生きたいと願うことと死ぬ覚悟をすることの狭間で闘ってくれた人のことが知れて良かった。読むのが辛く、何度も泣いたけど、でも真実を知ってこれからのエネルギー政策を自分事として考えるために必要だと思った。ありがとうと、あのとき頑張って支えてくださった現場の全ての方に言いたい。
0投稿日: 2013.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログあの時、実際現場でどのような対応がされていたか、現場の人達がどんな考えをもって動いていたのか、インタビューを交えながら書かれている。 現場がメインなので、この一冊が全てとは言わないけれど、読みやすいのでお薦めする。
0投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島第一原発の事故後の現場は、戦場そのものだったようである。その中で現場の人たちがまさに命懸けで対応していた。 この本を読むと、東日本に人が住めなくなる状況が現実にせまっていて、現場対応でギリギリ回避されたことがよくわかる。感謝しかありません。
0投稿日: 2013.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ感動した。日本人なら、四の五の言わず読め、と言いたい。 3・11の津波に起因する福島の原発事故。その被害を最小限に食い止めようと、命を賭して、そうまさに命を賭して守った吉田所長とメンバーたち。 自身、あるいは家族を思いすぐにでも逃げ出したいような状況下であるにもかかわらず、踏み止まり戦った。 戦争ではないが戦ったという言葉が適切だろう。 そして吉田所長のその後の運命はあまりにむごい…
0投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島の現場では、こんな戦いがあったなんて本当に衝撃的である。この男たちがいなかったら日本は滅んでいた。所員達の決死の行動に只々感謝である。
0投稿日: 2013.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発事故と闘った現場の人たちに敬意。この話が知りたかった! 〜 もうダメだ。と思った時に一緒に死んでくれる同僚、部下の顔を思い返していたというくだりにはジンときた。
0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ原発に関しての主義主張の違いなどで、原発に対する批判も管理体制に関する批判も当時の様々な事に関しての批判はあるだろうけれど、それはまずは横に置いておいて読みたかった本。 「責任」とは何か。 失敗した人を探したり、犯人探しをしたり、言い訳をしたりするのではなくて、起こった事態に対して、どんな決意と意志で立ち向かって行くのかーーということを見せつけられた本。 私には、何の力も取り柄も強さもないけれど、自分自身で自分自身の国を環境を未来を考えなければならないのだと、強く感じさせられた本でした。
0投稿日: 2013.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ原子力発電所の是非や、事故対応の是非について読みたい人は、別の書籍を読んだらいい。 ここには、何かの是非を問うようなことは書いていない。 実際に起きたことと、それを決断するにいたるまでの逡巡が書かれている。 ただ、管元首相を批難する記述が多くて気になる。 悪意がある気がする。支持している人は本人への取材なくこのように書くことを不快に思うでしょう。 事故が起こった頃にテレビの報道でかいつまんだ情報しか知らなくて、この本を読んでたくさんのことを知ることができた。 テレビの報道がいかに偏ったものであったのかも分かった。 政府に意見できない東電本店の方たちは、たくさんの人生を脅かすような事故を前になんて情けないのだろうと思ったけれど、吉田所長のような優秀な人材をしっかり活かせる立場においていたのだから、そこは評価されるべきじゃないかとは思う。 この筆者の別の本も読んでみたいものがあるから挑戦する。
0投稿日: 2013.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ必死に原発を冷却させようとしていた人々の努力も尊いし、よく伝わってきた 圧倒された ただ一方で、現実として大きな問題が発生しているわけで そこの総括はどうなの?というのは思う 本自体もやや現場礼賛に偏っているようには思うものの迫ってくるすごい本であった
0投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
原発の報道は、正直難しくてよく理解できなかったが、この本に書かれているようなことが現場では起こっていたなんて、ほとんど報道されていなかったはず。 この方たちのおかげで今の暮らしが維持できているのかと、感謝、という言葉でも軽い。 当時、東電バッシングが酷くて、東電は良くない企業というような印象が世間に広まったのは、すごく悲しい残念な事。 被害を受けたら、それが自然災害でも『悪者』を吊るし上げて、共通の敵を責め立てることしか、人にはできないのだろうか。 『ここは泣かせる所だな』というところで心は動かなかった。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログフクシマで何が起こったのかについて、国会事故調の報告書などは、淡々と「組織的意思決定のミス」や「リスク認識の欠陥」を責める。それはリスクや防災や経営の学術的な研究としては意味のあることかもしれないが、自分は手を汚さないという人による他人事の視線という感は残る。 菅や福山など政治家側の回顧本は、彼ら自身が感じてた責任感はわからなくもないが、つまるところ自分たちを弁護するものに過ぎないし、彼ら自身がダメージコントロールにあたるべき人ではなかったことを露呈しているだけだ。 それらに対し、本書のようなルポルタージュは、若干の脚色はあるにしろ、あの時現場で当事者が自分自身の肉体的危険と責任との葛藤にどう苦しんだかということを、絶対的な迫力で伝え、読む者の心を揺り動かし、そして一人ひとりに自省することを求める。自分ならどうしただろうか、と。
0投稿日: 2013.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直言ってページをめくる度に泣ける本だ。昨年の暮に喫茶店でお茶を飲みながら読んでいたが涙と鼻水が溢れてきて大変な思いをした。 大震災後に暴走する原子炉を食い止めるようとして、命を賭けて現場に踏みとどまり原子炉の側まで行き圧力弁を開けようとしたり注水をしようと必死の戦いを挑む男たちの物語は、まさに中島みゆき「地上の星」がバックに流れるようなドラマだ。勝利が見込めない中で何ができるのか、そして大半の人間を退避させた後に最後まで残る彼らの活躍は胸を打つばかりだ。 だがしかし、その時に現場で休憩も取らずに食うや食わずの作業を続けた彼らの一人ひとりの活躍は確かに凄いと納得はするのだが、それを無条件で賞賛することだけで良いのだろうかという疑問も持つのも事実だ。 即ち、感動のドラマ一色になっている本書の影で、原子炉の暴走に際して本当に吉田所長を筆頭にした彼らの作業の内容そして手順が本当に最善であったのか、もしかして被害をもう少しばかりでも小さくするための方法があったのでは無いだろうか、という観点の検証は本書には決定的に欠けているのが残念だ。 原子炉の事故としては史上最大級のものであり未だ被害の収束すら覚束ない現実、そして未だに東電本社・政府の役割と隠蔽工作もどきの大本営発表の繰り返しで本当の検証がされる気配すら見えない現実を考えると、現場の努力にだけ焦点を当て「精一杯やった」ということだけでは後世に何も残らないことが危惧される。ようやく現場の作業に従事した人間のインタビューができる状況になったこのタイミングだからこそ、その観点で作業内容の再構成をする努力をするべきではなかろうか?
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでニュースやNHKスペシャルで断片的に見聞きしてきた情報がストーリーとなった本。想像を絶する窮地の中でも人間の執念と信念の強さを知ることができる。家族のことを忘れるまで仕事に没頭する凄まじい現場の迫力に圧倒される。最後は不本意ながら涙が出てしまった。どうか吉田所長のご無事を祈りたい。
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ多少ページ数はあるけど、読むべき価値のある本だと思います。 地震当日、状況が把握できないままに判断をするしかなかった、現場にいた責任者の方々の一貫した使命感と責任感に打たれます...。また、『チェルノブイリ×10』という最悪の事態になっていれば、関東を含めた日本の3分の1が汚染され住めなくなる可能性があったという衝撃も、恥ずかしながらこの本で初めて知りました。ニュースで断片的にしかわかっていなかった当時の様子を、現場の視点から追体験できました。
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時のことを思い出しながら読んだ。 当時も今も福島県いわき市に住んでいる。 近所の小学校に避難してきた、いわき市内の津波罹災者の支援をしながら、毎日、風向きを心配していた。 確か3月15日だったと思う。その日家族は東京へ避難した。いわきに残った私は、少なからず覚悟した。事故後の原発で復旧にあたる人びとと比べれば小さい覚悟だったとは思うが。 日本は現実を直視し、直視した現実の上に論理を構築する必要がある。 台風が来ることが嫌であれば、憲法に台風は来るべからず、と書いておけばいい、戦後このかたの日本人の考え方は、そのような考え方だ。 原発は相応の危険がある。そのための準備と訓練が必要だ。信義に悖る外国もある。そのための準備と訓練が必要だ。そのように平たくシンプルに考える必要がある。 訓練以上の対応は難しい。 平和ボケから目を覚まそう。
0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ福島原発。世界中が知ることができなかった、「あの日、そこで何が起きていたのか」を、綿密な取材により克明に描き出している。 原発の是非を問うものではなく、あの場で命懸けで闘い続けた者たちがいたという人間ドラマ。 著者の“意思”が入った部分も少なからずあるが、これは一人でも多くの人に読まれることを願う。
0投稿日: 2013.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙でボロボロになりながら、新年を迎えてしまった。 吉田所長を始め、現場の皆様がぎりぎりの状況でいかに戦ったか、また、避難された方や津波で亡くなられた二名の東電社員のご家族の話。 それにしても、リーダーの器かどうかは、危機的状況の時にばれちゃうものですね。それが、一国のトップだったのが、日本の不幸。リーダーって自分が現場で作業するのではなくて、大局を見ていかに先を読むかが重要であり、それが難しい。現場でガーガーいうのは簡単だけど、その簡単なことに逃げちゃいけない。 とにかく、いつもの年末年始を迎えられたことに感謝。
0投稿日: 2013.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。 あの地震、大津波、全電源消失、炉心の冷却不能、水素爆発という極限状態の中で吉田所長を初めとする現場の方たちはどのような対応を行っていたのかを綿密な取材をもとに描いた著者渾身のノンフィクション。 感想は敢えて控えたい。どんな言葉も陳腐なもの、軽いものになってしまうから… 死も覚悟してひたすら現場で奮闘した方たち、そして実際に津波に巻き込まれて亡くなった2名の作業員に心からの感謝と最大限の敬意を表します。読んでいて涙が出そうになります。
0投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ3.11の福島第一原子力発電所の事故についての書籍は巷に溢れかえっている。 本書はなぜ事故が起こったのか、原子力は必要かという事には言及せず、3.11の事故から現場の人はどのように考え、どのように行動していたのかをインタビューを通して紹介している。 現場の人にインタビューし、書籍化したのは少ないのではないかと思う。 この点では本書は他にはない特徴である。 内容に関しては、筆舌に尽くしがたいという印象である。 発電所がブラックアウト(前交流電源喪失)し、建屋内の放射能濃度が高くなり現場に行く事が困難であるという状況で、東京電力の操作員は決死の覚悟で現場に行き、バルブをひねったのだ。 マスコミがよく言うように、指をくわえて何もせずに中央操作室で立っていただけではないのだ。 現場の生の声。 報告書やどっかの専門家、コメンテーターが書いた本とは一線を画する書籍であり、まだまだ東京電力も捨てたもんじゃないな。と思える一冊である。
0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ東日本大震災に伴う福島第一原発の事故は、安全基準の見直しを する機会があったのにそれをして来なかった東京電力の罪は重い。 しかし、起こってしまったことはどうにかしなければいけない。 本書は地震直後から福島第一原発の最前線で事態の対応に当たって 来た人々のドキュメントである。 予想を遥かに超える大地震と大津波。全交流電源喪失、そして発電機 の水没。本来であれば制御盤に表示される原子炉の状態も分からない。 1、2号機の中央操作室の当直長や運転員たちは、重装備の上で 何度も原子炉建屋への突入を試みる。 原子炉建屋への注水作業に駆け付けた自衛隊員は、防護服の内側の 線量計が鳴る中、信じられない光景を見る。自衛隊の放水を誘導する 為に、ひとりの職員が外に立っている。 「各班、必要最小限の人数を残して退避せよ」。原発が最大の危機を 迎えた時、当時の吉田所長から部下や関連企業の作業員に退避 命令が出る。 福島第二原発に退避した人たちは、その後、続々と第一原発へと 戻っていく。関連企業の社員は、戻ることを許可いしない社長に 対して涙ながらに懇願する。「行って、手伝ってやりたい」と。 このまま、ここで死ぬかもしれない。そんな極限状態の中で、 暴走しようとする原子炉をどうにかしようとあらん限りの力を 注いだ人たちの証言が満載だ。 原発事故関連の本はあまたあるが、現場の人々が実名で登場し、 あの緊迫した状況の中で、いかに対処して来たかがよく分かる。 そして、改めて当時の首相であった菅直人には呆れた。事故翌日 の現地視察や東電本店へ乗り込んで怒鳴り散らしたことは他の 本にも書かれている。 現地視察の際、出迎えた東電の副社長に挨拶もせず食ってかかる。 免震重要棟へ入る際に「除染を…」と言われれば「そんなことをしに 来たんじゃないっ!」と怒鳴りつける。周りには作業から返った 作業員が大勢いるのに…だ。 「逃げようとしても逃げられないぞ」。本店へ乗り込んで怒鳴り 散らした時には、テレビ会議システムで第一原発にもその声は 届いていた。 逃げるどころか、踏み止まって事態に対処している人たちにもその 声は聞こえていた。 アメリカからのプレッシャーでおかしくなっていたんじゃないのか? 本書では菅直人本人にも話を聞いて、言い訳を掲載しているが どう考えてもあの時の日本は「宰相不幸社会」だったよ。 福島第一原発の事故は人災でもあった。だから、美談とは捉えた くはない。しかし、その現場には一度は自らの命を捨てようとした 人たちがいたんだよね。
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ暴走する原子炉。それは現場にいた人たちにとって、まさに「死の淵」だった。それは自らの「死の淵」だけではなく、故郷と日本という国の「死の淵」でもあった。 このままでは故郷は壊滅し、日本は「三分割」される。 使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いをつづけた男たちは、なにを思って電源が喪失された暗闇の原発内部へと突入しつづけたのか。また、政府の対応は……。 「死」を覚悟しなければならない極限の場面に表れる、人間の弱さと強さ。 あの時、何が起き、何を思い、どう闘ったのか。原発事故の真相がついに明らかになる。 菅直人、班目春樹、吉田昌郎をはじめとした東電関係者、自衛隊、地元の人間など、70名以上の証言をもとに記した、渾身のノンフィクション。 原発推進派、容認派、脱原発、卒原発の別なく、すべてのかたに読んでいただきたいノンフィクションです。ニュース報道では知らされなかった真実がここにあります。
0投稿日: 2012.11.29
