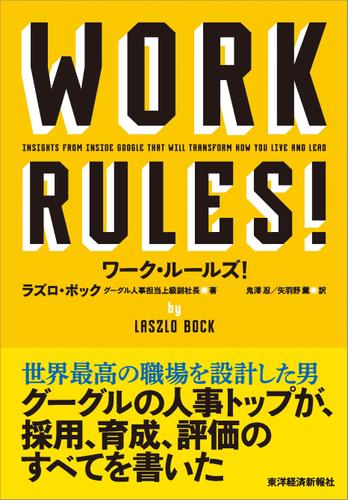
総合評価
(107件)| 24 | ||
| 34 | ||
| 26 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事施策的な話を人事担当トップが話してくれる。Googleという世の中の労働力の上澄みみたいのが集まる企業だから機能している仕組みもあるんだろうけど、いろいろと示唆に富んでいる。働きやすい環境を整えることはホントに大切だな。書名のワークルールズとして、仕事に意味を持たせる、人を信用する、自分より優秀な人だけを採用する、発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない、2本のテールに注目する、カネを使うべきときは惜しみなく使う、報酬は不公平に払う、ナッジ、高まる期待をマネジメントする、楽しもう!(そして①に戻って繰り返し)と整理している。
0投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事担当者による本。 翻訳なのか原文なのか、訳文が英語を直訳したそのもののような文体で、読みにくかった。もともとメタファーや修飾が多いのかもしれない。
1投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高の職場を作り続ける方法が学べる一冊 Googleの組織づくりにおける試行錯誤の過程がつぶさに語られている。実行するうえでぶつかった困難や、実施したことでどんな結果や学びを得られたのかなどが、具体例をふんだんに交えながら説明しているため非常に分かりやすかった。 Googleはただのエリート外資だと思っていたが、人間的な思いやりと野心に溢れる会社だと感じた。
0投稿日: 2025.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人事担当上級副社長が2015年に出版したグーグルでの人事制度を通じた人事の本。人事担当になったらもう一回読もう(ならないけど)。 1.仕事に意味を持たせる 2.人を信用する 3.自分より優秀な人だけを採用する 4.発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない 5.2本のテールに注目する 6.カネを使うべき時は惜しみなく使う 7.報酬は不公平に払う 8.ナッジ きっかけづくり 9.高まる期待をマネジメントする 10.楽しもう 失敗の話は考えさせられた。価値観によって動く組織のマネジメントの問題は「あなたが腕を振り回す権利は、誰かの鼻のあるところで終わる」すなわち言論の自由と他人への中傷の境目、要は「鼻はどこから始まるか」の認識が人によって違うことが問題。 食事のメニューでフリーチベットチョコ と出したらチベットは解放(フリー)されるべきだと示唆すると騒ぐ従業員が一定数いて、担当のシェフが解雇されそうになったエピソードは、最近のSNSの炎上に通じるものがある。無料の食事でミートレスの日を設けたら、無料の食事の権利を奪われたという意識の一部の社員が怒りを爆発させた。既得権を侵されたと感じたからだという。 複数の人が集まると、極端な意見を持つ人が含まれ、そういう人を含めたマネジメントをどうするかという問題に、グーグルは性善説で向かい合っているらしい。曰く、これだけ厳しい面接を潜り抜けて社員になった人に、悪い人はいない。ただ勘違いしているだけだから、データや事実を隠さずに公表して、個人の極端な意見を修正してもらおうというものらしい。人事施策(査定の方法やマネジャーの権利)もアジャイルで小さな実験を繰り返して改善して、それらを社内で全て公開しているとのこと。ちょっとグーグルで働いてみたくなったりして・・・・
0投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり、翻訳本は、頭にスッと入ってこないので、、、良いことが書いてあるのはわかるのだが、苦手。。。 いろいろな工夫、事例、成功例、失敗例が書かれているけど、、、 結局、世界で一番優秀な人が集まり、世界で一番給与体系が良い会社なんだから、うまくいって当たり前だし、、、って思ってしまった。。 自分の理解度不足。。
0投稿日: 2024.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ欧米企業は、ジョブ型や実力主義など、 人に関して、もっとドライなのかと 思っていましたが、本書より、 そうではないことに気付かせてもらいました。 社会環境や時代が移りゆく中で、 変化してきたのではないかと思いますが、 こうした側面を情報として新聞等で、 取り上げてほしいと感じました。 答えをすぐ求めずに、 仮説を立て、実験し、 社内で実験をすることを伝え、 進めている点は、公平性、透明性がありました。 その中で、変化に対して耐性が付き、 創造性も磨かれていくのだと 感じました。 人事系(育成/採用)の方は、もちろんのこと、 人事系でないマネジャーの方も、 読んでおくべき良書としてお薦めです。
0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleのソフトウェアエンジニアリングの中でたびたび紹介されていたので読みました。人事責任者がGoogleの職場をつくってきた哲学が実例とともに書かれています。大前提として性善説、そして文化の大切さ、楽しい環境が生産性を向上させるという考えに基づいていて、自身の職場でどう適用するか悩みながら読み進めました。そんな中でも、小さな実験を繰り返すこと、そして目標とフィードバックを繰り返すという地道な積み重ねが強固な文化を維持するために必要だと感じました。
0投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なんとなく」を脱する必要があるなと感じた。 施策は効果を測定すること。 それがベストなのか、きちんと確認すること。 何を改善すべきなのかは社員が教えてくれる。 どう測るべきかも社員が考えてくれる。当人が有する知識はもちろん、その人がアプローチできる人脈も活かす。 自分より優秀な人を雇い、優秀な人にはきちんと報いる。 なにより、やっぱり「きちんと人を選ぶ」こと。雇って終わりではなく、この組織で成果を出す人はどんな人かを分析して定義して、マッチする人を雇う。
0投稿日: 2022.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃくちゃ良書。 この本の思考を素直に実践すれば、間違いなく良い会社になると思う。実際、多くの会社はわかっていてもできないことが多いんだろうなと。だからこそ、抜きん出る。イケてるスタートアップは、取り入れてるし、ワークしているように聞く。(メルカリとかラクスルとか) 「大企業には無理」という言い訳はできないと思う。Googleは大き過ぎる企業なのだから。 細かいルール云々というよりは、トップの姿勢そのものが重要で、全部それが根底にあるのが容易に想像できる。 そして、必ずしも、お金のかかることでもない。 以下、個人的ポイント抜粋。 ・必要なのは、社員は基本的に善良なものだと言う信念。そして、社員を機械ではなくオーナーのように扱う勇気だけだ。機会は与えられた仕事をこなすが、オーナーは会社やチームの成功に必要なことなら何でもやる。 ・成功する組織は、自分たちが何を生み出すかについてはもちろん、自分たちがどんな組織であり、どんな組織になりたいかについて共通の意識を持っている。 ・全ての人が素晴らしい機会を持てるようにすること、また彼らが有意義な影響与え、社会の改善に貢献していると感じられるようにすること ・重要なのは、私たちがこのミッションを決して達成できないことだ ・たとえ数分間であれ、手を貸そうとしている相手に従業員を合わせる事は、彼らへの最大の動機付け要因なのだ ・自分が世界に変化を起こしていると知ることほど、モチベーションを高めるものはない ・他の社員が何に取り組んでいるかを誰でもわかるようにする ・週に1度の全社員ミーティングで、会社の誰からの、どんなテーマについての質問にも30分をかけて回答する ・質問が選ばれる方法にまで透明性が行き渡っているへ。慣習の関心を反映する度合いに従って質問に優先順位がつけられる ・時間をかけてでも、自分より優秀な人だけを雇え ・大切なのは会社に何をもたらすかであり、これまでどうやって自分自身を際立たせてきたかだ ・マネージャーに自チームのメンバーの採用を任せてはならない ・あなたが雇う最初の数人の社員は、その基準を満たすだろう。だが、彼らが採用する側に回ると、あなたと同じ基準で人を雇う事は無い ・適任という求職者が見つかるまでは、ポストを空席にしておいた ・大きな質問を小さく扱いやすい質問に分解することによって、より多くのより質の高い人材を紹介してもらえるようになる ・本当に優れた人々は仕事を探していない ・あらゆる社員をリクルーターに変えるべく、人材の紹介を依頼する。友人を贔屓するバイアスを抑制するため、客観的な立場の人に採用を決めてもらう必要がある ・採用活動を全社員の仕事の1部とする ・受験者を採用すべきかどうかは、4回の面接によって86%の信頼性で予測できることを発見した。その後の面接では1階につき1%しか予測精度は向上しなかった ・組織の改革において、唯一にして最善の方法は、より良い人材を採用すること ・ステータスシンボルを廃止する ・マネージャーの意見ではなく、データに基づいて意思決定する ・社員が不満を感じている領域を選び出し、その修正を任せてみよう。期限や予算といった制約があれば、その内容を伝えておく ・目標と主要な結果を定める。 ・他の社員やチームが何をしているかを調べる方法があること、また会社が成し遂げようとしている大きな構図の中で自分がどんな位置にあるかを理解するよう促す ・大半の組織は最高の人材を過小評価し、正当な報酬も払わないでいる ・私たちが手を貸すのは、社員全員ではなく、必死でもがき苦しんでいる一握りの社員だ。それでもうまくいかなければ、別の役割を見つける手伝いをする。たいていは、これで平均位までは業績が上がる ・最高のマネージャーを要するチームは業績も良く、離職率も低かった。実際、マネージャーの質は社員が辞めるか残るかを予測する唯一にして最高の指標だった。社員は会社を辞めるのではなく、だめなマネージャーと働くのをやめるのだと言う格言を証明した ・マネージャーに関する匿名でのフィードバックを各チームに求める。この調査を思いやりのあるツールとし、報酬や罰ではなく、成長に焦点を合わせるべき。 ・成績が下から40%のところにいる人を下から50%に引き上げてもメリットは小さいが、下から5%にいる人を下から50%に引き上げる効果は大きい ・トップレベルのスキルの持ち主は学習への取り組み方が私たちとは違う。雨のゴルフ練習場で何時間も同じショットを打つように、動作を細かく分割して何回も繰り返す ・社内で最も優秀な人教師にする ・平均するとキャリアの早い時期は貢献に対して報酬が少なすぎ、後半になると多すぎる。公平な報酬とは、報酬がその人の貢献とつり合っていると言う事 ・優秀な旋盤工の賃金は平均的な旋盤工の数倍だが、優秀なソフトウェアプログラマーは平均的なプログラマーの10,000倍の価値がある ・最も優秀な社員1人を何人となら交換してもいいか。5人以上なら、最も優秀な社員の報酬が少なすぎるだろう。 ・最も優秀な社員が平均的な社員の10倍の影響をもたらす場合、報酬を10倍にする必要はないが、少なくとも5倍にするべきだ ・経験や物を受け取った社員は、現金を受け取った社員より満足感が長く続いた。金の喜びはつかの間だが、記憶は永遠に残る。 ・イノベーションは社会集団の(構造の隙間)で生まれやすい ・ある場所ではよく知られている当たり前のアイディアが、別の場所に持っていくと新しい価値を見出される ・ナッジと言う概念を、(選択肢を排除せず、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャの要素)と定義する。 ・果物を目の高さに置く事はナッジであり、ジャンクフードを禁止する事はナッジではない ・特定の選択肢を選べと命令するのではなく、選択する行為に影響与える ・実際、多くのナッジは、不十分な選択によって健康や幸福が損なわれた現状を変えるためのもの ・チェックリストはとても効果的。人を見下すかのように簡潔な内容でも構わない。私たち人間は、最も基本的なことを忘れる時もある。 ・最も優秀なプレイヤーを手本にチェックリストを作って真似をするだけでなく、彼らに社内の教師もやらせる ・採用のプロセスが適切なら、悪戦苦闘している大半の人は、本人が無能だからではなく、間違った役割を与えられているせい。 ・自分たちが働きたいと思う場所を作ることから始める ・3分割ルールを導入し、独自の人事組織を構築。典型的な人事畑、戦略コンサルタント、分析力の高い人。 ・得意な分野と強化の余地がある分野を特定し、チームを築くためにどのような人を採用するか。
1投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカでは、HRの重要性が高まっているのだろうか? 会社がどうなっていくか、どのような文化を作るか。そんな土台を作るために、HRがキーになってきている。 ただ、米系の会社は、優秀な人材ありきで会社が成りっているように見える。2本のテールの話は、橘玲氏の「無理ゲー社会」を思い出す。一部の優秀な人達が優遇され、その他大勢が脇に追いやられる。そして分断が起きる。 国レベルで起きている分断、対立が、会社でも起きるのではないか、そこに文化は生まれるのだろうか、という疑問が残る。
0投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ元グーグル人事担当上級副社長が書いたグーグルのマネジメントの基本な考え方。 著者の入社以降、6,000人から60,000人に拡大する中で フォーチューンから「もっとも働きやすい会社」に繰り返し指名されたとのこと。 成功だけでなく失敗事例も随所に書きちりばめられております。 なお、本の半分近くを採用に費やしております。 これは「採用の失敗は教育では取り返せない」ことを前提としており、採用を重要視しているためです。 本書で私が特に感銘を受けた箇所を紹介します。 グーグルの人事組織に「3分割ルール」を導入。典型的な人事畑の経験のある人の人員は3分の1を超えないこと。次の3分の1はコンサルティング業界(人事コンサルティング会社は対象外)から採用。最後の3分の1は分析力の高い人を採用する。 これらの3つの採用のコンビネーションがなければ本書で紹介したことはほとんど成し遂げられなかった。人事部門では人事の経験がある人だけを雇うのは間違っている。 本書は採用・育成・組織文化を担当している人事の方は当然ながら、世界トップ企業がどのような人事施策を行っているのか興味がある方にもお薦めです。
0投稿日: 2021.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogle 夢のようなマネジメントだが、資金があるからこそ。中小企業はもっと創意工夫しなければならない。
0投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事役員の方が書かれた本です。素晴らしい企業文化でした。こんな会社で働きたい!と思うほど、羨ましい限りです。是非、企業の役職のある方には読んで欲しいです。
0投稿日: 2021.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの文化がいかに試行錯誤の上で成り立ってきたか、失敗と成功例と共に説明されていてよく分かった。 自分の働く会社との意識の雲泥の差を感じた。。
0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ創造性を引き出すためにオープンを原則とし、全社を巻き込みながら実験的な取り組みや必要な議論を行いつつ、よりより環境を構築していった過程を赤裸々に記してある。 今ある会社を変えるには相当に力がいるだろうが、これから会社を作るという人は優秀でミッションビジョン価値観に共感する人を集め、初めからこのようなルールで組織を運用できると面白いだろう
0投稿日: 2021.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事部が明かすさまざまな社員への制度や処遇について明かされている。如何に働きたくなるような会社であり続けるための工夫や他では見られないような制度の導入に驚かされた。
0投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleがいかに人を大事にし、課題に対して対処を行なっていったのかがよくわかりました。 良い職場環境を作ろうと試行錯誤しており、リスクを恐れずに常にチャレンジをしているところが印象的でした。 一方で普通の日本企業であれば反発を恐れてここまでの改革を常に行うことは無理なんだろうな、と深く感じました。 私もこの本に倣って常にチャレンジすることを忘れないようにします。 企業の経営層と人事にはぜひ読んで欲しいと感じた本です。 また心に残った表現は以下の通りです。 ・人は会社がなくても生きていける、しかし会社は人がいないと存在できない
0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ考え方としては、最近読んだ「ウォーフォータレント」の内容に親しいところがあったが、失敗事例も含めて、「あのグーグル」が、どう試行錯誤し、どうしているのか、というベストプラクティスがふんだんに盛り込まれているところが良い。 本書内にもあるとおり、そこで取られている施策の大半はコストもそれほど掛からないし、難しくはない。従来のやり方とのギャップに大半の組織がなかなか踏み出さない、二の足を踏むような物がほとんどだ。 被雇用者側の立場から読むと、たしかにこんな自由な会社なら居心地は良いだろうし、仕事をするモチベーションにも繋がるのかなと思った。 いずれまた読み返したい。
0投稿日: 2020.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログp406 部活動ないな〜 作ってもいいかも、何かを学ぶ会 p420 コロナ禍でのgoogleオフィスのあり方は? p426 社員の生活の負担を減らす 社員が死亡した際の制度:配偶者やパートナーを会社として支える 産休中も給与やボーナスを支払う p331 デリバレイト・プラクティス(熟考した練習) 似たような小さなタスクを繰り返し、即座にFBや修正、実行を加える練習 ・今日の目標は? ・今日どうだった? ・何を学んだ? ・変えるところと変えないところを確認しあう >1on1についてのnoteさがしてみよう >1on1のコツとしていいかも p339 G2G(グールラーtoグーグラー) 本業とは離れた得意分野を講師になって教える場。 クラスを開講し、登録して受講する。 >絵をかくクラスとかつくってほしいなあ。こういうのが車内にあれば、自分の好奇心も承認欲求も人脈も広がってよいなあ。 >コーチングの資格や心理学出身の人、マーケ出身の人もたくさんいるだろうから、そういう人たちに話ききたいなあ。 >>今後新人向けの勉強会をやるから、それの講師のタグ付け、考えますか! >>>講師の人の日報漁ってみよう。 >>インターンに対して、前知識なくこういうのが出来てたのはよかった。きっと先輩たちがこういうコミュニケーションとってくれてたおかげで、イメージがスッと入ってきてた。 p348 研修プログラムの4つのレベル:反応(ストーリーが好まれる)・学習(会のアンケではかる)・行動(追う)・結果(評価する) >>座談会でのコツをTLにお渡しして、tipsツールにしてもらうおう >>この間のインターン間の勉強会、次は行動フェーズやろう! >>インターンをうけいれてもうすぐ1か月。1か月の振り返りをする? お金や人事権がないから、なんちゃって推薦書(配属された上司あてになりそうなもの)とかつくってみる?お金以外の「恩恵」をじゅんびしてあげたい。(サイボウズの本の感想にここらへんのメモ残してた気がする!) p513 つねに発展的な対話を心がけ、安心と生産性につなげていく あなたがもっと成功するために私はどんな手助けができるか、という心がけで向き合わなければ、相手の防衛本能が高まり学習の回路が閉ざされる p514 >>インターンにペアで仕事をしてもらってるから、それで気づいたことがあればきいてみる? p464 採用スローガン:グーグルで働いて長生きしよう
0投稿日: 2020.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みづらい。Googleの大事にしている価値観を人事のあらゆる場面(採用、評価、育成、異動etc)で徹底しているということを伝えるために各章毎に同じことを繰り返している印象。 4章まで読んだので、必要に応じていつか続きを読む。
0投稿日: 2020.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
グーグルの人事制度をまとめた本。結構読みづらい。 書いてある通り実践できたらいいけど、実際には2018年にセクハラ、パワハラで従業員の抗議活動が起きている。どう解決していったのか、続報を読みたい。
0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リーダにはより毅然とした態度が求められる、不安や失敗に直面しても自分の原則に忠実でありつづけ、組織に対する攻撃の盾となる人が、その言葉と言動で、組織の魂を形づくる、そのような組織に人々は加わりたいと思うだろう
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleを受ける人は必読の一冊。 信念やカルチャー、採用基準がよくわかる。 とても参考になりました。 読了時間:5時間弱
0投稿日: 2020.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleのミッションだったり、透明性、権限の考え方は参考にしています。 科学的な採用手法はすごく勉強になります。
0投稿日: 2020.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ①社員は生活の大半を仕事に費やしているにもかかわらず、ほとんどの人にとって仕事は骨の折れる労働であり、目的のための手段に過ぎない。 ②自分が創業者になりたいのか、従業員になりたいのか。創業者のように行動する。 ③リーダーの課題は有能な人々がインスピレーションをもたらす目標を生み出すこと。 ④社員に与える責任、自由、権力の程度は安心して与えれるものよりやや大きいものにしよう。 意思決定をなるべく少なくする。一個の意識決定にエネルギーをより多く使うために、簡略化する。 月一の新入社員を囲んだミーティング。ランチ。 意図を持つ、持たせる。
1投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ田端大学の課題図書という事で、オンラインサロン未加入者ですが、読んでみました。 Google人事がわかる内容になっており、Googleがここまで大きく発展したのも、バックヤードの社員が、Googleの理念と社員の発展・ライフスタイルを重視し、取り組んだことが貢献しているのでしょう。 社員一人一人が経営者視点で仕事に取り組むという記載と、「プロジェクト・オキシジェンの8つの属性」は心に留めておきます。
1投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ<キーフレーズ> 「文化が戦略を食う」。ミッション、透明性、発言権が重要、学習する組織、ナッジ/選択の背中を押す <きっかけ> 本屋で確認して購入(2015) →勤め先での対話で何度も「文化」が話題したことをきっかけに、積読本に目が止まり、ようやく読み頃になったようだ(2021)
0投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日、カンファレンスでGoogle人事の人の話を聞く機会があり、関心が再燃したため読みました。実際の事例の話や取り組みの事例が盛りだくさんでした。Googleは、データをうまく使うテクノロジー企業というイメージがありますが、ヒューマニティやデザインも同じくらい大切にしていることが伝わってきました。学術的な背景も踏まえながら、適切な実験計画を作成し、適切に評価しながらそれを繰り返していくプロセスは非常に汎用的だと感じました。このプロセスの実装自体は、状況によって変化しますが、フローはすごく参考になりました。
0投稿日: 2019.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事責任者が採用、育成、評価について、語った本。 Googleの全てを完全オープンに、という訳にはいかないようだが、 それでも結構、通常であれば「社外秘」にしてもいいようなところまで、 オープンにしてくれている。 「会社」という場所で一度でも働いたことのある人なら、 誰もが「ウチの会社のこの部分、おかしくない??もっとこうすればいいのに」と感じたことがあるはず。 Googleなら、全てとは言わないけれど、大体の部分で、そういった「おかしいところ」が解消されているように感じた。 少なくとも、自分が「もっとこうなっていれば、会社はよりよくなるのではないか?」と感じた部分は、 大抵、この本の中に書かれていた。 自分の場合は、その「おかしいところ」の改善策を自分の感覚として持っていたが、 Googleの場合はそれをきちんとロジカルに分析して改善していた。 それなりのサンプル数がないとできないこともあるかもしれませんが、 それでも感覚ではなくデータで語る人事の秘訣は説得力がありました。 自分は人事のプロではないですが、勉強になったところが至る所にあり、 将来会社を経営したり、自分の会社を立ち上げた時に参考にしたいと思います。
2投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が仕事に情熱を持てる理由を分析できた。 一つ。我社では稀有な客を見たことがある珍しい社員だから。奨学金ブログラムとその後の事例は納得だ。 一万時間の法則。タイガーは同じショットを繰り返して体に染み込ませた。所望の動作を細かく分解し、その細かい動作を熟考できるまで。私の絵のアプローチと同じだ。これをデリバレイト学習という。 逆に継続的なトレーニングでないと何もトレーニングしないのと大して効果は変わらない。投資の無駄。振る舞いが変わるまで継続的なフィードバックのかかるトレーニングが効果的。
0投稿日: 2019.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ制度や施設の突飛さばかりがフィーチャーされるGoogleなのでいちどその「狙いと取り組み」を読むとだいぶ見る目が変わります。 ・大事なのは社員、部下に対して性善説であること。管理って信用していない気持ちの表れだよね。 ・失敗を恐れるなと言いつつ、失敗してもよい土壌ははたして醸成されているだろうか? ・単なる能力の総和でなく、チームこそ大きな成果を達成できる(特に創造性に関して)と本当に思えているか? ・情報を開示するのに理由はいらない。隠すことにこそじゅうぶんな理由を求めるべきだ。 結局「安心感のある関係性」はまずここから始めないといけないのかもしれません。
0投稿日: 2019.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働きやすい会社」「働きたい会社」「すばらしい制度のある会社」「最もイノベーティブな会社」など、多くの賞賛を得ているグーグルの人事トップが、同社の人事制度についてとても詳しく書いている。これは、HR担当の方にはとても参考になるのではないか。また、組織のリーダーにとっても多くの学びがあると思う。基本的には、人を信じ、あらゆる情報を共有し、任せること。より良い状態とはどういうものか一人一人が当事者意識を持つこと。間違いはすぐに正すこと。
0投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事(採用、育成、評価)の本。 『How Google Works』とかなりかぶっている感じ。もちろん著者も違うし中身を流用しているわけではないが、Googleの文化の紹介や採用のあたりは内容的には同じなので、なんか前にも読んだなという印象を受ける。
0投稿日: 2019.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計的アプローチが人事という職務において必須であることがよくわかる一冊。 理想ではある、が、日本企業がこの水準に至るにはとてつもないハードルがあるだろうな…
0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読者自らが創業者だと考えるようになってほしい。これは所有権の問題ではなく態度の問題だ。 大抵は自社ブランドを神聖化するが、それすら遊び道具にしてしまう →ポッキーもおなじ態度か? do a barrel roll 革命を起こすのは利益やシェアではなく、理念や道徳。重要なのはこのミッションが決して達成できないこと。 自分より能力の高い分野を持つ人材しか雇わない
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事担当 ラズロ・ボックがGoogleの人事について書いた本。Googleだからこそ成り立っている部分もあり、少し綺麗事に過ぎる部分もある。 例えばラズロ・ボックはマイクロマネジメントを禁じている。マネージャーの意見でなくfactに基づく事。それは恐らく優秀な人材を獲得をしているところと放出に思いっきり差をつけているところとセットになってくる。部下の失敗は上司の失敗であり、それ故にマイクロマネジメントを上司はしがちだ。 とはいえ他企業のリーダーも昭和型のリーダーでなく未来型のリーダーになる為に参考になる所はある。 ラズロ・ボックはGoogleに入る前にGEに在籍している。GEではパレート方式による20対70対10のランキングシステムを作成しボトムは解雇される。 Googleではランキングするところまでは同じだがその他は違う。Googleでは最高と最低の「二本のテール」を管理しそのデータを未来に生かす。最低の社員も改善のチャンスがありそこに手を差し伸べるべきだと。「フィードバック」こそ大事でそれは上司でも同じだ。 以下メモ書きである ※Googleでは自分の手柄を鼻にかけるリーダーは嫌われる。「私達が」より「私が」を口にし「どうやって」より「何を」を口にするリーダーを。 ※リーダーは社員が安心して自分の意見を言えるようになることが大事だ。 ※目標とフィードバックをたてる →デリバレイテッド プラクティスが自分を成長させる ※リーダーやマネージャーは「意思決定のヒエラルキー」として必要。 ※教育より優秀な人材の採用を。優秀な講師は外部より社内にいる ※ルールよりきっかけづくりを。行動経済学のナッジの概念↑また勉強する ①仕事に意味を持たせる ②人を信用する ③自分より優秀な人だけを採用する ④発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない ⑤2本のテールに注目する ⑥金を使う時は惜しみなく使う ⑦報酬は不公平に払う ⑧ナッジ きっかけづくり ⑨高まる期待をマネジメントする ⑩楽しもう!
1投稿日: 2018.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ社員は基本的に善良だという信念。そして社員をオーナーのように扱う。 自らを創業者と考え、創業者のように行動する。 採用活動を第一に投資する。時間をかけて最高の人材だけ雇う。 何らかの点で自分より優れた人材だけを雇う。 マネージャーに自チームのメンバー採用を任せてはならない。 マネージャーの意見ではなく、データに基づいて意思決定を行う。 最善の学習方法は教えること。 1.仕事に意味を持たせる。 2.人を信用する。 3.自分より優秀な人だけを採用する。 4.発展的な対話とパフォーマンスのマネージメントを混同しない。 5.2本のテール。上位と下位に注目する。 6.お金を使うべき時は惜しみなく使う。 7.報酬は不公平に払う。 8.ナッジ。きっかけを作る。 9.高まる期待をマネージメントする。 10.楽しむ。
1投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルのピープルオペレーション担当副社長が明かす、グーグルにおける人事活動のすべて。人財の採用、褒賞、昇進などグーグル独特とは言えないが、一般的でない実施事項が満載。グーグルらしさの源泉はここから生じるのかな?と思った。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログHRのイロハのイもわからないまま読んだ。 よくグーグルの凄い点として語られる、素晴らしい制度・文化、優秀な人材はあくまで結果に過ぎない。とわかった。 同じ企業として学ぶべきは、 ・試練の前でも信念に従って行動すること ・スモールテストを繰り返して失敗を乗り越えること ・情報の透明性を土台に、自律、議論、挑戦を促進すること である。 ●疑問点 グーグルのミッションは道徳的であるがゆえに素晴らしい、という趣旨だった。個人的には、道徳的なミッションは誰にとっても当たり前であるがゆえに魅力的に感じないのでは?と思った。
0投稿日: 2018.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・ピンクの「FA社会の到来」の関連本、amazonで。 【期待したもの】 ・働き方に関する新しい知見が得られる? 【要約】 ・ 【ノート】 ・著者はGoogleの人事担当の重役。よって、内容としても、そういう人事担当という視点からのものになっている。それがかなり現場サイドに寄り添ったものになってはいるけど。 ・あと、例えば今の自分の職場では、あまり関係がないというか、夢物語というような箇所も多かった。 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆自分より優秀な人材を採用する きっかけをつくる。 困っている人に手を差し伸べる。最高の人を観察する。
0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ①当たり前のことをしている ②みんなそうであろうと思っているけれども、どうもそうならない何かがある。 ③そして、それが伝わらない。
0投稿日: 2018.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人事のトップがグーグルの人事制度の肝を解説。 採用と評価と社員の健康が大切。より最善な仕組みを作るためにA/Bテストのようなことも社内で実施して、データを重視する。 組織は人を管理するために巨大な官僚制度を築きえげる。そのような管理体制は人を信用していないと告白しているのと同じだ。
0投稿日: 2018.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変参考になる示唆が凝縮されている。No RatingやOKRなど、昨今流行りとなっている事を含め、評価・育成周りについては特に興味深い。一点、Google以外の企業が福利厚生を含めた制度を真似できないのは資金があるからではなく、採用に力を入れて優秀な人材が集まっているからというのは大きいと思われる。とはいえ人材マネジメントフロー変革の起点となるのはマネジメント力向上も含めた評価・育成周りにある。
0投稿日: 2018.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2/20読了 4冊目 途中まで読んで長いこと積読になっていたがやっと読み終えることができた。 正直全てが日本的な文化の中で当てはまるわけではないと思うが、大原則は変わらないはずだ。人事部門の業務であっても、フラットな視点をキープしながらPDCAを高度化させて回し続けること。 あと、採用で妥協しないという点は大いに賛同する。いずれ機会が訪れた時にはこの本を引き合いに会社に言いたい。
0投稿日: 2018.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳文は読みやすく、すらすらと頭に入ってくる感じだった。 もっとも、米国人的感性のギャグに注が付されたりしていて、 翻訳文ではなく、文化の違いでちょっと立ち止まることもあった。 記されていることは明快で、人事施策をどのようにグーグルが講じてきたのか、 ひとつひとつ丹念に、時折、諧謔を挟みながら、テンポよく説明してくれている。 こんな日本企業があるのだろうか、と思ってしまった。
0投稿日: 2018.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ『「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにする」 この種のミッションが個人の仕事に意味を与えるのは、それが事業目標ではなく道徳だからだ。歴史上きわめて大きな力を振るった運動は、そこで求められたものが独立であれ平等な権利であれ、道徳的な動機を持っていた。こうした考え方を拡張しすぎたくはないが、革命を起こすのは利益や市場シェアではなく理念だと言っていいだろう。 重要なのは、私たちがこのミッションを決して達成できないことだ。整理すべき情報もそれを使えるようにする方法も、尽きることがないからである。これが、絶えずイノベーションを起こし、新たな分野に進出するモチベーションとなる。』 素晴らしい人事の考え方。社員を愛し、社員に愛され、モチベーション高くイノベーションを起こせる会社は根本的に考え方・志・取り組む熱意・割り当てるリソースが違うなぁ〜。非常に良い勉強になった。
0投稿日: 2018.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ数万人という規模の会社になったことを考えても、 この本を読んで学ぶことがない人なんていないと感じる内容だった。 大きな目標に挑戦し続け、 ときには自己犠牲が伴う協力をし、 たゆまぬ改善を行うことで、 チームとして機能したときに信じられないような成果が上がるのかもしれない。 そんなチームを会社に作るための一歩として、 今やっていることに何かフィードバックをかけることが見つかる本だと思いました。 (以下抜粋。○:完全抜粋、●:簡略抜粋) ○賢明さや勤勉さは成功のための必要条件ではあっても、十分条件ではない。わが社は幸運でもあったのだ。こうしたことを知れば、グーグルのホームページにある「I'm Feeling Lucky」ボタンはまったく新たな意味を帯びてくる。(P.43) ○「グーグルが掲げる10の事実」は以下の通り(グーグル公式サイトより)。 ①ユーザに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。 ②1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。 ③遅いより早いほうがいい。 ④ウェブ上の民主主義は機能します。 ⑤情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。 ⑥悪事を働かなくてもお金は稼げる。 ⑦世の中にはまだまだ情報があふれている。 ⑧情報のニーズはすべての国境を超える。 ⑨スーツが無くても真剣に仕事はできる。 ⑩「すばらしい」では足りない。(P.61) ○ 「仕事の完了」についての誠実性が高い人ーーつまり、ほどほどのところでよしとせずに、仕事が完了するまでやり遂げる人ーーは、自分のチームやチームをとりまく状況に責任を感じる傾向も強い。言い換えれば、雇わられている者というより、むしろ企業のオーナーのように行動することが多いのだ。(P.157) ○あなたの行動がチームに前向きな影響を与えたときのことを聞かせてください。(補足質問:あなたの主要な目標は何であり、その理由は何でしたか?チームメイトの反応はどうでしたか?今後はどんな計画がありますか?)(P.160) ○目標達成のためにチームを効果的に運営したときのことを聞かせてください。あなたはどんなアプローチをとりましたか?(補足質問:あなたの目標は何であり、個人としてまたチームとして、それをどう達成しましたか?チームのメンバーそれぞれに応じてリーダーシップをどう変えましたか?こうした特定の状況から学んだ最も重要なことは何でしたか?)(P.160) ○他人(同僚、クラスメート、顧客など)とうまく協業できなかったときのことを聞かせてください。あなたから見て、その人とともに働くのが難しかった理由は何ですか?(補足質問:問題を解決するためにどんな手順を踏みましたか?その結果はどうでしたか?ほかにどんなことができたと思いますか?)(P.160) ○ある程度の謙虚さを備えている(自分が間違っている可能性を認められない人は、これがなかなか身につかない)、きわめて誠実である(従業員ではなく企業オーナーであってほしい)、曖昧さを楽しむ余裕がある(事業がどう進展するかはわからないため、グーグルのかじ取りをするには社内で多くの曖昧さと向き合わなければならない)、人生において勇気のいる、あるいは興味深い道を進んできたという証拠を手にしている。(P.166-167) ○第1に、目標を正しく設定する。それを公にする。目標は野心的なものにする。 第2に、同僚のフィードバックを集める。(P.284) ○第3に評価のために、何らかのキャリブレーション・プロセスを導入する。私たちが好むのは、マネジャーが一堂に会し、ひとつのグループとして社員について検討する会議だ。時間はかかるが、評価と意思決定のための信頼できる公正なプロセスを実現できる。(P.284-285) ○プロジェクト・オキシジェンの8つの属性 1 良いコーチであること。 2 チームに権限を委譲し、マイクロマネジメントをしないこと。 3 チームのメンバーの成功や満足度に関心や気遣いを示すこと。 4 生産性/成果志向であること。 5 コミュニケーションは円滑に。話を聞き、情報は共有すること。 6 チームのメンバーのキャリア開発を支援すること。 7 チームに対して明確な構想/戦略を持つこと。 8 チームに助言できるだけの重要な技術スキルを持っていること。(P.312) ○UFSの質問事項サンプル 1 上司は、私が成績を上げるための実行可能なフィードバックをくれる。 2 上司は、「マイクロマネジメント」をしない(部下が処理すべき細かいことにまで手出ししない)。 3 上司は、私をひとりの人間として見て、思いやりをもって接してくれる。 4 上司は、優先事項である結果/成果物にチームを集中させる。 5 上司は、自分の上司や上層部から得た関連情報を定期的に知らせてくれる。 6 上司は、ここ半年のうちに私のキャリアにかかわる有意義な話し合いをしてくれた。 7 上司は、チームの目標を明確に伝えてくれる。 8 上司は、私を効率よく監督できるだけの専門知識(例、技術部門ではプログラミング、財務部門では会計)を持っている。 9 私は、上司を他のグーグラーに勧める。(P.315) ●私が自分の評価を初めて公表したとき、それが自分のチームの平均を下回っていたので、内心びくびくしていた。(中略)私に対するチームの支持率は77%だった。(中略)下位25%のマネージャのチーム支持率は72%だと言えばひどさがわかてもらえるだろう。(中略)私は、明確なフィードバックを出すこと、(中略)広く努力することを部下に約束した。(中略)やがて、チームは満足度を向上させ、うまく機能するようになり、私の評価も上がった。(P.318-319) ●学習に費やす時間の長さではなく、時間をおdのように費やすかだ。(中略)つねに状況を確認しながら、小さなーーほとんど気が付かないようなーー修正を重ねて改良する。エリクソンはこれを「デリバレイト・プラクティス(熟考した練習)」と呼ぶ。(P.328) ○その際に、具体的なフィードバックをもらったうえで、同じ課題にさらに3回、繰り返したら、学んだ内容をはるかに深く吸収できたのではないだろうか。(P.330) ●彼は必ず私をわきに呼んで質問した。「今日の目標は?」(中略)そして、ミーティングを終えて車でオフィスに戻りながら、彼は再び私に質問した。「君のアプローチはどんな結果を出した?」(中略)ミーティングの直後にフィードバックがあり、変えるところと変えないところを確認し合う。(P.331) ●グーグルに転職するほぼすべての人は、入社時の給料は前職より安かった。(中略)ときには10万ドル下がってもかまわないと言えるのは、リスクを追いかける起業家肌の人だからだ(P.361) ○グーグルの業績管理の制度を変更するたびに、2つの心理が自ずと明らかになる。 ①業績管理の制度を歓迎する人はいない。 ②現在の制度に対する変更の提案を歓迎する人はいない。(P.488) ○今や数万人の社員と数十億人のユーザーを擁するグーグルには、想像の機会が無限にある。そして、無限の創造に挑みたい人が集まってくる。ただし、自由は絶対的なものではない。チームや組織の一員であるということは、ある程度は個人の自由をあきらめ、ひとりよりチームのほうが大きな成果を達成できる可能性を受け入れるということだ。(P.494-495) ○問題は何も解決しなかった。 このように大規模な議論が騒々しいほどに盛り上がり、結論が出なくてもかまわないのは、透明性があって意見を恐れないという文化の一部だろう。すべての問題がデータで解決できるわではない。理性的な人々が同じ事実を見ても、意見は分かれる。(P.499) ○グーグルは私たち自身が理解している以上に野心的だ。それのめ毎四半期のOKRは70%を達成すれば優秀とされ、ラリーは「ムーンショット(困難だが壮大な挑戦)」を信じている。(P.501) ○社員が最も困っているときこそ、人生最大の悲劇や喜びに遭遇したときこそ、会社はカネを惜しんではいけない。緊急の治療が必要なときや新しい家族が増えたときに、会社の寛大さは最も大きなインパクトを与えるだろう。(P.515-516) ○経営陣からのアイデアは、すべてが理想的なわけではない。(P.528)
1投稿日: 2017.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事担当役員が書いたGoogleにおける人事制度(採用から評価まで)が詳細に書いてある本。Googleは色々と考えた人事制度を持っているなぁ、と感心すると共に、全部の制度を採用するのは難しいなぁ、とも思った。 ただ、非常に示唆に富んだ内容でもあるので、部分的でも取り入れると効果が高いんじゃないかな、と思ったりもした。
0投稿日: 2017.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ワーク・ルールズ」の感想: プログラマの思索 http://forza.cocolog-nifty.com/blog/2017/01/post-2059.html
0投稿日: 2017.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ序盤に気づきは得られません。第三章から読み始めることにしました。 グーグルの職場は自由度が高いと言われます。最も有能な人々は自由度の高い企業で働きたがります。マネジャーに自チームの採用を任せたりはしません。権力が集中してしまうからです。採用はチームで判断します。 グーグルが選択した採用方法は、「元から優秀な人材を雇う」ことでした。社員にかけるトレーニング予算を削り、採用資金に集中させたのです。その額は平均的な企業の2倍以上となりました。 優秀な人材は10%しかいないと言われます。そのため待つことも必要になります。また、優秀な人材を見極めるには、自分より優秀な人だけを雇えばよいのです。
0投稿日: 2017.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用やひとの評価に携わる機会がある方は必読です。 新しい会社に集う、新しい人々。そして、新しい働き方、新しい評価の必然性に目が向くはずです。 実はだれしも、上司や先輩、古いしきたりやルールに染まりやすいものです。選ばれる側、評価される側だったときに感じたことも、いざ選ぶ側、評価する側になった途端に忘れてしまいがちです。 評価を数値化し、細分化して公平化し、結果の「上」には傾斜、「最下位」は排除する制度が古いことがよくわかるはずです。
1投稿日: 2017.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界的企業Googleの人事トップが語るのは,採用・育成・評価の仕組みと新しい働き方。それは決してGoogleでしかできないことではありません。さまざまな組織やそこで働いている人,そしてこれから働く人にも役立つアドバイスとなっています。
0投稿日: 2017.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ就活に向けて購入した。基本的に優秀。あと楽しそう。自分にとってはまだレベルが高かった。またあとで読もう。
0投稿日: 2017.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事の仕組み。業務、スキル、状況も全く異なるが、通常良しとされるシステムが構築できていない分、一周回って類似するところがある。 一工夫必要。 〇自分を創業者とみなすことを選ぼう。 〇人事予算をまず第一に採用活動に投資する。 〇自分が求めるものを徹底して具体的に描くことによって、最高の人材を紹介してもらう。 〇採用活動を全社員の仕事の一部にする。 〇自分自身で採用候補者を見つける。 〇採用候補者を客観的に評価する。 ・一定の評価基準のための決まった質問をする。 〇採用候補者には入社すべき理由を伝える。 ・素晴らしい社員に会わせて、仕事のミッションを伝える。 〇社員全員で自社を評価する。役職ではなくデータに基づく意思決定を行う。 〇目標設定、全員評価とキャリブレーションによる人事評価システム 〇ボトムテールに集中した研修等の投資を行う。 〇トップテールを観察し、学びを得る。 〇マネージャーの評価:業績とチームの満足度 〇良いマネージャーのチームの8つの属性 1.良いコーチであること。 2.チームに権限を委譲し、マイクロマネジメントをしないこと。 3.チームのメンバーの成功や満足度に関心や気遣いを示すこと。 4.生産性/成果志向であること。 5.コミュニケーションは円滑に。話を聞き、情報は共有すること。 6.チームのメンバーのキャリア開発を支援すること。 7.チームに対して明確な構想/戦略を持つこと。 8.チームに助言できるだけの重要な技術スキルを持っていること。 〇上司を評価する質問事項のサンプル 1.上司は、私が成績を上げるための実行可能なフィードバックをくれる。 2.上司は、「マイクロマネジメント」をしない(部下が処理すべき細かいことまで手出ししない。)。 3.上司は、私をひとりの人間として見て、思いやりをもって接してくれる。 4.上司は、優先事項である結果/成果物にチームを集中させる。 5.上司は、自分の上司や上層部から得た関連情報を定期的に知らせてくれる。 6.上司は、ここ半年のうちに私のキャリアに関わる有意義な話し合いをしてくれた。 7.上司は、チームの目標を明確に伝えてくれる。 8.上司は、私を効率よく監督できるだけの専門知識(例:技術部門ではプログラミング、財務部門では会計)を持っている。 9.私は、上司をほかのメンバーに勧める。 〇自分のフィードバックを公表し、至らなかった点について、改善するよう努力して範を垂れる。 〇デリバレイト・プラクティス:消化しやすい量に分割して、似たような小さなタスクを繰り返し、即座にフィードバックや修正、実験を加える練習方法 〇職場内のトップが教え合う。 〇成果への賛辞、熟慮の上での失敗に報いる。 〇nudge:選択肢を排除せず、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能なかたちで変える選択アーキテクチャの要素 〇新人との対話、質問をする、役割を理解する、チームの位置づけを考える、目標を設定する、フィードバックをする。
2投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはやっぱり、グーグルだから出来るんでしょといいたくなるわけですが。 情報漏洩が起きてもなお、全社員に向けて情報公開するという、社員を信じることに関しては、純粋にすごいなと思う。 自分が求める人材を明確に定義してみるとか、やってみると面白いかも知れません。
0投稿日: 2016.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ〈メモ〉 ・従業員に創業者のように振る舞う余地を残す。 会社全体の創業者でなくても、チーム、家族、文化の創造者であると思えること。最高の創業者はほかの創業者が自分と並び立つ余地を生み出すもの。 ・グーグルには文化的礎石として、明確なミッション、情報の透明性、発言権がある。 ・素晴らしい文化を築くために、自分の仕事は重要なミッションを持つ天職だと考えよう。社員に与える責任、自由、権力の程度を、安心して与えられるよりやや大きくしよう。不安を感じていなければ十分ではないということ。 ・採用のために。資源が限られていることを考え、人事予算をまず第一に採用活動に投資すべき。時間をかけて最高の人材だけを雇う。なんらかの点で自分より優れた人材だけを雇う。マネジャーに自チームのメンバーの採用を任せてはならない。 ・卓越した採用候補者を見つけるために。自分が求めるものを徹底して具体的に描くことで最高の人材を紹介してもらう。採用活動を全社員の仕事の一部にする。最高の人材の注意を引くには、突拍子も無いことでも恐れずやってみる。 ・問うべき資質、一般認識能力、リーダーシップ、グーグル的であること、職務関連知識 ・社員への権限委譲のために、マネジャーの意見ではなく、データに基づいて意思決定を行う。社員が自分の仕事や会社の指針を定める方法を見つける。期待は大きく。 ・業績評価のために、目標を正しく設定する。同僚のフィードバックを集める。キャリブレーションを活用して評価を完了させる。報酬についての話し合いと人材育成についての話し合いを分ける ・グーグルのプロジェクトオキシジェン 良いコーチ、チームに権限委譲しマイクロマネジメントしない、メンバーの成功や満足度に関心や気遣いを示すこと、生産性成果思考、コミュニケーションは円滑に話を聞き情報共有する、メンバーのキャリア開発を支援、チームに対して明確な構想戦略を持つこと、チームに助言できるだけの重要な技術スキルを持っていること ・日本のテールを管理するために、困ってる人に手を差し伸べる。最高の社員をじっくり観察する。調査やチェックリストを使って真実をあぶり出し、改善するよう社員をせっつく。自分のフィードバックを公表し、至らなかった点について改善するよう努力して範を垂れる。 ・学習する組織を築く 講義を消化しやすい量に分割して、明快なフィードバックを提供し、繰り返し学習する。社内で最も優秀な人を教師にする。トレーニングを受けた人の振る舞いを変えるようなプログラムに投資する。 ・不公平な報酬 社内の摩擦を恐れず、不公平な報酬を払う。パフォーマンスのべき分布を反映して、報酬の決め方に幅をもたせる。報酬の内容ではなく実績を称える。メンバーが愛を伝え合う環境を作る。熟慮したうえでの失敗に報いる。 ・ワークルールズリスト 1仕事に意味を持たせる 2人を信用する 3自分より優秀な人だけを採用する 4発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない 5 2本のテールに注目する 6カネを使うべき時は惜しみなく使う 7報酬は不公平に払う 8ナッジ きっかけづくり 9高まる期待をマネジメントする 10楽しもう
0投稿日: 2016.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ8章だけでもお金を払う価値がある。 ボトムテールの扱いをどうするか。社員の心情と状況、会社のコストを考えて対応を決め、実践して結果を考察している。 本当によく考えて実践していると思う。 上からの押し付けではなく、実践して事実をもとに判断しているので、社員も納得感があるだろうと推測する。
1投稿日: 2016.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に良書。500ページを超える分厚い本だけど、読んでよかった。 Googleを「People Operations」(Human Resourcesではない)から十年以上ささえた著者のグーグラーとしてのキャリアライフからはたくさんの示唆にあふれる。 とはいっても、一つ一つはエキセントリックなものではない。 ・Fact(Data)に向き合い、インサイトし、進化のための仮説を得る ・スモールスタート、小集団で実験し、効果が認められたら全社に展開し本採用 それを、著者が担当する範囲で愚直に実行した結果だと思う。 必ずしも、全てがFact(Data)に基づき切った仮説というわけではないが、逆にそうでないものには、人としての気持ち・感謝・感動があった。このバランス感もとても勉強になる。
0投稿日: 2016.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の採用プロセスを考え直すために、読んだ。 本書の前半は採用に関することばかりだが、その前半に書かれていたことをできる限り取り入れてみたら、会社の状況は劇的に良くなった。 名著。後半については喫緊で必要なことは書いてなさそうだが、近い将来読み込みたい。
0投稿日: 2016.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前提として、私は前評判からGoogleは天国のような会社であり、 旧態依然とした軍隊を作ろうとする日本の会社は地獄・悪であるという 偏見を持っている。 奇抜な採用試験をしていることが過去に話題になったことがあったが、 その試験で採用した人間は0人だったという話は印象に強く残った。 Googleほどの大企業でなくとも、 自社内に独自の採用の仕組みや部署を持つことは 結果としてコスパの良いことなのかもしれないと感じた。 私自身の過去の経験として、外部のヘッドハンティング会社経由で ヘッドハンティングされて来た部長が会社の方針とは異なる方向へ走り、 結果、左遷>退社という道を辿ってしまったのを見てきたからかもしれない。
0投稿日: 2016.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグル社のHRM(people operations)に関する内容です。採用、研修、報酬、厚生等についてグーグルらしい手法が紹介されています。不断にクリエイティブであり続けるために、多くのデータとエビデンスでグーグラーを育成している努力がみてとれます。
0投稿日: 2016.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログWORK RULES! - http://store.toyokeizai.net/books/9784492533659/
0投稿日: 2016.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
個人の働き方に関しての本かと思ったら、組織の話だった。でもGoogleの組織で行われていることをここまでオープンに書物に記すのはやはりGoogleたる所以だと思った。こんな企業で働けたら素敵。
0投稿日: 2016.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人事担当役員が書いた人事制度に関する本。 そこからグーグルの企業文化が感じ取れて面白い。 わかりやすいミッションが大切。 「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにする」 というグーグルのミッションはわかりやすい。 社員に与える責任、自由、権力の程度は、安心して与えられるよりやや大きくする。不安を感じてないとしたら、十分に与えていないということ。 自分の考えを確証するために情報を探す「確証バイアス」。 カーネマンの本で読んだ気がするが、他の本で、他の例で読むと理解が深まるし定着する。 《面接で問うべき質問》 ①一般認識能力 ②リーダーシップ ③「グーグル的」であること →愉快なことを楽しむ、ある程度の謙虚さを備える、極めて誠実、曖昧さを楽しむ余裕がある、人生において勇気のいる、あるいは興味深い道を進んでいきたいという証拠を手にしている。 ④職務関連知識 サラリーマンを「過去の日本に特有の年功序列と終身雇用を土台とするキャリアを示す用語」と説明しているのが面白い。 やっぱり世界的に見たら変な慣習なんだ。 意思決定が、トップダウンではなく、現場の意見を大切にしている感じがする。 とても好感が持てる。 タイガーウッズが雨の中でのショットの練習をしていたという話は、絞り込むことの価値を端的に伝えている。 キャリア25年の中学講師が、フィードバックの無い反復した授業を繰り返した結果、20年間同じ1年の繰り返しをしていて、進歩していなかった。 学習のプロ達が掲げる、「70対20対10のルール」は、大概が機能していない。 ・何をするべきかが明確で無いから ・するべきことがわかっても、成果を測定する手段が無いから ・学習の資源や経験を70対20対10で配分することが効果を上げているのか、厳密に証明する方法が無いから 《チームや職場を変える10のルール》 ①仕事に意味を持たせる ②人を信用する ③自分より優秀な人だけを採用する ④発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない ⑤「2本のテール」に注目する ⑥カネを使うべきときは惜しみなく使う ⑦報酬は不公平に払う ⑧ナッジーきっかけづくり ⑨高まる期待をマネジメントする ⑩楽しもう!(そして、①に戻って繰り返し)
0投稿日: 2016.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
HR改め、ピープルズ・オペレーションとして、Googleの採用、育成、業績評価などがわかる一冊。業容拡大のために物凄い勢いで優秀人材を採用しつつ、彼らのパフォーマンスを最大化させるのが凄い。やはりデータに基づいた施策を行っているのは頷ける。
0投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグル人事担当の人が書いた本。 人事担当でなくても、会社をこのようにしたいというような夢を描く参考になるはず。
0投稿日: 2016.04.09人の適性とは、能力とは。
Googleが実施してきた、採用、育成、評価に関して、実際のエピソードを交えながら書かれている本です。 個人の観点よりは、制度や仕組みの話が多いので、何かしらこういった分野に関わる方じゃないと、読み進めるのがつらいかもしれません。 個人が最大限能力を発揮するためには、どんなことに配慮する必要があるのか、適性とはどう見るのか、など、人間の本能的な行動も踏まえながら体系化されています。 定性的なものを、どうやって誰もが納得できる形にするのかは、すごく本質的ですし、難しいけれどやらなければいけないこと。それを形にしているのはすごいの一言です。 何よりGoogleの強みは、こういったトライアンドエラーを、短サイクルで実施し続けていること、自分たちが決めた事をまずは信じきることなのかな〜とかんじた本でした。
3投稿日: 2016.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログHRという視点がガラッと変わった ・・というほどではないが。 Googleという企業の特殊性よりは、「これからの」企業への示唆が強いのかも知れない。 なるほどということがない訳ではないが、すごく売れている理由はあまり分からなかったりもする。 どう評価するか判断が難しいので、とりあえず中立。
0投稿日: 2016.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ人事の仕事をサイエンスしており、アウトプットが論理的であり公正である。日本の人事評価制度は機械的で妙に平等であり、底辺を重視しすぎる。公正な評価で、より人財を活性化するためにどうするかというエッセンスが本書に書かれていると思う。
0投稿日: 2016.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログむかーし昔、ある人たちと「従業員が他の従業員に投票してボーナスの金額を増やす」仕組みを入れよう、と盛り上がったことを懐かしく思い出した。偉い人たちにかるーく一蹴されましたけどね。なるほどGoogleでは導入済ですかそうですか。 「自分がやろうとしていることを信じる」、そして「失敗はつきものだからトライ/実験する」、というシンプルなことを突き詰めていくとこうなる、という話。なのにほとんどの会社ができないのだから、人事はかくも難しい。 最適な人的資源管理は会社の数だけあるので、本書の事例を真似すりゃいいってことではないですが(それを勘違している人がどれだけ多いことか!)、考え方について示唆に富んだ本です。
0投稿日: 2016.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleというと凄い組織だという印象があるし、たどり着いた結果(20%ルールなどが分かりやすいだろうか)は必ずしも普通の企業に出来るものではないように思える。 ただ、この本を読んで分かるのはその原則が思った以上にシンプルに映った。 人の本質、経営の目指すところをただ追い求めて試行錯誤をした結果というところだろうか。 まずは全体感を捉えるために読んだ一回目。細かい吟味はまた改めて行いたい。
0投稿日: 2016.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れたGoogleの人事を書いた本。各論として何度か読み直したいと思うが、思った以上に基本に忠実にPDCAを回した結果ということのように思えた。急がば回れの重要性を改めて感じた。人事にも王道はなさそうだ。(いしの)
0投稿日: 2016.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人事に関する仕組みや哲学を教えてくれる本書。 スタッフに権限委譲したり、自由度を高めたほうがアウトカムは向上するのだ。 グーグルが仕組みを作るときに、比較対象試験をして統計学的に根拠を出して、仕組みを実行に移しているのはさすがグーグルというところ。
0投稿日: 2016.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ人事の端くれとして読んだが、自社とGoogleの違いが大きすぎて、あまり参考にならなかった。 様々な人事制度やGoogleという会社や事業について、もう少し学んでから再読したい。 こんな会社で働いてみたい、とは感じたし、日本の会社もGoogleのように変革を恐れず、多様性を受け入れる制度・風土を整えるべきだと思う。 訳は非常に読みづらい。英語が多少分かる人なら時間をかけてでも原書で読んだ方がスッと入ってくるかも。
0投稿日: 2016.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳がイマイチだったけど、すごい組織の裏側も表側もさらけ出されていて、人事の人は確かに必読だなと思った。無理な理由を探すのではなく、理想を掲げて実行あるのみだと思う。
0投稿日: 2016.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事担当上級副社長の著書。 Googleにおける採用、育成、評価について書かれておりいくつもの「新しい働き方」の原理を知ることができる。 また、一貫して根底に流れている価値観は、Googleのリーダーシップは社員に賞罰を与えることではなく、業務の妨げになるものを取り除いてチームを鼓舞することに集中するというもの。 そして、それを実現するために出てくるフレーズが「内発的動機」。 これを、社員を成長させるための大きな鍵とし、いかに内発的動機を自然に引き出し、社員がいっそうの自律と能力を感じるられるかを重要視している。 内発的動機を引き出すためには、従来的な業績管理システムはその動機を破壊するものとみなし、職場ではより大きな自由を認め、自らが最善の直感にもとづいて人事問題に対処している。よって、これらの判断において、データや理論によって補足しようとはしていない。 ゆえに、Google社内では「人が正しいことをすると信じると、ほとんどの人が正しいことをする」という哲学が強く生きており、従業員が「自分は奴隷ではなく主人公なのだ」と思えるようになっている。その結果、業績向上だけではなく、一個人としての活力、自尊心、幸福の増大という点でもよりよい結果をもたらしているということである。
0投稿日: 2016.02.01データの裏付けは凄いですね
Googleの人事トップが書いた本。データの裏付けがあって流石にGoogleらしいと思いましたが、これはこれであれだけの会社だからできるのかな、とも思わなくもなかったり。 電子書籍&ちょっとずつ読んだせいか、あまり記憶に残ってないのが難点...(^^; 翻訳が合わなかったのかな?
0投稿日: 2016.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログいまや全世界に6万人の社員を抱えるGoogle社。その人事担当上級副社長ラズロ・ボック氏による著書。「世界中の情報を整理する」使命を掲げるGoogleらしく、人材育成についても貪欲にトライ&エラーしてExcellentを求め、その経緯とノウハウを惜しみなく公開している。 常識に捉われず、ゆえに結果は常識どおりだったり非常識だったり。いずれの施策にも共通して言えるのは奇を衒ったわけではなく人材の重要性を理解したからこそトライした施策だったということだ。例えば話題にもなった高速道路脇の看板に掲示した難問による採用テストは意外にも採用数ゼロだったことだ。理由は孤高の天才ではなくチーム力のある天才を求めていたことを改めて理解したから。ほか、べき乗の不公平な報酬を行ったり、gThank!による称賛するシステムを導入したり、かと思えば最高と最低の2テールを比較することでまるで新人のようなチェックリストを作りナッジを推進したり。これは何が最もExcellentかを追及しているからこそできることだろう。 いつの時代も流行の企業の経営手法は持て囃され、栄枯盛衰を繰り返していくが、本書を読む限りGoogle社の驀進はまだまだ止まりそうにない。人事担当者は必読の一冊だ。
0投稿日: 2016.01.19人事方面からGoogleの失敗例を紹介した希有な本
Googleの人事のトップがGoogleという会社を如何に育てていくために悪戦苦闘したことを赤裸々に綴った本です。 Googleを育てるとはいっても、技術方面の話ではなく、人事、文字通り人を雇う為に行ってきたこと、社員教育、昇級、そして福利厚生の方面の話がメインとなっています。 世間一般の会社は見習うべし。と、いったものやら、これは会社の業種によっては真似したらかえってマイナスになりかねないといった話まで臆面も無くさらしてくれています。 Googleの凄いところは、新しいシステムを自社に用いるのに、必ず検証を行うところ。 そして、実験的システムを実行するのに一番大切なことは「サービス期間で永続的なものではない」ということを社員全員に告知することです。 過去に、この告知をしなかったら、Google社員が暴動を起こしたそうですから・・・(笑) また、Googleの意外な一面として、社員教育に重きを置いてないことです。 本書では「がんばれベアーズ症候群」と呼んでいますが、教育さえ施せばどんな社員もエリートに負けないという幻想に囚われていると切って捨てています。 「がんばれベアーズ」とは、自分が子供の頃に放映していた、アメリカのドラマです。落ちこぼれ集団である、少年野球チームが幾多の試練を乗り越えて、最後にはエリートチームに勝利する話です。 Googleでは、質の高い人物を入社させることがなによりも大事だと結論付けています。 ただ、質の高い人物は、必ずしも学力の高い大学出身者ではないところが肝でもあります。 この本を読んで、Googleは挑戦者なんだなと改めて思いました。 どのくらい挑戦してるかというと、経営陣でさえいつの間にか知らないプロジェクトが立ち上がって、知らない間にプロジェクトが閉鎖されているそうですから。 会社を買収して大きくなった会社というのは、一側面だったというわけです。 成功例ではなく、失敗例を多く載せていることから、会社の人事の人は一度読まれた方がいいです。 一つの成功例は、他の会社には適用できないことは当たり前ではありますが、一つの失敗例は多くの会社に当てはまりますから。
0投稿日: 2016.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ所在:展示架 請求記号:336.4/B61 資料ID:11501493 世界各国で「最高の職場」として認められているGoogle、その新しい「働き方」を知ることができます!! 選書担当:伊藤
0投稿日: 2016.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ"ワークルールズ グーグルの人事責任者が書いたこの本。 500ページを超えて読み応えがあります。 参考になる点もありましたが、 それ以上に、やはりGoogleという企業は素晴らしい!! そう感じさせられる1冊でした。 世界の歴史の中で、 世界で最も人類の成長に貢献している会社はどこなのか? 答えは Google ではないかと思いますね。"
0投稿日: 2016.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事(people's operations)担当上級副社長のラズロ・ボックがGoogleの人事のルール - 採用・評価・報酬・人材育成など- について自ら書いた書いた本。Googleのポリシーがそうであるのを反映してのことであろうか、かなりオープンにその仕組みや経緯が語られている。が、その分結構長い。kindle本だったので、最初は気が付かなったが、なかなか進まなくてもう少し短く凝縮できたんでは、とは思う。でも当然内容は悪くない。 Googleの人事の基本は、優秀な人を集めてその主体性に任せること。ものごとをオープンにして、社員の間で闊達で自由なコミュニケーションを取らせること、だ。Googleが、それができる会社になったということが重要だが、やはり最初からその思想があったればこそとも言えるかもしれない。すでに一般にも有名になっているTGIF会合や20%ルールもその表れだが、この本を読むとその思想が(少なくとも著者が見る範囲では)常に意識されていることがわかる。また、人材はべき乗分布にしたがうものという認識を持つことが重要であり、そのために報酬は不公平でいいという点は意外でもあり、Googleらしくもある。 Googleの特長は、とにかく優秀な人を彼らのチームに惹きつけるということである。そのための採用活動に非常に多くのリソースとアイデアを費やしていることもわかる。「自分より優秀なものだけを雇え」や「採用とは利用できる人事機能のうちで最も重要なものだ」といった言葉はそのことを示している。Googleはここに至るまで、ものすごいスピードで事業規模を拡大し、その社員数を増やしてきた。また事業のグローバル化も推し進めてきた(東京オフィスが最初の海外オフィスであったというのは驚き)。その中で、最初はともかく入社希望者はそれを上回るペースで増えたため、Googleへの入社は非常に狭き門となった。Googleの成功はそういった環境の中で「スマート・クリエイティブ」を集めて最大限に能力を発揮させることに腐心したことにある、とこの本は言っているようだ。「人事という仕事は、最上級の敬意を払われる対象ではない」と自ら認めながらも著者はその仕事に誇りと、そして最大限のやりがいを感じているように思う。長くて読むのちょっと疲れたけど、それは伝わってきた。 最後に、この本の中でもそうまとめられていたことを書き出してみたい。 ①仕事に意味を持たせる ②人を信用する ③自分より優秀な人だけを採用する ④発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない ⑤「2本のテール」に注目する ⑥カネを使うべきときは惜しみなく使う ⑦報酬は不公平に払う ⑧ナッジ -- きっかけづくり(※ ナッジについては『実践行動経済学』などを参照) ⑨高まる期待をマネジメントする ⑩楽しもう! なるほどって思うだけではダメなんだろうな。 ※ 数少ない日本に触れられた箇所でこういった表現がある。「歴史的に、日本の大学生は塾での欝々とした時間と「サラリーマン」(過去の日本に特有の年功序列と終身雇用を土台とするキャリアを示す用語)生活の単調さをの狭間で、遊びと自由という最後のあがきにふける。日本の大学の成績は採用データとしては実質的に意味がないが、どこの大学に通っていたかを知ることは、少なくとも新卒者については役に立つ」 - 今でも、またGoogleから見てもいまだこうなんだろうか。昔は確かにまったくその通りだったよね。少し残念。なんだろうか、アメリカと日本とが、この20年ほどであまりにも遠く離れてしまったような気がする。
1投稿日: 2015.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ生き方とリーダーシップを変えるために 天職は自分の考え方次第 まずは小さいところから始める マネジャーは極めて重要 いいコーチは技術スキルを持っている 間違いから学ぶ 自分で選ぶ 必死に働け、見せびらかすな
0投稿日: 2015.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人事担当者が書いた本。 人材について考えさせられました。 【記しておきたいポイント】 『報酬ではなく成果を称える』 『社員に自由を与えれば、驚くようなことをしてくれる』
0投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログp311〜で一旦返却 何回も、借りては返し。 を繰り返し。 しかし、今日読んだらハッとした。 グーグルの採用、おもしろくない⁇ 人事で採用の仕事をしてる方にはオススメ。 もちろん、このインフラは、グーグルだから、デキるんだけどね! はじめは、『リーダーシップ』を学ぶためにこの本をとったが、違った。 と、思ったが、リーダーシップとは、つまりは、組織創り→採用 なのか! と思えた。 転職する気がある人も、読んだ方がいいと思う。 249 リアルタイムでフィードバックを受ける方が1年後に言われるより良い
0投稿日: 2015.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ直結はせずとも、どこかで生かせる内容だと思う。Googleの何でも試す社風は素晴らしい。実験してみてダメならばやめれば良いという前向きな取り組みをしたいものだ。人事評価についてはどこでも悩んでるんだと再認識。
0投稿日: 2015.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグル人事のトップによる、世界最高の職場を導く採用、育成、評価を記した本。 採用については、自身が採用に携わった時のポリシーと同じ言葉があった。「自分より優秀な人だけを雇う」そして、最高の人材の「最高」とは知性や専門技術といった唯一の属性によって定義されるものではない。そして、マネージャーに採用権限を与えてはならない。さらに、面接では、ケース面談や、飛行機にゴルフボールを何個入れられるかといった奇問系は全く意味ない、時間の無駄とバッサリ。実際の仕事とリンクしていない。ではどうするか?一般認識能力(地頭)、リーダーシップ、グーグル的であること(愉快なおことを楽しむ、謙虚、曖昧さを楽しむ余裕がある)、職務関連知識(専門性は優先順位が低い)を評価する。 育成に関しては、兎に角新人から若手教育にお金と時間を注ぐ。◯◯グルという、社内である道のスペシャリストから学ぶ機会を提供している。これは自発的な動きであり、それが全社的にうまく行っている。社外の人が自社と全く違う商品を誰に売るかというようなセミナーはやはり効果薄だろう。最善の学習方法は教えることだ。社員が教えること、教わることともにやればいい。 評価は、キャリブレーション(評価の適切な調整)が本質。本人の評価に対して、マネージャーが集まって評価案を検討し、調整を入れる。一方で、直近バイアス(最近やった事案のイメージがついている)が最もやっかいなので、議論の方向性が間違わないようにガイダンスを作っている。
0投稿日: 2015.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★2015年11月7日読了『ワーク・ルールズ!―君の生き方とリーダーシップを変える』 ラズロ・ボック (著) 評価B PRには、Googleの人事トップが採用、育成、評価のすべてを初めて語った。創造性を生み出す、新しい「働き方」の原理を全公開!とあるので、内容にはあまり期待していませんでしたが、何かのアイデアのネタがないかと読んでみました。勿論、世界最先端の会社と米国カリフォルニア州の本社というあまりに違いすぎる環境は分かっています。それらは置いておいて、以下備忘録に残す人事評価の部分については、やっぱりそうか!というところとなるほど!という箇所はありました。まあ、読んでも無駄ではなかったということでしょうか。 以下備忘録 *Working Rules 1仕事に意味を持たせる 2人を信用する 3自分より優秀な人だけを採用する 4発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない 常に発展的な対話を心がけ安心と生産性につなげていこう 5 2本のテールに注目する 最も優秀な人と業績の悪い人にコンタクト 間違った役割を与えられている可能性がある 6金を使うべき時に惜しみなく投入する 7 報酬は不公平に払う 8ナッジ きっかけ作り 9 高まる期待をマネジメントする 10 楽しもう!! *人事評価の公正さを確保する為にキャリブレーションというマネージャーのグループで部下の評価案を検討している。 それでも、ホーン&ハロー効果 直近効果 根本的な帰属の誤り 中心傾向 可用的バイアスなどに気をつけなければならない。 帰属的とは、ある人の能力に注目しすぎて彼らのパフォーマンスに及ぼした状況を軽視する事 可用的バイアスとは、よく頭に浮かぶ事が実際に起こる事だという錯覚 *業績評価と人材育成を結びつけてはならない。これら二つは同時に議論してはならない。人材育成の議論は常に行うべき *マネージャー向けガイド 業績全般 継続的に行う事と次のステップ 改善すべき事と次のステップ より長期の目標 まとめ *プロジェクト オキシジェンの8つの属性 優れたマネージャーは呼吸と同じで必要不可欠な存在 マネージャーを向上させるのは新鮮な空気を吸うのと同じ。 1 良いコーチである事 2チームに権限を委譲しマイクロマネジメントをしない 3チームメンバーの成功や満足度に関心や気遣いを示すこと 4生産性 成果志向である事 5コミュニケーションは円滑に話を聞き情報は共有すること 6チームメンバーのキャリア開発を支援すること 7チームに対して明確な構想や戦略を持つこと 8チームに助言できるだけの重要な技術スキルを持っていること *組織やチームの学習効率を上げる方法の一つは、学習するスキルを細かい要素に分けて具体的なフィードバックを即座に返すこと そして人に教える機会を与えること きちんと教える為には教える内容についてじっくりと考える必要がある。そのテーマに通じていて、他人に知識を伝える洗練された方法を身につけなければならない。 *ナッジとは きっかけのこと
0投稿日: 2015.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-12090275774.html
0投稿日: 2015.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業にとって優秀な確保することは、最優先の課題といえる。よくぞここまで公開したものだ。今年のビジネス書を代表する本。現在のグーグルはこの先を行っているんだろうなぁ。
0投稿日: 2015.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ評判が高い本だけど、あんまり感銘は受けず。そりゃ、1個や2個は、ヒントもあるのだが、全部を読む必要はないくらい、内容の割には分厚すぎる。
0投稿日: 2015.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事を担当する著者が、Googleの人事、具体的には、採用・教育・業績評価・報酬福利厚生など、とかく変わっていると噂されるGoogleのシステムについて明らかにしている本書。わずか20年弱で数万人規模に大きくなったベンチャー企業Googleが、優秀な人材の採用と会社の発展のために必要性にかられ試行錯誤して創り上げた人事システムです。世界中の優秀な人々が集まった会社であるからこそ出来る部分もある、真似はできない、という要素は多分にあるが、自分の職場でもこうだったらなぁ、と参考になる要素はたくさんある。少なくとも、何も考えずに官僚のいいなりになって、内実を伴わない安直な”トップダウン”組織へ改革していく日本の組織の”トップ”には参考にして欲しいと感じた。
0投稿日: 2015.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
google社の採用、研修、評価といった人事から福利厚生までを含むピープル・オペレーションとして、どのような思想と取り組みを行ってきたのか。 失敗事例や不満足な取り組みも含めた紆余曲折が語られているので、実情が分かる半面、冗長に感じた。 社員をグーグラーと呼び、創業者のように考えることを求め、性善説に立ちつつ少数の悪を想定範囲として許容してしまう(もちろん問題を起こせば過失でも解雇する)企業文化に、自分の勤め先との大きな違いを感じた。 働き手の自由度を上げ、それぞれに創業者のような思考と活動を認めても、すべてが上手くいくわけではないが、こうした日本ではユニークな企業文化の会社が営業的にも成功し、成長することを願う。また、そうしたユニークさの、出る釘を打たないような度量が、意識として広がることを願った。 15-217
0投稿日: 2015.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのトピックを知る必要に迫られて、ちょうど社内においてあったので手にとって慌ただしく読んだ一冊。 日本だけではなく世界でも常に「働きたいランキング」のトップレベルとして評価されるグーグル。そのグーグルの人事部門の責任者が(かなり)具体的な社内事例や詳しい仕組みとそのフィロソフィーをまとめた、550ページを超す大作です。 大作すぎて積読リストが滞ってる人には中々キツイ一冊なので、どうしても効率的にエッセンスを得たい人は目次と巻末に記された人類の叡智であるチェックリストにざっと目を通して、気になるトピックだけピックアップして読む、という使い方も出来る便利な一冊です。 グーグルの働き方については現場のエンジニア目線で語られた「チームギーク」、トップマネジメント目線で語られた「How Google Works」ともはや食傷気味のラインナップではあるのですが、本書は人事部門(グーグルではHRではなくPOと呼ばれるらしい)トップ、つまり人事の現場責任者が大きな力を割いただけあり、前述の二冊を読んでいてもなお目覚ましい発見をいくつも見つけられる良書でした。さすが「働きたいランキング」トップの常連と言えます。 個人的に興味分野であったグーグルガイスト(ツァイトガイストではない)とOKRについて、そのフィロソフィーと変遷、細かい運用の仕組みはとても参考になりました。勿論、人事労務管理の仕組みというのは個人それぞれに適した千差万別の学習方法があるのと同じで、ある一つの方法が分け隔てなく全ての企業に完全にマッチする事は無いと思います。ただ、地球上で最も優秀な部類に入る人々によって支持されている仕組みならば、猿真似であっても最低ラインの合格点は取れるのだろうという腹落ち感があります。 改めて感じるグーグルのスタートアップらしくあろうというフィロソフィーはこういう人事労務管理についても根付いているのだろうなぁ、と感じる一冊です。グーグルは紛れも無く大企業ですが、レガシーな人事労務システムを抱えてジレンマに陥った大企業の人事担当者や、ベンチャーで右も左も分からない状態で(企業が抱える問題として大きな部類に入る)人事労務をなんとかしたいと思う担当者、様々な層にうってつけの一冊だと思います。
0投稿日: 2015.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこれをただの理想論と思うか、一つでも自分の仕事の中でやってみようと思うか、が問われるのだろうな。紹介されているシステムは型破りだけど、実によく人間の本質を見ていると思う。驚いたのは、全ての仕組みについて、すべからく論理的に根拠を説明できていること。説明ができるから、多様な人に受け入れられる。奥が深い。 個人的には、マネージャーの役割定義「意味を見つけるサポート」とナッジ「選択を強制するのではなく、選択しやすい環境を作る」というところに大きな学びがあった。また読みたい。
0投稿日: 2015.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ感動!こんな自由な組織を作りたい。グーグルの文化の3つの礎石:ミッション、透明性、発言権。意外だったのが、マネジャーの重要性。そのため実施されるUFS。まずは所長が評価を受ける必要あり?
1投稿日: 2015.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人財に対する考え方。Human ResourceではなくPeople Operationsという呼称が意味するところ。どのように同じ基準で採用人数を増加させていったかなど参考になるところが多くあります。
0投稿日: 2015.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ全世界で約6万人の社員を抱えながらも「大企業病」に陥ることなく、世界中で「最も働きたい職場」に選ばれ続けるグーグルの人事責任者が、同社の人事戦略の”肝”を解説した一冊。 グーグルでは、あくまで「性善説」に立って社員を信頼し、徹底した権限移譲と情報共有によって「創業者意識」を醸成する一方、ともすればヒエラルキーに頼りがちな人間の「弱さ」を見抜き、政治や権力ではなく、「データ」と「集合知」を基にした客観的な議論や、多くの「実験」による検証を通じて意思決定を行う。例えば採用も評価も昇進も、直属上司だけでは決められず、必ず他のマネージャーなどの複数の目でチェックされることで「公正さ」や「透明性」が確保されるという。 結果としてマネージャーはチームのために「奉仕するリーダー」となり、社員は内発的動機に従って目標達成に向けて努力し、様々な場面で相互にフィードバックがなされることで成長し続ける。グーグルは、官僚主義とは無縁の、いわば”最強の学習する組織”を追求している。企業に限らず、全ての組織が個人との関係を根本から見直すべき時期に来ているとすれば、本書を単なる「理想論」で片付ける組織に未来はない。
0投稿日: 2015.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「最も働きやすい米企業100選」(フォーチュン誌)に4年連続、6回目の首位に選出されたグーグル。そのグーグルの人事担当責任者を務めるラズロ・ボック氏が、同社の企業文化から採用、評価、報酬の決め方に至る人事政策について、認知心理学や行動経済学の理論を駆使しながら平易かつロジカルに解説しているのが本書である。 グーグルが目指すのは、究極の「自由度の高い」組織。地球上で最も有能な人々から最高の洞察と情熱を引き出すには自由主導型の組織でなければならないという信念に基づいている。 同社では、マネジャーが他人の意見を聞かずに採用、報酬、昇進を決められない仕組みになっている。現場のマネジャーに代わって、部下、他のマネジャー・グループ、委員会、専門チームが、採用、評価、昇進をそれぞれ意思決定する。組織の上位者にとって都合のいい人が評価される仕組みになると、情報の透明性や、自由に発言できる文化が崩されるからだ。マネジャーの役割はチームに奉仕することという考えが徹底されている。 権限より透明性を重視する文化は、データの活用方法にも表れている。同社では「グーグルガイスト」と呼ばれる年次の社員に対する匿名調査がある。結果は全社で共有され、見落とされてきた社員のニーズや問題点が明らかになる。マネジャーはその結果から何を改善すべきかを学ぶことができ、人事部門は新たな評価システムの進化につなげる。評価尺度や職場環境をよりよくするためであり、社員の帰属意識を把握するような監視が目的ではない。 従業員6万人を超える大企業に成長した同社が、創業時のベンチャー精神を失うことなく進化し続けているのは、社員が尊厳を持って扱われ、自由に発言できる自由主導型の組織を目指しているからに他ならない。 本書で紹介される人事政策の多くは「グーグルだからできるのだろう」と思わせるところもある。世界で最も優れた人材をそろえようとする同社だから実現できる形かもしれない。しかし、情報技術の発達で機械化される仕事が増えつつある中、従来の指揮統制型の組織が生み出す価値は確実に低下しつつある。多くの企業はこの点に気づきつつ何から手を付けていいかわからない状況にある。本書にはそのヒントがちりばめられている。社員が生き生きと創造性を発揮する組織にしたいと考える経営者や人事担当者はもちろん、新たな働き方や組織に関心がある人に必読の一冊である。 原題=Work Rules! (鬼澤忍・矢羽野薫訳、東洋経済新報社・1980円) ▼著者は72年ルーマニア生まれ。グーグル人事担当上級副社長。 《評》日本リサーチ総合研究所主任研究員 藤原 裕之
0投稿日: 2015.09.06
