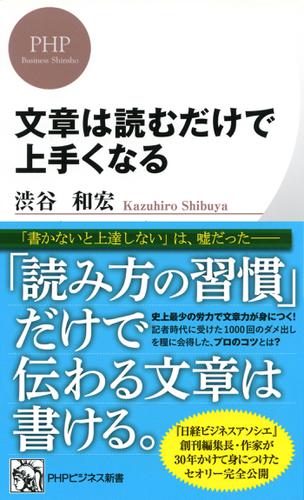
総合評価
(12件)| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、文章を書く機会が多くなった。自分の文章力をあげたい!と思って読んでみた。 【感想】 1新聞の社説は、既に要約されているので、リーダー文を勉強できそう 2頭で考えるより、手を使って「書き出す」という作業が重要 3季節感や、自分の知識▪経験を活かすことで説得感のある文章が書ける
0投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文のリーダー、フォロワーを意識して文章全体を読むことで、文章力が身につくという内容です。 実際の記事やラジオ原稿の例文を使って文のリーダー、フォロワー、スケルトン構造を解説しているので、理解しやすいです。 ◆スケルトンの2つのタイプ 1.△(三角)型 これから何を書きたいのかを冒頭で示した後で、それを具体的に強調するエピソードやコメントを紹介 2.▽(逆三角)型 インパクトのある一文もしくは小段落で文章が始まります ▽(逆三角)型の構成はまず「著者は何を言いたいのだろう」と読者の好奇心をかき立てます 印象的なエピソードから入る▽(逆三角)型は最も応用範囲が広い ◆「印象的なエピソード」から始まる▽(逆三角)型の最も典型的な構成 1.最も印象的なエピソードやコメントから入る 2.冒頭のエピソードやコメントが言わんとする内容を書く 3.言わんとするところを補強する二番目に印象的なエピソードを書く 4.三番目に印象的なエピソードを書く 5.なぜそうなったか、理由(原因)を書く 6.原因(理由)のよってきたる本質やその意味するところを書く 7.結び やってはいけない四ヶ条 ・文章中の「こと」「なか」を排除する ・体言止めはとりあえずやめる ・説明と描写を混同しない ・ありきたりな比喩を使わない
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わりました。 文章術の本はたくさん読んできましたが、この本は今後すごく影響を受ける一冊になりそう。 すごく面白かったので、付箋いっぱい貼っちゃいました。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがに本書自体も読みやすく、グイグイ読める。書き出しのセオリーを身につければ分かりやすい説得力のある文章が書ける
0投稿日: 2018.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ日経アソシエなどの編集長を務めた著者が、その経験から会得した上手い文章を書くコツを紹介しています。 さすが雑誌記者という視点での文章術は、最初にリーダーとなる文を持ってきて、インパクトを与え、それを説明する文を続けるという形を繰り返すものであり、雑誌で目を引くような書き方をしていると思いました。 確かに最初の一文で、その後の印象が決まってしまい、その最初の一文をつなげれば、大まかな構成が理解できる、といったあたりは、仕事で使うような分かりやすく、簡潔な文章を求められる場面では有効です。 そのほか、ここで示されたコツやルールはぜひ意識したい。 また、著者の言う「文章は読者へのプレゼントだと考える」という思いで書く文章は、きっといい文章になるはずです。 <この本から得られた気づきとアクション> ・読みやすい文章を書くためには、決まったルールを守る必要がある。決して難しいものではないため、ぜひ意識したい ・これまで自然と使っていた言い回しが、かえって分かりにくさを増していた表現があった。気をつけること <目次> 第1章 文章の読みやすさは、文の順番で決まる(読むだけで文章力が身につくコツとは さらにとっておきの「読むだけで文章力を磨くコツ」 「リーダーとしての文」をつなぐとスケルトンになる 読むだけで、読者を引き込む▽型のスケルトンを体得) 第2章 「読む」から「書く」への効率マニュアル―「伝えたいこと」を口ずさむ(最も伝えたい内容・メッセージを声に出してみよう) 第3章 「伝わる」だけではない「人を動かす」ビジネス文章―説得し、気持ちを揺さぶる「絞り込みテクニック」(文章は読者へのプレゼントだと考えよう 書く内容を絞り込むほど文章の説得力は増す 絞り込みのコツその一 「なぜ今か」を考える 絞り込みのコツその二 「なぜ私なのか」を考える 読まれる企画は「逆Tの字型」) 第4章 「あの人文章うまい!」と言われたい人のために―だれでも守れる「やってはいけない四カ条」(“こと"“なか"れ主義から脱却しよう よく使われる比喩は文章のイメージダウンをもたらす ルポ&小説風文章に潜む失笑もののワナ 文章を名詞で終える体言止めはとりあえずやめよう) 第5章 人々を巻き込み、オンリーワンの成果を実現する―あの人たちが発揮した文章の力(「僕らの武器はミドリムシ」 「実は私はJALが嫌いだった」)
0投稿日: 2015.10.19よく分からなかった。
語り口は非常にソフトで感じが良かったが、内容は思ったより難解で一回読んだだけではあまり理解できなかった。 むしろ例文として出されるエピソードの方が面白くて先へ先へと進んだ。 書くことを職業としている人ならすんなり飲み込めるのかもしれないが、そうでない人には二、三回読む覚悟が必要だろう。私はそうまでしたくはないが。
0投稿日: 2015.07.06裏側から見えるもの
本書は、出版社の記者として長年働いた著者が、文章を書くにあたってのノウハウを自身の経験を元にまとめたものだ。一般人からすると記者といえば文章のプロというイメージを抱く。ただやはり最初から一人前の文章が書けるというわけではなく、著者自身も当初はとても苦労したようだ。しかし、そこから経験を積んでいくうちに、読みやすい文章が持つ様々な共通点に気づいたという。 まず最初に著者は、文章の読みやすさは文の順番で決まるのだと指摘する。例文を通して、同じ文章でも文の順番の違いで読みやすさがこうも違うのかと気づかされる。そして、読みやすい文章は、その段落を象徴する文章を最初の一文に持ってきて、後にそれを説明するような文章が続いているのだと説明する。文章を通してこの規則はなによりも重要なようだ。 ここで著者は視点の転換を図る。文章を読むときにこの規則を意識して、もしそれが守られていない場合には、自分の頭の中で文の順番を入れ替えることでその規則に当てはめながら読み進めるようにする。これを続けていくことで文の順番に対する感覚が高まっていくというのだ。これはまさしくタイトルにあるような、「読み」によって「書き」を向上させる方法に通じるものだ。 以降も同様のプロセスで、「読み」から「書き」の向上を目指す。 内容としては、実際に文章を書くにあたって選ぶテーマは内容を絞り込むことで読者の興味をより引きつけられること、文章を書くという行為は読者へのプレゼントであることなどの書き始める前の心がけや、より文章の内部を掘り下げて、言葉の表現方法や使い方まで言及していく。 このように、書き方から読み方のヒントを得て、またそれを書く際に役立てるというサイクルは、「読み」と「書き」は表裏一体であるという事実と、双方向からお互いを捉える視点の重要性を示しているのではないだろうか。 本書を読む前と後では、文章を読むとき、書くときの意識が大きく変わっていること請け合いだ。
1投稿日: 2015.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ記者視点での読みやすい文章の書き方講座。 文章構成などで読み手を惹きつけたり、理解度を上げたり。ブログなどで人に読んでもらう文章を書いている人には役にたつと思われる。 仕事での報告説明には応用が効きづらいものだった。
1投稿日: 2015.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の心に届く文章の構成がよくわかりました。 今まで自分がどれだけ間違った書き方をしてくたか、気づくことができ、よかったです。
1投稿日: 2015.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ元日経BP社で働いていた記者が相手に伝わる文章の書き方について紹介している。 何でも著者は、入社時に同期と比べて文章がうまく無く散々赤入れされて原稿を真っ赤にされていたらしい。そうした中で上手い人の書き方の法則を見つけ、それに基づいて文章を書いているうちに、文章が上達したらしい。 リードの文章を最初に持っていくこと、前後の繋がりに沿って文章をつなげる事など、まあそうだよね。と言う事が多いが、じゃあできいるのか?と振り返ると、リードの文章や順番などは書き出す前にあまり意識していないと思うし、とにかく書いて読み返した後に順番を変えたり、文章の足りないところを加えたりして、てんでバラバラの文章になっているように感じる。 書き出す前にリードやつながりや構成を考えて書けばきっともっと早くわかりやすいメールを作る事が出来るのだと思った。 また文章の2つの種類(三角型、逆三角型)の説明はわかりやすかった。 三角型:これから何を書きたいかを冒頭で示して、それを具体的に強調するエピソードやコメントを紹介 逆三角型:インパクトのある一文もしくは小段落で文章が始まる。
3投稿日: 2015.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読むだけで文章が上手くなるのは、上手な文章のセオリーの知識を適用しながら、文章の構成を読み解いたり、添削を考えたりの取り組みあってこそ。 そのセオリーとして、リーダー文を小段落の先頭に置き、フォロワー文を続けること、リーダー文だけでスケルトンの構成をなすこと。スケルトンの構成としての△型と▽型。 また、書くための4つのステップ(もっとも伝えたいメッセージの言葉化、伝えたい理由の言葉化、スケルトン、導入部)。文章は読者へのプレゼントであるという意識と絞り込み(なぜ今か、なぜ私か)。 "こと"、"なか"を避ける、紋切り型の比喩を避けるなど、アドバイスも参考になった。 15-27
2投稿日: 2015.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「もし何を書いていいかわからず、なかなかアイデアを思いつかなければ、「何を書けば読者に最も読んでもらえるか」の視点で企画・内容を考えてみてください。」 何を意識すれば良い文章が書けるかについて書かれた本。読むだけで文章はうまくなる、と謳っているが、意識して読む必要がある。 ・リーダーとしての小見出しを各段落の頭に用意する。 ・読者の好奇心をそそるような小見出しにする。 ・最も印象的なエピソードを具体例の初めにする。 ・入り口は狭く。 ・”こと”や”なか”を使わない。 ・”において”や”における”を使わない。 とても参考になった。特に”こと”や”なか”を使わずに文章を考えるのというのが勉強になった。今後は、”こと”や”なか”を使わない文章を意識していきたい。
3投稿日: 2014.12.31
