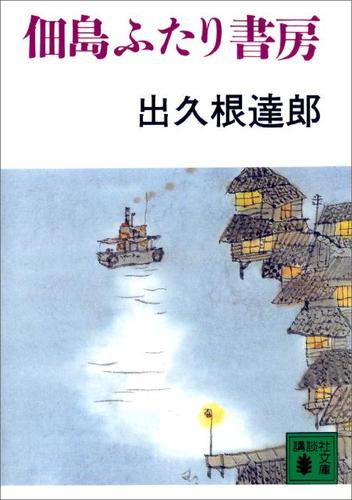
総合評価
(19件)| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治から大正、昭和の高度成長期までの東京を背景として描かれる、古書店主2人の人生模様。諸々の人間関係や伏線が回収されるでもなく、なんとも寸止め的な展開に、現代の小説と比較すると物足りなさを感じる向きもあるかもしれないが、これはこれで余韻があって良い。
1投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ上手く印象を掴むことのできない一冊でした。 明治の終わりから昭和の戦後まで、古書店の小僧として出会った二人がどのように生きてきたかを追いかけていく物語、のように感じました。 上手く感情移入することができず、どの登場人物も印象が薄いです。どこに焦点をおいて物語を読めばいいのかがわからず、最後まで読めば何かが一つにつながって物語が面白くなるのではないかと思っていましたが、結局最後まで物語として何かを掴むことができませんでした。 直木賞に選ばれているということは、このお話の何がしかを掴むことができたら、もっと違うものを得ることができたかもしれませんが……私には合わなかったようです。 面白いと感じたのは、今ではほとんど残っていない『渡し場』のこと。渡し場があるうちは、その島は『島』であるのに、橋ができて、歩いていけるようになってしまえば『地続き』となって島ではなくなったと感じている。そういう、外界と隔絶された感覚が『島』にはあるんだなと、読んでいて感じました。
0投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログスピーディな展開、魅力ある人々、謎。 こういう小説が好きだ。 夏の描写で、うなぎ食べながらかき氷の話をして、 「暑い暑い、28℃もあるよ」が、うらやましかった。 昭和30年代の終わり頃。
0投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内容(「BOOK」データベースより) 佃の渡しが消えた東京五輪の年、男は佃島の古書店「ふたり書房」を立ち去った―大逆事件の明治末から高度成長で大変貌をとげる昭和39年まで移ろいゆく東京の下町を背景に庶民の哀歓を描く感動長篇。生年月日がまったく同じ二人の少年が奉公先で知り合い、男の友情を育んでいく。第108回直木賞受賞作品。 書店のほんわか話かと思いきや、古書が熱かった時代の闇をはらんでいます。昔は本がとても大きな力を持っていたんだと読んでいてある意味うらやましい気持ちになりました。本を語り合ったり議論したりは楽しかっただろうな。 色々盛り込み過ぎて商店がぼやけているのが残念。
0投稿日: 2018.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ(オーディオブックにて) 佃島の話、というのに惹かれて読み始めた。 古本屋の歴史。 あまり期待していなかったに、気がついたら引き込まれていた。 過去の出来事から今に到るまでの佃島を中心とした素敵な話です。
0投稿日: 2017.12.31時代に翻弄されながらも本に関わり生きる
明治後期から昭和にかけて本に関わりながら生きた人達のお話。 登場人物も立ってるし、時代や環境の設定に面白くなる要素はふんだんにあるものの、 人同士の関わりなのか、本との関わりなのか、 どちらをメインに描くのか、いまいち焦点が合っていない感じでしょうか。 それでも読了させるだけの力はあるんですけどねぇ。
1投稿日: 2015.07.03期待しすぎたかも
レビューを読んで、期待しすぎてしまったようで・・・。直木賞作品だし。 残念ながら、ストーリーでそれほど引き込まれるものはなかった。 この時代背景で東京が舞台なら、浅田次郎氏の「天切り松」シリーズのほうが面白かった、かな。好みの問題ですね。ごめんなさい。
2投稿日: 2015.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ出久根達郎さん、1992年の直木賞受賞作 古本屋の話、本好きにはそれだけでも楽しい しかし物語は結構入り組んでいて、佃島という特殊な地域に対する愛着をたっぷりこめながら、共産主義や友情や恋の話を絡めつつ、過去と現在を行ったりきたりします こうやって振り返るといろいろ詰め込みすぎ、作者が描きたかったのはなんだったんだろうという疑問も出てくるけど、タイトルそのまま、佃島の二人書房の物語を描きたかったということかな いずれにしても楽しく面白く読めることは間違いなしです
0投稿日: 2015.01.19「書籍」好きには、たまらない一冊です
本屋さんが舞台だったり、図書館が舞台だったり、そして、本そのものが題材だったりする小説は、あまたあります。いずれも、「本」に対する愛情やこだわりが根底に流れ、本好きにはたまらないものばかりでありますが、この小説もそんな一冊です。 でも、「本」というより、「書籍」といった方が的を射ているかもしれません。電子ブックを読んでいても、本当は、もし大きな大きな書庫を持つことが可能ならば、大好きな本を並び連ねてみたいという願望を誰しも持っているはず。そして、一度くらい古本屋さんをやってみたいなんて思ったことがある人も多いはず。とくに一昔前の本は、装丁からして凝っていますもんね。 この小説は、そんな「書籍」好きには堪らないお話です。舞台は、東京佃島の古本屋。そして、時代は、昭和から関東大震災前までさかのぼります。下町、そして猥雑で混沌としていた時代。そこに生きる人々。ほら~、これだけでもう触手を動かされるでしょ? 物語は、昭和39年、佃の渡しがなくなろうという時、梶田という人が久しぶりに昔働いていた佃島の古本屋を訪ねるところから始まります。その古本屋に住む母娘とこの男の関係、少々ワケありらしい、なんていう冒頭から、古本屋の仕入れの仕組み等興味をそそる内容が続き、梶田の過去話として、関東大震災、そして、幸徳秋水、菅野スガ、平民社まで登場します。あの混沌としていた時代から高度成長期にかけて、必死に何とか生きてきた庶民の息づかいがヒシヒシと感じられる、流石の直木賞受賞作であります。 筆者は書店で働いた経験があるとかで、「あとがき」にも本や本屋さんに対する愛情が感じられます。物語上の「ふたり書房」の「ふたり」とは最後まで謎なのでありますが、この「あとがき」を読むと、筆者の切ない思いが伝わってきますよ。
3投稿日: 2014.11.17あとがきがまたいいんだ
もともと出久根さんのエッセイは好きで、本に対する蘊蓄もさることながら、語り口調が小気味よくて愛読していた。なのでこの作品にも興味はあったんだけど、タイトルやあらすじからしてなんとなく明治大正昭和の日本を描くNHKの朝ドラ的な感動ものを期待してしまって、、、いや、嬉しく裏切られました。 ちょっと昔の日本、昭和39年オリンピックで東京ががらりとその姿を変えたその頃、佃の渡しも静にその歴史に幕を下ろす。物語は佃島の古書店、ふたり書房の店員郡司のそんな“今”と明治の末の大逆事件や関東大震災といった若かりし郡司の“昔”とが描かれている。昔編は色々な事件もあり、ちょっとやんちゃな郡司の活躍が楽しめ、今編の郡司はさすがに年を取ったが、その分ふたり書房現店主の澄子の若々しさがそれを補う。 そして全編を通して何とも言えぬ幻想的な雰囲気が漂うのがまたよい。作者の現在の年齢は昭和39年当時の郡司のそれだろうし、実年齢は澄子とほぼ同じはず。色々な視点が交錯し、当時の東京や古書店や佃島への郷愁と混じり合い、それらが不思議な味わいを醸し出している。で、ここまで読んで今一つ読む気が起きてこない方は「佃島ふたり書房 日本ペンクラブ」で検索し、本作第二部の抄録をご覧あれ。それで何とも来ない人はハイさようなら。
1投稿日: 2014.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ108回 1992年(平成4)下直木賞受賞作。東京佃島の古本屋で仕入れを担当しながら発禁書を収集する男と彼とゆかりを持つ女たちを明治・大正・昭和の時代とともに描いた作品。ストーリーの中につむがれた、歴史に潜む怪しい事件が楽しめる。おすすめ。しかし頻繁に登場する古き東京流おやじギャグは理解が難しく、これらは本当の意味で”死語”になっているのだな。
0投稿日: 2013.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「無明の蝶」が候補に挙がって居乍ら直木賞を逃したと云うから、受賞作の方も読んでみなくちゃと手に取りました。 出久根さんの長編て、どうももったりして、途中で視点が急に変わったりするので、読みにくいかなとあまり期待していなかったんですが、いやー面白かったです。 佃島の情景描写など最初から素晴らしく、質の高い映画を見ている気持ちになります。 主人公がとにかく本を愛しすぎ。 そしてみんなに愛され過ぎです。 古本を題材に、此処まで色々な物が織り込める筆力は (そしてこの長さでこの密度!) 本当に素晴らしい物だと思います。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大正12年(1923)、昭和39年(1964)と、関東大震災、東京五輪前後の東京・佃島周辺で織り成す郡司、六司、千加子の三人の若者の本に賭けた情熱。郡司は満州へ去り、六司、千加子は夫婦に。そして約40年ぶりの郡司と千加子の出会いと千加子の娘・澄子と郡司の心の通い合い。現在の新川周辺の隅田川の情景と合わせ、3時点の時空を超えて、江戸情緒の香りにあふれた素晴らしい作品でした。昭和39年の佃大橋の開通により、初めて渡し船が廃止になった意外な近過去も驚きです。古本は命をもっているという登場人物の澄子へのアドバイスなど、本が好きな人には堪えられない楽しい本でもあります。
0投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ古本屋の女主人が様々な謎を解く、三上延さんの『ビブリア古書堂の事件手帖』(メディアワークス)が少し前まで話題になっていましたが(もうブームは去ったの?)、古本屋を舞台にした小説で、こんな名作がすでにあったんですね~ 1993年の直木賞受賞作品ですから、単に私が無知だったってだけなんですが(苦笑) 作者が実際に古本屋を営んでいる方なので、古本屋の内情についてはとっても詳しく書かれていてすごく面白い♪ また相当な本好きなのが文章の端々に垣間見えて、それを読んでいるだけで幸せな気分になれます! あと細かい事を書くと、佃島と徳川家康とのこと、新しい橋の渡り初めにつきものだという「三代夫婦」による渡り初め、お神輿の担ぎ方や、江戸っ子の「ワッショイ」という掛け声に対する思いなど、明治から昭和にかけての風俗を知ることができたのも楽しかった。 こういう本、これまで読んでこなかったんですよね。 まるで本好き大人向け「ALWAYS 三丁目の夕日」みたい♪
0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ大分前に本や古本屋のエッセイを読んで面白かったので図書館で借りてみました。直木賞受賞されてたんですね~。昨今は賞を取られている方が多くて覚えきれません…。 古本屋の市や商売方法は面白かったのですがお話的にはそれほどグッとくるものがありませんでした。視点がコロコロと変わるからかな?郡さんと六さんのお話がメインなら面白かった気がします。澄子さん視点は余分だったような。何となく向田さんのあ・うんを思い出しましたがこの作品の二人にはそこまでの友情は感じ取れなかった気がします。六さんの描写が少ない所為かなあ… と言う訳で前に読んだエッセイの方が面白かったです。また機会があればこの作者の本を読んでみたいと思います。それにしても今は古本屋の形態も随分変わったろうなあと思います。個人的に神保町とかブラブラするのは大好きですがそのうち少数派になるのだろうな。本自体もそのうちデジタルにとって代わられるのかもと思うとさみしいですね。まあ暫くは大丈夫でしょうが…
0投稿日: 2012.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ佃島にある古本屋を舞台にした話。明治から昭和にかけての東京の歴史をちりばめ、展開する。読みやすかった。
0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ手を挙げるところについてだが、ポンさんの澄子への説教が著者による読者へのメッセージに思えてしまい、そのくどい説明に辟易してしまった。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ第108回直木賞。 佃島にある古書店・ふたり書房が舞台。女主人・千加子亡き後、店を運営するのは娘・澄子だが、物語の中心は老いた従業員・郡司。 彼の本屋人生の始まりからふたり書房で働くようになった経緯、明治時代の「大逆事件」と、大正時代の大震災などを背景とした本屋家業の苦労話など。
0投稿日: 2011.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ同年同日生まれの、郡司と六司。ことによると六司は、一生童貞のままだったのではないか?憑かれたように古本のセドリを続ける郡司の背中を想いつづけた六司と千加子。だれもが孤独だった、とは思いたくないけれど。 昭和初期の東京の古本文化や風俗について詳しく、まるで同時代を生きたような楽しさが味わえた一冊だっただけに、ラストはほんのりもの寂しかった。
0投稿日: 2006.12.13
