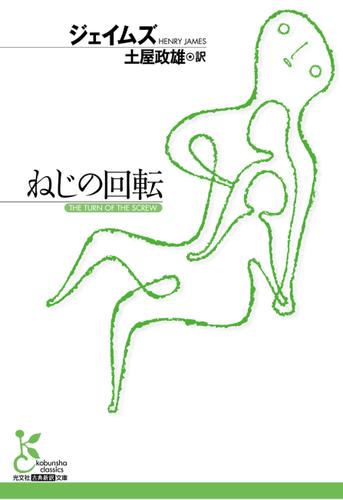
総合評価
(36件)| 7 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 0 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日読んだ翻訳家、鴻巣友季子さんの「ギンガムチェックと塩漬けライム」で紹介されていた本 両親を亡くし伯父の屋敷に身を寄せる美しい兄妹 「雇い主には今後没交渉、相談、苦情、連絡を一切してはいけない…」という条件で家庭教師として雇われた「わたし」は邪悪な亡霊を目撃する。 子供たちを守ろうと勇気を出して立ち向かうのですが… 手記なので「わたし」視点で話は進むのですが、途中から邪悪なのは亡霊なの??と思いました ・聡明で出来すぎた兄妹 ・疑心暗鬼で精神的に不安定な家庭教師のわたし どちらも言動が信用できなくなりました 著者ジェイムズの「なにかを説明しないまま読者の恐怖を征服する」から私が感じた恐怖は幼い兄妹です 私にとって子供は自由奔放で、泣いても笑っても怒ってもいいんです フローラとマイルズ兄妹はいつも笑顔で、あどけなさを演じているかのように愛らしく振る舞います そこに得体のしれない違和感があります その違和感は無口な亡霊よりも怖かったです 読了後、少し落ち着くと恐怖よりもモヤモヤ感が強くなり、もう一度読んだのですが一回でやめておけばよかったと思いました 結局何も起こっていないのにやっぱり怖い 恐怖は広がるのに真相にはたどり着けなかったです 違う訳でも読んでみたくなりました 東京創元社、新潮社、岩波書店にもあるようです 興味深い作品です
112投稿日: 2026.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ両親を亡くしたとある兄妹の家庭教師として、イギリスはエセックスの屋敷に赴任した主人公「わたし」の手記によって展開されるホラー小説。今作の興味深い点は何と言ってもやはり、「信頼できない語り手」の存在である。物語にて2人の幽霊が度々登場するのだが、唯一の語り手である主人公の「わたし」を除き、それらをはっきり見たとされる登場人物がいないため、そもそも幽霊がいるのかという疑問が読み進めていく中で湧いてくる。また、主人公と狡猾な兄妹との間で繰り広げられる緻密な心理戦も今作の見どころである。兄妹と幽霊の関係やマイルズの退学の理由など、主人公が対面する数々の謎は読者の興味を強くそそるに違いない。
1投稿日: 2025.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ購読している英語のテキストで紹介されていたので読みました。 不思議な世界観でした。ちょっとずつ気味が悪くて、でも続きが気になる感じで、おもしろかったです。
6投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ねじの回転』とは、うまいタイトルをつけたものです。ただ、終わり方が”ねじった”まま終わってしまうので、読者としては、まるでネジ舐めした状態で放置されてしまったかのよう。ただ、natsuさんがおもしろかったと書いていたとおり、先が気になって読んでしまう面白さで、とても楽しめました。 あらすじ: 物語は、あるクリスマス・イヴの夜、暖炉の前に集った男女が語り合う怪談話の最中でのこと。一人の男が不気味な出来事を綴ったある女性の手記を読み聞かせるところから始まります。その手記の筆者の女性は、かつて田舎の古い屋敷で、二人の子どもの家庭教師をしていました。彼女は働く条件として、雇い主である子どもたちの伯父から「いかなる事態が起こっても彼には一切連絡しない」ことをいい使っておりました。 屋敷に着いた彼女は、そこで働くグロース夫人と懇意になったり、教え子となる二人の美しい兄妹、マイルズとフローラにすぐに惹かれることになります。ただ、マイルズに関しては、学校に通っていたのに放校になって帰ってきたことが気掛かりではありましたが。 そんな中、彼女は屋敷で不穏な気配を感じるようになります。グロース夫人の語るところによると、この屋敷に勤めていた召使いのクイントと前任の女性家庭教師であるジェスルが不可解な死を遂げているとのこと。やがて彼女は、亡霊となった二人が子どもたちに取り憑いているのではと思い至り、子どもたちを守ろうと決意しますが……。 と、全体的に不穏な雰囲気と不思議な緊張感が終盤まで続くストーリー展開に引き寄せられますが、読み終えるとその結末は曖昧模糊とした亡霊の謎も相まって、なんだかスッキリしない。ただし、その亡霊を認識しているのが誰なのか、また大袈裟とも思える子どもへの偏愛、そして日記を書いた本人が既にこの世にいないこと、さらには日記に書かれている事を全て正しいと思うのは誤りなのではと思うと、『ねじの回転』のタイトルがしっくりきます。まるでゴシック・ホラーの形式で綴られた、著者のイタズラに翻弄されて、読者の”頭のねじ”の締まり具合を嘲笑われているかのようにも思われます。最初に”ネジ舐めした状態”と書いたのは、自分としては、P235を家庭教師が”本当にしてしまったこと”に書き変えると……可愛さ余って……ということなのかなと。あくまで個人的な推測ですけど、気狂いな家庭教師による○人じゃないかと思っていますが真相やいかに?ホームズが生きていた時代なので、ちゃんと仕事しなさいとまで思った自分は考えすぎでしょうか?それにしても、残酷なシーンも無ければ、読み手を怖がらせようとするわざとらしさも無いのに、妙に情景が脳裏に残る著者の書きようには感心しましたね。 ところで、古典の宿命で複数社から出版されている中で、光文社古典新訳文庫を選んだのはただの消去法です。新潮文庫は、2人の子どもの幽霊がこっちを見ていてヤダなと……読んでみて壮大な勘違いでしたが(笑)。 あと、岩波文庫は『デイジー・ミラー』とのカップリングで、タイトルが『ねじの回転 デイジー・ミラー』なのに、ページを開いたら『デイジー・ミラー』『ねじの回転』の順に掲載されていました。訳者は『アスパンの恋文』『ワシントン・スクエア』の行方さんなので好きですが、たまたま腹の虫の納まり具合が悪かったのか、頭に来て買うのをやめたという、なんともまあ、そんなこともあるのです。未読の『デイジー・ミラー』を読むときには岩波文庫にしようかな。
31投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログヘンリー・ジェイムズ初読み。 というかその御名すら寡聞にして存じ上げなかった。 タイトルもジャンルを窺わせない謎めいたもので(原題:The Turn of the Screw)、これがゴシックの系譜を継ぐホラー小説の先駆にして心理小説の傑作でもあるとは、このタイトルからはとても判断できない。 あっさりした文体ながら、そこから「え、こんな重大事をさらりと出す?」みたいな海外文学ならではのドライな意外性の味わい深さ。 まあこんな楽しみ方は邪道なのだろうが、近年においても何作も映画化されているのは本物の証左。
13投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろなことが、オブラートに包まれて語られていく… 時代的な背景があるからかな、と。 マイルズが口にした、退学の原因とはなんだったのか。 マイルズが、「わたし」に対して示した、「成長する」につれて起こる変化… 「わたし」が雇用主に感じている感情などなど… 不思議な話でしたが、最近目にした記事などで、いろんな方がこの本を取り上げていて、読まねば!と思っていたら、図書館の書棚で発見したもの。 新訳版ですが、新潮社からも小川高義さんの新訳が出ているので、いつかチャレンジしたいです。 いろんな側面から「取り憑かれた話」…と理解。 ぐるぐるした展開が難解さにつながっているなあと感じたので3.8点ぐらい。でも、大好きな雰囲気を持つ作品でした。
2投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私には難解で、この本の魅力が分からなかった。 読者に全て明らかにされることはなく、結局なに!?な結末は、読む人を選ぶのではないかなー。
2投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログいまいちよくわからなかった 評価が高い有名な本だから、自分の側の読解力の問題か どんな話なのかさえうまく噛み砕けなかった 丁寧に再読。 噛み砕けはした。 ピーター・クイントとジェスル先生の幽霊からマイルズとフローラを守ろうとする家庭教師。 家庭教師の妄想で、子どもたちやグロース夫人は主人公の家庭教師の異常性に恐れていると読めました。 それにしては、マイルズ1人残して、グロース夫人とフローラは伯父のところに行くっていうのが何故そんなことするのか意味わからない 最後もどういうこと?
3投稿日: 2023.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログわー!わぁぁああーーー! 読後、リアルに叫びました。そうなるのか!そうくるのかぁ!! 世界観がゴシックホラーで、イギリスのあのじめっとしたそれでいて美しい田舎の空気感が感じ取れるので、大好物でした。 言葉の使い方も絶妙で、ねじの回転が一回転でも多く回れば、そりゃぎりっと奥に押し込まれるよね!そんなふうに表現するの、すごいね!!って、驚きばっかり。 気になる表現は山のようにあるし、平凡な自分には永遠に生まれないような言い回しにはただただ、感心するのみです。 おもしろかった。もし、ラストネタバレされてたとしても、きっと同じように驚いて叫んでた気がします。
9投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは自画自賛から いやー面白かった そしてこの物語を面白いと感じられる自分、なかなかの読書人ではなかろうか 非常に読む側の技量を試される物語だと思いました 読む側の技量って何か知らんけども 多くのことを読み手の想像力に委ねてくるんです それでいて空白が少ないんですね 非常に緻密に計算しつくした上で必要最小限のことしか語ってないんですが、とてもたくさんのことが込められていて、読者はその想像力の及ぶ範囲で様々なことが読み取れる文章に感じました 読む人によって怪奇物語であったり、謎解きミステリーであったり、恋愛物語であったりとくるくると姿を変える物語 そしてそれは全て意図して書かれている さらに言えばいろんな人の感想を聞いてみたい物語でした 短い物語なんで是非とも手に取って頂きたいなと思いました 特に19世紀のイギリスの文化や階級社会なんかの歴史的背景に詳しい人が読んだらさらに色々なことが読み取れるんじゃないかと思い、またちょっと違う沼にはまりそうで恐いですw それにしても『光文社古典新訳シリーズ』凄いなこれ 歴史に残る古典の名作を新訳で読むってことに完全に魅入られたてしまった気がします どんどん読むぞ、待ってろ光文社!
43投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀から20世紀にかけて活躍したヘンリー・ジェイムズ中期の傑作。ゴシックホラーの様式を借りながら、無意識や語られぬもの=幽霊を巡って狂わされていく家庭教師とその家の子供2人。 Netflixでドラマ化されたように、単純にホラーとして読むことができる作品である一方で、怖いのは亡霊が出てくるからではなく、亡霊の出現を契機として破綻をきたしていく、家庭教師と2人の子供の顛末だろう。解説で言及されているように、それは19世紀末に登場したフロイト理論や心霊主義の影響を色濃く受けていて、どことなく亡霊によって狂わされていくマクベスを思い出させる。 著者のヘンリー・ジェイムズのお兄さんは哲学者のウィリアム・ジェイムズであり、とんでもなく文化資本を持つ家に生まれた人。解説によると『鳩の翼』『大使たち』『金色の盃』が後半期における傑作小説も面白いようなので、入手して読みたいと思う。今作自体も再読すると新たな発見がありそうなので、機を見て改めて読みたい。
3投稿日: 2023.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ幽霊小説でありながらセクシュアリティが中心に描かれており、本当に起こったことを描いているかのように妙にリアルで興味をそそられる内容であった。
1投稿日: 2022.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見すると論理的に見えなくもないけれど、その実、決め付けと憶測による強行的な推測ばかり。あまりにもヒステリックな推論のオンパレードに、昔だったらいざ知らず、現代において幽霊説を唱えるのは厳しくないか?と思ったらここの感想でも幽霊説を唱えてる人が結構いて驚く。うーん。 あの映画とかあの映画を見てしまった後だとアイデアの新鮮味は感じられなくて残念ではあったけど、ラストシーン(ヒステリー説をとるなら圧殺だ)はダークな捻りが効いていい。
1投稿日: 2022.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログセクシュアリティ、階級、社会構造をいろんな視点から見て、いろんな解釈を読者に与えるような本だと感じた。 面白かった。
2投稿日: 2022.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ宿泊者がクリスマスイブにを怪談を語る。一人が女性家庭教師の手紙を読む。手紙の中で女性は幽霊から子供たちを守ろうとしている。本当に幽霊はいるのだろうか?
1投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログじりじりと不協和音を聞かされているような感覚。 怪奇小説といいつつも、決して身の毛のよだつような恐ろしさはない。きっと何らかの精神世界のメタファーなんだろうなぁと思いつつ読み進めたが、それがはっきりと明示されるような表現があるわけではないから最後までいまいちすっきりせず。 確かに解説でも書かれているように、性への目覚めを感じさせるところはあったけど、ならば最後のマイルズの死は何を意味するんだろう。 語り口に惹かれず2時間半くらいでさくっと読んでしまったけど、じっくり何度も読み返していろいろなことに気づく作品なのだと思う。 村上春樹の東京怪奇譚が思い出された。
1投稿日: 2021.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ怪奇が起こる屋敷についての話だと思って読み始めたけど、だんだんこの語り手が恐れている亡霊は二人の子供たちに迫る「性の目覚め」を象徴するものなんじゃないか?という気がしながら読んだ。解説を読むに当たらずも遠からずというか、いろいろな解釈が可能であるように書かれた話のようで、怪奇の正体に思いをめぐらせて楽しんだ読者としては、書き手の狙ったとおりというところか。 巻末の訳者あとがきが軽快で地味に楽しい。読みやすい訳文で、原文の難解さはだいぶ緩和されていたのでは。
2投稿日: 2021.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログオチは今となっては珍しく無いが、神に背くゴーストやモンスターを祓って終わり!ハッピー!な内容ではない。脅威が迫ってきているのに上手く行かない、守る子供も邪悪な幽霊に魅了されている絶望的な状況が終始主人公の視点で展開されていく。100年以上前の作品とは思えないほど状況は分かりやすく書かれていて読みやすい。
1投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当は岩波文庫だったけど表示されなかったので。 表現が遠回しすぎて解説がないとわからない部分もあった。 やっぱ教師がノイローゼ説に1票。
1投稿日: 2020.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ怪奇小説として有名な本作。怪談話をすることになった男性がすでに亡くなった知り合いの女性の手記を読みます。彼女は家庭教師先で幽霊と出会うのですが前半はとにかく彼女の懊悩ばかりで全く幽霊の怖さが伝わってこず、読みにくかったです。後半一気に話が動き始め、読むスピードも上がったのですが、たどり着いたラストシーンには驚愕しました。その後戻ったり読み返したりして、自分なりの答えを見つけましたが、読まれた方によってきっと違う解釈があると思います。これはきっちりした日本の怪談とは違う不安定さが魅力なのかもしれません。
1投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳:土屋政雄、解説:松本朗、原書名:THE TURN OF THE SCREW(James,Henry)
1投稿日: 2019.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログうー。素敵な本だな。お屋敷に家庭教師として雇われた若い女。子供らの美しさ、住み込みの生活に満足するも、前任者の幽霊らしき物を見てしまう。あの二人は子供達を連れ去ってしまう!幽霊はいるんでしょうよ。描写も間違ってないようだし。そのストレスによる神経の揺らぎが話のメインであり、海の堤防が決壊するのを今か今かとハラハラするように、頼りない彼女の精神状態の描写が素晴らしかった。ナニー(子守り)のグロースさんがいい人すぎ。自分だったら主人公にキレる。
2投稿日: 2019.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログサスペンスだろうか。 1世紀以上前の小説だというのに、結末を握り続ける著者が妬ましい。 訳もわかりやすく、いわゆる古典はこちらを頼ろう。
0投稿日: 2018.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ出だしが面白い。いったいどんな話が、とそそられる。 内容も最後まで読める。今とは価値観がが違うので、そこはちょっと障害。
0投稿日: 2018.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
クリスマスの夜に怪談を語り合う会で、「わたし」はダグラスという男が、彼の妹の家庭教師であった女性の手記を読み上げるのを聞く。物語の本体は、この手記を「わたし」が書き直したものである。 家庭教師が田舎の屋敷に赴任するとそこで二人の亡霊を目撃する。女中頭のグロースに特徴を伝えると、屋敷の従者と前任の家庭教師らしい。生徒の兄は学校を退学になって屋敷に戻ってきているが、兄妹とも亡霊が見えているのかはっきりしない。グロースにも見えているのか分からない。何しろ家庭教師の一人称なので、その辺がとても疑わしい。 最後に兄は死んでしまうが、この兄が手記を読んだダグラスのはずなので、辻褄が合わない。「わたし」の創作部分なのだろうか。 ダグラスは家庭教師に恋心を抱いていたという仄めかしもある。グロースの物言いは常に中途半端で何が言いたいか分からない。家庭教師が思い込んでいるだけとも考えられる。家庭教師は雇い主である兄妹の叔父に惚れているという読み方ができないこともない。 そんな感じで多様に解釈できる要素がたくさんあるので、非常にもやもやする。 独自の読み方をするのが好きであればよいが、答え合わせを望む僕のような読者にとっては消化不良感が否めない。
1投稿日: 2016.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ霊を見た人の手記を他者が朗読するという形式の物語。ゆえに現実と虚構の境界がゆるゆるで、この本が多層的に理解可能になっている。いろんな気づきがあった面白い本です。
0投稿日: 2016.02.07大学の講義を受講したような読後感でした
「ねじの回転」。このタイトルから、つげ義春のマンガを連想してしまった私は、読者としてどうかと自分でも思います。 さて、書籍説明にある「文学史上もっとも恐ろしい小説」との文言にひかれて手に取りましたが、恐ろしいと言う点については、もはや現実世界の方がよほど恐ろしいことになっているので、昨今のホラー小説並の恐ろしさを期待すると肩すかしをくらいます。ここは、「文学史上」ということに着目して、格調高い邦訳の表現に浸りましょう。 ストーリーの構成は、あの「フランケンシュタイン」と同様に、伝聞の伝聞という形式を取っています。つまり、現実の話なのか、創作の話なのか判らない状況を作り出して、話が始まります。始まりますと書きましたが、実は、なかなか始まりません。そして、え?これで終わり?といった感じで終わってしまいます。肝心の部分が説明されていない!いったい何があったんだろうと、読み終えた後、色々こちらが想像を巡らさざるを得ないわけです。 そして何より、全体で300ページあまりの書籍でありながら、その内の44ページが松本朗の解説と年譜と訳者のあとがきに費やされています。この解説がとても素晴らしかった。よくぞ添付してくれた物だと思います。これにより、この小説の意義、価値というものが理解できました。じっくりと小説を読んだ後の詳細な解説は、まさに大学の講義を受けているようでした。でも、その解説にもありましたが、「謎に対する回答を与えないことによって、ジェイムズだけがすべてを知っている作者としての権威を揮いつづける物語」ってのは、読者としては少々つらいものですね。
6投稿日: 2015.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
何回読んでも後味の悪い作品だぁ(誉めてます) 物語はクリスマスイブの真夜中に行われたイギリス版百物語を発端として始まります。 その中の一人が、その中で語られたどの物語よりも恐ろしい話を知っている。しかも手記があるということで、場を改めてその手記を朗読することに……。 その手記はある屋敷に住んでいる兄妹の家庭教師になった女性が語ったことを記録したもの。 天使のように美しく愛らしい、そして聡明な兄妹。それは本当の姿なのか、そして家庭教師が見た不審な人物は兄妹とどんな関係なのか? 薄気味が悪いというのが初めて読んだ時の感想でした。 改めて読み返すと、うむむ、という感じで視点を変えると全く違う考えも出来るなと……。 彼女が見たものは妄想か、それとも現実か。真実はどこにあるのか、考え始めるとものすごく怖い^^;
1投稿日: 2015.07.16巧緻を尽くした心理小説
19世紀イギリスの貴族館での出来事。両親を亡くした幼い兄妹が伯父の館に身を寄せることになったのですが、貴族である伯父はロンドンで気楽な生活をしていて子供の面倒を見るのが嫌で、代わりに館で子供を養育してくれる家庭教師を探しました。幼い兄妹の家庭教師として雇われた若い女性が、館で遭遇した奇怪で悲惨な出来事を記した手紙が、数十年後に読まれるという形で物語は綴(つづ)られています。 貴族の館には二人の亡霊が出ました。二人の亡霊は、一人は身分の低い男性使用人、もう一人は前任の中産階級出身の女性家庭教師で、二人は、生前に兄妹と共に館で暮らしていました。この二人の亡霊は生前に邪悪な生き方をして身を滅ぼしたのですが、死んだ後も兄妹を自分たちと同じ邪悪な道へ引きずり込もうとして兄妹の前に現れるのです。 物語は家庭教師の手紙を通じて描かれますから、読者は、家庭教師の目を通してのみ様々なもの見ることができます。間接的にしか登場人物の会話も行動も見ることができません。薄曇りの窓硝子越しに物事を見ている、あるいは影絵を見ている感じですが、逆に家庭教師の心理は直接的に読者の目や心に訴えてきます。家庭教師の心を受け止めながら、起こっていることを自分で補いながら読み進めることが必要です。 更に、作品が書かれたビクトリア朝時代、教育を受けた人は不品行で恥知らずな事を口には決して出さないので、亡霊たちが行った肝心なところが婉曲的にしか言及されません。そういう意味でも読み解きが必要な作品です。 この作品は、極めて巧緻を尽くした技法によって描かれていますので、そういう面を味わうのが好きな人には楽しめる作品だと思います。
9投稿日: 2015.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ優れた心理描写のホラー小説……という認識で間違いないのかな? 『少年ノート』経由で出会いましたが、うーん。 もともと、海外文学には苦手意識があったのですが、やっぱり苦手だなぁと思いました。 確かに、「私」と子ども達の間で交わされる会話のかけひきには面白いものがありましたが、物語の芯を掴む前に話が終わってしまった印象です。 翻訳の過程で生じる誤差が、どうしても体に馴染まないんですよね…… 残念だなぁ。
1投稿日: 2014.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり、ダグラス=マイルズに思えて仕方ない と、なると最後、マイルズに起こったことは、何かの比喩なのかもしれない 幽霊もヒロインの幻覚だったのだろう それに、マイルズとヒロインの間には何かを感じさせる 人によって全く違った物語になると思う 読み終わったら、冒頭の、暖炉の前で話されている内容に注目してみると良いかも
1投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京創元社のよりは分かりやすく訳されていたと思う。ゴシック小説であり、たぶたび2人の幽霊が出る部分は読んでる側とし緊張した。最後マイルズの告白部分ではかなり息が詰る展開でしたが、結局フローラはあの後どうなったのかが気になるところです
0投稿日: 2013.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ不協和音。出てくる人がみな、半ば口を閉ざしている。話が妙にかみ合わない。語り手も妙だ。いまいち信用できない。どんな展開でも起こりえそうだ。フィナーレへの期待感で読ませるが、最後まで神経をひっかかれるような、もやもやのまま終わる。 明るい田園に美しい登場人物。しかし全員が重大な暗さを抱えている。もはや完全な白さは存在しないということか?いろんな読み方ができる。そこが1番のおもしろさかもしれない。
1投稿日: 2013.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ死者は生者を束縛する。ある者は永遠の情愛の対象として、またある者は尽きぬ憎悪の対象として。19世紀のイギリス、幼い兄妹が住まう屋敷に家庭教師として雇われた私が体験した怪奇譚は、会ったことのない死者の話に振り回され、語られぬ謎を多数残したまま唐突に物語は終わる。語られ切らぬ物語はだからこそ想像の余地を残し、それは死者のように私の中へ侵犯する。だからこそ、語り手の私は既に死者である必要があるのだがーええと、一言で表せば、残された者の死者に対する「ふざけんなよ!」という感覚、それを適切に表現していると思います。
1投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだろう、天使のような子供たちが一転、悪魔のような振る舞いを見せ始める、というモチーフはこの作品からなんだろうな。 確かに恐怖を感じるかも知れない、先生なような潔癖そうな人物は特に。 子供の不気味さを感じる。 幕切れはあっけない。 恐怖を感じるのは、あくまで子供の悪意にであり、底知れなさ。 2人の幽霊には恐怖は覚えない。 巻末の解説で詳細に語られるが、2人の幽霊の怖さは、社会的にタブーな領域に踏み込む怖さらしい。 恩田陸が大好きそうだが、恩田陸は怖いと言うより賢い子供が出てくるし、子供視点で話が進む。
1投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログひええ。おそろおもしろい。イギリス。お屋敷。家庭教師。ひたひたと忍び寄る恐怖。恐ろしいのは、亡霊か、人間か。みんな大好きイシグロ作品でお馴染みの信頼感がある土屋訳。圧倒的に美しい日本語。読書会の課題本にしたい。 (再読)一日で二回も読んでしまった本は久しぶり。
1投稿日: 2012.10.05
