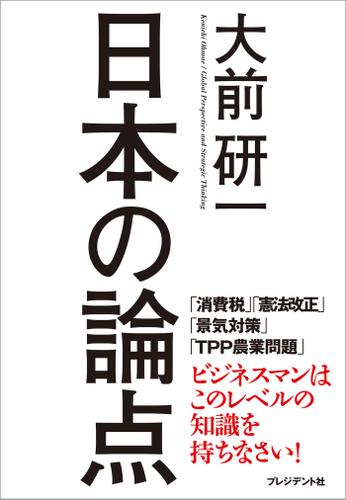
総合評価
(54件)| 5 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ遅まきながら大前さんの著書を初めまして。10年以上前の内容ですが、図書館で目に入り。 正直、極端だなと思うこともあったが考えがよく纏まっており、納得できる部分も多かった。「失われた20年」との表現があったが、その後10年は状況変わらずかと思うと、今後を憂いる気分にもなる。 スイスやデンマークのようなクオリティ国家を参考にとの内容もあったが、働き手が足りていなかったり、先の見通しが立ちにくい現状、何が本当の幸せなのか?から考え直すべきかもしれない。米国や中国との関係性ばかり気にして、日本はどうあるべきか?本当の幸せはどこにあるんやろう? 個人金融資産を出せ、動かせと言われても、日本の将来に見通しが立たない限り、恐くて仕方がない。 日本の病院は優しすぎる、介護施設代わりに使われているとの内容は、それが日本らしい優しさであり安心のひとつである気がして、個人的には受け入れられなかった…当然、医療費の問題など課題があることは承知。 憂いていても進まないので、多くのアイデアをぶつけ合うことで、色々変わる雰囲気が出てこないことには…橋下徹氏を評価されていたが、変わるかもと思わせてくれた点はあったし、同様の動きがもっと出てくることに期待。
18投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の問題に対して大前氏の考えが書かれた本。特に経済の考え方、日本企業の置かれた立場、中央機関や政治家に必要な力の部分が勉強になりました。
1投稿日: 2022.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログジャックアタリ氏と登山家三浦雄一郎氏との対談形式の内容が一番面白い。 後の部分は他の著者の本を読んでいればあまり真新しいことはない
1投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ日頃、“たかじんのそこまで言って委員会”や“ザ・ボイス〜そこまで言うか!〜”などの時事経済番組(その類のバラエティ)を楽しく視聴している人間にとって、 彼の書籍は本当に興味のストライクゾーンであり、面白くてたまらないはずだ。一方で、物事をある側面から断定的に一刀両断する、つまり主張の強すぎるオッサンが 嫌いな人にとって、彼の書籍は嫌悪以外の何物でもない。 僕は前者の様な人間であり、筆者と同じくらい自己主張の激しい父親のもとで躾けられていたため、違和感なく彼の著書を楽しめている。しかしまぁ、そんな僕が読ん だとしても、今回の自己主張はいつになく激しい。「だからあいつはつまらない!」「ほら、あの時から言っていたじゃないか!」およそ民意を味方につけることなど 不可能な筆者の自己主張のオンパレードは、堀江貴文氏程度であれば4〜5人をまとめて論破しそうな勢いすら感じられる。御年70歳、このファイティングスピリッツは 三浦雄一郎にも負けず劣らずだ。だが、そんな自己主張を拒絶するがごとく本書の評価を著しく引き下げる輩には全く納得がいかない。これまで彼が主張し続けてきた 事柄事態は、恐ろしく現実的でシンプル。是非に実行に移してみたいものばかりだ。例えば、 日本企業は研究開発から製造、販売までのワンセットで単品のヒット商品を生み出すビジネスにこだわってきた。自社ブランドでラジオを作り、テレビを作り、カメラ を作ってきた。しかし、長年手塩にかけて開発してきたそれらの製品は、今やすべてスマートフォンのアプリになり、アイコンに収まる時代になってしまった。 「あなたの会社が30年かけてやってきたことを集約するとこのスマホの3つのアイコンです」と経営者に言っても理解できない。〜04.下請けなのに、なぜ台湾企業は強いのか〜 観光立国を目指しながらも“一泊二食付き”などというサービスを押し付ける旅行会社。海外からの旅行者は食事の場所も自ら探して決めたいらしい。また、朝は9時 までに朝食をとらなければならず、10時ごろにはチェックアウト。そうでなくても隣の部屋の掃除が始まり、掃除機の轟音が聞こえてくる始末。日本人の様にあわただ しくホテルを飛び出し、絵葉書で見た風景を“確認するためだけの様な旅行”を好む旅行者はいない。どうしてもっとサービスを“ディスカバリー型の旅行”“滞在型 の旅行”へシフトしないのか。〜06.世界の滞在型旅行業は自動車産業より市場規模が大きいより〜 本書は、ここに引用し始めると、一冊丸ごと書き写したくなるほどアイデアに満たされている。もちろん、著者がこれまで書き溜めた記事の紹介であるため、知ってい る人からすれば特に目新いものではない。ただ、どうやら僕は、“この書籍を同僚に勧めなければならない!”といった使命感を感じているようだ。本書を読んで損な どあるはずない。 現実的には、実行に移すための障害が多すぎる著者のアイデア。多くの利権を無視し、日本を代表する経済人たちをこき下ろし、政治家を揶揄する。これさえなけれ ば・・・いやマジで、これさえなければ・・・でも言っちゃう(笑)自己主張の強さがあだになっていることは間違いないとしても、せめて愛弟子の橋下徹市長にはほ んの一部でいいので実現して欲しいものだ。自己主張の強さは真似しなくて結構。
1投稿日: 2018.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のアグレッシブな正論は健在。 ただ、著者には、「消費は美徳」「金を使うことは楽しいはずである」という大前提があるようだ。 老いてますます盛んなことはけっこうだし、うらやましいけれども、その前提はほんとかしら。
0投稿日: 2017.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ書かれていることは正論で最もだろう。ビジネスマンとして、このような知識は持っているべきだと思う。ただ、正論すぎるが故になかなかこの通りに事を進めることは難しいと思うけど、こういう大上段からみたvisionは必要だね。まさにちょっと前に読んだ「未来は言葉で作られる」のように。
0投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で公共事業に関わるようになったため、大前研一氏の主張が前よりよく実感できるようになった。 日本だけがとりたててダメとは思わず、なんだかんだいいつつもこれだけ平和な社会が保たれているのはすごいと思う反面、何がトリガーになって崩れるのか分からないというような危惧をはらんでいると言う事なのだと思う。 最後の方に”営業に元気が無い=>営業が元気になるようなプログラムを作るべきだ”というのでは、ただの出来の悪いコンサルタントと同じであるという表記にちょっと笑った。公共事業関連では、出来の悪い自称コンサルタントばかりだよ・・。
0投稿日: 2015.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログいかに自分が日本のことを何も考えずに過ごしてきたか、関心を持たずにいたか反省した。 特に債務問題は深刻。どれだけの日本人がこの深刻さに焦りを持って行動しているか、そして私ができることは何か。一過性にならずに考えねば。
0投稿日: 2015.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一氏の本は初めて読みました。 考え方自体は非常にわかりやすく、そしてリーズナブル。 道州制ですべて解決できるかはわからないけど、日本の抱える問題はかなりカバーできていると思う。 日々生きていく中で、「考えること」って少なくなってきていると思うので、そういう時に読むといいかも。
0投稿日: 2015.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログいつもながらの大前節で、論点はわかりやすく、発想はゼロベースで考えられていて鋭く、一貫性もあって、読んでいてはっと気づかされる視点が多い。ただ、表面的にさらっとまとめられているので、これでこの値段は少し割高かなぁ、と感じる。
0投稿日: 2015.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前氏の思想がたっぷり楽しめる社会人の教養本。特に憲法論「一から自分が草案するならどうするか考えるべし」とか「9条の拡大解釈は許されて改憲要件の96条は固持する理由がわからない」は、はっとさせられた。ゼロベースで考えることの大切さなんて甘い話じゃない。
0投稿日: 2015.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ★プレジデント誌の連載および対談記事を加筆修正して取りまとめたもの。2011年の記事もあるが問題の構造は変わってない。日本の抱える問題を頭に入れて一人一人出来ることを考えるしかない。
0投稿日: 2015.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログもう一年位、積読状態だった一冊。しかし三年位前に書かれた内容でも今もって通じる話という点に悲しくなるというか、日本は停滞一辺倒…もう救いようなしか、という思いになるけど最後の三浦さんとの対談が救い。今からでも、現状をよい方向に導くべく改革に着手すべき。一人一人が身近な所からでいいから、勉強・目標・行動。
0投稿日: 2014.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ論点全体を見て考えたのは、組織的に言えば分業は最適なのだけど、分業しすぎて全体像を考える人間がいなくなってしまった。そして、個別論点しか叫べなくなってしまった。っていうことでしょうか。 それに対し統治機構を変革して個別の戦略を作ることで日本は生き残っていく、と。 対談も良かったです。「おもしろくなるように工夫してみろ」。もし自分が親になってもこれは言いたい。間違いなくいい言葉です。
0投稿日: 2014.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大前研一の視点は明確でわかりやすいから好き。 平均年齢が50を超える前に改革しなくてはいけない。 歳をとると保守的になり,新しいことをやりたがらない。 為替で一喜一憂するのは三流国。クオリティ国家はコスト高を言い訳にしない。高くても売れる競争力ある商品やサービスを提供している。
0投稿日: 2014.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前さんの本を久しぶりに読んだが、ひとつひとつの言葉が心に響いてきた。 現在の日本の問題点(論点)について、根本的な本質を捉えて効果的な戦略を展開している。 大前さんのように明確なビジョンを持った人がリーダーになるべきだと思った。
0投稿日: 2014.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は大前研一の著作を読むのが今作が初めてであった。ビジネスマンとしての戦略云々は実感が掴めず敬遠しているところがあったがこの本はもっと広い視点で語られており、一日本人としての心得を学んだ。日本の政治家、官僚、国民の堕落が現在の経済状況を生み出したという指摘はごもっとも。世界がどうのこうのという以前の問題だ。
0投稿日: 2014.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログいくつかのテーマが書かれていたので、覚えているテーマについて徒然に。 最初の論点はバブル後の日本経済について。ケインズのマクロ経済が一切通用しないグローバル資本主義について軽く触れている。じゃぁ、いったい何が起きてるの?って点については、なにげに藤沢数希の「日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門」が詳しかったな、と今になって思った。 地方分権問題については橋下は俺が育てた、的な話。大阪都構想みたいなのは背景となる理論を良く知らなかったので、中立的に読んだ。まぁ、でも結局はゼネコン絡みになるのか。 憲法については知識の修正が必要になった。「占領軍が間に合わせで作った英文を無理やり翻訳したから、文章がめちゃくちゃ」みたいな批判をしてるので、あれ?と思った。たぶん池上さんの本で読んだ気がするんだけど、実は日本国憲法って民間の憲法研究会が提出した案を元にしてるんだよ、って話。そっちに理解が振れてたので。調べてみると「参考にした可能性もある」くらいの論調が安全なのかな。 それは別としても、実質改正が不可能になってる現状は深刻だな、と思った。 震災を起点とした原発問題。1,000年に一度の大震災を想定してインフラ整備とか馬鹿げている、というのは全くその通りだと思う。公共事業で道路の補強やっても投資になってない。稀な有事にはある程度の被害を受け入れる覚悟が必要。僕ら人類、期待値を計算したら飛行機事故で死ぬ確率よりも巨大隕石落下で人類滅亡に巻き込まれる可能性の方がずっと高いし、他にも惑星規模の絶滅因子はたくさんある。けど、何も対策してないし。ただ一方で、そういう事実はあるにしても原発にはまだまだ対費用効果の高い安全対策がたくさんあるはず。そういう事を考えて実行するのは投資になるかな。 新しいお家芸については、みんなわかっちゃいるけどノーアイデア。バイオ、ナノテク、ロボットみたいなシンギュラリティに繋がるような研究は戦略的に研究してきたはずなんだけど。蓋をあければSTAP細胞事件だったり、うまく言っても外資系企業に買収されたり。宇宙開発とかもっと盛り上がらないかなぁ。
0投稿日: 2014.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本の「合成の誤謬」を解説。とにかく硬直した日本のシステムを流動的にするシステムを作るしかないらしい。 そのためには道州制!道州制!!道州制!!!らしい。 今度はアンチ道州制の本を読む必要がある。 _____ p22 民主主義は短期的視野に陥りやすい 民衆は変化に敏感である。国家元首が制度の変更をすれば、それに付随する不安に呼応して、すぐに新たな変化を求める。 また、社会の変化が著しい現在、どんどん新しい変化の方針案ができる。そのたび民衆は変化の必要を感じてしまう。 それで、変化し続ける国「日本」である。毎年、首相を変えて、一新しようとする。 なのに何も変わらない。なぜか。変わるからさ。 p28 人口増加局面ではフローへ課税 日本の金融の実情が変わった今、税制を変えなきゃあいけないのに変えられない。人口も所得も増加していく経済成長期は、所得(所得税)や利益(法人税)などのフローに課税すれば効率よく税収を得られた。 しかし現在は低成長時代。本当に課税すべきは金融資産や不動産などのプールに課税すべきである。硬直した資産を動かし、経済活動に参加するようにしなくてはいけない。 でも、こういう課税は民衆から人気なわけがない。だから政治家はやらない。こういう税金こそ、国民の民度が試される。とくに、資産を保持するジジババに問われる。 p39 ケインズは閉鎖經濟でしか使えない グローバル経済環境では、国内でいくらニューディール政策のような有効需要を生み出しても、バラマキ政策をしても、そのカネ、モノ、ヒトは国境を超えてしまい、国内経済に反映されないからである。 それどころか、安い海外商品に依存するようになり、国内の雇用は減少してしまう。 p40 「身構える」がキーワード 先進国経済では個人資産がプールできるので「身構える」姿勢になる。「持つ者」の特権であり、「持たざる者」にはない。 しかし、この身構える姿勢が経済を停滞させる。この身構える姿勢になっている自分たちを理解できるかが、何よりも重要である。 日本は「倹約」を美徳とする伝統的思想が定着しているから、難しい。私も、倹約家だから。 p47 日本の軟着陸と50歳 日本は二十年も低成長を続けているのに、スペインのように失業率が50%を超えたり、あらゆる層の所得が100万も減っているのにストも起きず、ホームレスも全然いない。 日本はもう持たないといっても、一向に潰れる気配のない、最強の軟着陸国家である。すげぇ。ゆえにその分負債を蓄える時間も長いから、ヤバい。 どんな組織でも平均年齢が50歳を超えたら変化を嫌うようになり、改革という言葉も出なくなる。日本は2014年に平均年齢が47歳を超えた。2020年で49歳と予想される。ちなみに平均年齢のワースト3は日独伊らしいww p58 金遣えば免税にする いかにジジババの資産を引き出すか。「今お金を遣ったら将来惨めになるかも」という不安を「お金を遣えば人生は豊かになるし、子や孫から感謝される」そういう心理に訴える政策を実行しなければいけない。 たとえば、「家を500万円以上かけてリフォームしたら、残りの人生免税!」とか、「遺産の生前贈与を遣ったお金は相続税を免除!」とか、とにかくジジババの金を市場に持ち出す制度を作れば絶対に経済が変わる。 金が動くんだから、あたらしいサービスが生まれ、進化していくはず。それを促さなきゃあ。 p66 スマホのアイコンになるイメージを持て 現代のデジタル市場は「あなたの社が30年かけて開発してきたことを集約すると、スマホのこの3つのアイコンです。」という状態である。 今から新しいものを作るにしても、自分の開発したものがスマホのアイコンとして使われるデジタルな発想を持とう。今時、新しいハードを作ってもダメである。 日本の家電量販店もカンナで自分の身を削り合う勝負はもう限界の状態である。不採算部門はすぐに捨てる勇気!断捨離だ! p73 アメリカのような構造赤字になる 現在の日本男産業構造は、海外で安く作って日本に輸入するである。つまり輸入が増えて、貿易黒字を減らす原因になっているのである。これはかつてアメリカの自動車産業が陥った穴である。 生産拠点も海外に行ってしまったので、国内生産が減る。このままいくと、日本の貿易収支は赤字になり、黒字に戻せない構造になってしまう。いや、なってしまっている。 アメリカなんかは、日本の生産拠点を誘致できたから、輸入超過になる構造を改善できた。アメリカに良いようにされてしまっている。 p82 日本人の旅は確認型 世界の旅行のトレンドはディスティネーション・ツーリズムである。長期滞在で、登山やアドベンチャー、歴史学習、文化を体験し、買い物をしまくる、といった個人的な目標設定による旅行形態のこと。ツアーとか受動的な感動でなく、能動的に旅の感動を得るのがこれである。 これには、融通の利く宿泊形態や観光地のしくみが必要である。日本が観光立国を目指すならば、このトレンドを理解し、対応できなくてはいけない。 p87 税金漬けの自動車 日本最大の産業である自動車、これが売れなくなって、ついに買ってくれと若者に泣いてすがっているらしい。しかし、誠意が全くない。自動車税、取得税、重量税、消費税、、、ガソリン税、、、車検、、、保険料、、、高速代、、、駐車場、、、経費はかさむばかりである。 車は本当に贅沢品なのか?現代ではもう必需品の領域ではないのか?? 金もないのに若者に買ってくれ、そして税金も払ってくれ、意味が分からない。 p99 競争社会の必要性 ゆとり教育が生み出したのは「無能者」だった。日本国内では不幸は少ないかもしれないが、中国や韓国という競争社会を生き抜いてきた強者に喰いものにされて、より一層の不幸を招くことになる。 p104 農業は日本に不向きである 日本の国土の7割は山地である。大農場で農業機械を使って大規模生産に叶うはずもない。日本では1キロ500円で作っているコシヒカリを、オーストラリアでは1キロ25円で生産できるのである。 日本の技術者が外国の最適地で開業して、それを日本に輸入するそういうラインを作るべきなのである。 国内の農業をなくしたら有事の安全保障はどうするのか。という問いに対しては、有事には石油が輸入できなくなり、農業機械は動かせなくなるがどうするのか。という解で一蹴できる。 TPPをやるべきなのは、そういうことである。 p108 スウェーデンの医療 北欧先進国が医療費を無料にしているのは、日本のように医者にかからないから。だから医療費が低く抑えられる。 スウェーデンでは病気の定義があり、病院に電話して症状を問診して病気と認定されたら初めて病院に行ける。ただの風邪の場合は「この薬を買って飲んでください」と簡易処方を受けられる。 日本のように風邪でわざわざ病院に行かないし、筋肉痛で病院に行かない。日本は本当に無駄の多い医療システムのままでいる。 しかし現状の医療システムにつかりきっているジジババは涙に訴えて、現状維持を求めるだろう。こういう意見は無視して改革を断行してほしい。 p109 救急車の有料化をすべし 救急車の無駄な発進でどれだけ無駄が出ているのだろう。地方の過疎集落では病院へのタクシー代わりに救急車を呼ぶ輩もいる。 タクシーを呼べば2万くらいとるようにすればいい、けれど、緊急性のある病気の場合だったら保険適用が効くというシステムにすれば悪用を激減させられる。 p160 省庁の期限を設定 シンガポールでは任期を終えた役所は解体される。 要らない政策が予算確保のためだけに残っているとか、前例主義でできないことだらけの役所の在り方に風穴を開けられる。 公務員はリストラできないというのは、一番経費削減に貢献できない法律である。直ちに撤廃すべきである。 p165 アメリカの親中化 中国や台湾の人々はアメリカで必死にロビー活動をしている。日本はただアメリカの犬でいるだけである。自国留学生が教育を受けるアメリカの学校に寄付をしたり、シリコンバレーでの共同研究や出資など一生懸命である。そういえば23万人もいるのだ。このアメリカで学んだ学生が中国に帰って社会に出るようになれば、経済のパートナーになる。 もはや冷戦なんてあってもイデオロギー闘争ではなく、単純な経済競争である。だから、中国とアメリカも敵対というよりも経済競争をするライバルになっている。 p168 自民党のおじさんが外交を相続不可能にした 民主党が政権を奪取しても何もできなくてあっさり取り返された。これは民主党が悪いのもあるが、一番悪いのは、他の党では相続不可能な政治環境を作った、歴代の自民党のくそ親父たちである。 自民党の外交は田中角栄や森喜朗などのような個人的な力でまとめたものが多く、持続が困難な外交成績ばかりである。 民主党が普天間移設をしたくてもできなかったのは、間違いなく、日本国民には明らかにされていないが、アメリカの戦力には干渉できないという契約で返還されたからである。何も知らないのにギャーギャー喚くなとアメリカに一括されて沈黙したのだろう。 自民の政治の歴史には裏ワザがありすぎて、どの党が新たに政権をとってもコントロールできないようになってしまっている。最悪だ。 p178 非常用電源 原子力発電所の再稼働問題は、非常用電源をきちんと整えればできる。巨大津波への対応など無駄な金を投じてばかりいるが、本質的なのは、ミサイル攻撃されようが、隕石が降ろうが、すぐに外部独立電源で冷却装置を稼働させることなのである。これが本質であるのに、反原発アレルギーのせいか、解決策には目を向けようとしない。解決策として正しそうなものは拒絶しようとしてしまうのだ。 今回の原発問題で、安全・保安院は安全対策の「多重性」は準備していたが「多様性」は準備していなかった。いかに多重構造でも、おおもとの電源がなければ発動しない。最悪、アナログでもいいから冷却システムを作動できるように、多様性のある対策を用意するのが本質なのだ。 p185 ヒロシマの教訓よりデータ活用 ヒロシマの悲劇は国民感情によって、アンタッチャブルの領域である。しかし、日本政府は被ばく患者のデータや放射能汚染の浄化のデータをきちんと採取し、有効活用することが最良の責任の取り方のはずである。 しかし、原発問題でいかされず、感情論やヒステリックな拒否反応を鎮めることができていない。それどころか、野党は感情論を用いてヒステリックを煽っている様である。 感情に流されて本質を見失っていることが多すぎる。 p188 被爆よりタバコ 今回の放射能漏れで被爆した低線量放射能は、体内で長い潜伏期間を経て、運が悪ければガンを作り出す。しかし、ガンというのは案外簡単に作られるし、案外悪化する前に新陳代謝で排泄されてしまうらしい。 低線量の放射線はタバコやアルコールと同系列でとらえるものである。しかし、放射能というだけでヒステリーを起こしてしまうのは、それこそ原爆の被害である。 それなのに、日本人の被爆への認識の偏りは恐ろしい。同じ被爆なのに医療行為のレントゲンやMRIやCTスキャンは気にせず、どんどんやっている。CTスキャンの被ばく量は多くて、年度限界量を二回でオーバーしてしまう。この被爆でガンにならないのに、どうして原発の放射能だけはガンになってしまうのだろう。 p190 CTスキャンリスク OECDではCTスキャンを減らす傾向がある。危険という認識が広まっているのである。しかし、日本では増加している。唯一の被爆国:日本が!! それはCTスキャンがもうかるから医者が勧めるという実態もある。医療行為ならすべて正義に還元できるという、悪癖である。 p194 宗教と闘うとは 宗教と闘って成功するには「闘わないこと」が大事。 情報統制や隔離政策など規制によって宗教問題に取り組むのが一番危険である。 宗教対立は得てして権力闘争や経済格差が原因の結果であって、広く民が豊かな生活を送れば宗教自体が争いを起こすことはない。 規制で対抗せずに、教育で寛容さを育むことで、自立した宗教観ができて、対立を起こさなくなる。 やはり宗教問題だろうがなんだろうが、悪いのは金だし、解決の方法も金なのである。この金の捉え方を正しく教育することが大事なのである。 _______ あー全部正しく思えてしまう。 だからと言ってこの人の言っていることを全部対処したからってうまくいくわけない…かなぁ? とりあえず、今よりも真っ当な社会になると思う。 この人の言葉は、正しいことだけじゃなくて、大切なことも言ってくれているから、良い。 とりあえず、安倍さんがどんなにしてしまおうが、日本を変えてくれるよう長期政権を支持しちゃおう。 サービス。サービス。
0投稿日: 2014.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログゆとり教育のおかげでしゃかりきに勉強しなくなった弊害は今後大きくのしかかってくる。 都は1つでいいという石原さん、そもそも明治天皇は京都の名前を残したくて、本京都と、東の京都、東京・都をつくった。 地方の自立に対する抑えがたい願望と意思を貫いて実現したのは田中角栄、そのかわりばら撒きで陳情政治になってしまい、お金がなくなったら疲弊した。 かつては内務省が一手に引き受けていたので私鉄が日本でいっせいに広がって、日本の都市はスラムにならなくてすんだ。
0投稿日: 2014.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前先生の視点は、どうしてこう、鋭いのだろう。 目の付けどころを学びたい、吸収したいといつも思うのですが、たぶんそれは自分で磨き上げるしかないのでしょうね。 本書については、時事問題が深く掘り下げられていますが、それでいて簡潔に分かりやすく述べられています。時事ネタに関して、テレビのワイドショーレベルの知識しかない方には、ぜひご一読して頂きたいと思います。 TPPや原発問題など、賛否両論の問題に関して、良い面と悪い面を両方見た上で自分なりの根拠が言える市民が、どれだけいるのだろうかと感じることがあります。どちらか片一方の説明だけを鵜呑みにして異を唱えている人の多いこと、多いこと。 物事の両面を見て、自分なりに深く考え、結論を出して主張をするーーーという姿勢を持っていたいと思います。 物事の良しあしは当然あるにせよ、物の見方を学ぶには、大前先生の視点が大変役に立つと思います。
0投稿日: 2014.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ本文にも書いてあるけれど、以前の本たちのどこかに書いてある内容。なにも解決されていないのは驚くことではあるが。 著者の本を読んだことがなければ、入口として読むと面白いと思う。
0投稿日: 2014.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本が抱える課題を数ページにまとめているので、さくっと読めた。 CTスキャンの被ばく量はへたすると2回で年間限度を超えることがあるとのこと、福島での被ばくよりこちらのほうが危険である。 あと、外国の人に宗教を聞かれたら、無宗教であると言わないように。無宗教というとこいつは歯止めがきかないヤバイやつだと思われるらしい。 日本は八百万の神といって、山や樹木など自然界のあらゆるところに神がやどると信じられています。私もそう思いますと答えよう。
0投稿日: 2014.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に大前研一を読んだ。良いです。相変わらず勢いがあり、アイデアが斬新です。同意しかねる部分もあるけれど、総じて説得力があります。巻末の三浦雄一郎との対談も圧巻だった。三浦雄一郎が北大の獣医学部出身だったり、息子の豪太が医学博士だというのも凄すぎ。単なる冒険スキー野郎じゃなかったんですね。
0投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前健一氏の本は私が大学生(今から30年も前)に友達から紹介されて読み始めた本です、当時彼はマッキンゼー日本支社長だったと思います。 東京都知事選で失敗してからは、人生のリセットをしてウェブ上(初めはケーブルテレビ)に大学を開設して後進の指導にあたりつつも、コンサルタントとしての現役も続けられています。 彼の本を読むたびに、経済・社会で起きている事件・事象にたいする味方が甘く浅いものであると実感します。この本では、変わりつつある日本の論点として、消費税・TPP・憲法改正などについて解説がなされています。 定期購読の新聞をやめて久しくなり、新聞は会社においてあるものを時々目を通すのみですが、その代わりに、この様は本を読んで鑑識眼は鋭くしておきたいと常日頃思っています。 今後も、世の中で起きている事象の本当の意味、また私自身や勤務している会社・業界に与える影響を感じながら、幅広く読書をしていきたいと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・過去30年の歴史を振り返ると日本を変えるチャンスは3回あった、1)自民党一党支配が崩れて55年体制が終焉した細川政権、2)小泉政権のとき、3)橋下市長の登場の2012年頃(p5) ・公的債務の解決策として、増税・歳出削減・経済成長・低金利・インフレ・戦争・外資導入・デフォルト、しかないとされている(p21) ・人口や所得が増えていた時代は、所得・利益というフローに対して課税すれば良かったが、今度は資産に対する課税体系へとコンセプトを変える必要がある(p28) ・2011年現在で日本国を運営していく予算は220兆円だが、一般会計とよばれるのは92兆円、不足の半分は税金ではなく、保険・年金などの特別会計で処理、国債償還・利払いも同様(p32) ・失われた20年で得るべき最大の教訓は、ケインズ以降のマクロ経済理論は通用しない、バブル崩壊後に20年間で300兆円もの財政投融資(財政出動)、ゼロ金利・量的緩和を続けたが、効果が無かった(p37) ・アメリカでも、サブプライム問題でひっくり返ったのは、中流以下の低所得者層で、中堅企業の部課長クラスから上の層はほとんど困っていない(p39) ・私(大前氏)は25年前に平成維新を訴えた、一つ正しかったのは、国民の平均年齢が50歳を超える2005年を過ぎたら、改革はできなくなるというもの、どんな組織も平均年齢が50歳を超えたら変化を嫌うようになる(p47) ・今、世界で本当に隆盛を極めているのはBRICSではなく、スイス・デンマーク・フィンランド・ノルウェー・アイルランド、シンガポールなど、人口が500-1000万人クラスで、政治・教育・生活の質が高いところ(p49) ・お金を使ったら人生は豊かになるし、子供や孫からも感謝されるという方向が大事、そのアイデアは「大前流 心理経済学」に詳しい(p59) ・ホンハイ精密工業は、EMSで世界最大手で、意図的に 自社ブランドを持たないことで、他のほとんどの有力メーカのブランドを手がけている(p63) ・日本企業が長年手塩にかけて開発してきた製品は、今やすべてスマートフォンのアプリになり、アイコンに収まるようになった(p65) ・主役はアップルやグーグル、それを取り囲むサポート部隊はほとんどが台湾勢、その指示通りに動いているのが中国企業というのが世界のエレクトロニクス業界の構図、日本企業はいまだにリストラとコストダウン(p67) ・ネット時代の三種の神器は、ポータル・決済・物流、この三つの分野をしっかり握っているのがアメリカの強み(p68、75) ・日本のメーカが海外で生産した製品、OEM製品は貿易統計上は輸入にカウントされ、これが貿易黒字を減らす要因、この動きは5-6年前から(p73) ・救急車が有料で無い国は、日本・イタリア・イギリスくらい、他国の相場は2-4万円程度(p109) ・憲法改正は、敗戦国に限ってみても、ドイツ:57、他に、フランス:27、カナダ:17、イタリア:15回、中国と韓国:9、アメリカ:6回である(p123) ・大阪と京都が一緒になれば広域行政区域として大変なパワーとなる、関西圏は商圏でいうと世界第四位、ロンドン・ニューヨーク・東京、そして関西()p130) ・地域振興のため、マハティールマレーシア首相、台湾李登輝総統、中国薄き来など、プロジェクトを組んでやってきたが、構想を練ってから見通しがたつまでに最低10年はかかる(p143) ・この10年間に起きた変化は凄まじい、もはやG7,8の先進国中心の時代ではなく、インド・ブラジル・中国などを加えた、G20の多極化時代に突入している(p152) ・米メディアは10年以上前に中国シフトに切り替えている、日本からの移民100万人に対して、中国系は400万人を超えているからアメリカの態度は次第に中立になる(p165) ・北方領土の四島一括返還は、日本とソ連の接近を恐れたアメリカ(ダレス氏)の差し金で、ソ連に四島一括返還を求めないと沖縄は返還しない、という条件(ダレスー重光会談)だったから(p167) ・福島原発5、6号機が外部電源を喪失しながら助かったのは、6号機の非常用ディーゼル発電機が空冷式であり地下に入らず、高所においてありその一台が5,6号機に電力を融通したから(p178) ・チェルノブイリの10分の1程度の放射能をばらまいた福島第一原発事故では、放射線の直接的なダメージで死亡した人はゼロ(p187) ・海外で「あなたの宗教は何ですか」と問われたとき、「自分は無心論者です」という答えは避けるべき。自制心がきかない、自分しか信じていない、何をするか分からない、と思われる(p199) 2014年5月3日作成
0投稿日: 2014.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前さんご自身の論が元々確立されていらっしゃるので、論調にはだいぶ偏りがあるように感じた。が、日本の論点と大きく置いているだけあって近代経済理論からアジア企業のビジネスモデル、グローバルto日本の観光産業、ゆとり教育、TPPに対向する日本の農業施策、都構想や道州制など地方自治体の進むべき道…などと扱うテーマは幅広い。 ■ポイント ・優秀なトップ企業を抱え、高い一人あたりGDPを実現するスイスを筆頭としたクオリティ国家を研究すべし ・日本人の個人金融資産は1500兆円、平均3500万円を墓場に持っていく ・ネット時代の三種の神器、ポータル、決済、物流 ・税金だらけのモノなど誰も持ちたがらない、シェアリングが合理的 ・滞在型の観光という観点の欠如
0投稿日: 2014.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「消費税」「憲法改正」「景気対策」「TPP農業問題」・・・ 問題は山積み。 大前さんの考えには賛成だ。政治家の人読まないかな。
0投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の抱えてる問題の中で、著者が問題と考えている問題について、問題意識が持てたと共に、彼の考えについても知ることが出来た。 時間があればもう一度読みたい。
0投稿日: 2014.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬しつつも、大前研一さんの著書はこれが初めてでした。現在海外旅行中のリゾートビーチの浜辺であえてこうして読みたかった一冊です。全221頁で多角的なアングルから切り込まれるそれら論点は、日本から外に出て読むと理解が感情的になりはしますが、大前さんの仰る日本病という症状はとりわけ納得がいき、また、いい社会人をつくることが社会コストを下げるといった、それらは自身の世代を中心としたキーワードと捉え日本を憂う良いきっかけとなりました。
0投稿日: 2014.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前さんがプレジデント誌で連載している「日本のカラクリ」や対談記事を抜粋・加筆修正しつつ、まとめた本です。 この本で私が印象に残ったのは、道州制。 今までピンと来ていなかったのですが、大前さんが道州制を主張する理由がなんとなくわかったような気がします。 ・スイス、デンマークなどの「クオリティ国家」は人口500万~1000万人程度 ・日本の地方も、これらの国家と同程度の人口(例えば、デンマークと北海道の人口は同程度) ・にも関わらず、日本の地方はこれらの国家のような活力が無い ・これは中央依存(交付金依存?)の弊害 ・道州制に移行し、道州単位で自立した経営を行うべきである。 人口や面積などの点で日本の地方(道州)と同程度の国家が「クオリティ国家」として隆盛を極めているのだから、道州ももっと栄えるポテンシャルがある。 現在の仕組みでは中央からの交付金に依存する傾向が強く、ポテンシャルを発揮できていないので、道州として自立した地方経営をするべきである。 それがひいては日本の活力につながる。 という考え方でしょうか。 大前さんの本、初めて読みました。 雑誌での連載記事が中心なので、コンパクトにまとまった内容で、読みやすかったです。 他の本も読んでみようかな。
0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の現状、政治、原発などそうなんだと面白く読むことができた。と同時に今後生き抜いて行くためには、多くの知識を取り込んで、自分も何ができるのか真剣に考えなければという思いが大きくなった。
0投稿日: 2014.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一氏の著書は、新刊がでると一応目を通すようにしています。 本書は、ジャック・アタリ氏と三浦雄一郎氏との対談も含みますが、基本は、プレジデントの連載のものに加筆・訂正したもので、内容は今まで大前氏の主張をなぞっているに近いと思います。 この国のダメな点を挙げて、それを解決する策も挙げるのですが、毎回思うのは、この国は全く変わらない。そして、タイトルの異なる新刊本が出るので読むというルティーンになってきています。 この国が変わらなければならないのは確かですが、著者も提言だけではなくて、そろそろ何か実行するためには何が足りないのか、考えないといけない場所まで来ているような気がしますね。 ただ、大前氏の本を初めて読む人にとってはコンパクトにまとまっていてよいと思います。
0投稿日: 2014.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ国家財政、景気対策、クォリティ国家、グローバルな企業動向、貿易、教育、医療、改憲、自治、行革、外交、原発、宗教といった各方面での著者らしい課題認識と処方箋。 参考になる半面、鵜呑みにすることなく自分で実情を知り、考える必要性も感じさせられた。 4-14
0投稿日: 2014.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ他分野にわたる話があって面白い。著者の考えは、一歩踏み込んだ内容であるため、なにか考えるきっかけになると思う。
0投稿日: 2014.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ国家債務の膨張の危険な事として、民主主義の枠組みに於いて社会的な安定が構築出来なかった際、民主主義を犠牲にしてでも社会的な安定を求める人たちが出てくることです。移民排斥運動、極右勢力の台頭などです。 国家債務の問題は民主主義体制の映し出す鏡になる。 日本の債務を解決する唯一の方法は社会制度を変革することだが、日本人にその器量があるのか? (ジャック・アタリ 2011.3) ・どんな組織でも平均年齢が50を超えると変化を嫌うようになる。 国家もそれと同じで国民の平均年齢が50を超えたら、国を変えよう、社会制度を再構築しようというインセンティブは急速に失われる。 ・日本人は1500兆の金融資産を持っているが、これがマーケットに出てくれば公共投資など必要ない。 1500兆円の1%15兆円が市場に出るだけで、安倍内閣が発足時に決めた経済対策費10.3兆円の補正予算を上回る。 景気回復のポイントは政府が何をやるかではなく、1500兆円の持ち主である個人が何をするかだ。要は3500万円も持って死ぬことが本当に幸せなのか?と資産リッチな高齢世代が自分自身に問いかけたくなるような政策をすることが大事。 ・日本の若者が車を持たなくなった最大の理由はまるでペナルティのような税金の多さ。 消費税、自動車税、自動車取得税、自動車重量税と税金のオンパレード。そして若い人ほど自動車保険料が高い。 さらに駐車場代がかかり、ガソリン税がリッター53円。有料道路の通行料は別途かかり。車検も重くのしかかる(米・豪なら2~3ドル)。 ウンザリして売っても、日本の中古車市場は値下がりは激しく買い叩かれる。 「若者に合った車を作りたい」と自動車メーカーは努力しているが、持てる政治力のすべてを使って、課税を含めた車のランニングコストを安くする、中古車の査定を高くするよう努力した方が良いのではないか。 ・医療費の増大には、病気を定義した上でのスクリーニングの徹底。 救急車の有料化、入院依存からの脱却、窓口では自己負担とし還付にすべき。 ・時代状況の変化とともに必要な政策も変化する、役所もサンセットがあって然るべきで、歴史的役割を終えた役所は廃止、あるいは大胆に縮小すべき。 ・中央集権国家として役割を終えた日本が次のステップへ進むには統治機構を変えるしかない。 中央省庁を解体するか全ての権限、利権を剥奪するぐらいしなければならないが、中央集権を是としてきた自民党では中央省庁の利権を奪わない程度に権限を分け与える「特区」を作ることぐらいしか出来ない。 本来は、地域ごとに統治機関を持つ都構想、道州制への移行が必要である。 ・北方領土問題で四島一括を言い出したのは日ソ共同宣言が出された56年以降で、日ソの接近を恐れたアメリカの差し金で「四島一括を要求しなければ沖縄を返さない」と言われたからだ。 沖縄返還は軍政と民政を分け、民政を返しただけで、「米軍は自由に使って下さい」と軍政を残したまま、今日まで政府がその件を国民へ説明しなかったため拗れている。 ・事故とは物理現象なので物理的説明をしなければならない。 「想定を超える津波・地震があったから」ではなく「地震や津波で、何がどうなったのか?」である。 よって福島第一原発の事故が拡大した原因は一つしかない。 「すべての電源が失われる全電源喪失の状況が長期にわたって続いたこと」につきる。 ・宗教対立は結果であって原因ではない。原因は貧困にある。 そして貧困を克服する為の努力は出来る。すべての人々が教育の機会を均等に得て、生活が向上すれば社会の緊張は解きほぐせる。
0投稿日: 2014.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとも明解で、山積する問題も解決できそう。反論ももちろんあるだろうけど、私にとっては時事の指南書。あー覚えていれれば…。
0投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ビジネスマンはこのレベルの知識を持ちなさい』と書いてある帯で買った本。雑誌に掲載されているコラムを抜粋して編集された本なので、別の本で主張している内容がちょくちょく出てきていたが、やはりこの人の話は説得力がある。どの話もとても興味深く読むことができた。もはや国境など存在しない世界において、日本の中でぬるま湯で浸っていてはダメで、自分ももっと世界に目を向けて、感性を磨かないといけないのかなと思った。
1投稿日: 2014.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に原発の放射能不安について、冷静な分析が非常に参考になった。 教育・政治・外交の問題は、著者の他本でも論じられている内容。
0投稿日: 2014.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一さんのレポート集。 道州制の導入、税制の改革などとても勉強になる内容。 何度も噛み締めて読みたい一冊。
0投稿日: 2014.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の政策で必要なのは要は3500万円を持って墓に入る人からいくらとるかが重要というところは勉強になった。
0投稿日: 2014.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに大前氏の本。 前から主張してたようなことが中心だったと思うが、改めて読むと新鮮。 年寄り(プラス小金持ち)に金使わせるのがキモなのかね。 そういう点でも資産課税へのシフトは賛成。執行面でもそんなに難しくないとは思うけど、老人世代からの猛反発で困難だろうな。 金をどう使いたいかを全く意識しないままただ貯め込む人が私の周りにも多すぎるとホントに思う。 そういや貯蓄の推奨なんで戦時中の国家の都合ってのも最近なんかで読んで意外だったな。もっと歴史的な国民性だと思ってた。
0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「”一泊二食付き"などという世界で競っていては、観光立国など夢のまた夢。アジアの若い女性なら観光地なんて全然興味はない。彼女たちが見たい日本は、圧倒的に渋谷109だ。」 「これから先、グローバル企業のアジア本部でょうに誰がなるかといえば、間違いなく韓国人。日本人は韓国人の上司にレポーティングするのが関の山だ。しゃかりきに勉強しなくなった弊害は、今後重くのしかかる。」 福島第一原発の問題 ・全電源喪失と冷却源の問題 ・突き詰めると「すべての電源が失われる全電源喪失という状況が長時間にわたって続いたこと」が原因 ・原子炉に冷却用の水を送り込むポンプを動かすための電源が1つでも生き残っていたかどうかが分岐点 ・電源喪失の対策:非常用電源装置 → ダメでも外部電源 ・福島第一では、メインの冷却用ポンプと非常用電源の冷却用ポンプが同じ海に面して枕を並べて設置していた →津波で一斉に使いものにならなくなった
0投稿日: 2013.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前研一の日本への提言。継続して思考が停滞し、何も考えなくなっている政府に対して、誰しもそうだよねと思うところを切り口に政策や方針を提言している。本書だけでなく、大学院でもよかったなと思うことは、戦略を学ぶことと同じくらい、もっと大きな枠組みで考えることの重要性を学べたことだ。原発を無くそう!という叫びには何の論理的な根拠もなく、時にそれをマスコミが自社の利益のために煽動してゆく。一方で、ストレステストという方法でお茶を濁しても、何かが起きてしまえば100%だということ。そして、そこから思考が停止している。実は、電気系統がダウンしても大丈夫ということは、論理的にいえるのだから。TPPでは農業を守るために、国民の口に入る食料は自身で作るということをきまって言う。しかし、米どころか石油を止めたらすべて立ち行かなくなるのだから、むしろ効率的に様々な国に生産拠点をおけばよい。日本も高級米として十分戦えるわけで、何を心配するのだろうか。地球規模で物事を考えて、今目の前にある問題を解決する。ちょっと大事なようでいて、実は大切な思考の展開だ。
0投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクス、道州制、加工貿易立国からクオリティ国家への転換、グローバル社会に向けた教育の転換、TPPを好機と捉えた農業改革、医療制度改革、憲法問題、外交問題、そして原発・・・。 日本が抱える諸問題を、これでもかというほど取り上げ、分析し、改善案を提示する。書かれている内容は大前氏が常日頃からあらゆる書籍、媒体で提言している内容の総和といった感じで、特に目新しいものはない。日頃から氏の言動に注目している僕としては、本書を読み通すのは学んだことの復習のような感じで、知識の血肉化になる。(アベノミクスに関しては本書の直前に読んだ竹中平蔵氏の『竹中先生!日本経済次はどうなるの?』での竹中氏の主張と真っ向から対立する意見が多く、少し戸惑ったが。) 冒頭のジャック・アタリ氏との対談も示唆に溢れていて面白い。また最後の三浦雄一郎氏との対談はとても温かみを感じる。いくつになっても夢や目標を持ち、苦労から楽しみや面白みを見出し、やりたいことをやり続けろ、と。 本書で展開される様々な主張(特に日本の現状の悲惨な部分についての言及)にところどころ暗雲たる気分にさせられることもあるが、最後はとても前向きな気持ちになりました。
0投稿日: 2013.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の、登山家三浦さんの話がとてもよかった。 今度本などがあれば買って読んでみたい。 極端な表現が多く、反発心をすこし持ちながら読んでいたが、私ももっと大きい視野で変化をもたらす人材になれるよう、努力していこうと思った。 あとは、楽しくないことをどれだけ楽しくできるように工夫するか、という三浦さんの言葉を、仕事の中でも活かしていきたいと思う。
0投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養が一時期流行っていたが、教養の一環として読んだ。 論点が色々書いてあるが、農業に関して頭がスッキリした。そもそも日本は農業に適していない。山ばっかりだから。国土を守るためというのも嘘。そもそも石油は日本では産出で賄えない。他国と揉めたら終わりの国が日本。 平たくわかりやすい。
0投稿日: 2013.11.10日本というかお前(大前)の論点
旬な話題を大前研一が一刀両断。 少し的外れな記述もみられるが、三浦雄一郎との特別対談は面白かった。 値段たけーな。
1投稿日: 2013.11.06日本の論点
興味深い目次がずらりとならんでいますね。ただ連載を集めたものなので今更というものもあります。
0投稿日: 2013.11.06TPPと円高円安
最近の為替の動向とTPP問題が気になっていたので この本は興味深いです。
1投稿日: 2013.11.05本のタイトルに惹かれますが。。
目次もきになりますね そのようなことが本当に書かれているのか楽しみです
0投稿日: 2013.11.04MR.トンチンカン
この人至るところで的外れなコメントや寄稿してるよね。 この本はそこまでひどくないから暇な方は是非どうぞ。
1投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ大前氏は割と好きな作家でしたが、最近橋下を指示したり 政治の世界に首を突っ込んだり。経営や教育をやってれば いいのにと思うことも多々あり。 今回の本の内容も、ビジネスというよりも政治や外交(外交は昔 からよく書かれていましたが)の話題が多く。特にありきたりの内容 ばかりかと思いました。
0投稿日: 2013.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ変化を厭うアタマの硬い年輩の方も先々の日本の将来を担う若者も、全員読んだ方が良いと思う。 相変わらずの大前節。 でも、やっぱり納得。アタマの硬い年輩のハズの大前氏が、こんなにも柔軟に精確に日本を分析また予測しているのを1つの参考にして私たちは日々を過ごすべき。 危機感!
0投稿日: 2013.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
The ヒラの日本人の私ですが、日本の論点について大前氏の意見を拝見させて頂きました。 大前氏は、アベノミクスに懐疑的なんですね! やはり、賛否両論別れるアベノミクスですが、今まで見てきたアンチアベノミクスの人の中では一番冷静に捉えている感がありました。 「今問われているのは、過酷な事故になったときにすべての電力会社にそれを収束させる力があるのか?ということである。 これからの原発事業には、三つの大きな課題待ち受けている。一つは『再稼働、オペレーションの問題』であり、二つめは『燃料サイクルと使用済み核燃料の処理問題』、そして三つ目が『廃炉の問題』である。どの課題も電力会社が単独でマネジメントできる範囲を超えてしまっている。 原発事業は一つにまとめて公営化し、全国九電力の精鋭を集めてマネジメントしていくしかないだろう。」(p.182) 全国九電力がバラバラに対策するのではなく、連携して、原発問題に取り組んで行く。 そして、安全が確保された後、世間を納得させて原発再稼働というストーリーだろうか。 大前氏らしいスマートなやり方かな〜と思いました。
0投稿日: 2013.10.20
