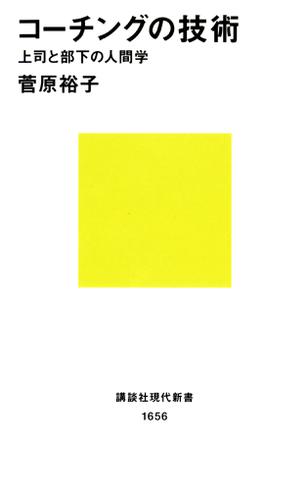
総合評価
(41件)| 8 | ||
| 15 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読んで、私はコーチングは難しいと思った。 人間性に長けている人ができるものだとも感じた。 「人を育てる」ことは自分が知っていることをただ教え込むことではない。 相手の可能性を信じ、相手が本来持っている才能を発揮させ、相手の成長を促すこと。 そして相手の成長をサポートするは自分も成長できる。 コーチングの技術を磨いて「人を育てる」だけでなく自分も成長することを目標としたい。
0投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングについて、言葉だけ知っていて何かは分からないという状態から始めて読んでみた本。ここからいろいろと広げていきたい。 プロジェクトの設定や、メンバーへの質問の具体的な方法など、コンパクトにまとまっていた。
0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ468 菅原裕子(すがはら・ゆうこ) NPO法人ハートフルコミュニケーション代表理事。有限会社ワイズコミュニケーション代表取締役。1977年より人材開発コンサルタントとして、企業の人材育成の仕事に携わる。従来の「教え込む」研修とは違ったインタラクティブな研修を実施。参加者のやる気を引き出し、それを行動に結びつけることで、社員と企業双方の成長に貢献。1995年、企業の人育てと自分自身の子育てという2つの「能力開発」の現場での体験をもとに、子どもが自分らしく生きることを援助したい大人のためのプログラム-ハートフルコミュニケーション- を開発。各地の学校やPTA、地方自治体の講演やワークショップでこのプログラムを実施し、好評を得る。1999年、有限会社ワイズコミュニケーション設立。企業を対象とした研修や企業文化変革のコンサルティングやプログラムを提供するかたわら、ハートフルコミュニケーションの活動にも力を入れる。2006年NPO法人ハートフルコミュニケーション設立。ウェブサイトはhttp://www.heartful-com.org/ コーチングの技術 上司と部下の人間学 (講談社現代新書) by 菅原裕子 ところで、中には社員が夢を語ったり、ビジョンを持ったりすることを怖れる組織があります。下手に社員が夢を持つと、「組織にとって都合のいい人」でいてくれなくなるからです。企業は力のある社員に対して、「組織にとって都合のいいように能力を発揮してほしい」と考えているからです。 しかし、人の持つ能力は、その人が夢に向かったときに発揮されるものであって、会社にとって都合のいい目標を与えられたときに出てくるものではありません。したがって、力のある社員は、自分の夢に向かって会社を辞めてしまうという不安定な構図ができあがります。 第一に挙げられるのは、物事を前向きに、肯定的に捉えることのできる能力です。数多くの思想家や哲学者が言うように、結局、私たちは自分の思い描いている自分になるようです。前向きな姿を思い描いていれば前向きに、否定的な側面を見て心配ばかりしていれば、心配どおりのことが現実となる、ということです。 物事を否定的に捉える人は、うまく他人を力づけることができません。しかし、対象者が「できない」と感じていることを、「いや、ひょっとしたらできるかもしれない。やってみたい」と思わせるには、コーチ自身がその事柄に肯定的な側面や、肯定的な取り組み方があることを知っている必要があります。肯定的な側面があることを知っているからこそ、同じ事柄をまったく反対の側から見せてやることができるのです。そして、コーチが肯定的な側に立つことで、対象者を目標の位置まで連れて行くことが可能になります。 なぜなら、考えているときは私の頭は、論理で埋め尽くされるからです。頭の中を論理で一杯にすると、直観が働くスペースがなくなります。考えるのではなく、相手の論理を理解しながら、自分の考えは休ませておく。これが直観を引き出す方法です。 直観は、自分の無意識を信じた分、その信頼に応えて働いてくれます。頭の中を、まず思考で忙しくするのを止めて、無意識のささやきに耳を傾けてみてください。 [自己チェックリスト(例)] ■自分 ① スケジュール表がウキウキする出来事でいっぱい。 ② 自分のことを好きだ。 ③ 好奇心で満たされていて、楽天的である。 ④ やりたいことをやり続けている。 ⑤ 結婚相手(パートナー) がいる。 ⑥ 子どもを授かる。 ⑦ 自由である。 ⑧ 常に何かを勉強している。 ⑨ 一つの価値観にとどまらず、いろいろな価値観を受け入れている。 ⑩ 自分に自信を持ち、イキイキしている。 ⑪ 過去の否定的な出来事に長くこだわることはない。 ■人間関係 ① 人と会うのが楽しみだ。 ② 両親を大切にしている。 ③ 心から信頼できる人がいる。 ④ どのような人とも(基本的に) 対等につきあっている。 ⑤ 自分の意見をはっきり言える。 ⑥ 人を幸せな気分にできる。 ⑦ 人間的に成長するような、他者とのかかわりを持っている。 ⑧ 自分を傷つけるような人間関係はない。 ⑨ 待ち合わせの時間など、人との約束を守っている。 ■健康 ① 心身ともに健康である。 ② 食事がおいしくいただける。 ③ 年を重ねるごとに、年相応の美しさがある。 ④ 平均体重を維持している。 ⑤ 身体によくないものは摂らない。(たばこ・過度の… ■経済状態 ① 自分と他人のために、使えるお金が十分にある。 ② 自分の将来に対して、投資するためのお金がある。 ③ 自分の仕事に対する正当な評価としての稼ぎがある。 ④ 寄付ができる。… ■環境 ① 自然に囲まれている。 ② 家族が幸せである。 ③ 身の回りが整っていて、居心地がよい。 ④ 家の中の不要品はすべて処理されている。 ⑤… ■仕事 ① 社会にも、他人にも、自分にも有益な活動(仕事) ができている。 ② 仕事の能力が向上している。 ③ 仕事が好きだ。 ④ 仕事の内容と収入が広がる… さて、いったん目標が明確になったら、あなたが見るもの、考えることのすべては、望むものを手に入れている自分です。望みどおり理想の体型になったあなたです。必要なだけの収入を得ているあなたです。人前で堂々と話しているあなたです。仕事に成功しているあなたです。 たとえば、「二ヵ月以内に、住まいを自分の思いどおりの快適な空間にし、友人を招いてパーティーを開く」という目標であれば、望みどおりになった家、そこでくつろぐあなたの様子、家族の喜ぶ顔、眺めのいい庭、パーティーの雰囲気、招いた客の一人ひとりが楽しむ様。それらすべてを、詳細に思い描きます。 仕事で成功している自分であれば、望んでいることを達成し、周りから祝福を受けている自分を思い描きます。そして、その絵から行動を起こしてください。その様子があなたの中で既成事実になるまで、繰り返し繰り返し思い描きます。人は、結果が見えていることには安心感からリラックスして取り組めます。 後は日々、決めたことを実行するだけです。 ところで運動能力や、音楽などの芸術的な才能は、年齢が低いときからレッスンを始めた方が、才能を開花させるには圧倒的に有利だと言われています。幼ない子どもにレッスンの楽しさを体験させることができれば、彼らは潜在的に持つ力を発揮することができるのです。 たとえば、タイガー・ウッズは、一歳半で父親とラウンドに出かけていたといいます。そのころの彼は、数字の五までも数えられないのに、パー5、パー4、パー3の違いを直感的に理解し、自分のスコアだけでなく父親のスコアもつけていました。 私の娘は本の虫です。いろいろな本を読んでいますから「何でそんなことを知ってるの?」と思うようなことをよく教えてくれます。そんな娘が中学受験をする際、学習塾に通うことになりました。 あるとき、塾のテストで「全身に酸素を運ぶのは」という問題があり、彼女は「ヘモグロビン」と書きました。ところがその答案に×がついてきたのです。不思議に思った彼女は先生に尋ねました。すると先生は、「まだヘモグロビンは習っていない」と答えたそうです。正解は「血液」だったのです。なるほど、これが「求められている以上のことはやるな」という世の中からのメッセージかと妙に感心したものです。 私にもよく似た体験があります。小学一年のときのテストです。動物とその動物が食べる餌を線で結ぶ問題がありました。私の間違いは、「ニワトリ」と「小魚」を結んでしまったところから始まりました。一番自信のあった解答です。兄の釣った小魚を、我が家のニワトリは喜んで食べていたのです。
0投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングの技術 菅原裕子 ◆人の可能性を開く 人は潜在能力を備えた存在でありできる存在である 人はよりよい仕事をすることを望んでいる ◆セルフコーチング 他人の作った流れで生きることの限界 私には結果がみえるまで必要なことは何でもし必要なだけ待つコミットメントがある 人生における重要領域 仕事 経済 環境 自分の内面 人間関係 学習 社会貢献ボランティア 趣味楽しみ 健康 ライフワーク 自己チェック プロジェクトを決める なぜそうしたい? 予想される弊害 具体的プラン 自分にまともでない要求をしてみる ◆問題をかかえているときにセルフコーチング 何がおこっているか その問題をどうしたいか どうなりたいのか 問題の本質は? どうしたら解決できるか 解決策をどう実行? 力づけ 人は才能を発揮するため生まれてきた
0投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングの基礎的な心構えを示した上で、そのための質問の投げかけや、どう承認するかのパターンを色々列記している。 さらに、コーチングが効果を発揮しやすい環境づくりや、セルフコーチング、ファシリテートなど関連場面への臨み方も書いてあり、わりと実践的。
0投稿日: 2020.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手の中の眠っている能力を引き出し、それを高めていくこと。 それがコーチング。 潜在的な知識やスキルを引き出し、それを知恵に高め、結果に結びつけていく。 やり方を教えるのではなく、自ら学べるように援助する。 ラポールの構築→会話への導入→現状確認→問題課題の特定→望ましい状態をイメージする→解決法の検討→課題を解決するためのプラン作成→プランの確認→力づけ→フォローの約束 ラポールの技術(相手の心を開く) ミラーリング・・・相手と動きを合わせる、視線をあわせる、目線の高さをあわせる ペーシング・・・話し方の速度、リズム、抑揚をあわせる、声の大きさを合わせる 聞く技術 聞き耳(自分の観念)を通さない バックトラッキング・・・相手の話の中からキーワードを見つけ繰り返す BUTからANDへ・・・否定せずに一旦受け止めてから自分の意見を言う 相手に質問をする・・・yesかno以外で答えられる質問 もし・・・だったらどう ゆっくり記憶をたどるのを待つ 質問者自身が本音を語る 疑問詞を使う 全般的なコーチングの技術について具体的なやり方を例に出して述べています。 そういう場面に出くわしたときに使える技術と思います。
0投稿日: 2019.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか理解するのが難しいティーチングとの違い。基本プロセスやポイントなどいまもコーチングをする機会には参考にさせていただいている。
0投稿日: 2018.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングのいい日本語訳はないだろうか。 部下が上司をコーチとして受け入れない限り,コーチングはできないし,当然,コーチングの効果は生じない。 誉める行為は上下関係を作る。コーチングは上下関係でするものではない。
0投稿日: 2017.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い上司とは、自分よりも優れた部下を育てる人。人を育てるためのラポールの形成・傾聴・ファシリテーションなど、基本的な技術が具体例とともに書かれている。効果的な質問の仕方はなかなか難しく、習熟が必要だと感じる。最もよかったのは、セルフコーチングの重要性とノウハウの章。人をコーチングするには、まず自分を上手にコーチングして成長する必要があるそうだ。自分を成長させることができない人に、人を成長させるのは難しいというのは、非常に納得がいく。早速実践したい。
0投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ#読書開始 ・2015/9/3 #読了日 ・2015/9/9 #経緯 ・マンガアプリのドラゴン桜を読み、参考文献にあがり興味を持ったため。 #達成、満足 ・即活用できるスキルがあり、実践中。結果、ウケもよく当著から学んだので大満足。 #感想 ・その辺の育成術本よりも内容を網羅しており、かつて学んだファシリテーションにもつながっていく。 ・コーチングとは、コーチングの目的、スキル、コミュニケーション、ファシリテーション、問題解決という流れ。 ・コーチング、メンタル術、コミュニケーションスキル、ファシリテーション、問題解決術が学べる良書。 ・自身の価値観、学んだこと、感じてきたことと共通しているのが良かった #オススメ ・部下、後輩を持つ人はもちろん逆も良い。 ・コミュニケーションが苦手な人にも参考になると思う。
0投稿日: 2015.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ聴く.待つ.出来ないならオレがやるよ!じゃなくてどうしたらできそう?聴くのは話すより早い,でも待つ.相手の話を繰り返す.ファシリテーション
0投稿日: 2015.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的に事例をあげて説明している そのために概略がつかみづらい ファシリテーターとして利用が可能か考察してみる
0投稿日: 2015.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な技術が書かれていますが、自分がいいコーチングを受けた経験がないと実践するのは難しいと思います。不適切な関わりをしない配慮には役立つと思います。ティーチング、マネジメント、リーダーなど、さまざまな技術がありますが、どれを使うかは相手次第。コーチングも決して万能ではないことを覚えておく必要があると思います。
0投稿日: 2015.04.10理論と実践の反復
東大受験漫画「ドラゴン桜」で紹介されていたので、気になって読んでみました。 コーチングや教育学の知識はまったくありませせんが、平易なことばで具体例を交えて書かれているので、スラスラ読み進めることができました。 コーチングのメリットはもちろん、その限界やコーチングが効果を発揮するための条件などについても触れられているので、バランスがとれていると思います。
1投稿日: 2014.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ部下の信頼を得て、モチベーションをアップさせ、最大限のパフォーマンスを引き出すような上司を目指して、望ましいコミュニケーションのあり方について具体的に述べたもの。 教育界ではカウンセリング・マインド、傾聴などと言われているものに近いと思うが、部下を「出来る人間」とみなして、出来るだけ話を聞いてやり、部下自身で可能性を開いていけるようサポートする、というもの。おれは対生徒、ということになるが、それ分かっているんだけど難しいんだよな、と思う。「沈黙が怖いのでしゃべってしまう」というのはまさにおれだな、と思った。沈黙してしまう原因4つ、そして「ラポールを築くことができれば、沈黙は怖くありません」(p.113)というのが、ドキッって感じだった。「沈黙の技術」を身につけたい。 はじめは胡散臭い本だなと思ったが、基本的な技術が一通り書かれている点は良いと思った。上意下達の組織では能力のある人が逃げていきますよ~というあたりは今の組織の上層部に聞かせてやりたい、とか、別の意味での読むモチベーションを得たのも大きいけれど。でも、やっぱりおれこういう研修とか苦手なんだよな、と思った。他にラポールを築いて部下の能力を引き出す方法はないものなのかと思ってしまう。(14/06/29)
0投稿日: 2014.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログまだコーチングを学んでいない人にとって、この本を読んだからと言って、コーチングの技術が身につくかどうかは、正直なんとも言えません。 ただ、ちょっとした会話の際に活かせるものはあると思います。 一方、すでにコーチングを学んだ方にとっては、色々振り返りができてよい本だと思います。
0投稿日: 2014.06.21コーチングの技術 上司と部下の人間学
今さらコーチングという感もあると思いますが、この著者の他の本を読んで、こちらも購入してみました。 先に読んだ方は家庭での子育て支援に関わる内容で、コーチングのスキルを生かし、子どもを生き生きと伸ばしていく働きかけとはいかにあるべきか、が書かれていたのに対し、こちらはその活用場面が世間一般でより認知されている、職場でのコーチングの活用法が紹介されています。私は基礎的なことが分かりやすく、具体的に書いてあると感じました。同僚や上司・部下など、職場の人間関係を改善したい人や、コーチング面白そうだけど、まだあまりよく知らないという人、自分自身をセルフコーチングして高めたい、という人におすすめです。
3投稿日: 2014.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2回目。内容が具体的、いろいろな例があってわかりやすい。「直観力」は神の声でも宇宙からの交信でもなく、自分の無意識の中に蓄積された情報が何らかの刺激によって飛び出してきた結果。(納得)
0投稿日: 2013.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
相手の中の眠っている能力を引き出し、 それを高めていくことが本当の指導である。 「すでに知っていることを引き出すために共に働く」 「指導者が具体的で分かりやすい行動のヒントを与える」と、 対象者の行動に劇的な変化が起こります。 「部下の話を聞く力」は最重要課題です。 「黙って視線を合わせ、相手の話す速度に同調して相槌を打ってください」 「黙って視線を合わせてうなずく」といのは、 コーチからの魔法の言葉です。
0投稿日: 2013.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織において、一人ひとりが自立し、 指示ではなく自ら動けるメンバーが 多い会社は強いです。 逆に、指示がないと動けないメンバーが多いと 社内のムダが多くなります。 本日ご紹介する本は、 コーチングマインドやその手法が理解でき、 他のメンバーに対する関わり方や、 自らも自立できるヒントを学べる1冊です。 ポイントは 「支援」 コーチングでは 教えるのではなく、 相手が自ら学べるように 支援することが基本です。 そのことを通じて、自らも 会議や業務改善、プロジェクトへの 取り組みのレベルを上げていくことができます。 「否定しない」 相手の意見を否定してしまうと、 相手は話す意欲を無くします。 もし、相手の言うことが間違っていたとしても 最後まで聞きましょう。 そして、相手の考えを否定するのではなく その考えだとどうなると思われるのかを 客観的に伝えましょう。 「認める」 相手が良い行動をしたときに、 それを強化することで、良い行動が習慣化できます。 単に褒めるのではなく、 相手の行動によって、どのような良い影響がでたか、 ”自分が認めている”ことを ストレートに伝えます。 「事実を伝える」 相手がミスや失敗をした時に 相手を責めるのではなく、 事実のみを伝える努力をします。 たとえば、相手のミスによって ”他のメンバーの仕事が増えてしまった。” のような感じです。 できるだけ感情的な部分は排除して 事実を伝えることで、 次の対策を冷静に考えることができます。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指導者は仕事のやり方を教えるのではなく、対象者が自ら学べるように支援する 社員一人ひとりが自立していない会社では、実に多くのムダが発生している 価値観=ビジョンを実現するプロセスで何を尊重するか 目標達成とプロセスを活用して、社員の能力を伸ばす意識の高い組織ほど、コーチングが導入しやすい 質問ポイント=相手が省略している言葉を尋ねる「具体的に言うと?、~と言うと?」 相手が望む行動をしたときに、それを強化することで、行動を習慣化することが可能 目標を達成できるかどうかは、どのような目標を立てたかによることが多い 一人ひとりの社員が自分自身の「やりたい」を決め、共通の目標に向かって協力し合う姿こそ、企業に求められる 結果が見えるまで必要なことは何でもし、必要なだけ待つ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ 第1章 人の可能性を開くコーチング 第2章 コーチングが発揮される環境とは 第3章 コーチングの技術 第4章 グループコーチングの技術「ファシリテーション」 第5章 セルフコーチングのすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆マインドマップ◆ http://image02.wiki.livedoor.jp/f/2/fujiit0202/1e6cb993d8d173d3.png
0投稿日: 2012.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングを技術論で語るのは、本当はよくない気もしますが、そうはいっても現実問題、なかなかうまく実践できない人にとっては、役立つことが並んでいると思います。 ここに出ている考え方や手法をきっかけに、まずは初めて要領をつかんで、次のステップに進んでいくことができればな、と思います。 まずはやってみる。
0投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前に購入したものの「積ん読」状態になっていたこの名著を読了した。 最近、後輩の指導で悩むことが多いので、コーチング入門編とも言えるこの名著はとても良い指針になった。 一番参考になったのは、第3章の後輩が相談しにきた時のケーススタディだ(こういう場面は実際似よくあるので)。 まずは、対象者に普段から関心を寄せていることを示すためにラポールを形成して会話に導入し、現状の確認・問題や課題の特定をして、対象者と共に対象者の「望ましい状態」をイメージする。その後、解決方法を2人で検討して、その課題達成の為のプランを構築する。最後に、プランがプランのままで終わらないように、対象者に行動することを促してエールを送り、適宜フォローしていく。その適切な方法が詳細に描かれていて、「よし!やってみよう。」と思えることができた。 仕事の中で、コーチングを含めた他者とのコミュニケーション能力の醸成は永遠の課題だと思う。他者は須らく自分の思い通りには動かない。このことを認識した上で、この難解なスキルを身につけるためにもこれからもコーチングには積極的に取り組んでいこう。 そうすれば、他者に自分の思いが伝わって、他者が理想的な行動をお越してくれた時、相当な喜びが訪れ、他者ともその喜びを共有できるだろう。
0投稿日: 2012.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングがどんなものかの入門書という感じだった. 「but」ではなく「yes,and」での返事を心がける.
0投稿日: 2012.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログあれこれ人に構いすぎてしまうことは、その人の可能性を信用していないことと同じであることを痛感しました。 他人に世話を焼くのに他人からよく思われない人には、一歩引いた視点を掴むのに良い機会を提供してくれる本であると思いました。
0投稿日: 2011.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「コーチング」の技術が具体的に書かれていて読みやすい。第5章のセルフコーチングも今まで読んだ中で一番まともで実行に移しやすい。一目で理解できるように工夫すればもっと良い本になると思う。一読の価値有り。
0投稿日: 2011.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近よく聞くコーチングについて コーチングとは問題を抱えている相手に対して、答えを示すのではなく、それを相手に気づかせてあげる手助けをすることだ。 これによって問題を抱えた人は自ら問題を解決することができるだけだなく、やる気まであげることもできる。(答えを押し付けられるのは、不満だけでなく、やる気まで損なう可能性がある。) しかし、実際の現場ではコーチングの重要性に気づいていながら、コーチングになっていないことが多々あるらしい。 うまくコーチングするための注意点やこつなどが以下(当たり前のことだが、実践となると難しい) 黙って相手の話を聞く(目をみて) ペーシング ミラーリング フィードバック BUTからANDへ バックトラッキング 自分自身、塾で一浪生を教えているが、モチベーションをあげることがいかに大切であるか実感する。 講師である以上、教えること(teach)をする必要があるが、それ以上にコーチングによってやる気をあげると、生徒は非常によくがんばる。ただ、単に勉強しろ、いい大学に入れと言っても、そんなことでは勉強はしない。 僕の生徒も僕のコーチング(もどき?)によって自分の行きたい大学を強く意識して勉強するようになった。その意思を聞いたとき非常にうれしい気持ちになった。 やる気をあげるというのは仕事だけでなく、教育においても非常に重要であると強く感じる。
0投稿日: 2010.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] ビジネスのあらゆる局面で効果を発揮し、注目を集めるコーチング。 多角的にその技法を解説し、親子関係などへの応用法も紹介。 [ 目次 ] 第1章 人の可能性を開くコーチング(テニスではなく「バウンド・ヒット」を 「できる」を引き出す魔法の言葉 ほか) 第2章 コーチングが発揮される環境とは(マネジメントとコーチング 手放してはならない上司のプライド ほか) 第3章 コーチングの技術(コーチングプロセスのデザイン コーチングの基本プロセス ほか) 第4章 グループコーチングの技術「ファシリテーション」(非生産的な会議を何とかしたい GEにおけるワークアウト ほか) 第5章 セルフコーチングのすすめ(他人の作った流れの中で生きることの限界 日本中にあらわれた『やりたいこと探し難民』 ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングの基本がわかる本。 コーチングとは、を知りたい。これから始める。といった時には、丁寧な解説があるので、わかりやすい。 また、グループコーチングとして、ファシリテーションについても解説が。 初心にかえる時などに、1冊保管しておきたいですね。
0投稿日: 2010.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ菅谷さん所有 →10/08/01 平島さんレンタル →11/08/20 返却(本の会以外の場にて・竹谷預り)
0投稿日: 2010.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にためになった。しかし実践できるかが非常に問題。人との会話の中でコーチングを意識しながら考えるのは非常に難しいよね...「人は潜在的に能力を持っている。人はよりよい仕事をしたいと思っている」この2点を信じないとね。あと、観念の眼鏡を外して「今そこにいる」その人をみないとね。 ワークグループの具体例なども紹介してあり、とてもためになった。
0投稿日: 2009.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングというものを初めて知った本。今まで経験的に分かっていたものが、これだ!って感じだった。今まで読んだコーチング本で後にも先にもこれが一番分かりやすいです。
0投稿日: 2008.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ主にビジネス分野におけるコーチングの紹介の本。 コーチングって何?っていうひと向けで、 そこまで実践的ではないと感じた。
0投稿日: 2008.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007年8月30日 語り口:説明的 入門書。コーチングというのがどういう思想で成り立っているのかがわかった。概念としてはとても簡単。具体的なテクニックを知るには、他の本を読んだ方がいいのだろうな。
0投稿日: 2007.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングする側と、される側の対応の仕方が、とてもよくわかります。仕事だけでなく、親子間や、自分のセルフコーチングにも役立つと思います。褒めることに、危険な要素が含まれている事を知って、ちょっと、ドキッとしました。褒められる事で、次なる期待、プレッシャーを背負ってしまう事になるなんて。子供に対しては、褒めて育てろ式のやり方だったので、少し考えてみたいですね。
0投稿日: 2007.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司と部下だけでなく、コミュニケーションを使う生活全般に使えるテクニック満載です。 意外と役立ちました。
0投稿日: 2007.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ05-06-06 ドラゴン桜の桜木は、「受験以外にきめ細かく進路指導をしよう」という高原にたずねます。 「目の前に飢えて疲れている人がいます。あなたは魚を釣ってあげますか? それとも釣り方を教えてあげますか?」 高原は答えます。 「それは・・・・・・もちろん魚を釣ってあげます。」 国語教師の芥山は言います。 「高原先生、それではあなた、教師失格だ。それは生徒を全く信頼していないということにほかならない。」 魚を釣ってあげるのはヘルプで、釣り方を教えるのはサポートです。魚を釣ってあげることは、すぐに相手を救えるので、一見親切に見えます。しかし、魚の釣り方を知らない相手は、永遠に自分の力で生きていくことはできません。 教師と生徒に例えると、サポートをする教師は、生徒に学ぶ能力があることを前提にして、生徒が目標を達成できるように指導するのです。これは、「コーチング」をするときの姿勢です。 ドラゴン桜を読んで、少しコーチングについて知識を入れておこうと思い、菅原裕子「コーチングの技術」を買いました。するとなんと、上の話がそのまま載っているではありませんか。 また、第7巻67時限目の大学受験相談の話も、同じ本の、コーチングにおける「聞く技術」というところに載っていました(◎_◎;) 。ネタは、この本からだったのですね。 最近、「コーチング」という言葉をよく耳にします。「コーチング」とは、相手のやる気や潜在能力を引き出し、目標を明確にし、その人が目標達成できるようにサポートするコミュニケーション技術です。 「コーチング」は、当たり前のようで、そうでいて、意識しないとできないことですね(今のわたしには)。
0投稿日: 2007.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングの入門書的な位置づけ、なのでしょう。概念を概観するのには適しているのかもしれません。これを手がかりにより実践的な本に当たらないと身につかないとは思います。
0投稿日: 2006.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ例えば、部下が何か悩んでいたり、失敗したとしよう。置かれている状況を一番理解しているのは本人だ。だから、すぐに「こうした方がイイ」「それじゃダメ」だとか口うるさくしないで、「どう考えてるの?」と何を考えているのかちゃんと聞いて、必要な事を教えてあげる。そんだけ。 この本中身がそんなに濃くないから、必要だと思うとこだけ飛ばして読んだほうがいいかも。
0投稿日: 2006.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログサッと読み流しただけでも、コーチングとは何か?これで何が変わるのかがわかってくる気がします。よく2000円以上でコーチング関連書をみかけますが、その本を手に取る前に、本書を一読してみることを強くオススメします。
0投稿日: 2006.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ♪バウンド、ヒット ♪バウンド、ヒット テニスの打ち方を教わるとき、 ボールをよく見て打て!といわれるより、 ♪バウンド、ヒット ♪バウンド、ヒット 口ずさみながらラケット振ったほうが僕でもボールに当たるような気がする。 より具体的に指摘してあげるとうまく行くという好例。これがコーチングの極意ということらしい。 このエピソードもコーチングの話の枕として最適だと思う。
0投稿日: 2006.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングって“教える人が読むもの”だと思ったら大間違いで、“教わる立場の人”も知っておいたほうがいいことはたくさんあるのです。
0投稿日: 2006.03.11
