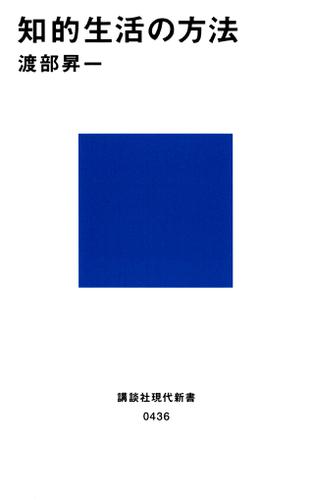
総合評価
(134件)| 32 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 4 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1976年の本なので、2025年から見たら……約50年前! こんな時代でも「情報洪水」とか書かれてる。構造は50年前から変わってない。 読む前は古い本ということで身構えていたが、目次の時点で「何書いてるんだ?」って興味が出る。文章も堅苦しくなく読みやすい。それも、後になるほど軽くなっていって、本を置く場所の問題とか、飲酒の話とか、「家族と親類は知的生活にとってはだいたいマイナス要因」だとか、果ては「まあまあ幸福な家庭生活と、まあまあ満足のゆく知的生活の両立を求めるのが無難」という話まで飛び出す。ちょっと笑ってしまった。 もちろん示唆に富む箇所も多い。 「わかった気になること」を怖れるという話では、著者の学生時代、普通に英語の本を読むより辞書や文法書を読む時間の方が長く、それでも理解できないというエピソードが印象に残った。「わからない」に耐えるのは、ChatGPTに聞けば何でも答えてもらえる現代こそ肝に銘じるべきことだろう。 繰り返し読んで、それでも読む価値があり、最後に残ったものが古典。たくさん読むことが良いことでは無い。私も読みたい本がブクログに溢れているが、考え直す必要があるのかも。読んでから忘れてしまっていることも多い。 本は財産になる。読み返すこともある。しかし、新聞記事のスクラップを読み返すことはない。この話も身につまされる。ノートアプリにどんどんスクラップを貯めているが、確かに読み返すことがない。というか、インターネットの未読記事も1000近くある。困ったぞ。 読書の時間が足りていないようにも思う。一方で、繰り返し読むものと、今後一切読まないものを決めるのも大事なのかも。本を紹介しあうブクログでそんなことを書くのも矛盾しているのだが。それか、読みたいものはすぐに読んでしまうかだ。
7投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1949102128288653747?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ全部知ったような顔をして生きてきた自分にとってはかなり突き刺さる内容だった。これから中身も問われる中で、読んでおいてよかった本 ●知的正直とは、わからないのにわかったふりをしないこと ★知的生活の真の喜びは、自己に忠実であって、不全感をごまかさないことを通じてのみ与えられる。 知的生活を行う者は、退行現象ということを考慮に入れてそれに備える心構えが必要 ●知的生活は、専門的な勉強、職業上の仕事のみでは不十分である。どうしても、知的な関心を持つ人たちとの、肩のこらない交流と、特定の目的に束縛されない自由の読書のための時間が必要
0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、半世紀前のもので、文献を調べようにも図書館を訪れないといけないような時期。今ではPCやスマホ一つで世界中の文献を閲覧可能だ。本書の要点は、分からないことを誤魔化す勿れ、そして、本は所有しておくべきこと、とある。現代は無論ネットが有るが、この50年前の言葉を現代向けに言い換えるには、著者の発言の真意や根本原理を考慮する必要がある。例えば、京大式カードというものは、使うべき時と否の場合があるだろう。情報整理は圧倒的にPCに軍配。しかし、発想の観点で言えば、カードも侮れないだろう!
21投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログおすすめ。 #興味深い #考えるヒント 書評 https://naniwoyomu.com/374/
0投稿日: 2025.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本棚に見当たらなかったので買い替えて読んだ。ああ、こういう意識高い系でいままで生活してきたら、いま頃、もっと業績あげられたであろうに。蔵書も数だけはあるけど、ただ買うだけになっている。諸事ありすぎだよな。年末なので新年に備えて心機一転したい。カントのような生活は、わたしも目指している。早起きして午前中に仕事して。著者は夜型のよう。 ただ、何事でも(したがって知的生活でも)、若いって何ものにも勝る価値だと思う。とくに目。老眼での読書はキツイ。
0投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が様々な本を読んで、実践してきたこと、自ら工夫したことを、"本を読んだり、物を書いたりする時間が生活の中に大きな比重を占める人たち"の参考になるように書かれた本である。 だから、本書が最も役立つと思われるのは、主に学者や作家という人たちになるだろう。 それ以外の人でも、知的生活を送りたいと考える人たちにとって、それを実践するためのヒントは得られるだろう。 また、カントやゲーテなどの偉人の生活を垣間見ることによって、スマイルズの「自助論」のような自己啓発書として読むこともできる。 本書の出版は1976年である。2024年の今から約半世紀前に書かれたものであるが、版を重ねており、いまだに新品で買うことができるということは、時の審判に打ち勝ち、世間から認められたという証である。名著であるが、決して固い本ではない。文章も内容も読みやすい本なので、「知的生活」という言葉にピンと来る人は一読をお勧めする。
0投稿日: 2024.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ何度も読みたい本。 読書や勉強に力を入れる時、再読して意義を確認したい。 一つの本を精読すること。読了で終わらず読破、深く理解し、感性を磨かれる読書をしたい。
0投稿日: 2024.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外の人が継続して本などから知識を得ているのに対して、昔から日本の社会人は本を読まないと言われたみたいですね
1投稿日: 2024.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろいし、おほむね賛成 いやあ初めて読んだが、いろんなエピソードが出てきてめっぽうおもしろかった。たくさん笑った。 たしかに後半、頻繁に精神分析を持ち出してきてオカルトめいてきたり、ワインとかビールとかいふ変な部分はある。 しかし全体的にかなり納得・共感した。たとへば、知ったかぶりをする子供は進歩がないとか、カントの規則正しい生活と血圧とか、見切り法とか、知的生活と縁のない配偶者とか。なるほど!である。しひて言へば知的空間のための建築の部分があまり現実味がないが、まあ理想を高く持てといふことであらう。
1投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に再読。もう46年前の著作ということで、後半のノウハウ的な部分は、色々な意味で時代性を感じる点も少なくない。が、「過去の成功例をそのままマネしても、意味がない」ということは、著者自身がそもそもちゃんと書いている。この点を念頭に置きつつ、どう応用できるかを考えながら読めば、今でもとっても参考になる1冊。 本書のなかでより普遍的なメッセージは、前半部分だろう。分かったつもりにならない・分かることを恐れる「知的正直」の大切さや、自分自身の古典を作ることの意義は、著者自身の読書遍歴や当時の世相も交えて具体的に語られているがゆえに、かえって古びない。
21投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版は1976年4月発行。時折読み返しているが、読むたびに新たな発見がある。 本書は知的生活の肝を「本との関わり」と定義しており、書斎の設計図まで提示されている。本をネットに置き換えて、有効な活用方法を考えるのも面白い。
4投稿日: 2022.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
渡部昇一「知的生活の方法」、講談社現代新書436、1976.4発行、再読。20代後半時に読んだ時、いい本だなと思いました。ハマトンの「知的生活」に触発されて執筆されたとか。自分をごまかさない精神、古典をつくる、本を買う意味、知的空間と情報整理、知的空間と時間、知的生活の形而下学の6つの章立てです。著者は本の購入と図書館を持つことに強いをこだわりを持ち続けられました。経済的に余裕があればいいなと思います。でも、今は、インターネット、パソコン、バーコードの普及で、図書館にある本は大体すぐに読める時代ですね。
1投稿日: 2022.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで読んだ知的になる本の中で、一番自分に合う感じがした。 学びの興味はあっても、選ぶコツだとかが適当だとうまくない。自由をとって幸せを取らないみたいなことにもなりかねない。 知的な自由でいながら満たされる可能性を感じられた。いつまでも勉強をしているけど、強い諦めも感じていた。少しマシになれそうな気がした。
3投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ金は時なり=時間という要素が一番大きい。 時間を買うためにも本は買う。 無駄な勉強に時間を費やさない。 上智大学では、英語に集中させるために第二外国語を見切っている。 早起きカント。起床は5時。7時まで準備。9時まで講義。1時まで仕事。 溶鉱炉は火を落とさない=仕事は4~5時間まとめて時間をとる。 半端な時間は、暗記する。 みんなと同じことをしていれば、みんなと同じ平凡なことになってしまう。断固として始発電車に乗った人の話。
1投稿日: 2021.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版と言うか第一刷を持っている。 本書の出る前は、知的と言うと京都大学教授の梅棹忠夫さんの知的生産の方法だった。 そこに上智大学教授渡部昇一さんの知的生活の方法が出た。 発想法、KJ法の東京工業大学教授川喜田二郎、 地球物理学東京大学教授の竹内均、 頭の体操の千葉大学教授多湖輝等々が活躍していた頃だ。 岩田一夫もその頃か。 知的生活には、エアコンが必要だ と書いて、一部からは 贅沢だと叩かれた という時代だった。 しかし本書は新鮮だった。 知的という言葉を、生産から生活に拡げた功労者だと思っている。 日経新聞のおかげで、渡部昇一さんの講演会を聴く機会を得たのも、本書の縁だと思っている。 まとまってないけど、リリース。
3投稿日: 2021.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ・著者の本への愛を感じた ・著者の体験が分かりやすく書かれており、エッセイのようで面白い ・本を読む姿勢を改めたいと感じた
1投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ●若かりし時代に読んだ本で、座右の一冊です。 ●私は読書が好きで、先人に学ぶ事や擬似体験する事が人間形成に役立つと考え、色々な本を読んできました。そのように、読書する事の意義を考えていた頃に、この本に出会い、その後の読書姿勢に役立ちました。 ●共感した点を少し書きます。「①知的な生活が細々とでも続いている確実な外的指標としては、少しずつでもちゃんとした本が増えているかどうかを見るのが、一番簡単な方法である。②十年間に一冊も本らしい本を買わなかった、ということは、この人は日常生活のみをやって過ごしたということをなので、知的生活はなかったと言ってもよいだろう。③知的な生活が細々とでも続いている確実な外的指標としては、少しずつでもちゃんとした本が増えているかどうかを見るのが、一番簡単な方法である。④あなたは繰り返して読む本を何冊ぐらい持っているだろうか。それはどんな本だろうか。それがわかれば、あなたがどんな人かよくわかる。しかしあなたの古典がないならば、あなたはいくら本を広く、多く読んでも私は読書家とは考えたくない。」長くなったが、今でも私の読書の座標軸です。 ●この本を早く読む事が出来てよかったと思っています。前述した他にも著者の経験談を元に参考になることが沢山あります。読書が好きな人に読んで貰いたい一冊です。蛇足ですが、本書は講談社現代新書史上最大のベストセラーだそうです。
35投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ己に忠実に。 ある知的生活者の日々の教訓を伺う本。姿勢を見習う。 ・「わからない」ということを恐れない。「わかった気になる」ことを恐れる。 ・小説を理解するには知的レベルが必要。読めないときは読まない。知的レベルの向上が先。 ・時間の間隔を置いて繰り返し読む。繰り返し読んだ本が何かで<わたし>が見える。
1投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書家に読んで欲しい本。 読書術や勉強術といった類いの本ではなく、知の巨人たちが如何に自分達の知的生活を持ち続けるかという本である。 少し前の時代の知の巨人の話を聞くことで学ぶことの原点を改めて見つめ直すことができる。
3投稿日: 2021.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語学者としてその半生を母校・上智大学での研究に捧げる一方で論壇の重鎮としても活躍し、戦後日本の言論空間に風穴を開け「知の巨人」と称された渡部昇一(2017年没)のベストセラー。日本が世界に類のない高度成長を遂げる中で、物質的に豊かになった日本人に最も必要なのは「知的豊かさ」であるとして、それを獲得する唯一の方法は「本を読むこと」に他ならないと論じる。自分にとっての古典、つまり何度も繰り返し読む本や作者に出会うことが最大の幸福とし、仕事に忙殺されて読書をしない生活は「日常生活であって知的生活では無い」と喝破する。読書環境の向上に多くのアドバイスを与える中で、日本の夏を克服して知的生活を守るにはエアコンが一番というようなユニークな視点も本書のスパイスとなっている。
1投稿日: 2020.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ期待して読んだが、自分にとっての学びは少なかった。本書は著者の考えや習慣等をまとめたものなので、必要な部分だけ読めば良い。それ以外は参考程度に流し読みするか、飛ばしても良いと思う。
4投稿日: 2020.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本は1976年に発売されている。 私は、1982年頃の大学生の時に読んだと思う。 で、将来は、自分も知的生活に入るということを、本気度はともかく、一つの目標にしたものだ。 で、時は流れて38年後の今、理想とは随分と違うようで、本に囲まれた生活になどなっていない。 本はほぼ図書館から借りて読み、時々買った本はブックオフに持っていく。 しかし、ブクログがあり、きちんと登録すれば、読んだ本はすぐに出てくるので、38年前には想像もできないような便利なツールが今はある。 感謝、感謝、大感謝! まあ、今後も出来るだけ、読書は続けていきたいものである。
13投稿日: 2020.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本に常にアクセスできる環境を整備したくなる本。 書庫の1ブースを考えごとをするスペースとして設計できるかがカギ。やはり寝室はスッキリしておきたい。
1投稿日: 2020.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活を送るための信念や方法を論じた一冊. 前半部の心構えは知的生活をするしないにかかわらずプロになるための方法とも思えた. これから知的生活を送るうえで本・情報源へのアクセスは近い距離がよいと思え,その量自体も沢山あるべきだと共感できた. 勉強する習慣は学生で終わりと思わないので,社会人になってからこの本を手に取りどう生きるかを再考するべきと思った. 以下章ごとの要約 自分をごまかさない精神 わかったふりをしない.わかるまでやらなければ器用貧乏のように終わってしまう. 古典をつくる 何度も何度も舐めるように繰り返すことが大事.そうすることで感性を研ぎ澄ますことができる. 本を買う意味 身銭を切ることでモチベーションをあげられる.手元に置くことでアクセス性が向上する. 知的空間と情報整理 知的空間の必要性やおすすめの間取りを紹介.情報整理についても筆者なりのやり方を説明. 知的生活と時間 知的生活を送る上での時間の使い方を説明. 知的生活の形而下学 知的生活を送るための具体的な食生活や人間関係を説明.
1投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ヤバい本を読んでしまった… 私の中で唯一で初めて☆1つですよ… いや、自分なりに先人の嗜好やライフスタイルを読み解いて、インテリはこういう生活してるんです、読書方法はこれです(何度も読む、数をこなす、腹落ちするまでは分からないことを認める)と研究してるのはいいと思う。 どうぞしてくださいと思う。 でも、新聞の切り抜きは意味ないとか、知的生活に相応しいのはワインとか、チーズとパンを食べる生活(カントを参考にしてるから。他の人の引用はなし)がいいとか、全く論理的じゃないし科学的根拠もない。偏ってるにもほどがある… そして極め付けは自分の知的生活を邪魔しない妻を選べ、妻には献身的に家事や空気読みをしてもらえと。妻に寝る前の読み聞かせをしてもらうという例を出すとか、子どもを作ったら知的生活ができなくなるとか、ないなーと思いながら読んでしまった。自分のことしか考えない子どもなの?(イラ) 自画自賛だし他人のことバカにしすぎだしこの人友達いるのかな?と思ってしまった。 知的生活を送ってる人って、もっと謙虚でフェアで広い視点で世界を見られているのでは。 知的生活について本当に知りたいのは例えば「子どもを作ったら知的生活ができなくなる」じゃなくて「どうしたら子と一緒に知的生活ができるか」でしょうが。 なんか、全体的に「愛」が足りない!(怒) 自分のことしか考えなくていいと思ってる人にとっては参考になるであろう本でした。
1投稿日: 2019.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書はいわゆるHow to本といったたぐいのものではありません。どちらかというと、知的生活のための姿勢や考え方を説いた書というべきでしょうか。 とにかく著者の妥協を許さない姿勢に圧倒されます。読み進めるたびに「ああ、自分は己に甘かったなぁ・・・」と反省することしきりであったとともに、勉学に対するモチベーションが一段と高まりました。 「1.自分をごまかさない精神」では、わかったふりをせず、わかるまで突き詰めることの重要性を説いています。 「2.古典をつくる」では、繰り返し読むこと。それを通して本物を見極める眼力が身に付き、手元にも本物だけが残っていくことが述べられます。 「3.本を買う意味」では、身銭を削って本を買うこと、どんなに貧乏であっても本を買い、読み続けることの大切さを、実体験などを引用して説明してくれます。 「4.知的空間と情報整理」は、本書には珍しい情報整理のHow to説明です。カードシステムを用いた情報整理法にとどまらず、知的生活を送るための家の間取りを、設計図(間取り図)までつけて説明しています。 「5.知的生活と時間」、「6.知的生活の形而下学」では、日々の生活上の工夫や人との交歓や食について説明しています。知的生活を送るうえで好ましい食材・料理を取り上げる中で、カントの食べた献立なども紹介されておりユニーク。 印象深いのは「1.自分をごまかさない精神」において、「本当にわかる」ことの体験談を述べている下りです。 「・・・しかし一生を外国語にかけた男として、そのような状態には決して満足したわけではなかった。私の頭からは少年のころに、あのようにぞくぞくする気持ちで読んだ『三国志』や少年講談や捕物帳のことが去らなかった。 ・・・「私の英語は本物ではない」という不全感は常に去らなかった。 ・・・どうしてもその不全感に耐えかね、断固とした手段をとることにした。つまり留学のし直しである。」 留学することの是非はさておき、その徹底ぶりはやはりすごい。 そして、留学先で外語小説を本当に「わかった」時の描写、 「(『マジョリー・モーニングスター』を読み始めたところ)引き入れられるように面白い。そして終わりに近づいてきたら、がくがくと身震いがしてきて、読み続けることができなくなった。 ・・・私は心を落ち着けるために風呂に入った。そして残りの4ページ半を読んで、この記念すべき小説を読了した。これは私にとってまさに記念すべき夜であった。 ・・・それを子供のころに少年講談や『三国志』を読んだ時のような興奮で読み終えることができたのだ。ついに英語についての私の不全感は吹き飛んだのだ。私は踊り狂いたいような気になった。」 これが「わかる」ということなのだ!といわんばかりの描写です。自分がこのような興奮をもって読了した経験が果たしてどれだけあったことか・・・。 このような興奮をもたらす作品に出会うまで、著者は本を読み漁ります。それほど熱意を持って臨まねば本物には出会えないが、出会うことができたならば、これに勝る幸はないことを教えてくれるエピソードです。
4投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ一章が一番面白かった。 筆者の読書人生の礎となる、幼い頃の原体験があまりに強烈だったためと思われる。最も熱量を感じた。 何度も繰り返し読む、知的オーガズム、「わからない」に耐える
1投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、梅田望夫さんの「Web時代を行く」という本で取り上げられていて、気になったので読んでみた。 本当に面白いと思えるものを見つけること、そして見つけたものに対して継続的に活動や努力をし続けることが知的生活の根本的な考え方かなと。 好きなことを見つけたら、余暇のほとんどの時間をそのことに費やしても苦にならないし、モチベーションも維持できるというものだろう。 知的生活には、絶えず本を買い続けることや、知的正直(わからないのに、わかったふりをしない)であることの重要性が書かれている。 後半は、ワイン、散歩、クーラー等の効用が書かれていて、さらっと面白い。 また、知的生活には、家族との付き合いや結婚にも慎重であるべきというような記述や、本の置き場所が重要だから書斎や書庫、部屋が載った家の設計図まで載ってて、どこまで!?という感じもするが、そこは著者の情熱なのかなと。 なかなかよい本でした。
3投稿日: 2019.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的な喜びの源泉は、自己に忠実であって、不全感をごまかさないことを感じてのみ与えられる。分からないものをわかったふりをするはせずに、面白くないものを面白いというふりをしない。 面白くない本を無理して読んでも、読後に何にも残らないのは確か。知的向上を図るためには、自己に忠実であるべき。 自分の古典を見つけるというのも、新たな知的発見が可能となる。早速、2-3年前に読んだ本の読み返しを行おうと思う。
3投稿日: 2019.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活=読書といってもよい。 自己投資。お金の使い方はとりもなおさず、本を買うことであり、買うという行為が身を引き締めて知識を得ようとする行動につながるのだ感じる。 1970年代の本であり、現代には参考にならない箇所もあったが、精読や知的生活の大切はよく理解できる。 何度も読む本が自分のとっての古典になるという点は実践したいと思った。 また知的内容の濃い生活を送れているか自問する良いきっかけとなった。 知的生活者にとって、Time is Moneyであり、時間も金で買うことは大事。これは、行列に並ばないこと、VIP席に座ることなど、生活のちょっとしたことに対する自分の価値観と比較して、どれが一番良い選択肢を選ぶことも知的生活を生きるという意志にもつながると個人的に思う。それは、お金で解決したことによって、それから生ずる時間のゆとり、心のゆとりを獲得し、さらなる知的生活を過ごせる時間を生み出すことだと個人的に思う。 退行現象の話は面白かった。カント、ダーウィンなどいずれも知の探求者はどこかで休息が必要で、それが睡眠方法だったり、妻の音読だったりする。
1投稿日: 2018.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログメディアの進化や男女観等、時代を感じる部分はあるが、今に通じる部分もある。 彼の言う知的生活がどんなものかは理解することができたように思う。私自身は本を所有するということに重きを置いてこなかったので、所有する利点について気づきがあった。
3投稿日: 2018.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログカード式についての見解が興味深い。金があるなら、本買った方が良いが、金がないなら、カードしかない。しかし、時間はかかってしまうことは覚悟すべきということ。単に、身銭を切らないと身に付かないと言っているのではないところに注目した。また、繰り返し読むという点にも注目。古典の形成過程を分析して、繰り返し読むことの意義を論じているところは、興味深く、納得できる内容だった。
1投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活を実践するには!家の造りまでにも限定している。梅棹忠夫さんの「知的生産の技術」とならぶ名著。
1投稿日: 2018.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ。 ・書斎を持つこと。欲しい ・タイム・リミット。勉強し続けないで、見切りをつけることは大事。 ・中断されるおそれがないこと。これはほんとうに重要。仕事でも、会議多すぎ。
1投稿日: 2018.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ渡部昇一さんの考え方が好きで憧れを持って読んでみた。知的生活を行うための態度として特徴的と感じたのは「分からないことを恐れないこと」と「静かなる持続」の2点だった。 簡単に言えば、僕らは「勉強」をする時にその成果に対してせっかちになりすぎているのかもしれないな。と本書を読んでいて気付かされた。 結果は後からついてくると信じて、知に大きく投資する勇気を持とう。
7投稿日: 2018.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い本だから、そのままは当てはまらないことが多いけれど、考えて自分の行動を決めるという普遍的なことに対しては非常に参考になる。
2投稿日: 2018.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログお金がなくても本を買おう、時間がなくてもやりくりして本を読もう。そういう基本的スタンスは、この本に影響されて身についたものだと思います。今の自分をかたちづくっている、自分にとって意味のある本のひとつです。(1997年頃読了) 【以下2018年5月26日追記】 ふと、本棚から取り出してペラペラめくってみました。ああ、なつかしい。 この本でカードシステムということを知って、大学時代、必死にカードを作ったものです。ただ、途中からカードを作ることが目的化してしまい、結局研究はものになりませんでした。なんのためにカードを使って研究するのか、考えが浅はかでした。 そのことに対する自戒として一文引用します。「いいことをしている気になっているのだから、時間を浪費しているという反省がない」(162ページ)。 これは、今の自分にも当てはまります。仕事でも日々の読書でも、一見役に立ちそうに見えて、実は時間の浪費に過ぎないことに注力することはよくあることで、すこし視点をずらして冷静に考えたら気づけるはずなんですが、有益なことを一生懸命しているという気分になってたら、なかなか気づけないんですよね。 逆に、時間の浪費に見えるけど、実は有益だということもあります。たとえば、哲学の原典を通読すること(ま、最近私は翻訳で読んでますが…)。哲学事典や解説書で十分なように感じられますし、なんなら、ネットの要約などを見たら内容はモノの数分で把握できてしまいます。なのに、数週間、下手すれば1か月以上も時間をかけて小難しい文章を読む。これは本当に価値があることなんです。このことをどう表現したら他人に伝えられるかよくわからないのですが。 今回、久々にぺらぺらめくってみて、知的生活を充実させるにあたっての時間の使い方がいろいろ気になりました。
8投稿日: 2018.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ分からないものを分かったふりしない、繰り返し読む自分の古典をつくる、身銭を切って本を買う、自分なりの書斎をもつ、散歩の時間をもつ、等、知的生活を送る上での具体的な話が参考になった。
1投稿日: 2018.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ永遠のベストセラー 現代の日本国に於いて基準となるものです。というかなってます。 当時のヒルティ「知的生活」になるでしょう。 この著作を抜きにして啓発本は語れないと思いますが。 何時かは突き当たるものでしょう。 電算機隆盛の今の時代は果たしてどうなるのでしょう。 渡部氏が御壮健でいらしたらどういう答えが聞けるのでしょうか。
1投稿日: 2018.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ文句なしの名著。とりあえずみんな読もう。 p160 ハトマン「知的生活(intellectual life)」:人生を空費させる最も大きな敵は、「下手な勉強」 これにはドキッとした・・・
1投稿日: 2017.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから、いかにも「インテリ向け」という印象がしたが、そうではないという誤解がないような配慮を冒頭に記している。まだインターネットがない頃の本。後半の書斎スペースや家族との時間を持ちながら読書時間を捻出する課題については、インターネット、ネット書籍などが解消してくれる気もした。 個人的に、著者や歴史の教科書に出てくる偉人にも「退行」となる行動はある意味必要だったということに衝撃を受けた。自分の生活パターンや脳の働き方について考えるきっかけをもらった。
1投稿日: 2017.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の体験をもとにかなり具体的に「知的生活」について実践的な方法を提示してくださっている。なかには庶民には真似できないようなこともあるが、まるっきり真似ることが重要なのではなくあくまで参考にし自分の生活にあった知的生活をとりいれるのが正解なのだろう。 しかし女性や同性愛を軽視したような発言があるのはいただけないと思った。それも彼が知的生活を保つことを重要視しているとともに、その難しさを十分に理解しているからこそなのだろうが。
1投稿日: 2017.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ何十年ぶりかで読んだがとても楽しく面白かった。 若い頃に読んだときは早く結果を出したいと焦っていたためか、 「得るところは無かった。しょせん私立大学の教授レベルだ」 などと不遜な感想だった。 反省している。 歳を取り、経験もそれなりに積んでこそ分かることがあるのだと改めて感じ入った。 テクニックやノウハウは古くなっている箇所もあるが、読者がそれを現代の手法に置き換えれば良い。 役立つ面白さでなく、分かる面白さだった。 今はすぐ成果の出るビジネス本がたくさんあるので、つくづく今の人は幸せだと思う。
1投稿日: 2017.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
物を読み書きし勉強することを一生を通して行っていきたいという人のための、実践的な方法を紹介している。 内容は、精神性から情報整理法、時間や食事方法まで知的生活に関することを具体的に示している。一般人には到底真似できないと思うような理想のような記述もあるが、知的生活を実践した先達の言うこととしていくつか自分のできる範囲で実践していきたいと思った。特に、下手な勉強は時間の空費ということについては常に意識したい。 著者のその後の本を読むと、本書にある家庭は知的生活にとってだいたいマイナス要因であるという考えは変わったようである。
1投稿日: 2017.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本でも有数の蔵書をもつ著者の、本への愛が詰った一冊。 一言でいえば読書のすすめだ。 たくさんの本を読まれてきた著者なので、多読を勧められるのかと思いきやそうでもなく、むしろ精読を勧める。 漫然と次から次に読むのではなく、気に入ったものを何度も読むことで細かいディティールや背景が分かり、微妙な変化に対するセンスが磨かれるという。 知的生活には適度なコウスティング(退行)が必要とのことで、カントやダーウィン、ヴィトゲンシュタインの例が示されているのは面白い。 また、ワインを飲むことや、散歩をすることも思索に良い影響があるということ。
2投稿日: 2017.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ身銭をきってでも本を買いなさい。そして手に置け。 蔵書を作れ それを実践した結果家が大変なことに(笑)
2投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活を送る方法 納得できるものがたくさんあった 理想としてはそうしたいと思うものが たくさんあったので、それを実現していきたい!
0投稿日: 2016.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ憧れます「知的生活」。 本当は今の職業を選んだのだって、多少なりともそういう部分があるかなという期待があったわけですが、現実は全く違いました。 これを読んでいると、やはり研究者とか大学の先生くらいしか、こういう生活は送れないのかなあ。 しかし、あまり難しいことを考えるのも私にはできそうもありません。やはり、知的生活はあきらめるしかなさそうです。 この本は、いろいろな文献からの引用が豊富で、過去に知的生活を送ってきた人たちのエピソードが読めて面白いです。憧れると同時に、自分には到底たどり着くことはできない極みのような気もします。 2章の「古典をつくる」というのがなかなか面白いです。同じ本を何度も読んで、それでも読みたいと思えるような作品に出会う。それが、その人にとっての「古典」です。 そういうものに出会うと、本物とそうでないものが簡単に見分けられるようになる、と簡単に言ってしまえば、そういうことなのですが、同じ本を何度も読む、確かにあまりしてなかったなあと反省させられました。 私にとっての古典は、いつ生まれるのでしょうか。
1投稿日: 2016.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログわからないのにわかったふりをしないことを貫くことが大切 同じ本を繰り返して読む。 反覆することで、文体の質や文章の背後に ある理念のようなものを感じ取るセンスが磨かれる。 本物の読書家は、繰り返して読むに耐える その人自身の古典を持っている。
1投稿日: 2016.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読了。指導教員の指導内容の出所はここか、と得心する。とまれ、できること、納得できることは取り入れていきたい。
1投稿日: 2016.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自己啓発本というより、勉強方法や読書に関するエッセイみたいなもの。 梅棹忠夫の「知的生産の技術」の方が参考になる。 書斎の窓は、はめ殺し。 低血圧なので、朝に無理して頑張る必要はないというのはありがたい話だが、環境がそれを許してくれないんだよね。
1投稿日: 2016.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ渡部昇一氏による1976年発表のベスト&ロングセラー。 本書の執筆の動機について、渡部氏は「はじめに」で、英国のP.G.ハマトンが1873年に発表した自己啓発・上達論の古典『Intellectual Life(知的生活)』に刺激を受けたと述べているが、一方で、慶應義塾大学の塾長であり、今上天皇(明仁天皇)が皇太子時代の教育参与も務めた小泉信三氏が1950年に著し、現在も読み継がれる『読書論』を強く意識して書かれたとも言われている。 「知的生活」というコンセプト、ライフスタイルを一般に広めた記念碑的作品であり、この種の書籍では梅棹忠夫氏の『知的生産の技術』(1969年)と並ぶ古典といえる。 内容は、著者の半生記的な性格を持ち、かつ、テーマがインプット&アウトプットという知的生産術にとどまらず、衣食住環境や家庭生活等に及び、また、知的活動を直接的な職業にしている人間の理想像を語っている部分もあり、出版から40年が経った現在、一般の職業を持った人間にとっては正直参考にはならない部分もある。 しかし、「あなたは繰りかえして読む本を何冊ぐらい持っているだろうか。それはどんな本だろうか。それがわかれば、あなたがどんな人かよくわかる」、「本を買いつづけることは、知的生活者の頭脳にとっては、カイコに桑の葉を与えつづけることに匹敵するようにさえ思われる」等、刺激を受けるフレーズも少なくはない。 知的生産のノウハウを得るために1冊の本を選ぶのであれば他の本を奨めるが、「知的生活」をテーマとした古典として目を通すのも悪くはないだろう。
1投稿日: 2016.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ・この知的な歓びの源泉は、私が少なくとも読書に関しては「自己に忠実」であったことの報酬として与えられたものであると解釈している。少年のころの「おもしろさ」をどこまでも忘れずに、そこに至らないおもしろさは本物でないとしてきた、そのほうびであろう。
1投稿日: 2015.05.17確かに存在する知的生活
書籍説明に「知的生活とは、頭の回転を活発にし、オリジナルな発想を楽しむ生活である。」とあるが、その核となる読書生活を中心に話題は展開していく。筆者の実体験をもとに、読書によって得られる喜び、それを手に入れるための読書に対する考え方から、知的生活のための住居空間の活用法、日々の時間の使い方、食事や睡眠、などが図や引用も交えつつ深く考察されている。 なにしろ40年も前の本であるから、所々時代の違いであまり参考にならない部分(例えば、当時はクーラーがあまり普及していない)などあるが、著者が語る本質的な部分については全く色あせていない。読書習慣のあまりない人が本書を読めば大いに啓発されるであろう。 内容とは直接関係ないが、著者の執筆生活についてもいくらか書かれているので、渡部氏の他の著書を読む予定がある方は、その前に本書を読んでおくといくらか参考になるかもしれない。
2投稿日: 2015.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名から想像されるようなインテリっぽい内容とは真逆で、主に文筆業を営む人にとっての、その情報収集の源となる、本の読み方、取扱い、保管方法等について。 時は金なり、如何に効率的に情報を得るためにはコストを惜しむべきではなく、その姿勢を突き詰める事が必要なのだと。 1976年に初版となり、手元の新書で2008年版73刷となるロングセラー。 現在発達したインターネットをどのように活かすのか改めて聞いてみたい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E9%83%A8%E6%98%87%E4%B8%80
1投稿日: 2015.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的正直じゃなくて、[正直]だけじゃだめなの? ただの馬鹿は怖くないけれども、学問した馬鹿は理屈をこねるので、一番始末に悪いバカだ 平凡な著者の本を次から次へと読んでいくのは頭の中をやかましくさせているようなものだ
1投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ無類の本好きの書かれた本。 様々な切り口から読書について提唱されている。 高血圧は朝型、低血圧は夜型、知的生活に一番良いアルコールはワイン、ビールは人格を穏やかにするけど頭を働かせるのには向かない、書斎には窓をなしにしてクーラー、とにかくお金に苦労しててでも本は買って線を引いたりして使いまくれ(借りるな、売るな)、メモなんかも作る必要なし(時間のムダ)などの提言満載で、読書への愛が素晴らしく、くすっと笑えるところもあった。 中でも、本は何度も何度も読み返すことが大切というのは、なるほどと思った。読み流すのではなく、まずは最近三ヶ月くらいの間に読んだ本を読み返してみるように、とのこと。実践あるのみ。
1投稿日: 2014.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ先程レビューを書いたのになぜか全部消えたので再度書き直し。 私が生まれる前に書かれた本ですが、とても新鮮で良い本でした。 今も昔も人間に対する問題点はそんなに変わらないのだなぁと感じました。 特に私の響いたのは 「本当に自分の心に響くところがあっての勉学でなく、有利な社会コースに乗るための、目先の手段としてだけの勉強という要因が多いのではないだろうか」ということです。 特に大学生などそのような傾向があるような気がします。 大学ってそういうところなんでしょうか…? そしてもう一つは 「昔から日本人は学校を出ると本を読まないが、それに反して外国人はガリ勉はあまりしないが、本を読み続けると言われてきたものである。」 不景気なせいもあるかもしれないが、なんだか表面的に自分を守るためだけの世の中になったのかなぁなんて感じます。 途中、本を書くためのノウハウみたいな感じであまり私には必要な情報ではありませんでしたが、それ以上にたくさん得られ、考えさせられる本でした。 とても良かったです。
1投稿日: 2014.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ研究者としての時間活用術。一読して「そんな時間どこにあるの」という印象を持つ方も多いかもしれないが、やはりこれが一種の、理想的な知的生活であり、人類の叡智がそこから生み出されてきたことも事実である。 この生活をそのまま実践することができる人は一握りであり、大半の人は日々の仕事に忙殺されている。しかし、研究者として、大いに参考になるところがあった。
1投稿日: 2014.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の少年時代の話に心温まった。読んでいると自分も知的生活上級者になれるような錯覚を起こせる。この時代に考案した建築が現代建築デザインに引けを取らないくらい洗練されていて驚いた。
1投稿日: 2014.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和51年初版の著書。さすがに時代を感じました。すべてがアナログだった時代、苦労して得た知識をカードに書き写して貯めておく、大枚をはたいて耐火書庫を建築する、などなど。でもこうしたインテリ層は今でももの凄い蔵書を持っているんだろうことは想像できる。面白かったのはいくつか提案している住宅の間取り。とっても現代的で、当時としては先進的だったと思う。あと、読んだ本をを読み返すことが少なかったのを反省。
1投稿日: 2014.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的余生の方法 / 渡部 昇一 / 2012.4.10(14/93) 少ニシテ学ベバ、即チ壮ニシテ為スアリ=良い学校を出ると、卒業後に腕を振るえる自由度が大きくなる。 自分が興味をもったものを、毎日毎日少しずつでもいいから勉強していく。この小さな蓄積が定年と同時に花開く。=内発的興味。好きでやったことは、身に着くから忘れもしない。 若いころに強いストレスを脳に与えないと優秀な脳に育たない。 老人だから、余生は静かでのんびりした場所で、というのは間違いで、年をとったからこそ、刺激のある便利なところ、というのが案外正解。 ふるさと=遠きにありて思うもの。 親に財産があれば、遺言に残してほしいから、子は親を大切にする。子供たちは親の気持ちを考えざるを得ない。粗末に扱うことができない。ここに、シニア族にとっての資産の意味がある。こうして、老後、子供たちとのきずなを形成する。 分ける財産のない親へは子供は寄り付かない。そんな親のところへ頻繁に通い、親を大切にするほど、今の子供は道徳的ではない。 子供は親が考えているほど、親思いではない。子を思って狂う親はいても、逆はない。親孝行が忠君愛国と並んで、最高の美独だったが、戦後の占領政策で、戦前のこれらの美独は失われた。そのため、財産の必要性が高まっている。「老いた親の面倒も見られない者は、いかに偉くても、施行者としては世間は見てくれないものだ」という世間は消滅した。 インターネットの情報と読書から得る知識は違う。食物とサプリの関係。 なにも求めずに生きたら、その時点で自分を捨てたと同じ。 群盲象を評す 友達と酒は古いほうがよい。 よき友3つあり、1つはものくれる友、2つは医師、3つは知恵のある友 ダメな友ー思想信条が違う人、支払能力の差、教養の差 楽しいことばかりの、ノッペラボウな人生は、その時は良いかもしれないが、後々の記憶としては薄れがち。でこぼこがあるから、良い記憶として残る。そうした苦労は、人生の手ごたえといえる。いつの間にか年をとって、気がつくと、平たんで、あまり特色のない、鮮烈な記憶のない人生になる。 結婚したばかりは、無理してでも休みを取り、夫婦で何か記憶に残ることをやりなさい。旅行=上記の苦楽を共にする。 リーダーの条件=朗らか、大らか、寛容。
0投稿日: 2014.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の愛読書の選び方や、読書に対する自分への誠実さを大切にする、という部分に共感。 図書館に暮らした話や、本棚・書斎を中心に家を考える所は、読んでいてわくわくした。
1投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ真の意味で知的生活を追求する本である。ここに登場する方々は、あまり生活には困っておらず、自分の思うがままに知的生活を送っていらっしゃる。だからと言って、それを批判する気にもならない。家の床が抜ける程本を買い集める、生涯を通じて規則正しく、思考を極める生活をする、どれも本来人間が追求すべき究極の姿のように思えるからである。私はあと5年以内に人工知能が、人間の知的機能の多くを占めるのではないかと思っている。でも、それは人間が職を失うといった悲観的な話ではなく、答えの分かっている仕事は機会に任せ、答えのない自由な思考、知的思考を可能とする未来ではないかと思っている。そういう意味で、この本に書かれていることはリアリティがあると感じている。
0投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーになったときに、斜め読みしましたが、再読すると、納得する所が多く、何度読み返しても飽きないものが自分とっての古典、なるほどです。
1投稿日: 2013.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知的な生活、それはあこがれるもの。 だけれどもそのためには… お金がかかるのです。 だけれどもそれが出来ない人にも この著書には希望をきちんと与えてくれています。 今は便利になってきたので 一部部分に関しては古いものになってしまいました。 電子書籍やブログでの情報出力があれば さらに知的生活は広まることでしょう。 だけれども調べられるようにするのは大事ですね。 いつでもその生の情報が 振り返られるようにするのは。 まだそれが出来ていないので努力しないと。
1投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ自堕落な生活を送るのではなく、いかにして知的生活を送るか、「本を読む」ことを中心に据え、そのあり方について時間の使い方や本を置く空間にまでもがこの本の中で言及されている。 ある目的(たとえば仕事)のためだけでなく、あくまで自分の人生を充実させるために自然に本を読む、つまり知的生活を送ることが理想の境地。確かに、ただただ仕事のために生きる人に自分は全く魅力を感じないから、渡部氏の主張することには納得。「知的正直」、つまり「わからない」ことを怖れず等身大の学習をせよ、そうすればいずれ然るべき年齢で然るべき教養が身に付いているだろう、ということなんだろう。夏目漱石だって若いうちから理解できるわけない、と。なんだか安心。(少しの背伸びは大切だとは思うが)教養とは簡単なことの積み重ねなのだ。きっと。 ただし途中から、特に最後の方の食事には余計なお世話、という気がしないでもない…正直なところ。嫌味に聞こえる箇所もあり(笑)。
1投稿日: 2013.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ■知的生活の方法 A.知的生活の喜びは、「自己に忠実」であることによってもたらされる。英語で言うところの「知 インテレクチュアル・オネスティ的正直」(わからないのにわかったふりをしないこと)を貫くことが大切である。自己の実感を偽ることは、向上の放棄に他ならない。 B.知的生活を維持する上では、休息、心理学で言う「コウスティング」が重要である。人によってコウスティングの仕方は様々だが、誰にとっても有効なのは安らかな睡眠である。
0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ* 知的生活の方法 - 渡部昇一 [2011-02-13 日 22:40] ** よく分からないのにわかったふりをする子どもは進歩が止まる。知的生活と当てずっぽうは相容れない 英語なら「なんとなく会話ベースで理解してしまう」のと、「一字一句追って意味を理解していく」のでは理解度が雲泥の差になる。 間違いから学ぶ、という言葉にしても、よくよく考えて出した結論であるからこその間違ったときの学び、なのであって、当てずっぽうで導いた結論では「何が間違いなのか?」の理解ですら当てずっぽう、いい加減になっちゃうよ。 ** 知的生活を守る気概と「情理至当」に流れる弱さ 家族が、子どもが、仕事が..十中八九の人は「世間一般からして『もっともらしい』理由」をつけて知的生活を堅持することを諦めてしまう。 問題は量ではなく質と継続性。知的生活のみを探求できる立場でないのなら、蛇口から時折垂れる水滴のように細く、しかし確実で終わりのない営みを目指すべき。 ** 本業に集中するために「お金で時間を買う」という発想 集中、想像、省略..2時間掛かりそうな仕事を集中して1時間で終わらせるための環境にお金をかけたり、想像力を養うため良質の音楽や芸術に触れる機会をもったり、本のメモを取る時間を節約するために本は必ず買う、など。濃い時間を過ごすための工夫をする、という意識 「残された時間をどの程度延ばしたいのか(1時間→2時間なのか、5年→10年なのか)」お金をかける、ということの長期性も意識する ** 使えるものはなんでも使え。 日本の夏にクーラーは必須だ 日本の夏3ヶ月はとても集中して勉強などできない。ヨーロッパ人と比べてあまりに不利。それを補うにはクーラーが不可欠。やれ病気になるだ、麻薬みたいに離れられなくなるだ言わずに使ってみるといい。機密性の高い部屋に住めば冷暖房効率もあがってなおのこといいよね。 イメージ、先入観、伝聞情報で試す前から「批判的な意見を持つ」のは愚の骨頂。少しでも自分の目的のためにメリット、有意なことであるなら真っ白な気持ちで試してみるべき。 ** タイム・リミット 着手前に「〇〇分、◯時間でできなければ諦めて次に進む」を決めておくこと。一日は24時間しかなく、ダラダラと「可否が不明なこと」をやり続けるには時間が足りなさすぎる。 ** 勉強が最大の「時間の無駄」になる場合 学生には許される「重箱の隅をとことんつつく」ような、まさに一字一句辞書を引きながら原典にあたる語学の勉強のような勉強法は、社会人にとっては「最大の時間の無駄、しかも本人が勉強してる気になってるから更にたちが悪い」ということになりかねない。 語学であれば「原典と現代訳の対訳」を使って必要に応じて原典にあたるなど、変なこだわりを持って「最後の2割を埋めに行く」ことを見切る気持ちが大事 ** コウスティング(Coasting) 知的生活のスイッチを短期間完全にオフにする方法 退行、睡眠など、ゆったりと安らいだ状態を作り、知的生活におかれ張り詰めた脳みそを揉みほぐすのはとても大事。方法は睡眠が一番だけど、どんな格好で寝るとか、寝入る時の所作とか、色々と工夫して「Get the most out of every night sleep」を目指す。
1投稿日: 2013.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活ってなんでしょうね。気になります。私もできることなら知的な生活を送ってみたいものです。頭よくなりたいなー(゜p゜)ポヘー 知的生活とは「頭の回転を活発にし、オリジナルな発想を楽しむ生活」のことだそうです。仕事をするうえでも普段生活するうえでも知的生活ができれば今よりも何倍も有意義な毎日を送れそうです。 この本によれば知的生活を送るうえで何よりも大切なことは「わからないのにわかったふりをしない」(=知的正直)ということだそう。自分をごまかし、ズルする人はそれ以上成長できません。「分からない」と言うことが知的生活の第一歩です。しかし、「わからない」と大っぴらに話すことはちょっと勇気もいることですよね。そもそもどこからが「分かった」で、どこからが「分からない」なのかも疑問・・・。 そこで著者は「ぞくぞくするほど分からなければ、分からないのだ」ということを原則としています。読み終わるのがもったいないほど面白い小説ってありますよね。背中がゾクゾクするほど面白くて、時間を忘れて没頭するくらいの。その感覚が著者にとっての「分かる」ということなのだそうです。例えば夏目漱石でも「坊ちゃん」や「こころ」などを読んだだけで分かったとは言いません。時間も食事も忘れて夢中になれるくらいのめり込んではじめて「分かった」ということができるのです。 うーん、ただ「分かった」というだけでも大変な道のり・・・。ともかく、「分かった気になることを怖れる気持ち」を常に頭の中に入れて忘れないことが大切ですね。私も今度からは怖れずに「分からない」を連発していこうと思います。 この本では他にも知的生活を送るためのヒントや方法がたくさん記されています。容易ではありませんが、読んでおいて損はなし。もっと若いときに読んでればよかったと悔やまれます・・・!大学生や社会人になりたての方にオススメの1冊。
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ『知的生活の方法』 渡部昇一 ほんとうはおもしろいと思わないものを、おもしろいなどというふりをしてはいけないのだ。他人に対しても。特に自己をいつわってはならない。自己の実感をいつわることは、向上の放棄にはかなわないのだから。(p36) 自分の価値観を持ち、しっかりと自分で見極める必要がある。それを大切にしなければ、自分は自分でなくなる。 繰り返して読むということの意味はどいうことなのだろうか。それは筋を知っているのにさらに繰り返して読むということであるから、注意が内容の細かい所、おもしろい叙述の仕方にだんだん及んでゆくということになるである。これはおそらく読書の質を高めるための必須の条件といってもよいと思う。(p52) つまり辻原式にいうと、運命を知りながら読むことである。それは神の視点である。 読んだ本の内容というものは忘れるものだ。それは唖然とするほどよく忘れるものだ。ところが多少記憶に残ったり、また物を書いたりするとき、思い出すものもある。(p73) その瞬間は懐かしいものにあったように心躍る。 つまり一般的な知的生活としてものを読む場合は、おっくうになるようなことをしないのが、賢明なのである。(p75) カードシステムについて。読書の最中には何もしないほうが良いといっている。しかし後の処理を考えると、どうだろうか? 本は不思議なものである。買えばよいというものでもないが、買わなければまた駄目なものである。(p77) まさに。身銭を切らなければ、身にならない。蔵書も充実しない。
1投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活を送るためのノウハウ本。ただ、学者や作家?向けかなと思うところが多かったが、いくつか参考になることはあった。でも今の時代にあったこの手のノウハウ本は山とあり、目から鱗というものではなかった。期待し過ぎて読んだだけに、ガッカリ度も大きい。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログどこかの書評でオススメされてたので、図書館で借りた。 20代ほぼ本を読まず薄っぺらい人生だったなと実感、これから様々なジャンルの本を読み知的好奇心を求めていきたい。
1投稿日: 2013.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと古めだが、学者や知的探求者を目指す人々に対するアドバイスをまとめた本。携帯もインターネットも存在しない年代の本なので、(おそらく)我々が最も時間を奪われるであろう、インターネット関連の話が語られていないのは誠に残念だが、基本的な思想は今現在まで通用するものだと思う。 特に、知的探求者たるもの本を絶えず買うべきという姿勢は感銘を受けた。また、本棚に並べられている本は絶えず新陳代謝されるべきで、そうでなければ知的成長は見られない、という主張には、個人的に新しく感じるものがあった。もちろん、本を読んでいない人がいくら本を集めても無駄だとは思うが、その人の本棚を見れば、その人の思考や人格もなんとなく透けて見える時があるので、その主張は面白い。 一読しておくには、面白い本である。ただし古い。
2投稿日: 2012.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり書斎は男の夢。 しかし、一般的なサラリーマンが書斎を持ったからといって本当に知的生活を送るのか、本当に必要なのかと問い詰められると、答えに窮する。 昨今の不況下では、本書に紹介されているような庭付き、書庫付きの家が、一般的なサラリーマンに建てられるのかという状況ではあるが。 (書斎どころか、家を建てることさえ、容易ではない)
0投稿日: 2012.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直、鼻につくことや、???なところも多かった。でも、参考になることも多かった。「金は時なり」には目が鱗だった。全体としての「知的生活」には見習いたいところが多かったので、できるところは見習ってみたい。
1投稿日: 2012.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を買いつづける事は、知的生活者の頭脳にとっては、カイコに桑の葉を与えつづける事に匹敵する p92 (自分への言い訳) カードを作って較べながら考えていれば、偉い学者もその著書の中でいいかげんなことを言っているのに気づくだろう。そこが論文の出発点になる p130
1投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の知的生活をとても羨ましく思った。 知的生活に関して、情報処理・読書については勿論 食事や結婚など内容が多岐に亘っていて、 こんなとこまで言及するかとも思った。
0投稿日: 2012.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的に生きることをここまで考えて抜いている人がいることに感心した. いくつかまねをしたいと思ったが,凡人が中途半端にしてもかっこわるそう. 最後の節にもあるが,自分の能力に応じて知的生活と家庭生活の両立を図るのが良い生き方だと思った.
1投稿日: 2012.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【目的】 ・改善活動を加速するアイディアを見つける。 【結果】 ・ご飯の量を制限する。(とくに夕食)
0投稿日: 2012.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ――――――――――――――――――――――――――――――○ マルクス主義論争には多分に儒学の訓詁学的要素があるらしいのだが、訓詁学はより古い文献、より古い注釈書を持ったものが断然有利なのだ。万一、完全に社会主義国家となれば、このような強力な書庫を私有することは許されず、国家がそれを手に入れるであろう。そして国家や党を相手に論争できる個人も消えるであろう。106 ――――――――――――――――――――――――――――――○ 中断されるおそれがなく、時間はほとんど無限に自分の目の前に広がっていると感ずるとき、知はまことにのびのびと動く。いつ電話がくるかも知れない、などという気持ちが意識下にあるときは、知はその自由な動きをすでに失っているのだ。173 ――――――――――――――――――――――――――――――○ ヴィトゲンシュタインは、ケンブリッジ大学で知力の限りをつくした講義をしたあとは、映画館で三文映画を見ていたという。彼の兄弟には精神病者もいたし彼自身もそれに近い状態にしばしば近づいたように思われるが、それを救っていたのは案外こういう退行だったかも知れないのである。(…)知的ボルテージが高ければ高いほど、退行欲求も十分に満たされなければならないのだ。186 ――――――――――――――――――――――――――――――○
0投稿日: 2012.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今、お金やら何やら、生活のことでいっぱいになっているけれど、知的な思考もするように、努力していかなくちゃなぁと思った あと、記録の仕方も載ってる
0投稿日: 2012.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ繰り返し本を読むことの重要性 本の内容を書き写さない重要性 だけど書き写すやり方とその重要性 世間が評価しても、自分にはつまらん感覚の重要性などなど・・・ 今は趣味として教養として、読みたい本だけをピックアップしている自分にとって、コレでいいんだなーと感じて楽になった。てか本蔵を確保するために、家の設計図まで書くなんて、本に対する情熱ヤバすぎw それぐらい本を愛してるやつじゃないと知的と言えん!と言ってるが、少しわかる気がする。
0投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ効率的に読書・勉強が出来る生活構築の方法論。 内容は読書法、勉強法に始まり、 果ては食生活や結婚生活まで扱っている。 個人的に目から鱗が落ちる思いだったのは、 内容をカードに書く事を非推奨にしている点。 (ただし時間が有って金が無い場合を除く) 私もブクログにせっせと引用を書き込んできたが、 これは書くのも探すのも時間がかかってしまう。 本に付箋でも貼っておけば十分である。
0投稿日: 2012.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ知の向上への不断の努力には、ある種の「退行現象」が副作用としてついてくるということを忘れてはならないという。かの天才哲学者ウィトゲンシュタインもケンブリッジ大で知力の限りをつくした講義をしたあとは、映画館へいって三文映画を見ていたらしい。こうした健康な退行現象をコウスティングという。人間はバランスの生き物なので真面目なことばかり考えていたら歪みが生まれてしまう。だから、上手な息抜きが必要なのである。万人に共通して有効な退行の方法は安らかな睡眠であることはいうまでもない。眠っているあいだに、増大したエントロピーを掃除して、整理しているのだから、睡眠の重要性というのは強調してもしすぎるということはないのである。この他知的巨人たちの生活が書かれているので参考になる。特にカントの生活はあれだけの高齢まで大量の仕事をこなせた理由もむべなるかなと納得するものだった。
0投稿日: 2012.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のすすめるライフスタイルは現代では難しい事柄も多いが、一流の学者になるため、もしくはそれに準じた知的な生活をするためには、ためになると思う。
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者「知的生活」における態度、行動、その徹底ぶりに圧倒された。 勉強、読書に対するモチベーションを刺激されるので、自己啓発として定期的に読み返したい。 (読み返す行為もまた知的生活において重要だそうだ) ----- 引用 【自分をごまかさない精神】 p13 知的正直(intellectural honesty)とは、わからないのにわかったふりをしないということ p30 簡単にわかった気になることを怖れる気持ちは、知的生活に不可欠 p35 おとぎ話だろうが冒険物だろうが、その時に「本当に面白い」と思ったその感じを忘れてはいけない (わからないのにわかったふりをして愛読書は漱石だなどと言っていると本当に理解できるようになる前に漱石を読むのをやめてしまう) p36 自己の実感を偽ることは、向上の放棄に他ならない。 p45 一度基準が立つとおもしろくないときは「これはおもしろくない」と自信を持って放り出すことができるようになった 【古典をつくる】 p65 古典とは何度も何度も読み返され、時代をへているうちに残った本のことである。 p66 「時間の間隔を置いて繰り返し読む」それに耐えられる本や作者にめぐり合ったら、その人自身の古典を発見したことになる。 p67 「あなたの古典」がないならば、あなたは読書家とは考えたくない。まず、2、3年前に読んで面白かったと思う物を読み直してみるとよい。面白かったらとっておき、また来年か再来年読み返してみる。 【本を買う意味】 p72 いつか読んだ本がふと読みたくなることがある。その時に、それが手許にないことは致命的である。 p92 本を買い続けることは、知的生活者の頭脳にとっては、カイコに桑の葉を与えつづけることに匹敵する 【知的生活と時間】 p160 古典を読むときは、英訳対照になっているもので満足しろ、原典を注と辞書で読もうとするな。(時間とエネルギーの空費である) p162 「見切り」をうまく使うことによって大きな効果をあげることができる p183 通勤や通学のための時間は、語学に実によく向いている。 p188 知的生活に成功した人は、本能的に健全な退行、つまりコウスティングをしている。 ダンテを勉強した後で、アガサ・クリスティとなるのはむしろ自然である。 p190 誰に対しても有効なことは、安らかな眠りこそが最も良いコウスティングである。 この退行欲求が満たされることが、知的生活の基礎である。
0投稿日: 2012.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ啓発本というよりはエッセイのようで渡部昇一という人の人柄がかわいらしく、文体も簡潔で読みやすい好著。 ・子供部屋よりまず書斎をつくれ ・家庭生活における諸々が知的生活を相当に妨害する など、少し過激な要約になったけれどこんなことが書き連ねてある痛快な内容。 さらにはこうした思想の元に考え着いた理想の間取りまで(パースも)提示されていてなおおもしろかった。 パラパラとまた気軽にめくりたくなる一冊。
0投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活、それはたとえ研究者や教授など知的職業についていないとしても、毎日本を読み、毎日自分の頭で思索する孤独な時間を持つこと、そしてそれを生活そのものにまで習慣化すること、と定義づけて、いかにしてそんな生活を守るか、を古今東西のさまざまなエピソードを駆使して書いています。一番いいなと感じ、心に留めておきたいと感じたのは「知的正直(インテレクチュアル・オネスティ)という考え方。「わからない」ことを怖れない、わかってもいないことをわかったふりをしない、自分が納得しないものを、世間が面白いというからといって自分も安易になびかない、などなど。「知的生活で生産性を上げて、年収○倍を目指そう!」というような、ありがちな「他者評価を高める」系のノウハウではなくて、「内なる知的生活を死守するために、時にはいかに貧乏に耐え、いかに空間を作り、いかに時間を使い、いかに生業と両立するか」という、とことん「自己充実」の人生哲学であるところが、好ましいです。身銭を切って本を買え、というくだりなども面白い!知的生活にとって結婚と家庭は足かせである、という主張にはさすがに失笑ですけれど。
1投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ131222 精読で再読。この13年やってきたことに近いので少々自信がついた。 110718 速読で再読 110124 TOPPOINT PremiumSelection Vol.2
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほどと思ったところもあるが、 今の時代それは無理だろうということも多々あった。 ただ、この本に書いてあるような生活はしてみたいもんです。
0投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者がどのように、知的生活=読書生活をしてきたかについての本。 空間の使い方、時間の使い方、食事など。 電子書籍の時代に空間の使い方などは古いだろうが、時間の使い方はためになった。自分の好みに合った部分を使えば良いという印象の内容。
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ長年版を重ね続ける名著。筆者の論壇での発言に賛同できない方にも、本書に関してはお薦めです。 知的な生活について考えるためのヒントが満載です。
0投稿日: 2011.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ知的生活を送りたい人へ筆者の経験からアドバイスを書いた本。本は繰り返し読みなさい、本は身銭を切ってでも買いなさいといった感じで書いていることは普通の How to 読書本だった
0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ論文を読み論文を書く人で、しかも都会に住んでいる人で、かつ低血圧の人ならば、夜型の方がよいと断言してもよいと思う。 「毎日、必ず始発電車に乗ることに私は一生の希望を托しているのです。そうでもしなければ、みんなと同じ平凡なことになっちまうからなァ」 知的な活動に従事する時間は、自己実現の時間である。
0投稿日: 2011.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ文句なく五つ星。高校時代に読んで感銘を受け、以後覚えてるだけで七回は読んだ本。知的生活に憧れた。四十を過ぎてまた読みたくなった。フォトリーディング。目次を読んだだけで何が書いてあるか思い出せる。高速リーディング。面白かったが、かつて七回目位で感じた「もう十分」と言う感覚も感じた。
1投稿日: 2011.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ早起きと、毎日の日記と、夕ご飯の量を減らすのは実践したい。 また、暗記の隙間時間の活用の習慣、英語の小説もよもう。
0投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の大切さ、というか素晴らしさというか。。。 すごく本を読みたくなった。 暗記カードの使い方など、現在では使いにくいことも書いているが、 根底としてある、読書のあるべき姿は非常に参考になった。
0投稿日: 2011.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 知的生活とは、頭の回転を活発にし、オリジナルな発想を楽しむ生活である。 日常生活のさわがしさのなかで、自分の時間をつくり、データを整理し、それをオリジナルな発想に結びつけてゆくには、どんな方法が可能か? 読書の技術、カードの使い方、書斎の整え方、散歩の効用、通勤時間の利用法、ワインの飲み方、そして結婚生活……。 本書には、平均的日本人に実現可能な、さまざまなヒントとアイデアが、著書自身の体験を通して、ふんだんに示されている。 知的生活とは、なによりも内面の充実を求める生活なのである。 [ 目次 ] ●自分をごまかさない精神 「わからない」に耐える ●古典をつくる 繰りかえし読む/『半七捕物帳』 ●本を買う意味 身銭を切る/貧乏学生時代 ●知的空間と情報整理 図書館に住む/ファイルボックス ●知的生活の形而下学 ビールとワイン/結婚 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.11.12
