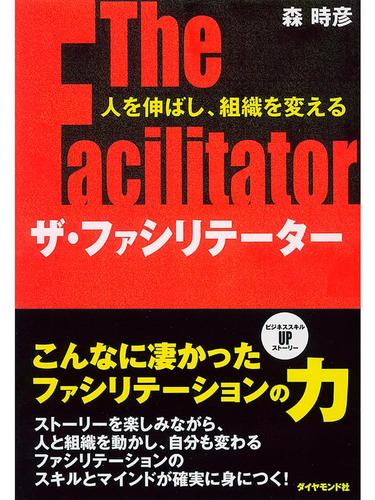
総合評価
(202件)| 79 | ||
| 69 | ||
| 38 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなにより物語形式で面白かった。 スキルが身についたとはとても言えないが、知識としては確実にインプットがあった。 時間もかからずに読めるので、サラリーマンは一度読んでみて損はないと思う。
0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ・小説形式というのがよい。ライブ感があり、読者である自分自身の課題も想起され「自分ならどうやるだろう?」ということを自然に考えさせられた。 ・ファシリテーションのツールというかフレームワークがわかりやすく説明されている。「こんな手法があるのか」とともに「こんな風に使うのか」がセットで描写されているので、非常に分かり味が深い。 ・読後に仄かに自分の中に熱がこもっているのを感じる。 ファシリテーションについて興味があり、読んでみた。 2004年出版と少し古いように思ったが、読んでみて全く色褪せていないと感じた。 日々仕事をしている中で感じているモヤモヤが解消されていくような感覚があり、読書中自分の中に熱を帯びるのを感じた。良著です。長期休暇の前半に読むのがおすすめかも。
0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織を変える力のある人の凄さを感じる本。 1回読んだだけでは身につかないし、理解したとしても実践していかないと全然近づけないだろうな。 こんなリーダーの元で働きたいし、自分も働きながら目標達成のために、自然と議論を進めてチームに相乗効果をもたらしながら進んでいける人になりたい。 会社のMTGでも、今までみんなの頭を整理してしっかり可視化して、全員が同じ認識をしっかり持てたことがなかったのではないかな、と怖くなった。 一緒に働く仲間に自分ごととして危機感を感じさせたり、やる気にさせたり、もっと良くなりたい、とモチベーションを上げさせたり、人をポジティブに変える力を本当に身につけたいと思った。
7投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリー仕立てで進んでいき、その中で具体的なファシリテーションの方法が紹介されていくのでわかりやすかった。 とはいえ、本質的にはファシリテーションの手法をレクチャーするものではなく、ソフトな変革(一人一人の意識や行動が変わること)をどのようにして起こしていくか、ということの重要性をファシリテーションを通して、伝えるという趣旨の内容してた。 とても面白かったです。
0投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公はもともとマーケティングで成果を出して、その能力を買われて、経験のない開発部門の部門長に異動となるところから始まります。 経験がない畑でも、主人公のファシリテーションのスキルで組織に変化をもたらしていくところが面白かったです。 単なるノウハウ本ではなく、小説のようになっているので体系的な知識だけでなく、人の感情の動きがあって、その時どんなテクニックを使うのが良いかという点がとても参考になりました。
0投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語 ストーリー仕立てで、自然に頭に入ってくるので、すぐ読め終えられる。自己啓発本読むより内容充実、実践できる。
1投稿日: 2024.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2004年発行とかなり古い本だが、最近読んだ本で参照してあったので図書館で借りたような。 経緯はともあれ、時代設定は古かれ、人間の本質はあまり変わらないので、組織慣性あるあるの課題に対して、若きビジネスリーダーが如何に立ち向かうか、というこの種の本の定番設定だったので、安心して読めた。 フレームワーク自体は、どこかで聞いたことがあるような、というものが多くて、目から鱗系のネタはないものの、如何に実践するか、という点で参考になる点多々。 主人公のような30代のバイタリティ溢れる女性上司に50代男子が仕えるのも今風でよいかも。
12投稿日: 2023.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は良かったです。 ただ後半に進むにつれ、言いたい本質は理解するものの、現実的にそのやり方はちょっとな感じがしたのと、全体のストーリー、設定も20年代に読むと時代を感じますね。書かれた当時の時代背景を知らない若い人が読んだらどんな印象なんだろう。
0投稿日: 2023.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022-10-01 再読。 やはり、ファシリテーションできそうにない。 遠いところの話として読んだ。 だけど、本物のファシリテーターがいっぱいいたら世の会議は生産的になるのになあ
0投稿日: 2022.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ【概略】 三年前、SCC社の事務機器分野のマーケティング・リーダーとして業績を大きく伸ばした黒澤涼子に、亀井社長より新たなミッションが与えられる。それは開発センターのセンター長。さらには全社での大幅なコストカットと、売上を伸ばすというもの。この大胆で無謀なミッションに挑む黒澤涼子の武器は、ファシリテーション。ファシリタティブ・リーダーとして黒澤涼子は、社員のモチベーションをあげ、ミッション完遂なるか?ストーリーテリングでファシリテーションの有用性を説いた一冊。 2022年08月30日 読了 【書評】 1年半ほど前に先に2を読んだうえでの1。印象としては続編の方が洗練されたように思えるけど、十分にストーリーを楽しめ、同時にファシリテーションとはなんだろう?円滑なファシリテーションのために有効な交通整理の方法とは?というものを紹介してくれているのだよね。 (リアリティが薄いという批判はあるかもだけど)例えば島耕作といったものが好きな人は、小説という意味でも楽しめると思う。ガチガチに肩に力を入れて「ファシリテーションを学ぶんだ!」という感覚じゃなくても、いい。 続編に対する記憶が薄れ、印象というレベルでしかない中で、どうして続編の方が洗練された感じ(没入感?)があるのかなと考えたのだけど、主人公の黒澤涼子が少し薄い(彼女を軸にした描写が少ない印象)なのと、アクが強いキャラクターが少ないってことなのかなと・・・無理矢理な理由探しをしてみた。前者については、「ファシリテーション」という意味でいうと成功なのだよね。剛腕やミラクル連発の主人公だったら、ファシリテーションで一番大事なコトを語れないものね。後者の部分でいうと、渡瀬という人物が登場してるのだけど、この人をもっともっと濃い感じにしてもよかったかもね。作中「渡瀬天皇」なんて描写もあることだし。ただ、やり過ぎるのも難しい。社内の権謀術数といった部分で読者をハラハラドキドキさせるという狙いのものじゃないから、これは。 作中にあった「目隠し道案内」、形態は少し違うけど、経験したことがある。目隠しをして、相手に委ねる側の経験ね。たった少しの間だったけど、まさしく盲目的に誘導してくれる相手を信じるしか、ない感覚、あった。自分が経験したのは、お芝居をやる際のアイスブレイク的な時間帯でのことだったのだけど、いつかどこかでこういうのをやってみたいと思ったものだったよ。またここで会えるとは思わなかった。 続編の書評を書いた時にも触れたけど、ファシリテーション協会の門をたたく時期がきたのかもしれない。
0投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「人と人とのインタラクションを活発にし、創造的なアウトプットを引き出すもの」、「フォーミング、ストーミング、ノーミング、パーフォーミング」、「ストレッチゴール」、「WOW!作り」、「ファシリタティブ・リーダー」、「アイスブレーク集」、「フォース・フィールド・アナリシス」、「チーム名決め」、「コンフォート・ゾーン/ストレッチ・ゾーン/デンジャラス・ゾーン」、「このミッションは感性に訴えるか?」、「バック・オフィスのアウトソース」、「90日以内に実績」、「コントローラブル/アンコントローラブル」
0投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターに必要な素質やスキル・フレームワークについてストーリー形式で書かれているので、小説を読む感覚で学ぶことができる本。一般的な解説ではなく、実際にファシリテーションを行う時にどういう場面でどういうことが必要なのかを頭の中にイメージしやすかった。この本を読んだ後に実践をすることが大切だと思うので、まず会議やmtgの場で少しずつ実践していきたい。
0投稿日: 2022.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれで3回目くらい。 仕事でファシリテートしそうかなってタイミングで読み返している。 何回読んでも思うのは、 ファシリテーターは目的から絶対に目を離さない、間に落ちるボールに意識を向ける、視野を広げたり縮めたり視座を高くしたり低くしたりして自分の位置を変えながら色んな視点で意見を投げかける、無理矢理結論づけず発散と収束を繰り返す、 これらの観点。 また本書の主人公リョウのように、場面によっては自分も意見をどんどん言うファシリタブリーダーになる必要もある。 ファシリテーターをいう役割を初めて教えてくれた本なので、今後も必要な場面で読み返したい。
0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリー仕立てでファシリテートするときのツールや使い所が随所に出てくる感じ。ファシリテーターって色々我慢すべきところもあるのだなぁと思った。むずかしいなぁ。
0投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021/05/21 私は人が好きだ。ファシリテーションはそんな私の武器になる、そう思って購入した一冊である。 内容としては、ある社員がファシリテーションを通じて企業を再生させるフィクションだ。 ファシリテーションの目的は、ものごとを前進させることだと学んだ。その前進を阻害するものは多い。人間関係や予算、慣習など多岐にわたる。みなさんも、そのような課題を前にした経験があるだろう。 そんなときに役立つのがファシリテーションだ。データを活用するのはもちろんのこと、人のポテンシャルを最大限に発揮するための潤滑油として役立つ。本書では役員クラスや若手が、それぞれチームを作り、問題解決を行う。 ファシリテーションは、ただのテクニックではない。マインドの部分も大きい。日本では空気を読むことを頻繁に求められるが、このようなマインドやテクニックを学び、議論をすることも大切だろう。もちろん、大人だけでなく、子供たちにも身につけて欲しいと感じた。
0投稿日: 2021.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターは実践をしてみて、身につくものであるが、それを疑似体験できるような内容なので理解はしやすいと思う。 ブレストとKJ法はベースとなる手段であり、 役割と道具箱を覚えたら、あとは実践あるのみ。 何度もやってトライアンドエラーを繰り返すことがスキルアップと自信につながる。 あとは堂々とやることが大事。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「えっ、私がですか」「君ならやれるよ。いや、開発センターを大きく変えるには君しかいないと思っている。マーケティングを変えたようにね。二年で変えてくれ。 その後は、またマーケティングに戻ってもらうから…」マーケティング部門のリーダーだった黒沢涼子が、畑違いの製品開発センター長に抜擢される。 はたして専門知識面でも、年齢でも自分を上回る男性の部下を率い、組織を変えることができるのか…。 ストーリーを楽しみながら、人と組織を動かし、自分が変わるファシリテーションのスキルとマインドが確実に身につく。 <サマリ> ・1周読んだだけでは難しくて理解できない。2~3周読むと内容が深く理解できる。 1周目:全体を流れるように読んでストーリーを楽しむ 2周目:ストーリーのおさらい+要所で活用されているファシリテーションのフレームワークの概要を抑える 3周目:ファシリテーションのフレームワークのそれぞれについて深く調べて利用イメージを膨らませる ・ストーリーとしては30代後半のマーケティング部署の女性リーダーが、なぜか急に製品開発部署の責任者(本部長?)をやることになったが、 異動先は全員年上の男性かつ一流技術者であり、畑違いの場所に放り込まれハンディキャップありまくりの中で、 ファシリテーターの技術を駆使し、ビジネスリーダーとして活躍、さらには製品開発部署を飛び越え、社長・役員を巻き込んで全社の意識改革をしてしまう。 よくある定番のサクセスストーリーだが、その中でファシリテーションのフレームワークの使い方や実例やその効果を解説している。 ・現場業務よりも数段上のレイヤーである経営課題を解決するために必要な心構え・考え方が濃縮された1冊で、必要なタイミングで都度繰り返し読み直す価値がある。 ・ストーリーで登場したファシリテーションのフレームワーク/用語/手法の一部 ーリーダーズインテグレーション -グループダイナミックス -タックマンモデル -ギブの4つの懸念モデル -ジョハリの窓 -ストレッチゴール -SWOT分析 -作業仮説 -期待と課題のマトリクス -ファシリタティブ・リーダー -アイスブレーク -発言を促す技術 -浮力の原理 -マインドマッピング、発散と収束 -ゴールツリー -グランドルール -フォース・フィールド・アナリシス
0投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターの役割の重要性を物語形式で読めるビジネス書。 色々な手法が出てくるのと、カタカナ横文字が多くて、少し読みづらい。 ファシリテーションの入門書としてはよいのではないかと思います。
0投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションの手法といえば手法だが、すぐに実践できるテクニックというよりは、長期で行う組織再生に寄った本だった。
0投稿日: 2021.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に実践的な手法が散りばめられていて ストーリーも面白いのでとても楽しくて有用だった。 タスクフォース的な動きを、いかに生産性高く行うかが重要だと思うが、 タスクフォース自体はトップが決めたとしても 議論をうまく行うことで、ボトムアップに変化していくのがとても面白かった。 目標を達成する上で、増えるものと減るものを思い浮かべるという手法が面白かった。 堂々巡りになったら可視化して、堂々巡りを見せつけるのが面白かった。
0投稿日: 2020.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテータおよびファシリテイトによって、個人および組織がどのような変化を生むのか? 実践的な話よりもストーリーによって、適材適所にスキルを用いて課題に取り組む方法を紹介。
0投稿日: 2020.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションのやり方を物語風に解説したもの。しかし、ここの物語が無理やりファシリテーション手法と関連づけている感があり、いまいちか。
0投稿日: 2020.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事上ファシリテーションに接する機会はないが、興味があって購入した。 ファシリテーションとはどのようなものかをストーリー仕立てで説明している。 正直言って、ビジネス用語に疎い私は、カタカナ語のオンパレードに「日本語で話してくれ」とひたすら懊悩していた。 ビジネスって、そういうものなのだろうか。 また、様々なファシリテーションのテクニックが披露されているが、ストーリーのような断片的なものではなく、体系的にまとめられたものの方が分かりやすいと感じた。
1投稿日: 2020.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019年9月読了。 会社指定図書。 単なる「ファシリテーター」と「ファシリタティブ・リーダー」は違う。 いや、「単なる」と言ってもファシリテーションは難しいのだけど。 多分後者はファシリテーションをしながら、最後の意思決定は自分がするとかそんな感じだろうか。 衆知を集めないと課題解決はできないので、如何に異なる立場や意見の人もフラットに物を申せるか、それをどうやって吸い上げるか、最後にそれらを統合して納得解が出せるか、リーダーと呼ばれる人(どのジャンルかに限らず)にはその辺りが求められていると思う。
0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ変革のファシリテーションとしてみたときに亀井社長の矜持に惹かれる。行動の変化を誘発するファシリテーションなのかな
0投稿日: 2019.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションを学びたい方に初めに読む本としてお勧めしたい。 ファシリテーションスキルを活用することにより、組織がどう変化するのか、また組織で働く人々がどう変わっていくのか、などが理解できる。物語仕立てになっておりファシリテーションのイメージが付きやすい。 20代の頃に読んだがピンとこなかった。組織の中堅になった今、読んでみると必要なスキルであることが実感できる。
0投稿日: 2019.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ前プロジェクトで成功を収め、開発センター長に昇格出世した主人公が新たなフィールドで成功に至るまで物語を通じて、ビジネスにおける”ファシリテーティング”とはどのようなことかを丁寧に解説している一冊。 自身、悲しくも出世街道からは遠く外れて裏方でコツコツ頑張っている身なので、どうせ使われる側だし~、って感情的に読むのを止めようと思いつつも、結局一通り読み終えました。 ”ファシリテーティング” 組織(メンバー)が目標に対してのあらゆる物事を建設的に”確実に”前進させる為にエスコートしていくこと 本書はカタカナ文字がひたすら多い。マッキンゼーとかじゃあるまいしって本書に出てくる旧態部長さながら心の中で何度かボヤきましたが、具体的なアクションはかなり「なるほどー!」と思えるファシリテーティング例が多かったなと思いました。仕事の難しさ、楽しさ、しんどさ、やりがいって結局”人間関係”による影響が支配的なんだけど、本書は対人関係で生まれる心と頭の緊張をほどく具体的アクションがいっぱい盛り込まれてて、著者はプロだなって思いました。 ボール投げの話とか、アイスブレークとか、新しいアイデアを知れたし、「もっと金を稼げるようになりたい!」というモチベーションのもと、もっと多くのビジネス書を読んで多くのビジネスTIPSを習得するのも意外とありだなって思いました。
0投稿日: 2019.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みにくい。ファシリテーターを知っている人は頭に入ってくるのだろうが、知らない方は何をすればいいのかと思う。小説と捉えれば良いのかもしれない。 「えっ、私がですか」「君ならやれるよ。いや、開発センターを大きく変えるには君しかいないと思っている。マーケティングを変えたようにね。二年で変えてくれ。その後は、またマーケティングに戻ってもらうから…」マーケティング部門のリーダーだった黒沢涼子が、畑違いの製品開発センター長に抜擢される。はたして専門知識面でも、年齢でも自分を上回る男性の部下を率い、組織を変えることができるのか…。ストーリーを楽しみながら、人と組織を動かし、自分が変わるファシリテーションのスキルとマインドが確実に身につく。
0投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ女性リーダーが畑違いの製品開発センター長に。物語調にファシリテートで組織がよくなる様が描かれていて分かりやすい
0投稿日: 2019.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログとても勉強になった。 これを、日々のソフトウェア開発の中にどう活かしていくかが、自分のミッションと感じる。 2も楽しみだ。
0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ人を動かすためにはどうしたらいいのか。 ビジネスのリアルな現場において、ストーリー形式で数々のテクニックが語られる。自分がリーダーとなるとき、マネージャーとなるときの、理想的なイメージが掴める本。 ややカタカナの概念やフレームワークが多いので、そのまま現場には持ち込めない。ある程度こちらで噛み砕きながら、現場に合わせて輸入する必要があるだろう *ファシリテーターとは触媒のようなもの
0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターの持つ可能性を広げてくれた本。ビジネスの現場での活用ノウハウにあふれた良書。腰を据えて学びたいもののひとつになった。
0投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテータ気になるけど、本を読むのが苦手な人に進める小説立て。 導入にはもってこい。ビジネスに興味がある人なら小説としても楽しめる。
0投稿日: 2018.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログアマゾンの読者レビューの評価が高かったのと,今の仕事でのプロジェクトで何かヒントがあるかもと思い購入してみた。 ファシリテーションのエッセンスが小説仕立で上手く解説されており,読んでいてアキる事はなかった。日本の会社を舞台に,企業変革や危機への対応などのリアリティあるストーリーはケーススタディとして,場面場面で異なる議論の方向性とそれをコントロールするための手法を分かりやすく提示している。上級職の変革への抵抗や感情的な反発などといった,現実にもありがちな要素も盛り込まれており思わず自分の境遇に照らし合わせてしまう。ストーリーはあくまでも,ファシリテーションの手法を提示するために書かれているため,現実の世界がこのように進むわけではないことは無いのは当然である。読み手としては,この本で提示された様々な手法を場面に応じて臨機応変に使い分け,自分のやり方に落とし込むことが必要なのは言うまでも無い。特に,ファシリテーションの道具箱としてまとめられているページは今後も何度と無く参考にすることだろう。 ファシリテーターとなるべき人間は,場面に応じた機転の利く受け答えが求められる。そうしたスキルは,ファシリテーターである以前に,ビジネスに対する日ごろの問題意識とそれに対する自分なりの考えを常に持っていることによって磨かれるものであろう。いくら,ファシリテーションの手法を知っていても,総合的な知識とコミュニケーション能力がなければ意味が無いのは肝に銘じておかなければいけませんね。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.目的 ファシリテーターのあり方を知る 2.得られたこと 最近話題となっている働き方改革、組織の不正問題、企業買収など、てんこ盛りの内容を敏腕女性ファシリテーターが変革を起こしていく様が圧巻。もう、スカッとします! 3.アイデア 会議シミュレーションの題材にしたい。
0投稿日: 2018.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前に参加したファシリテーター講座でおすすめされていた本。 仕事をしていると、謎な会議、会議のための会議にちょくちょく参加することになる。そんなときには結局この会議の目的ってなんでしたっけ?と聞いてしまうような人間ではあるものの、会議を生産的な方向に転がしていく方法論は全くわからず状態だった。 この本ではファシリテーションを「人と人との相互作用を活発にして、創造的なアクションへつなげる」と定義づけ、スーパーウーマン的なファシリテーティブリーダーを主人公にある会社の変革を描く物語形式で進行する。 そもそもファシリテーションが会議の進行だと思っていたくらいなので、この本に出てくるファシリテーションモデルはほぼ初耳。それでもこういうことあるよね〜と生臭いところにも触れながら読み進めることができる。 こんな大胆な変革ができなくても、一個の会議を生産的にする一個のアクション・発言はすることができる。楽しい仕事はなかなかないけど、自分達が置かれている状況を把握し、コントロールできること、行動を起こせることをはっきりさせることはできる。 折に触れて読み返す本になると思う。
0投稿日: 2018.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログリョウが任された組織変革。 その中で"ファシリテーター"としてのスキルを存分に発揮していく。 ストーリー仕立てでとても読みやすく、勉強になった!!
0投稿日: 2018.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ意見が行き詰まり答えが出そうにない会議、話が行ったり来たりする会議、みんなが違うベクトルからモノを言っていると感じる会議、、、 数え切れないほど参加者が迷子になっている会議がこの世に存在する。というか、世の中の会議はほとんどそうだろう。 ある程度リテラシーが似通った人たちが集まる会議、バックグラウンドが明らかに違う人たちが集まる会議、、、その時々でうまく立ち回りつつ、一つの目的を共有して仕事をしていく必要がある。 ある時、行き詰まった会議で自身が問いかけた質問で会議が動いた時に、ファシリテーションの重要性を感じたため、学び始めました。まず導入にこちら。 リーダーで且つプレーヤーの時に、どういう風にミーティングをファシリするのがいいのか、と一瞬悩んでたときにちょうどこの本を読み、ファシリタティブリーダーという立ち位置もアリだと気付きました。
0投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファシリテートって聞いたことあるけど、具体的には?? と思い手に取った一冊。 ストーリー仕立て(三枝匠著書 『V字回復の経営』を彷彿とさせる)でわかりやすくファシリテーターの効能がまとめられていた。 ・アイスブレイクの重要性 ・5W1Hを意識させる問い掛け ・部分最適ではなく全体最適の考えを促す ・逆接的な質問 など参考になる点は目白押しだった。 一方でストーリーとしては、途中からファシリテーターと言うより事業立て直しのコンサルタントとしての面が強くなり期待と違う方向へ。ゆえに星は3つ。
0投稿日: 2017.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションの基本が物語形式で学べる。 今の仕事柄、一番必要なスキル。 この本を何年かけても自分のものにしなくては。
0投稿日: 2017.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターとは何か、とか、ファシリテーションのコツ、とか、いくつか本を読んだり実際にやったりもしていたけど、この本がいちばん分かりやすくて読みやすくて面白かった。 とある会社の組織変革のストーリーが、ファシリテーションのスキルをベースに描かれていて、具体的にイメージできるのがとても良い。 ある程度能力のある人がいることは前提だろうけど、性善説で考えれば、会社を悪くしたいと思っている人はいないわけで。でも、それぞれが目指す方向性を共有し、目標の達成に向けてチャレンジしていこうというか気風があり、そのプロセスに納得が出来ているか、そんな土壌が整っているのかが、組織のパフォーマンスを決めるのだということが、よくよく感じられた。 それが個人の働きがいにもつながるのだろうし、ファシリテーター的な動きが出来るように、そして周りもそうなれるようにしていきたい。
0投稿日: 2017.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログfacilitate、ファシリテートという単語には、「促進する」という意味がある。会議のファシリテーターという言い方をすれば、従って、それは、「議論を促進する人」というくらいの意味があり、実際の場面でもそういう使われ方をすることが多いように感じる。 が、この本での「ファシリテーター」という言葉の意味は、「思考を促進する」「良いアイデアを生み出すことを促進する、促す」、更には「仕事そのもの(この本では、それは「変革」と言っても良い」を促進するという大きな意味が含まれている。 それは、考え方でもあり、方法論・スキルでもある。
0投稿日: 2016.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファシリテートの技術を小説にして説明している感じ あまり現実味が無い気がする たぶん、自分はそれほどファシリテーションについて詳しくないからかも ファシリテーションについて少しでも知っている、経験があるという人なら上手く使えるのかも知れない
0投稿日: 2016.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーとしては大企業チックなところが多いけど、チーム仕事をする人全般に通ずる大事なことが書いてあると思います
0投稿日: 2016.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションを通じて組織改革を行う物語。 とても面白かったです。 ファシリテーターは会議を効率よくまわす人と思っていました。本書ではファシリテーションスキルを活用し、人を動かし、組織改革を行う物語となっています。 前半は製品開発センターの組織改革、そして物語の後半は会社の組織改革といった構成です。 物語的に面白いのは、主人公の女性が会社の組織改革のファシリテーションで十分な結果を出せないこと。順風満帆にいかないところがリアルさをかもし出しています。そんなところから、スキルが云々ということではなく、まさに自分がその組織の中で会議や組織改革に参加してるリアル感を感じられます。 組織改革というと日産の話を思い出します。そのときの話は、クロスファンクションチームCFTを作ってとかいった何をしたというWHATがメインな感じがしますが、本書では、それをどのように導き出したかといったHOWの部分が語られているイメージです。 ファシリタティブなリーダシップを発揮して、どのようにして人を動機付け、問題を見える化し、行動に落としこんでいくか、そしてそれを続けるかということが、物語を通して、わかりやすく具体的に書かれています。 なので、この物語で最終的に導き出されている改革のアイデアは正直いまいちな感じがしますが(笑)、それを導き出す過程がとても参考になります。 本書ではファシリテーション含めて、さまざまなスキルが出てきます。残念ながらすべて覚えきれません..(笑)。216ページにファシリテーションの道具箱としてまとめられています。 しかし、所詮はツール。そのツールを使ってどうするかがポイント。そのツールを使ってアウトプットを出すことが重要です。それをファシリタティブなリーダとして、定義しています。 ぐいぐい引っ張っていくようなリーダをディレクティブリーダ、意見を引き出し、よく聴き、触発してチームを引っ張っていくリーダをファシリタティブリーダとしています。 ファシリタティブリーダ、あこがれます。格好いい! #いや、主人公が女性だから影響を受けているわけじゃなくて とてもお勧め。
1投稿日: 2016.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログプロジェクト運営や社内外のコミュニケーションに共通する「人を動かす」という点について学べる要素があると期待し、読み進めた。 ファシリティブ・リーダーが組織を変革していく様を通して、ファシリテーションの狙い・効用・手法を改めて理解することができ、関係者全員に読んでほしいと感じた。小説風に描かれており、また様々な立場の人間が登場することで、社内で似たような立場の登場人物に自分を置き換えてみたり、気持ちの変化も感じ取りやすく、実践したくなる内容であった。 読み終わっての感想は下記。 ・仕事は決して1人で完結できるものではないという理解のもと、いかに一緒に働く関係者を巻き込んで、各々が様々な状況下において主体的に思考し、前向きに問題解決していけるようにチームを導くかの方法論とその狙いが理解でき、実践してみたくなる。 ・議論を成果につなげるためには、発散→収束のプロセスを経ること。そこに導く手法としてもファシリテーションが有効である。 ・ファシリテーションはあくまで道具である。ファシリテーションを用いて、チームをリードし、成果を上げるのがファシリティブ・リーダー。反対に、自らぐいぐい引っ張っていくディレクティブ・リーダーと呼ぶ。 ・ファシリテーションを用いてチームが活気づいても、継続させなければ意味はない。継続させることはリーダーの仕事。そのために90日以内に小さな成功でも良いので、ひとつこだわってやり切ることと、その評価を大々的に行い、成功体験を積めるようにする。 ・MTGにワークアウトを取り入れたい。ワークアウトの狙いと効果を要約すると5点。 ⑴ひたすらストレッチする ⑵システムシンキングを育てる ⑶既成概念にとらわれない水平思考を促す ⑷本当の権限委譲と説明責任を生み出す ⑸短サイクルでの変革と素早い意思決定を手にする
0投稿日: 2016.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ二分割法 真ん中に線を引いて、「賛成意見/反対意見」「Controlable/un-controlable」にわける。
0投稿日: 2016.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーター 論理思考は独創的でセクシー 与えられた目標に対して、より高い自己目標を掲げなくては初期目標を達成できない。達成せずできなかった理由を探すだけ。 …ストレッチゴール! 大きな枠の目標から小さな個々の目標に。 論理の構造化して可視化する。 二次元思考。言葉だけでは難しい二つの軸を同時に考えること。xとy 質問の引き出しを持つ。1全体を意識させる質問。多様性を意識させる質問。自分たちがコントロールできるものとできないものを意識させる質問、時間軸を意識させる質問。基準を意識させる質問。 1自分の役割だけでなく、それがシステム全体でどういう役割を果たしているかを考えさせる質問。 ex目標を頭に、それを達成させるツリーをつくる。逆に自分たちが目標だと思っているものは何かの手段ではないかとツリーを遡って書いてみる。 2平均でなく分散値をみる。いつもそうですか? アウトオブボックスシンキング! more or less. 将来の姿をイメージしてビジョン作りなどをする時に使われるファシリ。 プロセスマッピング ものや情報の流れをブロック図にする フォースフィールドアナリシス 現状と夢のgapを生んでいる力を書き出す。 KJ法?同様のものをわけるの?? コンフォートゾーンからストレッチゾーンにメンバーを引き出す。チャレンジの心を呼び覚ます エグゼキューションにおけるファシリテーションのポイントは、目標をノルマと感じさせず、チャレンジの対象と思わせ続けること。目標を達成し、さ、にそれをこえることに燃える雰囲気を作り続けること。 左右に、賛成意見と反対意見、や、コントローラブル・アンコントローラブルを書いた上で自分んのいけんをいう
0投稿日: 2015.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに再読。 現実はこんなにうまく進まんし、所々日本語の使い方が気になったけど、教科書として使えるかな。
0投稿日: 2015.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターという言葉だけは知っていたけれど、キチンと勉強した事がなかったので、概略だけでも知っておこうと読んでみました。 本を読む前は会議を促進させる役割だと思っていたのですが、個人の意識改革をさせることもできるんだなと感じました。
0投稿日: 2015.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説形式でファシリテーションに関連する理論や手法について解説されていて、興味深い。 小説形式と言えばTOCのザ・ゴールが思い出される。あの本でTOCにハマったので、どうやら自分は小説形式が興味を持ちやすいらしい。 ファシリテーションの手法としては、既に幾つかの書籍で読んでいたTOC思考プロセスのツリーやシステム思考のループ図と類似の手法が有ったのでイメージがしやすいものがあった一方で、グループダイナミクス等知らなかった概念もあり、勉強になった。 しかし手法が多岐にわたるため、実践を通さないと身に付いてはいかない気がする。 小説形式なので、手法を体系的に学ぶのには向かないが、そちらは本文中に参考文献として幾つか示されている。
0投稿日: 2015.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションについての小説。ザ・ゴールの様な形式で架空の大手企業の組織変革をファシリテーションを使いこなすバリバリのキャリアウーマンが率いていくというストーリー。脳内イメージでは髪を後ろで縛った長谷川京子という感じ。 ファシリテーションとは何か?本書の中でも当然ながら度々触れられう質問ではあるが、それを一言で言い表すような副題たる言葉は出てこない。その都度によってファシリテーションが成している事を説明するにとどまっている。 ただ一貫して主張、説明されているのはファシリテーションによってチームの問題解決のスピードと質を圧倒的に上げているという点だ。この事から個人的に考えるファシリテーションとは、チームが問題解決に取り組み実施するスピードと質を上げる技術と理解している。 そしてこの技術は企業だけではなくチームで問題解決に取り組む場面であればどこでも利用出来るのが特徴的だ。学校のスポーツサークル、趣味のバンド活動、もっと飛ぶならば友人と企画する海外旅行でも使えるだろう。 本書でもそれとなく何度か提言されているが、この手の技術は是非学校教育のレベルで組み込んで欲しいと思う。現代においても個人で圧倒的に成果を出す人間が居ない事は無いが、多くの場合はチームで成果を出す場面だろう。チームは単なる協調性や空気を読む感覚だけでは活動しない。行動心理学を基礎とした論理的な対応が求められる。
0投稿日: 2015.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想は以下。 http://masterka.seesaa.net/article/417559176.html#more
0投稿日: 2015.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ学び ①出来ることに集中し、さっさと決め、アクションを起こす ②会議を整理する方法 ホワイトボードを左右に分け、 左:賛成意見/コントローラブルなこと 右:反対意見/アンコントローラブルなこと を書いて意見を可視化する ③フォース・フィールド・アナリシス 目標/ミッションに対して妨げになっている「事象」ではなく、その「事象をつくりだしている"力"」はなにかを考える アクション ①自分が今何が出来て/何が出来ないのかを整理(→今週土日)、出来るに該当するものは、とにかくやる、先輩から奪う ②そのまま実行 ③自分の理想(目標達成時、半年後、サブアシ卒業まで)についてこのアナリシスを行う→今週土日
0投稿日: 2015.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
速読意識して120分 340ページ超だから3p/分 まあよし 漫画でわかる、、、タイプよりも文字だけの方がいい。 どうせ漫画でわかるタイプも頻繁に文字で説明するからな。 この手のことの基本を何となくナメるには、いいかな。 ITパスポート参考書を読んでも同じ気もするが。
0投稿日: 2015.04.10頭に入ってきやすい
全体として順調すぎる部分はあるものの、勉強スタイルではなく ストーリーなので、頭に入ってきやすい。 ファシリテーションのツールも色々あるものの、変革を導くメンバーの気持ちをいかに 奮い起こせるかが重要なポイントとなっている事で、共感しやすいのだと思う。 一点、具体的に逆境を乗り越えるための対応について、気持ちのもっていきかた等 もう少し具体的に話が展開されると、より良かったなと思う。
0投稿日: 2015.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリー仕立てで、上手くファシリテーターの役割を説明していてわかりやすい。とはいえ、トップマネジメントのサポートがない状態では提案できても実行できないという状況もあるだろう。ダイナミックな変革を起こすにはある程度環境が整っていないと難しいか。スピード感を持って課題を解決していく手法として参考にしたい。
0投稿日: 2015.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログきれいにまとまって、要所を押さえてあるけど、 読書後あまり印象に残ったことがなかった。 ストーリーも淡々とした感じで、意外性がなかった。
0投稿日: 2015.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常におもしろい ある組織が変革していく物語なのであるが、散りばめられたスキルそして考え方、ファシリテーションの奥深さを改めた知る一冊となった。 強いて言うなら 三枝さんの「V字回復の経営」に似ているが、「V字回復の経営」が志をターゲットに展開していくところからすると、この本はどちらかと言うとファシリテーションのスキルを有効に利用したリーダー像とは?を示したような作りとなっている。 だからこそ、非常に参考にし易いとも感じた。 古本屋で出会ったてから、読み終えるまで早かった。 2が出ていることがわかったので、速攻でamazonでポチってしまった。
0投稿日: 2014.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションとは、 「人と人のインタラクション(相互作用)を活発にし、創造的なアウトプットを引き出すもの」
0投稿日: 2014.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションって会議進行を円滑にする司会者の専門スキルと思っていました。組織変革やPJ等でも使えるスキルであることが良くわかった。トップ上層部の言いなりで納得ないままの施策は会社は良くとも働く人にとっては痛みを伴う。ファシリティブリーダーでは皆が一体感もって共通する目標に向かう、納得と説得ができることがわかった。 ザ・ファシリテーター 70 ジョハリの窓 対人関係における気づきの図解モデル フィードバックと自己開示 214 タックマンモデル 組織は、形成(フォーミング)された後、すぐに機能(パフォーミング)しはじめるのではなく、その前にストーミング(混乱・対立)があり、ノーミング(統一)が進んではじめて機能しはじめる 302 内発的な動機付け エグゼキューションにおけるファシリテーションのポイントは、目標をノルマと感じさせず、チャレンジの対象と思わせ続けること
0投稿日: 2014.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み物として非常に面白いです。 そして、設定がとてもリアルで、会社員として働く人にとっては自分の身の回りのことのように感じることができます。その分、この作品の中で起こる変化が、自分たちにも実現可能なのではないかと思わせてくれます。 「ご都合主義」「うまく行き過ぎ」という批判が想定されます。 しかし本書は小説の形式をとっているものの、文学作品ではないので、説明しようとしている手法が成功裏に進まなければ意味がないと思うのです。 ファシリテーションを、体系的・網羅的に解説しているわけではないですが入口としては、大変有益で面白い一冊ではないかと思います。
0投稿日: 2014.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織をへんかくするのは、リーダーではなく、数いるメンバーである。 そのメンバーが、全員、共通の目標に向かって、自分が行うべきことを自覚し、行動するように、ファシリテートする。 リーダーとして、HOWではなくWHATや、与えられた目標よりも高い目標を掲げなくては目標を達成できない、給与を払ってくれるのは顧客という記述には同感。 また言葉に対して、言葉をボールに見たてて会話すること、言葉は人によって伝わり方は千差万別であることなど、改めて納得することも多かった。 人はいつの間にかコンフォートゾーンに居座ってしまう。常にストレッチゾーンにいられるように取り組んで行こう。
0投稿日: 2014.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな会議の進め方をしたい、という明確なビジョン(というかもはや夢)をもてるようになる本、だと思う。ノウハウなどは他のハウツー本のほうが充実している印象。
0投稿日: 2014.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語形式で読みやすいのだが、そういう本の欠点は理論的な部分が最終的にあまり残らないところ(まぁ、そういう本に限らないのですけど…)。この本も然り。
0投稿日: 2014.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ値段が高い割には、実践力として身につきそうな感じはしなかったので、時間が経ってからもう一度読み返してみる
0投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションで会社の様々な問題を解決していく話。気になるのは主人公があまりファシリテーションを行わなかったこと。
0投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本には「実際、問題がぶつかった時にどう解決するか」といったことが贅沢に盛り込まれています。思考ツールを使って解決したり、喧嘩腰や弱気の議論を良い方向に転換させたり、視野を広げさせる等・・。あらゆる問題に対して、適切な解決方法を実行していきます。全てを実践で活かすことは難しいかもしれませんが、それもやるかやらないかだと思います。
0投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリー式の中にファシリテーション技術を詰め込んだ本。物語としては面白いが、細かくノウハウが書かれているわけではないので、細かく一から教えてほしい、という人にはむかないかも。 ただ、話の流れの中に技術がもりこまれているため、イメージは掴みやすいかもしれない。
0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーの中にファシリテーションの技術の解説やテクニックが入れられているので理解はしやすいが、見返そうと思った時にまとまっていないので一度まとめなければ細かなところは身に付かないと感じた。
0投稿日: 2014.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説仕立てになっており一気に読んだ。 ファシリテーションのポイントを学べる本。 ・組織は形成(フォーミング)されたあと、ストーミング(混乱)があり、ノーミング(統一)が進み、パフォーミング(機能)するという。往々にして会議はだらだらしがちだが、うまくファシリテートできれば、統一に向かうはず。 ・ジョハリの窓。学生時代に教えられ、以降忘れていた。お互いが分かっていることを広げていくこと。 ・ファシリテーションとは、人を触発して、クリエーティブなアイディアを生む。動機づけ、行動を変えるもの。 さて、これらを実践できるかが大事。
0投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションの重要性を物語の中に組み込み紹介。 自分に大きく欠けている能力だと思いました。 ファシリテーションとは周りを巻き込み進行していく力、ひっぱるリーダーシップではなく、巻き込み型リーダーシップだなと思いました。 物語風になっているので、ファシリテーション技術だけではなく、自己啓発にもなりました。
0投稿日: 2014.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターの効果を小説風に紹介 ファシリテーターは触媒のようなもの。ものごとをスムーズに上手く進めるために存在する進行役。組織を活性化させるための重要なツール。 小説風と言いつつ、物語が普通に面白かった。ファシリテーターとしてのツールの紹介や使うタイミングを丁寧に説明しており分かり易かった。 こんな風に組織が活性化されたら凄いと思う。受け身ではなく全員が主体的に動ける組織。
0投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ電子書籍で読みました。 ファシリテートを、ストーリー仕立てで書かれていることで、とてもわかりやすいですが、、、、こんなにうまくいくといいな‐‐‐という感じです。 結局は、このエッセンスを何度も繰り返し使うことで、身につくことだと思います。
0投稿日: 2014.01.05「ザ ゴール」のついで買い
2011/6/28読了。 親友にすすめられた「ザ ゴール」を 買いに言った際、隣に並んでいた本でついつい同時購入。 こういうビジネス小説は、かなり食いついてしまう。 前半戦とか、涙腺が弱いのか目頭熱くなる始末。 こんなドラマチックでなくていいから チームを活性化させる力を養いたいと思う。
0投稿日: 2013.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディオブックにて読了。 リアリティのあるストーリーでファシリテーションの凄さを感じることのできる著書でした。 ただ、これを読んだだけで同じようにファシリテーターとして動けるか、と問われると、出来ないです。頭の中に体系的にまとまっていないためですが、それは別のファシリテーターの道具箱という著書などで整理する必要があります。
0投稿日: 2013.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・初対面の人達に混ざり合うスキル その人の知っていること、知りたいことを本人の居ない場で議論する ・ギブの提唱した4つの懸念モデル 他人との関係に置いて、人は自分の心身を守るために、ある程度防衛的な関係を築こうとする。この4つの懸念を解消して行くことにより、グループは成長する。 ・ジョハリの窓 フィードバックと自己開示によって解放領域が広がり、信頼関係を築きやすい ・SWOT分析 機会と脅威、強み弱みに分類してマトリクスにすることでいかにマネジメントするかを考える ・ゴールツリー 大目標を起点にそれを達成するための中小目標を枝分かれさせながらツリー状に書いて行くしくみ ・循環する理論 論点を円上に書き出し、堂々巡りの構造を可視化することで今出来るコットに集中させる。 ・二分割法 賛否・メリットデメリットを整理し、書き出すことで建設的な話をする手法 ・人を変えるのは前向きな気持ち
0投稿日: 2013.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス小説、サクセスストーリー。 ファシリテーターにはいろんなスキルが必要だが、最終的本質的には人間力。利他でないと成功はない。 組織はその中で働くソフト(社員)がすべて。どのように働きかけ動機づけし変えていくかが鍵。現実はそんなに甘くないが実践してみる価値あり。 いくらいい戦略やプランを立てても、叱咤しても、社員がその気になって、日々の行動を変えなければ組織は変わらない。195 ファシリテーターたちは、チームが達成すべき目的からを離さない。その上で、人と人とのインタラクションに着目している。333
0投稿日: 2013.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションで会社が変わる。これは、フィクションだけれどトップの意思次第で現実に、なるのでは?と思わせられた。ファシリテーションのスキルや効果的な使い方を具体的に学ぶにも良い本だと思う。
0投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ改革をファシリテーションする方法が、フィクションの物語の中で具体例と共に書かれている。読み物としても面白いし、ファシリテーションの勉強にもなる非常に優れた書籍と思う。プロジェクトのファシリテーションを通してメンバーの意識が変わり成長していく姿は感動した。
0投稿日: 2013.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションスキルは、単なる会議の司会だけではなく、組織を動かす際に用いられ効果を発揮することもある。フィクションでありこんなにうまくいかないよと思いつつ、それでも面白く読めた。
0投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通りファシリテーションに特化したビジネス小説。改革が迫られている会社の中で、改革を求めない社員を巻き込みながらどう会社を変えていくか、そこで使われる様々なファシリテーションのスキルとその効果、注意点を読みながら理解できます。ビジネスマンに必須のスキル、身につけるために必読です。
0投稿日: 2013.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファシリテーターというものに非常に興味を持っている。 一方で、本当に効果があるのか?という猜疑心も持っている。 ファシリが研修参加者より圧倒的に上の立場、または実力で上と認められている場合、参加者が自ら参加している場合は、効果を発揮すると確信を持つ。もちろん、ファシリの力量は一定以上あったという前提の上で。 ただ、年下、ポジション的に目下、分野によっては参加者の方が上の場合など、どのくらいの効果を発揮するのだろうか? もろサクセスストーリーとして描かれている本書だが、参加者の素直さに助けられている気がしてならない。そんなにうまくいかねーよ、とどうしても思ってしまう。フィクションなんだからしょうがないじゃん、って自分もいるけど。 フレームワークやファシリの道具箱的なものは身につけておくとそれだけで大きな進歩のような木もする。
0投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて本格的に読んだ、ファシリテーションの本。仕事に取り入れたいなぁ。 ストーリーの中で、ファシリテーションが実際の業務にどうやって盛り込めるのかを想像することができるし、参考文献というか、ところどころに関連書の情報が盛り込まれているので、厚みはありますが、入門書としてお薦めです。
0投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ザ・ファシリテーターは、ダイヤモンド社の本で、エリヤフ・ゴールドラット博士の「ザ・ゴール」シリーズと同じ様な装丁です。 内容も、ビジネス小説を楽しみながら、ファシリテーションが理解できるという狙いです。 著者は、森 時彦さんという方なので、舞台は、日本の会社で、マーケティング部門のリーダーだった黒澤涼子(リョウ)が、開発センター長に抜擢されるところから始まります。 実は、この辺が、どんくさい?感じがして買うのを躊躇していたのですが、内容は、なかなかリアリティがあるし、ファシリテーションのスキルが、これからのリーダーには欠かせない資質であることが良くわかります。 さて、リョウは、自分よりも年上で、技術者として優秀な10名の室長を部下にして、社長から与えられたミッションをどのように達成するのでしょうか? 厚みは、約25mm(あとがきを入れて353ページ)ですが、小説仕立てなので、読みやすく、大切なことはしっかり押さえられており、しかも、例が載っているので、理解しやすいです。ジョハリの窓など、心理学的な面も抜かりなく紹介されており、応用も効きそうです。
0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ電子ブックで読了。初の海外出張で打ち合わせをすることになったのと、先日受けた社外研修の講師の名刺がファシリテータとなっていて、ピンと来たので。 詳細な感想は別途。小説仕立てでとても読みやすい。ザゴールとかが好きなひとはピンと来るんじゃないかな?
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーターのスキルを広めるという目的のために、小説にそれを埋め込む、というスタイルは、新しいと思った。 小説に埋め込むことによる以下のようなメリットを感じた。 1) 情報の羅列でなくそれらが有機的に結びついているので、印象に残りやすい 2) "ありがち"なキャラクターを持った登場人物がそれぞれに合ったタイプのファシリテーションを見せてくれるので、自分にはどのようなファシリテーションが向いているか考えやすい 3) プロジェクトを進める上で"ありがち"な問題が何パターンも具体的に描かれているので、実際に自分が直面する困難と照らし合わせやすい ストーリーに抑揚があるので、純粋に小説としても楽しめると思う。
0投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織を前向きに変革していく具体的な手法が散りばめられた小説。 大変面白く読めると同時に、なるほど!と唸るようなアイデアが満載で、時間を忘れて読んだ。 ここで出てくるファシリテーションの技法は、ぜひ実際に使ってみたい。
0投稿日: 2013.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
相手が変えられることを伝え続けることが重要。 ベストプラクティスの共有 通常平均値に引っ張られやすいが、分散をきいてあげたりし、コントローラぶるな議論にもっていく 積み上げ式ではなく、広い視野から目標設定を行う事 プロセスマッピング バリューチェーンを再構築する。 目標をノルマではなく、チャレンジの対象とすること 内発的な動機付けを大事にすること ダッシュボードメトリクス
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ買います! 図書館で借りたけど間違いなく買います。これ、ビジネスマン必要なツールがいくつか上がっていて、今後使いながら振り返る本として手元においておいたほうが良い本です。 いろいろなフレームワークはありますが、フォースフィールドアナリシスやパーキングエリアなど、僕の不勉強で追いつけてなかった概念もたくさん。 使って悩んで読み返して、という使い方が良い本です。道具そろえに極めてお勧め本です!!
0投稿日: 2013.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションについてノウハウ、効果、進め方を分かりやすくフィクションにしたもの。マーケティング部を立て直したリョウが研究開発センターを任される。
0投稿日: 2013.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディオブックで読了。日本のどこの会社も、もっとファシリテーションのスキルをつけて、仕事を行えば、きっと効率的にビジネスやアウトプットが得られる気がした。 ファシリテーションをする上で、重要ないくつかのフレームワークが出て来た。実践で使えるようにしていきたい。
0投稿日: 2013.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログメーカーの企業改革のフィクションを通して、ファシリテーションのアウトライン、諸々のスキル、そしてTipsを教えてくれる名著。
0投稿日: 2013.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーション。 組織の中で働いていくには身につけておきたい技術。 特に、代理店営業など、社外の組織の行動を変えていくためには、アクションオリエンテッドな議論すること、動機付け、モチベーションを持続させるための数字の管理は重要。 実践したい。
0投稿日: 2013.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説仕立てのファシリテーションスキルの本。組織にどのようにファシリテーションが活かせるのか、ということが面白く理解できる。
0投稿日: 2012.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公クロサワリョウコさんが特命部長の役割を担い、会社の建て直しを薦めるストーリー。ストーリー仕立てで読みやすい。手法や「道具」について、お話しである故に、使い方がわかりやすい。一方、効果については、客観性がないと思う。自分が改めて、それを使ってみて効果があるかどうかを評価する必要があるでしょう。 話は、社内の改革抵抗勢力をファシリテーションを使って巻き込みながら「改心」させていく、というサクセスストーリーである。こういう風にうまくいけばよいのだが・・・。
0投稿日: 2012.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語風に書かれているため非常に読みやすい。随所に大切なエッセンスが多数散りばめられていた。 具体的手法・ツールについては別で学ぶ必要があるかも。
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ***** 「メタ認知」の視点を肌で感じられたことが一番の収穫。 場のメカニズム、参加者の心の持ちよう、自分自身の心の揺れまで、 表層的な言動+コンテキストのダイナミズム+個人の哲学。 あらゆるレイヤーを認識しながらゴールを目指していく。 ***** 場の空気を読もうとしすぎる、という特徴も、 ファシリテーターとしての持ち味にきっとなりうる。 場に働きかけられる強さと一体であれば。 *****
1投稿日: 2012.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションという今流行の言葉を知る。前半に面白さが集中しており、後半の物語は流し読みしました。ファシリテーターの役割って何?を知りたい人にぜひ。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ同僚の勧めで読んでみた。もちろん沢山知らなかった知識は勉強になったが、やや強引だったりハウツー要素が強かった。
0投稿日: 2012.09.03
