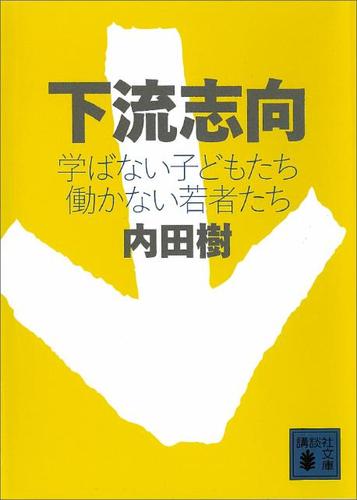
総合評価
(258件)| 84 | ||
| 96 | ||
| 32 | ||
| 8 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「分からないことがあっても気にならない」 ・分からないとこがあっても気にならない。若い人ほど分からないものをそのままにする傾向が増している。分からないものを分からないままに維持して、それによって知性を活性化させるという人間的な機能が低下しているような印象を受ける。例えば分からない言葉を調べずにそのままにするなど。そういった人々は世界の意味が分からず穴だらけで世界を見ているのではないかという不安を覚える。分からないことにストレスを感じない。 「等価交換が染み付いている」 ・現代は子供も消費者として始まっており等価交換が染み付いている。昔の子供は労働者として家事手伝いから始めて家族に役に立つことを証明することが先だった。手伝いをして感謝され認められ、徐々に与えられる手伝いを増やして家庭内で社会的な承認を得ていく。今は子供にできる家事がない上に、子供は余計な仕事を増やすので何もしないことが求められている。加えて早い段階からお金をもらう。お金を使うと個人の能力関係なく大人と対等に消費活動が出来る。お金を使うことで、家事手伝いで社会的な承認を得る前に、社会経験を獲得してしまう。ここで現代の子供は経済合理性の概念を正しい考え方と捉えるようになる。 ・勉強や仕事を始める前に当人が理解出来る範囲で有用か無用か判断してからじゃないと始められない。なのでこの授業は何の役に立つのかなどと聞いたりする。そこで有用だと理解出来なければ、それが不快や苦労に見合わないから、等価交換とは言えず不合理と考えられるので、やらないという判断になる。ただし勉強はそれを学ぶまで何の役に立つか分からないものなので、勉強する前に有用かを判断することはそもそも出来ない。 ・学びからの逃走/労働からの逃走に関して経済合理性(等価交換の原則)の観点からは突き崩すことは出来ない。何故なら学びは学ぶまで有用か判断できないから。また労働は組織利益のために必ず労働者が損するように出来ているから。もしくは労働に対してより難しい仕事という報酬を与えるので経済合理性の観点からは不合理。 「自分が時間的に変化することを想定してない」 ・自分自身を時間の流れの中に置いて、自分自身の変化を勘定に入れてモノを考える知性が必要。自分自身も時間の中で変化するということを勘定に入れることが出来ない思考を無知という。学びからの逃走/労働からの逃走とは己の無知に固着する欲望のこと。
0投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017. 金沢大学 人間社会学域 地域創造学類 後期 小論文 2023. 岡山大学 教育学部 養護教諭養成課程 前期 小論文
0投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログすでにこの時代にこう言われていて、今やそれが加速して行っている気がする。AIが出てきた今、どうなってっちゃうんだろうなぁ
0投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2回目の読了。 日本でニートという言葉がニュースを賑わせたのが2005年頃。 この本が2007年刊行。 2008年のリーマンショック以降はニート単独で問題にされにくくなった気がする。 僕が初めてこの本を読んだ2010年頃、勉強かっこ悪い、努力かっこ悪いみたいな風潮を理解できずにいたけど、この本を読んでとても納得した覚えがある。 「消費主体」としての彼らは、「最小の出費で最大の効果を得ること」に当然努力すべきであり、その価値観を学習のフィールドに持ち込むと、「なるべく努力せずに卒業する」ことが正義になってしまう。彼らは怠けているどころか、ついうっかり努力し成長してしまわないように、必死で努力しているのだ。 市場経済は原則として「無時間モデル」という発想には強く納得。 「成長」とは、時間のダイナミズム、つまり「可能性とは常に未来に開かれているもの」ということを信じられる人にしか訪れないのかもしれない。 すくなくとも「今・ここ・自分」に縛られていては、「この先に何があるかわからないもの」に貴重な原資(努力のこと)を差し出すことはないだろう。 我が子たちよ、君たちの可能性は、未来に開かれているぞ。
0投稿日: 2025.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログP151~の「雪かき仕事」の内容にハッとさせられる。経済的な合理性だけを求めていると、こういう視点に立てない。 消費行動は本質的に無時間的な行為という一節にしびれた。 コスパやタイパという言葉があらわすように、本書が出版された当時よりも更にその傾向は強まっている気がする。 学びという概念について改めて考えさせられた。
0投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びとは時間的なもの。学び始める時にはそれがなんなのかわからない。学ぶにつれてその価値や意味がわかる。時間的流れの中にいて自分自身の変化を受け止めていく。 生徒が消費者として教育を受けているのはひしと実感できた。
0投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ等価交換をしようとする子どもたち、それは無時間的であり、消費であることだ。消費をすることの危険性を述べていた國分功一郎先生の述べていることも通ずるが、勉強をして、学習過程が終わるまで学習する意味がわからないという、絶対的時間性の学習というものに、消費的な思考を介入させることは大きな矛盾である
7投稿日: 2024.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
下流志向「内田樹」読書メモ 学びからの逃走 【問題提起】 学習しないこと,労働しないことを誇らしく思う, 「新しいタイプの日本人」の出現 論件2つ →①新しいタイプの日本人がどのような歴史的コンテクストから生み出されたのか →②学びや労働から逃避した日本人が溢れる危機的未来にいかに対処していくべきか 【現状分析(具体例)】 ・勉強を嫌悪する日本の子供 ・学力低下は自覚されない →相対的な指標(偏差値)が支配的だから ・「矛盾」と書けない大学生 ・わからないことが気にならない若者 →「わからない」ことよりも「わからないことがあっても気にならない」ことの方に危機感を感じる筆者 現代の若者は意味がわからないことをスキップすることに慣れている,意味がわからないことをストレスに感じない ↑ 自分の知らないことを存在しないことにしている 無知のままでいることに生きる不安を感じずにいられる ・世界そのものが穴だらけ ・オレ様化する子どもたち ・想定外の問い 「学ぶことは何の役に立つのか?」という問い 子どもたちにとって授業を受けることはある種の「苦役」 子どもたちは教師に対して「支払い」をしていると捉えている 別の言い方をすれば,「苦痛」や「忍耐」という形をした「貨幣」を教師に対して支払っている. それに対して,どのような財貨やサービスが「等価交換」されるのかを彼らは問うている →教師は絶句 なぜか,それは「そんな問いかけが子どもの側から出てくるはずがない,ということが教育制度の前提だから」 「どうして人を殺してはいけないのか」という質問は, 「自分が殺される側に置かれる可能性」を勘定に入れていない それと同様に 「どうして教育を受けなければならないのか」という質問は, 「自分が学びの機会を構造的に奪われた人間になる可能性」を勘定に入れていない 例)世界に無数にいる戦争や災害で学ぶ機会そのものを奪われている子どもたち 実際には,この想定外の問いに対して, 絶句する大人や先生が少なく,子どもにも分かるような功利的な動機づけで子どもに勉強させようとする. 子どもたちは自分たちの差し出した問いが 大人を絶句させるか 幼い知性でも理解できるような無内容な答えを引き出すか そのどちらかであるかを人生の早い時期に学んでしまう ある種の達成感 →それが何の役に立つのか?どんな「いいこと」をもたらすのか その答えが気に入ればやるし,気にいらなければやらないという, 「等価交換」する子どもたちが誕生(経済合理的,功利的な価値基準が幼い頃から染み付いてしまう) ・家庭内労働の消滅 消費主体としての自己を確立している子どもたちは, 学校に入って教育の客体とされることに不本意である. 自己のアイデンティティの基礎づけ 社会関係に入っていく過程が,労働から入ったか,消費から入ったか ・教育サービスの買い手 超少子化→シックスポケッツ 初めての社会経験が消費すること お金を使う人間として立ち現れる場合には, その人の年齢や識見や社会的能力などの属人的要素は基本的に誰もカウントしない ↓ 金の全能性の経験を持ってしまう ↓ 金の多寡ではなく,「買い手」という立場を先取すること ↓ どのような場面でもまず対面的状況において自らを消費主体として位置付ける方法を探すようになる 学校でも子どもたちは「教育サービスの買い手」というポジションを無意識のうちに先取しようとする. 等価交換的な取引の一番大きな特徴:買い手はあたかも自分が買う商品の価値を熟知しているかのように振る舞う(=十分な商品情報を持って,適切な商品を購入するのが消費主体としてのあり方) 消費主体として人生をスタートするということは 自分の前に差し出されたものを何よりもまず「商品」として捉えて, それが約束するサービスや機能が支払う代価に対して適切かどうかを判断し, 取引として適切であると思えばお金を出して商品を手に入れる. 消費主体にとって,「自分にその用途や有用性が理解できない商品」というのは存在しない そのようなものはそもそも商品として認識されない 子どもたちがひらがなを習うと,何の役に立つのですか?」という質問をするのは 消費主体として「この商品は何の役に立つのですか?」と聞くのと同じこと. ・教育の逆説 等価交換の取引の場での有用な交渉術 「その商品には興味がない」という無関心を誇示することで取引を優位に進められることを知っている 有用な交渉術を学校現場に即して置き換えると, 「そんなもの要らないよ.だって,それが何の役に立つのか(というよりむしろ何の役にも立たないこと)を,僕は知っているから」 この問いがある種の全能感を子どもにもたらす 教師が差し出す教育的サービスを「そんなもの要らない」と拒絶することは 人類が営々として築いてきた知的構築物を一蹴するに等しい行為であるのは全能感がある 教師が商品の売り手になりさがり,何とかお客さんである子どもたちに教育サービスを買ってもらおうと懇願する 子供の目から見て教育サービスのうち,その有用性が理解できる商品がほとんどないということ 教育サービスが何の役に立つのかをまだ知らず,自分の手持ちの度量衡では,それらがどんな価値を持つのか軽量できないという事実こそが,彼らが学校にいかなければならない当の理由だから. 教育の逆説は, 教育から受益する人間は,自分がどのような利益を得ているのかを,教育がある程度進行するまで,場合によっては教育過程が終了するまで,言うことができない.ということ 昔の子どもたちは「承認」の感覚を求めて労働主体としての自己形成のプロセスを進んだ 消費主体としてのあり方として, ①目の前に差し出されたものを「商品」として認識 ②「商品」を値切ろうとする(=最小の貨幣で最大の商品を手にしようとする) ・不快という貨幣 教育サービスの対価として,自らを消費主体だと認識する子どもたちは何を支払っているのだろうか? →「不快」を貨幣として教育サービスと等価交換しようとしている 教室は不快と教育サービスの等価交換の場となる 「不快という貨幣」を最高の交換レートで「教育商品」と交換しようとする 「最高の交換レート」で,ということはすなわち, 例えば,その授業の価値が「10分間の集中(不快)に耐えること」であれば, 残り40分間分の「不快」はこの教育サービスに対する対価としては「支払うべきではない」ものであり,その時間は隣の生徒と私語したり,ゲームで遊んだり,漫画を読んだり,立ち歩いたり,居眠りしたり,子どもにとって「不快」でないとみなされる行為に充当される(というより,充当されなければならない(=子どもたちのある種の努力)) ・生徒たちの意思表示 授業に対して何の意味もないということを示したいのではなく, 等価交換が適正に行われることを何よりも重要視している. ・不快貨幣の起源 子どもたちは「他人のもたらす不快に耐えること」が家庭内通貨として機能するということを,人生の極めて早い時期に習得している. 「先に文句を言ったもの勝ち」のゲーム ・クレーマーの増加 「先に文句を言ったもの勝ち」のゲームになれた子どもたちは 「被害者」のポジションを先取りする能力に長けている 「私は不快に耐えている人間」であり,あなたは「私を不快にさせている人間である」という,被害―加害のスキームを瞬間的に作り上げようとする. ・学びと時間 不快を記号的に表示することで交換を有利に導こうとするタクティクス →学校教育の組織的な破壊をもたらした 等価交換は空間モデルによってでしか記述することができない ⇅ 学びのプロセスは空間的に表彰することはできない →「時間」の有無 「学び」は等価交換の空間モデルによって表彰することができない 「学び」は時間的な現象である そして,時間的でないような「学び」は存在しない. ・母語の取得 母語の取得を始めたとき,これから何を学ぶかということを知らなかった 起源的な意味での学びというのは, 自分が何を学んでいるのか知らず,それが何の価値や意味や有用性を持つものであるのかも言えないというところから始まる というよりは,自分が何を学んでいるのかを知らず,その価値や意味や有用性を言えないという当の事実こそが学びを動機づけている. 学びのプロセスに投じられた子どもはすでに習い始めている すでに学びの中に巻き込まれてしまっているのでなければならない 子どもは学習の主権的で自由な主体であるのではありません まず学びがあり,その運動に巻き込まれているうちに, 「学びの運動に巻き込まれつつあるものとしての主体」という 事後的に学びの主体は成立してくる. 私たちはそのつどすでに学びに対して遅れている 学びとは, 学ぶ前には知られていなかった度量衡によって, 学びの意味や意義が事後的に考量される. ダイナミックなプロセスである ※「買い物する主体」は無時間的な存在 消費主体;等価交換を行っている過程で,消費主体は決して変化してはならない, その価値観を変えてはならない,その交換レートを変えてはならない,その度量衡を変えてはならないという厳重な禁則から逃れることができない →学びの場に消費主体として登場してしまった子どもたちも同じ禁則に縛られることになる. ・変化に抗う子どもたち 「成長」へと押し流そうとする圧力(=学びへと誘う流れ)に全力で抗っている 子どもたちがまず学ぶべきことは「変化する仕方」です 学びのプロセスで開発すべきことは何よりもまず「外界の変化に即応して自らを変えられる能力」です ・「自分探し」イデオロギー 「自分探し」とは,自己評価と外部評価の間に乗り越えがたい,「ずれ」がある人に固有の出来事であるということができます. 自己評価と外部評価のズレ自体には問題がない 問題なのは,自分でも納得の行くくらいの経緯や威信を獲得するように外部評価の好転に努めるというのが,普通の人間的成長の行程であるが, 外部評価を全否定してしまうことが問題である. 人々が何かを行おうとするとき,その行為の動機がどれだけ個人の心の内側から発するものか.教育心理学の用語を使えば,「内発的に動機付けられているか」どうかによって,私たちの社会はその行為を価値づけることに慣れ親しんできた. 打算や利害によるよりも,自発性が尊ばれる. 金儲けや,権力,名声の獲得といった,自己に外在的な目標を目指して行動するよりも, 自分の興味,関心に従った行為の方が望ましいとみる. 個性を尊重する社会では,自己の内側の奥底にある「何か」の方が外側にある基準よりも行動の指針として尊ばれる. 問題は「自己に外在的な目標を目指して行動するよりも,自分の興味・関心に従っていた行為の方が望ましいとみる」という点である. 仮にひろく社会的に有用であると認知されているものであったとしても, 「オレ的に見て」有用性が確証されなければあっさり棄却される この価値付けが教育崩壊の根底に横たわっている. ・未来を売り払う子どもたち 「現代思想を学ぶことの意味は何ですか?」 もしこの問いに説得力のある回答をしたらそれを学んでも良いが, 答えに納得できなければ,「学ばない」と宣言している. つまり,ある学術分野が学ぶに値するか否かの決定権は自分に属しているということを問いを通じて表明している. →傲慢さと無知さ 20 歳の学生の手持ちの価値の度量衡をもってしては軽量できないものが世の中には無限に存在している. 喩えて言えば, 愛用の30センチの「ものさし」で世の中の全てのものを測ろうとしている. その「ものさし」では測れないもの,例えば,重さとか光量とか弾力と言ったことの意味を「ものさし」しか持たず,それだけで世界の全てが軽量できると信じている子どもにどうやって教えることができるだろう?
0投稿日: 2024.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ当座の報酬の期待値の低さ・不確定性に対し、経済合理性の下、消費者マインドで「こんなん何になるんだよ」と突っぱねちゃうのがニートと不登校、つまり労働や学びの拒否の始まり。 その曖昧さや不確定性に対して「きっとなにかになるはず」と、気長かつ楽観的・期待的に身を投じて、労苦を負って行くこと。そして自己の不確定な変化という性質を認め、受け入れ、期待し、勘定に入れた上で学びに向かうこと。それらの勇気ある殊勝な態度が知性。 また「自身の存立」時点で社会や周囲の人間から受けてきた恩義、つまりは贈与に負い目を認められ、その反対給付義務意識に駆られて積極的に労働という(返報)贈与を社会に行っていくこと。それこそ伝統的人間らしさ・文化人類学的知見に合致する労働者マインドであり、労働の倫理・哲学・美学である。 ※ただこの倫理に関しては(薄給なだけならともかく)ハラスメントや長時間労働強制、肉体的・心理的安全性侵害が横行するような、日本に跋扈するブラック職場では成立しないと思うけど(2005年の本だししゃーなし?)。 含蓄が多い本だと感じました。 勇気と忍耐のある、道徳的な内発的動機づけに強く意志付けられた人間になりてぇ。
0投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分も含めてですが、コスパよく結果がでることや収入が得れるというのが一般的な時代になっています。そんな時だからこそ本書で述べられている 教育という本質的な部分は忘れてはならないと感じました。親と子で学ぶ。なぜ勉強するか?そこは問わずに楽しいよね?学ぶって出来るってという変化をしっかりとみてあげること。子どもも含めて感謝をする。人間として大事な教育という土台をもう一回作り直して現行にも活かせる一冊だと感じました。
0投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭の事例は「事実の一部」、「メディアで変に強調されているところだけ」を基にしているように思われたけど、「消費主体」という視点にはかなり納得。そしてリスクヘッジの意味を再認識させられた。
0投稿日: 2023.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どうして勉強しなくちゃいけないの?」 こういった子供の問いに、大人として最適なふるまいとは『絶句』してそのような問いは「ありえない」と斥けることだと著者は主張しています。 なぜなら、その答えを教師から引き出すという体験によって、子どもがあるゆることにおいて自分に有益そうならやるし、気に入らなければやらないという採否の基準を身体化した『等価交換する子ども』になってしまうからだと言います。 それは子どもたちが「家で労働する」という体験から自己形成をする機会がなくなり、その代わり早い時期から消費活動への参加を促されていることに原因があるとのことで、その説明は納得するところもあるのですが、平和で豊かな生活を送る日本の子どもが、勉強の意義を考えることがそんなに悪なのでしょうか?とも考えてしまいます。私もなんとなく考えたことあったと思うし。 そんな質問に教師として「答えがない問いに答える必要はない」と斥けるのは、「つべこべ言わずにやれ」という昭和の感覚をよっぽど引きずっているのではとも思ってしまいます。 「君は歴史で習った、戦時中の子どもの話を聞いてどう思った?これがその質問の答えになると思うから、一度自分で考えて、あとで先生に教えて」 みたいな子どもに気付きや考える力をサポートするのが最適なのでは。 ちょっと自分と意見が違うけど、子供をとりまく教育、家庭の構造がわかって面白かったし、色々考えるきっかけになりました。また読みたいです。 ちなみにこのあと『ドラゴン桜2』を読むと、なかなか味わい深くなります。「考えるな!動け!」
0投稿日: 2023.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ぶことができるという環境を放棄している日本の子どもたち。納得のいく内容でした。 生産と消費がかけ離れ、生産することへの尊敬と感謝が失われている日本社会。たくさん消費することが良いライフスタイルであることのように報じられるメディア。日本はどうなっていくのでしょう。
3投稿日: 2023.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 本人も書いておられるように「ずいぶん力んで書いている」力作であります。 消費者として全てを同時性の中で生き、世の中を等価交換で見る体質。 こういったことが学びを馬鹿にし、労働を無意味なものと見る価値観に結びつくと見る。 解明していく際の気押される程の勢いある文章に引き込まれて行く。 学校内の状況は改善はされてきているのだろうか。 ニートの数は減少しているのだろうか。 外からは見えない隠れた部分。実態を知る術が無いが、良くなってきていることを望む。 対談部分は文庫化に際して削っても良かった気がする。何か著者にもしがらみがあるのかも知れないが…
4投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだ中でベスト・オブ・ベスト。 ウチダイズムの原理というか、ベースを知れた=社会の構造。 如何にして社会的上層と下層の差が生まれているのかそしてその原因は何なのかを考えさせられる書籍である。個人主義がいかに恐ろしい思想であるか。 そしてすべて個々人に降りかかるという、良い意味でも悪い意味でも。 勉強を放棄してもそれは将来の自分が連帯保証人として存在する。
2投稿日: 2023.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は、筆者の娘の中学校での学級崩壊の様子から、話が始まります。 学ぶという行為をなぜ子供たちはやめ、あまつさえ努力してまで学ぶ・働くことから遠ざかるのか、という疑問です。 その原因を端的に言えば、幼年期からの消費者としての商取引の蔓延、と解しました。 ・・・ 筆者は労働と消費の二項を導入します。 かつては子どもは労働に従事させられた。それは家庭内の小さな手伝いであったり、兄弟の面倒などの家族のサポートであったりした。その結果、家庭内がよりうまく回ったり、時に小遣いがもらえることがあったりもしたと。その労働の世界では搾取されるのが当然の世界で、子どもはその世界で自らの社会化を始めた(その搾取された労働のおかげで家庭であったり社会であったりがうまく回り、再配分が行われるということのよう)。 対して、現在の子供たちは労働の世界に馴れ初める前から、消費者としてマーケットに参入していると。ここでは原則は等価交換・無時間性です。 つまり交換は受領するサービスとその対価は等価であり、かつ瞬時に交換されなくてはならない。もちろんマーケットメーカーですから、値段に納得がいかなければ交換しないし、交換するならば今すぐそのサービスやバリューが提供しなければ納得しません。値切ったり交渉があったりするかもしれません。 ・・・ ところが、教育というものが、そうした消費という概念におそよ馴染まない世界であることから、教育という世界と消費者たる学生との間で齟齬をきたすことになります。 まずもって教育とは時間がかかる。今日受けた授業で、生徒が成長を明日にでも実感できるものではありません。また教育がそもそも功利のみで語られるものばかりでもありません。しかも教育を受けたとて、それで将来の成功が保証されるわけでもありません。 このような教育の本質は、消費者として等価交換を考える学生のメンタリティとは合致しないことになります。 ・・・ ここで、等価交換という消費の原則に、「不機嫌」という貨幣が導入されます。 交換される財とサービスは等価でなくてはならない。 では学校では何が交換されるか。そう、授業というサービスです。学生にとって意味を見出せない授業とは自分が交換している時間に大いに見合わない。そこで交換を等価にするために支払われるのが「不機嫌」です。 「不機嫌」という通貨。なんだそれ? ほら、振り返ってみてください。昭和世代の「父親」が歯を食いしばって宮仕えをし、給金を家庭へと持ち帰ってきた様子を。いやな仕事もお金の代償とばかりに、家出は不機嫌顔で録に家族と話もせず寝てしまう。子どもたちは、親のこの態度を学習したと。 授業という意味を見出せない(無時間的に価値ありげなものも提供してくれない)ものに対して時間を(強制的に)交換させられている。でもこれは子どもたちとって等価ではない。この交換を等価にするべ、生徒たちは「努力して」授業を妨害している、と。 つまり学級崩壊は、生徒の等価交換の実現であると言えます。 ・・・ しかも、「自分らしさ」「内発的動機」「自己決定」などを称揚する潮流が事態を悪化させたとしています。 例えば「自己決定」。これは、自分が価値を置くものを自ら選択・決定するってことですね。逆に言えば、他人や世間がこれをやりなさいって言っても、強制されないわけです。パターナリズムの否定です。 生徒の立場で「自己決定」を言われると、授業や教育とは、生徒が意味を見出すもので、先生が一方的に授与するものではない、ということになります。意にそぐわない授業を聞くことは「自分らしく」ない。 塾で習う方がコスパ・タイパよくね? てか歴史なんか勉強して意味なくね?俺達将来を生きるんだし。 暗記とか時間の無駄だし。ネットで検索でオッケーじゃね?…すべて等価交換を念頭に置いた自己実現・自己決定であります。 ・・・ さて、この「自己決定」ですが、その決断の正しさを担保するのは何でしょうか。 もちろん、将来の自分です。でも将来の自分が正しくなかったとき、どうなるでしょうか。もちろん、将来の自分が毀損します。 しかし学ばない子、働かない子は、安全網を破棄していることが多いと言います。 基礎教育を得ていない(「俺的に授業はイけてなかった」「人からやらされることは嫌い」)、労働経験が少ない(「チョー面倒なことをやらされるんだったら、収入なしの方がマシ」(無労働と定収入の等価交換・自己実現))、などです。 もちろん、勉強なんて何の意味があるか分からないことも多いです。そして何に役に立つのかも分かりません。また、そうした努力が必ずしも実を結ぶとも限りません。 しかし、生きる力がない・生きられないというリスクをヘッジするという観点から言うと、たとえ努力が実を結ぶと信じなくても、こうした努力・勉学を続けることこそがリスクヘッジとなるのです。 そして「内発的動機」を重視しまくり「自己決定」した人がこうしたリスクヘッジをできず、ニートになり得る、と結論づけているように見えます。 ・・・ ということで内田さんの著作でした。 問題は複合的であり、一概に原因を特定したり、断定できるものではないかもしれません。内田氏もニートの統計が少なく、状況について断言しかねる旨、仰っています。 なお、こうしたニート達については、特効薬もなく、労働や勉学にも価値があるということを少しずつ理解してもらう、彼らを受け入れるような共同体を回復させる、等々を簡便に仰っていました。このあたりは宮台真司氏の考えに似ているかもしれません。 とうことで、本作、日本の教育事情、日本現代文化、社会学、思想系に興味がある方には興味深く読んでいただける作品かと思います。
2投稿日: 2023.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない働かないを自己選択する若者たちの気質を読みといた一冊。示唆に富んでいて非常に興味深い。 背景として、日本社会が集団主義の護送船団社会から個人主義の自己責任社会に移行したこと、子どもであっても経済合理性(コスパ・タイパ)を判断軸にしていることがありそうだ。 教育のジレンマとして、ある程度修了しないとその効果を実感できないところがあり、即時的な効果を求めづらい。 「なんの役に立つの?なんのために学ぶの?」の質問はここから来ている。 学校教育を経済合理性で考えた場合、じっと座って授業を聴く苦役および時間を差し出すことで、教師から教育サービスを受けるモデルと考えられるが、現在の社会は学歴が将来の雇用や収入を保証しない。 周りが勉強しないなら、全体の没落により偏差値は下がらない。 結果として、学力の二極化が起こる。 高偏差値層の医歯薬系の人気も、高校生が投資回収の早さを理解しているからだろう。 労働についても、労働は本質的に等価交換ではない。利潤を得るためには賃金以上の働きが必要。その点が理解されていない。労働による承認は賃金や周囲からの評価だが、賃金は労働対価以下であり、承認は送れてやってくる。 即時的な効果を得られないことに対して、結果が不利だと分かっていても低い自己決定をする流れがありそうだ。
1投稿日: 2023.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに現代教育の核心をついている。過去のフォーマットにしがみついている場合ではない。評価で釣って、子供に勉強をさせる手法は限界だ。そもそも学問とはそういうものではない。損得勘定でしか人間が動かなくなる。生徒は消費者目線で学校にやってくる。まさに、この通りで、変えることは困難であり、どう折り合いをつけていくのか。
0投稿日: 2023.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃめちゃ面白かった。 幼年期から経済主体として成長している。 この視点から現代の問題、例えばクレームする親や教育に反抗する子供などを説明していた。 これがすごく新鮮で、25の自分にも当てはまるところが多分にあった。 懐古的に昭和時代の大きな家族ぐるみの付き合いを失ってしまったことを嘆いている。 一家の大黒柱が働けない家族を含めて支えていた時代を。 こんな友人や家族を築けたらいいなと思う。
2投稿日: 2022.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログp.31意味がわからないことにストレスを感じない →生まれた時からデジタルな仕組み分からないものだらけ p.57教室は不快と教育サービスの等価交換の場 → 消費者の立場で社会参画するからクレーム(自己利益を少しでも増やす合理的判断)。 →売買は無時間モデル。教育は学んだ後でないと価値が分からないものであるのに。 ・世の中がビジネル思考になった。 ・師をもつことが師である条件。オビワン。
0投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時勧めてくれた友達に、「読んだよ!なんか、哲学者なのに読みやすい語り口だね、堅くないし」と言ったら「わたしは内田樹の本のことはあるある本だと思ってるから」と返ってきたのを覚えてる
1投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書では、子どもが授業を真面目に聞かないこと、勉強をしないこと、すぐに転職する若者が増えていること、ニート問題など、人によっては近頃の若者はけしからんと根性論で片付けてしまいそうなテーマが扱われている。 しかし、実はこれらの背景には共通しているものがあり、それが消費者マインドだということがわかりやすく説明されていて、なるほどと大変感心した。 現代社会において、消費者マインドは、重要かつ不可欠な思考であるというイメージがあったので、教育などの場に持ち込まれることで弊害にもなり得るというのは新たな学びだった。
1投稿日: 2022.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ●著書は人生上がりの学者かとちょっと偏見があったが、この本は良かった。 ●なぜ最近の学生が学ばないのか、すっきり解説してくれている。腑に落ちた。同じくニートが働かないのも然り。 ●たしかに、なぜ勉強しないといけないのかなどの質問にはまともに取り合う必要はないはず。 ●ニートの解決策はほぼないという身の蓋も無い結論だが、その通りではないか。今後我々が税金で補うしか術がないのは悔しいが…
1投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすくて非常に面白い。なるほどね、と頷きながらあっという間に読んでしまった。 君たちはどう生きるかを読んだ直後だったのだけれど、消費主体として自己確立をする子どもの話は両者に指摘されていて興味深い。 経済的合理性だけを目指す教育や社会、どうなんでしょう?
1投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自由な生き方を自分自身で選んでるようで、実は選ばされているという視点が、今までの私にはなく新しい視点だった。 格差が広がる過程がよくわかる本。 格差が広がる。社会が助け合いを忘れギスギスする、自己責任を強く問われ弱者がどんどん追い詰められていく、一部の上流階級以外みんな弱者になっていく。じゃあそれをどう解決していくか、ということがあまり書かれていないが、著者的には自分で考えろってことなんだろうな。 でもどうしようもなくね?って思ってしまう。それも短絡的なのかな。 家族の絆や地域の絆を程よく保つみたいな取り組みはNPO法人でチラチラ行なっているのをみるから、そこに期待。 そして、私自身も、人との関わりがとっても億劫だけど、少しずつでも無理のない範囲で増やせていけたらなと思う。 自分の住む地域が、そして日本全体が、また総中流社会になれたらなと思う。
2投稿日: 2022.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は両親に、姉妹で私立の中高大と通わせてもらい、毎年のように夏は家族旅行に連れて行ってもらったりしていた。だが私自身は2人の子供達を公立でも大学までやることができるかも不安な財政状態で、家族旅行にもほとんど行けない。子供達はびっくりするくらい家庭学習をしない。なぜだろうと考えていたことに、ひとつの解答を得た気持ちだ。2007年に出版されていたとのことで現在の状況を鑑みても、非常に先見の明があったと思う。当時はまだ子供もいなかったし、読んでも同じように感じたかはわからないけど、もっと早くに読んでいたら、今が違ったのかなと思った。
2投稿日: 2021.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 若者の学力低下はいつの時代も叫ばれているが、近年問題になっているのは「学力低下」だけではなく、「学ぶ意思の喪失」である。 学ぶことは間違いなく人生を豊かにする。それは社会階層の向上や年収の増加といった、即物的なステータスの改善のみにあらず、見識の拡大や未知の遭遇への楽しさといった、より複雑な「人間性」の部分を育んでくれる。 しかし、今の子どもたちは、そうした「複雑で長いプロセス」を嫌うのだ。 本書は、学ぶことから脱落していくのではなく、自らの意志で主体的に学びを放棄する子どもたちの思考・行動原理を探った一冊だ。タイトルにもなっている「下流志向」とは、たとえ社会階層の下落が明白であろうとも、学ぶことを拒否する若者を、痛烈に皮肉った造語である。 筆者は、若者たちの「下流志向」の理由は、「消費者マインドによって教育と向き合っているからだ」と語る。 昔の教育現場は、教師を中心としたコミュニティがあり、学力の向上だけではなく、人間性・社会性を鍛えることにも重きを置いていた。この場において「勉強」とは即効性のあるハウツーレッスンではなく、より複雑で、無駄な情報の多いものであったことは疑いようがない。 しかし、現代の生徒は、教育を「役に立つか立たないか」で品定めするようになる。子どもたちはまず「それがなんの役に立つの?」という功利的な問いを口にするようになったのだ。 この質問に対し、教師は的確な答えを用意することができない。 学びとは、学ぶものがそこからどのような利益を得ているのかを、教育がある程度進行するまでは言うことができないし、それが教育という制度を成り立たせている。 筆者は「教育は市場価値には変化できない」と語る。 消費というのは本質的に無時間的行為である。購入の前と後で時間差があってはならず、買った商品と手に入れた商品の性質が全く異なっていては取引にならない。 一方、教育は時間的行為だ。ある物事を教わったあとに、それを受け入れる前の自分との間で変化が起こっていなければ、教育は失敗であるからだ。 自分が何を学んでいるのか知らないという当の事実こそが、学びを動機づけている。母語を知らず知らずのうちに学習していったように、「これを学んでおけば有利だ」と判断してから学習が始まるのではない。 しかし、消費者たる生徒はその事実を拒否する。そして、教室の中での45分を自分の時間との「取引」であると考え、「オレの大切な時間を浪費するな」という態度を取る。その結果が、授業中におしゃべりする、出歩く、居眠りするといった問題行動なのだ。 ―――――――――――――――――――――――――――――― 「下流志向」は学生よりも社会人の間で広範に見られる、より深刻な現象ではないだろうか。なぜなら、内田氏が本書で述べているような時間制と無時間制の倒錯――「すぐ食べられて、すぐ効く教育」を強く求めているのは、社会人のほうであるからだ。 学びという過程をインスタントにすませ、複雑で多層的な知識を「役に立つ」というふるいで選別する。自らの役に立たない情報=意味が分からない情報であり、世界が「虫喰い」になろうとも不快に思わない――本書で述べられていた若者の特徴は、残念ながら社会人にもそっくりそのまま当てはまってしまうだろう。 ある意味では、子どもたちが役に立つものだけを摂取する社会人を見て育った結果、「何の役にたつの?」という問いを投げかけるようになったのかもしれない。 ――――――――――――――――――――――――――― 【本書のまとめ】 1 学ばなくなった子どもたち 学びからの逃走…教育機会から「主体的決意」を持って去り、下流社会への階層降下を自発的に行うこと。 日本の子どもたちは今や世界で最も勉強をしない子どもたちになってしまった。 今の子どもたちは、わからないものがあっても、どうやらそれが気にならず、わからないままに維持しているようだ。新聞やテレビなどのメディアを通じて見える世界は「虫喰い」的に、一面に意味の穴が空いている。そして、それを不快と思っていない。 学力低下の危機的な要素の一つは、子どもたちが、自分には学力がないとかを多少は自覚していても、そのことを特に不快には思っていないという点にある。彼らは、「自分の知らないこと」は「存在しない」ことにしているのだ。 どうして、子どもたちはまず「それがなんの役に立つの?」という功利的な問いを口にするようになったのか。それは、子どもたちは就学以前に消費主体としてすでに自己を確立しているからだ。 時代が進むにつれ、子どもたちが小さいころからお小遣いを手にするようになり、家庭内労働における「労働者」という立場よりも先に、市場での「消費者」としての態度を身に着けるようになった。消費主体にとって、「自分にその用途や有用性が理解できない商品」というのは存在しないのだ。 子どもたちは消費者マインドで学校に対峙している。彼らはただ、「自分の不快に対して等価である教育サービス」だけを求めている。関心は教師と自分の間で等価交換が適正に行われることだけだ。 そのため、教室は不快と教育サービスの等価交換の場となる。授業が不快と思っている子どもにとって、教育サービスとの等価交換というのは、全力で値切ること、すなわち決められた時間以上授業を聞かない努力をすることである。粗暴なふるまいをし、悪い態度を取り、学校から受ける罰を少しでも安くしようとする。 子どもたちは、自分が何を習っているのか、何のためにそれを習っているのかを、習い始めるときには言えない。自分が何を学んでいるのか知らないという当の事実こそが学びを動機づけているからだ。母語を知らず知らずのうちに学習していったように、「これを学んでおけば有利だ」と判断してから学習が始まるのではない。 教育の逆説は、自分が学びによってどのような利益を得ているのかを、教育がある程度進行するまで、言うことができないということにある。 「何の役に立つのか?」という問いを立てる人は、ことの有用無用についてのその人自身の価値観の正しさをすでに自明の前提にしている。しかし、「私」が採用している有用性の判定の正しさは誰も担保してくれない。唯一いるとすれば、「未来の私」だけである。 2 リスク社会 リスク化とは、社会の不確実性が増し、個人にとっては将来の生活予測可能性が低くなるということ。これだけの努力をすればこれだけのリターンが保証されるという、努力と成果の安定的な関係が崩れ始めることがリスク化社会の特徴であり、「二極化」を招く。 努力しても報われないという事実がありながらもなお学習努力を続けられる子どもと、学習努力を放棄してしまう子どもの間にはあきらかな学力差がつく。 リスク社会におけるリスクはすべての社会成員に均等に分配されているわけではなく、階層ごとにリスクの濃淡があるのだ。リスク社会とは、そこがリスク社会であると認める人だけがリスクを引き受け、あたかもそれがリスク社会ではないようにふるまう人々だけがリスクをヘッジできる社会なのだ。 リスクの少ない社会階層に属する人々は、当然ながら、日々の実践を通じて「努力は報われる」ということを確認し、それによってますます努力するが、逆の人々はますます悪くなる。 リスク社会におけるもっとも賢明なふるまいは、できるだけ巧みにリスクヘッジをすること。しかし、それがどのような操作であり、どのような資質を要請するかということは、なぜか僕たちの社会ではほとんど語られることがない。 リスクヘッジは個人だけではできない。AかBかの二者択一で揺れている人に、両方とも選べとは言えない。そのため、「リスク社会をどう生きるか?」という問いは、「決定の成否にかかわらず、結果への責任をシェアできる相互扶助的集団をどのように構築することができるか?」という問いに書き換えられねばならない。 社会的弱者とは端的に言えば、「相互扶助組織に属することができない人間」のこと。獲得した利益をシェアする仲間が無く、困窮した時に支援してくれる人間がいない人間のことである。 現代日本人は「迷惑をかけられる」ことを恐怖する点において、少し異常なぐらい敏感だ。「迷惑をかけ、かけられる」ような双務的な関係でなければ、相互支援・相互扶助のネットワークとしては機能しないにもかかわらずである。 社会的弱者とは、「自立した人間」ではなく「孤立した人間」だ。 「日本の比較的低い階層出身の生徒たちは、学校での成功を否定し、将来よりも現在に向かうことで、自己の有能感を高め、自己を肯定する術を身に着けている。低い階層の生徒たちは、学校の業績主義的な価値から離脱することで、『自分自身にいい感じをもつ』ようになっている」 3 労働からの闘争 ヨーロッパのニートは階層化の一つの症状である。本人に社会的上昇の意思があっても機会が与えられないからだ。しかし、日本のニート問題はヨーロッパとは違い、社会的上昇の機会が提供されているにもかかわらず、子どもたちが自主的にその機会を放棄している。 本来、「侵すことのできない権利」として要求すべき「学ぶこと」が、どうして「苦役」とみなされるようになったのか。それは、経済合理性の原則が社会のすみずみに入り込んだせいである。 労働から逃走する若者たちの基本にあるのは、消費主体としてのアイデンティティの揺るぎなさである。彼らは消費行動の原理を労働に当てはめて、自分の労働に対して、賃金が少ない、十分な社会的威信が得られないことに「これはおかしいだろう」と言っているのだ。 学びからの逃走、労働からの逃走とは、おのれの無知に固着する欲望である。
11投稿日: 2021.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
封建制を否定し、地縁共同体を霧散させた近代日本の歪みを解決してくれるのは封建的要素かもしれないのかと考える。それはまた封建制の問題を浮かび上がらせるだけなのだけれど、良い中間は多分ない。 そういえば、外山滋比古といい内田樹といい、自分の子供時代の教えは良かったとよく言う。人の話は丸呑みせずに考えることも必要だけど、訳もわからず受け取って、後でこういうことだったのか。と気が付くには、現代の生き方は早すぎるかもしれない。
4投稿日: 2021.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログある意味ホラーです。生まれついての消費者は、バザールの商人と同じ,儲かるか損するかが価値基準で有り、その行動原理は、幼き時より深く精神を支配していると師範はときます。
1投稿日: 2021.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済原理が行き渡りすぎた結果、教育が「等価交換」サービスと誤認される、という考察は頷ける。 「統計的に言うと」と言及される個所がいくつかあるのだけれども、そこに出典が明記されていれば、そちらも辿って読むことができるのだが、その点惜しいと感じる。
2投稿日: 2021.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年 6冊目 『下流志向』 石川先生に読めとの一冊。笑 幼い頃からの消費者意識と個性尊重の社会背景から、学校で学ぶこと、働くことを放棄する若者がいる。 労働は共同体存立の根幹にかかわる公共的な行為であることを忘れちゃいけないし、自由に生きることを履き違えちゃいけないよ、わたし。
0投稿日: 2021.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ぶ意味、働く意味を考えることは重要じゃない。そんなのは学ぶ、働くうちに見つけるもの、或いは見つからなくても良いもので、学ぶ、働くというのは当たり前のこと。という理解は強引かな? 内田さんは子供のうちに労働主体として生きることを経験するべきと言っている。そうかもね。自分が生きている社会は誰かの労働の上に成り立つもので、生きているだけで恩恵を受けている。働かずに生きていくというのは難しいこと。 私が物心ついた時、労働というものは自分以外の他人が担うもので、その対価に自分の何かを差し出すという考えはなかった。親が子どもに「寝床と食事は与えるからその分働け」なんて言ったら虐待扱いされますもんね、今なら。でも昔は子どもも働き手とみなされてたんですよね。食べていくためには子どもも働く必要があった。そうしないと家族が生きていけなかった。 何のために働くのか、とか考えることもなかったんでしょう。働かなきゃ生きていけないから。 今は働かないでも生きていける人がいる。衣食住やそれに相当する金銭を他人が与えてくれれば。子どもが生きていくのに必要なものを、子どもの労働なしに親が与えることもできる。余裕があるんでしょうね、昔に比べたら。 働きたくない人が働かないで生きていけるようにはならないのかな?今は他人を養う余裕がある人がいるわけで、その余裕を機械に労働させたり仕事を効率化させることで大きくしていけばいいのではと思うんだけど。 でも賃金が安いから共働きじゃないと子育て、生活が厳しい人も増えてる。これから余裕はむしろ小さくなっていくのかな。 労働からの解放というのは実現されないかなぁ。星新一さんの世界みたいだけれど。働かないでも生きていける社会になったら、どれくらいの人が働いてどれくらいの人が働かなくなるんだろう。いっぺん見てみたい。 政府から半年分くらいの生活費が全国民に与えられて、その期間働く必要はないと宣告されたら。物が買えなくなるしサービスも提供されなくなる。電気も水も使えなくなるかもしれない。働く人がいないから。水が使えなくなったら死ぬから、水道局に出向いて仕事を教えてもらって実践するかもなぁ。水道局の人に教えてもらう対価には何を差し出したらいいだろう。めんどくさいからって拒否されたらそれまでだしな。 食べ物は?スーパーに出向いていっても営業してなかったら、無理矢理こじ開けて盗むかもしれない。警察だって働いていないかもしれないし。そうなったら法律が機能しないから誰かに危害を加えられる可能性もあるね。なんか殺伐としてきたな。 やっぱり労働がある世界の方がいいか。働く人が大勢いるからこそ毎日食べる物があってインフラがあって安全に眠れる家があるんだし。 でも1日2時間週2日労働くらいに短縮されないかな、なんて理想はまだ持ってます。皆がもうちょっと楽できたらいいのにね。
18投稿日: 2021.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ばない子どもたちの一人として、ストンと胸に落ちるという訳ではないがかなり納得させられる論だった。学びは何の役にたつの?という質問に対して、"答えることのできない問いには答えなくてよいのです"という考えはかなり納得のいくものがあった。自己責任論の危険さの話もかなり良かった。
1投稿日: 2021.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
対価を支払う価値があるのかを確認する作業から学ばなくなり、働いたら負け、との理論が成立する。 リスクヘッジがキーワード
1投稿日: 2020.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ集団名を一括りにして語るのは、物事を他のことに汎用化しにくくなるため、あまり好ましくないのではないかと思った。 本書では、現代若者が一括りに語られていたが、若者の中にも自分の人生の目的にもとづき、その手段としての勉強は不要だと考えた上で勉強をしていない者もいる。結果だけに着目せず、過程にも着目し、細分化する方がより有効な議論が出来るのではないかと思った。 散々批判はしたが、著者の言うとおり、たしかに、(若者に限らず)何も考えていない人が、今いっときの悦楽に溺れるのは解決すべき問題であると思う。そのために、長期的な視点を持つことは大事であると思う。ただ、人それぞれ考える能力は異なる。考えない人でも考える能力がある人と同じだけの社会性を身につけるのはやはり学校なので、教育について深く考えることは大切なのであろう。
1投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ現状として起きている問題、不勉強な若者や働かない若者を社会やイデオロギーの変化に基づいて分析している。著者の言語化能力の高さに驚嘆する一方で、主張の一貫性のために少々誇張されていると感じる部分もあった。ただ、それは私自身が現代日本の実状について勉強不足であるのかもしれない。
0投稿日: 2020.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹さんの著書1冊目 物々交換の話、文化資本の話、子どもの学力について。 内田さんにハマるきっかけとなった本
0投稿日: 2020.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2005年夏に行われた講演の書籍化であるが、ここで取り上げられている問題は2020年現在でも未だ解決の道筋が見えていない(むしろより根深くなっている?)ことばかりである。 ここで論じられていることが過去の事になるのを願うとともに、我々よりも後の世代には負の遺産を残さないよう自分に何ができるかを改めて考えたい。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版の2007年に読んで衝撃を受けた本。世の中に対する違和感が説明されていくミステリー小説のような爽快感があった。そこから14年たち何回目かの再読。やはり面白い。当時と異なり人生も後半に入り、子供もできて、世の中のことも少し分かるようになり、読み方も変わる。自分の子供に伝えたいメッセージがたくさん含まれている本だ。 趣旨はタイトルと前書きで分かるように、教育崩壊の原因を消費者マインドにあるとして解説したものだ。クレーマー天国やニートも同様であると。これで終われば「ふ~ん、平和ぼけでバカが増えたんだね(笑)」なんだけど、そこからが内田先生の真骨頂「学びのプロセス」「リスク格差」「リスクヘッジの要諦」「自信満々の構造的弱者」「無知への居着き」と論が続く。 この論の正しさは、かつて教育や労働から逃走したバカな若者だった人たちが、2021年現在、一部はKKO(キモくて金のないオッサン)になり、一部は8050問題の中高年ニートになり、一部は無敵の人と化して街中でテロ行為を起こしてネットの嘲笑を浴びる反面、2世、3世の政治家、経営者、資産家が上流を占め、実家の太さと自分の能力を勘違いした者たちが繰り広げるピカピカマウンティング合戦をしている姿を見ることで確認できるだろう。「努力におけるわずかな入力差が成果における巨大な出力差となることがある」と。 自分は、幸か不幸か、上流にも下流にも行き着かなかったが、思えばご多分に漏れず若者特有のおかしな熱病で下流転落スレスレまで行った人間だった。ただでさえ何の特技もないのに、若さと人生を捨て値で投げ捨てる一歩手間まで行った。 子供に財産を残すことはできなそうだが、本が読めるようになったら、その教訓と本書は教えてあげたい。下流転落とはどういうことを指すのかということとともに。あまり説教臭くならないように内田節を借りて。
0投稿日: 2020.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身が考察対象になっている世代であり、学校の授業に対する考え方や態度は、まさにそのとおりだった。自分が必要と思うところだけを聞いて、ダルそうにして、自分が求める結果にいかに効率的に到達するかが大切だった。大人になって仕事をしてみて初めて、後になってその意味が理解できるということがあると知った。 後半の座談会の中では、おじいさんの懐古主義的な主張が多く、霊的だの何だのはちょっと引いちゃうが、本編は気付かされることが多かった。 それが何の役に立つのか?コストパフォーマンスは?と、何に対しても問いがちな現代において、このモノサシでは測れないものがあるということを忘れずに生きていたい。
0投稿日: 2020.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なぜ学ばないといけないんですか? 納得できる答えがないなら 学ばないという宣言。 それはまさしく消費者が 価値のある商品なら購入するけれど、魅力をセールスしてみせろという問いかけと同じ。 学べる世界が当たり前な環境にいるからこその問いかけ。 学べない環境についての想像はなく、そこにあるのは問いかけた本人が、自身の価値観の正しさを疑うことがない。 歯切れはいい。 未来の自分に対して、投資する意味さえ想像もつかないし したくもない そんな状態。 面白くてすぐ役に立つ そんな性急な授業だけが 選ばれる。 なんの役にたつんですか? この言葉には、楽しくなさそう、努力したくない、時間や費用をかけて 一体どれくらい 目に見える得があるのか?ないだろう、 あるなら してやってもいいよ という傲慢な感情をわたしは感じる。 説得して学ばせる意味はもうそこにはなく、 学びに喜びや満足を感じる人種と 全く感じない人種に二分化されていくのではないか。 また本書には、自分探し として次々と職を変えたり 誰も知らない土地へ行く若者 人々についても触れている。 自分を探したいなら、自分をよく知る人々のなかでじっくり探す 自分に対しての考えに耳を傾けてみるほうが よほど探せる と。 全く同感。 レベルアップしているようで レベルダウンしていることも多々あるのでは? もちろん転職や 生きる世界を変えること全てが間違いだとは思わない。 しかし、学ばない若者 と同様、 実は問題は自らにあるのに 問題を外に求めているところを気づいたら、きっと 自分は 見つかるはず。 そしてまた、今日の教育システムのなかで素直に学んできたなかにも 二分化されつつある と著者はいう。 学ばない若者の項にも通じるが、 試験のためだけの勉強オンリー 合格に役立つ試験勉強以外を、意味のないもの としてきた人々の 合格以降の様子。 昔ながらの上流社会においてのリベラルアーツ 芸術や 他国の文化、文学なんかについて全く話題にできない学生の存在が 少なくないというはなし。 文化資本の欠如という言葉を使って。 自分が文化資本の欠如しているとわからないからこそ努力するモチベーションは上がらない。 そして 二分化は ますます顕著になる。 知らないことを 知ること。 わかっていない自分をはっきりわかること。 そこから学びにつながる。 何のために学ぶのですか? この言葉は、まるで反抗期あたりの不良がかっこいいという程度の価値観に思えてならない。 そして 今後その問いかけを直接耳にしても、何にも言わないだろう。 だってそれは、あなたの人生だからと考えるから。 学びの先に広がる至福な世界を知らないまま、 井の中の蛙でいるのも また選択の自由。 何度も読みたい本でした。
0投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「君が私に就いて学ぼうと思っているものとは違うものを君は私から学ぶことになるだろう。これがこの人を師としたわけだ」
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ【概略】 なぜ、日本の子ども達が「学び」に対して積極的でなくなったのか?なぜ、日本の若者は「仕事」に対して積極的でなくなったのか?その答えは、労働主体と消費主体というキーワードにあった。「それをやることには、なんの意味がありますか?」という言葉の裏に横たわる「学び」とは?というテーマから広がる「学びの楽しさ」の扉。教員・必読の一冊。 2020年03月18日 読了 【書評】 いやーーーー、面白かった!興味深かった! この本は大きく分けて二つの側面に対して広がってる。「学び」と「仕事(労働って言葉の方が合ってるかな?)」という点。この二つについて「子ども・若者」といった若い世代の思考を読み解く形になってる。そのキーワードとして「労働主体」「消費主体」というものが挙げられてる。 教員免許といったものは持っていない自分だけど、「これって意味あるんですか?」なんてセリフ、教える場所で沢山耳にしてきた。自分も使ったことがある、生徒だった時代にね。二次元の観点で見た意味の有無と、「時間」という奥行をつけた三次元での見方による意味の有無、全く違う。これは自分にとっては残念ながら大人になってから実感したのだよね。学生時代に救いがあったのは、この「時間」という要素は、「今は踊り場のような感覚があっても、目の前に記されている説明が全く理解できなくても、時間をかけてこなすことで理解できる」という経験ができていたことぐらいかな。 「学び」というものは、決して「勉強」という言葉でくくられる狭いものではなく、人生における教訓であったり、人格形成に影響する経験であったり、その全てを包括するものだと思う。だからこそ、「今、辛い」「本当、死にそう」なんて状態の「後」、「時間」というエッセンスを加えた自分自身の変化そのものが「学び」なんだという感覚を知っておくといいし、そこに「ストーリー」が形成されるのだと思う。ただし、そうはいっても、「今、まさに」艱難辛苦の状況に陥っている立場の人達にとっては、そんなことを考えていられる余裕などないのが、本当に辛いところ。 本書で語られている「学び」について、連想した2人の発言がある。一人目は総合格闘家の青木真也さん。先日の ONE CHAMPIONSHIP という格闘技団体が開催した試合に解説として参加していて、その解説ぶりが絶賛されていて。後日、別の YouTube 動画で「なぜ、それほどに解説(言語化)が上手なのか?」「逆に他の格闘家が、なぜに上手に解説できないのか?」という質問に、青木さんは、「MMA(総合格闘技の略)の合理化が挙げられる。合理化が進んで、若い世代は、それを型として覚えているから。もっと言うと、無駄な練習をしていないから。僕は無駄な練習を滅茶苦茶している。無駄があるから技術の意味がわかる。今の子たちは無駄を省いているからその技術の持つ次の展開、もしくは前段階、技術の背景みたいなものをわかっていない」としていたのだよね。 さらに二人目、こちらはイチローさん。とあるインタビューで、「無駄なことって結局無駄じゃない。もちろん、今やってることが無駄だと思ってやる訳じゃない。無駄に飛びついている訳じゃない。後から思うと無駄だったということがすごく大事。遠回りすることが一番近道」としています。イチローさんはことあるごとに、このような遠回りに対して「深みが出る」という表現をしているのだよね。 青木さんとイチローさんのこの表現、お二人とも取り組んでる瞬間は、「意味あるの?」とか「無駄なんじゃなのかな?」とか、試行錯誤・思考の材料としては思ったこと、あるかもしれない。その「自らの思考」の先に形成されたお二人の総合格闘家・野球選手としての姿がお二人にとっての「学び」の結果、なのだよねぇ。 もちろん、毎日、なにかしらの結果を出していかないといけないし、生きていかないといけない訳なので、そこはそこで意味を見出していく必要は、ある。けれども、「時間」という奥行を加えた自らの成長という部分に関しては、本書で筆者が語っている内容は、一度、目にしておく必要があると思ったなぁ。 もう一点、「仕事」という部分に関して。こちらについては、本書が出版された2009年の情勢と、2020年現在の情勢、とりわけインターネット技術の革新という要素が、本来の「仕事」という要素を大きく「一見」変えてしまっているところがあり、「学び」の項目ほど「おぉ、目からウロコ!」みたいな感じにはならなかったかな。 根っこの部分、労働主体、そして、自身の満足(当人にもたらす利益)のためという発想のみならず、周囲の人達の不利益の抑制という発想を加えることなどについては、今後も変わることもないと思うし、むしろこれからの時代、ビジネスとしては「周囲の人達の不利益の抑制」という要素を素材にしたら大きく化けるのでは?と思う。 ただ問題は、ここ数年の、労働=自分の時間を差し出す、という概念からの変化とその変化を促進するインターネット技術の革新、なのだよね。もっというと、これからはヘタしたら「どれだけ脳内快楽物質を出せる事柄を自分の周囲におけるか?結果、仕事となってるか?」という時代になるような気がしてね。となると、本書から感じた「仕事=労働(時間を差し出すもの。それは時として自身が望んでいないもの)」という感覚を前提として語ることができない時代になってくるのじゃないかなとね。本書ではニートを生産能力(いわゆるお金を稼げない?)のないようなニュアンスで取り上げていたけど、ヘタすればニートの方が稼いでる時代になってきてるしね。 もちろん、そんな「俺が俺が」な人達ばかりじゃないから、今までと変わらない感覚(誤解のないように。この感覚が悪いと言ってるのではない)で働く人達もいる訳で。そして、さっきも書いたように、「周囲の不利益を抑制する」感覚を「自らの喜び」に変換できる人、バイプレーヤーや縁の下の力持ちみたいな立場の人は、絶対的に重宝されると思うしね。あとは、「自分の好きを仕事にする」ってのは、決して「必ずそれで食べていける」というものじゃないしね。 よく「英語の音読、意味ありますか?」とか「ディクテーション、意味ありますか?」とか、まぁ色々と耳にする(笑)大体そういった質問を受け取る側の方達は、そんな「意味ある?」「無駄かな?」を試行錯誤して、時に無駄だったと顧みて、その方達ならではの「深み」を得てきてる・・・なんてことを、思いながら読ませてもらったよ。 筆者の内田樹さん。本当に自分は不勉強で、「いつきさん」と思ってた。申し訳ないです。「たつるさん」なんだよね。あと、色々なところの発言で、思想的に自分とは合わない箇所もあるのかなぁと思っていたのだけど、どうしてどうして、(少なくとも本書に記されていた点については)合う合う。リスクヘッジの概念や、それに対しての日本人の「正しいソリューションだけを選択し続けなければならない」というくだり、戦争をしていなかったと書くあたり(もちろん、戦争を礼賛してるのではない)や、師匠と弟子の関係を重要視するあたりなど、すごく共感できたなぁ。 人生のバイブル10冊(和書編)の仲間入り!
1投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の社会への対し方が消費者としてのそれであり、その行動原理に忠実に行動することにより、価値判断を行動に先行して行わなければならない。時間変化を加味しなければならない行動であっても、価値判断を先行しなければならず、逆説的な価値判断を要する行動への疑義を唱えるという行動の説明がされている。 時間的な変化を含んだ行動の価値は時間変化後にしか判断され得ないことが逆説的な価値判断であり、その原理で価値を保っているのが、学習である。それの出来ない消費者マインドの子供たちが学習の意義を唱えている。
0投稿日: 2020.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ2005年の夏に行われた講義をもとにしていると本書ですが、2019年の秋でも、批評性は失われていません。そのことを著者は残念と思っているかと思います。 この本は日本人として教養の1つとして、是非、多くの人に読んでいただきたい。 タイトルからは、子どもや若者にフォーカスされている内容と想像してしまいますが、現在の日本全体を覆う、何とも言いようのない、掴みようがないものの正体を、解き明かしてくれています。 経済合理性というものが、世の中のあちこちで聞かれますが、それをそのまま鵜呑みにぜずに一度立ち止まり思考することが大切であるとの気づきが、本書を通じて私にはありました。 皆さまがどのような学びを本書からされるかは、当然ながらそれぞれあるかと思いますが、これまでとは違う視座から見ることができるようになり、物事の捉え方が少しもしくは大きく変わることは間違いないと思います。
1投稿日: 2019.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なぜ勉強をするのか」 「なぜ人を殺してはいけないのか」 その言葉には、 勉強がしたくてもできない人の思いや、 自分が殺される可能性というものが 排除されている。
0投稿日: 2019.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田先生というのは講演したものを本にしているパターンが多いようだが、自分の軸をきちんともっておられるようである。 賛同できるところとできないところはあるが、説得力はある。 思わず納得してしまう。 最後のほうで「日本人は付和雷同なところを活かせばいい」みたいなことを言っていたが、これは面白い発想。見方を変えれば危険な思想でもあるが。
1投稿日: 2019.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ05年執筆で古い内容も含まれてはいるものの、学生や若者の間にある、学びや労働からの逃走という傾向は、現場にいて実感的な内容でした。 なかなか衝撃的な内容です。文化的な格差、考え方、習慣的な格差みたいなものが広がっているのかな、と感じました。 子供たちは幼少期から消費者意識を植え付けられている、たしかに教育にビジネスモデルをそのまま投影することは危険だと感じました。 読んでいて、ここは内田樹が賢いから、体を鍛えた体力ある人だからこういうふうに考えるんだろうけど、と思う事もなくはないですが、ちかごろの生徒の話を聞いていると頭の良さは変わっていないのに、幼い振る舞いが目立ったり、長い目で見る、長期的に考える、そういう視点が抜け落ちている感覚がありました。 なぜ内発的動機だけではいけないか、そういったことも理路整然と書かれています。 学校のしんどさがどこからやってくるのか。 現場にいる人間としては、こちらから見えない社会的要因を俯瞰して若者を語ってくれたことだけでもありがたい。 昔の学校が手放しで良かったとは思わないけれど、何かが行き過ぎて歪んでしまっている感覚、気持ち悪さだけはあったので。
1投稿日: 2019.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強しない、労働しない若者が増えてきていることに対して、述べられた本。 勉強や労働によって発生する不快に見あうリターンが得られないという考えが、勉強・労働に対する拒否を生むと述べている。 特に、教育の効果については数値での計測は不可能だとの主張は納得できた。
0投稿日: 2019.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ賛否両論あるようですが、私は高評価。世間一般論ではない視点。目からウロコ、というよりも、自分の中にモヤーっとイメージであったものを言語化してくれたようなスッキリ感。ニートについては、うーん、まわりにいないのだから、わからないのは仕方ないのでしょうね。
1投稿日: 2019.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでみると、わたしも若い人世代に入る部類なので、ドキッとさせられるものも多かった。 特に、最近の情報量の多いネット社会で生きている自分は、「自分の知らないこと」はスキップするように生きている。すなわち、「なんだかわからないもの」は「ない」という文章にはものすごくハッとさせられました。 無知に対しての不安や不快を感じることが少ないということに気づかされました! わからないことに対してしっかりと目を向けて学ぼうとする姿勢を取り戻そうと思った一冊でした。
1投稿日: 2019.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の子どもと昔の子どもの考え方や捉え方の違いがよくわかった。便利な時代になったぶん損をしてる部分も多いと感じる。
0投稿日: 2019.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私の好きな内田樹氏の本。結論「おまえの小さなものさしを後生大事に抱えながら、世の中すべてのものごとを測って斜に構えてんじゃねーぞ」っていう話。 【どうして義務教育を受けなければならないの?】 義務教育は義務ではなくて、子どもが教育をうける権利があるということだ。教育というのは自分の解釈では学びを得ることであり、それは明日からの行動の変化につながるもの、つまりその人の人生の可能性を広げるものだと思っている。 でもそう思えない人もたくさんいると思う。その人たちには「学びの機会を奪われた想定に立たせる」ことが1つの解決策になる。「なんで義務教育を受けないの?」に真正面から向き合って考えたことがない人がほとんどだろうから。 【「これは何の役に立つんですか?」という傲慢と無知の極み】 本の一節で「20歳の学生の手持ちの価値だけでは計算できないものが世の中には無限にあります」とあったけれど、これは何歳になってもそうだと思う。この質問をする人は、愛用30センチのものさしで世の中の全て、例えば、重さとか光量とか弾力とかすらも、で測れると思う勘違いをしている。 「何の役に立つのか?」という問いを立てる人は、ことの有用無用についてのその人の価値観をおしつけている。大切なことは、その価値観の正しさの根拠について目を向けることだ。 上記2つの問いの問題点は、自分の知っている範囲でしかものごとを判断しようとしない姿勢にあるのだと感じる。自戒も込めて、常に、事象(What)に対してはなぜ?(Why?)で考え続けなきゃと感じた。
0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の文庫版あとがきで泣いた。こんなにも、こんなにも日本のことを真剣に憂え、訴えている人がいるのに、なぜ日本の教育は、経済は、産業は真逆の方向へと進んでいくのか。私は悲しくて仕方ない。
0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと想定している時代背景が古い感はあるけれど、かなり納得させられる本。 日本人は時間をかけて、他者とのつながりを切ってきた。その結果、弱者ほど孤立する国になった。そして弱者は好んでどんどん他者とのつながりを切っていく。 リスクのヘッジの仕方を知らない世代。 教育の場で、他者とのつながりを復活させることの重要さを改めて認識した。
0投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ主張しておられることは概ね合っていると思うのだけど、少し前に書かれたものなのでイマイチずれている部分もある。
0投稿日: 2018.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田節炸裂!の一冊。 今の日本は、大人も子どももなにか焦っている、 より正確には、焦らされている、という感じが しているんだけれど、その理由が本書の中で 「消費主体」というキーワードで理路整然と 説明されていた。 この切り口と切れ味はさすが。 本書のそこかしこに、気になる考え方や表現が あったが、ここではいちばん印象に残った箇所 を抜き書きしておくことにしよう。 聴衆との質疑応答の中で出てきた一節。 "申し訳ないんですけれど、今の方がされた「日本 社会は均質的で、アメリカ社会は価値観が多様で ある」というような言い方って、それ自体が日本人の 均質的ものの見方の「見本」みたいな言葉づかい だと思うんです。失礼ですけど。「だったら均質的 な社会でいいじゃないか」というような横着な物言い の方にまだしも多様性の芽があるわけで、「均質的 だから多様化しよう」という発想そのものがすでに して絶望的なまでに均質的なんです。"
0投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今の格差社会の原因を探る書籍は、その原因を現在の経済システムに求めるものと、個人の精神力、モラルの低下に求めるものに分かれる。本書は、後者である。そして、その精神力、モラルの低下を教育環境に起因すると主張する。で、どうすりゃいいの? こういう主張する人たちの気持ちは良くわかるが、経済システム派の方が、論理的且つ、救いがあるような気がする。
0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ家庭が裕福で働く必要がない若者がニートになるとばかり思っていたが、内田氏の分析では、一生懸命に働いても最低限の生活から抜け出せない親を見て、働くことの意義を見出せないことが原因であると。また幼いときにお手伝いをする「労働主体」としてではなく、「消費主体」として社会に接してしまうために、学びも同様に等価交換を求める。鋭い!
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生の時に父に勧められて、読もう読もうと思ってたけど、結局読むのは大学生になる時でした。お父さんごめんね。ありがとう。まさに目から鱗の教育論でした。
0投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログうん・まぁ面白かったかな。 この作者が、寝ながら学べる構造主義、と同じ作者なのは驚きだけど(笑)。 本論とは少しズレるのだけれども、改めて、昔の家族・親戚関係とかは、リスクシェア(ヘッジ)のまさにその形なのであって、今の「個」の形は、確かに失敗したら結構アウトな仕組みかもしれない。ぶっちゃけ、お墓まで買えないほどの失敗ってあまりないけど、でも、お墓もまぁある種そういうことだったのかも、って、少し思った。 本論としては、最近の学力低下は、教え方がどうとかカリキュラムがどうとかいうのではなくて、最近バカになったとかでもなくて、突き詰めれば、子どもたちの怠惰の帰結であるのではなく、努力の成果である、ということ。 というのは、確かになるほどな、という感じではある。 また、なかなかニューな言説だなと思ったのは、子どもがオレ様になったり、個人主義になりすぎたり、労働に対する評価など時間軸の時間の流れのなかで自分を考えられなくなったのは、一つには幼い頃から消費主体として完成されて、即時的・強い立場の「取引」が当たり前になりすぎたからだというものがある。だから、教育も労働も、不満ばかり。これが何になるのか、正当に評価されていない、という発想になる。 面白かったのは、師弟関係の話かな。 「師であることの条件」は「師を持っている」こと。弟子として師に仕え、自分の能力を無限に超える存在とつながっているという感覚を持ったことがある。ある無限に続く長い流れの中の、自分は一つの環である。長い鎖の中のただの一つの環にすぎないのだけれど、自分がいなければ、その鎖はとぎれてしまうという自覚と強烈な使命感を抱いたことがある。そういう感覚を持っていることが師の唯一の条件だ、と。 p.210
0投稿日: 2018.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書でさらっと読んだだけではあるが、刺さる言葉がいくつかあった。 特に、転職や転校を繰り返す人が、自分のいる場所に文句ばかりをいう下りには納得。
0投稿日: 2018.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びの意味や意義は事後的に考量される 勉強することに一生懸命になれない子どもが増えているのも当然だと思う。知りたいと思ったことが指先ひとつで調べることができる時代において、本のページをめくることはたいへんな重労働ではないか。
0投稿日: 2018.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログやや断定的な主張が目立つものの,初めて触れた考え方に「なるほど」と思ったところも多々あった。 中でも,学びからの逃走・労働からの逃走が「等価交換」の意識からくるものだという主張は自分にとって新鮮だった。 勉強をさせられる「苦役」を代価としてその教育サービスから得られるもの問う。 「それは何の役に立つんですか?」 仕事で得られる給料が自分の払った時間・作業量に見合わない,または,仕事内容が自分の持つ能力に見合っていないという文句。 「給料が安いからここでは働きたくない」 「よりクリエイティヴで,やりがいのある仕事をしたい」 「学びというのは,(略)学び終えた時点ではじめて自分が何を学んだのかを理解するレベルに達する」 何かを学んで,それが何の役に立つのかは実際に学んでみないと分からない。勉強の「苦役」に対して対価が支払われるのにはタイムラグが生じる。仕事にしても,実力が評価されて給料アップに繋がるまでには時間を有する。我々は消費主義における”無時間的な等価交換”に親しみすぎたのかもしれない。 本書のもとになった講演がもう10年以上前だというにもかかわらず, 今でも著者の主張に唸らされるのはどういうことだろうか。 学び・労働という問題にタイムリーに直面している今の時期だからこそ, よく考えていきたいテーマである。
3投稿日: 2017.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ国際的な比較で現代の日本の子どもたちの勉強時間が、とても少ないことは一体どういうわけなんだろうと予々疑問に感じていたのですが、これを読むと納得できます。 学ぶことは本来、自然に湧き上がってくるもので直ぐに成果が出たり形に現れるものではないのですが、戦後の日本社会では物が溢れ、お金を出せば小さい子どもでも欲しいものが手に入るために、消費行動に慣れ、教育もそれと同じ原理だと考えてしまいます。 「学びからの逃走」という表現は、学ばない、働かない子どもたちのこれまでの日本人の価値観と異なる現象を意味しています。学ばない、働かないことが誇らしいとか自己評価の高さに結びつくというのですから信じられない考え方です。 しかし、よくよく考えると内田先生がこの本で解説しているように、教育も日頃の消費行動と一緒の「等価交換」であるとするなら、自分の気に入らない授業などに出席しているのは不快に耐えているということでしかなく、その代わりに好きなことをして過ごしている、ような授業光景が当たり前になるのが道理です。 クレーマーの増加などもこれと同じ現象で、家庭生活での親たちの不快を表現する形が、先に言ったもの勝ちという行動に結びつくということです。 この他にも、ほんとうの自分は何者かなどと自分探しの旅に出かける人の考え方もばっさり切っています。これも痛快でした。 それにしても、今後の日本人は益々劣化していくのでしょうか…憂いを感じます。
0投稿日: 2017.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹の下流志向を読みました。 学ばない子どもたち、働かない若者たち、というサブタイトルがついた若者論でした。 現在問題になっている小学校の学級崩壊や若者のニート問題が、子どもたちが育つ過程で「等価交換」があたりまえになっていることが原因であると考察しています。 子どもたちが育つ過程で賢い消費者であるために有利に等価交換を行うことが自分に有利になると学習します。 しかし、学びや労働は等価交換ではありません。 学校は支払った対価に対してサービスを提供する場ではなく、学校は自分が成長するための場である、ということが「等価交換」を前提として育ってきた子どもたちには理解できないのです。 このため、子どもたちは自分たちの幼い判断基準で学校の価値を判断し、「いまここで勉強して何の役に立つんですか」という質問をすることになります。 労働についても本来労働というものはオーバーアチーブ(得られるものは提供するものより少ない)のが前提となっているのですが、現在の若者は消費主体として労働に対する適正な対価を求めます。 このため、働かない方が消費主体として有利であると判断してしまうわけです。 いま世の中で起きている、何か変だなあ、と思える事象の原因が明確に解説されています。
0投稿日: 2017.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ複数再読。何度読んでも新たな発見がある、ちょっとした古典になるんじゃないかと思う本。著者作品にありがちなブログの寄せ集めでもなく、論旨が一貫している。 この本の次に言えることは、消費者マインドに付け加えて、投資家マインドということも考えるべきだと思う。レバレッジを利かせ、最大限の効果を引き出そうとする精神性を指す。例えば、ネトウヨ。まとめサイトレベルの卑小な知識に、強気や嘲笑といったレバレッジを利かせ、対象を最大限に嘲り、優越感という効果を最大化する人たち。 政権与党もそうだろう。与党政治家達は、自分たちを不誠実な答弁者とは思っていないだろう。政策について少ししか勉強していないのに、はぐらかしや恫喝というレバレッジを利かせ、野党を嘲り一強を演出する、優れた投資家を自認しているはずだ。
0投稿日: 2017.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ構成のほとんどが著者の思い込み、聞きかじり、個人体験によるもので、科学的なエビデンスは皆無に近い。 他者の著作から"引用"したと思われる部分はマシだが、それも引用部分を明確にしていないので著作権法上の問題がある。
0投稿日: 2017.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は「学ぶ」ということは「買い手(教わる立場の者)が、買う物の価値を解っていて買う(教わる)」のではないという考えだ。 教わって初めてその価値が解るからだ。 しかし、消費者として市場の原理で自己を確立している今の子ども達は「価値が解らない=価値がない」としてしまい、勉強を「役に立たない」と切り捨ててしまう。 学ぶ前から価値が解るはずがないのに「役に立たない」と切り捨ててしまうことで、 「学んだことで得られたかもしれない利益」を放棄し、「学ばない」と「自己決定」した不利を未来の自分に負わせているのである。 つまり身も蓋もない言い方をすると、「役に立たない」かどうかは学んで理解するまで解らないんだから先に学んどけ…ということになると思われる。 しかし、現実の子ども達が、単に怠惰の結果として学習しないのではなく、学びから逃走するという「自己決定」をすることで、自己有能感や達成感を得ているのだとすると、教育技術やカリキュラムの改訂といったテクニカルなレベルでは、この問題を 解決できない、としている。 …以上が、色々と本書の面白い箇所や例えの妙を削ぎ落としてしまって個人的に要約してしまった内容となる。 本書を読んだ方が解り易く、面白いこと請け合いなので、扱っているテーマについて気になった方は本書を手に取って読んでもらえたらと思う。
0投稿日: 2017.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹さんの著書は初めてだったが、とても多白かった。なぜ若者は勉強や仕事をしたがらないのか、ゆとり制度の弊害とか、親の経済的な理由とか、いろいろ言われている中で一つもピンと来なかったが、この解説は腹に落ちた。人間にはわからないことの先送りという能力が備わっているが、最近の若者はこの先送りを大量に行っていること、またそのことを無かったことにしていること。6ポケットで育った子供たちは、労働主体ではなく消費主体の人格が小さな頃から備わっているので、教育にしても労働にしても金銭価値に置き換えて考えるようになっている。ゆえに、なぜ勉強しなければならないのか(=それは何の価値があるのか。実は「価値がない」と思っているけどねの裏返し)、一生懸命労働したところで低賃金で苦しい生活が見えているのになぜ働くのか、という基準で判断する。同時に、親や社会の言いなりにならず、自分で判断できる人は自立した人であるとか、先のことはわからないから今を楽しもうという人はカッコイイという価値基準を持っているので、いくら努力を訴えたり、将来のリスクやリターンを語っても効果がない、など。 自分を振り返り、乱読していて思うのは、自分が知らないことは価値がわからないということ。わからないのに「価値がない」などと判断することは恐ろしい。知らない人と話したり、知らない土地に出かけたり、異なる価値観に触れてみたり、芸術、スポーツ、歴史、ビジネス、なんでもそうだと思うんだけど、知ることで成長するし、同時にリスクをヘッジできることになる。これこそが学びだと思うなあ。
1投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい売れてるみたいです。それもそのはず。なぜ子供は勉強を嫌がるのか、なぜ若者は働かないのか、読んですっきりする本なのです。本人曰く、これは世の社長さんクラスの目線で書いた本だと。その目線になりたい人が多いと言うのもこの本が売れた一因なのではとのことですが、そんなことも意識して読んでみるとますます面白いかも。
0投稿日: 2016.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ『学ばない子どもたち、働かない若者たち』 の背景を かなり理解できた。 その現象は 中国にもあるなぁ と感じた。 私は 中国人のもつ向銭主義だと 理解していたが、どうも違うところがあると 納得できない部分だった。 『消費体験→消費主体』が先にあり、 『労働体験→労働主体』が 後にあることで、 『等価交換』という仕組みにならされることで、 学ぶことを 『何のために必要ですか?』と 問いかけてしまう ことから、学ぶことの無意味を 理解してしまった。ということが、 内田樹の『仮説』であり、今の状況を説明可能だと思った。 家事労働の需要性、どんどんと家事労働がなくなったこと。 父親の職場が 理解できないこと。 そして、不機嫌がお互いの等価交換となっている。 家族は 『不機嫌』であることを 競い合う。 『知らないことを読み飛ばしていく』 『知らないことを知ろうとしない』 今まで、『無関心』ということがなぜ起こるのか? ということに対しての 氷解があった。 確かに、知ろうとしない ところがあり、関心がないで終っている。 情報の洪水の中で、自分の好きなことだけ、見ていると 結局は『無関心』になるのだねと思った。 なんにでも 食いついていく 私の好奇心とは違うようだ。 『ニート•ひきこもり』が 省エネルギー生活だというのは、 確かに、そうかもしれない。 しかし、なぜか 恐ろしい時代が来ているような感じがする。 ニートが 増殖するひとつの要因に 『自己責任 自己決定』ということがある。 それを 「ニートになったやつは自己責任だから、勝手に飢え死にしろ」 ということで、ますます 増殖する。 一人では成り立たない社会である認識をつくれるようにする。 内田樹は『ニートを孤立させてはならない』と言う。 学ぶ意味をなくすことで、働く意味もなくしてしまうというのは、 マイナススパイラルの 人生になっている。 負担が大きくなったり、責任が重くなったりすれば、 そこから、逃げていくというのも、ひとつの現象なのだ。 それが、なぜなのか?と思っていたが、 そんな根底的なところから、問いかけられていることに すこし、絶句しなければならない。 中国における一人っ子政策において、 子供への負担が多すぎる。かなりの詰め込み教育の中で、 とにかく宿題が多い、落ちこぼれ現象が 生まれている。 親は 熱心であるが、 それが 更に子供へのプレッシャーになっている。 これが 学ぶことへの逃亡をうみだすきっかけににもなる。 確かに 学ばない学生がいて、働かない人がいる。 その現実をどう変えるのか? とにかく、仮説を 実証することから始めなくては行けない。 教育は、『等価交換』ではないという認識と実践。 時間的視点でモノを見る ことの実証的な方法論が 必要だ。 何れにしても 消費主体 であるものを 労働主体 にかえる。 何か、雲をつかむような むつかしさが 横たわっている。
3投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ下流志向 内田樹14冊目 今回は主に教育論・労働論。 ・学び 学びとはそれらのものが役に立つかまだ知らず、自分の度量衡では価値が図れないものを得ようとする、もしくは価値が分かるようになるということなのである。しかしながら、現在の子供は「これは何の役に立つんですか」という問いをはじめ、ビジネスマインデットに学びを考える。何の役に立つのかを知るために学ぶのだから、わかるはずないし、その答えは受け手の数だけある。そして、学びとは、母語の習得からわかるように、すでに遅れている状態からはじまり、何のことかわからないながらも聞いているうちに、あるパターンが導き出され、意味のある記号に変わり始めていくというものなのである。そもそもどうしてこのような子供が増えたかといえば、自らを労働主体としてではなく、消費主体として形成したからであるというのが内田の論旨である。つまりどういうことかというと、消費主体としての自己は、お金の透明性により、主体が何であれ一人の自己として認められる。つまり、買い手として、商品の価値を決める(知っている)という状態が骨身にしみついてしまい、自分の価値のわからないはずのものにも、あたかもわかるように接し、値踏みするようになる。消費は、自分が買う瞬間とそれを使うときの価値の変化を意図的に無化している活動なのであるという点で、無時間的な行動だが、子供はその習慣により、学び始めたときと学び終えたときの自分が変化しないというルールに自ら縛られている。 ・共同体 自立とは、属人的な性格ではなく、その人の判断や言動が適切であることが確証されたときに周りから補助や連帯を頼まれるということであり、集団的経験を通じて事後的に獲得されるものである。これに対し、今の日本は、だれにも頼られず、だれも頼らない自立した自己を美徳とする節があるが、これはリスクヘッジが全くなっていない。 なぜリスクヘッジしないかと言われれば、損失が目に見えないからである。自分が何かすることで集団にプラスになり、自分にとってもプラスになることはやるが、誰かがやらないと集団にとって、ひいては自分にとってマイナスになることをやる人がいま、いない。プラスはわかりやすいが、マイナスは可視化しにくい。マイナスを可視化し、それを防ぎ、維持のためにコストをかけられる人が、集団の中で必要とされる自立した人間である。このように、マイナスを可視化できないのは、企業の評価において、30年間つぶれなかったことよりも、1年間で何%収益を上げたかということの方が評価される傾向があるからである。維持のためのコストと、リスクヘッジ。ビジネスマインデッドならわかるはずのことが消費主体として生きる人にはわからない。むろん、だれにとっても正しい選択をするに越したことはないが、それを決めるコストの方が高くつく場合が多い。最高の2時間の映画をゲオで探しているうちに2時間探し続けてしまったという本末転倒な事態が起こるのなら、初めからそれなりに面白い映画を借りて2時間見るほうがよい。今の日本には、「それなり」がなかなかできない。これはとてもうなずける。バレーでも、どのフォーメーションも完ぺきではない。グダグダ話さずに、欠点を認めつつそれなりでやっていくうちに、うまくまとまっていくものではないか。 ・師 師を持っている人が、師となれる。自分が師を超えたと思った瞬間に人の成長は止まる。逆に、自分はまだまだこの人には勝てないなと思っている間は何歳でも生き生きと成長できる。もともと、師弟関係でも、師は体力的に老いるし、弟子の方が強いということはかなりありうる話である。しかしながら、弟子は師を尊敬し、いうことを聞く。それが学ぶということで最も大事なことである。弟子がなぜ師を尊敬するかは単純な問題であり、それは師が自分の師を尊敬している姿を知っているからである。尊敬しているという行為を教えられなくても、師が身をもって行うことで、弟子はそれに倣う。数学者の藤原正彦さんの本に書いてあったが、数学者が育ちやすい地域の特徴に、宗教的でもなんでも何かを崇拝するということがあるという。絶対的なものに対し、ひれ伏し、自分はまだまだだと思っているうちは自分でも驚くほどに成長できるのである。ニュートンは神の存在を信じ、神の摂理を証明するために科学を研究したといわれるが、かつての西洋にもビジネスマインデッドではなく、何かをひたすらに尊敬して、謙虚でいる文化は十分にあった。 少々拡大解釈したがこんなところ。
1投稿日: 2016.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論「等価交換で考えているようではだめ。ファイナンス的思考で教育は考えるべきだ」ということ。 とても納得。「なんで勉強する必要があるの?」という問いはナンセンス。無駄しないで生きようという考え方を自分がしていただけに、気づきが大きな1冊でした。 ・労働は私事ではない。労働は共同体の存在の根幹にかかわる公共的な行為。だから、仕事をするしないというのは、自己決定によってしたりしなかったりできるものではない! ・どうしはこの額壊死は「矛盾」という文字をこれまで20年間の人生、読まずに済ませてきたのか? 本を読まなくなったと片づけるのは簡単だが、実際いろんなところで目に触れているはず。 →おそらく彼女は、その文字を読み飛ばしている。 →意味がわからないことにストレスを感じない(無視すればすむという考え)。意味がわかるまで調べて、無意味なものを意味あるものにすることはしない。無意味なものがあっても気にしないという心理機制を採用する。 →この結果として鈍感になるという戦略を採用し、結果学力が低下している。 ・どんなに動かぬ証拠があっても「やってねえよ」と突っぱねる。まずは、ふっかけてから等価交換(損しないように)することに重きを置く。 →その背景には、お金があれば、子どもでも大人から同質のサービスを受けられるという消費体験から社会と接点をもってしまっているところが大きい。 昔は家庭という最小の社会関係の中に仕事があり、それをする対価としてのお小遣いがあった。 →教室は不快と教育サービスの等価交換の場となっている。家庭でもそう。不満をもつものが偉い、癒される、慰めてもらえると思っている。 仕事がつかれたという夫、家事が大変という妻、勉強が忙しいという息子。疲れているものが勝者。 ・義務教育というものを、今の子供たちは、教育を受ける義務があるという理解をしている。これはもちろん間違いで、子どもには、教育を受ける義務はない。子供には教育を受ける権利があるだけ。 教育を受ける権利は、子ども達にとって、その人生の可能性を広げるための、もっとも大切な権利。その権利について、当の子供たち側から、「どうしてこんな権利を行使しなければいけないの?」という問いが差し出されることを日本国憲法の起草者だって想像していなかった。 →自分たちがそのような問いを口にすることができることそのものが敵視的に見て超例外的であることを彼らは知らない。 →人を殺していけないのはなぜか?というのは、自分が殺される可能性を勘定にいれていない。同じように、どうして教育を受けなければならないのか?という小学生は、自分が学びの機会を構造的に奪われた人間になる可能性を勘定に入れていない。 ・自分探しの旅。自分のことを知っている人間がいないところなら、どこだっていいんです。要は、今の自分の評価に不満がある人に多い。自己評価と他己評価のずれ、こんなんじゃないのに...という評価を受けている人に多いのでは? 本当の自分が知りたいなら、自分のことをよく知っている人たちにインタビューをしてみるほうがずっと有益 ・これは何の役に立つんですか?という傲慢と無知の極みの質問。 20歳の学生の手持ちの価値の度量衡をもってしては計算できないものが世の中には無限にあります。彼らのたとえは、愛用30センチのものさしで世の中の全てをはかろうとしている子供たちに似ている。 そのものさしでは測れないもの、例えば、重さとか光量とか弾力とか、世界のすべてをものさしで測れると思っている、勘違いに似ている。 「何の役に立つのか?」という問いを立てる人は、ことの有用無用についてのその人の価値観の正しさをすでに自明の前提にしています。 「私」が起用している有用性の判定の正しさは誰が担保してくれているのか? ・子供たちが自信をもつのは、彼が属する社会集団において支配的な価値観に合致するとき。 つまり、美術や音楽について感覚の優れている子供がいたとして、彼が芸術性に高い評価を与えられる集団に属していれば自信をもてるが、運動能力やビジネスセンスに高い評価を与える 集団に属していればあまり自信を持つことはできない。 ・青い鳥を探しに行く人たちには、どうも雪かき仕事にたいする敬意がいささか欠けているのではないか?そのような散文的な仕事に対する嫌悪や侮蔑に動機づけられて、ここではないどこかへふらふらとさまよい出してしまう。 若い人がよいいう、クリエイティブでやりがいのある仕事というのは、やっている当人に大きな達成感と満足感を与える仕事。でも、雪かき仕事は、当人にどんな利益をもたらすかではないくて、周りの人たちのどんな不利益を抑止するかを基準になされるもの。
0投稿日: 2016.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
教育から逃避する子ども。 労働から逃避する子ども。 労働主体ではなく、消費主体として教育サービスの受けてとなった子どもは、教育を不快、苦痛と取引される等価価値だと見なし、それを拒否することで自己決定権を保とうとしている。 ニート問題。 自分の労働が即時に財貨で評価されにくい、もしくは、評価に納得がいかないこと。 この人の務めるお嬢さま大学は、昔は花嫁修業の場みたいなもんだった。いまは、やはり実学じゃないと、高い学費をかけたが労働で回収できない学生が増えるだけだろう。 指摘はするどいけど、これまでニートだった人は税金で救うが、これからニートになる人は増やさない方向で、というのは無理がある。だってロスジェネ世代以降がニートの最大層。下手するとすでに50代もいる。どうやって、若年労働者層で支えるのか。 この人がニートを雇って働かせてくれるのなら別だが。
0投稿日: 2015.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分のことは自分がいちばんよく知っているというのは、残念ながらほんとうではありません。「ほんとうの私」というものがもしあるとすれば、それは共同体的な作業を通じて、私が「余人を以って代え難い」機能を果たした後になって、事後的にまわりの人たちから追認されて、はじめてかたちを取るものです。 それは上層家庭の子どもは「勉強して高い学歴を得た場合には、そうでない場合よりも多くの利益が回収できる」ということを信じていられるが、下層家庭の子どもは学歴の効用をもう信じることができなくなっているということです。ここにあるのは「学力の差」ではなく「学力についての信憑性の差」です。「努力の差」ではなく「努力についての動機づけの差」です。 教育の「権利」と「義務」と読み替える倒錯が起きた理由は、経済合理性の原則が社会のすみずみまで入り込んだせいです。子どもたちが成熟の最初の段階でまずおのれを「消費主体」として立ち上げるというようなことは歴史上初めてのことです。それは単に生活が豊かになったとか、物質的欲望が亢進したということではなく、そのさらに以前の問題として子どもたちが「時間」と「変化」について自らを閉ざすように、幼くして自己形成を完了させてしまったということです。 でも、ここには日本的な評価システムについての上司と部下の意識の「ずれ」もかかわっています。日本の勤務考課システムでは、有能と評価された部下にはただちに賃金を上げるというかたちではなく「もっとむずかしい仕事」「もっと重要な仕事」を与えるというかたちを迂回して測ることができた。でも今の若いサラリーマンの中には、自分の方が同僚よりも困難な仕事が与えられると、それを自分の能力に対する評価としてではなく、単なる迷惑として受けとめる傾向があります。 経済合理性というのは、その経済活動に付随するもろもろの人間的価値を排除してしまう。だからすごくすっきりしている。でも、視野から排除されたせいで致命的なダメージを受けたものってたくさんあると思うんです。教育もそうだし、労働もそうだし、育児もそうだと思います。児童虐待の事例がだんだん増えてきていますけど、これは育児を等価交換で考える習慣の必然の帰結ように私には思えます。育児ってすごく時間のかかる仕事でしょう。でも、今の若いお母さんって育児をロングスパンで考えることができない。すごく短いスパンで考えている。それはおそらく育児をビジネスの用語で考えているからだと思うんです。自分の子どもは自分が作り出した「製品」であり、親の「成果」は「製品」にどんな付加価値を付けたかによって査定されると考えている。その成果が評価されると、親は育児の「成功」というかたちで社会的な自己実現を果たしたと考える。メーカーが工場から送り出した製品の売れ行きや評価に一喜一憂するのと同じメンタリティです。 時間は現在・過去・未来という順序で不可逆的に進行しているわけじゃない。未来までたどりつけないと過去は確定できないし、過去が確定されないと未来は成立しない。時間というのはそういう高速度で往還する力動的なプロセスなんです。それは音楽を聴くという経験を考えればわかります。音楽を聴いてリズムやメロディを味わうことができるのは、「もう聴こえなくなった楽音」がまだ残響していて、「まだ聞こえない楽音」の予感がするからです。今この瞬間に聞こえる楽音だけでは音楽は成立しない。過去の音がいまだ過ぎ去らず、本来の音がすでに予感的に到来している、そういうダイナミックなプロセスの中にある時しか音楽は音楽にならない。
0投稿日: 2015.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ論旨がはっきりしていて、非常に参考になった。 子どもたちは消費者としてのアイデンティティを持ってしまったがために教育を等価交換で得ようとする。等価交換というのは無時間モデルであり、それを行っている過程では、消費主体は決して変化してはならない。教育や労働でのリターンはあとからやってくるのだが、その時間のズレに耐えられなくなっている。学びからの逃走、労働からの逃走とはおのれの無知に固着する欲望である。
2投稿日: 2015.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほどなあ~と思う考え方が多かった。特に、幼いときから消費社会で生きているから、等価交換の考え方がしみついているというのは、納得した。
0投稿日: 2015.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ教員からの意見、という視点は私は持ち合わせていなかったので面白く読めた。 思想を研究していることも相まって、論理的思考が歴史的背景から説明されているのは面白く感じた。 教員資格を取ろうと考えているひとが読むとより一層楽しめる内容に思えた。
0投稿日: 2015.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身が「未来を売り払う子ども」であったこと、「リスクをヘッジできない大人」であることに気づかされた。一方で、結局は恵まれた人の上から目線の本という印象があったのも事実。
0投稿日: 2015.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ[読むきっかけ] いま田舎の個人塾を手伝ったり、田舎の飲食店で10代〜ハタチ前後と働いたりしているなかで、彼らの環境や思想に世代なのか地方特有なのか、私との差異を感じたため。 150707-150715読了。 面白い視点がいくつもあり、なるほどなと感心すること多し。 一方で、なんだ論点先取で非難しているだけじゃないか、勘違いはだはだしい、という反発心が起こる点もいくつかある。 せっかくだから勢いで書いてみる。 生き急いでいる人にもっと先を見ろと言うのなら分かる。 しかし、人は有限の時間に生きていて、すべてを選択することはできないのだから、常に今その時点で判断しうる最善の選択をしようとするのは若者に限らず、すべての人間の性質である。 その若者の切実な未来時間の使途として「(ほかでもなく)現代思想を学ぶ意義は?」の問いに言葉を失ってしまう著者は、無限の時間でもお持ちなのだろうか。 今あるものさしで世界を捉え切れるわきゃないだろう。だからって今あるものさしで目の前の世界に入るしかないのだから、今あるものさしで判断するしかないだろ!プンスカ!テキトーなこと勝手に言いやがってー!所々面白かったけれどもー!
0投稿日: 2015.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学びからの逃走」としての学力低下問題と、「労働からの逃走」としてのニート問題を掘り下げ、その核心に迫る試みです。 現在の教育問題の根本にあるのは、子どもたちが自身を労働主体としてではなく消費主体として捉えていることだと著者は言います。子どもたちは、学校という場所においても「教育サービスの買い手」としてのポジションを取ることになります。彼らは、教育サービスの対価として「不快」を払い、そのことを示すことで教師に対して戦略的に優位な立場に立とうとします。こうした考え方が、無意識のうちに現在の子どもたちの行動を規定していると、著者は考えます。 しかし、学びの本質を、等価交換の枠組みで理解することはできません。学びとは、自分が学んだことの意味や価値が理解できるような主体を構築していく生成的な行程だと氏は言います。事前に学ぶことのメリットを評価してそれに見合った「不快」を支払うような、時間的に変化しない主体を前提とする経済合理性に基づく消費者の立場からは、その意義を捉えられないと述べられます。 さらに著者の議論は、人類が最初に異なる部族の間で沈黙交換をおこなったとき、等価交換というシステムは確立されていなかったというところにまでさかのぼっていきます。むしろ、何かを「贈り物」として認識し、「ゲームはもう始まっている」と思い込んだ人が生まれることで、初めて交換というゲームが成立することになります。気がついたときにはすでに贈与の義務を負うプレイヤーとしてゲームに参加しているというのが、交換というゲームの基本的な構造です。 こうした著者の考えは、いわば「メタ労働主体」というべきプロセスに光を当てたものとして理解できるようにも思えるのですが、著者自身の議論はあくまで、ゲームを生きている主体の観点を離れて、理論的な上向へと進んではいません。
0投稿日: 2015.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに引かれて購入。 勉強しないのは?今までの選択は、正しいのか? 読了後、妙に納得してしまう。 「嫌われる勇気」の本を、以前、読みましたが、比べてみると面白いかも。
0投稿日: 2015.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ傾聴に値する論考を続ける内田先生の10年前の講演の内容ですが、そこで論じた問題が解決するどころか安倍政権のもとでひどくなっているのを感じます。 ただし、自己決定に頼り親を師としない私の生き方も、この問題に含まれているのがわかり、剣先を突きつけられた気がします。
0投稿日: 2015.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログいろんな要因が混ざり合って生まれた問題を、分かりやすく説明してくれる。時間の経過を無視して何かを得ようとする、この姿勢が危ないと指摘されていた。 読みなれないジャンルだったけど、面白かった。
0投稿日: 2015.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びからの逃走、労働からの逃走というのが本書のテーマになっている。けれども、もちろん全ての子どもたちが学びから逃走しようとしているわけではない。「相対性理論てなに?」ときいてきた中3男子がいた。しばらくすると、今度は「いま相対性理論の本を読んでいる。お父さんが持っていた。」という。私もついつい付き合って、光速に近づくと・・・とか、太陽の重力で光が曲げられ・・・などという話になってしまった。(学生時代に一応半年間講義を受けたはずだけれども、いま話ができるのはこの程度のレベルだ。)あまり、勉強が好きそうでない中2女子。休み時間に本を読んでいるのでのぞきこむと、「変身」東野圭吾ではなくカフカだ。「へー、そんな本読むんだ。おもしろい?」「私こういう話好き。」それらは、ちょっと特殊なケースかもしれない。もっと、ふつうに一生懸命勉強をする生徒がいる。学校が休みの日など、早くから出てきてずっと自習している。ときどき質問に来る。一人はちょっとドキッとするような難しい問題、もう一人は「まだこれわかってないの・・・」というレベル。いずれにしても、どうも学ぶことが楽しいようだ。たまたま私のところに来ている生徒がそうだということではないだろう。もちろん、授業を苦痛としか感じていない子どももいるに違いない。けれど、決してそれで全てを語りつくしたことにはならない。最近の中学生も捨てたものではない。大部分で確かにそうだなあと納得しながら、一部分ではいやいやそんなこともないよ、などと感じながら本書を読みました。
2投稿日: 2014.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ下流を選択的に志向するには理由がある。 リスクに対する考え方についてなるほどと思えた。 即時的即物的な生き方と時間を考慮した俯瞰的生き方。 再読したい。学生はどう考えるかな。
0投稿日: 2014.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログとても示唆に富んでいて面白かった。 特に、第一章の「学びからの逃走」は、学びを拒絶する子どもの心理的経緯が非常に興味深かった。 消費社会がこんなところにまで影響しているんだなと驚愕した。 また、教養のある人の存在を知らないことで、皆自分程度と思ってしまう怖さ。 確かに文化資本の豊かな教養のある人に出会わなければ、そんなことに思い至る術はないと思うと、置かれた環境の大きさに慄然とする。 教養のない人は、もしかしたら自分だったかもしれないのだ。 「師であることの条件」は「師を持っている」ことというお話もとても興味深かった。私は師でもなければ、師と仰ぐ人もいない。 だから著者の言わんとしていることの半分くらいしか理解できていないと思うが、上記の言葉は非常に重要なことだと感じた。 先日読んだ「日本人はどう住まうべきか?」でも語られているように、もう少し長いスパンでものごとを考えることが大切なんだろう。 そして、消費社会は即物的な思考に陥りやすく、そこに留意したい。
0投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ学びを権利でなく義務と思う、出世を嫌がるなど、この本で説明している「若者」はまるで自分のことを指しているかのようと感じた。はじめに消費者としての立場を確立したから、という説は面白い。もう一度読み返して身につけたい本です。
2投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014.10.20 ~P.59 学校教育が何の役に立つか。この難問に対して己の回答を見つける過程の履歴こそが学歴の本質である。自分で勉学に対し前向きな目的根拠を持つ事。学びの中でしか人生は存在しない事が見えてくる筈だ。 2015/06/27 読了 現在、教育や労働から逃走中である社会的に弱者とみなされた集団に私自身も属している事もあって、本書に書かれた内容に予想外だが啓発された部分はかなり大きい。今やっている事に何の意味があるかと自問を繰り返し、やってる事に対する報酬が割に合わないとか、誰も俺を理解してくれようとしないと不満を募らせたり、結局、自分はユートピア主義だっただけなんだと見透かされているようで、天地が開闢するような視点の逆転を体験した。人との関わりは確かに煩わしいし、自分のやりたい事の障害にしか思われない部分もあるけれど、人と関わることで生き死にに関わる危険リスクをヘッジ(回避)できたり、思わぬ励ましやヘルプを差し出して貰える事も、大いにあるのではないか。助け助けられる相互扶助的な関係を作れるのは生活個人ではなく社会集団においてでしかない。 尊敬できる人間を身近に持つ必要性と重なってくるが、等価交換を人間関係に適用したりすると全ての関係は破綻するし、何故に尊敬するかと云う基準さえ本当は必要ではなく、これまでの人間が歩んだ歴史に対して頭を下げるのであっても良い訳だ。自分の殻に閉じこもる事のリスクは、人から伝えられるものの素晴らしさを味わえない事が一番大きいのではないだろうか。どんなに引き籠もりをしようとしても、誰かが用意してくれた揺り籠の中でジッとしてる以外に居場所はなく、誰かに迷惑を掛けている自分を何処かで必ず認めなくてはならなくなる。勿論、人と関わることで嫌な経験を堪え忍ばねばならぬ時もあるだろうし、対外的な危険度はそれなりに高まる事はやむを得ない。それでも、人との中でしか、何かを作り上げたり、育てていく事ができないとすれば、自分自身を行動する主体として、世の中に対して立ち上げる意義は大きいのだと思われる。 たった短い期間であれ社会の中で働ければ、働く者としての悩みや苦労も味わえるだろうし、そこで自分の声を上げる機会だって巡ってくるに違いない。ネットに文章をアップする事は誰にも阻害されない点でコミュニケーションとは呼べないのではないか。社会の只中に身を置いて、行動しながら発言していく事にこそ本物のコミュニケーションがある。勿論、組織の中に停滞する硬直した習慣の押し付けや有無を云わさぬ不条理な業務命令も横行しているし、現場の地獄を嫌ほど味わう事になるかもしれない。しかし、自分の真の声を、巡り巡ってきた何処かのチャンスで発信し、社会にまかり通っているおかしい何かを改善させる事に繋がれば、立派な社会行動だと認められるだろう。その意味でも、私も何らかの形で社会復帰して、様々に被ってきた恩を少しずつ返したいと思っている。 決して、働いたり学んだりする事から自分を完全に切り離してしまってはならない。本書からは、そのような強いメッセージを受け取った。まだ、人生はこれから。希望や勇気を沢山この本から頂いた。だから、自分が弱っていると思っている方々には本書を紐解いてみて欲しい。そして、再び停滞した孤立状態から一歩でも歩み出せる事を期待している。弱い者同士は連携し合わねばならない。社会に立ち向かっていく為の基礎を共に築かなければならない、そのように私自身は考える。自分の殻に閉じこもるのは、本当に危険なのです。行動しながら幾らでも自分のことは考えられるし、次の一手を打たねばリスクは再び我らを襲うでしょう。連帯こそが社会の中で一番の武器になります。まずは、自分に出来る事で誰かを救ってあげましょう。その為には、日頃から必死に社会と自分自身の現状や問題点を考え続けなければなりません。冷静になって思考を重ねられる安全な環境をいち早く構築しましょう。まだ言い残している事は沢山あるだろうけれど、いま述べられる私の考えは、以上になります。
4投稿日: 2014.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なるほど」と「そうかなぁ」を行き来しながら読みました。 考えるきっかけが豊富にある、という意味で読みながら濃密な時間を過ごせた一冊でした。 「不快」は「貨幣」として流通する、という考え方がおもしろかったです。 不快さを競い合うなんて、変だなぁと思いつつ、確かに一番不機嫌な人が場のコントロール権を握っていることも多いなと思いました。 また、「リスクヘッジ」についての考え方も、専門職として自分が行っているのはこれだったのかなと思いました。 「文化資本」の格差についても言語化されることで腑に落ちる感じがしました。 言葉が与えられると、経験やぼんやりと想像していたものが整理されていいな、とも感じました。 子どもの臨床場面において、目の前で起こっている現象の解釈のひとつとしてこの視点を持っておけるといいかもしれないと思いました。
0投稿日: 2014.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ売れている本のようなので、読んでみた。が、何故、売れているのか、さっぱり分からない、というのが正直な感想。確かに共感できる部分もあるにはあるが、ほとんどが共感できない。論理が飛躍しすぎているというか、単なる著者自身の勝手な思い込みとその理屈づけ。理論に裏付けられたものでも、経験に裏付けられたものでもないという印象。でもって、ふと著者名を見て、そういえば前に読んだ『街場の大学論 ウチダ式教育再生』と同じ著者だと気づいた。成る程ね、と納得。。。
2投稿日: 2014.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか本を読む時間がとれなくて、1ヶ月かけてようやく読み終わりました。。。 なぜ勉強をしなければならないか?子供にそれを理解させるのは経験・知識が不足しているってことですね。それが理解できるようになるために勉強するのですから。なかなか興味深い本でした。
0投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学ばない子どもたち 働かない若者たち」の根底にあるものを、鋭く、わかりやすく述べている。 若手に対して研修をすることが多い立場として、納得ができる点が多い。勉強や仕事に対価を求める姿勢そのものの問題であることが多い。 若手も若手を教える大人も、ぜひ読んでほしい。
0投稿日: 2014.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の教育・労働に斬り込む作品。進んで教育を受ける権利を放棄する?積極的に労働しない?その背景に潜む考え方とはなにか。 ものごとは、長い目で見ることも必要。そんな、現代の人々が忘れているかもしれない感情を湧き上がらせる一冊。
0投稿日: 2014.05.05教育崩壊の実態
なぜ子どもたちが学びを放棄してしまうのか。 教育現場で起きている「学ばない」という問題の原因が分かりやすく書いてありました。 学校教育の制度、特に公教育の制度が根幹から揺らいでいることを感じさせられます。より良い次世代を、より良い社会を創り出し発展させていくために、そもそもの学校というもののあり方を議論してもいい時代に来ている気がします。
1投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の若者の価値判断が「消費主義」、「経済的合理性」に準拠している。 鮮明な切り口で論じられた、新たな若者論。 現代の若者にとって、生まれて初めての社会的行動は「消費」となる傾向にある。つまり早い段階で消費主体になり得る。(かつては家庭内労働) ここで問題になるのが「消費主体」とは「他者からの承認に先立って貨幣を手にした時点ですでに主体性を確信し終えている」ことである。 そして、若者は消費行動において可視化可能な「経済的合理性」を取り入れる。 授業であれば、自身の時間という貨幣と教師の授業の面白さを天秤にかける。 後者が勝ればきちんと授業を受けるが、それに値しないと判断すれば授業を受ける必要は無いと考える、何故ならそれは「等価交換」ではないからだ。 このような思考が、「労働」と基本的に相容れないのがニート化の一因になっている。何故ならば労働とは本質的に不等価である、つまり自身の労働量以上の利益を確保して成り立つものでだからである。 筆者は、ニートを紋切り型に批判せず、「ある時代の支配的イデオロギーの被害者」と分類する点も興味深い。 ふと若者の言動を省みてみると非常に納得のいく内容であった。 何故勉強しなければならないのか?それは自分にとって利益になるのか? 明確な、可視化出来る利益を信仰し、自身の合理性を突き進む彼らに対して、どのような対策が講じられるのか? 課題は浮き彫りであるが、その答えはこれから模索しなければいけないのだろう。
2投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時間に関する指摘(教育はそれが自分に与えるものが与えられるまで理解されない=時間による成長の効用)は吉田健一の「時間」にそのものずばりの文章があり両者に感心した。
0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
労働主体としての非こどもから保護の客体としての子どもへ,という流れは一般的なものだが,そこで内田は「消費主体」としての子どもという像を提示する。これは,保護の客体から権利の主体へ,という流れの中で生まれたきた子ども像の一つであろう。すなわち,教育の権利,労働の権利を自明のものとして,それを行使しないことが「自己の意思に基づいた選択」であれば正しい,という考え方だ。内田はこれに警鐘をならし,教育は受ける前のその価値の時間軸的評価ができないということを示し,保護主義的・パターナリスティック的な議論を打ち立てる。 p126「現代日本人は,「迷惑をかけられる」ことを恐怖する点において,少し異常なくらいに敏感ではないかと僕は思います。「迷惑をかけ,かけられる」ような双務的な関係でなければ,相互支援・相互扶助のネットワークとしては機能しません。「誰にも迷惑をかけていないんだから,ほっといてくれよ」というのは……他人に迷惑をかけたくないからそうしているのではなく,他人から迷惑をかけられたくないからそうしているのです。自己決定について他人に関与されるのが煩わしいので,「あなたの生き方にも関与しない」と宣言しているのです。 p128「孤立した人間」⇒学びからの逃走(学ばないことのリスクは自ら引き受ける) <ー>「自立した人間」:自立というのは,集団的な経験を通じて事後的に獲得される外部評価です。ですから,「自立した人間」は,……多くの他者に取り囲まれています。そのネットワークの中で絶えずおのれ地震を造形し,解体し,再改訂し,ヴァージョン・アップするのが「自立した人間」 p140「自己決定したことであれば,それが結果的に自分に不利益をもたらす結果であってもかまわない」=自己決定フェティシズム ⇒「私はわたしの運命の支配者である」という自尊感情のもたらす高揚感が間違った選択肢のもたらす心身のダメージをカバーできるかぎり,自己決定は有用である ……ここでいう「間違った」とはどのような基準か? P142「『自己決定することはいついかなる場合でもよいことである』という信憑が社会全体に根付いている社会では,自己決定は多くの+をもららす可能性が高い。でも,そうでない社会はそうではない。そして,日本はそういう社会ではない。」 ……単純にすぎないか。近年の社会変動を十分に考慮していないのではないか。 p182「知性とは,詮ずる所,自分自身を時間の流れの中において,自分自身の変化を勘定に入れることです」「無知とは,時間の中で自分自身もまた変化するということを勘定に入れることができない思考のことです」「学びからの逃走,労働からの逃走とは,おのれの無知に固着する欲望であるということです」
0投稿日: 2014.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜニートが増えるのか。学ぶことや働くことから逃げる若者が増えてきているのかを真正面から取り上げた本。説得力があるし情熱を感じる。しかし、何となく背筋が寒くなり、「じゃあ、どうしたらいい?」って考え込まざるを得ない問題提起である。 代償と利益のバランスを考えた時、苦労して勉強をしたりがんばって働くことは割に合わない、って思う感覚はわからないでもない。「理由なんかわかんなくてもいい、とにかくやれといわれたことをやれ」というのは今時通用しないし、僕自身も疑問を感じる。 しかし、確かにそういう問答無用が必要な部分はたくさんあるし、特に教育などというのは、そういうことを前提にしてるのは、注意深く考えてみればわかることだと思う。 そういう価値観のようなものが時代の流れの中で変わっていっているとすれば、学校の先生がどんなにがんばろうが勉強しない子どもは勉強しないことになる。おそらく、「あの先生がおもしろいって言っているなら、今の自分はおもしろいと感じないけど、やってみる価値があるものだろう」と思ってもらえるような魅力を、ひとりひとりの先生が持つしかないのだろう。そしてそれは、流れる激流を上流に向かって泳ぐような困難なことのように思える。 でも考えてみれば、自分自身も「なんでこんなことするのかさっぱりわからない」といいながら、苦労することから逃げ回っていたような気がする。でも、結局本当に逃げ切ることなんかできもせず、適当にあきらめたり折り合いをつけたりしながら大人になったのだろう。そう思うと、実は若者の方の変化がそれほどあるわけではなく、「逃げ切ることができてしまう」くらい、表面的には豊かになったということなのかもしれない。
0投稿日: 2014.01.31
