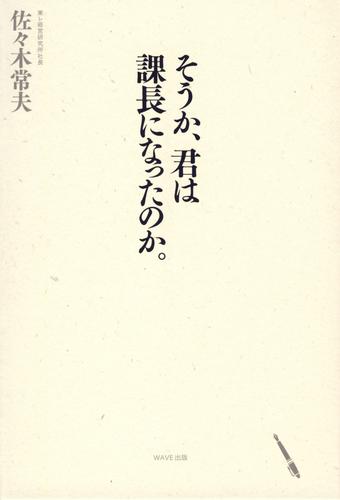
総合評価
(175件)| 37 | ||
| 68 | ||
| 49 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ定期的に積読する本。課長に限らず、多くのマネージャーリーダーとなる人が読むことをオススメ。そんなに特別ななことを書いてる訳でないが、読み易く腹落ちしやすい。
0投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に読んだが、実際に課長になって、改めて読み直した。今のほうが実感として、著者の言いたいことがよくわかる。これまでとは全く異なる仕事、プレイングマネージャーになってはダメで、課として成果を出すことに注力すべき。よくわかるが、実践するとなると難しい。ただ改めて、課長としてやるべきことを認識できた。
0投稿日: 2025.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、著者の経験から導き出された課長職の真髄をまとめ、ある架空の新任課長に向けた応援の手紙のように構成されている。課長にとって一番大切なことは、何かを成し遂げようとする「志」であり、何としても部下を育てるという「志」であり、スキルやノウハウは後からついてくるということがばしめにで書かれている。本書の中でも、志や課長の仕事について説かれた後、具体的な方法論が紹介されていて、大変勉強になった。まだ課長という立場にはないが、本書の内容、特に仕事の進め方10か条を意識して、今後仕事に取り組んでいきたい。 1. まずはじめに、「志」をもちなさい 課長の仕事 ①課の方針策定:課の経営方針の策定と遂行状況のチェック ②部下の監督と成長:部下の直面している現実を正しく把握し、その仕事のやり方を指導し、組織全体を最高の効率にもっていく ③経営と現場のコミュニケーション:自分の課で起こっていることを経営に的確に報告するとともに、経営の意思・目標を課全員に的確に伝える ④社内外の政治:社内外の関係者を自分の目標どおりに導いていく政治力 2. 課長になって2か月でやるべきこと 仕事の進め方10か条 ①計画主義と重点主義:まず、仕事の目標設定→計画策定をし、かつ重要度を評価すること。自分の在籍期間、今年・今週・今日は何をどうやるか計画すること。すぐ走り出してはいけない。優先順位をつける ②効率主義:目的を踏まえどのやり方が有効かできるだけ最短コースを選ぶこと。通常の仕事は拙速を選ぶ ③フォローアップの徹底:自ら設定した計画のフォローアップをすることによって自らの業務遂行の冷静な評価を行うと共に次のレベルアップにつなげる ④結果主義:仕事はそのプロセスでの努力も理解するが、その結果で評価される ⑤シンプル主義:事務処理、管理、制度、資料はシンプルをもって秀とする。すぐれた仕事、すぐれた会社ほどシンプルである。複雑さは仕事を私物化させやすく、後任者あるいは他者への伝達を困難にさせる ⑥整理整頓主義:情報収集、仕事のやりやすさ、迅速性のため整理整頓が要求される。資料を探すロスの他に、見つからずに結局イチから仕事をスタートするという愚を犯す ⑦常に上位者の視点と視野:自分が課長ならどうするか部長ならどうするかという発想での仕事の進め方は仕事の幅と内容を豊かにし、自分及び組織の成長につながる ⑧自己主張の明確化:自分の考え方、主張は明確に持つと共に、他人の意見をよく聴くこと。自分の主張を変える勇気、謙虚さを持つこと ⑨自己研鑽:専門知識の習得、他部署、社外へも足を運ぶこと。管理スタッフならば、管理会計程度は自分で勉強し、身につけておくこと。別の会社に移っても通用する技術を習得すること ⑩自己中心主義:自分を大切にすること→人を大切にすること。楽しく仕事をすること。健康に気をつけること。年休をとること
0投稿日: 2024.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象に残った点 ・課長とは人を動かすのが仕事です。「自分の出世のため、利益のため」という思いから人を動かそうとしても、周りは決して動いてくれません。 ・挨拶がきちんとできているかは、職場のバロメーター。信頼関係が活性化の源。 ・文書で示すだけで、君の考え方が浸透するほど甘くはありません。とにかく、反復連打です。現場の仕事にあてはめて、具体的に説明してください。 ・ビジネスマンは時間厳守が鉄則。 ★細かい知識などは、虚心坦懐に部下に聞くとして、大きな流れについては君が判断し、指示する。 ・「礼儀」をもって、手を突っ込む。 ・会社の仕事は大抵平凡。平凡であっても、その仕事が「何のためになるのか」ということを明確に示してあげることが重要。 ★勘違いする課長がいる。秀れものを酷使し、チーム全体の底上げはしない。それほど大きな成果は出ない。 ★重要なのは個々人のモチベーションを高める。仕事の結果に差をもたらすのは、能力というよりは熱意。 ★黙って仕事をするのではなく、仕事の前に明確な言葉で確認し、相手の意見を聞く。そして、ある程度業務が進んだところで確認する。要所要所で念入りにコミュニケーションをとる。 ・家庭の事情もオープンに ・褒めるが8割、叱るが2割 ・話すが2割、聞くが8割 ・一つのカラーに統一しようとする圧力の働くチームというのは極めて脆弱。異質な考えを排除し、選択肢を狭める。 ★責任は君にあります。絶対に、部下のせいにしてはなりません。 ★上司を味方につける。対応を間違えば最大の障壁になる。 ・2段上の上司とのコミュニケーションは、できるだけ短時間にする。 ・口は災いのもと。特に、他人の悪口には気を付ける。 ・大局観を養う。上位者視点で考える。 ★考える力を養分ければ、読書は有害。 ★課長の仕事に専念せよ。具体的業務を卒業して。 ・管理職は長時間労働をしてはいけません。課の経営方針策定・部下の監督と育成という本来業務に傾注し、志をもってしなやかに働く。
0投稿日: 2024.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長になった方もまだの方も読んでいただきたいです。 色々な例をもとに回答する形で進んでいきます。 結局のところは家族は大事だということでしょうか。 内容(「BOOK」データベースより) 課長ほどやりがいがあって、おもしろい仕事はありません。部下の成長を確認したり、チームとしての結果が出たときの満足感はなにものにも代えがたいものがあります。一緒に働いた仲間との「絆」を築くことができるのは、部下一人ひとりとダイレクトに付き合う課長時代だけと言っても過言ではないのです。課長になったら、まず最初に読む本。
10投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長とは、厳しい仕事であるが楽しい仕事。そう思うための取組み、考え方が書かれている。自分も将来、課長になるのであれば、「大変だけど楽しい」と思える仕事の仕組みを構築したい。
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長でも何でもないのですが、、著者の事が知りたくて読んでみました。 あたたかく厳しいながらも、優しい平易な言葉で、手紙形式で書かれていて、読みやすかったです。 随所に心に響いたり、実際に働く上で参考になる箇所が多くありました。 ・働く上での10箇条 ・社内政治のむつかしい時 ・部下など人が複数集まったら、2人は好ましく感じ、2人はとても苦手に感じる。あと残り多数はどちらでもない。どこでも、集団となると大体の割合は同じだと思っておく。 一気に読んでしまったので、折にふれて、また読み返していきたいです。
2投稿日: 2023.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司が読んでいたため。久々に感情や愛情あふれるビジネス本を読んで、良かったと思った。もっと部下に対して親身になる、他の会社の人と交流する、志を持つ、表明する、をやっていきたいと思う。
0投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ■なぜ手に取ったのか プロジェクトを一緒に進めているメンバーが話していた時に、 気になりメモしており、手にした本です ■何が語られていたのか 書名のとおり「課長」というポジションについてのあり方を語られています。 社長、部長、係長ではなく「課長」です。 著者はその「課長」という役職が一番面白くてやりがいがあると説きます。 スキルやテクニックではなく、社長である著者が、自らの体験や反省を 踏まえて、これからの課長に対してどうあるべきかといったあるべき姿を 提示し様々な視点で語られていました。 ■何を学んだのか 私自身も課長ですが、記載にあったことは一部実践しています。 しかし、まったく全く異なる視点や、視座の高いことをアドバイス頂いています。 さらに、具体的な実践方法を記載されており、具体的な課長としての 役割がなんであるかを得ました。 ■どう活かすのか これまで仕事に関わって生きた実績や、人から得たものを、 なんとか形にし、成果を出そうという気持ちにさせてくれる本でした。 もちろん会社のためではなく、自分自身のためです。 答えは一つではありませんが、実践あるのみです。 ■どんな人にお勧めなのか 今、課長の人、今、係長や係員の人、組織のミドル層、 部下育成に困っている、指針が欲しいと思っている人にお勧めの本です。
2投稿日: 2022.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ東レの元社長、佐々木常夫氏。自閉症の長男と鬱病の奥さんと暮らし、ワークライフバランスを実現したということから興味をもった。 説教臭い内容かと思いきや、ピュアにストレートに語りかける様は、本当に人柄を表しているのかなと感じる。
0投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長職を意識する年になってきたので読んでみた。大切なことが書かれているが、10年以上前の本ということもありおおよそは既に理解していたり、心掛けていることではあった。
0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には好きなスタイルのマネジメント。コロナでコミュニケーションがどうしても少し希薄になる中でどれだけこれを体現できるか。。
0投稿日: 2021.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのタイミングで読めて良かった。 新任課長がこれから直面するであろう様々な迷いや課題に対して、示唆に富む内容で回答されており、感銘を受けたところが多数あります。 手元に置いておき、何度も繰り返し読みたい本です。
0投稿日: 2021.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・志+パッション。会社/部下の成長のため。人を幸せにする。 ・プレーイングマネジャーになるな。 ・課長の業務:指示、育成、方針策定、コミュニケーション、政治力。 ・仕事の10カ条:計画/重点化、効率、フォローアップ、結果、シンプル、整理整頓、上位者の視点、自己主張の明確化、自己研鑽、自己中心主義、時間厳守 ・課長は大きい流れを決める。細部の実行は部下。 ・優先順位付け ・自責→部・自分でできることを実行する。 ・やりがい ・コミュニケーション:5W2Hをはっきりと伝える。 ・ほめるが8割、叱るが2割。 ・他部署への協力→自部の評価・部下の評価 ・部下の失敗≒自分の失敗と捉えて、指導・フォローする。ただし、ミスの再発防止ができることを部下に求める。 ・結論まっしぐらを意識する。
1投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長になる人必読書。大事なことがありすぎて付箋だらけに、、、 大丈夫と書いてはあるが、凡人の自分に本当に身につけられるのだろうか。。。 ただ、なる一年前くらいが本当はベストなんだろう。 読まなきゃと思うのは二月前くらいになってしまう気がするけど。
0投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長職に昇格したが、課長って何をすれば良いのか漠然としていたので、部長におすすめの本を聞いたら、この本をオススメされました。耐え前やカッコつけではなく、本音で心に刺さる内容で、とても読んでよかったです。
0投稿日: 2021.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ中間管理職に元気をくれる本 言葉が実践的なものでわかりやすい 初めに志をもち 部下と同僚、上司と関係性をつくり 部下に仕事を与えて褒めて認める 社外でもネットワークもち、自己研鑽し続ける
1投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ東レ経営研究所の佐々木常夫さんの著書。課長だけでなく管理者が心得ておくべき事項を項目ごとにまとめられている。手紙形式でストーリー性があり、簡潔に伝えたいことが伝わる。スキマを活用して要点は何度でも見返したい一冊。
0投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族のサポートと仕事を両立させながら東レの取締役まで昇進した著者による課長の入門書。課長に昇進したばかりの架空の人物に向けて書いた30通の手紙を通じて、課長という仕事に従事する人々を応援する一冊。 社会人になって間もない頃にヒットし、いつか読もうと思っていた。よくある日本企業の根性論、人生自慢盛りだくさんの内容とは一線を画し、限られた資源を有効活用して成果を出すためのtipsを紹介している。How to 本はあまり好きではないが、ミドルマネジメントに関して具体的に示した本がそもそも少ないので、参考になる方も多いと思う。一部多読不要論、父親不要論など「?」な内容があるのはご愛敬か。
0投稿日: 2019.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長たるもの… 心得がよくわかる 新任の課長となって、 誰にも聞けない、様々な見識があるのもわかってる そんな理論的な話をこうやって読むことで整理できたと思う これから先、いろんな壁を乗り越えなければならないだろうが… 頑張りたいと思う一冊
0投稿日: 2019.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ”タイトルにひかれて購入。管理職になりたくない症候群への処方箋をみつけたい --- T: P: O: --- <読書メモ> 「課長」という仕事に使命感を感じ、元気が出してやっていけそうな本でした。”
0投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ書評】そうか、君は課長になったのか。/佐々木常夫 課長になった時に最初に読んで参考にして、色々トライした。部下が課長になった時にプレゼントした。 以下ポイントの書き出し。 「自分の頭で考える」 「読書で得た知識を現場の仕事にあてはめてシミュレーションしてみる」 「良書は何度も読み返す」 「自分の意見ははっきり述べる」「一番怖いのは思い込み」 「他者とぶつかるからこそ考え方や価値観は磨き上げられる」 「口は災いのもと」陰口を言わない。言い方を工夫して本人にも言う。 課長の仕事は、 1)方針策定、 2)部下の監督と成長、 3)経営と現場のコミュニケーション、 4)社内外の政治。 「下手な温情は、部下を殺してしまいかねない」 「正面の理、側面の情、背面の恐怖」 「対話とは聞くこと」 「話すが2割、聞くが8割」 「仕事の目的を明確にして」「部下に仕事を発注する」という考えで「礼儀をもって部下の仕事に手をつっこむ」 方針や考え方は必ず文書にして渡し、折に触れて現場にあてはめた具体的な話で反復連打。 忙しいと、口頭がいいやと思ってしまうこともありますが、けっこう伝わったかなと思っていることが、伝わっていない。文書にすると、初めて理解してもらえる。「口頭より文書が効率的」 披露宴でのスピーチを頼まれたので、本人に「恥ずかしくなるくらい自分を褒めた自己紹介文を書きなさい」といって持ってこさせたら私のスピーチの原稿は1時間で出来上がった。(やらせるということだ)
1投稿日: 2019.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長になった時に読んだ。 家族に病気の人がいて早く帰らなくてはいけなくても、時間を作り出す、部下の管理はできる。結局自分の力や工夫でどうにでもできるのだという気にさせてくれた。 大変勉強になった。 よくありがちな偉くなった人の自慢話とは感じなかった
0投稿日: 2019.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ★本書のメッセージ 課長ほど面白い仕事はない。部下を家族と思い、その活躍のために、尽力しよう ★読んだきっかけ 上司の立場の思考を学びたいと思って読んだ ★本の概要・感想 うつ病の妻と自閉症の子どもを支えながら東レ経営研究所になったスーパービジネスパーソンパパ、佐々木氏による課長・上司論。そんなに目新しい記述や、奇抜な意見は少ない。聞けば「そりゃ、そうだよな」という話が多い。他のマネージャー論にもあるような。ただ、その実践レベル、度合いがものすごかったのだろうか。佐々木氏のすごさは尋常じゃないと思うが、他のマネージャー論の本と比べて、その違いをうまく読み解けなかった ★本の面白かった点、学びになった点 *仕事と家庭の両立が大変なのではない。仕事が楽しいから家庭も頑張れるのだ ・課長業ほど面白い仕事はない。その仕事を楽しんでいるからこそ、家庭での妻や息子とのふれあい、世話も楽しむことができた ・仕事に癒されていた。仕事を辞めて家庭に入っていれば、おかしくなっていたかもしれない *プレイングマネージャーなどできると思うな。課長業はそれまでの仕事と訳がちがう ・課長になれば、普段の営業業務ではなく、全体がどのようにすればうまく回るのか、常に意識を払うべき ・自分の営業の片手間にできるような仕事が課長業ではない。常に部下に気を払い、話をし、現状を把握しながら、目標の達成の手助けをするのが仕事である *部下の昇進の手助けをしよう ・部下には「部長に、~くんがんばっているから、昇進させてくれと言っておいたよ」と伝えよう。査定の前に ・そういう、頑張りを認めてくれる、自分のために頑張ってくれる上司がいれば、より部下は奮起して仕事に励む ・査定や昇進の結果が出た後に、そのことを伝えてももう遅い *常に、自分の立場よりも上の人のことを考えて行動しよう ・平社員なら「係長ならどうするか」と考えて動こう ・そういう、高い当事者意識が、その人を成長させる ・課長であれば「部長であればどうするか。部長であればどう考えるか」と意識して動くだろう *課長業とは、人づくり ・自分の悩みをさらけ出すことで人もついてきてくれるようになる ・自分の信念と志を共有し、全力で仕事にあたろう ・そのための、コミュニケーション、言葉の文書化、明文化にこだわろう ・いったことを実行しない、うそをつく、裏切るなどはあってはならない ●学んだことをどうアクションに生かすか ・部下との関係性で悩んだ時、迷ったときに定期的に読み返すとよさそう ・仕事が楽しいから育児や妻のサポートも頑張れる、という発想は面白かった。それぐらいの意気で仕事を面白がり、家事育児に全力投球できたらいいなぁ
2投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ手紙での会話形式でわかりやすい。 課長は大変ですが、確かに課員とダイレクトに繋がっているのでやりがいはあることが伝わります
0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年度から課長の立場になったため読んでみました。 課長になる上での心構えが新人課長への 手紙というかたちで記されています。 課長の役割だけではなく、社内政治についても アドバイスが書いてあり、これまで無関心だった分野 だっただけにいい勉強になりました。これまでと違って 上司部下との密なコミュニケーションが必要だと わかったので少しずつ実行に移していこうと思います。
0投稿日: 2019.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ悩んだり壁にぶつかった時に、何度も読み返す大切な本。耳のイタイ話ばかりで読むと更にヘコむのだが。 志を持っているか。真剣に考え抜いているか。本気で生きているか。 自分の薄さや浅さを思い知らされます… 傷に塩を塗られるような痛みと共に、大事なことを思い出させてくれる原点のような本。
0投稿日: 2019.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ社内昇格試験に向けて読んだ本。 かつての部下が課長になりその部下に向けての手紙、というストーリーで話が進む。 課長としての大事なことや壁にぶつかったときの対処を、著者の軽経験をもとに優しく諭してくれるような記載である。 今後も手元に置いておく一冊。
0投稿日: 2019.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、肝臓病・鬱病を病んだ奥さんと自閉症の息子さんとを抱え、育児・家事を担いながら課長職を務め、東レの取締役を経て東レ経営研究所の社長となった人物。 しかし、この本ではそういった苛烈な状況での仕事とプライベートの両立という要素はあまり前面に出てこず、オーソドックスな「課長道」が説かれています。 「プレーイング・マネージャーにはなるな」「最初に君の信念を示す」「誉めるが8割、叱るが2割」など、なるほどと思わされる部分がある一方で、「社内政治に勝つ」の章では如何にも日本企業的なテクニカルな面でのアドバイスにも結構紙幅が割かれているあたり、面白いなと思います。 しかし、最初に『志』や『信念』の大切さを強調していながらも、『評価』されるためには『社内政治』に勝つことが重要であるというところに話が落ち着いていってしまうのは、極めて現実的ではあるのですが、少々青臭いことを云わせてもらえば、やはり『会社』という『組織』の中で生きることの限界みたいなものを感じてしまったりもします。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログマネージャーであり、現場で業務を行う課員にも接することができる課長。 部下の力を引き出しチーム力を高めるにはどういうアプローチをしなければならないかがよくわかりました。大事なことは読むことではなく、読んだ上で実際の状況に当てはめ、シミュレーションをすること。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長になってみたいと思わせる本です。 新人課長に手紙を送るという形式なので読みやすいです。 課長は部長や役員よりも難しい仕事のようですがやりがいがあるようです。 仕事の10か条はまねて実践してみます。 気になった言葉 ・部下を動かすのはスキルではない。部下の心を動かす、君の高い「志」だ。 ・プレーイングマネージャーになるな ・一緒に働いた仲間との絆を持つことができれば、それは幸せな仕事人生というべき。
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はタイトル通り管理職になる、もしくはなったばかりの人向け。元上司から新任管理職に向けた手紙形式で書かれていて、とても読みやすく構成されている。やはり管理職としての重要な仕事は人づくりと書かれている。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に目新しいことが書かれているわけではないが、ビジネスマンとして心掛けていかなければならないことを再確認できた
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ実務者の発言は説得力があると前々から繰り返し感じているところだったので、家庭に問題を抱えながらも、仕事でも成功を収めた人がどのような助言をするのかが気になって読んでみた。 自分としては具体的な身の上話を求めていたのだが、かなり一般化してしまっているところが非常に残念。 一つ意外だと感じたのは、部下への対応について。 「私は、基本的には、どのような人材でもあきらめずに指導、教育し、戦力化することが課長の本分と考えていますが、世の中には箸にも棒にもかからない人がいるのも事実です。 …厳しいようですが、そういう人は切って捨てるしかありません。」ときっぱり見捨ててしまっていること。こういう本だとだいたいあきらめるなっていってしまいがちだが、あっさり言い切っているあたり、さすがだなあと思った。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者は多分どの本も書かれていることは同じでしょう。おそらく2冊くらい読めばいいのではないかと思う。 考え方にはとても共感。課長というより、組織を動かす立場の人は必読の書だと思う。 自分としては大体実行できているが、対上司の部分は、今後意識的に実行していこうと思った。
0投稿日: 2018.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ前に一度読んだ気がするが、読み直し。 大枠、素晴らしい指南書。一つの完璧なロールモデルと思う。 一方、現実に合っているか?というと分からない。特にプレイングマネージャーになるな、の点。ただでさえ、日本企業は階層が深すぎる。それぞれが専門性をもって、プロとしてコラボしていくべき時代に、マネージャーと平社員はどういう関わり方をしていくべきだろうか?
0投稿日: 2018.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ渕上さんが読んでいたので習って読んでみようと思って手に取った本。 課長どころかまだまだ一般社員なので、実感がなくあまり刺さらなかった内容。 そのうち読み返したらおもしろいのかも。
0投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本屋で目につき購入。 (感想) ・尊敬する先輩に語りかけてもらう感じで、読んでいて面白い。 ・一気読み可能。 (備忘録) ・何よりも大事なことは志を持つこと。 ・プレイングマネジャーにはなるな。今までの担当としての仕事の延長線上にあると考えるのは間違い。部下の仕事をやってしまうと、課長の自分がやるべき仕事を放棄することになる。課長の最重要ミッションは、部下の監督と成長、及び組織内での上下のコミュニケーション。 ・前任課長からの引継ぎを鵜呑みにしない。一応聞いておいて、あとは自分で確認。 ・部下と面談する。部下の担当業務についてではなく、「君はこの課がどんな風になればいいと思う?」など、部下の職責とは関係ないレベルのことも聞く。 ・在任中に何を成すかを決める。遅くとも着任した2ヶ月以内に決める。目標をブレイクダウンして、優先順位をつける。 ・はっきりと言葉にする。空気を読むとか、阿吽の呼吸が仕事をダメにする。 ・人事評価ではじぶんをおしころす。自分の価値観から離れてみる。部下がやるべきことをやっているならば、そのことは評価する。 ・やる気の落ちた部下がいたらじっくり話を聞きなさい。酒を飲みながらではなく、素面で向かい合う。 ・部下のミスについて。再びミスをしないようにしてあげるのが部下を守るということ。 ・部長に、定期的に時間をとって報告し、相談する。 ・「私たちは、部長が親しみの表現として気さくにしてくださるのは理解してますが、彼女はそう受け取っていない様なので、今後は接し方を変えて頂くようお願いします。」。
0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
さらっと読めるが、ストンと落ちやすい話だった。 課長の一番のミッションは、部下のモチベーションを高め、生産性を最大限に高めること。 そのために、何ができるかをじっくりと考え、それを部下にしっかり伝え、さらにはその方針が行き渡っているかを何度も繰り返して確認する。 このようなマネジメントに、普遍的に一番優れた方法などはない。自分の人間性を振り返りながら、ベストと思われるマネジメントを考え抜いていく必要があるのだと感じた。 また、日頃、自分が世のため人のためになるには何をすれば良いか悩んでいたが、難しいことは何もない。 この本からは、部下を元気に生き生きと働かせることができれば、それは、部下の人生を幸せにすることなのだということだと学んだ。 何人もの部下を生き生きと働かせることができれば、僕の人生が人の役に立ったということに繋がるのだろうと感じた。 以下、備忘録。 部下は家族だと思って扱うこと、真剣に部下と向き合うこと、行動指針を文書化して共有すること、モノをしっかり考えること(本を読むだけではダメ)などを学んだ。 自分の人間性を大切にしたり、分からないことは部下に聞くなど、あまり肩肘をはらないことも大切。
1投稿日: 2017.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ◾︎課長の仕事 1、課の方針策定 2、部下の監督と成長 3、経営と現場のコミュニケーション 4、社内外の政治 ・在任中に何を成すか?を決め、プライオリティをつけて、リソースを突っ込む ・部下の仕事に手を突っ込めるのは課長だけ →部下の能力を見極めて指示を出す ・部下の人生にコミットする ・異端児を大切に。ダイバーシティー、
1投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
そうか、君は課長になったのか。 ・課長になるからといって、何も身構える必要ない。能力と人間性を素直にそして全力でぶつけて。 ・部下の心を動かす「志」とパッションをもたなければ、だれもついてこない。 ・部下の成長や幸せのために本気で指導にあたっているということが伝わらなければ、 決して本当の意味で味方になってくれることはない。 ・人間の究極の幸せは、人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされること。 ・世のため人の為に生きることが、自分のためになる。愛されたり尊敬されるために働く、それは自分のためになること。 ・最近、担当業務もこなしながらマネジメントもする「プレイング・マネージャー」をせざるを得ない課長がふえていますが、決してそんなことをしてはいけません。課長の仕事は二兎を追ってできるほど簡単なものではないのです。 ・課員全員をひとつの目標に向かって行動させ、結果を出すというミッションを持っている。要するに人を動かすのが仕事。 ・部下の数が多く、質もバラバラなので一筋縄ではいかない。一人一人の個性に合わせ、あの手この手で対応する必要がある。 ・ところが課長自ら現場の仕事をしてしまうケースが多い。部下を成長させるという課長の 責務を放棄しているわけです。 ・これは逃げです。作業をやってるほうが落ち着くんですよ。だけど課長に現場仕事をやってる暇はありません。 ・へとへとになるのが、長続きするわけがないし、当然結果も出ない。 ・課長になるということは、具体的業務を卒業し、まったく新しい世界の仕事に向き合うことなのです。 課長が要求されるのは、 ●課の経営方針の策定と遂行状況のチェック(方針策定) ●部下の直面している現実を正しく把握し、その仕事のやり方を指導し、組織全体を最高の効率にもっていく。(部下の監督と成長) ●自分の課で起こっていることを、経営に的確に報告するとともに、経営の意志・目標を課全員に的確に伝える。(コミュニケーション業務) ●社内外の関係者を自分の目標通りに導いていく政治力(政治力) ◆仕事の進め方 10か条 ①計画主義と重点主義 まず、仕事の目標設定→計画策定をし、かつ重要度を評価すること。自分の在籍期間、 今年・今月・今週・今日は何をどうやるか計画すること。すぐ走り出してはいけない。 優先順位をつける。 ②効率主義 目的を十分に踏まえ、どのやり方が有効かできるだけ最短コースを選ぶこと。通常の 仕事は拙速を尊ぶ。 ③フォローアップの徹底 自ら設定した計画のフォローアップをすることによって自らの業務遂行の冷静な評価 を行うとともに、次のレベルアップにつなげる。 ④結果主義 仕事はそのプロセスの努力も理解するが、その結果で評価される。 ⑤シンプル主義 事務処理、管理、制度、資料はシンプルをもって秀とする。すぐれた仕事、すぐれた 会社ほどシンプルである。複雑さは仕事を私物化させやすく、後任者あるいは他社への 伝達を困難にさせる。 ⑥整理整頓主義 情報収集、仕事のやりやすさ、迅速性のため整理整頓が要求される。資料を探すロス の他に、見つからずに結局イチから仕事をスタートさせるという愚を犯す。 ⑦常に上位者の視点と視野 自分が課長ならどうするか部長ならどうするかという発想での仕事の進め方は仕事の 幅と内容を豊かにし、自分および組織の成長につながる。 ⑧自己主張の明確化 自分の考え方、主張は明確に持つとともに、他人の意見をよく聞くこと。自分の主張を 変える勇気、謙虚さを持つこと。 ⑨自己研鑽 専門知識の習得、他部署、社外へも足を運ぶこと。管理スタッフならば、管理会計程度 は自分で勉強し、身につけておくこと。別の会社に移っても通用する技術を習得する こと。 ⑩自己中心主義 自分を大切にすること→人を大切にすること。楽しく仕事をすること。健康に気を付け ること。年休をとること。 ・このような考え方や方針は、必ず文書にして渡す。口頭では頭の中を素通りする。 また文書化することによって、自分の考えを整理することができるし、自分が何を大事にするかが発見できたりする。 ・部下に説明するときは、10か条をそのまま言っても伝わらない。現場の仕事にあてはめて、具体的に説明する。 ・在任中に何かをなす。タイムリミットで自分を追い込め。そのためには現場に起こってい る事実を知りつくす。わからなければ部下に細かいことを教えてもらう。プライドを捨て きちんと教えを請わなければ、間違った判断をすることになる。経験の浅い上司を馬鹿に する部下もいるが、そういうのは未熟なひとだから意に介せず、気持ちの上で一段上に立 ち、かつ謙虚に教えを請えばいい。 ・何が事実か。を正しくつかめば、それほど間違った結論は出てこない。会社で起こる ことの解決策というのは、たいていは「常識」で判断できるもの。 ・そうなったらあとは課長として毅然として結論をだすこと。勇気をもって、部下が難色を 示したとしても、決断する。部下の批判意見が自分を磨くことがある、けれどもあくまで 最終判断をくだすのは自分。細かい知識は虚心坦懐に部下に聞き、大きな流れについては、 自分が下す。 ・「為すべきこと」をまず決めたら、次はそれをブレイクダウンする。2年計画ならば1年目は何をするか、今月は、今週は、今日は。。。 ・計画通りに進まないケースがほとんどだから、その都度計画を修正しなければならない。 しかし計画をもたずに成り行きに任せる仕事の仕方は時に決定的なロスを生じる。その計画性の無さが、部下に負担を掛ければ信頼関係を損なう。 ・課の業務は、プライオリティを付けなければならない。何らかの為すべきことを達成するには課全体の仕事のやり方を変えなければならないはず。重要度の低い仕事はやめるか、 やるとしても6~8割の水準で完成させるという調整が必要になる。従来の仕事を捨てることを恐れてはならない。 ・安易に人を増やすことは実現しないし、考えないほうがよい。闘う武器を会社がすべて用意してくれることは少ない。課長はマネージャーであり、その手腕が問われる。つまり業務のプライオリティをつけて、しかるべき形に組みなおす。 ・他責、武器を与えない会社が悪い、ではだめ。与えられた条件で「では何をすべきか」と知恵を絞って自らの力を頼って実行していく、自責の発想でいかなければならない。 ・課長は部下の仕事に手を突っ込む。業務の完成度、納期も設定しないのはおかしい。 業務のプライオリティを5段階に設定してみる。実際には5の業務は、ほとんどない。1か2の仕事はやるなと言ってもいい。しかし部下の言い分も聞く。こうして効率化が実現 でき、為すべきことに力を割くことができる。ただし、部下の仕事に手を突っ込むのは礼儀をもってしなければならない。誰だって自分がやっている仕事について「これは重要ではないからもっと適当にやってくれ」と言われたらやる気を失う。「君にはもっと大事な仕事に力を注いでほしいから、この仕事はもう少し簡単に済ませて欲しい。」という言い方に工夫が必要。 ・部下は発展途上人。成長にコミットする。何のためにこの仕事があるのか、明確にしてあげなければならない。 ・モチベーションを上げてあげること。仕事の結果に差をもたらすのは、能力というよりは熱意。 ・はっきりと言葉にする。あうんの呼吸を信じてはいけない。 ・コミュニケーションが大事。会社の仕事では自分ひとりでやる「業務処理」と、チームでやる「情報処理」があり、その比率は4:6。チーム仕事のほうが多い。 ・チームで仕事に着手するときは、「何のために」「いつまでに」「どの程度まで」「誰と誰がするか」ということをしっかりと決めなければならない。これをしないと膨大なロスになる。 ・こんなことにならないように、何事も言葉でしっかりと伝えること、相手の話をしっかりと聞く努力をすべき。 ・部下は不満を感じても黙っていることが多い。部下の意見もきちっと聞くように。 ・黙って仕事をするのではなく、仕事の前に明確な言葉で確認し、相手の意見を聴き、そしてある程度業務が進んだところでその仕事を確認する。要所要所で念入りにコミュニケーションをとる手間をかけることで、ロスは大幅に減る。 ・自分の悩みをさらけ出すことで部下は自分や周りの人の抱えている悩みなども話しやすくなるもの。その人のことをこころから心配して何かあったら手を差し伸べたいと思う気持ちが伝われば、相手はいろいろと打ち明けてくれるもの。 ・部下が会社の中でのびのびと100%の力を出し切るにはプライベートが健全で悩みが少ないことがとても大切で、耳を傾けるだけでもいいし、力になれるかもしれない。 ・運命を引き受ける。苦難が訪れたとしても、「それがどうした」と平然と生きていくしかない。そういう人が共感を受けるもの。 ・自分のチームの人たちを家族と思え。 ・褒めるが8割、叱るが2割。叱ったチームは当初は緊張して頑張るが、叱ってばかりいるとモチベーションが下がる。ちなみに最悪だったのは何も言わないチーム。 ・比率に正解はないが、本気で褒めて、叱れば、部下はついてくる。 ・部下はさまざまなので、打たれ強い人もいれば繊細な人もいる。その人の性格に合わせた対応をすべき。ただしえこひいきはNG。 ・人事評価は、きわめて重要な仕事。正しい評価ができなければ最も大事なミッションの 「部下の監督と成長」をまっとうすることができない。 ・人事評価は、本来、給与と処遇を差をつけるためではなく、部下の現状を正しく評価することによって、これから身に着けるべき能力、技術、人間力について自覚させるとともに 自分が上司として指導するためのもの。 ・できれば部下をすきでいたほうが良い。人を好きになるのも技術がある。好きになれば、人事評価でも過ちを犯すことが少なくなる。 ・好き嫌いで評価してはならない。人を評価するには少し無理をしてでもフェアな視点を持たなければならない。自分の主義主張から離れて客観的に冷静に評価する必要はある。 ・部下の昇格のため、少し甘い評価をしよう。部下本人には自分が思う冷静な本来の評価をもとに、厳しく対応すべき。甘くつけた点数分については、自分の指導によって必ず部下を成長させなければならない。そうしないと「社内で評価インフレが起こるのではないか」という批判にこたえることはできない。 ・仕事は成果であるという考えに間違いはない。ただし、アメリカのように200~500倍の 差をつけるべきではなく、極端に差をつけることは活力につながらない。多くを評価したところで働く人はもともと働いているのだし、リスクは、報酬を下げられた人のモラルダウンのほうが大きいと考える。 ・大事なのは、部下の仕事を一人の人間として認めてあげること。人の生きがいはそこであり、報酬ではない。これらを与えられるのは課長だけ。 ・部下との対話は、話すが2割、聞くが8割。このときに部下が納得できない点があればそれに対する対策を考える。そうすればモチベーションは上がる。 ・モチベーションが下がっている部下には、話を聞くことがだいじだが、酒の席は、あまりよくない。素面でじっくりと向かい合うことが大事。 ・異端児、ダイバーシティがなぜ大切か、それは異質な考え方の提案によって組織の中に対立が起こり、既存の考え方の検証が行われ、それがイノベーションを起こすから。 だから異端児は生かさなければ損。 ・課長だからと言ってカッコつけるな。誰の目にも明らかなミスをしたときは丁寧に率直に謝罪すべき。たとえ部下のミスであっても、自分の責任。絶対に部下のせいにしてはならない。そのように素直に謝る態度を観て、部下も上司を評価する。 ・ある仕事について部長の考え方と異なるために叱責を受けたケースでは、謝る必要はないが、「部長の意見を踏まえ、もう一度つくりなおしてみますので、お時間をください」と局面を変えるような対応をすべきである。部長は自分よりも経験があり、違った角度で問題をとらえている可能性があるので、自分にも勉強になるかもしれないし、いきなり反論を述べるのは得策ではない。 ・たとえカッコ悪いところを観られたとしても、そのこと自体で部下が自分の評価を変えることはない。動揺することはない。 ・部下が失敗してもうろたえることはなく、ともに涙を流したり、とことん慰めたり、ようは自分の感じているまま、人間性のまま自然体でふるまうこと。 ・リーダーではあるが、あくまでも一個人。そのことを、部下もよく知っている。素直に感情を出そう。恰好つけてもたかが知れている。 ・部下は家族。ミス、家族に病人、関係部署からの非難についてはカバーしてあげなければ ならない。特に部下のミスによらない批判に対しては、断固として部下を守る姿勢を貫くべ き。 ・ただ養護するのは間違い。イージーミスを繰り返すようなら、課長がミスを減らす工夫をしてこなかったことが原因ではないかと疑われる。再びミスをしないようにしてあげるのが「部下を守るということ」 ・部下を守るということをはき違えないこと。温情は部下を甘やかす。一生懸命やってる、というような主観的判断は言い訳にならない。十分反省させたうえで、2度と同様のミスを発生させない対策を練ったうえで、ボーナスのカットもあり得る。イージーミスの怖さを叩き込んでおくことが本当に部下を守るということ。下手な温情は部下を殺してしまいかねない。 ・精一杯指導してもどうしようもない人材は、速やかに他部署へ移動を画策すべき。会社の中には、それほどの人材でなくとも務まる部署はあるし、人で不足で猫の手も借りたい部署もある。切ってすてるしかない。会社は人助けの組織ではなく、あくまで戦闘集団。 ・上司の指示命令には従ってもらう。組織とはそういうもの。 ・「正面の理。側面の情。背面の恐怖。」リーダーが仕事を進めるうえで、部下に対しては まず「理」で説得し、時々「情」でサポートする。しかし、「それで従わなければ、わかっているな」ということ。「恐怖」はなるべく使わないほうがいいが、しかるべき時にしかるべき方法で使わなければリーダーとして仕事はできない。 ・部長と常日頃コミュニケーションを取って信頼を得るというのが課長の大事な仕事。 上司を味方につけ、その力を最大限に利用するのが得策。最も余裕のある日を選び、 2週に一度くらい30分程度のアポを入れる。定期的に報告相談するのがミソ。一定のスパンで。アポの際には用件を紙で書き、文書で差し出す。部長は、どんな用件なのかすぐわかる。 ・上司の了解を得れば大きい。ほかの部署や取引先に対し、「上司もこの方向でやれと言ってる」ということができる。仕事が断然やりやすくなる。万一反対を受けても、再び部長に「先日賛同いただいた件で苦戦しているので、お力添え願いたい」ということができる。 部長は力を貸さざるを得ない。こうした力学を使いこなそう。 ・たまに上司の悩みを聞いてあげれば、がぜん信頼が厚くなる。つねに部長をウォッチして大切にし、味方につけること。 ・2段上の上司との付き合いも大切。まず第一は、きちんと挨拶をすること。「先週のスピーチは感動しました」などの相手の琴線にふれるワンフレーズが良いでしょう。 ・日頃、このようなコンタクトを取っていれば困ったときにも思いもよらないアドバイスを もらえることがある。 ・2段上の上司も2段下の話を直接聞いてみたいと考えているもの。ただし長い話は禁物。 結論まっしぐらを徹底すること。 ・社内政治を生き抜かなくては、会社で実現したい理想は成就できない。どんな社会にも 政治はつきもので避けて通れない。有力な役員、部長など花形とも言える人たちと日常的 に接触し、顔見知りになっておくことが必要。日頃から何かと理由を付けてはその人たち とコンタクトをとって良好な関係を築く。 ・とっぴな動きをする必要はない。誰ともわけ隔てなく付き合うという人間として当然の ことをやればいい。幼稚園で習ったことをできるだけでリーダーになれる。「誰とでも仲 良くする」「仲間外れをつくらない」「悪いことをしたら謝る」「困っている人がいれば助 ける」こうしたことをやっていれば、自然と人脈が広がり、皆が助けてくれる。 ・部下の昇格は全力で。さもないと部下との信頼関係を保てない。社内政治で勝つ。 上司対策では、折に触れ部下の有能さをPRする。(これは彼がやったんです) ・こうした根回しの状況は、当事者の部下にはある程度伝えておく。「あの業務の件で部長 には君のアイディアだとほめておいたよ」など。よしんば仮に昇格できなかったとしても 課長としての努力を多としてくれる。 ・昇格の時期は部下の弱点を補強する絶好のチャンス。普段ならあまり気にしない部下で も、昇格が絡んでくると結構気にして態度を修正するもの。 ・部長の人格に問題がある場合。根本的に治らないと思え。失敗した部下をとことん責めて 省みることなく。直接注意することは、まず選択肢としては無い。さりげなく2段上の 上司に頼むというやり方はある。 ・上司と喧嘩をしてはならない。 ・自分の意見をハッキリと述べよう。ことあるごとに、会議や普通の会話でも。仕事で一番 怖いのは思い込み。言ってもわかってもらえないくらいだから、何も言わなければそれこ そ何もわからない。 ・自分で発言することを通じて自分の考えをまとめられるメリットもあるし、相手との主張 の違いを明らかにすることによって議論を深めより良い解決策を導くことができる。 ・2~3時間の会議で何も発言しない人、上司の話を聞くだけの人は、会社の役に立たない し、他人からも評価されない。自分の考えがないか、もしくは自信をもって主張できない 他者の考えとぶつかるからこそ、考え方や価値観は磨き上げられ、人は成長する。 ・上司の欠点を指摘してあげることで部下から不評な部分を是正して行けることもある。 ・口は災いのもと。どうにも我慢がならなかったら陰口ではなくて、本人の前でも同じこと を言おう。 ・仕事は忙しすぎる、若い頃はひたすらなんでもやるしかないと思い、またその中で力を蓄 えるものだが、課長になれば目先に捕らわれたことでは成果が上がらない。なんでもやれ ば無駄になる。もっと広い視野、高い視点で仕事をとらえる必要ある。すなわち大局観。 ・課に求められていることが何かという大局観があれば、何が幹か何が枝葉ということがハッキリする。枝葉の仕事は60~80%の完成度でも拙速を尊重し、幹の仕事に注力すれば 最終ゴールに早くたどり着く。 ・大局観を養うにはどうするか。常にひとつ上の立場でものを観て考える癖をつけること。 ・課長になってから課長の勉強をするようでは遅い。課長の時は部長のつもりで、部長のときは役員のつもりで。 ・仕事に熱中することが20~30代では大事。40代になれば働き方をよく考える。無理をすれば体が壊れる。誰も助けてくれない。自分の身は自分で守る。だから部下の仕事にタッチしてはならない。もっと高度な仕事が雨あられのように降ってくる。積極的に社外と付き合って見識を高める。社内の常識は世間の非常識ということが肌で学べる。社内にいても真のリーダーにはなれない。 ・読書するのも大事だが、自分の頭で考える人間にならなければならない。本を読むうえで大切なのは、そこに書いてあることが本当に真実か冷静に見極めること。どうすれば考える力をつけることができるか。読書で得た知識を現場の仕事に当てはめてシミュレーションしてみること。現実にどのように機能するかを徹底的に考えつくす。それで役にたたないのであれば、その知識は捨てる。 ・多読よりは、これぞという本を何度も読み返す。自分の成長につながるような本。何度読み返しても新たな発見、新たな教訓をくみ取ることができる。 ・不本意な部署でも、腐らずにコツコツとまじめにしごとをするかどうかしっかり周りは観ている。意外なことを深く学べることもある。 ・どの課長も四苦八苦している。どんな成功者も、その壁を乗り越えてきている。そんなときにお勧めは、メンバー全員でブレーンストーミングをすること。全員が思っていることを聞き出すことが目的。そのときは他人の意見を否定したり批判することは禁止。こうして全員が参画意識をもつようになる。漫然と意見を聞くのではなく、課のメンバーの総力を結集し、なんとか業績を上げたいというパッションを示す、そうすれば部下が援軍になる。 ・もしメンタルで参ったなら、とにかく休むこと。課長だからと気負っていたなら、考え直そう。特殊な才能が必要とされているわけではない。部下を直視し、考えを聴き、事実は何かを把握し、対策を相談し、それをまとめあげる。自分は自分、それ以上以下でもない。
1投稿日: 2017.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそもプレイングマネジャーは要らなくなるといわれている。より高度化する仕事には、チームをまとめる専門のリーダーが必要だからだ。だからプレイングマネジャーが活躍できる組織は、メチャクチャ切れるリーダーがいるか、人材開発を疎かにしているかのどちらかでしかない。 日本では後者の組織がほとんどかもしれない、、、
0投稿日: 2016.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長としての志の重要さを教えてくれる内容で、部下との接し方や課長としての仕事の進め方10か条など参考にしたいと思った。本著者の本は他にも数冊読んだが「志」を重視していることが再確認できた。
0投稿日: 2016.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ係長レベルになった頃に買い、その後も折に触れて読み返しています。 奥様が病弱ということで読んでみた「ビッグツリー」は、こちらも余裕がなく、綺麗事が多いと反感も感じたのですが、この本はとてもすんなりと腑に落ちました。
0投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2016/7/24 現場の長である「課長」に求められる役割、家庭・部下・上司、、自身をとりまく人々の期待とそれに対するアプローチが、分かりやすく整理されています。 課長へのウォーミングアップとして、係長級から読んでおきたい一冊。記述にもありますが課長の責務は膨大、課長の職務に就いてからも、行いを顧みるため、定期的に読みたい一冊でもあります。
0投稿日: 2016.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に一読したのだが、再度手に取ってみた。時がたったためか、内容の理解度が高まり当時と異なる気持ちをもった。著者の経験に基づき、はっきり、単純化して、諭すように課長職について書かれた本だった。学術的な文脈でなく、あくまでも一例として形式を整えれば、ここまで内容を濃縮できるのか、と改めて感じた。一般化された理論でなくとも、読者自身が賛同しさえすれば成立する書籍のジャンルが多いということも頭に浮かんだ。労働者として、何らかの福音書のようなものを求めている時期に、本書のような本をよみ、記述内容を信じることで、何か良い方向に向かうと直感すればそれで十分なのだなと思った。 http://www.tyg-business.jp/activities/2013/images/2013-5_131211.pdf
0投稿日: 2016.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログセミナー講師の佐々木さんの著書。課長じゃないけど、電車の中で読んでみた。基本、今までの佐々木さんの著書と大差はないが、課長ならではの点として、部長は課長に選ばれた社員を相手にすればよいが、課長は様々な種類の人間を相手にするため、より高い次元の人材育成能力を求められるという事。なので、課長はプレイングマネジャーになる余裕はなく、その時間を部下の育成に用いるべき持論が展開されている。う~ん、そんな課長は見た事ないが。。。
0投稿日: 2015.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下が印象深い。 部下の人生にコミットする。 手塩にかけて育てる。 部下の成長にコミットする力を持っている。 一人の人間の人生を変える力を持っている。 これは大事業、生半可な気持ちでできる仕事ではない。当然、この仕事は難しい。
0投稿日: 2015.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ町工場的企業でのリーダーシップチーム、まさにこれはいわゆる課長の仕事だなと改めて実感。そうすると、プレーイングマネージャーになるなということ。本当はそうだと思う。でも本当にリソースが足りない時はどうすればよいのだろう。
0投稿日: 2015.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐々木さんの温かさが十分に伝わる作品でした。ただ、実践という点では他の著作を読んだ方がよさそうです。 例えば、6時にみんなが帰れるようにするには実際何をしたのかが書かれておらず、物足りなく感じました。
0投稿日: 2015.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログマネジメントについて考えてみるため人の薦めもあり読んでみました。 「時間厳守」、「プレーイング・マネージャーにならないこと」、「家庭の事情もオープンにすること」、「異端児 こそ大切にすること」等々が書かれています。 同じ著者の部下を定時に返す・・・・の方が具体的でよかったような気がします。
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長受難の時代に、「病に倒れた妻と自閉症の長男を守りながら、部下をまとめ上げ、数々の事業を成功させた上司力の真髄」東レ経営研究所所長が書いた本。「課長ほどやりがいがあって面白い仕事はありません。部下の成長を確認したり、チームとしての結果が出たときの満足感はなにものにも代えがたいものがあります。一緒に働いた仲間との絆を築くことができるのは、部下ひとり一人とダイレクトに付き合う課長時代だけと言っても過言ではないのです。」
0投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長職にとって受難の時代。 上からも下からも要望が上がって、それをこなしていかなくてはならない。 なんとなくで課長職が務まる時代では無くなった。 この本では、課長になった際に、 ・志 ・課としてやるべきこと ・部下を動かす ・社内政治 ・自己の成長 を考えて行動するように勧めている。 自分はまだまだ管理職の器にはなれませんな。
0投稿日: 2015.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は家族の看護をしながら大手企業の役員を勤め上げた人物である。課長になった君へという架空の手紙形式で、課長たるものの心構え・部下への接し方が詳しく示唆されている。「在任中に何を成すか」目標を定め、そのためにこの1年は何をするか、1ヶ月は1週間はという風に成すべきことを落とし込んでいくということ。「プレイングマネージャーになるな」ともすれば部下の仕事を援助してしまうが、課長には他に課せられた大きな仕事があり、それを見失うなという2つの話が印象的で心にとめておこうと思った。
0投稿日: 2014.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者から元部下への手紙という明確な人物設定がありわかりやすい。 ひとつひとつが今の自分の環境にあてはめて考えやすく、現状の出来不出来、得手不得手を整理するきっかけにしやすい。 課長としてあるべき姿にとどまらず、全てのチームに置き換えて考えることができる。また、課長でなくとも自分自身の現状を見つめ直すきっかけににできる良書。
0投稿日: 2014.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長という中間管理職的な役職について、心構えと具体的行動の両面から解説されている。手紙形式で書かれていて読みやすく、入門書として良書だと思う。
0投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大切なのは志 一緒に働いた仲間との絆を持つ 自分の幸せのために、世のため人のために尽くす 計画主義、重点主義、シンプル主義 上位者の視点と視野 自己研鑽、自己主張、自己中心主義 すべての部下と面談する 在任中に何を成すか パレートの法則、8割2割 与えられた条件の中で何をすべきか 仕事ダイエットプロジェクト 8割褒めて、2割叱る 部下の性格に合わせて叱る ある仕事で成果を出した人には、仕事で報いる 自分がしかるべきポジションに就いたら、絶対改革する 異端児をいかして、創造的なコンフリクトを生み出す ダイバーシティ、多様性の受容 自分は偉くなってもああいうことは絶対にしない 読書で得た知識を、現場の仕事に当てはめてシミュレーションする 家族のことを心底愛していれば、仕事に精力を注いでも気に病むことはない
0投稿日: 2014.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本棚の断捨離で、並んでいる本を読み返しています。 この本は、何度か読んだのでポイントは頭の中に入ってるんですが、今回も新たな発見あり。
0投稿日: 2014.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マネジメントが苦手なので、読んでみました。 実務についていた人ならではな話が書いてあり、おもしろかったです。 プレイングマネジャはダメだとあるものの 小規模チームで動いているベンチャーなんかでは そこの脱却は非常に難しく思いました。 課の方針策定や、そのチームの長になる考え方。 プレイヤーとマネージャーは明らかに違うものだということを再認識しました。
0投稿日: 2014.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が課長になったときに、部下に対してどのように振舞うべきか?を意識しはじめていたので、読んでみました。 本の中身としては、課長としての心得や、社内政治をうまくきりぬける方法などが書かれており、それなりに役に立つ情報を得ることができました。 課長までなると、やはり人を動かすためのパッションや志、コミュニケーションを深くとることなど、いちプレーヤーだったときとは違った行動が求められそうです。
0投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて課長になる石田さん(仮名)にあてた本。 佐々木氏は、一般社員の時から「自分が課長になったら絶対にやること、やらないこと」を書き留めていたという。自分は課長になるにはまだ早いけれど、そういう意識を持って仕事をしようと思う。 ■在任中に何を成すか、を決める。
0投稿日: 2014.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
働き方とか仕事へのかかわり方を見直すことができる本でした。 そもそも「働くってどういうことなのか、何を求めるのか」から、課長をはじめとする中間管理職はどういったポジションなのかといったことを教えてくれる。 多読それ自体が良いことではないこととか、仕事量が結果に直結しないっていうところが大きな収穫かな。 課長になる前に読む本。課長になったあとでは、遅い。
0投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ職業がら課長とかそういう職位はないのだが、それでも人と一緒に仕事をして人に動いてもらう場面もこの頃増えてきた手前、やはりこういう本も読んでみたくなって購入。そういう現実的なニーズにより手に取った本書であったが、氏のたんなるメソッドやテクニックのみではない、その奥にある「情熱」「気迫」「やさしさ」「思い」が言葉の裏側から染み出てきて、目を熱くする場面も多々あった。やはり気持ちが、何をやるにも大切なのだと再認識した1冊であった。 単なる仕事ではなく、仕事を通して君は何をしたいのか、と人生そのものを問われている、本書そのものが大局観に立った1冊であった。
0投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログいえ、まだ課長にはなってないんですがね。 昨今、課長職には人気がないのです。なりたいと思わない。魅力的に見えないし、ただただ忙しそうで。多少、給料が増えても、これじゃあな…。というのが、ちょっと前までの自分の感覚。世間の同世代も同様の感覚でしょう。 そういった悩ましい課長職に向けた心構えや魅力が記された自己啓発書です。著者は、東レ研究所社長の佐々木常夫氏。 大事なことは、志、情熱。これらを持って、どれだけ真剣に取り組むか。正直、技術よりも何よりも、これがあるかないか、資質はこれに尽きますね。 あとは、部下や家族を含め、自分の周りにいる人に対して絆や愛情を大事にできるか。 政治的な話は興味深いですね。やっぱり上がっていく方は、そこまでしてるんだなと。自分は苦手な分野。頭では理解しても、まだそこまでのガツガツさを出し切れない。。 幸いなことに、最近の自分は魅力的な上司にも恵まれ、本書の内容とほぼ同様のことは、上司から常々教わっています。おかげで役職を目指すことに対する考え方が少しずつ変わってはきていました。だから本書を手に取ろうという気にもなったんですね。これ読んだらモチベーションあがるかな、迷いが吹っ切れるのかなと。 さて、読み終えて迷いが吹っ切れたのかどうかは、うーん、まだ分からん。でも、このモヤモヤは責任に対する不安感だけな気がする。最後は腹くくるしかないんでしょうね。
0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://www.wave-publishers.co.jp/np/isbn/9784872904499/ , http://sasakitsuneo.jp/
0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ○遅くとも2ケ月以内に、君の「在任中に成すべきこと」を明確にして、課員全員に明示するように(59p) ○人というものは、自分の抱えている問題を平然と受け止めて、当たり前のように処する人に共感するものです(91p) ○家族の絆は一緒にいた時間の長短ではなく、親が子どもに注ぐ愛情の深浅によるもの(187p)
0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ■軽くなく、重すぎず。文句なしに良書。 ■実践的な内容も盛り込まれている。 ■一度読んだら、2回目以降はどこからでも読んでよい。仕事の中で悩んだら開くような、辞書のような使い方もできると思う。
0投稿日: 2013.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者の経験を踏まえて、はじめて課長になる人に向けてメッセージを書いた本。 もちろん個人的な意見なのでいまいち共感できないところもあるが、基本的には非常に具体的で、とてもためになる。といってもまだ課長になっていない私にとってはイメージするしかないところも多いが、いざ課長になったときにはとても役に立つんじゃないかと思った。 付箋をはりたいところが多すぎて、一冊買ったほうがいいんじゃないかと思う。 1つ、今でも心に留めておきたいと思ったのは、「二段上の上司」との関係性。学生時代の経験も合って、上司とはなるべく垣根をつくらずこまめに報連相するよう心がけてきたが、二段上の上司との関係性はうまく作れていないなと思う。恐縮しきらずに、コミュニケーションを図っていきたい。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前から気になっていたが、もう少し早く読んでおけばよかったと後悔。しばらくしたらもう一度読み返すことになるのかも。
0投稿日: 2013.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の佐々木さんが自ら「一番書きたかった」と言われた一冊。課長という職を説き、その処世を説き、その心得を説く。凡人である我々には想像もできない苦労をした著者ゆえに厳しくもあり、温かくもある指南書である。
0投稿日: 2013.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1課長の仕事 ①課の方針策定と進捗のチェック ②部下の監督と指導 ③経営へ報告と経営から部下への伝達 ④社内外を調整する政治力 2仕事の進め方10カ条 ①計画と優先順位 ②効率 ③計画のフォローアップ ④結果主義 ⑤可能な限りシンプルに ⑥整理整頓 ⑦上位者の視点で ⑧自己主張を明確に、人の話を聴く ⑨自己研鑽(人脈作り・知識習得) 10自分を大事に(楽しく/健康/休み) 3大事なこと ①時間厳守 ②挨拶 ③お世話になったらお礼 ④嘘をつかない ⑤間違ったら謝る ・重要でない仕事は拙速に 4仕事ダイエット ①1週間の業務内容と時間を計画 ②実時間を計測し、計画と対比 ⇒仕事の予測能力向上/プライオリティ
0投稿日: 2013.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
•一緒に働いた仲間との絆を持つことができれば、それは幸せな仕事人生というべき。 •志さえ高ければスキルなど自然と後からついてくる。人生に喜びを見出すかどうかは心の持ち方で決まる。 •人間の究極の幸せは人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人から必要とされることの4つです。働くことによって愛以外の三つの幸せは得られるのです彼らが働こうとするのは、社会で必要とされ、本当の幸せを求めている人間の証です。 •プレーイングマネージャーでは疲弊して結果が出ない。 •挨拶がきちんとできているかどうかは、ある意味で、その職場の活性化のバロメーターでもある。 •方針や考え方は必ず文書にして渡すこと。とにかく反復連打です。何度も何度も繰り返しこの話をする。 •きちんと挨拶する、お世話になったらすぐにお礼をいう、嘘をつかない、間違ったことをしたら勇気持って謝る、これらのことができない人は一生一人前にはなれない。 •会社で起こっていることの解決策は、大抵は常識で判断できるもの。 •今、その課にとって重要なことは何か?従来の仕事を捨てることも忘れてはいけない。 •私は部下に仕事を発注し、部下からは私から仕事を受注する。 •上司と部下がその業務の重要度、納期を議論することによって、部下はその業務が会社や課にとってどれほどのものかを認識することができる。 •その仕事が何のためにあるのかということを明確に示す。 •部下一人一人が熱い情熱を持って仕事に取り組むようになって、その総力として強いチームができる。 •何のために、いつまでに、どの程度まで、誰と誰がするのか、ということをしっかりと決めておくこと。 •部下の現状を正しく評価することによって、これから身につけなければならない能力、技術、人間力について自覚させるとともに、上司として指導するためのもの。 •仕事の成果は仕事で報いる。 •対話とは聞くこと。こうしたコミュニケーションがしっかり取れていれば部下はきっとモチベーションを上げてくれる。 •異質な考え方の提案によって、組織の中に対立が起こり、既存の考え方の検証が行われ、それがイノベーションを起こす。 •下手な温情は部下を殺してしまう。 •定期的に報告し相談する。一定のスパンで上司と意見交換したり相談したりすることが上司の信頼を得ることにつながる。 •自分の意見ははっきり述べるべき。他人とぶつかるからこそ、考え方や価値感は磨き上げられ人は成長する。 •社内の常識は世間の非常識 •読書で得た知識を現場の仕事に当てはめてシミュレーションしてみる。そして現実にどのように機能するかを徹底的に考え尽くす。
0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前の職場の上司に借りた本。私は課長じゃないけど(笑) 非常にわかりやすく読みやすかった。 今となってはほとんど内容忘れてしまったけど、印象的だったのは「人が幸せを感じるのは、誰かに愛され・褒められ・役に立ち・必要とされたとき。仕事では愛以外が実現可能だ」 みたいな事が書かれてて、なるほど~確かにそうかもと共感した。
0投稿日: 2013.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がいかにマネジメントをできていないか、考えさせてくれました。 求められている立場と実際の立場を見つめなおし、どうすれば良いか考えさせてくれました。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本版「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」ですね。 但し、日本版では親子ではなく上司と部下になっています。 でも根底にあるのはどちらも「愛情」ですね。
0投稿日: 2012.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ【心に残ったキーワード】 ・プレイングマネージャになってはいけない ・課長はとても素晴らしい役割なんだよ
0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログいい本。 課長だけじゃなく、一団を率いる全ての人に。社内政治に対する考え方なども秀逸。分量もないのですぐに読み終えることもできる。 ただ、スキル面の記述はそんなに多くはないので、この本では考え方を手に入れつつ、実践は別の本も参考にしたほうが良いと思う。課長つながりで言えば「課長の教科書」とか。
0投稿日: 2012.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ- 在任中に何を成すかを決める。現在の職にはタイムリミットがあると常に意識する。 - モノカルチャーの集団ではイノベーションは起こらない。異端児を活かす。 - 部下の昇格には全力を尽くせ。 - 会社の常識に染まらない
0投稿日: 2012.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ課長とはどうあるべきか? →まずは自分の志とパッションを伝え、在任期間中に何をやり切るか決める 課長の役割は、 1.方針策定 2.部下の監督と成長 3.コミュニケーション業務 4.政治力 よって上司は細かい知識については部下に聞けばよく、大きな流れだけ判断、指示する
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕は、課長や部長といった役職とは関係のない仕事をしているので、この本を書店でみかけてもスルーしていました。 でも、なんとなく気になっていたのです。 図書館で見つけたときにも、何か惹かれるものがあったので、読んでみました。 課長という立場の難しさを、喜びにできるヒントが書かれていると感じました。
0投稿日: 2012.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、会社で開催されたワークライフバランスに関する講演を拝聴しました。著者の佐々木常夫氏は東レ経営研究所特別顧問ですが、ご自身の実経験から「働き方」に関する社外活動にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。 内容は、初めて課長(管理職)になった人を対象にした啓発本。佐々木氏が自ら実践した具体的なアドバイスが豊富にまたとても分かり易く紹介されています。もちろん、その示唆に特段目新しいものがあるわけではありませんが、そのひとつひとつが「自らの体験」に深く根ざしたものである点が、他の類似本と比較しての決定的な差異でしょう。
0投稿日: 2012.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ信念を、パッションをまず最初に示すこと、そして仕事の進め方10ヶ条はなかなか参考になる。全体的に優しい語り口調で書かれていて素直に受け止められる事ばかり。内容は似たようなビジネス書に書かれている事ばかりで目新しくはないが、佐々木さんを理想の課長像としてイメージさせる事で、この本を読みやすくしているのかなと思う。一つだけ納得いかないのは、多読は毒という決めつけた考え方。多読が悪いんじゃなくて、少し本をかじった程度で何も考えずに行動するって事でしょ?多読は自分の考え方を整理し反する意見を読んで更に深化させる大事な行為だと思います。
0投稿日: 2012.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ新たなチームを指揮する事になったタイミングだったのでいい時に読めたと思う。 部下が動かないのは自分のコミュニケーションが悪いというのは、忘れがちなのでしっかり覚えておこう。 ビジネスマンの父からの30の手紙の本と読んだ感じが似ている。
0投稿日: 2012.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人にほめられ、人の役に立ち、人から必要とされる ・在任中に何を成すか ・課長たるもの「自責」の発想をしなければなりません。与えられた条件のなかで、「では、何をすべきか」と知恵を絞って、自らの力を頼って実行していく。 ・異質な考え方の提案によって、組織の中にコンフリクトが起こり、既存の考え方の検証が行われ、それがイノベーションを起こす。 ・長時間労働は、必ずしも会社の成長には結びついていません。労働量で結果が出る時代は終わり、知恵や工夫がなければ結果が出ない時代になったのです。
0投稿日: 2012.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「君はこの課がどんなふうになればいいと思う?」「どんな新入社員がほしい?」はモチベーションを高める質問だなあ。
1投稿日: 2012.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から読んでみたいと思っていた本をとうとう読了。 引き続き、「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」を読んでみようと思う。本を読んで思ったことは、是非課長時代の佐々木さんの下で働いてみたかったなと思う。この本は小手先のテクニックよりも志が重要なテーマになっているが、是非身近に感じてみたかった。プレイングマネージャーにならず、部下1人1人の成長を考えた恩師になれるように努力したい。(会社を離れても結婚式に読んでもらえるような上司に)
0投稿日: 2012.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログバイブルに巡り逢う。 読み返し、染み込ませたい。 志を土台に、情熱と計算を併せ持つ。 人間として、熱く、器をでかく、そして、「しなやかに」。 なんで、言った通りにやってくれないのか?ではなく、熱意が自分にないからなのでは?? そして、家族を大切に。。
0投稿日: 2012.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこれだけではわからない事が多い リーダーやプレイングマネージャーの書籍を併読する事が必要 また、全般的に読みやすい文章ではあるものの、読みづらい(理解しづらい?) これは、筆者が多読は止めたほうがいい、との考え方から納得した
0投稿日: 2012.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐々木さんの著作は、現在の若い仕事人への応援歌。どのレベルの人にも役立つ言葉が多い。「すべての源は”熱い志”である」
0投稿日: 2012.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ部下を持つ立場である課長の仕事を語る本。実際に著者自身が課長時代に知り得た、人を預かり育てる立場の意義・重要さの真髄を、余すところなく開陳している。精神論ではあるけど、具体論もたくさんあり、非常に実用的。僕は課長じゃないけど。
0投稿日: 2012.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司からのお勧め。 ビジネス書が不得意な私でも読みやすくわかりやすい本でした。 この手の本は、さらりと一度読むだけではなく、きちんと噛み砕いて自分で行動してみながら考えていかなければいけないな、と。 鵜呑みにせず、自分自身と自分の環境に置き換えて、もっときちんと考えながらやっていきたいと思います。
0投稿日: 2012.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の本棚に置いてあったのを拝借。 さらっと2時間くらいで読める。ためになることも書いてありそうな感じだけど、この手の本は読むだけではあまり意味ないんだよなあ。。自分の境遇に置き換えてよくよく考えてみないと...。機会があればゆっくりもう一度時間をとって読んでみてもよいかあなあ、と思ったり。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ“The サラリーマン”が詰まった一冊。良い意味で。 私も会社人生3年にして良くも悪くも自分の環境におきかえ考えさせられる言葉が多々ありました。 この語りかける手紙形式には、ひと言ひと言に胸を熱くさせられました。
0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身もこの佐々木氏と同じような経験をした。 しかし、その当時の私は両方を支えるだけの器の大きさを持ち合わせていなかった為、家族の方をとり、課長職を返上した。 今となっては。。の話になってしまうだけなのだが、やはり思うのはこの本をその当時の自分に読ませることができたのなら。。 また人生は違ったのかも知れないが、今は今で十分幸せ。
0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ東レ研の佐々木さんの著書。ビッグ・ツリーなどとは違い、マネジメントに近い領域を取り扱っている。仕事10か条は定番だが、全体的に30代から40代前半向けには分かりやすい内容だと思う。 ノブリス・オブリージュ、白洲次郎にも関連するが、必要な姿勢だと思う。経済合理性、利己主義でいつまでもやっていては、周囲は白ける。高い視座で物事を捉えるようになりたいもの。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象に残ったフレーズ「批判精神なき読書は有害」「志さえ高ければ、スキルは自然とついてくる。高い志が人を動かす。」「大局観を養うためには、常に上位者の視点で考える。」
0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は課長ではないけれど、課長クラスの人はこうあって欲しい、と頷けることばかり書かれていた。 上司はどーんと構えていてくれたらそれでいい。そして、困ったときには指示を出してくれるぐらいがちょうどいい。
0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「課長」ではありませんが,管理職の端くれに昇任してから,何冊か管理職ビギナー向けの本を読みました。 内容は他の本と同じような点が結構あるので,目新しいことはそれほどありませんが,印象に残ったのは, 「要は,君が感じているまま,君の人間性のまま自然体で振る舞うことです。」 「確かに君はリーダーですが,あくまでも一個の人間です。」 という部分。 昇任して半年,「管理職としてどう振舞わなければいけないか」ということを無駄に考えすぎて,肩に力が入りまくって,少々空回り気味なところに,この部分を読んで,少し立ち止まって考える機会を得られてよかったと思います。 別の機会に読めば,また違った感想になるかもしれません。
0投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ週刊東洋経済連載時から愛読。当時は部下を持っていろいろ悩みながら仕事をしていたので、この連載からほんとにいいアドバイスをたくさんもらった。 ー仕事の進め方10か条 ー仕事ダイエットプロジェクト ー自分の家庭事情含めたなやみを自分からさらけ出すことで部下も話しやすくなる ー課長だからといって格好つけるな ー上司を味方につける『定期的に報告し相談する』 ー部下の昇格には全力を注げ ー20-30代は思い切り仕事に熱中することも大事、平凡な働き方ではなかなかその道のプロにはなれない。
0投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ部長に事前に相談し、味方につけておく。 今いる会社が最終の職場ではない。そのつもりでスキルをのばす。 読書で得た知識は現場に生かす。 自己実現がいかにモチベーションになるか。成し遂げるべき志をもつ。 仕事をいかに捨てれるか。必要なものは二割。君にはもっと大事な仕事に携わってもらいたいから、この仕事は少し力を抜いて構わない。 資料、事務処理、はシンプルにすること。 常に上位者の視点と視野にたつ。
0投稿日: 2012.01.22
