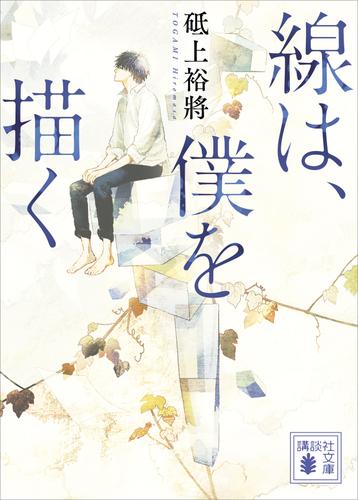
総合評価
(270件)| 106 | ||
| 92 | ||
| 49 | ||
| 7 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を体験した。 そう感じさせるような"美"の表現に惹きこまれた。 ただ形の、技術の美しいを探求するのではなく、水墨画における真髄を追求、模索してゆく姿にただただ憧れた。 自分は青山君のように懸命に挑んだことがあるだろうか。 心のうちを表現する事が苦手だ、何事にも希望を持てないなど何処か共感を誘われるような青山君を通して自分を改めて捉えなおしてみようと感じた。 これからの青山君の姿を見る事は叶わないが目に浮かぶように成長していく姿が想像できた。
12投稿日: 2025.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ芸術を文章であらわすのはすごいと思う。透明感のある作品。 生きるを線で表す技術もそれを感じとれる感覚も芸術センスがある人は見方が違ったりするのかな。
8投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログへのあこがれを持つ自分がいることを気づかされた。水墨に携わる作者による作品だけにより、迫るものがあった。白い世界、死でなくてもだれもが持つものなのか。私にもある。だから救われる作品であった
0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログメフィスト賞っていうからもっとドロドロしてると思ってたけど、透明感がすごい。読みながら何度「水墨画」で画像検索したことか。水墨画って趣味のイメージ(好好爺が描いてる)だったから、プロが少ない筆数で精巧なものを仕上げるとは知らなんだ!揮毛会、見てみたいなぁ。何度も緑茶を飲む描写が出てきて、私もついつい飲みたくなってしまった。
0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ『日日是好日』を読んだ時のような清々しさと静けさに包まれる、気持ちの良い時間を過ごせた。自分としっかり向き合う時間を捻出するのは忙しい現代人にはなかなか難しいが、わずかでも設けたい。綺麗すぎるストーリーに反発を覚える人も少なくないと思うが、そこは二の次でただただ未知の水墨画の世界とその世界観に浸ることが心地良い。霜介のように没頭できることに出逢えることが奇跡だが、気軽に何かを始めるフットワークの軽さを持たねば。映画も観てみたい。
2投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ先に続編の「一線の湖」を読んでからの読了。 正直に言ってしまうと続編の方が面白かったため、是非続編の方を読んで見てほしい。 ひょんなことから水墨画の世界に入った青山君が、水墨画を通して両親の死に向き合っていく。 作者がプロの水墨画絵師ということで内容は本格的で芸術的な面が強い。私は全く芸術に縁のない人間だが心ととにかく向き合い作品を生み出す彼らの生き方に心が動かされる。 水墨画ののように全てを書きすぎず余白があるような感じを受けた。
1投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説は文字のみの表現であり、そこには読者に想像の余地が残されている。誰もが、自分の中で登場人物のイメージを作り、その世界を楽しむ。しかし、その想像を超え、自分の知らないはずの感覚が生まれ、心酔してしまう作品がごく稀にある。まさにこの作品がそうだ。水墨画を知らないはずなのに、青山君の心を通して、頭に浮かぶ絵に感動した。一種の絵画療法的な面もあるが、青山君の純粋さが水墨画に取り組むことで、周りの人の温かさを吸収していく。小説の文学要素というより芸術性を感じさせられた。
1投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ砥上裕將さんの作品を初めて読みました。これまで私とは全く接点のなかった水墨画が題材になっています。 水墨の世界に入っていくきっかけに少し無理があるようにも感じましたが、美しい文章でその場面を想像しながら読み進めました。 とにかくやってみる、観察して、真似をして、繰り返し練習する、いろいろなことに通じるなと思いました。 自分の全く知らなかった水墨画という新しい世界を少しだけ知ることができました。技術技巧だけでなく命を描く、シンプルなだけに逆に奥が深いのだろうと感じました。
45投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を全く知らなくても何故か見える…そこにどんなものが描かれているか何となく見える…気がする。 毒のないストーリーが読みやすい全員推せる。
14投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵を描くことが好きなので、初めて知る水墨画の世界に魅了されました。 白黒の濃淡の世界に見出す「生命の美しさ」 水墨画に没頭し、人と関わる中で自分の中の喪失感に折り合いをつけていく主人公。 見出してくれた先生との、病院でのシーンはとても良かった。 どんな菊を描いたのか、とても見たくなりました。
1投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ともかく描くことだ。そして常に問い、立ち止まり、顧みて、また描く、その連続だよ」 本作を読んで、湖山先生の言葉一つ一つが僕に突き刺さった。この作品のモチーフは水墨画であり、言葉で表現することは至難の業であるが、砥上さんの表現力によって、すんなりと読むことができた。 殻に閉じこもっている主人公を救い出した芸術は、水墨画だけでなく絵画や音楽にも当てはまると思う。 ギターをやっている身からして、1番上に書いた文に深く共感した。正解のない世界で、ひたすら考える主人公に感情移入した。 水墨画がやってみたくなる作品でした。
2投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ両親を二年前に突然交通事故で二人とも亡くした青年霜介。 あまりのことで何も考えられなくなって 自分の世界、何もない世界に閉じこもってしまっていた。 ひょんなことから 水墨画の世界に導かれる。 彼の純粋な心が水墨画の世界と響き合い 自分だけの世界から外の世界へ抜け出し 生きることの意味を見いだす。 水墨画を通して描き手の所作、心情を 丁寧に描写していく。自分が 描き手や水墨画をあたかも目の前にするように感じられた。 水墨画のことはあまり良く知らないが、ここに登場する湖山先生、湖峰、千瑛先輩ら、そして主人公霜介の絵をぜひ見てみたいと思った。 もちろん これは小説なので見れないけれど どこか水墨画展で出会えたら嬉しい。そう思わせられた小説でした。 ちなみに 作者は水墨画家だそうです。
1投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ千瑛が青山君のことを、ただのド素人だと思っている頃は面白かった。でも、自分にない無いモノを持ってるんじゃないかと気付いてからは、ただの説教臭い普通の小説になってしまった。キン肉マンであろうがドラゴンボールであろうが、自分の隠された素質を知らない内が一番楽しいのだな。
0投稿日: 2025.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
楽しむ.自然に. 四君子 春蘭: 深山幽谷に孤高に咲く理想の姿,風格 竹: まっすぐスタッと立っていて,折れずに柔軟というところが理想の姿 梅: 厳しいときを耐え抜きながら花を咲かせるというところが理想の姿 菊: 厳しい寒さの中でも薫り高く咲いているところが理想の姿 そうありたい. この物語はとても美しい.水墨画の話を通して主人公が水墨画を通してみた美しい世界を文字で表して自分に見せてくれているようだ. 自分にも同じようにつらかったことがある.誰にでも同じようにつらかったことがあるだろう. それを同じように表すことができるくらい深みにまで到達できていない.もしくは外に表現するやり方を見いだせていない. 今,私の目には細かな美しさの潰れた圧倒的な光の集合体のような美しさしか見えていない. いつかちゃんと見れるといいのだけれど.
1投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ第59回メフィスト賞 第3回ブランチBOOK大賞2019大賞 第17回 本屋大賞 第3位 花を見る目が変わると思った。 花は水墨画の重要なモチーフであり、花を描くことは、命が刻々と姿を変えている瞬間を線で表現するということ。花は今この瞬間を生きていて、同じ姿は二度と見られないのだと理解したら、より美しいものに思えてくる。 白と黒だけで描かれた花が真っ赤に見えたり、余白さえも彩りとなるという水墨画の魅力を知り、興味がわいたし、線一つ描くことへの重みが伝わってきて芸術の世界はすごいなと感じた。 さっそく水墨画を生で観てみたい気もするけど、素人の私がなにかを感じ取れる自信が全くない。 絵画だって、説明を聞いてもそうなの?としか思えない芸術感覚の乏しさ。 だけど文字で綴られるからこそ伝わる感覚もあると思うので、本書のおかげでちょこっと水墨画を理解したような気分でいる。 ストーリー自体は、単純だし、そんな上手い話がと思うので感動的なわけではないけど、私は青山君が羨ましい。 巨匠に導かれながら水墨画を通して自分を解放していく、そんなのめり込める手段を持てるのは誰だって憧れると思う。 湖山先生の名台詞がたくさん出てくるのも魅力の一つ。一番好きなのはこれ。 「拙さが巧みさに劣るわけではない」
45投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ①私自身、書道を習っている。 水墨画と書道は似ているところがあるように思う。 手本通りに書くのではなく、生命力のある見た人に感動させる作品を描きたいと私はいつも考えている。 この点は、似ていると感じた。 自分も、より良い作品を作るために、主人公たちのように、努力を続けたいと思う。 ②本作品を読んで、1度、春蘭を描いてみたいなと思った。 ③水墨画という芸術を文字だけで読者に伝えてることを単純に凄いなと思った。 主人公の成長に感動するオススメの1冊です! 何度も、読み返したくなる作品です。
1投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。過去に辛い経験をして無気力に生きていた主人公が、ある日ひょんなことから才能を見出されて水墨画の世界で生きる意味を見つける。こう書くとよくあるストーリーだけど、読み易いし描写も素晴らしいし、何より水墨画という題材がいい。イメージは出来るけどあまり知らない世界で読んでてとても興味が湧いた。 実写にするなら師匠の爺ちゃんは木場勝己のイメージ。
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログあなたが表現する方法を持っていますか・・・ 家族を失い生きる希望もなくなんとなく生きていた時 バイト先で偶然出会った水墨画の巨匠・篠田湖山に気に入られる・・・ タイトルが気になって読むことにしました。 人生の哲学が詰まっているような小説だと感じました。 如何に自然体でいられるか簡単なようでとても難しく感じます。 一つの線で人の人生を感じることができると思うと日々の文字や線の息遣いを感じてしまいそうです。 映画化もされているそうなので、どのように映像化れせているのかも気になる作品でした。
41投稿日: 2025.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章がとても美しく、水墨画に向かう人たちの美しい気持ちをそのまま表していると思った。心の動きをこんなにも細やかに、繊細に表現できることに圧倒された。
3投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ芸術について文章で表すのは難しいと思っていました。『美しい』などの普通の形容詞だとありきたりですし、奇をてらった表現をされるとついていけないし… しかしこの作品は、主人公が水墨画に対して感じたことをとてもわかりやすく真っ直ぐに描いており、一体感を感じながら読み進めることができました。霜介が水墨画と出会えて良かった。
13投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ両親を亡くし塞いだ青年が出会う水墨画の世界。 無限の心を通して描く、再生の物語。 青春小説のような瑞々しさよりも 人との繋がりや自分との対峙、 水墨画の奥深さに向き合った作品。 臨場感を持った描写は作者が水墨画家だからこそ納得がいく。 人との強い繋がりを断たれる怖さを知る霜介が踏み入れた、人との繋がりが濃い世界。 師匠の心意を図り、あらゆる技法を組み合わせた上で自分の線を描くことを模索していく。 ライバルの千瑛は同じ志を持ち互いを認め合う仲間でもあり、その想いが憧れなのか好意なのか、家族か理解者か、答えを出さずに続く2人の関係性がよかった。 水墨画の知識が全くなかったため、 読了後、四君子について調べてみた。 繊細で儚い筆致を帯びた美しい線には 画面越しでさえ引き込まれるなにかがあった。 今の心模様も、心が捉えた景色も 全てを描く一筆書きの水墨画。 自身の心と正直に向き合えたときに初めて 自分の線に出会えるのかもしれない。 霜介が最初に教わった墨をするときの心持ちは 水墨画にとって大事な精神だったのだとわかる。 邪念なく、穏やかに。実直に。 外の世界へ自分を探す旅もいいが、 水墨画を通して自分の内なる冒険もしてみたい。
3投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ墨の香りが漂ってくるような 静かでどこまでも美しい 水墨画といえば中国の山奥の仙人の というイメージしかなかったけど 文字で表現される墨の絵がとても美しい 1人の青年の深く沈んだ心が 水墨画と携わる人たちとの関わりで 自分自身を 命を見つめることで 変化していく様子がとてもきれいでした 自分自身を語る術を持つことの 尊さが感じられる作品でした
1投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで水墨画について触れたことが全く無かったので興味深く読んだ。 水墨画の世界はとても深くて主人公が水墨画を通して自分の人生と向き合い成長していく様子が応援したくなる。 読み終わってから著者の方が水墨画の方だと知り、著者の方の水墨画をネットで見て作品の余韻を味わえた。
1投稿日: 2025.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これまで全く知らなかった水墨画の世界。 読み始めたら、一気に読み終えてしまった。 たくさんの書き留めておきたい言葉が有りましたが、私には「必ずしも・・・・・・」「拙さが巧みさに劣るわけではないんだよ」との湖山先生の言葉が印象に残りました。 本当に良い物語でした。
17投稿日: 2025.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を通じて再生と成長を描いた物語だ。両親を亡くして心を閉ざしていた主人公・青山霜介が、ひょんなことから水墨画と出会い、師である篠田湖山やその孫娘・千瑛との交流を通じて変わっていく様子が感動的に描かれている。 印象的な場面の一つは、霜介が初めて「無」の感覚を体験するシーンだ。墨を紙に落とし、線を引く瞬間に、彼は自分が墨の流れと一体化していくように感じる。水墨画では、線が単なる形ではなく、描き手の内面や心情そのものを映し出すものであることが、この場面から強く伝わってきた。また、篠田湖山が語る「空白もまた絵の一部だ」という言葉が印象的だ。描かれていない部分にこそ意味があり、そこに見る人の想像が広がるという考え方は、霜介が人生の空白を抱えていることと重なり、物語全体に深みを与えている。 さらに、千瑛との関係性も霜介の変化に影響を与える。水墨画に真摯に向き合う千瑛は、当初は霜介に冷たく接していたが、やがて互いの葛藤を理解し合うことで少しずつ心を通わせていく。二人が切磋琢磨しながら成長していく姿に、友情や信頼の大切さを感じさせられた。 この作品を通して、人生には形のない空白や欠落があるが、それを恐れず受け入れることが大切だと気付かされた。また、何かに真剣に向き合い、自分の心を表現することで、過去の傷や失ったものさえも意味を持ち始めることを教えてくれる。水墨画の繊細さと奥深さを感じながら、自分自身を描くように生きることの大切さを学んだ。
0投稿日: 2025.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画には興味ゼロだったけど、面白かった。絵師の描写にが言葉巧みですごい。 水墨画の揮毫見てみたい。
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画は、学生時代に授業で描いた記憶がありますが、これほど奥の深い素晴らしいものだとは気づきませんでした。水墨画家ならではの視点で描かれているので、描写がとても丁寧で面白かったです。
1投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
事故で両親を亡くし孤独感と喪失感で心を閉ざした青年がひょんなことから水墨画界の巨匠の内弟子として水墨画を学び周りの人たちと触れ合ううちに自分と向き合い生きる意味を見出す物語。文字を読んでいるのに目の前で水墨画が描かれているような臨場感に思わず息が止まる場面が多々あり。 少し説明っぽくてくどさを感じる部分はあるけど流れるような繊細な文章そのものがとても美しく著者がそもそも水墨画家ということに納得。ライバルが超絶美人黒髪ロングお嬢様はベタすぎると思わなくはないけど心を閉ざした青年を刺激するにはちょうどいいかと納得。 もちろん物語の設定は違うけど少し前に読んだ『ひと』と核の部分で似たところがあるような気がした。とりあえずかれこれ30年以上黒髪ストレートロングの私は水墨画を始めてみるか。いや違うたぶんそうじゃない。
1投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ心情表現が抜群に上手いですね。 主人公の境遇は自分とは全く異なりますが、その辛さや心の成長などが非常に良く共感できます。 馴染みのなかった水墨画の美しさも、文字で書き表すからこそ良く表現されています。自分は読後水墨画に興味を持ち、色々と調べました(春蘭には心躍りますね)。
0投稿日: 2025.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
両親の事故死が原因で心を閉ざした少年。その少年が水墨画と出会い心と現実を取り戻していくお話。 水墨画のなんたるかをまったく知らない私でも水墨画が描かれていく様子が想像できた。筆と紙、その周りの道具の在処。墨を磨る、筆をとり、紙の上までの運びやその所作まで文章でとてもここまで表現できるものなんだと感心しきりでした。 それが読み進める上で好奇心になりまた、関係する人物も個性がはっきりしていて悪い人はいない。なので安心して読みすすめられた。 結論として、エンタメとしてすんなり入っていける物語と、途中ハッピーエンドがみえてくるので気持ちのいい読書時間となりました。
19投稿日: 2025.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を通しての心の成長を描く物語。 全く馴染みのない芸術だけど、なんとまあ深いものかと感じさせる小説。技術は勿論のこと、心の在り方、それに伴う世界の見え方全てが筆跡に反映されていく。この有り様をよく物語にできるなあと思ったら筆者自身が水墨画家とのこと。色んなバックボーンの小説家さんがいて面白いですし、自分の知らない世界を描きだしてくれる小説家さんにもっと出会いたいなと思いました。 扱うテーマ、主人公の背景から仕方ないですが、内面描写が非常に多い。それ故にストーリー自体はあまり波が無く感じる部分が少し気になりました。
35投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公は両親を事故で突然失くしており、埋められない喪失感の中、ただただ生きている。そんな青年がある老人と出会い、心を取り戻していく。 水墨画の世界をこの小説で初めて知った。今までは美術の教科書で見る程度。この芸術の世界を少しでも知ることができて良かった。 書道も字を見ればその人の性格などが分かるというが、水墨画も同様で、筆一つで性格や心が表れるそうだ。 一つの対象をよく見ることの奥深さ、難しさ。写実的にとらえるのではなく(水墨画でそれは難しい)その対象にどのように命を吹き込むのか。このような課題に直面しあがくうちに変わっていく青年の心の動きや変化がよく表現されていたと思う。
2投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ線は、僕を描く。この一文は深い。 自然になることは、とてつもなく難しい。今、自分は自然だ、と思うことは自然ではない。 普段から気をつけていることは、綺麗なものを綺麗と言えること、素晴らしいことを素晴らしいと素直に思えること、道端の小さな草木に目を留めることができること。これらは自分にとっては凄く難しい。主人公の素直な心がうらやましい。
0投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ事故で家族を失った大学生。 何に対しても無気力で、孤独から抜け出せなかった主人公が、水墨画と出会い、先生、友人を通して、孤独から解き放たれる物語に涙が出る。 水墨画を通してなぜ孤独、無気力から解き放たれたのか、ここがこの物語で最も重要な部分。 『命を見なさい』 孤独のつらさ、人は一人では生きてはいけない事を改めて感じる。 大ドンデン返しとか、意外な犯人とか、お涙頂戴的な脚本でもなく、人物の内面や、物の状態、表現方法が多彩で、活字でなければ表現できないことが中心にくるところが、とても良い。こういう本がいいね。 『濃緑の葉がみずみずしく映る。 命としての花も極限のところでは、刻々と姿を変えている。現象に対して、手は遅すぎる。』 『美の祖型を見なさい』 表現、言葉というものは素晴らしい。 自分の心が豊かになっていく事を感じられる作品。 ご一読を。
8投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ優しさが溢れ、気持ちが温かくなる絵師のお話。美とは何か。水墨画と向き合うことで見出していく主人公の苦悩と喜びが瑞々しく描かれている。そこに言葉はいらない。絵が全てを物語る。筆遣いや息遣いが生々しく浮かんでくる迫力は見事です。才能を見出す巨匠や尊敬しあうライバル、くすり笑える心優しい友人。心が洗われる思いです。テンポも良く、主人公の成長も自然な流れで良いものを見せてもらった感覚になりました。最初の数ページを読んで引き込まれ、結局深夜にかけて一気読みになってしまった。大好き度❤️❤️❤️❤️❤️
15投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりテーマにならない水墨画をテーマにした作品 水墨画を通して人の心の成長を描くいい作品だと思った 「花に教えを請いなさい」という言葉が好き
1投稿日: 2024.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を通して、心が変化していく様子がとても繊細に表現されていて美しい物語でした。 水墨画のことを全然知らなくても、読み終わった時には水墨画の魅力をすごく感じることができました。
20投稿日: 2024.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「水墨画の世界」はこんなに奥深いのか...!と感じた。 一本の線を見ただけで描いた人の性格や感情がわかる程あらゆるものが筆致に表れる。 上手い下手が優劣にはならない。 力強さや柔らかさ、繊細さや大胆さなど描く人によって唯一無二の美しさが宿る。 しかし、誰が見ても圧倒的に美しい作品を描くためには相当な修練が必要となる。 超有名水墨画家の湖山先生が開催する大会。 ここで授与される湖山賞の獲得を目指し、一心不乱に腕を磨き上げる。 著者が水墨画家だと後から知って納得した。 そうでなければこの作品は生まれないと思う。
3投稿日: 2024.12.05線によって心が絵になる
たった一筆、サッと線を引いただけで、紙の上に蘭の葉がありありと立ち現れる。 透けて見えるほどの葉脈や、葉そのもの重みまで伝わってくる。 ただの一本の線が美しい絵となる様は、さぞや息をのむ瞬間だろう。 素人は筆の動かし方に目を奪われるが、穂先にどれほどの水分を含ませているかなんて想像にも及ぶまい。 そこに薄墨と濃墨がどのような割合で含まれているかなども。 線の太さや細さも、肘の上げ下ろしだけで繊細に調整されている。 主人公は過去の辛い体験からガラスに向かい思い出すということをずっとやっていた。 小さな狭いガラスの部屋で、記憶だけを眺めていた。 そのおかげで、師匠のたった一度の手本を何度も頭の中に再生できた。 腕や手の動き、その速度まで何度も執拗に繰り返し反復することで、水墨画初心者の腕前はいつしかプロも舌を巻くほど上達していく。 弟子の前で実演してみせる際、師匠はあらかじめ見るべきポイントなど伝えない。 あとから弟子が見るべき場所に注意を払い、練習でそれを再現できているかを黙って観察する。 「君はよく見ていた」という言葉は、最上の褒め言葉だろう。 主人公は重度の引き蘢りで拒食症気味。 少し話をするだけで疲れてしまうコミュ障の青年に、たまたま出会った水墨画の大家から目を掛けられ弟子としてマンツーマンの指導を受けるわ、見目麗しいその孫娘がわざわざ自宅までレッスンの送り向かいをしてくれ、最後はその彼女と賞をかけて対決するという、何とも少年漫画のようなシナリオ。 ただ、水墨画の面白さは十分に伝わってくる。 穂先で一本の線を引くことで、真っさらな平面の紙上に、空間が生まれ、時間が生まれる。 何かを始めることで、そこにあった可能性にはじめて気づくように、書き手の心は、線によって表われ絵になる。 何もない場所に突然、描き出され映しとられる人生そのもの。
0投稿日: 2024.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画の話でしたが、これほど興味がない題材で面白く読めたのはこの作品だからかもしれない。 経験もない素人が水墨画の才能を見いだされ、苦悩葛藤しながらも、丁寧に基礎を重ねることで成長していくものがたり。 登場人物の性格や考え方、気持ちの裏側を描くのがとても興味を惹かれました。 個人的に面白かったのはやはり主人公の人と関わりを避けていた故に身に付けた常人にはない超感覚。 視力を失った人間の聴力や嗅覚が常人のそれよりも優れたものになるのと同じことが起きているのを物語で感じられるゾワゾワ感が凄い。
1投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を通した人のドラマが書かれていました。こういうジャンルは個人的にツボなので、高評価なのかもしれませんが、最初から最後まで心にくるものがあり、読み終えた後に、また明日からも自分の人生を頑張って、誠実に生きようと思えます。良い作品です。感謝。
1投稿日: 2024.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉にできないようなあやふやで繊細な心の様子をうまく表現している。 水墨画はよく分からないけど、一本の線を通して心の内側が、言葉より良く相手に伝わる描写にはとても感動した。 主人公は先生から褒められるものの、褒められる絵を描こうとするのではなく、ひたむきに絵と自分の心と向き合い続けるところがすごいと思う。 自分だったら褒められたいと思い、褒められるようなお手本に似せた絵を描きたくなると思う。 周りにある素晴らしいものに気づける心、そして他の人の想いや幸福によって自分の心も満たしていける心を持てるよう生きていきたいと思った。
1投稿日: 2024.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画「ピアノの森」を読んだ時、音の世界を画と文字で伝えられるってすごいと思い、蜜蜂と遠雷を読んだ時、今度は文字だけで音を伝えるのかと驚いた。 今度は、水墨画の世界を文字だけで伝えている、伝わってくる。 モノトーンで、強さも儚さも動きも一瞬で決まってしまう、後戻りのできない絵画。 そんな世界があって、そこに情熱をかける人たちがいる。 お話は、再生とそれを包み込むやさしいものでした。
0投稿日: 2024.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024年、150冊目 臨場感あふれる表現が秀逸。 まさにそこで見ているような書きっぷりだった。 水墨画に興味を持たせる良作、映画も気になる。
19投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を先に観て静粛の使い方が絶妙だったので原作を読みたくなりました。 水墨画を描くシーンを文字だけでどのように想像させるのか興味がありましたが臨場感のあるすばらしい描き方でした。 当然ながら各登場人物がより深掘りされていて背景が良くわかりました。ただし、静粛の裏返しでラストに向けて盛り上がりは控えめです。
8投稿日: 2024.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画ってそんなにいきなり描ける?と思いながらも気持ちよく読了。もう少し挫折も欲しい所ではあるけど、その辺りは続編の「一線の湖」に期待。千瑛のイメージは完全に今田美桜だね。
1投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ綺麗。そして多幸感。 ここまで綺麗な小説に出逢った事がなかった。物語の構成、言葉選び、登場人物の言葉、登場人物の心(解説にもあるが、とくに主人公の素直さ)のすべてが、緻密で、繊細で、意地の悪さが取り払われた、一切の濁りを含まない清水のような小説だった。 読んでいて常に心地が良く、ここまで快いものを描ける著者の技量と精神に脱帽した。 私自身は、自分の生を全うすることをどうでもいい(あるいは辞めたい、止めたい)と思いはじめたときのことを思い出すと、「真っ白」というよりかは、どちらかと言えば出口の光が見えない「真っ黒」な空間にいる感覚がした。たぶん、大事なものを失って目の前が白紙になるというのと、他人の悪意や自分の過ちによって先の人生が見えず真っ暗になるというのは絶望の種類が違うんだろうなと想像する。ゆえに、両親を亡くして心が真っ白な部屋に閉ざされてしまった主人公が、どんな感覚の痛みを身体に抱え、もがき、克服していったかについては想像してもし尽くせないし、すべて共感できたかといえば嘘になる。しかし「命」について粘り強く向き合い、他人と、そして自分が「命を生きること」(=生命)の意味を理解していく主人公によって綴られる言葉、また、そんな主人公へ惜しみ無く与えられる湖山先生の教えの一言ひと言は、「人生に疲れている」私の胸にも深く突き刺さり、読むたびにボロボロぼろぼろと涙が止まらなかった。 命とか人生を語るにはあまりにも綺麗過ぎて、きっとこれが全てではないだろうと捻くれた感情も抱きつつ、(それは私が捻くれた人間なせいであって、この作品のせいではない)こんなにも心地良い他者の著作を読む事ができて、幸せだと思った。作者に心から感謝したい。
1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「勇気がないと線なんて引けない。一筆だって間違っちゃいけない場所に、勇気を持って挑んでいくのが水墨画」 たった一筆を表現する言葉のなんと緻密なことよ。目の前で描かれていくような、緊張感と臨場感。本来目で楽しむ水墨画の魅力が文字でいきいきと余す所なく描かれていて、書道を始めたい私には、同様の世界観にワクワクが止まらなかった。 映画の方も是非見てみたい。
7投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ第6回ビブリオバトル全国大会inいこまオンライン予選会4で発表された本です。 https://www.youtube.com/watch?v=UDHFwzeI8_I 2021.2.21
0投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【2024年177冊目】 「飾り付けをするだけの簡単なお仕事」そう言われ、僕こと青山想介がやってきたのは水墨画の展示会場だった。謎の老人に声をかけられ、なぜか一緒に水墨画を鑑賞することになった僕だったが、白と黒で構成される世界観に興味をもつ。それは喪失を経験してからの初めての感情で――ふとした偶然の出会いから始まる僕が僕を描くための物語。 刺さらなかった〜申し訳ないくらい刺さらなかったので、途中からずっと「なんでこんなに話が入ってこないのか」と悩みながら読んでました。読み終わってから水墨画を改めて検索してみたんですけど、読む前に見といたら良かったなこれ。想像だけの水墨画が頭に浮かべながら読むには、描写される絵を頭の中で上手く描けなかったのが第一の敗北です。 あとは、細かなところのストーリーに疑問ばかりが生じてしまい…なんというか、物語に余白がないというか余裕がないというか。斉藤さんが止めちゃった理由も、「西澤さんと湖山先生は関係ない」みたいな話も、それまでにそんな話出てましたっけ?ってなったし、そもそも主人公に感情移入が全然できなかった。両親が死んで打ちひしがれているのはわかったけれど、両親とどう過ごしたのかとかの描写が一切ないので、ただ肉親が死んで悲しいしか受け取れなくて、それ以上の心のうちがわからなかった。 あとは、見ただけで悲しさがわかるか?というのもあるし、会って間もない人間を弟子にしようと思うのがあまりにもご都合主義ではとも思うし(創作だからと言われてしまえばそれまでですが)水墨画をほとんど知らなくて、でも習い始めて、いうてもそんなに頑張ってる描写あったか…?水墨画の基礎についても調べずに先生のところに習いに行く…?すごい先生だってわかって、やってみようって思うなら2回目以降何かしらの知識入れて行かないの?わからん、主人公がずっとわからん。 あと、紙を立てた状態で絵を描いたら、墨が下に垂れないのだろうか、絶妙な力加減?垂れをも計算した絵を描いてる?空気感だけですごさを描写していたような気がする…。 描写とかは多分美しいんですけど、なにぶん、全く頭に入ってこなかったので、楽しめなかった…賞を取ったりをしている作品なので、私の読書の仕方がこの作品とあってなかったんだと思うんですけど、ここまでピンと来ない作品も珍しくて、好きな方には大変申し訳ない。 映画とか漫画の方が、一つ一つの描写に間を持たせてるかもしれない、見てないのでわかりませんが。なんというか、呼吸がしずらい作品でした。
2投稿日: 2024.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ知らない世界を感じることができる一冊。 色や香りが広がる感覚。右脳を刺激され続けました。 自分の内側を深く見つめる事ができ、また周りのあらゆるものから命を感じ取ることができるる主人公、絵師たち。命を感じで命を吹き込む。美術や書画の世界はわからないと敬遠してましたが、ちょっと違う目線で鑑賞してみたくなりました。
2投稿日: 2024.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ喪失感が一杯の彼の元に水墨画が生きる意味をもたらしてくれたことを丁寧に描いた作品。繊細な青山君が前を向く姿に感動した。
1投稿日: 2024.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年本屋大賞第3位。 主人公が水墨画と向き合う中で、様々な人と出逢い、立ち止まっていた人生を再生させていく。 主人公の内側が中々見えない分、出てくる登場人物が皆、個性的で、いい味が出ていた。 タイトルが美しく、内容もまさにその名の通り。全く知らない「水墨画」の世界に魅了されました。 最後の一言も美しく締めくくられている。綺麗な余韻。 早く先が知りたくなる、、との感覚はなく、ゆっくりと読み進めました。
3投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくよかった。水墨画の世界に圧倒された。水墨画を描く描写に、息を飲んだ。水墨画を通して、青山くんがいろんなことに気づき、成長していく姿は素晴らしかった。線は生き方そのもの。水墨画を知って、外側の世界が美しくみえた。―心の内側に宇宙はないのか?
1投稿日: 2024.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ白黒の世界と思っていた水墨画で、花の色が判るって、水墨画って凄いんだなあと思いました 一度、しっかり鑑賞したいです
0投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画の話。 水墨画ってどんなものかネットで調べて、その絵をイメージするとより内容が頭に入ってきておもしろい。 人物が皆あたたかくて、嫌味がある人は出てこない。 その分読みやすいのがこの本のいいところ。 本の内容としては、両親を亡くした主人公が何も手につかず虚無感の状況から、大学の手伝いをきっかけに水墨画に取り組んでいく話。なんかこれといって、名場面というか盛り上がりみたいなのはないが、主人公の真面目さというか言われたことを貫く姿勢は読んでいて気持ちいい。あと、作者の水墨画に対する知識に感服した。
13投稿日: 2024.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学で特にやりたいこともなく過ごしていた青山霜介は、友人の紹介で水墨画展の設営を行っていたところ、ある老人に声をかけられる。一言二言会話したところ気に入られ、弟子になることに。その老人ははたして、水墨画の巨匠篠田湖山であった。湖山に弟子入した霜介は、湖山の孫娘の千瑛と、次年の湖山賞をかけて水墨画で対決することとなる。 ストーリーがわかりやすく、文句なしに面白い作品である。ろくにあらすじも読まずにタイトル買いした一冊だが、これは子供でも楽しめるエンターテインメントだ。 と大きくぶっては見たが、本作を一言で表すと「異世界に行かない異世界作品」と言い表せるだろう。なんの取り柄もない、目立たない主人公が、一言二言喋っただけで達人に見出され、自覚していなかった超強い能力を無意識に駆使して、超絶美少女でツンデレのライバルと対決を果たす。思いっきり異世界物のプロットだ。 脇役もお調子者で常時サングラスを掛けている同級生、その同級生に惚れたこちらも調子の良い事をいう小うるさい脇役ヒロイン、冷静沈着で冷たい絵を描く弟子、エモーショナルで軽い弟子と、完全にアニメの配役である。だからといって悪い意味ではなく、キャラクターが立っている。 また情景も師匠の家、自宅、学校(当初全然出てこない)と絞られているため、違和感を感じることも少ない。学園祭のときにどこでどうなったのかわからなくなるくらいだ。 アニメ世代のエンターテインメント小説。中学高校の読書感想文にちょうどいいボリュームとわかりやすさでおすすめ。 アニメ化でもしてるのかと思ったら、映画化されてたんだね。実写は大変そうな話である。
0投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作品、ドラマや映画にしたら良さそう、と思って読み進めていたところ、すでに映画化されていることを知り、以降は霜介と千瑛が脳内ですっかり横浜流星と清原果耶に。内容は予定調和、ご都合主義なところもあって、なんというか霜介の出来が良すぎて非現実的だ。関西風に言うと「なワケあるかい!」。これでは天才の物語になってしまう…。心に残った言葉。「四時無形のときの流れにしたがって、ただありのままに生きようとする命に、頭を深く垂れて教えを請いなさい。私は花を描け、とは言っていない。花に教えを請え、と君に言った」「たった一輪の菊でさえ、もう二度と同じ菊に巡り合うことはないのだ。たった一瞬ここにあって二度と巡り合うこともなく、枯れて、失われていく。あるとき、ふいにそこにいて、次の瞬間には引き留めることさえできずに消えていく。命の輝きと陰りが、一輪の花の中にはそのまま現れているのだ」
5投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は、うそん?で始まる。 曲がり角で女子とぶつかって変な転び方しちゃって平手でぶたれて、で何かが始まった的な立ち上がりで。しかも孤高の美女ときたらひがむで。素で。 ただ中盤からが真骨頂で、静謐というものが作品に加わり出すと途端に別の顔を見せる。幽玄な世界がゆらゆらと立ち上ってきて、なぜだか胸を締めつけらる気持ちになった。 消えかかる美、死んでいく星みたいな。 墨を扱った作品でいうと『墨のゆらめき』(三浦しをん)しか知らないけど同じように面白かった。書の道は裾野が狭まる一方だし、とことん過去と向き合うことになる。その中でも未来志向の人間がいることが力強く目に映る。 ──ほんとうは力を抜くことこそ技術なんだ。 主人公が悟った瞬間の言葉。それよ。 ありふれた生活の中でも、この技術は役に立っている。
33投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名に惹きつけられたのと、映画化されてたので興味があって読んだ。全く知らない水墨画の世界だったけど、新しく知れて楽しかった。よくこんなに水墨画のことを細かく、詳細を描写できるなと思ったら著者が水墨画家さんなんですね。映画でどんな水墨画が描かれているのかも見たくなりました。
11投稿日: 2024.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画ってこんなに奥が深いのか、ととてと驚きました。絵を描くのが好きな私だからこそ共感できるところもあり芸術って難しいなって思いました。
0投稿日: 2024.06.28本質をよく捉えた良い題名だと思う。
どことなく夏目漱石の「草枕」を思い出した。読み進んでゆくうちに、「草枕」とは真逆だということに気づいた。「草枕」は、現実の世界からドロドロした欲望や感情を取り除き、現実世界を清浄な一枚の絵として見ようとする作品だった。この本は、一枚の水墨画の中に、作者の焦りや孤独や生命そのものを込めようとする。油絵やCGと違い修正のできない水墨画であるから、ひと筆ひと筆を描く、その瞬間の心情が絵に影響してしまう。失敗できないという恐れと、それを超えるための勇気。失敗しないための集中力。それは、私が線を描くのではなく、線が僕を描くような境地なのだろう。この本の題名は、この本の本質をよく捉えた良い題名だと思う。
0投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ハチクロ」や「スラムダンク」のように、圧倒的な才能と長年の努力とのぶつかり合いは個人的に大好きです。そこに恋愛や芸術や青春や大会が絡んできたら、そりゃもう、堪りません。 読後にヨダレを垂らしながら感想書きたくなる。そんな名作です。
2投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画に出会い成長する大学生の物語。水墨画といつ文化や奥深さ、大学生活やコンクールを通じたエンタメ要素で飽きずに読める。水墨画に興味がわく一冊。
1投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わったあと、水墨画の実際を見たくなって、映画の方も続けて見ました。ストーリーはだいぶん変わってたけど、青山霜介役は横浜流星さんがピッタリでした。
34投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ何個か印象に残ってる言葉たち 「失敗することだって当たり前のように許されたら、おもしろいだろ?」 →失敗したらどうしようって考えは、ほんとに怖いし首を絞めるもの。後輩や子供を育てる時に、失敗してもいいからどんどんやろうって言える人間になりたい 「少なくとも今日は楽しかった。それだけで、僕にはほかのどんなことよりも価値があった」 →両親の死によって心を閉ざした主人公が、本当に久しぶりに楽しさを感じられたシーン。心にじんわり響いた。 「たぶん僕が与えられた場所ではなく、歩き出した場所で立ち止まっているからだろう」 「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」 →歩き出した場所で立ち止まることには意味がある。後者の言葉はよく聞くけど、主人公の経験を通して、この言葉がすっと心に入った。とにかく歩き出すことで見える景色があるってことを、なんとなくはわかってるけど、自分でも実現はできてないし、人にも上手く伝えられないんよなあ。 水墨画に関しては、主人公は少年漫画の主人公チート感(元々激弱だけど芯に才能があって根気強くがんばって周りを驚かせる的な)あった
3投稿日: 2024.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を知らなかったけど、その世界観や精神性を垣間見れた気持ちになる。孤独な青年が人との繋がりを取り戻していく形もセンチメンタルでなく描かれていた。読んでいるのに水墨画の絵が広がっていく不思議な感覚。表現力が素晴らしいです。
6投稿日: 2024.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語は単純で読みやすいが、水墨画で描かれた作品や薔薇の花の描写が細やかで芸術の奥深さを感じる作品。技術だけでなく表現、自分の生き方が線に反映される。自分も音楽をかじった身として、頭に置いておきたい。
3投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログある日大学生の青山霜介が芸術家の巨匠篠田湖山と出会い、水墨画の道を歩き始めるお話で非常に感動する作品でした。 水墨画を奥深く感じさせる文章は、読み応えたっぷりで凄く良かったです。
4投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画を通して1人の青年が生きる意味を見出すお話。自分の想像力が足りず、絵の描写がよく分からないところもあったけど、読み切れた。 展覧会に行ってみたくなった。
3投稿日: 2024.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画のことはまったく分かりませんが、優しい世界観がとても綺麗だと感じた 登場人物もみな温かく、やや異質な古前くんと西濱さんがとても好きです
2投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログまるで漫画のような小説 目で見る絵が言葉を尽くして表現されている 水墨画をきちんと鑑賞したことのない私にはその表現からその絵を想像できなかったけれども 内面が映し出される水墨画を今度鑑賞してみたいと思った
1投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログお話が優しすぎてちょっと私の好み的に、、、 えっ!横浜流星くんで映像化してるんですね ぽいぽい、確かに青山くんっぽい
25投稿日: 2024.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ細やで美しい描写のおかげで、小説で絵を描くということを見事に成されている作品。この作品きっかけで水墨画に興味が湧いたので、展覧会へ見に行ってみます。 若干、ラストにかけての長さとラストの興奮が比例しない感じはありました。そのぶん主人公の心理描写はかなりしっかりしているので、心動く場面は多々ありました。。。 主人公はこの先どんな絵師になるのか、ぜひ続きが読みたい……!
8投稿日: 2024.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ静かに優しくそして力強く、水墨画のような素敵なお話でした。 大きなドラマがあるわけではないけれど、真摯に向き合うことの力に心を動かされる。
1投稿日: 2024.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨の世界を文字で表現されたような美しい文体 後半自宅に帰る場面では静かにひたひたと感情が揺さぶられ なぜだか分からないが涙が滲んだ。
1投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとって価値ある読書体験は、現実の生活にも本の影響が及ぶことだと思っている。 この本を読んだあと、道端に咲く花の花弁一枚一枚や葉の一枚一枚が、それぞれ全く違うものなのだという当たり前のことに、目が向くようになった。自然に生きているということを、すっかり忘れていたような気がする。生きている植物たちとともに日々を過ごしてみたいと初めて感じた。 また、水墨画に向き合う霜介の姿を通して、水墨画の魅力を知ることができた。実際に見てみたい、書いてみたいと思わせる丁寧で愛のある描写で、作者が水墨画家でなければできない表現だと思う。霜介の内面の描き方も分かりやすく、それでいて深い。きっと作者は普段から、様々な事象をよく観察し、考察し、そして大切にしているのだろうと伝わってきた。水墨画についてイメージしづらい部分や難しい言葉は出てくるが、それを越えるとても心に響く作品だった。
0投稿日: 2024.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画って美しい。 シンプルな黒だからこそ、その濃淡や太さ、掠れ具合までにも書き手の想いが溢れてる。
0投稿日: 2024.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画という知らない世界ながらとても楽しくて、先が気になり一気読み。両親の突然の事故死から心を閉ざしてしまった霜介が水墨画を通して、真摯に生きる姿がとても心に染み入った。湖山先生の一言一言がとても印象的だった。
2投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の時に両親を事故で亡くし塞ぎ込んでいた青山霜介が水墨画と出会い、描くことを通して再生していく話。 先に映画を観ているけれど、小説のほうがより霜介の心情を細かく描写している。 命=心を描く水墨画。ガラスの部屋から出れずにいた霜介が周りの人々に影響を受けながら自分を取り戻していく。 読んでる間は特に意識してなかったけど読後感が本当に爽やかで、読んでよかったなあとじんわりと感じる作品だった。
2投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログまたひとつ、大切にしたい本に出逢ってしまった。 とても静かに、決して急ぐことなく、丁寧に読みたい本。 青山くんの中のガラスの部屋の様相も、水墨画を描く過程も、クリアで繊細で美しい文書で描かれていて、読み終わってしまうのがもったないと感じるほどだった。 水墨画とは、こうも奥が深いものなのか。 青山くんと水墨画、青山くんと出会う人たちとの関わりの中から、生きるということを考えさせられた。 心に留めておきたいたくさんのフレーズたち、読中に感じたそこはかとない静寂を纏う空気、心洗われいつまでも物語の余韻に浸りたいような読後感。 いつかまた、必ず再読したいし、続編も必ず読みたい。
2投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ青山君が白い部屋から出て、湖山先生とのやりとりで少しずつ自分の線を見つけていくところが、人間に血肉が通っていくようでよかった。素直に他者の意見を取り入れることができたのは、自分がなかったからだろう。線を見つけてから、どう成長していくのかが楽しみ。 翠山先生とのやりとりがとても好きだった。 それに西濱さんの自由な感じは、みんな好きだろうな。
1投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ砥上裕將『線は、僕を描く』 2021年 講談社文庫 第59回メフィスト賞受賞作でデビュー作。 主人公である大学生青山がとあることから水墨画の巨匠と出会い、内弟子となり、水墨画を通して人生を再生していく物語。人生の再生というより心の再生。 あまりちゃんと水墨画鑑賞をしたことがないので、文章で書かれた水墨画の世界を理解しきれるかなとも思ったのですが、読んでいると頭の中にどんどん水墨画が広がっていきます。 途中、「春蘭」など画像検索してみたりもしたけど。 まさに水墨画の世界を通して広がているけれども、そこには人としての心の在り方、見つめ方などを説いていました。 師匠である湖山先生の言われることが心の教訓でもあり、僕の心にも考えるきっかけをくださっていました。 じんわりと、でも鋭く心に響く素敵な作品でした。 #砥上裕將 #線は僕を描く #メフィスト賞 #講談社文庫 #読了
1投稿日: 2024.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
途中リタイアのため、評価なしです。 水墨画の大家である老人に未経験者である主人公が見そめられ、その孫娘と一年後に対決? 何やらドラマチックな展開に一抹の不安。 かなりの遺産を残して亡くなった両親。 2人の死をきっかけに自分の世界に閉じこもった主人公。 その後、なぜか大学に通うようになり、なぜかゼミに潜り込むことができ、そこでなんだか良い人っぽい友人に出会い…。 うーん。都合が良すぎる。。 とても評価が高い作品なのに、 カバーイラストも良い雰囲気なのに、 水墨画という新しいジャンルに興味をひかれたのに、 ちっとも気持ちが物語に入って行けない。 友だちの登場シーン以降は 読みたいと思う気持ちがしぼんでしまった。
23投稿日: 2024.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ水墨画との出会いを機に繊細な主人公が自身の内面と向き合う術を得ていく。文章で表される水墨画の世界が脳内で映像化され感動に震え幸福感で満たされるような感覚になり後半は涙が止まりませんでした。著者は水墨画家さん。
10投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ第59回メフィスト賞受賞作。メフィスト賞はミステリ色が強いですが、面白ければ何でもOKな賞で、懐の深さを感じます。水墨画という馴染の薄い分野なのに、それを感じさせない筆力が見事です。素直に面白かった。
1投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしかったです。感動でした。 水墨画のことはほぼ何の知識も無い私は 日本古来の文化であり、「墨で描く絵画」ぐらいにしか思っていませんでしたが、これほど奥が深く 心揺さぶられ、感動するものだと知り 読み終えたあとも 動画で何度も水墨画の木や草などに生命が吹き込まれる様子を見惚れていました。 笑笑 物語は、 両親を突然亡くし、心を閉じこめ何も感じることも出来ず孤独感や喪失感だけが体の中で渦巻いていた、青山霜介が、 水墨画に出会う事で少しづつ少しづつ 自分の心にある孤独感、喪失感を解放して 世の中のすべての生を感じ表現することの難しさやきびしさを、師匠である篠田湖山や その孫でありライバルの 篠田千瑛にアドバイスや見守られ成長していきます。 最後まで、あっという間に読み終え 生きるとは、極めるとはとたくさん考えさせられるお話でした。
31投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今までほとんど触れたことのない水墨画の世界。 多少難があるけれど、水墨画の魅力、そして一つの芸術に向かい合っていく覚悟を、上手に文章に乗せていた。 初めて見た絵を、画家の意図を汲み自分の中に受け入れる能力を主人公の霜介は持っている。 技術は練習すれば身につく部分が大きいだろう。 だが、霜介の持つその能力・センスは持って生まれたものであり、後天的に身につけることは難しい。 宗助の目に、若い頃の自分と同じ虚無を見た篠田湖山はただものではないが、篠田湖山に見出された霜介が持つ、作品の本質をつかむセンスを努力で磨いたのは霜介自身だ。 霜介の、内向きすぎる思考を、あっけらかんと外に引きずり出してくれる大学の友達・古前くんがいい味出している。 ただ、両親が死んでからほとんど食事もとらず、死んだように生きていた霜介の保護者であった叔父夫婦。 誰も住んでいない霜介の実家を処分することもせず、光熱水量を払い続けるというのはちょっと現実的ではない。 特に霜介が大学進学で家を離れてからも、そのままにしておくのは果たして正解なのか。(結果的には正解) また、電車で1時間しか離れていない霜介の一人暮らしの家に、一度も様子を見に行かないというのもどうか。 だって、ご飯食べない子なんだよ。 てっきり霜介に興味がなくて、厄介払いをしたのだと思っていたら、心配していた…と。 うーむ…。
2投稿日: 2024.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館の片隅に置いてあったこの本をたまたま手に取った。帰りの電車を待ちながら読み始めるも、今まで見たこともない清らかな言葉に心奪われてしまった。 水墨画って雪舟が描いてたやつだよね?レベルの芸術に疎い私でも、目を閉じれば目の前に真っ赤な薔薇が浮かぶくらいの著者の表現力たるや… (解説を読んで著者の正体を知り納得) ※ここからはネタバレ 個人的に刺さった表現が第四章にある。 「今いる場所から、想像もつかない場所にたどり着くためには、とにかく歩き出さなければならない。自分の視野や想像の外側にある場所にたどり着くためには、歩き出して、何度も立ち止まって考えて、進み続けなければならない。」 この長い一文は、水墨画に出会い自分との対話を通じて素晴らしい作品を創りあげた主人公の生き様を表しているのではないかと思う。
2投稿日: 2024.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログひょんなことから水墨画の世界に足を踏み入れることになった青山霜介 墨と水だけで描く世界の奥深さが面白かった 水墨画、見に行ってみたい 水墨画を習い始めたばかりの霜介への湖山先生の言葉 「おもしろくないわけがないよ。真っ白な紙を好きなだけ墨で汚していいんだよ。どんなに失敗してもいい。失敗することだって当たり前のように許されたら、面白いだろ?」 初めてのことに挑戦する時 失敗についてこんな風に言われたら 挑戦することが気楽で楽しく感じるだろうなと思う
2投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログめっちゃ頑張って描いてたレビューが 投稿前に消えてしまって 心折れましたが、気を取り直して。。 あぁ下書き機能がほしい。。。 さて続編が出たということで再読 読んだ本をすぐ忘れちゃうので 新たな気持ちで読めましたー! こちらは水墨画の話 なかなか馴染みのない水墨画ですが 読んでいると絵の様子や 描いている姿が目に浮かんできます 素晴らしい表現力です 主人公青山の気持ちも丁寧に描かれていて 少しずつ心が溶けていく様子が伝わってきました この物語は出てくる人がみんな素敵です 湖山先生はすっとぼけているのに キメるところはビシッときめてかっこいいし 西濱さんの周りを和ます空気が素敵だし 千瑛さんの情熱的で実は素直なところに 読み進めるほど好きになります! 翠山先生や斉藤さんのように 言葉少なな人たちも 魅力的に描けるのってすごいです! 個人的には古前くんが結構好きで 『彼はいつも斜めに向かって とても真っすぐな男なのだ』 という表現が気に入っています(^^) こういう登場人物に魅力のある作品 大好きです!!! 常に自分の内側と向き合って 水墨と向き合っている人たちが発するセリフは とても響くものが多かったです 中でも できることが目的じゃない やってみることが目的なんだ という言葉はハッとさせられました 自分も、子供達にも そんな気持ちでいろんなことに 取り組んでいきたいと思いました 映像化されてるんですねー! 気になるなー!!!
122投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ引きこもりがちの僕が水墨画に惹かれていく話。 水墨画に興味が持てる良い機会でしたね 作者様が水墨画をやられてる?とのことで素晴らしい表現描写が光る作品でした~ ただ、心の部分を丁寧に書かれているため想像力が試される本かなと 個人的には久しぶりに文字が浮かぶ本で最初から最後まで良い時間を過ごせました
3投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
両親を事故で亡くし塞ぎ込んでいた霜介が水墨画と出会い成長していく話なのだが、水墨画の表現がとても美しい。 実際に絵はないが文字を追っていると脳内に再生される。 あと古前くんと川岸さんがなんとも言えないいい仕事をしていた。
19投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく不思議。 朝の電車で、ちょっと読んではこっくりしていたところから、降車駅の一駅前まで、降車駅に滑り込むまで、そしてついには乗り過ごした。 主人公の置かれた境遇も 今どき珍しいどこかカタイ会話も 題材としている世界も すべてが自分とはかけ離れていて、最初の数ページを読んだ時には、退屈とさえ思ったのに。 夢中になる、とはどこか違くて。 先が気になる、とも何かが異なる。 最後までこの人たちを見届けたい。 ただ自然に、静かにそう思う感じ。 水墨画なんて少しも知らないわたしの胸の奥にさえ、作中で描かれていく作品が立体感をもって立ち上がる。 文章表現の技術がすごい。 これだけくどくど書いておいて、最後にそんな陳腐な言葉しかひねりだせぬ、わたしの表現力のなさよ 笑
3投稿日: 2024.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読んだことがあって、タイトルのみでは内容が思い出せなかったので再読しました。 心を閉ざした僕が、水墨画によって心を開いていくという話です。 続編も出たと聞いたので、そちらも借りてみようかと思います。 水墨画の表現について細かく書かれていて、とても素敵だと思いました。
4投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。感性が感じられる文章。水墨を観てみたいって思う。アートだ。小説日日是好日を感じさせた。 分からないわからないともがき、自分なりの答えを出すこと、人生そのものだな。
6投稿日: 2024.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
水墨のことは全くのど素人ですが、表紙と映画の宣伝に惹かれ、オーディブルで読了?聴了?しました。 言葉よりも描くことは雄弁だと。描くことで言葉のせかいの外側に行ける。言葉では伝えられない、言葉がなくても伝わるものにすごく印象に残っているけれど、それを表しているのもまた言葉なんですよね。それがまたすごいことだと。挿絵ひとつ見ない中で、文字だけで水墨画を表現されたこと本当にすごいなと思いました。水墨画見に行ってみたくなりました!
3投稿日: 2024.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログひとつのサイコセラピーのようなお話だった。両親を事故でいっぺんに亡くした青年の止まったままの時間が、水墨画と出会うことで少しずつ動き始める。両親がいないことを青年はだれにもあまり話したがらなかった。悲しみを言葉にしてしまうと、それがあまりにも心から乖離したものになってしまうことがわかっているからだった。深い喪失から救われるためには、言葉のいらない絵を描くことが必要だった。絵を描くことは自分を描くことであると、静かに教えられた、否、気づかされた。 読んでいる間、漫画の絵を想像するくらい、きれいで凛としている小説だった。それが青年のピュアな心を醸していた。ラノベっぽさもあった。水墨画という渋みのある文化がテーマであるだけに、ギャップがあるが、そのギャップは昨今ではめずらしくない。登場人物がまさにアニメキャラのようであったから、もっと奥行のある描き方だとさらによかったように思う。
12投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと積読だった作品。 その時から書名に少し疑問がありました。 線は、僕を描く どういうことかな?と思っていました。 主人公は大学の法学部に籍を置く、青山霜介。 展示会のアルバイトで水墨画の巨匠・篠田湖山と出会った。 そこから霜介は水墨画を通して自分と向き合っていく。 ひたすら線を描く。 ひたむきに描く。 そして、作品を生み出す。 主人公の霜介が失っていた感情を線を描くことで恢復していく様子を読んでいて、これは「生」の物語だと思いました。 水墨画という作品がどのように生み出せれ描かれているのかも知ることが出来ました。何より、水墨画を描かれるシーンが細部まで書かれていて、筆の動き、墨の濃淡、体の動きが容易に想像できるくらい素晴らしい表現でした。そして、書名のことも解りました。 水墨画の奥深さと迫力の中に霜介の「生」が描かれていて涙なしでは読めませんでした。 是非、続編を読もうと思います。
25投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆や墨に憧れるものの、どうも苦手にしている。それでも書についてはたまに作品展などに出かけることもあるし、NHKなどで講座なので技法や精神などを見聞きすることはある。翻って水墨画。寺院や博物館で古典的な軸や襖絵を見ることはあるし、水墨画で描かれた年賀状を目にすることはあるのだが、現在活きている作品として水墨画を意識することはなかった。 自分の心のなかのガラスの部屋から抜け出すことが出来ずにいる青山霜介。アルバイト先の展覧会場で水墨画の巨匠・篠田湖山と出会い、なぜか湖山に気に入られ、その場で内弟子にされてしまう。とんでもなく非現実的な話の展開に戸惑うが、謎は徐々に明かされていく。 湖山の孫娘、篠田千瑛、兄弟子となる西濱湖峰・斉藤湖栖、大学の友人古前・川岸、湖山の盟友藤堂翠山やその孫の茜。そうした人々と触れ合いながら霜介は水墨画に惹かれていく。その過程で読者も何故水墨画?という疑問が解消できていく。 やがて、湖山の描く姿のなかで霜介は自身のガラスの部屋で湖山が描いていることに気づく。命とは変化し続けるこの瞬間のこと。命のあるがままの美しさを見ることが美の祖型を見ることであり、水墨とはこの瞬間のための叡智であり、技法なのだ。自らの命や森羅万象の命そのものに触れようとする想いが絵に換わったもの。それが水墨画だ。 水墨の線が命を、自分の周りの人々をつなぎ、自分自身を描く。そして「誰かの幸福や思いが、窓から差し込む光のように僕の心の中に映り込んでいるからこそ、僕は幸福なのだ」と気づく。読者も物語を読み進める中で自分の幸福を気づくと思う。 作者は、水墨画家とのことだが、小説でも次作も期待したい。
4投稿日: 2023.12.24
