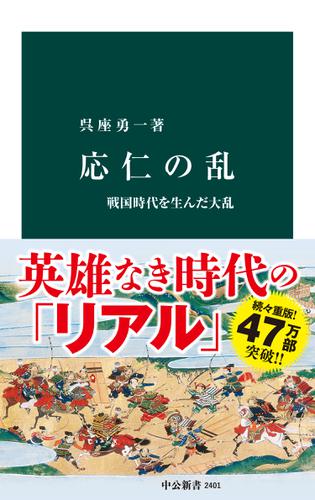
総合評価
(187件)| 30 | ||
| 67 | ||
| 51 | ||
| 15 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログたしか新書大賞だった本作。ずっと積読いてあったんだけど、ふとこのタイミングで。しかしこれ、だいぶハードル高いな。確かに、名前は小学生以来知っているけど、その実態はというと、ほとんど分からなかったりする応仁の乱。そういう点で興味があるのは間違いないけど、考えてみれば、それで新書一冊って、相当深い内容になりますわな、そら。本書は、高校日本史程度の知識は当然で、そこからさらに踏み込んで考察します的内容。これを読む前に、日本史の読本をまず読まなきゃってことだわ。失礼しました。
0投稿日: 2025.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ興福寺の僧による日記を主なベースとして、応仁の乱前から、乱後までを詳しく紹介してくれます。ただ登場人物と年号が多すぎて、巻末の年表に頼らないと、前後関係がわからなくなります。なんとか読み終えた感想としては、室町版「仁義なき戦い」をダラダラと続けていたのだなあと思いました。応仁の乱のはるか昔に、ローマがカルタゴをザマの会戦(アフリカ大陸)で破ったことを思うと、本書に描かれている争いのスケールの小ささに悲しくなりますよ。
10投稿日: 2025.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前は知っているがその内実はほとんど知られていない応仁の乱。そのあまりの縦横無尽ぶりに高校の教科書でも概要以外はさじを投げるほどだが、本書ではその応仁の乱を大和国・興福寺・畠山氏の諍いから方程式のように紐解いていく内容となっている。 大元は6代将軍足利義教の短気が尾を引いていること、日野富子と足利義視、細川勝元と山名宗全の関係は義尚誕生時点でも決して悪いものではなかったこと、実質的には勝者のいない泥試合でも形式的には結局どちらの勝ちで終結したのか、応仁の乱は何をもたらして戦国時代に繋がっていったのかなど、視点を変えるだけでこれだけ明瞭になるものかと非常に驚く(ただ、これでもまだ相当に複雑ではあるが…)
1投稿日: 2025.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史上屈指の大乱ということであるが、応仁の乱が始まる前もそこかしこで戦いは始終起きているし、乱が終わった後もいろいろなところで戦が絶えない。京の都が思いっきり戦場になったというところや、動員された軍勢の規模が違うのだろうが、この情勢であればいつ大きな戦争が起きてもまったく不思議がない 著者は応仁の乱が当事者の意図を超えて拡大した様子を第一次世界大戦になぞらえるが、『八月の砲声』を読んだときも、「列強がそれぞれ軍事力で相手を潰すことしか考えていない。これは戦争にもなるよな」と思ったので、両者が似ているという点に関しては同意見である 名前がたくさん出てくるし、集合離散も激しいし、一族の中でいがみあうので、誰と誰が敵で、誰と誰が味方なのか、頭の中を整理するのが大変。国みたいなものもぶつかり合いではなく、やくざの抗争のほうが近い
4投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前にこの本がかなり売れていたと聞き読んでみた。応仁の乱は「あー学校で習ったな」くらいの知識量だったのでとにかく読み進めるのに苦労した。とにかく登場人物が多いし関係も複雑。それだけ応仁の乱が難解ということか。 第三章に入ってからは割とすんなり読めた。 笑ってしまったのは、戦乱が長期化してきた頃、西軍の仲間うちで正月の遊びをしたところ勝敗を巡った喧嘩に発展し、80人の死者負傷者が出たと言う箇所。いやなにやってんの?!と思わず突っ込んでしまった。 せっかくこの本を読んだので、応仁の乱が舞台の小説「室町無頼」を読んでみようと思う。
2投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代の契機となったとされる応仁の乱を大和国興福寺の視点を交えつつ描く。戦国時代の始まりは、応仁の乱とされるが、明応の政変がきっかけと著者は指摘。応仁の乱後もかろうじて維持されていた守護在京制は、明応の政変を機に完全に崩壊し、守護は国元帰り国人を統率せねば領国を維持できなくなった。
0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ呉座勇一氏の作品は2作目。前作「陰謀の日本中世史」が面白かったので手に取ってみた。応仁の乱というと学生時代に1467年(人の世むなし応仁の乱)というゴロで覚えさせられたのしか記憶にないが、本書を読むにあたっては最低でも東軍と西軍の主な顔ぶれくらいは知っていた方がより楽しめる。ごく簡単にいうと東軍は細川勝元、畠山政長、斯波義敏、京極持清、赤松政則、武田信賢。西軍は山名宗全、畠山義就、斯波義廉、一色義直、土岐成頼、大内政弘。これに将軍家の跡取り争いである足利義尚と義視が加わるのだがこの義尚と義視が東軍についたり西軍についたり両軍入れ替わりするので話がややこしくなる。この乱は結局東軍が勝つのだが東軍の大将・細川勝元の当初の真意は、足利義政→義尚という伊勢路線でもなく、足利義政→義視という山名路線でもなく、足利義政→義視→義尚という規定路線の維持だったと考えられる。また乱の前に伊勢貞親・季瓊真蘂(きけいしんずい)・斯波義敏らの失脚=文正の政変があり伊勢貞親という共通の敵がいなくなると、細川勝元と山名宗全の激突は避けられないものになったという。応仁の乱が勃発した要因は複数あるが、直接の引き金になったのは畠山氏の家督争いである。つまり政長と義就の争いである。そして朝倉孝景の寝返りが応仁の乱の戦局の転換点であったことは学界でも共通認識となっているらしい。(朝倉孝景は東軍に寝返った。)詳細→ https://takeshi3017.chu.jp/file10/naiyou34402.html
0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年も前に話題になった本で、ずっと読みたいとは思っていたのですが、ついつい後回しにしてしまい、このタイミングでようやく手に取りました。 応仁の乱については、小学校でも中学校でも高校でも習ったはずなのですが、戦いの中身についてはほとんど記憶に残っておらず…。 そんなわけで、新たに学ぶつもりで、読み進めました。 応仁の乱は、領地の争いや家督の争い、後継者問題、役職の争い、武士としての仁義、過去のしこりに由来する仇討ち、といったものが入り組んでの戦いであり、しかも、戦い開始時の東軍の総大将の細川勝元と西軍の総大将の山名宗全は、別にバチバチの関係にあるわけではなく、むしろ畠山氏の家督争いに巻き込まれた結果、いずれも総大将になるなど、応仁の乱は、覚悟を決めてのスタートではなく、やむにやまれぬ事情で始まったのですね。 まったくの素人の自分からすると、詳しすぎてついていけない部分も多かったのですが、それでも、応仁の乱の概略はつかめた気がします。 ちなみに、本書は、奈良の興福寺にまつわる二人の僧(経覚(きょうがく)と尋尊(じんそん))が残した記録が柱となって構成されているのですが、約500年前でありながら、京都での出来事を奈良にいながら把握していた二人の情報網は、驚き以外の何物でもありません。 本書を読んでいて思ったのですが、応仁の乱をもっとちゃんと理解するには、当時の価値観や道徳観や生活や制度をもっと知らないとだめですね。 今回は、それらがないまま読んでしまったので、浅い理解で終わった気がします。 そこはやむを得ないとは思いつつも、反省点。
2投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱(1467-1477)は、日本史の画期と言われる。 画期というからには、日本史は「応仁の乱」前と、「応仁の乱」後に区分出来るということだ。 ということは、我々は「応仁の乱」後を生きている、と言える。 日本の文化、日本人の宗教観•意識、日本語は、この乱を境に大きく変貌した。 本書は、その画期を成す乱をコンパクトにまとめているが、その全容を掴むのは極めて難しい。 何故なら、保元•平治の乱のように、敵対勢力を明確に区分して、勝ち負けをはっきりさせることができないからだ。 最初は、敵味方、勝ち負けがはっきりしているように見える。 しかし、それがズルズルと全国レベルに広がり、10年以上もそんな状態が続くのだから、明確さを欠くこと夥しい。 我々が歴史で習うのは、将軍家、摂関家、各大名家の対立による、京都を戦場とした戦いだ。 「応仁の乱」は、細川勝元と山名宗全を両対象とする戦乱であると習ったはずだ。 だが、それは「応仁の乱」の発端に過ぎない。 守護大名から、寺院、地侍に至るまで、あらゆるレベル、あらゆる地域で、内紛、抗争が、燎原の火のように広がり、日本列島全体が混乱の坩堝に巻き込まれたのだ。 それが「応仁の乱」の捉えどころのない真の姿だったのだ。 誰もが直ぐに終わると思っていた京都の擾乱は、直ぐに地方に飛び火し、従来の体制を悉く破壊し尽くし、遂には、戦国時代の幕を切って落とす。 本書は、日本史の時代の変革を画する日本最大の内乱の動的メカニズムを詳細に描く。 しかし、それも簡単ではないことは言うまでもない。 読み通すには、忍耐が必要とされるが、読む価値はある。
0投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国乱世の扉を開いた応仁の乱はいかに起こり、なぜ長期化したのかを読み解いた本。 高校日本史の知識が身についていることが必要。授業だけでは見えてこない、戦の経緯や室町時代の本質を学べます。
0投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ経覚・尋尊という奈良 興福寺の僧侶の眼を通しての、新しい「応仁の乱」像。 経覚の父は関白・九条経教、母は浄土真宗大谷本願寺の出身。尋尊の父は関白左大臣一条兼良、母は中御門宣俊の娘と言う、所謂良家の出家者。当時はこのように公卿からの出家者は、大きなお寺の今で言う貫主の地位につけたようだ。 さて新しい視点の「応仁の乱」と言っても、高校の授業で、恐らく教科書の数行程度の記述でしかなかったと思われ、自分にとっては新しいも古いもなく、そのまま素直に読解することを心がけた。 この時代、敵になったと思ったら寝返ったり、親子・兄弟の間でも敵味方になったりと、実にややこしい。で、なかなか読み進めることが出来ない。 自分にとっての発見は、この時代、新しい文化が武家の経済的支援によって花開いていったということ。 15世紀後半以降、在国するようになった守護・守護代は、国元に立派な館を築いている。 実際守護館(守護所)の遺跡は発掘調査によって全国各地で見つかっているが、そのほとんどが平地の、一辺が150~200mほどの方形館で、その敷地内には連歌や茶の湯を行う建物「会所」があった。主殿・常御殿・遠侍などの配置も判で押したようである。主家斯波氏に対する「下剋上」を果たした朝倉氏の居城として知られる越前一乗谷の朝倉氏館も例外ではなく、地域的な特色・個性は見られない。こうした守護館の構造は、「花の御所」(室町殿)などの将軍邸を模倣したものだったらしい。 山ロも周防守護の大内氏によって、京都をモデルにした地方都市として整備された。しばしば「小京都」と呼ばれるこの都市の原型は、大内氏が抱いた京都文化への憧れによって生み出されたのであるとのこと。 一方、現実の京都はというと、守護や奉公衆の在国化によって住民が激減し、市街域も大幅に縮小した。 と言うことだ。 京都のほとんどが焼けただけではなく、新しい芽が外に伝播して行ったのね。
13投稿日: 2024.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ享徳の乱の勉強をするにあたって、中央で起こった大乱を無視することはできんやろうと思って、再読。 まぁ理解度は6割ってとこだけど。
0投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。以前にベストセラーとなった本だが、複雑怪奇な応仁の乱を前後を含めて、大和の僧の視点から論述しているが、分かりやすく読みやすい。
0投稿日: 2023.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ年号は覚えたが、前後の出来事はほぼ知らない状態で読み始めた。一応、最後まで読んだ感想は、難しかったの一言。 しかし、少なくとも読む前よりは「応仁の乱」の理解が深まったので、2回目があればより理解できると思う。特に、応仁の乱後の戦国時代への流れや京の文化が全国的に広がった経緯など、なるほどと思う。 「終章 応仁の乱が残したもの」がまとめ的だったので、この章を先に読むのも有りかと思った。
0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史は応仁の乱前後で分かれるといわれるほどの戦いなのに、ほぼ内容を知らなかったため、手に取りました。 主に以下のことが新しく知れて、興味深かったです。 ・応仁の乱の発端は、足利義政の後継者争いではなく、有力守護大名の畠山氏の家督争いであった。 ・主な対立軸である細川氏、山名氏は早めに和睦を結んだものの、他の同盟者の思惑が入り乱れ、最終決着が長期化。 ・足利義政が、畠山氏や他の有力者の争いで、討伐と釈免を繰り返し、節操が無さすぎる。。 ・応仁の乱までは、守護大名は京都に住むのが普通であったが、乱後、自国の統治の重要さを感じ、自領地に住むようになった。 ・足利義政・義尚親子のどちらが最高権力者か不明、義尚より後の将軍家がニ系統で分裂など、権力機構が思ったよりあいまい。 ・将軍の力が弱くなった故、細川氏は、要職である管領を儀式の時だけ仕方なく拝命し、その後辞職する自由さ。 興福寺のニ高僧の日記をもとに当時の状況が説明されているため、直接応仁の乱とは関係ない興福寺及び奈良周辺の説明が長い、家督争いとそれぞれの同盟関係等が重なり、勢力図が覚えられない、そもそも人名が読めない等、読むのが困難な部分が多かったですが、全体的な応仁の乱前後の流れが知れて、とても有意義な本でした。 デマや噂話も多く、詳細な記録を辿るのも難しい時代を、このようにまとめられる学者の方の凄さも改めて感じました。
8投稿日: 2022.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
応仁の乱の直接的な引き金は、畠山氏の家督争いにある。畠山氏の弱体を図って当初は連携していた細川勝元と山名宗全だったが、細川方による山名方の弱体化を図るような動きに、様々な大名の利害関係が絡み、東軍と西軍が形成されていく。8代将軍の義政は、片方が優位にならないような策をとっていくが、両軍は互角で戦線は膠着していた。したがって西軍の朝倉氏を東軍に寝返らせ、最終的に東軍の勝利で乱は終わりを迎える。応仁の乱が残した大きなものとして、守護領国制の崩壊を筆者は挙げている。大名は次々と自国へ帰り、分国支配を保証するものはもはや幕府の権威ではなくなった。大名自身の実力がものを言う時代、つまり戦国時代へとつながっていくのである。
0投稿日: 2022.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜかこの難しい本がベストセラーになったらしい。 なかなか理解が不足していると感じているが、中央の幕府の力が弱まって、地方の力が相対的に強くなったことで戦国時代が始まったとも言えるという側面は良く分かった。 何度か読み返して、理解を深めたいと思うのと、大河ドラマ「花の乱」は出来が良かったらしいので、いつか見てみたい。
0投稿日: 2022.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ複雑。戦乱に直接関係はないと思われる経覚と尋尊を軸に語っていることが、読者にとっても幸いしているのかもしれない。客観的に見れたし、二人の物語りに若干の興味を持てたので、何とかダラダラとしつつ、複雑な、この戦いの顛末を最後まで読むことができた。 内容としては大満足。昔読んだ専門書ではない、一般読者向けの応仁の乱の記述に対する自分の記憶がかなり誤っていたのがわかった。自分の記憶だけでなく、当時の記述自体もあやしかったものだと思う。 実質東軍の勝ち、というとは勉強不足で知らなかった事実。また、足利義視が徹頭徹尾西軍だった訳ではないことも、記憶の修正対象案件。
0投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に話題になった中公新書の応仁の乱。これをきっかけに中公新書は歴史実証的な著作が増えていく。 本書については、個人的な知識の問題で登場人物がビビッドにイメージできずにやや字面を追っていたところがある。とはいえ、メインのストーリである管領家をめぐる対立がきっかけとなって天下の大乱に至り、和平交渉もステークホルダーの多さから落とし所をつくることができずにまとめることができなかったこと。すなわち、幕府の力が低下し大名をまとめられなくなっていたこと、加えて将軍義政が日和見的でどっちつかずになっていたため、各勢力がお互いの利益を主張しあった結果、いくさにもなり和平もできなかったという点は理解できたんだろう。結局、幕府の力が落ちていてもはやまとめる力を持ち得なかったということなんだと思う。室町幕府のこのどうしようもない弱さはある意味興味深い。鎌倉・江戸と比べて何がいけなかったのか・・・。 加えて、応仁の乱によって京都が荒廃したこと、守護大名が地元で直接統治しないと統治が難しくなったことなどを背景として、京都の文化が各地に広まったということは興味深かった。越前や周防などの小京都と呼ばれる文化を花開かせたことを、多大な被害をもたらした応仁の乱の副産物として見ることもできるわけで、ありきたりだけれど歴史は一筋縄ではいかないなとも思う。 それにしても、現代の基準で見てはいけないことは当然ながら、いくさばかりで庶民はどうやって暮らしていたんだろうという点、そして代替わり時には徳政令を出すのが当たり前とされていて商売人はどうやって対策していたのかという点は素朴に疑問に思う。現代において徳政令なんて出したら金融が成り立たなくわけで、デットファイナンスはなくなってエクイティファイナンスだけになったりするのではと思ったりするけれど、それでも金融業は続いたんだろうし。
0投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログロシア文豪による長編小説のような複雑さと面白さ。多くの人がしているように、登場人物とその相関図をメモしながら読んだ。800年も前なのに、こんなに詳しいことがわかっているなんて驚き。日本人って昔からほんとに筆まめ。
0投稿日: 2022.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ再チャレンして完読 人名が出るたびに ノートにメモ 人間関係を 見ながら 読んだ 引き込まれる内容 最高
0投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の本は登場人物が多く、状況の推移を追うのには根気がいる。本書はよく整理されていて読みやすいのだが、やはり根気は必要。手っ取り早く応仁の乱とその後の見取り図を得たいならば、終章および後書きを読むだけでも十分勉強になるし、そこだけでもかなり面白い。
0投稿日: 2022.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
応仁の乱 - 戦国時代を生んだ大乱 (中公新書) 新書 – 2016/10/19 馴染みの無い登場人物が多すぎる為に途中で挫折する可能性高し 2017年6月24日記述 呉座勇一氏による著作。2016年10月25日初版。 1980年(昭和55年)東京都生まれ。 1999年3月 海城高等学校 2003年3月 東京大学文学部国史学科卒業 2008年3月 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学 2011年6月 「日本中世の地域社会における集団統合原理の研究 領主の一揆を中心として」で博士(文学) 2012年4月 東京大学大学院 人文社会系研究科 研究員 2014年4月 東京大学大学院 総合文化研究科 学術研究員 2014年10月 角川財団学芸賞 2015年4月 国際日本文化研究センター 客員准教授 2016年10月 国際日本文化研究センター助教 昨年から異例の売上部数を誇っており、気になった為読んでみた・・ 2017年6月23日(金)の読売新聞朝刊の広告には38万部とあった。 しかしである。本書を途中まで読み進みあまりの登場人物の多さに辟易した。 購入された方々も読んできちんと内容を消化しきれているのかどうか疑問だ。 別にマルクスの資本論のような訳のわからないレトリックや修飾語が使われている訳では無い。 本当に知らない人物が多すぎるのだ。 しかも殆ど馴染みの無い人物ばかりだ。 数ページおきでは無く数行おきに出てくる感じだ。 (池田信夫氏もTwitter上で登場人物が多すぎで途中で読み止めたと指摘している) あと奈良の地名や地理についてある程度把握していないと 土地勘も無い為イメージがわかない部分も多い。 地図が多く載っていれば問題ないが、本書にはそれが無い。 自分自身、大学受験で日本史Bを使ったし歴史は好きだし得意だと思っていただけにまさか歴史の本で途中で読むのを諦めるとは予想も出来ず驚いている。 途中からじっくり読み込むのは止め経覚、尋尊の記述部分のみさっと読んだ。 ただ客観的事実の羅列で本書から何か今の時代に通じる何かを読み取るのは難しいと思う。 *もっと知識があれば本書から多くの事を吸収できるとは思う。 しかしそんな読者が何人いるのやら。 個人的に非常に参考になった部分は下記の内容だ。 尋尊が経覚が死ぬ前に経覚の謝金が興福寺に及ばないように尋尊が経覚の弟子ではない事を証明する文書を集積し理論武装していた。 この危機管理、危機回避能力は凄い。 ビジネスパーソンも是非見習うべき点だ。 突き詰めると井沢元彦氏や磯田道史氏のような一般人レベルに伝える、伝わる記述スキルが 現在の呉座勇一氏には欠けていると言わざる得ない。 結局、難しい専門的な話を、格好つけて難しく書いても一般大衆には伝わらないし、 影響力は持ち得ない。 しかし呉座氏は多くの人に届けたいからこそ新書で世の中に出したのではないか。 学術論文ではないのだから、もっと多くの工夫、編集が本書には求められた。 本書のヒットは残念ながら一過性のもので継続性はないだろう。 ただ本書には巻末に人物索引が付いている。 これは高く評価できる。なぜなら索引をつけることは編集の最後になってしまう為に 非常に面倒で索引が無い専門書が多いのだ。 この索引のない専門書は本では無いということを野口悠紀雄氏は常々指摘している。 本書はその意味で紛れもない専門書である。 *ただし一般人には敷居が高い。 願わくば本書の入門的な情報を網羅したものが必要だろう。 (というかたくさん出てる) 池上彰氏が本書を紹介するとしたらその点は指摘するであろうと思われる。
0投稿日: 2021.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
難しかった。 この本は戦乱の中心地の京都ではなく大和国の興福寺の別当の二人、経国、尋尊から見た応仁の乱を記録したものを中心に書かれている。興福寺は守護が置かれず、実質的に興福寺が大和を治めていた。戦乱についてもだが、世間の噂や興福寺の所有する荘園の年貢の徴収など、いろいろと書きつけていたようだ。 人の世むなし(1467)応仁の乱、くらいの知識しかなかった私なので、難しく思えたのかもしれない。 家督相続争いが重なり、そこに所領問題が関係して、戦乱が起こっていったが、犠牲が出ると、それを埋め合わす何かを得ないと戦を止められない、という気持ちがどんどん戦を長引かせてしまった。仲間を引き入れると、さらに埋め合わす何かが必要になって、ますます戦乱が長引く…。そこは現代と同じかもしれない。 また敵の補給路を断つ、というのが戦いに勝つ手段というのが昔も今も変わらないのが面白かった。戦いというのは武力だけではない。 名前も知らない武将が沢山出てきたが、畠山義就に関してはドラマにしてもいいんじゃないか、というくらい傑出した武将だったと思う。畠山氏の家督相続が応仁の乱の一因であることは間違いないと思うし、日野富子じゃなくて、畠山義就を中心にしたドラマのほうが面白いと思うけどなあ。 山名宗全が畠山義就の肩入れを御霊合戦の時にしてしまったのが、山名宗全と細川勝元の決裂の引き金なんて、武士はメンツで生きているんだなあ、とつくづく思う。 あと山名宗全と細川勝元の年齢差が驚きであった。
5投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ室町時代の動乱期をあるお坊さん2人の記録をもとに紐解く本書 お坊さんのそれぞれの性格の差から来る事件等の評価の違いもおもしろいし、もちろん歴史の事実としての応仁の乱(とその前後)もおもしろい。 ただ、登場人物の多さに誰が誰だかわからなくなってくるところがたまに傷であり、そこは乱れた世相だったから仕方なしとして頑張って読み解いていかなければならないのがすこし辛かった。 自分は動乱の歴史とか読むのが好きなのでそういった人にはオススメ
0投稿日: 2021.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史書を読むことは人の名前を読むことで、その点でいつも苦労する。人名索引と行ったり来たりで、できれば索引にもフリガナを振っていただけると助かる。資料の綿密な読み時による詳細な説明と考察には敬服する。
0投稿日: 2021.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時以来、日本史が苦手で予備知識ほぼゼロの私のような者が手を出しても、読み終える頃には多少は「応仁の乱」について語れるようになっているような、それくらい丁寧に、噛んで含めるように解説してくれている一冊。 「応仁の乱」がわかりづらい最大の理由は似たような名前の登場人物がやたら多くて(そもそも論な気もするが)、各地でひたすらダラダラと競り合いをしているから。 一周読み終わるまでに10日くらいかかったが、地図と照らし合わせつつ順を追って読み解いていけば決して理解できないものではない…と思う。 とりあえず、足利義政という男はいっそ潔い程の日和見主義者。 細川・山名の争い、斯波氏の後継争い、将軍家の跡目争い、それぞれを理解することが大切。 それにしても乱の真っ最中に風呂とそうめんを楽しんだ古市胤栄という人に一番興味が湧いてしまった。 3刷 2021.7.4
1投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代に突入する直前の、混乱した室町時代後期。 仏教勢力が支配する大和国の二人の僧が残した日記を読み解き、応仁の乱の起こる背景、直接の切っ掛け、戦況をつぶさに記します。 近年の歴史研究の飛躍的な発展を反映させており、紋切り型でない実情を交えた記述に感じるところが多くありました。 実際の領地支配の様子、地域支配者同士の小競り合い、室町幕府と有力な大名との関係などがわかりやすく感じました。 その後の戦国時代、織田信長が仏教勢力に手を焼きつつ徹底的に武力でけりを付けようとするのも尤もだと思う一方、筒井氏を守護に任命したあたりが、改革の放擲とも感じられる、破滅への転換点だったのかも。少々飛躍して思いを馳せました。 江戸時代の講談などを元に、俗説で語られる事の多い歴史ものとは一線を画し、最新の歴史学の成果を誠実に、しかもわかりやすく示した良書だと思いました。 主に用いる資料は二つ。 経覚による『経覚私要鈔』 尋尊による『大乗院寺社雑事記』 本書の特徴は「資料に書いてあるから」と、無責任に現代語訳する態度ではなく、 資料を記した二人の僧の性格にまで思いを巡らし、実際の出来事と記録の差異までを読み解いている点です。 「噂を鵜呑みにして、驚喜している。」 「×○と予測しているが、見事に的中した。」 というような感じ。 この効果がよく出ているのが、 古市胤栄についての記述だろうと思います。 従来の記述だと、文化人としての側面と、強権的に家中を統率する人物像が一致しません。 でも、この一冊を読むと「なるほどな。」と思いました。 同じく、足利義政についても「こんな人だったんだろうな。」と人となりが感じられるようでした。 実像をあまり描いていない重要人物が畠山義就です。 で、今wikipediaを読みました。なるほど、この人にはスポットライトを当てないのが無難だろうな、と思いました。
0投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ各メディアで紹介された話題のベストセラー。かつてない明快さと圧倒的な筆力! 室町後期、諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場として戦った応仁の乱(1467~77)。細川勝元、山名宗全という時の実力者の対立に、将軍後継問題や管領家畠山・斯波両氏の家督争いが絡んで起きたとされる。戦国乱世の序曲とも評されるが、高い知名度とは対照的に、実態は十分に知られていない。いかなる原因で勃発し、どう終結に至ったか。なぜあれほど長期化したのか・・・・・・。日本史上屈指の大乱を読み解く意欲作。 (当書裏帯裏紹介文より) 2020年大河ドラマ『麒麟が来る』の主人公が明智光秀。描かれる時代が室町時代末期から安土桃山時代で『応仁の乱』のその後になっていたことが実に良いタイミングでした。 ドラマで聞いたことのある人物名が出てきたり、応仁の乱から戦国時代にかけての期間が100年にも及ぶことをドラマで言われたり、本とドラマが良い感じでリンクしていて面白かったです。特に戦乱が100年にも及ぶ、ということが自分の中で改めて浮き彫りになったことで『江戸時代の平穏が200年に及んだのは世間が平穏を切望していたから』と実感できたことでしょうか。 私、日本史は○○時代って覚えています。 『平安時代⇒鎌倉時代⇒室町時代⇒戦国時代⇒安土桃山時代⇒江戸時代⇒明治・大正・昭和・・・』って感じで。 でも江戸時代から明治の間には幕末の動乱があり、京都・江戸・北陸・東北と続く内戦が存在するんですよね。そういう意味でいうと室町から江戸の間にも戦国時代が存在しているわけですよね。その戦国時代の引き金になったといわれる『応仁の乱』。 ということで、判りにくいことで有名な『応仁の乱』を判りやすく解説している。 という評判を聞いて読んでみました。 正直、まだしっくりと来ていないです。出てくる人物が多すぎて自分の中で上手く咀嚼できていない、といったところでしょうか。 あと2~3回、読んでみないと自分の中に入ってくれないかな、と思っています。 司馬遼太郎の幕末モノを、複数作品・何度も読んだことで、幕末史を覚えることができた経験があるので。 不満点は一つ。 人物のフリガナを振ったり振らなかったり、というところ。読み方、一回では覚えきれません。ずっとフリガナ振ってほしかったw
0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までほとんど関心のなかった時代だったので、新しい発見があって面白かった。この時代の権力者や武将の名前もほとんど知らないうえに、登場人物が多くて読むのに時間がかかった。
0投稿日: 2020.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱の全貌が結果的に乱の発生につながった紛争にまでさかのぼり、そこから丁寧に時系列に追って書かれている。応仁の乱の原因は単純な対立構造によるものではなく、対立の背景に加え偶発事象や意図の不一致などが重なったことが分かり、応仁の乱の全貌がある程度整理された。現実世界を単純化してとらえようとする風潮もあるが、この本はそうした風潮を否定し、複雑なままとらえる必要性を伝えるものであろう。
0投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱について、著者の意見が述べられている。 「はじめに」と「終章」に特に著者の意見が書かれており、他の部分は補足資料的な側面が強い。(まぁ、そもそも形式的にそういう本である。) なので、それら2つの章を読んで、気になった部分だけ他の章を読んだ。 応仁の乱の展開が整理されていて、資料として面白く読めた。また、足軽の誕生などの副次的なお話も興味深くて良かった。
2投稿日: 2020.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ呉座さんの名前を一躍有名にした本。登場人物が多すぎてこんがらがりますが、応仁の乱がそういう戦争何だから、これはしょうがないです。
0投稿日: 2020.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦国時代到来の契機とされる応仁・文明の乱について、興福寺塔頭大乗院の尋尊・経覚という二人の高僧の著述を通して語られる。個人的には応仁の乱に関する内容もさることながら、下克上により旧来の秩序が崩壊していくことに嘆息しつつ、武家達の勢力争いの中で、自らもワンプレイヤーとして寺院経営に腐心する中世寺院の記録として非常に興味深かった。
0投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ大量に出てくる人名に混乱しましたが、乱の詳細についてよくわかりました。 教科書等に出てくる乱発生直後の勢力図、 ・東軍…細川勝元、足利義視 ・西軍…山名宗全、足利義尚 はいつ改まるのでしょうね。
0投稿日: 2020.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2020/5/10 読了 結局、決め手を持つものが現れず、だらだらと終結まで11年もかかってしまった、というところだろう。大義名分に乏しいだらだらと続いた応仁の乱は、第1次世界大戦に類似していると呉座は説いている点に注目。どちらも欲望渦巻く時代だった、ということか。
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大和国(奈良)の2人の僧の視点を中心に応仁の乱を描いている。 そのため京都より大和での動きが中心になり応仁の乱の詳細を知らない人にはちょっと分かり辛く知っている人に新たな視点を与える作品。
0投稿日: 2020.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログヒット本との事で読み始める。 年号と大まかな内容しか暗記していなかった身としては、はじめの方は読みにくく、やめようかと思いながら、頑張って読み進める。 だんだんと、いろいろ抱えた人たちの、各々の事情がわかってきて面白くなり、読了。 もっと早く読んだら良かった。
0投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルほど、応仁の乱そのものではなかったが、 それでも奈良興福寺を中心として、 嘉吉の乱あたりから明応の変にかけてまで、 どのような時代変遷があったのか、とてもわかりやすくまとめられている。 恥ずかしながら、教科書レベルの知識しかなかったが、 そもそもなぜ室町幕府がかくも脆弱だったのか、 守護代が台頭したのはどのような理由なのかといったような、 初歩的な知識、そして疑問にも的確に答えてくれる。
0投稿日: 2020.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱。室町幕府の形骸化そして戦国時代がここから始まる・・・と歴史の授業では習う。京都の人は、先の戦さ、というと、太平洋戦争ではなく応仁の乱のことを指すらしい。。。 ということを、日本人の多くは知っている。じゃあ、実際にはどんなことがあったのだろうか?そもそも、東軍と西軍、どっちが勝ったのだろうか? 大和国を支配する興福寺や土豪たちの内部抗争から、大和守護畠山家内の家督争いに発展する。そして時の将軍義政、次期将軍候補で弟の義視、管領細川勝元、勝元の舅・山名宗全たちの派遣争いへ。権力者たちの思惑が各地の守護や守護代たちを巻き込み、越前、播磨での紛争にも発展する。その後は京での疱瘡流行をきっかけに、補給路を確保した東軍が有利に傾く。山名宗全・細川勝元の死を経て、最終的には1477年、東軍が勝利する。。。 乱の後も幕府内の争いは続く。将軍職は足利義政の子、義尚→若くして死後に義視の子、義材へと引き継がれる。そして1492年、日野富子らは明応の政変で、堀越公方足利政知の子を義澄をして将軍に擁立。こののち義材側と義澄側、2つの将軍系統の覇権争いとなり、戦国時代が本格的に幕開けをする・・・ というのが流れのようだ。きっかけと終わりがわかりにくく、人の流れが複雑なので、時系列ごとに図示しなければ理解が難しい。そして、応仁の乱にとどまらず、明応の政変まで記載することで、後の戦国時代への流れをつかむことができる。そして、応仁の乱のことをよく知らなかった理由もわかった。 惹きつけるものが少なく、地味なんだわ。始まりは奈良県内そして大阪府東部の小競り合い。当事者の思考は自分の領地や肩書を保持すること、魅力的かつ革新的な人物も不在。大将たちが死んでも終わることなくズルズルと続く。そして何が変わった?何も変わっていない。 ということを、丹念に読んでいけば理解ができる、良書であった。
1投稿日: 2020.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱は、はじまりは知っていたつもりでも、読んでみるとやっぱり複雑怪奇。それに、終戦の方がより分かりづらい。非常に複雑怪奇だ。もうお腹いっぱいです(苦笑)。 ただし本の内容自体は読みやすかった。とは言えボリュームある内容だったので、二度三度と読み返したほうがより理解できると思う。
0投稿日: 2020.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでになく分かりやすい応仁の乱の解説書 視点を興福寺に定めて視界を京付近に限定し 関東を始めとした諸国情勢はばっさりカット 登場人物たちも小説的キャラ立てをせず 時系列に沿い事実を書き連ねることに徹して 全体の流れがとても把握しやすい とても良くできている解説書ではあるが それでも通り一遍通しただけでは 全体を織り成している個々の事件が どのようにつながり合っているか把握するまでは難しい 例として 興福寺が視点舞台であるから ごく冒頭に衆徒と国民についての解説が出てくるが これを重要で問題にしやすくテストに出しやすいからと 繰り返し解説するような冗長なことはしない 全文全体で記されるそれぞれの事柄も 同等に全体をつくる部分であり 言ってみれば新書にあるまじき 歴史事実に贔屓をしない教科書的な構成になっている この姿勢を一貫しているからこそ 連なった過程が事実まとまりを欠くこの題材を ひとつの筋立てとして通して描けているのだが といってこの時代のふつう主役であろう 室町六代将軍すら大仰に飾り立てることが無いので まさに教科書のように自身の知識に欠ける点をメモし 理解の助けになるよう重要な事柄を整理して 二読三読を重ねなければならない内容でもある 一体歴史解説書とはどのように書かれるべきだろうか 読者の様々な知識と興味に沿う様々な正しさがあるが 応仁の乱という重要でありながら どんな面から見ても理解を拒む華々しくない題材が この解説書の形でその正しさの一面を教えてくれる
0投稿日: 2019.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説でもないのに語りが響きました。 ★ 私の受けた何十年か前の義務教育では 細川勝元と山名宗全が戦い、都が荒廃した。 その程度しか習った記憶がありません。 おまけに私の高校の日本史履修は1年間だけで 鎌倉幕府成立で終わったのです。 そんなわけで小学生並みの知識なのに 手に取ってしまいました。 何とか投げ出さずに 読み終えることができました。 (なんのこっちゃわかっていないところが多いと思います) 畠山氏、斯波氏の家督争いとか そんなことは初めて聞いたぞってレベルです。 私には覚えることが多すぎました。 応仁の乱ってこんなに面倒くさいのか っていうのがほの見えて さらに面倒くさくなりました。 でもこういうぐちゃぐちゃした時代や環境は 知識がつけばすごくおもしろいのは わかる気がします。 たとえば志向の違う畠山義就も 古市胤栄の人となりも私には印象的でした。 明応の政変に至るまでがわくわくしました。 日野富子が細川政元に 小川殿を返そうとするものの、 結局清晃(後の義澄)を住まわせようとした。 しかし義視は入居前に小川御所を破壊して 富子は父子を敵視したという経緯。 明応の政変に以降の混乱も それが戦国時代の素地になっているんだな つながっているなと感じると もはや感動的ですらありました。 私のものの見方が偏っていて 浅はかさを露呈するかもしれませんが 中央と領主の関係とか中世だなあと思いました。 当時の興福寺側からの史料を読むことで どのようにして世界が構成されていたのか 事実らしきものを集めて 根拠を持って、 検証を進めていく、 論争していく。 歴史っておもしろいですね。 と、最後まで小学生レベルの感想でした。
0投稿日: 2019.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめに 第一章 畿内の火薬庫、大和 1 興福寺と大和 / 2 動乱の大和 / 3 経覚の栄光と没落 第二章 応仁の乱への道 1 戦う経覚 / 2 畠山氏の分裂 / 3 諸大名の合従連衡 第三章 大乱勃発 1 クーデターの応酬 / 2 短期決戦戦略の破綻 / 3 戦法の変化 第四章 応仁の乱と興福寺 1 寺務経覚の献身 / 2 越前の状況 / 3 経覚と尋尊 / 4 乱中の遊芸 第五章 衆徒・国民の苦闘 1 中世都市奈良 / 2 大乱の転換点 / 3 古市胤栄の悲劇 第六章 大乱終結 1 厭戦気分の蔓延 / 2 うやむやの終戦 / 3 それからの大和 第七章 乱後の室町幕府 1 幕府政治の再建 / 2 細川政元と山城国一揆 / 3 孤立する将軍 / 4 室町幕府の落日 終章 応仁の乱が残したもの 主要参考文献 あとがき 関係略年表 人名索引
0投稿日: 2019.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログその乱の名前は歴史の授業で憶えさせられたのに、中身を説明できない筆頭。それが応仁の乱。中世までの乱は、人物相関が複雑で、人名の読みも難しく、なかなか頭に入ってこない。経覚と尋尊という2人の僧侶が、それぞれの感覚で日記=将来読まれるであろう記録を残してくれたことに感謝。10年以上続き、京都・奈良を破壊し尽くした内乱が、政治経済的に止めることができなかった為政者や当事者の事情が、少しだけ理解できた。
0投稿日: 2019.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとした室町ブームがきてるらしいので乗ってみた。 複雑だから理解しにくいというよりもストーリーらしきものが希薄なので理解しにくいという感じか。 でちょっと検索かけて知ったのだが、著者の周辺にイデオロギー闘争の感あってドン引きした。
0投稿日: 2019.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ売れていたので買ってみたが、やはり自分が関心のないテーマだったので、面白くなかった。本のせいではなく、自分の関心がなかっただけ。
0投稿日: 2019.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ英雄も目覚ましいリーダーも登場せず、状況を決定するほどの戦闘もなく、利害関係が複雑にからみ、それを調整することも出来ず、ひたすら分かりにくく長期化して、燻り続けて戦国へ……。という印象でした。 関係人物が多く、戦乱の長期化で代替わりもあり、同じ一族内で似た名前の人物が争っていたりするので、私の頭では付いていけずに一度挫折しました。 慣れるまではメモをとりながら読んで、リベンジ達成です。
1投稿日: 2019.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人名がたくさん出てきて、途中で分からなくなることがあった。結局、畠山氏内部の争いに山名氏と細川氏がなんとなく介入。完全終結する前に将軍の後継争いが…そこでダラダラ続く事に、という感じでしょうか。室町将軍による、大名同士を対立させて拮抗させよう、という政策もトラブルの原因のような。でも、一番思ったのが、信賞必罰の不徹底さだと思いました。何回許しているのかと。
0投稿日: 2019.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書ではサラッと流れる応仁の乱。実はこの前後で人々の考え方や行動が大きく変わった出来事だった、として、この戦いを掘り下げた書。戦いの構造の複雑さ、、英雄の不在、決定権のなさ等から、ズルズルと10年以上も洛中が戦禍に苛まれた。この間、徐々に、下克上や地方の自立の機運が上がってきているのが本書に描かれる。 興味深かったのは、奈良が畿内の火薬庫だったこと。複数の軍事勢力を微妙なバランスで興福寺が御していたようだ。まるでチェコスロバキア。。。
0投稿日: 2019.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ5、6年前だったか?ふと、「応仁の乱って、結局どういうものだったんだろう?」と思ったことがあって。 例によって、アマゾンで「応仁の乱」で検索してみたんです。でも、特にない。岩波新書やちょっと高そうな学術書っぽい本くらいで。 あとは、『花の乱』がまさにその時代とわかったんで。とりあえず、1巻だけレンタルして見たんですけど、両脇が切れた画面だと、な~んか見る気がしないと(笑) そんなわけで、それっきりになっちゃった「応仁の乱」ですけど、思うに、実はそういう人って結構いたんじゃないでしょうか? そんな風に、長年にわたって「応仁の乱」にモヤモヤしたものを抱えていた人たちの前にいきなりパッと現れた光明。 この本がヒットした理由って、ソコなんじゃないかと(笑) というのも、ネットや読んだ人の評価がまちまちだったんですよね。 「面白かった」、「よくわかった」という人もいる反面、「あの本は応仁の乱じゃなくて、応仁の乱の時代の大和の話」とか、「むしろわかんない」という人まで。 それどころか、「買って読み始めて、かれこれ半年…」なんて、妙に詠嘆口調の人もいたり(笑) かく言う私自身、本屋でペラペラめくってみて。 興福寺がどーちゃらこーちゃらと始まる内容に、「興福寺って、藤原氏の氏寺だろ。どーでもいいよ、そんなもん。平重衡エラい!」などと暴言――思っただけなので正しくは暴言ではないんだけどw――を吐いて、面白そうなミステリー小説を買っちゃったと(笑) なのに今更読んでみたのは、たんにアマゾンで古本が安かったからなんですけど、読み始めてすぐ思いました。「呉座勇一さん、お見それしました。興福寺さん、ゴメンなさい」と。 いやはや、これは面白かったです。もうほとんどオタク!それもコテコテの。 しかも、ちょっと陰にこもったオタクさ(笑) 確かに、外側から書くしかないんでしょうね。「応仁の乱」って。 だって、主人公になる人がいないんだもん。 一番活躍(活発に暴れまわった?)した畠山義就を視点に見たところで、それは「応仁の乱」の元(&厄介者w)であって、「応仁の乱」の全体じゃないわけですもんね。 「応仁の乱」といえば教科書的には山名宗前と細川勝元ですけど、彼らは主役というよりは、火に油を注ぐだけの脇役に近い。そもそも乱の終息を見ずに死んじゃう。 かといって、将軍義政や日野富子の視点で見るというのも微妙に違う。 乱の元である家督争いが将軍家にまで及ぶことで、義政・富子も渦中の人になっていくわけですけど、そこは殿上人。イマイチ切迫感がない(ま、殿上人なりには切迫してたんでしょうけどねw)。 つまり、第三者という外側からの視点で輪郭を描いていくしかないわけで、それを興福寺の経覚と尋尊による日記にした(一番適当だった)ということなんでしょう。 さらには、この「応仁の乱」。いわゆる教科書的な「応仁の乱」の西軍と東軍の戦いをメインに書いちゃうと、結局「応仁の乱って何だったの?」になっちゃうという、なんとも厄介な出来事で。 その前と後も延々書いとかないと、「応仁の乱」が見えてこないという、ほとんど四次元世界(笑) そんな四次元的大乱をよくここまで咀嚼してくれたなーと、著者には感謝感謝なんですが、とはいうものの「じゃぁ応仁の乱ってどういうことだったの?」となると、「あれっ!?」みたいな(爆) 確かに流れは理解したんです。ほぼ(笑) とはいえ、この「応仁の乱」の特徴である、個々の出来事と出来事の絡み合いを完全に把握できてないんでしょうね(完全というのも変ですけどw)。 ただ、それはもう一度読み返すとか、他の「応仁の乱」本を読むとかしないと…ということなんでしょう。 とはいえ、それはとっても楽しみだったり(笑) この『応仁の乱』とその前に読んだ『戦国誕生』で長年抱えてきたモヤモヤがやっと解消された「応仁の乱」ですけど、「応仁の乱」そのものよりも興味を引いたのは「武士」というモノです。 気づいたのは、「武士」というモノを、(たぶん)江戸時代の侍のイメージで見ていたんだなーと。 さらには、この時代の武士は、その武士の政権である「幕府」を今的な政治をする存在としていたのではなく、諍いの調停をしてくれる存在としていた傾向が強いということ。 それは、鎌倉幕府(あるいはその前の武士の棟梁)に求められていたことからほとんど変わっていないということで、つまり、同じ幕府でも江戸幕府とは全然違うということなんでしょう。 この『応仁の乱』では「終章 応仁の乱が残したもの」で書かれていますが、守護が在京し、守護代が領国を治める室町時代前半の形態が「応仁の乱」によって変わり(というよりそれが応仁の乱の原因でもあった)、守護(や守護代)が直接治めるようになって。さらに、領民や家来に離反されないよう、領国経営をするようになっていく。 つまり、わかりやすい例では信玄堤ですよね。年貢増のために、収穫を増やすために、領民のために領国に注力せざるを得なくなっていく。 一方、中央(幕府と朝廷)は伝統と慣習によって保たれている権威で権力を取り戻そうとするものの、その権威も地方の有力者たちに利用されるだけのものになっていく。 かくして、時代は(地域の)群雄割拠の戦国の世に突入していくということなんでしょう。 また、「応仁の乱」がここまで要因と要因が複雑に絡み合っているのは、武士が不届きな事をしたとしても追放されてお終い。命までは取られないという、この時代の慣習?(将軍と足利一門、その他武士のなあなあで成立している幕府ゆえ?)のも大きかったように思いました。 幕府から追放されたり、領国に逃げちゃっても、ほとぼりが冷めたらまた戻ってきて(あるいは、将軍や管領の都合で呼び戻されて)。でもって、ある者は過去の恨みで騒ぎを起こし、ある者は敵対していた者についたりと。 とはいえ、トップの義政からして、東軍だったかと思うと西軍寄りになったりなんて状況ですからね。「応仁の乱」を速やかに終わらせるのは、CⅠAを従えたアメリカ大統領だって難しいんじゃないですかね(というか、アメリカ大統領はもっと無理?w) また、応仁の乱というと、将軍義政のダメダメっぷりが随所で出てくるわけですが、それでも腐っても将軍なんですね。この時代は。不思議なくらい権威と威光がある。 信長の時代、どう考えたって木偶の坊にすぎない足利義昭が妙なくらいしつこく活躍出来たのはこういうことだったんだなーと、納得できました。 いやー、この呉座勇一氏のオタクっぷりは本当に面白い。 個人的にはそのオタクっぷりで、あの鎌倉時代の血みどろの粛清の歴史を解説した本を書いて欲しいなぁ~。
0投稿日: 2019.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ大和国”守護”の興福寺、そのトップ(摂関家出身)の日記を軸にややこしい応仁の乱の推移をたどっていく。中世奈良の権力の有り様、河内国での戦乱の様子もわかる。戦後に起こった階級闘争史観から脱却している。
0投稿日: 2019.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論、しごく真っ当で硬派な歴史本。やたら複雑な登場人物たちについて、間違い覚悟でえいやで書くとこんな感じ。 ① 各種のもめごとの積み重なり - 天皇家。南朝と北朝を足利義満に統一させられたが、「たすきがけ人事」の約束を反故にされ北朝系の天皇が続いたことから南朝は激怒、後南朝が生まれてぶち壊し。 - 将軍家。ゴッドファーザー足利義満の死後は権力弱体化。「決められる政治」を期待され将軍となった義教は、いざ強権を発揮すると「一強を許すな」とばかりに謀殺されてしまう。8代義政は後世いわれているようなバカ殿様ではなかったが、自分の後継者問題でしくじり派閥形成を許してしまう。 - 興福寺。摂関家の貴重な天下り先。が、内輪もめで一乗院系と九乗院系とに分裂して対立。荘園経営を地方の武装集団に委ね権力争い。 - 大名。将軍の側近として権力を揮いたい細川家と山名家、地方でえばりたい畠山家。が、畠山家で内輪もめ。ライバル畠山の弱体化を狙いたい細川が一方に肩入れ、反対側に泣きつかれた山名も後ろ盾を買って出る。結局山名対細川の壮大な派閥抗争に。 - 農村。地方武士は、荘園経営の代理人と言いつつ、年中土地をめぐる小競り合い。農民は農民で、あるときは興福寺系武装集団と組み、あるときは地方豪族と組み、またあるときは一揆として独立し、縄張り争いに参加。 - こうして、各地の小規模紛争解決にてこずっている間に大名同士が将軍候補を掲げて全面戦争突入。 ② 下剋上、の意味 - 身分制度を打破して実力でのし上がる男のロマン、という面もあるだろうが、どちらかというと「主従関係も度外視、常に有利な側に寝返りまくる理念なき合従連衡」というのが実態に近そう。 - よって紛争解決に必死なのはむしろ義政ら権力者側。ただし、彼らも自分が不利な状態で終わるのは絶対嫌なので乱が止まらないのもまた事実。 それぞれがそれぞれの思惑で利害を主張しているからいつまでも終わらない、どころか戦火は広がる。平和なときは、それを維持する強大な軍事力がいる(ことが多い)。なににせよ、「平和のために一歩も引かない」と言っている限り平和はこないな、大事なのは「落としどころ」を探るセンスだな、というのが読後感。
0投稿日: 2019.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前は知ってるけど、説明できない。どうして起こったのか、誰が戦い、誰が勝ったのか、よくわからない。そんな不思議な日本史事実の一つが応仁の乱。ネームバリューだけは高い室町時代の戦乱をじっくりと解説したのが本書。 応仁の乱は約11年続いたが、当事者の誰もがそんな長期戦を求めていなかった。長期戦になった理由は戦いの目的がコロコロと変わってしまったから。足利将軍家の跡継ぎ争いもあれば、有力大名の細川氏と山名氏の覇権争いに地元国人同士の争いもあった。それらが複雑に絡み合い、終わりたくても終われない戦いがダラダラと続くことになった。それが応仁の乱をわかりにくくしている。 本書の参考資料の中心が奈良県の興福寺僧侶の経覚と尋尊の日記。京都で起こった応仁の乱を京都からやや離れた場所で様々な情報を集約し、客観視した情報だから信頼がおける。が、坊さんの意見ゆえに冒険譚的な面白みはない。 そんな複雑な戦乱をまとめているのだが、読んでみても知名度のない人物ばかりが登場し、決してわかりやすくはない。そんな本がベストセラーになったのは不思議だ。それなりの歴史マニアでなければ読み通せず、おそらく多くの読書は読破を放棄しているはず。
0投稿日: 2018.12.10勉強になりました
ようやく電子化されたので読んでみることにしました。まさに群雄割拠の混乱の時代を当時興福寺の僧侶だった経覚と尋尊の目と耳を通じて語られるます。 登場人物が多くて辟易しますが、互いの遺恨や利益を巡って繰り返される小競り合いがやがては東西に分かれて戦う大戦へとつながる経緯が丁寧に描かれています。 面白かったし、何よりも勉強になりました。
0投稿日: 2018.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都で「先(せん)の戦(いくさ)」といえば〈応仁の乱〉のことを指すのだ、と言われるくらい京都に大ダメージを与えたといわれる中世の大乱。戦国時代の先触れとも位置付けられるこの戦、細川勝元VS山名宗全の対立が原因と簡単に片づけられることが多いようだが、果たしてそうなのか?10年余りにもわたって京の町を焼き尽くし、室町幕府を終焉に導いたとされるが、そんな単純に片づけていいものだろうか。 誰でも知っているけれど、本当のところはややこしすぎてよくわからない。そんな「応仁の乱」の全貌を、奈良・興福寺の二人の別当の視点から解き明かした渾身の意欲作、と言えるのではないだろうか。とにかく登場人物が多すぎるうえ、名前がこんがらがりがちになるが、著者はできるだけ懇切丁寧に、わかりやすく順序立てて論じてくれている。 視聴率的には惨敗した大河ドラマ『花の乱』が大好きな私にとっては待望の一冊としか言いようがない。〈応仁の乱〉について、さらなる研究が進むことを望みたい。
0投稿日: 2018.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ・細川勝元が山名宗全と提携したのは、畠山氏を押さえ込むためだったが、畠山氏が内紛で弱体化すると、山名氏との同盟の重要度は低下した。山名氏の分国と境を接し、その圧迫を受ける備中守護家など細川氏庶流家は山名氏との提携にもともと否定的であった。山名宗全の側も、赤松氏再興に手を貸した勝元に不信感を持った。結果的に、新興勢力山名氏が覇権勢力細川氏に挑戦するという形で応仁の乱は生起したのである ・応仁の乱はなぜ起こったのか。直接的な要因は畠山義就の上洛であろう。それは、応仁の乱が勃発した後、足利義政が畠山義就を帰国させることで事態の収拾を図った事実からも裏付けられる。ただし、義就を上洛させた山名宗全も当初の狙いは無血クーデターであり、細川方との全面戦争を企図していたわけではなかった ・大内政弘や斎藤妙椿らの奮戦により局地的には勝利することもあった西軍だが、東軍に補給路を遮断されたため、最終的には戦争継続を断念した。将軍足利義政を戴く東軍が反乱軍たる西軍を屈服させる形で終戦となったわけだが、乱の前後で幕府の権力構造は大きく変化した。特筆されるのは、乱後ほとんどの大名が京都を離れ、在国するようになったことである。これは、大名による分国支配を保証するものが幕府による守護職補任ではなく、大名の実力そのものになったからである
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ畠山家の家督争いに山名宗全が乗じ、足利義視が、一旦将軍職を譲ると約束したのを反故にした義正を敵視し・・・というようなきちんとした読み方にはとても付いていけなかったので、大体こんな雰囲気ね、で満足。当時の世情がよく分かる。人名や地名が難しく読めなくても、諦めずに通読する価値はある。三度くらい繰り返し読めば頭に入るのだろうが、二度目の読み返しで挫折した。 応仁の乱は、なぜ起こり、なぜ11年もだらだらと続いたのか:情熱の本箱(180) http://hon-bako.com/bookbox/bookbox_passion/%E6%83%85%E7%86%B1%E6%9C%AC%E7%AE%B1180/[/private]
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱の登場人物、時代背景、戦乱が起こるまでの経緯などを丁寧に解説する学術書。昔教科書で習ったような足利義政・義尚と義視の家督を巡る争いに、東西両軍が肩入れして乱が拡大したような単純な図式ではなく、3つの政治勢力のせめぎあいが根本にあることが分かった。 著者はあとがきで第一次世界大戦を例に挙げているが、当事者の利害関係が複雑に絡む場合、戦闘の目的は曖昧になり長期化するのは避けられないのではないか。
1投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
名前だけは知ってても、で、何がどうなったのか全くわからないまま放置してた応仁の乱。新書一冊なのでこれでわかりやす… ダメだ。ややこしいというのはよくわかったが、きちんとノートをとりながら読み直します。(特に、冒頭で興福寺云々から始まって面食らった。勿論、その先を読み続けてなぜ興福寺から始めなければならないのかわかりましたが)
0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ興福寺別当(で合ってたか…?)2人の日記を中心に、従来の定説とは異なる解釈を試みたもの。「応仁の乱」という言葉は耳にしていたものの、たしかにいつからいつまでかはよく知らない…と思っていたので、これを読んで、いつからいつまでかはよくわからないらしい、ということがわかってすっきり?した。 ちょうどこれを読み終わってから司馬遼太郎の「国盗り物語」を読んで、戦国時代への移り変わりの雰囲気がなんとなくわかったような気がする。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログアメトーークの読書好き芸人の回でカズレーザーが推してたので借りてきた。 とにかく聞き慣れない地名と人名に圧倒されて内容はほとんど頭に入ってこなかった。 ただかなり詳細に且つリアルに描かれており、歴史好きや応仁の乱にある程度知識がある人ならかなり楽しめたんじゃなかろうか。 著者の呉座氏は70代か80代のおじいちゃんを想像していたのだがまだ30代ということでかなりびっくり。
0投稿日: 2018.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎知識がなさすぎてなに一つついてけなかった。初心者にとっては易しくないかな。 なんとなく読んでなんとなく理解。 基礎が分かってれば人間模様がよく書かれてて面白くなるんだろうが
0投稿日: 2018.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱当時の興福寺の権力の大きさはわかったが、当方の理解力が足りないのか、結局何が言いたいのかよくわからなかった。興福寺の僧からみた、応仁の乱という対岸の火事についてということなのか。文章が硬いのも辛い。
0投稿日: 2018.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログよくわからない史実を丁寧にまとめてある。 確かに応仁の乱で日本は不安定になっていったのかもしれない。 最近、奈良に興味があって興福寺のすごさを改めて感じました
0投稿日: 2018.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史書としては異例のヒット!とテレビで紹介されていた事と再放送を含め毎週観ている「英雄たちの選択」でも取り上げられていたので読んでみました。 学生時代、「応仁の乱」という名前だけは教科書に載っていたことは覚えていますが内容までは覚えていませんでした。 読み進めても登場人物が多く、原因や期間が長すぎるし複雑すぎるしでよくわからなくなりました(笑) 私は歴史好きの域を出ないからわからなかったのかもしれないけれどこれではテレビ番組の題材として弱いし、教科書でも載せづらいだろうな、と思いました。 全体的な流れをぼんやりとしか理解できませんでしたが皆、勝敗ではなく「後に引けない」というところが無駄に戦死者を出し出口戦略を誤ってしまったんですね。 理由や大義名分が弱い戦いは破滅しか起きない。
0投稿日: 2018.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
難解な応仁の乱を奈良興福寺の記録から読み解いていく。出てくる人物が、貴賤問わずおしなべて目先の益ばかり追い求める小物ばかりで、その小物の判断と行動が積み重なって大乱になったということがよくわかった。Googleマップを見ながら読み解くと、地理関係がわかって更に面白さが倍増する。
0投稿日: 2018.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、アメトークでカズレーザーが紹介していた際に強い関心を持った。 はずだったのですが・・・。 読み始めて人物がほとんどわからず戦国ほど人の魅力を感じず。 やっぱり戦国と三国志以外は読まんとこ。
0投稿日: 2018.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ合戦にかんする物語を読むとワクワクするという人は多い。だからこそ中世の軍記物語の時代から今日に至るまで、歴史モノ・時代モノは文学の一大ジャンルとして栄えているのである。しかしその中心は戦国時代や幕末などで、NHK大河ドラマの舞台もこの2つの時代に集中している。ではひるがえって、その戦国時代のキッカケとなったともいわれ、教科書でもかならず教わる、「応仁の乱」(あるいは「応仁・文明の乱」)を描いた本作はどうか。じつは、コレがちっともワクワクしないのである。小説ではなく新書だから? いえいえ、肝腎の戦乱の中身があまりにもしまりがないからである。なにせ、本作の販促で新聞に掲載された広告には、「スター不在」「ズルズル11年」「勝者なし」という形容が踊っている。じっさいに本作を読んでみるとまさしくそのとおりで、そもそもなぜこんなことになってしまったのか、読んでみてもよくわからない。ちょうど同時多発的にお家騒動が勃発し、また体面を保つために無意味に加勢した陣営も多く、さらに度重なる和平工作の失敗……、ととりあえず理由は示されているのだが、それでも着地点が見えないような争いばかりで、歴史小説とは真逆の、読んでいてイライラさえ募る展開である。日本史上きわめて重要なトピックでありながら、教科書ではココまで詳しく教わらないため、そうだったのかと思うことも多かったが、逆にこの内容を知っていたら、たしかに教科書にはいちいち細かく載せていられないであろう。
0投稿日: 2018.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ちょっと前に「これを読むと、応仁の乱がよくわかる!」ということで、結構ブームになった本。 しかし結論を申しますと、やっぱよくわかりません、応仁の乱。 歴史はストーリーとして覚えると理解しやすいなんてよく言いますが、それでもわかりません、応仁の乱。 なぜかというと、登場人物が多い割にはヒーローがいないし、伏線は回収されないし、構成の妙はないし、要はぐだぐだなんですの。 ただわかったことは、室町時代って、はじまりも終わりも合従連衡なのだということ。 後醍醐天皇とたもとを別った足利尊氏が作ったのが室町幕府。 しかし後醍醐天皇だって、黙って引き下がったわけではない。 南朝と北朝という二つの皇統が互いの正当性を主張していたのが室町幕府なのである。 そして、幕府自体も尊氏と直義が兄弟で争っていた。 さらに、守護を置かない大和の国を実質支配していた興福寺も一乗院、大乗院に分かれ、摂関家も二手に分かれ、それぞれに門跡(院主)を置く。 八代将軍義政のあとを巡って今度は将軍家が二手に分かれて争い、諸侯も父と子、兄と弟、叔父と甥などに分かれて、とにかく争う争う争う。 天皇も将軍も最早絶対的な権力など持ち合わせないから、和平交渉はことごとく失敗し、関係者が膨大過ぎて、もはや落としどころが見つからないから、個別の手打ちと相成るのである。 なぜ始まったのか、いつ終わったのか、よくわからないまま10年以上もだらだら続いて、京都はすっかり焼野原。 だから、領地の経営を手のものに任せて、自分たちは京都で貴族のように遊んでいた守護たちが、京都にはいられなくなって領地に戻り、そして力を蓄えて戦国大名へとなっていったのだね。 明治維新の種が関が原に蒔かれていたように、応仁の乱の種は室町幕府成立の時に蒔かれていた。 絶対的権力者がいるうちはいい。 けれど、権力者の力が弱まった時、みんな自分の都合で、面子で、欲得で動く。 大局的な視点なんてない。 引きどころがわからないままずるずると続く戦い。 山場もないまま終わってしまった。
0投稿日: 2018.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題となっている本というのもあり、読んでみた。「応仁の乱」は教科書で習い、語呂合わせもあり、有名である。足利家、赤松氏、畠山氏との関係などによって、乱が更に勃発し、山名宗全との関係なども乱や戦国時代の混乱期に更に影響し、大和の勢力争いなど、戦国時代を象徴するこの乱の本質を垣間見えた感じである。箸尾氏の力関係もこの乱に影響を及ぼしていたことも感じられ、大和、京の都の発展に繋がるものがあると感心。この応仁の乱から戦国時代の終焉、安土桃山時代、江戸時代となり、現代の生活の礎ができるという歴史の転換点を感じる。
0投稿日: 2018.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
秀作。 よく調査されている。貴重な本ではないか。 登場人物が多く、状況が変化していくので、理解し難い。 人間の性、我がままぶりがよく分かる。時の権力者の気持ち次第で世の中が変わってしまう。現代もそこはかわらないのではないだろうか。
0投稿日: 2018.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ知らなかった歴史の話。戦国、幕末は何とはなしに聞き及ぶけれど、それ以前は表面をなぞるようにしか知らない。前に読んだ平将門も含めて、今度は鎌倉時代も読んでみたい。そう思わせてくれる本。
0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ長くつづいた応仁の乱を膨大な資料と丁寧な説明で、中世の時代の仕組みの一端と、戦乱には多面的な要因があったと改めて認識させてくれる。 そのかわり、読破には大分じかんがかかったけど、寺と国人の関係性やそれぞれの立場はすごく興味深かった。
0投稿日: 2018.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ丁寧な解説。ワクワクとまでは行かないが、納得の説明。応仁の乱は、東軍細川vs西軍山名というより、多数の参加者が各々の利害で行う争いの集合体だったのね。 それにしても、ややこしすぎて名前が覚えられん。 親書で、このテーマで30万部ってどういうこと?というのが購入動機だったけど、何故そんなに売れたのかは、やっぱり不明。興福寺視点というのが、逆に応仁の乱の全体像を分かりやすくしているというのは有る。 京都のあの狭い中で、両軍武士団が堀を巡らした構(=城)を作りあっていたというのが驚き。二条城のような感じだと思うが、幾ら何でも、構同士近すぎじゃないの? 毬杖(ぎっちょう)という遊びがあったというのが面白い。ポロまたはホッケーですね。モンゴル辺りで生まれて、東西に分かれて伝搬、進化したということなのね。 小ネタでいろいろ発見あり。
0投稿日: 2018.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ興福寺の僧が見た応仁の乱。 乱以前から幕府は揺らいでいたこと。時の将軍の義政の優柔不断さ。乱後は大名が京を離れ、自国の統治に注力したことなどが、わかりやすく描かれている。 応仁の乱に英雄はいないとのことだが、どうしてどうして、細川勝元、山名宋全、義政、日野富子と登場人物は個性豊か。ただ、他の戦の時代に比べ、○○の合戦といったものが少なく、グダグダ続いたのが、物語としての盛り上がりには欠けるのかもしれない。が、その後の影響を見ると正に歴史の転換点だったようだ。 時々出て来る筆者独特の比喩に?中国国連加盟とか(^^;
0投稿日: 2018.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017年は応仁の乱開戦550年の年だった。それに合わせて話題になった本である。それほど歴史に詳しくない私は、応仁の乱については長い間戦っていたくらいの認識しかなく、誰と誰がどのような大義で戦い、勝者は誰というのも知らない。本書でさっくりと応仁の乱の概要を知りたいと思い、読み始めた。新書だから2時間くらいで読み終わるつもりでいたが、それは無理だった。内容が濃密なのである。容赦ない歴史上の出来事の解説や登場人物の多さ、事前知識がない私にとっては文字の洪水に襲われた感覚である。事実に混じって著者の解釈が入り、当時の情景が目に浮かぶようで、そんなところが話題になった要因かもしれない。楽しく読めるわけではないが、知的好奇心は刺激される。
0投稿日: 2018.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ奈良目線で応仁の乱を読み解いていた点が面白かった。 大和・河内・山城辺りの地理が頭に入っていないと、たぶんちんぷんかんぷんなので、もう少し地図等が挿し込まれているとよかったと思う。 かなり学術的な読み解きが中心なので、なぜここまでのベストセラーになったのかは謎。
0投稿日: 2018.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱の新しい解釈と言われても、現在の通説自体をよく解っていないので、正直、どこが新しい解釈かはつきりと理解は出来ていないと思う。登場人物を把握するには、自分で図でも作らないと無理。
1投稿日: 2018.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ篤実な研究者による、応仁の乱論。 足利将軍家だけでなく、畠山、細川、山名などの諸大名のお家の事情、興福寺の権力との関係などさまざまな側面から、多面的に語られる。 浮かび上がってくるのは、この大乱の錯綜ぶり。 単純な図式化不能。 複雑なものを複雑だと示すこういう本が売れるとは。 と、わかった風に書いてみちゃいるが、実際読み通すのはかなり根気がいる。 二週間もかかってしまった。 へえ、というより、初めて知ることばかりで。 どこかに人物紹介ページ、作ってくれ! 年表作ってくれ! と思うことしばしば。 本当に、この本が売れるってすごい。 とはいえ、思わず身を乗り出してしまうような、面白いところもあった。 一つは、戦い方の変化、特に都市への流民を組織することで成立した足軽が、戦いを変えていったという指摘は面白い。 足軽を動員して補給系統を乱したり、略奪・放火で軍や土地を疲弊させ、町を荒廃させたという。 それから、興福寺が、寺にとって不都合な衆徒・国民(いずれも武士)の名字を籠めるという呪詛を行っていたことも。 これは寺内の合議で決定されることで、相手の武士への制裁措置となるらしい。
0投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史書としては異例のヒットとなった『応仁の乱』。新進気鋭の中世史学者である著者が、『経覚私要鈔』『大乗院寺社雑事記』という2人の興福寺僧(前者が経覚、後者が尋尊)の日記をベースに、「試行錯誤を重ねがら懸命に生きた人々の姿をありのままに描き、同時代人の視点で応仁の乱を読み解」いている。 「階級闘争史観」のような先入観なしに、応仁の乱を一次史料を駆使してありのままに描くという点で、本書は優れた歴史書であると思ったが、正直、なぜここまで売れたのかというのはよくわからなかった。売り方が良かったという面と売れたから(より)売れたという面はあったのだろう。 正直、登場人物が多すぎて、内容を把握するのがたいへんだった。応仁の乱が、様々な人を巻き込んでだらだらと続いた大乱であったことはよくわかった。第1次世界大戦と似た構図を持っているという著者の見立ては理解できる。 当事者たちはそれなりに「出口戦略」を考えており、終戦に向けて様々な努力や工夫をしていたが、各々の当事者が「損切」に踏み切れず、コミュニケーション不足やタイミングのずれによって、終戦工作は失敗を重ね、戦争は無意味に続いたという著者の指摘は、確かに現代にとっても大きな教訓となると感じた。 登場人物の全体像を掴み切ることはできなかったが、本書の「主人公」としての経覚と尋尊の2人については、記述が厚かったこともあり、両者の個性をだいぶ掴むことができた。対照的な性格の2人だが、特にしたたかな尋尊に興味を覚えた。
1投稿日: 2018.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史において、”戦国時代の入口”となった重要な出来事とされる、応仁の乱。 京都で長い期間、戦闘が行われたという認識はあるのですが、なぜ起こってどのような結果になったのかは知らない、というのが正直なところでした。 その応仁の乱について書かれた新書が話題になっていると知って、遅ればせながら読んでみることにしました。 著者は日本中世史を専門とする学者さん。 応仁の乱はどのような背景で起こったのか、11年という長い乱の期間どのような経緯をたどったのか、そして乱はその後の日本にどのような影響を与えたのか、という構成で進んでいきます。 著者が主に参考にしたのが、奈良興福寺の二人の僧侶が書いた日記。 意外に感じましたが、この時代の奈良はどのような統治のされかただったのか、京都と奈良の地理的、政治的関係というのはどのようなものだったのかが冒頭に書かれているので、新たな視点を得ることができました。 その上で応仁の乱の経緯が記述されているのですが、正直なところ、登場人物が多くて全体像を理解するのは難しいなあと、感じました。 戦乱というと、家と家の争い、というイメージを持っていましたが、応仁の乱についてはそこに、それぞれの家の相続争いが、重要な要素として含まれていたのですね。 山名宗全と細川勝元という二大勢力の争いとされますが、それぞれの”連合軍”には、個別の事情を抱えた人物が複数集まっていて、それがこの乱に複雑さ、解決困難性を与えたのだと、理解しました。 京都を荒廃させた上で誰も勝者がいなかったという、応仁の乱。 これまで関係書籍を読んでこなかったので、理解を一歩、進めることができました。 関連する小説などを探して、さらに理解を深めていきたいと思います。
0投稿日: 2018.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書の歴史評論がミリオンセラーになるほど面白いのか? 歴史は好きで歴史評論も幾多読んで来たが、応仁の乱はほとんど意に介さなかった私は内容の前にこの社会現象的な売れ行きに惹かれて読み始めた 果たして、この本は面白い! と言うか、応仁の乱とはなんと面白いのだろうか! 応仁の乱の時も現代も人の欲と駆引きと、そして人生に対する達観と諦めは変わらないと思い至った 応仁の乱は将軍家のお家騒動くらいの予備知識で読み始めた本書には、煮詰まった時代は時風雲児やヒーローが改革するのではなく、多くの人の積もり積もった個々の念が泥沼と化して混沌を生み、やがて新たな芽を吹くのだと改めて思わせるものがあった それは小説のように感情を移入しないからこその面白さだった
0投稿日: 2018.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔から”応仁の乱は10年以上続いたのに、英雄や象徴的なエピソードを聞かないのはなぜだろう?”と疑問でした。乱暴に言うと、特定地域の人たちが天下布武などの特定の目的を持たずに無目的に小競り合いを続け、辞めるきっかけがなかったから、ということのようでした。現代社会でもこうゆうのあるよね。 続きはこちら https://flying-bookjunkie.blogspot.jp/2018/02/3_20.html
0投稿日: 2018.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰もが知っているが意外と中身を知らない「応仁の乱」について、興福寺の僧が残した日記を手掛かりに時系列を追い、定説とは異なる角度から再検討を行う。既に知られている史料であっても、扱い方を考えればこれだけ説得力のある話ができる、という好例と言えるのでは。
0投稿日: 2018.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログブームに遅ればせながら読みました。 歴史に関する本を読むと、いつも思う。事実の詳細を追って、調べて、まとめ上げて書くのは、それはそれでとても大変な作業だとは思うけど、それだけでは、…だから?ってなって、何も得るものはない…。素人の私に言われたかないだろうけど、もうちょっと作者独自の意見とか、独自の読み解きとかないと、素人の読者には伝わってこない。本書も応仁の乱の詳細を書いてあり、応仁の乱の前後の流れも書いてあるが、素人の私はこの流れをどう捉えれば良い?高校で習った室町後期から戦国時代へ移る時代を、どのように書き直せば良い?結局、そこは答えが出ないから、出せないから、やりきれない思いがある。 なお、本書を読んで気になったのは、足利義政と日野富子の夫婦である。もっと詳しく知りたい。読んでいて、キーマンは、この2人なんじゃないか、と思ってしまう。
0投稿日: 2018.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争の長期化を誰もが望んでいない中で、ズルズルと終結の機会を逸し、退っ引きならない状況に嵌っていく構図。
0投稿日: 2018.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の前書きでは東洋史家の内藤湖南の、現在の日本と関係があるのは「応仁の乱」以後で、それ以前の歴史は外国の歴史と同じ、という発言を引用し、応仁の乱の重要性を訴えている。 一方で、応仁の乱の難解性も指摘しており、本書では興福寺の経覚と尋尊が残した史料を中心に、応仁の乱を解説している。 たしかに、自分も応仁の乱と言われても、「人よむなしく応仁の乱」と覚えた程度で、歴史小説でお目にかかったこともなく、これまで興味を示したこともなかった。 今回本書によって、応仁の乱の前後の時勢も含めて詳細に認識することができたことは大きな知識となった。 特に応仁の乱の以後は大名が京都から去って自国に戻ってしまい、幕府の求心力がさらに低下し、それがその後の戦国時代につながっていったということは時代の転換点として非常に興味深い見解であった。
0投稿日: 2018.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終わった・・・ 人が・・・人が多すぎる・・・ 隠居したと思ったら復活する坊さんとか・・・ でも、日野富子が引き起こした なんだか長い戦争ではなかったということはわかった。 応仁の乱が一つの転換期になったというのには納得。 でもでも、これを自分で誰かに説明するのは無理だ。 呉座さん、半端ないっす。
0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題だから買ってみたが、そもそも応仁の乱に興味がないからか、読み切れなかった。テーマがある歴史の本を読む人でも、この時代の日本史が好きでないと、興味が湧かないと思う。
0投稿日: 2018.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になっているということで手に取った本。 呉座さんの本は2冊め。 奈良・興福寺の二人の僧侶の日記を中心的な資料としつつ、応仁の乱の流れを奈良(大和国)の情勢とあわせて追っていく。 日本史、高校で1年だけやってたけど、ご多分に漏れず応仁の乱って結局なんなのかよくわかってなかったので、この本でやっとわかった気はする。
0投稿日: 2018.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017年流行った本だし、日本史好きとしては読んどかないとと読んでみた。 でも、これがなんで流行ったのかわからない。 応仁の乱と同じようにだらだらと書かれた本に感じました。
0投稿日: 2018.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ興福寺の高僧の日誌を研究して、わかりやすくしてくれているけど、やっぱりわかりにくい。というか、基本的にこちらに登場人物の予備知識がないので、入ってきにくい。 NHKのヒストリアを見たのとこの本で、ようやく、とっかかりができた。
0投稿日: 2018.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ利害関係者多数、これといった決定打ではなく小さなきっかけの積み重ね、それが招いた大乱。 それゆえ何が起こっていたのかわからない応仁の乱を、諸説紹介しつつ極力わかりやすくしてくれた良書。 が、正直それでもよくわからない部分がある。応仁の乱、奥深し。
0投稿日: 2017.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史の中でもとりわけ難解な応仁の乱を取り扱う。時系列を追うだけでも大変だが、それでも本書はわかりやすく記述している。 応仁の乱は、義政・義尚と義視の対比や、日野富子を中心に描かれることが多い印象だったが、そうした表層的な理解が必ずしも正しくなく、室町幕府内の権力闘争が幾重にもなって起きたものであることがわかった。 室町期は、武家同士が好き勝手に争うことが前提となっているのか、現代の社会とはかなり異なる構造になっていると感じた。
0投稿日: 2017.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ応仁の乱について解説した本。 といっても、『経覚私要鈔』及び『大乗院寺社雑事記』という興福寺僧の日記を主な史料としてるため、必ずしも通説通りではない部分もあり、かつ12年以上にわたる戦いのため登場人物も多く非常に複雑である。 従来と違う視点で応仁の乱というものについて知ることで着た。
0投稿日: 2017.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際にあったと思われる細かなイベント等をつなぎ合わせて歴史を見ており、興味深い。ただ、なぜ京都があんなに破壊されたかをを知りたかったので少し欲求不満。
0投稿日: 2017.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ石原莞爾のいう最終戦争を、まったく机上の空論と断ずることはできない 事実、関が原から大阪夏の陣までの一連の戦いを経て 関白の推薦権を幕府が握ったことにより 長い平和と安定が、日本列島にもたらされるのだから しかしそこに到るまでの戦乱の歴史は、まさに酸鼻を極めるものだった 源平合戦、南北朝と、全国規模の総力戦が繰り返されたが 人々はそれに飽かず、続いて戦国時代の幕を開けた その端緒として知られるのが、応仁の乱である それは当初、将軍の権勢に生じた小さな綻びにすぎなかった しかし対立する部下たちになあなあの態度しかとれない将軍家の無力が そこからどんどん露呈していくものでもあった なぜそんなことになったのか 元をただせば無力だからこそ 大名どうしを争わせて直接の反乱を抑えたい将軍家の意向だったのだ そういう、いわば体制維持の必要悪に 歯止めが効かなくなって生じた大乱だった ただし、その長期化・泥沼化の根本原因には 軽装歩兵「足軽」の誕生が無視できない 足軽になったのは食い詰めた牢人や、いわゆる悪党たちであり その主な仕事は補給の遮断にテロ活動 すなわち略奪行為、下手をすると独立ゲリラと言ってよいものだった 戦争を口実に、諸大名が承認を与えるのだから連中にはこたえられない 乱も終盤になると 戦を終わらせぬよう無用の混乱を作り続けたのは 現場の足軽たちではなかったか? その時代、奈良の興福寺は仏教の求心力でもって 安定した統治に寄与していたが 戦の激化から、その影響力はやはり衰えていた 寺の生き残りをはかる経覚は武士に接近し 結果として、尋尊が尻拭いをさせられた ふたりの動静から応仁の乱を読み解こうとする試みが 成功したと言えるかどうかはよくわからんが 階級闘争史観によって語られがちだったという戦後歴史学に 一石を投じようという著者の意図は汲み取れる
1投稿日: 2017.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログアメトークで観て「分かりやすい」と言っていたので購入しましたが、やっぱり難しいです・・・。 登場人物が多いのと名前が似ているので、読んでてわからなくなります。 まぁそもそも応仁の乱自体に興味を持っていない事が原因と思いますが。 正直最終章だけ読むのもアリかと思いました。
0投稿日: 2017.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログやりたくもないのにずるずると大きな戦いになってしまったのは、太平洋戦争を思わせる。 直接の関係者ではないが、近いところにいた関係者の日記をもとに語らせるのは、塩野七生氏の『コンスタンティノープルの陥落』のようだ。 読み進めるとだんだん彼らに感情移入してきて、大変さや苦悩、寂しさといったものを、より感じさせるものがあると思う。
0投稿日: 2017.11.28
